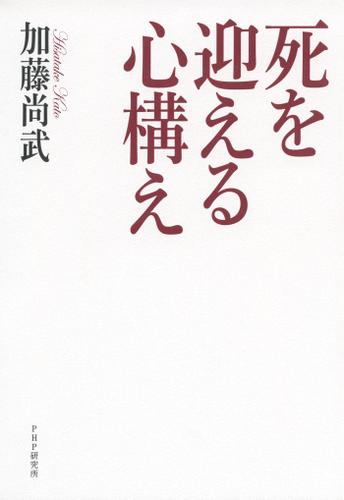
総合評価
(2件)| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ某名誉教授にいただく。哲学者として古今東西、文理を架橋して死の問題を論じている。安楽死や治療中止については違法性についての事前公示の原則を主張している。一章一章は独立性が高く全体としての論旨が見えにくいが、死の問題について考えるべきことが多々述べられている。
0投稿日: 2018.10.13老齢者の処世訓?否、当事者研究本である。
むかし、この著者の生命倫理学に関する著作を何冊か読んだ記憶があります。 1990年代の中頃だったはずです。 内容は正直まったく覚えていません。 ボンクラ丸出しです。 しかし感銘を受けたという記憶はあります。 だからこそ著者の複数の著作を読んだのです。 ちゃんとした記憶はないものの自分の気づかぬところで、みずからの血肉となっているのでしょう(そうあって欲しいものです)。 本書は著者80歳を目前に書かれたものです。 学者として生き、老齢期に入り、来し方を見やって、今の自分の考えを理知的論理的に、そして可能な限り率直に述べようとしています。 本書は、学術的な記載であるべく様々な引用が用いられています。 それらは、もちろん見るべき知見であり聞くべき言葉であります。 しかしながら、そして僭越ながらですが、それらの引用よりも著者ご本人の「なまの声」こそが、説得的で貴重だと感じられました。 わたくし的には二つの見るべき点がありました。 ひとつは、「お年寄りあるある」的な、老いの実感を表現しているところです。 たとえば、歳をとり記憶を手繰りよせることがままならないことを、図書館と出納係のたとえで説明するくだりがあります。 また、未来がなくとも未来があるふりをすることや好好爺ぶって芝居することの大事さを語るくだりなどがあります。 共に上手なたとえであり、老いてからの処世術としてとても説得的だと思います。 ただ、若干表層的かもしれません。 講演受けする、共感を得られやすい話なんだろうな、とも思いました。 もうひとつは、パーソナルで切実な、老いの実感を綴っているところです。 著者は「息子には自殺する権利はない。なぜなら、息子が自殺したら父親である著者はみずからの同一性を保持しえないから」と言います。 また、「夜中に悪夢から醒めたとき、ふたたび悪夢を見るのではないかと恐れたときは、『おとうさん』と何度か唱える。今でも父の言葉に支えられて生きている。」とも言います。 身内への愛情の回帰というか愛情の再強化というか、そういったものが感じられます。 こころの深層に迫るもので、身につまされます。 本書は、老齢者自身による「老いに関する当事者研究」の本であって、あるいはそこにこそ眼目がある、そう言ってよい本であると感じました。
0投稿日: 2018.03.20
