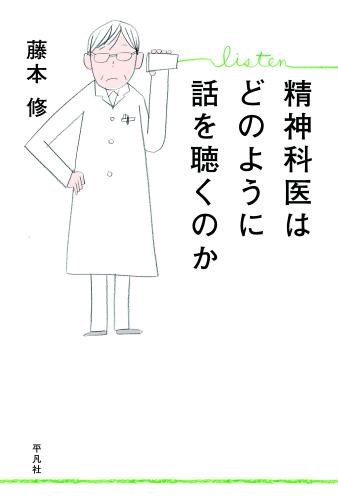
総合評価
(8件)| 0 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、いとうせいこうと、彼と同じバンドメンバーで担当医師(精神科医)である星野概念の対談を読み、精神科医の話の聴き方に興味をもった。 仕事上、相談を受けることは多い。しかし、プライベートでの相談とは異なるタイプのものだ。何か参考になるものはないか。そう思っていた時、そのものズバリ『精神科医はどのように話を聴くのか』という本が平積みされていたので、手にとった。 タイトルの通り、精神科医である筆者が、治療の場で患者からどのように話を聴いているのかが書かれている。 そのため、(一部は触れられてはいるが)傾聴や共感の詳細な方法について知りたいとか、精神科医がしている傾聴を日常生活に活かしたいということを期待して読むと、それは裏切られるかもしれない。 精神科医が患者との面談を、どのような環境で、どれほどの頻度と時間で、どのような記録をとって、どういうことに気をつけながら傾聴しているのか、といったことは分かりやすく書かれている。 仕事で相談を受けるときに環境づくりの面も含めて参考になることが多かった。 「聴き上手になるための10箇条」 特に、巻末に載っている「聴き上手になるための10箇条」というリストが大変良い。 聴き上手になるための10箇条 ・まず「受け止める」準備を ・感情面での支持・共感を示す ・感情の受け入れと論理的な理解のバランスを ・自分の役割をはっきりと意識する ・聴かれたことに常に正しい回答をしなければならないと思わないように ・専門家への紹介も考える ・話し手に考えさせるように返すことが大切 ・話の”間”を上手にとる ・時間の設定を配慮する ・秘密を守る 「精神科医として」という前置きがつくのだろうが、これを「教師として」と置き換えても機能するリストである。 例えば、リストの最初の「1.まず「受け止める」準備を。」には次のように書かれている。 ”聴き上手になるためには、まず、話し手に「この人なら受け止めてくれる」と思ってもらうことが必要です。つまり、相手の話を受け止める態勢が聴き手側に備わっていることを、言葉や態度で伝えることが大切です。聴き手側にこころのゆとりが感じられない状態では、話し手の方がためらってしまいます。時間や場所に対する配慮、聴き手側の表情や服装、身振りなどから、話しても大丈夫だという安心感を抱いてもらわなければなりません。 そして、まずは自分の意見をあまり挟まずに、傾聴して下さい。相手の話していることの真偽や善悪は別にして、まずは話している内容を受け止めてあげて下さい。” 普段、急き立てられるに学校での生活を送っている教員に生徒は相談をしようと思えるだろうか、生徒の話に集中して向き合える環境のなかで話を聴けているだろうか、少し思い返すだけで自分の配慮が足らなかった場面が思い出されてくる。 相談をする前から、相談をするかどうかを生徒は教員の立ち振舞い(話を聴いてもらえるだけの余裕があるかどうかを含めて)で判断していると思うと、自分はどうであったかと振り返るきっかけを与えてくれる。 他にも「時間の設定を配慮する」(長時間、かつ終わりの時間を設けずに話を聴くことを良しとしがちだ……)、「聴かれたことに常に正しい回答をしなければならないと思わないように」(何か気が利いたアドバイスを思いがち……)と、項目ごとに読んでいくだけでも耳が痛い…… さらに「長時間の終わりを決めない話を聴いてしまうと、どのような悪影響があるか」というようなデメリットについても書かれているので、分かりやすい。一つひとつの項目の説明は省略するが、ぜひ説明も読んでほしい。 関係を崩さないこと 留意しなければならない点として本書のなかで繰り返し書かれていることは「医師と患者の関係を崩さない」ということである。 職業柄、患者から恋人や親族、友人にするような相談を受けることも多いそうだ。しかし、そのような相談にも応えることの危険性を、筆者は次のように述べている。 "その際、医師が相談請負人の役割を果たすのは、決してよいこととは言えません。それは、一時的にお互いに満足感を満たすことになっても、長い目で見た時に患者さんのこころの成長を促すことにならないばかりではなく、治療関係を壊すことにつながるからです。医師は患者さんとずっと一緒にいることはできず、あくまで治療のために関係を持っているにすぎないからです。" これは「教師と生徒はずっと一緒にいることはできない」というようにも置き換えられると思う。 なんでも応えてあげることで、生徒が教員に依存し、自立する機会を奪ってしまっては意味がない。生徒の心配事に応えようと手を尽くしてしまいがちな教員にとって、念頭に置いておきたい言葉だ。 教師の自己開示は必要か? 異なる職業なので当然と言えば当然だが、精神科医と教員の話の聴き方で異なるのではないかと感じたところもある。 話を聴いている中で、精神科医は医師個人の話をしないとする一方で、教員自身は生徒などに自分の経験やプライベートのことも話すことがあるからだ。精神科医のそれは医師と患者の関係を崩さないためという理由がある。 教員の場合、教師のパーソナルな部分をさらけ出すことで、それが相手を勇気づけたり参考になったりする場合がある。もちろん、教師と生徒の関係が崩れてはいけないが。 教員に寄せられる相談の種類は多い。勤務校では、教育相談として生徒から相談を受ける時間を学校として設けているが、その事前アンケートに悩みの種類という項目がある。勉強・成績のこと。家族のこと。友人関係。先輩後輩関係。家族。身体。その種類は多い。つまり、教員が生徒からそれだけの種類の相談を受けるということでもある。 どこまで親身になって話を聴き、どこから相談者自身も問題として距離をおくのか。どこまで自己開示をし、どこから隠すのか。それらのバランス感覚は、経験で分かる部分とセンスによる部分もあると思うが。肌感覚でつかむしかない。 話を聴くときの環境づくりや取り組みの留意点に加え、無理なことをはっきりと伝え、線引をする精神科医としての立ち振舞や在り方は参考になった。 生徒や保護者、同僚からの相談にとにかく応えてあげようとして、結果的に相談を受けている側もしんどい思いをしがちな人にお薦めの一冊。
2投稿日: 2022.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ2019/07/14読了 ブクログさんから、献本で頂きました。 精神科医の著者が、聴くことの重要性についてや精神科医の仕事・心がけていることなどを書いている本。 精神科医の仕事って、なんとなーく精神的に参っている人の話を聞いて肯定していくとか、そんな感じかなぁ。とか思ってたけど、この本を読んで見方が変わったなぁ。 肯定していくと言うより、受け入れるってイメージ? 精神科医だって一人の人間だから、色んな思うこととや感情があるはずなのに傾聴して受け入れるって、感情のコントロールが相当大変なんだろうなぁ。 医師は裁判官ではない、患者主体で話を聞くって、簡単に書いてあるように見えて大変だろうし、求められればできるだけ応じたいって言う気持ちもコントロールして役割!と割り切れる精神力がすごい。 最後にある 聴き上手になるための10箇条 は、精神科医の仕事っていう面以外にも、日常にも役立ちそう。 知らない世界を知れました!
0投稿日: 2019.07.14大変読みやすい
共感、傾聴の本として興味を持ったので読んでみた。大変読みやすく精神分析や森田療法、認知療法なども分かり易く説明されている。心理士と精神保健福祉士とソーシャルワーカーはどのような違いがあるかという話も面白かった。最近はお医者さまも時間に追われて効率化を迫られ診察をしながらカルテを入力するのが当然になっているようで、そのプラスマイナスについては参考になった。やはり患者さんの話を聴くことに集中できないというマイナス面は否めない。日常の仕事にも活用できる内容であり巻末に聴き上手になるための10箇条も付いている。
0投稿日: 2017.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神科医が何を目的として、どういった点に注意して、どのように患者の話を聞くのかを具体的に説明している。精神科や心療内科に通う当事者やその近親者は参考になると思う。どのように医師に自分の状態を伝えようかを考えるきっかけになるかもしれない。 また、これまで精神科や心療内科に行ったことがない人や行き始めて日が浅い人は、その不安感を和らげられると思う。内科などと違って、精神的な不調で病院に行くことにためらいを持つ人は多いだろうから。
0投稿日: 2015.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ専門家としてのヒアリング手法の説明がわかりやすくまとまっている。が、この手法を一般人が応用するのは難しいだろう。悩み相談とか問題解決ではなく、あくまでも診断・治療が目的なので。患者側もそこを混同しないように気をつけないといけないのかも。
0投稿日: 2015.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ“精神科医療の現場における聴き方”にテーマを絞っており、『幻聴・妄想はどのように聴くか?』『死にたいと言われた時にどうするか?』『時間外の相談にはどう対応するか?』など、現場で困ってしまう豊富な事例が取り上げられている。内容はオーソドクスで教科書的であり、基本を再確認することができた。また、精神科医・カウンセラー・ソーシャルワーカーと、それぞれの立場における患者との関係性・距離感・スタンスが異なることに改めて気づかされた。精神科医が患者の話を聴く目的は、主に診断や治療のためであり、『治療者―患者という治療構造を安易に崩してはならない』とくりかえし述べられ、『医師と患者の関係は、親子でも兄弟でもない。まして友達でも先輩でも同僚でもありませんし、恩師でも恋人でもありません。赤の他人です。』と言い切っている。そこらへんの感覚は、地域の支援機関とはかなり異なっているのだなと感じた。終章の『聴き上手になるための10個条』は、たしかにこれさえ守っていれば大きな間違いは犯さないであろうと思えるほどよくまとまっている。
0投稿日: 2011.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ患者に対してどのように接するのか。 医師の対応についてこちらはどのように考え、何をどのように聞けばいいのか、ということがわかった。かなり有意義だったと思う。
1投稿日: 2011.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神科医はどのように患者さんの話を聴き、診断・治療するのか? その技術をわかりやすく伝え、診療への不安を解消する。巻末の「聴き上手になるための10箇条」は職場でも参考になる。
0投稿日: 2011.01.27
