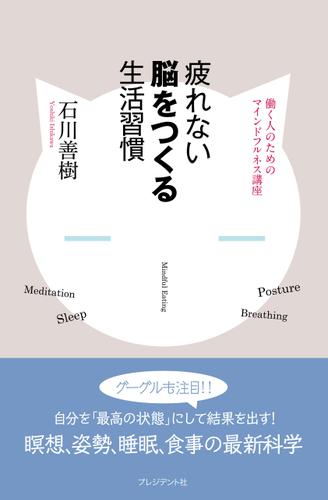
総合評価
(67件)| 9 | ||
| 29 | ||
| 18 | ||
| 3 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ脳を疲れさせないためには、呼吸、姿勢、マインドフルな心が必要と事。確かに振り返ると呼吸も意識してないし、姿勢も気が付くとだらっとしている。実践してみます。
0投稿日: 2025.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネスと脳の仕組みが知りたくて選んだ本。実生活寄りに言及しているので実践しやすいと思いました。
0投稿日: 2023.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「マインドフルネス」の効果と、その効果をさらに高めるための「睡眠」「姿勢」「食事」の方法が近年のエビデンスと共に解説されている。 具体例が載っているので、色々と習慣化したい点があった。
0投稿日: 2022.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネス関連の本を読むのはこれが初めてです。入門として読むには分かりやすく読んで良かったです。 考え方を変えるとか極端な意識改革ではなく、注意の向け方を変える、今のあり方のままで良いという点が受け入れやすくて良いなと思いました。
0投稿日: 2021.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
Newspicksで初めて知って以来、著者の考え方や発想にとても考えさせられることがあり、また、well-beingを説く予防医学者のマインドフルネス講座とあって手に取った本(実際は、プレジデント購読特典。。) マインドフルネスが医学的にも人間にプラスの影響をもたらしていることをいろんなケースを用いて紹介をしたり、疲れない脳を作るために睡眠・食事の大切さを説いている。 集中瞑想は、最近やってないからまた習慣化しよう。
0投稿日: 2021.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネスの入門編。 瞑想だけでなく、良い睡眠、良い食事、良い運動など良い習慣について学べるお得な一品。 少しずつ実践していけばいい、というスタンスも悪くない。 この手の本にしては良書でした(^^)
0投稿日: 2021.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間が1日に使える意思決定の量は限られる 1日5分の瞑想で判断による疲弊を停止させ、いまここ、に集中 背筋伸ばして肩は落とすことで、横隔膜使えて深く呼吸 集中瞑想
0投稿日: 2020.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ●内容 ・疲れない脳を作るための生活習慣 ・マインドフルネス「いまここ」が大事 ・睡眠は6時間以上 ・糖のコントロールが大事 ・異性化糖は良くない ・3食とった方が血糖値を上げにくい ・水をたくさん飲むことも大事 ・座位での生活時間が長いと寿命が短くなる ・姿勢は、坂本龍馬を真似しろ ●学び ・頭脳労働が増えてきている現代だからこそ、脳の休め方が非常に大事。 ・血糖値を上げにくい食事に心がける ・グーグル社員の3大スキルは、料理、睡眠、運動
1投稿日: 2020.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ気軽に実践できそうな内容だったので、スマホでどうでもいい情報を見ている時間を瞑想や睡眠に当ててみようと思った。 自分の生活を見直すきっかけにしたい。
0投稿日: 2020.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本はどちらかといえば上達の法則みたいにインデックス重視の本。 さらっと読めて大事なことをおさらいするのに良い。 気が散ってしまうのは集中力がないからみたいなザックリした課題設定で終わらせずに、姿勢が悪かったりしっかり吐けてなかったりして呼吸がうまくできていないからでは?みたいにチェックできるきっかけになる。 1日5分の瞑想生活も始めてみよう。 それでいうと、集中する瞑想と、客観視するタイプの瞑想の2種類あり、効果も違うということが知れた。
0投稿日: 2020.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ瞑想したくて読んだけど、まだ自分には早かった。瞑想できるほど時間取れないし集中できない。 でも著者の石川さんは好き。 まあ立って本読んだり、デスクの位置とか大事だよねというたまにやること書いてあったのでそれはやってる俺!やったぜという気持ちにはなった、いつかはマインドフルネス
0投稿日: 2020.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ特段目新しいことはなかったが、読みやすいので忙しい人も負担なくすぐに読めます。 『マインドフルネスとは、朝ワクワクして目が覚めて、夜満ち足りた気持ちで眠りにつくこと』と言う一文には、痺れました。
0投稿日: 2019.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分がこれから取り組んでいきたいテーマが机上の学習ではなく、こうした心体に戻っていくものであることを改めて感じることができた
0投稿日: 2019.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネスについてはあまり興味をさほど持っていたという訳ではなく、この著者がほぼ日のサイトで糸井さんと対談してたのをきっかけにこの本を手にとってみたのだが、(たしかに一時本屋さんによくその手の本が並んでるなという印象はあった。ただそれだけだった)総じてどういうものをマインドフルネスと言うのかはよく分からないけど、(またそれぞれに細かく違いはありそうだけど)著者が言うマインドフルネスの定義は「いまここでの経験に評価や判断を加えることなく、能動的に注意を向けること」らしい。そこで不思議だがピンときた。これは俺がネタをやってる時に自分が気をつけている感覚だと思った。受けている時、受けていない時で何が一番違うかといえば受けてない時は客の反応を気にし過ぎる、今ここでの反応に評価したり判断したりして気がとられてしまうのだ。そうなると結局は自分たちのペースで出来ないのであまりいい結果にならない。反対に良い時は客の反応を気にするのではなく自分たちのペースでやることにうまく集中出来てる、と得てしていい反応が得られることが多い。(もちろんフラットにネタを聞いてもらえることが大前提やけど)と考えるとマインドフルネスというのは、持っている能力をいかに能動的に出させる為の方法ということか。それなら瞑想だったり姿勢だったりその他食事についても学ぶべきことは多そうだ。その他仕事の「終わり」の時間を決めることが大事や、トイレで石鹸で手を洗うことの些細なことを丁寧にやるかやらないかというところは実は全て現れているということなどは成る程なと納得した。このあたりは早速取り入れようと思う、この本以外の他の著作をぜひ手にとってみたい。
0投稿日: 2019.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ・Google社員の三大スキルは「料理」「運動」「睡眠」 ・アンドレアガシの毎朝「今夜ベッドに入るとき、僕は自分を誇らしく思っている」
0投稿日: 2018.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間が1日に使える意思決定量は限られている。 疲れない脳をつくるためにすぐできることは、背筋を伸ばして、深呼吸をする。 瞑想の三要素は姿勢と呼吸と心を整えること。 集中瞑想 呼吸に注意を向ける。→注意が散漫になる。→再び呼吸に注意を向ける。 観察瞑想 思考や感覚が拡散する。→思考や感覚が拡散していることに気づく→気づいた思考や感覚を観察する。 マインドフルネスは次世代のメンタルトレーニング。 考え方を変えるのではなく、注意をどこに向けるか。 新しい習慣を身につける方法。 1.少しずつ始める。 2.いつもの習慣のついでに始める。 3.本来の目的以外の喜びを得る。 瞑想で寝てしまうのであれば、一旦やめて寝る。 時間管理の肝は睡眠にある。まず睡眠時間を7時間確保する。 姿勢に気を配る。特にデスクワークでパソコンに向かう時は気にする。 モニターを目線の高さにする。キーボードは膝の上がよいとのこと。 座り続けることはよくない。30分ことに2分程度歩くことが目安。また意識的に水を飲む。 ドローインエクササイズ。胸を張り、細いズボンを履くイメージでおへその下を引っ込める。これを10から30秒続ける。立っている時でも、座っている時でも構わない。歩きながらでもよい。 血糖値に気を配る。 三食きちんと食べ、更に3〜4時間おきに食べ物を摂取するとよい。 更にゆっくり食べることもマインドフルネスにつながる。味覚に集中するということ。 料理、運動、睡眠がGoogle社員の三大スキルとのこと。 マインドフルに生きる過ごし方の例 朝 毎朝決まった時間に起きる。 タンパク質と炭水化物をミックスした朝食を摂る。 体を動かしながら、太陽の光を浴びる。 ドローインウォーキングで出社する。 深い呼吸をして、背筋を伸ばす。 昼 低GIのメニューを選ぶ。野菜、果物、豆類、海藻類など。 サラダ→タンパク質→炭水化物の順番に食べる。 ながらランチをしない。 午後 3〜5分の瞑想トレーニングをする。 水を飲む。座り過ぎない。 仮眠を活用する。 間食は原材料や成分表示を見て選ぶ。 肩のストレッチをする。 夜 なるべく自分で料理をする。 ゆっくり食べる。 夕食は就寝2〜4時間前に済ませる。 刺激の強い光を浴びない。 就寝1時間前に軽いストレッチをする。 お風呂はぬるめ。 就寝時刻と起床時刻を決める。 考え方を変えるよりも注意を変える。 瞑想、睡眠、姿勢、食事。まずは一つ整えてみる。
0投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネスを中心にして、睡眠、姿勢、血糖値などに言及し、いかにして脳を疲れさせないようにしてパフォーマンスを上げていくかについて述べた本。NASAの取り組みやGoogle取り組みなども興味深い。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ・ストレスや疲れを感じたら、背筋を伸ばして、2、3分でいいのでゆっくり深い深呼吸をする。深い呼吸のポイントは、ゆっくり吐くこと。鼻から5秒ぐらいかけて吸い、吐くときは口からでも鼻からでもいいので、10秒から15秒かける ・集中力、記憶力、意思決定を鍛える「集中瞑想」…?調身=姿勢?調息=呼吸?調心=集中・観察 ・調心(集中瞑想)のプロセス…「ひとつの対象(呼吸)に注意を向ける」→「しばらくするとつい別のことを考えて注意が散漫になる」→「再び、対象に注意を戻す」 ・調心(観察瞑想)のプロセス…「思考・感覚が拡散する」→「思考・感覚が拡散していることに気づく」→「気づいた思考や感覚を観察する」 ・ボディスキャンで「離見の見」を身につける…仰向けになった状態で体の各部位に意識を集中させる。「頭→顔→首→背中→腹→腰→右手→左手→右足→左足」体の上のほうから下に向けて順番に注意を向けていき、そこで起こる感覚を感じ取る。重要なことは、余計な判断をさしはさまず、一瞬一瞬の感情や感覚を客観的に観察すること ・起床から1時間以内に、太陽の光を浴びて、朝食をとること(体内時計をリセット) ・肩こりや腰痛を防ぐために「キーボードを膝の上に置く」 ・30分ごとに立ち上がり、2分ぐらい歩く。たくさん水分補給することで、トイレが近くなり、頻繁に立ち上がることになる。加えて、「代謝の活性化」「疲労回復」「関節を柔軟にする」「腎臓の働きを促進」「高血圧の予防」「便秘の予防」など、健康維持にもなる ・本は立って読む…「立ち読み+線引き」で集中力も高まり、眠くならない ・ドローイン・エクササイズ…胸を張って、細いズボンをはくイメージでへその下をひっこめる。この状態を10〜30秒続ける。立っているときでも、座っているときでも、気づいたときに何度でも実践すると、姿勢が大きく改善される ・食品の原材料名は使用料が多い順番に記載される ・清涼飲料の栄養成分の「炭水化物」は「糖質」とイコール。角砂糖1個は3グラム ・血糖値を急激に上げないために、低GI値の食品から順に食べる。GI値は、炭水化物→タンパク質→脂質の順で低くなる ・間食には無塩のナッツがよい。ナッツは5〜7割が脂質なので血糖値が急に上がることはない ・「呼吸、瞑想、姿勢、睡眠、食事」を生活の中心に据えることが、結果的に仕事のパフォーマンスを高めることになる ・パソコンやスマホを見ながらの「ながらランチ」は脳の負担を増やす ・肩のストレッチ…立った姿勢で肩に指をあて、大きく5回回す(前後に) ・質の高い睡眠を得るために…就寝1時間前に軽いストレッチをする。風呂の音頭は少しぬるめにする
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネスに関してまとめられた本。 いっていることはどこかで聞いたことがあるような内容も多いのだが、こうしてまとめられていると、この内容すらできていない自分にも気づくし、この内容さえできればいいのかもしれない、と勇気が湧いてくる。 まずはこれをどう実践するかを考えるべきか。
0投稿日: 2018.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近疲れを感じるので読んでみた。やはり睡眠と食べ物は重要だなあ。あと瞑想と姿勢。本を立ったまま読むっていうのは思いつかなかった。試せそうならやってみたい。
0投稿日: 2018.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前からマインドフルネスには興味があったのですが、一人で仕事をするようになり、より必要性を感じ手にとってみました。 マインドフルネスについて、コンパクトにエッセンスがまとめられており、最初に手に取るには最適の書物ではないか、と思います。 瞑想の効用、睡眠・姿勢、食事(血糖値の管理)の重要性など、生活全般にわたり、「疲れない脳」の作り方が指南されています。 全ては実践できていませんが、落ち着いて短時間でも瞑想することを心がけるようになって、脳の、心の落ち着きが少しでてきたように感じます。 ・「考え方」を変えるよりも「注意を変える」 ・「いまこの瞬間を最大限に味わう」 という言葉に気づきと共感を感じました。
0投稿日: 2018.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネスのハウツー的な内容はあまりない。どのような心身の状態で日々過ごすことが望ましいのか、及びマインドフルネスやら何やらが自分をその状態に導くためにどのように寄与するのかを中心とした内容。一言で言えば題にもある通り、望ましい「生活習慣」の作り方。姿勢(デスクでの座り方、歩き方)の観点は自分には無かったのでタメになった。
0投稿日: 2018.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ姿勢と呼吸、そして瞑想により仕事全般のパフォーマンスを向上させる働きがあるということ。実践すれば、ガラリと変わるという説得力があった。
0投稿日: 2018.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネス実践者が、医学博士の立場から、客観的説明に努めた本書。今までで一番腑に落ちました。 瞑想だけでなく、睡眠、姿勢、食事まで、科学的根拠に基づく重要点が過不足なく実に濃密。 165ページ。良書。
0投稿日: 2018.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネスにもとづいて、生活習慣を正しくしていく方法をこまごまとまとめた一冊。 言うは易く行うは難し、を形にした内容ですが、気になったのは7時間の睡眠時間を確保しなさいという、いわゆる睡眠負債のことで、5時間を切っている自分としても考えないといけません。
0投稿日: 2018.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ・消極的休息(睡眠等)と積極的休息(ランニング、筋トレ)。積極的休息をするからこそ、血行が良くなったり、ストレッチ効果を得られるため、疲れてるからこそ逆に身体を動かすことの重要性を初めて理解 ・マインドフルネスは5分でも。「集中瞑想」と「観察瞑想」 ・12時に寝て、7時に起きる習慣を作る(土日も) ・姿勢。目線の高さにモニター。キーボードは、膝に。 ・血糖値を制する者は仕事を制す。朝ごはんも食べる。 ■2017年は時間をとことん使って仕事をしていたが、疲れが溜まり、死後に集中できない日が続いた。なので思い切って仕事に区切りをつけ、生活習慣を変えて見ることで、パフォーマンスはどう変わるかを試して見ることにします。
0投稿日: 2018.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネスの本。 マインドフルネスだけでなく、もっと浅い習慣...深く呼吸することとか、低GIの勧めとか、簡単なことも割と豊富に書いてあって、暮らしに役立てやすい。人に勧められる本。
0投稿日: 2018.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の石川先生から献本頂いた一冊。 脳を疲れさせないための生活パターンが何個か紹介されている。 また人間の感情の上下は脳のどの部分が作用するかもさっと書いてあるので興味ある人はぜひ。
0投稿日: 2017.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで数々出版されている本に、マインドフルネスを付け加えたような本。まとまっているので、読みやすくはある。
0投稿日: 2017.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ20世紀の心理学者たちは、「人間が1日に使える意思決定の量は限られている」ことを発見しました。 20181215 仕事中心の生活を続けている限り、脳は疲れていく一方です。 →学生時代、全然勉強してこなかった自分は、挽回しようと、就職してから、ずっと仕事の事ばかり考えてきた。 49歳の今、卒業しよう!
0投稿日: 2017.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
マインドフルネスは既に同じような本が多いので新鮮味にやや欠けるが、血糖値コントロールなど、脳にも効果的な食事方法(それも奇をてらったものではなく、常識的な提案)もあり、その部分は新たな学びがあった。
0投稿日: 2017.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本、すごく良いです!! こっち系の本って今までにもたくさん読んだ気がするんですが、残ってることってあまりなくて。 多分書いてあったことが 専門的で理解し辛い事だったり 実践することが難しい内容だったりしたからなんですが。 ・・・その点、このは理解しやすく読みやすく説明してくれるし 今日からすぐにでも実践できることがたくさん書いてあります。 しかも 瞑想、睡眠、姿勢、食事・・・ 「今ここに集中して生きること」(=マインドフルネス=疲れない)を実現するために色んな切り口で書いてくれています。 自分的には6時間睡眠と7時間睡眠の、たった1時間の睡眠の差がもたらす影響とか目からウロコでした。 (6時間睡眠の人は7時間睡眠の人と比べて 脳の老化が2倍のスピードで進む!?ひええ) この本は超買い。 身近に置いておきたい本決定!!!
0投稿日: 2017.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネスの説明はあまり詳しく書かれていない。よく言われる脳を健康にする習慣がざっと並べられている。習慣を実行する気になるかどうかはこの本を読んだだけでは甚だ難しい。
0投稿日: 2017.04.06お手軽です
最近疲れているせいかこういった類いの本にやや手が伸びがち。しかも、頁が少なくてお手軽そうなやつ。(笑) 結局、ふーん、で終わってしまった感じ。唯一?の成果は最近「マインドフルネス」って時々見たり聞いたりするけど、こういうことなのね、って何となく分かったことかな。
0投稿日: 2017.03.26脳の休め方が分かった
日々の生活のなかでなんとなくやる気が出ない、疲れるっていう症状って中年以降の方ならだれでもありますよね。 そんな時、この本を読むときちんとした休み方がわかりますよ。高校生や大学生くらいの年齢ならただひたすら眠れば気力も体力も戻ると思いますが、年をとるときちんと積極的に脳を休めて体をいたわる必要があります。 でもいったいどうやって休めばいいの?って思いませんか。 そんな疑問に明確に答えてくれました。ストレスで疲弊している方、絶対読んだ方がいいですよ。
0投稿日: 2017.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ瞑想だけでなく、マインドフルを改めて生活の中でも実践しようと思った。食事を食べ物の味を味わって食べるようにしようと思う。血糖値を安定させるために、炭水化物だけでなく、たんぱく質と一緒に取るとか、余り食事の時間をあけないように間食をするとか、人工調味料は甘みが強く、血糖値を急激に上げるので、却って甘味がほしくなるとか、知っていても気をつけられていないなと再認識した。
0投稿日: 2017.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
マインドフルネスの効果を科学的な根拠を示しながら説明している。 マインドフルネスのトレーニング本としては「マインドフルネス瞑想」の方が良い。 ・人間が1日に使える意思決定の量は限られている。1日の早い時間で意思決定の量を使い果たすと、疲れが溜まりそれ以降の仕事に影響が出てしまう。 ・瞑想には、集中力、想像力、記憶力、意思決定、モチベーション、コミュニケーション力などの「仕事全般のパフォーマンス」を向上させる働きがある。 ・姿勢、呼吸、心を整えることが大切。 ・姿勢は、背筋を伸ばしたら一度肩を落とす。 ・呼吸は、5秒くらいかけて鼻から吸い、10秒くらいかけてゆっくりと吐く。 ・調心は、一つの対象に集中する「集中瞑想」と、思考や感情や体の変化などを観察しながら受け流す「観察瞑想」がある。 ・集中瞑想をすると、前頭前野が活性化されて、集中力、記憶力、意思決定といった認知能力が高まる。 ・観察瞑想では、わき起こる思考や感覚をそのまま観察する。頭に浮かんだことを、もう一人の自分がそれを映像で見ているように観察する。 ・観察瞑想をすると、想像力や発想力、対人関係、コミュニケーション力に関わる脳の領域が活性化される。 ・瞑想を長年続けている人は、前頭前野や海馬の神経細胞の密度が増加している。さらに、扁桃体を縮小させる。扁桃体は怒りや恐怖に関係する部位。 ・脳には習慣を司る部位があり変化を嫌うため、新しい習慣は少しずつ始めることが重要(漸進性)。 ・睡眠時間は7時間が理想的で、6時間になると脳の退化が7時間に比べて2倍速く進行する。さらに寝不足が溜まって日中の認知機能が低下する。 ・レム睡眠(浅い眠り)にはストレスを緩和させる効果があり、入眠から3時間のノンレム睡眠(深い眠り)には成長ホルモンの分泌が活発になる。またレム睡眠が記憶を定着させ、ノンレム睡眠が記憶を統合する効果がある。 ・体内時計は「光」と「食事」で調整されるので、規則正しく日光を浴び食事をとることが重要。 ・休日の起床時間は平日の±1時間に抑える。眠い場合には昼寝をする。 ・PCモニタの位置をモニタの上3分の1の高さに調整すると姿勢が良くなる。さらにキーボードを膝の上に置くと腕と肩が下がって体への負担が減る。 ・座っている時間が長いと死亡リスクが高まる。座っていると脂肪の燃焼に関係する酵素の働きが止まってしまうため。 ・仕事中に30分毎に立ち上がり、2分ほど歩くと良い。 ・姿勢を矯正するのには、ドローインが良い。胸を張って細いズボンをはくイメージでおへその下をひっこめた状態を10~30秒続ける。ドローインウォーキングではその状態で歩くのも効果的。手のふり幅が前後で同じくらいにする。 ・血糖値を一定に保つとイライラしなくなる。そのためには、朝昼晩の3色を規則正しく食べること。朝食を抜くと昼食後に血糖値が急上昇してしまう。 ・食品のラベルには、「原材料→食品添加物→アレルギー表記」の順で記載され、さらに使用料が多い順に記載されている。 ・炭水化物=糖質と換算する。角砂糖1つが3g。 ・異性化液糖(加糖ブドウ糖液糖、ブドウ糖加糖液糖、高加糖液糖、コーンシロップ)は、血糖値が上がりやすいが満腹感が得にくく脂肪が着きやすい。 ・人工甘味料は砂糖の100~600倍の甘さがあり、血糖値が上昇してしまう。 ・朝食には、太陽を浴び、タンパク質と炭水化物を摂取する。パンと目玉焼き、ご飯と納豆、卵かけご飯などが良い。 ・食事をするときには、サラダや野菜などの食物繊維が多い料理→タンパク質中心のおかず→ご飯などの炭水化物の順に摂取すると血糖値の上昇がゆるやかになる。 ・間食には無塩ナッツがお薦め。ナッツは5~7割が脂質で血糖値が上がりずらい。また脂質を摂取すると満腹感が刺激される。 ・夕食は特にゆっくり食べる。 ・習慣化のうまい人は、何かを終える時間を決めている。終わる時間を決めないとダラダラとやって効率が下がり脳が疲れてしまう。 ・アガシは、朝目が覚めると「今夜ベッドに入るときに自分を誇らしく思っている」と自分に言い聞かせている。朝わくわくして目が覚め、夜満ち足りた気持ちで眠りにつく。
0投稿日: 2017.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ観察瞑想 ①拡散思考を抑制しない ②わき起こる拡散思考を意識する ③気づいた思考や感覚を観察する DMN(デフォルト・モード・ネットワーク) 起床から1時間以内に日光を浴びて朝食をとる パソコンのモニターは目線の高さに 食べる順序 食物繊維→タンパク質→炭水化物 習慣化がうまいかどうかは「何かを終える時間を決めているか」
0投稿日: 2016.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログいわゆるマインドフルネスやメディテーションを中心においた生活法に関する書籍で、とても分かりやすくまとめられていて、そしてそれを実践するアプリなんかも開発されていて、ストレスが気になる方にはおすすめの一冊です。 ヨガを初めてもうすぐ2年。この世界観が人生をリラックスさせる。いい状態を維持するために非常に重要だなとは身をもって体感しているだけに、非常に興味深く読めました。必要な睡眠時間とか、もっと意識した生活を続けていきたいなと。頑張りすぎずに、できる仕組みを作っていこうと思います(2016年12月上旬読了)
0投稿日: 2016.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネスが何なのかようやくわかった。こういった本の主旨(睡眠、運動、食事の常識)がはやく一般化してほしいと思います。寝不足は美徳ではありません。
0投稿日: 2016.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ今までヨガとか瞑想とかオーラソーマで学んできたことが 一気にここに書いてある。 今ここにいること シンプルなことが1番難しいのかもだけど だいぶ実践できている自分がいる(*^^)v あまりに◎な本だったので、図書館で借りて 2回も読んでしまった。
0投稿日: 2016.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞広告で気になって図書館で借りた、と思う。 以下メモ。 ●人間が1日に使える意思決定の量は限られている。朝どの服を着て行こうか、LINEでどう返事をしようかと意思決定するたびに心はすり減っていく。 ●集中瞑想のやり方「1つの対象※呼吸などに注意を向ける」「しばらくするとつい別のことを考えて注意が散漫になる」「再び、対象に注意を戻す」さっと集中できるようになる。 ●観察瞑想のやり方「頭の中に思い浮かんだことを脳内で実況中継する」閃きやすい脳を作る。 ●立ち読み+線引き、は脳が活性化し眠くなって困ることもなく、座りすぎ解消にもなる。 ●食べる順番は「サラダや野菜など食物繊維の多いもの」「タンパク質中心のおかず」「ご飯、パン、麺類などの炭水化物」 ●仕事中心の生活から卒業する。食事や睡眠を生活の中心に置く。
0投稿日: 2016.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログとてもコンパクトで読みやすい本でした。 瞑想や睡眠、食事など、ストレスフルな状態 から抜け出すための生活習慣を学べました。
0投稿日: 2016.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書から学べる最も大切なことは、どのようにしたら脳がなるべく疲れないまま高いパフォーマンスを発揮できるのか、という問いを持つということそのものであると思う。 そのための方法として食事、睡眠、運動、呼吸など様々なことが紹介されているが、それらを実際に行うかどうかは、どうしたら疲れないだろうかと疑問に持てるかどうかなのである。 個人的に1番驚いたのは、人工甘味料はエネルギーとしては使えないけど、血糖値は上がるという話だった。
0投稿日: 2016.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ・キーボードは膝の上に置く ・水は百薬の長 ・「原材料」「栄養成分表示」を見て買う。 ・使用量が多い順に記されている ・エナジードリンクにご用心
0投稿日: 2016.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
新書感覚でサラりと読めてよかったです。 情報が多すぎず少なすぎず◎ 挿絵のイラストやグラフが手書き風でかわいらしいな。 ヨガ・セロトニン・マインドフルネスetc. ここ最近よんでいた本が必ずたどり着く先に「瞑想」 というキーワードが出てきて、むむむ…。 瞑想って、どことなく宗教チックな感じがしていて どちらかというと避けてきた帰来があるのだけども こうまでつづくとさすがにやってみようかな?瞑想… という気持ちになってきました。 ◉体内時計は2種類あった 「主時計」 … 1日のリズムをつくる司令塔となる時計 光によって調整される 「末梢時計」…主時計からの指示は受けつつ食事による 刺激によって調整される 狂ってしまった2つの体内時計を同調させるには? ⇒ 起床後1時間以内に太陽の光を浴びて朝食をとる ◉新しい週間を無理なく身につける3つの方法 ①少しずつはじめる ②いつもの習慣の「ついでに」はじめる ③本来の目的以外の喜びを得る まずは2週間つづける → 2ヶ月つづけば定着する ↑③の部分をもう少し掘り下げてほしかった… ◉ドローイン・エクササイズのすすめ 「draw in」 = 引っこめる 胸を張っておへそを引っこめた状態で10~30秒キープ 姿勢が良くなる→深い呼吸→集中力UP→高パフォーマンス ◉血糖値を左右する2大要因 ①どれだけ欠食しているか 1日3食+間食 3~4時間ごとに食べ物を摂取 → 血糖値が一定となる → 脳のパフォーマンスUP ②どんな炭水化物を摂取しているか リンゴジュースよりリンゴ、白米より玄米 ◉低GI値の食品で脳のパフォーマンスアップ 間食にはナッツが◎ 5~7割が脂質なので血糖値が上がりにくい 脂質を摂取 → 十二指腸からコレシストキニンが分泌 → 脳へ満腹シグナル送る → 空腹感がおさえられる ◉朝は3つの「た」からはじめる ・太陽 ・炭水化物 ・タンパク質 瞑想、睡眠、姿勢、食事
0投稿日: 2016.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ心身ともに疲労が蓄積して思考停止状態、曜日の感覚すら無くなってしまったのがきっかけで手に取りました。今、生活を変えないとマズイ!という危機感にかられて即購入。 グーグルが、マインドフルネスの従業員向けプログラムを作り活用しているというのは有名な話で関連書も出ていたので、気にはなっていました。 読み終わって1週間ほど。マインドフルネスのための基本的な習慣のうち、姿勢と呼吸に意識を向けているだけですが、以前よりもストレスが軽減されて身体が軽くなったような。「今ここに集中する」マインドフルネス、もっと深めて活用していきたいです。
0投稿日: 2016.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ瞑想、ブルーライト、血糖値、姿勢、呼吸、等々広く浅くという感じ、いろいろ書いてあるが全て知っている。初めての人には新鮮かも
0投稿日: 2016.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構前に読んだ本 マインドフルネスに興味があったのよねぇ~ 付箋部分を紹介します ・深い呼吸のポイントは、ゆっくり吐くことです。鼻から5秒ぐらいかけて吸い 吐くときは口からでも鼻からでもいいので、10秒から15秒かけます(p15) ・瞑想をするうえで大切なことは、「調身」「調息」「調心」の3つです。すなわち 姿勢、呼吸、心を整えるということです(p209 ・さらに瞑想は、脳の真ん中にある扁桃体を縮小させるという研究も報告されています。 扁桃体は、怒りや恐怖に深く関係している部位です。(p34) ・「マインドフルネス」を「いまここでの経験に、評価や判断を加えることなく 能動的に注意を向けること」と定義しています(p41) ・でも、瞑想を続けていると「あれ?今日の呼吸はなんかいつもと違うな」ということを感じるようになります。 こうしたかすかな変化を感知する能力が、脳を鍛えていくうえでは決定的に重要なのです(p49) ・ボディスキャンとは、「離見の見」そのものです。つまり、自分という劇場で起きている感情や感覚の演技を 観客として観察することが肝要なのです(p51) ・消極的休養も積極的休養も、目的は同じです。疲れた脳を休ませるということです。 脳を上手に休ませることが、長期的には疲れない脳をつくり、高いパフォーマンスで仕事を続けることができる(p78) ・本は立って読め(p94) ・習慣化がうまい人の特徴を研究しているのですが、いちばんのポイントは 「何かを終える時間を決めているかどうか」です(p137) ・人前で立派に振舞っているように見えても、その人が一つひとつの行動を大事にして生きているかどうかは 手洗いのような些細な振る舞いから透けて見えてしまうのです(p143) ・息をゆっくり長く吐くと、セロトニンの分泌が増えるので、ストレスが軽減し、心がゆったりとした状態に 落ち着いていきます(p149) ・人間の脳は「古い脳」「真ん中の脳」「新しい脳」の三層に分かれていますが、習慣を司る「古い脳」は 新しい変化を極度に嫌がります。その意味では、人間は保守的に行動をしてしまう生き物なのです(p158) ・瞑想、睡眠、姿勢、食事(p160)
0投稿日: 2016.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログまあ正直言うと既知の事柄が多かったのでそれほど感銘を受けるということはなかったけれど、普段の生活の中でもできる瞑想や睡眠や食生活の注意点など改めて確認した。 椅子に長く座る習慣のある人は死亡するリスクが高いとのこと。 間にいくら運動をしても座る時間がながければ意味が無いようだ。 ちょっとパソコンを使う時間を減らそうかと考えた。 水を多く摂取し深い呼吸をするよう心がけようと思う。
0投稿日: 2016.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
内容自体は平易で入門的かとは思いますが、著者のやさしい語り口から、すいすい読めて、飽きさせないようになっていると思います。 「最近疲れが溜まりやすくて」、とか、「瞑想って興味あるけどどうやるか分からない」、とか、本書の表題や帯の紹介文に少しでも引っかかりがある初学者(と言うのか?)の方には、もってこいかと思われます。 私自身としては、本書の内容自体目新しいものは多くなかったので、評価は星3とさせていただきます。
0投稿日: 2016.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆☆☆☆ここ最近、ラジオでチチョコチョコ「脳に関する」解説で耳にしていたので、YouTubeで観てみたら、好感の持てる若者姿が映っていました。そこで、どんな文章を書くのかなぁと思って手にとって、読んでみました。 感想、ラジオ、YouTubeの石川善樹さんそのままが語ってくれていました。とても分かりやすく、活用しやすいように身近な知恵を授けてくれます。東京大学医学部卒、ハーバード大学大学院修了。とありますから、難しい本ばかりたくさん読んでこられたのではないかと想像していましたが、「『マインドフルネス』とは?」を日常の生活のシーンにスタンスをおいて、説明してくれています。 では、この本から得た幾つかの知識と気づきを紹介します。 まずは、 ①瞑想には【集中瞑想】と【観察瞑想】があり、それぞれ働き方が違うということ。それを実践、継続をするアプリ「MYALO」がオススメ ②「脳には複数の領域で構成されているDMN(デフォルト・モード・ネットワーク)がある。 このDMNは.過去のさまざまな感情や記憶などをつなぎ合わせるときに、重要な役割を果たしている。」 この知識とそれをイメージとして持ち、自分の脳の働きを想像すると『閃き』の大きな手助けになると感じました。 ③「扁桃体ハイジャック」という言葉。(この分野を研究する人たちの中ではよく知られているようだ) 扁桃体が活発になると、体内でコルチゾールという、理性的な思考を奪い、感情を暴走させるストレスホルモンが発生する。という仕組みなのだけど、「怒りが怒りを呼んで手がつけられない状態」を想像すれば良いのだけど、この言葉を知ることによって、自分がこの状態になったときにより速くブレーキを踏めるようになったと思える(試してみよう) ④あと、これは知識ではなく気づきなのだけど、なぜ、修行僧たちは1日の大半を瞑想に費やすのだろうか? その理由は紹介されていないが、脳科学的な効果としては前頭前野や海馬の神経細胞の密度が増すということが実証されているそうです。 マインドフルネスの定義である『“いまここ”での経験に、評価や判断を加えることなく、能動的に注意を向けること』でこれに近づけるということなのだろう。 それにしても、仏教の世界では脳の構造のこともわからない昔からそのようなことをしてきたことと、それによってどのようなことを社会にもたらしてきたのだろうか?と疑問は尽きない。 ⑤〜〜楽器を習ったばかりの人は、演奏中に「うまく演奏できるだろうか」とか「失敗したらどうしよう」といった余計な判断をくわえてしまいます。一流の演奏者は、自分と楽器のみならず、楽団や聴衆とも一体化しているような感覚で演奏することができると言います。つまり、余計な自我が演奏に顔を出してこないのです。〜〜 という状態は感覚的には良く理解ができるのですが、何かもっと良い、科学的なアプローチで説明してもらえたらなぁといつもこの手の説明文で感じてしまいます。 2016/07/07
0投稿日: 2016.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
某生放送から(笑)、石川さんのお人柄に惹かれて手に取りました。 結論、ものすごく役に立ちます!すぐに実践、生活の中に取り入れることができて、特別な物は何もいりません。呼吸と姿勢に意識を向けて、集中。これだけです。 デスクワークで疲れにくくなるために、目線はディスプレイの3分の1、キーボードはひざの上、心臓病などのリスクを減らすため、水分を多めに取り、 できれば30分に1度は2分程歩く。より良い脳のパフォーマンスのため、質の良い睡眠、血糖値を一定に保つ食事を心がける、などです。 わたしはいつも6時間睡眠だったのですが、7時間睡眠の方と比べて脳の老化スピードが2倍になるらしく、よろしくないとの事。石川さんが触れていましたが、自己啓発や時間管理のハウツー本は多くても、その中で睡眠時間の確保が軽視されていると。確かにその通りです。寝る時間、起きる時間を最初に決めて、そこに向かって行動した方が、効率的だし何より自分のためになりますよね。 日々の暮らし、やりたい事とやれる事、忙しさや自身の怠惰などで雑になりがちな所、大切な事を思い出すため、時々読み返して忘れないようにしようと思います。
0投稿日: 2016.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近流行っている、Googleがやっているからを謳い文句とするマインドフルネス関連ビジネスは「マインドフルネスを自分の目的のために用いている」ような気がしている。「あるがまま」「いまここ」に気づくことを重視するより、その状態となった結果生じる「パフォーマンスの向上」を目的としているような気がする。 別にそれが悪いというわけじゃないけれど、結果を求めてマインドフルネスを目指すこと、瞑想を行うことは「正解とならない(パフォーマンスの向上が図れない)」限り、マインドフルネスに失敗している、となってしまう気がする。 そうなってくると、もうマインドフルネスと違うのではないかなぁ……と。 しかしながら、どういうきっかけでマインドフルネスに触れるのかという機会を奪うのもどうかなぁともおもうので、一概にNGとは言えない。 マインドフルネスに関しては、いろいろな本が出ているけれども、個人的に「マインドフルネスストレス低減法(ジョン・カバットジン)」をオススメしたい。
0投稿日: 2016.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ[図書館] 読了:2016/6/2 マインドフルネスの本を何冊か読んだ後には目新しくない内容ばかりだった。 姿勢を良くして呼吸を深くすることが、仕事にも子どもの勉強にも大事、これくらいかな?
0投稿日: 2016.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ毎日をもっと良くしたくて購入した一冊。 10代まではなんだかんだと規則正しく健康的な生活と精神状態だったけれど、20代から色々と起こる出来事に飲み込まれ、もやもやする日々でした。 まず瞑想を試してみました。 一度やっただけですが続けていったら気の持ちようや、物事への向かい方、考え方が変わるだろうなと思いました。 続けます。 あとは、睡眠の質を上げること。 これは難しそうですが焦らず、瞑想で落ち着くことを体得しながら眠りも充実させたいです。 そして食事。 30代となった今、20代の荒れていた頃よりだいぶ健康的なものを摂取していますが、食べる順番や食べ合わせを気をつけたり、自炊を心がけようと思います。 当たり前といえば当たり前のことが書いてあります。 だけど、それがなかなかできない。 やらなければならないこと、いつも何かに追われているから、私は自分を整えることをおろそかにしていました。 この本に書いてあることを真面目に実践してみようと思います。 手のひらの中にいつも世界とつながる道具があることは便利だけれど情報が多すぎて疲れる。 それでも覗いてしまう。 けれども一度読んだものがどこに行ったかわからなくなるし、なんだか根拠のないものに思えてしまうことがある。 手にとって、触って、ページを繰る方が自分の性に合っているし、実感が得られる。
0投稿日: 2016.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ疲れが抜けないなあと思ったので、思わず衝動買い。 考え方を変える、ではなく注意をむけている対象を変えるというのは確かに納得。 こういった本は実践してナンボ。読むだけでは変われないので星は少なめです。
0投稿日: 2016.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ疲れない脳を作るために、瞑想、睡眠、姿勢、食事の4つの視点から書かれています。 そして、マインドフルネスな状態で1日を過ごすために、朝、午前中、昼食、午後、夜の習慣が提案されています。 ただ、私は朝食抜き健康法を実践しているので、朝食をとることは絶対必要という主張には賛同できませんでした。 瞑想なら瞑想で、もっと詳細に書かれた書物がたくさんありますし、食事に関してもそうです。 それぞれの事に関しては基本的なことしか書かれていないので、あまり得るものがありませんでした。
0投稿日: 2016.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログトイレのあと石鹸で手を洗う人はできる人が多い気がすると印象を語ることも多々あってちょっとどうなの? ということ以外は参考になるのかなと… ただこんな本はたくさんある気もする。 新しい発見があったかといえば大体知っている話グーグルがー、ジョコビッチがー。
0投稿日: 2016.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ食事、睡眠、瞑想。 家族との時間の確保と限られたオフィスで過ごす時間の両方を今より充実したものにしたいので、いろいろ気づきが得られる内容でした。 血糖値のコントロールをさっそく意識してみよっと。
0投稿日: 2016.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログここ2年間仕事をしていて思っていたことは、ある種の理想的な業務の姿を追い求めるのではなく、他部課よりかなり多めに課されたタスクをいかにうまく処理するかであった。当座は、個人としてはそれらに熟達し、また集団としてのチーム内で処理能力を高めることを心がけていた。そうした中で特に求められるものは、体力・気力と、いるメンバーでとりあえず何とかする力(計画・調整・実施・フォロー等)だと思っている。ただやみくもにそれらの力を各方面に注いだところで、限界があることもわかってきた。個人及び集団の処理能力を上げるには、個々人の善意とか、単なる気合いとかがんばりだけでは無理そうだった。 そこで、本書にあるようなマインドフルネスについて興味を持った。高度な判断を伴うタスクを処理するには、頭の中の脳が正常に作動することが必要なのは当然である。この本には実際に脳の働きを維持・管理する方法が紹介されている。依拠した論文もアペンディックスで示されている。また多くの製作スタッフが係っていた点も記されており信頼できる印象を持った。主な取り組み活動は以下のようなものだった。 ・深呼吸 ・7時間睡眠 ・姿勢(PCの操作時、draw in エクササイズ) ・禅のように呼吸に意識を向け「いまここに」在ることに集する瞑想 ・拡散思考を意識し、客観的に外から自分を見て受け止める観察瞑想 ・低GI値の食事 以下のアプリを用いることで実践しやすくなる。 https://myalo-app.com/LP/
0投稿日: 2016.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ・人間が1日に使える意思決定の量は限られている ・習慣化のうまい人は何かを終える時間を決めている ・マインドフルネスな状態とは、「朝わくわくして目が覚めて、夜満ち足りた気持ちで眠りにつくこと」
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログジョコビッチが実践しているメンタルトレーニング「マインドフルネス」を題材にした健康本。 医学的な資格を持つ著者と研究結果を交えて、脳に良い効果をもたらす5つの生活習慣を教えてくれます。 脳の働きに密接な関係がある、睡眠・食事・姿勢・瞑想から一日の過ごし方(朝・午前・お昼・午後・夜)に当てはめて実践できます。 ◇朝習慣の、動きながら日光浴と、午前習慣の、深呼吸しながらドローイン・ウォーキングは併用できそうです。 日頃、疲れや集中力低下を感じる生活からの脱却に役立ちました。
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を手にしたとき、紙の手触りといい色合いといい、優しくて落ち着く感触があった。装丁はクラフトエヴィングさんだとあとがきで知り、納得。素敵な装丁のはずです。 肝心な中身ですが、マインドフルネスをはじめて知る人にはいいかもしれません。 私の場合は、チョプラ氏の『心を満たせばカラダはやせる』の方がわかりやすく実践的だったので、もう一度読み返そうかなと思っています。 いずれにせよ、マインドフルネスが日本にキタかなって流れは、なんとなく嬉しい。
0投稿日: 2016.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ脳が疲れない食事や睡眠などの生活習慣を教えてもらえる本ですが、面白かったのはGoogleで働く人が取り入れている習慣。 瞑想を持つ時間が公式に推奨されているのは、やはり進んでいるのでしょう。 何十年か前は、日本の企業ではラジオ体操を取り入れていましたけど、これからは瞑想する時間がとられる事もあるのかな?
0投稿日: 2016.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかく石川よしきさん節がでてる本です。つながりの本も読みましたが、それ以上にこちらはおもしろかった笑 姿勢が龍馬はツボでした笑 早く直接いろいろお話ししてみたいです。
0投稿日: 2016.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログマインドフルネス 呼吸器などに意識を向ける集中瞑想 外から自分を見て受け止める観察瞑想 瞑想 食事 睡眠 姿勢
1投稿日: 2016.02.20
