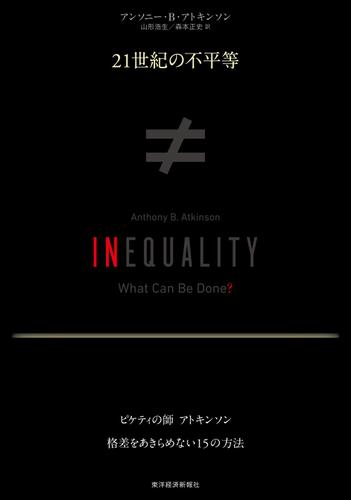
総合評価
(16件)| 2 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に難解だった。理解出来た点をいくつか。 高技能者が便利な仕組みを作れば世の中便利になるが、低技能者は失業し、格差が広がる。考えもしなかったが、確かにネットの発達で店舗は減少している。ただ、運送業者は忙しくなっており、店舗からすると失業という形にはなるが、全体を俯瞰すると再分配されているとも取れる。 資本所得の増税はすべきだと思う。問題なのは貯蓄しすぎな事なので、資産に合わせて課税されないと不満しか出ないだろう。 とにかく未来の世代のためになる富の分配が必要で、皆が同じ意識を持つ事が大事だと思う。
1投稿日: 2023.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログピケティの師匠であるアトキンソンの、経済格差問題の本 ピケティが『21世紀の資本』で経済格差の内容を明らかにして 本書でより現実的な政策提言を行う感じの流れがある
0投稿日: 2020.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の経済的不平等の解決策について、オックスフォード経済学者により書かれたもの。ピケティの「21世紀の資本」では富の実態を明らかにしたが、これに続き富の不平等を是正するための方策を具体的に述べている。所得税最高税率65%、児童手当や年金の増額など、社会主義に近い大きな政府を目指す政策を推奨していると思われる。論証は論理的かつ学術的であるが、労働者のインセンティブ維持が難しいように思う。イギリスを題材にしていることから、必ずしも日本に適用できない部分もあると思う。富の実態を詳細なデータで示したピケティの「21世紀の資本」の方が興味深かった。 「中国とインドのジニ係数は50%に近く、北欧諸国のおよそ2倍だ。ブラジル、メキシコといった中南米諸国も高く40%を超えている。その次に高いのがアメリカとイギリスだ」p25 「裕福な家庭は、世論調査の回答率が低い」p57 「失業は、不平等の源」p89 「企業は学習してその手段のやり方を改善し、生産コストは常に減少する」p102 「不平等の減少は、市場所得の不平等減少と効果的な再分配が組み合わさることで実現したことを歴史が示している」p127 「人間によるサービスの側面を軽視すると、予算削減は所得を労働者から資本に振り向けるのに貢献する(機械化が進む)」p135 「労働者の雇用性を増大するような方向を奨励し、サービス提供における人間的な側面を強調すべきである」p136 「(金融サービスが儲かる理由)常識では、仮に閉じられた集団内で人々が紙片を交換し続けたとしても、これらの紙片の総価値はそれほど、いやまったく変化しない。もしその閉じられた集団の中の誰かが桁外れな利益をあげたとすると、これらの利益は他のメンバーの犠牲の上のみで成立する」p189 「EUをめぐる最近の政治論争の多くは、その根底に国際リーダーシップ喪失をめぐる懸念がある」p274 「単一企業とは違い、国には対外的な不均衡に対する調整プロセスがある。輸出が減って輸入が増えれば、為替レートは下がり、輸出業者や財やサービスを、輸出市場と見合いの価格で売れるようになる。同じく、為替レートが下がると輸入財が国内価格で高価になり、その価格を適正な水準にする」p316
0投稿日: 2018.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ提案の方向性はおそらく正しいものだと思う。ただし、膨大な項目にそれを引用する上での留保。理解する上での前提の多さ、この留保や前提は数字のことではあるものの、どこか宗教的感性が必要だ。これは、この人の物言いがそうなんじゃなくて経済学の話全般に言える胡散臭さや問題点だと思う。テレビでの解説は概ね簡略化されている。コメンテーターもわかりやすく言うが実相が見えている人は表に出てこないで金を稼いでいると思う。そういう人たちの野心の強度に比べて学者の言論は心許ないなというのが正直な印象。合意を形成して目指すにしてはもっと別の枠組みも必要になると感じた。
0投稿日: 2017.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログアトキンソンはピケティの師と帯には書いているが、序文にはピケティの文章が載っている。 格差と不平等に関する論考で、現状を歴史も含めて検討し、それに対する対策を提案し、またその反論に対する論駁を述べている。数字はたくさん出てくるが、ピケティの本に比して数式は少ないので読みやすいが、やはり翻訳本であるので、文章がこなれてないところは多少ある。また経済学の基本を理解していないと本当の理解には進まない部分もある。ただ格差と不平等を学ぶ教科書であることは間違いないのであろう。
0投稿日: 2017.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ不平等縮小のための15の提案。再配布だけでなく、移転前所得の不平等を減らすための施策。議論の基礎としての歴史や経済学、実現可能性の考察が加わる。 社会で育ち暮して普通に当たり前と認識してきた富に関する前提が、そうではない世界もあり得るということを示してくれた。
0投稿日: 2017.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは専門的過ぎる。この内容は精緻な学術書だ。小生程度の知識では読みこなすことは困難との感想を持った。 トマ・ピケティの「21世紀の資本」は社会学の専門書にもかかわらず興味深く読めたし多くの刺激をも抱くことができた。本書も社会学の本であるし、翻訳者もピケティ本と同一人なので期待したのだがちょっと残念。 思うに、ピケティは一般人も読める専門書を書けるだけの幅広い教養を持った稀有な社会学者だということなのだろう。 本書では、世界的に不平等が拡大しつつあることが詳細に明らかにされている。それを乗り越えるための多くの提案をも考察しているが、必要性は理解できるものの実現性は現在では困難なものばかりとも思った。道は遠そうである。 2017年2月読了。
0投稿日: 2017.02.09ピケティの明解さの背景にある泥臭い蓄積
今日の格差・不平等の実態およびそれがもたらす影響と、様々な対応策とそれがもたらすであろう影響について、主に英国の政策集として練り上げていく地を這うようなアプローチがすごい。 例えば社会保障について、受け取ってもらえない手当がいつまでも続くことの背景にある勘違いなどを摘出し、改善策を提示していく手腕と明晰さは、実社会における経済と向き合い続けた生涯の証明なのだろう。 2017年1月1日逝去、R.I.P.
2投稿日: 2017.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
☆は3にするか4にするかでちょっと悩んだけど。 普段、経済政策の話って実はあまり読むことなくて、不平等を経済政策としてゆっくり考えたの初めてに近いから、そういう意味で、いいきっかけになったから、4にしました。 つまり、これまで、個別に社会保障問題、年金、税率、社会サービスへのアクセスなど、考えたりはしてきているけど、それを全体政策として捉えきれてなかったし。社会サービスへのアクセスも、貧困層が弱いのはもちろん自明だったし拡大すべきと思っていたけれども、その捉え方はどちらかというと、人権思想であり、まあ、capabilityアプローチであって、それがすなわち所得の拡大と同義だ、なんていう考え方はしたことなかったがら。なんか、本題はとりあえず置いておいても、なるほどな、って思ったよ。
0投稿日: 2017.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログピケティを受けて書いていることがいろいろなところに出てくる。 意外と読みにくいという感じがしたが、イギリス経済を語る上には必須のほんであろう。
0投稿日: 2017.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ11.20.2016 読了 ピケティからアトキンソンを読む方が思考がスムーズだ。アトキンソンもピケティの研究を踏まえて論じている。 15の提案とそれに対する反論という構成。 速読、斜め読みの方は、第I部をパラパラと読んで背景、前提を確認したのち、第Ⅱ部の15の提案と検討すべきアイディア(p355に全掲)、第Ⅲ部のまとめとを読み流せばだいたいのことは掴めるはず。かく言う私も斜め読み。
0投稿日: 2016.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログピケティの本をさらに深堀りしたような本と認識している。未来に関心がある人であれば、まず読んでおいて損はないと思われる。
0投稿日: 2016.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ1部は不平等の証拠をつらつら並べているだけ 2部は過去の政策から得た教訓からの提案15案を説明しているだけ。 この厚さ、必要だろうか?
0投稿日: 2016.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は不平等の研究の先駆者。ピケティが序文を寄せている。分析ではなく、行動計画に専念した本。一般の人が読了するのは難しいと感じた。
0投稿日: 2016.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
イギリス式の政策を中心にした格差是正方策の検討。日本と引き比べてみるとやはりEUって大きいんだなあ。
0投稿日: 2016.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ序文に登場するのはトマ・ピケティ。献身的で皮肉な本、という素敵な言葉を送っている。印象としては、ピケティよりも楽観的かつ現実路線を目指した本、といえようか。 世の中は一度不平等がやや減ったのに、再び不平等な世界になった。第二次大戦中は不平等が縮小した。では戦争をすればいいか? もちろん違う。 主にイギリスを中心とした欧米のデータがメインで語られる。不平等はなにか単純な理由だけで起きるのではない。けれど長期トレンドよりエピソードをみたほうがつかめるものがある。 最後に、広く検討されずにいて過激である、とする15の提案を挙げている。 全部書くのは面倒くさいので省略するが、国民貯蓄国債を通じてプラスの実質利率を保証しろ、だとか、全児童へ相当額の児童手当を払い課税所得として扱う、児童ベーシックインカム、などなど。 「政治では重要なものが二つある。一つはお金で、二番目は何だったか忘れた」という有名な言葉がある。それでも政治は大切だ。折しも日本では、死ねとかブログに書くと間接的に政治が動いてくれるという構図が現れたが、これが単一省庁での行動になっては予算消化レベルで終了だろう。それでも、過去に不平等の削減が起きた時の原因のひとつは、政府の介入が成功したことだという。逆にいえば政府の介入で不平等をより大きくすることも出来る、のは僕らがよく知ることである。
0投稿日: 2016.03.18
