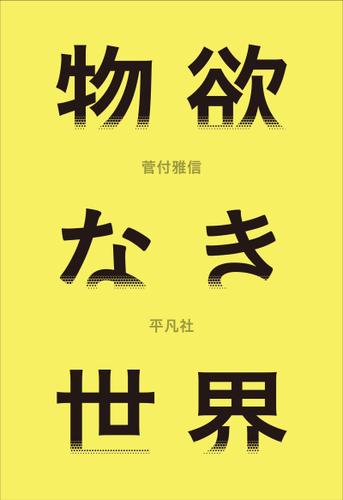
総合評価
(42件)| 6 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 7 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ10年前に書かれた本ですが、2025年の今の方がより実感を持って読めました。 本の途中からはお金の話になり、ストックではなくフローとしてのお金の新たな価値と可能性についてはとても興味深かったです。 ストックからフローへの移行はすでにモノの世界では起こっていることですが、それがお金においても同様な感覚になるんだと考えるとさらに今から少し先の未来の世の中の感覚が掴めた気がします。
0投稿日: 2025.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ人々はモノを買わなくなったのか?自分自身の物欲が低下しっぱなしだったので手に取ってみました。筆者がいろんな角度からこの事象について考察しています。2015年とやや古い内容ですが十分に面白いです。ただ全体的なムーブメントが主で、私自身の感覚をしっかり説明してくれるものではなかったかも。図書館で借りて読みました。
0投稿日: 2025.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログワクワクして、未来に希望が持てる本! 成長経済の名のもとに大量消費、そんなのいつまでも続くワケないじゃん。不安に煽られて仕事に生活が侵食され続ける… 資本主義ってもうダメくない? という私の疑問に、各界で活躍する人たちの実践と考えを提示しながら答えてくれる! 10年前にすでにこんな事考えてた人がいたんだー、やっぱアタマいい人は違うなぁ。 「近い未来、人は自分自身が持っている、もっと 根源的な価値で支払うようになる」 私はどんな根源的価値をどれくらい持てるだろうか。どのような根源的価値を私は周りに求めるんだろう。 お金じゃない信用を獲得できるとしたら、それが可視化できたら、スゴく楽しそう♪ 可視化できるかどうかはともかく、今からどんな価値を獲得できるのかは私次第。ワクワクする!
1投稿日: 2024.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
青山ブックセンターに立ち寄って新しい本を物色していた際に目に留まった。ちょうど今お金を極力使わずに楽しめる工夫を模索していたこともあり、資本主義的な快楽・物欲との付き合い方について考えるきっかけを得たいと思い読み始めた。 冒頭はライフスタイルというキーワードを軸に物欲を中心にした従来型の豊かさからの変化について様々な識者の意見をまとめ、現代はただ物欲が無くなっただけでなく、個々人が持つ本当の趣味嗜好の追求や社会貢献から得られる充足感のような、経済成長とは反対の方向に豊かさの質が変わっている事が説明されている。 経済的には貧しさに繋がるのかもしれないが、長い歴史の中で経済成長が無かった時代に華開いた文化も沢山あったという事例が興味深く、現代の減速感が停滞ではなく成熟だとすればポジティブに受け止められると感じた。 また、働いている身としてはそのような価値基準の変化に逆らわずに、それでも世の中で必要とされているものを提供し、急成長はしなくても緩やかに事業を紡いでいく事が大切になるので、物欲・豊かさに関する新しい考え方をインストールできて良かった。
0投稿日: 2023.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々に面白かった! また読み返すかも。 消費社会の在り方、これからの世の中でどうやったら人々がお金を払って経済が回るか考えさせられる。
0投稿日: 2023.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015年の本。ライフスタイル消費から入りキンフォークやポートランドがすごいという話でなんだか懐かしい古い話と一瞬思うが、読み進めるほどにそんなことはなく。最後の2章は、資本主義の行き詰まりと次なる低成長時代は日本にとってチャンスである(なぜならいち早く低成長時代でやってきてるから)という話などは、2021〜2022年辺りで議論されてるアメリカの分断だとかGAFAMの隆盛だとかと繋がるし、ラストの「果たして自分は何が欲しいんだろうか?」という問いに答えられるようになることがこの新資本主義(あるいは新民主主義。要は今の経済成長路線ではないなにか)を生きるための指針になるという点は、2023年の今でも変わらない論点だ。 にしても、脱成長と日本は確かに相性良い気もする。 みんなで手を取り合ってて勝てないのが日本と思ってるが、勝つ(成長)のを是とせず不条理な格差を生まずにみんなまあまあ幸せ("攻めない"最大多数の最大幸福みたいなもの)を狙うという感じは、確かに相性良さそうだし。 -- ファッションから経済への接続。つまり自分の仕事から社会や世界への接続。栗野さんのモード後の世界で感じたそれとはまた違った、客観から捉えて編集し切る感じもまた良い。 -- 菅付雅信、編集の巧さ、マジで好き。2013年に見た講演でドギモ抜かれて以来。
0投稿日: 2023.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015年に出版された本。 なので、新しい感じはしない。 コロナ前のことなので、今はこの本の内容は当たり前になっているのかもしれない。 そして、予想外のことも起こっているかもしれない。
0投稿日: 2022.08.04そうは言っても、やはり見通せない今後の世界
まずファッションの話から始まりました。私自身は、ファッションには全く興味はなく、服を買う基準は、サイズが合うかどうか、着ることが出来るかどうか、でありましたので、そもそもファッションに対する物欲はありませんでした。でも、「ライフスタイル」がブームであると言うことは判ります。 「欲しいものがない時代」う~ン確かにそうかもしれません。私の生まれた頃は、今から思えば何にもありませんでした。冷蔵庫もなかったらしいですが、それは記憶にはありません。でも小学校時代はずっと白黒テレビでしたし、自家用車もありませんでした。ただねぇ、今の若者が物欲がなくなったというのは、単純には言えないでしょうね。欲しくても買えない人も多いでしょうし、その一方、スマホの新機種がでれば人々が殺到するという現実、まぁ、これもファッションなのかもしれません。 話は、モノとの新しい関係、共有とかシェアについて述べられていき、そして徐々に資本主義の先の世界への考察に移っていきました。最後の章は、筆者の意見と言うよりも、様々な学者さん等の考えていることや事例の紹介でしたけど、これが大変興味深いものでした。成熟した社会とはどのようなものか。日本の今後が成熟なき衰退にならないかと懸念する人等、色々ありましたけど、今後の世界を考える際、巨大化した貧富の差はいかんともしがたい障害となるでしょう。その中で、おそらく1番良い解決策は、本の中で紹介された「最低所得と最高所得の幅を制限する」というものかもしれませんね。でも、地球規模でこれを実現することは不可能だろうねぇ。資本主義の先の世界、どうなるのでしょうかね。
0投稿日: 2022.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初はファッションの話が中心かと思いましたが、後半に色々な事柄についてさらっと触れており、考える種をくれるような本でした。 自分が求めているものが何なのかを、きちんと把握して言語化できるようになりたいです。
1投稿日: 2021.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこの系統によく出てくる本(既読) 『スペンド・シフト』 『消費するアメリカ人』 平川克美『消費をやめる』 ガルブレイス『ゆたかな社会』 ピケティ『21世紀の資本』 アタリ『21世紀の歴史』 ボードリヤール『消費社会の神話と構造』(未読) 村上春樹もオレゴン州ポートランドに好ましい評価してたな。でも実際は勝ち組が住める土地であって、勝ち組を目指す若者には向いてないとのこと。勝ってからいかないと路頭に迷うらしい。それって、近年の地方移住やワーケーションでも一緒なのかも。地方は都会から若い世代(ファミリー世代)を呼び込んで、ネットさえつながれば~っていうけど、実際ネットだけで生活していける人(クリエイター職種、デザイナー、ライターとか?)でないと、住民からはよそ者扱いされるは仕事はないわ不便だわでろくなことない。それを、癒しを求めて無鉄砲に移住する人が多すぎる。 カーシェア、シェアハウス(子育て世代と高齢者など含む)、シェアオフィス 若者は自己実現の前に経済的自立、の考え方が変わってきた リベラルアーツ(教養)を軽視、人文科学系大学の規模縮小など世界の流れに逆行する日本 大石繁宏『幸せを科学する』 いったん食、住の基本的な欲求が満たされればそれ以上の年収は幸せの向上にはつながらない。高収入は仕事のストレスが多い。 ラトゥーシュ『<脱成長>は、世界を変えられるか?』 消費の少ない社会の実現 ショア『プレニテュードー新しい<豊かさ>の経済学』 稼ぐためには長時間働かなくなければならなくなり、労働時間が長くなると幸福感も減る 広井良典『定常型社会ー新しい「豊かさ」の構想』 セックス・アンド・ザ・シティ=知性のかけらもない話(笑)買い物リストを埋めていくことが幸福 スウェーデン映画「さよなら、人類」信頼の交換 市場で求められる価値は変わっていく 新しい、見た目がいい、機能が多い、高級→かかわっている人の顔が見える、信用/信頼できる、長く使える、公益的=本質的な消費
0投稿日: 2020.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ沢山働いてお金を稼いで、ブランド物や高級車を買うのが幸せだと思われていた時代から、もっと別の価値観へ変わりつつある今について書かれた本。 もっと周りの人とのコミュニケーションを取ったり、自分が納得できるものを少しだけ買ったりして、充実した日々を送ろうとする人が世界中で増えているらしい。 ライフスタイルの雑誌である「KINFORK」などがその代表例。シンプルでとても美しい写真で、オーガニックで心が満たされるような日々を提案している。 確かに今、価値観が変わりつつあると肌で感じる。 世界で一番インフラが整った安全な国の日本が、長時間労働で幸福度が低いのもそろそろ考えなくては いけない時が来ていると思う。 全世界でデータを取ると、やはり労働時間が長いほど幸福度は下がるらしく、つまり人間は仕事中じゃなくて自由な時間に好きなことをしたり、家族や友人とすごしているときに、幸せを感じるんだと思う。 誰もが広告やCMを鵜呑みにして消費社会をひた走った日々は今終わりを告げようとしている。 著者はそれは資本主義の成熟で、これから各自がどんな風に時間 を使って充実した日々を送るのか考えるいい機会なんじゃないかと書いている。 たとえば洋服でいえば、ヨーロッパに若者は蚤の市(フリマ)で買った安い服を上手く合わせてカッコよく着こなしていたりするが、日本人はぼくが学生だった頃(90年代後半)はみんなヴィトンの財布やバックを持って喜んでいた。 今の中国なんかはまだその頃の日本のように、高級品至上主義のようだけど、貧しいところから成長する段階だと、そういったものに憧れるんだと思う。 日本人もこれからは値段よりも、合わせ方やシルエットの大切さを多くの人が知って、オシャレな人が増えるといいなと思う。 といった興味深い事が沢山書かれていて、全部書くと長くなってしまうのでこの辺にしておきますが、すごく面白いし、資本主義が向かう先がどうなるかがとても楽しみになりました。 この転換期に生きる自分も、どのように時間を過ごし、充実した日々を送るのか模索しながら楽しく暮らして行きたいと思います。 多くの人に読んで頂きたい、素晴らしい本です。
0投稿日: 2020.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本の冒頭で紹介されているドキュメンタリー映画「365日のシンプルライフ」をちょうど観たところだった フィンランドのヘルシンキでペトリ監督が1年間、モノを買わない&部屋に置かない(今まで部屋にあったものは倉庫に保管して1日1点だけ自宅に持ち帰っていいというルール) 「もう欲しいものは特別ない」 という彼の感想に納得したのは私だけではなかったんだな…と思った。 物を買う=幸福=満足 ではなくなってきた現代 この流れは世界的なものなのか? 著者はふたつの超大国についてもリサーチしている つまりアメリカと中国 中国というと「爆買い」のイメージが強い 著者によると中国の人々の「物欲」も変化しつつあるという。ロハス的な生活スタイルにシフトしようとする人々も登場し始めているのだとか。とは言いつつもまだまだ少数派…。でもそこは中国。人口比に比べて少数派でも巨大な市場につながるというのだから人口の多さは侮れない。一方、欧米のブランドを支えている購買層の多くはなんと中国人だそう。 著者は社会発展の過渡期として「物欲」が生み出されていくという。 ではアメリカはどうかというと、ポートランドに代表されるロハス的な生活スタイルやストーリーのある物作りなどで若者によるムーブメントがどんどん広がっているという さて日本はどうだろう? そしてどんなムーブメントが巻き起こるのか? ポイントは「シェア」なんだそう ものをシェアするだけでなく子育てなどもシェアしていくスタイルになるのでは…とのこと。 そして今後世界で注目されているのが「お金」 子供でもお年寄りでも持つことができる 電子マネー的なものが今に登場するのではないだろうか? コロナ禍でお金の持ち方も変わってきた そして生活スタイルも大きく変化した 人々の価値観もコロナ禍で大きく変わってきたように思う 物ではなくまた違う何かに人々の欲望が向いていく さてさてそれは一体何なのだろう…
13投稿日: 2020.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログやはり資本主義は終わりを迎えていると再確認。 貨幣よりも信頼に価値が出てくるというのは、『シェアライフ』と同じだった。 物を持っていること、金持ちだということが幸福とは限らない。まだまだ気づいていない人も多いのではないだろうか。
0投稿日: 2020.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログライフスタイル ファッションからライフスタイル自体がファッション化している ライフスタイルは切り売りではなく、時間をかけて自分たちのものにしていく。 ノームコア カスタマイズにより、ゴミは無くなる 需要から供給へつなげる お金の支払いにありがとうを載せる SNSにより、自慢がしにくくなった。周りが見えすぎるせいで。 →だからモノの方がどんどん下がっていった。
0投稿日: 2020.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 モノをできるだけ買い集めることがいずれ懐かしいノスタルジーになる。世界中で計測されたのは、これからの地殻変動。この本はその胎動を、僕たちにいち早く教えてくれる。
0投稿日: 2020.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
モノの溢れる世界でファッションは衰退。次の時代の売り物は「ライフスタイル」。ラグジャリーよりオーガニック。電子マネー以降の決済システムから貨幣論へ、自己実現から幸福論へと話は広がる。最終的にはミニマリストかっていうと、そうでもない。つくづく人間って面倒臭いよなあ(笑) あ、ガルブレイスのベストセラーは「ゆたかな世界」じゃなくて「ゆたかな社会」ですな、細かい事ですが。
1投稿日: 2020.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人差もあるだろうが、私自身、最近物欲がなくて、周りもそういう傾向があるような気がして、では、何故物欲がなくなってきたのかと。一つには、物欲はあるのだが、年収が上がらず税金や通信費の負担が増えた事から、単純にお金を使えなくなったという事。SNSの普及が、物理的に近くの友人関係における価値基準に囚われる事から解放し、価値観の多様性を後押ししている事。これにより、アレを身につけている事がステイタス、といった意識が変わってきているのではないだろうか。残念ながら、本著によるこうした考察は浅く、やや物足りない。面白かったのは、最終章における資本主義の先にある幸福の話。年収に上限を設けるような、共産主義との折衷策はありだな。ただ、地球規模での税制と、富の再分配が前提となる。資本主義を進化させるには、地球規模での法令が必要。難しい議題。
1投稿日: 2019.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近なんとなく感じている、消費する事への虚しさみたいな事。 反面で若者に物欲が無くなっている、という経済の落ち込みに対する不安もある。 今はモノではなくコトを売る時代だし、色々なものをシェアリングする、その流れも必然だとも思う。 ただ、なかなか物欲は無くならない。ネットで欲しいものを検索している自分がいる。
1投稿日: 2019.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・ファッションからライフスタイル消費への移行。 ・情報が圧倒的に増えたため、関係性の中でしかモノの価値を認識できなくなった。自分がエンゲージ(関与)したものしか欲しくないとか。心を満たすかどうかがより重要に。 ・市場で求められるものの価値基準の変化。 新しい、見た目がいい、機能が多い、高級という価値より、関わる人の顔が見える、信用信頼できる、長く使える、公益的といった価値に重きが置かれるように。 ・物欲が減ると、人々はサービスやアクションを欲するように。
0投稿日: 2018.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ技術革新により、労働がなくなっていく世界、「楽園」はつまり、少数の仕事を奪い合う世界でもある。それは慢性的で宿命的な不景気とほぼ同じことである。 「物欲なき世界」とは、資本主義末期に宿命的に進行する不景気から逃れるための処世術なのか。あるいは単に我々が「消費疲れ」を起こしているのか。 ただひとつ言えるのは…モノを消費することが幸福の象徴である、とされた時代は遠退きつつある、ということだ。 個人的にはかなり関心のツボにハマって面白かった。 P23 <ファッション誌はもはや一般紙ではない> 今までは間違いなく、ファッション誌が一般紙として雑誌文化の中心にありました。(略)誤解を恐れずに言うならば、一般紙だったファッション誌がオーディオや兵器などの趣味雑誌と同等のものになりつつあります。要するに万人にとってジェネラルなものではないということ。(略)どれだけ素晴らしい内容のファッション特集を作っても、ある一握りの人たちのためのものになってしまい、結果としてセールスを作れない。だから一般紙として生き抜くために、もっとライフスタイルの方を取り上げることが大事かもしれないと考えたんです。 (大手有名雑誌が軒並み、ファッションだけでなく、ライフスタイル特に食の特集に力をいれいてる) P33 これからの消費行動がコミュニティ・ビジネス化していくことを示している。 P34 消費は投票である(消費とは単にものを買うだけではなく、その理念や行動に賛同した上での行動である、ということ) (アメリカではロハスなあり方が一般化している。中国ではまだまだ少数派で、一般大衆はラグジュアリーな消費を目指すが、一部ではそのようなあり方を疑問視する消費者もいる。中国国内では少数派だが、13億もいるので1%でもかなりの市場規模となる) 3Dプリンターという”ミシン” ・3Dプリンターはかつてのミシンのように、ネットと繋がることで、生産の手段も民主化した。アメリカでは「カスタマイゼーション」というのが大きな流れとなっている。 ・プロダクトデザイナー、深澤氏いわく、世の中は「かたまり」のようなものと「くうきのようなもの」のあいだ ・『SFを実現するー3Dプリンタの想像力』 ・『脱物質か社会』(ウェイトレス化) コラボ消費 1プロダクトサービスシステム:所有せずに使った分だけお金を払う:カーシェアリング 2再分配市場:中古品の売買 3コラボ的ライフスタイル:時間や空間、スキルの共有 自宅の空きスペースを宿として貸し出す。 P131 子育てシェアのひつじ不動産、代表甲田氏 「小さい子と向き合っていればストレスが溜まるのは当たり前ですよ。それをママが一人で抱え込む。両立できなくて仕事をやめると、世帯収入が減ってよけい贅沢できなくなって引きこもる。親が引きこもると子供は色々な価値観や社会性を学ぶ機会が減る。人に頼るのはよくないことなんだと子供は潜在意識に刷 り込まれてしまう。そして思春期以降に孤独感を強くいだいたり、自分を価値のない人間と思ってしまったりする。すべての根元は引きこもり子育てなんですよね。だから子育ては頼った方がいいんです。オンラインでの繋がりとオフラインの地域交流の場作り、この二本立てで様々な課題を解決できるよう、どんどん広めていきたいと思っています。」 P135 シェアリングとは必然的に他者とのコミュニケーションを産み出す。それが広がれば、コミュニティが形成される(はず)。そのときに重要視されるのが、お互いの信頼度だ。(略)「(略)オンラインでの取引は(略)テクノロジーが古いかたちの信頼を新しい形に変えているのだ」 P169 人々の食に対する関心はますます高くなっているが、反対に先進国の人々のラグジュアリー製品に対する消費が落ちているという調査結果がある。 (このしょうでは、スタンフォード卒の女性農家をとりあげ、アメリカではオーガニックな食品にたいする需要と関心が高まっていることを述べている) 資本主義の「両の車輪」 「最大多数の最大幸福」と「少数による利益の独占」 (現在の資本主義は人工的には少数の大口株主(資本家)が株式市場を動かし、収益の最大かを目指している。つまり彼らの最大の利益効率を求めるシステムとなっており、民主主義からはほど遠い) P218 いままでは、市場事態が拡大することでこのふたつが奇跡的に両立していたがそれが崩れつつある。 そのひとつの兆候は若年層の失業率の高さ(世代間の格差)。 もうひとつは先進国は全体としての経済背長がないため、国内において富めるものと富めないものの格差を拡大させることで、資本家が利益をだそうとしている。(略)このような失業の増加と格差の拡大によって、民主主義を支える中心的母体である中産階級が急速に痩せ細っている。 (略)健全な民主主義社会を維持するには、中産階級が大きな比重を占め、富裕層と貧困層に二極化しない社会であることが重要とよく語られるが、(いまの日本では)急速に中産階級の層が減り、二極化が進んでいることが浮き彫りになっている。 <中間層が没落すると消費ブームが戻らない> P221この(経済の)グローバリゼーションの影響をもっともうけているのが、先進国の中間層だ(人件費の安い国へ仕事がアウトソーシングされることにより仕事、賃金が減る)。(略)世界的な物欲レスの進行は、中間層の没落と密接な関係があるのだ。 P222 <「楽園」とは?> 技術革新により 「働かずともすべてが手に入る楽園」にちかずづくと、 少数の労働で多くの生産があげられるようになるということは、その少数に富が集中するということである。先進国の富の集中を裏付ける。 これを極限にまで推し進めると、「すべてのものを働かずに手に入れられる”楽園”」では、成果のための給与が誰にも支払われないということになり、結果として全員が現金主丹生ゼロの、慢性的失業率100%という状態に陥ることになる、という。 経済成長が極端に進んだ「楽園」的な国には、少数の者だけが働き、多くが失業する釈迦になる。まさにヨーロッパで、そしていまの日本で起きていることもこれに近い。 P228 これからくるであろう三度目の定常期(量的には成長しないが質的な豊かさを求める社会の時期)は、経済の量的成長はほとんどないが、より少ない資源でより質の高いモノやサービスを産み出すための技術革新が求められ、技術やサービスの向上を巡る競争は高まると広井氏は予想する。 P234 経済が豊かな成熟を迎えるために、私たちは何をやればいいのか。 井手氏は「互酬と再分配のための新しい同盟関係を構築するか、市場経済に屈服するか。私達が立たされているのは歴史の岐路」という二つの可能性を示した。 市場経済に屈服しないためには、偏りのない搾取と再分配が要求されるが、そのいちばんの壁は大企業による税金逃れである。 それには、巨大企業に対抗する世界国家の構想が必要である。 P241<モノが幸福のシンボルではなくなる時代へ> ここで「消費が意味を持たなくなる」であろう、来るべき「物欲なき世界」のがいようをまとめてみよう。まず私たちの日常を取り巻く日用品/コモディティは、グローバリゼーションの中でますます低価格化するだろう。一方で高級ブランドは意図的にさらに高級化し、一部の富裕層をのぞいて人々はそれに対する憧れや渇望を失い、または時代遅れと見なすようになる。またオーダーメイドやハンドメイドはより普及するだろうが、それらは属人性が強すぎるが故にその人のブランディングにはあまりならない。そうなると、自分が買うモノがその人を雄弁に語ることが少なくなる。日用品以外の、あこがれのある、夢のある消費というものが急激に減る時代で、人々は自分の欲望の再確認を迫られるだろう。 一方で「私(たち)が欲しいものは、私(たち)が作る」という考えは、名カームー部面との恩恵もあり、ますます定着するだろう。欲しいものは、自ら関わる、作る、交換する。受動的消費から、主体的かつ参加的消費/生産が奨励されるだろう。 市場で求められていくものの価値基準も変わるだろう。新しい、見た目がいい、機能が多い、高級といった価値よりも、関わっている人の顔が見える、信用/信頼ができる、長く使える、公益的といった価値に重きを置かれるようになる。でも、よくよく考えれば、後者の方がきわめて本質的な消費だということがわかるはず。私たちは、自ら欲するモノを買っていたのではなく、本来は欲しないモノを半ば恣意的に買わされてきたことにようやく気づいてきたのだ。 20世紀後半の高度成長、大量消費・大量生産の時代は、幸福は買い物リストを埋めていくことだった。ラグジュアリーな服、高級車、大型家電、マンションまたは家、さらには別荘と、それらを購入し、買い物リストを埋めていくことが幸福の証とされていた。『セックス・アンド・ザ・シティ』はまさに買い物リストを埋めていくことがドラマだったといえる。社会学者のジグムント・バウマンは『幸福論ーいきづらい時代の社会学』野中で見事に指摘する。 「モノやサービスを購入することが幸福につながると考えて没入することは、常にお店で消費することをしいられる。このマーケティング至上主義の成功は、逆に悲惨な反動を生み出す。幸福の自己追求は、常に消費し続けることが当たり前かのような最悪の結果を伴うのだ(筆者訳)」。 しかし低成長下、さらには定常化社会に向かう中で、シェアやレンタルが当たり前の「物欲なき世界」に突入し、買い物リストを埋めることに積極的な意味を持たなくなると、幸福のあり方が変わらざるを得ない。つまり個人の思想・信条が強く含まれているが、他社とも価値観を共有できる「いい物語を持った人生」が最大の幸福になるだろう。 参考文献 経済の時代の終焉 井手英策 ラトゥーシュ 脱成長は世界を変えられるか 広井良典 定常型社会 新しい豊かさの構想 ジャックアタリ 21世紀の歴史 365日のシンプルライフ ピケティ 21世紀の資本 水野和夫 資本主義の終焉と歴史の危機 ピケティの提案する解決方法 世界的な累進課税
1投稿日: 2018.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ『「くらし」の時代』で何度か引用されていたので借りて読んでみた. モノを買ってもなんだかワクワクしなくなってきた?というあたらしい自分を発見しつつある,40代に乗っかったばかりの自分. お金を使ってモノを手に入れるのではなく,どれだけ豊かに感じられる時間を過ごせるか.自分の興味がどんどんそちらに向かっている中,じつはその傾向は自分が年をとったからだけではなく,社会としてもそちらに向かっているという,自分の物欲停滞感と「物欲なき世界」がじつはシンクロしていたという発見がありました.
0投稿日: 2018.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログいかに世界から、特に若者から物欲がなくなっているか極めて冷静に教えてくれる本。 資本主義の終焉も示唆されている。今、読んでおくべき本。
0投稿日: 2018.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の価値を高める。ライフスタイル。だんだん興味がなくなりつつある。所有欲は減りつつ…あっ積読笑 中国。シェア。3Dプリンタ。 いつだって中途半端な世界。ピケティよ。日本はやはり成長しないのか…
0投稿日: 2018.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ大量生産・大量消費の経済が崩壊つつある現代の世の中をどう生き抜くか。 DIY・シェア・リサイクルなど、ムダな消費を控え今あるものを有効に活用することがそのヒントになる。
0投稿日: 2017.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ色んな人の言葉の引用や、様々な国の状況が細切れに登場して具体例はてんこ盛りだが、筆者が語る言葉が少ないように見えた。そもそもこういったトピックは語り尽くされていて、特に真新しさは感じなかった。雑誌のようにビジュアルとセットならば、響いたのかも。
0投稿日: 2017.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ健康的、幸福、心地よい コモディティ化の反動で、個人的に好きなもの、心動かされるものを選ぶ 何かを買う行為は、その団体や会社を支援すると表明する行為 成長の限界(資本主義の限界)に突き当たり適応する事に関して先進国でもあると捉える?
0投稿日: 2017.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ライフスタイルと欲求の変化」から始まり、「オープン化」「シェアリング・エコノミー」「格差」といったトピックは様々。 「○○離れ」は悪いことでもなんでもなく、次なる社会や体制に脱皮するためのサインではないかという、なかなか興味深い一冊でした。
0投稿日: 2017.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ過去の読書会のうちで、評判の良かった課題本なので図書館で借りた。読む前は、ミニマリストについて語っている本かな?と思ったが、ミニマリストについての話というより、そのようなあり方が一種の流行となっている現代において、どういう広告・商品を提供するのがいいのか?これからの日本経済はどういう方向へ向かうか?について論じている本。著者が雑誌の編集長だからなのか、新聞記事みたいな文章で読みづらかったし、主張内容に目新しさは全くなかった。
0投稿日: 2016.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016.07.29 マーケティング、広告を生業にしているものとして多くの示唆をもらった。この本の中で紹介される本のいくつかはすでに読んだが、著者の視点が加わることで改めて今後のあり方を考える良いきっかけになった。次の時代の構想をしなければならないと再認識した。経済の時代から○○の時代へ、その中で経営やマーケティングは、教育はどうあるべきか?難しい課題だ。
0投稿日: 2016.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこれといった強烈な着眼点がある訳ではないので、5年前からこんなことを言ってるなぁ〜、5年後もこんなことを言ってるだろうな〜と乱読しました。 ●定常型社会の概念 「経済は物質的な富の拡大という目標が目標として機能しなくなった今、それに変わる新たな目標や価値を日本社会が見出さないでいるところに閉塞感がある。景気対策のみをしていることに病理や社会不安の根本原因がある。」 と終盤出てきて行き詰まってしまった。 面白い記述はモノは人間の身体と壁の間にあるということ。壁に寄って行ったものは機能だけ残し消滅した。
0投稿日: 2016.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ分析というのは、物事が発生してからでないと出来ない。 と、誰か偉い人が言っていたような気がする。 ミネルヴァのフクロウは夜飛び立つとか何とか。 著者が編集者という性質からか、様々な立場の人の言葉や考えを紹介しているような印象が強いです。参考文献を探すための手引き書、という感じ。私はあまり読み応えを感じませんでした、気になる本は幾つか出てきたかなー。 「資本主義」が終焉を迎えた先に何があるのか。 新しい世界に直面している事を、多くの人が感じ取っている。 経済とは社会を構築する一部分でしかないが、あまりにも大きく支配的であったという文章が出てきました。 だからこそ、これだけ力の強かった「資本主義」の限界が見えたとき、まるで大国が崩壊することの恐怖や不安が蔓延してきている…のかな? そんな私は、「どんな社会が来るのかなー」とワクワクしている一人です。 有機的な超個人主義社会が来てくれるといいなー。他者を重んじられる、戦前のムラ社会とは異なった、信頼を基本とした柔らかい社会。どうだろうなー、実現は難しいけど。 色んな予測をたてられるのは楽しい。もっと色々勉強しなきゃ!
0投稿日: 2016.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分的には文章が少々読み難かったですが、ポスト資本主義の可能性を多岐に渡る切り口で示唆しています。 ・これからのブランドはトレンディーなだけじゃなくて、意味があるものにならないといけない(P60) ・人類の長い歴史の中で、服が自分たちで作るものから既製品を買うものに変化したのは、わずか半世紀ばかりのこと(P89) ・コンテンツは無料のものも多いし、物欲よりもはるかに自由にいじって楽しめる(P139) ・人々はみな長年にわたって、懸命に努力するようにしつけられてきたのであり、楽しむように育てられていない(P254)
0投稿日: 2016.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
物欲をもてあましてルミネをふらふらして、 ユナイテッドアローズに入ったらピクルスとかふりかけとか売っている。 その近くのBSHOPでは、バケツやほうきや軍手をすてきな感じで売っている。 最近のルミネはどうなってるんだ。 といいつつ、自分自身、ライフスタイルブームにまんまと感化され 「&premium」を舐めるように読んでいる。 このままでは職人が作り上げるうつくしい櫛とか(1万5千円)、 世界でひとつの山ぶどうのカゴとか(5万)に手を出しかねない。 そんな自分に冷水を浴びせたくて読んだ本書。 ライフスタイルブームを論じた本って今のところ他にみたことがない。 どちらかというと物欲にまみれているのが悩みだけれど、 だからこそ物欲なき世界というタイトルに心惹かれた。 だが読んでみると、あまり物欲はおさまらなかった。 なぜなら、このライフスタイルブームに対し、 著者がとことん礼賛姿勢、批判的視点がないのだ。 印象に残ったのは、 先進国の人々はもはやモノを得ることへの欲望から、 使うことへの興味にシフトしている。資本主義社会の成熟の証ってところ。 得るから使うへ、という対比はわかりやすい。 でも、使うという目的に対して結局物欲が向かっているのは私だけだろうか。 すてきないいものほしいほしい!と渇望する人々より、 もうモノなんていらない、上質でていねいな暮らしを営みたい と言いながら数万円の山ぶどうのカゴを特注している人間のほうが、 欲望の業が深い気がするのは私だけだろうか。
0投稿日: 2016.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まさに時代は変わりつつあります。 今の若い世代は贅沢にお金を使う事自体を 諦めているという点もあるかもしれませんが、 人生の中で、 お金を追い求めるということに対して 高い価値を感じていない。。 そういう時代になってきているのだと感じます。 この本は本当に勉強になりますよ!!
0投稿日: 2016.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近流行りの、モノをほとんど持たない、いわゆる「ミニマリスト」的な生活についての書籍、という訳ではなく、資本主義社会によって産み出された大量消費・物欲社会の行き詰まりという現状認識から、既に先進国で始まりつつある物欲なき社会という近い未来社会への移行について論じている、経済社会に関する内容。後半からかなり興味深い内容だった。まぁ、前半は、アメリカのポートランドの様子、モノでは無くライフスタイルが売り物になりつつある状況、先進国の若者の間の消費離れ状況などのレポートが中心。大量生産された既製品の大量消費社会というのは実にこの50年ぐらいの短い歴史であることや、近年の自分でモノを作ることを楽しみながら最低限の消費、量から質への転換を見つつ、後半は貨幣経済や現代の電子マネー、ビットコイン、信用取引などの根源について論じていて示唆に富んでいた。既に誰もが感じている種々の資本主義社会の行き詰まりは、このシステムではもはや解決できない転換点に達しているのかもしれない。次の社会へのソフトランディングは無理なのかも。本書を読むと、アベノミクスがやっていることは、完全に前近代的な、終わりつつあるマネー資本主義の論理の枠組み内におけるその場しのぎで、手段の目的化に過ぎないなぁ、と感じた。だからと言って、次の社会を目指して世界をリードする度胸と知恵がなければ、「この道しかない」のかもしれないけど。
0投稿日: 2016.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初の数十ページしか読んでいないけれど、ちょっと想像と違う内容だった。もっと「モノ」に対する精神論的なことや、文化的な変遷が語られるのかなーと思っていたのだけれど、実際はライフスタイル誌の変遷や、セレクトショップの複合化などを、いろんな人の引用でまとめている内容。雑誌名や人の名前ばかりがシャワーのように浴びせられ、肝心の内容があまり入ってこない。読みづらい本だったので、途中で断念。
0投稿日: 2016.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ資本主義が成熟し完成形に近づくと成長が、とまり定常型社会になる。 知識、関係、信頼、評判、文化がこれからの経済に、変わる価値。 市場での価値も信頼性や公益性に置かれる。 自分が何が欲しいかを経済の言葉でなく語れる人が来るべき物欲なき世界を謳歌できる。 成長が見込めない先進国で利潤を追求すれば収益は少数の大株主に集中し、格差は拡がる。 富と仕事は少数のものに集中する。 経済成長しても中間層の賃金は上がらない。 鍵は富の再分配。 割り当ての最初の配分は国に割り当てられる。 キャップオークショントレード ハーマンデイリー エコロジー経済学 難しいのであとで再学習
0投稿日: 2016.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ファッションブランドが従来の売り方から、ライフスタイルを重視していく方向へシフトしていっている。アメリカ、中国という大国では、従来の消費主義から少しずつロハス、スローライフというった脱消費主義の芽が出てきている。 つまり世の中の価値観は、物欲なき世界へと少しずつ移行していっているのだ。 ルームシェアやカーシェアリングが近年増えてきている事も、所有より共有の方がコストが低くてすむ証明である。それと共に、高価な物質の所持によるステータスよりも、効率よく共有する方が賢明であるという価値観に変わってきているというケーススタディを多く用いて説明している。 後半ではお金=幸せという形に疑問を投げ、事実データとして、そうではない結果が出ている事を述べた上で、これからの時代における資本主義社会の限界と離脱が書かれている。 う~ん、確かに一部分でそういった動きは見えているが、まだまだ資本主義から抜け出すというのはイメージしにくいのが本音のところかな。とはいえ、そういう動きに目を向けるきっかけになったかも。
0投稿日: 2016.02.18なぜ、「モノを持つことがダサい」時代になったのか?
車、時計、宝飾品、奇抜なブランドものの服、靴、高級オーディオやテレビ、家電・・・・形のあるものが売れないと言われて久しい昨今、一体何が起こっているのか。元「エスクァイア」「Cut」の編集者が自身の体験と、多くのインタビューを通して考察する一冊。 著者は学者ではないので、客観データに乏しいと感じるところはあるが、多くの体験・世界中の事象からまとめられており、説得力がある。 消費のパラダイムシフトを読み解く良著だと思う。 ・モノが売れない、欲しくない、むしろモノに縛られることがダサい ・モノ(ファッション)を通して、自分を表現し、他人より優れていることを示す必要がなくなった ・この現象は日本だけでなく、あらゆる先進国で起きている ・それはインターネット・情報化による、「作ることに金がかかり環境負荷の高いモノ・ハード・アトムの世界」ではなく、 「サービス・ソフト・バーチャルの世界」への変化が背景にある ・その変化を紐解くキーワードが「ライフスタイル」という言葉。その具体例が掲載されており、 アメリカの一田舎町だったポートランドが全米で最も住みたい街になっている理由はそこにある ・代官山ツタヤ、ツタヤ家電が生まれた文脈も同じところにある。 その代官山ツタヤで一番売れている洋雑誌は「ヴォーグ」ではなくポートランドで創刊された「キンフォーク」 ・今流行りのシェアリング・エコノミーの解く鍵も同根にある ・ライフスタイル的な生き方は、働き方の価値観にも大きく影響を与えている ・地方再生や、若者の農業への回帰、スローフードなどの動きも同じ文脈でなぜ注目されるのか見えてくる ・経済成長がなくても、文化の成長が人間の幸福度を高める。むしろ、経済成長を第一義にしていたこの数十年は特殊な時代だった 「文化の成熟」がこれからの時代のキーワード。 今起きている世の中の変化が、一体何なのか考察するのに適した良著。 社会の変化に興味がある人は是非。 ※資本主義そのものに対する考察はちょっと素人の思い込み感が強かったので個人的には「ホンマかいな」と思いながら読んでいたので★は4つ。
9投稿日: 2016.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の菅付雅信は、雑誌「月刊カドカワ」、「エスクァイア日本版」等の編集部を経て、「コンポジット」、「インビテーション」、「エココロ」の編集長を務めた後、独立し、現在は出版からウェブ、広告、展覧会までを編集するグーテンベルクオーケストラの代表である。 本書は、著者が「もう欲しいモノは特別ない」と感じる人々が増えているという実感に基づき、自ら世界の実態を確認し、その後に来る世界の在り方を考察したもの。 前半は、ファッション・ニュース・サイト「MODE PRESS」に2013~14年に連載された「ライフスタイル・フォー・セール」をベースにして、世界の高感度な人々の消費の動向が紹介されている。具体的には以下のようなものである。 ◆“ライフスタイル”が消費のキーワードとなり、生活や生き方をテーマとしたライフスタイル・マガジンと呼ばれる雑誌やライフスタイル・ショップが急増している。 ◆大量生産の商品ではなくカスタムメイドの商品が指向され、3Dプリンターなどのデジタル工作機械の急速な普及がそれを加速化している。 ◆自らが所有するのではなく、他人と共有することを前提とした、ハウス・シェアリングやルーム・シェアリング、カー・シェアリングなどが急速に拡大している。 ◆それらの結果、消費行動がコミュニティ密着型に移行しつつある。 そして、後半では、いずれもベストセラーとなったトマ・ピケティの『21世紀の資本』、水野和夫の『資本主義の終焉と歴史の危機』のほか、広井良典の『定常型社会』など、多数の経済学・社会学の書籍を引用して、資本主義の限界とポスト資本主義の社会について考察している。 即ち、我々が過去数十年に亘って過ごした、資本主義が機能していた社会は、「少数資本家による市場の占拠と彼らの利益の最大化という強欲な利己主義と、最大多数の最大幸福を目指す民主主義の平等主義の、対立するふたつの考えが共存する」社会であったが、その奇跡的な両立を支えていたのは、全体として経済が成長してパイが拡大する世界の存在であった。しかし、今や地球上のどこにもフロンティアは残されておらず、経済全体が拡大しない世界において、資本主義は、限られたパイの奪い合いにより、(若者の)失業率の上昇と格差の拡大を引き起こすという大きな問題に直面している。そして、それらを乗り越えるためには、「脱成長」を前提とした社会、即ち、資本主義を越えた社会を作らなくてはならないというものである。 そして、その目指すべき社会とは、世界の一部の人々が(「資本主義の限界」をどこまで意識しているかはわからないが)既に指向している、前半に示された“物欲なき世界”そのものであり、「そこにおいて幸福は、より個人的で、かつ普遍的な価値を共有出来るものに向かう。つまり個人の思想・心情が強く含まれているが、他者とも価値観を共有できる「いい物語をもった人生」が最大の幸福になるだろう」と結んでいる。 もともとはマーケティングの視点から書かれた著作と思われるが、後半の考察は現在の経済学・社会学の最大のテーマに切り込んでおり、タイムリーかつ内容の濃い作品となっている。 (2015年12月了)
1投稿日: 2016.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ中身が全てサンプリング的な内容で著者自身のクリエイティイティはあまりない。サンプリングの内容のうち、自分自身あまり知らない世界である1章や2章は、ファッショントレンド的視点での時代解釈で非常に興味深かった。一方で自分の関心の高い後半の経済や幸福論に関する章は、ありきたりの内容の紹介にとどまり、目新しさはない。そして物的欲求に関心がない層というのも、先進国においてもマイナーな部類であり、ましてや大多数の発展途上国に住む層については、まだまだ物的欲求をクリアできるほどの豊かさには至らず。そういう意味でグローバル的にはあまり説得力がない。
0投稿日: 2016.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ良くも悪くも2010年から15年ぐらいの消費の価値観の変化総集編って感じ。後半の資本主義の終焉みたいな話は10年ほど前から言われてることの焼き直しがだいたいで、思想に根本的な目新しさは特にない。チェックリスト的に把握してる流れを再確認するにはいいけど。
0投稿日: 2016.01.02
