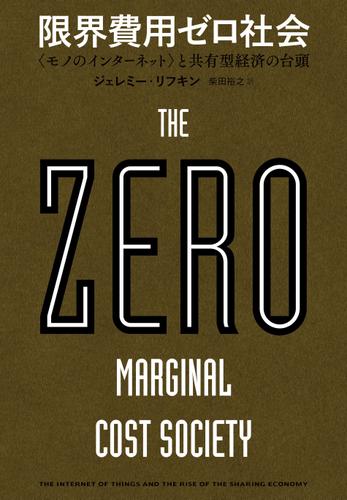
総合評価
(59件)| 9 | ||
| 25 | ||
| 18 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログIoTを中心としたインターネットの発展によって、財やサービスを1ユニット当たり生み出す費用がゼロになる。物質を追求する資本主義社会から、他者との親交を追求する協働型コモンズの社会が到来するという、2015年当時では先進的な主張が展開される。 限界費用ゼロになるというのは、ケインズが「100年後に人間は労働から開放される」と主張したものの、人間の飽くなき物質的追求欲を見誤ったように極端だとは思うが、先進国のGDP的成長率が低減していく中で、「本当の幸せとは何か」を考える風潮や世代は増えている。テクノロジーの飛躍的進化を享受した後、人類は何のために何を目指すべきかを考えさせられる良著。事例は冗長に感じた。
1投稿日: 2024.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ資本主義から協働型コモンズに世の中が変化していくこと、またそれによって、テクノロジーによるコミュニケーション、エネルギー、輸送に関する変化、それによりビジネスや人の生活が変わっていくこと、その上でどのように生きていかなければならないのかを少し考えさせられる本。 第一次産業革命から、世界の革命による変化の歴史を知ることができること、今すでに限界費用が限りなくゼロに近づいている教育などの具体的事例なども解説されており、勉強になった。 読んでいてまだ理解が難しい点、読みにくい点も多かった。また改めて読み返したい。
0投稿日: 2024.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ所有しない経済。クラウドから好きなコンテンツを楽しみ、3Dプリンタによるインフラに居住し、シェアリングされた車で移動。ユニバーサルアクセス可能な電力やネットワークを使い、バーチャル空間で人間関係を満足させ、性欲を満たす。 資本主義の跡継ぎとして共同型コモンズで展開されるシェアリングエコノミーがある。そうする事で過剰な生産が抑えられ、地球にも優しい。人間の労働にもゆとりが生まれ、貧富の差も縮小する。 理想は分かるが、これだとグローバル公共経済を実現した共産主義にならねばならず、プラットフォーマや、そのシェアリングインフラを保守、提供する側のモチベーションはどのように保たれるのか。脱成長論は究極的にベーシックインカム民族と、インフラ維持民族に二分される?ような印象だ。インフラ維持勢のみ子作りトークンを配る?面白そうだが(この本には、そんな事書いてない)、結局、経済モデルが示されないと、社会が緩慢にしか動いていかない。現状資本での利益を獲得できるだけ、その転換を引き伸ばそうとするからだ。 確かに、世界のGDPの伸びが鈍り続けている。エコノミストはその原因を高いエネルギーコストや人口動体、労働人口の伸び悩み、消費者と政府の負債、世界の収入のうち富裕層に回る額の増加、出費を嫌う消費者による買い控えといったものを指摘するが、財やサービスを生産する限界費用が様々な部門でゼロに近づくと言う理由も関係している。だが、段階的にだ。車を所有する人がある時からゼロ、とはならないように。 そしていまだに、人口の2割が電力の使用に不安があり、他の2割は電気のない生活を送っている。女性の解放に必要なものは、電力。電力へのユニバーサルアクセスが可能になれば、女性が勉学に勤しみ、家事から解放されることで出生数は下落。これにより、最貧国の人口の急増にも歯止めがかかり、先進国とのアンバランスな、ヤンキー子沢山問題のワールドワイド現象に片がつく。 変化は、徐々に徐々に。しかし、間に合わないなら、一気に価値観を変えるカタストロフィ。このチキンレースのサーキット場が、社会資本のあり方について、という事だと思う。
9投稿日: 2023.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ全く図表が出てこないのでなかなか読むのに疲れます。IoTしかり太陽光しかり限界費用ゼロの世界観が詳述されます。他方でネットゼロ排出の世界に向けては水素や二酸化炭素の吸収のような途方も無いコストがかかる分野への研究開発・インフラ投資も必要な訳で分野に応じたメガトレンドの見極めは大事になるでしょう
0投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログモノのインターネットと共有型経済の台頭による経済パラダイムの大転換について、3Dプリンター等の事例をもとに変革のメカニズムと未来展望を説明。 メルケル独首相のアドバイザー等を務めるジェレミー・リフキン氏による2015年の書。
0投稿日: 2022.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史上のあらゆるインフラシステムの3要素は①コミュニケーション、②エネルギー、③輸送マトリックス。 歴史的には以下のように変遷してきた。 ・第一次産業革命以前 活版印刷+水車+馬車 ・第一次産業革命 蒸気印刷+石炭+蒸気機関車 ・第二次産業革命 TV・ラジオ+石油+自動車 ・第三次産業革命(現在)インターネット+再生エネ+自動運転 第二次産業革命は希少資源がベースであったため、中央集権的社会を構築。 歴史的に見て、人間の意識の変遷は、神話→神学→イデオロギー→心理→生物圏(他者や他の生物と地球を共有)のように変わっていく。
1投稿日: 2021.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ限界費用ゼロのコモンズ型経済が、教育、環境、エネルギー、格差の問題を解決しうる、という希望にあふれた1冊。実際には、今の資本主義社会の既得権益を受けている「抵抗勢力」に阻まれて実現は容易ではないと思うが、コロナで中央集権的な国家・企業の必要性が問われる今、著者の展望は意外と早く実現するかもとも思う。 限界費用ゼロ社会により、モノの交換価値ではなく使用価値が重視され、物欲主義が克服されるとき、人の「幸福」の在り方も問われていくだろう・・・ということも考えさせられた。
1投稿日: 2020.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
5年たって、この本が言ってきた方向にきたものとそうでないものを分けたのが何かのそのそと考えながら読む。まだもじゃもじゃしていて書けない。考える良いきっかけになった。
1投稿日: 2020.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログモノを1ユニット生み出すのに必要な限界費用が、テクノジーとインターネットの普及で限りなくゼロになり、利益が出なくなっている。これは資本主義の究極の形であるが、その性質ゆえに、自壊していくという矛盾を秘めている。 IoTシステムの要は、コミュニケーションインターネットと輸送インターネットを、緊密に連携した稼働プラットフォームにまとめること。 IoTが、出現しつつある協働型コモンズに命を吹き込んでいる。→シェア文化に始まる「協働主義」が生まれ、新たな経済パラダイムを築きつつある。GDPによる景気動向の評価という、社会の考え方が根本から変わりつつあり、その代替品として「生活の質」という新指標を考え直す必要がある。 資本が企業家の元に集められ、労働者が自らの労働力を原材料に加え付加価値(商品)を大量に生み出し始め、資本主義が始まった。 過去においても、蒸気による鉄道輸送というインフラと、蒸気による大量印刷というコミュニケーション手段が、経済と産業のビジネスモデルを一変させた。 こうしたビジネスモデルは大量生産される財と流通を構成するのに、巨大で複雑なモデルを必要としたため、垂直統合型で中央集権化された少数企業が、各業界を独占した。 古来より考えられてきた労働力(財には自らの労働力を与え付加価値を増すものであり、したがってその所有権は労働した者にある)の価値観は、資本家という存在の出現によって大きく変わることとなる。 今後の生産性の向上に大きく貢献するのが、モノのインターネット(IoT)というインフラである。 肝心な疑問は、あらゆる人間とあらゆるモノがつながったとき、個人のプライバシー権をしっかり守るためにはどんな境界を設ける必要があるか、だ。 半導体の性能は2年ごとに倍になるというムーアの法則は、現在テクノロジー分野だけでなく、エネルギー分野(太陽光発電や風力発電の性能とコスト)にも及んでおり、このまま行けば、2040年にはエネルギーの7割を再生可能エネルギーによって生産することが可能となる。 3Dプリンティング 従来の工場は、素材が除去されるプロセスが多い。(原材料を切り刻み、より分けられるため廃棄が多い。) 3Dプリンティングは、溶融した材料をソフトウェアにより一層ずつ積み重ねるため、効率と生産性で有利。また、少数生産による在庫抱えのコストも少ない。 IOTインフラに接続できる環境であれば、エネルギー、製品、輸送手段等がほぼ限界費用ゼロで販売できる体制になると言えるだろう。グラム・パワーという新興企業が、スマートマイクロ送電網をインドの田舎の村に設置して、グリーン電力を供給している。 大企業による大量生産から大衆一人ひとりによる生産が可能となれば、もはや何もないところから現在文明を築くことができる。とりわけ、発展途上国におけるインフラの整備及び貧困の撲滅にはかなり効果的だ。 ガンディーは、分散・協働型の新型経済を提唱し、中央集権化したトップダウン型経済から、上下の差がないグローバルかつローカルな経済にパラダイムシフトすることこそ、人間の幸福に役立つとした。 【教育】 MOOCというオンライン教育の台頭は、従来の教育観を揺るがしている。今まで知識というのは教員から生徒への一方的なトップダウン型教育によって伝えられたものであり、「なぜ?」よりも「どのように?」といった即物的な知識が重要視された。 この先の時代では、知識は「共有」されるものであり、その時代の教室においては教師は生徒達のアドバイザーであり、生徒たちは学問分野の垣根を取り払い、より統合的な流儀でものごとを考え、他生徒との協働型の創造性を発揮させることが可能となる。互いが互いを教え合う時代の始まりだ。 学習とはけっして孤立した営みではなく、人々のコミュニティで最高の結果を出す協働型の企画なのだ。 スマートメーターの設置とエネルギーインターネットの発達により、消費者自体が生産者となり、エネルギーにおける限界費用をほぼゼロへと近づける。また、使用できる周波数帯域の増加により、国に無料Wi-Fiを整備する計画もある。 あらゆるコモンズがフリーライドのせいで破綻すると運命にあるという主張は、オストロムの研究により、個人は市場で私利だけを求めるのではなく、コミュニティの利益や共有資源の保全を優先するということが判明し、覆った。 コミュニティの生活を管理する方法を最もよく知っているのはコミュニティの成員自身であり、そこにある公共の資源や財やサービスは、コミュニティ全体で管理するのが最善であることが多い。 こうしたコモンズは生物学の分野にも及び、遺伝子情報を共有し、特許権を認めない判例が下された。 インターネットというバーチャルスペースのインフラを、企業による囲い込みから解放しようという動きが、ハッカーを中心に行われている。それは、コモンズを商売に利用しようとする企業と、コモンズを開かれた資源として活用することで、限界費用ほぼゼロを達成し世界を繁栄に導こうとする人間との戦いだ。 市場における財産の交換と深く結びついた資本主義に代わり、「所有からアクセスへ」を掲げるシェアリングサービスが人気を集めている。 限界費用がほぼゼロになることの恩恵によって、協働型コモンズにおける経済活動の占める割合が拡大すれば、旧来の資本主義が支配力を失っていくことは間違いない。 商業はつねに文化の延長として存在してきた。そこにはまず文化による成員の社会的結びつきがあり、それに裏打ちされた社会関係資本がある。決して貨幣と商業が、人間の文化より先にあるわけではない。2008年の世界金融危機において、実体経済に見合わないほど膨れ上がった貨幣の価値が、人々の希望や幸福を破壊しつくすのを見た。 【持続可能性】 富裕層と貧困層の間に存在するエコロジカル・フットプリントの不均衡の問題に取り組む必要がある。 物質的主義が富裕層と貧困層の間で不信感を植え付けるのは、その主義が教官という本質を奪うからだ。人間はもっとも社会性の強い動物であり、社会に根を下ろすことを切望する。 ミレニアル世代は他の世代に比べ、共感に基づく関与の増加、他社への支援、LGBTへの配慮、多数の人々への集合知の信頼性が高く、逆に政府、専門家、物質主義への懐疑性が見られる。 この物質主義から人生の有意義性へのシフトは、2008年を境に起こっており、これは協働型消費や共有型経済の急拡大とぴたりと一致する。 【希少性の経済から持続可能な潤沢さの経済へ】 人類史には、たえず自己の枠を超えて、いっそうの進化を遂げた社会的枠組みの中にアイデンティティを見出そうとした、幸福で調和のとれた時代が含まれている。人類の歩んだ歴史を振り返ると、幸福は物質主義ではなく、共感に満ちたかかわりの中に見出される。 ミレニアル世代には、保守対革新、資本主義対社会主義について論じることはない。政治行動を判断するときには、組織がとる行動が中央集権的・トップダウン的・強権的・専有的という性格か、分散型・協働型・透明性が高く、ピアトゥピアなのか、といったこと。 【感想】 この本を読む前は、世の中に出現し始めているシェア・サブスクリプションに対して、あくまで人々の節約を促す一サービス程度にしか考えてなかった。 この本では、そこから一歩踏み込み、環境を持続可能的に、人々を協働に、世界をより水平かつ透明性の高いものに変えていこうとする人々の取り組みや、今後の展望を描いている。 ここで出てくるのが「限界費用ゼロ」という概念だ。 太陽光などのエコ・エネルギーによりモノを動かすコストが限りなくゼロに近づき、 モノの生産にかかる限界費用も限りなくゼロに近づいていく。 そうした究極の資本主義社会の先に待っているのは「資本主義の終焉」なのだから、なんとも皮肉な話である。 だが、本書は資本主義の終焉に対しても「それでいい」という態度を取っている。 幸福は物質主義ではなく、共感に満ちたかかわりの中に見出されるため、 人間が社会的動物である以上、生きる上で大切なことは物質の多寡よりも「社会との関わり」であるからなのだ。 この本を読んでから改めて自分の生活を振り返ったときに、いかに多くのモノが自分の手の内という「閉じたコミュニティ」の中だけに存在していることを知った。
0投稿日: 2020.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ分散型、ネットワーク、ピアトゥピアの関係に基づいた社会の事例を数多く集めた内容です。なんだろう、そんな社会だと多様な人々と関われる機会がそれまでと比べて非常に増える。一瞬ごとの共感を大事にして暮らそう。
0投稿日: 2020.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ長かったが、勉強になった。 限界費用とは物やサービスを作る費用がゼロになること。 これによって、資本主義からのパラダイムシフトが発生するかもしれない。 経済は熱力学的の第一第二法則に支配されていることにエコノミストは気づいていない。 ■第一部 1400年代ヨーロッパを中心に水車、風車の登場で、封建社会の経済パラダイムシフトが発生。 それと同時期に印刷機が発明され、コミュニケーション革命が起こった。 今日の資本主義は18世紀後期の蒸気の動力が導入されてから。 蒸気という強力な動力を得た資本家は、株式会社を組織(鉄道など)し、限界費用を押し下げていった。 垂直統合型の企業の誕生。 電話と電話の普及てさらに限界費用が下がった。 自動車のフォードも電気の恩恵にあずかっている。 現在、少数の企業が、莫大な経済力をほこっている。 自然の摂理を後ろ盾に経済パラダイムを正当化する傾向がある。むしろそれしかない? IoTの登場で、垂直統合型の企業ではなく、分散水平型の経済を生み出す。つまり限界費用がほぼゼロの社会を育み、世界観をかえる萌芽期である。 ■第二部 限界費用がほぼゼロの社会 IoTは生産性を大幅に高める可能性を秘めているが、プライバシーなどのセキュリティ面ではまだ課題がある。 再生可能エネルギー(太陽、風力、地熱、バイオマスなど)も限界費用ゼロになりつつある。その結果、化石燃料による発電所は採算がとれなくなってきており、駆逐され始めている。 遅くとも2040年よりも前に、再生可能エネルギーによる電力が全エネルギーの八割に達すると予測される。 化石燃料は限界費用ゼロには決して近づかないが、再生可能エネルギーは限界費用がほぼゼロになりつつある。 マイクロインフォファクチャリングとは、3Dプリンタのように、情報による製造のこと。 3Dプリンタは製造業の中央集中型の製造体制を根本的に崩壊させる。物作りを特別な企業のものではなく、個人で、考えられる物は何でも作れる世界が近づいているかもしれない。 ビット(情報)を使ってアトム(原子)を配列するというハッカーのアイデア。 アプロプリエートテクノロジーとは、地元で手に入る資源から作れて、協働型文化でシェアできる道具や機械を生み出すこと。 インドのガンディーは水平型の経済力という考え方を信奉していたが、一方で中央集中化されたものが成功しているのを横目に、ある矛盾に気づけなかった、あるいは気づいてはいたが、迷いがあったか? 資本主義体制を突き詰めて新しいテクノロジーが生まれることによって、ガンディーが思い描いていた水平分散型の経済パラダイムがおこりつつある。 教育においても、学習は個人的な経験、知識も専有するものと考えられていたが、協働の時代においては、学習はクラウドソーシングの過程ととらえられている。 サービスラーニングに参加することによって問題解決技能や認知的な複雑性の理解などの能力が向上した。 スタンフォード大学の教授が人工知能の講座をインターネットで開催したところ16万人の生徒がいた。 大学では年間5万ドルの学費を払っているのに無料で提供された。 moocのキッカケである。 世界で最高の教育が限界費用がほぼゼロになり、オンラインでほぼ無料で配信されるとき、それを単位として認められたとき、大学はどのように考えるか。 製造業もロボットの導入で限界費用がゼロに近づいている。 小売業の実店舗も今後は少なくなっていくだろう。 生産性が上がっても労働者は増えない 第8章まで読み進めているけど、社会主義、共産主義みたいに感じてきたんだけど、、、 (クリーンウェブでの着想、市内の避難所案内をルート案内できないものか?) アメリカでは、全ての人に無料のWi-Fiをと連邦通信委員会が提言した。これは既存の通信事業者に大打撃を与えそう。 封建制度下のコモンズではなく、ネットワーク化されたコモンズが、IoT社会の統治モデルとなる。 ■第三部 協働型コモンズの台頭 コモンズは規約がなければ、荒廃していく可能性が高い。 昨今、遺伝子の特許が出されてきたが、ある営利企業に遺伝子、あるいは生命を生むものに対して独占すべきではない。 これこそコモンズによる統治が必要だと説いた。 コンピュータの性能が上がったことによって、DNAの塩基を解析するコストが急落しており、限界費用がほぼゼロに向かっている。 数年前までは限られたエリート集団にしか許されなかった研究が今や誰でも可能になってきている。 ITと生命科学の一体化。生命情報をどのようにするか最も興味深い情報とビル・ゲイツは述べている。 この考えに近い人々はピアツーピアのコモンズ方式が適していると考えている。 しかし、ビル・ゲイツはソフトウエアをフリーで使用することに窃盗だとも言っている。これに対してGNUやLINUXなどが登場し、フリーソフトやオープンソースソフトウェアが登場した。 一方で、コモンズを囲い込み営利企業が独占する状況も続いていた。 これらのコモンズの再開放を求めてアラブの春を代表とするソーシャルメディアでつながり行動を起こしている。 今後、資本主義体制か協働型体制のどちらが発展していくかは社会インフラにかかっている。 現在のコミュニケーションネットワークはGoogleやFacebookに牛耳られそうになっている。 なぜならユーザーの情報が独占され、囲い込まれてしまうためである。 コミュニケーション媒体の商業的な囲い込みという問題は今後議論されていくだろう。 エネルギーコモンズについても、同様の問題を抱えている。しかしアメリカの1930年代の電力事業にヒントがある。 田園地帯に電力を供給しようと電線の敷設を農村の協同組合で実施し安価にアメリカ全土に拡げた。(結果的にそうなったというのはあるが)今でもこの協同組合による電力供給は続いており、原価で電力を提供している。 次にロジスティクスコモンズに関して、従来の垂直統合型の運送会社だと、社内の最適化は可能だが、グローバルな視点で見ると、積載率は6割というムダな状態であった。 これが倉庫を共有したり、複数のドライバーで積荷を届けるような分散水平型のやり方が出始めている。 ■第四部 社会関係資本と共有型経済 カーシェアリングサービスの登場で、自動車が減り、二酸化炭素の排出量も減った。 シェアリングエコノミーは市場機会ではなく、経済パラダイムの変換点か? ナップスターが登場し、p2pで音楽をシェアリングし音楽業界を一辺させた。 エアビーアンドビーのように個人宅をシェアしたり、庭を農地にシェアするコモンズも生まれてきた。更には、個人情報の最機密である疾病情報のシェアで、希少疾病の患者主導の研究などが始まった。 3Dプリンタで臓器も作成できるようになってきている。しかも限界費用がほぼゼロで。 広告業界においては、人々の受け身の態勢から自ら情報を取得することによって危機的状況になる可能性がある。 2008年のリーマンショックによって、貨幣に対する信用が低くなった。 各地で地域通貨と呼ばれる物が増えてきた、地元で資金を循環させるためのものだ。 分散水平型のインターネットの破壊力も金融の領域には及ばないというのは視野が狭い。 ■第五部 潤沢さの経済 潤沢というのは主観がはいる定義である。 2050年には人口が今より35%増加し(25億人)2030年の時点で、今の水準の資源消費は地球2個分が必要。 幸福度はあらゆる研究で、横軸を貧困度に取るとベルカーブを描いて上下する。裕福になっても幸福度は落ちる。物質に所有されるという状態になる。 ミレニアル世代のほうがミラーニューロン(共感ニューロン)が発達している? お金では幸せは買えない、ベーシックインカムは貧困層をなくすという意味でいい施策なのかも? 富裕層のエコロジカルフットプリントを減らしても、貧困層の出生率は下がらず、資源が不足する。 貧困層の子供はいわば労働の保険だ。 貧困層の出生率を下げるだめには、電気の安定供給が不可欠だというデータがある。 そうすると出生率2.1以内に収まり、世界の総人口は50億人にまで減少する。 これを実現するための不確定要素として、温室効果ガスによる温暖化である。 2100年には4.5℃以上上昇する可能性がある。 現在でもあらゆるところで異常気象が観測されている。 世界中で旱魃が発生しており、農作物の収穫量が減少している。このため、摂取カロリーも減少しており、栄誉不良の子供が増えると予想されている。 異常気象を乗り越えるためにも再生可能エネルギーに移行すべき。 潤沢さの経済への移行に向けた取り組みの障害になり得る不確定要素の2つ目は、サイバーテロだ。 サイバーテロにより、アメリカの大規模な変圧器が破壊されたら、復旧するまでに甚大な被害が発生するだろう。 日本の状況は化石燃料にいまだ頼っており、ドイツに比べて非常に遅れている。再生可能エネルギーの資源はドイツの9倍あるにも関わらず、生み出しているエネルギーは1/9である 日本は大きな岐路に立たされている。旧来の持続不可能な古いコミュニケーションテクノロジーに固執すれば二流の経済になり下がる。
2投稿日: 2020.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログp11 資本主義体制を蝕んでいるのは、それを支配している稼働ロジックそのものの劇的な成功の結果に他ならない。 p21 〜将来、限界費用がほぼゼロまで下がる時代が必然的に訪れることが明らかになる。限界費用がほぼゼロの社会は、一般の福祉を増進するにはこのうえなく効率的な状態であり、資本主義の究極の勝利を象徴している。 p31 コミュニケーションの手段と、エネルギー源と、何らかの移動手段がなければ、社会は機能しなくなる。〜IoTは、コミュニケーション・インターネットとエネルギー・インターネットと輸送インターネットから成り、この三者は単一の稼働システムとして協働する。 p39 世界中で見え始めてきている新しい種類の長期的景気低迷と思しきものについて、〜それは経済が市場での交換価値から協働型コモンズでのシェア可能価値へ移行するという、目下進行中の大転換の表れなのだ。 p40 世界のGDPは〜伸びが鈍り続けている。〜その要因は、〜財やサービスを生産する限界費用がさまざまな部門で〜ゼロに近づくなか、利益は縮小し、GDPは減少に転じ始めている。〜かつては購入していた財を、共有型経済の中で再流通させたりリサイクルする人が増えたため、〜ライフサイクルが引き延ばされ〜。しだいに多くの消費者が、財の所有よりも財へのアクセスを選択し〜。一方、自動化とロボット工学、人工知能(AI)のせいで、何千万もの労働者が職を失い、〜購買力は縮小を続け〜。それと並行してプロシューマーの数が増え〜。要するに〜資本主義体制の緩やかな凋落と協働型コモンズの台頭であり、経済的繁栄は市場資本の蓄積よりも社会関係資本の集積によって評価される p61 ギルドは、利益を挙げることよりも従来どおりの暮らしぶりを維持することを好み、自らの財の代価として、市場価格ではなく、「公正価格」と呼ぶものを請求した。〜現状維持を重んじた。 p65 〜かつては自らの道具を所有していた職人たちは、商売道具をむしり取られ、資本家という新種の親方に仕える賃金労働者に仕立てられた。〜土地の囲い込みと、職人の道具の「囲い込み」〜どちらの場合にも、何百万という人が、経済的に生き延びるための手段の支配権から切り離されてしまった。 #当時の市場ニーズは「衣食住を満たす」にあったか。今では生産力が上がりすぎて、生産コストが下がってニーズは希薄になり、資本家は生産力を所有しても利潤を得にくくなっている?
0投稿日: 2019.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログIT情報革命が起こって、インターネットに影響影響が、社会の隅々で見られるようになった。過去数十年で、利便性という点では、人類始まって以来の急激な変化だと思う。 生活は、格段に便利になった。 しかし、便利になった代償もある。 その代償とは、人間が「モノ化」したことだろう。 つまりアマゾンで売っているように価格が付いて、機能と役割が、明記されているようの「モノ」になってしまったことだろう。 この人間の「モノ化」の勢い衰えず、急速に広まっているように思う。人間をまるでモノか何かのように使うというのは、人類の歴史を見れば、普遍的に見られる現象だが、ある社会の価値観で、強制的に人間の価値が数値化されるようになったのは、現代だけだと思う。 人と人とのコミュニケーションも、すっかり変わってしまった。コミュニケーションする側が、される側を、価値や機能や役割を重視して見るようになった。これは果たしてコミュニケーションなのか?この現象が、二人同士から、複数人、人類全体と広がり、無限回数繰り返されて、旧来のコミュニケーションスタイルとは、全く違うコミュニケーションが出現している。 ある人は、孤独を感じ、旧来形のコミュニケーションスタイル、顔と顔を合わせ、存在を認め合うスタイルを求めるが、今、それは非常に困難となっている。このミスマッチが現代でよく見られる悲劇を生む根本原因になっているのではないだろうか。 この変化の帰結は、容易に見通すことができる。 変化に対応できる人は、生き残り、対応出来ない人は、淘汰される。対応出来ない人同士が争うようなことが起こっている。この現象が、今社会のあちこちで勃発している。 この変化に対して、具体的には、どう対応すればいいのか?それを知る上で非常に参考になる本です。
0投稿日: 2019.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ17/2/28 ■モーニングサテライト リーダーの栞 015年に創業し、SIMカードを使ってIoT=モノとインターネットをつなげるサービスを提供するIT企業ソラコムの玉川憲社長。今回紹介するのはアメリカの文明評論家ジェレミー・リフキン氏が書いた「限界費用ゼロ社会」。この本によるとIoT(モノのインターネット)の広まりにより、モノやサービスを1つ追加で生みだす時にかかる費用がほぼかからない社会が到来し、それにより資本主義は衰退、それに代わり共有型経済が台頭してくるといいます ---------------- アマゾン 書評 野口悠紀雄の『仮想通貨革命』、水野和夫『終わりなき危機、君はグローバリゼーションの真実をみたか』、ジャック・アタリ『21世紀の歴史』とかとこの本を併せ読むともっと立体的に現在何が起きているのか、もしかすると封建時代以来かもしれないような変化の時代に我々が生きているかもしれないということがより理解できるかもしれない。
0投稿日: 2019.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
IoTはコミュニケーションインターネット、エネルギーインターネット、輸送インターネットから成り、この三者は単一の稼働システムとして協働する。 さらにレンタルや再流通のネットワーク、文化交流、専門的技能や技術的技能の交換といったシェア可能な他の部門の将来系も劇的に高める 希少性の経済がこれまでの資本主義なら限界費用ゼロ社会は潤沢さの経済である。 潤沢さが整ったとき従来の物質主義的な嗜好は弱まり、他社と協力したり、共有したりすることに人々の欲求がシフトすることが期待される。 そして、そのとき従来の資本ではなく、社会関係資本こそが源泉となる。 最後に日本企業への提言として、日本とドイツを比較して、日本の目指すべき方向性を示していた。 それは旧来のインフラを少しずつ変えていく、変えなくてはいけないという意識をもつことである。特にIoTを導入していくにも現状エネルギー企業が長期的には効率の悪い原子力や火力に拘っている。これは限界費用がゼロに近づく社会で日本の競争力を阻む原因となる。
0投稿日: 2019.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ一見正しそうに感じるが、システムを構築するためのコスト・見えない負担などが上手く隠されているように感じ、理想論になってしまっている印象。
0投稿日: 2019.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ原著は2014年刊行ですが、2018年末現在、日々萌芽する限界費用ゼロなシェアリングサービスを予測しています。資本主義の膨張競争の果てに待つのは破滅ではなく、IoTで強化された協働型コモンズでの共生ならば、それは人類にとってとても望ましい事に思えます。 人類が年間に使う470エクサジュールのエネルギーは太陽の88分の放射に等しい、とか明日から使える知識が山盛りです、が、全編文章がちょっとくどい気も。
0投稿日: 2018.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ旧来の資本型経済は終わりを告げ、新しい共有型経済が台頭しつつあると主張する本。最後の章で日本向けに書かれている章が結構衝撃的。ドイツと日本を比較し、共有型に移りつつあるドイツとだいぶ遅れている日本とを比較し、日本の進むべき道を示している。共有型主義が資本主義の後継なのかどうか。これからの時代が興味深い。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ【由来】 ・ダイヤモンド2016/3/5 書評 河野龍太郎 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・ 【目次】
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
IoTと3Dプリンターと再生可能エネルギーがシェアエコノミーしいては第3次産業革命を起こすということを書いた本(第4次産業革命とも言われているが、正確には第3次らしい)。内容もよく練れておりそれなりに納得感もあるが、最終的に限界費用が限りなくゼロに近くなる社会が訪れるということが俄かには信じがたい。マイケルサンデル張りのpublic societyが最終的な社会形態ということだが、人間は本当に自らの欲望(利己心)を克服して利他的に行動するようになるのだろうか?結局のところ、自分が最も得をするようい行動するという人間の本来の性向を考えると、なかなか実現しにくい社会だと思う。生産性が低すぎて協力しなくては生きていけなかった中世ならいざ知らず。ただし、このまま欲望のままに資本主義を発展させていくと最終的に社会の成長を地球が賄い切れなくなるというのはあるのだろう。まあ、ローマクラブが何十年か前にも同じことを言っていたが。。。
0投稿日: 2018.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
私有財産制が近代的市場を存続可能にしていることは、一般に認められている。だが、執行可能な法体系なしでは、見知らぬ人どうしが財やサービスを交換する匿名の市場は存在しえない事実に気づくことも重要だ。市場で運営される私有財産制が完全に機能するには、売り手と買い手に契約の義務を果たさせるような、警察と裁判所に支えられた法律制度が必要とされる。封建時代のコモンズにおける保有者の義務から近代的な市場での財産権への移行に足並みを揃えて成熟したイングランドの法体系は、古い秩序から新しい時代への移り変わりを確実にする上で役立った。(p.54) 営利へ向かう新たな熱狂は広がり続け、しだいに多くのカトリック教徒やその他の人々を市場の中へ取り込んだ。それ以前は、被造物を構成する「存在の大いなる連鎖」のどの段階に存在するかで封建時代における各自の生き方が決まったが、原初的市場経済の新しい自主的な個人は、市場で私有財産をどれだけ蓄えるかによって自らの生き方を決めることになった。(p.93) 蒸気機関によって人間は封建時代の農奴制から解き放たれ、資本主義市場で物質的な私利を追求できるようになったとすれば、IoTによって人間は市場経済から解放され、協働型コモンズにおいて非物質的でシェアされた利益を追求できるようになった。全部とは言わないまでも、私たちの基本的な物質的要求の多くは、限界費用がほぼゼロの社会でほぼ無料で満たされるだろう。稀少性ではなく潤沢さを中心とした経済では、インテリジェント・テクノロジーが重労働の大部分を担う。今から半世紀後、私たちの孫は、私たちがかつての奴隷制や農奴制をまったく信じられない思いで振り返るのと同じように、市場経済における大量雇用の時代を顧みることだろう。(p.205) グローバルな金融崩壊のせいで、商業取引は原初からの制度であるという長年の前提が思い込みにすぎなかったことが露わになった。人類史上、文化に先立って商業的な市場や交換が成立した例はない。私たちは誤って、商業が先行し、文化の発展を可能にしたと信じ込んでいたが、実際はその逆だったのだ。文化とは私たちの交流の場だ。そこで社会の物語を紡ぎ出すことによって、私たちは共感する対象を拡大し、より大きな架空の家族として団結できるようになる。同じアイデンティティを共有しているという意識が社会的信頼の絆を培い、その絆のおかげで私たちは、統一された全体をとして機能できるだけの十分な社会関係資本を蓄積することが可能になる。アイデンティティの共有があってこそ、私たちは約束手形として役に立つさまざまな象徴的通貨を創り出し、互いに信頼しあって、過去の商業的な約束も将来の取引も相手に尊重されると考えることができるのだ。(pp.405-406) 人類の歴史的なナラティブには別の側面がある。人間の意識の進化と、より広く包括的な領域への共感の拡大こそがそれだ。記録にこそ残されてはいないが、人類史には、たえず自己の枠を超えて、いっそうの進化を遂げた社会的枠組みの中にアイデンティティを見出そうとする人間の衝動によってもたらされた。幸福で調和のとれた時代が含まれている。共感を抱くとはすなわち、文明化することであり……文明化するとは、共感を抱くことにほかならない。じつのところ、両者は不可分なのだ。(p.468) まだ日本は気づいていないが、台頭しつつあるIoTは、これまでの歴史上のあらゆる経済革命を特徴づけてきた三つの決定的に重要な要素から成り立っている。その三つとはすなわち、より効率的に経済活動を管理する新しいコミュニケーション・テクノロジー、より効率的に経済活動に動力を提供する新しいエネルギー源、より効率的に経済活動を進める新しい輸送手段だ。(p.477)
0投稿日: 2018.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ネット等の台頭により、単位増加に伴う限界費用がゼロに近づき、あらゆるものの価値観が変わろうとしていることを幅広く深く紹介した本。3年前ではありながら名著。 <メモ> ・スマートシティ文脈のIoT。構造的健全性を評価し、修理を判断。自動車や歩行者の最適化を図る。駐車スペースを知らせる。交通情報。保険料率の適正設定。照明の最適調整。ごみ収集ルート最適化。 ・IoTは地球の生態系管理の向上のため。急速に自然環境に適用されつつある。 ・セキュリテイシステムの高度化。 ・第三次産業革命では、IoTにより、生物圏の複雑な構成の中へ人類が自らを再統合し、地球上の生態系を危うくすることなく、劇的に生産性をあげるのを助ける。 ・インフラには三つの要素が必要。それぞれが残りの二つと相互作用し、システム全体を稼働させる。コミュニケーション媒体、動力源、輸送の仕組み。コミュニケーションがなければ、経済活動を管理できない。エネルギーがなければ情報を生み出すことも、輸送手段に働力提供もできない。輸送とロジスティックスがないとバリューチェーンに沿って経済活動を進めることはできない。 ・コモンズは市場も政府も提供しない様々な財とサービスをもたらしてくれる。コモンズは資本主義市場と代議政体のどちらよりも長い歴史を持つ、世界で最も古い制度化された自主管理活動の場。 ・利益率の激減に直面している巨大な資本主義企業は限界費用がゼロに向かう激しい勢いに対して、そう長くは持ちこたえられないだろう。協働型コモンズ、経済が台頭する。
0投稿日: 2018.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなく気になっていた「限界費用ゼロ社会」、詳しく読んで納得。今後の社会の変化の基礎となる、前提条件を学んだ気がする。限界費用ゼロということは希少性を生み出すことができなくなるわけで、購入=所有では利益が出せなくなる。シェアリングエコノミーの勃興はこれがベースになっていると考えると腹落ちする。著者は、エネルギーさえコストゼロに近づくと予想していてその先端がドイツであると評価。日本は建設コスト・維持コスト・管理コストが高い原発にこだわっていて両者の差は広がるだろうと予言している。一方、西洋では当たり前の「共有地の悲劇」が起こらない数少ない地域が日本であるとして期待もしている。
0投稿日: 2018.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ生産や教育の限界費用がゼロに近づき、モノは所有からシェアへ、資本主義の源泉たる利益が得られなくなってきた。雇用も失われる。資本主義はゆるやかに協働型コモンズに変わっていくだろう。 製造業に、人やお金やエネルギーをかけていた時代が終わりつつあるというのは理解できる。次は協働型コモンズとのことだけれど、福祉や医療やサービスというのも含まれるんだろうか?労働者はどこで稼げるんだろうか?
0投稿日: 2018.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログものを作る限界費用がゼロに近づくと資本主義社会が崩壊し、新たな価値観を持つ共有型経済が台頭すると予測している本。
0投稿日: 2017.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
面白かった。 ホントにこんな社会がやってくるのかは、今暮らしてる僕らにかかってるんだろうけど、ワクワクした。 きっとこれから混乱するんだろうなぁ。けど、全く新しいルールでできている世界、楽しみです。
0投稿日: 2017.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ2012年頃に書かれた本。 「インターネット広告は、従来の広告より単価が安く、ユーザーはレビューを重視して広告は信用しないので生き残れないだろう」という当時の筆者の予想は今読むと外れています。 この本は、ネクストソサエティのような予言の本ではないけれど、一つ一つの事実を知るにはまとまっていました。 ・1995年から2002年にかけて、全体の生産量は3割以上増えたが、製造業の雇用は2200万人分も消失した。 ・GDPの上昇と雇用は相関しなくなっている ・トレーラートラックのグローバルな輸送の積載率は1割にも満たない。輸送は効率化の余地が大きい。 ・ロジスティクスは分散型インターネットのアーキテクチャを用いて改善すべき。最初から最後まで一つのトラックで運ぶのではなく、輸送拠点を途中にいくつも設けることで輸送を効率化できる。 ・生産・ロジスティクス等エネルギー効率の改善、持続可能エネルギーの普及、シェアサービスの普及、で限界費用はゼロに近づき、希少性をもとにした資本主義の次の時代、潤沢さが前提となる時代が訪れるだろう(しかし、食糧問題は未解決) ・20世紀に入って、ヨーロッパやアメリカをはじめとする国々で女性を家事から解放したのは電力だった。地球上の人口を安定させるには、電気へのアクセスが鍵となることが分かり始めている。最貧国において、大家族というのは実質的に保険のようなもので、たとえ子どもの中に若くして命を落とすものがいても、その仕事を引き受けられるほかの担い手を確保できることを意味する。 ・ミレニアル世代が家や車を所有したがらず、出世欲も少なく、物質的豊かさよりも人と人との関わりをより重視するのは、世界金融危機の影響が大きい。
1投稿日: 2017.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログGNUがある程度成功しているのは、それなりに収入が保証されている研究者が仕事の片手間にやっているからで、利益を求めない世の中への貢献がトレンドになりつつある例として挙げられるのはどうかとも思う。
0投稿日: 2017.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ技術の進展が限界費用をほぼゼロにすることにより起こる、変化の経済・社会的側面に迫るもの。 歴史的な流れの中での考察。 潤沢、幸福とは何か。 日本の現状に対する認識興味深い。ザ・ヨーロッパ的思考。 ・人間の思考、提案もフリーで集約できることによる新たな開発の方向性 ・シェアリングの先の所有権の放棄と物質管理の容易化があるのか ・資金もフリーで集約できることによる社会の多様化があるのか
0投稿日: 2017.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ資本主義は素晴らしく世界を進歩発展させたのだが、このままでいいの?という疑問も膨らませている。協働型コモンズが来るのかどうかの予測は別として、そんな未来の方が幸せかもしれない。
0投稿日: 2017.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログうん、2000年ぐらいに言われていたことをまとめた本で、1周廻った感じ。当時IoTはM2Mって言われていたしね。
0投稿日: 2017.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
I o Tはコミュニケーション・インターネットとエネルギー・インターネットと輸送インターネットから成り、この3者は単一の稼働システムとして協働する。情報とエネルギー(再生可能エネルギー)の生産と流通の限界費用がほぼゼロに近づく。価格がほぼゼロに近づく。 AIの進化によって人間がAIにとって代わられる。 このような社会ではコモンズによる協働が主力になってくる。協同組合はその例。 物流の限界費用(価格)もゼロに近づく。 排他的所有からシェアに代わってくる。
0投稿日: 2017.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「限界費用」つまり、プラス1単位の生産コストがゼロになったとき、人々は「所有」の概念から解き放たれることになる。そこに出現するのはユートピアか、ディストピアか。 再生可能エネルギーで皆が自活するようになり、3Dプリンターでなんでも手元で作り出せるようになり、すべてがネットワークでつながることで、所有からアクセスへの大転換が起こるとする。それは、資本主義社会の終焉でもある。ロボットが労働を駆逐し、生活に必要なものがなんでもピア・トゥ・ピアで融通されると、労働者は資本家から報酬を得る代わりに、協同的に働き、協同的に消費するようになると説く。 現在、起こりつつある技術の変化を革命的に読み替えるとこうなるというか、行き着く先の究極を予想していくところにおもしろみはある。しかし、突き詰めて考えられてはいるが、論理に飛躍があることは明白であり、読む人によっては1冊丸ごと夢物語的な感想を持つかもしれない。
0投稿日: 2017.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログシェアリングエコノミー、IoT、3Dプリンタが経済の形を変える!とコンセプトは意外と目新しさが無いと感じたけれど、それはそういった世界が現実になりつつあるという認識が既に当たり前になっている証拠なんだと、少し落ち着いて振り返れた点は良かった。
0投稿日: 2017.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
インフラの コミュニケーション エネルギー 輸送 の一体的な革新により、価値の軸とビジネスモデルの勝ち筋が大きく変わる
0投稿日: 2017.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
シェアリングエコノミーの話をこえた未来予測に非常に感銘を受けた。 これまでの第1次、2次産業革命の社会の変容と合わせての現在起こりつつある第3次産業(社会)革命ととらえるアプローチが斬新かつ面白かった。 これらの革命は決して、産業にとどらず社会自体をかえていく、第3次革命がたどり着くところが、1次革命以前のコモンズ(共有地)と言う。ただし、規模はインターネットを基盤とする世界規模の。 そこには、資本主義の次に来る、協働社会。語られている事象をとらえれば、確かにこのまま資本主義が続くというより協働社会の実現を感じずにはいられない。 その原動力は、物欲より共感を重視するミレニアル世代。 ミレニアル世代は、周りに手に届くところにすでにモノやサービスがあふれそれを所有することに価値を見いだせないというのも納得でした。(決して、欲望がないのではなく、欲望の価値観が違う。) 最後の特別章「岐路にたつ日本」も非常に的を得た提言でした。ドイツに比べやはり危機感の足りない日本。日本がたぶん世界でもっとも技術的には、限界費用ゼロ社会の実現がしやすく、かつ必要性があるにかかわらず、相変わらずの垂直統合的資本主義に縛られている、この本が発行されたのが1年前なので、少しは進展しているように感じますが、たぶんさらなる加速が必要ですね。それが日本の将来の姿であればいいと説に願います。それが来年1年でさらに顕著になればいいですね。そして自分がこの時代の変化にどう適用していけるかを考えていかなければならないと感じます。
0投稿日: 2016.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログIoTとシェアリング・エコノミーという現代のバズワード的な技術動向を産業革命と社会(ここではコモンズ)変化の側面から表した1冊。特にエネルギーの重要性を再認識させられる。
1投稿日: 2016.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ★資本主義を突き詰めるとシェアリングエコノミーになる。稀少な資源を奪い合う時代から、潤沢な資源を分け合う時代へ。そのための障害は、地球温暖化問題、食糧問題、テロの問題。3つをいっぺんに解決できないだろうか。例えば人工光合成みたいな技術で。ミドリムシもいいかも。
1投稿日: 2016.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に面白い。レイ・カーツワイルの『Singularity is Near』が指数関数的成長をビジョナリーを語ったものとするなら、本書は学術的寄りに歴史から指数関数的成長の到来を考察した一冊だ。 Marginal Costが限りなくゼロ化することで、利益マークアップの資本主義が弱まり、協働型コモンズが訪れるという主張は相当の説得力がある。IoTによる超効率社会とエネルギー・インターネットによりエントロピーが矮小化した潤沢な社会は、希少性を重んじていた我々現代人とは全く別の世界の到来を予感させる。 前半は経済学書のような骨太な考察が楽しめるが、中盤以降は協働型コモンズの萌芽、つまり現段階の事例紹介が多い。前半のような論理的展開で、協働型コモンズとなった社会の経済状況、資本主義からのシフトなどが読みたかったので、そこだけはやや物足りなかったため減点。 とはいえ兎に角新しい経済システムを提示する興味深い一冊だ。
1投稿日: 2016.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ未来を予測するには、一度思いっきり極端な方に振ってみると良い。そういう意味で、極端なまでに限界費用ゼロ社会/協働型コモンズの普及を説いているこの本は、将来の予測のために役に立つ。
1投稿日: 2016.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ30年前にエイモリー・ロビンスが「ソフトエネルギーパスで提唱した分散型のローカルエネルギーにさらに分散型ロジスティックとコミュニケーションをプラスして、第三次産業革命を提唱している。 ロビンスの思想がIOTで実現される時が来た。
1投稿日: 2016.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ我々の社会の未来をここまで刺激的かつ具体的にまとめあげた本はなかなかないのではないだろうか。それくらい面白い。 500ページ弱となかなかのボリュームではあるが、以下のような要点に収斂される。 ■IoT、AI、ロボティクス、3Dプリンティング、スマートグリッドといった近年のテクノロジータームの新しさは「限界費用がほぼゼロで新たな財を生産できる」という点にある ■資本主義社会は資本を集中させ生産性を高めてきたが、そろそろ生産性の限界に達し、かえって労働者を不要とすることで貧しい人々を生み出すという「資本主義のジレンマ」とも呼べる事態に陥っている ■そうした中で、従来の資本の担い手であった政府(=国有化)、民間(=民営化)とも違う第三の資本の統治形態としてコモンズ(=共有型)が着目されるべき。実際、社会関係資本(Social Capital)への注目や、共有型経済(Sharing Economy)の台頭は、この文脈で理解される。特に共有型経済においてはこれまでの資本主義とは異なり、資本や生産手段の分散化が図られるという点が重要 ■歴史的に見れば、文明や社会の変革は、 ・コミュニケーション ・エネルギー ・交通/輸送 の3つのインフラがリンクしながら変化することで引き起こされている。IoTは限界費用がゼロという特徴から、まさにこの3つを抜本的に変化させる可能性を秘めており、共有型経済に必要な分散化を実現するのに最も適した技術。数十年の時間は必要ではあるが、間違いなくこの流れは第三次産業革命として、今後の社会を大きく変革させていく 特筆すべきは上述のテクノロジータームについて、限界費用ゼロという共通項を導出したその観点の鋭さにある。限界費用(Marginal Cost)とは一般に経済学において、新たな財を一単位生産するにあたって追加で必要となるコストのことを指す。よって、限界費用がほぼゼロの世界においては、生産前の初期投資は必要であるものの、いったん初期投資さえ済んでしまえば、追加のコストはほぼなしに財を生産できる(これを会計学のワーディングに置き換えれば、固定費はあるものの、ほぼ変動費がゼロで財の生産ができる、ということに等しい)。例えば、ロボティクスは人間を介在させないことで人件費を省き、ほぼ電力コストのみで財の生産を可能とするし、スマートグリッドにおいてはネットワークに組み込まれた再生可能エネルギー源(太陽光、風力など)からほぼ限界費用ゼロでエネルギーを創出することができる。 個々のテクノロジータームの正確な概念描写等は脇に置いておくとしても、これだけ広範な概念をこの一冊にまとめあげた価値は非常に大きい。
3投稿日: 2016.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界の中でガラパゴス化にならないように願いたい。先を見る目、先端にたつ勇気がほしい。そのための思考や技術はあるのに…
1投稿日: 2016.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログIoTによりコミュニケーション、エネルギー、輸送の新たなインフラを形成し、限界費用をゼロまで押し下げ、その結果、資本主義の凋落は必然となる。 経済の専門家では到達できない内容、刺激的です。 IoTのインパクトが単なる生産性の向上といったビジネスの仕組みを変えることに留まらないことが理解できる。
1投稿日: 2016.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログFREE以来の衝撃だった。 資本主義の競争の原理により、製造コストは下がり続ける。一時的に寡占企業がその流れを阻止しようとも、大局的には、製造コスト=限界費用は限りなくゼロに近づく。それは、すでに資本主義を看破したアダム・スミスの予測するところでもあった。 という刺激的な論考により始まる本書、IoTありソフトウェアあり、シェアエコノミーありと、この数年来からの市場のある一面を理解するのにとても最適な書。 ただし、それはインフラ投資という巨額が必要な部分については、すでになされている、あるいはオプティミスティックに生協方式などで構築できるだろうというスタンスを取っているのが、少々納得感にかける。 しかしながら、里山資本主義や社会貢献型の企業など、オープンイノベーションなどの流れやairbnbなどに代表されるシェアエコノミーの確実な発展をみると、少なくとも、無意識ではいられないことを感じさせる。 やはり、ハブアンドスポークのような形態になるのか、それとも多重世界のような形態になるのか。市場経済が消えることも、シェアエコノミーが発展せずに四散することも起こり得ないとするなら、その経済活動の間でどのような事態が起こるのか。それとも、過去に起きた囲い込みが違う形で起きるのか。それとも、なにも新しい経済活動ではなく旧来から存在していた地域社会における経済活動がただインターネットという媒介を介して広く広く延びていくだけなのか。興味は尽きない。
2投稿日: 2016.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ膨大な資料と参考文献からまとめられた考察された本。分厚いのでざっと読み。 協働型コモンズ。 コミュニケーション、エネルギー、ロジスティック。 IoT 3Dプリンティング MOCC教育、プロシューマー。 自主管理、フリーソフトウェア、インテリジェントインフラ バーチャルスペースの独占企業 所有からアクセス、クラウドファンディング。
1投稿日: 2016.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ近年のインターネットの急速な普及を主たる背景に、かつては相当の対価を払って得ていたサーヴィスが驚くほど安価になっている…、という経験には誰しもが思い当たることだろう。 また、Webから離れても、例えばカーシェアリングというシステムが特に若年層を中心にこれほど受け入れられるとは、団塊ジュニア世代の私としてはちょっと不思議だったりもする。 本書で著者のジェレミー・リフキン氏が指摘している通り、車に限らずミレニアル世代のシェアリング傾向が高まっていることは間違いない。 先進国のみならず途上国においても、現代の経済構造を大きく変革するパラダイムシフトがまさに起きている最中であることは否定しようがない。 著者はその大きなうねりに対して、多角的にスポットを当てて、主観を交えながら現状を解説してくれていて、現在進行形のグローバルな動きを知っておくという点において、とても意義のある一冊だ。 既に急激に下落しつつある、データの流通における限界費用が今後ますますゼロに近づいていく、という予測はほぼ間違いないとして、ではそれにまつわるイニシャルコストや、過程で必要な知的労働の対価等は誰がどうやって負担するのか、という問いに対する答えとしては、公共税として国民から広く徴収する、というものしか結局ないのだろうか? どう読んでも著者のポリシーの背骨となっているのはある種のコミュニズムなわけだが、これから実現させるべき世の中の仕組みを、瓦解して久しい共産主義社会と一体どう差別化していくのか、そしてそれは本当に持続可能なシステムなのか、そのあたりの疑問は依然拭えない。 そして当然IoTに関してはセキュリティの問題もあり、いくらミレニアル世代の価値観が我々と異なっているとしても、ビッグデータを取り扱う人間側の欠陥をまったくのゼロにしてしまうのは不可能である、という不可避な事実があるわけだから、IoT化が進むほどに深刻なトラブルがどんどん露見するだろう…、と悲観的な予想をしてしまうのも仕方がない。 畢竟、ガンガン進化を遂げていくソフトウェアを動かさねばならないハードウェア、つまり我々人間がいかにヴァージョンをアップデートすることができるか、ということにかかっているような気がする。 巻末に特別章として収められた日本に関する著者の考察については、実はそれほど期待はしていなかったのだが、読んでみると現状分析は非常に的確で、説得力に満ちている。 まさに、中途半端、という言葉が見事に日本経済の針路を言い表している。 他、本書の全体的な感想として、あらゆる考察を詰め込み過ぎてヴォリュームが過多であるように思った。 枝葉をもっとシェイプしても著者のフィロソフィーは充分伝わるし、その方が読み易くもなるだろう。 通読するのにここまで時間が掛かった本は初めてかも。
1投稿日: 2016.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ事象を多元的に検証しながらの文章なので、繰り返し感が多い。 が、内容は示唆に富んでいて、加えて最終章で日本に向けた提言もありお得感高し。 コミュニケーション・インターネット、エネルギー・インターネット、ロジスティクス・インターネット。この三者は単一の稼働システムとして協働する。
1投稿日: 2016.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ資本主義では、新しい技術により生産性を上げ、売り手が前より安い単価でより多くの財を生産することを可能にし、より多くの財が供給されれば、それに対する需要が生まれる。その過程で、競争者は独自の技術を発明して生産性を上げ、自らの財をさらに安く販売し、顧客を取り戻すか、新たな顧客を惹きつけるか、をせざるを得なくなり、この過程全体が永久機関のように稼動する。 この競争過程の結果としてこれ以上ないというほどの「極限生産性」になるとすれば、無駄を極限までそぎ落とす技術を導入し、生産性を最適状態まで押し上げ、「限界費用」すなわち財を一単位追加で生産したり、ザービスを一ユニット増やしたりするのにかかる費用はほぼゼロに近づくことを意味する。財やサービスの生産量を増加させるコストが実質的にゼロになれば、その製品やサービスがほとんど無料となる。 IoTは、この無駄を極限までそぎ落とす技術となる可能性がある。すでに、3Dプリンティング、MOOC,再生可能エネルギーによる発電、自動車の自動運転など、その兆候が現れ始めている。IoTの要は、コミュニケーション、エネルギー、輸送の3つのインターネットを、緊密に連携した稼動プラットフォームにまとめ、連携していくことである。これらの流れの中で、生産性が上がり、限界費用がゼロとなり、商品サービスがほとんど無料となることで、資本主義が縮小していく。資本主義拡大のための生産性の向上が、逆に資本主義を縮小させることになるのである。 資本主義の縮小に伴い、分散型、協働型、水平展開型といったインターネットの特徴を活かした、協働型コモンズが台頭する。コモンズは、封建社会の崩壊と近代的な市場経済の台頭、資本主義体制への移行で終止符を打ったかに見られたが、何百万もの自主管理組織や慈善団体、協同組合、信用組合など、シェアというその精神は細々と生き伸びていた。現在、自動車や宿泊施設、患者主導の医療情報ネットワークなど、共有型経済ともいえるコモンズが台頭してきている。これは、いろいろな方面で、ますます伸びていくであろう。 日本は、諸外国と比べてIoTへの対応が遅れている。特に、エネルギーは、原発事故後、諸外国が原子力発電所を縮小に向かわせているにも関わらず、近年再稼動の動きが見られ、化石燃料への依存度が高く、再生可能エネルギーへの転換が遅れている。日本は今、歴史上の岐路に立たされている。日本が、企業家の才能を発揮し、技術を動員し、潤沢な文化的資産を活かせれば、限界費用ゼロ社会と、より平等主義的で豊かで、生態学的に持続可能な時代へと、世界を導くことに、十分貢献できる。
1投稿日: 2016.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログsub :モノのインターネットと共有型経済の台頭 限界コストがゼロに近づいていくことによる資本主義の衰退。共有型経済になるか。インフラ。 集中と分散かな? IoT(Internet of Things) C0098
0投稿日: 2016.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報・エネルギー・ロジスティックスの三分野におけるネットワーク構築論を軸に、現在様々な局面で起こっているシフトチェンジを幅広くカバーした大著。資本主義経済が現在の陣容をもはや保てないことを鋭く指摘した上、ローカルコモンズの水平的連帯による新たな社会の到来を予言している。ユーフォリアの匂いは嗅ぎ取れないではないが、少なくとも完全に閉塞しきった現代金融資本主義の次に来るべき社会についてポジティブに考える材料を豊富に提供してくれている。「利益を出すことが企業の社会貢献」であるとする戦後日本経済を支えてきたクリシェは、ひょっとしたら時代遅れになるのかもと考えさせられた。なお終章の日本への賞賛と警告は必読。政府は官製相場で既存の大企業を甘やかしている場合ではない。
1投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ私自身、この本を読んでかなり夢が広がりました。この資本主義社会に飛び込み、新社会人として働いていくことに絶望しか感じていませんでしたが、この本のおかげで4月から仕事をすることに少し希望を見出せました(たまたまこれに関与できそうな仕事でよかったです)。 http://yuhbook.hatenablog.com/entry/1051654651
0投稿日: 2016.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログネットワーク同士を相互に接続するのものがインターネットである。今、私たちがインターネットと呼んでいるものは、コミュニケーションのためのインターネットだ。これが電力のためのエネルギーのインターネット、輸送のためのロジスティックスのインターネットに拡張する。そこでは、様々な財やサービスの限界費用はほぼゼロとなり、希少性を奪い合う経済とは異なる価値に基づく、全く新しい経済体制が作られるという。 冒頭と巻末の大文明論と、中ほどの様々な実践の事例紹介とのスケールの乖離は感じるものの、この三つの「インターネット」が実現する潤沢さにもとづく社会を構想することはとても魅力的だ。 問題は、その実現までこの世界が持つのか、ということだろう。
1投稿日: 2016.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログコミュニケーション、エネルギー、輸送という3つの分野でのイノベーションが経済的発展に寄与してきたという筆者のフレームワークは新鮮で、首肯すべきものであった。 特に近年、インターネットの普及により、電力、輸送、製造のコストが劇的に低下するというシナリオにも同意できる。 しかし、市場経済を「悪」と見なし、現在のイノベーションが市場経済を駆逐し、筆者が「善」と考えるコモンズが取って代わるという予想には同意できない。 筆者は博識かつ洞察は鋭いと思うが、それらをすべて、この予測の牽強付会の材料にし、押し付けがましく感じた。
1投稿日: 2016.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログIoTとは何か?を求めてたどり着いた本です。著者には見えている明日、それが明確な分だけ、見えてない自分には戸惑いを感じさせます。だけど、きっとそんな明日はきっと来る、という確信も芽生えます。ドイツのインダストリー4.0の意味もなんとなくわかったような気がします。インターネットが創り出す社会の変わり方ってこれからなんですね。それにしてもこういう大きな視点でテクノロジーを語ること、日本でも盛り上がるといいな、と思いました。
1投稿日: 2016.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログIoTでコミュニケーション、エネルギー、交通などが限りなく無料に近付き中央集権型の資本主義から分散型の共有経済へ移行するのがデジタル革命の本質であると、資本主義の歴史を含め、様々な事例を持ち出して説明する。Twitterの黎明期にもお金だけではなく信頼をウッフィーで表現するなど共生経済的な話が盛り上がりましたが、あまり持続しませんでした。SNSだけの情報のやりとりでは無理があったのが、IoTで現実味を帯びてきたということでしょうか、とても興味深く読みました。 ちなみにタラハント氏がその著書「ツイッターのミクス」と使った「ウッフィー」はコリィ・ドクトロウ氏の著書であるSF小説「マジック・キングダムで落ちぶれて」からの引用で、この小説は各自の脳が直接ネットに繋がっていたり、肉体が死んでも意識のバックアップから再生できるなど、究極にデジタライズされたIoE世界です。
1投稿日: 2015.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ限界費用がゼロとなると、資本主義においては価格を付けることができず、そこから利益も生み出せない状況になり、利益の創出を前提とする資本主義を崩壊させる可能性があるという。いわゆるシェアリング・エコノミーによる協働型社会の出現である。もちろん、シェアリング・エコノミーは一部ではすでに実現している。代表的な例では2015年になって日本でも多くの人が知ることとなったUberやAirBnBがある。著者の主張は、限界費用ゼロの経済原理はさらに広がり、2050年までには世界の大半で経済生活の大半を占める結果として、現在の資本主義社会を根本的に変えてしまうということである。それは、希少性や交換価値ではなく、潤沢さや使用価値・シェアを経済活動の中心に置くということになる。 著者はIoTインフラの専門家で、ドイツが進めるインダストリー4.0の提唱者の一人でもある。IoTへの取り組みは各地で進んでおり、巨大企業のGEのIndustorial Internet、CiscoのInternet of Everything、IBMのSmarter Planet、SiemensのSustainable Cityなどがその例だ。インフラには三つの要素 - コミュニケーション、エネルギー、輸送 - があるが、IoTはこれらのシステムと連携し単一の稼働システムとして協働させるものだという。IoTは中間業者を一掃し、このようなインフラの限界費用をほぼゼロにできるのだという。IoTを実現するための技術要素にかかる費用はどんどん低下しており、例えば無線ICタグは1年で4割価格が下がり、今ではひとつ10セントもせず、ジャイロや加速度センサ、圧力センサなどのセンサ類もこの5年で8~9割下がっているという。エネルギーについても太陽光発電により限界費用をゼロに近づけることができるという。自動運転の進化も輸送インフラに影響を与えるだろう。3Dプリンティングや、認知を得られつつあるMOOC (Massive Open Online Course)、なども製造や教育の状況を変えるであろう限界費用ゼロ社会の象徴だ。 本書では、最後に日本版のために特別に書き下ろした章がオリジナルから追加されている。「日本は、限界費用ゼロ社会へのグローバルな移行における不確定要素だ」から始まるこの章は、日本ついてのやや一般的ではあるものの、適切な批判がつづられている。「その苦境を理解するためには、日本の現状をドイツの現状と比べてみさえすればよい」とIoTなどの新しい技術に対する国家としての取り組みの差についてドイツとの比較で語られる。メルケル首相が2005年に就任したとき、著者が新しい指導者に招かれて将来社会の変革について意見を聞かれたという贔屓目を差し引いても、ドイツと日本との取り組みに差があるのはその通りだと思う。ドイツにもユーロ問題はあろうが、世界から日本がどのように見られているのかが垣間見られて暗鬱になる。 もちろん日本に向けたメッセージなので、日本の持つ潜在能力についても言及してもらっている。二十世紀に成し遂げた成果、超高速インターネット接続インフラ、再生可能エネルギー源(太陽光、風、地熱)はどこにも負けていない。このままだと二流国に落ちぶれるが、日本のもつ力をIoTを活用した明日の限界費用ゼロ社会に振り向けることができれば、世界を導くことに十分貢献できるだろう、というどっちの結果になっても間違いがない言葉で終わらせているのはご愛敬だ。 夢中になって読んだかと言われるとそうでもない。どちらかというとコンサル的にきれいに(楽観的かつ空想的に)まとめすぎのような気がする。たくさん数字が出てきて興味深いのだが、何かごまかされている感じがするのはそのせいかもしれない。それでも、こういう社会の認識の変化には備えないといけないのだろうなと思う。20年前にインターネットや携帯ネットワーク・端末が今あるように進化をして、世界を変えるということは想像しなかったし、GoogleやFacebook、Amazonといった企業がここまで台頭して生活を変えるということを想像してみることもできなかった。そういう意味では、エネルギーや輸送インフラの将来像については丸ごと信じるわけではないが、大きく変わるということと、その大きな方向性については同意する。そういった数十年かつグローバルな世界の変化について考えを巡らせるきっかけになるということにはなるのかと思う。
3投稿日: 2015.12.27「稀少性」から「潤沢さ」へ、「所有」から「アクセス」への緩やかな転換
単にあらゆるモノがインターネットにつながる、という話ではない。 読む者の遠くない将来の姿を暗示する本だ。 いまの職場や持ち家に別れを告げ、身の回りの自分のモノを手放し、これまでの人間関係や考え方さえ一変する未来の姿。 著者にとっては年来の予言した未来の到来であり、ドイツのメルケル首相とともに積極的にこの社会の実現にコミットしている。 どのような社会か? いまの成熟した資本主義経済がいよいよ最終段階を迎え、それこそ究極の勝利を手にしようとするまさにその時、体制の核心にある矛盾から主導権を失い、かわりに協働型コモンズの社会が表舞台に立つようになるという。 資本主義体制が崩壊するという一時期さかんに喧伝された話ではない。資本主義市場は縮小し、より狭いニッチへと後退するが、生き延び続ける。それが経済の辺縁部であろうとも。 「あらゆる人とモノを結びつけるグローバルなネットワークが形成され、生産性が極限まで高まれば、私たちは財とサービスがほぼ無料になる時代に向かってしだいに加速しながら突き進むことになる。そしてそれに伴い、次の半世紀の間に資本主義は縮小し、経済生活を構成する主要なモデルとして協働型コモンズが台頭してくる」 「遅くとも今世紀なかばまでには、世界の雇用者の半数以上が協働型コモンズの非営利部門に属し、ソーシャルエコノミーの推進に尽力する一方で、必要とする財やサービスの少なくとも一部を従来の市場で購入するといった状況になるのではなかろうか。そして伝統的な資本主義経済は、少数の専門職と技術職が管理するインテリジェント・テクノロジーによって運営されることになるだろう」 それにしてもなんとも皮肉な話である。「生産性を押し上げ、限界費用を押し下げるという、競争的市場に固有の起業家のダイナミズム」が、無駄を極限まで削ぎ落とすテクノロジーの導入を強い、それによって生産性は最適状態まで押し上げられ、最終的には生産にかかる費用がほぼゼロに近づく。生産コストが実質ゼロであるなら、その製品やサービスはほとんど無料になるということだ。「仮にそんな事態に至れば、資本主義の命脈とも言える利益が枯渇する」し、所有権は意味を失い、市場も不要になる。これは、旧来の経済学者の言葉を失わせる事態だ。 「ほとんどのモノがただ同然になれば、財やサービスの生産と流通を司るメカニズムとしての資本主義の稼働原理は何もかも無意味になる。というのも、資本主義のダイナミズムの源泉は稀少性にあるからだ。資源や財やサービスは、稀少であればこそ交換価値を持ち、市場に提供されるまでにかかったコスト以上の価格をつけられる。だが、財やサービスを生み出すための限界費用がゼロに近づき、価格がほぼ無料になれば、資本主義体制は稀少性をうまく活用して、他者に依存される状態から利益を得ることができなくなる」 稀少性ではなく、潤沢さやシェアを中心に経済生活を構成するという考え方は、従来の経済理論はとはあまりにもかけ離れているため、すぐに想像することはできないが、それこそが今まさに起こり始めていることなのだ。 限界費用がほぼゼロの社会は、一般の福祉を増進するにはこのうえなく効率がよい。 ・インターネット上での情報の大衆化 ・エネルギーインターネット上での電力の大衆化 ・オープンソースの3Dプリンティングを用いた製造の大衆化 ・MOOCを活用した高等教育の大衆化 ・ウェブ上での保健医療の大衆化 GDPの一貫した下落の原因も、著者によれば、資本主義体制の緩やかな凋落と協働型コモンズの台頭によって説明できるとする。 「財やサービスを生産する限界費用がさまざまな部門で次から次へとゼロに近づくなか、利益は縮小し、GDPは減少に転じ始めている。そして、しだいに多くの財やサービスがほぼ無料になるにつれ、市場での購入は減少し、これまたGDPにブレーキをかける。かつては購入していた財を、共有型経済の中で再流通させたりリサイクルしたりする人が増えたため、使用可能なライフサイクルが引き延ばされ、結果としてGDPの損失を招いているのだ。しだいに多くの消費者が、財の所有よりも財へのアクセスを選択し、自動車や自転車、玩具、道具といったものの使用時間に対してだけお金を払うことを好むようになりつつあり、これがまたGDPの減少につながっている。一方、自動化とロボット工学、人工知能(AI)のせいで、何千万もの労働者が職を失い、市場での消費者の購買力は縮小を続け、さらにGDPが減少する。それと並行してプロシューマーの数が増え、市場における交換経済から協働型コモンズにおける共有型経済へと経済活動が移るにつれ、GDPの伸び率はさらに縮まっている」
1投稿日: 2015.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ10年以上前に「水素エコノミー」を著した未来思想家。あらゆるリソースがインターネットを介してシェアされることで実現される限界費用ゼ口の社会。 ドイツのインダストリー4.0のきっかけ?IoTの重要性を説く論説。
1投稿日: 2015.12.06
