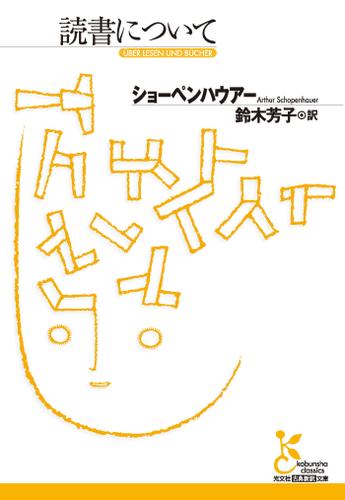
総合評価
(113件)| 32 | ||
| 38 | ||
| 25 | ||
| 2 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書とは他人の頭で考えること。自分で考える力を身につけなければならない。私はできているでしょうか?今後は意識して実践していきたいです。 ショーペンハウアーはヘーゲルと三文文士が嫌いなようですね。訳し方かもしれないけど、めちゃくちゃに言っています。「読書について」ってタイトルの本を手に取ったはずなのになぁ、といった具合。こんなにたくさん文句を並べているのに200年も残るというのは良本の証拠、なのか? 現代は情報に溢れ、本で調べなくてもネットである程度の困りごとは解決します。自力で解決策を捻りだすなんてことはだんだんしなくなってきました。それがなんだか悲しく思えてきました。たまには、じっくりゆっくり本を読んで、いつか必要な時に閃けるような知識や発想を蓄えたいです。
0投稿日: 2026.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者は「読書とは、他人に考えてもらうことだ」と論じる。 筆者が生きた時代とは異なり、現代は本だけではなく、テレビ番組や、youtube動画、XなどのSNSがある。コンテンツにありふれた現代では、日々様々な論調や情報に接する機会が多い。 筆者の主張を現代に当てはめると、読書だけではなく他人の考えに触れられるコンテンツ全体が、他人に考えてもらうことになるだろう。 実際に私がこの本を手に取った理由は、「他人の考えに触れられるコンテンツを日々消費したところで、自分は何か変わるのだろうか?」と思ったからである。 日々、読書・youtube・Xから他人の考えを取り入れて、自分のものにしようとはしている。しかし、情報過多に陥ってインプットはしているものの、それが何かしら自分自身のアウトプットとして出ている感覚がなかった。 おそらく筆者が述べているように、「反芻して自分でその事柄に深く向き合わないと、自分のモノにならない」ということだと思う。 多読して日が経って、読んだ内容を忘れる。結局それを繰り返している自分がいる。 自分が感じている課題をいくつか並行して日々考え続けるとか、何かしらの行動に繋げて日々アウトプットを修正していくとか、そうやっていくしかないのだと思う。 2026年は新しく本を色々買おうとしない。ネットにあるコンテンツは見過ぎない。暇があれば、自分が感じた課題・問いに向き合い続ける。一つの本を何度も読み、出来るだけ多くのことを吸収しようとする。 地道に積み重ねて、強い自分となるための土台を作る。そんな一年にしようと思える作品でした。
0投稿日: 2026.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ思想強すぎて草ぁ…と思わず笑ってしまうほど辛辣だが、頷ける部分も多い 読書を娯楽として楽しむ人もいれば、勉学、単なる現実逃避、あるいは救済を求めるかのように貪る人もいるわけで、本の読み方だの悪書がどうだの余計なお世話ですわと思っていただけに(終了
0投稿日: 2025.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初のページから「おお…すみません」と思わず呟いてしまったほど読者への叱咤激励と当時の文芸や言論空間への批判で溢れていた。今出版されていたら、こいつ何を言い出すんだとめちゃめちゃ叩かれていそうだ。翻訳者の鈴木さん、ショーペンハウアーの文章を訳すという大役を任され、さぞ大変だっただろう。ドイツ語は全くわからないが、翻訳された文章を見るに非常に理路整然としていて格式高いのだろうと思う。距離をとって、これはこれで一つの意見だと気楽に捉えるのが良いだろう。
4投稿日: 2025.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書という姿勢について哲学的視点から読み方と良書の選び方を勧め単に読むことで情報を鵜呑みにするのではなく、自分の頭で考えながら思索し、批判的姿勢、疑問、問いを浮かべながら読むという行為をすることを推奨している。 本に限らず、動画やSNS等で様々な質の悪い誰が言ったのかもわからない情報や誤情報で溢れている。本でも同じことを情報への向き合い方について本著は示すものだ。100年前の書物であるが、良書とは何か、悪書とは何かを自分自身で吟味すると良いだろう。 著者が推奨する良書というのは時代を超えて価値を持つ本というものは、古典のように、長く読み継がれた理由があるもの。短命な流行書ではなく、世代を超えて人間の本質に訴える書物であり、その書かれた本の著者の独自の思想と体験に根ざしていること。金銭や人気のために書かれた本ではなく、思想や経験を伝える使命感から生まれたものである。 読者の思考を刺激し、創造性を喚起することであり、受け身の読書ではなく、思索を促すものであること、普遍的な真理や深い洞察を備えていること:単なる情報や技術書ではなく、人生や存在への洞察を提供するものを指している。 著者のショーペンハウアーは明確に「良書を読むための条件は、悪書を読まぬことである」と述べ、人生の時間と知的エネルギーには限りがあるため、価値の乏しい書物にそれを消費してしまえば、真に読むべき本に触れる機会を永遠に失うと警告しました。悪書は「知性を毒し、精神を損なう」とされ、彼にとって最大の敵と明確にしている。 私は思う。本著が指す内容を正確に読もうとするのは知的生産には特化しているが、本著もまた自身の読書について時代を超えて読まれるということは良書であるといえる。時間は有限であり、この著者が読書についてを発表してから100年経過して消えた本は数多にある。ネットの情報はもっと早いだろう。 本著は思索を読みやすく解説している。一度手に取り読むことをオススメする。読むという行為は人間である以上無くならない。デバイスは紙から変わるかもしれないがそれでも向こう遠い未来まで読み継がれる良書であるといえよう。
0投稿日: 2025.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書には『余録と補遺』(『意志と表象としての世界』の注釈)にある「自分頭考える」「著述と文体について」「読書について」の3篇がおさめられている。3篇の内容は、密接なつながりがある。 哲学者ショーペンハウアーの読書についての考え(ただ、本をたくさん読めばいいのではない。自分で考えなければダメ)は、聞いたことがあった。実際に文章全体を読んでみると、とても分かりやすく納得のいくものだった。“良書を読むための条件は悪書を読まない”ということも、肌身で感じているところである。“目の健康のために一定サイズより小さな活字を使わないよう”なんてことも書いてあり、配慮の細かさにびっくりした。 ドイツ人に対する手厳しい批評は痛烈だが、それだけ母国愛が深いことの裏返しと言えるかもしれない。ドイツ人の国民性にまで及んで論を展開している。ドイツ語が貧しくなっていることを危惧し、ドイツ人は文章作法がなっていないと、こっぴどく書いている。はて、日本語は日本人は現在どうか気になった。そしてドイツ人の現在も。言葉を大切にし、自分の頭で考えることの大切さを肝に銘じた。 【印象に残ったフレーズ】 ・思索は人間のようなものだ。いつでも好きなときに呼びにやれるわけではなく、あちらが来てくれるのをじっと待たねばならない。外からの刺激が、内なる気分や心の張りと、なごやかに首尾よく出会うと、あるテーマについて自然に考えられるようになる。こうした思索は、博覧強記の愛書家には決して経験できない。 ・少なくとも読書のために、現実世界から目をそらすことがあってならない。…具体的なもの、リアルなものは、本来の原初的な力で迫ってくるため、ごく自然に思索の対象となり、思索する精神の奥底を刺激しやすい。 ・書くときもあらゆる不要な詳述、総じてあらゆる過剰表現を慎み、けがれなき文体を心がけるべきだ。余計なものはみな、マイナスにはたらく。「飾らず簡素」という掟が崇高さとも調和するので、すべての芸術にあてはまる。 ・いつの時代も大衆に大受けする本には、…. 手を出さないのがコツである。 ・常に読書のために設けた短めの適度な時間を、もっぱらあらゆる時代、あらゆる国々の、常人をはるかにしのぐ偉大な人物の作品、名声鳴り響く作品へ振り向けよう。 ・良書を読むための条件は、悪書を読まないことだ。なにしろ人生は短く、時間とエネルギーには限りがあるのだから。 ・「反復は勉学の母である」重要な本はどれもみな続けて二度読むべきだ。 ・古典作家のだれでもよいから、たとえ30分でも手に取ると、たちまち心はかろやかに、清らかになり、高揚し、強くなる。 *ロシアの文豪トルストイは、友人宛ての手紙で次のように、ショーペンハウアーを絶賛している。 「今私はショーペンハウアーは多くの人間たちの中でもっとも天才的な人物だと確信します…これは信じられないほどはっきりと、美しく照らし出された世界です」(解説より) 以下、私の読書についての余談です。 今年(2025年)に入って“正岡子規の出てくるところを読みたい”という理由だけで、『坂の上の雲』を読みました。読後にユーザーの方々の感想を読み、あまりにも歴史を知らない自分に愕然としました。と同時に、長編を読む力も足りないということも感じました。 社会人になってから、読書の楽しみを忘れてしまい、読書量は微々たるものです。ユーザーの方々の本棚を拝見し、読もうと思ってそのままの本がたくさんあることに、ブクログをはじめて5年たって気づきました。 学生時代に読んだ方が良かった、日本や海外の古典や、歴史を学べる本を、今後も多く読んで思索を深めていきたいと思っています。
25投稿日: 2025.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ常に考え続けることを辞めてはいけない この本を読んでより一層そう感じました 惰性で本を読むのではなく、自分のアタマで考え続けることが重要
0投稿日: 2025.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「読書は自分で考えることの代わりにしかならない。自分の思索の手綱を他人に委ねることだ。」 「本を読むとは、自分の頭ではなく、他人の頭で考えることだ」
0投稿日: 2025.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は散漫な読書や軽薄な文筆に対する罵詈雑言集だ。 ショーペンハウアー曰く、 ・紙に書き記された思想は、砂地に残された歩行者の足跡以上のものではない。なるほど歩行者がたどった道は見える。だが、歩行者が道すがら何を見たかを知るには、読者が自分の目を用いなければならない。 なるほど、読書は受動的な行為であると考えていた私にとって耳が痛い言葉だ。 ・真の思索家タイプや正しい判断の持ち主、あるテーマに真剣に取り組む人々はみな例外にすぎず、世界中いたるところで人間のクズどもがのさばる。クズどもは待ってましたとばかりに、例外的人物の十分に熟考した言説をいじくり回して、 せっせと自己流に改悪する。 ・風刺は代数のように抽象的で不定の数値に向けられるべきで、具体的数値や量を備 えたものに向けられるべきではない。生きた人間を解剖してはならないように、風刺してはならず、これを顧みない者は皮はぎの刑、死刑に処せられるべきだ。 ・書く力も資格もない者が書いた冗文や、からっぽ財布を満たそうと、からっぽ脳みそがひねり出した駄作は、書籍全体の九割にのぼる。評論雑誌は当然、それらを容赦なくこらしめ、書きたい気持ちにまかせてペンを走らせる詐欺まがいの売文行為を阻止しなければならない。それなのに著者や出版業者とのさもしい馴れ合い から、それらを奨励し、読者から時間と金を奪っている。 心が痛くなるほどの批判の数々!どの言葉も骨身に染みる。
1投稿日: 2025.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体を通して批判的な文章なのだが、文章力強くエネルギーに満ち溢れていて一種の爽快感となっている。 本書内でも語られている通り比喩表現が秀逸で哲学書をあまり読まない自分でも比較的読みやすかった。 「著述と文体について」は当時のドイツ文学界に対する批判が延々と綴られているので現代に読む自分としては冗長に感じる部分もあるがそれだけ感情がこもっているとも受け取れる。 現代においても学ぶところの多い名著。
0投稿日: 2025.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログブ、ブチギレてる....? 清々しいばかりのキレ方と、その主張や論旨の鮮やかさに、スッキリ感満載の素晴らしい読書でした。今抱えている問いともぴったりでした。 大衆よ、アホになるから読書するなよ〜 他の訳は読んでないけどこの訳めっちゃ読みやすい!光文社の新訳シリーズほかにもチェックしてみようと思える!
0投稿日: 2025.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「自分の頭で考える」「著述と文体について」「読書について」の3章から成っているが、1,3章と2章で全く印象が異なる。 1,3章は現代にも通ずる鋭さがある。読書は他人の思索の過程をなぞる行為にすぎないという視点は秀逸。まぁ、何も考えないで生きてるよりは読書をする方が100倍マシであると思うけど。 しかしながら、2章が酷い。言ってることは「格式高い昔の文法を大事にしようね。端折るのはダメ。」ということだけなのに、それになんと106ページも費やしている。彼は「ドイツ人の文は曖昧で、入り組んだ長い挿入文が満載」と述べているが、ここまで綺麗なブーメランは見たことがない… それでも歴史的大著であることは間違い無いので、読む時は2章を飛ばしましょう
0投稿日: 2025.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書をしている人間なら、必ず一度は読むべき作品。 読書は自分で考える力を衰えさせるという言葉は、自分の胸に深く突き刺さった。ただ、彼の言葉を引用している時点で、私は自分で物を考えられてはいないのかもしれないが。 昨今読書の有用性ばかり主張されるが、今の世の中には悪書が蔓延っている。だからこそ、読むべき本は選ばなければならない。
0投稿日: 2025.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログブックオフの100円コーナー本クオリティ。 「悪書は読者から、本来なら良書とその高尚な目的に向けられるべき時間と金と注意力をうばいとる」(P144)とか言ってるけど、ブーメラン刺さってますよ。 本書の主張は以下に尽きる。「むやみに本を読むな、自分の頭で考えろ」「流行りの薄っぺらい本は読むな、古典の原典を読め」「文章はわかりやすく書け、文法を乱すな」。本当にこれだけなのだ。200ページ足らずのごく短い書物とはいえ、たったこれだけのことを伝えるには冗長すぎる。 残りのページはひたすら、「卑劣な三文文士」への憎悪を撒き散らすだけ。矛先は匿名の批評家、文法の乱れ、分かりやすさ重視の古典の解説書など。現代日本にもよくいる欲求不満おじさんみたいで、ちょっと見てられない。 これを「舌鋒鋭い批判」と形容する人もいるが、果たしてこれが相応しい表現なのか、以下の引用を読んで考えてみてほしい。 「(匿名批評家は一人称に)自己を卑下する形を用いるべきだ。たとえば「情けない取るに足らぬ私」「こずるい卑怯者の私」「覆面をした無能な私」「ろくでなしの卑しい私」などだ。それは、「ひとめにつかない田舎文芸新聞」の暗い穴から、シュシュッと走り出るアシナシトカゲのような連中、いいかげん悪行から足をあらうべき覆面の詐欺師にふさわしい修辞だ。」(P57)
2投稿日: 2025.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読むことは空っぽの水路に水を流す行為だ。 バカが金のために書いた本は読むな。 本を読んだだけ、行動しただけで、全てをわかった気になるな。自分でそこから考えろ。 思考しない読書なら読まないほうがマシ。 痛快毒舌本だった。
2投稿日: 2024.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「読書するとは、自分でものを考えずに、代わりに他人に考えてもらうことだ」はよく引用される箇所だが、それ以外にも「良書を読むための条件は、悪書を読まないことだ。なにしろ人生は短く、時間とエネルギーには限りがあるのだから。」だったり、「読書と同じように、単なる経験も思索の代わりにはなれない。」だったり、ギクリとする記述が多く見られる。その他にも古典や原著を勧めていたり、多読を批判していたりと、著者の読書についての独特の見解が読む者の心に突き刺さる。果敢に読書に取り組んできた自分にもこれらの言葉は突き刺さり、繰り返し問いかけた。読書できているのか、と。読む者に問いかける切れ味抜群の言葉たち。読書する者なら一度は手にして欲しい著書である。
1投稿日: 2024.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログショーペンハウアーの『余録と補遺』から、読書に関する3篇、「自分の頭で考える(思索)」、「著述と文体について(著作と文体)」、「読書について」を収録したもの。上記カッコ内のタイトルは岩波文庫版の訳である。 3篇のうち、「著述と文体について」が一番ボリュームがある。そこではまず、お金のために書かれた本だと気付いたら、その本をすぐに投げ捨てなさいと促している。その部分を引用しよう。 まず物書きには二種類ある。テーマがあるから書くタイプと、書くために書くタイプだ。第一のタイプは思想や経験があり、それらは伝えるに値するものだと考えている。第二のタイプはお金が要るので、お金のために書く。書くために考える。できるかぎり長々と考えをつむぎだし (中略) ただ紙を埋めるために書いているのがすぐばれる (中略) 書くべきテーマがあるから書く人だけが、書くに値することを書く。(p32-33) 今日の日本でも、特にビジネス書では、お金のために書かれた中身のない本が数多く出版されている。そういう本に当たると、うんざりさせられる。そういった駄本に時間とお金を浪費しないように、私たちは本を見分ける力を身に付けなければならない。 残りの2篇、「自分の頭で考える」と「読書について」に共通しているのは、多読への注意喚起である。 読書は自分で考えることの代わりにしかならない (自分の頭で考える、p11) 読書するとは、自分でものを考えずに、代わりに他人に考えてもらうことだ。他人の心の運びをなぞっているだけだ (読書について、p138) そして、ここでも「悪書を読まないこと」の大切さを説いている。それでは、どのような本を読めば良いか? 新刊書、流行りの本ではない。また、偉人について論じた本でもない。 アウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルの以下の警句を引いて、偉人自身が書いた本を読むことを薦めている。 古人の書いたものを熱心に読みなさい。まことの大家を。現代人が古人について論じたものは、たいしたことはない。(シュレーゲル「古代の研究」) (読書について、p146) そして、重要な本は「続けて二度読むべきだ」としている。その理由はもちろん、理解が高まるためである。 たしかに、現在でも読み続けられている古典は、時の審判を経たものなので、本当に優れていることが証明された本である。本書も古典のひとつだが、このような古典を繰り返し味わうのが一番効率が良い読書といえるだろう。 本書を強引にひと言でまとめると、「売れている本ではなく、古典を繰り返し読んで、自分の頭で考えよ」ということになる。 以上のように読書に関して様々な示唆を得られる本であるが、ショーペンハウアーの自己弁護にも見えた。自著の『意志と表象としての世界』が売れず、くだらない本が売れていることへの批判とも見て取れるのである。 最後に、別訳の岩波文庫 青 (斎藤忍随/訳)の文体について、違いを書いておく。 2024年の現時点ではどちらの文庫も現役本であるが、どちらを読むか迷った際の参考にしていただければ幸いである。 以下は出だしの部分である。内容は同じなので、読みやすい方、好きな方を選んでほしい。 【岩波文庫 青 (斎藤忍随/訳)】 数量がいかに豊かでも、整理がついていなければ蔵書の効用はおぼつかなく、数量は乏しくても整理の完璧な蔵書であればすぐれた効果をおさめるが、知識のばあいも事情はまったく同様である。 【光文社古典新訳文庫 (鈴木芳子/訳)】 どんなにたくさんあっても警理されていない蔵書より、ほどよい冊数で、きちんと整理されている蔵書のほうが、ずっと役に立つ。同じことが知識についてもいえる。
1投稿日: 2024.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「読書とは他人の頭で考えることである」 何度も何度も強調されています いやもうほんとおっしゃる通りです
0投稿日: 2024.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書とは、他人の掘った溝に水を流すようなものです。 作られた溝に水を入れ、思考の川を作ることです。 才能ある人によって作られた溝は、きれいな流れの川になります。 ですが自分の川ではない。 自分で考えることは、自ら溝を掘り川を作ることです。 苦労の多い方法ですが、完成した思考の川は自分にしっくりくるオリジナルなものになります。 天才の作る川より不恰好であったとしても、それは自分の考えです。 読書と考えることは似てはいますが、全くの別物です。 自分で考える習慣を大切にしたいです。
6投稿日: 2024.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ偏屈なおじさんではあるけれど、言ってることはまぁまぁ共感。学びて思わざれば則ちくらし、思うて学ばざれば則ち危うしってね。
1投稿日: 2024.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ想像していたような、積極的な読書をすすめる本ではなかった。 というかぼーっと読んでいたら途中から「本を読むこと」というより「文章を書くこと」の話になっていて、ドイツ語の批判と文法解説になってきたので途中読み飛ばしてたらまた最後に読書の話に戻っていた。 読書は他人の知識を自分に刷り込むような行為だと著者は批判していましたが、まさに私が、自分の思考を本を読むことで上書きしてしまおうという目的で読書をしているので、ちょっと自分とは考え方が合わないもようです。 もちろん自分の頭で考えることは重要だけど、自分で考えるにも限界があるわけで。 他人の頭で考えた代表的なものが哲学だったりするし。 「自分の頭で考え抜いた仮説を補う手段」として読書を活用するのは是非やってみたいです。
9投稿日: 2024.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書よりも自分の思考の方が価値高いでしょって話。その考えもわかるが、その話のレベル感が違う気がする。ショーペンハウアーは1788-1860の人。その当時と比べて現代人は圧倒的に読書量が足りなさすぎて、思考しようにも①思考体力がない②思考する題材がない(ないものは考えようがない)から、読書はあまりするなという主張はあまり現代には適切でないかも。って思います。 でもその自分の思考が最高価値だよって主張自体は間違いなく、これまでの「読書系」の本とは別角度の意見で参考になった。読書マニアになりすぎず、そこからどう生かすかを軸にしようと思った。
1投稿日: 2024.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書と著述について、一般に「善い」とされるそれら営為を改めて振り返り、愚鈍な手法について強い主観で批判した本。 ショーペンハウアーを読むのは初めてだったけど、最初から最後まで口が悪すぎて終始笑いながら読めた。ページをめくる度に新しい悪口が出てくる。 「読書」は著者の思索をなぞるだけであり、まず自身の思考軸を持ち、それを補するものとして接しない限りは空虚な営為だという批判が主。特に多読や流行り物を批判する。 これは昨今、web上でインフルエンサーの意見を多量摂取し、それをなぞった主張するだけの人へも同じ批判となるだろう。 流行りのビジネス書を何冊も読むより、現代まで残っている古典書をマイペースに読み進めて咀嚼する方が思考に深みが増す。これは自身の経験則とも一致する。 読書が進まないと流行りものに手を出してしまうものだが、読む度に空虚な気持ちになるし、自戒していきたい。 著述は著者の顔だとし、それに自らの誇りを持ち、整然とした文体で書かれるべきであるとする。文章の書き方としても学ぶべき論は多くあった。 一方、そうあるべきものを匿名で出すことについても厳しく批判する。なにを著述するにしても、この認識を持って人と対峙するようにしたいと思った。 なんにせよ「他人の思想を借りるのではなく自分の思想を持ち、その思想を正しく著述しろ」という主張は深く共感するし、常に意識していきたい。 下手な文章を書くとこんな感じで罵倒されそうなので、少しでもまともな言葉を紡げるように日々精進である。
1投稿日: 2024.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログエッジの効いた言葉が軽快に続いていく。なんならこれでラップできるんじゃないかと思うくらいのディスもあったりして、マインドがラッパーと通じるような新鮮な感覚だった。 その一方で、 「読書は自分で考えることの代わりにしかならない」という言葉は、少し寂しいな とも思う。 物語が読者と繋がり、一つの世界を一緒に創りあげていく面白さや、それが生活の一部となり生きる糧になることも沢山あると思った。 ショーペンハウアーに「頭が空っぽの凡人」と形容されても、凡人が故の楽しみ方もあると思う。凡人がいるからこそ、非凡が生まれて、素晴らしい作品ができるとも思った。 けど、こう思えることもこの本があってからこそ。やっぱり楽しいね、読書って。
1投稿日: 2024.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ思索と読書のバランスについて書かれた本です。いわゆる、学びて思わざれなすなわちくらしと言う事について書かれた本です。 ただ、これを真に受けて読書を怠れば、思いて学ばざればい即ち殆うしと言う事になりかねない。 この時代の人たちは、我々より圧倒的に読書していた事を忘れてはいけない。 要は友人同様、読む本は選びなさいという事。 ヘッセの読書術より訳文が平易で読みやすく、同様の主旨で書かれているのでおすすめ。 ただヘッセと違って、それなら何を読めばいいのかと言うリストはない。
0投稿日: 2024.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学書の中ではかなり読み易い部類に入るだろう。全く哲学に触れてこなかった人や中学生くらいでもこれは読めると思うし、衝撃的ながらも「確かに」と首肯してしまう内容になっている。 「読書について」とあるが、ショーペンハウアーはその冒頭で「読書するとは、自分でものを考えずに、代わりに他人に考えてもらうことだ。他人の心の運びをなぞっているだけだ」とバッサリ断じてしまう。しかしよくよく考えると確かにその通りなのだ。読書とは他人の思考をなぞる行為でしかない。下手な自己啓発本を礼賛する行為に嫌悪感を感じるのはそれが先鋭化されているからかもしれない。 とはいえ、ショーペンハウアーは読書そのものを否定している訳ではない。他人の心の運びをなぞる行為であるからこそ、良書を読み、自身で思考する力を育めと言っている。ただこれは非常に難しく、果てしない作業だと思う。ショーペンハウアーほどの飛び抜けた才能を持つ人ならともかく、我々は良書と悪書の区別が最初からつけられるほど賢くはない。悪書を読むことで良書を知ることもあるだろう。ショーペンハウアーは現代に残る古典を読むことを良書のみに当たる方法としているが、さすがに古典だけを読むわけにもいかないしね。(あるいは古典を読み耽った後であれば現代の良書もわかるという意味かもしれないが、そこまで簡単にいくのか?と個人的には感じる) しかしそっちの系統を読んだ訳じゃないので賛同も反駁もできないけど、いくらなんでもフィヒテとヘーゲル嫌いすぎじゃないこの人?
7投稿日: 2024.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ確か友人に勧められて買ってあった。「読書について」10「反復は勉学の母である」は耳の痛い話しだった。「重要な本はどれもみな、続けて2度読むべきだ。」ああ、そうなんだなぁと思う。8「古人の書いたものを熱心に読みなさい。まことの大家を。」かの出口治明さんもそうおっしゃっていた。でも古典難しいもんなぁ。
0投稿日: 2024.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログショーペンハウアーが、無能な作家や出版社のことをめちゃくちゃに貶しててそこが面白い。主張 は的を得ており、どれも本質的だ。
0投稿日: 2023.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ耳に痛い。本を読んでも身になっていないと薄々感づいてはいた。そういうことだったのかと一撃を喰らう。 下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるで、とにかくたくさん読めば得るものもあるだろうと読んできた。古典も新しいものもだ。欲深な私は両方を読みたい。せめてこれからは自分の頭でじっくり考えてから脳内にしまうことを心掛ける。 間違った使い方の日本語と匿名の書き込みが溢れる今の日本をショウペンハウアーがみたら何と言うか。罵られる。
0投稿日: 2023.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと読みたいと思っていた本。 本を読むのは大好きだけど、それで満足していてはだめ。 どんなにたくさん読んでも、自分の頭で考えずに鵜呑みにしていてはだめ。 自分の頭で考えろ! それが大事。
0投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読むとは、自分の頭ではなく、他人の頭で考えることだ。 衝撃を受けた一冊。読書は量ではなく質であると再認識させてもらった。悪書はすぐに切り捨てることも大事だと感じた。 比喩が巧みで舌鋒鋭い批判は爽快ですらある。
0投稿日: 2023.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「読書をすると頭が悪くなる?」 なるほど、、、と思いつつ、自分も前から思ってたことを昔の人も同じように思っていたことに感銘しました。 本読んで、感想をまとめて、もしくは線を引いたところを書き出して、そして読み返して、よく思索する、というプロセスは物凄く大事だと思いました
2投稿日: 2023.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「悪書から被るものはどんなに少なくとも、少なすぎることはなく、良書はどんなに頻繁に読んでも、読みすぎることはない。悪書は知性を毒し、精神をそこなう。 良書を読むための条件は、悪書を読まないことだ。なにしろ人生は短く、時間とエネルギーには限りがあるのだから」(ショーペンハウアー『読書について』鈴木芳子訳、光文社古典新訳文庫 pp.145-146)
0投稿日: 2023.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログSNSとかゲームとかに時間を食われている人間だから昔の時代の本ばかり読んでる人より頭悪いけど、ちゃんと本読むだけじゃなくて頭使わないとなって思った
0投稿日: 2023.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書のすすめみたいなものかと思って読み始めたら「本を読むより自分の頭で考えるべき」といきなり書かれていてズシリときた。「読書していると自分の頭で考える必要がなく、他人に代わりに考えてもらえるから気が休まるのである」というあたりは本当に耳が痛い。 とはいえショーペンハウアーだって本はしっかり読んでいるわけで、読むなら良書だけを読み、書かれた内容をしっかり反芻せよということ。 「著述と文体」という論説では、悪書ばかりが濫造される当時のドイツ文壇の姿勢から、ドイツ人の文章の書き方自体まで、くどいほどにdisりまくっている。(本当にくどいので途中から読まなくてもいい。くどすぎるので★を1つ減らした) 解説にも書かれているし各所でも言われていると思うが、比喩が的確でピリッとしていてとても伝わりやすいし、読んでいて楽しい。このあたりは流石。 自分の読書スタイルへの戒めとして座右に置いておくのもよいと思う。
2投稿日: 2023.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログショーペンハウアーの事をどんな人物なのかを知らず、タイトルからもっと緩いものかと手に取った。 なので初手からズバズバと読み手の心構えや匿名批評家へのヘイトをぶっこまれて逆に笑ってしまった。 そしてその辛口なコメントは不思議と小気味よく(訳が良かったのかもしれない)まあそうままならないものだけれど、気持ちは分かるし言ってる事は正しいと思うなと少し微笑ましくなど思った。 印象として苛烈な人だが、この人物には不思議と好感を抱いたので他の著書も読んでいきたいと思う。 読みすすめながら当時の時代背景などをググったりしていたが、なるほどなぁと解像度が若干上がった気がするので、たのしい。 ところでドイツ語の簡略化を嘆かわしい!と訴えていた訳だが実際例としてあげられているものを見ると『そこ変えられたら素人は本当にわからなくない?!』となる改変ぷりだったので、現在、まさかそれが主流になってたりするのか…?とちょっとドキドキしている。どうなんだろう。 時代の流れというのは、面白い。
1投稿日: 2023.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読もうと思った理由】 もともと生涯で読むべき古典リストの中にリストアップしていた書籍だ。 村上春樹氏の長編小説に対し、自分の中で苦手意識を克服できたので、文学に関しては小休止してもいいかなと思った。哲学・思想書の中では、本書がもっとも読みやすい部類だと思うので、哲学・思想書を久しぶりに読むのには、適切なタイミングかなと。また読書から得られる気づきを、もっと今後の人生に直結するものにしたかったので、今回読むに至る。 【ショーペンハウアーってどんな人?】 [1788〜1860] ダンツィヒ生まれのドイツの哲学者。「生の哲学」の祖。ゲッティング大学で自然科学・歴史・哲学を学び、プラトンとカント、インド哲学を研究する。イェーナ大学で論文「充足理由律の四根について」によりドクトルの学位取得後、1820年ベルリン大学講師となったが、当時ヘーゲル哲学が全ドイツを席巻、人気絶頂のヘーゲル正教授に圧倒され辞任し、在野の学者となる。主著である「意志と表象としての世界」(1819-1844)を敷衍(ふえん)したエッセイ「余録と補遺」(1851)がベストセラーになると、彼の思想全体も一躍注目を集め、晩年になってから名声を博した。フランクフルトにて没。ニーチェやヴァーグナーをはじめ、哲学・文学・芸術の分野で後世に大きな影響を及ぼした。 【感想】 本書を読む前の読書に対する自分の考え方は以下だ。その本を読む前から自分の知識として持っていた既存知識と、新たに読書を経て得た、新たな知識を融合して、新たな知恵として自分の血肉とする。(詳しくは「行き先はいつも名著が教えてくれる」の感想欄に書いてます) 上記の読書に対する取り組みで改善したかったところは、過去の知識を自分の記憶の中にいかに取り出しやすい状態で保存しておけるかだ。その部分がまだまだ弱いと思っており、そこを改善したかった。上記の課題をメインテーマに読んだ。 読了後に僕が感じた、著者が伝えたかったであろう本質の部分は以下です。 ・読書をするとは、自分でものを考えずに代わりに他人に考えてもらうことだ。 ・読書をして自分の血肉とできるのは、何度も反復しじっくり考えたときだけだ。 ・人生は短く、時間は限られている。なので読む本は厳選し、良書のみを読むべきだ。 ・重要な本はすべて続けて2度読むべきだ。 2度目になると内容のつながりが、より一層よくわかるし、結末がわかっていれば、出だしからより正しく理解できる。 ・真に正しく理解された哲学は、実質的で最良の叡智となる。 ・文章を書くときは平易な言葉を使い、非凡なことを書くべきだ。 【本書から得た気づき】 上記ポイントを考えている際に、あぁ、まさしくこのことが最も重要なんだと思った。本を読んでインプットした情報を、ブグログにアウトプットする際に、本質的に重要な部分だけをまとめるときに一番自分で考えている。 具体的には以下だ。 1.本を読んでいて重要だと思った部分に付箋を貼っていく。 2.読了後に、付箋を貼った部分のみをスマホのメモに書いていく。 3.メモに書いたものを全体を俯瞰して見て、思考する。 (具体的には、この部分とこの部分は一つの文章に纏めれるとか、この部分は内容が重複しているので削除できるなとか、分量として多すぎれば何を削るべきかを考えたりなど。) 4.出来上がった内容を何度も読んで、前後のつながりでおかしいものは無いかなど、チェックし添削する。(その際に村上春樹氏から学んだ、読んでいただける方に向けて、真心を持って、少しでも読みやすい文章になる様に推敲しまくる。) 上記一連の作業をしているときに、自分一人の力で考えている。あーでもない、こーでもないと。その思考時間が長ければ長いほど、自分の長期記憶に残りやすくなり、その後、期間が空いても、必要なときに記憶を取り出しやすくなる。インプットしてからアウトプットするまでの思考時間が、もっとも大事なんだと気づけたことが、今回の読書から得れた最大の気づきだ。 ブグログに感想をアップする前は、一冊の本を読んでここまで思考していなかったと思う。アウトプットそのものが重要ではなく、アウトプットするまでの思考時間が最重要だと明確化できた。このことが今後の人生において、結構ターニングポイントになるかもしれない。 【雑感】 本当はこの後、ニーチェの入門書(飲茶氏の本)を読んで、本番の「ツァラトゥストラ」を読みたかった。ただ図書館の予約本である、「口訳 古事記」(町田康氏著)が届いたとの連絡がきたので、次は上記を読みます。町田康氏は初読みだが、この人すごい異色の経歴の持ち主だ。元々パンクロッカーとしてメジャーデビュー後に、作家に転身。芥川賞も受賞している。今作は誰もが知っている日本最古の歴史書、古事記を口語でかつ、関西弁バリバリで語っているという。そんなハチャメチャな人は大好きなので、俄然読みたくなった。
72投稿日: 2023.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ正論を切れ味のいい辛口でズバズバ言い続けている本書。とにかく口が悪くて驚いたけど、自分の頭で考えることの重要性や自分の考えに責任を持つことの必要性を真正面から説いていた。ドイツ人の彼がドイツ国民をひたすら悪く言うのは愛情なのだろうか。祖国の未来を憂いて言っていたのか、愛想を尽かしていたのか。どちらだろう。
3投稿日: 2023.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「自分の頭で考える」、「読書について」という2つのタイトルに興味を惹かれ手に取りました。 「本を読むとは、自分の頭ではなく、他人の頭で考えること」というフレーズが衝撃でした。 確かに目的がなくただ読むだけでは「ふ〜ん」で終わってしまい、自分のものになりません。 なので、「本を読んでも、自分の血となり肉となることができるのは、反芻し、じっくり考えたことだけ」という考えには納得です。 「反復は勉学の母である」、「重要な本はどれもみな、続けて二度読むべき」を心がけていこうと思います。
1投稿日: 2023.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「頭の中は本の山 永遠に読み続ける 悟ることなく」 「父祖の残したものを完全に自分のものにするにら自ら獲得しなさい」 「誰だって、判断するより、むしろ信じたい」 耳が痛い、、 ただの多読は脳のビッグデータにはなるから、鵜呑みにはせず、ただ、思考の補佐だということも忘れずに
2投稿日: 2023.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ『読書は自分で考えることの代わりにしかならない。自分の思考の手綱を他人にゆだねることだ』 『多読に走ると精神のしなやかさが奪われる』 なかなか厳しい言葉で紡がれたこの本は、粗悪な文字書きや多読をする者、乱れた文体を使う者たちをばっさばっさと斬りまくる。 それと同時に筆者のショーペンハウアーは本当に本を、文章を愛していたんだな、と。 この本が生み出されて二百年。”書くこと”はより身近になり、それを”発信する”人も爆発的に増えた。 この世に溢れかえる文章たちに、彼は何を感じるだろう。
6投稿日: 2022.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ母国語を正しく使うことの難しさを痛感した。 先生によると、何も難しい言葉を連ねることが正しい日本語ではないようで、解りやすく、簡潔に、丁寧で美しい文字数を省かず、かといって長すぎず説く。 難しい言葉を連ねると「気取った三文文士」風になるという。 母国語の大切さ、大切にしようと努力を努める姿勢にも書かれている。 また、ホラー小説や犯罪小説が蔓延する中で道徳的観念と同時に本人が持つ知性や精神をそこなってしまうことにも警鐘を鳴らしている。 誰もが発言できるSNSや匿名の書籍にて、母国語を正しく使えていない人達に怒りの鉄槌を下す。 そして、その正しく美しい母国語の中に己の中の思想や哲学を語ることを説くが、簡単そうに響くがなんと難しいことか! その為に、立ち止まりじっくり自分の頭で考えて判断を下し、初めて発信できる。 読む専門、物書き志望の方はもちろん、本好きなら一読するべきではないかと思う。 知性を愛し、言葉を愛する先生の言葉はぐさりと刺さり、学ぶこともかなりあった。 読んで良かったと心から思えた本。
2投稿日: 2022.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【読了直後のコメント】 ディスり具合が痛快 タイトルから、読書の仕方の指南書かと思ったが、ショーペンハウアー先生が、その当時の「今どきの出版物の業界や言葉の乱れはなっとらん!!!」という怒りを筆に任せて書き連ねた力作。 ドイツディスり激しい(笑)(笑)(笑) 訳者あとがきにもある通り、現代日本も同様なので、今も昔も世界も日本も変わらんなと。 われこそは正統派という思いがあって、流行り物見てストレス溜まってんだなーってかんじ。 ショーペンハウアーとゲーテは同じ時代の人なんだなー。 【きっかけ】 Kindleを耳読書した「自己肯定感を上げる OUTPUT読書術」のアバタローさんが「読んでみては」といっていたのが聞こえた。短いし読みやすいのでと言っていたような。短いはともかく、読みやすいか? アバタローさんみたいに早稲田文学部卒業だと読みやすいのかもしれない。 【目的】 身になる読書をたくさんしたいのでノウハウを知りたい 【Amazon Kindle 耳読書】 【要再読】 耳読書なので実践に移すには必要箇所を精読 耳読書、細々したところはまったく頭に入っていない。とりあえず流した感じ。 【読了後の内容メモ】 ・読書は他人の思考なのでよろしくない(読書否定派かっ。基礎知識がないと思索はできないだろうから、勉強は否定してないと思う。思想家や学者が他人の思考で飯を食って偉そうなのが気に食わないということだろう) ・肝心なことが言えるほどの能力がないのに偉そうに見せるために薄っぺらい文章をこねくり回し、それを称賛する読者がいることへの嘆き。 ・ 文法の乱れへの嘆き怒り、嘆き(事例を上げて細々説明してくださっているが、外来語わからんので雰囲気だけ聞きました。私も日本語警察なところがあるので、お怒りはよく分かる。) ・古典は良い。新しい本は他人の思考をこねくり回した薄っぺらい本なのに、読者はそれをもてはやすのでムカつく ・売文業、偉く見られたいための文章を軽蔑。 ・こっちは名前出して文章書いて出してるのに、匿名の読者が批判してくるのムカつく ・偉そうに見せるために、読者がわからない言葉を使うことへの批判。言いたいことは普通の言葉で話せ by シェークスピア(学者さんや専門家が普通の人に伝えるときには専門用語で話すなと、よく言われますね) ・良い本はすぐ2回目を読むべき。2回目は結末がわかっているので導入部の工夫などを新たな視点で読める ・(KindleをAlexaアプリ/Androidで読み上げさせると、「神のみぞ知る」が「神の味噌汁」に聞こえるのでクスッとなる)
1投稿日: 2022.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログなじめなかったー 「正しい文章」も大事だと思うけど、言葉や表現のゆらぎを楽しむのも読書の楽しみのひとつなのではないかなと個人的には思います。もちろん、言葉への正しい理解の上に立つという前提がありますが。 「多読に走らない」とか、「本は食物のようなもの」という考え方には共感できました。
2投稿日: 2022.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ(全ページ読破した書籍のみ、減点方式でレビューを投稿しています) 哲学者のショーペンハウアー大先生が、読書について(主に警鐘を鳴らす目的で)著述した本。 読書を “自分の思索の手綱を他人にゆだねること” とし、 多読を “たくさんの旅行案内書をながめて、その土地に詳しくなった人” と否定し、 新刊書の著者を “陳腐で底の浅いもの” と断ずる。 いやいや、そこまでボコボコにしなくても。 そうは思うものの、論理は簡明かつ簡潔で切れ味が鋭く、最後の「訳者あとがき」で訳者が言うところの「ハハーッ、ごもっともでございます」と完全に気持ちが一致しすぎて笑ってしまいました。 ただ言葉の端々に憎悪のようなものが滲み出ており、お説教というより憂さ晴らしのように見える部分もしばしば。 訳者解説でショーペンハウアーが自分の自信作を評価されなかったことや、本人がかなりプライドが高い人種であったことが記載してあり、腑に落ちました。 恐らく、彼の生きた時代は「人々が新書に群がり、多読に走る一方で、自分の本は売れない」という状況だった環境だったのだろうな、と気の毒には思いましたが、 単純に言葉遣いが汚いと感じたので、星を一つ減らしました。 読書を意味のあるものにするためにも、自戒を込めて何度も読み返したい本でした。
2投稿日: 2022.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
初ショペンハウアー!読書についていろんな考え方を知りたく、小林秀雄の「読書について」に続いて読んだ読書、哲学に関して述べられた本。これを機にほかのショペンハウアーの本も読んでみたくなった! 著者は、文体や体裁のような「読みやすさ」から、作者の思想や思索の深さまで含めた様々な観点から良書/悪書とは何か、をはっきりと主張している。伝わりにくい文章や、よく練られていない内容を出版する作家を痛烈に批判しており、これまで以上に読んだ本に対して、評価する(その本を読むことに使った時間の価値を考える)ことができそうだ。 これまではほとんど評価することはなく、自分にとっての新情報が発見できればいいや、くらいに考えていた。 また、多読についても厳しい意見を述べている。本を読むことで「考える」ことを放棄するのはいかがなものかということである。興味深かった! ただ私は、良書を見極めるための眼を養うためには、一定期間、多読に挑戦しても良いのではないかと思う。著者が言いたいことはきっと、読書を自己研鑽の手段として位置付けているにもかかわらず、読書そのものが目的化している人への批判なんだと思うが。 著者に考え抜かれた「読書とは」は、何度も読み返して咀嚼したいフレーズがたくさんあったので、ぜひ購入したい。(基本図書館で借りる人間) P106 ・いい加減に書く人は、初めから自分の思想に大きな価値を置いていないと告白するようなものだ。というのも、自分の思想がいかに重要で真理を含んでいるか確認していれば、情熱がおのずからわき起こる。その情熱は、倦まずたゆまず、最も明瞭で美しい力強い表現を追求するのに欠かせぬものであり、一般の人なら聖遺物や計り知れない価値のある芸術品、金銀の器に対してのみ沸き起こるものだろう。 P138 ・無知は人間の品格を落とす。しかし品格の下落がはじめるのは、無知な人間が金持ちになったときだ。貧しければ、貧苦が枷となり、仕事が知識の肩代わりをし、頭は仕事のことでいっぱいだ。これに対して無知な金持ちは、ただ情欲にふけり、日ごろ目にする家畜と同じだ。さらにそうした連中は富と暇を、もっとも価値あるものに活用しなかったという非難がくわわる P138 ・読書するとは、自分でものを考えずに、代わりに他人に考えてもらうことだ。他人の心の運びをなぞっているだけだ。(中略)したがって読書をしていると、ものを考える活動は大部分、棚上げされる。自分の頭で考える営みをはなれて、読書にうつると、ほっとするのはそのためだ。 P141 ・作家には説得力、イメージの豊かさ、比喩の才能、大胆さ、辛辣さ、簡潔化、優美さ、軽快な言い回し、さらにウィット、意表をつうコントラスト、簡にして要を得た表現、飾り気のなさなど、さまざまな特性がある。だがその作家の作品を読んだからと言って、そうした特性が私たちの身につくわけではない。しかし私たちが、そうした特性を素質として、ポテンシャルとして持っていれば、読書することでこれらを心に呼び起こし、自覚することができる。 P149 ・読んだものをすべて覚えておきたがるのは、食べたものをみな身体にとどめておきたがるようなものだ。(中略)身体が自分と同質のものしか吸収しないように、私たちはみな、自分が興味あるもの、つまり自分の思想体系や目的に合うものしか自分の中にとどめておけない。 ・重要な本はみな、続けて二度読むべきだ。二度目になると、内容のつながりがいっそうよくわかるし、結末がわかっていれば、出だしをいっそう正しく理解できるからだ。また二度目になると、どの箇所も一度目とはちがうムード、ちがう気分で読むので、あたかも同じ対象をちがう証明のもとで見るように、印象も変わってくるからだ。
4投稿日: 2022.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書<考える 因って、人生を読書に費やすな! ということらしい。 哲学者の読書についての本なので、何の気なしに買って読んだが面白かった。 「人生を読書に費やし、本から知識をくみ取った人は、たくさんの旅行案内所を眺めて、その土地に詳しくなった人のようなものだ。」(「自分の頭で考える」より) アナロジーが秀逸でクスッと笑える。時々、他の哲学者や作家をディスる。 あまり本を読まず自分で思索せよというのが著者の言い分だ。読むなら良書を読めと。しかも時間をかけるなと。 「良書を読むための条件は、悪書を読まないことだ。なにしろ人生は短く、時間とエネルギーには限りがあるのだから。」(「読書について」より)
0投稿日: 2022.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「本を買うとき、それを読む時間も一緒に買えたら、すばらしいことだろう。」 「読んだものをすべて覚えておきたがるのは、食べたものをみな身体にとどめておきたがるようなものだ。」 本が沢山あろうとなかろうと、自分の時間は変わらない。そして、読んだ本を消化して自分の中に落とし込むのもまた時間が必要である。読んだ本を忘れない、という人がすごいと思ってた。でも、大事なのは内容を覚えてるだけじゃなくて自分の中に取り入れること。自分の、思索体系に。 読めなくて苦労する本があっても、それは自分に間違いじゃないことがわかった。 前読んだ岡本太郎の本に「知識は積み上げるな、むしろ蹴飛ばしてしまえ」と書いてあったのはこういうことか、と思った。岡本太郎もショーペンハウアーに読みふけっていたそうだ。なんとなく、つながった。 『著述と文体について』ではドイツ語の乱れと金儲けのために物書きをする風潮を激しく批判しいる。ショーペンハウアーは言葉を非常に大切にしているのだと感じた。それゆえに考えなしに言葉を使うこと、もとより乱れた言葉を使うほど何も考えてないことを鋭く批判している。 自分の頭で考えろ。 哲学の先人に、言葉で殴られた気分になるほど目が覚める本だった。
3投稿日: 2022.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログショーペンハウアー「読書について」読了。3つ小論で編成されどれも参考になった。読書に関する事はもちろん文章を書くための明快な指摘が良かった。例えばタイトルはシンプルでわかりやすい事。生真面目なショーペンハウアー先生が愚痴を溢しながら説教してくれる様子が幾度となく思い浮かんだ。
1投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は少なからず読書信者なところがあるけど、そこに釘を刺される機会を与えてくれる本だった 知識を蓄えることは大事だけど、何より大事なのは自分の頭で考えること それは自分の考えなのか他人の考えなのか吟味することを怠れば自分自身の核が失われてしまうだろう ✏こうして見ると、自分の頭で考える思索家と博覧強記の愛書家を、その話しぶりに接するだけで容易に見分けられるのは不思議ではない。自分の頭で考える思索家は、真剣で、直接的で根源的なものを取り扱うという特徴があり、自分の考えや表現をすべてみずから検証してゆく。これに対して博覧強記の愛書家は、なにもかも二番煎じで、使い古された概念、古物商で買い集めたがらくたにすぎず、複製品をまた複製したかのように、どんよりと色あせている。型どおりの陳腐な言い回しや、はやりの流行語から成る彼の文体は、他国の硬貨ばかり流通している小国を思わせる。すなわち自分の力ではなにも造り出せないのだ。 ✏セネカが言うように「誰だって、判断するより、むしろ信じたい」(『幸福な人生について』Ⅰ、四)からだ。 ✏だが真に価値があるのは、自分自身のために考えたことだけだ。思索者は第一におのずから思索するタイプ、第二に他者を指向するタイプ、この二つに分けられる。 ✏第一のタイプは真の思索家だ。二重の意味で〈Selbstdenker〉、自分の頭で、自分のために考える人だ。本来の哲学者、知を愛する者だ。すなわち、かれらだけが真剣に問題と向き合っている。かれらの生きる喜びと幸せは、まさしく考えることにある。 第二のタイプはソフィスト、詭弁家だ。「~らしさ」を求め、他人の目に哲学者らしく映ることに幸福をもとめる。かれらはこれを真剣に追究している。二つのタイプのどちらに入るかは、やり方全般をみれば、ほどなく気づく。リヒテンベルクは第一のタイプの鑑であり、ヘルダーは第二のタイプに入る。 ✏思想の価値を決めるのは、素材か、表現形式だ。素材とは「何について考えたのか」であり、表現形式とはどう素材に手を加えたのか、「どう考えたのか」だ。 ✏したがって有名な本なら、それは素材のおかげか、表現形式のおかげか、よく区別しなければいけない。 ✏しかしながら一般読者は表現形式よりも、素材にずっと多くの関心を向け、まさにそのためになかなか教養がつちかわれない。 ✏何ひとつ悪とみなさない人間にとって、善もまた存在しない。 ✏「どのように」考えたか、つまり思索の根っこにある特徴と一貫したクオリティを精確に写し出したのが文体だ。文体は、?その人の全思想の外形的特徴であり、「何を」「何について」考えていようとも、常に同じはずだ。 ✏読書するとは、自分でものを考えずに、代わりに他人に考えてもらうことだ。
4投稿日: 2022.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
印象に残った言葉 読書は自分で考えることの代わりにしかならない。 自分の思索の手綱を他人に委ねることだ。 習得しただけの真理は、義手や義足、義歯、蝋製の鼻やせいぜい別の肉でこしらえた降鼻術のように、私たちに貼り付いているにすぎない。だが自分で考えて獲得した真理は生まれながらに備わっている四肢に等しい。それだけがほんとうに私たちの血となり!肉となる。考える人と、単なる物知りとの違いはここにある。
1投稿日: 2022.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ自らの頭で考え、読書することの大切さを教えてくれる作品です。 中盤の、当時のドイツ文学会への批判は、やや執拗かつ冗長に感じたため、読み飛ばしました。これらの批判的な考えは、当時の学問の発展においては重要な意義をもっていたのかもしれませんが、現代人には共感しにくいもののように思います。
1投稿日: 2022.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書について知見を広めたくて色々漁ってたら見つけた本。普段こういう本って敷居が高くて手が出しにくいけど、電子書籍になってたので結構読みやすかった。 まず、ドイツ人、ドイツ文学批判が凄すぎる!笑 著者の豊富な語彙力が巧みに生かされ、辛辣な言葉で言いたい放題。これ、ドイツの人は怒るのでは?レベル。すごく刺激的。 基本的には読書は良いものである、という考えのもとで話が進むと思いきや、読書ばっかりしてる人間はダメだ!という主張から始まった。面白い。詳細にいうと、読書は他の人の考えを自分の中に落とし込む行為だから、読書ばっかりして自分で何も考えなくなったらオシマイという意味でしたが。 あと古人の名作を読まないで現代人の書いた最新作を読みたがるというくだり。いやいや、現代にも素晴らしい作家はいますよ!と共に、なんだかんだ近代文学は敬遠しがちなので、挑戦してみなきゃダメだなと思った。思ったけど実践するかどうかはわからん。読書は娯楽派だから…。
1投稿日: 2022.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
再読 本書は自分で考えるとは何か、本に対する姿勢、読むべき本について書いた本。本書の内容と自分の考えを以下にまとめる。 まず自分の頭で考えると言う事は、自説を立てて後から得た情報をもとに学ぶ。だから自説を補強するに過ぎない。しかし本ばかり読んでいる人は本から拾い集めた考えで全体を構成しており肝心となる骨組みがない。だから本を読むより思考に励むことが重要。 本書引用 「頭の中は本の山 永遠に読み続ける。悟ることなく。」ーポープ 「誰だって、判断するより、むしろ信じたい。」ーセネカ 本はあくまでも助言であり、正解ではない。しかし信じてやまない人が多くいるために、ポープやセネカの言葉を用いて説明したのではないだろうか。 怪しい宗教や著名人の考えを一部切り抜いた記事がはびこるのも説明がつく。 思考することをやめ、他人の考えを信じてしまえば楽なんだろう。しかし人生はそんな簡単なものではない。その人はその考えで上手くいったが、誰にでも当てはまることではないと思う。つまり人生とは自分で思考し模索しながら自分だけの正解を探していく旅だと思う。 次に読書する姿勢について。読書っていうのは他人の考えをなぞる行為であると言う事、つまり本を読むばかりでは骨休めになっても自分の頭で考える能力はつかない。本当に自分の力になる時は反芻しじっくり考えたときだけ。 本書引用「書き記された思想は砂浜の足跡以上のものではない。歩行者のたどった道は見えるが、歩行者が見た景色が見えない。」 本はあくまでも他人の思想だ。自分の思想ではない。 だから思考や体験を通して自らの思想を確立する必要がある。いつまでも他人の思想に寄りかかっていては自分の生を本当の意味で生きることができない。 自らの目で人生を見つめ、自らの足で人生を歩むのだ。 最後に読むべき本について。本書ではもっぱら不朽の名作をお勧めしている。 そして「現代人が古人について書いた本は大したことない。」と述べている。 この考えに関してはいかがなものかと思う。確かに今もなお、読み継がれている作品は良書が多いが、中には現代にも当てはまるのだろうかと思う作品も少なからずある。 名作には読み継がれる理由があるのも理解できるが、だからといって現代人が書いた本は大したことないと言うのは誤りでは無いだろうか。現代の作品が今後読み継がれる可能性も充分にある。名作は確かに良いが、そればかり読むのはどうなのだろうか、現代人の柔軟な思考をした作家の作品も読むべきだと思う。 これに関しては自分の中ではっきりとした正解が出ていない為に少しあやふやだ。 ショーペンハウアーの他の作品も気になるな。
2投稿日: 2022.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「著述と文体について」 文章には主張・思想が必要である/それを伝えるために簡潔・明解でなければならない/したがって正しい言葉を使わなければならない、ということをブチギレながら3、4回は繰り返されるので、疲れる。サラウンドで怒鳴られている気分。自分がどこを歩いているのかわからなくなる。 それを除けば、主張が丁寧に、何度も出てくるので読みやすい。
4投稿日: 2022.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ショーペンハウエル 18.19世紀のドイツ文豪で、ゲーテとも関わりがある。 外国の方の書いた本を読んだのはいつぶりか分からないが、やはり日本の本とは全く違う視点で書かれていて新鮮だった。ドイツの国民気質や歴史についても少し知る事ができた。 全体的に比喩が巧みであり、切れ味のある文章だと感じた。本文でも述べられていたが、物事の本質を理解するには、身近な比喩が出来ることが重要となる。それを自ら体現していると感じた。 読書をすることは、自分で思考するのを辞めて、他人に代わりに思考してもらっている状態である、という指摘。どうすれば良いか、流行りの本ではなく、昔から廃ることなく読み継がれている良書を読み、続けて2度読み、思考するべき。
2投稿日: 2022.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ【本を読む、それだけで終わらせないために】 いまこうやって、どんな感想を書こうかパソコンの前でぼんやりしていると、ショーペンハウエル先生の、「書くまで考えないタイプの物書きは、運を天に任せて狩りに出る狩人のようなものだ。多くの獲物をたずさえて帰路につくのは難しい。」というお叱りの言葉が聞こえる気がしてきます。 うう……申し訳ございません(私は物書きではないけれど)。 現代の文章ではあまり出会えない、はっきりした批判の言葉に圧倒されつつ、たまにめげそうになりつつ、たくさん刺激を受けて読了。 「本は著者の思想を印刷したものにほかならない。思想の価値を決めるのは、素材か、表現形式だ。素材とは『何について考えたのか』であり、表現形式とはどう素材に手を加えたのか、『どう考えたのか』だ。」 「真に簡潔で力強く、含蕃のある表現をするためには、どの概念にも、どんなに微細な変化や微妙なニュアンスにも厳密に対応する語を自在にあやつる国語力がなければならない。」 などなど。 ショーペンハウエルはただ本を読むこと、冊数を重ねることを良しとしないけれど、それは読書の否定的な面を指摘することで、「読む」ことの一歩先へ進みなさい、と読者に促しているのだと思います。 厳しく激しい批判の言葉の数々は、それだけ強い危機感と真の思想への愛の裏返し。 「読む」だけで終わらせずに、「自分の頭で考える」……うーん、難しそうだし、大変だなあ、と思いつつ、次に手にとる本は、本書に書かれたヒントを意識して読んでみよう、と少しわくわくしています。
21投稿日: 2022.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想を書くのにこんなに気が重たくなる本もなかなかない。 「自分の頭で考える」「読書について」では、多読するな、本当に優れた本だけを読め、という旨の主張が豊富な比喩表現で示されている。 多くの箇所で、読書なんか他人に思考を預けることでしかないんだからあんまり時間かけてやるもんじゃないよ、という主張がされているが、気になったのは以下の箇所。 ———————————— 読書が書く修業になる唯一の方法は、私たち自身の天賦の才の使い方を学ぶことで、それは私たちがそういう素質を持っていることを前提とする。この前提がなければ、読書から学べるのは、冷たい血の通っていない、わざとらしい技巧だけで、私たちは底の浅い模倣者になってしまう。 ———————————— ここは、ショーペンハウアーが、読書を我々が役立てる方法や有益性について語っている(数少ない?)箇所なのではないかと感じた。 たしかに、適切な訓練を積んだ上で優れた本を読むと、「あぁこうやって表現すると良いのか」というのが真に理解できるという気がする。 他にも、新聞記者やジャーナリストが多く攻撃されているのが興味深い。現代だと、特に新聞記者なんかは、文章に関する訓練を受けている人という印象が強いけれど、ショーペンハウアーのこき下ろしようは凄まじい。また、そもそも「読書」というものが文化としてどう捉えられているかが、現代とショーペンハウアーの生きた時代だと異なるんだろうと思った。 現代だと「読書」は、(漫画を除き?)正統なあるいは若干スノッブな?文化だと捉えられている気がする。一方、ショーペンハウアーの時代は、今よりも娯楽の要素が強い気がする。 とすると、現代で例えばYouTubeやTikTokが旧世代から下に見られたりするのと、相似な事象なのかもしれないなと、なんとなく感じた。 あとは、ドイツの国民性をいやにこき下ろすが、これはドイツを嫌っているというよりも、憂国というか、ちゃんとしてくれよと喝を入れているように感じた。 最後に、ショーペンハウアーは「読書会」をどう評価するんだろうと、ふと思った。本を読むこと自体はたしかに彼がいうように誰かに思考を受け渡すことかもしれないけれど、読書に刺激されて他人と議論を交わすことは、より能動的な作業なので、少しはポジティブに評価してくれるかな、と。
6投稿日: 2022.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ・議論の余地ある問題に権威ある説を引用して、躍起になって性急に決着をつけようとする人々は、自分の理解力や洞察の代わりに、他人のものを動員できるとなると、心底よろこぶ。かれらにはそもそも理解力や洞察力が欠けている。こうした人々は無数にいる。セネカが言うように「誰だって、判断するより、むしろ信じたい」からだ。論争するとき、かれらが共通して選び出す武器は、権威の説だ。権威を笠に着て、戦闘を開始する。巻き込まれた者が論陣を張って防戦しようとしても平然としている。というのも、かれらはこうした論拠に対して、いわば思考不能・判断不能の大河にどっぷり漬かった不死身のジークフリートなので、権威筋をうやうやしく証拠として持ち出し、勝利の雄叫びをあげるのだ。 ・いちばん最近語られた言葉はつねに正しく、後から書かれたものはみな、以前書かれたものを改良したものであり、いかなる変更も進歩であると信じることほど、大きな過ちはない。真の思索家タイプや正しい判断の持ち主、あるテーマに真剣に取り組む人々はみな例外にすぎず、世界中いたるところで人間のクズどもがのさばる。クズどもは待ってましたとばかりに、例外的人物の十分に熟考した言説をいじくり回して、せっせと自己流に改悪する。 ・仮説は頭の中で生まれ、そこを住処に息づくが、その生は有機体の生に似ている。つまり外界から自分に有益な同質のものだけ摂取する。これに対して異質で有害なものはまったく受けつけないか、あるいはやむを得ぬ事情で送り込まれたときは、自分は無傷のままそれを包囲壊滅する。 ・文体は書き手の顔だ。精神の相貌が刻まれている。それは肉体の顔よりももっと見まちがいようがない。他人の文体をまねるとは、仮面をつけることだ。仮面はどんなに美しくても、生気がないためにまもなく悪趣味で耐えがたいものになる。醜くても生きた顔のほうがいい。
1投稿日: 2022.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書家は自慢することではない。 読書についてとタイトルにあるので読書を勧める本かと思いきや。書くために必要なことは読みすぎないこと、むしろ自分の頭で考えることと説く。言葉の乱れや匿名の批評に関する意見はまるで現代の日本に対する警告としても通用する。新刊本ばかり読んでいる自分、その人の著作そのものではなくまとめられた後世の本ばかり読んでいる自分に、著者の言葉が突き刺さる。せめて古典を読もう、再読しよう、読んだ後には反芻しよう、と思う。
3投稿日: 2022.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書は他人の考えを摂取するためにすることで、自分で考えるのに煮詰まった時や燃料がなくなった時にするもの。 本ばかり読んでいては意味がない。 同じ主張をいろいろ例を変えて何回も繰り返すので、全部は読まなかった。 匿名の書評家への痛烈な批判は、Twitter等により一般の人々が自由に匿名で誰かを批判できるよう現代では、更に突き刺さる。
2投稿日: 2021.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ端的に言うと、本をただ読んでいるだけではダメだ。思考しろ。と言っている本。 読むのなら古来から存在する名著を読み、新書は読むべきでないと主張しているが、イマイチ論理が通っていない気がしてしまった。
1投稿日: 2021.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで、なんとなく知識を付けた気になるために、たくさんの本を読んでいた。 そして、この本にたどり着き、怒られた。 多読に耽る者はカスである。と、1800年代を生きた哲学者に、200年正論パンチを喰らわされた。 辛い。
4投稿日: 2021.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書について批判的に捉えようとしてこなかったから、勉強になった。やっぱりいつの時代も、自分の頭で考えることが大事なんだな。 読書は食事と同じだという新しくも納得できる発想を手に入れた。
0投稿日: 2021.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログブクログ利用者に冷水を浴びせる名著となるか。 それとも、ただの腹立たしい炎上商法か。 読書をすべきではない。 特に新書。数年後に忘れられる本を読む時間があるならば、 その有限な時間を古典に注ぐべきだと説く、不思議な刺激を受ける「本」です。 本から本の批判をされる、面白い体験をしました。 そして、言い方が力強い。 20世紀のSF作家、スタージョン(世の中の90%はクズ、で有名)や、 現代の堀江貴文、ひろゆきに通じる痛快さがあります。 注釈を含めても160Pそこそこ。その短さから、勢いは終わりまで弱まること無く、最後まで読み切れました。 自分がもっていた固定観念をこの短いエッセイで壊してくれたこと。 この1つの大きなメリットで、星5評価にしています。 その偏見は、 「誰もが読書をすべき。」 「読書をより多くするほど、人格は深まる。そうでない人は、考える力が弱い。」 どちらも、諸先輩方から繰り返し教え込まれ、同時に諸後輩達に伝えていたメッセージです。 ショーペンハウアーは、こうした読書至上主義をシンプルな言い回しでたしなめてくれました。 読書という、いわば「巨人の肩に乗る」行為が過ぎると、思考力は洗練されるどころか、弱まる。これまでとは逆の説です。 そして、この本を読み終えたあとに、私の偏見は一部修正を余儀なくされます。 「誰もが読書をすべき。ただし、自分で考える時間を優先し、日がな一日読書に費やさないこと」 「自分で考える時間をより多くするほど、人格は深まる。ただし、四六時中は難しいので、その補助として書籍を活用する。」 ブクログを使っている方は、読書が好き。少なくとも、関心が高い方だと推察します。 だからこそ、この本を読んで、どのような感想をいだくのか興味がわきます。 どのようなことでも、一見メリットしか無いようでいて、デメリットも必ず備えている。両面思考を学ぶ良書でした。 余談です。 先日この本をテーマに読書会を行いました。 ただ読んで終わりにするのではなく、自分の考えを深める。さらに他人と共有する機会をもちました。 著者に賛同しつつも、個々の参加者から出た意見がとても参考になりました。 ・自分の考えを補強するために読む ということに終止すると、 その反対意見を見過ごすのではないか。自己正当化バイアスに陥らないか。 ・悪書とは何なんだろうか。これはショーペインハウエルに求めるのではなく、令和の日本に生きる私達、個々人が定義すべき。 ・大衆を避けるべき、という点は部分的に同意できる。しかし、大衆が好きな本だから、という理由で避けているとしたら、価値基準はやはり大衆文化になるのではないか、出版部数や書評を気にせず良書を追い求めるという視点がよいのではないか。 考えながら読む、そして友人と話すテーマとして「読書について」は最適でした。 ショーペンハウエルは私達の頭の中を解きほぐしてくれます。
9投稿日: 2021.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書とは他人にものを教わることであり、人はあくまで自分の思想を補強するために本を読むべきである。 よって風化しない古典を読むことで教養や人格を高めることが望ましい。また書き手は自分の思想を簡潔に表現する方法を身につけねばならない。全ての書き手と読み手に送る、鋭敏で軽快なエッセイ。
2投稿日: 2021.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログショーペンハウアーの不遇の時代に書かれた論文の付録のようなエッセイ。 当時の主流であった学派と別の学派であったショーペンハウアーは、60代まで評価される事がなかった。 そのためかこの本にも、書評雑誌への痛烈な批判と、大衆の良き本への無理解に対するそれが多数盛り込まれている。 心に残った箇所の要約 •書評雑誌や出版社は新刊を売りたくて仕方がない為、良き本でないものも宣伝して買わせようとする •書評家は匿名で意見を述べるべきではない •良き本のすべてを理解出来る者は中々現れない。ある人がほんの一部を理解し、またある人が別の一部を理解する •良き本でない新刊を読むくらいならば古代ギリシャ哲学書を読むべき 中々辛辣なのだが、不思議と読ませる、そんな文体と内容だった。
1投稿日: 2021.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書をよりよくするフレーズがいくつもあった。母語への誇りを持って書いたというのがよく分かり、著者への印象は良い。実名で批判しまくるのは痛快ですらあるが、悪質文士への指摘は同じこと何回も言っていて冗長で退屈。自信で言っているように明快にサクッと終わらせてほしい。 予め考えていた人の著作だけ読む価値がある。 最新の本が常に正しいと信じて安易に手を出すべきでない。先人のすぐれた知恵を改悪していることがあるため。大衆ウケする本でなく、できれば、原著者、そのテーマの創設者、発見者の書いたものを読む。 本の価値を決めるもの=素材、表現方式。 智者の言葉はわかりやすく明快。回りくどい曖昧な言い方をしない。
2投稿日: 2021.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書についての名著といえばショーペンハウアーは外せない。 読書、とくに多読であることは世間一般には良いこととされている。しかし本当にそうなのか。 とにかく本を読んでいれば賢くなれると思い込んでいる読書家の脳天に雷(いかづち)を落とす一冊。本書を読んで頭をガツンとやられた人も多いのではないかと思う。 なぜなら、つい笑顔になるほどまでに辛辣な書き方がされているからだ。特に多読にはそこまで言うかと思うほどに、痛烈に批判している。 ボクは月25冊以上、年間300冊以上はここ数年読書している。 そんな中で、多読にはなんとなく違和感を持っていた。だから今以上に読書量を増やすことも出来るけど、それはあえてしないと決めている。 1日8時間以上働くサラリーマンとしては、学びや思考の時間を失うことが目に見えているからだ。 本書をしっかり反復して読んだ上で言わせてもらいたい。とりあえず多読をしてみるのも、やっぱり悪くないのではないかとボクは思う。 まず多読してみて、自分がどう考えるか、きちんと読書を地肉にできているかを反省してみてから決めればいい。 著者がいうことをそのまま受け入れてしまうのでなく自分自身で思考してみる。これは本書で何度となく書かれている「自分で考える」ということだ。 だから「多読をすれば馬鹿になる」というショーペンハウアーの主張もそのまま受け入れてしまう必要はない。ボクはそう解釈した。 これだから古典はおもしろい。
3投稿日: 2021.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ(読書について) 常日頃乱読してきた自分にはとてもショックな、そして説得力のある言葉「読書は自分でものを考えずに代わりに他人に考えてもらうことだ」は、今後の読書感に大いに影響されそうです。たくさんの読書で色々な考え方を得ていくと錯覚してきたが、ハウアーの言うところである多読のために愚かになる、は確かに一理ありそう。自分が経験しないであろうできごとを追体験出来る読書はある意味娯楽でしかないと思う。ただ、昨今のテレビや動画サイト、スマホのザッピングなどよりは積極的に読む必要のある読書のほうが遥かにマシだとも思うが。 これまで以上に良書を探したい気持ちが高まるが、良書を2度3度と読む気持ちにはなかなかなれそうにない。これを氏曰く乱読と呼ぶんでしょうけど。 (自分の頭で考える) 考えて自ら生み出し、発表出来る器量のない自分は残念と言わざるを得ない。 (著述と文体について) ハウアー氏、大いに怒る。文壇の愚物を清々しいくらいにコケおろしてます。良書を見分ける「より簡潔に、具体的に、分かりやすく」を今後参考にしたい。文体については読み飛ばしました。
1投稿日: 2021.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ本を読むことは他人の頭で考えてるにすぎなくて、しっかりと自分の頭で考えなきゃいけないんだなぁと思った。しっかりと自論や自分の考えを持って、その補強や確認のために本を読むのであって、目的もなく読書することは思考力を鈍らせてしまうのだと思った。
1投稿日: 2021.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分で考えることと、本を読むことでは精神におよぼす影響に大きな違いがある。 多読に走ると精神のしなやかさが失われれる。 本を読むことは他人の頭で考えること。 課題は、ほどよく分散されることが必要。 去る者は日々に疎し。書き留めておかないとどこかに埋もれる。 テーマがあるから書く。書くために書かれたもの、は読まない。書く前から考えていたことを書いたもの、に価値がある。 無知は人間の品位を落とす。 出来る限り偉大な知者のごとく思索し、だれでも使う言葉で語る。 ドイツでは、かつてはラテン語で文章を書いた。 本は読まずに済ますコツを身に着ける。大衆受けする書物は読まない。 重要な本は2度読む。 ショウペンハウアーの生活は、規則正しく午前中3時間が執筆。それ以上は使わない。 『余禄と捕遺』『意志と表象としての世界』
1投稿日: 2021.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「本に呑まれるな」 読書は思考のサポートにはいいが 多読のし過ぎは他人の思考の残りカスで 埋もれてしまい自分で考えるのをやめてしまう。
0投稿日: 2020.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ書き手が文法や表現にこだわった原文に対して、読みやすいようにと過剰な編集を加えてしまった結果、読み手に伝えたいことが歪曲して伝わるような本なら、悪書と呼べるかもしれない。一方で、書き手に敬意を表して原文に真摯な姿勢で向き合い、丁寧に意訳された本が読めるなら、読者としてはとても幸せ。
1投稿日: 2020.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書についてと言語について どんな本を読もうかと悩んでいる時にシンプルなタイトルに惹かれ読んだ。本を読むことが本当に正なのかを問われる内容に衝撃をうけた。 また、読書についてとして読んでいたらいつの間にか言語の堕落について延々と語られていた。長ったらしく結論を装飾するなと言っているが、この本が長ったらしくないか?と感じた。 今後どのような本を読もうかと言う人に、読書の概念と本を選ぶ基準を与えてくれる。
0投稿日: 2020.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ>本を買うとき、それを読む時間も一緒に買えたら、素晴らしいことだろう。 ほんとそれ!それな!! >学問、文学、芸術の時代精神は30年ごとに破産宣告を受ける 幽霊の寿命が400年というけど、そっちだろうか。 流行りが繰り返される方だろうか。 >本は原典に当たれ。安易な解説書に手を出すな。(意訳) はーい。
2投稿日: 2020.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書を見直すきっかけになる ショーペンハウアーの切れ味の鋭い主張が新鮮だった。 ・良書を選りすぐって読むことの重要性 ・自分の頭で考えることの重要性 ・世間にはジャンキーな情報が溢れている などなど、「読書」をする上での、基本スタンスを学ぶことができた。 今後、ReadHubを用いて、数多くの本を読んでいくことになると思うが、この本で学んだことをベースに読書をしていこうと思う。
0投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の頭で考えずに他人の考え方を多読しても惑うだけでなんの価値もない、量は少なくとも自分の頭でじっくり考えた読書にこそ価値があるんだよと約170年前のカリスマドイツ哲学者が語ります。 私の多読を全否定wwww
1投稿日: 2019.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の頭で考えよう。思索しよう。 暇と富を価値あるものに活用しよう。 じぶんのあたまで考える ・思索しよう、自分の頭で考えたことは本を読んで思考を代用してもらった考えよりも素晴らしいよ。 著述と文体について ・シンプルに表現しよう! ・比喩で伝えられれば、素晴らしい!それは洞察力の証拠だbyアリストテレス ・文章の表現の基本は、一度に一つのことについて ・「何について考えたか」「どう考えたか」 読書について ・古典読もうぜ!現代の人が過去の人を紹介するのなんてハエみたいに増殖してくるからさw ・暇と富を価値あるものに活用しよう。 私が感じたこと SEO的にシンプルに構造化するのは正しいし、現代で古典的な著述が有効されているとしたら、ありがてぇ!これは好機だ! 古典なんて、あぁ〜そうですかなるほど〜なんてならないから面白い。 だから繰り返し読んで、美味しい感じになるまで読み続けられる面白さ。
4投稿日: 2019.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログお気に入りの本屋で置いてあり、立ち止まって読んだ時に、以下の文章が気に入って購入 ・読書は自分で考えることの代わりにしかならない。自分の思索の手綱を他人に委ねることだ。 読書をしている時の違和感、アップデートのしにくさは、基本は自分の頭で考えた根の部分が存在する事が前提となっていない場合であり この考えを助けてくれた一冊 1章と3章は読書についての著者なりの考えが書かれてあり非常に有用 古典を読む意義にも通じる
3投稿日: 2019.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログP11 「真実と生命は、もともと自分の根っこにある思想にだけ宿る。私たちが本当に完全に理解できるのは、自分の考えだけだからだ。本から読み取った他人の考えは、他人様の食べのこし、見知らぬ客人の脱ぎ捨てた古着のようなものだ。」 沢山の本を読むのがえらいんじゃない。 自分の頭で考えて、手に入れた真理こそ価値がある。
3投稿日: 2019.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログうひぃーっ!娯楽小説読みには「本ばっか読んでないで考えろ」が、耳に痛い!ドイツ語ラブなショーペンハウアー博士の怒りが炸裂ですよ!面白かったです。
0投稿日: 2018.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書とは人の頭で考えることである。そうショーペンハウアーは言う。では、少ない書物をじっくり吸収し、自分の頭でで考えることが必要であるという。仮設を立て、それを論証するために多読をするのは良いが、仮説を立てるために多読をして人の理論を積み木のように組み立てるだけではダメだと説く。そういう人は、これはxxが言ったことだとか、人の意見ばかりならべ、自分の意見がないとのこと。自分に引き比べた時そんな風にはならないつもりだが、なっているようなところも多く気をつけねばと、身を引き締めた。フォトリーディングの読み方はある意味、ショーペンハウアーの勧める読み方になっているかもしれない。何を知りたいかを明確にして、それを意識して高速で読む。これは、仮説を立て、それを立証するために読んでいるのではないだろうか?
1投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログとても長い時間をかけてようやっと読了。他の人のレビューを見て、「どんだけひねくれてる人なんだろう、友達絶対できなさそうな人でしょ」と思い読み始めてみたけど、ホントに遠慮がない。特に「著述と文体について」では、売れる本ばかり書いているとボロクソに言っている。読み手である自分にとっては、ほんとにその通りです……スイマセンと思うこともあった。 この本には3つの作品が収録されているが、共通して言えることは、本読んで知った気になってはいけないということだと思う。本を読んで、自分で考えたり、行動に移したりする。ただ、本を読めばいいわけではない。もちろん、読んで益になればいいのだけれど(少し毒)。
6投稿日: 2018.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログどこでショーペンハウアーを知ったのか…何かで読んで面白そうだと思って購入した。 もう読んでいて刺さる刺さる。めっちゃ痛い。それにこれ書かれたのいつなの?ってくらい、現代にも通じるから怖い。 読書という行為だけじゃなくて、書く側の人間への苦言もある。この本を読んだ後、自分が創作してますなんて、なんだか趣味の世界で悠々自適、読者なんて知らないわ~なんて言いながらすらも書くのが怖くなってくる。 読んでいて、ショーペンハウアーって友達いないんだろうな、なんて思ってしまったのは、真実をストレートに、そして刺さると一番痛い箇所に入ってくるからだろう。 彼が長生きしたので、ちょっとほっとした自分がいる。
0投稿日: 2018.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログただ本を読むだけじゃだめだってさ。自分で考えないと。楽しているだけだって、って書いていることすらすべて受け売りじゃん。orz. 難しい本ではなく、すらすらと読むことができるし、内容を理解することができる。 著書のいう「言いたいことがあるから文章ができる、論じられる」ということについては、日頃の仕事にも精通する。書くことが目的ではいけない。これは至極同意。また言葉の使い方をよくよく吟味しふさわしい表現を選択することが肝要だと意識したい。伝えるべきことを適切な語彙を用いて明確に表現するという意識は今後文章を書く上でも、是非とも忘れないようにしたい言説である。
0投稿日: 2018.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ単語の省略が人の思考に悪い影響を与える、様な事が書かれていましたが「1984年」のニュースピークを連想しました。作者の同時代や、文学作品の例だけでなく、同時代の日本でも、同じ現象は起きていると思います(単語や文を省略・短くして書く、略語を用いて会話する等)。 ○○には二つがある、それは△△だ、様な書き方をよくしていましたが、哲学の考え方は、二項対立で考えるのが基本なので、こういった書き方をしているのだと思います。社会・現実は二項対立で単純に考えるモノではなく、また考えてはいけないと思います。 三篇のエッセイを読んで、作者が読者に最も伝えたいことは、「読書について」の最後に書かれていた悲劇の文学史のくだりだと思います。時の試練を受けて、読み継がれている作品の多くは、悲劇の文学史に名を残していると思います。
0投稿日: 2017.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ今を生きる私たちもにも参考になることが多い本。 いつの時代にも色褪せない教えというのは多いのだと思い知らされる。 とこの本でも売れている本ではなく、教養を培う本を読み、自分の頭で考えること。 当たり前だが、意外とできない。
0投稿日: 2017.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『余録と補遺』から訳出された「自分の頭で考える」「著述と文体について」「読書について」の3編。読書への警句である。 自分で考えよ! 読書は何も考えられない時だけにせよ! 読書は他人の頭で考えてるだけなのだから、多読に走ると自分では全く考えられなくなってしまうぞ! 少量でも自分で考え抜いた知識は、自分で考えずに鵜呑みにした大量の知識よりずっと価値がある。 自分の精神をつちかうような重要な本は続けて二度は読むべき。何度も反芻してじっくり考えることでようやく自分の血肉になる。 読書の指針となる書に出会えた。
0投稿日: 2017.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログP-11の言葉に感動! 読書をどれだけしていても、人それぞれで何が違うのか納得しました…(^◡^)/ 「学者、物知りとは書物を読破した人のことだ。 だが思想家、天才、世界に光をもたらし、人類の進歩をうながす人とは、世界という書物を直接読破した人のことだ。」
0投稿日: 2016.12.19ショッキングな読書術
読書というと、何となく知的なイメージがあります。 もちろん、娯楽として読書を楽しむ人も多いけれども、履歴書に書かれる“無難な趣味ナンバー3”に読書が入ることは間違いありません。 しかし、仕事や家事の合間をぬって、せっせと読書に励む私たちに、ショーペンハウアーは言うのです。本を読むことは何も考えていないことに等しいと。 「絶えず本を読んでいると、他人の考えがどんどん頭に流れ込んでくる。これは自分の頭で考える人にとってはマイナスにしかならない。」 えええええー!? まるで今までの読書を否定されたような文章に自尊心を傷つけられながらも、それじゃあ何を読めばいいのか、どう読めばいいのか、ショーペンハウアー先生は教えてくれます。 これからの読書時間をより有意義にものにするために、読んでおきたい一冊。
10投稿日: 2016.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前に、渡部昇一氏の同書の訳本というのを 読みましたが、あまりにも訳者の文書ばかりだったので オリジナルを読みたいと思いました。 少し現在の環境とは異なる部分があるかもしれませんが 逆に現代の日本においても全うな指摘も多くみられる。 昔のデカンショと言われる一人であることを考えると 痛烈なアフォリズムではありますが、非常に面白く 有用な内容であったと思います。 光文社の古典新訳文庫は非常に読みやすく、いろいろな 古典が読めてとてもいいと思います。
0投稿日: 2016.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログニーチェ等に多大な影響を与えたドイツの哲学者による、痛快なアフォリズムの数々。 自分の頭で考えないと、血肉にはならない。 本を読むにしても、咀嚼して血肉にせねばならない。 無闇な多読は、思考力を衰えさせる。 新刊書ばかり読まずに古典を読むべし。 本書の第一部に当たる「自分の頭で考える」を一見すると、読書そのものを否定しているかにも読めるが、そういうわけではなく、あくまでも、無批判・無思考的な多読を戒めたものというべきだろう。 書物に対する匿名批評の無責任さを徹底的に批判する箇所は、インターネットにおける匿名文化がまさに花開いている現代社会においても強く妥当しよう。
1投稿日: 2016.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「誰だって、判断するよりも、むしろ信じたい」 ドキっとさせられましたね。 # ショーペンハウアーさん。 ドイツの哲学者さんだったそうです。 1788-1860、だそうなので。ご活躍は主に19世紀。 日本で言うと、坂本竜馬さんとか新選組とかっていう時代に、死んだ人ですね。 「二都物語」などの、イギリスのチャールズ・ディケンズさん。 「三銃士」などの、フランスのアレクサンドル・デュマさん。 「初恋」などの、ロシアのツルゲーネスさん。 この辺が皆さん、ショーペンハウアーさんと同世代。 ちなみに、ショーペンハウアーさんが生まれた年に、ロンドンでは新聞「タイムズ」が創刊。 # グーテンベルグさんが15世紀。 ルターさんが聖書をドイツ語に翻訳して出版、 世界で初めて、 「ラテン語が読めない庶民でも、 聖書を書物として読めるようになった」 これが、16世紀。 イギリスから始まった産業革命が18世紀。 つまり、中世から近世になる。 いろいろあっても国家権力が整備される。 街道ができて、商売が大きくなり始める。貿易が始まる。 会計が必要で帳簿が必要で。 読み書きの能力を身に着けた人口が膨張したでしょう。 そして、 「農民に比べると、時間の余裕のある、成功した商人」、 という階層が成立してくる。 # そういう流れを受けて。 ディケンズさん、デュマさん、ツルゲーネスさん、 このあたりからようやく、 ●新聞・雑誌などが、特権階級以外の人々向けに 娯楽・情報媒体として普及。 「ジャーナリズム」「職業作家」が成立するようになる。 ●「印刷物を愉しみとして読む」ことが、 これまた、特権階級以外の広大な人数に普及。 「本屋」「ベストセラー」「ベストセラー作家」が誕生してくる。 という時代なんですね。 ※もちろん、今と違って強烈な身分格差があったでしょうから。 「貴族や役人以外が、活字を読むようになった」と言っても、 「ブルジョワジー」「市民階級」と呼ばれていた人たちに過ぎなかったのでしょう。 人口全体からみると、恐らく1割程度だったのでは。 農民、労働者階級、は、まだまだだったと思います。 ※ちなみに、日本は恐らく世界比較しても、かなりな「読書大国」。 印刷技術は木版だったり、恐らくいろいろ違うのでしょうが、 ほぼ同じ時期に同じような普及があったようですね。 平和が長かった江戸時代のお蔭で、恐らくまずは京大阪、次いで江戸で、「出版物を娯楽として愉しむ余裕のある商人=ブルジョアジー」が成立したからでしょう。 「好色一代男」(1682)、「曽根崎心中」(1703)、などは、出版物として話題になったそうですし、ちょっと下ると、 「東海道中膝栗毛」(1802)、「北斎漫画」(1814)、「南総里見八犬伝」(1814)、と、今でも有名な出版物が続々ベストセラーになっています。 東海道中膝栗毛は、「もうネタがないのに、版元が、売れるから書け、と言ってきてやめられない」という記録が残っているそう。 うーん。2016年のマンガ界と、既に同じ現象(笑)。 # 閑話休題。それはさておき。 ショーペンハウアーさん。「読書について」。 ショーペンハウアーさんは、上記のような時代を受けて、1800年代の中盤くらいに活躍。 つまり、「国家や貴族や国立大学という権威に認められる」というだけではなくて。 「書きたいものを書いて、それを出版して、それが売れて話題になる」という選択肢があった世代の哲学者さん。 プラトンさんとか、ソクラテスさんとは、違うわけです。 また、曲がりなりにも2016年現在と同じように。 出版界とかジャーナリズムとか、 またその中にも、「売らんかな」の酷い媒体もあれば、 岩波書店みたいな?インテリ向け硬派もある、 という状況を生きていた人なんですね。 すぐに忘れ去られるベストセラーもあれば、 「永遠の古典」も本屋さんに並んでいる。 そんな時代。 ということを踏まえての、「読書について」。 光文社古典新訳文庫。 恐らく1850年前後くらいに、 そこそこ老人で晩年のショーペンハウアーさんが書いた、まあ、今風に言うとエッセイ、と呼んでいい文章が3篇。 ※①「自分の頭で考える」②「著述と文体について」③「読書について」。 ②は、ドイツ語の文法についての論で、これは正直サッパリでした(笑)。 # けっこう、面白かったです。 ショーペンハウアーさんというと。 かつて昭和のインテリ文系大学生たちが 「デカンショ、デカンショで半年暮らす」 と言われたのですが、 デ=デカルト カン=カント ショ=ショーペンハウアー の略ですので、つまりは「なんだかムツカシイ哲学者ベスト3」。 色々と実は大事なんでしょうけど、存在とか真実とか定理とか認識とかっていうオハナシは、僕は一切、興味がまだ持てません。 なので、「哲学者ショーペンハウアーは、つまり、どういうことを、訴えたのか」ということについても、実は興味なし。 ただ、本を読むのは好きなので、 「エライこと昔、読書という習慣が始まったばかりのころのインテリさんが、読書についてエッセイ書いてるんだー。読んでみよう」ということです。 # で、だいたいどういうことを書いているか、というと。 これがまあ、笑っちゃうくらい、2016年現在でも通用するお話ばかり。 ※光文社古典新訳文庫、やはり読み易い。 他社版とちょっと比べてみたけど、あまりに違う(笑)。 「なんでわざわざそんな難解な日本語使うの?」 # ●あんまり読んだ知識ばかり詰め込んでも、あかんで。自分で考えるのが大事やで。つまり、自己啓発本とか、ハウツー本とかに依存したら、あかん。 ●特に、「今、これ、売れてます!みんな読んでます!」という広告に踊らされたら、あかんで。新しいものっていうのんは、悲しいかな、「いちばんおもろいもの」では、ほとんどないねんで。 ●やっぱりな、読みにくいかもしれへんけど、読み継がれてきてるものにはそれなりに価値があんねん。古典をお読み。 ●新聞、雑誌、ネット記事、みんなそうやけど、「伝えるべきことがあるから書いている」のと、ちゃうねんで。 あれは全部、「売らなあかんし、〆切あるし、食べてかなアカンから、必死になってマスを埋めています」というだけやねん。 取り上げている話題について、問題について、ほんまに深く考えて、愛情を持って、色々検証して、勉強して、考え抜いた末の文章...では、無いに決まっとんねん。 早い話が、ベテラン俳優のインタビュー記事があって、書いてるライターがその俳優の重要な仕事を全部、観ていて、十分に比較検討して、考え抜いてインタビューしている...なんてことは、まず無いに決まっとんねん。 上から言われて、お金が欲しいから、一夜漬けで無難なことを書いてるだけやんか。 そんなん、読まん方がええねん。 (活字じゃないけど、テレビもそうですね) ●もっと言うとな、匿名で書かれたものなんて、ロクなものはないで。 結局雑誌かてネットかて、ほとんど匿名やろ? 匿名で、誰かさんの誹謗中傷、あるいは尻馬で褒めそやす。 オリンピックのメダリスト。スキャンダルの芸能人。 ほめるにせよ、けなすにせよ、マッチポンプで、まともに取材もせんと、憶測と型にはまった物語に相手を押し込めて、二束三文の文章で、「一丁上り」。 いやー、ほんま、物書きのひとりとして、腹がたって、しゃあないわ。 # ...まあ、意訳すると、本当に、こういうことが書き連ねてあります(笑)。 例えの部分は、当然僕が勝手に書いていますが、要点はほんとに、こんな調子です。 そして、なかなかに、毒舌です。 なんだか、筒井康隆さんの文章を読んでいる気分(笑)。 ### ほんとうに、 「自分で考えろ! なぜなのか、どうしてなのか、考えろ!」 ということなんですね。 「みんな言ってるから」 「偉い人がそう言ってるから」 「ネットで書いてあった」 「新聞もそう言ってた」 「テレビもそんなニュアンスだった」 ...そういうことでは、アカンねん! ということ(笑)。 そらまあ、確かにその通り。 だって、たったの80年くらい前に、そうだったわけですからねえ。 「みんな言ってるから」 「偉い人がそう言ってるから」 「ネットで書いてあった」 「新聞もそう言ってた」 「テレビもそんなニュアンスだった」 なーんて信じているうちに。 その頃だって、初めのうちは。 「ほんとに戦争になんかはならない」 「戦争になっても、すぐに終わるし、市民に実害はないよ」 「だってねえ、正義は俺たちにあるんだからサ。あの国、あの民族が、だいたいおかしいんだよ」 なーんて言われてね。 信じてるうちに、何時の間にやら。 ユダヤ人っていうだけで虐殺されちゃったり、虐殺する側になっちゃったり。 聖戦だ神風だ非国民だ特攻だ「欲しがりません勝つまでは」、まで、行っちゃったんですからねえ。 ...ま、そういうの、確信犯で始めたグループのメンバーで。 「鬼畜米英」って煽ってたのに、敗戦後は、こっそりアメリカの言いなりになって。 それでもって、「あの戦争は悪くなかった」「俺は悪くない」と言ってた人。 そんな人のお孫さんが、長く君臨している国ですから。 君臨させているのは、他ならぬ僕らなんですが。 怖い怖い... # 「誰だって、判断するよりも、むしろ信じたい」 そこの弱さに、付け込まれるような情報の摂取。 本、雑誌、ネット、テレビなど。 つまりは、メディアとの付き合い方。 「気を付けようね」。 ...っと、ショーペンハウアーさんは、 150年前におっしゃっておられます。 いやあ、ほぼ衝動買いだったので、予想と全く違う内容の本でした(笑)。でも、面白かったです。薄かったし。
6投稿日: 2016.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学者ショーペンハウアー、噂には聞いていたがここまで辛辣で歯に衣着せぬ物言いをする人だったとはw 母国語であるドイツ語を正しく扱わない文筆家など人間のクズだ、とおっしゃっておりました。 また「読書ばかりしてると他人の言ったことを鵜呑みにして自分の頭で考えなくなるから気をつけよ」とも。論語でいうところの「学びて思わざれば則ち罔し」ってやつですね。肝に銘じておきます、はい。
0投稿日: 2016.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書好きのみなさんにとって、本書の内容は耳の 痛い話ではありませんか?なにを、どう読むか。 あるいは読まずにすませるか。読書の達人であり 一流の文章家だったショーペンハウアーが贈る知 的読書法。
0投稿日: 2015.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の素晴らしさについて書かれた本かと思って読んだら大違い。自分の頭で考えることの大切さを説いた本だった。 読書とは自分でものを考えずに、他人に代わりに考えてもらうこと。本で読んだ知識を自分の血肉にするには反芻し、じっくり考えなければならない。
0投稿日: 2015.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとも辛口な方だったのですね。ショーペンハウアーさんは。3章のうち2章目ドイツ語に関するものはちょっとドイツ語わからないとついていけない、正直厳しかった。でも言葉の乱れについては今も当てはまるなあと思う。1章と3章はわりとストレートでわかりやすくまた読み返してみたいです。あえて☆はつけたくない感じで。後世まで残るようないい作品を読め!というのは納得しました。
0投稿日: 2014.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
東京ドームそばの、あゆみBOOKS小石川店のポップを見て、買わざるを得なくなりました。 これだから、本屋通い・巡りは、やめられません。
0投稿日: 2014.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ<自分の頭で考える><著述と文体について><読書について>の三部からなる哲学者ショーペンハウアーの新訳。「自分の頭で考えているか、そうでなければ誰の影響を受けたものなのか。自分の思考を自分で把握できているか。」というのは常に自分のテーマであるので、特に<自分の~>を読みたくて購入。ふせんを貼りながらじっくり読んだ。恥ずかしいことにドイツの哲学者やドイツ語について無知なので<著述~>は具体的に理解することは出来なかったけれど、迷いがある時や思考が自立できないと感じた時にはこの本に戻ってこよう。
2投稿日: 2014.10.02
