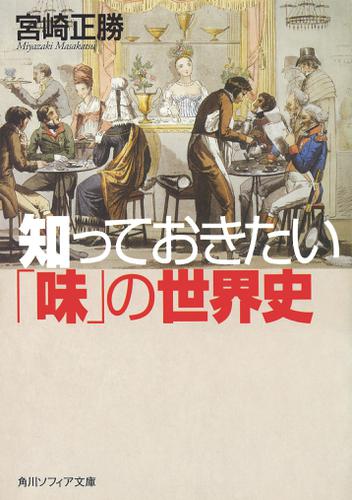
総合評価
(5件)| 0 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
読めば味がみえてくる!
知っておきたいというか、知ると(とても!)面白い、味についての歴史。 ありがちな、うんちく・知識の披露ではなく、塩味、甘み、苦味、酸味の4原味+うまみの誕生秘話?から始まって、経済的理由も絡めた世界への広がりを、軽妙な文章で語ってくれます。 このレビューを書いているのは秋=鍋の季節なのですが、「あぁ、鍋って味の民主主義を体現しているのかぁ」と、一人にやけながら食べてます(当然家族には変な目で見られます^^;)。 ラストの食への警鐘も忘れずに。
12投稿日: 2015.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ味の文化は深い。 スパイスから砂糖へと高級志向が移り変わったのと、砂糖を作るべく、黒人奴隷が酷使された背景を見ると……業が深いなぁー人間。
0投稿日: 2015.10.06辛味、甘味、塩味、苦味、酸味、旨味から紐解く人間の欲望と世界史
五大味覚と言われる辛味、甘味、塩味、苦味、酸味に加え、日本人が発見した旨味。 当たり前だと思っていたこれらの味わいが100年単位で流行り廃りを繰り返し、現代まで繋がっていることを実感することができる良著。 世界史や地理、文化人類学の観点から見ても面白い。 トマトとこぶだしにグルタミン酸の共通点があったりして、人類が美味しいと感じる味には共通項があって、それを別の場所で、違う方法で見つけて大事にしてきた文化があることが文化人類学冥利につきるというか、好奇心をそそる。グルタミン酸(昆布など植物系)とイノシン酸(カツオだしなど動物系)を組み合わせると「うま味の相乗効果」で飛躍的にうまみが増すとのことだが、日本のだしは、なんと合理的なものだったのか誇らしい気持ちになる。 フランス革命と現代のフランス料理・レストラン文化という、「社会体制」と「味」の民主化が連動しているのが目から鱗だった。美味しいものは貴族が独占してたんだなあ。旨いものは価値があり、莫大な金が動いていたと。奴隷制度の必要性もそのあたりにあるとすると、なんだかフェアトレードなんかにも興味が湧いてくる。 ものを食べるということを新しい視点で捉えたいひとは是非。雑学自慢としても使えます。
8投稿日: 2015.09.07読み物ではなく雑学集
ストーリー性のある物語ではなく、味覚についての雑学を多数収載したものです。 記述が淡々としているせいか教科書を読んでいるような錯覚にとらわれる。 世界史がらみのエピソードなどをもっと読みたかった。
1投稿日: 2014.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ2008年6月25日初版発行 5味(甘。塩。酸。苦。うまみ。)の歴史。ナルホドザワールド。 苦味:生まれたばかりの子供は甘味と塩味には飛びつくが、苦味と酸味は拒絶するそうだ。 甘味と塩味は生きていく上の重要物質。一方酸味は腐った食べ物につながり、苦味は毒につながるための本能だという。生き延びるため人間はすごい能力を持っているものだ。 塩味:狩猟時代人間は動物の血や肉で塩分は足りていた。農業にて穀物や野菜など繊維質を摂取するようになるとカリウムで塩分が排出され、人間の体は塩を摂る必要がある身となった。 甘味:昔、砂糖が入ってくるまで、日本の甘みは、柿だけだった。 酸味:リンゴの爽やかな酸味は催淫とされ「リンゴをかじる」は誘惑に負けるという意味だそうだ。そういえば最近リンゴはかじれない。歯が弱くなったということはそういうことか笑。 うまみ(こしょう):黄金に匹敵する高値で取引された。 うまみ(発酵食品):偶然によって出来上がった新たな食物たち。たとえばビール。寝かせておいたパン生地に偶然酵母が混入し発酵パンになり、パンに唾液をまぜたらビールになった。たとえばソーセージも発酵食品で、塩を使って動物の腸内で肉を腐敗を防いでいた。ソーセージは5000年前のメソポタミアですでにつくられていた。 それまでの香辛料を圧倒した唐辛子の発見、コーヒーの実を食べたヤギが夜中に踊るのをみてコーヒーの実を食べ夜どうし祈祷する修道士。他。 知っておきたい「酒」の世界史、知っておきたい「食」の世界史、 も読んでみたい。
1投稿日: 2009.04.28
