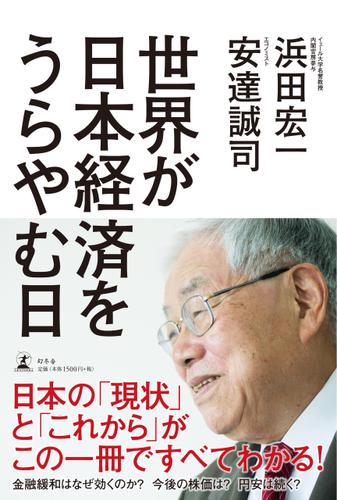
総合評価
(12件)| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログアベノミクスは成功だったのか。 最後の章の以下の4つが今後重要なのは、2019年になった今でも変わらないように思う。 「規制緩和」「女性の社会進出」「TPPの推進」「大幅な法人税減税の実施」 でも、その流れにはなりつつも、スピードが遅いかも、というのがあるよなぁ。世界が日本経済をうらやむ日は遠のいているような感覚。
0投稿日: 2019.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会人のマクロ経済学再入門ともいえる金融緩和をはじめとするアベノミクスの啓蒙書です。非常に分かり易く、アベノミクスの効果と仕組みを説明してくれています。一般人をはじめとしていろいろな方に読んで、アベノミクスに対する理解を深めてほしいと感じた一冊です。
0投稿日: 2016.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。経済学の論争の歴史は「金融緩和が効くかどうか」に集約される。あとがきにも有るけど、この本は社会人のための「マクロ経済学再入門書」と間違いない。アベノミクスの思考整理にもなる。金融の分野で働くこれからの人には必読と思われます。オススメの一冊。
1投稿日: 2015.09.22『経済学派の仁義なき戦い』
不況脱出に金融緩和が効くか効かないか? マクロ経済における「貨幣」の役割について、喧々諤々の議論がされてきた歴史があります。 経済の父であるアダム・スミスは『国富論』で有名な「神の見えざる手」が働くから介入は行わない方が好ましいから、それに異議唱えたのがケインズでした。ケインズはマクロ経済学を立ち上げ、不況時には神の見えざる手に経済を委ねず、金融財政政策を用いることを主張しました。 ここで一つケインズ経済学の弊害として、不況時には金融政策よりも財政政策が効果があるとケインズが結論づけたこと。なぜなら、ケインズの時代は固定相場制であったから、金融緩和を行うと為替レートは通貨安の方向に動きますが、固定相場制の維持をすると外貨準備が枯渇するために、金融政策は封じられていた事実が無視されていることです。現在、変動相場制になったというのに、未だケインズ経済学の教科書に旧時代の記述が残されたことが弊害となっています。 このあと、フリードマン、トービン、ルーカス、プレスコットを紹介しながら、要点を交えて経済学の歴史をおさらいしていきます。 経済学の論争の歴史は「金融緩和は効くか否か」であり、金融緩和は経済に効くという考え方は少数派どころか、異端扱いされていたことにビックリしました。 そして、この状況で著者が怒り心頭なことが2点あります。 ひとつは、経済の歴史を真摯に学ばず、「デフレは、生産年齢の人口の減少によって生じた現象である」などという本がベストセラーになる日本の情けない現状。 もう一つが優秀な日本の若者がアメリカに留学して、新しい古典派的な経済学に毒されて帰国する現状。 事実、著者はこう言われたこともあるそうです。「浜田は昔の経済学を学んだ人間であって、私のほうが新しい経済学を知っている」 さて、現実問題としてアメリカ経済の復活は、FRBの金融緩和政策が正しかったことを示していますし、 「なぜ、これまで金融政策が効かなかったといえば、それは金融政策がアメリカですらまもとに実行されてこなかったからです。効かない、効かないと言って、試されたことがなかったからです。」 と、経済学者のクリスティーナ・ローマーが身も蓋も無いことを言ってます。 さて、デフレは生産人口の減少による減少を著者は否定してましたが、本書ではデータを用いて反論しています。単純に人口減少している日本以外の国と比べるとデフレが起きているのは日本だけという事実です。 したがって、外国人労働者の受け入れで労働人口を増やせば、デフレ脱却に効果があると短絡的に考えることは危険だと感じました。 このあと、浜田氏、安達氏の共同著者が対談形式として、アベノミクスを反対している勢力分析とヘッジファンドの投資戦略を語っていきます。 なぜなら、日本の経済復活した富を奪われないためには我々も知恵をつける必要があるからです。知恵がないといくら情報が目の前にあっても、正しい決断ができませんから。 本書は、アベノミクスに対しての記述がメインではありますが、今回はあえてそこは省いての感想文にしました。なぜなら、そこを抜きにした「経済学の仁義なき戦い」が面白く、また為になったからです。
0投稿日: 2015.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2015/06/16:読了 勉強になったこと。 年金の株式保有割合が低いため、株価があがると、割合を減らすために売らなければならない。 ただ、値下がりの時に、株の保有割合が多いと、年金原資を減らしてしまう。 後者の問題をクリアできれば、株式保有割合をあげるのもメリットはある。それが出来ないと、食い荒らされるだけになる。
0投稿日: 2015.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログアベノミクスがなぜうまくいっているのかを解説している。特に金融緩和の効果について説明している。 金融緩和は日銀が国債を買い取り、銀行のキャッシュを増やすもの。キャッシュとして持っておくのがもったいないと感じる銀行は資金の活用をはかる。 デフレの小体を少子高齢化とするのを真っ向から否定している。 デフレが景気が悪い原因。インフレ目標をもって、これから景気が上昇するという期待を持たせることで、景気が回復する。 貯金をしておかなくても大丈夫という不安を取り除く必要がある。
0投稿日: 2015.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ『アベノミクス』の生みの親と言われているイエール大学名誉教授浜田宏一氏による現時点では成功?と言われている金融緩和による経済対策の解説。 教育学部出身の私レベルにでも非常に分かり易い内容でして、まあ、この教授も色々叩かれているみたいですが、通貨安(円安)の必要性は理解できますし(実際に円高による名目GDPが減少してる事実)、失業率の低下等、その他色々と数字が良くなっている訳で・・・・それなりに評価していいのではないかと思いますが。 ただ輸出で儲けている企業はGDPの14%と言われている中で本当に円安でいいのかと思っておりましたが、あらら、現実の株高。本当にありがとうございます。飲み代は確保できました。 一部の大手企業の為のアベノミクスと言われている中、まあ、ある経済対策によって日本人全員の懐が一気に潤うって事はあり得ないわけで、まず大企業から儲かって長いタイムラグあって我々庶民に行き渡るってのが普通だと思うのですが、それを認めない社会主義者風の輩もいるのも事実でして、なら、そもそも大手企業が儲からなかったらその裾野で展開してる俺らはもっと死ぬぞって、分かってんのかよおい、と優しくお伝えしたい本日の株式市場を売り攻撃で昨日の損失を取り戻した私です。嫁にバレずに済みました。 真面目な話、財政政策ではなく金融緩和による初めての成功例がリーマンショック後のアメリカでありまして、この事実をしっかり受け止め、このままいい感じで株高が続く事を高い所からではございますが御礼も込めて厚くお祈り申し上げます。
0投稿日: 2015.04.07ガテンのいったアベノミクス本。
イェール大学教授であり、 現内閣官房参与でもある浜田宏一氏のアベノミクスのこれまでの評価とこれからの課題の提案である。 2014年4月の消費税増税を除き、アベノミクスには合格点を付けている。私も何冊かのアベノミクス本を読んだが、一番合点のいく内容だった。 ただある程度経済学の知識がないと難しいかもしれない、と言っても理解不能というほどでもないから考えながら読めば十分楽しめる本だと思う。
2投稿日: 2015.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に分かりやすいし、データのまとめた方、そのデータを使った主張とも納得がいく。大学の教授の本だから当たり前か。。。しかしながら、同じデータを他の本では違う取り方をしており、主張をどこまで信じて良いかはわからない。多分、2年後くらいにアベノミクスの結果がわかった時にこの本の評価も決まるのだろう。
0投稿日: 2015.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ財政政策よりも金融政策の方が有効である事が判りやすく理解できる。また、マクロ経済学、ミクロ経済学も理解が進む。大学の経済学部を思い出す。読むのに時間がかかるのはやむを得ないか。
1投稿日: 2015.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログまあ、リフレ派のことも頭から否定しないで、彼らはアベノミクスのここまでの状況と今後の見通しをどう見ているのだろう?と同派の大御所とされる浜田氏の著書を読んでみています。 しかし…半分くらいまで読んで投げ出したい衝動を抑えているところです…(笑 言っている論理が私にはどうにも理解出来ないんです。いえ、頭から否定しないでちゃんと聞く耳を持とうと思って読んでいるのですが、分からない。 最も根本的なところとして、彼らはアベノミクスは大成功しているという認識なのですね。(少々驚きましたが) まあ、それは良いとして、金融緩和が効くことは分かっていた。実際に効いているじゃないか。デフレは悪だ、インフレは善だ。と言うのですが、金融緩和によりどういう道筋でインフレになる効果があるというのかがまず…彼らの説明からは…理解できないでいます。 「期待」(予想)が経済に与える影響は大きく、重要。ここまでは分かりますし同感・同意見です。しかし、金融緩和策の「期待」に与える影響以上の、インフレ惹起に効果があるというロジックが分からない… 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 頑張って読了。 しかし、申し訳ないですが、全く腹落ちしませんでした。 まず、前半は「トンデモ本」ではないかと思うような記述の散見が続きます。 曰く、 ・中央銀行は為替レートを「自在に」コントロールできるのです。 (ならば各国はなぜ自国の為替レートの意図せざる方向への極端な動きに悩ませられ続けているのか?) ですとか、 ・ウォン/円レートの4割のウォン安は韓国製品が4割やすくなることを意味して日本は韓国との競争力を4割削がれたと言える (韓国は日本からの部品輸入が必要であり、それにはウォン安はマイナス要因である点が全く考慮されていない) ですとか。 そして後半は今度はとても「ずるい」論理展開が続きます。 曰く、 ・金融緩和をしても銀行貸出が増えていないのでマネーサプライは増えておらず実体経済への効果はないという首長があるが、それは企業は先ずフリーキャッシュフローを取り崩しているからだ。この後フリーキャッシュフロー分の投資が一巡すると銀行からの借り入れが増えることになる (しかし、その検証・証明の記述はない) ですとか、 ・論理に「マーシャルのk」を持ち出して来ているのに、ではマーシャルのkは実際に日本でもある程度一定の値をとっているのか?の検証がない(実際には一定でなくなっている) ですとか、 論理の証明が自分の都合のいいところで終わっている部分が散見されて、気持ち悪くて(スッキリしなくて)仕方がありません。 そして、私が何よりリフレ派という人たちのことがどうも好きになれないのかこの本を読んでよく分かったのですが、「自分たちの考えに賛同しない人たちは人にあらず。日本を不幸にする非情な悪人」みたいな書き方をなぜするんでしょう? 閉鎖経済モデルでは説明しきれない複雑系の世界に入ってしまっている世界経済ですから、色々な意見があって良いですし、色々な意見を闘わせてこそ経済学も国の経済運営も発展があると思いますので、リフレ派だろうと反リフレ派だろうと相手の主張に一理あるところには耳を傾ければ良いと思うのですが、自分の主張に反対する主張の人は人非人みたいな言い方をするのはどうなんでしょうね…と感じる次第です。
0投稿日: 2015.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログアベノミクスの早くからの提唱者の浜田教授が、金融緩和の意義、効果を説き起こす。経済学の基礎を分かり易く解説、もろもろが「スッキリ」する書。題名通りの日が到来する日を強く希求する。
1投稿日: 2015.02.11
