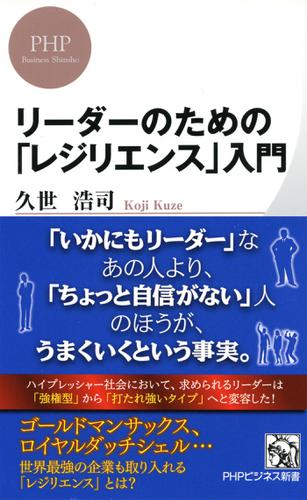
総合評価
(11件)| 1 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ2025/4/19 読了 倒れても何度でも起き上がる勇気をもらった。意思の強さが重要。実話が複数あって身近に感じた。
0投稿日: 2025.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ【由来】 ・確か図書館の新書アラート 【期待したもの】 ・ 【要約】 ・ 【ノート】 ・ 【目次】
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ序章でほぼレジリエンスについて語られている。 「逆境や困難、強いストレスに直面した時に、適応する精神力と心理的プロセス。」
0投稿日: 2017.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代のリーダーに求められるストレス耐性のあるリーダーシップ、レジリエンスについて書かれた本。 心理的な心構えが大きく影響していると理解。 物事を事実として受け止め、その解釈をポジティブに捉えること。 強みを活かし、また自分のWILLと接続の取れた仕事に向き合っていること。 逆境やどん底を経験し、何とかなると楽観的に構えること。 などが必要要素として挙げられる。
0投稿日: 2016.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ流行りのレジリエンス。実例満載で面白い。 これまでの仕事における自分の辛かった経験を乗り越えたことを、肯定してもらった気分。ありがたい。 折れない心で、心折れそうな出来事を乗り越えるぞ。
0投稿日: 2015.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ★★★★ 「レジリエンス」が求められるようになってきたのは、社会が知識労働で満たされ、変化のスピードが物凄くはやくなり、多様になったため。 経験に裏打ちされた従来型のカリスマ的なリーダーシップでは、最前線にいる社員をエンパワーし、組織やチームを前に進めることが難しくなってきている。 そんな社会の中で、様々なストレスに晒されながらも、強いリーダーシップを発揮できるためのテクニックを、身近な具体的な何人かのリーダーの例を紹介しながら、説明してくれている。 巻末の推薦図書、および【レジリエンス・リーダーのための7つの習慣】 は、リーダーとしての道を切り拓くのに役立ちそうなので、活用させてもらいます。 2015/11/10
1投稿日: 2015.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[読んだ理由]================== [読んだ後の感想]============== [内容纏め]==================== 今日からできる!レジリエンス・リーダーの7つの習慣 ①気持ちのクールダウンをする ②感情のラベリングをする ③ストレスの宵越しをしない ④お手本を見出す ⑤ストレングス・ユースする ⑥サポーターに感謝をする ⑦時折立ち止まって半生を振り返る [メモ]======================== ■はじめに:なぜ今「打たれ強さ」なのか ナレッジワーカーが増えるに連れて、カリスマリーダーはリスペクトなりにくくなります。 知識を武器とする部下は上司よりも豊富な知識を持っているので、リーダーに、いくら経験に裏打ちされたカリスマ性が合ったとしても、その経験や知識が時代遅れになってくるからです。 ■序論:レジリエンスとは何か? 事故の強みを理解するための便利なツールが心理学者によって開発されています。私のお気に入りはアメリカのVIA研究所が著作権を持っている「VIA・IS」です。15~20分ほどの時間があれば無料で事故診断できるツールを提供しているので、興味のある方は www.positivepsych.jp/via.html ■第一章:胆の据わった「楽観力」という強み 薬物に頼らなくてもうつ病の治療に効果のある「認知療法」を開発したアーロン・ベック博士も「嫌な出来事そのものがネガティブな感情を起こさせるのではなく、その出来事の「認知と受け取り方」がネガティブ感情を起こさせる」と言っています。 私達の内面の強さを開発する上で主要な障害となるのは、私達の「説明スタイル」にあるのです。 具体的には、説明スタイルとは、ある出来事を体験した時に、 ・なぜその様な出来事が起きたのかについての原因の分析 ・どれだけの長さで影響するのかという将来の予測 ・どれだけの範囲で影響するのかという将来の予測 の3津に関して、次文に対して説明する仕方のことです。 楽観的な人は、同じ出来事に対して異なる捉え方をします。 ・失敗の原因を自分だけにあると狭く考えう、環境などにもあると考える(外的) ・理由もなしに悪い出来事は続かないと考える(一時的) ・その原因は固有のもので、血に広がるとは考えない(限定解釈) ポイントは、起きてしまった出来事をどう柔軟に捉えるかなのです。 レジリエンス・リーダーに必要なのは「地に足の着いた楽観力」です。 世の中の全てのことが、自分の思い通りに行くとは考えていません。 それらのリスクを無視せずに、izaとなった時に大きな損失を被らないために準備はしますが、リスクを恐れて行動回避に陥る音もない。なぜなら、自分の内側の根本に「最後にはなんとかなるだろう」という楽観力が備わっているからです。 勉強をしたからといって、理念が降って湧いてくるわけでは有りません。教科書に自社の理念となるものが書いてあるわけでも有りません。毎日のように「なんのために経営をするのか」を自問する日々が続きました。 経営者として数々の修羅場をくぐり抜け、逆境でもまれるうちに、人物が寝られ、リーダーとしての器が大きく育ったからです。器量のある人は、自分を偽る必要が有りません。ありのままの自分をさらけ出し、自分らしさを貫くことができるのです。 本当に仕事の出来る人になるためには、ビジネススキルだけを磨いても十分では有りません。それはあくまで表層的なものであり、根本ではないからです。必要なのは、その人の「人物」ができていなければならない。 どうすれば人物を養うことができるのでしょうか。その秘訣は2つある。 第一は、古今の優れた人物に学ぶことです。同じ時代に生きるリーダーを模範として学ぶか、それができなければ古典を通して古人に学ぶこと。とくに「大学」や「中庸」、「論語」や「孟子」と言った中国古典は歴史のふるいにかけられた優れた書物であり、優れた古人に学ぶことができるといいます。 私淑できる人物を得て、座右の書となりうる愛読書を持つことが、リーダーとして人物学を修める条件となるのです。 第三弾会が「見識」を持つことです。目的意識が高まると、その理想に照らして現状に対する反省や批判が生まれてきます。自分に足りないものも自ずと認識するようになります。見えていないものが見えてくるのです。見識は知識とは違います。 ■第二章:「持続可能な熱意」という強み 米国ペンシルベニア大学の心理学者であるアンジェラ・リー・ダックワース博士は「成功の鍵はGritにある」と、500万回以上もびゅーされたTEDでの公園で伝えています。Gritとは、私達日本人には聞き慣れない言葉ですが、「やりぬく力」「気概」「気骨」といった意味があります。 もう一つ重要なのは「パッションとロジックのバランス」です。熱意と論理をバランスよく持っているのが、プロのアントレプレナーであると徳重社長は考えているのです。 会社でも論理的思考が強い人がリーダーになることが有りますが、「ロジック中心の人はゼロから何かを立ち上げる時に行動できないことがある」と徳重社長は考えています。さらにロジック中心で構築したビジネスは、成功した途端にそのロジックを理解できる大手が参入して、一気に崩されてしまうリスクも有る。 日本にいる時には、徳重社長は起業家精神と大学の偏差値は反比例していると考えていました。ロジックに強く学歴の高い人ほど、パッションが必要な起業家には向いていないと思っていたのです。ところがシリコンバレーで見た後継は違った。ロジックに強い人が、パッションも兼ね備えている。そんな人材がゴロゴロいたのです。 「ミッションを語ることに依り、人を巻き込む」リーダーシップです。徳重社長が実際に行っているリーダーシップ・スタイルがまさにこれです。「使命感があれば、ロジックで説得されない人も、パッションで動かされない人も、「とにかくこれはやらなければいけないことだ」と感じて着いてきてくれる」 ■第三章:聖人君子ではない「利他性」という強み 毎日寝る前にかかさず行った習慣が「動機善なりや、私心なかりしか」という問いかけでした。 「広告なんてものは皿みたいなもので、そこにどういう提案とかを盛り込むことができるかというのが、本当の売り物なんだという音に初めて気づいたんです」 ストレスの損切り: 逆境なんてものは、誰かれ構わず日常茶飯事で起こることなんだと思います。その時に何かに気づくかだけだと思いますね。感情の揺れ動きは人間なんで当然ある。でも、つらいな、と感じるだけで理解できない人もいます。自分の体験を眺めて、感じることと理解するということを同時にしなければ、逆境なんだけど逆境と気付かないまま終わるケースも有る。 自分の中にもうひとりの自分じゃないけど、操縦している自分と言うんですかね『ああ、ちょっと今落ち込んでいるな』と感じながら見ている、もうひとりの自分がいれば、もっと冷静に理解することができるはずだと思います。 ■第四章:「根拠ある自信」という強み 普段から他社に寛大に接している『ギバー』タイプの人は、数年間音信不通になっていた休眠状態の『弱い繋がり』の人からも役に立つ情報を手に入れやすい。なぜなら多くの人は、誰かから親切にされた時に、「いつかはきちんと報いたい」とかんがえる傾向があるからです。 ■第五章:意志の力が支える「勇気」という強み キャリアの節目にも、この有機は試されます。例えば40歳を前にして将来の自分のキャリアに迷いが生じることが有ります。現状の仕事はそこそこやり甲斐はあるし、待遇も満足している。でもこのままの状態が次の10年続くかどうか先が見えず、不安と怖れを感じるのです。その時に行動医師を優先するか、おそれに支配されるかが問われます。 希望が高い人が有する力の一つが「ウィル・パワー」、つまり「意志の力」だからです。これは、目標に行き着くまでの見通しを持ち、生涯に対しての対策も入念に準備した上で、「勇気ある一歩」を踏み出す際に必要な、自分を動機づける力です。 「リーダーは自分のウィルを語るだけでなく、積極的に部下が何をやりたいのかを聴くことが、彼らの一番のモチベーションに繋がる」 「採用の候補者が打たれ強いかどうかは、見た目ではわかりませんし、面接をしてもなかなか判断することは出来ません。ただ、その人が本当に何をやりたいのかを理解することは出来ます。本心でそれをやりたい、達成したいと望んでいるのであれば、結果的に打たれ強くなるはずです。困難に直面して凹んでも、すぐに立ち直ることができる」 リーダーが信条を語るメリット: 1つ目は「信頼感」です。人生の大きな転機や将来を左右されるような逆境体験により生まれた価値観や洞察は、それがどれだけシンプルであっても個性的で揺るぎない独自の信条となります。自己啓発書や格言集から借りた受け売りの信条とは一線を画します。 2つ目は「親密感」です。ユウキに掛けた人は、自分の事を覆い隠し、意思決定のプロセスを見せようとしない秘密主義を撮る。 3つ目は「ブランドの形成」です。リーダーは信条を語ることで、自分独自のパーソナル・ブランドを確立することが出来ます。自分のブランドを示すことは「自分の存在が意味するものを相手に教えることだが、押し付けがましくない自然な形で行われるために、相手はそれを自分の認識として受け止める」効果があります。 「リーダーの進化は、本人が去った後に試される」リーダーが不在であっても、ビジネスの成長を維持できるような組織力を構築することが重要だということです。 ■レジリエンス・リーダーになるための必読の15冊 ■今日からできる!レジリエンス・リーダーの7つの習慣 ①気持ちのクールダウンをする ・外からやって来るストレス自体をゼロにすることはできない。 しかし、ストレスに起因して生まれるネガティブな感情はコントロール可能。 ・(ネガティブな)感情のコントロールには、感情を認識する余裕が必要。 そのために、まず感情をクールダウンする習慣を持つ。 ・最適な方法は「マインドフルネス呼吸法」。 4秒ほどかけて息を吸う⇒6秒ほどで息を吐く、の深呼吸を繰り返す。 ②感情のラベリングをする ・ラベリングにより、見えない感情を見える化する。 感情の正体を明らかにすることで、主導権が自分に戻り、対処もしやすくなる ③ストレスの宵越しをしない ・その日に生まれたネガティブな感情は、その日の内に気晴らしをする。 翌朝の寝起きも良くなる。ストレスが蓄積せず、心が折れにくくなる。 ・「運動系」「音楽系」「呼吸系」「筆記系」など。 自分が好きで、生活のリズムに合ったものを選ぶ。 ④お手本を見出す ・「心理的な筋肉」を養うには、「自己効力感」を高める事が効果的。 高めるのに最も有効なのは「実体験」を重ねることだが、 「代理体験」でも十分有効。 ・自分が必要としている能力を持った「お手本」を探す。 ・新しい職務についた時には特に大切。 ⑤ストレングス・ユースする ・自分の「強み」を把握して、それをリーダーとしての仕事に活かす。 それにより自尊心が高まり、幸福度が向上し、不安や睡眠障害などの 抑鬱の症状が軽減する ⑥サポーターに感謝をする ⑦時折立ち止まって半生を振り返る ・忙しく働く生活で時折立ち止まり、自分の半生を振り返り、 うまく行ったことや失意や苦労を落ち着いた心で俯瞰して、 己の本質を理解して自分の内側にある自分らしいリーダーシップの核に気づく
0投稿日: 2015.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ雑誌の本紹介特集で紹介されていた本 やっぱりレジリエンスって大事よねぇ~ってことで買ってみた なかなか、面白かったわ 付箋部分をご紹介します ・レジリエンスとは、「逆境や困難、強いストレスに直面したときに、適応する精神力と 心理的プロセス」と定義づけられる(p22) ・レジリエンスの高い人の特徴 1つ目が回復力 2つ目が緩衝力 3つ目が適応力(p24) ・経営学者のピーター・ドラッガーも「何事かを成し遂げられるのは、強みによってである。 弱みによって何かを行うことはできない」という言葉を残している(p30) ・自分の思い通りにならないストレスフルな出来事やネガティブな問題は、誰にでも起こりえます。 ところが、悲観的な人と楽観的な人では、同じ出来事が起きてもその原因を自分にどう説明するかに 大きな違いがあるのです(p45) ・心の内側にダイナモ(発電機)を持つ(p67) ・本当に仕事のできる人になるためには、ビジネススキルだけを磨いても充分ではありません。それは あくまでも表層的なものであり、根本ではないからです。必要なのは、その人の「人物」ができて いなければならない(p69) ・元気に溢れる人が志をもつと「志気」を手に入れることになります(p71) ・「成功の鍵はグリットにある」グリットとは、「やり抜く力」「気概」「気骨」といった意味があります(p79) ・恩送りとは、誰かから受けた恩を直接その人に返すのではなく、別の人に送ることを意味します。 その結果、恩が世の中をぐるぐる回って行き、社会の善の連鎖が起きることが期待されます(p114) ・逆境なんてものは、誰かれかまわず日常茶飯事で起きることだと思います。その時に、何かに気づくかだけだと 思いますね(p140) ・私たちは、年を重ねるほど「休眠状態の弱いつながり」が増えていきます。しかし、自分の態度次第で、 その人たちとの「ゆるいつながり」は価値ある貴重なつながりへと変容するのです(p152) ・スナイダー博士は「希望とは、目標が達成できるという期待感である」と定義づけしました(p188) ・レジリエンス的思考の持ち主は、変わらないものを懸命に変えようとするのではなく、自分で変えられる ものにフォーカスします。この場合、自分でコントロールできるものは、ストレスではなく、ストレスの 結果内面で生まれるネガティブ感情なのです(p220) ・感謝が豊かな人は、思考・感情・身体がとても健康的なのです(p230)
0投稿日: 2015.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体的な論旨展開もわかりやすく、エピソードも引き込まれる内容なので飽きずに通して読了できる。 内容はかなり充実しているため、控えのノートに色々書こうとするとそれなりの量になってしまった。 「本書に手を取られた方は巻末の『今日からできる!レジリエンスリーダーの7つの習慣』だけでも、読んでみてください」とありますが、それだけでもったいないと思う。 全編読まれたい。 序章でほぼ本書の要約となっている。 レジリエンスリーダーとは打たれ強いリーダー。 今求められる理由は①カリスマリーダーの限界(知識労働にシフト、リーダーの部下も知識ある人が増えた)②グローバル化による変化適用力が必要になってきた③リーダーのメンタルの課題。(そもそも、リーダーは『感情労働』であるという認識がなされていない) 著者が取材して回ったリーダーの共通点は ①自己認識力が高い(もしくは関心が高い) ②どん底を経験している(生まれつきタフとは限らなく、むしろ元々小心者だった人も多い) ③ピープルファースト(大きい野心と強い情熱) また5つの強みは ①肝の据わった「楽観力」⇒第1章 ②持続可能な熱意⇒第2章 ③聖人君子ではない「利他性」⇒第3章 ④根拠ある自信⇒第4章 ⑤意志の力が支える「勇気」⇒第5章
0投稿日: 2015.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログカリスマリーダーではない、打たれ強く利他的なリーダー像を提唱 そこは同意できる部分なのですが 落ちの部分の 今日からできる レジリエンスリーダー7つの習慣 が残念な内容でした 打たれ強さを向上させる習慣 という意図なのだと思いますが、これやっても 強い動機と高い能力 は得られませんね 逆に 強い動機(と高い能力) があれば必然的に打たれ強くなるのだと思います とはいえ各エピソードは読みやすいし面白いので興味があれば読んで損するようなことはないと思います
0投稿日: 2015.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログPHPビジネス新書、全般に言えることだが、「読みやすく、役に立つ」一冊。詰まるところなく、スラスラ読めた。今流行りつつある「レジリエンス」がよく分かる。逆境グラフやライティングセラピーなどは参考にしたい。様々な本が引用・紹介されており、その点も役に立つ。
0投稿日: 2015.01.05
