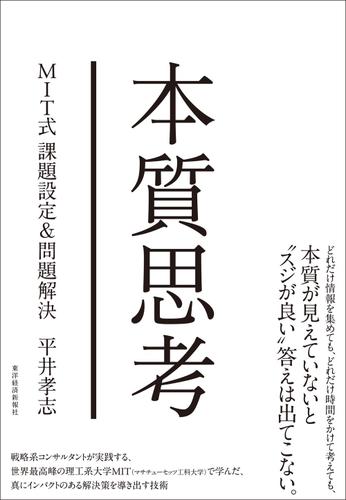
総合評価
(29件)| 6 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現象の表面のみを切り取って、課題の裏返しのような解決策を導出するのではなく、その背後にある「本質=構造(モデル)×因果(ダイナミズム)」を読み解くことの重要性を説いた一冊。主張自体はシンプルに感じたが、同じく日々コンサルティングに従事するものとして、そのシンプルなことを実践する難しさは理解できる。 特に思考のクセ(p.22)の分類は、セルフレビュー/他者のレビューを行う際に、視点として効果的と思う。また、p.78(以下参照)の記述は、極めて本質的であり、言い換えると「予断なく現象を観察する」「意味のあるMECEを導出する」ことと解釈した。 特に印象に残った箇所は以下の通り ・「「思考のクセ」の分類 ①裏返しの結論のクセ②一般解で満足してしまうクセ③フレームワークに依存してしまうクセ④カテゴリー適応のクセ⑤キーワードで思考停止に陥るクセ⑥初期化説に固執してしまうクセ⑦考えている目的を失ってしまうクセ⑧プロセス偏重のクセ⑨主体性を喪失するクセ」(p.22) ・「逆説的だが、複雑なものであればあるほど、モデルとダイナミズムでシンプルに考えるべきである。なぜなら、複雑なものはそれを構成する要素も多く、要素分解しても、今度は構成要素の数の多さに頭を抱えることになってしまうからだ」(p.63) ・「本質から考えた上でのピラミッド構造や仮説は、現象から出発したピラミッド構造や仮説とは明らかに質的に異なってくるということだ」(p.78) ・「モデルを考える上でのヒント 因果に注目し、相関は無視する」(p.100) ・「システムダイナミクスの中には「原因と結果は、時間的・空間的に近接しているとは限らない」という考え方がある。これもレバレッジポイントを考える際に、常に意識しておいて良い言葉だ」(p.168)
0投稿日: 2024.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、システムダイナミクスの実践本。 本質思考とは、物事の現象をその裏側にひそむ「構造(モデル)」と「因果(ダイナミズム)」として捉えること。 ロジカル=スジがいい、とは限らない。 スジがいいのは、本質を捉えている時。 思考のよくある落とし穴やスジの良い事例などがあり、どのレベル感が本質を捉えられているかがイメージつきやすい。 <本質思考の4つのステップ> ステップ1:モデルを描く ステップ2:ダイナミズムを読み解く ステップ3:モデルを変える打ち手を探る ステップ4:行動し、現実からのフィードバックを得る <本質思考を鍛えるトレーニング(抜粋)> 例1:思考の雛形を増やす(アナロジー) 急成長して破綻(日本スターバックス急拡大による失敗) 好循環による成長(facebookのネットワーク外部性) マイナスの差別化(ダイソンのフィルター無し掃除機) ゼロサムゲームからの脱却(沖縄基地問題。誰かが損を被る構造を変えない限り、同様の問題が別の場所で繰り返される) 例2:思考の見える化(ホワイトボード) 例3:自論を他人にぶつける 例4:歴史観を磨く(歴史は根源的なドライバーで動く)
0投稿日: 2023.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容は理解できたものの、思考法として定着させるには常にこの本を持って実践する必要があり、出来るイメージが持てていない自分がいる。
0投稿日: 2023.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ本質思考ができない人の頭の使い方から説明し、本質は物事のどこにあるのか、本質思考をするにはどうすればよいかという内容が後に続く。 本質思考のためには物事の様子を端的に表した「モデル」という図を用いるといいらしい。しかし、思い付いた文章をひたすら書いてストックしている自分にとって、いきなり右脳で思い描いたモデルを紙に描いてみるのはハードルが高かった。モデルは知識やまとめる能力が無ければ描けないものではないか?と思いながら読み進めていった。 けれども、モデルはハードルが高くて描けないという発想自体が、自分の考えをノートに書くだけで満足しようとしていることに起因するのではないか?と本書を読み終えて思った。このように、ちょっとしたことでも本質に迫るために考え方の切り替えを意識するようになれたので、この本を読んで良かったなと思う。
0投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ本質=モデル✖️ダイナミズム と分解しているが、本質に迫るという抽象的な表現を色んな角度からのアプローチが書かれていてとても勉強になった。特に思考の癖からスタートしていて、正に陥りがちな注意喚起をしてくれてから、実ビジネス場面での具体的なシーンで様々な思考法が紹介されていてとても勉強になった。繰り返し読み直す。
0投稿日: 2022.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログダイナミックスとモデルで問題解決を図るのが主旨 キモが2つあります。 1つが、本質思考を妨げる9つのクセ: 本質を考える上で、陥りがちなバイアスとしての9つの思考のクセ この解説が前段 もう1つが、本質思考の4つのプロセス: ①モデルを描く、②ダイナミズムを読み解く、③モデルを変える打ち手を探る、④行動し、現実からのフィードバックを得る 個々のプロセスの説明が解説が後段です。 フィードバックを伴う、システム工学をベースとしていますが、事象を表現することがわかりにくく、具体化するのが大変かなと感じました。
5投稿日: 2021.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ書いている軸となる理論は真っ当で、現象の裏側にある要因の相互関係からなる構造(モデル)とモデルが何周も回ることにより起こる展開を読み解くダイナミズムの組み合わせが「本質」であるというもの。 問題に直面している時(つまり日常)は、本質を見てモデル自体を変えることでしか本当の解決にはならないので、ツボとなるレバレッジポイントを突くべきであるという。 ただ、出てくる例え話がどれも少しピントがずれていて気持ち悪かった。
1投稿日: 2021.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ本質とは何かとは、システムダイナミクスにおいては物事の本質を現象の裏側に潜む構造と因果として捉えると理解しやすい。モデルとはその現象を生み出す構造つまり構成要素や相互の関係性のこと。ダイナミズムとはそのモデルが生み出す現象について長い目で見てどんな結果動きが見られるのかと言う事つまりどんなパターンが見られるのかと言うこと。 部下が望んでいるのが、単に働きやすい環境や優しい上司だけではないと言うことに気づく瞬間がある。部下は自分が成長し、会社や顧客に貢献できていると言う実感を求めているのである。誰しも認められ意味のあることをやりたいと思っている。そう考えると、リーダーとしてどう振る舞うかも大切だが、リーダーが何を目指すのかのほうがもっと大事だということに気がつく。つまり部下はその人についていくのではなく、その人が目指すものについていくのである。
2投稿日: 2021.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「本質思考」 1.購読動機 ビジネスを展開するにあたり、本質とは?という不明瞭、重大かつ永遠の課題を、目の当たりにしているから。 2.本質とは? ①モデル ②ダイナミズム の2要素であること。 ①モデル 自社 インプット 成果、解決したいこと アウトプット ここに、 競合、サプライヤー、影響者を絡ませて図式化。 ②ダイナミズム 原因→結果 3.2.本質を捉えてるには?はじめの一歩 だから、それで? なぜ? そう、問いをすること。 そして、図式化→他者にプレゼン→揉み直し で精度をあげること。 4.私のなかの自覚 展開中の業務を、わがものとして消化したい。 そこに辿りつくために、本書を手に取ってみた。 絵として、捉える。 この頻度を高めることからか、、、。
12投稿日: 2021.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「本質」を因数分解して解説している。 考える力をつける、という本をいくつか読んだが、いまいちピンと来なかった。 まさに、「構造」と「因果」を用いて腑に落ちる内容だった。 あとは実践あるのみ
0投稿日: 2021.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログざっと読み終わって、言われてる思考ができれば役に立ちそうと思ったけど、一読だけでは全く身についていない実感。もう一度振り返りながら咀嚼して、日頃から意識できるよう、どうにかして行動に組み込まないとならないと思った。欲を言えば、どう行動に組み込めるかまで解説してもらえるとありがたいけど、それは甘え過ぎかとも思う。自分なりに体得できるか否かが人と差をつけるポイントになると思う。
0投稿日: 2020.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『本質思考』要約 ■そもそも「本質思考」とは何か? 結論をまとめると、 本質=構造(モデル)✖️因果(ダイナミズム) で成り立っており、 「本質思考」とは、物事をモデルとダイナミズムから考える思考のこと。 この思考には4つのステップがある。 ①モデルを描く →構成要素と関係を1枚の絵で表すことで、「どうしてそうなっているのか?」という因果関係を明らかにする。注意点として、因果は入れるが相関は入れない。 モデルを考える上で、以下の5つの構成要素を入れると良い。 1:インプット元 2:アウトプット先 3:競争関係 4:協力関係 5:影響者 ②ダイナミズムを読み解く →モデルが生み出す結果を長い時間軸で捉える。その際に、「ストックとフロー」「非線形」「作用と反作用」などを意識すると、ダイナミズムが特定しやすい。特定したダイナミズムを検証する時は、「物語として成立するか?」「因果の終着点までたどり着くか?」を確かめると良い。 ③モデルを変える打ち手を探る →大きな変化を生む小さな「くびれ」=レバレッジポイントを探す。モデルが変われば問題は解決する。 ④行動し、現実からのフィードバックを得る →①〜③を繰り返すことで、実際に自分が考えたモデルやダイナミズムの精度を検証し、現実からのフィードバックを得てそれを高めていくことが本質思考のアプローチである。 ■なぜ「本質思考」が必要なのか? 一言でまとめると、「スジの良い答えは本質から考えないと生まれない」からだ。 本質から考えずに、目に見える表層的な部分だけをみても、スジの悪い答えしか出てこない。だから結果に繋がらない。 これはプライベートもそうだが、特に様々なビジネスシーンで役に立つだろう。 具体的には、「何が問題なのかがわかる」「何をすべきかが明確になる」「関係者を説得できる」「関係者の共感を得られる」「行動に移すことができる」「問題を解決できる」といった効果を発揮する。 ■どうやって「本質思考」を取り入れるのか? 本質思考は、現象や情報に惑わされず、ものごとを抽象化し、自分の頭で考えるという、情報に頼らない考え方である。 裏を返せば、本質思考を鍛えるためには、情報を収集して知識を詰め込むだけではいけないことがわかる。 つまり、考えるための切る口や、使えるアナロジーを増やすことの方がはるかに重要となるのである。 〈本書に書かれているトレーニング法〉 ・新聞や雑誌の記事のタイトルから連想する →タイトルを見て、記事の内容をモデルとダイナミズムで捉え、記事のストーリーを自分なりに描いてから記事を読む ・「思考の雛形」を増やす →頭の中の思考の雛形が多いほど、色んな角度からモデルを考えることが可能になり、より物事の本質に近づく可能性が高くなる。 ・思考の「見える化」を行う →思考を見える化し、描き出したモデルとダイナミクスをクリティカルに見て、考えを深化させる。 ・持論を他人にぶつけてみる →メリット①ストーリー作りの訓練になる メリット②相手の賛成や反対、質問などによって、自分の自論が進化・深化する。 ・歴史観を磨く →根源的なドライバーを考えるという発想を育む。 ・答えのない問題に取り組む →ロジックだけで解けない問題、人によって大きく考えが異なる問題などは、本質思考を鍛える上で大いに役立つ。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■その他メモ ・「現象の裏返しは決して答えではない」 なぜなら、現象はあくまで結果であって原因ではないからである。原因を解決しないものは対症療法にしか過ぎず、結果的に時間とエネルギーの無駄になる。 ・本質に目を向けると論理的思考や仮説思考の威力が増す →本質から考えた上でのピラミッド構造や仮説は、現象から出発したピラミッド構造や仮説とは明らかに質的に異なってくる。
2投稿日: 2020.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログvol.292 MIT式、課題設定と問題解決の方法。スジが良い答えを出せる考え方とは? http://www.shirayu.com/news/2015/
0投稿日: 2018.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ本質思考(システム思考)についての導入。各論について大変わかりやすく、まさに本質を解説し、初期導入方法へと読者を導いてくれる。しかし、対象と見込む読者を広く取っているためか説明に使われる例がどうも表層的すぎて筆者の推薦する本質思考の魅力を貶めているように感じた。
0投稿日: 2018.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログシステムダイナミクスという考え方を下敷きに物事の本質に迫ろうというもの。システムダイナミクスとは、モデル(構造)とシステム(因果)を読み解き、レバレッジポイントを探して、モデルを変更(少しずらす)ことで、システムを変化させ、問題を解決していくという考え方のようだ。本書の最初のほうの思考の癖の章がなかなか面白かった。これを意識するだけでも、本質に迫ることができそうである。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログシステム思考の入門本。 モデルとダイナミズムについてシンプルに語られている。 抱える課題について、モデルとダイナミズムを考え、実践を今からしていこう。 なぜなら、相転移の根源的ドライバーはストック的なものだから。
0投稿日: 2016.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ本質思考とは、物事が起きている事象をみるのではなく、それの裏で起きているダイナミクスやモデルに焦点を当て、物事の解決の際にそこにアプローチをする試みである。 以下、まとめ、 https://www.evernote.com/l/AjF4RCsQuhdPtqfF2TpWIs-oYwqXmCUUyE8
0投稿日: 2016.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分にとってはまだ難解だった。 本質とはそのものがそのものであるために必要な最低限の要素のこと。 本質はモデルとダイナミズム、すなわち構造と因子からなりたっている。 その因子を「なんでそうなっているか」を追求して見つけ出し、長期的なプラスをもたらすために考えていくことが本質思考(なのだと思う。) また自分がいろんなインプットをして理解が進んだらもう一度読んでみたい。 <本質から考えるためには> 「なぜそうなっているのか」説明できるようになる。「なぜ」を繰り返す。「なぜ」「なぜ」「なぜ」。 例えばフレームワークを使うにしても、「なぜそのフレームワークを使うのか」意識しておかなければ意味がない。用語もただ覚えるのではなく、なぜその用語が重要な意味を持つのか考えなければいけない。 ・相関関係と因果関係は別物(因果関係を見つけるのが本質思考)
0投稿日: 2016.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログさらさらと読めました。読み流してしまって深く考えながら読んでいないという意味では良いのか悪いのか。 思考の癖というのは確かになー。常識を疑わないといけないし、誰かのせいにしちゃうし、カテゴライズして満足しちゃうし、かっこいい分析手法を知ったら途端に全部あてはめたくなっちゃうし、現象の裏返しの対処しちゃうし、仮説に沿って考えねじまげようとしちゃうし。あるあるだよね。 そーゆう、ちょっと普通よりは頑張ってみているけれど目的と手段が変わってしまってるパターンにちょ、待てよて言われてる感じ。 構成要素やそれらの相互関係からなる構造(モデル)と、モデルが生み出す現象の時間軸を見た場合の結果や動き(ダイナミズム)から本質を考えてみる。 ちょっと本筋と外れるけど、相転移とかモデリングとか、理系的な思考の癖をつけることが仕事を回すうえでは大事なんだろなーと思いました。ただそれをうまく平易かつ的確な言葉で表現するちからが合わさってこそ仕事できるヒトってのが出来上がるんだろなー。 思考停止にならんように気をつけてね~って言われてる感じ。
0投稿日: 2016.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ・現象の裏側にひそむ構造(モデル)と因果(ダイナミズム)を明らかにすることが大事 -表面的に見える事象の裏返しでは対処療法にすぎず根本的な問題解決にならない ・下記の4つのステップで問題解決を行う -モデルを描く -ダイナミズムを読み解く -モデルを変える打ち手を探る -行動し現実からのFBを得る ・モデルを考える際下記の5つをもらさないようにする -インプット元 -アウトプット先 -影響者 -競争関係 -協調関係 ・モデルやダイナミズムが見えていればストーリーで語れ、面白いと感じるはず ・思考を始めるとき、どういうプロセス・考え方(FW)で考えるべきかをまず考える ・アウトプットのタイミングを決める。人と約束する
0投稿日: 2016.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ●読むキッカケ ・世界はシステムで動く、を読んでシステム思考に興味をもった ・手軽にシステム思考が出来る様になる本としてこれを選んだ ●サマリー ・目を通してしまっただけで終わってしまった ・どうしたら出来る様になるかをもっと考える必要が有るため、再読する ●ネクストアクション ・実際に出来る様になるまで、反復して読むようにする ・出来る様になることを目的に、読むようにする ●メモ ・特になし
0投稿日: 2016.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
モデルとダイナミズムを考える。 言うと簡単だけど実際には難しい。 モデルを読み解くのはできると思うが、ダイナミズムを読み解くには知識と経験・深い洞察力が必要だ・・・
0投稿日: 2015.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ20150822「本質思考: MIT式課題設定&問題解決」 http://booklog.jp/item/1/4492557563 #booklog 混乱の今の時代を生き抜く知恵の本である。 今の時代とは、「高度成長」時代の遺産に頼る我々はその本質を理解さ無いまま小さな改変のみを繰り返し続けて自らを混乱の渦に飛び込んでいるようなものである。 「そもそも」と本質を問う質問をしてみる。思考のクセを知りそれを回避する。「モデル」を描き、ダイナミズムを読み解き、モデルを変える、行動する。 これを読むことで、自分の間違いに気づく、本質を見抜き変えることは時として必要である、ということに改めて気付く。自信、自身が無いと、否認したり、流されたりするが、同じ悩みを持つ人、同じ考えを持つ人がいるということで安心した。
0投稿日: 2015.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常にタメになった。 自分が携わっている業界や自社自体でしっかりと落とし込み、考えれるようにしていこう。
0投稿日: 2015.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログWBSに新たに非常勤で加わったベルガーの平井先生の1冊。書いていることは非常に参考になった。でも、そんなに目新しいものは無かった。奇抜な内容を期待している方にはお勧めできません。 本質を捉えるということは、斬新なことではなく、地に足を付けて看取するものであると考えれば、平井さんの言いたいことには合点がいくと思いました。
0投稿日: 2015.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ本質思考を妨げる9つのクセ →フレームワークに逃げる、など「あー、あるかもな」というもの多数 筋のいい問題解決(対処療法ではなく根本対応)するための、思考の組み立て方の説明と具体的な取り組み方が書かれている本です。 いきなり全てできないので少しずつ取り組んでいこう、と思った。
0投稿日: 2015.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ現状の構造を表す「モデル」と、そのモデルで起こっている現象の「ダイナミズム」を分析して、問題を解決するための打ち手を探っていく、と。言葉では書きにくい… 意外と「落ち着いて今の状況を一枚絵で描く」ということはできていないので、まずはこういうところから進めていけばいいのかな。
0投稿日: 2015.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
システムシンキングを少し勉強したくて手にとりました。現象を構造化し要素間の因果を読み解いていくことで本質的な課題を読み解くということです。当然この本だけで身につくものではありませんが、初めての手引き書という意味では平易に書かれており解りやすかったと思います。
0投稿日: 2015.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
MITスローンスクールで教えられるシステムダイナミクスをベースにした問題解決の手法。 モデルを描く、ダイナミズムを読み解く、モデルを変える打ち手を探る、行動し現実からのフィードバックを得る、というステップ。 モデルを描くための5つの要素(インプット元、アウトプット先、競争関係、協調関係、影響者)、そしてレイヤー(階層構造)の観点。 その後のステップを進めるための考え方やヒントは示されているが、現実的な適用は素人が個人的に取り組むような気持にはなれない。 15-41
0投稿日: 2015.02.24
