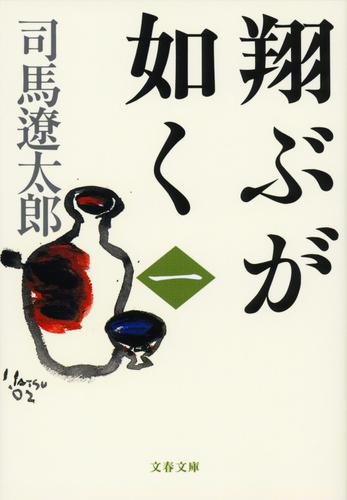
総合評価
(129件)| 25 | ||
| 60 | ||
| 30 | ||
| 5 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ西南戦争(西郷隆盛)の話。問題作。7巻くらいまで非常に辛い。もう2度と読みたくない。でもラスト3冊の展開は圧巻。
0投稿日: 2009.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ全巻通読後のレビュー。 全10巻という超大作であるが、もともと毎日新聞に連載された小説であるから、多々同じ記述が見られる。 しかしながら、明治維新後の日本の姿を鳥瞰的手法で世界史と関連付けて論じられている点で、日本近現代の始まりを理解する際の基礎理解には最適の入門書であると考える。 島津久光という超保守派の考え方から、維新を支えた革新派の面々の考え方が手に取るように分かる小説である。重要なのは士族の不満、百姓の不満がどのようなものであったか、であるが、それもこの小説では網羅されている。 物語は維新開始直後から、西南戦争(明治10年)を経て翌年の紀尾井坂の変(大久保の死)、さらに川路利良の病没までを描く。 明治維新は天皇の威を借りた王政復古という形でスタートした。それが後に軍の独走いうものを招くが、この時点ではそうせざるを得なかったということも、小説中で書かれている。 後の日本を支えていく山県有朋、伊藤博文、板垣退助、軍人で乃木希典、川村純義などが登場する。 西南戦争は8巻の半ばくらいから始まる。桐野、篠原ら薩摩隼人に担がれた西郷、悲劇のような最後の激闘である。西郷が桐野や篠原といった兵児(へこ)を最も愛し、彼らと生死をともにしたことは、西郷をうかがい知る上で、見逃せない点である。 西南戦争の中身についての描写は一流である。 時間がない方にも、8~10巻は読むことをお勧めしたい。
0投稿日: 2009.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ大いなる鐘、西郷について。 旧体制の感情の処し方、法治について。 外交が技術であるよりも国民的情念の表現、もしくはその情念のヒステリー発作というにちかい性質をもっているのではないかとさえ思える(122頁)
0投稿日: 2009.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこの歳になってようやく面白みが分かってきた作品。 高校の頃に一度読んだはずだけど、すっかり忘れてた。復習&堪能中。
0投稿日: 2009.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬版西南戦争。 前半おもしろかったのに、後半読むのきつかった…。正直苦痛だったぞ。 最後の大久保・川路組の顛末には色々思うところありましたが。 木戸スキーからしてみると、西郷さんへの記述が木戸さんにそのまま当てはまる部分が多くないか、と思うのですが。西郷ファンに怒られますか。 私的には似てると思うのよね。ただ、資質が似通っているはずなのに相容れない理由は、結局本質的なところで、木戸さんは政治家で西郷さんは思想家だったってことなのかな。 それって結構致命的だよね…。とも思う。妄想。 でも、おかげで徳富本でさっぱり掴めなかった西郷さんの行動が司馬流解釈とはいえようやく一本につながりました。めでたい!
0投稿日: 2009.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「竜馬がゆくの続編」といってもいい。 幕末の動乱から明治の国家成立までを西郷隆盛、大久保利通という幕末の巨頭を通じて描く長編小説。 この小説にところどころ見られる司馬史観とも言える江戸までの日本と昭和の軍人政治との断絶に関する考え方は 日本人として知るべきでしょう。
0投稿日: 2008.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎に初チャレンジした作品。が、10作もあり読むのに2ヶ月超もかかってしまったww 舞台は戊辰戦争後の明治初期。西郷隆盛を大きな軸として揺れ動く日本政府の動向をあらゆる人物の観点から追っている。よくもここまで調べたなって感心してしまう
0投稿日: 2008.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ竜馬がゆくなど幕末モノを読んでいると、維新が起きて明治になってめでたしめでたし、と思ってしまうのですが、当然の如く明治維新後の10年間というのは混乱の時代だったわけですね。 幕末時に維新の志士として倒幕に活躍していた面々が維新後は国を動かす立場になります。かつては倒幕で志が一致していた面々にも争いが起こります。 大久保利通はすごい男だな、と。 でもやっぱりなんか暗いイメージがあって好きな歴史上の人物にはならないですが。 彼は明治初期に日本の代表として清に交渉に来ているんですね。そのときに宿泊したホテルを見てみたいと思って色々調べてみたのですが見つかりませんでした。もう無いのかな。 この本を読むと薩摩人て特殊だな、と思う。男としてかっこいいなとも思う。 ちなみにこの本、1巻だけBOOKOFFで100円で買ったものの、続きが気になり2巻からは北京の外文書店で購入したのでかなり高くついた。。
0投稿日: 2008.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ川路利良のポリス論など、明治維新初期の外遊組の衝撃の大きさが詳細に記述されており、 当時の知識も未成熟な状態で、よくここまで自分のものにできたなと感心する。 大久保利通の落ち着いて、「私が目を開けていては話しづらいだとうと思ったからです」といったコメントが好き。 あまり知らない明治初期の流れがよく分かり、大変ためになる。
0投稿日: 2008.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ革命軍の象徴として事業を成した大将、西郷隆盛は最終的には国賊者として終わった。西郷をそのように転換させた征韓論とは何だったのだろうか。夷(外国)を攘(はら)うことをスローガンにした革命後、日本は矛盾にも積極的に開国し、必死に欧米に追い付こうとする。欧米諸国を訪問した者達は、征韓論は弱小日本には無理であることを痛感していた。また征韓論を唱える西郷は、革命後の不平士族たちの鬱憤を外征で抑えようという気持ちもあった。それに韓国を征することで、欧米からの防壁とすることを期待した。両論の確執は更に奥が深まっていく。 2008/02/20
0投稿日: 2008.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ西郷を殺した男として不当な評価をされる大久保利通をきちんと評価している。国家のために私情を一切捨てた大久保はすごいと思わせてくれた。 それでもやっぱり日本人は西郷好きなんだろうな。
0投稿日: 2008.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ知っているようで知らなかった西郷さん。今更ながら読んでみた。・・・・ビスマルク曰く大国はつねに武力解決しようとする。小国はあわれなものだ。国際公法は小国を守ってはくれない。小国がその自主の権利をまもろうとすれば、孜々としてその実力を培う以外にない。侵略国とは英仏のことである。かれらは海外に植民地をむさぼり、しきりに強奪政策をおこなっている。わがゲルマン国は海外への野望はいっさいもたない。・・・・日本は江戸中期以後に各藩単位で清吏の風が確立し、清国や李氏朝鮮のように官僚体制そのものがどう仕様もない汚職体制であるというアジア的形態からまぬがれており、木戸孝允にとっては日本の官吏が汚職するなどは思いもよらぬことであったらしい。ただ官吏の独善に走って民意を汲みあやまることは国家をみだすもとである、という。
0投稿日: 2008.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ薩摩中心ですが、注目はやはり木戸。幕末以上に苦労人な気がします。 人民を愛する漸進的民権家の木戸が素敵だ!!そして明治政府のなかで政治家と いうより革命家な彼がいい。 陰で奔走していた博文もよかった。 明治といえど幕末の雰囲気がまだあったのだと感じます。 ただ薩摩がいかんせん中心なので「長州来い!」と少しもどかしい。
0投稿日: 2008.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治初年の1年間は、これまで日本が経てきたどの時代よりも変化が激しく、著者いわく、洪水と大火と自身が1時に襲ってきたような観さえあるような時代であった。そんな時代、薩摩は明治維新を成し遂げた主役となった藩であるにもかかわらず、その藩風は、どの藩よりも士族の習慣が濃厚に残っていた藩でもあった。薩摩人は、挨拶口上でさえ多弁を恥じるところがあり、言葉を信ぜず、心を信じるという風があった。動作と表情によって表したのだ。 この時期、日本の朝野を問わず征韓論で沸騰しており、西郷はその渦中にいた。西郷がこの渦を巻き起こした張本人のように見られており、事実、西郷という存在がなければこれほどの騒ぎにはなっていなかったろう。といっても、当の西郷の心境は複雑で、西郷は扇動者というより、逆に桐野ら近衛将校たちが朝鮮征すべしと沸騰しているのに対し、”噴火山上に昼寝をしているような心境”と書き残しているように、自分の昼寝によってかろうじて壮士的軍人の暴走を抑えているつもりであった。 薩摩人は心情的価値観として冷酷を憎むことがはなはだしく、すべてに心優しくなければならないということを男子の性根の重要な価値としていた。また薩摩の武士道徳においては、無学も恥とするに足りなかった。戦国期を通じて、薩摩藩で最も高貴とされてきた人間の価値は、いさぎよさと勇敢と弱者に対する憐れみという3つで、武士の学問などはほどほどでよいとされていた。桐野利秋も生家は極貧であったが、それはむしろ精神美にさえしていた。 西郷は、司馬温公の例をあげて、一切胸中に秘密がないことを政治家としての自分の理想とした。幕府という得体の知れない政府を倒すときこそ寝技は必要だったかもしれないが、西郷の理想である太政官政府が成立したとき、一切の寝技は必要ないという態度を示した。正論ならば必ず通るという政府を作るためにこそ幕府を倒したからだ。 次に桐野利秋である。心が鬱すれば桐野に会いに行け、と薩摩人の間で言われたほど、桐野は足元からたえず爽風の立っているような男だった。話も面白く、何でもない話でも桐野の人格を通して語られると、ひっくり返るほど滑稽になったり、目を洗われるほど心地よい風景が現出したりした。ある人が西郷に、もし大軍を海外に派遣せねばならないことになったら、その総帥は誰が適任でしょう、と問うた事があるが、、そりゃ板垣どんじゃ、と答え、もし板垣がだめなら次はだれですか、と問うと、そりゃ桐野じゃ、と答えたと言う。桐野は恐らく100万の軍を統帥できるであろうし、更に言えば、桐野はそれ以外にこの世に存在価値がない男とまで西郷は思っていたかもしれない。桐野自身も、俺に文字があれば天下をとっちょる、といっていたほどだ。 18~19世紀にかけての産業革命は、商品のはけ口を海外に求めるということで、欧米は非常な勢いで、アジアにやってきた。欧米はその経済社会の要求に駆り立てられて、砲艦による市場開拓をやったのだった。 大久保だが、大久保には人間としての面白みは皆目無かった。日本人が他人を敬愛する場合、その人の弱点の部分をむしろそれが人間味があるとして惹かれたりするが、大久保にはまるでそれがないようであり、例えば酒でも女でも失敗することがなく、道楽と言えば囲碁だけだった。 西郷は、国家の基盤は財政でも軍事力でもなく、民族が持つ颯爽とした士魂にあると思っていた。そういう精神像が維新によって崩れた。というより、そういう精神像を陶冶してきた士族のいかにも士族らしい理想像をもって新国家の原理にしようとしていた。しかしながら出来上がった新国家は、立身出世主義の官員と、利権と投機だけに目の色を変えている新興資本家を骨格とし、そして国民なるものが成立したものの、その国民たるや、精神の面で言えば恥ずべき土百姓や素町人に過ぎず、新国家は彼らに対し国家的な当夜をおこなおうとはしない。こういう新国家というものが、いかに将来国庫が満ち、軍器が精巧になろうとも、この地球において存在するだけの価値のある国家とはいえない、と西郷は思っている。西郷の書簡や座談から彼の言葉を簡潔にまとめると、外征することによって、逆に攻められても良い。国家が焦土に化すのも、あるいは可である。朝鮮を触ることによって逆にロシアや清国が日本に攻めてくることがあるとしても、それはむしろ歓迎すべきである。百戦百敗するとも真の日本人は焦土の中から誕生するに違いない。国家にとって必要なのはへんぺんたる財政の収支表や、小ざかしい国際知識ではない。というようなことであった。かといって、西郷は焦土を望んでいたわけではないが、かれが新国家の基盤に一個の高貴な原理性をすえようとした思想は、その後、日本国家がついに持たなかったものであった。 国家は会計によって成り立つものにあらず、ということを西郷は様々な表現で言った。高き、見えざるもので成り立つ、これを失えば品位の薄い国になる。そういう国家を作るために、われわの先人達が屍を溝に晒してきたのではないと、西郷を言うのである。西郷は日本に生まれたことが不幸であった。西郷にとって困難なことは、こういう種類の思想を表現するための日本語が成熟しておらず、結局はこの俺を見てくれ、と自らの人間を理解してもらう以外にないということであった。彼が西洋の小国に生まれていれば、例えば1冊の聖書を取り出し、国家の基礎はこれである、ということも言えた。あるいは、既成の論理と述語を駆使し、かれが言おうとしているところの、国家はよろしく高邁ならざるべからずという、高邁の内容を十分に説明できたに違いない。しかし、彼は明治初年の日本人であり、おいがこう申す、と俺の人間を見てもらうしかなかった。確かに西郷の立論は、現実への把握が乏しく、多分に実際面において堅牢でなかったが、しかし、西郷の哲学的論理からすればそれこそ実際的であり、なぜならば、日本民族はこれによってこそ苦難を経て草木とも一新するだろう。維新の意義はそこにある。極端に言えば、日本民族の半ばが戦火に倒れるともアジアの一新に役立てばよいのであり、それはあたかも維新前夜の薩長に似ている。そのとき薩長は偶然勝つことができたが、しかし藩が滅びても良い覚悟は長州にも薩摩にもあった。アジアの規模に引き直せば日本が薩長に該当するのである。征韓論の廟議は結局は大久保が優位に立った。金がないからダメだ、という財政面から押し続けていけば、いかに優れた政策案でも無力にならざるを得なかった。 不平士族が征韓論を唱えているが、要は、廃藩置県への恨みからだ。全てはそこから出発している。武士階級がその特権と経済的利益を奪われたのだから恨みは深刻である。廃藩置県の号令が発せられたのは、明治4年7月14日だ。西郷は政府要人の集まった会議の中で、『この上、もし各藩で異議が起こりましたらば、拙者が兵を率いて討ち潰します』と言った。この一言で全ての議論が収まったと言う。西郷にすれば苦しかったに違いない。西郷は藩兵を率いて維新をやることで島津久光をだました。更にこの度、薩摩士族をひきいて市ケ谷の尾張藩邸に入れ、フランス風の軍服を着せ、階級を与え、近衛軍人にすることによって一挙に廃藩置県をやった。そのことによって、彼ら薩摩士族から士族の特権を奪ったのである。西郷は士族をもだました。『衆恨は私一身にあつまるでしょう』と西郷は言ったが、近衛軍人たちは西郷は恨まず、政府を恨み、具体的には同藩から出ている大久保を恨んだのである。廃藩置県による士族の不満に対し、その一手で蓋を押さえているのは西郷であった。『俺達は利用され、だまされた』と近衛軍人達は言った。それらの不満を西郷はなだめ、おさえ、苦心しぬいた。西郷はこの分に会わない作業のために、内心傷だらけになってしまっていたに違いない。ところが岩倉や大久保は廃藩置県に安堵して、政府ぐるみと言ったほどの大陣容で外遊してしまった。西郷は留守をさせられた。留守中の最大の問題は不平士族の反乱を抑えることであったが、西郷にとってこれほど苦しいことはなかった。元来、廃藩置県を可能にしたのは近衛軍であったが、この薩摩系近衛軍人団そのものが不平の巣窟になったのである。西郷は彼らをだました形になっていた。薩摩系軍人たちは幸い西郷をそのように見なかったが、それは西郷に対する情義によってそう見なかっただけで、理屈では明らかに西郷がだました。近衛軍人に言わせれば、誰が父祖代々の自分の権利を捨てるためにわざわざ東京へ出てくるであろう。だまされたのである。西郷はだました意識を持ち、そのことで苦しんだに違いないが、やがて長い外遊から帰ってきた連中は西郷のその苦しみを理解してやらなかった。大久保が理解するべきであった。しかし大久保にはそういう西郷の苦しみを共に苦しむような情緒感覚に天性欠けているところがあった。もし大久保に言わせれば、西郷は陸軍大将であるがためにそれを苦しむのが当然で、職分として苦しむべきである。自分は文官で、他のことに専念しなければならない。なすべきことが無限にあり、西郷の苦しみなどに構ってはいられない、というところであったろう。中央集権による東京政権が確立したのは、廃藩置県のおかげである。廃藩置県がなければ、岩倉や大久保が大きな顔をして、為政者ぶってはいられないのである。その廃藩置県を可能にしたのは薩摩系近衛軍人で、かれらは政府にだまされたとは言え、その功績は大きかった。しかしかれれは尽く政府に激怒している。大久保はそれに対して冷然としている。西郷はその大久保の態度に、配下の軍人と同様に憤りを覚えたであろう。その西郷が近衛軍人や士族たちの憤りを他へ向けるために征韓論を持ち出した。西郷としてはこれ以外にこれ以上押さえ続ける自信がなかった。その征韓論を大久保が蹴った。西郷としては帰郷せざるを得なかったであろう。しかし、国家を興す者は、その冷然たる大久保であると言わざるを得ない。 一方、廃藩置県についての長州藩の捉え方である。長州藩は周知のように、毛利元就から興った。元就が織田氏の急速な伸張をながめつつ、70余歳で世を去らざるを得なかったとき、輔佐政治と言う家憲を残した。元就の後の輝元は平凡な人物で、自分が平凡なことも知っていた。元就の遺言によって、2人の叔父である、吉川元春、小早川隆景の補佐を受けた。補佐官は時代によって変わったが、藩運営の精神は伝統として残った。この伝統によって、長州藩は、官僚組織が早くから発達し、その組織の精錬の度合いは、他藩よりはるかにぬきんでていた。そのかわり、藩主は機関になった。自然人というより、『君臨すれども統治せず』という長州的法理論のもとに歴代の藩主は存在した。しかもどういうわけか長州藩は、代々凡庸の人ぞろいで、一度も英気溌剌とした藩主を出さず、また、自分に個人的忠誠心を強いる自我の強い藩主も出さなかった。これらの事情が長州藩を独自なものにした。幕末における長州藩が毛利敬親を形式的にいただくのみで、藩士達の藩に対する認識は、近代の法人観念に驚くほど酷似していた。このことが、維新を迎えた長州人において、廃藩置県もさほどの抵抗を持たなかったし、太政官の官員になった長州人たちが、ごく自然に、明治国家を『公』として考える基礎的事情にもなった。薩摩は、西郷とその私淑者集団が強烈なばかりに薩摩的『私』を立てたとき、その『私』の倫理世界に我が身を投ずることをしなかった者達に外遊組が多かったことは、外遊組の薩摩士族は、外国から日本を見てしまったことで、薩摩独特の『私』の倫理観が後退してしまった。横浜から船が出ると同時に、そういう内面変化が起こったに違いなく、ごく自然に日本国を『公』と見るようになった。大久保や西郷従道が、いかにも薩摩離れをしてしまったのは、そういうことであろう。 大久保は積極的に天皇を利用しようとした。大久保の側からいえば、無理もないところもあった。旧3百諸藩の士族がなお東京の政権に不平を抱き、事あれば佐賀のように乱を起こしかねず、太政官の内部でさえ陸軍省のように廟議に対して批判を持つ勢力を抱いている現状では、天皇と詔勅を絶対化してゆくしかなく、これが日本統一の政治的魔術であると見ていた。薩摩士族はこういう大久保の権力のための天皇利用の態度を卑怯だと見ていたようだし、大久保を嫌う暗黙の一因にもなっていたであろう。 さて、話はいよいよ西南戦争の勃発に繋がっていく。私学校の生徒が政府が管理する海軍造船所の火薬庫を襲い弾薬を奪ったのだ。この変を桐野が知ったとき、桐野は『大事をあやまった』とつぶやいたものの、政府から当然犯人引渡しを要求されるだろうが、それは出来ないというのが桐野の答えであった。まさに、『反するも誅せらる。反せざるも誅せらる。如かず、大挙して先発せんと』であった。その変を西郷が聞いたとき、西郷も桐野と同様に『シモタ!何事だ、弾薬など奪って!』と、平素いかにも柔和な西郷が、このときばかりは怒気を発したらしい。 刺客問題というのは分かりにくい。そういう噂がながれていた。決起には名目が必要であり、刺客というものをもって、政府の非を鳴らすというのは少なからずあったであろう。刺客問題の口供書は、多分に作ったものだと、鹿児島権令の大山綱良は後日言ったが、今となっては真偽は定かではない。ただ、そう思わせるような言動が太政官、ことに大久保と川路にあったが故に、そう信じられ、暴発の最大エネルギーとなったのであろう。西郷は、詰問するために東京へ行く、そう思っていたに違いない。ただ、数名で東京へ行くのではなく、私学校生徒を引き連れて行くという、桐野以下の思いにたいし、西郷の裁断を仰いだとき、西郷は『自分は何も言うことはない。一同がその気であればそれでよいのである。自分はこの体を差し上げますから、あとはよいようにして下され』というような意味のことを言った。東京までの道中、何事も無く進めるとは思っていなかったであろう。 西郷は人物を見る場合、偏奇するところがあったであろう。西郷の幕僚格としては、桐野や篠原の他に、村田新八や永山弥一郎がいた。村田は物事に接して熟慮する人間で、少なくとも単純頸烈な薩摩隼人ではなかった。さらには欧州を見てきただけに見聞も広かったが、西郷はその村田の言動に動かされることはなく、村田もまた自分の言葉で西郷を動かそうとするようなことを不遜と思っていた男で、西郷の前では意見らしい意見を吐いたことがなかった。永山は村田より更に知的で、日本と世界との関係や、日本の中の政治や軍事についても、桐野、辺見流の単純さはなかった。西郷はそういう村田や永山から積極的に意見を徴しようとはしなかった。西郷はその性癖で、人を可愛がることが並外れてスキで、そういう可愛がる対象としては、村田や永山は年寄りくさくもあり、好みにふさわしくなかった。可愛がるには、桐野、というよりも端的な対象としては、若い辺見十郎太や別府晋介こそそうであったろう。犬好きの西郷が、狩猟につよい猛犬を可愛がるような気持ちとやや似た気持ちで。この偏奇こそが、西南戦争に西郷が身を委ねてしまった最大の原因のように思う。西南戦争は、ごく単純に言えば、私学校における若者の暴発から出発し、その暴発に西郷が身をゆだねたことで起こった。その暴発の気分の中心的存在が辺見らであり、決して村田や永山ではなかった。桐野や篠原、辺見なども、自分達こそ、村田や永山に比べ、西郷から溺愛されていることを良く知っていた。かれらにとって、西郷から愛されていると感じる時が最大の悦びであり、また愛されていることが、自分自身についての価値意識のほとんどであった。ただ、西郷の大度量というのは、むしろ敵に対してはそうであった。江戸城開城などもそうである。薩摩隼人は負けたものに対し哀憫の情をかけろと言って育てられてきたせいもある。このため、同藩の者や同調の集団に対しては、時に実に狭量であった。幕末、長州に対してもそうであった。 それに対し、政府軍も人モノ金をつぎ込んで、これでもかというほど重厚な布陣で臨もうとしていた。『戦いにおいては緒戦が大事である。小さな隊でも同じだ。最初に敵と出遭った時、どんなに無理をしても勝たなくてはならない。最初の戦闘で負けると、敵の士気をあげてしまうだけでなく、味方の士気が低下し、敵を恐れるようになる。そのひらきは埋めがたいほどに大きい。また、緒戦で負けた指揮官は、次の戦闘で名誉を回復しようとし、つい無用の無理をし、また負けたりする。いかに次の機会に苦闘し、そのつぎの機会に苦闘しても、あれは名誉回復のためにあせっているのだとしか見ず、正当な評価をしてくれない。戦闘は最初において勝たねばならない』と、作戦会議で、谷干城の作戦会議の中で、与倉中佐は力説していた。 一方、薩摩方は、『彼らは進むを知って、退くを知らず。唯、猪突を事として、縦横の機変に応ずるを知らず』と、私学校が暴発した当初、政府方にいる、薩摩出身の陸軍大佐 高島鞆之助が陸軍卿山県有朋に言っている。まさに、上代の隼人が翔ぶがごとく襲い、翔ぶがごとく退いたという集団の本性そのままに引き継いでいるかのようである。ただ、高島はこれを自分の出身集団の美質であると思っており、更に言えばかれらに機変に応ずる才や能がないとは思っていない。無いのではなく、戦いに臨んで小才を利かせて右往左往することを美的に嫌う習性があることを長州人である山県に説いているのである。
0投稿日: 2008.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ不屈ながら、「維新って冬が終わって春が来た状態」だと正直思ってた。あぁ、なんて愚かな。 そんな単純なわけなかろー。 維新も列強相手によーやりましたわ。 国が続くか、滅びるか―。 現在まで日本が侵略されなかったことは誇りであるだろう。もちろん、この時期に日本のことを考えてくれた人のおかげやなーってつくづく思います。
0投稿日: 2007.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログシリーズ全巻 西郷隆盛と大久保利通、新しい日本をつくるために尽力し、明治維新の功労者となった二人は、ともに薩摩人。 情と理、対照的な性格を持つ二人の友情を軸に、幕末から明治を鮮やかに駆け抜けた英雄たちのドラマ。
1投稿日: 2007.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ全10巻。 『竜馬がゆく』に並ぶ名シリーズ。 好漢西郷。。。 対称的な問題児桐野www こんなのが周りに居たらとんだとばっちり受けそうで困るネ。 しかし陰湿なところがなくサバサバしていて勇敢で、行動の善悪は別にして性格がかなり男前でかっこいい・・・。 作品の内容は結構切ないかなー。 『竜馬がゆく』よりこっちのほうがのめり込んで読んでたかもしれない。 限りなく5つ星に近いです。
0投稿日: 2007.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ全10巻。「竜馬がゆく」を読み終わったあと、スグに読み始めました。西郷隆盛と大久保利通という人物の最後には何ともいえない気持ちに…「武士」がいなくなって何が残っていったのか、現代人はよく考えてた方がイイのカモしれない…
0投稿日: 2007.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新の後のお話。幕末の動乱をくぐり抜けた猛者たちのつくった明治政府、なかでも薩摩藩の動向を書いた小説です。 初代の大警視(現在の警視総監に相当する)川路利良は、洋行帰りの新知識として日本初の警察機関の発足に尽力しようと決心する。司法卿・江藤新平の配下ではあるが江藤と対立する大久保利通に身を寄せる川路。しぜん、こころから心服し、兄事していた西郷からも離れざるをえず…大好きな西郷どんが心配でたまらない川路。不穏な動きをみせる桐野利秋。大久保利通と木戸孝允の溝は深まり…征韓論で沸き立つ明治政府。しかしそれは波瀾の序曲でしかなかった…。木戸さんの記述がイイ。中背ながらよくひきしまった体、とか、洋服が似合うとか、言葉づかいが上品で眉目が涼やかで貴公子風、とかさvそしてやっぱり大久保さんとの仲の悪さに萌える。
0投稿日: 2007.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ竜馬が好きです。 でも、この本を読んでいたら 西郷どんってどんだけいい人なんじゃろーって思った! カリスマ性なんて言葉じゃ片付けちゃいけないと思った。 そのぐらいいい人なんです。
0投稿日: 2007.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新とともに新政府が立ち上げる。その政府の抱える問題に、西郷が唱える征韓論がある。新政府の取り組み、特に外国からの知識の習得が紹介され、また、西郷の苦悩のはじまりが描かれている。
0投稿日: 2007.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新の立役者たちの、政府創世記。 倒幕のエネルギーの中で、新しいものを運用するための日本人のルール作りの苦手さを感じることが出来る。 西郷隆盛という幕末の志士を中心とした話である(今のところは)。 ちょっと小説でも読んでみようかと思って手に取った司馬遼太郎。 普段小説を読まないので、この手の硬めのものならなじむかなと。 賢人は歴史から学ぶと言うこともあるし、歴史小説で最も有名な著者の作品を選んだ。 で、翔ぶが如くになったのは、単純にそれが図書館にあったから。 読んでみると、それなりに読める。 単行本のサイズの割には、読む時間もそれなりにかかる。 関連知識が乏しいため、状況を整理しきれないところもあるが、もう少し読んでみようという気になった。
0投稿日: 2007.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ全10冊。 我ながらよく読んだと思う。 明治維新後何が起きていたのか、教科書ではさくっと流されてさっぱりだったのが、多少は頭に入ったような・・・とはいえいまさら知ってどうなんだろうか・・・・。 そして、いまいち好感の持てなかった西郷隆盛、、益々好感度が下がった。
0投稿日: 2006.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ維新後の日本国作りというものは、会社の経営と似ていた部分があるのかも知れません。経営者は風土作りに頭を悩ませ、意見と見聞と実行実践をしていきます。実名人物が各人キャラクターがあって、まさに小説の如く面白いです。幕末から日本敗戦にいたるまでの道のりを知りたい方が読んでみたら、いっそう興味深く読み進んでいけると思います。昭和の戦争をひもとくときに、幕末からの時代のうねりに伏線が張られていたことがわかってきます。
0投稿日: 2005.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ全十巻です。かなり読み応えがありました。「燃えよ剣」の後に読みました。 西郷隆盛、木戸孝允のその後が気になったため、読み始めました。この作品は主人公が特定されておらず、登場人物が入れ替わるため感情移入は静ら買ったですが、明治という時代を感じることは大いにできました。 しかし、西郷隆盛はなぜ象徴になり行動力がなくなってしまったのか。残念でなりません。
0投稿日: 2005.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ幕末の西郷隆盛・大久保利通を中心とした薩摩藩と西南戦争についての小説です。司馬遼太郎さんの司馬観と呼ばれる観点から、維新後の西郷隆盛・大久保利通を主とした薩摩藩がどのようなものだったか、そして、西南戦争が何故おこり、どの様なものだったかを10巻にわたって書いているうちの一巻めです。
0投稿日: 2005.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎の最高の駄作。10巻読み終えるのにかなり時間がかかった。良く調べたなぁと思うが、調べた事をダラダラと書いているだけ。
0投稿日: 2004.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ両親が鹿児島出身って言うのもあって、ものすごく思いいれを持って読んだ小説なんだけど(司馬さんの小説で、3作品目ぐらいだったかな、読んだの)、本当に悲しかった。 それに、もう、結末は歴史で習って知ってたわけだから、どうしてもね、、、最後になればなるほど、どんどんページの進み方が遅くなって、読むのにだいぶ時間がかかった。 でも、一番可哀想なのは、村田新八なんじゃないか、という気はする。 限りなく5に近い★4つ。 ちなみに、鹿児島に帰った時、村田新八のアコーディオン(手風琴って当時呼んでたみたいだけど)も飾ってあった気がする。
0投稿日: 2004.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新後の日本の話しで、幕末に活躍した人達のその後の生き方を知れるということが面白い。続「竜馬がゆく」を読んでいるような感覚だ。作者の個人的感情がだいぶ入っているが、伊藤博文や大隈重信や板垣退助など、エラいことをやったと思われている人達の欠点を欠点としてはっきりと書いていて、彼らもその他と大差ない人間だということが感じられるというのは新鮮な感覚だ。教科書はその人間が行った実績や事実は書くけれども、その人はどういう人間であったかということまでは書かない。どこまでが真実でどこまでが司馬遼太郎の私見なのかはわからないけれども、明治の、今に名が残っている人々の生き方を知ることが出きるというのは面白い。 大久保には厳乎として価値観がある。富国強兵のためにのみ人間は存在する、それだけである。かれ自身がそうであるだけでなく、他の者もそうであるべきだという価値観以外にいかなる価値観も大久保は認めてない。 なんのために生きているのか。 という、人生の主題性が大久保においてはひとことで済むほどに単純であり、それだけに強烈であった。歴史はこの種の人間を強者とした。(p.76) 薩長の士は、佐賀人とは政治体験がちがっていた。個々に革命の血風のなかをくぐってきて、「才略や機鋒のするどさだけでは仲間も動かせず、世の中も動かせない」ということを知るにいたっている。むしろなまなかな才人や策士は革命運動の過程で幕吏の目標にされて殺されるか、そうでなければ仲間の疑惑をうけて殺された。たとえば幕末に登場する志士たちのなかで出羽の清河八郎、越後の本間精一郎、長州の長井雅楽、おなじく赤根武人といった連中は、生きて維新を見ることができたどの元勲よりも頭脳が鋭敏であり、機略に長け、稀代といっていい才物たちであったが、しかしそれらはことごとく仲間のために殺された。結局、物事を動かすものは機略よりも、他を動かすに足る人格であるという智恵が、とくに薩摩人の場合は集団として備わるようになっていた。(p.155) 江戸期の武士という、ナマな人間というより多分に抽象性に富んだ人格をつくりあげている要素のひとつは禅であった。禅はこの世を仮宅であると見、生命をふくめてすべての現象はまぼろしにすぎず、かといってニヒリズムは野孤禅であり、宇宙の真如に参加することによってのみ真の人間になるということを教えた。 この日本的に理解された禅のほかに、日本的に理解された儒教とくに朱子学が江戸期の武士をつくった。朱子学によって江戸期の武士は志というものを知った。朱子学が江戸期の武士に教えたことは端的にいえば人生の大事は志であるということ以外になかったかもしれない。志とは経世の志のことである。世のためにのみ自分の生命を用い、たとえ肉体がくだかれても悔いがない、というもので、禅から得た仮宅思想と儒教から得た志の思想が、両要素ともきわめて単純化されて江戸期の武士という像をつくりあげた。 西郷は思春期をすぎたころから懸命に自己教育をしてこの二つの要素をもって自分の人格をつくろうとし、幕末の激動期のなかにあってそれを完成させた。(p.220) 長州人の集団というのは薩摩人集団とちがい、頭目を戴くということを習慣としてもっていない。幕末、長州藩を牛耳った革命集団は書生のあつまりであった。かれらの師匠は死せる吉田松陰で、死者だけに頭目としての統率力はもっていない。長州の革命秩序は、せいぜい兄貴株の存在をゆるす程度であった。この兄貴株が、すでに亡い高杉晋作と、明治後まで生きて元勲になった当時の桂小五郎、いまの木戸孝允である。 木戸がもし薩摩にうまれておれば悠揚たる親分の風格を身につけたにちがいないが、長州人集団ではそういう型の人間を許容せず、書生気分を維持することを必要とする雰囲気があった。木戸は、あくまでも書生気質を維持している。(p.226) 斉彬はライフル銃を作ろうとした。かれは帰国の前日、幕閣に、ぜひ、そのめずらしいものを拝見したい、と乞い、一挺を借り、一晩でそれを分解して図面に写しとり、幕府に返し、帰国した。帰国後、からは「集成館」と名づけているかれの工場に、「これを三千挺つくれ」と命じた。集成館には、この小銃をつくるだけの工作機械がそろっていたのである。ペリーも、かれが愚弄した日本国のなかでライフル銃を大量製造しうる侯国が存在していることを想像すらできなかったであろう。物理学や化学などの基礎学問や応用化学や機械学などもアメリカのハイスクールやその種の職業学校程度で教えられているぐらいの内容のものは、肥前佐賀藩や薩摩藩ではすでにもっているということもペリーは知らなかった。(p.300)
0投稿日: 1999.05.01
