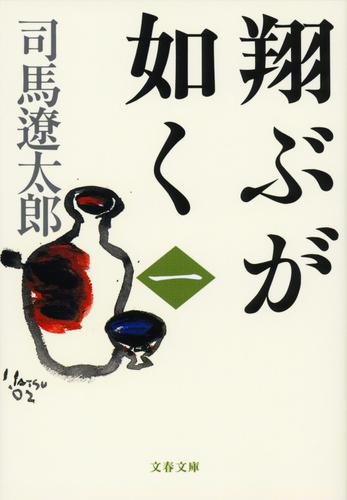
総合評価
(128件)| 25 | ||
| 59 | ||
| 30 | ||
| 5 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ征韓論を大久保利通、大隈重信、木戸孝允といった新政府高官からの目線と西郷隆盛の目線とを上手く書いている。まだ一巻。これからごう続いていくか楽しみ。 あれだけ多くの犠牲を出した維新が多くの人にとってどのような意味があったのか。起こるべくして内乱は起こる。
0投稿日: 2026.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ征韓論へと至る経緯や薩長の主要人物の関係性や性格が何となく分かる。 セリフが少なく、司馬先生の考えの分量が多いので、他の小説とは趣向が違う。そのため登場人物に感情移入するよりも歴史の流れを知る、という読み方になる。
0投稿日: 2025.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ維新の巨魁、西郷隆盛をどの様に描いて良いのか司馬遼太郎も模索しているのを感じられる。 圧倒的な存在感を有しつつ、大きな赤ん坊のごとく描くのが面白い。 ・滅私の精神 ・自己犠牲 ・滅びの美 ・豊富な感情量 等 日本人が好きな要素が詰め込まれた人と言えるのか。 以下に、私が好きな文中抜粋を記載します。 ・西郷はまるで柿泥棒でもして近所の老人から説教される子供のようにうなだれ、終始木戸の話を聞き、「いちいち、ごもっともなことごわす。」と、一言の弁解もしなかった。 ・禅はこの世は仮宅であるとし、生命を含めて全てはまぼろしにすぎない。かといってニヒリズムは野狐禅であり、物事の本来のあり方(真如)を求めることにより真の人間となる。 ・西郷の巨大な矛盾 ・たかだか才子にすぎない大隈は、西郷ほどに巨大な感情量をもたなかった。 ・大久保からすると、西郷は巨大な落魄者であった。 ・才略や機鋒の鋭さだけでは仲間は動かせず、世の中も動かせない。人を動かすは人格。 ・ぼっけもん ・沼間守一「自分は実はフランス語ができない。我らは活眼さえあればこの文明を見ることができ、その文明を作っている法を察することができる。武士たるか武士たらざるかがあるのみである。」 ・変節家ジョセフ・フーシェ
7投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ文中の、大久保が留学中の大山巌に手紙で伝えたなかの「国家の事は、一時的な憤発とか暴挙とかでもって愉快を唱えるようなものではない」ということばが、自分の身にしみました。 「国家」を「自分の人生」に置き換えて、反芻しています。
0投稿日: 2025.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
明治維新後の日本政府を様々な視点から書いた歴史小説。歴史小説というか歴史資料と言っても差し支えない程、詳細に説明している。 第一巻では主に、それぞれの観点からみた「征韓論」について述べている。征韓論は国を滅ぼす危険性を持つという考えや、士族のやり場のないエネルギーの矛先となり日本を活気づけるという考えなど様々なものがあった。 この時代に列強国へ赴き、自国の遅れと向き合い未来の日本のために事を為そうとした人がいた。その一方で、幕末の革命の熱気に当てられ続け、先の時代を見据える事が出来ていない者たちにも焦点を当てていた。今日、もしかすると自分は後者なのかもしれない。未だに学生時代を引きずり前に進めていないのかもしれない。これを期に先の時代に目を向けられる大久保や川路、岩倉のようになりたいとかんじた。
0投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「翔ぶが如く」第1巻は、明治維新を詳細に描いた全10巻シリーズです。この第1巻では、川路と桐野、西郷隆盛の偉大さとその離反の理由、征韓論、島津久光、薩摩隼人等がテーマとなっています。 まず、川路と桐野の対立が描かれています。謹厳実直な川路と豪放磊落な桐野の対照的な性格が興味深く、彼らの行動は相手との間合いを保つことで偶発的な戦闘を避ける姿勢を学ばせてくれます。 次に、西郷隆盛の偉大さとその離反の理由についてです。西郷は部下や敵対した藩に対しても尊大な態度を取らず、その謙虚さから庄内藩に西郷遺訓が残りました。しかし、黒田や川路はヨーロッパを見た後、西郷の魅力が薄れたと感じました。新政府の腐敗に失望した西郷の生活ぶりは川路に不安を抱かせましたが、その言動は「命もいらず名もいらず名誉も金もいらぬ人は始末に困るものである」として名を残しました。 征韓論は、西郷が革命の成功による不要なエネルギーを没落した階級への憐憫に向け、外征を通じて救おうとしたと理解されます。朝鮮に攻め込むのではなく、まず大使として東アジア共栄のために話し合おうという意気込みでした。ただ、島津斉彬は、日本の危機を防ぐためには機先を制して支那に兵を送るべきだと考えたことは残念です。これを西郷が信奉していたとは思えません。 島津久光に関しては、西郷と大久保を反逆者として許せず、彼らが島津家を騙したと非難しました。しかし、圧倒的に人気がある西郷を逆臣扱いにした久光の評価は斉彬ほど高くありません。 薩摩隼人については、敏捷性と武士の意味を持ち、今でも鹿児島県人の優しさとして少しは受け継がれています。 最後に、著者の広範な歴史知識がこの作品に深みを与えています。明治維新を好意的に描写し、その後の日本の手本となったことが感じられます。
0投稿日: 2024.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024.12.6読了 明治維新後、歴史にとってそれぞれの重要な人々がどう感じどう動いていたのかがよくわかりおもしろい。普段読むジャンルとは異なりなかなか難しく感じるが、読み進めていきたい。
1投稿日: 2024.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ鹿児島に行く機会があり、新政府軍に反旗を翻した人物でありながら、なお薩摩の英雄として厳然と存在感を放っている西郷隆盛という人物についてもっと知りたくなり、手に取った。 小説というよりは、司馬遼太郎の維新論が述べられている風だか、やはりきちんと小説として話が進んでいる手法は流石である。 英雄としての西郷ではなく、人間西郷が描かれている。続きが気になる。
0投稿日: 2024.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎作品において正直前評判があまり良くなかったので、期待はしていなかったが、個人的にはとても面白かった。 西郷隆盛という、歴史的偉人について、司馬遼太郎作品らしく、多くの史実や独自の視点から紐解いており、改めて尊敬すべき偉人だと感じる。 ここからどのような展開になっていくか楽しみである。
1投稿日: 2024.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ征韓論。なぜ急にこんな論が持ち上がったのか、と不思議に思ってました。やはり一概に語れるものでは無いんですね
0投稿日: 2023.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまでの司馬遼太郎作品と比べるとなかなか進まなかったのが正直なところ。 でも巻末に近づくにつれ、島津斉彬に対する西郷隆盛の忠誠心・想い、その想いを汲んだ”征韓論”の位置付けが明確になってきた。 というより、孤島としての日本の歴史に染み付いている畏れみたいなものが見えてきた。
1投稿日: 2023.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ西郷は革命の成功者でありながら、革命か引き起こすであろう惨禍のほうを一身て引き受けようとした。古今東西こういう革命家は存在しなかった。 通常革命後、反動で反革命運動が起これば、それを新政府軍で殲滅するのが、「反革命層のほうが、あわれだ」という革命家が、どこにあるであろう。179
0投稿日: 2023.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「尊王攘夷」のスローガンで始まった筈の倒幕運動から、明治維新が為ってみたら、幕末からの開国方針が何も変わっていないという、この歴史の流れが、長らく釈然としなかったのだが、これを読んで、漸く腑に落ちたというか――当時の士族達も釈然としなくて、だからあちこちで士族の反乱が起きて、最終的に西南戦争に至ったのね、と。しかし、旧支配層の武士は既得権益を取り上げられ、庶民は税金やら兵役やら負担が激増した、この明治維新という大改革が、よく破綻・瓦解しなかったものだという、新たな疑問が湧いてきた。
0投稿日: 2023.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ読めばきっと大久保利通を好きになる作品。 司馬遼太郎の良いところは、好きな登場人物を持ち上げ過ぎないところじゃないかと思う。長州人のこと好きだよね?・・・ね?
0投稿日: 2023.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ西南戦争の物語。全10巻なので導入の導入という感じ。 日本の近代史は、明治維新という輝かしい改革に始まり、太平洋戦争の敗北という悲劇的結末に終わる。 生命は生まれた時に死も内包しているというが、大日本帝国にしてもそうだろう。 西欧列強に伍さんと近代化を目指すことは是としても、アジアへの進出は後世では侵略として語られることになってしまっている。 現代の価値観で裁くことは愚かだが、それでも別の方法があったのではないか。 それを成さんとしたのが西郷隆盛だったのである。 ・・・と、大袈裟かもしれないが、私はこのように読んでいる。続きが楽しみ。
2投稿日: 2021.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログちなみに今読んでいる本は以下(この本)である。 最近買うのは原則文庫であり、時代小説中心の読書である。 以前はたくさん読んでいた自己啓発ものは、もう興味がわかず読まない。もてはやされる成功者も結局は逮捕者や社会”だまし”が多い。それよりも自分で如何に楽しく健康でがんばって行けるかに注力したいと思うようになった。よって自己啓発本は9割以上をBook Offしてしまった。(2008.2.22HPの日記より) ※2007or2008年購入 2008.2.22読書中 2008.2.27読了 2017.5.6売却@Book Off
2投稿日: 2021.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
~全巻通してのレビューです~ 主人公の西郷隆盛が捉えどころのない茫漠たる人物として描かれているので、読後の感想も何を書こうかといった感じで難しいですね。 西郷は征韓論を言ってた頃はわりとはっきりした人物像でしたが、西南戦争が起こってからは戦闘指揮をするわけでもなく神輿に乗ってるだけでしたから。 司馬先生ももっとはっきりした人物が浮かび上がってくる見込みをもって描かれたのではないでしょうか。 もう一人の主人公ともいうべき大久保利通は一貫して冷徹で寡黙な人物として描かれてます。 台湾出兵後の清との交渉では、大久保の粘り強さと決断力炸裂で面白かったですね。 あとは、やはり最後城山で薩軍が戦死する場面が良かったかな。 テロリスト桐野や狂人のような辺見はずっと見てきてお腹いっぱいに感じてたので、やっと終わるかと。 読んで爽快感が得られる本ではないので、評価はなかなか難しい作品かと思います。 でも、この日本という国を理解するうえでは、読むに欠かせない作品かと思いました。
1投稿日: 2021.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログさすが、司馬遼太郎だないう感想。 期待を裏切らない。 あまり前知識を入れずに読み始めたために、 西郷や大久保、木戸孝允が話に絡んでくるまで、話に入り込めなかった。 しかし、少しずつ話に入り込むと、明治日本を作った人間たちのそれぞれの思いや行動に、時には納得し、時には疑問に思うこともありながら、それぞれの正義に向かって進んでいく姿勢にワクワクしつつ読み進めてしまう。
1投稿日: 2021.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに読み返したらややイメージが違かった。 学生時代に結構読んだ司馬遼太郎、今読むとまた含蓄が違う。 時代が令和になっても面白い。 情報量が多いので面白かった所は忘れないようにマーキングしておこう。
0投稿日: 2020.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
p.194-195 かれは一方では自分のつくった明治政府を愛さざるをえない立場にあり、一方では没落士族への際限ない同情に身をもだえさせなければならない。矛盾であった。 矛盾を抱えたまま、西郷隆盛はどのような道を歩んで行くのか…。残り9巻。ゆっくり楽しんでいこうと思います。
0投稿日: 2020.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ外交問題(作中では征韓論)が、欧米のような技術的な事柄でなく国を二分する内政問題として現れる、という視点がおもしろかった
0投稿日: 2018.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ全10巻の1巻だから、本当に序盤の序盤。 まだ面白いかどうかは、判断はつきにくい。 今、毎週 大河ドラマも観ているからその内容と同じ?と思ったけれど、こっちはもっと先の維新後からのスタートだった(あらすじは、よく読みましょう;;;) 今年、維新を迎えてから150年目の節目に当たる。先人達の熱い息吹と、血潮を感じてみるのも良いものである。
5投稿日: 2018.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「翔ぶが如く(1)」(司馬遼太郎)を読んだ。 あの遥けき時代・・・明治。 現在の日本国の礎を築いた「異能者」達がいた。 私は日本人にあるまじき程に「西郷隆盛」という人物について無知である。 全10巻かあ。長っ!!
1投稿日: 2018.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
秀作。 司馬遼太郎、流石。その中でも長編大作。面白い。 若い頃は、大久保を尊敬していたが、歳を重ねて西郷が好きになってきた。 綿密な調査、凄い。 さすがに長い。 今の日本にも引き継がれている政治家の隠蔽、庶民を騙す手口。政府は信用ならない。計画性なんて無いと疑ってみる。 日本人は、野蛮だと、つい150年前の出来事。忘れてはならない。
2投稿日: 2018.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、鹿児島に住んでいた時に読んだので、15〜16年振りに再読。御一新が成就して新たな時代がスタートし、盟友の西郷さんと大久保さんの関係に距離が出てきた。最後にあった師匠とも言える島津斉彬公のお話は興味深く、征韓論は斉彬公のアジア同盟構想からスタートしたことは、なるほどと思わせることはあり、久しぶりに照国神社に行きたくなった。
2投稿日: 2018.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ川路利良の汽車内でのエピソードに衝撃。。それはともかく、西郷隆盛のイメージを固めた作品であるはずだから、腰を据えて読むつもり。
1投稿日: 2018.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「小さく撞けば、小さく鳴り、大きく撞けば、大きく鳴る」とは龍馬が行くで龍馬の西郷評だが、その人となりを第一巻では色々描写している、島津斉彬との関係、盟友、大久保利通との立場の違いなど。来年の大河ドラマの予習になった。
1投稿日: 2017.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
来年の大河ドラマが西郷(せご)どん、であることから原作ではないが明治初めの政局、動きを知りたいと思って再読のはず。 本棚には2巻まで揃っている。
0投稿日: 2017.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史は倫理ではなく感情の結果として成るという形容のままに、維新前後に現れた天才達の心理描写を深く描いている。 坂の上の雲でも描かれた郷土意識なくして明治時代は語れないようです。 主な登場人物を整理して読むと理解しやすい。 〈備前佐賀〉 江藤新平 大隈重信 大木 〈薩摩〉 大久保利通(日本最大の策士) 東郷平八郎 島津斉彬 島津久光(保守主義) 川路利良(警視総監) 〈公卿〉 岩倉具視 三条実美(さねとみ)、新国家の首相 〈土佐〉 板垣退助 坂本龍馬(既に死せる) 〈長州〉 木戸孝允(たかよし、桂小五郎) 井上馨(かおる) 山県有朋 大村益次郎(首相、暗殺) 高杉晋作(既に死せる) 伊藤博文 副島種臣 桐野利秋(陸軍少将) 氏の作品らしく、その他多くの人物が登場して知的好奇心を十分に満たしてくれ、この時代に大いに興味を掻き立てられる。 しかしこの流れで10巻もあるなんて、しかも維新成立後からの物語とは。。
2投稿日: 2017.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ来年の大河ドラマの主人公、西郷隆盛についてここのところ何冊か読んでいるが(海音寺潮五郎氏の西郷隆盛・伊東潤氏の西郷の首等)やはり司馬遼太郎作品「翔ぶが如く」に尽きますね。10年ぶりくらいに読み直しです。
2投稿日: 2017.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ【あらすじ】 明治維新とともに出発した新しい政府は、内外に深刻な問題を抱え、絶えず分裂の危機を孕んでいた。 明治6年、長い間くすぶり続けていた不満が爆発した。 西郷隆盛が主唱した「征韓論」は、国の存亡を賭けた抗争にまで沸騰してゆく。 征韓論から、西南戦争の終結まで新生日本を根底から揺さぶった、激動の時代を描く長編小説全10冊。 【内容まとめ】 1.西郷隆盛・大久保利通の出生からではなく、明治維新後の物語 2.薩摩隼人という現代日本人とは一線を画す民族の詳細 3.薩摩隼人は「得たいが知れない」!! 【感想】 日本史はとても面白い。 いつの時代も魅力的だが、やっぱり個人的に特に好きなのは、幕末から明治初期にかけてのこの激動の時代だな! とは言え、坂本竜馬を主人公とする「竜馬がゆく」以外はあまり詳細を知らなかったこの時代の出来事。 戊辰戦争?鳥羽伏見?うーん、新撰組の終焉なども含めて、この数年はポッカリと穴が開いたようにあまり詳しく知らない・・・ 「翔ぶが如く」の主人公は、西郷隆盛・大久保利通を始めとする薩摩っ子たち! 桐野利秋、川路利良(としなが)も、やや属性は違うものの薩摩の血を強く感じる魅力的なキャラクター。 余談にそれる度に彼らと疎遠になってしまうので、余談は楽しいけど寂しさが勝ってしまうんだよなぁ・・・ また、「はじめに」の内容が面白すぎる。 筆者・司馬遼太郎でさえ主人公である薩摩隼人の全貌が分からないというのだ!! ・行動が俊敏 ・「自分たちこそが日本人」という確固たる優越感 ・やさしさとユーモア ・気性の荒さと残忍性 確かにこの人たちは「得たいが知れない」よね!!笑 同じ時代にこんな奴らが居たとすれば、こんな安穏とした生活は送れなかっただろう。 余談にそれなければ、半分、いや3分の1程度のペースで物語が終結するのではないか? 勉強になるし、学校では絶対教えてもらえない歴史の内面が詳しく知れて楽しいし、なによりそれが司馬遼太郎作品の良いところなのは否定できないが・・・ 早く物語の続きが見たい!!!!笑 長編ですが、のんびり読もうと思います。 【引用】 「君たちは得体が知れない」 隼人と呼ばれるほど行動が敏捷で『自分たちこそ日本人の原型である』という優越感を持ち、優しさとユーモアが共通していて、不思議としか言いようのない気配を歴史の上に投影した薩摩藩民の物語。 こういう機微が分からなければ、うかつに薩摩のことは書けないとまで思い悩んだとのこと。 p75 大久保は執拗な性格を持っている。 物を考えるときには眼前の人間を石のように黙殺することができた。 彫りの深い端正な顔には無用の肉はすべて削ぎとられていて、どうやらそのことは容貌だけでなく精神もそのようであった。 彼は仕事をするためにのみ世の中に生まれてきたかのようであり、他に無用の情熱や情念を持たず、そういう自分の人生に毛ほどの疑いも持っていなかった。 p82 ・隆盛は間違い、父の名前 通称 吉之助、名乗りは隆永 西郷は訂正しにもゆかず、彼自身は常に吉之助を称していた。 自分の名前などどうでもいいという桁外れたところがこの兄弟にあった。
7投稿日: 2017.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「翔ぶが如く」司馬遼太郎さん。文春文庫で全10巻。1972-76の新聞連載小説だそう。 日本史上、最大規模で、最大に哀しくダイナミックな、「幼馴染の、かつての親友同士。歳月を経て対立、そして殺し合い」の叙事詩。 「オトコとオトコの思いが、銃弾と血の中で、歴史を描いて、炸裂する」という感じ。 オトコ友情路線とすると、「ヒート」とか「RONIN」とか「ミスティック・リバー」とか「男たちの挽歌」とか「仁義なき戦い」とか。 そういう趣もある、巨編です。 # (元が長い、かなり無愛想なところもある小説ですし。 以下、完全に自己満足な備忘録、メモです) # 出来事としては、明治6年(1873)の「征韓論騒動」から始まって、明治10年の西南戦争、そして明治11年の大久保利通の暗殺までを描きます。 つまり、5年間のおはなし。 水滸伝か! … と、いうくらいに色んな人が出てきて魅力的に描かれます。 が、まあ、主に言うと。 敵味方に分かれて戦う幼馴染のふたり。西郷隆盛、大久保利通。 そして、それぞれの番頭的な部下である、桐野利秋(幕末では西郷のボディガードとして「人斬り半次郎」。明治後は軍人)、そして川路利良(日本の警察制度を作った官僚)。 という四人の薩摩人がいちおう主人公。 なんですが、序盤から話はあちこちに飛び。 大勢の人物が出てきて、それぞれ立ち位置や経歴やエピソードが描かれ。 それぞれの事件について、流れの中でどういう位置づけなのか、幕末からの経緯が語られる。 司馬遼太郎さんの小説の中でも、だいぶ、「散文的」になってきている。そんな大長編。 ですが、オモシロイ。 # 「ちょんまげで、徳川幕府で、年貢で鎖国だった日本が。 洋服で政府で税金で、外交官とか外務省とか、そういう近代国家になる」 ということを、とにかくわしずかみに描いています。 それが、ものすごいわくわく感。 # なんとなく、「幕末」というのはイメージがあります。 どうやって、徳川幕府が倒れたか。 言ってみれば、戦いですね。 坂本竜馬、新選組。 ところが、その後、どうやって「明治日本が出来上がったか」というお話です。 つまり、 「えっと、どういう国にしようかな...」 というところから始まるんです。 もう、無茶苦茶に乱暴で、混乱で、混沌なんです。 # そもそも、新しい政府っていうのは、どういうことかというと。 徳川慶喜が「大政奉還」します。 「もうガタガタいうのなら、幕府、辞めます。わたしは、徳川っていう一人の大名になります。ぢぁ、日本の仕切りまとめ、っていうのはさ、朝廷がやんの?やってみろよ」 ということです。 押し付けられちゃって出来たのが、「新政府」。 何の能力も無い、公家と天皇家だけなんです。 もちろん、何も出来ません。 彼らは、薩摩、及び長州の、 「言いなり木偶のぼう」な、だけですから。 つまり、薩摩と長州の、せいぜい30代~40代前半くらいの若者たちが、徳川慶喜から「ぢぁあ、お前らやってみろよ」と、「日本」を投げられちゃいました。 # 「新政府」というのを企業に例えば、天皇家と公家だけいる、ペーパーカンパニーだったんです。 実際は、「薩摩」とか「長州」というよその大企業の、課長クラスか係長クラスの連中が、彼らを動かしていました。 仕方がないから、薩摩長州から人材を「新政府」に入れる。つまり、出向みたいなもの。 急造新政府は、直属軍隊が1名もいない、というむちゃくちゃな政府。 その上、お金もまったくありません。 結局、「大政奉還」という寝技を前にして手も足もでなくなります。 そして、ヤクザのように「とにかくさあ、徳川さんよお、政権だけぢゃなくて、財産もこっちよこせや」という難癖をつけるしかなくなります。 もう、正義もへったくれもありません。 こうして、鳥羽伏見の戦い。戊辰戦争。江戸無血開城。彰義隊。会津戦争。五稜郭...と、内戦が続きます。 戦争自体には、勝ったり負けたりでハラハラドキドキのドラマがある訳ですが、まあ、これは新政府が勝ちます。 (このあたりの、どうやって勝てたのかっていう魔術が「花神」という小説、大村益次郎という人物) で、どうするか、なんです。 # 結局、徳川幕府の時代、というか江戸時代っていうのは。 「武士」という階級のひとたちがいっぱいいて。この人たちは、まあ、行政官、政治家、役人、国家公務員、地方公務員、だったりするんですが。 それにしては、人数が多すぎたんですね。 もうとにかく人数が多すぎる。そしてほとんどが、簡単に言うと、働いていないんです。 でもこの「武士=無駄な正社員」たちを食べさせないといけない。なので、農民から搾取します。農民は悲惨です。 そして、「武士=正社員」たちには、「米」をギャラとして渡す。 というのが、仕組みだったんです。 ただ、長い平和のお蔭で、経済と流通が発達します。 コメ本位では、経済的に行き詰ってきます。 なので、勘の良い企業(藩)は、内実として「コメ生産に完全に依存する経済」からの脱却を図っていました。 それが成功した藩は、お金に余裕が出来ます。幕末に、政治活動とか軍事活動を行うゆとりができます。 (つまり、多くの藩は、幕末に政治活動とか戦争とか、そもそもやる余裕が無いところが多かった。もう、生きてるだけで精いっぱいみたいな経済状況) # さて、「新政府」と言っても、色んな意見と色んな思想があります。 その中で、実績があって、世界観やビジョンがあって、意見を通す実力がある。そういう人物は誰だったのか。「明治初年~6年までの新政府」っていうのは、つまり、誰のことだったのか。 西郷隆盛。大久保利通。木戸孝充。 この三人なんです。 生きてさえいれば、大村益次郎、坂本竜馬、中岡慎太郎、あたりもここに割り込んでいたでしょう。 でも、死んぢゃってますから。 上記三人に、一段落ちたところに、 江藤新平、井上馨、伊藤博文、黒田清隆、山形有朋、大隈重信、板垣退助、勝海舟...と言った面々がいる、という様相。 (他に、岩倉具視、三条実美なんかもいますが、あくまで乗っかっているだけで、ゼロから国体を創造する、という意味では、「その他大勢」に過ぎないと言えます) さあ、という訳で。 「西郷、大久保、木戸は、どういう国を作ろうと思ったか」 ということです。 # 幕府を倒す、というエネルギー、幕末というお祭りは、ペリーが浦賀に黒船で来て、武力脅迫で鎖国を破った事件への、反発から始まりました。 とんでもないことなんですが、 「日本何千年という国法、鎖国を復活せねば」 という、誤解の情熱なんです。 歴史教育というのは、恐ろしいものです。 「鎖国を貫けない幕府を糾弾せよ」 「そんな幕府なら要らない」 「天子様を中心に新しい体制で、鎖国復活だ」 という流れなんです。 ところが。 # ごくごく一部の、インテリさんたちだけが。 「どうも、中国などの例を学んでみると。 それから、欧米の現実を知ってみると。 国の仕組み、工業能力がかけ離れている。 下手すると、ほんとに植民地にされちゃう。 防ぐためには、神州不滅、神風だのって吠えてちゃ、だめなんちゃうか? 彼らのマネをせな、仕方ないんちゃうか」 という、善悪はともかく、戦略的な現実地点を判り始めます。 そして、 「選挙?市民?自由?平等?貿易?経済? うーん。欧米の、国の仕組みっていうのは... けっこう実は、良いトコロいっぱいあるんちゃうか?」 「もうこりゃ、鎖国アゲインっていうのは...現実、ありえへんな」 ということまで、感じて来てしまいます。 (主に、いちばん先頭に立って、外国人撤廃運動=攘夷 を突っ走った、長州と薩摩の実務担当者たちが、初めにそれを痛感します。つまり、西郷であり、大久保であり、木戸です) # 徳川慶喜だろうが、勝海舟だろうが、坂本竜馬だろうが。 そして、生き残って勝ち組になった、「西郷、大久保、木戸=新政府首脳」にしても。 各々にエゴや事情はありますが、国家をどーする、という次元では、 「中国みたいに、植民地、あるいは準植民地みたいにならないように、する」 というのが圧倒的に第一位の強烈な焦りであり、欲望であり、危機感なんです。 その為に、どうしたらええんやろ。 日本刀では、銃に大砲に軍艦に、勝てない。 銃、大砲、軍艦、を、買わなきゃ。 作らなきゃ。 その上、徳川幕府から引き継いだ、「負の遺産」があります。 「不平等条約」です。 訳の分からん間に結んでしまった条約は、 「貿易をしてもまともに関税が取れない。つまり、経済的に搾取されるばかりになる」 というヤバイものだったんです。 このままぢゃ、経済的に「準植民地」にされかねません。 武力として強くならないと、イザという場合に話にならない。 それだけぢゃなくて、 「ほら、皆さんと同じ、文明国家ですよ」 という姿を見せないと、「条約改正」が行えない。 これが、新政府の課題です。 つまり、西洋風の近代国家にならねば、あかん。 # 近代国家には金が必要です。 だけど、金が無い。 「新政府」は「大名サイズ」で言うと、そんなにデカくないんです。 その上もう、コメ本位でぶんまわせる金額では、近代国家に必要な、「議会、学校、病院、軍隊、エトセトラエトセトラ」は、経営できません。 「武士」という人々を「リストラ」しなくてはならぬ。 = 廃藩置県。 # 廃藩置県。 これは、すごいことだったんですね。 どうしてかっていうと、日本全国の武士たちが、政令ひとつでイッキに無職になってしまう訳です。 なんというか、大量にいた、全国の地方公務員たちが、紙切れ一枚で、「明日から無職」という感じです。 更にすごいのは、結局、明治維新とか、戊辰戦争とかっていうのは。 彼らこそが、武士たちが、成し遂げたわけです。 100%とは言いませんが、ほぼ100%。 武士が頑張って、武士が戦って、武士が命を賭けて、達成した事業なんですね。 しかも、彼らのほとんどは「鎖国アゲイン、アンチ西欧」という謳い文句で踊った訳です。 # なので、つまり。 勝ち組の武士たちからすると、啞然、憤然、激怒、だった訳です。 さらにたちが悪いことに、「西郷、大久保、木戸」を筆頭に、「勝ち組の武士たち」の一部の連中は。 東京に呼ばれて「政府の大臣とか高級官僚」になっているわけです。 そこでは、勃興する資本主義とともに、高給を取り、商人に接待を受け、多くが浮かれて豪華な暮らしをしていたわけです。 そして、そういった少数の勝ち組は、思いっきり西洋化していく訳です。 これぁ、地方にいる、勝ち組(だったはずの)武士からすると、最早、殺意な訳です。 だって、こっちは一方で、突然ギャラがほぼゼロになって、路頭に迷っているんです。 # 結局、「翔ぶが如く」っていうのは、つまりこの「廃藩置県」の余波の話なんです。 もっと言うと、「武士階級の滅亡に伴う、壮大な反発の叙事詩」な訳です。 そこには、250年の江戸時代に、思想にまで高められた「武士道」みたいな精神が、無価値に落とされることへの反発があります。 「武士道」的な、実に前近代的で、実に非経済的な、美学みたいなものの、追い詰められた自爆の花火の壮麗さです。 # 武士たちは日本全国で猛反発です。 さらには、国民皆兵によって、「武士以外が、兵士になる」ということも、激怒を買います(大村益次郎さんは、コレがどうやら主原因で暗殺されたようです)。 一方で、農民だってたまりません。 根本的に農民にとっては、維新とか、近代化とか、全般的にどうでもいいんです。 なのに、勝手にそうされて、税金がコメではなくて、現金になります。 現金なんか作れません。全国で小規模百姓が、税金のために小作農に身を落とします。 その上、慣れない「近代化」を進める中で、まだまだ「国家官僚」の意識、モラルも低く、全国の地方行政でも汚職不正がはびこります。 全国で、百姓一揆も頻発します。 (司馬さんが書いていて面白かったのは、全国の百姓一揆と、「怒れる武士たち」が連携したら、政府は恐らく倒れていただろう、という。 でも、そうならなかった。なぜなら、「武士たち」は、百姓と連携することなどを、拒否するプライドがあったからこそ、怒っていたんですね。 ここンところ、なるほど、と、面白かった) という訳で、つまり。 明治6年~明治11年くらい、この物語の頃っていうのは、明治新政府も、かなり辛かった。 ぎりぎりのところで資金をやりくりして、不渡り寸前でハラハラの経営に追われる中小企業の経営者みたいなものです。 # で、結局。 西郷さんは、「新しい近代的な国民国家」、もっと言うと「武士無き世界」っていうものが、生理的に受け付けなかったんですね。 恐らく、理性では判っていたんでしょうけれど。 大久保さんは、その国民国家の成立のために、命を賭けることが出来た。そこに向けた、苦しい中小企業の経営の道筋が見えていた。 リストラの非難をかぶって、誹謗中傷されても、折れない強さがあった。ハードボイルドな、経営者だった。 (木戸さんは、頭が良くてほぼすべてを見通せていたのでしょうが、評論家タイプだったようですね。) (ちなみに面白かったのは、大久保、木戸は、始めから、[やがては選挙、憲法、議会。ある程度の民主主義が必須だ」と、思っていたんですね。「ただ、まだ早い」と。) # そして結局、西郷さんという、「武士的、男性的、人望を肉体にしたような男性」は、不満武士の暴発に担がれて、大将になってしまいます。 確かに、この前後の史実に残っている西郷さんの言動を見ていると、もうなにか、悟ったかのような、無抵抗な「おまかせ」で生きています。 そして、明治政府の軍隊、大久保政府に敗北して死ぬことで、「武士の時代の終り=明治維新の完成」の立役者になるんですね。 # この西郷と大久保、というのが、結局はほぼ同じ村、同じ町内から出てきた、同じような下級武士。 少年時代からの親友同士。 ふたりで、唯一無二の「相棒」として、薩摩藩で頭角を現して。 京都に、江戸に登り、時世に身を投じ、白刃の下をくぐり、陰謀と密談と度胸比べを生き残って、「新しい日本」の幕を切って落としたんです。 そんなふたりが、ふたりして生き残ってしまった。 そんなふたりが、互いに、日本を二分する巨大勢力の主として、戦争を戦う。 近代以降の日本で最大規模の内戦の、両首領となるんです。 うーん。これはもう、ドラマですね。 「マイク&ニッキー」。 「インファナル・アフェア」。 うーん。もっとスケールがデカい。 日本史ってすばらしい。 # 全体に随想風な部分も多いです。 更には、時系列を行ったり来たりしながら、明治維新とは、明治の国作りとは、という風景を、編み物を編んでいくように見せてくれます。 面白いことこの上ないんですが、やはり、司馬さんの幕末モノをある程度読んでからぢゃないと、多分、根気が続かずに挫折すること、請け合いです(笑)。 実は僕自身、今回が恐らく30年ぶりくらいの再読になるんですが、10代の頃に読んだ初回は、恐らくあまり面白いと思えずに、意地で読み切った気がします...。 「燃えよ剣」あたりからは入って。 「竜馬がゆく」を愉しんで。 「世に棲む日々」で長州っていう風景を知って。 「花神」で大村益次郎と共に、明治2年まで生きて。 それから「翔ぶが如く」。 が、良いような気がしました。 そして、万が一(?)、無事に「翔ぶが如く」を完読して、かつ楽しめたら。 冷めないうちに「坂の上の雲」に進む。 というのが、「翔ぶが如く」の(そして「坂の上の雲」の)正しい味わい方な気がします...。
0投稿日: 2017.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ平成29年4月 司馬遼太郎の本が好きなので、読み始めた。 江戸の時代が終わり、次の時代が始まろうとしている変革期のお話。 作るって大変だよね。 江戸幕府を倒して、じゃあ、って言ってもね。 みんなもっている考え方が違うんですもの。 西郷と大久保と木戸と・・・。さてさて、ここからどうなるのでしょう。
0投稿日: 2017.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2017年1冊目の読書はこれまでに読んだことのない司馬遼太郎さんの小説。読んだ感想は、司馬さんの西郷隆盛、大久保利通、川路利良の人と成りを考察したものを本にしたものという感じ。過去大河ドラマにもなり、もう少し物語性のあるものを期待していたので、読んでみてその点は期待外れの感が強い。それでも歴史の授業程度にしか知識のない所なので、文章は難しくても興味深く読むことができた。西郷隆盛の人物像がこれまでのイメージとは違い意外な感じがした。引き続き読んでいくかはまだ考え中。感想はこんなところです。
0投稿日: 2017.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ龍馬がゆく、燃えよ剣、世に棲む日々、と幕末を描いた司馬作品は多いけど、これは明治維新後の話。坂ノ上の雲に繋がる作品。重い固い話なんだけどこの作品だけ残ってたから頑張って読もう。
3投稿日: 2016.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ鹿児島に行って西郷隆盛さんに興味がわいたので読み始めました。 明治維新が成り、明治政府が混乱のなか実際イマイチな政権として一部にだけ極端な政策を推し進め、海外視察を行っている間に留守政府の間で征韓論が勃発し始めたところから、これまでの経緯を簡単に説明しながら物語が始まったところです。 鹿児島で感じたのは、西郷さん人気はあっても大久保さん人気はそれほどなさそうってこと。 それと、島津斉彬さん人気はあっても久光さんには低体温な反応だったことです。 また、この本を読んで、日本が韓国を押さえようとしたのは、多分に欧米列強の植民地政策と中国のヘナチョコぶりが大きく影響していたのだな…という対外的な部分が1つ。 そして、明治政府がしょせん抽象的な大局を論じて具体策を持たない下級武士あがりの寄せ集めで、小さな枠内で自分たちだけがエラそうにしていて、何百万という旧士族階級から身分だけを奪って無策に放置していたことから生じる大きな社会的不満に対して、彼らに何か目的を与える必要があると西郷さんは感じていた…という説明に「へぇ~!」って思いました。 実際、何もかも新しくしようとする新政府の政策にはお金がかかるし、結局そのお金は自分たちが貿易で稼ぐとかじゃなくて、農民さんや商人さんたちから搾り取るしかないので、幕府が倒れても民衆の生活は良くならないどころか、場合によっては余計メンドウになっただけだったんだろうね。 なんだか、明治政府の流れをくむ今の政府が「明治の日」を作るとか言いだしているけれど、笑止千万ってところだよなぁ~。
0投稿日: 2016.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016年最初は、司馬作品の大作、「翔ぶが如く」(全10巻)に挑戦。明治維新直後の新政府の動きを西郷隆盛(知ってことがこんなに少ないとは、、、と読み始めて思ってます)を中心に、西南戦争まで(まだ読み終わってないし、歴史知らねーなーと痛感)を描く大作のようだ。。。まだ1巻、しかもぽんぽん読めない(泣)2016/1読了。
1投稿日: 2016.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ大久保は書類から目を離し、川路には顔を向けず、紙障子の一点を黙然と見続けた。物を考えるときには、眼前の人間を黙殺できた。
0投稿日: 2016.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ新しい日本を夢見て、大きなエネルギーを見事なまでの瞬発力で維新を成功させた我が国日本。 生きるべき時代を生きた英傑たちが、維新を成し遂げた後の覚束ない情勢の中で何を思い、どうしていったのだろうか。 「日本の防衛と欧米の列強国に肩を並べるべし」という思想の中で内包された維新後のエネルギーはどこへ向かっていったのだろう。 やはり、司馬遼太郎さんの長編歴史小説はとても楽しい。
0投稿日: 2015.10.07司馬史観ファン向けかなと。
明治維新の登場人物が出てくる面白さ。歴史上誰でも知っている人物像の描写の面白さ。1巻だけではまだ物足りないが然りとて更なる欲求も其れ程でも無かったです。吉田松陰がもっと出るといいな。
0投稿日: 2015.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語半分、解説半分といった内容。 倒幕後の薩長土肥が新政府を作り上げいく話。 新政府の役人がヨーロッパで学び、それを新しい日本に活かそうとしているなか、留守番組である西郷隆盛が征韓論を唱え始め、事態は緊迫していく。 西郷隆盛の性格や考え方の解説が多く出てきている。
0投稿日: 2015.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
征韓論をめぐる歴史小説。日本は警察を作るため、汽車の窓からウンコを投げ捨てた。 もちろんウンコは保線夫に命中した。 西郷隆盛を知りたくて読み始める。ところが、彼を中心にその周囲の一人一人のことが詳しく語られている。幕末・維新は竜馬や西郷とかがインパクト強すぎるけれど、大久保利通がじつは一番重要なキャラなのではないかと思う。次のターゲットが決まった。 ______ p45 ジョゼフ=フーシェ ナポレオンのもとフランスの警察組織を創設した男。川路利良の最も尊敬する男。カメレオンのようにその主義思想を変幻し、穏健共和派だったところからルイ16世処刑に賛成し革命を支持し、革命後ロベスピエールと対立しナポレオンの政権奪取に貢献した。ナポレオン没落後は王政復古に加担したが、ルイ16世の処刑で王殺しの悪名がついており、のちに失脚した。権謀術数に優れた男である。興味深い。 p58 失敗しないことが大事 明治の新政府に対して外国人顧問はしきりに「権限は一人に帰するべき」と進言している。しかし、旧幕藩体制の名残で、権限を分散させることが依然として大事とされた。例えば奉行が必ず二人置かれて、合議制のもとあらゆる物事が決断された。それにより極端な行政はほとんどなくなり、変化は乏しいが失敗の少ない保守的な体制になっていた。 これが明治新政府にも色濃く残っていた。この江戸時代と同じような慣習の残った描写が作品中によく出る。そういう時代だったということ。明治は表面では劇的変化だが、内面では変われないでいた。 p69 誰の国家か 当時の固まっていない行政府組織において、内務省を抑えたものが実質、政権を掌握できた。内務省には警察の権限が含まれ、自分の思惑に沿わない者は公然と取り締まれたのである。川路は警察の長として大久保利通につくか江藤新平につくか迷った。それはどちらについても、内務権限を持って反対を排除するだろうからである。慎重になる必要があった。大久保国家か江藤国家か、日本のいく末が川路の肩に圧し掛かったのである。 p75 大久保は怖い 西郷隆盛は人情味厚く、おおらかな態度で人の話に傾聴する。話に行けば喜んで迎え入れ、質問にも優しく答え、話し相手に春風の吹いたかのような心持にさせる。 対して、大久保利通はこわばった顔で何も言わず、相手を威嚇するかのような威厳を以て対した。話し手は緊張し、言葉を選ぶようになり言いたいことも言えなくなる。 そういう人物だった。 p110 征韓論 西欧列強の植民活動のやり方。①独立を謳って対象国の内戦・紛争の火種に火をつけます。②武力や資本を提供して傀儡政権を作ります。③独立後、傀儡政権を骨抜きにして植民地にします。 征韓論はアジア極東の地で西欧列強進出の機会を与えるに等しい行為であった。だから反対意見が多かったが、それでも征韓論派が出た。まだまだ感情が強い時代だったのだ。 p118 西郷の犬「寅」と「ツン」 西郷は犬好きであった。京都では寅という蘭犬を飼い、犬好きで粋な人物という評が起った。またツンという薩摩犬も飼い、上野公園の銅像もツンであろうと言われた。が、銅像のモデルは薩摩藩の仁礼景範の愛犬が使われたということである。でもツンに似ているらしい。ww p130 日本の外交における呪術性 大陸国における外交は国家利害に尽きる。利害を求めて国家一丸になる。しかし、日本の外交問題には内政の不和がつきまとう。それは離島国家ゆえに発症する、外国に触れることへのアレルギーのようである。司馬氏はこれを外交に働く悪霊的な呪術力と比喩する。 明治維新では鎖国・開国を巡っていたらいつの間にか国の利害を超えて徳川政権をめぐる話になった。日米安保の時も外交問題の利害を超えて思想的爆発がおきた。 これが日本人の特徴でもある。外交に関する考えは利害だけに収まらない、これを冷静に自分に投影してみるべきだね。外交問題を考える時、背後にお化けがいないだろうか。 この作品の征韓論でもお化けが出ているのである。 p133 日本人による朝鮮人への不理解 朝鮮人にとって昔から日本は野蛮人で儒教の教養のない後進国であると思っていた。そんな国が1592の壬申丁酉の倭乱で秀吉に攻め込まれると甚大な被害をこうむった。秀吉にとって朝鮮はただの外国で、中華思想なんて予備知識は対して持っていなかった。ゆえに攻め落とし配下に加えて打倒明帝国の案内役にすればいいと思っていた。しかし朝鮮は儒教国家で、宗主国の明に助けを求め抗い続けた。結果、秀吉も朝鮮も明も被害だけが甚大で得をするものがなかった。この時から朝鮮の日本への恨みが決定的になった。 その後の日本は朝鮮を理解するようになったかというと、そうはならなかった。征韓論の時代もただの外国としか見れないものが多多いた。そのため儒教国の朝鮮に日本のように開国するよう進言したり、大きなお世話をしたのである。それを聞き入れられず、独善的な論調で征韓論を推し進めようとする血の気の多いものがいたのである。 p161 西郷の征韓論 温和な征韓論。軍事行動はダメ。特命全権大使を派遣して、懇切丁寧に朝鮮と話し合う。それでも聞き入れてもらえなければ、世界にその儀を証明してから実力行使に出る。朝鮮との交渉に際しても一切丸腰で臨み、命がけで交渉にあたる。その危険な役目を西郷自身が買って出ていた。 ちなみに最も過激だったのは板垣退助である。 p166 銭勘定 大隈重信が土佐藩出身ながら身を立てたのは銭勘定が得意だったから。薩長の志士あがりの人材は思想をもっていても銭勘定が苦手だった。特に国家財政は新しい近代国家のしくみのものなので、特殊なセンスを要した。近代化とはそういう困難もあるのである。 大隈は才略機鋒を誇りとし、秀才偏重主義のある土佐藩らしい優秀な人材だった。 p190 大久保はずるい 明治維新は薩摩藩の金で成された。藩主島津久光は新たな征夷大将軍になれると思って戊辰戦争に加担した。滑稽。その久光を謀ったのが大久保利通である。西郷は久光に嫌われた。真っ直ぐに保守的藩主に向かったからである。維新後、久光は西郷と大久保を世界の二大悪党と罵った。 廃藩置県によって不満に満ちた士族の鬱積は、西郷に向けられた。その頃大久保は外国視察に出ていたのである。権謀術数に長けたマキャベリズムである。 p193 革命というのは 革命というのは光と影である。既得権益者が涙を呑んで、革命勢力がその利を新たに貪る。正義のオブラートで包んでも、弱肉強食の野蛮さがある。 西郷は革命の成功者にありながら利益にありつくこうとせず、敗者の救済を望んだ変人であるといえる。彼は没落した武士階級の不満を受け止め、外征によってそれを晴らそうと考えた。そこを死に場所と決めたのだ。 彼は自分のおこした革命を愛し、自分の倒した者に憐憫した。「巨大な感情量」という言葉、司馬氏は頑張って生み出したのかな。感情の、量って、なに!? p197 堯舜の世 中国神話の名君主。太平の世を作ったとされる。 p202 独裁 西郷は独裁者にならなかった。それは西郷が江戸時代の人間であるからだと司馬先生は言う。江戸時代は合議制のもと、権力が一つに集中することをしなかった。独裁者を作らないことを良しとする風があった。 大陸国の革命後には独裁者的な頭首が出る。しかし日本の明治維新は天皇を奉じたものの、明確な独裁者はいない。そういうお国柄なのである。 p221 魑魅魍魎 魑とは山の神で虎の化身、魅とは沢の神で猪の化身である。征韓論を唱える幕末志士の急進派は、慎重派にとって合理性を理解できない魑魅魍魎のようなものだったろう。 _____ ウンコみたいな小説だ。いや、ウンコの小説だ。いや、いや、下痢の小説なのだろうか。。。
0投稿日: 2014.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新の中で活躍する西郷隆盛らの話。司馬氏の調査に基づいた物語が好きだったが、本作は調査報告的文体なので少々読みづらい。司馬初心者にはお勧めでは無いかも。 しかし、やはり明治維新の背景の話を興味深く書いており読ませる。 【興味深い】 明治維新は言うまでもなく薩摩藩の力でできた。 西郷隆盛、日本の警察と陸軍(廃藩置県で混乱が起こると予想していたので、集めた三藩の官軍が元)を作る。 西郷は、征韓論の渦を巻き起こした張本人として見られており、事実西郷がいなければこれほどの騒ぎにならなかったににちがいない。が、部下の将校がいきまいており、西郷自信は暴走を押さえているつもりであった。 韓国:李氏が王朝をひらくとき、明国に乞うて国号を「朝鮮」と決めてもらった。
0投稿日: 2014.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログイライライライラしながらやっと読み終わった。 後半、西郷さん何考えてたんだろう。 てか取巻きの無意味な縦社会というか脳みそ使わなさは異常。 というのはかなり前に読み終わった記憶の残り。 大久保は良かったような気がするが、西郷さんと最終的にコミュニケートできてないし。 と、全て読んでから川路イントロを思い出してまぁいいや寝ようと思う。
0投稿日: 2014.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ思うところあり読み返すことにした。 最も司馬遼太郎らしい小説と言えるのではないか。 史伝(当時の噂話を含む)、評論、小説が入り混じっていて、その境界が分からない。 配分も絶妙。 その効果でノンフィクションを読んでいる感覚に陥る。 近代国家に生まれ変わろうとする日本。 明治元年から明治10年にかけての日本に何が起きたのか? 西郷隆盛は、何故、死ななければならなかったのか?
0投稿日: 2014.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新後、新生日本のを造り上げゆく偉人たちについて。 この時代は日本史の中でも指折りの激動な時代だったのだと改めて感じさせられた。
0投稿日: 2014.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の歴史の中でも、激動の時代としてはやはり幕末から明治初期と言えるのではないだろうか。稀代の名士が生まれては消え、それぞれが激しく燃える競うようなそんな感じがする。現代のだらけた経済社会しか知らない自分たちには、この様な時があったことが奇跡のように思える。しかし日本人は昔からこうなのだ。今後も日本人としての矜持をもって生きて行かねばと思わせる作品である。
0投稿日: 2014.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ再び司馬遼太郎作品を歩み出した。今年になって「功名が辻」全4巻、「最後の伊賀者」しか読了していないので、少ない方である。 さて、本作品を手に取ってみるきっかけとなったのは、8月に全50話観終えた「篤姫」の影響。主人公の篤姫、小松帯刀、西郷隆盛、大久保利通、島津斉彬など主要人物の多くを占めていたのが薩摩藩関係者であり、このつながりでもっと薩摩藩を知るべくチャレンジしてみたのだ。チャレンジという表現を使ったのは、本作品は全10巻もある「坂の上の雲」並の大作であり、更には後半には西南戦争の戦記が長々と綴られていて軍事マニアではない私にとっては戦々恐々だからである。 本作品はご存知1990年放映の大河ドラマ原作であり、全話鑑賞済み。私にとっては初めての幕末ものだったが、結構楽しんで観ていた記憶がある。 で、この原作は…。 大河ドラマとは全然違う。というよりも、大河ドラマの前半、つまり幕末については回想程度に触れられているに留まり、明治維新からのスタートなのだ。よって、西郷隆盛と大久保利通が主役級であるのは変わらないとしても、征韓論をテーマとした政治学的小説なのである。そして、西郷隆盛下野、西南戦争と続いて終わるらしい。これで全10巻とは長い。が、意外にも1巻はスラスラ読めた。時代背景や登場人物のバックボーンなどをある程度理解しているからだろうが、何よりも司馬遼太郎の描き方が巧妙なのだ。単なる人物紹介でも、ついつい引き込まれて読み入ってしまう。登場人物は新政府幹部から幕末藩士までかなりの数であるが、今のところ、西郷隆盛、大久保利通、桐野利秋、川路利良の4人の薩摩出身者が柱か。本作品により、政治や外交というものの勉強ができればと期待する。
0投稿日: 2013.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨年、司馬遼太郎の「坂の上の雲 全8巻」を読みました。 坂の上の雲の中ですごく気になったのは、司馬遼太郎が描く薩摩藩型のリーダーシップ。 ネット上での解説を少し転載します。 明治時代も終わりに近づいた頃、ある座談会で、明治の人物論が出た。 ある人が「人間が大きいという点では大山巌が最大だろう」と言ったところ 「いや、同じ薩摩人だが西郷従道の方が5倍は大きかった」と反論する人があり 誰もその意見には反対しなかったという。 ところが、その座で、西郷隆盛を実際に知っている人がいて 「その従道も、兄の隆盛に較べると月の前の星だった」と言ったので、 その場の人々は西郷隆盛という人物の巨大さを想像するのに、気が遠くなる思いがしたという。 西郷従道(つぐみち)は「ウドサァ」である。薩摩藩(鹿児島)の典型的なリーダーの呼ばれ方である。 本来の語意は「大きい人」とでもいうようなものだ。 従って、西郷隆盛などは、肉体的にも雄大で、精神的にも巨人であるという点で、 まさに「ウドサァ」を体現した男であると言えよう。 薩摩藩型リーダー「ウドサァ」の手法は二つある。まずは最も有能な部下を見つけ その者に一切の業務を任せてしまう。 次に、自分自身が賢者であろうと、それを隠して愚者のおおらかさを演出する。阿呆になりきるのだ。 そして、業務を任せた有能な部下を信頼し、自分は部下が仕事をしやすいように場を平らげるだけで、後は黙っている。 万が一部下が失敗するときはさっさと腹を切る覚悟を決める。これがウドサァである。 日本人はこのリーダーシップのスタイルに対してあまり違和感を持っていないと思う。 日本の組織のトップはリーダーというよりは殿様なのだ。殿様は知識やスキルではなく人徳で勝負。 細かいところまで口を出す殿様は 家老に 「殿!ご乱心を!」とたしなめられてしまう。 でも、このリーダーシップのスタイルは世界のスタンダードではないと思う。 世界の卓越したリーダー達で「ウドサァ」みたいなスタイルだった人を私は知らない。 スキピオ、ジュリアスシーザー、アレキサンダー大王 ナポレオン、リンカーン ・・・ ビルゲイツもジョブズも孫正義も 部下に仕事を任せはするが、後は黙っているなんて事は絶対にない。 古代中国の劉邦と劉備は「ウドサァ」かもしれない。(だから日本で人気がある?) 私も大きな組織で働いているが トップに非常に細かいことまで指示される事を想像すると辟易してしまう。 そのくせ、「トップの方針が明確でない」みたいなことを言ってみたりもする。 どないやねん! 1年以上かけて、ようやく全10巻を読破しました。 いや〜〜長かった。 面白かったけど、やっぱり長いよ司馬さん。 「翔ぶが如く」本線のストーリーは、征韓論から西南戦争に至るまでの話なんですが、水滸伝のように、周辺の人物の描写や逸話に入りこんでしまって、本線のストーリーが遅々として進まない。。 新聞小説の連載だからなのかもしれないが、ふだんノンフィクションの実用書ばかり読んでる身としては、かなりじれったかった。 本線のストーリーだけ書けば、半分ぐらいの頁数で済むのでは? と思ってしまいました。 [読んで思ったこと1] 本書を読み「薩摩藩型のリーダーシップ」について理解するという当初の目的は果たせませんでした。 著者にとっても、西郷隆盛という人物は、スケールが大き過ぎて掴みどころのない存在のようでした。特に征韓論以降の西郷隆盛は、現在の我々からは訳がなかなか理解し辛い事が多いです。 しかし、リーダーシップとは何かという事について、いろいろと考える事ができました。昨年一年間かけて考えた、私なりのリーダーシップ論は、後日別のエントリで纏めようと思います。 [読んで思ったこと2] 西南戦争は、西郷隆盛を担いだ薩摩藩の壮士と、山縣有朋が徴兵して編制した政府軍との戦いでした。 当時の薩摩藩は古代のスパルタのような軍事教育国家であったため、壮士達は世界最強の兵士とも言える存在でした。 しかし兵站という考え方がほぼ皆無に近かった。 一方で政府軍の鎮台兵は百姓出身者が大半であり、本当に弱く、戦闘となるとすぐに壊乱してしまう有様でした。 しかし、山縣有朋の綿密な軍政準備により、予備兵・食糧・弾薬などの後方支援が途切れる事は無かった。 両者が激突するとどうなるのか。 短期的には薩摩藩が圧倒的に有利なのですが、戦いが長期的になつてくるとジワリジワリと政府軍が有利になってくる・・・ 古代ローマ帝国とカルタゴのハンニバルの戦いを見るようでした。 いや、普段の仕事についても同じ事かなと思いまして。 仕事でも、短期的に物事をガーと進められる人に注目が集まりますけど、さまざまな兵站をキッチリ意識して、長期的に組織的に物事を動かせる人の方が最終的な結果に結びつくのかなと。 この間、絶好調のアップルの決算発表がありましたが、今のアップルの収益性を支えるサプライチェーンとロジスティクスの仕組みを確立したのは、現アップルCEOのティム・クック氏だとの事。
0投稿日: 2013.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新直後の不安定な時代を描いている。 征韓論から西南戦争にいたる5年間が舞台。 西郷隆盛を始め多数の人物のエピソードと緻密な時代考証にその時代を知る思い。
0投稿日: 2013.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ古本で購入。全10巻。 征韓論争とそれに敗れた政府首脳・軍人らの下野(いわゆる「明治六年政変」)から西南戦争までを描く、司馬遼太郎屈指の長編。 川路利良らの欧州視察行から書き起こされる冒頭が実に象徴的。 後に大警視として日本警察の礎を築くこの薩摩人に対し、ある意味でこの作品の主題とも言うべき言葉を投げかける男が、旧幕臣の沼間守一である。 彼は帰国の途にある船の上で、川路にこのようなことを言う。 「時勢という悍馬には手綱がないのが特徴だ。時勢そのものがくたびれきってしまうまでその暴走をやめない」 「英雄ほど悍馬にのせられる。英雄とは時勢の悍馬の騎乗者のことをいう。西郷という人がそうであった。時勢の悍馬に騎り、270年の徳川幕府をあっというまにうち倒してしまった。幕府は時勢という悍馬に蹴散らされてたのであって、西郷その人に負けたのではない。が世間はそうは思わず、倒幕の大功を西郷に帰せしめた。このため維新後、西郷はとほうもなく巨大な像となり、ただ一個の人格をもって明治政府に拮抗できるという、史上類いない存在になった。 (中略)悍馬は西郷の尻の下だけに居る。この巨人は役目(倒幕)の終わったはずの悍馬なのに、なおも騎りっぱなしになっているのだ。新政府に不満を持つ連中は、ことごとくその騎乗の西郷を仰いで第二の維新を願望する」 これこそ『翔ぶが如く』という作品で作者が描こうとしたテーマのように思える。 明治初期という時代は、「悍馬」に騎った「西郷隆盛」という巨大な虚像を中心に回った時代であった。 時勢という悍馬、そして勇敢無比の薩摩人が、“翔ぶが如く”跳梁した時代だったように感じられる。 作者がこの作品で試みているのは 「西南戦争とは、西郷隆盛とは何であったか」 という問いに対する答え探しなのだろう。 しかし司馬遼太郎をもってしても、結局は「西郷」というものがわからなかった。 賢者であったのか、あるいは愚者であったのか。 下野した西郷の目的・真意は一体どこにあったのか。 非常に茫漠とした存在として読者の前に現れる西郷という人間は、確かに巨大である。 おそらくこの作品を読んだ多数の人が思うことだろうが、これは「小説」とは言い難い。 作者が己の中のテーマの下に書き綴った「エッセイ」と言った方が、実情に近いように感じる。 しかし明治初期の政治を中心とした膨大な情報が詰め込まれているため、読んだ人間が興味に応じてそこから広がりを持たせられるという点で、おもしろいと思う。 前半は少々退屈だが、後半(8巻)以降、西南戦争の記述に入るや俄然おもしろくなる。 そのあたりは司馬遼太郎の面目躍如というところか。
0投稿日: 2013.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ川路利良のパリ行きから話が始まる。 この人と桐野利秋(中村半次郎)を低い身分から取り立てたのが 西郷隆盛 時代は明治で着々と地歩を固める実務派と 廃藩置県などで居場所をなくした武士階級に乗る征韓派 というのがアバウトな構図 6 明治10年まで独立薩摩国 18 示現流、鳥羽伏見で切られた幕府軍は頭蓋骨粉々 58 複数合議制、江戸も明治初期も 65 大久保=内務省、江藤=司法省。犬猿の仲 68 江藤=フランス、大久保=ビスマルク、プロシャ 71 薩摩人、執着力の希薄さ 73 大久保、厳格で怖い。西郷と大違い 75 伊藤、大久保より。木戸はうつ病的評論家、西郷は世評のみ大 76 大久保、度量が広かった、と伊藤 77 大久保党、西郷党、島津久光党。酔ってくだをまく「芋ほり」 79 大久保、行儀の良い囲碁。珍奇なほどに上品 81 大久保、富国強兵のためにのみ人は存在する 83 大久保、即答しないので有名 88 隆盛?従道?新政府に名前届け間違いを放置 93 人斬り半次郎 105 西郷、酒は飲まない 152 中村楼騒動、店壊した 165 大隈、晩年は珍妙な自己肥大漢。外国人を怖がらず日本の利益主張、銭勘定が達者。2つの特性 181 江藤、抜けている薩摩人を利用して切り崩し、長州も 187 廃藩置県、島津久光は激怒 190 天皇が明治5年に薩摩に行って怒りを解くことを狙う 221 壮士・志士上がりの近衛軍(桐野)徴兵制の国防軍鎮台(山県) 229 「朝鮮」国の名前は中国に決めてもらった 237 禅と朱子学、武士の基 248 木戸、山内容堂に「なぜ武市を殺したのか」酒席で聞く 262 木戸の大久保嫌い 272 コメ麦なし肉OKのダイエット、西郷 279 黒田、酒精中毒者。人を尊敬できるのが長所 292 江戸の名物、立小便。見せ付ける 296 単衣、一着しかもたない、西郷。乾くの待つ、遅刻 303 農民、維新にがっくり。租税負担重くなり徴兵 316 島津重豪 342 床の間を枕に寝る薩摩人。畳の上にアタマを載せない
0投稿日: 2013.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ新国家が成立する過程が面白くて一気読みしてしまった。 西郷隆盛と大久保利通。手を取り合って維新を遂げた2人の盟友が、維新後では理念の違いによって袂を別れる運命に歴史の因果を感じてしまう。
0投稿日: 2013.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ警視庁の創設者、川路大警視が出てくる事から手に取った一冊。司馬史観が随所に盛り込まれ、余談は多いが面白い。征韓論の背景として、革命家は自国の革命を輸出したがるものとの分析に納得させられた。フランス革命しかりロシア革命しかり。
0投稿日: 2013.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今まで読んだ筆者の歴史小説とは異なり、物語調でなく、歴史背景を十分に説明したのが本作。序盤は、正直楽しめない部分が少なくなかったが、途中から竜馬や容堂と、薩摩藩の関わりが述べられてい件などがあり、下地の知識があるからか関心を持って読めた。 大久保と西郷がどう役割分担をしながら、国づくりにいそしんでいったのか次巻からの展開に期待。 再読 初読時は、「龍馬がゆく」との違いに面白さを感じずらかった。今回は、学術書数冊から知識を仕入れたこともあり、読みやすかった。 各人考えは違えど、独自の国家観を持ち、日本を築きあげなけてはという思いの強さは同じ。考えの違いから、その人がどんな人かを、筆者は上手く浮かび上がらせている。
0投稿日: 2013.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎をだいたい時代順に読んできたけど、このシリーズでもう終りにしよう。内容も盛り上りに欠けるし。。
0投稿日: 2013.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ西郷隆盛を中心に維新後の人間模様を描く。 合わなければわからない西郷の魅力。 考え方は違っても、それぞれの理想を追求して 維新後の日本を作ろうとしている人たち。 西郷に認められ警視庁をつくる川路、 西郷の懐刀、近衛軍を指揮する桐野 同じ薩摩出身でも考え方がの相違で 対立しながらも認めあう大久保。 それぞれの気概ある人物像が描かれる
0投稿日: 2013.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
学校で習う歴史には色がなかったけれど、司馬遼太郎さんの本で読むと歴史にも色が付く。 西郷隆盛は不思議な人だ。 何か滑稽さをまとっているように感じるが、作中ではそれは悲哀のようなニュアンスとなっているようだ。ピンとこなかったのだが。 この人のどこに魅力・実力があるのか、読み進めて見極めてみたい。
0投稿日: 2013.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初は小説でしたが、途中からノンフィクション的な文章になってきます。 西郷隆盛とは?薩摩隼人とは?明治維新とは?多くの問いが溢れた作品です。ラストの一文がすごく心に残ります。
0投稿日: 2013.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ【本78】シリーズ一作目。内容ももちろんだが、日本の外交に対する性格を鋭く指摘している。今後に期待。
0投稿日: 2012.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1.全体レビュー 歴史小説は初めて読んだが、中学高校の歴史の教科書には書かれていない過去の偉人の人物像・人間関係・各種政策の背景まで触れられており、興味深く読めた。 2.メモ (1)外交問題 本来論理的に遂行されるべき外交問題が内政問題の解決の手段として用いられるという考え。征韓論。士族だったものが平民として急遽扱われるという不満。その不満を解決する手段として朝鮮を制圧するという考え。内政では解決できない不満や問題を外に向ける、そもそも無理があり矛盾や不合理に対する思考停止が発生しやすい状態。 尖閣問題。格差社会に対する不満を持った者を中心にした反日運動。通ずる面がある?国際司法裁判所が下す結論が日本の主張通りにならなかった場合の日本は?大国による支配。 (2)西郷隆盛と橋本大阪市長 維新後の西郷隆盛。異常なまでの質素な服装。このこと自体が普通ではなく反政府的であり、不満分子が担ぎやすい状態。橋本市長。市民の不満を解決してくれそうな存在。橋本人気。
0投稿日: 2012.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ西南戦争までを描いた、西郷隆盛の存在感をありありと見せつけられるような小説。 西郷 対 明治政府という図式が成立するほどの圧倒的な存在感が描かれています。
0投稿日: 2012.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ維新後の話で面白くないことはない。 ただ、「~藩出身者はこういうやつだ」といった、出身地から人の性格などを決めてしまう文言がどうしてもなじめず(時代的や作者的にそうなのかもしれないが)、1巻で挫折。 章の中でも話がすぐそれてあっちこっち飛ぶのも読んでてイライラした。 自分に合わなかっただけだろうと思いたい。
0投稿日: 2012.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎さんの「竜馬がゆく」「燃えよ剣」と並列に読んでいます。 この時代の流れを様々な視点から覗き見ているようで、ひとつひとつが新鮮な感動を覚えます。 西郷隆盛を「感情量の豊かな」と評して、その人物の大きさを表しているのが流石です。
0投稿日: 2012.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
司馬遼太郎の代表作の一つ。明治維新後の日本の近代化を歩む過程が描かれる。 薩摩、長州、土佐、肥前を中心に構成される国家の中心機構と近代化に導いた軍や士族の両面からの視点や思考が面白い。 特に「征韓論」というキーワード一つとっても授業では駆け足で通り過ぎた感があり、いろいろと勉強させられる物語となりそうだ。
0投稿日: 2012.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ老後の楽しみに取っておこうと思ってたけど、つい読みはじめてしまった。司馬遼太郎の文章は文体はもちろん、脱線の仕方まで心地よい。
0投稿日: 2012.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ何年か前、誕生日に父親が全巻送ってくれた時は びっくりしたものですが、全10冊。時間かかった。。。あしかけ、3年はかかったんじゃないでしょうか。9巻くらいはここ数か月で読んでしまったわけですが、とにかく長かった。。。 西南戦争が勃発するのが、8巻。ここに至るまでが8巻で、これからまだまだある、のである。司馬遼太郎さんの歴史への愛情を感じる、細かい描写と、尽きることのない余談。英傑たちの生き生きとした姿に魅せられました。 おそらく、ですが、二度と来ないであろう、この時代への郷愁がにじみ出ていたよう。200数十年の封建社会を打倒する革命を成し遂げ、諸外国に対抗しうる独立国を打ち立てる、という歴史に立ち会うことができた英傑たちへの憧れをして、この大小説を書くに至らしめたに違いない。(司馬風) 当時の人たちは、西郷の姿を見たものはまれであった。彼の姿を知ることなく、戊辰戦争の奇跡的勝利や江戸城の無血開城をして、彼をほとんど神に近いほどの威光を与えしめたのである。しかしながら、彼と向かい合って、その魅力に触れたある士族の述懐。 「一日かの人に接すれば一日の愛生ず。三日かの人に接すれば三日の愛生ず。しかれども予は接するの日をかさね、もはや去るべくもあらず。いまは善悪を超えて、この上はかの人と死生を共にするほかない 」 布団の上で死ぬよりは、戦場で死にたい。今聞けば、冗談みたいな発想を、無邪気に信念として持っていたのが薩摩隼人だった。西郷を担ぎながら、その美学の昇華を願って、従軍した多くの薩摩隼人の純粋で、ひたむきな姿は、時に滑稽で笑えてきます。これがほんの百年前の同じ日本で起きたことだと思うと、感慨深いものがありますね。 近くで、戦闘がおこっていることを聞いた薩摩軍のある小部隊は、とにかく、身近で戦闘がおこっていることへの興奮と、遅れまいという焦りに、、、 「駆けんか。戦さ(ゆっさ)に遅るるぞ。」 と、たがいに声をかけつつ走った。 それも、ほとんど道なき道をとった。あぜ道を駆けたかと思うと、山に登っている。 歴史小説の金字塔ですね。読了。
0投稿日: 2012.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ西郷はあくまでも武士革命者で、町人百姓の次元の低い利己的精神ではかれの考える新国家はできないとおもっていた。むしろ外征をおこしてゆく過程において日本中を武士にすることによってのみこの国を世界のなかに屹立せしめられるとおもっていた。このあたりの西郷の考えは革命的論理性からいえば計算性にとぼしく、多分に夢想的であった。しかし西郷はこの場合冷静な理性よりもゆたかな感情―同情心―でとらえた。 「日本は産業もなにもない。武士のみがある。武士という無私な奉公者を廃止していったいなにがのこるか。外国に誇るべき精神性がなにもないではないか」 とおもった。これをおもった瞬間、すでにこの大革命家は、反革命家に転じていたのだが、それは西郷の知ったことではない。かれは一方では自分のつくった明治政府を愛さざるをえない立場にあり、一方では没落士族への際限ない同情に身をもだえさせなければならない。 矛盾であった。 ビスマルクは大風呂敷をひろげた。 「余は小国にうまれた」 と、ビスマルクはドイツを小国として規定している。 「余が少年のころはプロシアはじつに貧弱な国であった。長じて余は列強の暴慢を知るにおよび、怒りをおぼえた。たとえば国際公法というものがあってもそれは列強の都合で存在するものであり、自国に都合のいいときには国際公法をふりまわし、自国に都合がわるくなると兵力を用いる。小国はじつにあわれである。国際公法の条文懸命に研究し、他国に害をあたえることなく自国の権利を保全しようとするけれども、列強というものは破るときには容赦なく破る」 ビスマルクは、小国であったドイツこそ日本の手本であると言いたいのであろう。 ビスマルクが国際公法の限界について論じたのは、木戸らの随員が、それを質問したからである。坂本の信仰が、志士あがりの連中たちのあいだでなお生きていたといっていい。 「小国がその自主の権利をまもろうとすれば、孜々としてその実力を培う以外にない」と、ビスマルクはいう。 「温公の腹の中には、他人に隠さねばならぬことはひとつもなかったといい申す。ところが顧みて自分を思えばまだまだ他人に話せぬことが多か。このあたりが公に遠く及ばず、温公がもしいまに存さば、自分はよろこんでお供をする」
3投稿日: 2012.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ全巻読みました。とりあえず、大河ドラマとは別物ですねえ。桐野利秋が好きなんですが、司馬さんの桐野描写にはいささか違和感があります。まあ主役ではないから仕方ないのですが。軍人としての桐野だけではなく、農人としての桐野にスポットの当たった作品も読みたいです。あと、余話多いです。それも味ですかねえ。
0投稿日: 2011.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ10巻まで読了済み。小説というよりは教科書っぽい感じ。近代国家と前近代が交じる明治初期の偉人たちの思いの交錯。
0投稿日: 2011.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔やってた大河ドラマのように、西郷さんの伝記物かと思っていたら、維新後の征韓論から西南戦争の話だった。 読むのに時間かかるけど、頑張って読破します。
0投稿日: 2011.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治という近代から現代への過渡期の話。時代を動かす英傑が沢山いる。 明治維新を終え、一気に現代へひた走る日本の状況が良く分かる小説だ。
0投稿日: 2011.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新が革命であったのだと認識を新たにする。政権を天皇に戻す大政奉還を果たした西郷どんは革命家なのだ。ならばなぜ、チェ・ゲバラのようなTシャツが売られていない。毛沢東語録本のようなものが売られていない。人の国のことよりはまず、自国の革命家をよく知るべきなのだ。義務教育で、そこのところを詳しく教えるべきなのである。 ちなみに、西郷どんの顔がプリントしたTシャツを着て歩くには勇気がいる。西郷語録本はジュンク堂に行けば手に入るのかもしれない。10巻完読したら探してみたくなるのかな。
0投稿日: 2011.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ1?5巻読了。西郷下野、私学校、台湾出兵あたりまで。西郷隆盛という人間像を描き出すために、彼の周囲の人物、出来事を深く掘り下げている。印刷したい面の周囲を掘る版画のような描き方が非常に新鮮だった!
0投稿日: 2011.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
8巻までぐらいは人物紹介などがほとんどで痛快さを感じないが、明治維新から日清・日露戦争前までの歴史観を埋める意味では読んでおく必要があり、西南戦争やその他の士族の変や乱がなぜ起こったのか再認識させられた。熊本城、田原坂の戦役は地元出身者には位置関係が把握でき、激戦の様子が手に取るように伝わってくる。 歴史の表舞台にあまり登場しない熊本協同隊(宮崎八郎)の奮戦が描かれており興味深い。 西南の役最後の激戦の地、城山には翔ぶが如くを手に、何度か足を運んだことがあるが、桜島が目前にあり雄大でいつも勇気をもらう。そして西郷隆盛も最後にこの桜島を目にしたのかと思うと時代の流れを感じると同時に、先人たちの残した軌跡の上に今の平和な時代があることを痛感させられる。 最後に司馬先生が4年数か月をかけて執筆された翔ぶが如くを史跡を訪ねながら読ませていただきましたが、最後まで西郷隆盛という人物のことが分かりませんでした。
0投稿日: 2011.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ【MM198 mylibrary マイライブラリ・アウォード!2007 2008/1/30】 【第8位】『翔ぶが如く(1)~(10)』(司馬遼太郎著、文芸春秋、1975年) http://tinyurl.com/3dt4ry (コメント)大河ドラマにもなった司馬遼太郎の長編歴史小説の代表作。メインテーマは征韓論と西南戦争ですが、明治政府の誕生後の苦悩など、官僚制度の出発点なども随所に紹介されています。昨年『竜馬がゆく』を読んで以来、幕末・維新ものにどっぷり浸かってしまいました。昨年読んだものは、この『竜馬がゆく』以外のこれらの作品です。 参考:『竜馬がゆく』http://tinyurl.com/y66dce →マイライブラリ・アウォード!2006【第1位】 『最後の将軍-徳川慶喜』http://tinyurl.com/2494yp 『吉田松陰』http://tinyurl.com/2ylvz4 『燃えよ剣』http://tinyurl.com/ys8dm5 『世に棲む日日』http://tinyurl.com/2bk6v7 『花神』http://tinyurl.com/253xnc
1投稿日: 2011.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
竜馬がゆくを完読し、西郷隆盛にすごく興味をもちこの本を購入。読んでゆくうちに、この話西郷・大久保がほとんど出てこないなとおもいつつ先に進むと、いきなり征韓論をめぐって西郷vs大久保攻防戦で、西郷隆盛のダメさぶり発揮。敬天愛人という考え方で、尊敬する人が多いこの人は、明治維新後はすっかり世捨て人になってしまっていて、たんなる革命家だったということでがっかりです。この先読もうかどうか悩んでいます。
0投稿日: 2011.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ【69/150】以前読んだのだが、途中で挫折した本。そのときはちょっと分かりづらく感じたのだが、今回読むとそうでもない。 他の司馬作品をいろいろ読んできたからかなぁ〜。でもこのシリーズはまだまだ長い。
0投稿日: 2011.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ長い! 途中まですらすらと快調だったが、司馬さん特有の細かい人物描写、戦闘場面の地理の不理解から9巻でばったり止まってしまい積読。結局足掛け数年。ようやく読了。感想を書く段になって最初の方の良い場面を忘れてしまった。情けない!ともに幕末を戦い、明治政府の立役者だった大久保と西郷、朋友でありながら、意見の相違から対立、敵対。無念ながら西郷を討ち、同時に大久保も暗殺される。実にドラマチック。大物はどんどん消え去っていく。幕末から維新、征韓征台、日清日露戦争と国際社会へのデビューがなぜかねじれていく。外国との戦争は時期早といいつつ、戦争に突き進んでいく矛盾。この流れはとめる事のできない必然?昭和の2つの大戦に通じる歴史を検証するためにも明治を知る必要があると思った。
0投稿日: 2011.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ幕末の物語は多いが、維新後から西南戦争までの西郷、大久保を中心とする物語。明治の近代化はこの後始まると言ってもよい。
0投稿日: 2011.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったけど長かった、、、。戊辰戦争後~西南戦争までの話で、こんなに不安定な時代だったのは知らなくて勉強になりました。川路、西郷、大久保等々の偉大さに比べ、当時の偉人でも人によってはあっさりと小物扱いされるのが司馬遼太郎らしいですね。
0投稿日: 2011.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎がはじめに「うかつに薩摩のことは書けない」と書いているが、うかつに薩摩のことは読めないという実感である。 それはは薩摩弁がたびたび登場するが、内容を理解しにくいのである。 しかしいろいろな人物の描写がかかれていて、読んでいて面白く、ときには吹き出して笑う箇所もある。とにかく司馬遼太郎を信じ、前進あるのみである。
0投稿日: 2011.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ川路利良が仏蘭西の列車の中でうんこを我慢しているところから始まるので、たまげる。司馬遼太郎幕末明治講談の一篇。作者による解説、人物評の開陳が多くて、なかなか話が先に進まない。
0投稿日: 2011.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎の本で一番好きかも。 西郷隆盛という人間が俯瞰して書かれている(と思われる)点がいい。小説にありがちの架空の人間関係があまり登場しないのもいい。
0投稿日: 2010.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかく大久保卿が好きすぎて、読んだのはだいぶ前ですが本棚に入れておきたくて、代表で一巻を登録。佐賀の乱における野津少将も好きです。野津さんは兄弟でいい味だしている。
0投稿日: 2010.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ全10巻。 10年くらい読むのを抵抗してた。 司馬先生が嫌いで。 ついに。 まあ。 逆に一番良かった。 過去に読んだ司馬先生の中で。 自分が司馬遼を嫌いな一番の理由は、 物語をほっぽって本人が出しゃばって来るとこ。 こっちは物語に入っていきたいのに、 その都度現実に引き戻される。 小説としての物語が面白いだけに腹が立つ。 すごい騙された気分になる。 そんなにしゃべりたいなら物語なんて書かないで 学者みたいな論文を発表しろとずっと思ってた。 で。 これが一番良かったのは物語性が薄いとこ。 最初っからずっと筆者がしゃべってる。 中途半端に物語が入ってこないだけ そういう物として読めた。 あいかわらずこうるさいし、 閑談休話が多く、 とても好きにはなれないけれど、 そういう物として読んでるからそんなにイラッとはしない。 個人的に知りたかった西南戦争への経緯なども 今までで一番しっかり勉強させてもらったと思う。 また、時代が近い上に、史実に基づいて真摯に書かれているため、 自分はどうかという、やらねばという気持ちが、 焦燥とともに、すごくリアルに蓄積していった。 つくづく凄い時代、凄い人達だと思う。 前述したように、 やはり自分は司馬先生のこうるささは嫌いだ。 鬱陶しいし話も見失う。 でも今回は初めからその顔つきしてたから 騙された感は無い。
0投稿日: 2010.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「竜馬がゆく」読了後の次の司馬作品はこれを選びました。 第1巻は西南戦争と征韓論の原因の分析です。今のところ、面白いです!でも時代順的に「歳月」を先に読んでしまおうか悩み中。
0投稿日: 2010.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ・2/2 2月に入ったからとか智の学校が始まったからというわけではないが、いよいよ全十巻の本作に挑むことにした.司馬遼太郎は久し振りだ.ほんだらけで高橋克彦の「時宗」全四冊セットを買ったせいもあるのかも.戦国時代以前を選ばなかったのは、特に最近明治時代の雰囲気に飢えているからかもしれない. ・2/7 読了.
0投稿日: 2010.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ全10巻中の第1巻。 ということで、話の導入部です。 明治になったばかりの日本。 江戸幕府とは違う、日本という国家をつくる幕末の壮士たち。 ちょっと、政治的な話とかが入ってくるので 幕末ものよりと比べると、動くことよりも考えること。壊すことより、興すこと。といった印象を受けました。 まだまだ、先が見えてこないので、感想はあまり書けないのでこの辺で。
0投稿日: 2010.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ全10巻。いやー長い。そして読みにくさを感じた。説明多いしね。 でも読み終えた後の達成感は半端ない。 しばらく10巻並べて悦にしたってた。 内容も歴史が動く時は凄く面白かった。 そこだけ読むスピード3倍くらいなったし。 大久保さんが死ぬときは・・・目頭が熱くなりました。
0投稿日: 2010.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新から、たぶん西南戦争あたりまで。 西郷さァと、その周りの人々。 学生時代に勉強してきた歴史、 いつも良い人、悪い人、 いい事、悪い事 を決めつけてきた。 そんな簡単じゃない事を思い知らされる。 そして、文句なしに面白い。 冒頭の川路さんのエピソードに驚きつつ、 これからの長い長~いオハナシを、 じっくり楽しもうと思う。 ほんとに楽しみ。
0投稿日: 2010.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬さんの得意領域、幕末シリーズの薩摩論の1冊。 幕末の司馬作品は総じて評価が高いが、 本作品は評価が二分することが多い。 (西南戦争までが長い、などの理由) ただ、西南戦争前は徹底して 「西郷隆盛」という男の矛盾性というか 2重人格性をよく語っており、 「ごわす、ごわす」だけのイメージの 西郷隆盛の核心に迫っているのは 非常に興味深いところです。 恐らく推測ですが、司馬さんは最後まで 西郷という人物のことがよく分からなかったのだと思います。 革命家としての理性要素、 そして人を愛し最終的に自分の命を落とすまでに至った、 感情が横溢する矛盾性を最後まで整理しきれなかったのではないかと 思うのです。 (司馬さんは竜馬のような単純明快、突進系が好きですので) だた、この矛盾こそが西郷そのものだと、私は思っていますが。
0投稿日: 2010.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューの必要を待たない雄大緻密な名作。大河ドラマをのみ知っていたのでクロニクルで無い構成が意外だったが魔法のような巧みさで核心へと着実に迫って行く。 強烈な印象を残した箇所が2つ。 一つは西郷の師父ともいえる斉彬評。「龍馬がゆく」に於ける勝海舟評と同じく、この人の下で働いてみたい、と夢想してしまう。 もう一つが巻末。 川路利良が妻沢子に思いつくまま単漢字を羅列させその中から西郷に相応しい字を選ばせるというシーン。重厚緻密なドキュメンタリイの為油断してしまったが不意打ちのような情感にやられてしまった。
0投稿日: 2010.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ川路利良の初めの印象があまりに強烈で、そのイメージが脳裏に焼きついたまま一冊があっという間に終わってしまったという感じ。とても大警視という印象は感じなかった。
0投稿日: 2010.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ全十巻。初期の司馬作品と比べると娯楽要素が少なく(資料の引用、解説が多く少々堅苦しいかんじです。)時系列が前後することもあり、当時の歴史に興味があるとか人物に思い入れがあるとかで予備知識がないと全巻読むのはつらいかもしれません。入門編には向きませんが中級編くらいには持ってこいだと思います。薩摩、明治初期、幕末をお好きな方にはお勧めです。
0投稿日: 2010.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ西郷さんと大久保さんがどういう間柄であったのか、という事をこの本を読んで知りました。 こんな関係の二人は歴史上を見ても他に見つからないんじゃないか、と作中にありましたが本当にそう思いました。 他の本の中で、司馬先生が「西郷さんという人物は捉え難い」という様なことを書いていらっしゃいましたが、 たしかに手探りな感じがして、他の司馬先生の作品とはどこか作風が違うなぁという印象を受けました。 それでも丁寧に描かれていて、最後まで無理なく読めました。 この本を元にして描かれた大河ドラマも素晴らしい作品です。
0投稿日: 2010.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「竜馬がゆく」の感動覚めやらぬまま、明治維新後の日本の行方が知りたくて読み始めました。私としては竜馬にぞっこん惚れた後では西郷隆盛には感情移入はしにくいのですが、巻一を読み終わった段階でしっかり最後まで司馬遼太郎に再びつきあってみようと想いました。楽しみが募るばかりです。
0投稿日: 2010.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治維新の立役者となった西郷と大久保、そして彼らを取り巻く人物像を通し、征韓論から西南戦争終結までの激動の時代を描いている。 西郷隆盛の愛国者精神に乾杯。きっと西郷はサムライ精神を捨て切れない士族たちに最後の戦いの場を与え、せめて武士として死なせることが自分の生涯の仕事としたのだろうと思った。
0投稿日: 2010.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこれって小説? まるでその場に居合わせていたような描写はさすが司馬小説!歴史上の偉人達が身近に感じられます。 しかし、これは出来事が時系列に沿って進行するのではなくエピソードがいったり来たりするし、主人公がアレコレと動いていくのであんまり小説っぽくない。ので、燃えよ~やら龍馬~やらに比べると少々読みにくい感じが…。 小説ではなくて、エッセイとか司馬氏西南戦争を語る…的なものだと思えば大変面白い。 そういう風に思うのはまだ1巻だからだろうか。 1巻は一部官僚達が洋行を終えてきて…西南戦争前夜・征韓論論争の状況から。創成期の混乱が面白い。 様々な人物が語られるけど、それはどれも結局は西郷隆盛を語るための布石なのかな?西郷さん一回見てみたいわ~。 タイトルの意味に期待しながら以下読んでいきたい。 ちなみに、私が持ってるのも文春文庫だけど表紙違う…これ、一刷は80年!まだ私生まれてないし!読み継がれる名作ですね。
0投稿日: 2009.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ西南戦争(西郷隆盛)の話。問題作。7巻くらいまで非常に辛い。もう2度と読みたくない。でもラスト3冊の展開は圧巻。
0投稿日: 2009.11.09
