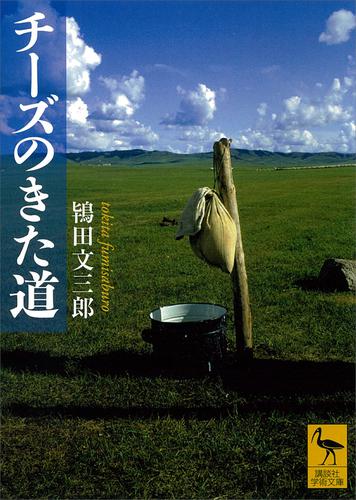
総合評価
(6件)| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://opac.lib.hiroshima-u.ac.jp/webopac/BB01905685||西・小型2階||648.18/To-33
0投稿日: 2025.06.23文明論がかえってうるさい
世界各国の素直なチーズに関する沿革や解説の部分はなかなか良かったが、中盤以降の世界史通史や文明論の部分は、半世紀前の通説が基になっているせいか、かえってうるさく感じてしまった。もっともっと食品科学的な記述や、世界の民俗的な記述を期待したのだが、十分に書かれていなかったのが残念である。
0投稿日: 2023.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2010年(底本1977年)刊。著者は信州大学名誉教授・農学博士。 モンスーン気候下にある地域では、牛・羊・山羊等の産出乳を利用した製品は定着せず、乾燥・牧草地で花開いたのだ。こういうステレオタイプ的思考を本書は排し、チーズを軸に乳製品利用の淵源から拡大への模様を解読していく。 生化学研究者・農学博士が、自ら専門とするチーズの、全く専門外の歴史的展開を叙述するのが珍しいはずだ。 西北アジア→欧州各地、西南アジア・アフリカ方面、印度→東・東南アジアと巡っていくが、欧州での適応放散的なチーズの多様性には吃驚させられる。 ところで、底本は古い。それゆえ、現代の理解と違う点も多いらしい。が、先駆的書ということで修正していないとのこと。
0投稿日: 2017.01.01いかんせん古い
電子版底本の講談社学術文庫版は2010年の出版ですが、大本の河出書房版は1977年とのことで、本書のそこかしこに時代を感じます。チーズといえば雪印のプロセスチーズだった初版当時と比べ、現在ではちょっと気の利いたスーパーに行けば10や20は簡単に超える種類のチーズが手に入るわけで、文字通り隔世の感があります。粉チーズのパルメザンと「チーズの王様」パルミジャーノ・レッジャーノを一括りで扱いながらチーズ本を名乗るなど現在ではとても許されないでしょう。 チーズの歴史を扱った本として見ても、根拠のない著者独自の説と文明論が前に出すぎていて、現在の水準からするとそのまま採用することはできないという印象です。まだ日本人がチーズに馴染みのなかった当時だからこそ許された本なのかな、と感じます。でも、「程度の低い文化」とか書いてしまうのは当時としてもどうかと思います。 あえて褒めるところを探すとすれば、著者の専門分野である発酵の科学的側面(現在の水準から見てどうかまでは判断できません)とアジアにおけるチーズ様食品の情報でしょうか。ただ著者の専門を反映してか、酸によるチーズ作りや熟成させないフレッシュチーズ、牛以外の動物のチーズなどを軽視している印象があります。参考程度としたほうがよいかもしれません。 チーズの歴史を扱った本としては電子化されていないものの、ポール・キンステッドの『チーズと文明』が良い本でした。電子化が待たれるところです。
0投稿日: 2015.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログチーズというのは、人類の歴史と共に歩んできた本当に面白い食品だ。その発生は諸説あるが、山羊の胃袋に乳を入れていたら、胃袋に含まれる酵素の影響で偶然できたものだという。その後世界各地で独自に進化を遂げ、数百種にも及ぶチーズが世界各国で食べられている。 最近チーズの勉強をしていて、ブルーチーズを食べてみたのだが、あの独特の臭みが僕は結構好きだ。
0投稿日: 2014.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書録「チーズのきた道」5 著者 鴇田文三郎 出版 河出書房新社 p215より引用 “筆者はかつて、「食の科学」(十二号、一九七五年)に、 「歴史的事実として、飢えを忘れた部族に生き残りはなかった」 と述べたことがあるが、一般に知られているように、部族の滅亡 の陰には、多くの場合この享楽型食文化が発展していた。” チーズ研究に明るい農学博士による、世界各地の乳文化、とり わけその中のチーズの歴史を記した一冊。 著者とチーズとの出会いから食事文化におけるチーズについて まで、人類史の出来事と並べながら書かれています。 上記の引用は、食事文化類別の中のチーズについて書かれた項 での一文。美味しい物を食べたいのはもちろんですが、楽しみば かりを追いかけて食べるのは考えた方が良さそうです。 いつでも楽しみを追い求めていると、結局満足できることが減っ ていくばかりのような気がします。美味しい物は、たまに食べる くらいでいいのかもしれません。 初版は昭和52年とのことですが、古さを感じない一冊です。 ーーーーー
0投稿日: 2013.08.06
