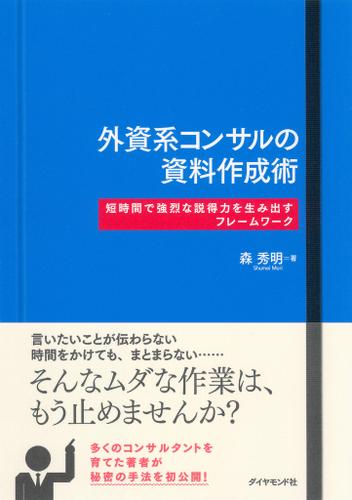
総合評価
(51件)| 2 | ||
| 14 | ||
| 25 | ||
| 5 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料作成の参考にしたいと手に取った。 ビジュアル、ロジック、アウトプット、コミュニケーションの4つのステップ。資料の形は論理で選択。メモ書き、チャラ書き、ホン書きのステップ。相手とのコミュニケーションが資料作成のキモ。 何点もの資料を見てきた著者ということで、やはり数見て自分でも作ってみるのが大事だろうな。
4投稿日: 2025.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料を作る際、ストーリーはまとまってもレイアウトに困ることが多いと感じて、書店で立ち読みしたときに12類型が気に入って衝動買い。別に斬新なデザインが求められる仕事ではないので、これぐらいの数の基本をしっかりできれば良い。仕事のときに手元に置いて活用しよう。
0投稿日: 2024.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ220718に読了とあるが、たぶん何もわかってなかった。 231228に今目を通すと、1h程度で振り返りとしていける程度には理解ができていた。 できるようになってたという安心感と、これをもっと時間をかけずにたどり着かねばいけないなあという切迫感と。
0投稿日: 2023.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ論法ごとにそれをうまく表現する構図が存在する。その対応関係を知っておけばスライド作成の時に整理しやすいよね。というのが知りたかったこととマッチしてたので購入 正直微妙 ある程度参考になる部分もあるが、なにより構図と論法が必要十分条件になっておらず、「その構図で別のも説明できるよね。なんならその構図を見たら別な構造のほうが先に想起されるよね」みたいなところが多い(結合論法のチャートや比較論法のベン図など) あとアジャイルに資料を作るなど、既知のことが多かったのも微妙な原因か 論法自体は参考になるため、とりあえず載っている論法を基準として、いろんな資料を読み漁って各論法のどれに当てはまるのか試してみる。そうしてもっとしっくりくる論法や追加の論法を自分で構築しよう 結局過去の資料を自分で見て、自分で「どんな論理展開の時にどんな構図を使ってるのか」を分析していくのが良さそう 空雨傘を意識する。 こういう緩和曲線(データ)があります。 緩和曲線がこれのときは〇〇って時だ(論理) だからdcnqiは〇〇だと思われます(結論) 後から読み返してすぐわかるようにメッセージラインだけ読んでもストーリーがわかるように 重要ポイント! 情報が集まってから思考を始めるんじゃなく、最初から思考する!情報を集めながら並行して思考することでアウトプットが早期から出始める。KOで仮説がだせるのは最初から思考をスタートさせてるから!!!
0投稿日: 2023.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログPowerPointスタイルの資料の作り方について、誰もが抑えるべき技法を解説している本。 主張の出し方は完全に型にはめましょう、資料を作るときはまずアウトラインを作りましょう。そして、手書きのラフなものから盛り上げていきましょう、といったようなところは類似の本でも何度も繰り返し言われてきたことである。 なので、著者の文章の書き方であったり、説明の仕方が自分に刺さるかどうかが、この本のポイントだと思う。残念ながら自分にはうまくマッチしなかった。 説明の図表が、抽象化した一般論で説明しているのか、あるいは具体的なものを使って説明しているのか、少し読めばわかるんだけれども、すっと入ってきにくい。また著者の自信満々な文章が鼻につくような感じもあった。 自分も試行錯誤しながら、このような本を読みながら、少しずつたどりつきつつある事はちょっと安心できた。
0投稿日: 2023.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容はとてもシンプルなのですが、読み進めるのに少々苦労しました。 外資系とタイトルにつけることで期待値を上げすぎてしまっているような気もしました。 実務に活かすべく、型を活用し、思考やコミュニケーションに時間をとれるようになりたいなと思いました。
0投稿日: 2023.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
論理構成毎に12の資料の型が紹介されており、実務に適用しやすい一冊。 計画段階に時間を割いてから資料作成しましょうね、という流れも解説されており入門書として素晴らしく、資料作成経験の無い人にとっても学びの多い一冊だと思われる。 (メモ書き→チャラ書き→本書き というまずは作成コストが少ない紙で作成内容決めてからパワポに落とし込むなど。) 個人的には12の型を論理構成毎に使い分ける思考は持っていなかったので習慣化していきたいと思います。
0投稿日: 2022.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログパワーポンとを使った提案書って、昔はほとんど使ったことがなかったのですが、 最近は何でもかんでもパワポな組織に所属してしまい、 さすがに基本を勉強しないとなぁ…ということで、 読んでみました。 伝えたい主張をどういう風に図示したらいいのか、悩んだりすることも多かったので、 基本のビジュアルの型がまとまってるのは有り難いです。 (まぁこれで完全に網羅されている訳ではないと思いますが、それでも助かる。) あとは、肝心のロジック構築だなぁ。 底がしっかり固まっていないと、どんなに見た目が素晴らしくても、 価値のないスライドな訳ですし。 この本では、ラフに手書きで構想を練るべし、と書かれていますが、 もうちょっと深堀して欲しかった感はあります。 でも、最初の一冊としては結構役立ちました。
2投稿日: 2022.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料作成術の一冊目としておすすめしたい。資料の基本パターン並びに作成方法は取り入れやすく、何度も読んで体に染み付かせてほしい。チャラ書きは未だに意識して使うようにしている。
0投稿日: 2022.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトルの通りスライドの作成術の本ではあるが、前半はスライドの類型を示し、後半はパッケージ全体の作り方・アプローチについて記述されている。 全体を通したメッセージはスライドやパッケージの作成にはロジックがあり、そのロジックを示すために個々のスライドが選択されストーリーが展開されるということ。 前半の個別スライドを細かくロジカルに解説したパートも勉強にはなるが、おそらく後半のパッケージ全体の作り方の方が書いていて著者も面白かったのではないかというぐらい熱量を感じた。全体像を作って全体的に徐々に仕上げていくスタイル、メモ書き、チャラ書き、ホン書きのスタイルは本当にその通りでこれがなかなか実践できず、一枚ごとに完璧に仕上げていく形になりがち。 時間割の例はワークプランを作るのにあたっても非常に参考になる。1日前に仕上がっている状態なんてこれまで経験したことがなかったので、ぜひ実践してみたいと思う。まだまだ身についていないことが多いので時間を置いて読み直したいと思う。 満足の内容なのだが、やや難しいところがあり星4つとした。イメージはわかりやすいのだけれど、文章がややわかりにくいという印象。
1投稿日: 2021.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
資料作成はインプットから始まってプロセスに移り、アウトプットで終わる3つの手順で行われますが、それぞれにおいて「センスがない」状態はどうなっているのでしょうか。 インプットでは、必要な証拠が十分にそろっていない、何か足りないという状態が「センスがない」状態です。プロセスでは、集めた証拠の分析や整理が不十分で、なぜそういうことが言えるのか、という保証を十分に示せていない状態。そしてアウトプットについては、できあがった資料全体のバランスがとれていない状態でしょう。 言い換えれば、ちぐはぐなアウトプットになっているということです。したがってセンスのないビジネス資料は、インプット、プロセス、アウトプットのいずれかにこうした問題がある、もしくは3つのステップすべてに問題がある資料だと言えます。 では反対に、センスがある資料とはどういうものか、インプット、プロセス、アウトプットの観点で考えてみましょう。 インプットでは、主張を語るのに十分な証拠がそろっている状態です。それも、ウェブ上で誰もが手に入れられるような情報ではなく、簡単には手に入らない情報、しかも鮮度の高い情報が示されている。たとえば、顧客の現場に出向き、そこで働くスタッフの声を集めたり、経営者の問題意識を聞き出したりすることから得られた情報は、証拠としてとても意味のあるものになります。 プロセスについてはどうでしょうか。肝要なのは、資料がロジックに従ってきちんと組み立てられていることです。証拠と主張と保証が明確であり、保証に関して「なぜなら~だからだ」という根拠が語られていれば、センスのある資料と言えます。 そしてアウトプットでは、全体としてのまとまりがあって、資料を見る相手が求めている内容であること。そして全体の筋が通っているものがセンスのある資料です。 このように、ビジネスの資料作成におけるセンスは、美的感性のように捉えにくいものではなく、ロジックの確かさと組み合わせ方に表れるものなのです。 したがって、センスのある資料を作成するためには、インプット、プロセス、アウトプットという資料作成の3つのステップに論理的に取り組むことが何よりも重要になります。
0投稿日: 2021.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は12パターンしかないと言っていて、テンプレートが用意されているので、それに当てはまる資料作成に役立ちそう。 いきなりスライドを作るのではなく、メモ書き、チャラ書き、ホン書きみたいに段階を踏むべきという話は納得出来るし、Sカーブの話も本当に身にしみる。 なんとなく、ビジュアライズに力を入れた本なのかなと期待してしまっていたので、その点はちょっと期待外れだった。
2投稿日: 2020.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ大変参考になる。仕事場にいつも置いてある本。ビジネス資料にかかわるビジュアルの類型が12しかない、と知った以上、グチャグチャ書くことはやめようと思った。あとは"チャラ書き"の大切さ。まず手を動かさなければダメということか。
0投稿日: 2020.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログロジックの流れは参考になった。(証拠→主張→保証) フレームワークに関しては、具体例が少なく、掴みにくかった。自分で実際に手を動かしてみないと、身につかないと思う。
0投稿日: 2020.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ・ビジュアル(12類型) ・ロジック(証拠→主張→保証)★ ・アウトプット(メモ書き→チャラ書き→ホン書き) ・コミュニケーション(共感と信頼関係) -------------------------- 一対一(事実→主張) 並列(複数の事実→主張) 結合(複数の事実を組み合わせる/因数分解/ピラミッド) 連鎖(風が吹けば桶屋が儲かる/ループ) 結合×連鎖(要素×時系列/業務プロセス図/事業展開図) 対立(要素×対立する主張) 比較(要素×比較対象となる主張/ベン図) 対立×比較(マトリクス) -------------------------- ★について 何々がある(証拠) だから何々だ(主張) なぜなら何々だからだ(保証) 裏返すと; 伝えたい結論は何か その結論を支える根拠は何か その結論はその根拠から合理的に導けるか →これらの問いでセルフチェック -------------------------- ・主張の流れがストーリーとなっているか ・5W1Hの要素が含まれているか 5 paragraph essay(序論、本論123、結論) -------------------------- 最初に空パッケージを。 資料のテンプレ。15枚前後が標準? 情報量×思考量=成果。思考はすぐに開始せよ -------------------------- 対話を通じてβ版をつくる。 他人の頭で考える。 相手のニーズを120%掴む(アウトプットイメージを揃える) 相手のニーズをチャートに落とし込める 相手のニーズは変化する前提だと認識している 永遠に未完成だと認識している あくまで物語であることを認識している 正解は1つではないと認識し、論理明快な主張にする
0投稿日: 2020.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログパワーポイントのフレームを提示しているが、一般的なものに過ぎないため、この本を丁寧に読む必要性に乏しい。
0投稿日: 2019.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ途中まで読んでいて、そのまま放置されていたものを先日見つけて読了。 メモ書き、チャラ書き、本書きのくだりは、納得。 部下、後輩はすぐにパワーポイントで資料を作り始めるが、伝えたいことの『熟成』が足りない。著者のいうようなプロセスをたどることで、抜け漏れを防ぎ、追加で必要な調査や資料が何かが見えてくる。
0投稿日: 2017.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ■ビジネスにかかわる資料に必要な4要素 資料の表現が一目でわかりやすいこと 筋の通ったメッセージがはっきりしていること 資料を作り上げる手順が実践的であること 相手の関心事に沿った内容であること ・伝えたい結論は何なのか ・その結論を支える根拠は何なのか ・その結論はその根拠から合理的に導くことができ るのか
0投稿日: 2017.06.23あなたの職場は外資系ですか?
パワーポイントなどの資料作成の基本について、概略が掴みたいならなかなか良い本だと思います。 ただし、プレゼン(説明)前提の資料作成のため、シンプルすぎて日本的な「読めばわかる」系の資料作成には参考にしづらい部分も多いです。
3投稿日: 2017.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章が少し長くビジュアルが少ないが、資料作成方法から、資料作成に伴う作業に進め方に関するアドバイスもあり、踏み込んだ実践書である。2~3冊目で読みたい本である。
0投稿日: 2016.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
12の資料の型、証拠・主張・保証、ロジックと資料の流れ、コミュニケーション大事、メモ書き・チャラ書き・ホン書き、作りながら相談しながら軌道修正
0投稿日: 2016.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料作成術についての本.ドキュメンテーションキャンバスという資料作成を始めてからプレゼンするまでの一連のプロセスを定義し,各ステップでの考え方について述べている.論理展開に応じた12パターンのテンプレートが載っており,型を覚えておくと役に立ちそう. 資料作成術の本だが,キレイな資料をつくるのに終始しないで,チャラ書きでもいいからお客様と対話しなさいって主張で最後を締めくくってて笑った.
0投稿日: 2016.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ少しくどいかなぁ。。わかりやすくプレゼンする方法を教える本の筈なのにちょっとわかりにくかった。根拠➡︎主張➡︎保証がロジックの一番大切な事でらあり、それを定型のフレームワークに当てはめる事で分かりやすいプレゼン資料を作ると言うのがポイントなんだけどもう少し整理できたのかな。。と
0投稿日: 2016.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ評価は高い本なのですが、個人的には震えるような点は見つけられず。ただ紹介されたフレームは有効そうなので、のちのち辞書代わりに使いたいなと。
0投稿日: 2015.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログプレゼンテーション資料の12パターンに、コンサルがよく使う手法(ブレストや戦略論など)と主張と証拠と保証。チャラ書きと定義した手書のドラフトの重要性。コミュニケーションをこまめにとって仕上げていく方法など。
0投稿日: 2015.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
伝えたい結論は何なのか その結論を支える根拠は何なのか その結論はその根拠から合理的に導くことができるのか ✩ひと目で分かりやすいこと ✩筋の通ったメッセージがはっきりしていること ・相手に納得してほしいこと、決めて欲しいことを記述。伝えたい結論は何なのか ・その主張の証拠、根拠。データ、事例 ・主張が証拠、根拠によって合理的に導かれるか。十分保証されている内容かを示す ✩資料作りの手順が実践的であること ✩相手の関心事に沿った内容であること ①一対一論法 ②並列論法 AはCだ。BはCだ。だからCだ ③結合論法 2つ以上の証拠が組み合わさって主張を証明できる
0投稿日: 2015.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ20150411 とにかく頭ではなく手を動かす事が大事なのだとわかる。自分でパターン化できれば色々な事が楽になると思う。
0投稿日: 2015.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログドキュメンテーションキャンパスと呼ぶ、ビジネス資料作成の型、ビジュアル、ロジック、アウトプット作成、コミュニケーションを学ぶ。 まず型を学ぶことは重要であり効率的。コミュニケーションの重要性が高まっているのはを今の時代のポイントであろう。
0投稿日: 2015.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログフレームワークとして適度にまとまってる感じ。外資系などとつけずにほんとに基礎の基礎を話している印象でよかったと思う。
0投稿日: 2014.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に基本的な内容であり、この手の他の書籍と比べて特に目新しいものはない。 新しいフレームワークや切り口を求めて読まれる方には、物足りなさを感じると思う。 ただ、資料を作成する上での本質は抑えられており、自分の手順を見直す上で参考になった。
1投稿日: 2014.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本的な考え方を整理するためには、役に立つ内容。 チャラ書きの重要性については、全く同感。 チーム内に展開することを検討中。
0投稿日: 2014.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料作成術。 言いたい事は分かるが表現が割と難解。腹落ちさせるのに時間がかかる。 資料作成の内容については、先日読んだマッキンゼーの図解の技術と言っている事ほぼ同じ。
1投稿日: 2014.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ表紙のひな形 資料の提出先24pt 資料のタイトル、資料の種類20pt 資料の提出日付、会社/部署名12pt、コピーライトの表示8pt 本文のひな形 メッセージライン20pt、タイトルの掲載18pt、本文14-18pt、注釈、出所など10pt、コピーライトの表示8pt、ページ番号8pt
0投稿日: 2014.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料作成の基本的な考え方が載っていてよい。内容の多くを占める資料の類型については、他のフレームワークの本などと併せて読むべきか。
0投稿日: 2014.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログビジュアル、ロジック、コミュニケーション。基本的なことが中心。ビジュアルの論法はコンサル感強い。ロジックの証拠、主張、保証は大事。コミュニケーションはまた普通のこと。総じるとまあ基本的な内容。
0投稿日: 2014.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料作りのフレームワークとして、ビジュアル(論理と連動した資料(というかパワーポイント等のスライド)の構造)、ロジック(そのものずばり資料で説明すべき論理の構造)、アウトプット(ラフスケッチから資料を作っていくという資料の作成法)及びコミュニケーション(資料そのものの作込より、説明すべき相手とのキャッチボールが大事という話)の4点を説明。 ビジュアルとロジックの話は、非常に単純で簡単そうな話だが、いざ実際にスライド等を作成するときは忘れがちな話なので、意識できるようになれれば良いと感じた。 コミュニケーションも、実践できるかどうかはともかく、重要だねという話は理解できた。 一方、アウトプットの所は、正直必要性という意味で?だった。長い説明資料作成するときに全体構造を考えるのは当然だけど、そのためにラフスケッチを作るとかそんなのどうでもいい話のような。それに手書きで凝ったもの作るより、明らかにパワーポイント上で適当に作った方が楽だし。 文句も書いたが、資料を作る際の頭の整理にはなったので、そこそこ有益だったかな。
0投稿日: 2014.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ保存用。 これまでの資料に関して体系的に整理されているのでハンドブック的に置いておこう。 さすがに著者の豊富な経験から、特に他者への指導の際には威力を発揮しそう。 ★全ての資料の構成 証拠 主張 保証 ※各項の主張だけ読みつないでもストーリになる ★ロジックを考えるときや、ロジックの確からしさを確認するときに役立つ③つの質問。 ①伝えたい結論は何なのか ②その結論を支える根拠は何なのか ③その結論はその根拠から合理的に導くことができるのか
0投稿日: 2014.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ外資系コンサルティング企業での経験を積んできた著者が、ロジカルで説得力ある資料のつくり方を教授する。伝える内容によって異なるフレームワークを紹介。 内容はロジックに基づいているのだけれど、フレームワークの数が多すぎて、全体的に散漫としている印象。資料をつくる時に辞書として参考にするのは良いと思うけれど、もう少し系統立ててまとめてあった方が印象に残りやすいと思った。
0投稿日: 2014.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログボストン・コンサルティング・グループなどで、コンサルタントとしての経験をもつ著者のパワポの資料作成方法についての本。 資料作りに時間をかけるのが嫌いで、ついつい手を抜く癖がある。手を抜きらながらも短時間で資料を作るコツが知りたくて購入。 似たような本は何冊か読んだことがあるが、そういった教科書的な本と比べるとより実践的。 例えば、実務でありがちな、作成途中での内容変更へのうまい対処方法なども書かれていてありがたい。 4つのステップに分けて解説している。 1.資料の形を決める(ビジュアルのステップ) ビジネスの資料は12種類のどれかに分類される(P34)。12種類のどれを使うかは論理で決まる。 2.資料の説得力を高めるための論理(ロジックのステップ) 何々がある。だから何々だ、なぜなら何々だからだが、一枚一枚に成り立つこと。 各ページの資料の主張だけをつなぐと物語になっていること。 3.資料の作成(アウトプットのステップ) メモ書き、チャラ書き、本書きと進める。(本書きのみがPCでの作業) 本書きで1枚30分以上かかる場合はそのページの論理がおかしい。 パワポで、15枚で十分。 表紙、アジェンダ、空の13枚の合計15枚を用意しスタートを切る。 どのページから始めても構わない。 情報量が上がってから(資料が集まってから)考え始めるのではなく、 はじめから思考量を上げることが成果の早い立ち上がりにつながる。 4.プレゼン相手の心と頭を理解する。(コミュニケーションのステップ) プレゼンする相手の時間軸に沿う。 プレゼンする相手の意見は常に変わるものと考え、常に変更する準備が必要。 いつも思うけど、コンサルティング会社の資料って、かなりシンプルやなぁ。
0投稿日: 2014.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ型破りとは稽古して型のある人がやるから型破り。型のない人がやったら、ただの型なしというのだ。 18代目中村勘三郎
1投稿日: 2014.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
どのように提案をおこなうか、論理、プロセス、ビジュアルなどについて。著者自身が今までどれだけの枚数を書いたり、見たりしたのかという部分がちょっと鼻につくが、言っていることは正論。プランニング、プレゼン初心者にはいいんじゃないかな。
0投稿日: 2014.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログNow I can understand well, I wonder when I should read this.
0投稿日: 2014.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログキャッチーなタイトルからハウツー本かと思われるが、そういう本ではない。資料に使う論理は12種類であり、その論理のそれぞれに適した表現(フォーマット)があると指摘している。つまり、大事なのは結論に至る論理であり、それが固まれば、それぞれに適切なフォーマットを当てはめれば資料が完成する。逆に表現で苦労しているときは、論理が煮詰まっていないのである。
0投稿日: 2014.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料作成への心構え、取り組み方とフレームワーク例が整理されている。といっても私含め大抵の人に既知のものであるだろうから、大きな収穫はなかった...今年からアメリカで社会人生活を始める弟にあげよう(笑)
0投稿日: 2014.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ主張を支える証拠だけでなく、そこにしっかりとした保証を明記することが重要 普段営業活動においてプレゼン資料等を作っているが、改めて真っ新な頭で見返してみると、資料だけではなんとも論理的に貧弱なもの。 当然、対面する担当者には説明でカバーできるのだが、直接は会話を交わせない上層部にとって、資料の論理と明快さが決め手となる。 本書を参考に早速骨太かつ明快な資料を作成する。
0投稿日: 2014.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこう言った本は沢山あり、十本十色なところがある。そして、実際のビジネスにおいて実践しないと何も意味を為さない本でもある。この本は個人的には一番しっくり来た気がするので、しばらくバイブルとして実践してみます。というより、もうし始めました。
0投稿日: 2014.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ提案書、企画書等、どの業界で働いたとしても、 避けて通れないドキュメント作成。 お金が関わる資料ということもあるからか、 何を書いたらいいか、どんな構成にすればいいかと、 色んな悩みを抱えてしまい、なかなか上手く作れない。 そういった人向けの資料作成術です。 外資系コンサルと書いてありますが、 ドキュメンテーションスキルのハウツー本として、 活用出来る著書だと思います。 【参考になった内容】 ・ビジネスにかかわる資料に必要な4要素 資料の表現が一目でわかりやすいこと 筋の通ったメッセージがはっきりしていること 資料を作り上げる手順が実践的であること 相手の関心事に沿った内容であること ・経営者と管理者の違い 経営者: これからの企業の存立基盤を考え、 10年単位で戦略を形成する 管理者: 直近での企業の成長を考え、 年度単位で計画を立案する ・資料構成として多いのは以下 表紙、目次、現状理解、背景、事業コンセプト、 顧客、体験、場、プログラム、事業の発展形、 展開スケジュール、収益モデル、収益予測、 体制、まとめ ・資料作成そのものに使う時間よりも、 顧客やプロジェクトのリーダー、メンバーとの対話の 時間を優先的に確保し、思考の時間をたっぷり取ること ・メモ書き、チャラ書き、ホン書きと進めるのが良いが、 ホン書きよりもメモ書き、チャラ書きに時間をかけること ・資料1ページにかけてよい時間は30分まで。 それ以上かかるときは再度関係者と話をすること。 なぜなら、自分が腹落ちしていない可能性が高いから。 ・完成した資料はない、永遠に未完成のままであると 割り切って資料作成を進めること ・正解は1つではないと認識して、 論理明快な主張を恐れないこと
0投稿日: 2014.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ報告書作成にあたっての参考に購入。内容が絞られている(というか薄い?)と感じた。 ラフがきからpptを作るとか、フォーマットを作っておくとか、当たり前だけど大切なことが書いてある。
0投稿日: 2014.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ・資料の主張だけを見れば物語になっている ・忙しい意思決定者は資料のメッセージだけを読んでいる ・エグゼクティブサマリはメッセージが一枚で俯瞰できるもの ・資料は永遠に完成しないβ版をブラッシュアップしていくものと心得る。相手とのコミュニケーションの回数、量が大事。 ・資料のマスターレイアウトは絶対に動かしてはならない ・意思決定者とは一枚の資料で語れる
0投稿日: 2014.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこれも今の自分の課題。 資料の要件は①ビジュアル、②ロジック、③アウトプット(作成手順)、④顧客・上司とのコミュニケーションである。 資料のビジュアルはロジックの組み立てに対応している。(12類型) ロジックは、①伝えたい結論は何か、②結論を導く根拠(データ)は何か、③根拠と結論の合理的因果関係はあるかである。 意思決定者は主張しか読まない。主張をつなげれば物語になっていることが大事。 こうしてみると、資料作成はシンプルなはずなのに、普段いかにごちゃごちゃ考えていることか。 この本の内容を少しだけ意識して作った資料が、上司から「100点満点」と言われた。(笑) まあそれは本当かどうかわからないけれど、身につくまで何度も読みたいと思う。
0投稿日: 2014.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料作成の基本。 社内の進め方に影響されてよく方向性を見失うので、 定期的に考え方を見直す必要がある。 内容はいつもの資料作成TIPSであるが、 資料作成の時間割についても言及があり、有用と感じる。
0投稿日: 2014.02.24
