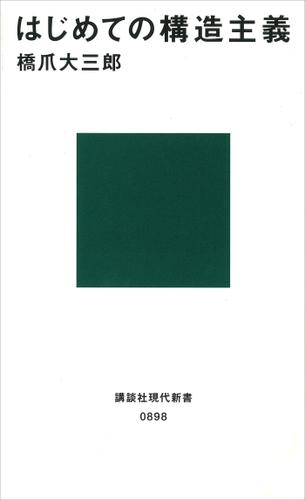
総合評価
(170件)| 48 | ||
| 56 | ||
| 34 | ||
| 2 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義者によれば、数学と神話には同じ秩序が宿っているという。近代以降において、普通私たちの多くは、数学は理性的思考そのものなのに対して、神話などは、わけのわからない荒唐無稽なでたらめなものに過ぎないじゃないかと思っていることだろう。 特に西洋では、たった一つの真理を探求する知の営みこそ崇高で、偉大な頭脳が目指すべき道であるとされていた。そうした知のシステムを支えていた大黒柱の代表格が<数学>であったことはいうまでもない。その数学と神話が同じなんてちゃんちゃらおかしいと考えてしまうだろう。 ところが、構造主義者たちはこう主張をする。 1)西洋(ヨーロッパ)の知のシステムは数学に代表されるような真理を目指している 2)しかし、その数学はただの制度に過ぎなかった。 3)したがって、これを敷衍すれば、西洋の知のシステムも制度でしかない。 ・・・と。 ゲーデルの不完全性定理でよく知られるように、数学は完全であることをその数学自身によっては示すことは決してできない。「正しさ」というのは公理という前提をどう置くかによって違うのである。ここに真理の相対主義が生まれることになった。ユークリッド幾何学で成立する「真理」は、非ユークリッド幾何学では成立しないということが起こるのである。人間によって創られたものである以上、数学も神話も同じような<構造>をもつことになるのである。
0投稿日: 2012.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログレヴィ=ストロースがどのように構造主義を確立したのかを順を追ってわかりやすく解説してある本。 構造主義ってクール。
0投稿日: 2012.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱりこれが一番シックリ来る。「主体的な人間」を超える《構造》(精神分析の見地においては、フロイトやユングはそれを「(集合的)無意識」と呼んだ)の存在を考えることは、現代社会を考える上で、とても有益である。“真理”というものも、ある思考枠組の中から生じるものでしかなく(つまり、“絶対的”なのは、その《構造》の中でだけ)、また、私たちの信じる歴史も、物語に過ぎない(その点、神話や伝承の孕む信憑性の問題を、同様に歴史に対しても抱かなければならない)からである。……うーむ。難解な言い回しはさておき、社会(心理)学の知識を国際関係の分析・検討に活かせたらよいのだけれど。
0投稿日: 2012.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは面白かった! 特にレヴィ=ストロースの人類学のアイデアや、それに関するモースの贈与論、ソシュールの音韻論や記号論などここまで詳しく、かつ分かりやすく書いてある本は他に読んだことが無い。 中盤の数学史と構造主義の関連を説明する部分は脳みそとろけるかと思うほど面白かった。 内田樹の『寝ながら学べる構造主義』の後に読むと、理解が深まって良いと思う。 これはオススメ!
1投稿日: 2012.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログレヴィ・ストロースを軸に構造主義思想に到るまでの歴史・道筋をたどっていく入門書。 「ませた中学生にもわかる」ように書いたと著者が語るように、専門用語を極力使わずに主義思想を説明してくれるのは好印象。
0投稿日: 2011.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
レヴィ=ストロースによる構造分析手続きの手法を丁寧に追っていくことで、わかりやすく構造主義の思想を解説している。 しかし現在の文脈で(さらにフェミニストの端くれという私の立ち位置も含め)考えると、いくつもの受け入れがたい表現が出てくるので、それにイチイチ苛立ってしまい、★5とはならず。 レヴィ=ストロースの議論自体がフェミニストからは叩かれやすい理論展開をしている(女性を交換物と見なすところなどまさに顕著)のでその理論紹介という面では仕方がないのかもしれないが、著者の文章からはどうもそれだけではなく著者自身の女性蔑視的考えがうかがえるので、とても不快になった。
0投稿日: 2011.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
構造主義について、おもにレヴィストロースに注目して書いている本。本当に入門って感じですらすら読めて、わかりやすかった。 そのなかでも構造主義にいたるプロセスについてわかりやすく説明があって、ソシュールやらデュルケームなどについても触れている。 うん、お勧めの一冊。でもこれ一冊で構造主義がわかるっていう本でもないかな?って感じ。
0投稿日: 2011.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕なりにまとめると、構造主義とは 「違うように見えて実は根本を探ると同じこと」が世の中のはたくさんある。 ということかなと思いました。 これは現代人は結構共通認識として持っているのではないかと思う。 例えば、ネットの世界。 ブログのデザイン。 ホームページ風にしているブログも、一般的なブログも仕組みは同じ。 技術はよくわかってないけれど、twitterやfacebookなども仕組みはよく似ているんじゃないのかなぁ。 簡略化しすぎだと思うけれど、そういうことかなと。 フィルターを通してみるとAやBやCは相似形ですよっていうのが 構造主義なのかなぁと、簡単に理解したつもりです。
0投稿日: 2011.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログべつに初めてじゃないけど、バラバラに理解した構造主義者たちを同じ地平に置くには良いかなと思い、読んでみた。 構造主義の変遷というよりは、構造主義がどんなルーツ(若干科学史のようだった)を持つか、そしてどうやって構造主義が産まれたか(ソシュール、レヴィ=ストロースとヤコブソンあたり)の説明が大半だった。 人類学のクロード・レヴィ=ストロースと並ぶ大家、文芸のロラン・バルト、精神分析のジャック・ラカン 、歴史学のミシェル・フーコーといったいわゆる『構造主義の四天王』といわれる人達はあまり出る幕がなく少し残念。 しかし本書ではどの人も行った手続きはそう変わらない扱いになっているから、わざわざ詳しく説明する必要もないと考えたのだろうか。きっとそうなのだろう、なにしろ「はじめて」であれこれ言われても分からないだろうし。 この本では、構造主義を構造主義の立場から解体してみせている。 本書でレヴィ=ストロース以外の人に湧いたら、付録のブックリストから構造主義者の著作をあたってみると良いかもしれない。
0投稿日: 2011.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「かなりおませな中学生の皆さんにも読んでいただけるように、書いてみました」というように、読者に語りかける口調で分かりやすく構造主義の成り立ちを解説している。 ここで説明されている「構造」とは簡単にいうと「深層に隠されている秩序」という意味で、あるテキストをいったんバラバラにして一定のルールに従って組み替えると、新たな仕組みが見えてくるというようなことだ。 レヴィストロースの入門書としておすすめ。
0投稿日: 2011.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の入門書として素晴らしい本。特に、構造主義の発生と近現代数学の発展との関係についての記述は、歴史の解釈の1つと割り切って読んだとしても、ワクワクする論旨展開になっていて、非常に面白い。そして、構造主義におけるブルバキの役割についてもはっきり言及されており、私が本書を手に取った目的を完遂することができた。モノに着目する際に、その表層(見た目)を無視して、裏にある機能の「構造」を切り出そうと試みることが構造主義だとしたら、代数系の間の準同型写像を構成するという現代数学の王道アプローチと、思想的にはほとんど変わりがない。(もっとも、現実のモノとモノの間に、厳密な準同型写像を構成できることはほとんどないのだが) ブルバキとは、「数学」の考察対象のすべてを「集合」と「写像」の概念で統一的に記述できるよう、病的なまでに注意深く「言葉(数学語)」を整備したグループである(たとえば、injectionやbijectionといった用語を「発明」したのはブルバキである)。レヴィ=ストロースがアンドレ・ヴェイユ(ブルバキのリーダー)との会合を重ねる中で、「構造」のアイデアを膨らましていった、というのは著者の仮説であるが(彼らに面識があったことを示す史料は存在する)、歴史の解釈の1つとして非常に面白いと思う。 【関連レビュー】 ・寝ながら学べる構造主義(内田樹) http://booklog.jp/users/asaitatsuya/archives/4166602519 ・ブルバキ―数学者達の秘密結社(モーリス マシャル) http://booklog.jp/users/asaitatsuya/archives/4431709266
0投稿日: 2011.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の入門書として本著は広く読まれているようだ。個人的にはレヴィストロース風の構造主義はまるで面白くないのだが、構造主義の骨子を理解するにはレヴィストロースが必要なことはなんとなくは理解できた。結局のところレヴィストロースが何をしたかったのかがまるでわからない。相対という言葉を使うけれど、<構造>なるものは真理ではないのか?と感じる。真理がないというが、構造であるならば相対を果たしきれてはいないのではないか?また、レヴィストロースの思想自体は他の思想への影響力は極めて強かったのだろうが、その思想自身がより根源に迫りきれるものなのかどうかというとかなり不確かにも思われる。個人的には哲学とは真理への志向性と本人の嗜好が混ざり合ったものだと感じている。それがどちらなのかわからなくなりそのわからなくなった先にしかしなにやら見えてくるものがある。もしそれに成功したならばそれが哲学と言っていいのではないか?著者が後書きで述べているように、現代日本では独自の哲学を持っている人は少ない。ビジネス書やら芸人やらがそれぞれ哲学という言葉を簡単に使っては本を書いているけれど、彼らはそれを手に入れるために懸命に考えたのではなくて社会的に成功した後に、自分が何を考えて行動したのかを文章化しただけだろうと思われる。現代日本においては誰でも言えるような台詞が、社会的に成功したという一点において素晴らしい台詞となってしまう嫌いがある。おまけに現代日本人は年々頭が悪くなっているようにも思う。二十年前とか、三十年前とかならばやや高度な内容のものが広く読まれた。もちろん、大衆にはそれを理解しきれないので実際はそれを読まずにおいた人が大多数だろうが、しかし広く流通したものはそうした高度な内容を持っていた。今はそうではない。今は誰でも書けそうなレベルのものが広く流通している。誰でも読める代わりにこれといって内容がない。そのようなレベルのものをなぜだか礼賛する。もはや思想や知識が馬鹿らしいものだと感じられているのかもしれない。今は情報があればいい、そういった傾向にあるのだろう、と著者の後書きに触発されて書いてみた次第である。 本著の内容を要約すれば、構造主義というものは相対性を肯定的に捉えようというものだと言えよう。ニーチェが言うところのニヒリズムが全てを相対化し虚無的に振舞うというのならば、構造主義は主客概念や西洋中心のヒューマニズムなどの近代精神への反省として生まれた思想であると言える。とはいえ、反人間主義ではない。西洋中心のヒューマニズムに反対しているだけであって、基本的に人間に重きを置いているところには代わりがないからである。レヴィストロースは自文化を相対化することで構造に迫ろうとしたのだ。個人的にはこれが真理といわずしてなんだろう?とは思うのだけれど、だから真理を相対化するというよりは、西洋中心の真理ではなくてより普遍的な人間としての真理を見つけるべきだと考えていたのではないか?とは思われる。だが、レヴィストロースについてはどうにも哲学者とは思われず、思想家というのはうなずけれるけれどきいていると人類学者にしか思えないのだ。一般に広く言われている構造主義やポスト構造主義は、構造主義の前後に繋がっている連綿とした流れから、それぞれが都合のいい部分を借用して自らの理論を作り上げているものの集合みたいなものでかなり混沌しているのは間違いない。とはいえ、その根本にあるものはソシュール的な言語学と西洋の遠近法より発達する幾何学と言えるようだ。そこにはかなりの根拠があるように映じる。とはいえ、その数学はどちらかと言えば文系よりな数学にも思われる。理論重視の数学とでも言えばいいのか。ちなみにレヴィストロース自体は抽象代数学に重きを置き、結果として空間的な分析を行っているのだが、これは相対性理論と比べるとやや相対性が不十分と言えるのかもしれない。このあたりのズレをどうにかできた人はいるのかいないのか不明ではある。ちなみにソシュールの言語学自体もそれが出現してくる必然性やそこに焦点が当たる理由もわかるのだが、実際に議論されていることはせせこましくてちまちましたものとなっているというのもまた事実なのではないだろうか?真理への志向性への反省としてその土俵自体を捉えようとするのがポストモダンであるはずなのだが、実際には周辺領域のテクニカルな議論に終始してしまっているような気がしないでもない。本著を読んでいて一番愉しく読めたのは数学的な部分だろうか?
1投稿日: 2011.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しい理論や概念の本質を分かり易く教えてくれるという意味で、とてもいい本に出会いました。 レヴィーストロースってすごい人なんですね。結婚・親族にかかわる全人類共通の構造を示して見せたのだから。なんて頭がいいのだろうと思います。こういった、できるだけ普遍的に仕組みを解き明かそうという考え方は自分にとっては興味があるものです。 しかしこういった人類学や社会学、神話学って、現実世界を変えてるんのかなと思いました。例えばニュートン力学や相対性理論が科学技術を生んだというような意味で。
0投稿日: 2011.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ修論に格闘してたとき、「君のやっているのは記号論なんやでぇ」と言われ、「記号論って何!?」と慌てて読んだ一冊。今思うと、なぜタイトルに「記号論」のキの字も入っていないこの本を手に取ったのかはまったく謎なのだが、結果的に現代思想の入門にはとても良かった。専門的な評価は分からないが、現代思想への導入としては、分かり易く、面白いので良いと思う。
0投稿日: 2011.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の入門書というと、それに属する人々の思想を簡潔にのべて終わってしまう場合が多く、はたして構造主義とはなんだろうという疑問がのこってしまうことが多い。しかしながら、本書はそのような個別の思想を箇条書きに記述するのではなく、あくまでも構造そのものを焦点にあてているので、エッセンスがとてもくみ取りやすいと思いました。
0投稿日: 2011.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログレヴィ=ストロースに焦点をあてて、「構造主義」の来歴とそのエッセンスを紹介したもの。フーコーなど他の構造主義の思想家については簡単な紹介にとどまっている。 ソシュールの言語学に端を発するある体系の対立的要素を書き出し、書き手という主体者を離れたテクストの「構造」を明らかにするという思考は、確かに斬新であるし、様々な分野に応用できる可能性を秘めていたことは理解できる。 これをきっかけに色んな構造主義の本に手を出してみるのも悪くないと思った。
0投稿日: 2011.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
構造主義とかポストモダンとか一体何なんだよ というように思って 一応、なんとなくは知っていたけど 入門書も読んだことがないな問うわけで読みやすそうな所から読んでみた で、わかったかっていうと やっぱりなんとなくしかわからなかった 一応自分なりに説明すると それまで未開の野蛮な文化西洋社会が見下げていた文化が 実は馬鹿にしたようなものでもないよと やり方や見てくれが違うだけで ちゃんと考えて調べれば論理的で合理的なシステムだよ と言いだしたレヴィ・ストロースさんという人類学者が発端になって生まれた思想らしい キーワードは数学 数学には公理とかいうのがあるらしいんだけど この公理というのは、昔はもうこれ以上分解できない、当たり前すぎて証明することができない、他の定理を証明することしかできない、自明の事実でこの公理から出発する数学(幾何学)しかないと思われていたわけ でも、ちょうどこのレヴィさんが生きていた時代あたりで、この自明の事実というのは、もちろん自明なんだけど、他にも、違う公理を使うことで出来る数学(幾何学)がありそうだぞ、ていうかある、作れるし作ったし という状況になって参りましてさあ大変 今まで唯一の真実だと思われていたものが実は制度のひとつにしかすぎないことが分かってしまった 出発点(公理)が違えば結果も違う 神様、真実ってあるんすか ということになりました で、その数学を文化にあてはめたのがレヴィさんなのです 彼は、西洋文化が唯一もっとも優れている文化 直線状で一番前に居る進化した文化だと思われていた西洋文化に対して 出発点が違えば向かう方向も違うし考え方も違う 西洋文化以外の文化は未開なんじゃなくて種類が違うだけなんだ ということを 数学的な考え方を駆使して それぞれの民族の婚姻制度だったりとか神話分析をしたりだとかすることで 西洋文化の皆様を論理的だと納得させて衝撃を与えたわけです で、構造というのは どんな文化にも在る、原則の様なものです ある設定のもとでどれだけ変化しても変わらない性質のことらしいんだけど ここは正直あまりわからない こんな思想らしい ここら辺から多様性っていう考え方が出てきたのかなあ そういえばもうかなり前の話だけど テレビやら漫画やらで多様性がどうとか 傲慢な西洋文明とかそういう言葉が出てきていたなあ 時間はつながっているんだなあ この著者がこういう数学的な説明をしている人はいないと述べていたので もしかしたら偏った理解かもしれない もう少し勉強しよう
1投稿日: 2011.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本当に易しい日本語で書かれているので、その点は苦しまずに読むことができました。読者に話しかけるようなスタイルで、とても親しみがもてます。 レヴィ=ストロースのことを主に話題にしていますが、彼がどのように発想し、思想を展開しようとしていたのか…ということが概観できると思います。 著者も本文中でことわっているように、レヴィ=ストロースに話を絞り、他の構造主義の思想家については紹介程度となっていますが、ほんとに紹介程度です…欲を言えば、もっと解説してほしかったです。 しかし、なにはともあれ、構造主義のイメージをつかむにはとてもいい本ではないでしょうか。
0投稿日: 2011.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学とは。情緒という抽象を計算という具体に置き換えて、世の中を何とかかんとか頭に押し込めて概念の世界を生きて行こうとする試み、だと思う。異論は許す。
0投稿日: 2011.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に構造主義が初めて分かった。難しいことを分かりやすく書いている。 レヴィストロースがやりたかったのはそういうことなのね。 ☆5つに近い!
0投稿日: 2011.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本的にはレヴィ・ストロースを説明することで構造主義を開設している。レヴィ・ストロースの悩みは人類学を機能主義的にすべて説明することが不可能だったこと。そこからソシュール(を学んだヤーコブソン)、モース、数学における構造主義からヒントを得て研究をした。 ソシュール言語学は「言語は差異のシステム」であり、そのため言語は恣意的であると言う。シニフィアンとシニフィエは恣意的に結びつけられているが、結びつきを解かれたとたんにどちらもなくなる。 モースはクラ交換を取り上げて「価値があるから交換する」のではなく、「交換するから価値がある」という発想の逆転を行った。この2人からレヴィ・ストロースは親族の基本構造の着想を得る。 さらに遠近法→射影幾何学→形式主義→<構造>と発展してきた数学から「神話素の置換群を調べることで神話の構造が見える」ということを発見?する。 又、ユークリッド幾何学の相対化などから、数学における真理が「制度」でしかなくなる。構造主義も同様にヨーロッパの知が相対的なものでしかないことを証明することになる。
0投稿日: 2011.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 西欧文明中心の近代に終わりを告げ現代思想に新しい地平を拓いた構造主義。 レヴィ=ストロースの親族・神話研究の、鮮やかな方法と発想の背景に見えてくる、ソシュール言語学やモースの贈与論。 そして遠近法にまでさかのぼる、数学史の水脈に隠された〈構造〉のルーツ。 モダニズムからポスト構造主義への知の戦線に、軽快な文章で歯切れよく迫る! [ 目次 ] ●『悲しき熱帯』の衝撃 ●天才ソシュール ●レヴィ=ストロースのひらめき ●インセスト・タブーの謎 ●親族の基本構造 ●神話学と、テキストの解体 ●構造主義のルーツは数学 ●変換群と〈構造〉 ●主体が消える ●構造主義に関わる人びと:ブックガイド風に ●これからどうする・傾向と対策 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2010.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ西欧文明中心の近代に終わりを告げ、現代思想に新しい地平を拓いた構造主義 まぁ小難しいことを言われてもよくわからないのがこの構造主義ってやつです 主にレヴィストロースについて書かれており、そこから構造主義とはどんなものなのかを解き明かそうとしている本です 哲学に関する本は一般に避けられるようなことが多いような気がしますがこの本は筆者の文章がテンポよく簡単に読み進めていける本だと思っています 人として尊敬される人って言うのは自分なりの哲学を持っており、そういう人っていろいろなものの見方を知っているような気がします ぜひ構造主義にも足を踏み入れてみましょう
0投稿日: 2010.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ未開の地におけるとっても驚くべき「構造」をレヴィストロースが発見、その考え方が他の学問にも応用できる構造主義へと発展した。『寝ながら学べる構造主義』は他の構造主義の代表者も紹介されていたが、こちらはブックガイド風にささっと紹介するにとどめている。こちらは構造主義の生い立ちを知るのに適していると思った。
0投稿日: 2010.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の成立過程と、その内容について簡単にまとめられている。ただ親族の構造に関する説明が、わかりにくかった。大まかに掴むには良い。
0投稿日: 2010.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義、主にレヴィ=ストロースの仕事について紹介。(というかほぼこの人についての解説にページを割いてある) 先が気になって一気に読んでしまった。 読んで目からうろこです。 この考え方は結構色んなことに応用できる気がする。
0投稿日: 2010.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白くてとても読みやすかったので一気に読んでしまった。内容は構造主義というよりは、天才の世紀ツアー・研究とはなにか、という感じだった。あとレヴィ=ストロース論。大学生に必要な研究の歴史の大体に触れられる内容で、高校生にも読める良書だと思う。
0投稿日: 2010.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学2年生の時分に読んだ記憶がある。 構造主義に至る近代思想を学ぶ入門書としては、本書と「新文学入門」を読めば基礎は完ぺき。
0投稿日: 2010.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく面白かった。この本を読むまで、構造主義はイデオロギー的なものとばかり思ってた。大学生活中にこういう本をもっと読まないといけないと思った。
0投稿日: 2010.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログレヴィ=ストロースが死んだので積読から読んでみた。 実存主義はもう十分読んできたので、それを攻撃した構造主義というものを知るにはタイミング的も良かった。 そして何よりこの本が明解で現代思想を知らない自分でも理解することができた。 実存主義は人間個人が主体なのに対して、構造主義は社会的なものだと思えば良いのかな。 そのため様々な学問にも汎用的なのだと。 自分は理系出身なのだが、数学にもそれが生かされて新しい発見があったということは全然知らなかった・・・(高校の微分積分で躓いて、大学でもろくに数学やらなかったので・・・)。 これを読んでポアンカレ予想を解いて後、表舞台から去って母親の年金で引きこもり生活をしている学者を思い出してしまった。 優れた数学者はきっと哲学者としても相当なもので、彼はきっと知ってはならない真理にたどり着いたのでは、と。 構造主義自体は真理そのものを否定しているようだが、ポスト構造主義を更に超えた全く新しい真理へ到達する思想は意外と数学者から生まれるのかもしれないと思ったり・・・。 構造主義者自体、数学に相当長けていたそうなので、そこにヒントがあるような気がしてならない。
0投稿日: 2010.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ進歩の順番は決まっていない。 ヨーロッパの人々は近代化を進める中、 植民地を増やして原住民を見下して いたけれども、レヴィ=ストロースは 違うんだよ、ということを親族研究や神話研究で証明した。 構造主義は人間や社会のあり方を歴史(といって悪ければ西欧思想の色眼鏡)抜きに直視する方法を発見した。
0投稿日: 2010.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこれだけで構造主義が分かったという感覚はまだ持てませんが、非常に要領よく書かれていると思います。“構造”という見方の源泉が数学にあるという説明には納得しました。生成言語学の「原理とパラメータ」でいう「原理」にも近い香りがするし、知覚心理学者ギブソンの言う「不変項」も遠からずかも。
0投稿日: 2010.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の生みの親とされるレヴィ・ストロースに焦点を当てて、構造主義を解説する。『寝ながら学べる~』の方を先に読んだが、それと比べると、数学との関係を論じているのが特徴。
0投稿日: 2010.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ西洋思想の入門書として最高。構造主義がどうだ、というよりは、構造主義を中心に、思想全般への入り口を開いてくれる。万人が読むべき本。
0投稿日: 2010.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログロンドン道中に読んだ数冊のうちのひとつ。 案外テツガク好きだし、コノ人の本は良き入門書として愛読している。 レヴィ・ストロースを中心に構造主義ってやつを紹介する入門書です。 視点によって真実は変わる アタリマエと言えばアタリマエだが 西洋からこんな考えを生み出すには、 それなりのブレークスルーが必要だったのでしょう。 ぱらぱら捲りながら楽しく読める一書です。
0投稿日: 2010.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログとってもわかりやすい。 1章と2章を読むだけで(120ページくらい)、構造主義の創始者であるレヴィ=ストロースについては十分理解できる。4章はレヴィ=ストロース以外の主な構造主義者と、ポスト構造主義者の紹介少しずつされている。 授業でもらったレジュメだけではさっぱりわからなかったのが、だいぶ納得できた。わかりやすいのでほんとにおすすめです。 レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』、読んでみたいと思う。
0投稿日: 2010.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「未開人」が「文明人」に負けない程偉いのは分かったよ。だが「構造」は、人類が作った覚えが無いのに、元々有ったのか。なら神が創ったのかよ。やはり、社会の発展の歴史の初期の段階で、先人が無意識に作ってしまったものではないのか。 「アマゾン文明の研究」という本を知ってるかい。レヴィ・ストロースが「野生の思考」を見出したアマゾンの原住民は、実はかつて都市文明を築いていたそうだ。レヴィ・ストロースは初めから間違っていたんだな。かわいそうだな。 この本はバブル時代に書かれたのか。マルクスの予言はことごとく外れただの、マルクス主義は終わっただのとはしゃいでいるが、この資本主義をどうするんだよ。現実を変革する気は有んのか。 それに構造主義が批判したのはマルクス主義ではなく、スターリン主義でないの?今や百科事典でもマルクス主義とスターリン主義は別物だぜ。 マルクスの絶対的窮乏化理論などは今や最先進国のアメリカなどで現実に成り、マルクスの予言通りに動き始めている。 ソシュールの記号言語学も破綻したと聞く。それを人類学に援用したのはともかく、全ての分野に援用したのが間違いだったのではないのか。構造主義こそ終わったのではないか。 三浦つとむの「マルクス主義の復原」の「第三章:構造主義とマルクス主義」を読まれたく存ずる。 参考先→http://blogs.dion.ne.jp/liger_one/archives/424023.html
0投稿日: 2010.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義って何なのよ?レヴィ・ストロースって何したのよ?という疑問と友達の紹介で手に取ったこの本なんですが、学問的に面白かった。自分の言葉で説明するのは未熟だから難しいけれど、いろんな事象の「構造」を見抜くためには支配的な“真理”あるいは“視点”から脱却しなければいけない。もっと具体的にいえば、西欧主義的からの脱出だろうか。本書の例から引用しよう。軍国主義が始まって世界進出が盛んになって以来、南米やらアフリカとかとうじでいう「未開」の社会は「おくれている」だの「まだ原始的である」と言われていて、それゆえいろんなものを分析するときに歴史性が重視されていたんです。「人間の歴史は一直線であり彼らは我々より前の段階におり、時間を重ねることで我々の段階まで追い付くのだ」、みたいな感じで。でもそこに異を唱えたのがレヴィ・ストロースさん。西洋中心主義を「西洋の色眼鏡」つって批判したんですな。例えばある民族のカリエラ型の婚姻規則に関して(もちろん“原始的”っていうレッテルが貼られた民族)。この規則って、実は人類(西洋)が二千年かけて発見した「クラインの四元群」とまったく同じなんですな。西洋が二千年かけて発見したものをこの民族ははるか昔から誰にも教わらずに、ちゃんと同じやり方で、自分たちの社会内で適応させていたわけですよ。もちろんこの分析に構造主義が関わってるんすな。他にも遠近法に関しての考察もある。詳しくは読んでほしい。それが手っ取り早いから。知の巨人たちはほんっとにすごいです。もうすぐしたら「悲しき熱帯」を入手しようと思う。 さぁこれから専門書を読みまくるで!!
0投稿日: 2009.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義というものを中・高生にも分かりやすく解説したという本。はっきりいうと良く分からない。ぼーんやりとしたものは浮かぶものの、霧のようで上手くとらえられない。 簡単にいえば、真理の相対主義というパラダイムシフトが起こったという事なのか? 構造主義というものに始めて触れたので、勉強不足がこのもやもやをもたらしているのかもしれない。
0投稿日: 2009.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログあー難しかった。しかしかなり分かりやすく、親しみやすく書いてくれている。 構造とは、変化しても残る特徴の組み合わせのことなのかな? あー頭に入っているのだかいないのだか、もう一回読まなきゃだめだなー
0投稿日: 2009.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ『はじめての○○』 なんて本を手にするのは、『○○入門』 や 『○○教室』 といった本と同じくらいに気恥ずかしい。しかし、『川づり入門』 (小学館 入門百科シリーズ) や、『英語長文読解教室』 (伊藤和夫著) などは、私にとって永遠に輝き続ける名著だ。 で、私はこの本を読了した今、「考える」 ことに入門しようと強く思った。今後この本が私にとって輝き続ける名著になるかどうかは、今後の私の考え方、生き方次第である。
0投稿日: 2009.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ極めて平易(ややくだけすぎ?)な文体で、物凄く分かりやすい。 結局、構造主義の内容については「大体こんな感じ」というイメージを提示して終わるが、入門としては十二分だと思う。 構造主義そのものに対してよりも、むしろそれを本文で追いかけてゆく中で通過した、幾多の学者や思想…こちらに惹かれた。 思想分野はこれまで何となく敬遠していたものの、本著を読んでそれに素直に興味が湧き、また西欧思想史がクリアになった感覚。 構造主義だけでなく、そのルーツである言語学、数学、幾何学…などが色々(しかも分かりやすい説明で!)出てくるので、興味を広げるよいきっかけになるのでは。
0投稿日: 2009.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ1988年(著者40歳)の刊行。人文学系、社会学系の研究分野での形式化運動としての構造主義(初期構造主義)の概説書で、とても平明。 数学分野の構造論(群論など)との並行関係が押さえられていて。構造主義の潮流について考えるなら、理科系以外の読者に大きなメリットが期待できる。
0投稿日: 2009.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこれ、学生のときに読んどきゃよかった。いまさらよくわかりました。 学生の時の知識がたくさん呼び起こされて、とても興味深くて新鮮でした。こういうのも読むようにしよう。
0投稿日: 2008.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代思想の始まりだとか。 まぁ近代までの西洋中心主義ってのは分かりやすい反面、 無視している部分が多すぎたんだよね。 それを見直していこう、っていうアレかな。 でも現代でもジェンダー論とかああいうのが流行ってしまう訳で、 何とも言えないよね。
0投稿日: 2008.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログいままで大学で勉強してきた論理学、社会学、言語学たち。 こんなちょぴっと勉強したって結局なんだかわかんないや って思っていたが、 まさかこんなところで全部が役に立つとは… いろんな分野に予備知識があったのですんなり読み切れました。 だけど、まだまだ構造主義わかっていません!! 1日で読んでしまったしね。 きちんと要約できるようにまた読み直しますw 09.4.11 2度目。 初めて読んだときとは違って本に出てくる人の名前で知っている人が増えてきた! 少しは成長したのかな? これから、もっと勉強していこう。
0投稿日: 2008.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生にもわかりやすいよう、丁寧に構造主義を説明しているが、数学の話になると、私にはよく理解が出来なかった。また、口語的な書き方が古かったり、読みにくい部分も少なくなかった。機能主義が「〜だから」というbecauseの説明体系であるがゆえに、循環論に陥ったり、偏見が介入する恐れがある一方、構造主義は感情や偏見によらず、差異があるからこそそれぞれの価値が見出せる、とか交換するから価値がある、といった新たな説明体系をもっているのが面白いと思った。進歩主義に見られる偏見や限界を超えるものであるのだろう。ただもっと込み入った議論になってきたり、その構造主義の適用範囲を親族や神話以外に広げる場合、実際的に意味があるのか、というと難しい。機能主義の方が、「〜のため」という理由づけを持ってものごとに役割を付与する分、実用性や説得力(それがたとえ表面的なものであったとしても)が高いように思われる。構造主義の考えは興味深いが、新たな発展を何かに促す力は弱いように感じる。
0投稿日: 2008.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の入門書だけど、主にレヴィ・ストロースの構造主義について書かれている。 文体自体は砕けていて非常におもしろい。でも構造主義はやっぱりむずかしいね。
0投稿日: 2008.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ私に脳内革命を起こしてくれた名著の1つ。 ここまで分かりやすく書けるのか。学問人としてその才能に嫉妬しました(笑) この人の本も分かりやすい。教育実習が無事に乗り切れたのはこの人から小室直樹にたどり着いたおかげでした。
0投稿日: 2008.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1章 「構造主義」とはなにか 第2章 レヴィ=ストロース―構造主義の旗揚げ 第3章 構造主義のルーツ 第4章 構造主義に関わる人びと―ブックガイド風に
0投稿日: 2008.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ近親相姦ってなんでタブーなんでしょうね。レヴィ=ストロースが面白いモデルを提唱したみたいです。コーゾーシュギくらいほんと一般教養だと思うんですが。
0投稿日: 2008.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ私が言わなくても有名ですね。大学生の必読書(?)です。本当は一年生の時に読むのだろうけれど……。非常に分かりやすいと思われます。ただ、やはり「構造」のイメージが難しい。理解するのは大変かも。
0投稿日: 2008.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ文化人類学を勉強してた時に読もうと思って手付かずだった1冊。レヴィ=ストロースの考えを噛み砕いてくれてて読み易かった。時折読み返す事になると思う。
0投稿日: 2007.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義者の中でも、レヴィ=ストロースに焦点をあて、理解しにくいとされる「構造」がいったいなんなのかを説明してくれます。 「構造」の説明が非常によかった。
0投稿日: 2007.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2007/07 立ち読みで全部読んでしまったのだけど、買おうかどうか迷っている。 リストにあげて端切れを紹介して「あとは違う本(自分の、か、原著)を読んでね」と逃げるのではなくして、しっかり序論本論結論しているのがよかった。レヴィ・ストロース一点買いの本です。
0投稿日: 2007.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の始まりを、レヴィ・ストロースの研究に沿って解説している本。入門には最適だし、最低限の事は網羅してあるのでおススメです。ポスト構造主義とかのたまう前に、まずは構造主義自体を理解するべきだと思いました。
0投稿日: 2007.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類の進歩という幻想や、人間中心に創り上げられていく世界に対して疑問を投げかける。つまり、世界は変化しているように見えるが、本質であるところの構造はなんら変化しておらず、構造というルールの中での出来事にすぎないという考え方である。新境地開拓ってかんじだ。
0投稿日: 2007.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ1回生のときからバンバン出てくる構造主義ですから、全然はじめてじゃないけどねwでもそーゆーことだったのねと気づいたり確認になったり、とても気さくに読めました。橋爪先生わかりやすいなあ〜
0投稿日: 2007.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の入門書としては内田樹さんの本かこちらか…。どっちも面白い本です☆こちらは僕の心の師、クロード・レヴィ=ストロースを中心に書かれています☆
0投稿日: 2007.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「構造主義」という言葉すら聞いたことがなかった私ですが、なんとなく理解できました。二回読みましたが。構造主義という「考え方」を理解しておくことは、他の本を理解するのにも重要です。
0投稿日: 2007.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ古い本ですが、読みやすい本です。 著者が、文化人類学者の名前とリーバイスを間違えた話や遠近法と構造主義の関係についての話があります。 哲学って難しい、社会学って何って言う人にお勧めです。
0投稿日: 2007.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログたまたまなんか新書でも読もっかなー・・・と思って、手にとったのがこの本でよかった! わかりやすい、おもしろいで、知識欲を刺激してくれる一冊。
0投稿日: 2007.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ今さら「はじめての構造主義」ってのもなんですが、やっぱり分かってないので気取ってないで読んでみました。 入門書だけど骨は太いです。いろいろ腑に落ちたので読んで正解。思い切って話を絞りつつ、バックグラウンドの説明は外さないので理解しやすい。「西欧近代の腹の中から生まれながら、西欧近代を喰い破る」って言い草が好き。西欧の知の大黒柱として数学についてページを割いてるのもGJ。理系の人に読んでもらって感想が聞きたいです。『国家の品格』の人(数学者だよ)はこういう西欧内部の相克に触れずして情緒とか言うから薄っぺらいのだ。最後、この本を読んだ後はポスト構造主義や新しいものに行くのではなく、日本ではろくに揉まれていない「近代」にさかのぼってもいいんでは、という提言には、うわっ、やっぱそうですよねとうなだれてしまいました。
0投稿日: 2006.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ東工大の橋爪先生が放つ珠玉の1冊。 レヴィ=ストロースの考え方を中心に、構造主義の全体を網羅しようとした意欲作。 イトコにもいろいろあるんだなと感心させられた。
0投稿日: 2006.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほど〜、と目からウロコが落ちるような内容でした。「はじめての」と銘打っている割には、読むのは決して簡単ではないと思います。しかし、目に見えないことを学ぶということは、常に難しさが付きまとうものかと思います。 この本では特に、オーストラリアの民族の婚姻クラスの話がなかなか興味深かったです。近親相姦はなぜ暗黙の了解として禁止されているのか?真実はともかく、非常に納得できる説明があり、とても感心してしまいました。 今までの思想は西欧中心主義だから、それを「相対化」してしまえば、何か新たな糸口が見つかるんじゃないか。構造主義は、決して古い考え方ではなく、今こそ改めて徹底的に研究しなおしてみる必要があるんじゃないかと実感させられました。
0投稿日: 2006.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学の授業で紹介されたのだけど、べつの本で「今では古い考え方」と書かれていて読んでません。 でも、どこが今となっては古いのか、とか根本的な考え方を知るためにはやっぱり読んだほうがよさそう。
0投稿日: 2005.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログその名の通り、構造主義の入門書。哲学、思想の初心者がこれから構造主義とどう向き合っていこうかと考える時、その方向性を定める時、とりあえず読む本。
0投稿日: 2005.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「寝ながら学べる構造主義(内田樹 著)」が各論だとすると、この本は構造主義ってどんなの?という総論を教えてくれる。ページ数の関係から各論についての記述はレヴィ・ストロース以外はほとんどないが、それでも構造主義の構造とはなんぞや?という疑問にきちんと答えてくれている、そしてわかりやすく答えてくれてるのは良いと思う。この本を読まないで「ソシュールの思想」を読んでも多分難しかっただろう。そういう点で、この本は構造主義のスタートに読む本としてふさわしい。また哲学の本だからと言って、数学的思考から、または数学から逃げていない点も評価できる。この本を初めとして、ここからさまざまな著書を読んでいくのが良いだろう。
0投稿日: 2004.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはとてもいい。 わかりにくい構造主義をとてもわかりやすく説明してくれる。 橋爪はこういう本がいいね。
0投稿日: 2004.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ橋爪大三郎って実はバカなんじゃないかと思っていたのだけど(新聞読んだり、横市大問題とかで)当然そんなことないと思わされた。 数多ある構造主義本では、ソシュールに沿って解説され、イマイチわからんかったけど、遠近法(幾何学)、群論での解説は素晴らしくわかりやすかった。 ただ具体例に乏しくて、(新書の限界・・・)まだまだ「とったど〜!」って感じにはなれん。
0投稿日: 2004.10.17
