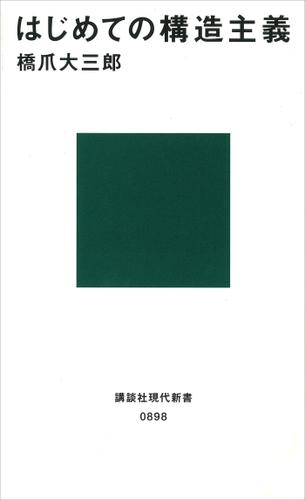
総合評価
(170件)| 48 | ||
| 56 | ||
| 34 | ||
| 2 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログはじめての構造主義 3章読み終えた。眠くて船を漕ぎながら読んでた。 図書館にいるから寝るわけにはいかないが。 クラインの四元置換群と婚姻関係(カリエラ型)の構造が全く同じ、というね。 人間主体関係なく物事を見て、共通項を見出す。 これが構造主義。 数学的な真理は制度でしかなかった。 様々な方法で真理を導くというだけで、絶対的な真理などではなかった。 サルトルの実存主義は「歴史に身を投じる」というのが本質。 人間存在は賽を投げられたようなものであって、意味などない。だから、何しても良いなら歴史に身を任せるのが一番よい、と。 マルクス主義を真と前提している主張であって、今となっては時代遅れ。 記号の価値は差異によって生まれる。(ここでいう価値は役に立つ、とかじゃなくて、意味の表出といった意味合いだと思う。 差異は音韻の違いね。) 経済的な価値も差異によって生まれる。 コミュニケーションも交換であり…… 人間は交換の生き物、と言える。(女性、財物、言葉) リゾーム……「対象を形式的に分析できないことをいう」 テクストの絶対性というのが、構造主義の考え方によって崩されてしまった。(聖書、資本論、文学作品とか。) 表面の裏側にある構造。 イデアとは少し違うが、イメージとしては似ていると思う。 あるべき姿、とかじゃないけども、表層(テクスト)を支配してる裏方というか。 トポロジー 同型写像(アイソモルフィズム) 群論 交叉いとこ
0投稿日: 2025.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の入口の入口。それくらい簡単に読める。 でも、構造主義の奥行きと広がりがデカすぎるので、むしろわからないことが多いことが自覚できる。哲学ってそういうもんだろうと思うし、そこが楽しい。 私なりの構造主義の感触↓ ・真なるものはない。唯一あるのはどこからそれを眺めているかの視点の違いとその関係性。 だから、今までの西洋哲学の発展⇔発展途上の図式は間違っている。 ・真なるものが無い世界でも、その関係性には共通的なことや分類できることがあり、それが構造主義の言う構造。 ・構造に良い悪い、善悪、発展と発展途上というような二元論的かつ一方向の流れは無い。故に、あるがままを肯定する力と、それでも構造的に問題を捉えたオブジェクティブな思考(人に責を負わせない思考)があることが、近代の哲学を否定してもなお、人間の考え方への希望となるもの。(月次な比喩だけど、多様性を知覚しそこに善悪を入れ込まない的なことかなと思えた) ・構造主義を理解するのは難しく、更に現在オンゴーイングで進んでいる分野なので、またどこかの機会で学び直したい。
7投稿日: 2025.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ橋爪先生の語り口はとても聞きやすく?読みやすく好き。 ひとつひとつの章はわかる…と思うのだが、では構造主義とは何かを説明してと言われたらふんわりしてしまう…まだまだ腹落ちしていない感じがする。もう少しじっくり勉強したい分野である。
1投稿日: 2025.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなくタイトルの印象だけで読んでみた。人類学方面から構造主義を唱えた第一人者であるレヴィ・ストロース視点の分かりやすい導入から始まる。 もちろん、これをいっぺん読んだだけで私が構造主義を一端に説明できるようになったかと言われたらそういうわけではない。 令和の世の中では、体系立てて物事を考えたり、抽象化して応用したり、それを言語化することがトレンドとして持て囃されている。その素地を作ったのがこの構造主義なのだろう。実際、この本ではソシュールによる言語学についても触れられている。 それらが普遍的な構造(Structure)として、パターン・ルールとして無意識化で成り立っている。かなり納得感がある考え方だ。 その構造主義に反人間主義だと異を唱え、ポスト構造主義の時代が訪れるのも趣がある。日常の痴話喧嘩にもありふれた「普通って何さ?」を地でやってる学問と捉えてる。これの良し悪しについてはニュートラルにいるつもりだが、その議論ができる素地として構造主義があるということは紛れもない事実。人類の素敵な発見だ。 この思想そのものより、人類がこうして年月を重ねてバトンを繋いできたということに心が動いた。
0投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ●2025年8月10日、グラビティの読書の星で紹介してる男性がいた。これと「言語が違えば、世界も違って見えるわけ」の2冊。 「ほぼ中身を見ずにタイトルだけで選んだ2冊 夏休みの間にしばく」
0投稿日: 2025.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログレヴィ・ストロースの構造主義を初心者向けに解説してくれている。数学や言語学に着想を得た人類学や神話学は、斬新で読む者を惹き付ける。終盤の読書案内も手厚く、読んでみたいなと思わせてくれる本ばかり。 未開の民族だから劣っている、文明が発達しているから勝っている、といった西洋文明主体の価値観に一石を投じたレヴィ・ストロースの構造主義。人類の文化は、それぞれの社会が持つ秩序の中で形成されていく。なので、そこに優劣の発想を持ち込むのは無意味である。 数学や科学、言語学といった記号の世界と、奇妙に対応を見せる人類の営み。個々の学問の持つ世界の広大さ、同時に、それぞれの学問が繋がりを得て一体になっていく感覚を味わうことができた。
0投稿日: 2025.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ(「BOOK」データベースより) 西欧文明中心の近代に終わりを告げ、現代思想に新しい地平を拓いた構造主義。レヴィ=ストロースの親族・神話研究の、鮮やかな方法と発想の背景に見えてくる、ソシュール言語学やモースの贈与論。そして遠近法にまでさかのぼる、数学史の水脈に隠された〈構造〉のルーツ。モダニズムからポスト構造主義への知の戦線に、軽快な文章で歯切れよく迫る。
2投稿日: 2025.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログはじめてじゃない人にも。 ある意味では「はじめて」構造主義からポスト構造主義への流れはそう読めばいいのか、となる。ポストしゃあないのか。なるほど。
0投稿日: 2025.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学や物理学の進歩が人々の思想にも影響している、という説明は明快で共感できるものだった。今後は背景にあったヨーロッパ的思想の推移を理解することで、構造主義の理解を深めていきたい。 ① 数理: ユークリッド空間におけるニュートン力学の成功が、理性による"(唯一の)真理"(↔︎啓示による真理)に依拠する時代を導いた。 思想: カントの「純粋理性批判」における問題意識には、理性による真理が強まった社会背景が関わっている。(人間が各々持つ"真理"像の解釈) ② 数理: ニュートン力学では説明できない現象が非ユークリッド空間で説明された(相対性理論, 量子力学)。これにより、唯一無二と思っていた真理が相対化された(公理(前提)の置き方次第で変わる)。 思想: 構造主義が公理の置き方次第で真理が変わる、という考えを突きつける。
0投稿日: 2025.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義と数学の関係性が非常にわかりやすかった。その関係性によって、構造主義の思想が捉えやすかった。
1投稿日: 2025.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に面白く読むことができた。レヴィ=ストロースの考え方を中心に、構造主義について様々な観点から理解できる。新たな世界の見方を教えてくれた。
1投稿日: 2025.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しかったけど、インセストタブーや神話学などレヴィ=ストロースの具体的な功績を知れて良かった。また、周辺の考え方や人物について、全体像を知ることができた。20年以上前の本だが、まったく古さを感じさせない良書。次はフーコーあたりを深掘りしてみたい。
0投稿日: 2025.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ驚きの構造主義入門書。 何度も読み返したが、その度に感動を新たにする、名著。 「構造主義は終わった」とマスコミやアカデミズムが合唱するのに対して、そんなことは笑止千万、と一喝。長嶋茂雄よろしく「構造主義は永遠です!」と高らかに宣言してみせる。 構造主義は、思想ではない。 では、何か? 構造主義は、方法論なのだ。 だから、古びることはない。 あるのは、構造主義以前と構造主義以後という方法論的時代区分だけだ。 比較するとすれば、「ニュートン以前とニュートン以後」、アインシュタイン以前とアインシュタイン以後」と言った科学史の区分だろう。 橋爪40歳、東工大の教授に就任する直前の作品。 構造主義のキモをレヴィ=ストロースを中心に明快に描いてみせる。 新書とは思えない、橋爪の思考と知見が詰め込まれた冒険の書だ。 「冒険の書」と呼ぶのは、数学、遠近法に構造の起源を見し出すという驚きの「構造主義起源論」を展開するからだ。 通常、構造の起源は、ソシュール、ヤーコブソンの言語学に求める。 その通説に対して、橋爪は、ブルバキの数学に、そして遠近法に構造主義の起源を求めるのだ。 これは、言語学起源論の強調へのアンチ•テーゼと言える。 構造主義を作ったレヴィ=ストロース自身が、その起源をソシュール、ヤーコブソンだと語っているのに、橋爪は、それを否定するのだ。 これこそ、構造主義方法論の真骨頂。 レヴィ=ストロースの無意識領域に潜む「構造」を炙り出したのだから。
1投稿日: 2024.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ語り口は軽快でとっつきやすかったが、途中、数式を例えに思想を説明してくれるあたりから、分からなくなってしまった。まだまだ勉強しなくては!と思えたので◎
0投稿日: 2024.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログアイデアは既存のアイデアの組み合わせでしか生まれないと本で読んだことがある。レヴィ=ストロースのアイデア(発見)も、言語学や数学など他の学問の組み合わせでできている。この本は、彼がどのようにそのアイデアを持つに至ったかをアイデアの元ネタから探れるようになっている。しかし、この本を読めば鮮やかなアイデアが浮かぶ訳ではない。むしろ、アイデアの元となるアイデアを深く理解して、内面化して、試行錯誤をしないと新しいアイデアは生まれないということを改めて認識させられる。
0投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログソシュール「一般言語学講義」 世界は言葉によって切り取られている。例えば、水や湯と日本語で表現されるものも英語ではWaterのみで表現されている。このように、世界から言葉を切り取って認識している(物質世界≠言葉) これを、言語の「恣意性」と呼ぶ 言語システムを複雑化することで精神世界を複雑にすることができる。言葉が何を意味するかを発展させる 音も、シニフィエもシニフィアンも対立によって規定されるわ 交換のための交換が基本、それが特殊に変化して経済が現れるにすぎない 真理は制度である。時代によって人が社会が勝手に決めるもの よって唯一の真理はなく、その時代、社会で制定される 定理は公理(それの証明が使用のないほどの定説)により証明される
0投稿日: 2024.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログPodcastから知った橋爪大三郎先生。 ご著書を読むのは2冊目。 先日読んだ川原繁人先生の巻末で対談されていたが、その際、川原先生が高校生時代に読んで影響を受けたとお話していたのがこちらだった。 今回、読書会で借りる本を物色していたら奇しくも出会えたので諸手を挙げて喜びいさんで借りて帰った。 数年前に某大学の講師の方が紹介して置いて行ったらしい。ありがたや…。 さて、構造主義やら、レヴィストロースやら、こちらもまずはここ2、3年の間にPodcastからその存在を知ったクチ。 音声を聞いているだけではなかなか理解の難しい内容だったけど、 書籍だしね、 わかんないところは戻れるしね、 何より橋爪先生も「ちょっと進んだ高校生、いや、かなりおませな中学生の皆さんにも読んでいただけるように書いてみました」って書いてあるし、 たぶんいまいち難しかった構造主義について理解が進むぞー! と、思って読みはじめた。 …いや、普通にめちゃくちゃ難しい…。 橋爪先生の語り口がとても軽妙で、文章自体は読み易くて面白いんだけど、 だからと言って内容が易しくなるわけではないんだよな。 まあとりあえず、読了ホヤホヤの今言えることは、どんな学問も全て繋がってるんだということがここにおいても痛いほどわかった。 言語学も数学も社会学も宗教も哲学も、ありとあらゆる…、 世界を知ろう、真理を追求しようと思う知的探求はどのカテゴリーであっても、なんらかの影響を受けたり与えたりしながら存在している。 ぜんぶ繋がっている。 この事実が本当に面白いなぁ。 まあでもいきなり本から入るのはやはり相当難しかったと思うので、 Podcastから構造主義について入門するのは私にとっては良かったな。 (というかPodcastを聞いてなかったら手にもしてないと思うけど) ただ、どの書籍から入るのがいいかもし聞かれることがあるなら、間違いなくこちらをおススメする。 この先に進むための参考文献についてもちゃんと記してくれているので、大変親切で優しい本です。 橋爪先生のお茶目な語り口もツボります。
0投稿日: 2024.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログインタビューデータの質的分析は主観的にならざるを得ない.インフォーマントの語りも事実を語っているわけではなく主観に引きずられている.そのようなデータをどう分析すれば良いかと言う点で構造主義が関係してくる.というわけで,構造主義の超入門書を読んでいるが『はじめての構造主義』がとてもわかりやすい. この本は数学や物理学と結びつけて「構造」を語っているのだが,客観的に存在する物体を見ている主観的な私(主体)との関係で世の中が見えていることを示していて,私(主体)の視点が異なれば客観的な世の中の見え方も変わること,その中で不変なのが構造であると言っている.ユークリッド幾何学で記述できる我々の世界と,脳に投影されている射影幾何学の空間は数学的な変換で関連付けることができる.変換によっても不変なのが「構造」である.こういう説明を読んでなるほどと思った.
0投稿日: 2024.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義のこれ以上ない入門書。『寝ながら学べる構造主義』も読んだが断然こちらがオススメ。中高生のうちにこれを読んだ人が羨ましい。 第1部はレヴィ=ストロースの伝記とソシュール一般言語学の系譜。ここは他の本と大差ない内容だが、構造人類学の方法論の記述はかなり詳しい。本書は中高生向けに特別易しく書いてあるらしいが、橋爪大三郎の文章は本当に読みやすい。 そして本書の白眉は第2部、構造主義のルーツ。構造主義の入門書でよくあるのが、ヘーゲル→マルクス→サルトルの近代哲学の流れを概説した上で構造主義の革新性を説くもの。これも興味深いが、そもそも実存主義に至るまでの哲学の流れが非常に難解だし、ゴリゴリの哲学と言語学、人類学の対決というとどうにも話が噛み合っていない印象を受ける。本書の最もすぐれた点は、これとパラレルに展開する数学史(あるいは、西欧の知の歴史)の流れから構造主義を語るところだろう。 ここで下手くそな要約を垂れ流すのは無意味だろうから、是非とも橋爪先生の文章で読んでいただきたい。キリスト教の凋落に伴う科学の隆盛、中高レベルの数学・物理の成立史、そしてその根本を揺るがす非ユークリッド幾何学の登場、「数学は哲学」たる所以の現代数学。一つ一つの物語それ自体が冒険活劇のように面白く、それでいて構造主義の解説としてこれ以上なくピッタリくる。久々にこんなに面白い読み物に出会った。 すっかり説明してしまった後で「これまで構造主義を紹介した人びとは、ソシュール以来の言語学とのつながりを、少し強調しすぎていたようだ。」(185P)と締める。橋爪先生カッコよすぎます。 あまりにも良い本すぎて、中高生のうちに読んでいればと悔しい気持ちにさえなった。良い本の証だろう。 一方で、こんなにわかりやすく解説されてしまうと、なんだ構造主義ってたったこれだけのものなのか、という気にも。内田樹の方の本にも、そういえば現代社会で構造主義は当たり前になりすぎていてもはや意識されることは少ないとあった。 むしろ「たったこれだけの」考え方に衝撃を受けた近代主義の方が、今となっては驚きだろう。 橋爪先生はこういう感想までもお見通しなのか、あとがきには「もういちど近代主義にさかのぼっていくというのも、面白いんじゃないだろうか。」(230P)と。いやはや参りました。
0投稿日: 2023.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログなんで読もうと思ったのか忘れてしまったが、構造主義について知りたかったのは確かだ。 構造主義とはなにかといえば、変換を通して不変の構造を見つける方法だと言えるだろう。ただし、細かい部分は本書を読んで欲しい。 参考図書にガードナーがピアジェとレヴィ・ストロースを並べた本が挙がっていた。ピアジェは子どもの発達を研究した心理学者だ。未開社会が文明社会に劣っていないのと同じく、子どもも大人に劣っていない。それを思うに、当時の西洋社会では権威の相対化とでも言える大きな流れがあったのだろう。他にもクライエント中心療法を研究したカウンセラーのロジャーズがいる。 ここからは私事だが、現在、社会福祉の勉強をしている。ピアジェもロジャーズも社会福祉向けの心理学に登場する人物だ。おまけに60年代の公民権運動に端を発するエンパワメントは社会福祉の分野では重要な概念だ。しかし、人類学者レヴィ・ストロースは登場しない。上記の概念を構造主義を中心とした大きな流れとして把握せず、小手先の技術として利用しようとしたことが日本の社会福祉の低迷の一因だと思える。
0投稿日: 2023.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ2023年9月17日読了。古典ラジオの構造主義の回で言及のあった参考資料を読んでみた。古典ラジオで内容を聞いていたせいか大学のゼミで構造主義を学んだ下地のおかげかはたまた著者の力量か、大変読みやすく構造主義のごく浅い部分についてと思うが理解できた。人間が自分の感覚で世界を理解しようとすると「未開社会は資本主義社会に進化すべき」「この世には理想の『イデア』があり万物はそこに向かう」「唯一神がすべてをデザインした」という考え方に陥りがちだがそうではない・あらゆるものの構造を理解することでその価値や機能は相対化できるのだ、とする考え方が構造主義なのだな…現代に生きる我々からすると当たり前ともいえる考え方だが、これを生み出したレヴィ=ストロースの仕事はものすごい人類史上の快挙だと思う。
4投稿日: 2023.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログカジュアルな文体で読みやすいが、意図的にやっているにしろ脱線が少し多いように感じた。 構造主義への理解は深まったと思う。 特に最後尾に記載されていた通り、思想は批判の積み上げなのだから、それ以前の思想も把握していないと完全に理解できないのに、日本においては、海外の最新の思想を「流行」として断片的に取り入れるモダニズムの延長が根付いているために、構造主義やマルクス主義といった思想について深く理解がなされない、というのは強く感じる点だった。
0投稿日: 2023.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログむ、ムズい……。 特に数学に関する部分は文系の私にとってはジャングルの道なき道を分け入っていくような辛さでほとんど理解できなかったが、ヨーロッパの超頭の良い数学者たちが2000年かけて導いた理論を、オーストラリアの“未開”の原住民たちがとっくの昔から使っていたという話にはとても感動した。
1投稿日: 2023.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりやすいけど、マルクス主義が何かを事前知識として入れとかなきゃいけない。いわゆる歴史(ヨーロッパ史)至上主義的なのに限界を感じて生まれたのが構造主義なのか。自文化を相対化し、異文化を深く理解する方法論。これに尽きるかなと。 橋爪さんの本ははじめてだったけど、文体に可愛げのある正直さとユーモアのある表現が隠れていて、読んでいてクスッと笑えた。ポスト構造主義と構造主義の繋がりとか、すごく言葉を噛み砕いて説明してくれるからありがたい。
0投稿日: 2023.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて構造主義を知るにはとてもちょうどよかった。構造主義にも、構造主義以前の思想にも、構造主義よりあとの現代思想にも、自分なりの思想を作ることにも、興味を持てるようなつくりになっていた。
0投稿日: 2023.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ分かりやすいとは言っても読めばすぐ分かるものではないので、何度も読んで理解を深めたい。 ただ構造主義を理解する上で、数学を取り入れる事はなるほどと感じた。
0投稿日: 2023.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ同じく構造主義に関する基礎的事項の説明がある『寝ながら学べる構造主義』(内田樹)を最近読んだためどうしてもそちらとの比較論になりがちなわけではあるが, 極力目を瞑ってほしい ちなみに結論から言うと解りやすさと話題の広範さについては『はじめての構造主義』が勝ると感じた まずは数学, 何よりも数学, 構造主義を論ずるには数学は不可欠なのだ 本著ではユークリッド幾何学以降のさまざまな幾何学を位相変換の概念なども交えながら, 簡単に紹介しただけではあるが個人的には大変刺激的であった 対してそのような内容は内田氏の書著では全く触れられておらず, 私自身も数学がこれほど密接に現代思想に関わっているのかと面食らってしまった 加えて, 当時の西洋思想家たち(レヴィ=ストロース,サルトル,フーコーetc...)の数学的/自然科学的素養のレベルの高さを鑑みると, 改めて日本の哲学及び(経済学などを除いたゴリゴリの)文系の学者における数学的/自然科学的素養の欠如を思い知らされた 思想の入門書というものは得てして、その主張や歴史的立場の説明に注力してしまうものだが, 本書は「ソシュールの恣意性原理」, 「ヤーコブソンの二項対立原理」等, 一見無関係にも思える言語学の変遷について論じられている それらの事柄がいかにレヴィ=ストロースの構造人類学及びのちの構造主義に多大な影響を与えたかについてある程度(ホントに, ある程度, すんなりはわからねぇよ)理解することができた 一方の神話分析に関してはレヴィ=ストロースのそれと同様、あまりにも再現性が低くちょっとやそっとでは初歩的理解さえままならなかった 第四章『構造主義に関わる人びと ほんのスケッチ』もとても魅力的だ 彼らの主張を一つ一つ説明しているわけではないが(不可能だと思う), フーコーやアルチュセール, デリダらがどんな人間であるかについて, ほんの一欠片ではあるがまさに「スケッチ」的に描かれている 最終的には当時の日本の思想に対する批判になってしまっていたが、その痛烈な批判もこの国の本質を言い当てており思わず唸ってしまうものだった 遥か彼方の未来, 構造主義が完全に過去のものとして葬られた時, まだこの日出る国が残っていたとしてもその国民はおそらく1960〜1980年代と同じように流行り物に飛びつくだけの中身のない雑食動物となるだろう...
3投稿日: 2023.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義を理解したかといえばまだそうとも言えないけれど、好奇心をくすぐられて一気に読めたのは確か。歴史や数学とのつながりはたいそう面白くかった。
0投稿日: 2023.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログレヴィストロースのバックボーンも含めた傑解説書 おそらくそれまでもあった、一部の人々の精緻な世界の見方を「構造主義」として体系化したことのインパクトは、今では想像できないがおそらく相当なものだったと思う
0投稿日: 2022.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ馬鹿でもうっっすら分かったような..気がする..? 言語学ぽいと→恣意的に区切った時に見つけられる二項対立の束 数学っぽいと→置き換え可能なもの集合の中に見られる、不変の共通項
0投稿日: 2022.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義とはなんだろう?という疑問を持ったので読んでみた。ざっくりと構造主義に関して骨組み的な知見が得られたように感じる。が、同時にまだまだ足りないのでやはり勉強をしなければならないな、とも思う。
0投稿日: 2022.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田さんの方がわかりやすい。 とりあえずレヴィ=ストロースの考え方がどのように生成されていったのか?をまとめた本。 数学や視点の話などがあり、面白かった。
0投稿日: 2022.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義、まだよくわかりません。 しかし構造主義について知りたいなら読んで正解だったと確信はしています。ブックリストもついてるし、何より興味を持たせるという意味で優れているなぁと。 なんとなく腑に落ちそうなんだよな、自分の理解があと一歩な感じ。 とにかく関連書物を読んでいこうと思います。 次は→町田健 「ソシュールと言語学」
0投稿日: 2022.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ自民族中心主義の色眼鏡があることの意識を促し、それを取り払う助けとなる思想が構造主義だと理解した。競争社会に身を置く、我々現代人にとって一読すべき価値ある本だと感じた。
0投稿日: 2021.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
橋爪大三郎著「はじめての構造主義(講談社現代新書)」(講談社) 1988.5.20発行 2021.8.31読了 1988年に刊行された講談社現代新書のベストセラー。ずいぶん前に買ってずっと読まずに放置していた。最近、田島列島著『水は海に向かって流れる』で、作者の田島列島さんがレヴィ=ストロースを読んでいたことを知り、家にあるそれ関係の本をひっぱり出してきて、あまり期待もなく読んでみたら、これがまた面白い! さすがに高校生には難しかろうと思うが、構造主義を知る上でまさに必読の書だと思う。 内容はほぼ100%、構造主義の祖と言われるレヴィ=ストロースの解説で占められていて、まさに私にとって打ってつけだった。もちろん、その思想の土台部分にあるソシュールの紹介も忘れていない。意外だったのは、レヴィ=ストロースが代数学から多くの影響を受けていたという点だ。文化人類学と現代数学が影響しあっているだなんて不思議なこともあるものだ。構造主義は一種の方法論だけれども、一体何が何の分析に役立つかなんて実際試してみないと分からないものだ。この世界は意外なところで変に繋がりあっている。 非常に有意義な読書タイムだった。 URL:https://id.ndl.go.jp/bib/000001923397
0投稿日: 2021.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義は、主体性を排除しようとする考え方である。公理の上に成り立つ定理は真理のように感じるが、それは、主体的に選ばれた公理上での制度に過ぎない。構造主義は、主体を前提とした考え方から、ある対象となるものを、無意識的な、集合的な現象として捉え、その構造を理解しようとする考え方である。
2投稿日: 2021.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ思いがけずに本書を手にすることになってしまった。橋爪さんの本は過去に何冊か読んでいるが、どれも分かりやすく面白く解説してくれる。本書もそう。本質を理解しているからなんだろうなと思う。構造主義が西欧中心主義を否定する形で出てきたと言う下りは納得感があり、スッと入ってきた。もちろん細部は難解で一度読んで分かるものではないと思うが、こう言う思想があるんだと言う事は勉強になった。しかしフランス人は思想が好きだし、学校でも沢山勉強させられると聞いていたのでまた腑に落ちた感がした。
0投稿日: 2021.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構面白くわかりやすい。 レヴィストロースの、ソシュールの系譜を継ぐ部分と数学的系譜を継ぐ部分はどちらも「構造依存的である」ということを人類学(異文化の説明)に応用したのだろう。と理解している。(言語は「いす」と発音した時、おそらく発声というか音の響きとか考えると同じ「いす」ではないのに私たちはその音をいつも同じ「いす」だと認識できる。数学の方は、じゃんけんで「グーチョキパー」も「きつね庄屋猟師」でも同じルールだと発見できる。それは構造に依存しているから。) それで「親族の基本構造」と「神話の構造」を表した。
0投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局、わかったような気がしたのは、西欧近代化が正とするマルクス主義に対して、「未開」と言われる地では、親族、女性の交換というか、結婚することのルールが、近代西欧が行ってきたことを、とっくにわかって実践していた。 西欧での真理は、神の真理と数学的真理があるが、これを数学的にレヴィ・ストロースが証明した。 そして、著者が一番言いたかったのは、日本には地に足のついたモダニズムがないところに、権力に対抗するマルクス主義が入ってきたが崩壊し、ポストモダンへと流れた。しかし、明治に輸入された日本のモダニズム(近代思想〕ではなく、日本は旧世代の思想と対決して、日本が自前で世界に通用する制度と責任の思想を考える必要がある。 だから、異文化を深く理解する方法論として、構造主義が役に立つから、学ぶべきだ、と言いたいのだろう。
0投稿日: 2021.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
言葉は知っているが、そもそも思想なのか理論なのか……。いちどゼロ地点に戻ろうと手にした本。構造主義の旗揚げとされるレヴィ=ストロースを中心に解説。神話学やら代数学やら、途中、私はなんの本を読んでいるのかと戸惑いつつ、最終ページの「自文化を相対化し、異文化を深く理解する方法論」という一文で、ゼロから一歩ほど踏み出せた気はする。新書一冊で理解できるものではないが、次に進む道しるべとしては最適に思えた。
0投稿日: 2021.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ同僚の先輩に勧められた本。 正直半分くらいしか理解できなかったけど、面白いと感じれることはできたのでよかったのかなぁ。 自分の読解力の低さにショック。
1投稿日: 2021.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「はじめての構造主義」読了。 先月「lGBTを読み解く クィアスタディーズ入門」を読んだが、LGBT(このように括ること自体が問題でもあるが)の言葉と、その「意味づけ」がどのような変遷を経て結びついたのかを知った。 その流れで、やはりソシュールやフーコー、アルチュセールと言った人々の本は読まなければ、と思い、早速先日図書館に行き上記の著作やバルト、デリダ、ピエール・ブルデューといった人々の本を借りたが、何故か(笑)レヴィ=ストロースの本だけ手が伸びず、(なぜかはわからないが、デュルケムの本でかなり頭が疲れた経験が妨げた可能性もある笑) 、でも彼の議論がわからないと他の人の議論もわからないかもなぁ、そうしたら本著が構造主義の草分けである彼にフォーカスしているということで拝読した。 完全に備忘録になるが、この本によるとレヴィ=ストロースの功績は、単純な進化論に立つ西洋思想への批判と同時に未開社会が「非理性的」であるというレッテルがはられつつも、その背後には極めて高度な関係性の婚姻があることを発見したことが一つ。そしてもう一つが神話学の研究を経て、テキストの背後に構造というものが存在すること、つまりテキスト自体が「読む」ものにしてしまったことである。つまり、真理なるものがはじめから存在しない、ということである。 このように簡潔にまとめてしまったけれど、人間の「主体性」とか「真理の追求」を信じていた人からすると、レヴィ=ストロースの議論がいかに衝撃的だったのかは想像を絶する。頑張って梯子を登っていたけどいきなり風で梯子ごと落ちるみたいな。 いま、フーコーの本も同時的に読んでいるけれども、ソシュール・レヴィ=ストロース・フーコーの流れを考えると先ほど申し上げた「LGBTを読み解く」の言っている意味が腹落ちする、 と言った意味で非常に面白かった。 はじめての構造主義 (講談社現代新書)
0投稿日: 2020.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の背景にあるもの。 歴史の変化、相対化。 現代数学の発展。 よく分かった。 近代思想に対する強烈なカウンターパンチとしての構造主義。 市民から思想を立ち上げることができるか。
0投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義、レヴィストロース、という言葉や人物くらいは知ってるけど、そういや構造主義が何なのか全くわからない…というような私のような人が最初に読むのにいい本。 堅そうななりをしてすごくわかりやすい。わかりやすいがでは構造主義とは何か、と聞かれても説明が難しい。中世近世と切り口を変えた比較論から導きだされる、人間の主体性の否定?何か違う。 構造主義を説くには構造主義だけを語ることはできず、というわけで中世思想からの流れも説明されているが、これもよかった。先に読んだデカルトもあり、こういう思想に沿ってるのか!と納得。これを踏まえて方法序説を再読しようかな。
0投稿日: 2020.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義がどれくらい近代思想にとって破壊的だったかよく分かる本。 哲学書の類いはほぼ読んだことが無かったが、詰まることなく読み進められた。分かりやすい。
0投稿日: 2020.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ1988年刊の本です。 その時代の空気を思い出させる、特有だった軽妙な文体がなつかしい。 ジーンズのリーバイ・ストラウス(リーバイス)を フランス語読みするとレヴィ=ストロースなのを今さらながら知ったのでした。 という枕からはいりますが、 今回読んだのは、人類学者で構造主義の本丸、 レヴィ=ストロース中心の構造主義解説書なのでした。 構造主義の入門書は通算二冊目になります(入門から先に進めません……)。 レヴィ=ストロースの人類学を見ていけば、 最近読んだ本たちによくでてきた、 黒人奴隷の問題の出口がわかってくるかもしれないという予感の元、読み進めていきました。 まあ、構造主義自体もう何十年も前にでてきたものなので、 そのころからすでに開かれた出口ではありますが、 今でも解決されていない問題ですし、 かといってそれ以降よい方向へ向かわせてもきただろうから興味がありました。 構造主義の「構造」とはなんぞや、といえば、 人間でも物事でも社会でも、その根っこの部分の仕組み、みたいなもの、 と言えるでしょう。 因数分解していって残ったところで眼前にあらわれる法則、と言い換えてもいいです。 そして、付け加えるならば、 それははっきりと言葉にできないし、 はっきり見えません。 それが「構造」なんだと理解しています。 たとえば、言葉にするとき、文章にするときに、 その元となる動機があると思うんです。 それは言葉になる前の状態なので、 ふわふわどろどろと形もなく、まだ名付けられてもいない。 そういうところを動機とし、スタートとして、 言葉が生まれる。 もうちょっと厳しく言うと、 言葉に当てはめる。 要は言葉という枠にはめることなので、 言葉になる前のふわふわどろどろしたものと、 言語化したものは等価ではありません。 まあ今回はそこのところはいいとして、 そのふわふわどろどろしたものを見つめてみる行為と、 「構造」を見つめてみる行為はちょっと似ているんじゃないでしょうか。 そんな見方をして知覚するのが「構造」なんじゃないでしょうか。 「構造」というものについては、まあ、そのくらいにしておきます。 レヴィ=ストロースの構造主義的人類学で見えてきたのは、 欧州中心主義の否定です。 それは、奴隷にされたアフリカの黒人や、 アメリカ先住民、オーストラリア先住民、アジア人など、 いわゆる未開の(あるいは未開とされた)民族への差別を許さないものでした。 欧州人は自分たちが優れている前提で彼らを頂点とするヒエラルキーを作りました。 そして、レヴィ=ストロースは、そんなヒエラルキー由来の、 欧州人が自分たちよりも下位に位置する民族たちからはいくらでも搾取をしていいのだ、 という植民地主義の間違いを露わにしたのです。 著者の橋爪さんは、 「西欧近代の腹のなかから生まれながら、西欧近代を食い破る、相対化の思想である」 と本書のはじめのほうで構造主義を表現していました。 そのくらい、衝撃的な思想なんですね。 本書はレヴィ=ストロースの仕事をなぞっていってくれています。 そこで、こういうレヴィ=ストロースの知見がでてきます。 「価値があるから交換する」ではなく「交換するから価値がある」でもなく、 「ただ交換のために交換する」というものです。 それをレヴィ=ストロースは、 人類学からコミュニケーション論に持っていったそうですが、 その点も僕には大いに肯けました。 その知見を通して私たちの日常生活を見てみると、 人は、内容なんかなかったとしても、他者に声をかけることが実は一番の目的 っていう欲求的な所(「構造」)に行き着くからです。 僕もそう思う人ですし、そのような小説を書いたこともありますから、 なお肯きました。 また、以前にリップマン『世論』を読んだときにでてきて、 そうだよなあ、と思った知見ですが、 人それぞれ考え方が違うから、それぞれが同じ対象に対して違う真理を見てしまう、 というのがありました。 人は見たいようにそれを見る、っていうものですけれど、 どうやらリップマン以前に、カントがその哲学で、そこをいろいろやったんですね。 本書で解説されていました。 だから多人数でいろいろな考え方をぶつけあう議論をしよう、っていうのが ネット世界でもありますけれど、そういうものを含めてカント的ですよね。 それと、ひところ言われた「集合知の高みにたどりつけるのでは」っていう考え方よりも、 カントの言うような、 「みんなで話し合えばとりあえず中の上くらいのところには落とせる」 という考えを前提としたほうがうまくいきそうです。 一人や二人じゃたどりつけない高みを、みんなの知恵をだしあって目指そう! っていう志で議論していくと、唯一の真理を目指すみたいなことになる。 そこで、たとえばイカロスの話。 彼は翼を得てどんどん太陽へと目指して飛んでいき、 そのうち太陽熱でロウ製の翼が溶けて墜落死した神話だけれど、 比喩的に読めてくわばらくわばらと思っちゃいます。 あと、今ちょっと出てきましたけれど、 「真理」についての構造主義の態度も「なるほど」と思えます。 「真理」とは「制度」だっていうんですが、 そこへの理路がおもしろいです。 ここに書き連ねるのは大変なので(何ページも写してしまわないといけない)割愛しますが、 とても説得力がありました。 と、まあ、そんなところです。 構造主義って実はその考え方が、けっこうこの日本の、今日において、 断片的にだけれど、いろいろなところに食い込んでいるように思えました。 それは個人個人のなかでも、 ちょっとしたところに構造主義的な思考回路を持っていたりするという影響を受けている。 こういった思想関係、近代から構造主義、そしてポスト構造主義なんかを 入門書レベルであってもみんなが体系的に学んだら、 たぶん思いのほか国民の生きざまが骨太になっていく、 そんな予感めいた思いを抱きつつの読了となりました。 おもしろかったです。
1投稿日: 2020.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
twitterのTLにフェミのひとが、「女性が男にできるだけ平等に行き渡る世界」を男の勝手な妄想、と批判する投稿をよく見かけるようになった。確か、構造主義はそういうことを扱っていたはず、と読んでみた。 インセスト・タブーは女性の実用価値を廃して交換価値にするためで、「価値」がうまくまわらないと社会がなりたたない。フェミのひとが激怒しそうな内容で、本書でもカッコでフェミのひとに配慮した断り書きが挿入されている。
0投稿日: 2020.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の生みの親レヴィ・ストロースがどのような経緯を経てこのような考え方を主張するに至ったかを易しく解説した本。ソシュールの言語学の方法論を応用。
0投稿日: 2020.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ#はじめての構造主義 #橋爪大三郎 著 #講談社現代新書 西洋文明を否定した構造主義。当時、どれだけ多大な影響を与えたか、その破壊力がよくわかる1冊。構造主義は人類学、言語学との関わりが深く、これらの話がメインになっていて、初学者にはちと厳しいかもしれません。タイトル通り、平易には書かれていますが厳しそうなら #寝ながら学べる構造主義 のあとに読むと抵抗なく読めると思います。 “構造主義は、人間のあり方を、歴史(といって悪ければ、西欧思想の色めがね)抜きに直視する方法を発見した。” “構造主義くらい人間に理解を示した思想は、これまでにないんじゃないか。これぞ人間主義の究極のかたち、と言わなければ嘘だ。” “名前にごまかされてはいけない。「構造」といっても、骨組みやなんかではなく、もっと抽象的なもののことである。そして、たぶん、現在数学にいう<構造>の概念と、いちばん似ているようだ。” “「未開人だ野蛮人、文明にとり残されて気の毒だと、偏見でものを見るのはよそうではないか。彼らは、繊細で知的な文化を呼吸する、誇り高い人びとだ。われわれのやり方とちょっと違うかもしれないが、そして、物質生活の麺では簡素かもしれないが、なかなか”理性”的な思考をする人びとなのだよ。」” “世界のあり方は、言語と無関係ではなく、どうしても言語に依存してしまうのである。...言語が異なれば、世界の区切り方も当然異なるのだ。” ““価値あるものだから交換される”のはない。その反対に、“交換されるから価値がある”のである!” “社会がまずあって、そのなかにコミュニケーションの仕組みができる、というのじゃない。そうではなくて、そもそも社会とは、コミュニケーションの仕組みそのものだ” “構造主義は、心理を“制度”だと考える。精度は、人間が勝手にこしらえたものだから、時代や文化によって別のものになるはずだ。つまり、唯一の心理、なんてどこにもない。” #本 #読書 #読書倶楽部 #読書記録 #本屋 #本棚 #本が好き #本の虫 #読書タイム #古本 #古本屋 #文庫 #文庫本 #活字中毒 #哲学 #構造主義 #ポスト構造主義 #人類学 #言語学 #レヴィストロース #アルチュセール #ラカン #フーコー #バルト #デリダ #ソシュール
0投稿日: 2019.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義とは本質的にはどんな思想なのか、「構造」とは一体何なのかという点には他の入門書と謳う本を読んでもずっと引っかかってたけど、この本でその部分が少しは掴めたような気がする。構造主義が数学に源泉を持つという話は所々で目にするけど、その関連性をここまでしっかり解説してる本に出会ったのは初めてだった。結びに書かれている日本思想のあるべき姿なんかも含めて凄く得るものが多かった。これを起点に色々と広げて行きないなと思わせてくれた。
0投稿日: 2019.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ”「ブリコラージュ」が載っていない。なぜだろ!? <抄録(抜き書き)> ・私の思うに、「構造」をどこかにある実体みたいに考えてしまうから、わかるものもわからなくなってしまうんじゃないか。名前にごまかされてはいけない。「構造」といっても、骨組みやなんかでなく、もっと抽象的なもののことである。そして、たぶん、現代数学にいう〈構造〉の概念と、いちばん似てるようだ。(P.28) <きっかけ> 人間塾 第74回読書会の『レヴィ=ストロース入門』を理解するための副読本として…”
0投稿日: 2019.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
正直言ってしまえば難易度は高いものです。 はじめての~ととは付いていますが 優しい代物ではないぜこりゃ。 だけれども、こんな考え方が世の中には 存在し、それを席巻する一方で どんな欠点があったのか、というのを 知る意味では興味深いものがありました。 最後の人物紹介は… おいおいちょっと待ちなさい、 夭折している人多いじゃないか!! 分からなくても、文章が良いので 面白くは読めるはず。
0投稿日: 2019.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「構造主義」という、言葉は聞いたことあるものの、具体的な定義や意味についてよく理解できていなかった代物について、初学者の私でも「少しは理解できたかな」という気持ちにさせてくれる本。 構造主義の始祖であるレヴィストロースの半生の解説から始まり、レヴィストロースがどのような人々と出会い、影響を受けたか、またその結果、なぜ当時の人類学とは違う論理体系(=構造主義)を構築することができたのかについて、分かりやすく、飽きさせない洒脱な文章で解説してくれます。 私のつたない理解で構造主義を一言で要約してしまうと、「抽象化」であると捉えられました。従来型の人類学では、事実を機能により意味づけすることで理解しようとしていたけれども、その分析には限界があった(具体例は後述)。そのような状況の中、言語学や数学の世界で発展していた「構造化」(=事実を抽象化し、その重要な要素をとらえる手法)を人類学に適用することで、単純な機能の説明ではなく、その事実がなぜ・どのように構成されているかを理解できるようにしたのだと感じました。 本書では、構造の具体的な例として、人類学における婚姻可能な範囲の問題と、神話学の体系化の大きく2つ挙げています。ここでは、特に面白かった婚姻可能な範囲の問題について触れます。 世界中の様々な文化・部族において、近親相姦はタブーとされていますが、その範囲についてはまちまちです。例えば、日本ではいとこの結婚はOKですが、ある部族では、いとこの結婚は認められず、またある部族では、いとこでも母方の交叉いとこの娘(=母の男兄弟の娘)はOKだが、父方の交叉いとこの娘(=父の女姉妹の娘)はNGなど。従来型の機能に着目した意味づけでは、父方と母方のいとこに違いは認められず、これは意味不明で説明がつかないことでした。 レビィストロースは、この事実を解釈するにあたり、「そもそも婚姻は親族や部族間での女性の交換である」という仮説を立てます。この仮説に従うと、母方の交叉いとこの娘は自分の所属する部族とは別の部族の出身となり、結婚相手の候補となりえますが、一方で父方の交叉いとこの娘は、他部族に嫁いだ母親の、その娘ということになり、女性が嫁ぎ先から送り返されているということになり、婚姻を女性の交換ととらえた際には認められないことになります。このようにぱっと見の事実を分析者の主観に基づき分析するのではなく、主観を排除しその裏にある構造に基づき事実を分析することで、より高度な理解が得られるというのです。 構造主義について勉強してみたい人の最初の本には最適だと思いました。
0投稿日: 2019.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1章 「構造主義」とはなにか 第2章 レヴィ=ストロース―構造主義の旗揚げ 第3章 構造主義のルーツ 第4章 構造主義に関わる人びと―ブックガイド風に 著者:橋爪大三郎(1948-、神奈川県、社会学)
0投稿日: 2018.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本当に初めて構造主義の本を本だが、書中のどこからどこまでが構造主義なのか、理解できなかった。しかし、興味を持てたので、関連する文献にも目を通したくなった。
1投稿日: 2018.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
構造主義については100分de名著で扱われてから気になっていた学問。それを、こんな私にも理解しやすい言葉で表現してくれる学者だな、と思っていた橋爪大三郎が解説。やはり分かりやすかった。構造主義のプリコラージュについては、大きく言及されてなかった(理解が及ばなかった)から、もうちょっと調べたい。神話の章は、再読したい。親族に関する内容はかなり興味深かった。 最後の章に言及されていた"日本的"という部分、もう少し突き詰めて考えてみたい。日本は思想を輸入しては分かった気になっているだけなのかも。 思想と宗教に関して、もう少し詳しく勉強しないと、やはりスッキリしない。自分のモノになった感じが、まだしない。
0投稿日: 2018.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
◯事前知識 ・構造主義 人間やイデオロギーなどあらゆる現象を細分化し、客観的で普遍な構造を追求 例:人間(男と女) ◯1章:構造主義とは何か ・火付け役(構造主義の四天王) クロード・レビィ=ストロース -> サルトル(マルクス主義)と論争 ラカン フーコー アルチュセール ・構造主義とは何か 歴史や西欧的な人類学を否定し、もう一度位置づけ直す。 現代思想(ポスト構造主義を含む)は構造主義を通ってきている 《マルクス主義→構造主義→ポスト工場主義》 ◯2章:レビィ=ストロース ・レビィ=ストロースに生い立ち ベルギー生まれ 哲学を学ぶ 人類学に転向、3年間ブラジルに渡る(よくフィールド調査をする) 戦争の後、アメリカへ亡命 言語学者ローマン・ヤーコブソンと出会う ・レビィ=ストロースが長年抱いていた疑問 「機能主義人類学のように親族を捉えていくだけでは、少しも原住民の魂に迫ったことにならない。」 機能主義人類学:全て機能で説明しようとする。AがBのために役に立ち、BがCのために役にたつという様に目的/手段の連鎖が一列に並んでいる考え方。 近親相姦や親族呼称など機能主義人類学では説明できない謎がある。 ・ヤーコブソンによる解答(解決方法) ソシュールの言語思想 言語学者ソシュール 印欧祖語の母音の研究で有名 しかし、言語の歴史的研究ではなく、人間と言語の深いつながりの秘密を明らかにしようとした 言語はまず体型(日本語、英語など)があり、音(シニフィアン)と意味内容(シニフィエ)で成り立つ 言葉が指すものは、世界の中にある実物ではなく、社会・文化的に決められているだけである ・レビィ=ストロースはソシュールの言語思想の中の音韻論を人類学に応用 「親族の基本構造」という書物を出版。 内容は「親族は女性を交換するためにある」という仮説を実証するもの。 モースの考えに影響される→近親相姦など「交換するからタブーである」(社会関係が関係する) 交換すること、言葉を話すことが「人間らしさ」 論文集「構造人類学」を出版 これが人類学だけにはとどまらず、大きな影響を与えて「構造主義」が知られるようになる 〜ここからは「後期のレビィ=ストロース」といわれる 神話学に没頭 人間精神の隠された<構造>を研究 神話学とテキスト(聖書など)を代数学的操作をすることで解体して、本来テキストが言いたいこと(神のお告げ)ではなく、本当の<構造>を探った マルクス主義も「資本論」や「共産党宣言」などのテキストがあることから、なしくずしに成立しなくなる これによって近代ヨーロッパの知の伝統を支配した、主体の形而上学がいよいよ解体していく では神話学の<構造>とはなにを指すのか→3章へ 人類学者モース 「価値があるから交換する」のではなくて「交換するから価値がある」 音韻論とは 言語学・・・音韻論、統語論、意味論に分けられる 音韻論・・・音韻音は言語がどんな音から成り立っているのかを明らかにするもの 統語論・・・文法 意味論・・・意味 音素・・・日本語をローマ字にした時に一文字にあたる 音(素)が似ているからといって、意味が似ている訳ではない(例:inuとisu) どういう音からできているかではなく、人々がどう区別しているかが大切 ◯3章:構造主義のルーツ ・構造主義に至るまでの思想上の系譜 遠近法と構造主義を結ぶものが数学 遠近法→射影幾何学→ヒルベルトの形式主義→ブルバギ(数学者グループ)の<構造>→レビィ=ストロースの<構造> 遠近法は見る場所・時間によって物体が違って見える 射影幾何学とは図形がスクリーン上にどのように表れるかを研究する学問 視点を移動すると、図形は別の形に変化する。それでも変化しないような性質のものを<構造>とよぶ。 <構造>は図形の本質のようなもので目に視えず抽象的なものである。 ・神話学の<構造> <構造>と(数学的な)変換とは、裏腹の関係にある。 だから、神話に<構造>があると考えるのと、神話はつぎつぎ変換されていくものだと考えるのとは、一緒のことである。 レビィ=ストロースは主体の思考(ひとりひとりが責任を持つ、リセ的で自覚的な思考)の手の届かない彼方に、それを包む、集合的な思考(大勢の人々をとらえる無自覚な思考)の領域が存在することを示した。それが神話である。神話は、行っての秩序 - ここの神話の間の変換関係にともなう<構造> - をもっている。この<構造>は、主体の思考によって直接捉えられないもの、「不可視」のものだ。 ◯4章:構造主義に関わる人々 ミシェル・フーコー(1926-1984):哲学者。レビィ=ストロースの構造主義に、歴史を持つ社会に対しての説明を付加した ルイ・アルチュセール (1918-1990):フランスの共産党員。マルクス主義の資本論を構造主義の手法で読んだ ロラン・バルド(1915-1980):フランスの記号論の草分けのひとり ジャック・ラカン(1901-1981):フランスの精神分析学者 ジュリア・クリステヴァ(1941-) ジャック・デリダ(1930-):ポスト構造主義 ◯5章:おわりに 構造主義とは・・・自文化を相対化し、異文化を深く理解する方法
0投稿日: 2018.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ軽やかな語り口で構造主義が分かる。 この手の入門書は「一冊読めば分かる!」みたいな顔をするが、この本はレヴィ=ストロースに多くを割くなど、自覚的に入門書たろうとしており、多くの本が紹介され今後の学習につながるよう工夫されているのに好感が持てる。
0投稿日: 2018.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義とは以前から名前だけ聞いていたが、つかめていなかった。池田清彦など構造主義生物学なるものもあって関心があった。歴史からの解放こそ現代的な思想ということだろうか。そもそもそれ以前の思想には生物学由来の進化論の影響が大きいわけだが、生物学は今も進化論が基本になっている。構造主義生物学が何を言いたいのかはなんとなく想像ができるようになった。 古代ギリシャ哲学に少し触れて感動していたが、現代にはやはり現代思想こそふさわしいのは当然で、時間はかかるだろうが学んでいきたい。
0投稿日: 2018.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログレヴィストロースの親族、神話研究の概要が理解できた。構造とは 視点を変えても 変わらない本質。視点を変えて 見て、視点の差異を無視することで 構造が浮かび上がる 構造は目に見えない抽象的なもの 。数学の話が 構造主義の理解に役立った。少し 構造主義が見えてきた 未開の地の親族の基本構造について、結婚は交換であり、近親相姦が否定されて 初めて社会が広がる という文章には 驚いたが、未開社会の集団思考の自然調和から 見出されたシステム と理解した。利害や必要に基づくシステムではなく、交換のための交換に基づくシステム。
0投稿日: 2018.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ『デリダ』を読む前に前段階として読みました。 そうした「おさらい」で読むには、ちょっともったいない内容で、構造主義というよりもレヴィ=ストロース入門といった感じでしょうか。新書でここまでできるのであれば、分厚い本って何だろうという感じがしないでもない。 ぼんやりしていた理解度が一気に高まる。素晴らしい。
0投稿日: 2018.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ覚悟していたよりは易しく書かれていてほっとしたけれど、やはりさっぱりわからなかった。が、構造主義の、この字くらいはぼんやり見えたような。 未開の部族でも現代人も思考が進化したというより、共通した構造があるということ?え?違う?
0投稿日: 2017.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ・宇宙論か仏教関係の本を読んでいて勉強しようと思ったが、何も覚えてないので難しかったんだと思う、二度目読書中。1回目読んだときに響かなかったところが、2回目読むとかなり異なる気づきを得られることが多い。(この本だけではないが)、ただ、結局構造主義がなんであるか理解できるレベルにはならなかった。 ・西欧近代は、知らず知らずのうちに、東洋やいわゆる「未開」の社会を、劣ったもの、自分たちより遅れたものとみなしてきた。それがどんなに根拠のないことか、はっきり示せるのが構造主義である。 ・人間の人間らしいあり方は、これまで西欧近代が考えてきたより、もっとずっと広いのだ。今まで片隅に追いやられ、正当な光の当たらなかったところにも、いくらも人間的な文化のしるしを見つけ出すことができるのだ。こう、構造主義は主張する。 ・日本人はふつう、世界が「山」や「水」や「ナイフ」や「犬」や…からできあがっていると信じている。しかし、それは、日本語を使うからそう見える、ということにすぎないらしい。英語だとか、他の言語を使って生きてみると、世界は別な風に区別され、体験されることになるだろう。つまり、世界のあり方は、言語と無関係ではなく、どうしても言語に依存してしまうのである。われわれはちう、言語と無関係に、世界ははじめから個々の事物(言語の指示対象)に区分されているもの、とおもいがちだ。ところが、そんなことはないので、言語が異なれば、世界の区切り方も当然異なるのだ。 ・シーニュ(記号)=シニフィエ:「犬」という記号が言わんとする意味内容+シニフィアン:「犬」という記号を成り立たせる音のイメージ(ソシュール) ・三すくみ(じゃんけん)の関係は、変換の一種である同型写像によって保存される、<構造>だ。ここでも、写像と<構造>とは、やっぱり裏腹の関係になっている。このように考えると、ジャンケンの仕組みを理解するのに、「紙が石をつつむから、パーの勝ち」というような説明は、あまり関係ないことがわかる。三すくみということだけが大切で、「紙が石をつつむ」とか「キツネが庄屋を化かす」とかいうのは、ことがらの表層(<構造>に関係ない、どうでもいいこと)にすぎない。そういう表層にとらわれないで、いろんなジャンケンのの間の変換関係を調べ、その<構造>をとりだすのが大切である。 ・ゲーデルの不完全性定理:数学が完全であることを、その数学自身によって示すことはできない ・要するに、オーストラリアの原住民の結婚のルールは、抽象代数学の、群の構造とまったく同じものなのだ。 ヨーロッパ世界が、えっちらおっちら数学をやって、「クラインの四元群」にたどりつくまでに、短くみても二千年かかった。つい最近まで、誰もそんなもの、知らなかったのである。ところが、オーストラリアの原住民の人々は、誰にも教わらないでも、ちゃんとそれと同じやり方で、大昔から自分たちの社会を運営している。先端的な現代数学の成果と見えたものが、なんのことはない、「未開」と見下していた人々の思考に、咳回りされていたのだ。 ・レヴィ・ストロースは、主体の思考(一人一人が責任をもつ、理性的で自覚的な思考)の手の届かない彼方に、それを包む、集合的な思考(大勢の人々をとらえる無自覚な思考)の領域が存在することを示した。 ・構造主義-自文化を相対化し、異文化を深く理解する方法論-
0投稿日: 2017.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
構造主義の説明として遠近法や数学を用いるのは成る程と思った 日本の様に文理が明確に分かれているのは概念の理解にはちょっと不利かと思う
0投稿日: 2017.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログもうこれで構造主義の入門書は何冊読んだことか。 要するに理解したい、そして実践したいと切望していながら、よくわかっていないんでしょうな。 でも、20年近く前に書かれた本書を読んで、今まで以上に構造主義の輪郭がはっきりしてきた。残念なことに、これまでの構造主義に関する本を読んだ後の感想はいつもこれなのだが。 けれども今回は、構造主義をこれまで以上に相対化できた。つまりこれって構造主義的な考えができるようになったってことかしら。 構造主義の入門書としてはこれまで読んだ中でベストだと思います。
0投稿日: 2017.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログでもつまり「構造」ってどういうものなの?!ってなりました、すいません。繰り返される思考パターンといったってそれっていったい具体的にどういうことなの〜??? 途中の婚姻の話と白川郷の話は面白かった。 思想の話を読むとなんでも論理的に説明しようとするのがそもそも間違いなんじゃないかっておもうんですけど、そんな批判はお門違いでしょうか。
0投稿日: 2017.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ評価できません。 なぜなら途中からさっぱり分からなくなったからです。 難しすぎて僕の頭では理解不能です。
0投稿日: 2017.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ思想書は理解するのが難しい。 でも数学や歴史と、レヴィ=ストロースの思想に到達した経緯を解き明かす下りは、絡まった糸を解くように鮮やか。 構造主義を理解するよりもむしろ、筆者のように盤石な論理構成で他者に主義主張を伝える能力がほしい。
0投稿日: 2016.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ兼ねてから気になっていた構造主義に関する入門書として読んでみた。中高生を含む初学者向けに書いたとのことで、確かに読みやすい。 構造主義は社会の相対化を導くということで、勝手に主客反転の思考プロセスで生まれたのかと思っていたが、言語学・科学・数学をルーツに持つことに驚き面白く読めた。 ただレヴィ・ストロースに偏っていること、この思想の影響が表層的にしか語られていないこと、提言が出版当時(1988年)の社会状況に依っていることなどには少し物足りなさを感じたので、「寝ながら〜」の方も併せて読んでみたい。
0投稿日: 2016.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会学者・橋爪大三郎による構造主義の入門書。1988年出版であるが、内田樹の『寝ながら学べる構造主義』(2002年)と並ぶ構造主義に関する好著として、いまだ評価の高いロングセラーである。 本書では、兎角わかりにくいイメージの現代思想・“構造主義”の本質を、「人間や社会のあり方を、歴史(と言って悪ければ、西欧思想の色めがね)抜きに直視する方法」、「西欧を中心としてものをみるのをやめ、近代ヨーロッパ文明を人類文化全体の拡がりのなかに謙虚に位置づけなおそう、という試み」、「西欧近代の腹のなかから生まれながら、西欧近代を喰い破る、相対化の思想」と、極めてシンプルに言い切っている。そして、構造主義の生みの親と言われる仏の文化人類学者・レヴィ=ストロースがそうした発想を得るまでの、フィールドワークと研究の過程・成果を具体的に説明している。 著者は「構造主義の代表格をひとりあげなさい、と言われたら、レヴィ=ストロースの名前を出しておけば間違いない」といい、ミシェル・フーコー、ルイ・アルチュセール、ロラン・バルト、ジャック・ラカン、ジュリア・クリステヴァ、ジャック・ラカンら、その他の構造主義者ついても触れてはいるものの、それぞれ3~4ページ程度である。 一方、内田氏の『寝ながら学べる構造主義』は、フーコー、バルト、レヴィ=ストロース、ラカンを構造主義の四銃士と位置付け、それぞれの思想を均等に解説しており、同じ入門書でも異なったアプローチをしている。 ただ、本書のわかりやすさは特筆すべきであり、個人的には、はじめて構造主義に触れるのであれば、本書から入ることをお勧めしたい。 (2005年7月了)
0投稿日: 2016.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義人類学者のレヴィ=ストロースの思想を中心に、構造主義の考え方をわかりやすく解説している本です。 レヴィ=ストロースは親族構造を分析することで、社会の交換システムとしての「構造」を発見しました。その後の彼の関心は、しだいに神話の分析に移っていきます。そこでは、物財の交換システムではなく、言語をメディアとする、意味のコミュニケーションシステムとしての「構造」が追及されることになります。 本書はこうした「構造」概念の変遷を概観し、さらに数学における「構造」との関連についても触れられています。射影幾何学や抽象代数学以降の数学では、変化を通じて保存される普遍的な性質に目が向けられることになりました。そうした数学的「構造」の理解が、レヴィ=ストロースを中心とする構造主義の発想のもとになっていることを、本書では直観的に理解できるよう、工夫を凝らして説明しています。
1投稿日: 2015.05.14学際的視点
人類学に数学モデルを応用した面白い視点の構造主義を紹介。著者の守備範囲が広いことから来る思い切りの良さと、軽妙な語り口が魅力の入門書。
1投稿日: 2015.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「寝ながら学べる構造主義」よりおすすめ。レヴィストロースに重きをおいた構造主義解説書。「はじめての~」と銘打っているだけあって比較的分かりやすく、なんといっても面白い。じっくり時間かけて理解しながら読まないといけないが、読み終わるころには構造主義とはなんたるか大体分かる。自分の場合は、最後の最後にやっと様々なことが一気に繋がった感じでした。
0投稿日: 2015.02.11良書です
学生時代に読みました。読みやすい語り口で、でも要点はしっかり頭に入るというか。 行列式の例は、なーるーほーどー!と、頭の中でパラダイムシフトが起きました。 知的刺激に満ちています。
2投稿日: 2015.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログMon, 21 Sep 2009 中心はレヴィ・ストロースの親族の基本構造についての話なんですが,そこから構造主義のイメージについて書いています. レヴィ・ストロースの格好いいところは, それまで曖昧模糊としてきた,人類学,広くは社会学,人間科学の世界に,その奥底に 骨格構造としての 変換群のような形式を見いだす事も,出来うることを示した事ではないでしょうか? この本自体は,すでに20年ほど前の本なのですが, 「構造主義」はある意味でブームだった時代があり,それを踏まえて書いているものだと思うので,今読んでも問題ない本だと思います. レヴィ・ストロースにはモースの「贈与論」やデュルケムの「分業論」が影響を与えたと述べられてます. また,デュルケムは,最近,読んだ本でも何度か出てきて,気にかかっている. あと,構造主義の他の人,特にフーコーなどについては,まったく読んでいないので,また学ばないとなと思ったのでした.
0投稿日: 2015.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の”構造”とは何かが、読み進めていくうちにスッと頭に入ってくる。最初は人類学と哲学との関連がよく呑み込めなかったが、非常にうまく料理されていて消化できた。 incestに関する禁忌の法則など、身震いするほど面白い。大学で自然科学を専攻し、理系人間として生きてきたのだが、本当はこういう勉強がしたかったのだと改めて気づかされた。
0投稿日: 2014.10.05レヴィ=ストロース入門
『はじめての構造主義』と銘打つものの、八割方はレヴィ=ストロース。一割はソシュール。最後の一割でその他の構造主義者や自称ポスト構造主義者を扱う感じです。分かり易く、レヴィ=ストロースの著書の内容を解説しています。最初は遠近法だの、幾何学だのがどうして構造主義に関係するのか想像つきませんでしたが、読み終わってみれば納得。構造主義関係の文献リストも付いて便利です。
5投稿日: 2014.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が若干十歳だった頃、湾岸戦争が始まった。ミサイルが降り注ぐ街を映すテレビを見ながら、父は自分にあの戦争の仕組みを解説してくれた。最後に父は「さて、アメリカとイラクと、悪いのはどっちだろう」という疑問を自分に投げかけた。自分は悩んだ末に「どちらにも立場があるのだから、一概に善悪の基準で判断できない」といったことを拙い言葉で伝えたと記憶している。 「はじめて」と銘打つだけあり、本書は構造主義が誕生に至るまでの過程とその成長をわかりやすく解説してくれている。カタログ的な構成であるため、構造主義の体系を俯瞰できて、はじめて構造主義に触れる人にも、考えを整理したい人にも良い本なのではないかと思う。 本書を読みながら、1991年当時のいち小学生にさえあのような構造主義的な見方をさせた、知的変動のうねりの大きさに思いを馳せていた。キリスト教圏ではない日本に生まれた自分には、その転換の意味が本当の意味では理解できないのかもしれない。しかし、きちんと構造抽出を行うことができれば、その意味を捉えることができるかもしれない。小学生のあの頃に自分が知らず知らずのうちに身に着けていた視点の源流を探しに出かけたいと思った。
0投稿日: 2013.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ口語調で構造主義についてわかりやすく解説されている。 内容自体はかなり難しいが、勉強の第1歩として適切かと思う。
0投稿日: 2013.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義の成り立ちを理解する本。社会学分野だけでなく、数学の分野の話もあるので、途中抵抗がありながらも、学問同士の垣根を取り除いた話が読めるので良い一冊。 哲学を学ぶときに知識を蓄えるような読み方でなく、提唱者の思考過程を追う楽しみを知った
0投稿日: 2013.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこれが構造主義だ!と、一言では定義できないのが構造主義だということと、レヴィ=ストロース(構造主義を始めた人)の仕事の概要はなんとなくわかった。 元言語学徒でありながら構造主義も知らないのか、とお叱りを受けそうだけど、生成文法は研究手法としてのアメリカ構造主義を否定する形で登場したという背景があって(ゴニョゴニョ)……で、さらにアメリカ構造主義はヨーロッパの構造主義とは違うんだとかなんとかかんとかワケワカメ。 「諸現象に共通する、数学的な構造に注目してそれを抽出する」という考え方は、生成文法でもXバー理論などに見受けられるし、統語演算をMergeのみに帰する最近のMP理論も、基本的な考え方は“構造主義的”といって差し支えないと思った(本書を読む限りでは)。そもそも、生成文法が想定する「普遍文法」という概念(全ての自然言語には、その言語の種となる共通のシステムが存在する、という考え方)からして、すごく構造主義的だ。 生成文法こそ最先端の構造主義だ、と言えなくもなさそうだけど、誰もそんなことは言わない不思議。 わかったような、わからないような。
1投稿日: 2013.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ小難しいイメージを持っていたので読むまでためらっていたが、読んでみえると口語体で書かれた文章が読みやすく、簡単な内容でわかりやすかった。意外にも2日で読めた。ソシュールの言語学やらブルバキの数学やら関連する人々とその考え方にも興味が沸いた。
0投稿日: 2013.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすくて、部分的には理解できるけど、全体として理解しにくいのは、構造主義そのものが複雑だからかな。 ヒルベルトの形式主義→ブルバキの「構造」→レヴィ=ストロースの「構造」っていう流れで、レヴィの構造の発想は数学を基にしているという。 さらにソシュールの言語学、ヤーコブソンの音韻論、そしてモースの贈与論を参考にする。 文化人類学のレヴィが『親族の基本構造』で親族は女性を交換するためにあると仮定して、関係が構造っていう感じかな。それぞれの親族関係が先にあって、女性を交換することで関係も成り立っていくというか。 「主体の思考(ひとりひとりが責任をもつ、理性的で自覚的な思考)の手の届かない彼方に、それを包む、集合的な思考(大勢の人びとをとらえる無自覚な思考)の領域がある」ってことだそう。 関係ないけどヤーコブソンの子音三角形がpとkとtから成ってて、看護で口腔体操で発音する「パ・タ・カ」は子音の代表なのかなと気になった。
0投稿日: 2013.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
平易な言葉で読み易いが、分かり易いかと言われると人によって微妙なところかもしれない。それにしても良書ではある。主にレヴィ・ストロースの思想から構造主義を読み解く入門書である。 レヴィ・ストロースの<構造>を、根底にあるブルバキ派の<構造>に従って抽出する橋爪氏の解説は面白い。また個人的には、ポストモダン信仰は舶来主義の延長ではないかという氏の指摘は鋭いと感ずる。
0投稿日: 2013.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識ゼロから構造主義を「なんとなく」わかるための入門書かな。タイトルどおり、はじめてのひと向き。噛み砕いた解説と、話し言葉に近い文体が読みやすい。
0投稿日: 2013.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ1988年(昭和63年)発行の構造主義の入門書新書版。 発刊当時は画期的な本で、図を入れながら新書の範囲で構造主義を解説している。80年代は、構造主義ってなに?海外では有名になっているぞ?みたいな状況で、その本質がわかっていない人が多かったような気がするので、その中でエッセンスを簡単に解説した本の価値は高かったと思う。今や図解や説明が簡単になったので構造主義の入門書としては本書にこだわらなくてもよいと思う。 しかし、著者の橋爪氏は、四半世紀後に「不思議なキリスト教」でもヒットを飛ばすわけで、本当にすごい人だと思ってしまいます。
0投稿日: 2013.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義とポスト構造主義についてかいつまんで分かりやすく解説したもの。数学の群の考え方が未開の土地での婚姻ルールになっているなど、知のありかは文明の如何に寄らないなどが描かれている。 人間の関係性を幾何学等の数学で解き明かせるという気づきについて知ることができる。
0投稿日: 2013.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013.01.09 一回読んでしっかり理解できるほどあまくはないが、ざっくりと構造主義の輪郭をつかむことはてきた。もう一度読んでポイントをつかむ。それから、関連図書もチェックしたい。
1投稿日: 2013.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログいかにもキャッチーな切り口でソシュール、レヴィ=ストロース、神話論、記号論などの取っ付きにくい構造主義の思想をコンパクトに概観した入門書。今でも読まれてるかな?
0投稿日: 2012.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ主にレヴィ=ストロースの定義した「構造」の解説、そしてレヴィ=ストロースが「構造」を発見するために必要となった諸概念と、「構造」を理解するための周辺知識を優しい文体で解説する本。もちろん親族体系と神話の構造分析についても触れている。そして西洋近代主義であるマルクス主義と実存主義をどのように批判し乗り越えていったのか、どうしてそれらを批判することになったのかを示す。フーコーやソシュールの言語学なんかにも触れている。 もっとも、親族体系と神話についてはどちらも扱いは軽く、特に後者は軽くさらうような感じなので、より詳しく具体的な分析手法について知りたければ小田亮の『レヴィ=ストロース入門』(ちくま新書)がオススメです(こちらは読みにくいと思いますが)。 特にこの本が良かったと感じたのは、現代数学で言う「構造」という概念からレヴィ=ストロースが文化人類学の「構造」を発想した、という部分の解説だった。なぜ現代数学的「構造」が親族体系と関係するのか、どのように応用されているのかを丁寧に、数学的な具体例も踏まえて解説している。 他の書籍では、「レヴィ=ストロースは数学から発想を得た。数学の抽象的思考と何か関係があったのかもしれない。」くらいしか説明がありませんが、何か関係があったどころの話ではなく、構造主義の根本的な考え方と密接に関係している、ということが本書から分かる。 数学における抽象概念である「構造」とはまず何であり、それをレヴィ=ストロースがどのように援用したのか、その周辺の話も含めて1章を割いている。 これが個人的には大変わかりやすく、本書を読んでよかったと思える点であった。何故他の論者はこの部分に触れずに構造主義を語ろうとしているのか、全く不思議に思えてくる。 巷では「『構造』という概念は分かりにくく勘違いされる傾向にある」と言いつつ、肝心の「構造」の定義についてはボンヤリとしか語っていない。勘違いされるのはそういう態度のせいではないんでしょうか。数学的な観点の話が抜けていてはそりゃ理解できまい、と思う。 自分はこの本を読んで、「構造」が全くわかりにくい概念であるとも感じなかったし、数学的な背景があるなら(定式化されているはずなので)もっと理解しやすいではないか、と感じた。実際に本書の解説するレヴィ=ストロースの「構造」は、かなり明快に理解することができた(本書の解説は著者独自の理解かもしれない、という批判は別問題として)。 構造主義に関する本はいろいろ読んだけど、結局なんだかわからずモヤモヤするなあ、という人にはオススメです。 最終章である第五章の、構造主義とポスト構造主義周辺の議論の捉えなおしについては、自分にとってはあまり聞いたことがなかった論点なのでとても興味深かったです。 ちなみに、先も述べたように、小田亮の『レヴィ=ストロース入門』(ちくま新書)を読むと、レヴィ=ストロースが「構造」を具体的にどう研究で用いているのかが分かると思います。 他に、内田樹の『寝ながら学べる構造主義』(文春新書)。こちらはどちらかと言うと構造主義を中心としたフランス現代思想に関する解説で、構造主義そのものの解説ではない(と思う)。構造主義が結局何であるのか、その根底にあるアイデアについては解説されていないのでまずわからないとは思うが、上記の本でもあまり詳しくはない周辺の論者(ソシュール、フーコー、バルト、ラカンなど)の考えたことが解説されている。 『はじめての構造主義』→『レヴィ=ストロース入門』→『寝ながら学べる構造主義』の順で読むとすっきりするかもしれない。(自分は真逆の順で読んでしまったので後悔してます…) 1冊目で「構造」の定義と周辺概念を理解して、2冊目で具体的な研究手法を見つつ周辺思想との関連に触れて、3冊目でフランス現代思想全体を見渡す、という感じになると思うので、3冊読めば「結局構造主義って何なの/何だったの」という疑問はそれなりに晴れると思います。
0投稿日: 2012.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ東大受験の現代文対策に挙げられてたり、 東大の某ゼミで参考文献に指定されているほどの 本格的入門書。 「おませな中学生でも理解できるように書きました」 とのことだが、 1000%無理だろっ!!! その中学生は金田一か銀狼です(IQ180以上)。 率直な感想を述べるなら、小難しいことをあくまで 「やさしい言葉で」書いただけであり平易にはなってない。 よって結構わからない。 速読タイプの僕が読むのに一週間費やしました。 そして本書の半分を構造主義誕生までに費やし、 結局のところ構造主義ってなんなのかは…イマイチ… (てか論理が飛躍してたり、話のつながりおかしくない?) と、ここまで書いたところで ほかの人のレビューを見たら↓ 「本当に中学生でもわかる」 「二時間で読めた」 「珠玉の入門書」 うーん、本気で俺は 頭が悪いんじゃないかと心配になってきた… それくらい社会の上積みの方しか読まない本なんだろう。 そう信じよう。。
0投稿日: 2012.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
名前の通り初学者向けの本です。主に構造主義者の一人レヴィ・ストロースについて取り上げています。構造主義は大雑把に言うと、異なる制度や法則から共通の関係を抽出し分析するものです。彼がどんな過程を経て構造主義という物の捉え方にたどりついたかもストーリー調で言及されており、一緒に考えながら読み進めることができます。
0投稿日: 2012.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ源流としてのソシュールとモース、そしてストロースのコミュニケーション三要素などには感嘆する。数学を柱としたギリシャから近現代までの歴史理解にも役に立つ。あとがきで表明される著者の懸念、近代を体現してこなかった日本のこれからのためには歴史学習が改めて必要なんだろう。構造主義じたいが歴史を排したとしても。 フッサール現象学への対抗思想としての、「書き言葉」の問題、デリダ(エクリチュール)、フーコー(ディスクール)、クリスティバ(テキスト)、この辺にはあたってみなければ。
0投稿日: 2012.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代思想の重要な柱である「構造主義」についての入門書。構造主義の祖といわれるレヴィ=ストロースの人類学、その発想の元となったソシュールの言語学、更に、ヨーロッパ世界の「理性による真理」の源流である数学(的思考法)の歴史に触れていく。難解に見えるが、物凄く平易な言葉(ときには砕けすぎに感じるくらい)で解説されており、読み易く分かり易い。数学史のくだりも、ごく最低限しか数式が現れない親切仕様。ただ、最後にもう一度くらい「構造主義って結局何なの?」というまとめが欲しかったなぁ、と。
0投稿日: 2012.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに読み直しました。前回理解できていなかった所(嫁とそれ以外の違いとか)が明白になり、有益な読書でした。だいぶ視界が開けてきた。それにしてもこの本は本当によくできています。入門書とはこうあるべきなんだなあ。
1投稿日: 2012.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ中三ぐらい?のときに国語の教員にすすめられて読んだ本。 構造主義って何?っていう中学生でもちゃんと理解できる本。 良書。 しかし構造主義なんてもはや死語とか言っちゃいけない
0投稿日: 2012.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログレヴィ・ストロースを軸に、構造主義がわかりやすくまとめられている本。素人の私には、特にソシュールの言語学についての解説が目から鱗。非常に読みやすく、思わず一気に読了してしまう。構造主義の最高の入門書。
0投稿日: 2012.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログすごいよかった!巷であふれる思想の混乱がすっきりする本。ポスト構造主義に突入する前にレヴィストロースと代数系をもう一度復習したい
0投稿日: 2012.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ比較的新しい思想である「構造主義」について書かれた一冊。 本著も入門としてはオススメながら、寝ながら構造主義、もおすすめ。
0投稿日: 2012.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ神話学が成功したからといって、あらゆるテキストにその方法が適用できるわけではないのでは?とか、レヴィ=ストロースの手法が鮮やかすぎる、他の人にはなかなか真似できないってんなら、構造主義者ってのは何してる人なの?とか、いくつか疑問も残ったけど、大体どんなもんかってのはわかった気がします。以下はまとめ ・流行の変遷 マルクス主義-社会は歴史法則に支配されている(資本主義→共産主義の流れ、革命が起こるべくして起こる等)。革命の成功が歴史によって約束されているなら、わざわざ参加して危険な目にあう必要もないという考えに陥りかねない。そのとき、個人の生きる意味は?マルクス主義は社会全体が一度に救済されることを目指すが、その代わり一人ひとりの運命・生きる意味などは蔑ろ(一人ひとりの人格に大きな価値を置くキリスト教と相容れない部分)。 ↓ 実存主義-人間の存在にはもともと理由がない、理由がない(無駄死にする)ならいっそ歴史に身を投じてみる。その方がはるかに値打ちのある生と言える。ただ、ニヒリズムに陥らないために、前提としてマルクス主義の言う歴史の存在を信じる必要がある。 ↓ 構造主義-マルクス主義のいう歴史、19世紀的なものの見方(社会が単純・原始的な段階から複雑・機能的な段階へ進歩・発展していく)はヨーロッパ人の偏見。人間や社会のあり方を歴史抜きに直視する。西欧中心のものの見方をやめ、比較方法論によって近代ヨーロッパ文明を人類全体の中に謙虚に位置づける。 ・〈構造〉のルーツ 絵画における遠近法-ひとりひとりの視点(主体)からみた世界を忠実に再現する。主体や客体、認識ということが十分意味を持つ。 ↓ 射影幾何学-視点が変わると図形は別の形に変化する(射影変換)。その時でも変化しない性質が〈構造〉(e.g.正方形を射影変換すると正方形・台形・たこ形・ただの四角形に変化。これら4つの四角形全ての共通点「四つの線分に囲まれている」)。 ↓ ヒルベルトの形式主義-公理(数学者の間の約束事にすぎない)をきちんと示し、様々な公理系から同じ幾何学を導けることを証明?(説明ほとんどなし) ↓ ブルバキの〈構造〉-フランスの数学者グループ。グループの一人、アンドレ・ヴェーユがレヴィ=ストロースの協力者。〈構造〉の概念を核にして数学の統一像を描き出そうとする?(説明ほとんどなし) ↓ レヴィ=ストロースの〈構造〉-レヴィ=ストロースの神話学はブルバキ派の〈構造〉の概念をそのまま神話の領域に持ちこんだもの。 ・親族研究(インセスト・タブー) 女性そのものの価値を直接味わえるようだと交換のシステム(社会)が成り立たなくなる。 親族(女性の交換システム)が成り立つためにはそれが否定されなければならない。同じ集団のメンバーにとって、女性の利用可能性が閉ざされなければならない。近親相姦が否定されて初めて人々の協力のネットワークが広がっていく。 “価値があるから交換する”んじゃなく、”交換するから価値がある”。”タブーだから交換する”んじゃなく、” 交換するからタブーである” 社会がまずあって、その中にコミュニケーションの仕組みができるのではなく、そもそも社会とはコミュニケーションの仕組みそのもの。 交換は利害や必要に基づくのではなく、純粋な動機(交換のための交換)に基づく。交換のシステムの中では女性や物財や言葉が「価値」あるものになるが、それらがその「価値」ゆえに交換されるわけじゃない。あくまで交換のための交換が基本で、それが特殊に変化・発達していった場合にだけ、経済(利害に基づいた交換)が現れるにすぎない。 交換のシステムは機能の観点から捉えきれない。→機能主義人類学を批判。 人々の利害が交換の動機になっていない。→マルクス主義とも対立。 ・神話学 オーストラリアの原住民の結婚のルールが抽象代数学の群構造と全く同じものだったことから、「人間の思考は一直線に進歩していくわけではなく、人間の思考のレパートリーはあらかじめ決まっていて、それを入れかわり立ちかわり並べ直しているだけかもしれない」と考えたが、親族研究では人間の思考以外の物質的要因が多すぎるので、人間の思考のレパートリーの宝庫であろう神話でそれを証明しようとした。 「未開」社会の人びとは「考えるのに便利 good to think」な自然の事物を使って彼らを取り巻く世界や宇宙について考える(野生の思考)。ありあわせの材料を使って考えていくので日曜大工のようなブリコラージュになる。その意味不明なエピソードに隠された〈構造〉(野生の思考に支えられた「神話論理」、個々の神話の間の変換関係)を明らかにした。 神話学はテキストを字義通りに読まない。それはテキストの表層に過ぎなくて、本当の〈構造〉はその下に隠れている。テキストをずたずたにしていろいろな代数学的操作を施しても構わない。(テキストの解体)→キリスト教における最高のテキスト(聖書)の権威を否定し、”神”をもかき消す。いったん構造主義の洗礼を受けた後ではどんな権威あるテキストも成立しなくなる。 神話学を理解するのに主体は関係ない。(主体不関与)→これまでの近代主義の思想(人間を主体とみる考え方)に打撃を与えた。 主体の思考の手の届かない彼方に、それを包む、集合的な思考の領域の存在を示した。〈構造〉はひとりの主体にこだわって世界を認識しようとしているあいだは現れてこない。 ・構造主義批判 〈構造〉は空間的なため、時間的な変化を捨象している。 人間の主体性がどこかに行ってしまった。 「作者の言いたいこと」を括弧に入れてしまう。
1投稿日: 2012.03.09
