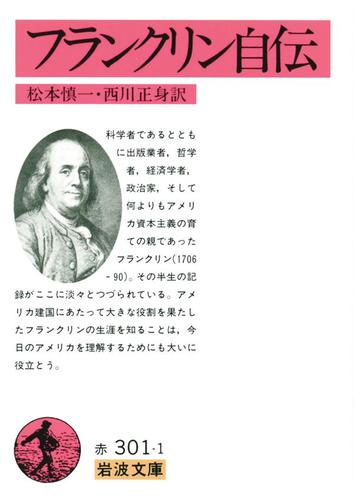
総合評価
(72件)| 18 | ||
| 29 | ||
| 14 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカの父の一人といわれるベンジャミン・フランクリンの回顧録。勤勉さや正直に生きることの大事さを伝えている。またアメリカ国民の元々の性質を理解するにも良いとされていたため読んでみました。
0投稿日: 2025.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ## 感想 「勤勉と節倹の徳」 この本をまとめるなら、この言葉になる。 印刷、消防、大学設立、病院建設など、公のために骨を折り、果てはアメリカ独立運動の立役者として、後世に大きな影響を与えたベンジャミン・フランクリン。 「私はいままでの生を初めからそのまま返すことに少しも異存はない。」 そう言い切るフランクリンの人生における成功の秘訣」は、『勤勉と節倹による徳』だと言う。 真面目に働き、無駄なことに時間とお金を使わない。 そうすることで信用を得られ、成功に繋がっていく。 こうした考え方は、以前読んだ渋沢栄一の『論語と算盤』に近いものがあると感じた。 私たちが生きる現代は、フランクリンが生きた時代に比べて、はるかに多くの情報が世界中を飛び交い、人類は発展したように思う。 しかし一方で、人類が歩んできたために生まれた問題が山積されている。 自分だけが儲かれば良いというのではいけない。 人が生まれるのは長い歴史の中で先祖がその時々で懸命に生きてバトンを繋いできたからであって、そのバトンは次世代に繋いでいかなければならない。 人が生きるのは、それぞれができる何かしらの形で、世界に対して良いものを残して、次に繋ぐことだと、私は思う。 私は今、勤めてきた会社の中で新事業を立ち上げる立場にある。 これまでにお世話になった方々に報い、そして次世代に良い形でバトンを渡せるように、自分の仕事の時間を使いたいと考え、社内で手を挙げ、自ら望んでその立場に身を置いた。 あくまで会社に雇われている身ではあるが、だからこそできる時間とお金の使い方がある。 私の場合はそれで世界に貢献するべきだと考えている。 本書にこんな言葉がある。 「時間をむだ使いするな。時間こそ、人生を形作る材料なのだから」 これからはより一層、自分の時間を世界を少しだけ良くするために使いたいと気の引き締まる一冊になった。 ## メモ 私はこの幸運な生涯を振返ってみて、時に次のようなことが言いたくなる。「もしもお前の好きなようにしてよいと言われたならば、私はいままでの生を初めからそのまま返すことに少しも異存はない。ただし、著述家が初版の間違いを再版で訂正するあの便宜だけは与えてほしいが」そうした便宜が与えられれば、ただ間違いを訂正するだけでなく、生の玉命の悪い出来事を工合の良いものにかえることが、あるいはできるしょうからだ。(p8) 同じ町にいま一人ジョン・コリンズという本好きの青年がいて、私はその男と仲よしになった。私たちは時々議論をしたが、二人とも議論が大好きで、互に相手を言い負かしたいと心から願ったものだ。ついでながら言うが、この議論好きという性質はともすると非常に悪い癖になりやすいもので、この性質を実地に生かすとなると、どうしても人の言うことに反対せねばならず、そのためにしばしばきわめて人付きの悪い人間になり、こうして談話を不快なものにしたり、ぶちこわしたりしてしまうほかに、あるいは友情がえられるかも知れない場合にも不愉快な気持を起させ、恐らく敵意をさえ起させるのである。私にこうした議論好きの癖がついたのは、父が持っていた宗教上の論争の書を読んだからである。その後私の見たところでは、思慮ある人物は選にこの悪癖に陥らない。(p24) 兄や他の連中が食事のために印刷所を出て行くと、私はひとり後に残り、大急ぎで軽い食事(それはたいていビスケット一つかパン一切れと、一つまみの乾葡萄か菓子屋から買って来るパイーつ、それに水一杯ぐらいのものであった)をすませ、みなが帰って来るまでの時間を勉強にあてることができたからだが、飲食を節するとたいてい頭がはっきりして理解が早くなるもので、そのため私の勉強は大いに進んだ。(p27) ただ謙遜な遠慮がちな言葉で自分の考えを述べる習慣だけはこれを残し、異論が起りそうに思えることを言い出す時には、「きっと」とか、「疑いもなく」とか、その他意見に断定的な調子を与える言葉は一切使わぬようにし、そのかわりに、「私はこうこうではないかと思う」とか、「私にはこう思われる」とか、「これこれの理由でこう思う、ああ思う」とか、「多分そうでしょう」とか、「私が間違っていなければこうでしょう」とか言うようにしたが、この習慣は、自分が計画を立ててそれを推し進めて行くにあたり、自分の考えを十分に人に呑みこませてその賛成をうる必要があった場合に少からず役に立ったように思う。いったい談話の主要な目的は、教えたり教えられたり、人を喜ばせたり説得したりすることにあるのだから、ほとんどきまって人を不快にさせ、反感を惹き起し、言葉というものがわれわれに与えられた目的、つまり知識なり楽しみなりを与えたり受けたりすることを片端から駄目にしてしまうような、押しの強い高飛車な言い方をして、せっかくの善を為す力を減らしてしまうことがないよう、私は思慮に富む善意の人々に望みたい。(p29) 理性のある動物、人間とは、まことに都合のいいものである。したいと思うことなら、何にだって理由を見つけることも、理窟をつけることもできるのだから。(p58) 彼は相変らず飲みつづけ、毎土曜の夜には、この気違い水のために、せっかく稼いだ給料の中から四、五シリングも支払わないではいられなかった。こんな費用は私にはまったく不要だったわけである。気の毒にもこうして職工たちは、いつまでたってもうだつが上らないのである。(p75) 人はみな世の中の舞台に登場するにって、それぞれ適当な時期を待つべきだということです。人の気持はもっぱら目前の一瞬間だけに向けられているため、私たちは最初の一瞬間のあとになお多くの瞬間がつづくこと、したがって人は生涯のあらゆる瞬間に合うように行動しなければならぬことを忘れがちです。(p124) 何かある計画をなしとげるのに周囲の人々の助力を必要とする場合、有益ではあるが、自分たちより ほんのわずかでも有名になりそうだと人が考えやすい計画であったら、自分がその発起人だという風に話を持ち出しては、事はうまく運ばない。そこで私はできるだけ自分を表面に出さないようにして、この計画は数人の友人が考えたことで、自分は頼まれて皆から読書家と思われている人のところを話して廻っているのだと説明した。この方法をとってからというもの、仕事は一段と円滑に運んだ。その後もこのような場合にはいつもこの手を使ったものだが、大概うまく行っているところから言って、私は心からこの方法を勧めることができる。現在名誉心を満足させることを少し我慢すれば、後で借いは十分に来るのである。誰の功績か、しばらくはっきりしないような場合には、君よりも名誉心の強い男がそれをよいことにして自分の手だと主張することもあるだろうが、そういうことがあっても、やがては君を嫉んでいる者ですら、偽りの名誉をはぎとって、正常な持主にそれを返そうと公正な態度をとりたい気持になるものである。(p131) 第一 節制 飽くほど食うなかれ。酔うまで飲むなかれ。 第二 沈黙 自他に益なきことを語るなかれ。駄弁を弄するなかれ。 第三 規律 物はすべて所を定めて置くべし。仕事はすべて時を定めてなすべし。 第四 決断 なすべきことをなさんと決心すべし。決心したることは必ず実行すべし。 第五 節約 自他に益なきことに金銭を費すなかれ。すなわち、浪費するなかれ。 第六 勤勉 時間を空費するなかれ。つねに何か益あることに従うべし。無用の行いはすべて断つべし。 第七 誠実 割りを用いて人を害するなかれ。心事は無邪気に公正に保つべし。口に出だすこともまた然るべし。 第八 正義 他人の利益を傷つけ、あるいは与うべきを与えずして人に損害を及ぼすべからず。 第九 中庸 極端を避くべし。たとえ不法を受け、貸りに値すと思うとも、激怒を加しむべし。 第十 清潔 身体、衣服、住居に不潔を黙認すべからず。 第十一 平静 小事、日常茶飯事、または避けがたき出来事に平静を失うなかれ。 第十二 純潔 性交はもっぱら健康ないし子孫のためにのみ行い、これに貼りて頭脳を鈍らせ、身体を弱め、または自他の平安ないし借用を傷つけるがごときことあるべからず。 第十三 謙譲 ィエスおよびソクラテスに見習うべし。(p138) 実際われわれが生れ持った感情の中でも自負心ほど抑えがたいものはあるまい。どんなに包み隠そうが、それと戦おうが、殴り倒し、息の根をとめ、ぐいぐい抑えつけようが、依然として生きつづけていて、時々頭をもたげ、姿を現わすのである。恐らくこの物語の中にもしばしばその自負心が姿を見せることであろう。なぜかと言えば、私は完全にこれに打勝ったと思うことができるとしても、恐らく自分の謙護を自負することがあるだろうから。(p151) またこの企ての規模が、一見ばか大きいからと言って、私は少しも圧倒されはしなかった。なぜかと言って、相当の才能のある人物ならば、最初によい計画を立てて、自分の注意を脇にそらすような娯楽や他の事業などには一切眼もくれず、その計画の選行を確一の研究とも仕事ともするかぎり、かならずや人類に偉大な変化を与え、大事業を炭親することができると私はつねづね考えているのだから。(p155) さらになく、しばらくしてから次のような方法を用いることにした。彼の蔵書に、ある非常に珍らしい本があると聞いたので、私は手紙を書き、その本を読んでみたいのだが、四、五日拝借させていただけまいかと頼んでやった。するとすぐ彼は本を送ってよこした。私は一週間ほどして、その厚情に感謝する品の手紙を添えて返却した。その後州会で会ったところ、それまでにないことであったが、向うから話しかけてくれた。しかも非常に感な態度であった。そしてその後あらゆる場合に私に好意を示してくれたので、私たちは仲のよい友達になり、二人の交わりは彼が死ぬまでつづいた。私が覚えている諺に、「一度面倒を見てくれた人は進んでまた面倒を見てくれる。こっちが恩を施した相手はそうはいかない」という古いのがあるが、これはこの謎が本当だということを示す一例である。これを見ても分るように、他人の敬意のある行動を懐んでこれに返報し、敵対行為をつづけるよりも、考え深くそれを取りのけるようにするほうがずっと得なのである。(p165) トマス知事はこの中で説明されているストーヴの構造がひどく気に入って、数年の期間中専売特許権を与えようと言ってきた。しかし、私はこういう場合につねづね自分には重要と思われる一つの主義があったので、これをことわった。つまり、われわれは他人の発明から多大の利益を受けているのだから、自分が何か発明した場合にも、そのため人の役に立つのを喜ぶべきで、それを決して惜しむことがあってはならないという考えである。(p188) 人間は何かやっている時が一番満足しているものである。というのは、仕事をした日には彼らは素直で快活で、昼間よく働いたと思うものだから、晩は楽しく過すのであったが、仕事が休みの日にはとかく巡らいがちで喧嘩っぽく、豚肉やパンや何かに文句をつけ、終日不機嫌でいるのだった。それで私はある船長のことを思い出したのである。彼は部下の者にたえず仕事をあてがっておくことにしていた。ある時航海士がやってきて、仕事はすっかりすんで、もう何もさせることがないと告げると、彼は言ったものである。「では錨を磨かせるがいい」(p235) 「人生を大切に思うと言われるのか。それならば、時間をむだ使いなさらぬがよろしい。時間こそ、人生を形作る材料なのだから」(p276)
1投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://opac.lib.hiroshima-u.ac.jp/webopac/BB01975191
0投稿日: 2025.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「徳」を身につけることの効用を論理的に解明し実践したフランクリン。謙譲な態度は人の信用を得て自分の考えに賛同させるのに効果的である、まずは節制と倹約によって富を築いてこそ誠実の徳を実践できる等々、精神論ではなく処世術としての徳であるところがユニークです。自身もある程度の富を得てからは「この町を(国を)良くしよう」と考えはじめ、街路の清掃などの小さいことから、軍備の増強、「合衆国」システムの基礎を置く、イギリスからの独立に尽力するなど政治の世界で活躍します。 この自伝は前半の方が明らかに熱を入れて書かれていて(途中まで書いたところで多忙になり書く時間と熱意とを失ったもよう)、無一文から処世の基礎を身につけ、そこそこヤンチャもしつつ成り上がる青年時代が読み物としてとても面白いです。後半はやや「やったこと」の単なる羅列になってはいますが、独立戦争前のアメリカやクェーカー教徒の拓いたペンシルヴェニアという特異な州の雰囲気も楽しめます。ところどころに心に残る一節が埋まっていて、時を置いて何度も読みかえしたくなる本です。
0投稿日: 2024.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の幸福というものは、時たま起こるすばらしい幸運よりも、日々起こって来る些細な便宜から生まれるものである▼相手を説得するために、正論など持ちだしてはいけない。相手にどのような利益があるかを、話すだけでいい▼老いた若者は、若い老人になる。ベンジャミン・フランクリン -1790 政治家・科学者 あなたが転んでしまったことに関心はない。あなたがそこから立ち上がることに関心があるのだ▼もし木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やすだろう▼馬の行きたい方向に馬を走らせるには手間も労力も要らない▼欠点のない者は取柄もない。エイブラハム・リンカーン -1865 英には永遠の同盟国も永遠の敵国もない。あるのは永遠の国益だけである。パーマストン -1865 アヘン戦争を主導 恐れはわれわれに自分の人間性を感じさせてくれる▼逆境に勝る教育はない▼愚か者はあれこれ思いをめぐらすが、賢い者は人にたずねる▼人間は環境の創造物ではない。環境が人間の創造物である▼評論家とは何者か。文学と芸術において成功できなかった人間である。ベンジャミン・ディズレーリ -1881 絶対に失敗しない唯一の人間とは、何もやらない人間である。セオドア・ルーズベルト -1919 屋根を治すとしたら、よく晴れた日に限る▼あなたの敵を許せ。だが、その名前は決して忘れるな。ジョン・F・ケネディ -1963 恐怖は逃げると倍になるが、立ち向かえば半分になる。凧(たこ)がいちばん高く上がるのは、風に向かっているときである▼20歳までに自由主義者でなければ情熱が足りない。40歳までに保守主義者でなければ知能が足りない▼過去をより遠くまで振り返ることができれば、未来をより遠くまで見渡せる▼歴史は勝者によって作られる。しかし勝者は事実によって裁かれる。ウィンストン・チャーチル -1965 もしきみを批判する者がいないなら、きみはおそらく成功しない。マルコムX -1965 あなたの今の生き方は、どれくらい生きるつもりの生き方なのか。明日死ぬとしたら、生き方は変わるか? チェ・ゲバラ -1967 あなたが正しいとき過激になりすぎてはいけない。あなたが間違ってるとき保守的になりすぎてはいけない。マーティン・ルーサー・キング・ジュニア -1968 思い切り泣けない人は、思い切り笑えない。ゴルダ・メイア(イスラエル首相) -1968 私はまた、私の敵にも感謝しなければならない。彼らが私を失望させようとしたことが、かえってこの仕事をやり通す力を私に与えたのである。ジョモ・ケニヤッタ(ケニアの初代首相) -1978 考えは言葉となり、言葉は行動となり、行動は習慣となり、習慣は人格となり、人格は運命となる。マーガレット・サッチャー -2013 勇者とは怖れを知らない人間ではない。怖れを克服する人間である。ネルソン・マンデラ -2013
0投稿日: 2024.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で借りた。 ベンジャミン・フランクリン、アメリカ合衆国建国の父として並べられるうちの一人。と言っても大統領などトップに登り詰めた訳ではないので、知らない人も少なくないかと思う。 政治家ではあるが、科学者や出版業者の側面もあり、私は「アメリカの渋沢栄一的な人かな?」と思った。私が知ったきっかけも科学者的側面だ。電磁気学の本で、有名な実験「凧揚げで雷が電気であることの証明」で知った。 そんな人の自伝が岩波文庫として、しかも赤(アメリカ文学)として残っている。それはなぜかと言うと、社会人がよく読むジャンル「自己啓発本」としてベストセラーになったかららしい。 たしかに怒るより好みから入り込むコミュニケーション術であるとか、女性の教育の考察であるとか、様々な側面で参考にはなる。現代でよく聞く定説が、ところどころで感じ取れる。 ただ読んでみて私の感想は、おじさんの半生自慢の印象のほうが強いかな(笑)
1投稿日: 2023.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「13徳」の「規律」と「沈黙」は、まさに自らに課したいものであった。またそれ以上に付録の『富に至る道』で謎の人物「貧しいリチャード」が言及する言葉の数々が実にいい。
0投稿日: 2023.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ気持ちが良いほどの勤勉さ、無欲。 言うのは簡単だけどやるのは難しい。 自分をもう一度見直してみようと思える1冊です。
0投稿日: 2022.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカ建国の父フランクリンの自伝 印刷屋見習いから始まり イギリスからアメリカへ渡り 立身出世していく 文体が古く、淡白な文章が読み難い
0投稿日: 2020.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログフランクリンの生い立ちとかはあまり興味ないし読み物としてもさほど面白くもなかったので読み飛ばしたが、周囲から評価され社会に貢献し続けている人生だったということはなんとなくわかった。 13の徳を積む具体的な方法、その週に重視し反省する徳目を定義するという話についてはかなりよさそうなので実践しているところ。そこだけ読めばこの本の6割くらいの価値はあるような気がする。
1投稿日: 2020.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生は短いので、だらだらしている時間をなるべく減らして十三徳の樹立と富の蓄積に励まなければならない。これが幸福への最速の道であると思う。
0投稿日: 2020.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ主に節制と勤勉の徳について書かれていた。自分で定めた13の徳を毎週一つずつに集中して身に付けようとしているのが印象的だった。
0投稿日: 2020.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログフランクリンの生い立ち、人生観だけではなく、当時のアメリカ黎明期をも知ることができ面白かった。 国籍関係なく、優れた人物だった。
0投稿日: 2020.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ”「フランクリンの十三徳」が有名だが、巻末の付録「富に至る道」を興味深く読んだ。 暦のなかで毎日良い言葉に触れていたとしても、いざ欲望の対象が目の前に来ると、教訓が吹き飛んでしまうことをもシニカルに描いた小ストーリー。いろんな意味を感じる。 なお、十三徳については、小さな工夫が随所にあることを改めて認識した。 ・明確を期するために、少数の名称に多くの意味を含ませるよりも、名称は沢山使って、各々の含む意味はこれを狭く限定しようと考えた。(p.137) ・同時に全部を狙って注意を散漫にさせることはしないで、一定の期間どれか一つに注意を集中させ、その徳が修得できたら、その時初めて他の徳に移り、こうした十三の徳を次々に身につけるようにして行ったほうがよいと考えた(p.138) ・1つの徳をさきに修得しておけば、他のいずれかの徳を修得するのが容易になろうとも思ったので、私は前に挙げたような順序に徳を並べたのである(p.138) ※苦手な順ではなく、身につけやすくなるように。 ・最初の一週間は、節制に反する行為はどんな小さいことでもこれを避けるように十分に用心し、他の諸徳は格別に注意しないでなるように任せておき、ただ毎晩その日に犯した過失を書き込むことにしたのである。(p.140-141) ・こうして最後まで進んでいくと、十三週間で全コースを一と廻りし、一年には四回繰り返すことができよう。(p.141) 4週ずつを13個まわすよりも身につきそう。マンディーノ本との違いはここか。 自分なりの十三徳をつくって実践しよう。 1つめは「振返」。これを身につけると、先の習慣化に大いに資するはずだし、いまできていないことだから。 ※富に至る道は、ブログへ抜き書き(なんと103個も教訓が書かれていた)。 <関連リンクとして設定> <キーフレーズ> ★ある男があって私の近所の鍛冶屋から斧を買い、斧の表面全体を刃の部分と同じように光らせてくれと頼んだ。鍛冶屋は砥石の車輪を廻してくれるなら、望み通り光らしてやろうと(略) 「もっと廻しなさい。その中にだんだん光ってきますよ。これではまだ所々しか光っちゃいませんよ」 「そりゃそうだが」と男は言った、「私には所々しか光っていない斧が一番いいようだから」 私は多くの人の場合、こうであったろうと思う。彼らは私が用いたような方法を知らないために、このほかの徳不徳の点でよい習慣を身につけ、悪い習慣を破ることの困難に出会うと、これと戦うことを断念し、「所々しか光っていない斧が一番いい」と結論を下してしまうのである。(p.146) ※これ、ある。 ・事実、規律の点では、私の悪癖は矯正しがたいものがあった。年を取って記憶力が衰えた今では、この徳の不足を身にしみて感じている次第である。しかし、大体から言えば、私は自分が心から願った道徳的感性の域に達することはもちろん、その近くに至ることさえできなかったが、それでも努力したおかげで、かような試みをやらなかった場合に比べて、人間もよくなり幸福にもなった。(p.147) ※心から願った、が重要! この記述をしているフランクリン氏は79歳!! ・私は1つ1つの徳について、短い註釈を書き、その徳を持つことの利益と、その反対の悪徳に伴う害を示すつもりであった。そして署名は、『徳に至る道』とする考えであった。(略) しかし、この註釈を書いて公刊しようという私の考えはけっきょく実現されないでしまった。(p.148-149) ※「富に至る道」の続編の予定だった? 自伝を書くことを強く勧めてくれたベンジャミン・ヴォーン氏の手紙にも記載あり。(p.120) ・各会員は問題の提出その他ジャントー・クラブと同様な規則を持つ従属クラブをめいめい創設することに努める、ただし、ジャントー・クラブとの関係は知らせないでおくというのである。(p.163) ※「ある大規模な計画」がこれ。「人類全体の利益の見地」から「修徳同盟」を興す。 ※陰徳という意味で隠しているのかと思ったけれど、意見が広まるという実利を兼ねていたみたい。p.164の記述より。 <きっかけ> 人間塾 2015年4月の読書会課題図書となったため再読。 手元の本には2004/7/6読了、とのメモあり。(2004年4月24日 第64刷発行) →現在書店で販売しているのはおもに新版で、文字が大きくなりページ数も増えているみたい(上のページ番号は旧版のもの)”
1投稿日: 2019.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ私が読書に目覚めたきっかけ。 最初の部分は冗長に感じられる所もあるが、とても知己に富んでいる。 ベンジャミンフランクリンは意外と面白い人なんだなぁ、、と思えるし、こんな人でも自分の欠点を治そうとして、でもうまくいかなくて、、でもここだけは気をつけよう、とか考えて生活してたのだなぁ…と思える。
0投稿日: 2019.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログベンジャミン・フランクリン。 健全な自尊心をもち、相当な読書好きで勉強をしたことがうかがえる。 何故この本が古典となったのか? その価値は青年に向けて、節制や勤勉や誠実であることの重要性を、一庶民であったフランクリンがそれらの特性を養いながら立見出身できたところにあるのではないか。 良い本は行動を促す本だと思うが、 まさにこの本はそれだ。
1投稿日: 2019.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
一度面倒を見てくれた人は進んでまた面倒を見てくれる。こっちが恩を施した相手はそうはいかない(190) 初めの百ポンドさえ溜めてしまえば、次の 百ポンドはひとりでに溜まる 金というものは本来繁殖力の強いものなのである(202) 本来の貧乏人一人にたいして、贅沢な貧乏人が百人(330)
0投稿日: 2019.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログデール・カーネギーの『人を動かす』に記述のあったアメリカ資本主義のキーパーソンであるフランクリン自伝を手に取ってみた。恐らく原文ではとても素晴らしいことを書いてあるのだろうと思うも、自分には直訳風の日本語訳が合わずしっくりいかない。原文を読めるような語学力がないのが残念。中でも有名らしい十三得を記す。毎日自問しこれを習慣化していくべしとの事。 いきなり食べ過ぎなワタクシである。 ≪十三得≫ 第一 節制…飽くほど食うな、酔うほど飲むな 第二 沈黙…駄弁を弄するな 第三 規律…物は場所を決め、仕事は時間を定めよ 第四 決断…なすべきことをなさんと決心しべし 第五 節約…浪費するな 第六 勤勉…時間を空費するな、益有ることに従え 第七 誠実…詐りを用いて人を害するな 第八 正義…他人の利益を傷つけるな 第九 中庸…極端を避け、激怒を慎め 第十 清潔…身体、衣類、住居の不潔を黙認するな 第十一 平静…小事、日常茶飯事に平静を失うな 第十二 純潔…性向に耽り頭脳を鈍らせ信用を失うな 第十三 謙譲…イエス、ソクラテスに見習え
2投稿日: 2019.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログいかにベンジャミンフランクリンが偉大であったかが一読するだけでわかる。さすが意識高い系の元祖だけあってかなり自分に鞭を打ってより良い幸福を得ようとしていた。 また彼があみだした十三徳は素晴らしいものである。 1 節制 頭や体が鈍くなるほど食べないこと。はめをはずすほどお酒を飲まないこと。 2 沈黙 他人あるいは自分に利益にならないことは話さないこと。よけいな無駄話はしないこと。 3 規律 自分の持ち物はすべて置き場所を決めておくこと。仕事は、それぞれ時間を決めて行うこと。 4 決断 なすべきことをやろうと決心すること。決心したことは、必ずやり遂げること。 5 節約 他人や自分に役立つことにのみお金を使うこと。すなわち無駄遣いはしないこと。 6 勤勉 時間を無駄にしないこと。いつも有益なことに時間を使うこと。無益な行動をすべてやめること。 7 誠実 だまして人に害を与えないこと。清く正しく思考すること。口にする言葉も、また同じ。 8 正義 不正なことを行い、あるいは、自分の義務であることをやらないで、他人に損害を与えないこと。 9 中庸 何事も極端でないこと。たとえ相手に不正を受け激怒するに値すると思っても、がまんしたほうがよいときはがまんすること。 10 清潔 身体、衣服、住居を不潔にしないこと。 11 冷静 つまらないこと、ありがちな事故、避けられない事故などに心を取り乱さないこと。 12 純潔 性的営みは、健康のためか、子供を作るためにのみすること。性におぼれ、なまけものになったり、自分や他人の平和な生活を乱したり、信用をなくしたりしないこと。 13 謙譲 イエスおよびソクラテスを見習うこと。 これらの徳を積むことによって彼は幸せになれると思っていた。
0投稿日: 2019.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ自伝を初めて読んだ。 こんなに面白いものだったなんて。 まず、決して裕福ではない時代、そして家に生まれたフランクリンですが、 彼が彼自身または書物よって導き出した考えにより、 合理的に誠実に動き、苦難にあいながらもまたそうする事で己の人生を運び成功して行く様がとても感慨深く、感銘を受けました。 中でも有名な十三の徳はとても実行してみたく思ったし、似たような事を自分でもすでにしていたことから自分のやっている事に確信を持ちました。 知る 事に遅いという事は言いたくはないものですが、 やはり知るのが遅い事に悔いてしまう。 それだけ素晴らしい書籍であった。
0投稿日: 2019.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近のフランクリン、マイブームに乗って読んでみた。あまりに昔の話しすぎるけど、現代でも役に立つことがある。変に13の徳目とかより、素直に自伝を読んだ方が良い。
0投稿日: 2019.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
フランクリンは、1706年ボストンに生まれ、印刷業で立身、政治活動にも身を置き、アメリカ独立宣言書起草委員会にも名を連ねています。アメリカの駐仏全権公使としてパリに居住し、フランスともゆかりのある人物です。雷の研究や発明でも有名と、多才な人物だったようです。 自伝は長い期間をかけて紡がれていて、その時々の正直な思いが盛り込まれています。栄達のため、というよりはより良い人生を歩むための人生訓を後世に残しては、という周囲の人からの薦めもあった、と書かれています。 有名なのは、フランクリンの13徳、でしょうか。一週間ごとに一つの徳目に集中的に取り組むことを繰り返し、年4回転させ習慣づけることから13という数字になったようです。節制、沈黙、規律、勤勉、誠実といった項目は、日本人の道徳感覚と近く、すんなりと受け入れられるものばかりです。 「ものぐさは、錆と同じで、労働よりもかえって消耗を早める。一方、使っている鍵はいつも光っている」 「畑仕事で身代起こしたく思わば、鋤にせよ鍬にせよ、自ら使え」 といった言葉を読むに、フランクリンの自助(Self Help)の基本姿勢が良くわかりました。今の時代にも通じる金言が多く、アメリカ建国時の空気がわかるような気がしました。
0投稿日: 2018.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ発熱で寝込んだ時に読み始めた。 もっと説教臭いのかと思っていたが、割と坦々とした内容であった。 時代を感じさせてくれるので面白く読めた。 言うならば、アメリカ開拓時代?の風景が想像されるような時代。 日本で言えば、戦後の昭和40年代から50年代ぐらい?として、勝手に映像化して楽しめた。 偉人伝ではなく、あくまで自伝なので、業績は他をあたった方がいいかもしれない。 幼稚園時代に、ベンジャミンという人が凧揚げをしていた漫画は読んだ覚えがある。伊東四朗とかの流れだったのかも。デンセンマンとか。 ちなみに有名な十三徳もメモしておく。 十三徳 1.節制 飽くほど食うなかれ。酔うまで飲むなかれ。 2.沈黙 自他に益なきことを語るなかれ。駄弁を弄するなかれ。 3.規律 物はすべて所を定めて置くべし。仕事はすべて時を定めてなすべし。 4.決断 なすべきをなさんと決心すべし。決心したることは必ず実行すべし。 5.節約 自他に益なきことに金銭を費やすなかれ。すなわち、浪費するなかれ。 6.勤勉 時間を空費するなかれ。つねに何か益あることに従うべし。無用の行いはすべて断つべし。 7.誠実 詐りを用いて人を害するなかれ。心事は無邪気に公正に保つべし。口に出ですこともまた然るべし。 8.正義 他人の利益を傷つけ、あるいは与うべきを与えずして人に損害を及ぼすべからず。 9.中庸 極端を避くべし。たとえ不法を受け、憤りに値すと思うとも、激怒を慎むべし。 10.清潔 身体、衣服、住居に不潔を黙認すべからず。 11.平静 小事、日常茶飯事、または避けがたき出来事に平静を失うなかれ。 12.純潔 性交はもっぱら健康ないし子孫のためにのみ行い、これに耽りて頭脳を鈍らせ、身体を弱め、または自他の平安ないし信用を傷つけるがごときことあるべからず。 13.謙譲 イエスおよびソクラテスに見習うべし。 [more] (目次) 少年時代 フィラデルフィアに入る ロンドンの一年半 印刷屋を開業す 勤倹力行時代 十三徳樹立 成功の道を歩む 社会的活動 軍事に活躍す 州民を代表して再び英国へ 富に至る道
0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカの建国に大きな役割を果たしたフランクリンの自伝記。本人の自慢話(ご自身も認めていますが)が鼻につくところはあるものの、18世紀自分だけの力で財やネットワークを作り、謙虚かつストイックに生きている姿に勇気づけられます。それにしても翻訳が読みにくいのが残念!他の役者で読んでみようかな。
0投稿日: 2018.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人的には科学者としての側面ばかり認識していたが、 本書を通して実に幅広く、かつ目覚ましい活躍をした人物であり また著しい立身出世を成し遂げた人物でもあるということを知った。 十三の徳については、その内容自体もだがいかにして身に付けていくか、ということの説明に大きな価値がある。 自分は俗物なのでなかなか実践はむずかしいが、それでも目指すものとして心においておくだけでもいくばくか違うだろう。
0投稿日: 2018.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
教養的読書。ベンジャミン・フランクリンといえば100ドル札紙幣に描かれているアメリカ合衆国建国に大きく貢献した人物として有名である。フランクリンは決して恵まれた家庭に生まれたとは言えず、植字工など苦労の多い時期を経験している。そこからの立身出世の物語はアメリカンドリームの原型なのだろう。フランクリンは自身で定めた「13の徳」の実践などから、勤労で実直な人物だったことが自伝から窺える。その影響は後にM.ウェーバーがプロ倫で資本主義の源流として言及したほどである。それだけの功績を遺した人物の自伝が現在でも読めることは大きな遺産だと感じる。
0投稿日: 2016.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログベンジャミン・フランクリン(1706~90年)は、米国独立運動の中心人物として活躍し、米国建国の父の一人といわれるが、本書は、概ね50歳台までを自ら描いた半生記である。 フランクリンは、政治家としてのほかに、外交官、実業家、著述家、物理学者、気象学者として幅広い業績を残した万能人であったが、本自伝で語られる勤勉性、探究心の強さ、合理主義、社会貢献は、まさに建国直後の米国の理想的人間像を象徴しており、本自伝は米国のロング&ベストセラーの一つとなっている。米ドルの100ドル札の肖像が、ワシントンでもリンカーンでもなく、フランクリンであることからも、米国人にとっての存在の大きさがわかる。 日本でも、明治時代にサミュエル・スマイルズの『自助論(西国立志編)』とともに盛んに読まれ、また、福沢諭吉の『福翁自伝』に影響を与えたとも言われている。 本作品では、自らの体験が、失敗も含めて率直に語られているのだが、そのスタンスは常に前向きである。失敗についても、そこから何を学んだかが記されており、著者が、単なる回顧録としてではなく、後に続く若者へ伝えるものとして書かれたことがわかる。特に、道徳的完成に到達することを目指して作った「十三徳」では、「第一、節制~飽くほど食うなかれ。酔うまで飲むなかれ」、「第四・決断~なすべきことをなさんと決心すべし。決心したることは必ず実行すべし」、「第十一、平静~小事、日常茶飯事、または避けがたき出来事に平静を失うなかれ」など、具体的なものから理念的なものまで、様々な心掛けが示されている。 また、本岩波文庫版では、自伝とは切り離されて出版され、主に勤勉と節倹の説いている『富に至る道』も付け加えられている。 自己啓発書としても、古き良きアメリカ的思潮を知る書としても読める古典である。 (2010年2月了)
0投稿日: 2016.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ信じる事と自分を自制すること それが己を高める第1の条件だと フランクリンは示してくれます 自伝ではありますが自分の思い描いたものを 手に入れるために勉強しますし 強い志を持つ同じような人が集まればいいなにかが生まれることを教えてくれます
0投稿日: 2015.12.14読了した
フランクリン自伝は、日本も明治期に盛んに読まれたそうである。アメリカ研究者が、読むべき本だそうだが、なるほど、 僕も読んで良かったと思う。彼が、息子に伝えたかったこと、それは、金言であり、一族の歴史であったろうと思う。 政治学や歴史学、ましてや独立戦争の話ではなく、しかし、私はこの本で有益な、インスピレーション、気づきを たくさんもらった。今の日本の現状や、指導者とはいかにあるべきかなど。評価は読む人によってだいぶ違う だろうが、どの方にも読むことをお勧めできる、良書である。教育論としても有益であろう。 いろいろ言ったが、魂胆や背景は無しである。一度読んでみることをお勧めします。
1投稿日: 2015.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「何か恩恵を受けると、その重荷を自分の肩からはずして、天なる神に押しつけようとするのがお坊さん連中のやり口だと知っているもので、それで君はあくまで地上においておくように工夫したというわけだね。」 ベンジャミンフランクリンの自伝。この本を読むと、彼がいかに自信家だったかわかる。はじめの少年時代が面白かった。他にも、周囲の人を巻き込んだ企画を考えた際には、自分が発案者だと隠し勧誘したほうがうまくいったという話が良かった。また、新聞への寄稿は乗合馬車とは違い、人を選ぶという話、寄付を募る場合には世間でそれを話題にしてから行うのが良いとする話も参考になった。
0投稿日: 2015.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ13の徳を磨く方法や、どのような生涯を送ったのか、時代背景、どれも楽しかった。日常に生かすにはっていう視点を持って読めた。
0投稿日: 2014.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログp8 もしもお前の好きなようにしてよいと言われたならば、私はいままでの生涯を初めからそのまま繰返すことに少しも異存はない。 p9 私は多分、大いに自分の自惚れをも満足させることだろう。 中略 自惚れというものは、その当人にもまたその関係者にも、しばしば利益をもたらすと信ずるからである。
0投稿日: 2014.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログベンジャミン・フランクリンは、日本ではあまり有名ではないが アメリカではThe Father of All Yankeesと呼ばれ アメリカ建国の父として非常にポピュラーな存在だ。 彼の肩書きは、印刷業者・ジャーナリスト・哲学者・発明家 ・慈善事業家・政治家・外交官・科学者・文学者と多岐に渡っている。 有名なシステム手帳のフランクリンプランナーも彼がルーツであるし 雷が電気である事を凧を使った実験で確認したのも、このフランクリンである。 フランクリンのマルチな活躍ぶりを支えていたのは 彼が一貫して主張している彼の"勤勉さ"である。 フランクリンは25歳の時に 道徳的に完璧な存在になるためにはどうしたら良いかを考え 下記の13の徳目を確立した。 フランクリンの13の徳目 1.節制: 頭が鈍るほど食べないこと。酔って浮かれだすほど飲まないこと。 2.沈黙: 他人または自分自身の利益にならないことはしゃべらないこと。つまらぬ話は避けること。 3.規律: 自分の持ち物はすべて置くべき場所をきめておくこと。自分の仕事はそれぞれ時間をきめてやること。 4.決断: やるべきことを実行する決心をすること。決心したことは必ず実行すること。 5.節約: 他人または自分のためにならないことに金を使わないこと。すなわち、むだな金は使わないこと。 6.勤勉: 時間をむだにしないこと。有益な仕事につねに従事すること。必要のない行為はすべてきりすてること。 7.誠実: 策略をもちいて人を傷つけないこと。悪意をもたず、公正な判断を下すこと。発言するさいも同様。 8.正義: 他人の利益をそこなったり、あたえるべきものをあたえないで、他人に損害をおよぼさないこと。 9.中庸: 両極端を避けること。激怒するに値する侮辱をたとえ受けたにせよ、一歩その手前でこらえて激怒は抑えること。 10.清潔: 身体、衣服、住居の不潔を黙認しないこと。 11.平静: 小さなこと、つまり、日常茶飯事や、避けがたい出来事で心を乱さないこと。 12.純潔: 性の営みは健康、または子孫のためにのみこれを行なって 決してそれにふけって頭の働きを鈍らせたり、身体を衰弱させたり 自分自身、または他人の平和な生活や信用をそこなわないこと。 13.謙譲: キリストとソクラテスにみならうこと。 フランクリンは、徳目を作っただけでなく この13の徳目を1週間に一つ身につけようと、表をつくってチェックした。 13週後にすべての徳目をやり終えたら、それを一番目から繰り返した。 この方法だと、1年で4回繰り返し13の徳目を身につける訓練ができる。 これがフランクリン・プランナーのルーツである。 フランクリンは、決して人間にとって善い事であるから勤勉を推奨しているのではなく 富や名声、個人の幸せを掴むのにもっとも近道だから勤勉を推奨する。この勤勉の姿勢こそ、見習うべきものである。
0投稿日: 2014.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこの様な自伝を読むのは、本当に久しぶりだ。人の一生を並走するという読書は、映画でいうロードムービーと同じで、自分がこれから何処へ行くのかを一緒に考えながら、読み進め流ことができる。人生の追体験の場を与えてくれる。国も、時代背景も異にしていても、通じる生きることの法則がそこには必ず存在する。それを、より多く映画や書物から、より抽象度を高めて自分の人生を豊かなものにするかに役立てたいと思わせてくれる作品だった。 *付録として、掲載された「富に至る道」に出てくる格言が、古めかしいながらも、重い言葉として伝わってきた。 2014.03.14
0投稿日: 2014.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校時代に手にとった本。存在を知り、親父に頼んで購入してもらったことから思い出深い本でもある。 十三徳の樹立など、あらゆる自己啓発の基盤となった作品と言っても過言でないと思う。 入社四年目に久しぶりに再読。新鮮さは薄れていたが、日々の習慣が大切なことを再認識。良い習慣を如何にシンプルに運用するかという視点は初読時には無かった。
0投稿日: 2013.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログたまに、特異なジャンルの本を読んでいると 知人から「マツモットはいったい何を目指しているのか」と聞かれる事がある。 そんな時は、こう答えるようにしている。 「そうだね~ まあ色々と野望はあるけど 最終的にはお札の顔ぐらいには、なってやろうかと思ってるね。」 で、今回はアメリカ100$札の顔、ベンジャミン・フランクリンの自伝。 ベンジャミン・フランクリンは、日本ではあまり有名ではないが アメリカではThe Father of All Yankeesと呼ばれ アメリカ建国の父として非常にポピュラーな存在だ。 彼の肩書きは、印刷業者・ジャーナリスト・哲学者・発明家 慈善事業家・政治家・外交官・科学者・文学者と多岐に渡っている。 有名なシステム手帳のフランクリンプランナーも彼がルーツであるし 雷が電気である事を凧を使った実験で確認したのも、このフランクリンである。 フランクリンのマルチな活躍ぶりを支えていたのは 彼が一貫して主張している彼の"勤勉さ"である。 フランクリンは25歳の時に 道徳的に完璧な存在になるためにはどうしたら良いかを考え 下記の13の徳目を確立した。 フランクリンの13の徳目 1.節制: 頭が鈍るほど食べないこと。酔って浮かれだすほど飲まないこと。 2.沈黙: 他人または自分自身の利益にならないことはしゃべらないこと。つまらぬ話は避けること。 3.規律: 自分の持ち物はすべて置くべき場所をきめておくこと。自分の仕事はそれぞれ時間をきめてやること。 4.決断: やるべきことを実行する決心をすること。決心したことは必ず実行すること。 5.節約: 他人または自分のためにならないことに金を使わないこと。すなわち、むだな金は使わないこと。 6.勤勉: 時間をむだにしないこと。有益な仕事につねに従事すること。必要のない行為はすべてきりすてること。 7.誠実: 策略をもちいて人を傷つけないこと。悪意をもたず、公正な判断を下すこと。発言するさいも同様。 8.正義: 他人の利益をそこなったり、あたえるべきものをあたえないで、他人に損害をおよぼさないこと。 9.中庸: 両極端を避けること。激怒するに値する侮辱をたとえ受けたにせよ、一歩その手前でこらえて激怒は抑えること。 10.清潔: 身体、衣服、住居の不潔を黙認しないこと。 11.平静: 小さなこと、つまり、日常茶飯事や、避けがたい出来事で心を乱さないこと。 12.純潔: 性の営みは健康、または子孫のためにのみこれを行なって 決してそれにふけって頭の働きを鈍らせたり、身体を衰弱させたり 自分自身、または他人の平和な生活や信用をそこなわないこと。 13.謙譲: キリストとソクラテスにみならうこと。 フランクリンは、徳目を作っただけでなく この13の徳目を1週間に一つ身につけようと、表をつくってチェックした。 13週後にすべての徳目をやり終えたら、それを一番目から繰り返した。 この方法だと、1年で4回繰り返し13の徳目を身につける訓練ができる。 これがフランクリン・プランナーのルーツである。 この時代、プラグマティズムという思想はまだなかったそうだが フランクリンの考え方は非常にプラグマティックである。 フランクリンは、決して人間にとって善い事であるから勤勉を推奨しているのではなく 富や名声、個人の幸せを掴むのにもっとも近道だから勤勉を推奨する。 そして私は、ある種の人間の行為は、神が禁じているから悪いのではなく また、神が命じているから善いものでもなく、おそらくそういった行為は 私たち人間にとって悪だから神は禁じているのであり 私たちに有益であるから神は命じているのだ、といった考えをいだくようになっていたのである。 人間の幸福というものは稀にしか起こらない大きな幸運よりは 毎日起こる小さな便利さから生じるものなのだ。 したがって、貧しい青年にヒゲの剃り方とカミソリの研ぎ方を教えてやったほうが 1000ギニーの金を与えるよりも人生における彼の幸福により大きく貢献する事になる。 私はかなり若い時分から「いかに手を抜いて、成果を出すか」という事ばかり考えていた。 私には兄が三人いる。 私の住んでいた地域の学区はさほど都心ではなかった事もあり 中学や高校は公立の学校に進学するのが当たり前だった。 有名私立校を受験する生徒は本当に稀であり 私立と言えば公立の滑り止めで受験するというのが一般的な考え方であった。 私の兄弟のうち、長男は横浜銀蠅みたいな出で立ちのヤンキーだったが 高校はなんとか市立の中位校に入った。 次男と三男は、それぞれ学区内の最上位の県立高校に入った。 私が中学校に入った時、高校は次男・三男と同じ県立高校に入るんだろうなと思っていた。 兄達からみれば、その県立高校は入れて当たり前、落ちたら負け犬である。 その状況下でどうすれば自分の存在をアピールできるか 私が出した結論は「兄よりも勉強しないで余裕シャクシャクで受かること」であった。 細かいことはあまり覚えていないが 試験が近づくにつれて、夜更かしをしてテレビを見ていた記憶がある。 親にはしょっちゅう苦言を呈されたが、それでも兄達より良い成績をとってきた。 自分の小さな自尊心が満たされる瞬間だったが、親兄弟は苦々しく私を見るだけだった。 現在の私は「いかに手を抜いて成果を出すか」とは考えていない。 成果は努力の量に"ほぼ"比例すると思う。 世界で活躍する人々は例外なく努力家であり 才能だけで輝けるのは若い頃のほんの一瞬だけだ。 しかし、勤勉や努力という言葉は、私の耳には少しカッコ悪い響きがある。 ジェームズ・ボンドや舘ひろしのような ステレオタイプなモテ像には、勤勉や努力は微塵も感じられない。 ただ、現実の世界を眺めてみると、モテる人々は例外なくマメであり 才能だけでモテるのは若い頃のほんの一瞬だけだ。 俗な事ほどプラグマティックな勤勉さがものをいうのかもしれない。
0投稿日: 2013.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログとっても良い本でした。これからどんなふうにに生きて行けばいいのか、イメージできる本です。有名な13徳も書かれていて、それは本当に素晴らしいのだけれど、堅実にやっていくという、当たり前のことを納得して実践したいと思う出来事が、いろんなストーリーの中に書かれています。付録として「富へ至る道」も収録されていて、いろいろな名言が心に響きました。
0投稿日: 2013.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログベンジャミン・フランクリンの自伝.生涯の3分の2くらいが語られている.アメリカ独立に尽力する部分はしたがって書かれていない.書かれた部分では前半の事業で成功するまでが断然面白い.禁欲的で勤勉.この部分は昔の日本人みたいで,明治の人たちの心を捉えた部分だろう.一方で,とてもあっけらかんとした生き方はアメリカの合理主義を強く感じさせる. 後半の政治家,軍人としての活躍は読んでいて退屈してしまった.科学者としての側面も数ページ触れられているだけでちょっと残念.
0投稿日: 2012.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ努力、勤勉、質素、倹約・・・それが幸福や社会的成功に繋がるという具体例自伝であり、自己啓発的教養の古典。植民地時代のアメリカの政治・経済・暮らしが分かるのも興味深いし、あけすけな語り口の自伝はそれだけでも面白い。 だけど教養として必読かというとそれほどでもないかな。
0投稿日: 2012.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログベンジャミン・フランクリンの生涯を描いた本。 フランクリン自体の話はもとより、一番おもしろいと思ったのは、時代背景であり、当然のように書かれていることが、「今じゃありえないよな。」って感想を抱かせるものが多くて、そちらの方に意識が集中した。 文章自体は結構散漫で読みづらいかも。
0投稿日: 2012.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
アメリカ合衆国の政治家、ベンジャミン・フランクリンの手記をまとめた本。 100ドル紙幣の肖像画に使われている。 子供のころから大人になって働くまで、そこから事業を起こした話、 自分のやったことなどをつらつらと書かれている。 ところどころに、失敗談や自分が学んだこと、 それに対する自分の対処法などが書かれている。 日記部分は「ふーん」くらいで読み流すくらいで丁度いい。 【学んだこと】 ・「自分はこう思われる」「かもしれない」と相手の意見を批判しない発言法 →人とムダに争わない ・自分の功績や功労は表に出さない。口にしない。 →人は自慢話を嫌うものだ ・「13の徳」とそれを身に着けるためのルーチンワーク化 →一気に全ての徳は身につかない。週代わりで行うことにより、無理せず身につく ・フランクリンの毎日のスケジュールとそれを守ることによる利益 →日々、自分の行動を見直し、ムダや失敗を反省することによる行動改善 ・「一度面倒をみてくれた人は進んでまた面倒を見てくれる。こっちが恩を施した相手はそうはいかない」という考え方と事実 ・エイブラハム老の言葉(リチャード・ソーンダーズの手記)
0投稿日: 2012.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みようによってはある成功者の自慢話。だけど全然いやみじゃない。それはやはりフランクリンの実際の功績と真面目に正直にやってきたことがリンクしていることが分かるからかな?
0投稿日: 2012.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「フランクリンの十三徳」 1,節制 頭や体が鈍くなるほど食べないこと。はめをはずすほどお酒を飲まないこと。 2,沈黙 他人あるいは自分に利益にならないことは話さないこと。よけいな無駄話はしないこと。 3,規律 自分の持ち物はすべて置き場所を決めておくこと。仕事は、それぞれ時間を決めて行うこと。 4,決断 なすべきことをやろうと決心すること。決心したことは、必ずやり遂げること。 5,節約 他人や自分に役立つことにのみお金を使うこと。すなわち無駄遣いはしないこと。 6,勤勉 時間を無駄にしないこと。いつも有益なことに時間を使うこと。無益な行動をすべてやめること。 7,誠実 だまして人に害を与えないこと。清く正しく思考すること。口にする言葉も、また同じ。 8,正義 不正なことを行い、あるいは、自分の義務であることをやらないで、他人に損害を与えないこと。 9,中庸 何事も極端でないこと。たとえ相手に不正を受け激怒するに値すると思っても、がまんしたほうがよいときはがまんすること。 10,清潔 身体、衣服、住居を不潔にしないこと。 11,冷静 つまらないこと、ありがちな事故、避けられない事故などに心を取り乱さないこと。 12,純潔 性的営みは、健康のためか、子供を作るためにのみすること。性におぼれ、なまけものになったり、自分や他人の平和な生活を乱したり、信用をなくしたりしないこと。 13,謙譲 イエスおよびソクラテスを見習うこと。
0投稿日: 2012.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカ資本主義育ての親として読むか、立身出世の風潮下の自伝として読むかで読み取れるものが変わるのでは。ただ人間的な苦悩のプロセスとかの記述はあまりないので、そういう人生論という意味では、トルストイの『人生論』とかの方読んだ方がいいのかも。むーん。
0投稿日: 2012.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ今風の自己啓発書として書かれたのではなくあくまで自伝であり、 フランクリンの少年期から晩年までを一歩ずつ追っている。 いわゆる自己啓発書と違って、ポイントレッスンのようなものがあってそこに付箋を貼るようなカタチではない。 書いてあることはただただフランクリンの行動とその時考えていたことだが、そのひとつひとつが素晴らしい教訓になっており、 付箋を貼ろうと思ったら全ページに貼ることになる (私は付箋を途中で放棄した)。 なんとも密度の濃い教訓の結晶のような本。 一度読んだだけではレビューにできない。 気持ちが怠けてきたり、財布の紐がゆるくなった時に繰り返し読むことになろうと思う。
0投稿日: 2012.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログフランクリンがどのようにフランクリンになったのか、 その秘訣が余す事なく公開されています。 自伝のため美化しているきらいはあるものの、 その「自己を律する能力・努力」は、 自分に甘いと自覚する私にガツンと喝を入れてくれます。
0投稿日: 2012.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生のときに読みたかった本です。若くして家を飛び出して、いろいろな経験を積んだ著者の生き方にわくわくします。彼の13の徳目は自分の行動目標にもいちぶ取り入れて参考にしているのですが「頭が鈍るほど食べないこと」と第一の徳目に入れておきながら、表紙にあるようにデブなのはちょっといただけないですね。
0投稿日: 2012.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の扱い方と自己の人格を陶冶する方法を知りたければ、ベンジャミン・フランクリンの自叙伝を読めばよい。読みはじめると、夢中になることは請け合える。また、アメリカ文学の古典でもある。(D・カーネギー『人を動かす』創元社・文庫版178頁)
0投稿日: 2011.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ奉公人からスタートし、印刷業で財を成し、 発明や科学実験、軍事、政治などでも活躍し、 幅広い業績を残したチートな人物の自伝。 アメリカ成功哲学の元祖であり、 明治時代の日本でも広く読まれ、 現代においても読む価値は十分にあるが、 18世紀のアメリカにおいては、 競争相手が少なくて弱かった事も 留意しなければならないだろう。 元々出版する意図は無かったのか、 友人に渡した原本は全て失われており、 底本になっている孫が出版した版では、 最後の8ページが省かれていたらしい。 そこだけ主観的で愚痴っぽくなっているので、 あえて載せなかったんだろうと思う。 と、なんだかんだと重箱の隅をつついたが、 フランクリンほどの偉大な人物は史上希であり、 彼に学ぶ事が有意義である事は間違い無い。
0投稿日: 2011.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
節制し、勤勉に生きていれば成功するというメッセージを受け取った。 ベンジャミン・フランクリンに関して予備知識は全くなかったが、この本を読んで彼がどのように生きてきたのかを追体験できた。 内容は主に青年期から中年期までについて書かれており彼の誠実な人柄が読み取れる。 最後に、フランクリンがなぜこのように成功できたか、という問いに対して私はこう思う。周りを巻き込む力が彼に会ったのだと。 また、ジャントークラブという会を作り、読書家の人達を意見を交わす機会があった。きっと皆それぞれの意見を出し合うとても有意義な会で、皆が深い交流をもったであろう。私はそれをとても羨ましく思った。
0投稿日: 2011.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「十三徳」と、巻末の「富に至る道」が面白かった。 これを世俗的と見るか、人生の真髄が表れていると見るかは、読者次第ということであろう。
0投稿日: 2011.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ金言も多いが、全体的に冗長なので、エッセンスだけ集めた類似書の方がおすすめ。 時代背景を考えれば、このようなことを出きたので一国の宰相にまで上り詰めたのでしょうか。
0投稿日: 2011.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログよく考えるための10冊/思考技術のためのプラチナ・クラシックス http://readingmonkey.blog45.fc2.com/blog-entry-500.html 昔、フランクリン自伝を読み始めたがつまらないので途中で読むのをやめてしまった記憶があるが、ガラス管の実験みたいな挿絵があったことくらいしか覚えていない。今回読んだら、挿絵もないし、話もおもしろかったので昔読んだ本は別の本だったのだろう。 「弁論家について」でも「慮り(おもんばかり)」の大切さにふれられていたが、こちらも処世術として頻繁にでてくる。 勤勉にすると周りからの評判がよくなるとか身も蓋もない理由もちゃんと書いてる。 この自伝に含まれる若者を教化する目的には年をとっているので該当しないが、単純におもしろかったのでよし。
0投稿日: 2011.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生あらゆる面で成功したじぃさんが、晩年になってから自慢しまくっているハナシ。僕はこんなにすごいことをしたが、それでも僕は謙虚で、勤勉で、万人から好かれているんだよ~~~で本を1冊書いちゃいましたって感じなのだが、面白かったので、星4つ。自慢をかくし切れないかわいさがあるので、きっと本人もたくさんの人に愛されていたのじゃないかしらと思います。 それにしても、彼の才能は多様です。本でもとにかく「勤勉であること」が重要だと何度も何度も述べていますが、常に改善し、上を目指す姿勢はすごい。お酒もタバコも飲まず、女遊びもせず、浪費もせず、それでも人生を全力で楽しんでいる。幸福に関するいろんな本を読んだけれど、彼の自叙伝を読むと、幸福とはどうして訪れるかのヒントを得られるような気がします。 ベンジャミンフランクリンは13徳というのでも有名です。詳しくは、13の徳のリストをつくり、これを週に1つずつ守るように心がけ、表を作って、守れたかどうかを書き記していたそうです。 すばらしい方法だとは思うのだけれど・・・。なんというか、発想が斬新だと思いませんか? 彼の自叙伝でためになるところは、「人は他人からどう見えるかが大事」という考えが根底にある徳について書かれているところだと思います。小難しい「高徳な人」のイメージではなく、他人の中でうまくやり、自分の目標に達する方法を考え、それを実践しています。 でも、向上心の非常に低いわたしとは違う人種だなぁ・・・と思って終わったわたしはやはり成功しない人種なのであろう。 だけどね・・・ 彼は人とうまくやるためにあらゆつ技術を開発し、全力でその技術を取得していき、その結果としてすばらしい結果を産み出したわけなのだけれど、実は自分の息子とは絶縁していた時期もあるらしい。(これは本には載っていないです)やっぱり、家族との関係は、技術だけではうまくいかないのかな・・・。 さて、最後に、フランクリンの13徳を挙げておきます。 1.節制 飽くほど食うなかれ。酔うまで飲むなかれ。 沈黙 自他に益なきことを語るなかれ。駄弁を弄するなかれ。 規律 物はすべて所を定めて置くべし。仕事はすべて時を定めてなすべし。 2.決断 なすべきをなさんと決心すべし。決心したることは必ず実行すべし。 3.節約 自他に益なきことに金銭を費やすなかれ。すなわち、浪費するなかれ。 4.勤勉 時間を空費するなかれ。つねに何か益あることに従うべし。無用の行いはすべて断つべし。 5.誠実 詐りを用いて人を害するなかれ。心事は無邪気に公正に保つべし。口に出ですこともまた然るべし。 6.正義 他人の利益を傷つけ、あるいは与うべきを与えずして人に損害を及ぼすべからず。 7.中庸 極端を避くべし。たとえ不法を受け、憤りに値すと思うとも、激怒を慎むべし。 8.清潔 身体、衣服、住居に不潔を黙認すべからず。 9.平静 小事、日常茶飯事、または避けがたき出来事に平静を失うなかれ。 10.純潔 性交はもっぱら健康ないし子孫のためにのみ行い、これに耽(ふけ)りて頭脳を鈍らせ、身体を弱め、または自他の平安ないし信用を傷つけるがごときことあるべからず。 謙譲 イエスおよびソクラテスに見習うべし。 12の健康ないし・・・ってところがちょっと笑けるんだけど。 子作りだけじゃないってところがちゃっかりしてません?
0投稿日: 2011.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ベンジャミン・フランクリンは、毎晩自己反省をして13の重大な過失を発見した。そのうちの3つは、時間の浪費、小事にこだわること、他人に難癖つけたり、反論したりすることである。 賢明なベンジャミン・フランクリンは、これらの欠点を取り除かない限り、あまり向上できないことに気付いた。そこで彼は一週間ごとに沢山ある欠点の中から一つを取り上げ、連日戦うことにして、毎日の激しい戦いで、どちらが勝つか記録をつけた。このようにしてフランクリンは自分の欠点との戦いを2年間続けた。 彼がアメリカで最も敬愛され、第一に模範とされる人物となったのも決して不思議ではない。 ベンジャミン・フランクリンはすごい。おそらく欠点と戦った2年間はとてもきつかったと思う。しかしその2年間があったからこそ人格者として世間に知られるようになったと思う。 なかなか自分にはできないことだが、自分の「軸」となる本としていつまでもとっておこうと思う。
0投稿日: 2011.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ習慣によってつくれる多くのことをこの本から学びました。社会人必読本かと。とくに、うまく習慣をつくることができない人の、「気合入れ本」として。 年代が長年にわたっている点も、フランクリンが時代に生きた実感が湧き、よかったです。
0投稿日: 2011.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこの書を元に、多くのビジネス書、成功本や自己啓発本が書かれてきた。その原点をあたる楽しさと、著者が生きた時代の自伝としての面白さを併せ持つ本書。今も残る著者の箴言が、どのような状況で生まれてきたのかが感じられる。
0投稿日: 2011.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログまた訪れた幸運な出会い。『ビジネスマンのための「頭」の整理術』書評検索→ブログ「活かす読書」→右下に書評ブロガーマトリックス2010→「水野俊哉の日記」でそのマトリックス拝見→ブログ「俺と100冊の成功本」→フランクリン自伝を推薦
0投稿日: 2011.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ『3週間続ければ一生が変わる』の中でおススメの一冊として紹介されていた本。 一度読んでみようと思ってチャレンジしてみたのだが… 正直ちょっと読みにくい。 50年前の本だからなのか、単に自分の知識がないだけなのか。 目次をみて終盤がおもしろそうなのでそこから読もうかな。
0投稿日: 2011.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカ独立の中心的な存在であるベンジャミンフランクリンは、同時に電磁気学研究の第一人者でもあった。 彼は自らを律し管理することを重視し、その上で外部に目を向けていった。彼のような、自分を徹底的に厳しく支配しようとする生き方は見習わなくてはならない。
0投稿日: 2010.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログまだ途中までしか読めていないので、読了後に編集します。 「人生の成功」において必要なものの1つに、 「人との出会い」があると思います。 それは時に生涯の友となったり、ビジネスのパートナーとなったり、スポンサーとなったり、、、、。 では、そんな出会いが勝手にやって来るのか、と言えば決してそんな訳は無く、 フランクリンの場合、大の読書家で、さらに人を集めて頻繁に討論を行っていたこと、あるいはその勤勉さで、 評判を聞きつけて向こうから「会ってみたい」と思われる存在となったこと、あるいは知人や仕事上の部下などからの信頼を得て、 そこから新しい人脈を獲得することに成功したのでした。 つまり、「向上心を忘れない」ことが、「人との(幸運な)出会い」に繋がったのだと思います。 まさに、「グッドラック」を地で行った、そんな感じの人生だと感じました。 そして、今では超有名なフランクリンその人をとってしても、 必ずしも順風満帆な人生だったわけではなく、 成功までの間に数多くの受難やアクシデントに見舞われている、ということを知りました。 そこから、最後に必要なのは、「諦めない心」ということではないかと思いました。
0投稿日: 2010.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人を動かす」で紹介されていた、フランクリンって誰?? ってな感じで読み始めた訳ですが、フランクリンの仕事に対する真摯さや読書に対する取り組みに感銘を受けました。十三の徳を樹立させ、それを実施していく方法がすばらしかったです。 個人的に書かれている箇所も多く読んでいてつらい部分もありましたが、総合的にはかなり良かったです。 たまにはこういった自伝というものも良いな。
0投稿日: 2010.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ○処世術 ・議論好きという性質はともすると非常に悪いくせになりやすい ⇒どうしても人の言うことに反対せねばならず、そのためにしばしば極めて人付き合いの悪い人間になる。 ・いきなり人の説に反対したり、頑固に自説を主張しないで、謙遜な態度で物を尋ね、物を疑うといった風を装う。 (クセノファン「ソクラテス追想録」) ・計画を持ち出すときは、できるだけ自分を表面に出さないようにして、数人の友人が考えたこととする方がいい ・いきなり相手の主張の不当を指摘して、快をむさぼるようなことはやめ、これに答えるにも、まず最初に時と場合によっては君の意見は正しいだろうが、現在の場合はどうも違うようだ、自分にはそう思えるがなどと述べる。 ・他人の敵意のある行動を恨んでこれに返報し、敵対行為を続けるよりも、考え深くそれを取り除けるようにする方がずっと得なのである。 ・我々は他人の発明から多大な利益を受けているのだから、自分が何かを発明した場合にも、そのため人の役に立つのを喜ぶべきで、それを決して惜しむことがあってはならない。 ○文章力 ・立派な文章を選び、文の意味について簡単な覚書をつくる。それを数日間放っておいてから、今度は本を見ないで頭に浮かんでくる適当な言葉を使って、覚書にしておいた意味を引き伸ばし、原文にできるだけ近く表現しながらもとの文章に戻すことを試みる。 ○習慣 ・理性のある動物、人間とはまことに都合のいいものである。したいと思うことなら、何にだって理由を見つけることも、理屈をつけることもできるのだから。 ・習慣の変化は一歩一歩徐々にやるのが良いという考えには大して意味は無い。 ・十三徳 ①節制~飽くほど食うなかれ。酔うまで飲むなかれ。 ②沈黙~自他に益ないことを語るなかれ。駄弁を弄するなかれ。 ③規律~物は全てところを定めておくべし。仕事は全て時を定めてなすべし。 ④決断~なすべきことをなさんと決心すべし。決心し足ることは必ず実行すべし。 ⑤節約~自他に益なきことに金銭を費やすなかれ。すなわち浪費するなかれ。 ⑥勤勉~時間を空費するなかれ。つねに何か益あることに従うべし。無用の行いは全て断つべし。 ⑦誠実~偽りを用いて人を害するなかれ。心事は無邪気に公正に保つべし。口にだすこともまた然るべし。 ⑧正義~他人の利益を傷つけ、あるいは与うるべきを与えずして人に損害を及ぼすべからず。 ⑨中庸~極端を避くべし。たとえ不法を受け、憤りに値すと思うとも、激怒を慎むべし。 ⑩清潔~身体、衣服、住居に不潔を黙認すべからず。 ⑪平静~小事、日常茶飯事、または避けがたき出来事に平静を失うなかれ ⑫純潔~性交はもっぱた健康ないし子孫のためにのみ行うべし。 ⑬謙譲~キリストおよびソクラテスに見習うべし。 ⇒これらの1つをその週の課題として、厳重に注意する。 ・ものぐさは錆と同じで、労働よりもかえって消耗を早める。 ・怠けるところを自分自身に見つけられるのを恥じよ。 ・暇がほしくば、時間を上手に使って作れ。 ○節制 ・わずかの収入で生命と健康とを維持できる。 ○学習 ・飲食を節するとたいてい頭がはっきりして理解が早くなる。 ・ひとつのことを何度も繰り返すことで上達する
0投稿日: 2010.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々にめぐり合った素敵な本でした。 ベンジャミンフランクリンと言えば、科学者、出版業者、哲学者、経済学者、政治家、アメリカ資本主義の父など多才であるゆえ、フレンチ、イタリー、スパニッシュを軽くマスターしてしまう人。 ここまでスゲーと何やらどこかの貴族とかお家がいい坊ちゃんだとか思ってしまうのだが、貧しく卑しい生まれであったとフランクリンはよく引き合いに出している。 そこで空っぽの頭で何で彼がこんなにすげーの?って考えてみた。 やぱチョー有名なフランクリンの十三徳でしょ。 1. 節制 飽くほど食うなかれ。酔うまで飲むなかれ。 2. 沈黙 自他に益なきことを語るなかれ。駄弁を弄するなかれ。 3. 規律 物はすべて所を定めて置くべし。仕事はすべて時を定めてなすべし。 4. 決断 なすべきをなさんと決心すべし。決心したることは必ず実行すべし。 5. 節約 自他に益なきことに金銭を費やすなかれ。すなわち、浪費するなかれ。 6. 勤勉 時間を空費するなかれ。つねに何か益あることに従うべし。無用の行いはすべて断つべし。 7. 誠実 詐りを用いて人を害するなかれ。心事は無邪気に公正に保つべし。口に出ですこともまた然るべし。 8. 正義 他人の利益を傷つけ、あるいは与うべきを与えずして人に損害を及ぼすべからず。 9. 中庸 極端を避くべし。たとえ不法を受け、憤りに値すと思うとも、激怒を慎むべし。 10. 清潔 身体、衣服、住居に不潔を黙認すべからず。 11. 平静 小事、日常茶飯事、または避けがたき出来事に平静を失うなかれ。 12. 純潔 性交はもっぱら健康ないし子孫のためにのみ行い、これに耽(ふけ)りて頭脳を鈍らせ、身体を弱め、または自他の平安ないし信用を傷つけるがごときことあるべからず。 13. 謙譲 イエスおよびソクラテスに見習うべし。 7つの習慣のコヴィー先生の言葉を借りるならば、ミッションステートメントって奴だね。 彼の最たるものは、毎日十三徳をチェックして日々の悪しき習慣を徹底的に排除し、良き行いを習慣にしてしまった点である。特に一定期間にどれか一つに注意を集中させ、その徳が習得できたら、また次の徳へといった具合でだ。 その徳たちは数百年たっても、彼の文章全体に宿り、たった一度の人生をどう生きるか、そのひとつの解を与えてくれる。文才というものがあるのも一役買ってはいるのだが、何より事細かに記されている彼の勤勉さ、節制、配慮の行き届いた人への接し方、彼の人となりが自己を振り返らせる機会となる。ここまで人は模範的に立派に生きられるだろうかとも思ったが、それこそ十三徳を追求していた結果なんだろう。勤勉さが彼を多才にし、節制が多くの富を生み出し、若い頃磨いた文才が彼を有利な立場に導き、決して争わない物腰柔らかい接し方が多くの友を連れてきた。 最初は何も持たざる者であった彼が、それなりの財産と素晴らしい名声を日々の努力で手に入れたという事実が僕を元気にさせてくれる本でした。
1投稿日: 2010.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学者であるとともに出版業者、哲学者、経済学者、政治家、そして何よりもアメリカ資本主義の育ての親であったフランクリン(1706‐90)。その半生の記録
0投稿日: 2009.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログフランクリンの十三徳 1節制 頭や体が鈍くなるほど食べないこと。はめをはずすほどお酒を飲まないこと。 2沈黙 他人あるいは自分に利益にならないことは話さないこと。よけいな無駄話はしないこと。 3規律 自分の持ち物はすべて置き場所を決めておくこと。仕事は、それぞれ時間を決めて行うこと。 4決断 なすべきことをやろうと決心すること。決心したことは、必ずやり遂げること。 5節約 他人や自分に役立つことにのみお金を使うこと。すなわち無駄遣いはしないこと。 6勤勉 時間を無駄にしないこと。いつも有益なことに時間を使うこと。無益な行動をすべてやめること。 7誠実 だまして人に害を与えないこと。清く正しく思考すること。口にする言葉も、また同じ。 8正義 不正なことを行い、あるいは、自分の義務であることをやらないで、他人に損害を与えないこと。 9中庸 何事も極端でないこと。たとえ相手に不正を受け激怒するに値すると思っても、がまんしたほうがよいときはがまんすること。 10清潔 身体、衣服、住居を不潔にしないこと。 11冷静 つまらないこと、ありがちな事故、避けられない事故などに心を取り乱さないこと。 12純潔 性的営みは、健康のためか、子供を作るためにのみすること。性におぼれ、なまけものになったり、自分や他人の平和な生活を乱したり、信用をなくしたりしないこと。 13謙譲 イエスおよびソクラテスを見習うこと。
0投稿日: 2009.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ意思の力で自分の人格を向上させ、貧しい出自から成功をつかんだ努力の軌跡。 けっこうメソッドは具体的。
0投稿日: 2009.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ自伝だけど自己啓発本の一つに入る。 13徳という独自の徳を掲げることで日々を充実して生きたフランクリン。 読めば俺もやらなきゃ!!!って気持ちにしてくれます!!!
0投稿日: 2008.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人を動かす」にちらりと触れられていて面白そうだったので購入。 俺、小さい頃伝記大好きだったんだよね。 小学2〜3年くらいのときとか。 そういうことを思い出しながら楽しく読みました。 まじめにがんばると出世できました、というお話し。
0投稿日: 2008.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカの父ベンジャミンフランクリンの自伝、彼の考え方から「7つの習慣」は生まれた。 これだけ、多くの実績を残したフランクリンから学ぶべきことは大いにあるだろう。 (小谷)
0投稿日: 2008.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学者であり、哲学者・政治家としても有名なベンジャミン・フランクリンが記した自伝。 私が手にしたものは、初版から50年経過し、なんと67版という超ロングセラーだ。 フランクリンといえば、雷が電気だということを示すためにタコを使った実験したということで知られているが、そのほかにも多彩だったということを伺わせる。 考えてみれば、米国の最高額紙幣である100ドル札の肖像画になっているような人であるということは、それだけ大活躍をした人物だということの裏づけでもある。 さて、個人的には私の使っている手帳、フランクリンプランナーの元祖ということで大いに期待して読んだが、手帳に使われている手法、常に意識し自己改善(刃を磨く)していたのは、それほど長い期間ではなかったようだ。 それぞれの時期に最も適したことを行った結果が、後世までの彼の地位を不動にしたのだろう。 この本の中では、悩みもなく、すこぶる順調な人生を送っているように見えるが、米国の成功本の類は今でもこういったスタイルが多い。 きっと、苦労話を聞く人は多くないのだろう。 いや、苦労話を過去の武勇伝ということで喜んで聞く人が少ないということか。 著者の人となりがわかり、手帳の使い方のイメージも膨らんだ。 直接関係はないが、国を興したという意味では明治維新の立役者たちを思い出した。 自分で切り開く感覚、たまらないだろうなぁ。
0投稿日: 2007.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ米100ドル紙幣でもおなじみのベンジャミン・フランクリンによる自伝。貧しい家の出でありながら晩年には政界に進出し大富豪となった。彼の成功の秘訣として有名なのが「13徳」と呼ばれる道徳戒律(節制、沈黙、規律、決断、節約、勤勉、誠実、正義、中庸、清潔、平静、純潔、謙譲)。凄いのは、13徳そのものではなくて、その身に付け方である。13×7の升目を用意し、それぞれに徳と曜日を記入。今週一週間は例えば「節制」を身につけるぞ、と決めたら節制だけに注意してそのほかについてはもしこれを破れば×印をつける。一つも印が付かなければその徳はクリアしたことになる。一つの徳をクリアするのに最低1週間かかるから、すべての徳を一回りするのに最低3ヶ月、1年では四回回せる計算になる。これを年々繰り返していけば13徳の完全制覇も時間の問題というわけである。「徳」というとふつうは、特定の選ばれた人たちだけが例えば深く瞑想することによってなんとか接近可能な高尚な理念、という感じがするだろう。それを、だれでも一定の方式に従いさえすれば手軽に(!?)身に付けられてしまうスキルのようなものに変えてしまったフランクリンのやり口には、いかにもアメリカ!!という感じがして痛快だった。
0投稿日: 2006.10.11
