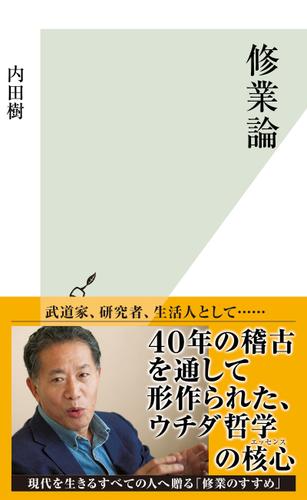
総合評価
(61件)| 7 | ||
| 24 | ||
| 15 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館にて借りる、第224弾。 (神戸市図書館にて借りる、第33弾。) なかなか面白かった。 神戸に道場をひらいてらっしゃることを知った。 なにより、 合気道を再開したいなぁ。
1投稿日: 2025.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ形にとらわれないということ。 居着かないということ。 現代の人は目標に向かって努力するが、 修行において目的は見えない。 見えないけれど、その先にある何かを信じ極める。そしてはじめの自分では想像もしない境地までたどり着く。 見えるもの把握できるものだけに、縛られないということ。 天下無敵とは、どんな相手と対峙しても勝てる、ということでは無い。 むしろ全ての敵を自分の一部にするということである。包含し、融合する。境界線は曖昧である。 自分という枠組みに、とらわれないということ。 イエスが海を歩く伝説を信じるか。 信仰とは、自分では理解できない現象が存在しうることを認めることである。起こりうると仮定することである。はなから否定することは、非科学的である。 信仰とは、自分の小ささを認めること。 この本に一貫する考えは、自分自身に居着かないという流動性である。修行とは、終わりのない自分自身の変革である。
0投稿日: 2025.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこの作家さん、武道家さんを知る最初の一冊‼️ 今後の期待を込めての星4つ‼️ 分かりやすい文章に好感が持てた‼️
0投稿日: 2024.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学を論じたりしていると同時に合気道の稽古を40年も続けているとは尊敬に値します。継続とは力なりで私も長く稽古を続けられるものを身につけたかったと思います。 さて、内田先生が合気道を始めたきっかけは自身の弱さを自覚していたから。身体的に虚弱であるために普通は強くなりたいと考えるのですが、先生の場合、自身の弱さの構造と機能について研究することだというのですから、いかにも哲学者らしい。 修業とは「いいから黙って言われた通りのことをしなさい」という理屈抜きのもの。努力すれば報われる、とか結果がこうなるとかではない予測不能、始める前は意味不明であくまで事後的、回顧的なもの。「努力とは一種の商取引である」という風潮からすると理解できないだろうと言います。 そして、稽古で身につけるべきもっとも大切な能力は、「トラブルの可能性を事前に察知して危険を回避する力」すなわち「生き延びるため重要な力」だと言います、稽古での力を発揮する場は現代では、生業の現場となります。ここでは集団をひとつにまとめる力が必要になります。非常時には「自我」がリスクになる。とは象徴的な言葉です。 昨今の雑踏での死傷事故や安易なsns利用で巻き込まれる事件などが思いあたります。 遥か昔に人類が身につけていた危険回避や集団で動く習性は生き延びるために必然でした。他者と共生する技術、同化する技術が、一見便利で安全と思われる現代では、より養わなければならない力なのでしょう。 この他にも、弱さと無知は同一の構造で変化することへのつよい抑制だと述べています。「無知」とは学び変化することを妨げる力である。学校教育がなすべきことは、学生の頭にぎっしり詰まって、どろどろに絡みついて、ダイナミックな「学び」の運動を妨げているジャンクな情報を「抜く」ことだというのは流石です。今の世の中、情報はネットの海に溢れそれに溺れている者を救うのは容易なことではありません。
0投稿日: 2022.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
問い 修行とは何か。 自分はどのように修業すべきか。 答え 修業は、「私の心身のパフォーマンスを低下させる要素」を最小化(できれば無化)することを目的として行う。それは、実はめざしていたものとは異なるものが得られる過程でもある。 「道場は楽屋であり、道場の外が舞台である」。舞台とは「真剣勝負の場」である。生業と稽古は表裏一体のものでなければならない 要するに、生業でのパフォーマンスを上げるために修業する場を自覚的にもつということ。 キーワード 修業、天下無敵、石火の機、卒啄の機、木偶坊・操り人形・案山子、弱さ・無知、居着き、科学的と科学主義的、鍛える発想、稽古、瞑想、額縁、狐疑・駝鳥、キマイラ的身体・複素的身体、自我着脱の訓練、安定打座、「我なし、敵なし」、ブリコロール、無刀の刀 抜粋 因果論的な思考が「敵」作り出す (武術は、)実践的な意味での生き延びる力である。 戦場では、先頭能力として示される力が、平時では例えば統治能力として顕現する。生き延びるためにもっとも重要な能力は、「集団をひとつにまとめる力」 「敵」とは「適切な方法を採れば、事前に除去しうるパフォーマンス向上の阻害要因」 「無敵」とは「私の心身のパフォーマンスを低下させる要素」を最小化(できれば無化)することが意味する。 「額縁」というのは、「絵を囲っているもの」である。「この中に描かれているのは現実ではありません。絵です」ということを私たちに指示するのが額縁の役割である。=「現実と非現実の境界線」 目の前に出現した「もの」に、最適の「意味の度量衡」をあてがうこと 「額縁を見落としたものは世界のすべてを見落とす可能性がある」 「私たちが適切に生きようと望むなら、そのつど世界認識に最適な額縁を選定することができなければならない」 瞑想のもたらす最も重要な達成は「他者との同期」である 「今・ここ・私」という不動の定点と思われたものから離脱して、「今」ではない時間、「ここ」ではない場所、「私」ではない主体の座に移動することである。 人間は汚れた場所では祈ることができない。祈りとは幽かなシグナルを聴き取ろうとする構えのことである。祈るためには五感の感度を最大化しなければならない。 (天才は)修業が不要な人のことではない。天才とは、自分のしているルーティンの意味を修業の早い段階で悟り、それゆえ、傍からから見ると「同じことの繰り返し」のように見える稽古のうちに、日々発見と驚きと感動を経験できる人のことである。
2投稿日: 2021.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ手軽に読めるエッセイだけど噛めば噛むほど味がでる書物(あとがき)なのが、内田先生らしい良書です。 この方、物凄く頭の良い方だと思うので、権威ばって難しく書こうとすればいくらでもできるのでしょうけど、どうやら無知蒙昧なバカな子供(私も含め)を啓蒙することをご自身の天職とお考えのようです。本書のテーマの一つに、「修行や学びは成し遂げた後になって初めて回顧的に理解できるように構造化されている」ということで、本来は、「分かってる人たち」と「分かりようもない人たちたち」に分断されているばずなのですよね。低いレベルに居着いている我らには、文字通り想像もつかない世界があり、そこは本来隔絶されてるのだけど、そこをできるだけ分かりやすく架橋しようとして不思議なサービス精神を発揮しておられ、なかなかこういう人はいない(だから人気)と思うのです。 内田先生には多くの著作があるのですが、「学び」を語らせると真骨頂で、根っからの教育者なのだろうと思いました。 あと、瞑想の章で、「自我は額縁であり、必要なときには着脱できなければ危機を生き延びることは難しい。その訓練が瞑想なのだ。」とありました。 レベルが異なる話かもしれませんが、コロナ禍で大量発生している歪んだ自我の洪水を見るにつけて、「生き残れない集団なんだな我々は…」と感じています。
1投稿日: 2021.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代遅れに聞こえる修行というものの意義がよく分かる。いつの間にかこんなところにきていた、というのが修業の成果。最後の坂本龍馬の話は読み飛ばし。
0投稿日: 2021.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ合気道を素人なりに齧っていると繰り返し聞かされる言葉に、「合気道の最強の技はなんですか?」との問いに塩田剛三先生が答えたという「自分を殺しにきた相手と友達になることさ」というのがあります。 合気道にも流派がありますが、著者の「武道家が目指す『天下無敵』とは、誰にでも勝つということではなく、、だれとも敵対しないこと」との趣旨の言葉も究極的には同じことを指しているのでしょう。 著者は、ここからそもそも敵とは何か、と考察を深めて、「私の心身のパフォーマンスを低下させるもの全て」と捉え直します。つまり敵が目の前にいないということは今の自分が可能な限り平静である、ということになるのですが、これをさらに進めると平静で無くなる「私」とは何か、という話になってきます。こうして、相対するものと相和す、気を合わせる、すなわち合気道とは決して神秘論ではなく、不測の事態に反応して押し勝つのではなく、外的な全てと同期する技術だということ、それは多かれ少なかれ武道に共通する思考回路だということが解き明かされていきます。 著者の議論はつねに著者本人の経験から語られるので、例えば西洋やアジアの他の国ではどうなのか、といった、普遍性のある議論にはつながっていきません。しかし、個人の体験として確かに腑に落ちるものを含んでいます。 戦前から、政治家や軍の将軍などが道場で稽古に励んだと言いますが、それは外敵を路上で倒すためではもちろんなくて、こうした瞬時の平静、言い換えれば危機での判断を研ぎ澄ますためのトレーニングだったとの捉え方は、まさに現代に生きる我々にとっての「修業」の的確な要約なのでしょう。
7投稿日: 2021.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログP11 はっと気がつくと 誰もいない場所を一人で走っている。 修業とはそういうものである P40 「天下無敵」とは 敵を「存在してはならないもの」と とらえない、ということである。 そういうものは 日常的風景として「あって当たり前」なので、 特段きにしないという心的態度のことである P41 因果論的な思考が「敵」を 作り出すのである P42 因果関係の中に身を置かない P53 心身のパフォーマンスを 低下させるすべてを敵と呼ぶ P55 武道修業の究極の目的は 「無敵の探究」である P58 「我執を脱する」という努力が、 達成度や成果を自己評価できる ものである限り、 その努力は「我執を強くする」方向に しか作用しない
0投稿日: 2020.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ幼児の神のくだりが最高に良かった なぜ レヴィナスと武道に傾倒したのか 分かりやすかった この本は 価値あると思う! 上から目線に聞こえたらごめんなさい
2投稿日: 2019.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ文化放送の武田鉄矢今朝の三枚おろしで、取り上げられていたのがきっかけで読んでみた。期待した程に良くなかったけれども、次の引用箇所がとても良い。 p203「そもそも原理的に言えば、「無駄な稽古」というのはないのである。いくらやっても上達しないというのは、ある意味で得がたい経験である。「なぜ、これほど稽古してもうまくならないのか」という問いをまっすぐに受け止めて、稽古に創意工夫を凝らしたものは、出来のいいプログラムを丸呑みして無駄なく上達し、ついに悩んだことがないというものよりも、しばしば深い。」 この部分があったからこの本は良いと言える。
3投稿日: 2019.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
好きな著者・内田氏の修行についての考え方。 【修行の意味は、事後的・回顧的にしかわからない】 ここでいう修行は、「与えられた努力を要するもの」という意味合いに捉えている。例えば、「古典を読みましょう」とか「滝行しましょうとか」。 その先には、「先人の知恵を得られるぜ!」「次の国語のテストでいい点取れるぜ!」というインセンティブを事前に与えてやらせることはできるけれど、それは修行の価値ではないよ、ということ。 本質的な価値は、古典を読んだ後に残る、「古典の思考を得られた」「点数の取り方がわかった」「好きな作家ができた」かわからないけれど、「個の意味付け」によって決まるから、事後的なんだよ、ということだ。 インプットは同じでも、それを介在する人が十人十色なので出てくるアウトプットがばらばらになる。至極当然。 でも現実は周りに決められた価値で染められてしまう・染められた方が楽だなと思う場合もあるから、まずやってみて、自分で解釈しないとだな。
0投稿日: 2019.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
社会が十分に正義でありながら、かつ十分に手触りの優しいものであるためには人間の生身が必要である。その生身の人間の弱さ故に人は修業するのだろう。生き方の知恵を効率よく学ぶより、日々の経験の中で感得するものである、と言える。
0投稿日: 2018.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ修行論は、内田樹さんの本で過去に実本で購入したんだけど処分してしまっていた。久しぶりにタイトル見て懐かしいな、と思いダウンロードして読み直したけど、相も変わらずの内田節満載で非常に面白かった。4つの文章を1つの本にまとめているので、ご本人曰く「幕の内弁当」の様な本とは書いてあるけど、どの文章も修行というのは何なのか、という本質に切り込んでおり、多面的な視点で修行についてわかるので非常に面白い本でした。また、忘れた頃に読み返したい。ただ、内田さんの語りは結構繰り返しが多いので、内田さんの類書を読んでいる人は、割と重複する内容も多いのでその点のみ要注意ですね。
0投稿日: 2017.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦はいつはじまるか判らない。 つまり、その瞬間に最大のパフォーマンスを発揮できるようにするのが日々の稽古であり修行である。 故に「次の○○大会を目標に頑張る…」などというのは、余り賢い発想とは言えない。 とにかく生き延びること。 それ以外の、例えば競争相手やタイムなどは全然取るに足らないモノである。 その生涯を通して走り続けるところに意義がある。 鉄人レースの醍醐味もそこにある。
1投稿日: 2017.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログまたしても魅力的な作品。 内田樹さんは、ハマるとぐいぐい心にヒットする。説明できないと思っていたことが、文章になっている。わかりにくそうでとてもわかりやすい。この作者に出会ってよかった。 無傷の完璧な状態にある私を「標準的な私」と措定し、不具合が生じている自分を「的による否定的な干渉の結果」と説明していることが、そもそも敵をつくる。因果論的な思考が作り出す。 敵を忘れ、私を忘れ、戦うことの意味を忘れた時にこそ人は最強になる。 自分の弱さの構造と機能について研究すること。 →辻信一さんの著書と通ず。 努力する方法を変える時、今までの評価軸が崩れるため、目標がわからなくなることから非常に抵抗をする。ただ、質は変化する 哲学者は「弱さ」は語らないが「無知」は語る →変化することへの強い抑制 心身の能力を開花させるには、 何か新しいことが加わるごとに、それを受け容れ組み込めるように、全体の構造が基礎から組み替えられるような、総合的な柔軟性をもつこと。 キマイラ的 複数の構造体、運動体がひとつになっていること 。異質なものの合成。 カタストロフ 突然の大変動。大詰め。 自我 自分ひとりの五感や価値観に居着き、自分ひとりの存在を優先し、他者との協働身体の構成を拒む 漸近線 限りなく近づくが交わらないし、接しない 錬度 訓練を積み重ねれ得られる熟練の程度 共振 振動する物体が、外部の振動と同期して更に大きく振動すること 自分が知的に探求していること 身体が感覚的に探求していること、は 同じものにいきつく 修行のメカニズム 師匠と生活を共にしていると、呼吸があってくる。共感度が増す。
0投稿日: 2017.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ引き続き「氣」についての知識を集めている。Web検索の合気道で引っかかったので読んだので、そもそも認識がずれている「修行の本」という事だったので、自分のリサーチ不足がいけないのだが、それでも内容が読みづらい。 ずいぶんややこしい物の考え方をするのだなと思う。カタカナをよく使ったり、本をよく読む私でも見慣れない言葉が多用されているあたりは、著者の我を感じる。 アプローチは面白いとは思う「強さの研究ではなく、自分はなぜ弱いのかの研究」だが、内容は殆どよく分からなかった。 その中でも興味のある一節 私達は普段、「ここまでは現実で、ここから先は非現実」という境界線を守って生きている。だが、武道では練度があるレベルに達すると、そういう因習的な内外の主客の境目が曖昧になってきて、自他のボーダーを越える「出入り」が可能になってくる。
0投稿日: 2017.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ『下流志向』(講談社文庫)や『先生はえらい』(ちくまプリマ―新書)と同じテーマを扱った本ですが、それらの本が既存の知性への批判が中心だったのに対し、本書では既存の知性に代わる身体に根差した知性のありようを「修業」という言葉によって直接的に論じているような印象を受けます。 書き下ろしではなく、著者がこれまでに発表した4編の論考をまとめた本です。とくに「修業論―合気道私見」と題された最初の論考がもっとも著者の思想がまとまって提出されているように思います。 なるほどとうならされるところも多かったのですが、やはり「身体の知」を批判原理としてではなく、直接的なものとして語ることには危うさを感じてしまいます。「修業の意味は、事後的・回顧的にしかわからない」と著者は言いますが、そうだとすればなおのこと、それは従来の知のありように対する批判原理にとどまるべきものであるはずです。そうした知が直接的に提示されてしまえば、それはあらかじめ批判的検討を封じてしまう独断的なものに堕してしまうか、あるいはそうでなくとも、私たちには独断と区別する術が存在しないようなものと言わざるをえないのではないでしょうか。
0投稿日: 2016.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログhttp://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334037543
0投稿日: 2016.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ修行とは何か、というところは今一つだった。面白い考え方はいくつかあったが。 修行の意味は、事後的・回顧的にしかわからない。 努力させる以上は、努力した後に手に入るものを、あらかじめ一覧的に開示しておいてほしい。そうすれば努力するインセンティブになるから、という人が多い。 修行の意味は事後的にわかる。そのため、修行がもたらす成果を、修行開始に先立ってあらかじめ開示することは不可能なのです。 敵とは新進のパフォーマンスを低下させるすべてのファクターのこと。ライバルも含まれるし、腹下しもインフルエンザウイルスも、加齢現象も、財務状態の悪化も、家庭争議も含まれる。 自分の意志で身体組成を現に改変しているという事実がはっきりと数値的に表示されるとき、それがもたらす「私は私の身体を支配している」という全能感はきわめて強烈なもののようである。 ものさしでは重さが図れず、はかりでは時間がはかれないのと同じことである。運動の質が変化するというのはそういうことである。 減点しても、それで術技が向上するということはない。「減点できる」ということは、「満点を知っている」ということが前提になるからである。 聖典のうち、自分が真実であると判定した箇所だけを信じ、自分が嘘だと思う貨車は読み飛ばす権利が自分にあると思っているものを、信仰を持つ人と呼ぶことは難しいと思う。 私を強めるための努力より、相手を弱めるための努力のほうが効果的。ものを創るというのは難しいし、手間はかからうが、ものを壊すのは容易であり、かつ一瞬の仕事だから。 額縁を見落としたものは世界のすべてを見落とす傾向がある。私たちはあらゆる世界認識に際して、額縁はどこかという問いを視点に置くことになる。
0投稿日: 2016.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログけれども、兵法者の仕事を妨害するものがいる。それを「反−兵法者」と呼ぶことにする。「勝負を争い、強弱に拘る」ことをつねとする人間のことである。 彼は、キマイラ的身体というようなもののあることを知らないし、その機能も有用性も知らない。反−兵法者は自我に固執する。自分ひとりの五感や価値判断に居着き、自分ひとりの生存を優先し、他者との協働身体の校正を拒む。 そのような利己的個体は、どのような危機的状況においても必ず出現する。そして、あらゆるハリウッド・パニック映画が教えるところでは、そのような人間が真っ先に死ぬのである。 説話原型的にはそういである。だが、説話原型が「そう」であるということは、「ほんとうはそうではない」ということを意味している。同じ話が倦むことなく繰り返し語られるのは、その教訓が少しも生かされていないからである。 残念がら、危機的状況において、人々は類型的な経験則に従って粛々と適切な行動を選択するわけではない。もし、いつでもそのように集合的な叡智に従って人々が行動しているならば、パニック映画など誰も作らないし、誰も見ないはずである。 これだけ執拗に恐怖譚やカタストロフを生き抜く物語が語られ、そのつど「危機に際会したときに自我を手放さない利己的人間のもたらす災厄と、彼の破滅」について描き続けているのは、そういう人間が類的な意味でほんとうに危険な存在であるにもかかわらず、そのような人間がいなくならないからである。 自己利益の追求を最優先し、「勝負を争い、強弱に拘る」利己的個体であることの方が、平時においては資源配分の競争において有利である。だから、平時が続けば、人々は自己利益の安定的な確保を求めて、どんどん「反−兵法者的」になる。なって当然である。 けれども、平時は長くは続かない。どこかで必ず、破局がやってくる。そのときに反−兵法者的な人々は、破局をさらに破局的な状態に導く最悪のリスクファクターになる。 幼児は鏡を見ながら、その動きを真似る。母親の表情筋の使い方を模倣して自分の表情筋を動かし、「笑う」という動作を学習し、それがどういう感情であるかを学習するのと同じことを、鏡像を相手に繰り返す。私たちは感情がまずあり、それが表情に表出されるというふうに考えがちだが、実際には他者の表情筋の模倣を通じて、他者の感情を取込み、それに同化しているのである。
0投稿日: 2016.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹著「修行論」 「修行」について書かれた内容ですが、武道のような身体的なことだけでなく、内田先生らしい思想的な面も多く書かれています。 ●努力と成果の相関 「努力と成果の相関」を信じて修行すると、人間の身体をシンプルなメカニズムとしてとらえてしまう。 そして「強化」ということを優先的に考えると、どうしても努力と成果の相関を数値的に現認したいという欲望に取り憑かれてしまう。 その例が「ダイエット」である。 「私は私の身体を支配している」という全能感は、きわめて強烈である。 ●他者の成長を阻害する理由 相手の成長を阻害したくなる理由として、勝負において「私が強い」ということと「相手が弱い」ということは、実践的には同義であることがあげられる。 そして「私を強める」努力よりも「相手を弱める」ための努力の方が、効果的なのである。 なぜなら「ものを創る」のは難しいし、手間暇がかかるが、「ものを壊す」のは容易であり、かつ一瞬の仕事である。 だから相対的な優劣、強弱、勝敗に固執すると、人は無意識のうちに、同じ道を進む修行者たちの成長を阻害するようになる。 ●「生きる力」を中心に 生命活動の中心にあるのは自我ではなく、「生きる力」である。 自我も実存も直観もテオリアも超越的主観性も、生命活動の中心に座することはできない。 内田先生の文章は痛快ながらも、日々感じる「モヤッ」とした現象を、明確で分かりやすい言葉で表現してくれるなあと思います。 時々自分に刺さる痛い言葉もあるのですが、それで目から鱗がボロっと落ちることも多く、これからも読み続けたい作家さんです。
0投稿日: 2016.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の時代、何かを求めれば、すぐに得られるようになってきた。人々は、見返りを期待して行動しがち。 長時間ふんばることは、どういうことか。それを考えたくて読んだ本。 時代の流れが速いからこそ、今、もらえない見返りは 将来的な価値がなくなるのか。 そうではない、普遍的な学びもあるはず。 生き延びる能力=これを鍛えるのはどの時代も同じ 集団をひとつにまとめること。 敵とは、わたしの心身のパフォーマンスを低下させる要素。これを物体的な敵に限定しないひとのほうが、生き延びる確率が、あがる。 何かの因果論があって、心身パフォーマンスが低下する。 修行とは、現在していることの連関が、開示されていない。
0投稿日: 2015.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ道場は楽屋であり、道場の外が舞台 武道の目的は強くなることより、弱さを小さくすること 日々の生活が稽古になる生き方
0投稿日: 2015.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
いつもながら教育論に通ずる気づきが非常に多い。 龍馬の修行について、そこにフォーカスしない司馬遼太郎の考え方ではなく、そこ自体に興味がわいたので深堀って欲しかった。 〈問い〉 ①合気道って? ②鍛えるとは何か? 〈敵とはパフォーマンスを低下させるもの全て。無敵は、それが敵だと思う自分を消すこと〉 ① 合気道の世界には「これでもうよい」という終着点はなく、常に上がある。だから、常住坐臥、日々の生き方そのものを稽古にしていく。 ② ・師匠が弟子を殴って何かをさせると、「殴られたくないからやる」という弟子側の合理性基準に合わせていることになる。そうすると、弟子は自分の合理性判断の客観性を過大評価になる。だからあまり採用しない方が良い。言葉で殴るのも同様だろう。 ・批判によって強化される「減点法」のマインドセットそのものが「負の力」をはらむ。減点法は、作り出すものより、損なうものの方が多い。減点するには、満点の状態を知っていないとできない。しかし、満点の状態を知っているという事実が、単一の度量衡に居着いていることになる。それ自体が致命的。
0投稿日: 2015.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田先生の本にしては何となく入ってきにくいなぁ(すみません!)と思いながら読みましたが、考えてみればそれもそうか、と思いました。 この本で繰り返し語られていることは、今見聞きしている世界(や自分という存在)は唯一無二のものではない。その枠組みを取り外すことこそが修業だ、ということでした。 当たり前と感じるものが当たり前じゃないと言われているわけですから、入ってきにくいわけです。 そのことを体得するにはそれこそ長い年月をかけた修業が必要なわけで、一読しただけで実感できないのは当たり前かもしれません。 あとがきにもあるように『噛めば噛むほど味の出るするめみたいな書物』とすべきなのかなぁと思いました。
0投稿日: 2014.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ僕が内田先生の話に耳を傾けるかというと、 それは先生の思想が「身体性」に裏付けられているから。 その「身体性」の元になっているのが、「身体的な」哲学者レヴィナスの思想と合気道なわけで。 修行について書かれた本書を読むことで、その思想のエッセンスに触れることができました。 今回も思考の額縁が少しずれるという、心地よい世界観の変化を体験しました。 「いくらやっても上達しないというのは、ある意味で得難い経験である」という先生の言葉は、 いくらやってもゴルフが上達しない僕にはとても嬉しい言葉でした。
1投稿日: 2014.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹さんが修行・修練について哲学を述べています。 自分は哲学のコトはよく分かりませんが、文章からは修行への心構えのような、また気休めのような印象を受けます。 読みやすいのですが、分かりやすいか?と問われれば返答に困る一冊です。
0投稿日: 2014.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログいま認識しているところの延長ではなく、別の次元にうつる感覚。 不射の射。 やっているときはわからないけれど、振り返ってみて気付くことに近いのかな? C0230
0投稿日: 2014.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「修行」じゃなく「修業」。 『稽古は、競ったり、争ったり、恐れたり、悲しんだりすることを免れて、ただ自分の資質の開発という一事に集中することが許された、特権的な時間である。道場はそれを提供するための場である。』(P115) 『「いるべき時に、いるべきところにいて、なすべきことをなす」ことができる能力。それが武道修行が開発すべき能力である。』(P212) またいつか。 20140818
0投稿日: 2014.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
武道をやっていなくても,スポーツにしろ何にしろ高みを目指すために大切ことが書いてあり勉強になりました.
1投稿日: 2014.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
喩えて言えば、「鍛える」というのはハードディスクの容量を増やすことであり、「潜在的な能力を開花させる」というのはOSをヴァージョンアップすることである。p96 「私たちが適切に生きようと望むなら、そのつど世界認識に最適な額縁を選択することができなければならない」p127
0投稿日: 2014.04.24「キマイラ」がよく分からなかった
何ができるようになるのか分からないまま、師の命じる通りのことを、意味が分からないままやる、というのは、「下流志向」その他でお馴染みの内田教育論。至極ガテンがいくのだが、その先の「キマイラ」が正直よく分からなかった。格闘する両者がキマイラと化し、自分が主導権を握る、というのなら、相手は弟子以外あり得ないじゃないか、と思ってしまう。自分に格闘技の素養が無いからだろうか? 合気道やれば分かるのだろうか?
1投稿日: 2014.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ入試の現代文で頻出の内田先生の文章。本書も引っ張りだこなこと間違いなしと思いながら読み進めました。それほどに読みやすくわかりやすくまっとうな文章です。
0投稿日: 2014.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログHANDSの行き帰りシリーズ2冊目です。 修行とはなにかばかりなのかと思えば、弱さについて考えたり、認知のことを書いていたり、とても参考になることが多かったです。
0投稿日: 2014.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「額面を見落としたものは世界のすべてを見落とす可能性がある」「先人が工夫したあらゆる心身の技法は生きる知恵と力を高めるためのものである」「私たちが適切に生きようと望むなら、そのつど世界認識に最適な額縁を選択することができなければならない」(p.127) ホロコーストは、人間が人間に対して犯した罪である。人間が人間に対して犯した罪の償いや癒やしは、神がなすべき仕事ではない。神がその名にふさわしいものなら、必ずや「神の支援なしに地上に正義と慈愛の世界を打ち立てることのできる人間」を創造されたはずである。自力で世界を人間的なものに変えることができる高い知性と徳性を備えた人間を創造されたはずである。 「秩序なき世界、すなわち善が勝利し得ない世界において、犠牲者の位置にあること、それが受難です。そのような受難が、救いのために顕在することを断念し、すべての責任を一身に引き受けるような人間の全き成熟を求める神を開示するのです(エマニュエル・レヴィナス『困難な自由』)(p.170) 好奇心にかられてドアノブを回して、見知らぬ空間に踏み込んだ学生は、その探求の行程の最後で必ず「思いがけないところに通じる扉」か「思いがけない景観に向かって開く窓」か、どちらかを見出す。(p.173) 悪とは「人間的スケールを超えること」。あらゆる非人間的な行為は、人間の等身大を越えた尺度で「真に人間的な社会」や「真に人間的な価値」を作り出そうと願った人たちによって行われた。自分の生身が届く範囲に「正義」や「公正」の実現を限定しようとせず、自分が行ったこともないような場所、出会うこともない人たち、生きて見ることのない時代にまで拡がるような「正義」や「公正」を実現しようとした人たちは、ほとんど例外なく、世界を人間的なものにする事業の過程で、非人間的な手段(抑圧や追放や粛清)を自分に許した。(p.180) 修行では、愚直にある技術を反復練習する。そのうちある日、自分の術技の質が変わっていることに気がづく。それまで「そんなことができると思っていなかったこと」ができるようになるのである。 ここで重要なのは、この「そんなことができると思っていなかったこと」は、「この技術を身に付けよう」と思ってそれに向かって努力していた当の技術とは、まったく別のものだということである。稽古の所期の目的と違うところに「抜け出る」。それが修行のメカニズムである。(p.189)
0投稿日: 2014.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むと色んなことに意欲がわいてきます。 過度に目的に捉われることなく、これからも自らの好奇心に従って広く伸び伸びと学んでいきたい。
0投稿日: 2014.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ特に、第1章「修業とはなにか」、第2章「無敵とはなにか」。もっと若い時この文章に接していれば、自分も今とは違った生き方ができたのかもしれない。稽古への考え方も、改めなくてはならないと思った。 さらに、Ⅲ「現代における信仰と修業」。「自分の生身が届く範囲に正義や公正の実現を限定」することの大切さ。肝に銘じたい。
0投稿日: 2014.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田先生の修業論。方々に書いた原稿をまとめて収録。 広い意味での修業というより、合気道の修業からの知見を書いていて、しかしやっぱり、広い意味につながってくるか。 印象に残ったのは「道場は楽屋だ」という言葉。合気道が試合を主にする武道でない以上、本番は、実生活だという。武道修業で培うものを役立てるのは、実際の生活・仕事という場所で。 また、修業というのは目標に向かっていくうちに新しい景色が開け、はじめの目標や目論みからどんどん逸脱していくものだ、という言葉もよかった。 合理や効率でない修業、 また読み返したい。
0投稿日: 2013.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ今考えていることとシンクロして非常にレベルアップできる本、非常に言葉使いも庶民派でわかりやすい。 千里眼、空中浮遊とか、オカルティズムではなく、人間の潜在的能力の可能性という視点で共感できた
0投稿日: 2013.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹という作家は最近粗悪品濫造のきらいがあったが、本書は4章を除けばかなりまっとうな書である。 敵=万全の自分を阻害するもの、キマイラとしての同機、「いま・ここ・私」を離れるための瞑想など面白いと思わせる部分がある。 一見意味がないと思われるルーティンの反復から何を得るかという視点は今さらながら再認識されていいだろう。 ただ、相変わらず歴史を語り出すと、てんでダメ。論述の方法がなってない。
0投稿日: 2013.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ人と対したときに生まれる社会的役割をよりよく果たすためには,まず自分がよりよい生物の固体である必要がある,とぼくは思っています。 上司,同僚,部下,友達,恋人,兄弟,息子,親,隣人など,相手によって僕たちはいろんな役割がある。その役割は相手があってのことだから「じゃあね」と言ってその相手と別れた瞬間にとりあえずはその役割から解放される(もちろん離れていても役割は続いているのだけども,対面のときよりは気配りは下がる)。なので,よりよい〇〇であるための努力の度合いが下がる。で,相手との関係性や場面よって自分の価値判断の基準は多少変わってくるので,僕らが何かにつけて下す判断はその時々に合った(ということは多少一貫性のない)ものになる。相手や場面によってぶつ切りの人間というか,そういうイメージ。アプリとかソフトを立ち上げてその都度対応するのとちょっと似てるかな。で,よりよい〇〇あろうとするためには,それぞれの場面で役割にあうカタチに自分を変える努力をしなくちゃいけないことになる。 忘れられがちだけど,そういう社会的役割って,自分が「生きている生物の個体である」っていう大前提の上に成り立っている。生物の個体であるってことは、まず私は Mac ですとか私はプレイステーションです,みたいな,自分がある特徴をもったハードウェアであるってこと。これを自覚するのがけっこー重要だとぼくは思ってる。本体が安定してないとソフトも安定して使えないのは当然なので,そっちの方が根っこなのは間違いない。だから,自分が上に書いたようなよりよい〇〇であるためには,ソフトの設定を調整することももちろん重要だけども本体のパフォーマンスを上げて落とさないことに気を遣う方が,同じ時間労力を注いだときのリターンがより広範囲に及ぶことになる。だから,まず自分が生物の個体としてより良くあろうとすることってのがすごく重要。… つづきはこちらでお読みください! http://blog.livedoor.jp/h_ohiwane/archives/52042803.html
0投稿日: 2013.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ武道家としての内田論で私には難しかった。 ただし、中島敦の『名人伝』の「無射の射」の解説と司馬遼太郎の書く剣豪たちへの考察はおもしろかった。
0投稿日: 2013.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹さんが「修業」について書いた本。 修行ではなく、修業としているところが、本気っぽい。 本書にも共感する部分は多かったけど、自分も含めて、武道にまったく疎いひとにとっては、内田さんの他の作品に比べて少しわかりづらかったように思う。 修業とは、将来こうなるため、にあるものではない。いつの間にか、知らない場所に出ていることである。 弱さを敵とみなさない。弱さと共存する方法を追及するのが武道である。 これらの部分に共感しました。合気道をやってみたくなる本。
0投稿日: 2013.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ武田鉄矢氏のラジオでの紹介で知り読み始めました。 当たり前に日常を生きていたら絶対にぶつからない世界。「何かが違う」違和感を持ち続けている人達へのメッセージ。勝ち負けで一喜一憂する事よりも深いことでしょう。名人伝の別のバージョン、あるいは解説書ともとれます。 キマイラの頁では大相撲をの取組を想像しました。相対して勝ち負けを競っているのではない。行司、審判、観客も含めての一つの'大相撲'になるのだと。立会いから決まり手までの流れが石火の機、啐啄の機であるのでしょう。それはアマチュアの自分有利に立とうとする立会いの相撲とは質を異にする。かつての落語家が落研出身者を弟子にとりたがらなかったのも分かります。 著者も書かれているように'するめ'のように何度も噛みごたえのある良書だと感じました。
0投稿日: 2013.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ修業の基本は、「黙って言われた通りにしなさい」というスタンスです。でも、「~しなさい」と言われると「それは何の役に立ちますか」と質問したくなります。 僕が子供の頃は「理由なんかない。やれ」という世界が、家族以外にも学校や地域との関係の中に残っていました。 ある意味、修業だったのかも。 内田氏の教育論の根底にあるものを見ることができたように感じられました。
0投稿日: 2013.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近気に入っている著者(昔から読んでいましたが)が合気道・武道に 関して、それから宗教と冥想に関して、最後に司馬遼太郎と坂本龍馬に ついて書いた本。 面白かったです。 無敵の解釈。敵の解釈として『私の心身のパフォーマンスを低下させるもの』 という解釈とそこから見出された無敵の解釈。昔武道(剣道)をやっていた 私としてもよく分かる部分が多い内容です。額縁をずらす。キマイラ的身体の完成。中島敦の名人伝。レヴィナスによる正義と悪について。等々。。 日々の生活や仕事への態度として非常に役に立つというか 根幹としてもっている感覚に合っているし基準となる考え方です。
0投稿日: 2013.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログhttp://kumamoto-pharmacist.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/post-424b.html
0投稿日: 2013.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ修業とは何か ということは、日本的なもので、なんとなく その 本のネーミングで とびついた。 身体と言葉の一体性というものが説かれているのかと思ったが 全然違った。 鍛える という言葉には 数値的な物差しがあるが 修業には それがないということが、繰り返し語られて 何となく納得した。いかにも日本的だと思った。 天下無敵とは何か という考察が 気に入った。 結局は 敵ではなく 私なのだ。 この修業論をよみながら、 池波正太郎の 剣客商売の 秋山小兵衛 をおもいだした。 加齢にも関わらず、歳をとっていくにもかかわらず、 小兵衛は 昔とった杵柄で 活躍する。 そして 息子も 徐々に成長していく。 あぁ。成長とは そういうことなのだ。 瞑想論 宗教の信仰心は おもしろいが ちょっと、よくわからない感じだった。 司馬遼太郎の坂本龍馬についての指摘は なるほど。という 鋭い指摘で、 なぜ 修業ということを 無視したのかを 司馬遼太郎の軍隊生活の 理不尽に対する怒りが背景にある というのは、実に卓越した見方である。
0投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ司馬遼太郎の「修行嫌い」の考察が面白かったです。龍馬も土方も、千葉周作もいきなり剣に強くなったかのように描かれてしまう。龍馬のブリコルール性、その状況においてもっとも有用なものを特定し、携行する物語りとして、長大な刀により差料、差料よりピストル、ピストルより万国公法があげられており、龍馬の哲学を感じます。どんな敵がきても対応出来る準備をしている。
0投稿日: 2013.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半二編は「いつもの話」だけど、後半二編に意外性があって楽しかった(編集さんがいい仕事した、と思った)。 第三部「現代における信仰と修行」 実は私の学部の母校(ICU)はヴォーリズによる建築。神戸女学院もヴォーリズとは知らなかったけど、その考察にはハッとさせられた。 「建物を実際にご覧になるとわかるけれど、ヴォーリズの建物には無数の暗がりがある。」(p.173) 「好奇心にかられてドアノブを回して、見知らぬ空間に踏み込んだ学生は、その探求の行程の最後で必ず『思いがけないところに通じる扉』か『思いがけない景観に向かって開く窓』(そこ以外のどこからもみることができない景色)か、どちらかを見出す。(p.173) 続いてレヴィナスによる正義と悪について。 「悪を根絶するというタイプの過剰な正義感の持ち主は、人間の弱さや愚かさに対して必要以上に無慈悲になる。逆に慈愛が過剰な人が、邪悪な人間を無原則に赦してしまうと、社会的秩序はがたがたになる。(中略)そういうデリケートなさじ加減の調整は、身体を持った個人にしかできない。法律や規則によって永続的に『正義と慈愛のバランスを取る』ことはできない。(p.182) 第四部「武道家としての坂本龍馬」 本書のハイライト。司馬遼太郎の描く剣豪はなぜ修行せずいきなり天才なのか?という、「そんなこと内田樹以外の誰も思いつかないし論じなかった」ことが書かれている。しかも、アクロバットに、自分の修行論(不条理に思えてもやることに意味がある)と司馬遼太郎の修行論(不条理なことを憎む)と作品世界(剣豪だった坂本龍馬が、剣で志半ばに死ぬ)の三つを肯定している。感服。
0投稿日: 2013.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ未来を予測しないもの、それがとりあえず、「無敵」の探究への第一歩を踏み出すときに手がかりにすることができる「私」の条件である。p64
0投稿日: 2013.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログいつもの内田節と言えばその通りかもしれませんが、2000年代初頭のガラガラポン、消費者としての役割ばかり強調されることで失ってしまった人間らしさが正解ではないと言い続けてくれるのは大変心強い。
0投稿日: 2013.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ内田樹の武道についての論は,こちらの常識的思考を覆されるようなところがあって、好きである。その武道に関わる修業についての論であるから、非常に楽しみにしていた。 読んでみて、相変わらずの発想の転換を求められる議論で、面白かった。ただ、4つの文章が「幕の内弁当」的に並んでおり、多少わかりにくいところもあった。アラカルト的な話題を用いて、主張は一貫しているのだけれどね。それでマイナス1。でも、非常に面白かった。
0投稿日: 2013.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は、40年にわたって合気道の修業を続けており、自分の道場まで建てたことはよく知られているが、ここには、修業をめぐる4つの考察が収められている。 第1章『修業論 ー 合気道私見』では、「修業とは、修業の主体(私)が、連続的に別のものに変容する過程である」と指摘している。これは、技量の上達を計測するものさしが、修業によって新しい段階ではもう適用できなくなるという事態が起こることを意味しており、数値万能主義に潜む陥穽を見事に言い当てている。 第2章『身体と瞑想』では、自我への執着(居着き)を捨て自己を解放する「瞑想」と武道における「機」とが結びついていることを指摘した上で、危機的状況に遭遇した際には、自我を脱ぎ捨てることの重要性が説かれる。 第3章『現代における信仰と修業』では、著者が師と仰ぐ哲学者レヴィナスの弁神論を援用しつつ、「神の支援なしに地上に正義と慈愛の世界を打ち立てることのできる人間」=「自立した信仰者」となるためには、身体的成熟が不可欠であることを解き明かしている。 最終章『武道家としての坂本龍馬』が圧巻である。『龍馬がゆく』を書いた司馬遼太郎が、剣術修行に全く目を向けていないことに着目し、これは、司馬自身が不条理な身体訓練を強いられた軍隊経験から来ているのではないかという仮説は正鵠を射ているように思われる。これに対して、著者は、坂本龍馬における剣術修業の重要性に目を向け、武道修業こそが、坂本龍馬の「危機を生き延びる力」を生んだという。龍馬は最後には、刺客により暗殺されることになるが、中島敦の『名人伝』を引用しつつ、「それでも龍馬は<無刀の刀>を以てテロリストを制した」とする結語は美しい。
1投稿日: 2013.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは武道の修業論であって(修行じゃないんだ…)それ以外の世界のものにはあまり適していないのかもしれない。 しかしながら、わくわくしながら読了してしまうのは、以下の境地があまりにも魅力的であるからであろう。(ただ、読みやすいが決してわかりやすい本ではない。かなりアクロバットな論理構造) 「武術の稽古を通じて開発される能力のうちでもっとも有用なものは間違いなく「トラブルの可能性を回避する能力」である。 それは「あらゆる敵と戦ってこれを倒す」ものではなく、「自分自身の弱さをもたらす災厄を最小化し、他者と共生・同化する技術を磨く訓練の体系である。 「私が考えている武道的な意味での「弱さ」と、哲学者が考察する「無知」とはたぶん同一の構造を持っている。 それは、変化することへの強い抑圧である」 「新たな学びを阻止する無知や弱さといったものを居着きととらえこれを解除し、「守るべき私」廃棄する。すると修業は自分を予想だにしなかった場所へつれていく。 …とカバーの文句をほとんど引用してしまったが、実生活ではほとんどこういう修業する場を得ることは難しいかもしれない。 が、あこがれる境地である。
0投稿日: 2013.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「修行」「時間」についての議論。「日本辺境論」からマイナーバージョンアップしていなくはないですが、ご自分で書いている「書き換えられた私」には到達していないような印象を持ちました。それと、内田先生が、どうして「論理の経済は」とか、「論理的には」という文言を多用するのか、ちょっとだけわかった気がします。師匠のレヴィナスさんが、「生身の身体感覚の上に、精緻な理知的産物を作り上げている」ので、自分もそうしたいんだけど、師匠に及ばず、「論理の経済は」と強引に言い切らざるをえない、そういうことなんじゃないかなあと思いました。はやく修行を経て、「書き換えられた内田樹先生」の著作を読んでみたい。
1投稿日: 2013.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはなんらかの稽古をしている人は必読だと思う。 各論については、瞑想を「認識の枠組み」と関係させるという斬新な切り方をしている。一時期のグレゴリーベイトソンを彷彿とさせる。
0投稿日: 2013.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログhttp://staygold1979.blog.fc2.com/blog-entry-490.html
0投稿日: 2013.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ7月20日に発売されたばかりの、「修業」についての、とても興味深く、スリリングな論考です。巻を措く能わず、ほとんど一気に読了しました。 著者によれば、「修業」とは、修業している段階にはなぜこれを行っているか分からず、できるようになって初めて遡及的に修業の意味が分かるという仕方で構造化されているものだそうです。 著者のように、武道に精通しているわけではない私には十分に理解できたと胸を張ることはできませんが、言わんとしていることはとてもよく分かります。 たとえば、このレビュー。私は著者に敬意を表して真面目に書いていますが、しょせん、ド素人の書評なんて無駄といえば無駄でしょう。 ところが、レビューをかなりのボリュームで書いた日は、出社後、仕事で書く原稿の執筆スピードが速まるという経験を私はしばしばします。頭がよく回るというよりは、体が勝手に動き出す感覚です。玄妙なものだと感嘆したことです。 恐らく著者の言う「修業」に最も近い感覚で、皆さんも、少なからず経験しているのではないでしょうか。 そういえば、華道家元池坊のDVDで脳科学者の茂木健一郎さんが、「型を繰り返すことで脳が最高のフロー状態となり、流れるように動作ができる」と語っていました。これも、著者のいう「修業」に近い感覚かもしれません。 しかし、本書を読みながら、私は興奮と同時に空しさも覚えました。「修業」を受け入れる風土が、この社会からはほとんど失われてしまったと痛感するからです。 たとえば、「渋谷区や港区内に事務所を構えるアート系のオフィス」(小田嶋隆さんの受け売り)では、絶対に受け入れられない、というかそもそも全く理解されない概念でしょう。 それだけでなく、巷には、こうすれば株で儲かるとか、こうすれば駆けっこが速くなるとか、実利的、即物的なノウハウが溢れています。大きな需要があるのでしょう。 端的に言えば、その需要とは「自己利益を最大化する近道を教えてくれ」と言うことができるでしょう。 もちろん、それはそれで大いに結構ですし、私自身、「君の行動規範をいくつか挙げよ」と求められれば、恐らく2番目くらいに来ます。 しかし、そのようなマインドがほとんど疑問も差し挟まれずに浸透していくことには一抹の危惧があります。 最後にいくつか思わず膝を叩いた行を。 「人はものを知らないから無知であるのではない。いくら物知りでも、今自分が用いている情報処理システムを変えたくないと思っている人間は、進んで無知になる。自分の知的枠組みの組み替えを要求するような情報の入力を拒否する我執を、無知と呼ぶのである」(P87) 「競技の本質的な陥穽はここにある。勝負においては、『私が強い』ということと『相手が弱い』ということは実践的には同義だからである。そして、『私を強める』ための努力よりも、『相手を弱める』ための努力の方が効果的なのである。理屈は簡単である。『ものを創る』のはむずかしいし、手間暇がかかるが、『ものを壊す』のは容易であり、かつ一瞬の仕事だからである」(P105~106) 「東電の原発事故のときに、『想定外の危機については対応しないこと』を、私たちの国の為政者たちが久しく『危機対応』のデフォルトに採用してきたという事実が露呈された」(P134) 「パニックに陥って、われがちに算を乱して逃げ惑っている人々を集合させ、ひとりひとりが見聞きした断片的情報を総合して、『何が起きたのか、これからどうすればいいのか』を推理するためには、キマイラ的協働身体の構成が急務であるということを知っている人間が必要である。それが沢庵の言う『兵法者』である。けれども、兵法者の仕事を妨害するものがいる。それを『反―兵法者』と呼ぶことにする。『勝負を争い、強弱に拘る』ことをつねとする人間のことである」(P149) 「自己利益の追求を最優先し、『勝負を争い、強弱に拘る』利己的個体であることの方が、平時においては資源配分の競争において有利である。だから、平時が続けば、人々は自己利益の安定的な確保を求めて、どんどん『反―兵法者』になる。なって当然である。けれども、平時は長くは続かない。どこかで必ず、破局がやってくる。そのときに反―兵法者的な人々は、破局をさらに破局的な状態に導く最悪のリスクファクターになる」(P151) 「そのつどの個人的なコミットメントに頼ることなく、制度として正義と慈愛を実践する社会システム、それはあらゆる権力者に取り憑く夢想の一種である。しかし、歴史上かつて一度として、『生身の人間の関与抜きの、非人称的・官僚的な正義と慈愛』が実現したことはない。それは正義と慈愛は本質的に食い合わせが悪いからである」(P181) ね? これだけでも十分に面白いでしょう? 司馬遼太郎がなぜ坂本竜馬の修業時代を書かなかったのかについての考察も目からウロコでした。さて、仕事仕事。
2投稿日: 2013.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「天下に敵なし」とは敵を「存在してはならないもの」ととらえないこと言うことことである.そういうものは日常的風景として「あって当たり前」なのである. 「因果論的な施行が敵を作り出すのである」 「敵を作らない」とは、自分がどのような状態にあろうとも、それを「敵による否定的な干渉の結果」としてはとらえないというこということである. 「無限の選択肢」などというものは、はじめからなかったと考える.とりあえず今、私が選択することを許されている限定された動線と、許された可動域こそが現実の全てであると考える.それが、敵を作らないということである. いきなり袋小路というのは良い兆候である.それは、「初期設定」が間違っていたということを意味するからである. 敵を無くすには、「敵」を無くすのではなく、「これは敵だ」と思いなす「私」を消してしまえばいい.論理的にはたしかにそれしか解がないのである. 私を消すためには「意思を持たない」「計画を持たない」「予断を持たない」「取り越し苦労をしない」ということが第一歩である. 度量衡の選択は「それを選択することによって生き延びる確率が高まる」かどうかを基準になされなければならない. 成熟を果たした人間にしか、「成熟する」ということの意味はわからない.幼児が事前に「これから、こんなふうな能力や資質を開発して、大人になろう」と計画して、そのようにして起案されたロードマップに基づいて大人へと自己形成するということはありえない.幼児は「大人である」ということがどういうことかを知らないから幼児なのであり、大人は「大人になった」後に、「大人になる」とはこういうことだったのかと事後的・回顧的に気づいたから大人なのである.
0投稿日: 2013.07.21
