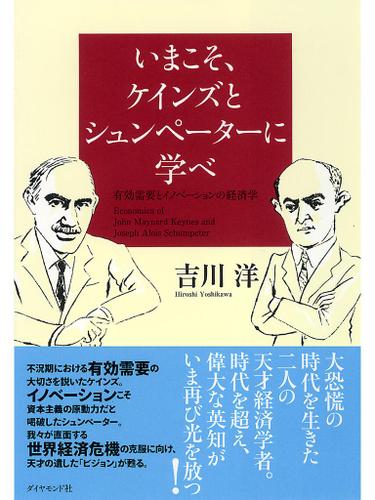
総合評価
(28件)| 1 | ||
| 13 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者のケインズの学説の進化を中心に紹介する新書「ケインズ」が面白かったので、こちらも読んでみた。 20世紀前半の2大経済学者と言っても異論はないであろうケインズとシュンペーターを当時の激動の時代と関係づけつつ時系列的に紹介したもの。 とは言っても、この2人の影響関係はよくわからなくて、シュンペーターはケインズを意識したようだが、ケインズの方はあまり眼中になかった模様。 個人的には、シュンペーターの経済学はちゃんと読んだことがないので、かなり勉強になった。彼のイノベーション論、創造的破壊論はこれまで表面的な理解しかなかったんだなと思い、「経済発展の理論」を読まなきゃという気になった。 私はケインズという人が好きなんだけど、彼の経済理論はいろいろ穴があってツッコミどころは多い気がしていた。が、先般、岩井克人さんの本を読んでいたら、「一般理論」は当時の経済学者が納得できるように学問的に精緻に書かれたものであるといったことが書いてあって、ここはちょっと違和感を持っていた。 こちらの本では、ケインズが経済学をちゃんと勉強したのは1年程度で、あとは具体的に当時のイギリスで、世界で起きていた経済問題に対する処方箋という意味を持った理論であると位置付けられていて、こちらの方が私のケイン理解に近い気がした。 きっと彼はそれまでの経済学をそれほど学んでいなかったからこそ、経済学的なブレークスルーができたんだろうなと思う。また、彼は学者というよりは、ステイツマンと考えた方が良さそうで、「一般理論」は経済学者に対する本であると同時に、当時の経済政策を決定する立場の政治家や官僚に対して書いたものだと思う。 その辺りのところが改めて整理できた。 著者は、ケインズとシュンペーターの議論は噛み合わないところが多いとしつつも、資本主義というものの本質をしっかりと対峙したという姿勢は共通するところと考え、この2人の理論は統合可能なものという目論見を書いている。 その統合の理論は、その後に出版されている読んだが、専門書で値段も高いので、しばらくそれは先送りをしておこう。
0投稿日: 2025.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済学の巨人二人の理論に秘められたビジョンを解き明かすという。新たな経済理論の可能性を考え、「100年に一度の世界経済危機」に対する指針を二人から学ぼうする。 ・ビジョンの有効性を熱量高く語る本だった。書き出しでその熱に、ぐっと引き込まれる。 二人の死から、すでに半世紀以上が経過した。この間に日本そして世界経済は大きく変わった。経済学も変わった。二一世紀に入った今日、半世紀以上前に生きた経済学者について考える意義はどこにあるのだろうか。ケインズもシュンペーターも人間としてひとクセもふたクセもある天才だ。人間的な魅力は十分なのだが、その経済学は二一世紀に生きるわれわれ日本人にとって有用なのだろうか。 こうした疑問が生じるのは当然だ。結論を述べるならば、現代に生きるわれわれは、ケインズとシュンペーターの経済学から大いに学ぶことができる。彼らの経済学に学ばなければならない。それは二人の天才経済学者が描いた「ビジョン」は、いまだに経済をみるときに不可欠の視点を提供しているからである。 経済は「生き物」だと言われる。ダイナミックに変化する経済の動きは、単純な方程式などでは到底とらえることができない。だが、複雑な経済を理解するためには、どうしてもそれを単純化し、重要だと考えられる側面に鋭く光を当てる必要がある。光を当てると言っても一体どこに光を当てればよいのか。どのような角度から光を当てればよいのか。それを決めるのが、経済についての「ビジョン」だ。 (中略) スミスと同じく、ケインズとシュンペーターは、経済学という学問が存在するかぎり永遠に引き継がれるであろうビジョンを提示した。時代が移り経済が表面的にはどれだけ変わっても、二人の経済学者が提示したビジョンの有効性は変わらないのである。 (2~3頁) ・ケインズとシュンペーターの二人がどんな仕事をしたのかを知らない私にとっては、マクロ経済学の重要人物くらいの解像度しかない。ビジョンを抽出するにしてもまずは概観したい。 ケインズもシュンペーターも生涯に超一流の仕事をたくさん残した。しかしケインズのビジョンは、主著である『雇用・利子・貨幣の一般理論』一九三六年、以下『一般理論』)で提示された「有効需要の理論」である。『一般理論』なくしてケインズはない。 (中略)言い換えれば不況は需要不足によって起きる。これが「有効需要の理論」のエッセンスである。(中略) シュンペーターも多くの著作を残した。いろいろなことを言った。しかし彼のビジョンは、一九一二年ドイツ語で書かれた『経済発展の理論』のなかの「イノベーション」と「創造的破壊」によって言いつくされている。(中略) 二人のビジョンはまったく異なるものである。(後略) (3~4頁) ・二人が示した理論は、どんなところで現代に生かされるのだろうか。デフレ・不況・大恐慌について見る。 ここではバブル崩壊後一九九〇年代の後半から一〇年の長きにわたり日本経済にとって最大の問題の一つであったデフレーションを取り上げることにしよう。『貨幣改革論』であれほどインフレの災禍を説いたケインズだが、『貨幣論』ではデフレの問題を強調した。(中略) そもそも景気循環が問題となるのもインフレ局面ではなく、デフレ局面がもたらす弊害によるのである。たしかにインフレの局面では、労働者から企業へ所得が移転される。しかしその間に行われる資本蓄積が経済全体にもたらす利益は、所得分配上の悪影響をはるかに上回る。資本蓄積がもたらす利益は労働者にも及ぶし、分配上の歪みは税制を通して是正すればよい。これとは逆にデフレは社会全体にマイナスの影響を与える。こうケインズは言っている。 (中略) 「フィリップス曲線」によれば、物価や賃金は実体経済が好調だと上昇する傾向にある。逆に実体経済で不況が深刻化すれば、その結果として物価や賃金は低下する。つまりデフレになる。これは近年日本銀行が繰り返し主張してきたことだ。ところでケインズによれば実体経済のアップ・ダウンに最も重要な影響を与えるのは投資だから、結局投資が著しく落ち込むことが貨幣数量とは独立にデフレの原因になる、というわけである。 (101~102頁) 現在の生産価格では売ることができない(したがって価格を下げなければならない)という事情が個別の商品ではなく経済全体で生じているときには、それはサプライ・サイド(引用者注:供給側)の問題ではなくマクロの「需要不足」の問題である。総需要を増大させる唯一の方法は投資を増大させることだとケインズは主張した。そのためには長期金利を下げなければならない。 しかし民間の投資に影響を与えるのは、リスクの低い国債の金利=長期金利そのものではない。国債の金利に「リスク・プレミアム」を加えた「資本コスト」である。それは株式会社の場合、株の収益率にほかならない。民間の投資への「近さ」ということで言えば、短期金利よりは長期金利、長期金利よりは株の収益率ということになる。ケインズの長期債購入のロジックを一歩進めれば、中央銀行による株式(ETF)購入というアイデアに必然的に行き着く。 (106~107頁) これこそが不況の真の原因なのだとシュンペーターはここで主張する。『経済発展の理論』において展開されたシュンペーターの基本的経済ビジョンを思い出してもらいたい。資本主義経済の発展は企業家によるイノベーションが群生的に生まれることによってもたらされる。これが好況だ。しかし、イノベーションの後にはそれが経済システムのなかに拡散していく「適応」の時期が必然的にやってくる。それはあたかも「祭りの後」のように沈滞した時期であり、人はそれを「不況」と呼ぶ。シュンペーターは、第一次世界大戦後一九二〇年代にイノベーションが盛んに起きた後に必然的に「不況」がやってくる、それが現在の不況だと言っているのである。 (中略) (121頁) (前略)シュンペーターも利子率の重要性を無視しているわけではない。それどころか、すでに説明したように『経済発展の理論』はウィーン学派の伝統に基づく「利子の理論」だった! ただ利子率は、あくまでもイノベーションの「結果」としてうまれる実物的変数なのである。シュンペーターは、貨幣的現象としての利子率が実体経済に悪い影響を与える、というような見方を真っ向から否定した。 これとは対照的にケインズは、貨幣的現象としての利子率を重視した。それは実体経済に大きな影響を与える。高金利を経済にとって「天敵」とみなし、したがって株暴落により低金利がもたらされるならばそれは「天恵」だとすら言ったのである。もちろんそこには一九二五年四月、チャーチル蔵相の決断に寄り第一次世界大戦前の過大評価された平価(一ポンド=四・八六ドル)で金本位制に復帰して以来、高金利に悩まされてきたイギリスの特殊事情があったに違いない。しかし国内・国際を問わず「金融」により決まる利子率が、やがて『一般理論』で「資本の限界効率」と呼ばれることになる「収益率」と衝突し、経済にとって大きな攪乱になるというケインズの基本的な考え方は、シュンペーターとはまったく異なる。正反対と言ってもよいものだ。 (123~124頁) ・二人のビジョンの違いはどこから生まれたか。 ロバートソンとケインズは「需要の飽和」を重視し、需要不足を「不況」の原因とみなした。一方、シュンペーターは既存の財・サービスに対する需要が飽和することは認めながらもそれを克服するものとしてイノベーションの役割を強調した。両者の違いは、結局のところ一九世紀末から二〇世紀初めにかけてのイギリスとドイツ・オーストリア経済の違いから生まれたと見ることもできるだろう。経済学者のビジョンは、当然ながらその経済学者が目にしていた経済によって形づくられるはずだからだ。 わかりやすく言うなら、ロバートソンとケインズは日本の「失われた一〇年」のような経済を目にしていたのだ。これに対してシュンペーターの祖国オーストリアと隣国ドイツは、ちょうど高度成長期の日本や今の中国のような経済だったのである。 (139頁) ・異なるビジョンを組み合わせて理論的に有効な経済政策はできるのか。 ところで総需要はなぜ不足するのか。なぜ労働や資本など生産要素が完全に雇用されるような水準にまで需要は増えないのか。モノをつくる能力がある社会で、なぜそうしたモノに対する需要は不足するのか。 (中略) 昔からあるモノやサービスに対する需要は必ず飽和する。このことはシュンペーターも認めた。そこから先がシュンペーターとケインズで違うのである。ケインズは需要不足は与えられた条件だとして政府による政策を考えた。シュンペーターは、需要が飽和したモノやサービスに代わって新しいモノを作り出すこと――すなわちイノベーションこそが資本主義経済における企業あるいは企業家の役割なのだと説いた。イノベーションによって新しいモノが生み出されるから「恒久的」に需要が飽和することはない。 (268頁) (前略)リカードが農業を念頭に経済学の公理とした「限界生産の逓減」は、テクノロジーがもたらす制約である。この限界生産の逓減が経済成長を抑制する。これは基本的にサプライ・サイドの考え方である。 これに対してロバートソンとケインズが指摘したことは、既存のモノやサービスに対する需要の飽和、有効需要の不足こそがマクロ経済の成長を抑制する――場合によってはマイナス成長を含む深刻な不況を生み出す――根本的な原因だということである。(中略) だとすれば、シュンペーターがリスト・アップしたさまざまなイノベーションのなかでも、新しいモノを作りだすプロダクト・イノベーション、そして既存のモノについても新たな市場・販路を見つけ出すようなイノベーション、つまり「需要創出型のイノベーション(demand-creating innovation)」こそが資本主義経済を根底において支える重要な核といえるのではないか。 そしてここにおいてケインズの経済学とシュンペーターの経済学は明確な接点を持つのではないか。 (269頁) ・最後に感想。 接合点を見出すための長い旅だったという気がする。著者の手法がちょっと比較神話学っぽい。面白い内容だったが中級程度の読書筋は必要という印象。理論の統合を目指す上で、逐次的な並記が乱立するのでかなり歯ごたえがある。 だいぶ荒っぽく抜き書きのメモを作ってみた、筋道は通っているのではないだろうか。あとは著者の手続きがこれでいいのか、という批判的検討がほしいところ。約15年前の本なので、いまならいろいろあるだろうから探してみたい。 個人的にはケインズ『貨幣論』がビジョン抽出の中心になっている気がすることと、シュンペーター『経済発展の理論』以外の仕事をもっと重視するか検討するかしていいのではないかということの二点が気にかかる。ただ現在地点での著者がどう考えているか見る方を優先すべきだろう。(私自身に見落としもあるはず)
0投稿日: 2025.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ第一次世界大戦に翻弄された二人の経済学者の話。わかりやすく解説。戦争で覇権を奪われた英国、戦争で帝国が崩壊したオーストラリア。 企業家のイノベーションの動機とは、「自己の帝国建設の夢想と意志」、「勝利への意志、成功への意欲」、「創造の喜び」である。
0投稿日: 2022.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉川洋 「いまこそ ケインズ と シュンペーター に学べ 」著者の結論は 資本主義経済の重要な核は ケインズの有効需要、シュンペーターのイノベーションの統合概念(需要創出型のイノベーション) ケインズ=有効需要の理論 *経済の活動水準は需要により決まる=不況は需要不足により起こる *投資の不安定性が資本主義経済の変動要因 *金融投資は 美人投票と同じ(自分が美人と感じる人に投票するのでなく、みんなが美人と感じる人に投票する) シュンペーター=イノベーション、創造的破壊 *資本主義の本質=企業家によるイノベーションに基づくダイナミズム→不況はイノベーションがもたらす必然 「不況なくして 経済発展なし」
0投稿日: 2021.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
シュンペーターとケインズの考えがわかる。 シュンペーターが経済の発展はイノベーションにあるとしたのに対して、ケインズは一貫して完全雇用を生み出すために、有効需要は政府が作り出さなければいけのいとする。 現代の企業活動を考える上で、また投資を考える上で参考になる。
0投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「いまこそ、○○○に学べ」というとき、 ○○○に入る人物は、ごまんといるのだろう。 学者や思想家、政治家から、芸術家、スポーツ選手に至るまで、 多くの偉人たちの膨大な知識の蓄積の上に僕たちは生きていて、 こうしている間にも、新たな知が生み出されている。 それらの知識を、たとえGoogleがすべて電子化したとしても、 一人の人間がそれらすべてを把握することは不可能だろう。 そのような中では、 純粋にまったく新たなアイディアや知識というものはあり得ず、 どんなに画期的な考えであっても、すでに誰かがどこかで 言ったり書いたりしたものの焼き直しに過ぎないという人もいる。 僕にはそのあたりの話はよくわからないけれど、 少なくとも昨今の金融危機〜世界同時不況という時代にあって、 「マクロ経済」なるものから目をそらすことはできない という気はしていた。 古典と呼ばれる知識を現在の環境に当てはめて考えることは 単なる懐古主義とは違った意義があるはずだ。 とはいえ、すべての古典に目を通すのも、正直しんどい。 そんなわけで、本書のような内容は非常にありがたい。 「いまこそ学べシリーズ」として 続編を出してもいいのではないかと思ったりする。 しかも本書が優れているのは、 単に読みにくい古典をわかりやすく解説するだけでなく、 当時の時代背景も含めた生々しい「人としての営み」が 垣間見える点と、タイトルのとおり、昨今の金融危機や、 日本の80年代のバブル崩壊など、 近年の経済環境を俯瞰した上で、 これまで対立概念として捉えられてきた(らしい) ケインズとシュンペーターの理論を統合化し、 今、そしてこれからの経済を考えるための示唆として 再構築している点にある。 「有効需要の不足」が不況の原因であり、 積極的な財政出動がその解決策であると説くケインズと、 企業家精神によるイノベーション(新結合)こそが、 不況脱出の鍵であると主張するシュンペーター。 著者は両者の主張を統合することこそが、 現状の世界的不況に対する処方箋になると述べ、 「需要創出型イノベーション」を提唱する。 これはまさに「いまこそ」考えなければならない命題であり、 (ケインジアンとして有名な)著者とは異なる選択肢を 自分自身で考えてみてもおもしろいかもしれない。 写真も随所に入っていて、文章として読みやすいことも 本書の魅力の一つである。学生時代にこんな本があったら・・・ と思う人も多いかもしれない。
0投稿日: 2015.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に良い本だった。影の立役者であるシュピートホフ、ロバートソンらにスポットライトを当てている点も興味深い!
0投稿日: 2015.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログシュンペーターを知らなかったが、ケインズと比較しながらもしかしたら分かりやすいかもと気楽に読みだして、後悔 これは経済学を少し本を読んで勉強しただけでは分からない きちんと勉強して、学者の考えをある程度概要を掴んでいないと、チンプンカンプンなところがある。 早まったか・・・ だが、それでも面白い。彼らの出生から時系列に比較しているが、まさに歴史の変動と大きく関わっているのが分かる。そうか。経済学の用語に出てくる単語は人の名前がこんなにあるんだ しかしシュンペーターの本はかなりの難物のようだ。 ここまで「読みにくい」と紹介されるとは だが中身は鋭い気はする。経済学では国、企業視点が多く確かに産業視点でないイメージをもった(そうでないのかもしれないが) また不況をイノベーションの収穫期と言い切る点、金融政策・財政政策では経済の動きは止めれないと言い切る点など、なるほどと感じる。確かに小手先感は否めない 経済を変えるのはイノベーションである点も納得である でも経済学者でも読みにくい本ww きちんと全てを理解することは出来なかったが、なかなか面白かった
0投稿日: 2015.02.02経済政策への蒙を啓く良書
まず前提として、当方教養課程で(新)古典派を学習、現代思想的関心による興味本位で資本論を読了。ケインズ派というかマクロはとっつき辛いと思っていたが山形浩生氏翻訳のクルーグマンの一連の公刊物で関心を抱き「一般理論」を(こちらも興味本位で)読了という経歴の、床屋談義メインな市井の野良ケインジアンという立場です。 現在の世界的不況、及びクルーグマンのノーベル賞受賞で(それまで古典派に何度目かの葬送が行われたにも拘わらず)改めて脚光を浴びたケインズ、そしてある意味ケインズ以上に「経済学者」でありながらあまり注目を浴びておらぬ同時代人のシュンペーター、この2人の人生を辿りながら、それぞれの主張と独創性を大づかみに描き出したのが本書といえます。 人生のタイムラインに沿った学説概略紹介は分かりやすく、また双方の欠点についても避けることなく触れているので、不況対策にどういう経済の捉え方をすればいいのかを理解するには好適書と言えるでしょう。個人的にはほぼ事前知識皆無だったシュンペーターについて理解を深められました。 現在アベノミクスへの評価という形で、(政権への支持は別として)消費増税以外は概ね支持を見せるケインジアン側と、強固な批判者として旧来のIMF的な財政健全論(これはかなり問題外)と「金融政策よりも構造改革」な古典派系との対立が見受けられ、両者の論議の断絶が気に掛かっていたのですが。 シュンペーターの主張する「イノベーション」を現在的に捉え直すと、「経済」はマクロな政策とミクロな経済活動、それと別の第三の評価検討軸として産業構造というものが必要になっているのではないでしょうか。産業全体を「第〇種産業の規模は…」と語るのでなく、各種産業自体の構造が硬直化していないか、「創造的破壊」を封殺して緩やかな自死を容認する構造になっていないかといった視点。そうすると、財政健全論はともかく構造改革論とケインジアン的マクロ政策論双方の強みを生かせるように思います。特に企業依存型経済になっている日本の場合においては。 シュンペーターが主に主張していた景気循環論は著者も批判しておりますし、個人的にも(経済史の視点としてならともかく)お話にならない印象があるのですが、この点については検討すべき視点を提供してもらえたし、価値があったと感じられました。
0投稿日: 2013.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ・ケインズもシュンペーターも障害に超一流の仕事をたくさん残した。しかしケインズのビジョンは、主著である『雇用・利子・貨幣の一般理論』で提示された「有効需要の理論」である。『一般理論』なくしてケインズは無い。 一国経済全体の活動水準は、生産要素がどれだけあるとか、技術水準がどれくらいであるかといった供給側(サプライ・サイド)ではなく、需要の大きさで決まる。需要が少なければ生産水準は低くなる。言い換えれば不況は需要不足によって起きる。これが「有効需要の理論」のエッセンスである。 ・イノベーションは、たしかに「非連続的な変化」だ。シュンペーターは、このことを「馬車をいくら繋いでも鉄道にはならない」という巧みな表現で説明した。 ・「購買力平価」という言葉は今日二重の意味で用いられる。一つは貿易財の価格について国際的な一物一価を成り立たせる「均衡レート」。これは現実の為替レートの長期的アンカーと言ってもよい。もう一つは一般物価水準をつりあわせるような為替レート。 …後者の意味での(東京とニューヨークの人々の暮らしを比較するような)「購買力平価」が1ドル=166円なのに、現実の為替レートは1ドル=100円なのは円が大幅に過大に評価されている、といった主張が誤りであることは理解していただけたと思う。 →為替と比較して考える時は貿易財の価格でのみ考えるべきで、非貿易財は別に考える必要があるとの事。 ネットで少し調べてみると、例えば有名なビックマック指数は牛肉などの輸入関税や、提供する際の人件費や競合圧力などで国により偏りが考えられる指標との事。一応、2007年のビックマック平価は1ドル121円となる。OECDが2005年のデータで算出した貿易財を基本にした価格だと1ドル150円だそうなので、いずれにしても、80円代などは安すぎたのかな。 ・インフレは悪いが、デフレは悪くないのではないか。こう考える人、エコノミストは当時もたくさんいたようだ。今でも「よいデフレ」論を唱える人がいるが、ケインズは「デフレは悪い」と断言する。 そもそも景気循環が問題となるのもインフレ局面ではなく、デフレ局面がもたらす弊害によるのである。たしかにインフレの局面では、労働者から企業へ所得が移転される。しかしその間に行われる資本蓄積が経済全体にもたらす利益は、所得分配上の悪影響をはるかに上回る。資本蓄積がもたらす利益は労働者にも及ぶし、分配上の歪みは税制を通して是正すればよい。これとは逆にデフレは社会全体にマイナスの影響を与える。
2投稿日: 2013.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ケインズとシュンペーターの著作を年代順に交互に紹介・解説したもの。 両者が交叉する一点を「需要の飽和」とし、ケインズはそこで立ち止まってしまうが、そこからがシュンペーターの出番=イノベーション、としている。(P.197) 「つまり『需要創出型のイノベーション』こそが資本主義経済を根底において支えるもっとも重要な核だといえるのではないか。」(P.269) 詳しくは、"Demand Saturation-Creation and Economic Growth" Aoki and Yoshikawa 2002 http://www.listinet.com/bibliografia-comuna/Cdu339-6986.pdf で。 なお、「シュンペーター的成長モデル」といわれるAghion and Howitt 1992も「墓の中でシュンペーターも苦笑せざるをえないだろう。」と一刀両断されている。
0投稿日: 2013.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこの混乱の時代にあって、どう経済を動かすか。どう経済が動いているのか。 シュンペーターの唱えたイノベーションや、ケインズの唱えた有効需要等がわかりやすく習得できる良書だと思う。 手許に置いてキーワードは読み返したい。
0投稿日: 2013.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ編年的に処女作や代表作、それぞれの思想に与えた事象等を挙げながら2人の経済学者の経済思想を解きほぐしていく。「昔からあるモノやサービスに対する需要は必ず飽和する」認識は共通だが、その後の打ち手や視座が異なる、と考えれば特に対立する思想でもない、という印象。その辺りを明快に説明している良書と思う。
0投稿日: 2012.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログケインズは主張した。豊かな社会が到来すれば、有効需要不足により「豊かさの中の貧困」が発生すると。人々は豊かになれば、もはやモノを欲しがらないからだ。 シュンペーターは言う。イノベーションこそが資本主義の枠を拡大し、需要を喚起し、資本主義そのものを発達させてきたと。 この2人を組み合わせることで、「需要創出型」のイノベーションができるのではないかと成長モデルを作ったのが筆者である。 その筆者が、なぜ今、ケインズとシュンペーターなのかという問いに対する解説をしたのが本書。
0投稿日: 2012.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログホントこういう事を大学時代にもっと勉強しとけば良かったと後悔しながらも大人になった今だからこそ面白い!!
0投稿日: 2012.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ同い年のケインズとシュンペーター、その違いと交差点を、経済書らしからぬ読みやすい構成で楽しめた。 s:企業家は単に生産要素を結合して生産活動を組織化するだけでなく新結合(イノベーションと呼ぶ)を遂行する k:貨幣改革論 企業家を成金に変える事は資本主義に致命的な打撃を与える。それは不平等な報酬を許容する心理的均衡を破壊するからである。 k:一般理論 穴を掘って埋めるといった 無駄な公共投資ではない。Wise Spending s:景気循環論 不況と回復は経済の進化のプロセスにおいて不可欠 ケインズは需要不足は与えられた条件だとして政府による政策を考えた。シュンペーターは需要が飽和したモノやサービスに代わって新しいモノを作り出すこと、すなわちイノベーションこそが資本主義経済における企業あるいは企業家の役割だと説いた。 2011.04.17
0投稿日: 2011.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ吉川先生の素晴らしさが凝縮されている珠玉の一冊。本当の知識人はこういう文章を、読み手を惹きつけるように書けるものなのだろう。僕も先生のような人になりたい。興味深いテーマと、綺麗な日本語に痺れるが良い。
0投稿日: 2011.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログケインズとシュンペーターの経済学の話 ケインズとシュンペーターの経歴から入るところから始まるので、ケインズとシュンペーターがなぜその学説を導きだしたかなどは、分かり易い。 ただ、この題にある 『今こそ』というところが、あまり触れられていない。 ただただ、ケインズとシュンペーターに関する本で、キャッチを売れるように作ったなという印象。 でもケインズとシュンペーターに関することは、これ一冊である程度わかると思われるので、経済学の常識としては一読の価値あるのかなと思う。
0投稿日: 2010.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容はともかく、もっとわかりやすく書いてほしい。 学べっていっているのだから、前知識が無い人にもわかるように。 ト、2010.27-29
0投稿日: 2010.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログまず、自分の知識がたりず、理解しきれていない とはいうものの、それは承知で購入した 問題はその内容であり、 『~~に学べ』というわりに、ほとんどが彼らの経歴云々に費やされている 実際、本書の目的は彼らの経済学を統合して現代社会に応用する というものだったはずなのに、それに対するページは最後の10数ページほどしか割かれていない それなりに学ぶところはあったものの お金を返してほしい
0投稿日: 2010.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨年の日経による、「経済学者に聞いた今年のベストセラー」みたいな企画で上位だったため、読んでみた。 タイトルは「いまこそ、~~学べ」となっているが、 金融危機後の世界経済に対して、二人の思想を用いると、 どういったアイディアが出てくるかという点の議論は意外と少なかった。 ただ、それを補って余りある、同い年生まれの ケインズとシュンペーター両名の人生をたどりながら、 それぞれの思想を解説していく手法は読んでいて素直に面白かった。 経済の知識が多少いるかもしれないが、 (自分はそこまであるとは思わないけど)なんとかなるレベル。 最終章 二人の遺したもの (タイトルからすると、ここがもっと分厚い内容かとおもってた・・・)より、 「昔からあるモノやサービスに対する需要は必ず飽和する。」この点は両者とも一致している。 ここからが違う。 「ケインズは需要不足は与えられた条件だとして、政府による政策を考えた。」 「シュンペーターは、需要が飽和したモノやサービスに代わって新しいモノを作り出すことーすなわちイノベーションこそが資本主義経済における企業あるいは企業家の役割なのだと説いた。」 これは接点がないということではない。 二人の思想をつないでみると、 「有効需要の不足こそがマクロ経済の成長を阻害する。そういった不足を解消するイノベーション(需要創出型、Demand-Creating Innovation)こそがまさに、資本主義経済の根底を支えるものではないか。」 という主張が出来るという論調。詳細は載っていないww この話をもっとほれればいいのに。でも、単純に読み物として面白かった。 以下、シュンペーターの考えの中での、「銀行家の重要性」についてのメモ。 新結合(イノベーションのこと)は、言ってしまえば「ベンチャー」 だからこそ、資金の出し手が必要。それが銀行家。 「銀行家は『新結合の遂行を可能にし、いわば国民経済の名において新結合を遂行する全権能を与えるのである。彼は交換経済の監督者である』」
1投稿日: 2010.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ20世紀前半の偉大な2人の経済学者の考え方を、その人となりを含めて解説した。ケインズは有効需要の不足を経済政策で解消する理論を提示したのに対し、シュンペーターは創造的破壊とイノベーションによる経済成長を論じた。日本経済との関係性は明示的には論じられていないものの、学ぶことが多い本である。(日経・福田慎一:2009/12/27)
0投稿日: 2010.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ一見矛盾する二人の経済学。なぜ両方が必要なのか? 今、直面する経済問題について、2人の天才が遺したものを振り返る。 2人の処女作に始まり、ターニングポイントとなる戦争・恐慌、また彼らの名著を紹介し、 彼らが行き着いた考え・理論に触れる編年体といった構成だ。 まず彼らの主張を見ていくと <ケインズの主張> 一国経済全体の活動水準は、供給側ではなく、需要の大きさで決まる。 言いかえれば、不況は需要不足によって起きる。 <シュンペーターの主張> 企業家によるイノベーションこそ、経済発展の要である。 またイノベーションは不連続であり、好況を生み出すものだが、 新しい均衡への調整(不況)が必要であり、不況なくして、経済発展はなしという。 お互いの注目すべきところを書き出すと <ケインズメモ> ケインズは投資が最も重要視されるべきものであるという。 →投資が孕む不安定性こそ、資本主義経済の変動すなわち景気循環の主因という。 投資が著しく落ち込めば、貨幣数量とは独立にデフレの原因となる。 投資が増えれば、GDPはその乗数倍に上昇する。 インフレの下で企業が行う事業はギャンブルとなり、投資の効用が劣化する。 →棚ボタで得た儲けは、心理的均衡を破壊となり、日本でいうバブル紳士に成り下がる。 「付和雷同」が正解となるゲーム。それこそが金融市場の本質。 <シュンペーターメモ> 1929年の世界恐慌は、第一次世界大戦後のイノベーションによって必然的に起きた不況だ。 金利は、あくまでもイノベーションの結果として生まれる実物的変数である。 イノベーションによって新しいモノが生み出されるから、需要が飽和することはない。 下記に示すマンキューの入門経済学で基本的な知識を漁ってからこの本に挑んだが やはり経済学を専攻としていないので、わからないところだらけだった。 ちょっと経済をかじったくらいの人には、おススメできない内容となっています。
0投稿日: 2009.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログdemand-creating innovationというアイデアの提案。やはり言いたい事は最後の「ケインズとシュンペーターをどう統合するか」だね、経済学説史の本というよりは。でも、僕のような能力値の低い院生には、英語でしかも経済物理系のマクロ動学論文なんてとても読めるはずもなく・・・。 中身は普通に読み物としても面白い。
0投稿日: 2009.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ同時代に生きたケインズとシュンペーターを比較論じたもの。 丁寧に読めば、得るものが大きそうなんだが。。。
0投稿日: 2009.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ『いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ――有効需要とイノベーションの経済学』(吉川洋、2009年、ダイヤモンド社) 有効需要政策を打ち出し、不況時には政府による公共投資を増やして失業率を下げ、マクロ的に新たな需要を生み出す必要性を説いたケインズ。これはディマンドサイドでみた経済学であり、戦後の成長の各国の経済政策に採用された。 一方、ミクロで見た場合の個々の企業のイノベーション(新結合)が新たな発展の原動力とするシュンペーター。彼によれば、不況すらイノベーションには必要だという。 本書は『いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ』という題であるが、お互いに相入れない二人の経済学の巨星の歴史をひもとくのが大部分を占めている。 2007年秋のサブプライム問題以後、2008年の「100年に一度」ともいわれる経済危機に際して、ケインズ経済学が「世界中で復活した」という記述がある(p.252)。本書には1980年代以降の経済の流れは記述にないので、少し補う。 ケインズ経済学は戦後、世界の多くの国で経済政策に取り入れられたのであるが、1970年台のスタグフレーション以後は衰退していった。その点、現代に至るまで興隆していったのが新古典派経済学である。いわゆる「ネオリベラリズム(新自由主義)」と呼ばれる政策パッケージであり、1980年以後は民営化や規制緩和が世界中で進められた。しかし、行き過ぎた規制緩和は不透明な投機マネーの流れを生み出し、その果てが今回のサブプライム問題とそれに付随する国際経済危機である。 この国際経済危機に対して、ケインズ経済学が復活したという。例えば、2009年1月に就任したアメリカのオバマ大統領は、総額8250億ドルの財政出動を発表するなど、ケインズ経済学への回帰が見られるのだ。その中でもオバマ大統領が「グリーン・ニューディール」を打ち出しているところが興味深い。何故なら、「ニューディール」というのは1929年の大恐慌を克服するために打ち出されたケインズ経済政策だったからである。 では、シュンペーターについてはどうか? 思うに、今日の日本は少子高齢化に伴う人口減社会への突入、あらゆる面での国際化を迎え、内的・外的に大きな変革期にある。このような変革期において、日本は科学技術に重点的に投資していかなければならない。新技術を開発し(科学の成果)、それを産業・経済活動に活かすこと(技術の成果)、すなわちイノベーションが今日の日本には必要なのである。新しい需要を生み出すためのイノベーション。まさにシュンペーターが指摘したことが今日の日本にもあてはまるのである。 (2009年6月19日) (2010年5月22日 大学院生)
0投稿日: 2009.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログケインズとシュンペーターを比較しながら、二人の経済学を紹介。 ちょっと難しかったり、面白くなかったりする部分もあるのですが、シュンペーターについてよく知ることができてよかったです。 「(シュンペーターの挙げる『企業家の動機』)第一は『私的帝国』ないし『自己の王朝を建設しようとする夢想と意思』。第二は『勝利への意思』あるいは『成功を獲得しようとする意欲』。第三が『創造の喜び』である」 「長期的にはわれわれはみな死んでしまう(In the long run, we are all dead.)」 「ゾンバルトの議論の特徴は、『贅沢』の元をたどっていくと結局のところは女性の力がリードする『恋愛』こそが『贅沢』を生み出す源泉だった、という明快な結論にある」 「賃金は『公正』『正義』の観念と切り離せないのである」 「本当に存在するのは循環そのものなのだ(Real is only the cycle itself)」 「現在では全ヘラス(ギリシア)にわたって子供のない者が多く、また総じて人口減少がみられる。そのため都市は荒廃し、土地の生産も減退した(中略)人口減少のわけは人間が見栄を張り、食欲と怠慢に陥った結果、結婚を欲せず、結婚しても生まれた子供を育てようともせず、子供を裕福にして残し、また放縦に育てるために、一般にせいぜい一人か二人きり育てぬことにあり、この弊害は知らぬ間に増大したのである」 ↑紀元前二世紀半ば ポリビオス … 写していて気がついたのですが、誤字がやけに多い。
0投稿日: 2009.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログケインズとシュンペーターは、実は同い年生まれ。マクロ経済学の発展に多大なる影響を与えた両者は、生前まったく交流がなく、相互に批判しあう関係であったという。 ケインズ経済: 一時的な有効需要の不足を財政・金融政策で解消しようという“短期の理論” シュンペータ経済: 創造的破壊とイノベーションによって、経済成長を実現しようという“長期の理論” 著書吉川洋教授は、この二人の理論を綜合する「需要創造を通じた経済成長理論」の主張者だが、本書ではその立場を封印し、それぞれの思想や理念を、初心者でも理解可能なように丁寧な説明がなされているという。 少子高齢化が進展する中で、日本の経済成長に対する悲観論も多い中、マクロ経済を考え直すガイド役となる。 日経新聞書評 千代田区立図書館蔵書 アダム・スミスの見えざる手、この洞察は精緻な数学的分析に裏打ちされているのではない。彼が提示したのは経済についてのひとつのビジョンである。ケインズとシュンペーターも示したのはビジョン。 一国経済全体の活動水準は生産性要素、技術水準などのサプライサイドではなく、需要の大きさで決まる。工場の稼働率低迷や失業が発生する理由を解明した。不況は需要不足から生まれるのだ。 資本主義の本質は、企業家によるイノベーションに基づくダイナミズムにある。静態的な資本主義は、形容矛盾であり、動き・変化のない資本主義経済は存在しない。
0投稿日: 2009.05.06
