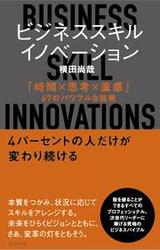
総合評価
(46件)| 6 | ||
| 16 | ||
| 12 | ||
| 4 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログなんやろ? なんか終始、上から目線でイラっとした。 いいことは書いてあるんだろうけど。 自信あるんやろなー、自分のやり方に。
0投稿日: 2024.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事をする上で、身につけておいた方が良い、概念的なものが並べられた一冊。ここにあるような発想を知っていれば、壁にぶち当たったときに役に立つこともあるだろう。
0投稿日: 2023.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間管理、名刺管理、無駄な会議の整理の仕方など、普段あまり気にしていないことについて独自の切り口を説明してくれる本です。 あまり他には無いポイントをついていて意外と面白かったです。
0投稿日: 2021.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ12.9.7 本日の一冊は、ベストセラー『ワンランク上の問題解決の技術』 の著者であり、情熱大陸にも出演した著者、横田尚哉さんによ る、待望の新刊。 ※参考:『ワンランク上の問題解決の技術』 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887596456/businessbookm-22/ref=nosim 著者は、GEで考案され、おもに技術の世界で広まった価値工 学(VE)の手法、ファンクショナル・アプローチを使って、 10年間で総額1兆円の公共事業を扱い、2000億円を超えるコス ト縮減を実現した改善のプロフェッショナルですが、今回の著 書では、個人の仕事術をテーマに扱っています。 ファンクションに視点を移すことで、未来が切り拓けるという のが著者の論調ですが、本書は、そのファンクショナル・アプ ローチの手法を個人の仕事に適用するものです。 「プロローグ」のなかで著者は、これから求められるビジネス スキルについて、こう整理しています。 時間管理は、量から質へ。 思考は、過去から未来へ。 物事のとらえ方は、知性から感性へ。 本書の主眼は、この読者の時間管理、思考、とらえ方に革命を 起こすことであり、そのために有効な手法がいくつも提案され ています。 通常、「仕事には想定の一・四倍の時間がかかる」そうですが、 これを一・一倍にまで圧縮する改善の手法、知的熟成を促すた めのマルチタスクのすすめ、ロスをなくす伝え方の技術、人脈 を整理する技術、集中力を上げるために「二五分間仕事、五分 間休憩」をワンセットにする「ポモドーロ・テクニック」など、 仕事を改善するさまざまな工夫・技術を提供しています。 それなりにビジネス経験のある方なら、既知のものも多いと思 いますが、ここまでホウレンソウや根回しなど、仕事で求めら れる作業の本質をきちんと整理した本は、珍しいと思います。 新人に与える読み物として、また自分の仕事を見直すツールと して、ぜひチェックしていただきたい一冊です。 --------------------------------------------------- ▼ 本日の赤ペンチェック ▼ --------------------------------------------------- ビジネススキルのなかでもとくに重要なのは、「時間」「思考」 「感性」の三つのスキル 時間管理は、量から質へ。 思考は、過去から未来へ。 物事のとらえ方は、知性から感性へ。 仕事には想定の一・四倍の時間がかかる 知的熟成を起こすためには、通常の五〜一〇倍の時間が必要で す。ただ、三日間で終わる仕事に三週間かけていると、まわり から「仕事が遅い」、「中断して放置するな。最後までやれ」 と言われかねません。そこでおすすめしたいのが、マルチタス クによるスケジューリングです 自分満足と他人満足の両方が低い仕事は「勘違い」 自分はやりたくないけど人に必要とされている仕事は「ストレス」 自分満足は高いが他人満足の低い仕事は「迷惑」 形容詞を使わず、数詞で話す 新人には明示し、達人には暗示する 報告は、過去の出来事に関するコミュニケーションです。緊急 性は低いですが、そのぶん正確性や記録性が求められます 相談とは、いま起きていることに関するコミュニケーションで す。現在進行形なので緊急性は高めです。過去を報告するのと 違い、内容は流動的、あるいは議論的です 連絡は、未来の予定に関するコミュニケーションです 決裁を経た書類を既決ボックスに溜めると、指示のロットが大 きくなります。もともと「Aをやってほしい」で済むのに、 「AとB、Cをやって」とまとめて指示するようになり、相手 に待ち時間を発生させてしまうのです 根回しの目的は、《インパクトを和らげる》コト 頼りになるのは、ルールよりモラル、マニュアルよりガイドライン 情報の有効性は、正しいサンプルから導き出したものかどうか で決まります 人脈でやりとりされるのは、その人の持つファンクション 「Value(価値)=Output(成果)/Input(リソース)」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ --------------------------------------------------- 『ビジネススキルイノベーション』横田尚哉・著 プレジデント社 <Amazon.co.jpで購入する> http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/483345047X/businessbookm-22/ref=nosim <楽天ブックスで購入する> http://bit.ly/OeGxJd --------------------------------------------------- ◆目次◆ 第1章 一・四倍で時間を見積もる 第2章 時間と感情のロスを減らす 第3章 チームをマネジメントする 第4章 感性でリスクを察知する 第5章 組織のムダを改革する 第6章 個人の能力を最大化する 第7章 時代の潮流をつかむ 第8章 未来のつくり方を考える ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■〔2〕編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 昨日は、全国に美容室を200店舗展開、200億円の年商を誇る、 アースホールディングスの國分社長と食事をしました。 現在、年収約4億円という著者ですが、「年収1千万円の人間 10人とつながれば1億円」という話が印象的でした。 どの業界にも、売上を上げる方程式というものが存在しますが、 店舗ビジネスの場合、それはマネジメントになります。 國分社長のマネジメント論、いろいろと伺いましたが、とても 勉強になりました。 どんな仕事をしていても、経営マインドを持っていること、素 直なことが成功要因なのだと、改めて実感させられました。
0投稿日: 2019.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログゼロベースで未来から予定を決める。イノベーションを起こすのは今でしょう。理詰めながら、鼓舞されます。
0投稿日: 2019.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ”時間×思考×直感”の67の技術、これを鍛えるべしー! ビジネスマンにとっては必須のスキルや考え方が定義されていて、読みやすく共感あり、実践しやすい良本です。
0投稿日: 2018.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログvol.169 意思決定に必要な時間は0.5秒!?進化し続ける人は全体の何パーセントか? http://www.shirayu.com/letter/2012/000340.html
0投稿日: 2018.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログファンクショナルアプローチの横田さんが贈る、ビジネスマンへの自己改革の勧め。最初はライフハック的な仕事のスキルから入り、最後は生き方ににまで踏み込んでくる。ライフハック的なところでは、1.4倍で見積もるというのが参考になった。途中では感性を磨く1.5秒トレーニングに心を奪われ、ネットとリアルについての関係について考えさせられるとともに、未来に向けたゼロベース思考を再度学んだ。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間のコントロール、思考方法、直感の鍛え方など。経験上、なんとなくわかっていることが確認できた感じ。
0投稿日: 2015.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報技術革命が急速に進む昨今、ビジネス環境も一変し、 情報技未成熟時代のビジネスモデルが通用しなくなった。 そのため、迷える子羊が多くなった。そんな子羊たちを 獰猛な狼たちは、ビジコン(ビジネスコンサル)という 皮を被り、日々捕食している。子羊、ざまぁ・・・
0投稿日: 2015.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人、組織の生産性をアップさせるスキルをじかん、思考、感性の3つの観点から具体的に紹介している。 私はヒラ社員なので、個人のスキルを実行計画に落とし込んだ。 ⚪︎時間→1.4倍で計画を見積もる ポモロードテクニックの活用(25分仕事、5分休憩) ⚪︎思考→知的熟成時間を確保するために、仕事はとりあえずひとかじりする。 ⚪︎感性→0.5秒トレーニング(0.5秒で右脳判断、そのご左脳で検証) 最後に、後書きに書いている下記フレーズが印象に残った 受講者100人にスキルを伝えたら、行動するのは20人、継続し、自分のものにするのは4人。 行動&継続は大切だ!
0投稿日: 2015.01.18時間を置いて読み返したいビジネス書というのも珍しい。
言わずと知れたビジネススキルの名著。「ビジネス書大賞2013年」入賞ですしね。当時、紙で購入して衝撃を受けつつ「今後ビジネススキルの執筆者はやりづらくなるなー」と思うくらいには、色褪せにくい体系的かつ本質的なスキルの本。 電子書籍で再読ですが、当時とは違った箇所が目を惹かれて面白い。昔は「仕事には想定の1.4倍の時間がかかる」「知的熟成の時間を持て」「ルールはマニュアルに、モラルはガイドラインに」辺りに感動したのですが、今は「根回しはインパクトを和らげるために行う」や「感性でジャッジし、論理的に検証する」に薫陶を受けます。特に後半の「感性でジャッジする」については、前後の文脈含め「当時の自分はなぜここを面白いと思わなかったんだろう?」と不思議になるくらいです。言い換えればデータを信頼するな、データで信頼させろ、になるのかな。 一旦読んだ方も、知的熟成した今一度、再読はいかがですか。
4投稿日: 2014.11.09ありきたりな内容
ビジネス関係の自己啓発書としては一般的な内容である。しかし、多くをわかりやすく網羅しているので、あまりこういう本を読んだことがない人にはよいと思う。自己啓発書をよく読む人には目新しいことはないと思います。
1投稿日: 2014.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ過去からの未来ではなく、未来そのものをどうやって見るべきか、と言う本。 感性で決め、知性で測定・検証すべきで、その逆ではない。 感性を磨くには、直感=反射を磨く必要がある。 ま、思考も「過去のデータに対する反射」に過ぎないし、論理的と言うのも、「他人と共有できる反射」でしかない。 初動に肝心なのは勘と言うのが、人間的でよいですね。 ちなみに、動物的勘は、過去経験への舜速的反射であって、極めて過去ベースな判断であるというのが、いま私が納得している考え方なので、あまり未来に結びつくものではないと考えています。
0投稿日: 2014.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構自分の考えとマッチしていた どんなスキルも知識で終わらせず、経験に変え、人に伝えられるよう昇華しなければならないなと。
0投稿日: 2014.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネススキルをただ学ぶだけではなく、自分なりにアレンジしてアウトプットしていくことが重要という、前提のもと筆者がアレンジを加えたビジネススキルが書いてある。 アレンジと言ってもデータから導き出したアレンジスキルなので、根拠がなかったり、主観的なものばかりではない。 スキルを知識として広く知っておくのに、いい本だと思う。
0投稿日: 2014.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス的なマインドを構造的に説明があり、わかりやすかったです。 考え方の引き出しとしては有効だと思いましたが、実務に即反映し転換していけるような内容は少なく思いました。 ただ、図解などで考え方が構造化されている本はなかなか見たことがないので、非常にわかりやすかったです。
0投稿日: 2014.03.10ビジネスマンの基礎知識として理解しておきたい内容がまとめられています
特別なことは書かれていません。ごく当たり前の事が丁寧にまとめられています。 社会人一年目に読んでおくと、時間を無駄にせずに済むと思います。 その後、5年後にもう一度読むと、理解や実感できなかった点について、新たな発見や反省を感じることができるのではないでしょうか。 書かれていることがきちんと実践できるようになるのはリーダークラスになってからかもしれません。
1投稿日: 2014.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ目次を見て、見たことない内容だなと思った方にとってはいい本だと思います。一方で、他の書籍などで仕事術などをいろいろと読んだことのある人にとってはちょっと物足りないと言う感じのないようだと思う。入社して2~3年くらいの人が読むのがちょうど良いかもしれない。
0投稿日: 2013.10.23ワークスタイルの棚卸し
筆者が思うスキルをいくつか紹介する本である。自分の働き方を再確認させられるとともに、ワークスタイルの棚卸しにも繋がり、使えるスキルもいくつかあることから、新しい働き方を模索している人や社会人1年目にオススメ。
1投稿日: 2013.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネススキル本として実践的かつ有用。文章も平易で読みやすい。難しい専門用語が使われていることもないので、分かりやすい。 だからと言って、ビジネスパーソンであれば誰にでも良いかと言うと、実は読み手に対してスキルもある程度必要であり、新入社員が本書を読んでいきなり理解できるかと言うと、それは難しいそうだ。これからリーダーになる人や、今リーダーとして活躍している人、ビジネスの最前線で活躍している人にとっては、ある程度体系化された知識を得ることができて良い。後は実践するかどうかの問題。
0投稿日: 2013.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル的に「時流に乗ってるなぁ感」をヒシヒシと感じつつも、ファンクショナル・アプローチ著者の横田氏の書籍であったため手にとってみた。 しかしながら内容はイノベーションと呼ぶには程遠く、どこにでもある普通のスキル啓発本である。入社2年目くらいの若手が読むにはちょうど良いかも。
0投稿日: 2013.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネススキルといっても、日常業務のスキルの話が多い気がする。ひと昔前だったら、ハック本の1つとして出てきていたレベル。帯に『究極のビジネスバイブル』とあるがもちろんそんな訳はない。
0投稿日: 2013.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログオシャレな表紙が目を引く一冊。 が、自身(新入社員)が読むには、ちょっと早かったな、と認識。管理職とか、上の立場になるときに読んでおくと、色々と仕事にいかせそうでしたね。 会議の運用方法などに関しては、そういうのを提案できる環境にいて、始めて活かせる気がしました。今のうちから蓄えても、どっかで忘れそうだな、と…笑 また、他の働き方に関する部分では、特に目新しいことは書かれていないように感じました。 書いた人や、この本が好きな人には怒られるかもしれませんが、よくある話を、回りくどく書いたような。そんな印象を受けてしまい、あまり好きになれませんでした。 もちろん、人脈の捨て方とか、ゼロベース思考とか、感性とデータの使い分けとか、ためになる話も書かれているので、これは僕の読解力の問題が大きいでしょうね。 自身には、どこかピンとこない、なんか合わなかったなぁ、と感じる一冊でした。
0投稿日: 2013.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ・リスク、ハザード、突発仕事により計画の1.4倍時間が掛かる ・難しい仕事はかじりそして寝かせる 寝かせることで考えをとめない ・ルール、マニュアルよりモラルを重視して仕事をする。 ・
0投稿日: 2013.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本のようなコンサルタントの人が書く、今までの知識をぶつける本が最近の好み。 読んでるときの感覚が、飲み屋とかで語られてるような感じ。 ただ、参考文献は明示してほしいわ。オリジナルとそれ以外はちゃんと分離してくれ。
0投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスに役立つスキル、というかちょっとした知恵をまとめた本。67もあるが、全てが全て斬新というわけでもなく見慣れた内容も多く含む。とはいえ、毎日これらが実施出来ているかといえばそうではない。特に気をつけておく点をいくつかをピックアップして、それらは時々振り返るとよいかもしれない 特にゼロベースでの思考とトレンド思考の根本的な違いはなるほどと感じた。 <メモ> ・会議の機能を数値化して見直す ・データに頼った判断を辞める。6割の情報で判断する ・名刺管理。不要な人脈は捨てる ・アウトプットは常にインプットで割る ・知識はお金で経験は時間で買う ・企業の経営は方針決定と事業の管理に二分される これらはイコールではない ・感性で決め、知性で測り、理性で示す 知性は過去(管理者)、理性は現在(作業者)、完成は未来(経営者)を意味する ・目標はゼロベース思考で設定する。 過去の延長、トレンド思考は過去に縛られてしまう 以上
0投稿日: 2013.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事術や時間管理の本を読んで、実行に移す。 でも時間が経つと、サボってしまう。 そんな、ついつい楽な方向に流れてしまう自分を、自覚しています。 ゆるんだネジを巻きなおすために、仕事術や時間管理の本はコンスタントに読むようにしています。 ということで、この一冊。 VA(Value Engineering)をベースに、企業の経営効率を改善する、コンサルタントによるビジネス書です。 時間管理から始まり、組織管理へと展開していきます。 その中で「リスクを察知するには感性が必要」という視点が加えられているのが、本著の特徴かと思います。 自分自身は、個人としての能率向上の部分に注目していたので、「仕事には想定の1.4倍の時間がかかる」「”寝かせる”時間を確保するために、マルチタスク化する」といったあたりが特に、参考になりました。 感性と知性を使い分ける。 今の自分の判断はどちらによるものなのかを自覚して、足りない一方を強化するように、心がけていきたいと思います。
0投稿日: 2013.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ新しい「機能」を創るという、初めてのミッションに取り組んでいる。「機能とは何か」を正しく知ることが重要と考え、横田尚哉さんの本を何冊か読んだ。「原因と結果」という過去思考から、「目的と手段」という未来思考への転換を促すビジネススキルを説明。この本はKindleで買っていつも携帯すべきだったかも!
0投稿日: 2013.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容が盛り沢山で消化不良気味・・・。 メモった内容の一部下 ・多くの人が見逃す変化に違和感を抱けるか ・0.5秒で判断。感性で判断して知性で検証 ・積み重ねた時間の分、未来を見通すことができる
0投稿日: 2013.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の主観的な仕事法で、あまり学ぶとこはなかったかな、という感じ。 そういう風に考えてる人いるよなぁ、と。 あと、カタカナ言葉が多い。(そういう人いるよなぁ…) また知識と情報の言葉の定義に違和感があった。 情報とは「目的達成に役立つ知識」のことで、役に立たなければそれは情報ではなく知識だそうだ。 (p136) …その真逆の定義をされたほうがむしろしっくり来るのだが。 割り込み仕事(電話・メール、オフィスで話しかけられる…)の扱いに関しては、共感できたし、学ぶべきことも多かった。 電話は取捨選択、メールはまとめてチェック、カフェでの仕事はかどる、オフィスでの仕事は誰か一緒にする仕事(打ち合わせなど)で活用。 全体的に管理職目線の内容だったように感じる。 ----- memo p96 大切なのは「1を知って、1を教える」から、「10を知って、1を教える」のレベルにいくことです。 p165 『通勤の役割を見つめる』 p169 『割り込み仕事から自由になる』
0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログいろいろなことが書かれているが, 通奏低音は「感性で未来を捉える」「時間を大事にする」ということだろうか。興味深い図表が多い (物事を 2 つの軸で 4 象限で整理するなど) のもポイント
0投稿日: 2013.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ8割は分かっていること。ただ、残りの2割を再確認し、気付き、他人に示唆できる形でまとめてくれているところに価値がある。 感性はまず経験し、発見するところから生まれて育つ。自分には縁遠いとやってみる前に諦めないで、とりあえず、目の前にあることから実践してみるのが大事だと改めて教えてもらった。 堅苦しくなく、読みやすいのでデザイナーに勧めたい一冊。
1投稿日: 2013.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報は事例でなく、原理で理解する ポモドーロ・テクニック 25分間は他のことを一切しない 知識はお金で、経験は時間で買う
0投稿日: 2013.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ何か仕事のヒントが一つでもあれば、程度の期待で読んでみたが良いことが色々と書いてあったので満足。 ただ、問題分析は全くその通りだと思うが、後半になるほど対策の抽象化が顕著になる印象。仕方ないとは思うし、考え方を示唆する狙いなのだろう。
0投稿日: 2013.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「誰のため、何のため」という未来思考の考え方に刺激をうけ、実際にお会いしてその人柄にも魅了された改善士 横田尚哉さんの新刊。 本書では67のスキルが紹介されていますが、読み進めるほどに、いかに日々の中に無駄が潜んでいるのかを実感します。 中でも強く取り入れようと思ったスキルをいくつか。 1.時間は1.4倍で見積もる。スケジュールに予め時間リスクを盛り込み、一方で仕事のやり方を工夫して時間リスクを減らす努力をする。 忙しいから余分に時間を見積もる余裕がないといって、予想時間きっちりでスケジューリングすると、ちょっとした横ヤリですぐに破綻してしまいます。捨てるべき業務を見分けることでスケジューリングもしやすくなります。 2.マルチタスクでアイデアを熟成させる。タスクの最低単位は20~25分以上。 これは私が勘違いしていたことで、本書の例にあるように、「Aの仕事に必要な資料をプリントアウトしている間に、Bの仕事の関係者にメールを打ち、終わり次第Cの仕事に取り掛かる」というようなやり方をマルチタスクだと思っていましたが、このやり方だと、集中力が高まる前に次のタスクに移行することになり、かえって効率が落ちるとのこと。だから最低でも20分は同じ業務を続ける。 3.ルールとモラルの違いを知る。 モラルは目指すべき中心点。ルールはモラルからこれ以上離れてはいけないという限界を示す境界線。ルールを守ることが目的化してモラルが軽視しがちになる。手段と目的を取り違えないようにすること。 4.0.5秒トレーニングで感性を磨く。 リスクを察知するのは感性。感性を磨くために普段から0.5秒で決断する癖をつける。その際、目的や役割を明確に意識すること。データは感性を刺激し修正する手段に過ぎないというのも、普段なかなか決断できない私にとっては意識しなおさなければならない点です。 今回特に「感性」が重要視されていたように思います。「今このときを大切にして生きるしかない。真剣に生きた時間の積み重ねが感性を高める」という言葉は胸に突き刺さりました。 スキルを伝えた100人のうち、実際に行動し、継続して、それを自分のものに出来るのは4人だけ。その4%の中に自分が入るのかどうか。「コントロールできるのは今日この瞬間だけ」という言葉を忘れずに進んでいきたいと思います。
0投稿日: 2012.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が考えたビジネススキルで有効だったものを 67紹介している本になります。 色々書いていますが、中でも多く登場したのが、 「感性」で物事を考えるというもの。 そこに行ってしまうと、経験がものを言うということとなり、 残念ながらスキルとして使えないものとなってしまう。 やはり経験無くして、作業効率を上げることは出来ないのか? そういった意味では、当たり前のことが書かれているだけといった感じ。 参考になった内容: ・スケジュールは想定の1.4倍で見積もること。 ・根回しの目的は、「インパクトを和らげる」こと。 ・問題が起きたときにトップに求められるものは以下2つ。 いまの手段の継続を優先すべき状況なのかを見極める力 見極めた道を躊躇なく進男気 ・情報量は6割で充分。6割の情報量を感性によって判断すること。
0投稿日: 2012.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
チェック項目13箇所。変化の激しい時代に求められているのは、本質をつかむ力です、物事の本質をつかみ、環境の変化に合わせてスキルをアレンジしていけば、従来のようにスキルの陳腐化に悩んだり、流行りのスキルを追いかけて自分をすり減らすこともなくなります。仕事のスケジュールは勝手に延びます、仕事が想定より遅れてしまうのは、仕事の遅さではなく、そもそもの見積もりに問題があるからです。8時間分の仕事でギッチリ埋めるのではなく、5,5時間分の仕事でスケジュールを組みます、これなら何らかのリスクイベントが発現しても、5,5時間×1,4倍=7,7時間で仕事が片付きます。私たちは自分の考えを、モジやコトバという共通のツールに置き換えて相手に伝達していることになります、ミスが起こりやすいのは、頭の中をコトバに変換するときです、自分の考えをコトバに置き換えるプロセスで情報に歪みが生じて、間違ったカタチで相手に伝わってしまうのです。変換ミスを防ぐために意識してほしいことが一つあります、それはコミュニケーションに形容詞を使わないことです、仕事上のコミュニケーションには、お互いが共通の単位として使えるコトバを用いることが必要です(具体的な数字)。仕事において必要なのは、分担作業ではなくチーム作業です、形式的まとまりの状態から、有機的なつながりの状態へ、それによってはじめて、個々の力の寄せ集め以上のことを成し得るのです。モラルは私たちが目指すべき中心点です、中心に近ければモラルが高く、同心円状に離れていくほどモラルは低くなります、ルールは、モラルからこれ以上離れてはいけないという限界を示す境界線です、ルールは、守るか守らないか、一線を越えたらアウトです。悪いのは社員の草食化ではなく、草食化した社員をマネジメントできないあなたのほうです、草食社員は危険を避け、安住の地を求めることを好みます、一方肉食社員は茂みに分け入ってでも、大きな獲物を探します。一を教えるなら、自分は10を知る、それにより、自分も一段上の高みに到達することができます。人脈づくりで大切なのは、受けの姿勢です、身を低くすればするほど、人脈が集まります。いま大切なのは、守りの時代においても攻めの姿勢を忘れないことです。経験は、自分で汗をかかないと手に入りません、お金を積んでも、人から経験を譲ってもらうことはできないし、借りることもできません。
0投稿日: 2012.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからのビジネス社会を生きる上でのスキルについて。 67個のスキルが紹介されているが、本質的には ・時間の使い方…量から質へ ・思考のベクトル…過去から未来へ ・本質をとらえる力…知性から感性へ この基本的な考え方を身につけることを目的としている。 個々のスキルにはすぐに実践に移せそうなもの、そうでないもの勿論あるし説明不足なものもある。だが、著者が唱える身につけるべきビジネススキルの本質部分については納得感があるので、それに根差したこれらのスキルをまずは一つ二つ取り入れて、その本質に近づくことにチャレンジしたいもの。 改めて自分の仕事に対する姿勢を批判的に捉える触媒として。
0投稿日: 2012.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・感性で決め、知性で測り、理性で示す。 →知性は知識によって厚みを増し、理性は訓練によって鍛えられ、感性は経験によって磨かれる。 イマジネーションにより、未来を見通す。 ・計画には、0.4倍の時間ロスを折り込む。 ・思考を寝かせて、知的熟成を待つ。 ・新人には明示し、達人には暗示する。 ・根回しは、相手が枯れないように配慮する為に行う。 ・既知、無知、未知 三つの領域。 ・過去、現在、未来 の判断基準で人脈を考える。 ・知識はお金で、経験は時間で買う。 ・意識、行動の先、察知、想像、発見でセレンディピティを。
0投稿日: 2012.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ縦軸に自己満足、横軸に他人満足 右上が理想、右下はストレス、左上は迷惑、左下はムダ 自分にとって満足な仕事をする時間と不満な仕事をする時間、他人にとって満足な仕事と不満な仕事。両方の満足が重なる理想の時間をいかに増やすか。 縦軸に、目的と手段。横軸に達人と新人 右上が暗示的、右下が指示的、左上が教示的、左下が明示的 指示には4つの種類がある。手段まで具体的に示す「明示的」指示か、手段については相手に選択と判断を委ね、目的のみを示す「暗示的」指示か、クリエイティブな仕事の場合は、明示→教示→暗示と進むのが、教える側にとって時間のロスがもっとも少ない。 縦軸に個人力、横軸に組織力 右上はチーム作業、右下は分担作業、左上は個別作業、左下は役立たず。 マニュアルは障害があったときに動けなくなる、ガイドラインなら、暗闇で音がするようなもの、自発性を育てる 10を知り、1を教える 理解には3つの段階がある 言語的理解、抽象的理解、体系的理解 未知の領域を理解する 情報の領域には、既知、無知、未知の3つがある 本当に大切なのは、未知の情報の把握。リスクは未知の領域から、いきなり表面化する 海陸両用の生き方を目指す 下層の欲求はリアルで満たし、上層の欲求はネットで満たすことが最適なバランスだと考える人もいるが、危うさを感じます。 人脈でやりとりされるのは、その人の持つファンクションです。リソースは、ファンクションを実現するための手段です。相手が求めているのはファンクションであり、リソースを直接的に求めているのではありません。 1980年代は「多様な生活や経済活動に対応できる国づくり」これらは物量がピークに達して、精神的な豊かさに視点が移ってきたことを示しています。 将来を見据えて行動するのは「プロアクティブ」ですが、現状に対応するのは「リアクティブ」です。経営者に求められるのは、プロアクティブな経営です。しかし実際はリアクティブに終始して、その姿勢をプロアクティブだと勘違いしているケースが多いのです。
0投稿日: 2012.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログよくあるビジネススキル本かと思いきや、直感に響く説明がなされており、良い本でした。 知性で検証、のフレーズはまさに我が意を得たりの思いでした。 ただ、後半は、この手の本にありがちな、著者の独り善がりな説明といった印象を受けるところもあったのが惜しいところです。
0投稿日: 2012.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ファンクショナル・アプローチ」で有名な著者による仕事術本。具体的なノウハウもあれば、心構えのようなものも含め、67のスキルが紹介されている。
0投稿日: 2012.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログさすがに67もあると全肯定とはいかないが、うなづける箇所多数。でも本当は納得できない項目も受け入れられる感性を育てることと、理解しているつもりの項目が実行されているかどうかを知性で検証することが大事なのだろう。 一番気になったのは本のサイズだったりもするが・・・
0投稿日: 2012.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ直感的に思っていたことをうまい表現でまとめられていたのでありがたい一冊となった。もう少し字数が少なくて図が大きければよかった。
0投稿日: 2012.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分か心がけてきたこと、今まさに考えていることがシンプルにまとめられているようで、すらすらと読むことができた。イノベーションとは特別なものではないが、起こすべき行動が他だ場当たり的では起こらない。 仕事をがむしゃらにやって来た人ほど立ち止まって読んでほしい。
0投稿日: 2012.09.04
