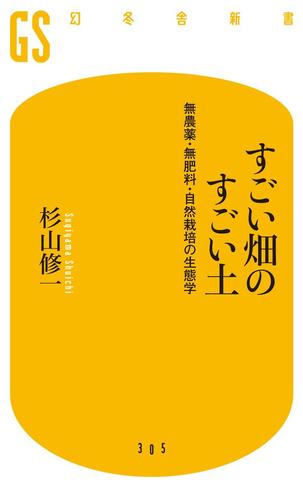
総合評価
(11件)| 0 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ軌跡のリンゴで実践されている自然栽培という農業を追い続け、科学的に優しく説明している。 通常の農業と自然栽培の違いを、生物学における「分子生物学」と「生態学」を例に比較するところは、なるほど、と納得。 本書もそれなりに興味深いのだが、以前読んだ『土と内蔵』の方がより面白かった。
2投稿日: 2025.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然栽培で作られた奇跡のりんごは、単なる奇跡なんかじゃなかった。複雑な生態系、美しい景観、豊かな土壌によって育まれたりんご! 美味しくないわけがない‼️ 内容が自分にはちょっと難しかったので星4つ。
0投稿日: 2023.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ奇跡のりんごとして、2006年プロフェッショナル 仕事の流儀で紹介されて、一躍有名となった。 とりわけ、脳科学者である茂木健一郎がもてはやした。 「不可能を可能にした」ともてはやされたが、りんごは農薬や肥料もない時にリンゴがなっていたのだから、不可能というのが、大げさすぎて、持ち上げすぎなのだ。 木村秋則は、「りんごをならせるのはリンゴの木です。主人公は人間ではなくリンゴの木です。人間はそのお手伝いをしているだけ」さらに「自然を抑えるのでなく、自然に近づくこと」と言う。 農薬も肥料もやらない自然農法。なぜりんごができたのか?は、木村秋則も説明できない。 ただし、りんごは「みずみずしい。素直で、ほのかに甘い、しかも腐りにくい」と言う。 生態学者の杉山修一が、なぜりんごができたのか?と言うことを科学の立場から解明しようとする。 木村秋則の農業は、「自然栽培とは生物の力を利用する農業」と言う。 再現性があるという設定が、科学的とは言えない。 著者は、無農薬と無肥料でやっている自然農業は、木村さんだけでないから、再現性があると言うが、科学における再現性とは、そう言うことではないと思う。再現性があることとは、実験条件を同じにすれば,同じ現象や同じ実験が同一の結果を与える場合,再現性があると言う。農薬と化学肥料をなくせば、りんごができたでは、再現性があったとは言えない。もともと、りんごはできるわけで、実験条件が、足りなすぎるのである。実際には収量が少ない場合があると言っていて、再現性があったと言う実験結果が違っているのだ。なぜ収量が少ないのかが、説明できないでいる。 つまり、木村秋則が言っている「手伝い」とはどんなことかを明らかにすることも必要だろう。自然に任せるだけでは、何もしないと同じでもある。 確かに、農作物を遺伝的に単一化することによって、病気や虫が発生しやすくなる。肥料が与えられた作物は病気にかかりやすい体質になる。多くの肥料を吸収した作物は、葉が柔らかくなり病原菌が侵入しやすくなると言っているが、体質や柔らかくなることではなく、硝酸態窒素が植物体からあふれ出ることで、それを病害虫が餌にするからである。 生態学者として、慣行と木村りんご園の比較されているのは、①土壌中の窒素量が多い②微生物が多い③虫が、慣行は16科57個体(そのうち寄生蜂25個体)で、木村りんご園は、28科308個体(そのうち寄生蜂121個体)④葉の中の内生菌(エンドファイト)が多いと言うことだ。 この現象をどう作り上げるかにあるのだが。 「植物が吸収できる窒素は、硝酸イオンやアンモニアイオンだけです」と言い切っているのは、最新の有機物が吸収されていると言うことさえも知らない。土壌の中にある窒素成分は、植物が利用しやすいアミノ酸などになっているので、肥料だけでなく、 「競争は人間や社会を活性化させる大きな力」といい、「競争原理」を説明するが、多様性を生み出した自然農法は、競争原理で説明はつかない。なぜ、それだけの多様性を生み出すのか? 著者は、りんごの免疫機能を回復できたと言って、①病原菌を感知するセンサー機能②病原菌を排除する攻撃システムができたと言う。なぜできたも仮説の段階でしかない。 まぁ。色々言っても、生態学的なアプローチでしか説明しきれていないので、まだわかっていないことが多いと言うことだ。自然農法を自然にできると言う関わり合い方だけで、収量が上がらないのは明らかであるとも言える。それで、自然農法で日本の未来があると思うのは、かなり妄想に近いのではなかろうか?
0投稿日: 2021.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ奇跡のリンゴの農家から学んだ自然農法のメカニズムについて、わかりやすく解説している。 遺伝子組み換えされた野菜や農薬がどのように人体に影響を与えているのか。 自然農法で微生物や虫などがどのように働き、助けてくれるのか。 家庭菜園で土作りを試行錯誤している中で、とても参考になる内容だった。
0投稿日: 2019.03.08重要なのは窒素フロ-
木村リンゴ園の実例から、自然栽培の科学的、技術的分析を行っていますが、筆者自身も触れているように、木村リンゴ園の分析結果はまだ少なく、一般論の説明となっています。有機栽培を含めて、畑に窒素成分などをあらかじめ投入しておき含入量を多くすることが栽培の基本であるのに対して、自然栽培では、窒素などを流入させるメカニズムが確立することが必要であり、そのための多様な植物、生物を共生させること、窒素を代謝する細菌叢が存在することなどが必要であることが理解できます。さらなるデ-タの分析を期待したい内容でした。
0投稿日: 2017.06.04科学的=トップダウン式ではなく、自然的=ボトムアップ式の農業
弘前大学農学生命科学部教授の杉山修一は、“野外における植物の適応プロセスを生理生態学的な方法やDNA解析をはじめとする分子生物学的方法により解明するアプローチ(研究室HPより)”によって、植物と環境の相互作用を研究している。 そして、『奇跡のリンゴ』で知られる木村秋則の自然農法を、科学的に解明することも研究のひとつとしている。 相当数のメディアに取り上げられ、映画にまでなった木村秋則の農法とそこに至るまでの苦労は、ストーリーとしてはとても美しく、諦めない人間の凄さを感じさせてくれる。 しかし一方で、科学の力を使わず、人間が手を入れることも最低限な自然農法に関しては、まだまだわからないことが多いというのが事実。杉山はそれを解明しようと木村の農園に通い始める。 分子生物学的にある特定の植物を分析しても、対処法としてはどうしても科学的な対応で解決するしかない。つまり薬品や遺伝子を変える方法になってしまう。 杉山はまだ解明途中ではっきりとした答えは出ていないとしながらも、いくつかの答えを見つけ出す。「生物の力」「植物-土壌フィードバック」「生物間相互作用ネットワーク」「植物免疫」などなど。トップダウンではなく、地道にボトムアップ式で作っていかなくてはいけないけれど、そこにはこれからの日本の農業だけでなく、国全体の未来を示唆するかもしれません。
0投稿日: 2014.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ植物生態学者の視点による、自然農法のメカニズムの解説が大変興味深く、自然農に取り組む上でとても参考になります。
0投稿日: 2014.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ奇跡のリンゴを生み出した、自然栽培のメカニズムが解説された本。 有機栽培と自然栽培の根本的違いは、プレイヤーとして振る舞うか、監督して振る舞うかの役割の違いにある。 なんか、コレを読んでハッとしました。 農的暮らしを取り入れるべく半農生活を始め、トライ&エラーで有機栽培をやってはいるんですが、やろうとしていることは、自然を抑えようとしているんだなと。 そうじゃなくて、自然に近づけることで生物の力を利用するんだと。うん。コッチのほうが無理がなさそう。 ちょっとうちの畑の一角を使って、自然栽培のアプローチで試してみようと思います。 本書の中盤は専門的な内容で眠かったので、、また改めて読み直します。
0投稿日: 2014.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ農業に興味がある、奇跡のリンゴに興味ある方にオススメ ・自然栽培とはどういうものか ・畑の土壌はどうなっているのか 自然栽培の触りを知りたい方に、オススメの1冊 土について勉強になりました。 私個人が「なるほど」と思ったところは、付箋、折り曲げがあります。
0投稿日: 2014.01.08ガーデニングにも応用できる
無農薬・無肥料で作る「奇跡のリンゴ」の栽培法である「自然栽培」の秘密について、科学的なアプローチにより、その解明を試みている。「自然栽培」は、一般的に知られる「有機栽培」とも異なる方法であり、「生物多様性」に基づいて、肥料も堆肥も使わずに育て、農薬も使わずに害虫や病気の影響を最小限に抑えるものである。 私は農家ではないが、この本に興味を持ったのは、ガーデニングで育てているバラの育成に役立つことがあるかもしれないと思ったからである。バラを育てている人であればよくご存じと思うが、薬剤散布を怠り、ひとたび黒星病にかかれば、あっという間に葉が落ちてしまい、春にきれいに花を咲かせたとしても、夏には丸裸で枝だけになってしまうこともめずらしくない。そのため、定期的な薬剤散布がかかせず、また、施肥も他の植物に比べれば多く必要で、作業負荷が高い。もっと楽にバラ栽培ができないか、と常日頃考えていたところであった。 リンゴはバラ科であり、通常のバラ同様、黒星病にもかかるのであるが、木村氏のリンゴ園では、病気にはかかるものの、ほとんど葉を落とさないという。また、施肥もせずに実がなり、収穫量も一般的なリンゴ園と遜色なく、味の方は一段上だという。これらのメカニズムは、すべて解明されているわけではないが、「生物多様性」によりもたらされていることは明らかなようである。 本書は、大学教授が科学的な見地から書かれているものなので、巷の園芸書のようにとっつき易くはないかもしれないが、今後の庭造りを考えるに当たり、大いに示唆に富むものであった。今後のガーデニングに、「自然栽培」の考え方を取り入れてみてはいかがだろうか。 「自然栽培」は、まだ研究途上であり、今後の発展への期待を込めて、星は4つとした。
0投稿日: 2013.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルにもサブタイトルにもないが、「奇跡のリンゴ」の自然栽培を軸にした話。生産者がプレイヤーをやめるのが自然栽培だけど、放置するのではなくて監督をやるのだ、と。僕は放置派だったのですが、それでは確かにうまくいかんのです。 生物相を多様化し、分子生物学的だった農業に、生態学の視点を。生物のネットワークから見ると、作物自体が一番の攪乱かもしれませんね。そういう結果を監督としてコントロールするのは、門外漢のほうがよかったりするのかもなあ、などと漠然と思ったり。 本としては、やや冗長だったり唐突だったりと感じるところもありますが、あかるい話でよい。
0投稿日: 2013.09.27
