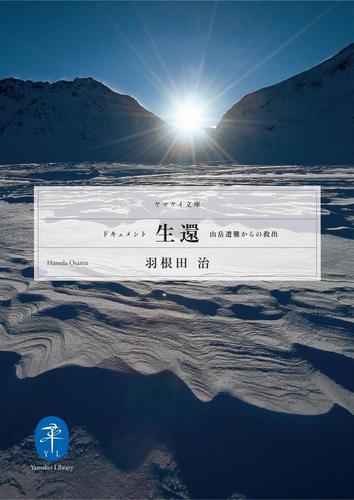
総合評価
(27件)| 11 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのシリーズ読んでから登山する気無くなったのは残念だけど、もし何かの機会があるのなら、日帰りでもツエルトと火・ストーブ・非常食は持っていくようにしたいです。 あと教訓としては ・家族などに計画書を伝える ・遭難したら救助をじっと待つ ・バスの時間などタイムリミットがあると特に冷静さを欠いてしまう。 そもそも登山なんて非日常の空間なんだから、基本的に冷静さというものは保つのが難しいと心得たほうがいいですね。 本書は生還した人の体験談ですが、生還なんて奇跡と言っていいくらい壮絶。たまたまマヨネーズ1本持っていたとかそういう「たまたま」が命を繋いでいました。しっかり準備することだけは怠らないでほしいです。
6投稿日: 2025.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ山岳遭難から生還した人のドキュメント集。 まず思ったのは、 人間って生きようという意思がある時の生命力は凄いんたな。 山は素晴らしいところなんだろうけど、やっぱり怖いよな… この本には生還できた人の話が書かれているけれども、この何百倍いやそれ以上の帰ってこられなかった人がいるのだろうし。 私は登山はやらないが、働き方や実生活に応用できる事もいくつもあった。 「予想外の事態に陥ったことで、ふだんの自分を失うほど気が動転し、結果的に判断を誤ってしまった』。 こんな事は山に行かなくてもいつでも起きうる。 少しでも本書から教訓を得ていかしていきたいと思う。 それにしても生きて帰ってきた人たちすごかった。まずは遭難しないように、遭難してしまったら体力の温存。その鉄則は多くの人が知っているのだろうけれど、その場になるとなかなか難しいのだろうな。
0投稿日: 2025.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ遭難には法則性があり、どちらも人間心理によるものとわかる。 ①楽観バイアス:遭難者はだいたい皆遭難してすぐに「何かおかしい」と違和感は感じるが、根拠なく「大丈夫」と判断し突き進んでしまう ②サンクコストに勝てない:違和感を感じたまま突き進んでいよいよ遭難したと気づいても、来た道のりをまた戻る労力を考え突き進む選択をとってしまう 山岳に限らず、仕事や生活でも同じようなことはおきるなあと思いながら読み進めた。 筆者の文章がうまいので、いつ何がどのような状況でおきたかと、そのとき遭難者が何を考えていたのかが、すんなり頭に入ってくる。
0投稿日: 2023.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
やっぱりこのシリーズ大好きです。 全く登山はしないけど、実際にあった話という事が面白いのかどんどん読んでしまう。 うじ虫が出たりと凄い状況でも生き残れるのが凄いと思う。
0投稿日: 2023.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味はあるものの登山は未経験、たまたま流れてきたトムラウシ山遭難事件のWikipediaの壮絶さに興味を持ったところ、おすすめして頂きこの本に辿り着きました。初っ端の西穂高岳遭難からあまりにも怖すぎて一気読み。普段私たちは人間が人間のために作り上げた世界で暮らしており、山は全くの別世界なんだな……と強く実感。ほんの散策のつもりが遭難してしまい山中で11日間生き延びた冒頭のエピソードといい、本格的な登山でなくても何かが起きる可能性は常にあり、準備してもし過ぎることは無いと心に刻みました。
0投稿日: 2023.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ山で道に迷ったらどうするか、頭では分かっていても…とつくづく考えさせられる。 私も単独行なので余計に。もし怪我をしたら、もし道迷いをして夜になったら、そのもしはすぐ近くにあったりするものだと改めて思う。 何回も改めるべき事。 追記にあったように日帰りハイキングであろうと火、ストーブ、ツエルトは必携。
0投稿日: 2023.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ山登りはほとんどしないけど、人間の力なんて及ばない山という世界に興味を持ってたので読みました。ちょっとした判断ミスで遭難して非日常に迷い込んでしまう・・・。やっぱ山って怖い一面があるなぁ。
2投稿日: 2023.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ遭難するかはほんの紙一重。ほとんどの人がその後に遭難場所を再訪したり、登山を再開していて驚きました。
0投稿日: 2023.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログある遭難者がインタビューで語った言葉が、私がインドで一人旅をしたときに感じたこととほとんど同じだった。 全く同じ状況でなくとも、個々人にとってある種の極限状態といえるに状況においては、人間の感じることはある程度似ているのかもしれない。
0投稿日: 2022.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ登山で遭難し、生還した方たちの体験談だが、実際は亡くなってる人もいるわけで、その人たちとの違いは何かなと思ったら、やはり「家族」かなと思った。 行き先を告げる家族、帰宅しないことに気が付く家族、幻覚の中に現れる家族、家族じゃなくても、そういう他者の存在が普段の生活にいるかいないかで、状況は大きく左右されると思った。
0投稿日: 2022.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章がいいので最後まで読むことができたが、日本人らしい意地悪な視線がそこここに見られて辟易させられる。我が国では「世間に迷惑をかける=悪」という価値観が根強く、生還した人をヒーローと称えるアメリカのような見方ができない。 https://sessendo.blogspot.com/2021/08/blog-post_25.html
0投稿日: 2021.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
7名の遭難者の方々の当時の状況・心境、対処法がかなりリアルに書かれています。 ガイドブックに書かれていない、読んでてゾッとする面もありました。 でもその分、頭にイメージがついて「気をつけなければならないポイント」がよくわかりました。 あとは読んだ事をどう活かしていくのか、気をつけなければ! とりあえず、マッチ持って行きます。
1投稿日: 2020.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ危機的状況に陥ったときに幻覚を見る人のなんと多いことか。そして、幻覚を見せるのも脳ならば、それをみて「これは幻覚だ」と判断するのも脳という不思議。 この本に出てくるさまざまな体験談が事実なら、一部の特殊な人だけが幻覚をみるわけではなく、どんな人でも一定の状況下では幻覚をみる可能性があるということだ。 考えてみれば結局のところ私たちは、感覚器官を通じて入ってきた様々な情報を脳が再構成したものを「見て」いるだけ。ならば脳はその気になればいくらでも幻覚を見せられるということか。 こんなに簡単に(というと言いすぎかもしれないが)幻覚をみるのなら、究極的には自分が主観的に見たものなんてアテにならない。
0投稿日: 2020.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ羽根田氏の「気象遭難」を読後、他の著作も気になったため、本作を購入しました。 登山好きを自称するには経験も微々たる自分ですが、こうした山岳遭難の事例を読むことで、もし自分が同じ状況下に陥ったときどうすべきかなど、教訓を得ることができます。 中でも最後の事例の大山(神奈川県)は、つい先日登った山でもあったため、自分が辿った道を思い出しながら、どこで分岐を間違えたのだろうか、と、条件が重なれば自分も同じ目に遭ってもおかしくはないのだと思い知りました。 登山時には ・行動計画を周囲に知らせておくこと ・低山といって装備など侮らないこと(緊急時にビバークできる程度の装備を常に携行する) ・もし遭難したならば沢の方には下らず、無闇に動き回らないこと 以上のことを自分自身も心がけようと思います。 また、遭難したときに絶対に諦めないこと、生きて帰るという強い意志を持ち続けられるよう、家族との日々の生活を大事に過ごしたいと感じました。
0投稿日: 2020.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は山登りはしませんが、少し興味を持ったので手に取ってみました。 淡々と書かれていてとても読みやすく、時々ゾクッとするような描写もリアルで大変惹き込まれました。
0投稿日: 2019.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ山登りはしないけど、いざというときの思考や行動に学ぶべるところがあるのではないかと思って 焦る気持ちや家族が心配してるんじゃないかとかあるのに、覚悟を決め動かずに救助を信じて待っていて、すごい 足が折れてしまったのに頑張り続けた人、目の前に車の通る道が見えているのは絶望感がすごかったのでは…
0投稿日: 2018.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログごく普通の山好き市民たちが遭難し、生還を果たす。なぜ彼らは遭難したのか、そして、どんな感情と行動で山中を過ごし、生還したのかをインタビューしたドキュメンタリー。 考えさせられるのは、ささいな不注意で山の自然に飲み込まれてしまう人間の弱さと、その一方で絶対的な窮地で開き直ったときの人間の強さだ。 皮膚から骨が突き出し、大量の出血、傷口にはウジがわき、それが目の中に入るという発狂しそうな状況で何日間も救助を信じて待ち続けた者もいる。 彼のように本書で生還を果たす人々はどれも自力下山をあきらめ、救助された者ばかり。遭難時には、体力の消耗を抑えて耐えるということが必要らしい。とはいえ、ベストは遭難しないことであり、そのためには周到な準備と来た道を後戻りをする勇気だ。 本書が教えてくれるのは遭難のノウハウではなく、絶対に遭難しちゃいけないってことだ。
0投稿日: 2018.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ遭難に巻き込まれた時の人の心の動きを知ること。人はどのような心理状態に陥って、どのような行動をとるのか。 2016.8.22
0投稿日: 2016.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ里山しか行かない自分に遭難なんて縁がないと思っていたが、結構自分にも思い当たるキッカケで遭難してるので震え上がった。
0投稿日: 2016.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ山で遭難そしてそこから救助されるまでの7話。 本編前の「はじめに」から、ひきこまれた。 どれも強烈な印象で 映画やドラマのような話なのだけど 全て現実で起こったこと。本当にこわい。 ラストの大山は衝撃的。 大山といえば小学校の登山遠足で行った場所。登山慣れしてる人でもそんな低山で....気の緩みってこわいな。 装備も含めいろいろ考えさせられる一冊。このシリーズは他にも読んでみようと思いました。
0投稿日: 2016.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ厳しい遭難を生き抜いた、普通の登山者8組の話である。 ヒマラヤの凄絶な遭難は高度な技術を持った登山家の遭難である。一方で、穂高や燕岳のような一般人の行く山での遭難、それは、山に対する立場や姿勢の違う遭難者からすれば、ヒマラヤに匹敵する壮絶な状況だろうと著者は語る。 ここに出てくる登山者は本当に僅かな油断から一般ルートを外れ、道に迷う。ちょっとゆっくりしようという気持ちから1時間休んだら悪天候で帰れなくなってしまう。 「ちょっとおかしい」と思いつつ、それでも引き返せない、その状況が実際の遭難者へのインタビューをもとに構成され、いかにももどかしい思いにとらわれる。 福島は飯森山に登った一條氏は、普段は12時には山頂に着かなくても引き返す、という自分のルールを決めていた。ところが、山頂から降りてきた夫婦に「あとちょっとですよ。(別な)沢コースをたどったら」と薦められると、普段持ち込んでいるビールの酔いも手伝ってか、山頂へ向けて出発。山頂には着くが、帰りに行ったことのない「沢コース」へと下り、3日間彷徨することになる。 幸いにも、我々は本書で紹介されている皆が助かることを「知っている」。だから、大丈夫と信じて読み進めることができるのだが、舞台となる山も、その遭難の仕方もいかにも自分がしてもおかしくないと思えることが手伝って、感情移入が容易にできる。それだけ身につまされ、どうやって生き抜いたのだとそれを不思議に思う。 最後に著者は、8つのケースから教訓を記す。 登山計画を出し、遭難しても必ず救助が来ると信じて待つこと。やみくもに動きまわらないこと。 最低限の装備を持つこと。特にツェルトと火(マッチ)とストーブ。 8つのケースは全てほんの少しの油断から遭難した。だが、最初のビバークをする時点で落ち着きを取り戻し、ここで待とうと腹を決め、救助を信じて待った人たちばかりである。 いざというとき、思い出すべきは本書である。
0投稿日: 2015.01.208つのストーリー
山岳事故、遭難から生還した人たちの8つのストーリーを紹介。遭難事故の取材をしている著者が取材の中でわかった事柄をまとめたお話になっています。遭難するきっかけはどれもたいしたことではなく「うっかり」「思い込み」などの小さな出来事からで、その後の気づきがなかったせいで大きな事故になっていく様子がわかります。 丹沢などの低山でも簡単に遭難することがあり、読んでいてぞっとするところも。たくさんの教訓をいただきました。
1投稿日: 2014.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ登山と遭難は残念ながら関係が深い。本書は山岳遭難しながらも生還や救助に至った8例を紹介し、遭難の原因と、生還できた理由について考察している。遭難の理由は様々だが、生還には幸運と、「必ず生きて帰る」という本人の強い意志が必要だったことが印象的。 冬の北アルプスから丹沢のハイキングまで紹介されている。また、大峰の釈迦ヶ岳のように、かつて自分が辿ったルートと同じものがあった。遭難は必ずしも難しい山だけで起こるわけではないことを実感した。これを読んで、さっそく位置通報用のホイッスルを購入した。
0投稿日: 2014.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ過去山に入って一度だけ道を見失ったことがある。北八ヶ岳白駒池からニュウに至る原生林の中、少しトレールをはずれ目標を見失った。本書の中の遭難事例も少しの差異で、普段であれば安全が確保されるはずの山行が遭難につながった。東京近郊の丹沢山系での遭難なんてと安易に考えず、山歩きのリスク回避の重要性を改めて感じた。
1投稿日: 2013.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ趣味で山を登る人なら必ず読んだ方が良い一冊。ごく普通の人々が本当にちょっとした事から遭難してしまい、そして生還するまでを克明に聞き取りしまとめたドキュメンタリー。丹沢へのハイキングから冬の槍ヶ岳まで8つの事例がありますがどれも本当に誰にでもありがちなパターンからの遭難で、だからこそ身につまされます。またどうして生きて帰って来れたのかという事も克明に書かれており、遭難したと認識した後に冷静に対処する事がどれほど重要か、ということも含めとても示唆に富む1冊でした。
1投稿日: 2012.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ無謀や無茶でなくても遭難する。 ハードな冬山や海外遠征でなくても。 普通の人が人生の楽しみとして行く範囲でも。 そこそこ経験があって、慎重に山に臨んでも。 普通迷うことがないコースでも。 生還の事例から装備や心の準備をすることはできる。 帰ってこれなかった人の話は聞けないのだなぁ…
1投稿日: 2012.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
山での遭難事故のドキュメント。 最近山に興味を持ったばかりなので、 遭難というものがどんなのか。 遭難してしまうということが、 山で死と向き合うことの怖さが、 少しはわかったような気がします。 自分の事のように緊張感を持ちながら一気に読めました。
0投稿日: 2012.03.26
