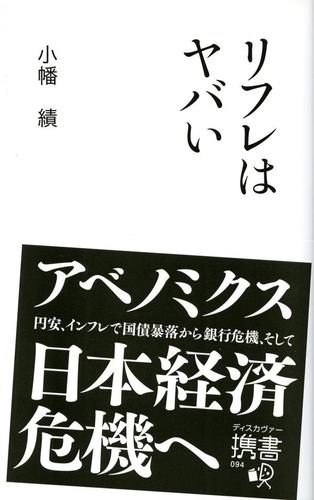
総合評価
(54件)| 5 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 6 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ「リフレはヤバい」 https://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51841652.html
0投稿日: 2025.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログアベノミクス批判の先鋒として、期待して読んだ。しかし、この本を悪魔の代弁者として考えるならば、やはりアベノミクスは妥当ということになってしまいそうだ。 結局のところ、この本では、これからは、ストックの時代であり、通貨高を維持して、資産運用で儲けましょうということで、資産を持たないものには厳しい世の中になりそうだ。 リフレに代わる解決策は学校を充実させるとのことであるが、これまでの学校との違いはよくわからなかった。 以下 ?なポイント ・インフレ率1%を目途とする。 ・景気が良くならないと需要は増えないので、インフレは起こらない。 ・インフレにするためには、景気がよくならなければいけない。 ・良いインフレ、悪いインフレ ・企業が 便乗値上げをするのはありない。 ・リフレを主張するのはほとんど男性。 ・今は、大きな貿易赤字を抱えている。 ・物価は最初に下落しない。需要不足で下落する。 ・景気が悪いので、需要が弱く、価格が下落する。から、デフレスパイラルは存在しない。 ・日銀はわざとデフレにしているわけではない。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ5年前に書かれた本で、その時点ならもうちょっと良い点が付いたんだろうけどね。 全く当たっておらんからなぁ・・・
0投稿日: 2018.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2013年刊行。反リフレ派の書。リフレ派も反リフレ派も需要の亢進を目的としている点では同じように思う(勿論、方法論はまるで違うが)。ただ、国債の価格下落に伴う銀行資産の毀損とドル資産調達確保に対するリフレ派の甘い見通しには呆れていたが、この点は明快に指摘。また、円安による景気回復は限定的(全体としては+と-があり、原材料費の高騰が景気回復の阻害可能性が高い。円安が日本全体の景気回復に、とは70年代迄)というのもその通り。とはいえ、需要の創出方法に関する本書の解説もまた稚拙である点は如何ともしがたい。 リフレ派の需要増・雇用増・所得増に対する現実感のなさはどうしようもないが、かといって、実学教育重視・拡張という帰結しか持ち出せない本書もまた?を付けてしまう(ただし、長期的に必要な施策であることは否定しないが、これはリフレ派も同様ではないか)。
0投稿日: 2017.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログリフレがヤバいことは感覚的に理解できる。アベノミクスも持続的な成長路線に乗せられなかったし、日銀のインフレ目標も事実上棚上げだ。インフレ状態にする唯一現実的なシナリオが円安とのことだが、為替相場は金融市場と米国の意向で決まるので実質的に日銀が操作できないこと、これ以外に人為的にインフレを起こすにはヘリコプターマネー以外に手段がないこと、仮にそれらの結果としてインフレになったとしても国民にとって何の利益もないことは良くわかった。マクロとミクロのバランスが取れていて非常に説得力がある。 ただいくつか理解できない点がある。 まず国債の暴落は円安が起点になるとのことだが、リフレで継続的に円安に誘導することはできないのではなかったか?そもそも日本国債の保有者は国内の機関投資家なのに為替変動で投げ売りが起こるのか?そんなことよりも財政破綻の方がずっと暴落のリスクが高いだろう。 また国債の暴落=長期金利の上昇が起こる場合、それはインフレ状態と同義ではないのか?物価が全く上がらず金利だけ上がることはありうるのか?一方でインフレは起こせないと言い、他方でインフレの懸念を主張しているように見える。 最後に円安で日本が滅ぶと言うのは極論を前提としていてナンセンスだ。もちろん制御不能な状態でどこまでも円が落ちていけばそうなるが、円が実力以上に過大評価されるのは国際競争力上明らかにマイナスだ。海外の企業を買いまくってグローバル経営を目指すのは結構なことだが、それは日本人の雇用を奪い、国内投資を縮小させる。いくら職業専門校を作ろうが、卒業生を雇う経営者は国内にはいなくなる。この辺りの認識が著者は甘いと言わざるを得ない。
0投稿日: 2016.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログリフレ政策反対。著者の意見を読むと全て悪い政策になる。一方の意見のみを読むと意見が凝り固まる。他方の意見も読むとちょうどいいかも。 経済素人からすると円安時のお金の流れが見えていいと思います。 リフレ政策は円安➡️オイル、食料品の高騰➡️給料上がるが狙いだが、給料上がらないため、無理。
0投稿日: 2016.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログリフレ政策の危険性がわかりやすく書かれていた。 実際に市場に関わっている人には、当然のこと。 リフレ派の人に読んでほしい。
0投稿日: 2016.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログまあ、こういう経済系の本はとんと読まないのですけれども、最近こういった分野に興味が出始めた自分を自覚し、読んでみたわけなんですけれども…まあ、これは著者の主張・言い分ですよね、ということを了解して読んだ方がいいかと存じます…社畜死ね!! ヽ(・ω・)/ズコー もっと有用な政策が他にあるのかもしれませんしね…ただまあ、安倍ちゃんが今やっている政策は即止めるべし! みたいな主張には僕も賛同の意を示すというか…どうしてもこういう主張系の本を読んでいますと著者が正しいように感じてしまいますね…社畜死ね!! ヽ(・ω・)/ズコー それと安倍ちゃんってアレですかね、経済の知識とかないんかなー? とか思うんですけれども、総理大臣も実は経済とかの知識とか皆無に近くて、何かしらの経済処置をする場合ってアレですかね、専門家とかに話聴くんでしょうか… そこら辺の関係がよく分からないんですけれどもまあ、景気なんちゅーものはそう簡単に良くはならないし、この本を読んでいると今後、日本が経済的に成長することもなさそう…さて、どうする!? というところで物語は終わります…(!) さようなら…。 ヽ(・ω・)/ズコー
0投稿日: 2015.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体的には面白く読んだ。特に第8章の「円安戦略はもう古い」で「真のグローバル日本企業になるためには、思考はドルでなさなければなりません。円で考えていると、単なる地元にこだわった、井の中の蛙になってしまうのです」という指摘はもっともだと思う。円安は株高につながって、株価の時価総額は上がっているが、さらに円安が進めば、企業価値や資産価値は目減りしていく。 面白かったのは「タコ紐理論」。インフレは凧と同じで高く揚がった時(インフレが進んだ時)は紐を引いて制御できるが、風がなければ、凧は揚がらない。つまりインフレは起きない。金融緩和で起きるのは輸入インフレだけだそうだ。 それではデフレ脱却にはどうすればいいのかという議論がこの本では物足りない。「おわりに リフレではなく何をするか?」にある数ページの提案は即効力に欠け、説得力も足りない。著者も認めているようにインフレを起こすには賃金を上げる政策が有効なのだから、どうすれば賃金を上げられるかを具体的に提案してほしいものだ。
0投稿日: 2014.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログリフレ政策による目先の円安、株高に浮かれる人々に対する警鐘と、安倍首相が、名目金利上昇のリスクに気づき、リフレ政策を修正することを望むという反リフレ派小幡績氏のリフレ批判本。 著者同様、本書の予言が実現せず、小幡氏の言うことは当たらなかったというシナリオが実現することを願うが、円安・インフレ妄信ムードの化けの皮がもうじき剥がれそうな予感が怖い。
0投稿日: 2014.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しかった。アベノミクスが目指す、意図的なデフレがどこまで劇薬なのか、判ったような判らなかったような。日銀と政権の駆け引きのところは、面白かった。
0投稿日: 2014.01.30安倍内閣が発足して1年。アベノミクスのリフレ政策を批判している小幡氏の主張はこうだ。
リフレは国債を暴落させる。 まず金融緩和で円安が進み、ドル建てで見た場合に日本国債の価値が低下する。次に今後も円安が進むと言うコンセンサスができると合理的な判断としては日本国債を売って米国債を買う。円売りドル買いなのでさらに円安が進むと言うのが解説だ。ちなみに財政破綻が原因での国債暴落は短期的には起こらないと見ていて、ヘッジファンドの売り浴びせは割安になって買い向かう国内投資家がいるために失敗してきたらしい。 現時点では円は100円近辺で安定しており、長期金利も底辺に張り付いておりすぐに暴落という状態では無さそうだ。 インフレは望ましくない。 デフレスパイラルがあるのならインフレ期待がじつげんするのもあり得るよな、しかしスタグフレーションがあると言うことは景気の循環とインフレデフレの関係はどうなってるんだろうとか考えながら読んでた所でデフレスパイラルは存在しないと来た。デフレの原因は需要不足であり景気が悪いから物価が下がると。通常のデフレスパイラルの説明は企業の業績が下がり、給与が下がるため可処分所得が減り需要がさらに下がる。小幡氏はデフレスパイラルはないと言うが別の所で円安は雇用維持の効果は有ると書いているように企業の業績と雇用の関係は当然あるだろう。デフレスパイラルがないと言うにはちょっと説明が足りてない気がする。 そもそもインフレは起こせない。 金融緩和で起こるのは資産インフレと円安だというのは間違ってなさそうだ。資産効果でじわじわと需要が増えると言う人もいるが、2%のインフレは需要が増えないと無理なのでは。一方円安のためにエネルギー価格などのコストプッシュのインフレは起こるがこれは誰も喜ばない。 現状どうなってるかと言うと、10月の速報でコアCPI,コアコアCPIともにようやく前年同月比プラスになったとニュースになってたが2010年比ではコアCPI100.7に対しコアコアは98.8。ようやく下げ止まったというところだ。しかもエネルギー価格はちゃんと上昇している。まだ1年なので評価には早いかもしれないが景気が回復したと言うにはほど遠い。白物家電が売れだしたと言うデーターもあったが駆け込み需要ならあまり景気回復には関係がない。 と言うことで今のところアベノミクスの成果は株価が昨年末の1万円近辺から5割アップ。為替が80円から100円に上がったが国債は安定。輸出企業の業績は回復し一方でエネルギー価格は上昇。10月の完全失業率は4.0%で有効求人倍率は0.98倍と雇用はやや回復。所得が増えるかどうかはまだまだこれからで評価には早いと。 小幡氏の主張で面白いなと思ったのはこれから人口が減るとフローが小さくなるのは避けられないがストックは減らない。貿易黒字でフローが大きい時代には円安メリットがあったが、ストックが大きい時代にはドル建てで見れば円高の方が得と言う見方。国内需要が増えなければ金は余っても設備投資は海外に向かう。ドル建てで見れば金持ちになってるんだから。まあそう言う見方もあるでしょう。
0投稿日: 2014.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ第二次安倍内閣が発足してそろそろ一年。アベノミクスのリフレ政策を批判している小幡氏の主張はこうだ。 リフレは国債を暴落させる。 まず金融緩和で円安が進み、ドル建てで見た場合に日本国債の価値が低下する。次に今後も円安が進むと言うコンセンサスができると合理的な判断としては日本国債を売って米国債を買う。円売りドル買いなのでさらに円安が進むと言うのが解説だ。ちなみに財政破綻が原因での国債暴落は短期的には起こらないと見ていて、ヘッジファンドの売り浴びせは割安になって買い向かう国内投資家がいるために失敗してきたらしい。 現時点では円は100円近辺で安定しており、長期金利も底辺に張り付いておりすぐに暴落という状態では無さそうだ。 インフレは望ましくない。 デフレスパイラルがあるのならインフレ期待がじつげんするのもあり得るよな、しかしスタグフレーションがあると言うことは景気の循環とインフレデフレの関係はどうなってるんだろうとか考えながら読んでた所でデフレスパイラルは存在しないと来た。デフレの原因は需要不足であり景気が悪いから物価が下がると。通常のデフレスパイラルの説明は企業の業績が下がり、給与が下がるため可処分所得が減り需要がさらに下がる。小幡氏はデフレスパイラルはないと言うが別の所で円安は雇用維持の効果は有ると書いているように企業の業績と雇用の関係は当然あるだろう。デフレスパイラルがないと言うにはちょっと説明が足りてない気がする。 そもそもインフレは起こせない。 金融緩和で起こるのは資産インフレと円安だというのは間違ってなさそうだ。資産効果でじわじわと需要が増えると言う人もいるが、2%のインフレは需要が増えないと無理なのでは。一方円安のためにエネルギー価格などのコストプッシュのインフレは起こるがこれは誰も喜ばない。 現状どうなってるかと言うと、10月の速報でコアCPI,コアコアCPIともにようやく前年同月比プラスになったとニュースになってたが2010年比ではコアCPI100.7に対しコアコアは98.8。ようやく下げ止まったというところだ。しかもエネルギー価格はちゃんと上昇している。まだ1年なので評価には早いかもしれないが景気が回復したと言うにはほど遠い。白物家電が売れだしたと言うデーターもあったが駆け込み需要ならあまり景気回復には関係がない。 と言うことで今のところアベノミクスの成果は株価が昨年末の1万円近辺から5割アップ。為替が80円から100円に上がったが国債は安定。輸出企業の業績は回復し一方でエネルギー価格は上昇。10月の完全失業率は4.0%で有効求人倍率は0.98倍と雇用はやや回復。所得が増えるかどうかはまだまだこれからで評価には早いと。 小幡氏の主張で面白いなと思ったのはこれから人口が減るとフローが小さくなるのは避けられないがストックは減らない。貿易黒字でフローが大きい時代には円安メリットがあったが、ストックが大きい時代にはドル建てで見れば円高の方が得と言う見方。国内需要が増えなければ金は余っても設備投資は海外に向かう。ドル建てで見れば金持ちになってるんだから。まあそう言う見方もあるでしょう。
0投稿日: 2013.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル通りの反リフレ政策の本。 インフレ期待を基にした論理のいい加減さ、円安インフレの懸念というか円安以外にインフレ要素が無いことの論証、需要の先食い=バブル、英国のインフレターゲット政策の内実などを一般読者にも分かりやすく解説してくれています。 とは言い条ラッファー曲線だって有意義だったと言われてしまう政治の世界ですし、著者の云うようなリフレの悪影響が出る頃には関係者は退陣しているでしょうから、正しさはあまり意味ないのかなと。 最終章の日本の国際企業がドル建てで動かないから円高で苦しむんだと云うのは暴論。日本人の給料は円建てで払われるのであって、国際競争力の源である「開発力」は円建てなのだから、目に見える事象の海外生産がどうのこうの何て本質じゃ無いんですよ。
0投稿日: 2013.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ今さら感もあるのだが、読みかけだったので、この度読了。 普段からマクロ経済をウォッチしているわけでもないので、 ひとまず本書の内容は、 「まぁ、こういうシナリオも考えられるのだろう。」 という受け止め方をしておきたい。 全体的に筆者の考え方が断定的なトーンで語られており、 ものを知る人であれば、もっと違う評価もありそうだ。 いずれにせよ、リフレに関するシナリオがどうなるかは、まだなんとも言えない状況だろう。 今後の動向を見るにつけての参考にしたい。 筆者の考え方と、筆者の考えるリフレ派の考え方には、 根本的に「成長」に関する見方の違いがあるように思える。 筆者は日本を成熟社会として、 ダイナミックな成長は期待していない。 一方、リフレ派の人々は、所謂「経済のダイナミズム」的なものを信じていて、 日本もまだまだ成長できると考えているようである。 理論的にどっちが正しいとは判断できないけれども、 主観的にはリフレ派の主張はバブリーな感じがして、「古い」という印象を持つ。 そこは筆者に共感するところだ。 バルブを経験しなかった私の感覚からすると、 「成長」を声高に唱える人たちは、 どこか過去を引きずっているように思えてしまう。 リフレ派の人々は、 世の中に出回る金を増やした結果、 どういう経緯で何が良くなるのか、 具体的に説明してもらわないと、 よくわからない、 というのが、私も含めたバルブ後の世代の感覚ではないだろうか。
0投稿日: 2013.11.08リフレ政策がもたらす国債の下落と円安への警鐘
本書は、リフレ政策がもたらす円安と国債の下落への警鐘の書です。 2012年に発足した安倍内閣が掲げる経済政策「アベノミクス」。 これで広く知れ渡ったのが「リフレ」です。 小幡氏のリフレの定義は明快です。 『リフレとは、意図的にインフレーションを起こすことです』 日銀総裁が金融政策の目標として2%のインフレを掲げているように、リフレはまさしくこの定義の通りです。 そのリフレがなぜヤバいのか? それは、円安が国債の暴落をもたらし、銀行危機、そして実体経済危機につながる可能性があるからです。 円安から国債の暴落への考えられるシナリオは以下の通りです。 円安がもたらすドルベースでの国債価格の下落が国債の売りにつながり、売って得た円でドルを買うためさらに円安になり、そのためさらに国債が下落する、というように 『円と日本国債の暴落スパイラルが始まります』 そして、国債が暴落すると、国債を保有する金融機関の含み損が増え、それが金融危機につながり、更に実体経済の危機につながる可能性があります。 危機の具体的事例として、1997年の円安と日本の金融危機を例に説明されています。 さて、アベノミクスが始まって1年。 事実として、円安は進みましたが、幸いなことに国債の下落にはつながっていないです。 『円安で注意しなければならないのは、国債価格の下落、すなわち、名目金利の上昇なのです。逆に言えば、これさえ起きなければ、リフレ政策でも何でもやってかまわないと言ってもいいくらいです』 と小幡氏が語るように、今は結果オーライなのでしょう。 しかし、今後、さらに円安が進んだ時には、国債価格の下落には要注意なのかもしれません。 最後に、一言。 「ヤバい」、「暴落」、「危機」という言葉のイメージとは裏腹に、本書の内容はいたずらに不安をあおるようなトーンではなく、経済学と歴史的事実をもとに冷静に論を進めており、また、円安に頼らない日本のとるべき戦略なども語られており、参考になります。
0投稿日: 2013.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ政権がかわり、株安、円安が進んできた。 以前よりは、日本の経済が元気になってきた。 多くの人と同じように、自分でも、漠然とそんなふうに感じています。 ではどのようにして変わったのか?と聞かれると「物価上昇のターゲットを決めていること」「円安を誘導していること」といったことぐらいしか答えられません。 そしてこれらの施策がどのように、景気回復につながっているのかは、正直よく理解出来ていません。 なので、関連する書籍を読んで、勉強してみようと思い立ちました。 この本はその、物価上昇を画策して景気を良くしようとする「リフレ政策」が”間違っている”と主張している本です。 冒頭でまず、リフレ政策とはどんな政策なのかを解説した上で、円安の解説、そして現在のリフレ政策の誤りの指摘へと、話が進んでいきます。 僕は特に、リフレ政策と円安について理解したかったので、前半部分の記述が参考になりました。 そしてなぜ、国債の動向に注目が集まるのか、また中央銀行のそもそもの役割など、経済の基本について、学ばせていただきました。 著者が主張する「フローからストック」への考えなどは、賛否がありそうですが、今後の日本経済の将来を考えるきっかけを与えてくれた、一冊でした。
0投稿日: 2013.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログリフレが「ヤバい」の押しつけなので、読んでいてあまり感じが良くはありませんでした。出版社「ディスカヴァー・トゥエンティワン」は大好きなのですが、これはちょっとお行儀の悪い1冊だったかな、と。 国民である私たちは、現政権の政策判断に賛成できるか否かを常に注視しなければなりません。そのために、「反リフレ派の意見はこういうものだ」と知るには適した書かもしれません。 「視点を変える 明日を変える」というディスカヴァー携書。確かに視点が変わったのは、景気後退と不況を一緒にしてはいけないという点です。景気は循環するもので、景気の後退は循環の中で必ず起こりうるもの(それがなければ上昇もない)だと認めるべきだということに気づかされました。 これに関連して、これまでの景気後退時の多くはデフレ経済とタイミングが一致していたので、「デフレが景気を悪くする」と必然的に私たちが思ってしまっている点が問題だと指摘しているところは、うなづけました。 因果関係が逆で、「デフレだから景気が悪い」のではなくて「景気が悪いからデフレなのだ」という点、これは、大事な見方だと思います。 よって、逆に「インフレになったので景気が良い」と決めつけてもいけないわけで、今後、統計的に物価上昇が見られた時に、「景気が良くなった」と結論付けてはいけないということです。 物価は経済活動の結果の1つとして数値(価格)で示されるもの。それを誘導していては、本来の経済力との間に歪みが生じる、それも理解できます。しかし、短期的に、刺激を与えるためのインフレ目標は、道具としてあってもいいのかな、と私は思いました。 反リフレ派の、ちょっと乱暴な本書を読んだからこそ、上記のような考えがまとまったのです。そういう意味では、逆説的ですが有意義な読書だったのかもしれません(笑)。
0投稿日: 2013.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ安倍政権が発足し、リフレ派が勢いをつける中、反リフレ派の主張はどうなのか興味があり、読んでみましたが、内容は徹底して、何が何でも反リフレ。 リフレによる円安の進行が、結果的に国債の暴落を招き、日本経済が再起不能に陥るといったシナリオについて解説しているが、結局のところ、リフレ憎しで叩いているだけではないのだろうか。 議論が表層的で、具体性や説得する根拠に欠け、理屈?だけの反リフレに終わっている。 安倍政権の発足直前から円安傾向になり、その後経済指数も上向きになるなど、安倍政権としてラッキーな面はあるが、現在(2013.10)の処、結果としてリフレ派の主張が正しそうに見えるだけに、もっと説得力のある展開をして欲しかった。
0投稿日: 2013.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ安倍政権が進めるリフレ。その危険性を論じる内容。 特に円安について、多くその頁が割かれている。 日銀悪論に真っ向から反対する本書。 感じるのは、これら両極端に位置する意見のどちらも聞き、 自分なりの正しい解を導き出すことではなかろうか。 本書にもあるが、国内だけに目を向けている施策の限界は自分も感じる。 もっと海外に目を向けた発想をすれば、自ずと施策の内容も変わってくるように感じる。 色々な著者の意見を読む必要性を感じる本。
0投稿日: 2013.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今一つまとまらない印象の本。 需要が少なくなってしまっている今の日本では、輸入資材の高騰によるインフレしかおこり得ないが、発展途上国とは違い、既に海外・国内ともにストックの多い国である日本では、通貨安競争は国富の毀損をまねくだけ、というのが主な論。 「日本だけがこういうことをしているのは間違い」という論調が非常に目立つのだが、日本だけがこんなにデフレなのでは?
0投稿日: 2013.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログアベノミクスでリフレ政策が進められているのに対して、真っ向から反対を述べているので、どういうことを言っているのかと思って読んでみました。全体の主張はだいたいわかりましたが(正しいのかどうかはわかりません)、論理的飛躍を感じる部分も見られ、AだからBだと言われても素直に同意できない部分もありました。私自身がこの本を読んだ上でリフレはだめかと聞かれても、読んでもやっぱり良いのか悪いのかはわからないというのが正直なところです。
0投稿日: 2013.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログアベノミクスは、リフレ経済だと言われるがその理論的な誤解などをわかりやすく説明した本。 リフレ批判としてはわかりやすいが、経済学は政策が正しいというよりも、結果がすべてだと思うのでその意味ではリフレ派の本も読んでみたいと思った。また、リフレが世界経済では異端的な立場であることはわかったのがよかったと思う。 できれば、リフレを批判するだけではなく、最終章には少し触れているが、リフレの代わりの政策を提言できるとよいかなと思った。
0投稿日: 2013.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログアヘン壺三がユダ金の命令で行っている日本経済破壊作戦が如何にキチガイなものか、よく分かる。この先生、竹中と同じ慶応の学者なのに、なかなかだな。
0投稿日: 2013.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
(要約) 「はじめに」で、小幡はリフレとはインフレをわざと起こすことであるという定義を示し、リフレは誤った政策だと主張する。リフレは国債を暴落させ、日本経済が崩壊するおそれがあるからである。 「第0章 リフレ政策とは何か?」では、リフレは謎の政策であり、なぜインフレを起こさないといけないのかよく分からないと疑問を呈する。小幡は現在進められているリフレ政策を4つの点から説明している。1)中央銀行に政策目標として具体的なインフレ率を設定させるインフレターゲット、2)日銀が国債を買い入れ、通貨を供給するマネーの大量供給、3)「期待」に働きかけること(ただ、インフレ期待は金利と資産価格には反映されるが、モノの値段には反映されないため、インフレは起きないと小幡は見ている)、4)国会又は政府の誰かに役員の解任権を持たせることを主張する日銀法改正、である。 「第一章 そのとき、日本経済に何が起こるか?」では、モノの値段は上がっても、給料は上がらないとの見方を発展させる。売り手が商品の値上げをするのは、1)コストが上がるとき(コスト・プッシュインフレ)か、2)値上げをしても売れるほど需要があるとき(デマンド・プルインフレ)、のどちらかであり、景気を良くするためにインフレを起こすのは無理であり、因果関係が逆だ。そのため、インフレは起こせないと主張する。人件費が上がらなければサービスは値上がりしない可能性があり、そうなれば、物価は上がるが景気は悪くなるというスタグフレーションとなる。インフレには良いインフレと悪いインフレがあり、コスト・プッシュ型は悪いインフレであり、デマンド・プル型はよいインフレだ。日本のインフレは円安・輸入インフレであり、円安による輸入コスト上昇分だけインフレが起こることになる。だが、円安になっても、賃金上昇・企業の大幅値上げにつながらないと思われるため、かつてのような大幅インフレはやっぱり起きない。 「第二章 円安はどのようにして起きるのか?」では、円高のほうが経済全体では、はるかに得だとの見方を示す。小幡は、円安のケーススタディとして、九五─九八年の円安を検証し、前半は為替介入の成果だが、後半は金融危機によるものだと説明。二〇〇〇年からの円安と二〇〇五年からの円安を比べてみると、最初の円安は経済悪化による円安であり、二番目の円安は経済回復時の円安であり、円安には良い円安と悪い円安がある。 「第三章 円安で日本は滅ぶ ─ 円安で金融市場と日本経済は?」では、円安による国債下落の危機について説明している。国債は、1)流動性が高いこと、2)国の信用力の評価をみんなが知っているという評価のコンセンサスがあること、3)固定利回りであることから、機関投資家が安心して投資できる対象であるとし、一方、国債に投資するリスクとしては、まずデフォルトリスクがあるが、より重要なリスクとして国債の値下がりリスクがある。円安になればドルベースでの値下がりリスクがある。だが、為替予約があるではないかという反論がありうるが、ヘッジコストもバカにならないし、円ベースでも値下がりすることは避けられない。では、国債を満期まで保有すればよいのではということになるが、小幡は、金融機関は有価証券を時価評価しなければならず、時価会計により、トータルで100兆円の資産減になると試算する。円安から銀行危機、そして実体経済危機へという流れが予想されるのだという。 「第四章 リフレ派の二つの誤り その 1 インフレは望ましくない」では、リフレ派が主張するインフレの六つのメリットを説明したうえで、デフレは継続的な物価の下落であり、デフレと不況は別であると説明。インフレの六つのメリットは存在しないと主張する。クルーグマンの主張には、1)賃金はインフレに完全に連動して上がり続ける、2)消費者は十二分な資産・所得があるという前提があるが、日本においては、これが成り立っておらず、クルーグマンは間違っていると主張する。例えば、近年の総合電機メーカーの大赤字はテレビ事業の大赤字によるもので、駆け込み需要のせいであり、エコポイントは最高の反面教師だ。物価が下がることと、個別企業の価格付けは別の話で、企業は自分で価格を決める。不況の継続を止めたいのであれば、所得を増やして需要を増やす以外に方法はない。だからデフレスパイラルは存在しないのだ。 「第五章 リフレ派の二つの誤り その 2 やはりインフレは起きない」では、リフレ派は、起きるはずのないインフレを起こそうとしていると批判する。中央銀行制度はインフレが起きないようにするために作られたものであり、だから中央銀行の独立性が確立した。リフレ派は、インフレを起こすことは簡単だと主張する。そして、今回の日銀法の改正の意図は日銀の独立性を奪うことだと批判する。リフレ派の人々は簡単にインフレになると思っているが、金融政策のタコヒモ理論というものがあり、引っ張って抑制はできるが、押して凧を動かすことはできない。つまり、インフレを抑えることはできるが、デフレ解消は難しい。インフレが起きるかどうかは需要が強いかどうかにかかっており、需要の強さは所得に応じる。所得増なくしてインフレなしである。 「第六章 それでもリフレを主張するリフレ派の謎 ─ なぜ、かれらはインフレが好きなのか?」では、インフレでいいことが何もないのになぜインフレが好きな人が多いのかについて考察する。まず、政治家たちは日銀批判をすれば目新しく、盛り上がる。金融市場関係者たちは金融資産が上がるからリフレを歓迎する。しかし、お金が金融資産市場にしか回らず、株価上昇では経済はよくならない。また、企業経営者が円安を喜ぶかどうかは人による。エコノミストと経済学者でリフレを支持している人は、現実を分かっておらず、見ようともしていないからであり、机上の議論が好きだからである。リフレ派は無責任な議論をして喜んでいるだけである。 「第七章 リフレ派の理論的な誤り」では、リフレを理論面で批判する。まず、バーナンキがインフレを望んいるとする見解が誤りであることを説明する。日欧米の中央銀行は同じ価値観だというのである。ただ、資産価値の維持と為替が重要なイギリスは例外である。今は成長力自体が落ちており、おカネがぐるぐる回れば景気はよくなるという考え方は根本的に誤っている。 「第八章 円安戦略はもう古い」では、まず、自国の国富を守るためには自国通貨の値下がりは最も避けなければいけないことだと説く。低成長時代を迎え、日本はフローからストックの時代へ入った。通貨を安くして韓国と競争するという発想自体が時代遅れだ。円安戦略では、日本は勝てない。真のグローバル日本企業となるためには、思考はドルでなされなければならない。 「おわりに」では、小幡はリフレ政策ではなく、雇用創出政策と採るべきだと提案する。そのためには教育を充実させるべきだと結ぶ。 (コメント) 「円安は、それ自体が国債価格の暴落を意味します」(116頁)の理屈がよくわからない。円安になると確かにドルベースでの国債価格は下落するが、それがどれほどの日本国債の売り圧力になるのだろうか。資金循環統計からは少なくとも海外部門が巨大な売り圧力になるほどの日本国債を保有しているとは読み取れない。
1投稿日: 2013.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかく、リフレを否定しまくる本。そして、ツッコミどころが多い本。経済に対して専門知識は持ってないが、言ってる事がおかしい。どうも反リフレ派の主張って、わかりにくい気がする。でも、著者によると、リフレ派の論理は分かりやすい、だから間違っているとないる。なんで? デフレスパイラルなど無いとか、インフレは起こせないとか、円高の方が良いとか。ウーン、そうですか? そもそも、全てをドルで考えれば円高の方が良い主張してますが、社員への給与もドルで払うんでしょうか? 最後に、リフレへの代案としての提言が雇用だと。雇用が増えれば景気が良くなるって、みんな知ってる。企業が雇用をするための資金はどうするのか。 リフレ派の主張の方が首尾一貫していて、納得しやすいのは、騙されてるからなんでしょうか。とてもそうは思えないが。
0投稿日: 2013.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は2013年4月から仕事の事情で(一般教養程度の)経済の勉強を始め、おりからのアベノミクスに乗って俄かに経済政策に興味を持った。どうせ何をやってもダメな日本経済なのだから、何かやってみるのが面白いという発想でリフレ政策を見ていた。 この本では、ひたすら文章でリフレ派の理論を否定している。風が吹けば桶屋が儲かる式の三段論法で、たとえば ・金融緩和 → 円安 → 日本国債の価値が下落 ・円安 → 輸入価格上昇、しかし賃金は増えない → 物価が上がっても景気は悪い 等が挙げられている。 正直、この本に書かれている数々の論理は「そうかなあ?」と腑に落ちないものが多々あった。しかし、反証できるほどの論理力や知識はこちらには無い。 今まさに金融政策を動かしている人も、それを批判する人も、完全な答えが無いから論争になっている。 アベノミクスが始まった今では1年先の経済がどうなっているか分からないし、1年後の経済が良かったとしても、その影響を受ける10年後の経済が良いとは限らない。リフレ政策が正しいかどうかは、時系列で異なると思う。 論理は腑に落ちないけれどざっと読み終えてしまおうとページをめくり、手が止まったのは「おわりに」であった。 リフレに反対するのはいいが、ではこの閉塞を打開する策は何なのか?その答えを、著者は「おわりに」で説明する。 答えは、「学び」である。いくら金融政策をいじっても実体の成長がなければ失敗するのなら、産業の基礎力を上げるために人的資本の価値を上げればよい。 この意見には賛成だ。私がかねがねそう考えていたことを思い出した。 さらに私は加えたい。教育は産業の基礎力を上げるだけでなく、人々に希望をもたらす。子供だけでなく、あらゆる年齢、職業、立場のための教育だ。 人は、今現在お金がなくても、学習を続けた先に収入のあてがあるとなれば未来に希望が持てる。 例えば、リーマンショックで大量の失業者が出たとき、どこかの市役所が期限付きの臨時職員を募集したが、応募者は定員に満たなかった。それは、期限が来たらまた無職になるという不安からだったと思う。 しかしそこに、何かが学べて将来につながる要素があれば、たとえ有期でも応募者は多かったのではないかと考えている。 私の考える教育の方向性は、そのようなものだ。 ただ、結局のところどのような教育が効果的なのか未知数だし、そりゃ学びの場がうまく回れば産業も社会も良くなるでしょうよ、で具体的にどうするの?という部分が詰められていなければ、リフレが希望的観測に基づいていて具体的な部分が抜けていると批判するのと同様に、「学び」の立国論も批判され得る。 それでもなお、私は「学び」の方向に希望を見出している。 はからずも最後の最後で自分の奥底に沈んでいた意見に出会い、ずいぶん長いレビューを書いた次第である。
0投稿日: 2013.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログそもそも、景気が良くなるからインフレになるのに、無理やりインフレを起こすのは順番が逆である、また無理やり円安に持っていくのも日本経済にとって全く良い事ではない、という主張。妄信的にリフレに賛成している人は、自分のメリットだけではなく、全体のことも考えよう。
0投稿日: 2013.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログまず本のタイトルにある[リフレ]とは 『インフレを起こす、ということです。 インフレとは、多くのモノの値段が上がるということです。』P.18 それでは本のタイトルにある[ヤバい]とは 『リフレ政策は、インフレをいったん起こしてしまうと、そのインフレが制御不能になってしまうことが問題なのではない。 インフレを起こせないのに、インフレを起こそうとすることが問題なのだ。』P.6 インフレとデフレのメリット・デメリットを挙げてみます インフレのメリット ・物が売れやすくなり景気が良くなる ・物の価値が上がり通貨価値が下がるので輸出で有利になる ・会社の売上・業績がアップするので働く現役世代に有利 インフレのデメリット ・極端にお金の価値が下がりすぎる(ハイパーインフレ)と物が買えない ・他国から輸入で物を仕入れる事も難しい ・通貨価値が下がりすぎると外国からの信用をなくす デフレのメリット ・資産をもっている人は資産を増やさなくても実質増えた事になる ・外貨、輸入品を安く買えるようになる ・退職リスクの存在しなく十分資産をもっている高齢者に有利 デフレのデメリット ・物が売れないので景気が後退する ・一般消費者の給料も減りることで消費行動を抑制してデフレが進行する つまりインフレ・デフレどちらの状況でも得する人と損する人がいるってことです その得する人と損する人とは若い人と高齢者の対立です インフレ・デフレどちらも良い面・悪い面があるとしても デフレ期よりもインフレ期のほうが失業率や倒産件数などデフレ期のほうが悪化しているので 個人的にはインフレ寄りだな・・・と再認識させてくれた本でもあります さらに厄介なことに高齢者にとって有利なデフレでも給付される年金はリスク資産で運用されているので 本来ならば資産を多く持たない多数の高齢者にとってもインフレのほうが望ましいのではないか? ハイパーインフレにならないことが重要なのであってインフレに行きすぎないためのインフレターゲットを兼ねているリフレ政策は必要でしょう
0投稿日: 2013.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログリフレについての説明と、リフレが問題であることの説明をしている本です。 恥ずかしながら、リフレについては、まったく知識がなかったので、いい勉強になりました。 また、日銀について勉強する必要性を強く感じました。 最後の提案については、今一つではありますが、「(自国通貨だけでなく)ドルで考えよ」というのは、日本人が忘れがちな相対的な視点を強調する意味で、よい指摘だと思います。 とりあえず、リフレ反対派の意見は、これで何となくわかりました。 今度は、リフレ賛成派の本も読んでみたいと思います。
0投稿日: 2013.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ論理的に解説を試みているので、わかりやすいが、リフレ政策がダメなら別に良い政策の選択肢が提案されているかというと、そうでもない。我々は金融商品の闇鍋を喰らいながらいいていくしかないのか?腹立たしい気持ちが強まって来た。
1投稿日: 2013.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在アベノミクスという名前のリフレ(インフレをわざと起こすこと、この本の著者による定義)が進行していて、目に見える現象としては、円安や日本株高をもたらしています。 個人的には、5年前くらいに始めてしまったドル預金等のマイナスがなくなって「ほっ」としているのですが、円安と原発事故による火力発電の増加のため、早くも貿易赤字となってしまいました。このままで日本経済や我々の暮らしはどうなるのでしょうか。 今年(2013)4-6月のGDP成長率をみて判断すると言われている消費税増税は、参議院選挙を経て、来年には実施されそうな雰囲気となってきて心配は増すばかりです。 この本は、内容があたらないというシナリオが実現することを願って、書か れています。束の間のプチ好景気を良いことに誤った判断をして、日本経済が失速したり日本人の生活が悪くなっていくことだけは避けたいものですね。 この本の一番のポイントと感じたのは、著者が、日本国債の金利さえ上昇しなければ、リフレでも良いとしている点(p88)でした。 以下は気になったポイントです。 ・今の日本でインフレが起きるとは、所得が上がらない状態なので、コストプッシュ型インフレ(1973のオイルショック)しかあり得ない(p52、54) ・円高の影響は、直接目に目に見ける形で一部の人(雇用を多く抱える大企業等)に集中して起こるのに対して、円安は間接的に目に見えない形で、すべての人に少しずつ影響が広がる(p63) ・円安が進む(例:1997年以降の円安)とは、ドルで考えると、日本の国債・株・不動産が大きく値下がりすること(p74、76) ・二度目の円安(2005-07)は、景気回復と同時進行で起きたので、良いとされていることから、現在リフレ政策を主張している人は、この型の円安が起きることを想定している(p78) ・円安で注意すべきは、国債価格の下落(=名目金利の上昇)である、これさえ起きなければ、リフレ政策はやってもいいくらい(p88) ・中央銀行は、その出自からして、インフレを抑えるために存在する(p162) ・インフレが起きるかどうかは、需要が強いかにかかる、その強さは所得に応じる(p177) ・オリジナルの量的緩和(2001に日銀が発明して導入)は、金融政策の目標を、金利水準からマネー量に切り替えたもの、いくらでもゼロ金利の短期資金を銀行が日銀から借りれるようにしたもの(p191) ・米国が導入したのはインフレターゲットではない、失業率の低下を優先し、それが高いままであれば、インフレ率が妥当な水準から少しずれても金融緩和を継続すべきとしたもの(p216) ・バーナンキFRB議長がインフレ率が1%より2%が望ましいとしている理由は、失業率が6.5%以下になったときには、経済は成長しているので、きっと2%程度だろうということ(p218) ・英国では為替と金利水準が重要、なのでユーロという通貨を使うことはできない(p226) ・LIBOR事件とは、英国銀行バークレーズが金融危機でないというストーリーを演出するため、金利を過小に申告していたことが発覚したもの、利子をもらうことになっていた年金基金、地方政府などが訴訟を起こしている(p227) 2013年6月2日作成
0投稿日: 2013.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ安部首相が掲げる三本の矢のひとつ、大胆な金融緩和、デフレ脱却を目標に行っているインフレを起こす政策、リフレ政策がいかに日本にとって悪影響なのかを述べた一冊。 リフレ政策とは、 1.本来政府から独立している日銀に、インフレターゲット2%を課すこと、(本来1%が目処で、日本にとってはこれが水準、そもそも日銀はインフレを起こさない目的で作られた) 2.マネーの大量供給するために金利の引き下げを行い、世の中のお金の流れを作ること、(実際はゼロ金利なので民間金融機関が持つ資産、すなわち国債、株式、リートを買う)量的緩和、すなわち民間銀行の日銀当座預金残高の量を増やすこと。いくらでもゼロ金利で短期の資金を、銀行が日銀から借りられるようにした。 3.インフレ期待に働きかけてインフレを起こす。 4.政府独立型で、日本経済のための金融政策を司る金融のプロ集団を、金融の素人である政府が傘下に置こうとすること、つまり日銀改正法。 である。 しかし、インフレは能動的に起こすことはできず、可能性としてあるのは円安輸入インフレのみ。 理由: ものの値段が上がるのは、店が値上げをする時のみ。 店が値上げをする理由は、上げても売り上げが下がらない程度の需要があること、つまり景気が良い時(demandpul型インフレ)。これは所得に応じる。もうひとつはコストが高くなり、上げざるを得ないとき(コストプッシュ型インフレ)。給料が高くなり、それに合わせて物価も上がるのは良い傾向だが、給料が上がらず、物価のみ上昇することは最悪(スタグフレーション)。これは円安輸入インフレの可能性が考えられる。 つまり、リフレ派が主張していることは因果関係が逆。 世論としても円高批判、円安歓迎の風潮。 円高で打撃を受ける企業は海外市場に依存している大企業。理由は円換算の利益が減るため。 もうひとつは質は高いが価格でアジア企業に負けている輸出企業。理由は価格競争力不足。 そこに政治家やメディアが飛びつき、誤った認識が広がる。 実際は輸出を円建てで行っている企業が多い。ニッチ品や高品質製品を能動的に売れているから。一方、輸入はドル建て。国際価格がドル建てで決まっているため。 そして、日本は輸出よりも輸入がはるかに多い。 今まで起こった円安も能動的ではなく、ドル高の裏返しであったり、そもそも為替水準は経済と金融市場の状況を表すものである。そして、国債の下落を伴う円安は経済危機に発展する。 今起こっている円安株高も、世界的な金融市場の動きがあった影響もある。 円安で気をつけるべきは、ドル建ての国債下落。 国債が買われやすい理由は 1.流動性が高いこと 発行額が多く、流通額も多いため、いつでも買いたいときに買え、売りたいときに売れる。 2.評価のコンセンサスがあること 格付けが多方向からされており、投資の説明責任を客観的に果たしやすい。 3.固定利回り 金融市場の投資は株(野性的)、債券(論理派)、その他に分かれ、債券は利回りが固定されており、長期運用としては値上がり期待ではなく固定額の利子をとりにいく運用ができる。 リスクはデフォルト、債務不履行で利子を払うことができず日本経済の破綻を意味する。これよりも可能性のあることは国債の下落に伴う利回りの変化。値下がりと利回りの上昇が同義らしいのだが、この関係性がわからない。その大幅なドル建ての下落が円安によって起こる。それに伴い、銀行の貸しはがしかわ行われ、政府は資金確保のため国債発行、供給過剰になり金利上昇、国債下落、という悪循環が生まれる。 インフレによる駆け込み需要や、駆け込み需要を促すエコポイント政策などあったが、間違っている。エコポイントによりソニーを始め、テレビ業界は赤字になり、物価が上昇する時にものを変えるだけの余裕がある時のみ駆け込み需要による効果が現れる。現段階ではあり得ない話である。 デフレスパイラルも因果関係が逆で、物価が下落するから景気が悪くなるのではなく、景気が悪く、需要がないから物価が下がるのである。 経済学に関する凧紐理論がある。インフレ加熱時、金利を引き上げて金融引き締めを行える。しかし、デフレで景気が停滞している時、この景気を引き上げることは難しい。 株価が上がる理由はふたつ。 1.景気が良くなり、実体経済が回復する 2.リフレでお金が溢れ、金融資産市場に流れる 毎年の所得、フローを積み重ねたものがストックで、年々のGDPの積み重ねが国富、国の資産になる。国富が十分大きくなれば、フローで稼ぐよりもストックの有効活用の方が、生活に影響してくる。 円安戦略で日本が勝てない理由 1.内需で国富を蓄積し、輸出で経済を発展させてきた。その時は通貨を安くし、国富を蓄積してきた。しかし、今や日本も貿易で日銭を稼ぐ時代から、蓄積した資産の運用、活用の時代に入った。金融市場、資産、ストックの時代。この時代では円高が有利。 2.日本は超成熟国家。質の高いものを安く、というアジア企業と同じ土俵で戦うのではなく、ソフトの戦いとなる土俵、つまり人間のアイディアや文化、ライフスタイルの厚み、歴史、独自性が発揮される分野に力をいれて稼ぐべき。 3.会社経営をドルベースで考えられていない。真のグローバル企業になれていない。 この本を通して、日本、世界の経済について、基本が知れた。これからも経済と政治の関連について考え、思慮を深めていきたい。
0投稿日: 2013.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログアベノミクスだ何だと言われてもてはやされている、現・安倍政権のリフレ政策に対して警鐘を鳴らしている本。リフレによる円安の進行が、結果的に国債の暴落を招き、日本経済が再起不能に陥るといったシナリオについて解説している。 まあ、安倍さんの言う3本の矢というのは分からないでもないが、自分はその3本の中では成長戦略というものが一番重要と思っているのだけど、残念ながらそれを具現化する方策がきちんと立てられているようには見えず、結局円安誘導で無理矢理数字をこねくり回して何となく景気が浮揚しているように見せているだけなのではないかというように見えてしまっている。その意味で、小幡さんのいうような展開になってしまう可能性は決してゼロではないし、よしんばしばらくの間景気がよくなったとしても、結局それが将来の成長の先食いでしかないのであれば、後の世代にとんでもないツケを残すことになりかねない。今先行して進めている2本の矢が有効なうちに、最後の1本を真剣に実現していく必要があるだろう。 本で書かれているシナリオについてはよく出来ていると思う。が、最後の最後で感情論に陥ってしまっているのが残念。結局のところ、リフレ憎しで叩いているだけになってしまっている。前の展開がよかっただけに、余計に残念。
0投稿日: 2013.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログリフレ派に対する批判的検討として国債の暴落と通貨安に対する是非が述べられています。前者はよく知られていますが、後者については円高を良しとするロジックは読み応えがあります。しかし、そのロジックの過程で広げられる客観的な例証が無いため懐疑的になる場面が多いです。最終章では日本企業の戦略論となってしまい、経済政策の域を離れてしまっています。全体的に”成熟化”や”フローからストックへ”、”差別化”といった月並みな論に終始してしまっている点で面白みにかけます。むしろ金融政策には限界があることを端的に述べたほうが評価が高かったかもしれません。
0投稿日: 2013.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で、買ってほしいと申請書出して、順番待ちしてて、ついに読めたぜ! 反リフレーション派の急先鋒、小幡績氏の痛快な1冊。 彼は、かなり、おもしろい人だよ。ケインズみたいな(というと語弊があるけど)エコノミストにして投資家でもあり、相場師としての視点があるからおもしろい。全ての経済はバブルに通じる、という。 この前、小幡績が出演してるニコニコ生動画で見てたら、おもしろすぎて笑い転げた。 オレの経済政治中心のツイートのIDでは、リツイートしてもらった。うれしー。 エコノミスト誌での飯田氏との激論対談でも、やっぱー小幡氏のほうが奥が深い。「経済学は不完全な科学だ」という内容のことを断言してた。普通に考えれば、当たり前だよね、そんなこと。だって、ひとつの金融政策、財政政策をめぐって、ここまで真っ二つに意見が割れてるんだから。そんなの、物理学や化学や生物学や、完成された科学ではあり得ないことだ。 経済学は、信用に足る科学ではない。科学以前だ。 オレは、小幡績のファンになった。
0投稿日: 2013.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ間違いのない名著です。 現在蔓延っている「リフレ派」の定義、問題点、反論、解決策について分かり易く纏まっていると思います。 金融緩和によるマネーの氾濫は、資産バブルを引き起こすだけだという警鐘は真摯に受け止めなくてはいけないと思います。 最後の「場」と「人」を大事にすべし、という一節は素晴らしいです。 金融関係で少し難しい話も入っているかも知れないですが、お勧めです。 リフレ派の本と比較すると尚良しです。
0投稿日: 2013.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログリフレとはインフレをわざと起こすことである。 日本経済がデフレ化(円高・株安・物価安)してから久しい。 が、去年(2012年)末政権交代し、安倍総裁によるアベノミクスが始まった途端為替と株価が動き出した。そして4月あたまの日銀総裁黒田氏による量的緩和宣言。彼のひとことで株価、地価は一気に跳ね上がった。 …でもこれってバブルの匂いがする…。 企業や商業がこれから伸びる時期にあるならいざ知らず、需要もないのに(借り手もいないのに)お金だけだぶつかせて…インフレ率だけ無理やり上げて中身が伴わない。こういうのってバブルっていうんだよね。 デフレ結構、円高結構。 日本はいまや成長期から成熟期に入っており、フローで稼ぐよりもストックを有効活用した方が賢い。グローバルな視点から見れば、円が強い方がいいに決まってる。円が強いうちに海外の優秀な企業を買収してより良い技術を導入した方がいい。でないと円安になったときに逆のことが起こってしまう。なんで政府は円安方向へ持って行こうとするのか。 結局今の日本は停滞気味なので刺激を求めてるんだなぁ。 実際投資信託でありがたく儲けさせてもらった私だけど、なんか怖い。リフレはやばい。
0投稿日: 2013.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
長く続く日本の不況。明らかにデフレを放置したことによる弊害が観られる中、自民党政権になりやっとデフレ解消に向けて動き出した。が、意図的なインフレ誘導にもやはり問題があるという。制御不能になってハイパーインフレが起きる、というのが論拠ではなさそうで、興味深く読んでみる。 アベノミクスなどと安易なネーミングでマスコミが持ち上げている状況もちょっと気持ち悪いのは事実である。その実体が見えない中で先行き期待に反応している株価や為替をもって浮かれかけているのがこわい。 インフレ誘導によって、賃金の増加よりも先に物価が上がってしまえば景気回復どころかますます消費は冷え込んでしまうだろう。 インフレはあくまでも好景気の結果に起こるものであってその逆ではない、ということだろう。 ただし、それでは他にどんな方法があるのか、というと難しい。納得のいくような答えはなかった。
0投稿日: 2013.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ今経済論壇が活発だし、まぁ売れてるみたいだし、この版元のこのレーベルは「電子書籍の衝撃」で印象もよかったので読んでみた。 論旨は明確で読みやすい。センセーショナルなタイトルの割にはちゃんと建設的。この辺がディスカバーさんのバランス感覚かね。全体としてリフレ派への評価を「~だと思います」としていて、論証責任を放棄しているのは誠実ではないと思う。こういう感情っぽさを入れた方が受けるのかな。 たぶん産業戦略のビジョンがリフレ派と違うんだろうなぁ。新しい価値、新しい技術革新で攻めていかないといかんという主張は割と好きなのだけど、もう一冊くらいリフレ派の本を読んでから自分の主張を決める。
1投稿日: 2013.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱ、リフレは非常にヤバい。 インフレターゲット2%?円安歓迎?? アベノミクスに盛り込まれたリフレ派のちゃんちゃらおかしさを上手く説明してくれている。
0投稿日: 2013.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ野口由紀雄氏の「金融緩和で日本は破綻する」に続けて本書を読み進んで、かつ文芸春秋4月号の神谷氏の論文も読むと益々アベノミクスに懐疑的になって仕舞ひました。個人的には株は三ヶ月が勝負、そして国粋的な小生でありますが、極力外貨資産へ逃避すべしと思考します。
0投稿日: 2013.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ遮二無二円安、インフレに仕向けるなと。こうなった背景として震災後の過剰な円高が悪とされているところにあるのだろう。インフレにすれば景気が良くなるという因果関係が全く逆であることに対し猛烈に批判。他国でのインフレターゲットをそのまま鵜呑みにして2%上昇とかぬかしている政治家等にも呆れる始末。かといって著者が考える対策にも現実味を帯びていない。
0投稿日: 2013.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログまずリフレとは何か、なぜリフレなのかから始まって、それが今の日本にそぐわない、ってかまずそれがムリでリフレは外野がデカい声で言ってたのを安倍さんが信じちゃったものだとゆう。 それ自体はともかく、経済学の知識で知らなかったことや自分の理解を覆す話があって面白かった。 例えば国債は流動性が高いからめちゃくちゃ需要があると、だから値が下がるとみんな買っちゃうからヘッジファンドが仕掛けてもムダだったこととか、でもみんなが日本国債売りに走ったら銀行が危機、それを止めるために国が資本入れればまた国債乱発、とゆう財政危機スパイラルの話とか、インフレの様々なメリットが実はそうでないとか、金融政策のタコヒモ理論とか、英国がインフレターゲットを設定してるのは、金融立国だからでゆえにユーロを使うこともできないってこととか。 突き詰めてゆうと円安については、輸入品が高くなるし、資産価値もドル建てで下がる。インフレについては実質賃金が下がるわけよな。 小幡さんの本はわかりやすいしその論理に納得がいく。
0投稿日: 2013.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ円安、インフラで・・・・経済危機へ という見出しにひかれ購入。 この政権になって、やたら円安を推奨している。 円安は、輸出産業にとって良いことは理解しているが、輸入に頼っているこの国では円の価値が下がり物価も高くなるこの円安は本当にいいのだろうか。 また、本当にインフレがよいのであれば、すぐにやってれば良かったのに何でやってなかったんだろうか?。 という疑問を以前から持っていた。 この本で得た知識は下記のとおり ・インフレになるためには景気がよくならないといけない。 景気を良くするために、インフレにさせることは逆効果 ・円安になると国債価格が下落する ・デフレ=不景気ではない ・エコポイントのような駆け込み需要を誘発するインフレは、よくない。 ・中央銀行はインフレを抑えるために生まれた。政府から独立している必要がある。 ・インフレが本当に有用であるなら、すでに日本銀行が行っていたはず。 これらは非常に納得できる。 ただ、不在者裁判とならないように、これを超えたインフレ推進者の意見も聞いてみたい。 この本では、インフレのデメリットはとても理解できた。でも、この景気対策をどのようにすればよいのか、説得性に欠けた。 人的資本の蓄積をもたらす雇用はわかるが、一つの提案が学校を作ることっていうのはいまいち。もうちょっと良い例があると思うが、、、、、。
0投稿日: 2013.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ明快。自分の実体験ともリンクする。 需要喚起しないでインフレだけすすめたら、単純に使える金が減るだけ。
0投稿日: 2013.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログさて、今のところとりあえず順調なアベノミクス・・・ その3本の矢のウチの1本・・・ リフレーション(大胆な金融緩和で緩やかなインフレを目指すヤツ)・・・ 略してリフレ・・・ リフレ派と反だか非リフレ派の長きに渡る果てしない攻防・・・ お互い、双方、それぞれ分かってない、という罵り合い・・・ どっちが正しいのか? 勉強の足りないボクにはわかりませんが・・・ この本はタイトルの通り、リフレ批判本・・・ リフレはヤバい、のヤバいは良くない方のヤバいです・・・ リフレ政策で驀進し続けたら日本経済崩壊しちゃうかもよ、と著者の小幡績さん・・・ ザックリと・・・ リフレ政策→円安、名目金利上昇→国債暴落→金融危機→日本経済壊滅っちゅー流れ・・・ 内容としては・・・ リフレ政策でインフレ起こせるの?実際どうやるの?できないでしょ? え?インフレ期待?インフレ期待を起こすったって、インフレになるからってみんなモノ買うの? 給料増えなきゃ、モノの値段上がるったってモノ買わないよね?逆に買い控えちゃわない? モノの値段上がる、インフレになるのはやっぱり需要があるからだよね! え?でも円安になればインフレにはなるね!このパターンはありうるね! でも、円安になると、ドルベースで国債が値下がりするから、運用担当者は日本国債売っ払って米ドルで米国債に投資するね!(実はここがイマイチよくわからない・・・) みんないっせいにそうするね!そしたら国債暴落だね! そしたら国債保有している金融機関(主にゆうちょや銀行)ヤバいね! そしたら金融危機だね!そしたら政府が助けなきゃいけないけど、お金ないから国債発行しないと!でも買ってくれるとこがない!日銀に無理やりにでも頼もう!あ、でも、日銀が国債引き受けしたらもっと信用されなくなるじゃん!ヤッベー! みたいな・・・ あとは段々とリフレ派をバカにするような感じになっていくので・・・ テンションが下がっていきます・・・ 話が大雑把ですし、結構勝手に言い切ってしまっている感じがちょっと・・・ 新書ではありますが、せっかく批判するならもっと込み入って根拠を示してほしかった・・・ そして、ネットで小幡さんの話よく読んでいる人には新鮮味はないです・・・ 最近のアベノミクス騒ぎでリフレ、というものを知った方は読んでもイイのかな、とは思います・・・ リフレはスゴい! これこそ日本を救う唯一の道だ!と信じまくってしまっている人にはオススメです・・・ 個人的には詳しく勉強したわけではないので、判断しかねますが・・・ リフレ政策、金融緩和をハイパー徹底すれば、デフレ脱却なんて出来るんじゃ、景気良くなるんじゃボケみたいな簡潔な感じが胡散臭く思っておりますが・・・ それだけで経済良くなるとはとても思えない・・・ 地道に頑張って生産性上げたりして経済成長していく路線しかないんじゃないかなとは思います・・・ 株とか上がる分にはイイんですけどね・・・ 著者の言うように、結果的には日本経済がトンデモないことになる、なんてならないことを祈ってやみません・・・ ホントにどっちが正しいのか・・・ なぞ・・・
0投稿日: 2013.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ金融緩和でインフレは起こせない、インフレにはメリットがない、為替介入は米国との協調介入のみとすべし、円安は日本国債の暴落を招き、金融危機から銀行危機となり経済危機へ陥ると説き、政治家が金融政策に注文をつけるのはタブー、日銀の独立性を損ねてはいけないとも主張する等徹底した反リフレ論を展開する。 また、フローからストックの時代に入ったとして次ぎのように説く。 『1500兆円の個人資産があるのなら、これらの利回り、つまり、投資による利益率が1%から3%に増えれば、利益額は15兆円から45兆円へ30兆円も増えます。名目GDPは480兆円程度ですから、30兆増えるというのは、GDP成長率で言えば6%以上の成長となります。成長率を1%上げることもほぼ不可能な現状ですから、これは大変なことです。』 FRBバーナンキの失業率を下げる金融緩和を支持していた割には日本の失業率への言及が無いのが気になるところです。最後に取って付けたように雇用問題についての言及があるが、教育を施せばみんながみんな、クリエィティブになれたり、マネジメントやコーチができるようになるなら苦労は無いと思うのだが。。。
0投稿日: 2013.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログイェール大学名誉教授の浜田さんの本「アメリカは日本経済の復活を知っている」 に続いてこの本を読んだ。 無知な私は浜田さんの本を読んだ時点では、 日銀が金融緩和すれば、円安になり、インフレになり、製造業が復活し、日本は全体として良くなるんだな と完全にそう思っていた。 しかし、この本を読むと、書かれている内容が真っ向から対立していて、しかもものすごく説得力があり、今頭の中の整理がつかない状況だ。 確かに円安になれば輸出は良くなるのだろう。だが、円安とは、他の通過と比べて円の価値が下がることなので、海外とのやり取りが不安になる感じは前から感じていた。 リフレがいいのか、悪いのか、もしくはなんともないのか、とても奥が深い。もっと知識を得て、理屈も、人間ならではの理論じゃどうにもならない雰囲気も様々なところから感じないと自分にはこの問題はわからないなと思った。 とにかく、互いの議論はすごく面白く、二人の討論番組でも見てみたい気分だ。この本をきっかけに、二つの対立する意見を自分で吟味し、考えていく力を身につけようと思った。
0投稿日: 2013.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日読んだイェール大学名誉教授の浜田宏一氏の『アメリカは日本経済の復活を知っている』では、日銀の金融政策でデフレ脱却、円高解消は出来ると書かれている。国債で大きな債務を抱えているが、同時に世界一の対外純資産を持っている世界一の債権国でもあり日本国民の将来の納税力があるため円の信頼はゆるぐことは無いと言っている。 一方この本の著者は、『リフレ』つまり『インフレを起こそうとすること』はまずいと主張する。金融政策だけではインフレは起こすことはできない。インフレが発生するためには強い需要が必要だが、所得が増えない状況では需要が増えずインフレは起きないという。円安輸入コスト高でインフレは起きるが、このインフレは求めるものではない。本当に給料は増えないのか? アベノミクスは別に金融政策だけではない。給料を上げた会社は法人税の減税の対象とする政策を同時に実施しているが、ここではふれられていない。 また円安ではドル換算でその価値が下がり国債が暴落すると主張する。国債を抱える銀行が厳しくなり、貸し渋り、貸し剥がしがおこり経済が回らなくなる。一方浜田氏の本は、借金は多くても国民の対外純資産は世界一であり、将来の国民の税金の支払い能力があるため円の信頼は揺るがないと主張している。 兎に角この2つの本は互いに対立している。この手の本、素人の私は読む度にそれが正しいと思い込まされるてしまう。一体どっちが正しいのか? 浜田氏の本は名誉教授という立場のやや上から目線でかかれいて、是々の論理は証明されていて自明、どこどこの偉い人がこう言っている、というような内容になっているので今ひとつスッキリしないのに対して、この本は非常に一つ一つの内容について丁寧に説明しようとする姿勢が見えるので、本としてはこちらの方が好感が持てる。 日本国債の空売りでヘッジファンドが何故損をしたのか、みんなの党がリフレ派であること、タコ紐理論とはどういうことか等、本題からはそれるが勉強になる内容もたくさんあった。楽しめた。
4投稿日: 2013.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ円安誘導もインフレターゲットも、金融緩和の結果であるにもかかわらず、あたかも日本を救う(しかも欧州やUSと比べてそんなに危機なの?!)究極の手段のように語られるアベノミクス。そもそも円で物事語っていることがすでにおかしい。日本の多くの企業が、成長の源泉を海外に求めていますよ。小幡先生の主張に同意。
1投稿日: 2013.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書を読むと、“インフレ”、“デフレ”、“スタグフレーション”、“景気”というような概念や、日銀等の中央銀行というモノが採択して推進する施策というものがよく判る。 “デフレ”状態が永く続いて困っているのだから、何とかしなければならないという論旨の本は少し前に読んだ…と言って、“インフレ”というものも、実は故意に発生させることが出来るでもない…結局「時代は変わった。世界は変わった」と「考え方を変えて対応する」他無い訳である… 巷で“是”とされているものに関して「それには“非常に悪い展開”をする可能性も在る」という話しは、本書の著者が断るように「彼が嘘を…」と批判されるような状況の方が善いのであろう。が、大勢が“是”としていることであろうと「本当にそれで善いのか?!」と考える材料を仕入れて考えることは必要なように思う…そうした意味で、本書は広く奨めたい一冊である。
1投稿日: 2013.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこれから始まる経済の動きを理解して予見できるようになるため、本気で勉強しなければいけないテーマだと危機感を持っています。 リフレとは、意図的にインフレを起こすこと。その鍵は日銀にあることがよくわかりました。円安を起こし、輸入品を高くすることで商品やサービスの価格を上げるというシナリオです。 円安で誰がどのように得をして、日本経済に好影響をもたらすというロジックかは理解したつもりです。 しかし、通貨の価値は高いほうがよいのでは?と単純に思う気持ちも捨てきれません。 本当に難しい話なので、自分の意見を持つためにはもっと勉強が必要です。 まずは日銀の仕事を理解することが必要なステップと認識しました。
0投稿日: 2013.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
アベノミクスを考えてみる。 – 『リフレはヤバい』 - HONZ URL : http://honz.jp/21706 「物価が上がり、給料があがらず」、スタグフレーションになれば、 反リフレと行っていた人の勝ち。 さて、どちらが正しいのか...
0投稿日: 2013.02.06
