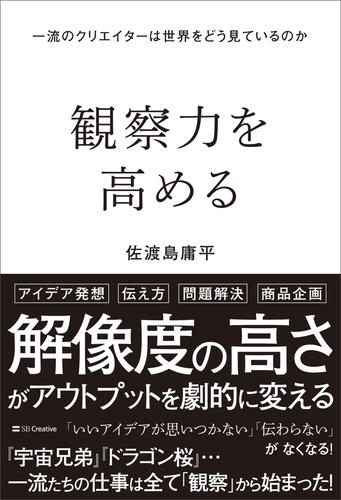
総合評価
(8件)| 1 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ人が持つバイアス、現実のあいまいさを前提として受け入れつつ、ものごとを観察して判断することが欠かせないことを知ることができる本です。 多様性のある社会になったと言われますが、それは実はあいまいさを受け入れる社会でもあります。 明確な正解があれば、繰り返していれば必ず正解には辿り着けますが、明確な正解などなく、あいまいだと、世の中は簡単ではなくなります。 観察によって気づいていないあいまいさを発見し、それをあいまいなまま受け入れることが大切と著者は言います。 観察力を鍛え、認知バイアスを武器につけ、未知のものへの不安を期待に変え、仮説立てと検証を繰り返すことが必要であることを学べます。 多様化が進み、正解がわからなくなったと不安に思う方などが読むと、対処に必要なマインドセットを学ぶことができそうな1冊です。 【特に「学びになった」と感じた内容の覚え書き】 (認知バイアスを武器に変える) 「この世界を正しく認知し行動するのを妨げているのは、まさに自分自身の脳で、自分とどう向き合うかが結局のところ全て。大切なのはバイアスから逃れることではなく、自分は認知バイアスの影響を常に受けていると自覚して、それを意識しながらモノを見たり、判断したりすること。」 (正解を手放す「アンラーン」) 「現実にはあいまいさがあふれるが、それを社会の常識、既知の枠組みで見ている限り、そのあいまいさには気づけない。自ら観察によって発見しに行き、それをあいまいなまま受け入れる必要がある。多様性のある社会とはあいまいさを受け入れる社会だが、実践は一筋縄ではいかない。」 「明確な正解があり、それを実現すればいいときは、繰り返していれば必ず正解には辿り着ける。世の中が簡単ではないのは、明確な正解などなく、あいまいだから。誰も答えを知らないなら、その中であいまいな結論を導き出して、前に進んでいかないといけないし、そんな仕事は多い。」 【もう少し詳しい内容の覚え書き】 (全てのスキルの基礎となる観察力) ・いい観察は、ある主体が、物事に対して仮説をもちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促し、問いと仮説の無限ループを生み出す。悪い観察は、仮説と物事の状態に差がないと感じ、わかった状態になり、仮説の更新が止まる。 ・本当の意味のクリエイティブとは、同じ土俵にいるライバルが考えもしない切り口で考えてみたり、アプローチしたりすることで、解像度を高めること。切り口の変化、視座の移り変わりのために必要なスキルが観察力。全く異なる視点で考えてみる姿勢や考え方こそが、最強のビジネススキル。 ・自分の身体感覚を鍛えると、同じ環境も変わる。普段、仕事をしている状態では脳という身体のセンサーを活用し、考えた思考を言葉で表現しがちだが、本来持つ身体感覚やセンサーを高めることは、観察力を高めることに大きく影響していると思われる。 (「仮説」起点の観察サイクル) ・具体的に行動にはサイクルがあり、「計画」→「実行」→「振り返り」のプロセスを踏むが、起点を「振り返り」にすると行動の熱量が高まり、計画が立てやすい。観察の場合、「仮説」が「振り返り」にあたる。雑でも仮説を立てると、仮説を検証したいという欲望が生まれ、熱量のある観察が始まる。 ・仮説を立てるには、目に映るものを愚直に言語化→SNSやAIを含めた外部の「評価」を参照軸にする→データに当たる(記憶は信用しない、主観的に見る)→徹底的に真似て型に気づく→自分だけのモノサシを育む、という手順がよい。 (認知バイアスを武器に変える) ・バイアスは、ヒトという種が生き延びるため、多くの判断を意識下ではなく、無意識下で速く行えるよう、遺伝を使い、時間をかけて作り上げた仕組みでもある。正しいことも多く、全否定する必要はない。判断を保留して「問い」を立て、状況を観察する習慣があれば、バイアスを意識できる。 ・人は自分が見たい世界だけを選んで見ているが、現実とは程遠く、妄想に近い。未来がわからないと人は不安を感じる一方、不安は未知へのワクワクにもなり得る。バイアスについて学び、武器にし、現実を見る準備ができていると、同じものを見ても不安ではなく、ワクワクできる。 (見えないものをどう観察するか) ・感情は、バイアスと同じく、危機的状況に即座に対応できるよう進化の過程で獲得してきた、最も合理的なセンサーだという考え方もある。一方で、使いこなせる人は滅多にいない。使いこなし、理性と調和することで、社会との距離感を適切に保てれば、快の状態を長く維持できる。 ・感情を使いこなすには、感情を観察することが必要。観察するためには仮説が必要で、そのためには最低限の知識がなければならない。感情は自ら選んでいて、いいも悪いもない。同じ情報を受け取っても、感情によって処理の仕方に大きな差が生まれ、異なる意思決定となる。 ・人は、その人単独で、個人として存在しているのではなく、その周りを取り囲む他者、場所との関係性の中にいる。関係性こそがその人の本質であり、中心はないと考えて、世の中を観察すると、個人とは確固としたものではなく、関係性が変わると個人の在り方も変わる。
0投稿日: 2025.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
114頁に、 “早逝してしまった瀧本哲史さんから、こんなことを言われた。「『起きていることは全て正しい』と思うことは大切ですよ」そのときは、そんなはずがない、正しくないことを正していくことが大事だ、と思ったけれど、この言葉はいろいろな場面で頭をよぎるようになった。そして、納得がいかない場面では、心の中で「起きていることは全て正しい」と一度、口にするようにした。 すると、正しくないと思わせているのは、自分のこだわりでしかないと気づかされた。” とある。今ここに集中出来ず未来に不安になるのも、《自分のこだわり》にあるのかもしれない。 少し時間を置いてから再読してみたい。
0投稿日: 2025.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログバイアスを認識して観察力を高めて仕事や人生を豊かに...という本なのだが、創作物への視座や筆者の認識が素敵だから好き。「物語の中で起きるような認知の更新がしたくて、僕は観察に興味を持っている」という文章が素敵。物語好き(小説でも映画でも漫画でも)としてはグサッとささる一文。
0投稿日: 2025.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
4. 観察力を鍛えるとは、バイアスに気づいて、バイアスを外して見直すことである 16. 観察力とは、「客観的になり、注意深く観る技術」と、そして得たことを、「組織的に把握する技術」の組み合わせと言えるかもしれない 21. いい観察は、ある主体が、物事に対して仮説をもちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す。 一方、悪い観察は、仮説と物事の状態に差がないと感じ、わかった状態になり、仮説の更新が止まる 29. 日本には雨に関する言葉が400種類以上ある 30. 世界を見て、面白くないと感じる時は、対象に問題があるのではない。自分が観察をやめて、観察をする前から、既存の知識で判断してしまって、毎回同じ結論に達してしまっているというサインだ 34. 視点は常に更新し続ける必要があるし、改めてゼロベースで目の前の事象をとらえてみる 36. 第六感は言語化できていない身体感覚。このような人が本来持つ身体感覚やセンサーを高めることが、自分自身の経験も含めて、観察力を高めることにも大きく影響している 37. どうやったら「普通」でいられるか。「普通」の状態を保つことができれば、特別なことを運良く成し遂げることもある。「普通」でい続けるのが、一番難しい 37. 観察をめぐる僕の思索、最初のアプローチは、言葉の意味を考え、語源を調べ、他の言葉との差を考えることだった 40. 「常識とは、あなたが18歳までに身につけた偏見の塊である」byアインシュタイン 41. 「虹」という現象を見ても、日本と東南アジアでは、見え方が変わる。それは色を表す言葉の数に違いがあるからだ。日本は7色を見出すが、インドネシアの人は4色、台湾は3色に見えるそうだ 41. 「人は、変えられるのは未来だけだと思い込んでいる。だけど、実際は、未来は常に過去を変えてるんです。変えられるとも言えるし、変わってしまうとも言える。過去は、それくらい繊細で、感じやすいものじゃないですか」 平野啓一郎「マチネの終わりに」 46. 観察によって、世界の見え方が変わるのではない。認知が変わることで、世界の見え方がかわる 58. 観察しようとするとき、「認知バイアス」「身体・感情」「(時空間の)コンテクスト」が観察の邪魔する。僕はそれらをまとめて、「メガネ」と呼んでいる。人は「メガネ」をかけてしか対象を観られないのであれば、そのメガネを意識的にかけかえればいい。その「意識的なメガネ」というのが「仮説」だ 64. 絵を観るとは、「絵を観て、動いた自分の心を観察し、その心の変化を生み出した絵のあり方と作者の意図に思いを巡らせる」という行為 66. 言葉とは、人間が唯一、時空間を超えて、携帯出来る武器だと思っている 67. 「ディスクリプション」。目に映るものを言葉に置き換えること 85. 観察力を鍛えるには、客観と主観、具体と抽象を、適切なタイミングで行き来する必要があり、その切り替えのタイミングを理解していくのが、観察力を上げる肝とも言える 92. この飽くなき仮説検証の中で普遍性を獲得しているものを、世間は「型」と呼んでいるのではないか 96. 「革新は、辺境から生まれる」 103. 型と型の組み合わせと、そこに入れる自分の記憶でオリジナリティが生まれる 123. 自分の仮説を強化する情報を見たときに、それを否定せず、より信じるほうにあえて使う。確証バイアスを意識的に使うことは他者との個人的な関係においては、より相手への尊敬を深めたり、自分の情熱をさらに高めたりといい方向にはたらく 125. バイアスは、進化の過程で獲得された。だから、否定するのではなく、どう使うのかが重要だ 128. 「悲観主義は気分だが、楽観主義は意志である」アラン「幸福論」 133. 同調バイアスとは、自分の持論に反したとしても、「みんながそう言ってるから」と大勢の意見を支持することだ 142. 「ハロー効果」。ある人物や物事を評価する際に、顕著に目立つある特徴に引きずられて、他の特徴の評価が歪められる傾向を示している 145. 全ての人と一期一会の感覚で向き合うことが、人生を豊かにすることだ 154. 「後知恵バイアス」。物事が起きてから、それが予測可能だったと考える傾向 157. 「正常性バイアス」。異常事態になった時に、パニックになるのを防ぐために、予期せぬ出来事には鈍感に反応するバイアス 172. 他者によって引き出される「分人」の集合体として、「私」という個人が存在するのだ 179. 感情を使いこなすことは、幸せへの近道かもしれない 180. 仏教では、七情と言って、「喜怒哀楽愛悪欲」の7つを基本の感情としている 180. 感情を理解するためにまず大切なのは、 ・感情とは選ばされているのではなく、自ら選んでいる ・感情にいいも悪いもない 183. 感情とは、意思決定を素早くするための道具でしかない 188. プルチックの感情の輪 202. 人の能力は関係の中で発揮され、人は関係に悩む。その人をその人らしくしているのは、その人の能力よりも、その人の関係だ 207. 僕らが、必死になにかを学び、わかろうとするのは、良い判断をするためだ 208. 「学ぶ」には2種類ある 1「スキルを身につけることで、無意識に行えるようにする学び」 2「身につけているスキルを、意識的に行えるようにする学び」 210. 「動作を無意識下に置く」 211. 観察とは、本能に抗おうとする行為 213. 「絶対」の反対は「あいまい」 222. 「わからないこと」「あいまいなこと」を受け入れられているから、惑わずなのだ 224. わからない状態に身を置き続けるとは、思考を停止しないということだ 251. 対象への愛がないといい観察ができない 253. 本当に創造的になるのに必要なのは、夢中ではなく、退屈 258. 「人は自分自身を理解することなしには世界の情況を変化させることに着手することはできません。もしあなたがそれを見るなら、その時即座にあなたの内部に、完全な革命が起こるのです」
0投稿日: 2025.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が編集者ということもあり、漫画で例えることが多かった。多岐にわたるバイアスあるというのは勉強になった。物事を見るときの偏見は知らず知らずのうちにしてしまっていうため、そこに対してのアプローチ方法を知りたかった。
0投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ観察力の重要性 - 観察力の定義: 観察力とは、客観的かつ注意深く物事を観察し、得た情報を組織的に把握する技術のこと。 - 客観性と注意深さ: 観察力は「客観的に」「注意深く」物事を観ることが求められる。 観察力の鍛え方 - 仮説の重要性: 良い観察は、仮説を持ち、観察を通じてその仮説を検証する過程である。 - 反復的な観察サイクル: 観察は「問い」と「仮説」の無限ループを生むプロセスである。 - 言語化の重要性: 見たものを言葉にすることで、仮説を明確にし、観察力を高める。 仮説と観察の関係 - 仮説は観察の道具: 仮説を持つことで観察がより深まる。古代からの哲学においても、仮説を持つことが思考の深化につながる。 - 誤った観察の回避: 悪い観察は仮説と現実のズレに気づかず、思考が停止することを指す。 メガネとしての認知バイアス - 認知バイアス: 観察を歪める要因として、認知バイアス、感情、身体の状態を「メガネ」として捉えることが重要。 - メガネの理解: 自分がかけているメガネ(バイアス)を理解することで、観察力が向上する。 型の重要性 - 型を学ぶこと: 型を真似ることが観察力を高める。型を用いることで、観察や仮説検証の精度が向上する。 - オリジナリティの生成: 型の組み合わせによって新しいアイデアや作品が生まれる。 感情と関係性の観察 - 感情の観察: 感情は観察の重要な要素であり、感情を観察することで他者や社会との関係性を理解する。 - 関係性の重要性: 人は関係性によって形作られるため、観察対象として関係性を重視する。 まとめ - 本書は観察力の重要性とその鍛え方、仮説の役割、認知バイアスの理解、型の学習、感情の観察に焦点を当てており、これらを通じて観察力を高める方法を解説している。
0投稿日: 2025.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1882028650004095034?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
0投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
編集者として、「観察力」に着目してクリエイターとともに取り組んだ著者の気づきなどが論じられています。観察することは、あいまいさを抱えることでもある。そんなお話が繰り広げられています。 … 処理しきれない情報に触れる日々のなかで、私たちは簡略化するためにさまざまなフィルターやカテゴリー化、予測をかけていますが、 観察は、普段は飛ばしてしまう細部に注目する作業であり、 いったん判断を留保する必要も出てきて、 普段用いるフィルターやバイアスをいかに意識的に外せるか、という挑戦でもあるように思いました。 そうしていかにフラットな目線で目の前のものに視線や感覚を向けられるか。 … 著者がこれまでに扱われ、ヒットしてきたマンガや小説は、主人公が、ある種の「わからなさ」を抱えた物語であるといいます。 __あいまいなまま、 向かい合い続け、観察する。そして、観察したことを、わからなさ、あいまいさを抱えたまま、物語にする。その物語自体は、あいまいではない。どんな主人公がどんな課題に立ち向かっていくか、あらすじは明確だ。わからないところもない。しかし、はっきりとわからないもの、あいまいなものを伝え、人があいまいなまま前に進む勇気をそっと添える。 粘り強く人間を観察すること。 すぐに答えを出そうとしないこと、ネガティブ・ケイパビリティにも重なりそう。 同じ絵を3時間眺めつづける演習のお話を思い出しました。 再現性や理論家が不可能な具体的な人間に迫り、そこにある一般化できない人間の原動力に触れる物語を紡ぐことが、心を揺さぶるストーリーにつながる、ということなのかな、と思いました。
0投稿日: 2024.12.30
