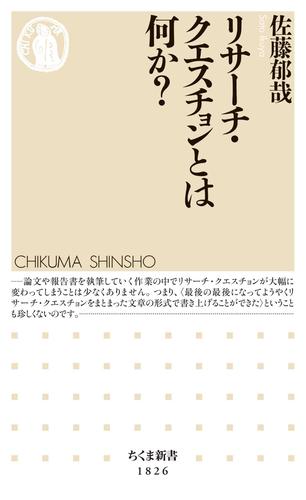
総合評価
(15件)| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ単純なようでわかりにくい、リサーチ・クエスチョン。論者や学問分野によって少しずつ扱いや定義が異なるからなのだが、この本では「社会科学系の実証研究のさまざまな段階で設定される研究上の問いを疑問文形式の簡潔な文章で表現したもの」(p29)と定義した上で、仮説はリサーチ・クエスチョンに対して平叙文で対応するものとされたり(pp59−63)、リサーチ・クエスチョンが実際には何度も見直され、完成した時の論文の構成におけるものが現実に行われた研究当初のものとは異なっていたとしても構わないのだ、その方が読者にとってわかりやすいのだから(pp170-173)とか、臨床研究をしているなかでなんとなく気になっていたことを丁寧に説明してくれていて、非常に助かった。
2投稿日: 2025.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ<OPAC> https://opac.jp.net/Opac/NZ07RHV2FVFkRq0-73eaBwfieml/Rg-hM6eXqIpu2kvVl3vTsnjMCse/description.html
0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会科学分野におけるリサーチ・クエスチョンの立て方にまつわる本。あくまで社会科学分野についての話なので、他の分野には適用できない。 研究を行う上では問いが必要だが、問いにもいろんな段階やレベルがある。良い問いを立てることが研究遂行には重要で、そのための色んな指標が世の中にはある。 とはいえ、問いは結局は良い研究のためだとすれば、問いの立て方や形式にこだわりすぎるのは本末転倒という気がする。本書ではリサーチ・クエスチョンの色んな条件が示されるが、ちょっと話が細かすぎるという印象。なぜそれが良いクエスチョンなのか、という部分の説明が乏しく、じゃあ別にその問いの立て方じゃなくてもいいんじゃない?と思った。
0投稿日: 2025.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初に立てた問いが一直線に進んで結論まで進んでいくように論文では書かれているが、実際には問いは何度も修正されブラッシュアップされている。問いを立て、調査をし、問いを修正し、それが何度も繰り返される。良い問いを立てることが大切であるとよく言われるが、その問いはどのように立てればよいのか知りたいと思って本を読んでいるが、一発で良い問いを立てることはできない。言われてみればもっともですね。著者によると修士研究者向けの入門書だそうです。
0投稿日: 2025.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
他の解説本ではあまり深堀されることのないリサーチクエスチョンについての解説。特に社会科学系においての「問い」は調査や研究、執筆が進んでいく上で変わっていく。反復行為が大事になる。また、論文についても完成系は一方通行であるが、作成に関しては後から問いをくっつけることもあるという現実的な指摘ついてもわかりやすく解説してあった。 大学の学部生で卒業論文を執筆し、今から修士の研究計画を立てる時期である自分にとってはタイミングの良い本であった。研究という作業を1通りやった人が読むとこれからの研究活動に活きる本だと思う。
0投稿日: 2025.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログリサーチクエスチョン=疑問文形式の簡単な文章で表現した社会調査で設定される研究上の課題・問い ⇔テーマ・課題などの名詞との違い:研究の基本的な方向性・明確な回答の明示を想定して進めることを明示 ⇔平叙文(仮説)との違い:実証研究が問いに対する答えを探す活動だと明示する。 2W1H:実態を明らかにする・因果関係を解明する問いで問題の本質に迫る →改善策・問題解決のための処方箋の問い ⇔5W1H:タイプが異なる複数のリサーチクエスチョンについてはそぐわない。 リサーチクエスチョンの3条件 ・意義:学術的 or 実証的な意義がある ・実証可能性:データに基づいて答えを出すことが出来る ・実行可能性:調査に使える資源・制約の範囲で答えを求めることが出来る 絞り込み型のサブクエスチョン: リサーチクエスチョンを比較的明確な答えが出るサブクエスチョンに落とし込む →具体的な調査項目の形に翻訳する。 ⇔拡張型のサブクエスチョン:試行錯誤の一環でリサーチクエスチョンを再構築 or 新たな調査研究による新たなリサーチクエスチョンの構築
0投稿日: 2025.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容はとても為になるが、本自体が読みづらい。 言いたいことが堂々巡りしているように感じるし、主張がはっきりしない上に、著者が焦点に上げている「リサーチクエスチョンの正しい立て方」を長々と説明しているように感じられて読みにくい。 とはいえ、内容は全ての人にとって役立つものであるため、その点は評価できる。
0投稿日: 2025.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. リサーチ・クエスチョンの定義と多様性 一見自明に見えるが、研究法文献では多様な対象が「リサーチ・クエスチョン」と呼ばれている 用語間の相互の食い違いも少なくない 「研究課題」や「研究テーマ」として序論で述べられる問いに限定する見方もある 2. 「問いを育てる」という視点 リサーチ・クエスチョンは最初に立てたら終わりではない 研究進行中に当初とは異なる形に磨き上げ、「育てる」必要がある このプロセスを通じて深い洞察へ繋げる 3. 問いの形式と内容 疑問文形式で簡潔に表現することが推奨(疑問符付き) 主要な2つのタイプ: What(記述の問い): 「どうなっているのか?」実態把握が目的 Why(説明の問い): 「なぜそうなっているのか?」原因解明が目的 WhatとWhyは調査研究全過程で相互に繰り返され、意味のある答えに辿り着く 4. 問いの目的と関心 3つの基本的な関心事: 個人的関心: 調査者個人の興味に基づく問い 社会の関心: 実務上・実践上の問題解決に関わる問い 学界の関心: 新しい知識・技術の創造に関わる問い 社会の関心では、What/Whyに加えHow to(処方箋の提案)を加えた「2W1H」が有効 What(検査)、Why(診断)、How to(処方)は医療行為に例えられる 5. 研究プロセスにおける役割 初期段階だけでなく、調査・分析、執筆といった全プロセスで重要 草稿執筆過程で大幅見直しもある 「結果報告」(表舞台)と「経緯報告」(舞台裏)の両面で重要な役割を果たす 6. メインクエスチョンとサブクエスチョン 包括的な「メインクエスチョン」と、具体的に掘り下げる「サブクエスチョン」がある サブクエスチョン設定では研究対象や視点の絞り込みが重要 包括的で抽象的な問い(タイプI)から具体的で各論的な問い(タイプIV)への落とし込みが必要 7. 事実に関する問いと規範に関する問い 事実に関する問い: 「あるがままの姿」を捉える(記述・説明) 規範に関する問い: 「あるべき姿」を探求(倫理的価値判断を含む) 実証研究に適しているのは事実に関する問い 8. 問いの再構築と拡張 研究進行中にリサーチ・クエスチョンは再構築・拡張される 対象の拡張(新事例追加)や視点の拡張(新概念導入)を通じてより深い洞察を得る
0投稿日: 2025.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ<目次> 序章 論文のペテン≪詐術≫から学ぶリサーチ・クエスチョンの育て方 第1章 定義する~リサーチ・クエスチョンとは何か? 第2章 問いの内容を見きわめる~何について問うのか? 第3章 問いの目的について確認する~そもそも何のために問うのか? 第4章 「ペテン」のからくりを解き明かす~なぜ、実際の調査と論文のあいだにはギャップがあるのか? 第5章 問いを絞り込む~どうすれば、より明確な答えが求められるようになるか? 第6章 枠を超えていく~もう一歩先へ進んでいくためには? <内容> 大学生、修士レベルの論文を書くための問い=「リサーチ・クエスチョン」の立て方から論文を書いていくにあたっての考え方=「リサーチ・クエスチョン」の深化(進化)の流れを具体例を交えながら解いていく。ややくどい気もするが、わかりやすい本であった。
0投稿日: 2025.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ【琉大OPACリンク】 https://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BD09368556
0投稿日: 2025.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこれから実証研究に関する卒論・修論を書く学生の皆さん必見です。 これまでゼミや研究会で「この研究のリサーチ・クエスチョンは何か?」という質問を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。でも思い返してみると、そもそもリサーチ・クエスチョンが何かについてしっかり教えてもらった記憶はないような…。 本書は、リサーチ・クエスチョンとは何か、何について問うのか、そもそも何のために問うのか、といった研究の基盤となる問いに関して、実際のリサーチ・クエスチョンの例もあげながら具体的に解説している初学者必携書です。 また、卒論などで初めて研究に取り組もうとした際に、自分の研究の参考にしようと論文を読んでみたものの、あまりにきれいにまとまっていて自分は何から手を付けたらいいのかわからない、と思うこともあるのではないでしょうか。本書では、論文になるまでの調査と実際の論文とのギャップについても「論文のペテン」というキーワードのもとに解説しています。 論文という研究成果の形にする以前に、いざ研究を始めようとしたときに、何を意識したらよいのか、そこでリサーチ・クエスチョンはどんな効果を持つのか。こうした研究についての基礎的な問いに答える本書は、これから卒論・修論を書こうとしている方にはもちろん、ある程度書き進めたけど行き詰ってしまったという方にも、それまでの研究の再整理としておすすめの一冊です。 (ラーニング・アドバイザー/教育 SONE) ▼筑波大学附属図書館の所蔵情報はこちら https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/opac/volume/4228614
0投稿日: 2025.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
IMRAD=序論、方法、結果、AND考察 論文は、結果報告と経過報告の役割がある。 調査結果を伝えるために、あとから問いが変化している。 問う内容は、どうなっているのか、またはなぜなのか。これを組み合わせたものがリサーチクエスチョン。 なんのために問うのか=個人的関心、社会の関心、学会の関心。 仕掛品のリサーチクエスチョンを元に、セレンディピティを探す。 良い問いは、分割または絞り込みされている。事例を絞り込むまたは分析の枠組み、視点を絞り込む。 かつてはリサーチプロブレムがリサーチクエスチョンと同じくらい使われていた。
0投稿日: 2025.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログリサーチクエスチョンの考え方について可能な限り解きほぐそうとしている著作です。研究を構想するのに悩んでいる人たちにとっては大変役に立つと思います。 自分は博士論文の研究計画を検討している時に読み、考えるべきことがクリアになりました。
0投稿日: 2025.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログリサーチ・クエスチョンという言葉は研究をするものにとっては日常語のようなもので、自分自身も学生に対して「リサーチ・クエスチョンをしっかり立てなさい」とよく言うが、実際にはリサーチ・クエスチョンとは何かという問い自体に明確に答えるのは難しい。 本書は、社会調査研究に長年携わり、教育してきた著者による入門書である。 一般書ではないが、これから社会科学分野で卒論を書こうとする学部学生と修士課程の大学院生にとって必読の本だろう。
0投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。リサーチ・クエスチョンの育て方について、社会科学系の学問を専攻する初学者向けに、ここまで丁寧に解説した本はないのではないだろうか? 個人的な印象では、リサーチ・クエスチョンは「必ず一度は聞くけど、それ自体問われることはない」言葉と言える。なぜなら、リサーチ・クエスチョンそのものが「問い」なのだから、それ自体を問うということは意味がわからないことだからだ。 けれども、著者は曖昧に使用されてきたリサーチ・クエスチョンに真摯に向き合い、定義を与え、分類を行い、育て上げ方の解説を行った。 社会科学系の学問を専攻する初学者は、本書を読むことで得られるものは大きいと思う。 ただし、最後の第6章が、若干物足りなさを感じた。単に書き疲れたのか、あるいはまだ十分に考えがまとまらない中で書いたのかはわからないが、もし解説する機会があるならば、第6章に焦点を当てた本も書いて欲しい。
0投稿日: 2024.12.11
