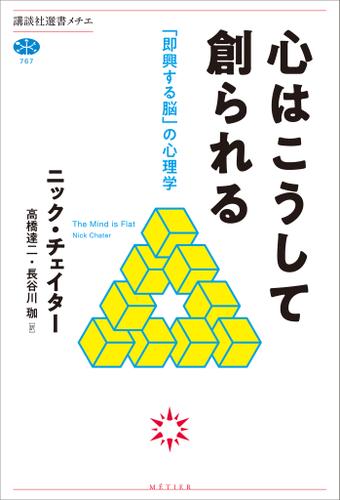
総合評価
(23件)| 7 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ心、人格、キャラクターは後付け…まあそうだろうね。ただ神の媒体、フィルター、パイプ、楽器としての個性はあると思う。
2投稿日: 2025.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ無意識は存在しないという、衝撃的な内容。 付随するこの辺の話は面白かった。 ・視覚の中心だけカラフルで実は周辺は白黒でぼんやりしている。 ・人間は一度に1単語、1つの形、1つの色しか認識できない。 ・五感から入力された物を過去の経験・記憶に照らし合わせて、即興で創造している物が意識。 ただ、いかんせん長い。どの章も結局、心の内側なるものは存在しないと同じ事を言っている。
1投稿日: 2025.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ〜だから、〜だ。例えば、雲ひとつない空だから、雨は降らないはずだ。雲ひとつない空は朗らかだ。笑顔も朗らかだ。創造主が朗らかな気分だから晴れたのだ。人が善行をすれば、互いに笑顔だ。人の善行は創造主を朗らかにし晴れさせる。 この推論が物語化、意味づけの正体ではないか。 この本が明らかにするのは、我々が意味づけをしながら世界を認知する生命体であるということ。それに加えて、斬新なのは「自らの身体的変化に対しても、何かしらの意味づけをして物語化する。そしてそれこそが、感情である」という仮説である。 ロールシャッハテストのような黒いインク。あれは、一度ネタバレすると、その形状にしか見えなくなる。これを外的な意味づけとして、物語化の基礎的なものだと考えるが、結局、黒いインクみたいな、断片的な刺激は内外にそこかしこ生まれ、それを結びつけて解釈し、自衛しているのが人間である。 難しい本を読んでやんわり分かった気になる。それは、分かる範囲で意味づけをしたギリギリの認知世界である。実はじっくり繰り返し読めば解像度は上がっていく。この直感的な認知が、荒い我々の感情物語の篩い分けに近い。 ー 心臓が早鐘を打っている、血液中のアドレナリンの量がこれこれである、呼吸が速くなっている。脳が体から受け取る知覚信号は、そういうかなり大雑把なものだ。しかしそれらは一体、何を意味しているのか?自分の内的状態についての知覚という経験もやはり、より広い文脈のなかに置いたときに意味をなす解釈によって左右されるのだ。つまりまったく同一の生理学的状態が、苛立ちという「気持ち」になり、嬉しさという「気持ち」にもなる。 ー いわゆる「頭」と「心」の衝突というのは、理性と感情の戦いなのではない。ワンセットの理性と感情が、もうワンセットの理性と感情と戦っているのだ。 我々は自らを物語として経験的に語るのみで、その内感受性により人格が知覚される存在である。身体がなければ、例えば内臓がなければ飢えは感じないし、満腹も、食い過ぎも感じない。安心も恐怖も感じない。それこそが感情である。
86投稿日: 2025.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ一般的に私たちが考えている「バックグラウンドで考え続ける」無意識というものは存在しない、という主張の本。つまり我々の思考や感情はその時その時に感覚器官からもたらされる情報と、記憶の蓄積から、脳が「即興的に」生み出しているだけ、ということだ。無意識なのはその即興性だ、というかそこ即興性が意識できない、ということ。「記憶」の解釈には踏み込んではいないが、バイアスやらスキーマのようなモノの見方も、解釈機関たる脳の「手癖」のようなものだ、と思えば納得できるかな。世界の見方を変えるには、やはりいろいろと新しい経験やら考えを記憶の棚に追加して、解釈の幅を広げるという地道な作業が必要なのだろう。「われら全てを無に引さらう永遠の創造、そんなもの、何になる?」
50投稿日: 2025.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ心は錯覚に過ぎないという非常に刺激的な言説。 その上で人間の即興性、柔軟性をむしろポジティブに捉えているのは斬新だった。 ただ原著が2018年ということで、AIの推論能力が超進化した現在、私は著者の言うような人間の独自性を確信できなくなってきている。 この後にNEXUS読んだら面白いのでは。
2投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
心はこうして創られる、というタイトル通りの一書。「心などなく、あるのは巧妙にストーリーを紡ぎ、何かを解った(知った)ように思い込ませる脳の働き」。 原題はMind is flat、心には奥行きも闇もなく、ただ表面を漂う、その時の気持ちのみ。 私がいままで自己啓発本や能力開発本を読んできたのと重なるところを列挙すると、 「本を読むとき目に入っているのはせいぜい1語。それを順に追いかけているにすぎない。その一語以外は視野にも入っていない。ページ全体が見えているように思うのは、脳が超高速で視覚画像をつなぎ合わせているから」…これだと速読法の根拠がひっくり返る。速読では、「ページ全体を写真を撮るように」頭に送り込む、としていた。 無意識の力の利用も同様。脳がそのことを考えていないときも無意識のレベルで、PCのバックグラウンド処理のように答えを探すわけではない。しばらく休んだあとに答えが見つかりやすいのはそのような理由ではない。もし、無意識が答えを運んでくれるのなら、難問が解ける割合は休憩の後に上がるはずだがそうなっていない。 同様に直感の正しさ、も単に過去の情報から目の前の事象と類似したものを拾い上げる能力が優れているだけ、ということになる。ユングのいう、広大な無意識や人類共通の記憶など幻想、ということになる。 それを一読しただけ受け入れられるかというと…今まで信じてきたものが崩された、ということ、なかなか受け入れられない。しかし…この本をもとに自分の思考を再構成すること、時間がかかっても必要なように思える。
1投稿日: 2025.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ心には意識・無意識といった区別よ深層心理といった深みなどなく表面的な振る舞いのみが全てであるという解説が書かれている。意識といった太古から人類が考え続けた事柄に関して心理学的にその本質をついている。身近な疑問から徐々に深いところに入っていき、疑問が順番に生じてくる点を順を追って解決してゆくので流れを追いやすかった。
2投稿日: 2025.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://allreviews.jp/review/6660 キーワードは、マインドイズフラット。深い深い無意識なんてものはない、脳は創造者、現在の思考や行動は緩慢であれ絶え間なく、再プログラムされている。一方で、認知学や心理学は、心には信念や欲望が蓄えられているという前提がある。このような、理路整然とした論証が、心理学である一方、脳の働きはニューラルネットワークによるパターン認識というこもわかってきた。 脳は、計算する内臓。情報処理者。 辻褄の合わなさと細部の欠陥は、フィクションの特徴のみならず、我々の性格の特徴でもある。
0投稿日: 2024.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ心は”即興”(ここでは瞬間的な感情に対する脳のはたらき?)の連続によって生み出されている。 この”即興”は、できるだけ思考や行動に一貫性を持たせること、「役柄(キャラクター)に徹し」続けることを任務としている。 我々が認知している深層心理や本当の自分などはなく、脳がその場で役柄に沿うように創り出す虚構なのだ。(要約) 興味ある章だけサラッと読んだだけだけど結構面白かった。場によって軸がブレてる人が容易に存在する理由にはうってつけの一説だと思った。
1投稿日: 2024.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024-06-09 心、のうち、理性に関する部分はなるほどおっしゃる通り。知性に関する部分もまあわかる。思考が一過性のもので、見えない何かが隠れているのは錯覚というのには説得力がある。 けれど、自己同一性に関しては全く納得いかない。フラットで一過性なものであると主張しながら、過去の体験を統合し変奏するって、さんざんその過去の体験は蓄積されないと言ってきたのでは?
0投稿日: 2024.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「深層心理」とか「本当の自分」とかなんてない、という主張の本。 今までの自分を振り返ってみると、「心は脳の即興」という筆者の主張がわかる気がするけど、だからこそ信念を持たなきゃならない、本当の自分に気づかなきゃならないと考えてきたので、信念までも脳の即興だって言われて、共感半分、疑い半分の気持ちで読み進めた。 第11章までは、要は脳は一度に1つのことしか処理できないよね〜ってことと、だから「深層心理」なんてあるわけないよね〜ってことが多くの実験結果を引用して何度も書かれていた。実験の話はたまに「その実験結果からその結論にいくの…?」と思うところがあったけど、筆者の主張は理解。 でもずーっと「じゃあ心って何?」という疑問が頭を離れなくてイライラしてたんだけど、最後の方にきてちゃんとそれに答えてくれてて、それがすーっと腑に落ちたので、すっきりした気持ちで読み終えられた。 「信念」へのこだわりとか「本当の自分」に気づかない鈍感な過去の自分も許せる。だってそんなものないとわかったから。下手な自己啓発よりもずっと自己肯定感上がるし、未来に期待がもてる気がするけど。
2投稿日: 2024.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ就活中に考えた「人生の目的」とか、流行中のMBTI診断とか、Strength Finderとか、本当の自分(の強み)を見つけよう、とか、全部疑わしく思えてくる。 本書に照らして言うならば、個性とかアイデンティティとか言うものは、今日まで生きた過程で得た経験の解釈(意味の押し付け)の中で最も馴染んだもの、程度のものであって、必ずしもそれらに基づき一貫した行動をする必要はない。 にも関わらず、どうして就職活動や転職活動では「あなたの軸は?」とか、過去から今、これからやりたいことへの一貫性とかを問われるのだろう? 思うに、わかりやすいストーリーなんか無くて、実際には都度都度の解釈で生きている、と言うことを、面接程度の時間で他人に説明することの難しさ(と言うか恐らく殆ど不可能)からきているのかも。 本音と建前ではないが、他人に対する自己紹介と、自分の意思決定との間の整合性なんて、考える必要もないと思えば、だいぶ楽になった。 そう言う意味では、就活生とか中高生とか、「本当の自分は何者なんだろう?」とアイデンティティに悩んでいるような人にこそ読んで欲しい一冊だ。
1投稿日: 2024.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ原題の「Mind is flat」のほうが内容を過不足なく表現している気もするが、まあ楽しい本だった。先に読んだ「言語は~」のほうは、言語のルールが即興ジェスチャーの伝統でしかないという話だったが、心もまた経験から判断される即興の場繋ぎでしかないとは。 部分しか把握できない人間が、意識できないレベルでの視点移動で全体を把握しようとし、そうしたトリックを意識それ自体は把握できず、ただ入力される感覚情報に頼るしかないなどなど、得心が行くとともに実に興味深い話ばかりだった。
2投稿日: 2024.01.18『みんな心は薄っぺら』
今年読んだ本の中ではベストの書だ。 「感動した」とか「泣けた」とかじゃなくて、せっかく一冊本を読むなら、こういう盲冥を照らすような書を紐解くべきだなと改めて感じた。 共著であった『言語はこうして生まれる』が面白く、訳者があとがきでも本書の紹介がしてあったので、興味がわき手にとったが、それでももっと話題になっても良さそうなのに、それほどでもないのはホント不可解。 強いて言えば、ちょっとタイトルが頂けないかな。 堅過ぎるし、ありきたりだし。 原題どおり『みんな心は薄っぺら』にすればと思ったが、ちょっと刺激が強すぎるか。 「心には”深み”も”奥行き”も”深層”もない。あるのは薄っぺらな表面だけ。心の奥に何かあるなんて信じてるのはオカルトですから、残念」なんて言ったら、自己意識を肥大させた読者の共感は得られんだろうなと思うけど、へたな心理療法にかかるよりよっぽど健康的だし腑に落ちるんだけど。 かつて話題になった『嫌われる勇気』は、本書だけで276万部発行され、しかも今も海外に読者を獲得していて、なんとシリーズ累計は全世界で1,000万部を超えるのだとか。 せめてその1/3くらいの読者を獲得してもバチは当たらないだろうに。 比較に出したからというわけではないが、無理に共通点を見つけると、両者ともどこに境界線を引くべきかという論点が通底している。 『嫌われる勇気』では、本来は他者の課題であるはずのことまで、「自分の課題」だと思い込むような承認欲求に縛られた生き方を否定するアドラー心理学を核として、「課題の分離」という考えを呈示している。 「ここら先は自分の課題ではない」という境界線を引き、他者の課題は切り捨て、自分の課題に集中しようと説いている。 一方の『心はこうして創られる』では、意識と無意識という従来の境界線自体を引き直す。 フロイト以来の精神分析で好んで常用されている、無意識という名の、水面下に暗く巨大な質量を秘めた氷山があるというメタファーなんて間違いだ、と。 そんな所に境界があるんではなくて、思考の意識的結果と、その結果を造り出した無意識のプロセスというところにこそ境界線があるのだ、と。 順に追っていくと、著者はまず、心の隠された深みの解明に失敗してきたのは理由があると説く。 そもそも「心には隠された深みがある」という発想そのものがデタラメだ。 心理療法、夢分析、何をどれほど試しても、人間の「真の動機」を取り出すことはできない。 見つけるのが難しいからではなく、見つけるべきものは何もないからだ。 心の内側の信念や動機や恐怖も、それ自体が想像の産物なのであり、その場でひねり出した自己解釈に過ぎない。 自分の知識や動機や欲望や夢についての私たちの説明は、実は薄っぺらな即興であり、事後的なでっち上げなのだから。 「人は自分の行動を説明するにあたって最終的な発言権など持ち合わせはしない。不完全な寄せ集めであり、どこまでも異論の余地があるという点で、本人の解釈と他人の解釈は何ら変わらない」 「私たちが自分や他人の言動を正当化したり説明したりするために語る筋書きは、細部が間違っているのではない。始めから終わりまで純然たる絵空事なのである」 こうなってくると行動の解釈の信憑性はどうなってしまうのか? 京アニ事件の裁判で、被告が事件の動機などに関して何を語るのかが焦点となっているが、どう考えたらいいのだろう。 検察は「犯行の動機は妄想だ」と主張しているが、著者の論に従えば、動機が妄想なのは被告だけなのかと問いたくなってくる。 困ったことにと言うべきか、我々の現実の人生も、小説などの架空のキャラクターの物語と大差ない。 主人公が何を信じ、どう行動するかといったことが創作であるように、私たちの信念や価値観も、その瞬間のうちに作り出されたもの。 内的な世界から生み出されてくるわけじゃない。 「思考というのは、創作作品と同じく、拵えたときに存在しはじめるのであって、その一瞬前にはどこにもない」のだ。 「心を覗き込む」なんて発想も誤りで、まるで自分の内側の世界をつぶさに調べることができるように考えてしまう。 しかし内観とは、内的世界の知覚ではなく創作だとすれば、内観する力なんてないし、そもそも内なる世界そのものが蜃気楼に過ぎない。 ただ我々は、自分自身の言葉や行動の意味をとるため、その都度リアルタイムで解釈をひねり出しているだけなのだから。 読者は小説の登場人物の隠された動機が行間に潜んでいるように感じているが、現実においても我々は、本人すらはっきりと把握できないような内的な欲望や動機に操られていると考えてしまう。
0投稿日: 2023.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間に深層心理は存在せず、脳がたった今処理した情報から過去の記憶に関連づけて「即興」しているにすぎない、心に深さはなく薄っぺらであるという内容。なんとか最後まで読み通したけど似たような記述や比喩が多くて斜め読みになってしまった。様々な図形を用いた実験の例は興味深かったけれど、筆者の主張に100%の説得力を持たせたかというと違う気がする……。最後の訳者の解説が端的にまとまっていて分かりやすかった。
1投稿日: 2023.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「なんじゃこの即興芝居人生」と思いながら生きてきたので「てか他の人も皆んなそうだよ Don’t worry ひとつずつ解説していくねー」と言われた気がして好き。この本。オススメ本。
1投稿日: 2023.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ無意識、深層心理は存在しない。 自分が何を感じているのか、認識しているのか。 脳のフィルターを通したものしか認識出来ないし、元になる情報がどのような解釈や変換をされたのか、過程を知ることはできない。 このラフな仕組みを持つことで今の生活が成り立っているのは不思議なことだ。
2投稿日: 2023.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「心の奥」なんてものは存在しないと言われると、「本当にそう言い切れるか…?」と疑ってしまう。そんな感じで、本書を読み始めた。冒頭を読んでいる間は、「なんだか言い過ぎている感じがするなあ」と思っていたが、読み進めていくうちに、「やはりこっちが正しそうだ」と説得された。 「心の奥」が存在しないことは、少し寂しい気もするが、むしろ存在しないからこそ、人間は変わっていけるし、クリエイティブになれるのだという、希望のもてる話であった。
1投稿日: 2023.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体的にイメージしにくい部分があり、やや理解に苦しんだが、脳は「心の奥」があるという錯覚を創り出しているのみならず、「心というものが存在している」という錯覚さえも創り出している。感覚情報のほんのひとかけらを解釈して意味付けした結果がその瞬間の意識となっているのみであって「心」と呼ばれるものはない と言うある意味衝撃的なセオリーだった。 以下、心(と言ってはいけないのだが)に残った言葉。 「喜びや怒りといった感情も、内なる深みから湧き上がってなどいなくて、人は自分の感情をその瞬間に解釈している。かつ、その解釈は、自分の置かれた状況(居合わせた人が浮かれているか怒っているか)のみならず、自分の生理学的状態(鼓動が速まっているか、顔が火照っているか)に基づいている」つまり、「感情というのは内側から自ずとほとばしり出てくるのではなく、そのとき置かれた状況に照らして、そのときの身体状態のフィードバックについて脳が作り出した、その瞬間の最良の解釈。つまり創作行為なのだ」と言う。 また、一人ひとりが類例なき存在である理由を一言でいえば、思考や言動を積み重ねてきた歴史の限りない多様性のゆえにである。脳の働きは原理原則にではなく前例に基づいている。思考のサイクルの新たな一回転が、そのとき注意を向けている情報の意味をとるのは、関連した過去の思考の残滓を手直しし、変換することによってである。そして思考のサイクルの一回ごとの結果は、それ自体がまた未来の思考のための、いわば加工用の素材となる。 そして想像の飛躍は人間の知性の正に核心である。
1投稿日: 2023.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後の方は畳みかけられて少し主張がぼやけたが、全体として脳の即興であるという筋は通っているし、実感とも近い。
1投稿日: 2023.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ【はじめに】 「心には隠された深みなどない」というのがこの本を貫くテーマである。原題は”The Mind is Flat”。心には深みなどなく、表面しかないということを示している。ついでに言うと、副題は”The illusion of mental depth and the improvised mind”。心とは即興で作り上げられるものであり、それを支えているような何か深遠な仕組みなどはないということだ。 「心の秘密は、その隠された深みにあるのではない。過去という主題曲(テーマ)のもとで現在という即興曲を奏でる驚くべき創作力にこそ秘密がある」 例えば、真の動機は何かと探っても、それは見つからない。なぜならそれを探るのが難しいからではなく、もともと何もないからだというのが著者の主張だ。私たちの心の中に内側から送り出すような「内的な思考世界」は存在しない。思考というのは、こしらえたときにはじめて存在しはじめる。内観というプロセスは、何かを知覚しているのではなく、創作するプロセスであり、その解釈の営みなのだ。その能力はそれとして驚くべきものであるのだが。 本書では、心のしくみについての一般的に広まっている誤解を一掃する。その上で、いかにして心が即興曲を奏で続けているのかのしくみを説明する。 【概要】 まず著者は、トルストイの小説のアンナ・カレーニナを紹介する。彼女には小説世界においてキ生き生きとしたャラクターはあるが、言うまでもなく本当の内面などは実在しない創作の世界の人物である。しかし、小説の中の主人公と同じように私たちは自分自身が創り出すキャラクターであるとも言えるのである。内なる知覚世界という幻想は存在しないのだから。 視覚について見てみるとわかりやすい。本書でも視覚に関わる実験や事実が数多く紹介されている。実は、われわれの眼が色を感じることができるのは中心窩の近辺のごく一部であり、また一度にはひとつの色しか感じることができないという。つまり、視野のほとんどにおいて色を感じていないのだが、認識上では視野全体において鮮やかな色があるように視野を構成している。また文字を読んでいるときも一度に見ているのは十文字から十五文字程度でしかないのに、われわれはほとんどページ全体に目を配っているように感じている。 また、著者は、内観のいい加減さについて心の中で想像する虎の例で説明する。われわれは活き活きとした虎を心の中で想像することが可能であるように思う。しかし、その虎の体の縞がどうなっているのか、足の縞は、さらには顔の縞はどうなっているのかを聞かれると実際には具体的な虎を思い浮かべていたと言えないことに気が付く。 感情というものも、身体の生理学的状況と社会的文脈を推論解釈したものであって、感情が生じたことによってその結果として身体に影響が生まれるわけではない。有名な吊り橋実験では、心拍数の増加を恋愛感情の高まりと解釈することで相手を好ましく思う われわれがいかに解釈するのが上手なのかはいくつかの心理実験でも明らかになっている。二人セットになった異性の写真を複数セット見せてどちらが好みかを選んでもらった後、それぞれなぜその写真の異性の方が好ましいのか理由を尋ねる実験で、ときどき選ばなかった方を指してなぜこちらの方を選んだのかを尋ねると、ほとんどの場合に自分が別の写真を選んだとは思わずに、過去に行った選択を正当化するべくその理由をでっちあげるだ。 選んだ理由をでっちあげる事例としてさらに衝撃的な実験として、ガザニガの分離脳患者の実験の事例が有名である。右脳に積もった雪景色を見せ、同時に左脳にニワトリを見せた後、右脳に見ている絵と合致する適切な絵を選択してもらう実験だが、右脳が選んだシャベルを左脳が選んだ理由をニワトリから全く疑問に思うことなく「ニワトリ小屋を掃除しないといけないから」という理由をでっちあげた。われわれの脳は、目の前の整合性が取れるように解釈を調整することとそれを信じ切ることに長けているのである。 以上のことは、心が即興で創作されていることのひとつの証拠であるのだ。われわれは思考や理由付けを紡ぎ出す速さと滑らかさによって、それが自分の内側にずっとあって、行動や発言の根拠としてゆるぎないという感覚を持つ。しかし、実際には行動があって後に思考に上るその動機の解釈があるのだ。 著者は、心の原理として、次のようにまとめている。 第一原理: 注意とは解釈の過程である 第二原理: 感覚情報について意識的に経験できるのはその解釈のみである 第三原理: あらゆる意識的思考は、感覚情報へと意味のある解釈を施すことにかかわっている 心は常にその瞬間に作り上げられている。繰り返すが、心があって、それによって思考したり行動したりするわけではないのだ。ましてやフロイト流の無意識など存在しないし、バックグラウンドでの思考などはどこにも存在しないのだ。 「私たちの直観とは裏腹に、意識そのものが愕然とするほどすかすかなのだ」 【まとめ】 著者のテーゼ”The Mind is Flat”であり、意識というのは後付けの解釈である、というのは最新の脳神経科学の知見の主流となっているように思う。少し前の本になるが、デヴィッド・イーグルマンの『意識は傍観者である』という本のタイトルにも取られた主張は、同じことを言っているとも言える。トール・ノーレットランダーシュ の隠れた名著『ユーザーイリュージョン』でも同様に意識というものが後付けの解釈でしかないということを強調する。 意識の主観性というものが、現代における先入観であり、科学的見地からは誤謬のひとつとして受け入れられるようになるのではないだろうか。それは、われわれが昔の人が天動説を当然のものとみなして地動説を受け入れることを拒否し、そもそもそうする理由もわからなかったという歴史的な事実を見るように、後世の人から見なされることになっても驚かない。われわれが今、意識を所与のものとして見ているさまを、将来に生きる人は、古く誤った考え方として見るようになるのかもしれない。そうなったときに社会や道徳や法はどのように変わるのだろうか。宗教がその座を奪われたときに社会と道徳と法が大きく変わったように、「人間」や「意識」というものへの認識が大きな変革を迫られた場合に何が起きるのか。過去の歴史上、大きく変わったことがあったことから、今後も何も変わらないという保証は当然のことながらないのだから。 ------ 『意識は傍観者である: 脳の知られざる営み』(デイヴィッド・イーグルマン)のレビュー https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4152092920 『ユーザーイリュージョン―意識という幻想』(トール・ノーレットランダーシュ )のレビュー https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4314009241
4投稿日: 2022.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ【書評】香山リカ氏が「ここ10年で最も衝撃的」「人生の意味を失うほどの破壊力」と語る1冊|NEWSポストセブン(2022.10.21) https://www.news-postseven.com/archives/20221021_1802935.html?DETAIL
1投稿日: 2022.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ直観的な理解とそぐわないことが、例えば物理学とか諸々とあり、人間の心に関する理解も同じ。視覚の例がわかりやすいが、人間が知覚してるのはほんの一部分で、あとは脳がさもいろいろなものを同時に見てるかのように補正している。心は平坦で探るべき深みなどなく、人間の内面世界は脳が都度即興しているものに過ぎない。 自分の感情も、生理的状態をその時の文脈で解釈したもので、好みですらごとに臨んだその時に捏造している。脳の働きは原理原則ではなく前例に基づくもので、思考のサイクルの残した痕跡の積み重ねである。
1投稿日: 2022.08.10
