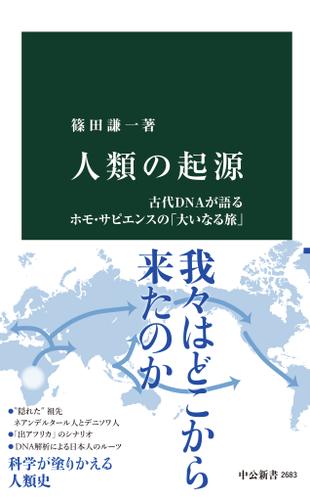
総合評価
(71件)| 13 | ||
| 23 | ||
| 27 | ||
| 4 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人類の起源(人類誕生からいかに人類が世界に拡散していったか)をミトコンドリアDNA、Y染色体、ゲノムから読み解いていく。まあ、面白いと言えば面白いが、もう少し遺伝子についての説明(特に中身で出てくる地域的、民族的、個人的な遺伝情報の差異の説明)があった方が内容が頭に入って来る。遺伝情報の差異をグラフだけで見せられても何なのか理解できない。
1投稿日: 2025.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログそもそも化石からゲノム分析が出来るというのに驚き。しかしあまりにも複雑すぎて読むのに時間がかかったわ。 「それぞれの個人はホモサピエンスという巨大なネットを構成する結び目の一つ」という表現、腑に落ちました。宇宙からものが見えている方の言葉ですね。 ちょっと違うかもしれないけど、福岡伸一さんの動的平衡、水の渦の例えを思い出しました。 分子生物学触ってるとこうなるのかな?
0投稿日: 2025.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ後半難しすぎる。 知りたかったとこだけ読んで終わった感じ。 科学の発達(DNA分析)でこれから先、今までの定説が覆ることもあるだろうし、より定説が詳細になる可能性だって秘めている。 いつの日か解明されることを願って。もっと詳しくなったら再読しよう
0投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
DNA解析技術の画期的な進歩により従来の説はひっくり返り、何が正しいのか分からなくなっているということ。 人類の起源はホモ属とすれば200万年前、ホモサピエンスとすれば20万年前となる。また今は「人種」という言葉は使わない。 ホモサピエンスが6万年前以降にアフリカを出た、という説も、今となっては怪しげのようだ。
0投稿日: 2025.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログいま話題の国立科学博物館・篠田館長のご専門は分子人類学であり、DNAなど遺伝子分析から人類の進化史を探る研究をされてきた。昨年のノーベル医学賞ではOISTのぺーポ博士が選ばれたように、遺伝子シークエンスによる我々のルーツ研究は日進月歩で発展している分野だ。 驚くべきなのは、ネアンデルタール人やデニソワ人といった絶滅人類とも交配し、現在の我々の遺伝子にもその数%の痕跡が認められることだ。そしてホモ・サピエンスには約30万年前と約10万年前の二度、出アフリカしたと考えられ、初期拡散は約20万年前には失敗に終わった。つまり最初は、他の人類との競争に敗れたのだ! この辺りの研究成果と、ハラリ氏の『サピエンス全史』等の考察を組み合せると、出アフリカ後の中央アジア地域の重要性に気づく。いわゆる肥沃な三日月地帯と呼ばれる、メソポタミア〜エジプト文明に至る農耕や牧畜の起源とされる人類社会揺籃の地において、ホモ・サピエンスが人口を増加させていった。それが他の人類を吸収・根絶させながら拡散する原動力となった仮説が浮かんでくる。 翻って現代の国際社会においても、この中東やウクライナを含むユーラシア大陸中央部は、食糧やエネルギー等の人類社会における最重要地域である。そして残念なことに、度重なる戦争によってこれら人類の進化史を記すような貴重な遺跡や化石資料が失われている状況でもある。人類はどこから来たのか、そしてどこに向かうのか。世界の中心はいまも混迷している。
8投稿日: 2025.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ著しい発展が日進月歩で進む人類の進化史は、今最も注目を浴びている学術分野の一つと言って差し支えないだろう。本書はホモ・サピエンスがいかに拡がり、そしてどのような集団を形成したのかを詳述している。 DNA配列の変異を追い、集団の近縁を知ることができるということを、多くの具体例やルートと共に検証していく過程にワクワクする気持ちを抑えられないほどに知的好奇心を刺激させられる。 日本史や世界史においての文明やクニの興りは、集団の移動の歴史とも捉えることができることは、いかに断片的な歴史認識をしていたかと考えさせられる記述が多く、科学と歴史の融合が非常に心地よく文に編まれている。 文理融合型の学びという例えが正しいのかは分からないが、双方からの知的欲求に耐え得る素晴らしい一冊である。
9投稿日: 2025.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学生の時に教養科目の中で考古学関連の講義を受講し、非常に面白かったことを覚えている。当時は2006年発売の書籍を基に講義をしていたが、そこからどれくらい研究が進んだかを知りたく、この書籍を読み始めた。 当時はネアンデルタール人はホモサピエンスと交雑することなく絶滅した、が有力であったが、それが覆されていることを知り、また、デニソワ人という、遺伝情報を基に定義されている人類が登場していることも驚いた。 書籍の中では人類の進化の概要を大きく説明したあとに、各大陸内の移動や交雑の状況を説明しているが、昔考えられていた内容とは比べ物にならないほど複雑な動きがあったことが説明されており、まだ発展途中の分野だと改めて感じることが出来た。 また、これまで人種(この言葉の使い方は怪しいがあえて記載する)の移動、文化の遍歴というのは、大体重なるモノと決めつけていたが、どうも「農業」という大きな括りでさえそうとは限らない、ということがわかりつつあるようで、今後の研究が面白そうだと感じた。
1投稿日: 2025.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・100万年前以降、まずホモ・サピエンスがネアンデルタール人とデニソワ人から分離。43万年前以降にネアンデルタール人とデニソワ人も分離。 ・遺伝子は設計図で、設計図に書き込まれた文字がDNA。DNAは意味のない部分がほとんどで、タンパク質を記述しているのは2%にすぎない。ゲノムは人ひとりをつくるための遺伝子の(最小)セット。 ・子どもは両親から遺伝子を半分ずつもらうが、ミトコンドリアDNAは母親だけから子に、Y染色体は父から息子に伝えられる。 ・ヨーロッパでは4万年前に中東の狩猟採集民が広まって旧石器時代が始まる。旧石器時代が終わる1万4000年前にも中東から狩猟採集民が進出している。(新石器→青銅器→新石器) ・中東で農耕が始まったのは1万1000年前で、ヨーロッパ南西部では最終狩猟民の一部がアナトリアからの農耕民によって周辺に押しやられた。 ・4900~4500年前に現在のウクライナを中心に牧畜を主体とするヤムナヤ文化集団がヨーロッパに進出。 ・一度目のペストは542~543年に東ローマで起こる。二度目は1346~1353年にヨーロッパで大流行したもの。三度目は1894年に香港で。 ・BC8c~BC2cにユーラシアのステップ地帯を支配したスキタイは遺伝的に異なる集団の連合体(牧畜民、農耕民、狩猟採集民)。BC3cの匈奴は東アジア集団とスキタイの混合。4c~5cのフン族。 ・弥生時代=弥生土器+水稲耕作+金属器。水稲耕作は長江中流域から伝わったものだが、青銅器の源流は北東アジア。
1投稿日: 2025.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ2025-01-01 Youtubeで著者のインタビューを見て読む DNA解析で判明したことは多いが まだまだわからないことは多い 人種間の差より個体差の方が大きい
2投稿日: 2025.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ近年のDNA検査の充実を基に、アフリカで生まれた人類がどのように移動し交雑していったか、日本人とは何か、など、最新情報が平易に語られ非常に分かり易い。
5投稿日: 2024.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
おもしろかった!!!! 専門的な内容ですが平易な文章でかかれていて毎晩すこしずつ、たのしくよみました。 超俯瞰的な規模で人類をみてみるとほんとうに人種なんて些細なものだなとかんじました。 ただ興味深くおもしろいだけの本ではなく、ただあたらしい知識を得られるだけの本でもなく。 人類間にいまだ根強くある差別について、人類の起源をたどるという形で一石を投じるような意義のある本だったと思います。 よむことができてよかったです。
1投稿日: 2024.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
新書大賞第2位ということで手に取ってみた。 以前は古人骨からミトコンドリアを取り出し分析することしかできなかった(十分すごいと思う)。しかし科学の進歩に伴い、21世紀になってから古代ゲノム解析が可能になった。古代ゲノム解析によって古人骨のかけらや便などからも多くのことがわかるようになった。それは性別や性別だけではなく食生活から集団の規模まで。それらの情報を集めることで人類の起源(どういった流れでホモサピエンスが世界展開を成し得たか)を読み解くのが本書である。 古代ゲノム解析によって非常に多くのことが解明できるというのは衝撃だった。特に遺伝的特徴を共有している集団と言語的集団が相関関係にあるというのは私にとって新しい発見だった。現代のグローバル社会ならいざ知らず、太古の昔であれば言語や文化を共有していると婚姻するのは当たり前といえば当たり前なのだが。 種の定義として「自由に交配し、生殖能力のある子孫を残す集団」とある。私もこの理解だったが、ではホモ・サピエンスとネアンデルタール人が別種である根拠は何なのだろう?交配は限定的だったから別種ということなのだろうか?また、アメリカ大陸に農耕が伝わった方法に関してもよくわからなかった。ベーリング陸峡を経てアメリカに渡ったのは狩猟採集民だよね? 内容は非常に濃密で興味深かったのだが、正直なところ私には少し難しかった。難解な内容が簡潔にまとめられているのだろうが、淡々と根拠と結論が提示されていくだけで、教科書を読んでいるような感覚になった。さすがは中公新書というべきか。予備知識があったりすればもっと楽しめるのだろう。 終章には古代ゲノム解析の結果を悪用し、人種や民族を差別することに対する警鐘を鳴らしていた。ここ最近読んだ『なぜ事実は人の意見を変えられないのか』でも人の行動の80%以上は共通しているとあった。人は皆そんなに変わらない。仲良くしていけばいいのにな。
3投稿日: 2024.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログネアンデルタール人の研究で成果を挙げた科学者が、2022年のノーベル生理学・医学賞を受賞したというニュースがありました。 DNA解析技術が、古代人さらには人類の起源についての研究に、大きな革命をもたらしていると聞いて、興味を持っていました。 そんな中、日本人著者が書いたこの新書が出版されていることを知り、アウトラインでも理解できればと思い、読むことにしました。 本書は第一章から第七章、および終章で構成されています。 序盤の第一章、第二章は、現代人:ホモ・サピエンスが、どのような進化の経路をたどって誕生したかの説明 古代人の骨がなくても、その古代人が住んでいた場所の土壌で、DNA解析できる場合があると知って、驚いてしまいました。 これらの技術によって、(まだまだ分からないことが多いながらも)従来の説を覆す新発見が続いているのだと、理解しました。 第三章は誕生の地、アフリカ大陸で、第四章はヨーロッパで、ホモ・サピエンスがどのように、広がっていったのかについて。 アフリカ大陸の中にいた間に、複数の系統が生まれ、離散と集合を繰り返していたのですね。 それだけ、アフリカ大陸以外に進出する前に、長い年月がかかったのだと理解しました。 ヨーロッパにおいても同様で、進化が一方向に直線的に進むのではないということを学びました。 第五章は、アジアさらには南太平洋への進出について。 第六章は”日本人“の起源について。 日本人集団の成立については、従来から言われていた通り、農耕文化の伝播が大きく影響している。 しかしその経路は、考えられていたよりも複雑なのだと、理解しました。 沖縄と北海道の文化の変遷も、興味深く読みました。 第七章は、アメリカへの進出について。 終章は、これまでの研究から何が見出されたか、それをどう活かすかについて。 アメリカ大陸へのホモ・サピエンスの進出は、従来考えられていたよりも前に始まっていた。 しかしその後、地球の気温変化により停滞を余儀なくされていた。 ここでも、進化が一方向には進んでいかないこと、時間がかかるのだということを、学びました。 読み終えてまず、新しい技術によって新たな知見が見出されていること、その中には、これまでの常識や定説を覆すものが含まれているということに、大きな可能性を感じました。 著者も書いているように、まだ発展途上の研究なので、さらにわかってくることも多くありそうですね。 まだ、古代人のデータ解析が進んでいない地域のデータも多いようなので、この分野の本は今後もチェックして、最新の知識を得ていきたいと思います。 .
1投稿日: 2024.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ現世人類(ホモサピエンス)がいつ発生して、どの様に地球上に広がったかを最新の研究に基づいて説明した本です。 元々興味があった分野の最先端の情報が紹介されており、時間を忘れて読み耽るほど面白かったです。出アフリカ後の人類は様々に枝分かれして、現在の形質を獲得したという漠然としたイメージを持っていましたが、集散離合を繰り返して現人類が形成されたという話は、今まで持っていた知識が如何に単純化されすぎたものなのか思い知りました。 また、本書に記載されてることが広く知られることは、社会的な意義も大きいと考えています。特に以下の事実についてより広く世の中に認知されるべきではないかと強く思いました。 ■現代人類は全員、遺伝的に99.9%同じである。 ■遺伝的な距離(差異)は、異なる民族間よりも、同じ民族内の個人間の方が大きい。 ■そもそも「民族」や「人種」といった概念は、科学的に定義できない。 民族や人種に自身のアイデンティティを求めるのは全く悪いことではないと思います。ただ、それは科学的な定義ができない曖昧な概念であると知ることは、民族や人種という考えがもたらす社会的な対立を避ける為に重要だと思います。決して大げさではなく、本書の内容が世に広まることはそういった社会の中の軋轢を緩和する一助となるのではないでしょうか。
1投稿日: 2024.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ安宅先生(慶応大教授)お勧めの本。 次世代シーケンサーによってゲノム解析は、急速に発達している。2020年代の最新の研究に言及されている点、これからの展望にも触れられている点など、とても興味深く良かった。 我々ホモ・サピエンスは単独で存在してきた訳ではなく、今までに様々に他の種を取り込みながらここまで来たのだと分かった。 また、ゲノム解析が進むことでどのように人類が移動してきたのかが分かってきて、歴史学や言語学、考古学など、様々な分野に影響が出てくるであろうとこは明白であり、非常に興味深い。
1投稿日: 2024.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ最新のDNA解析で古代人のゲノムを解析し、人類の進化をよりクリアに紐解きます。ホモサピエンスは一本道で進化したのではなく、ネアンデルタール人と交雑したり、たまたま出会った遺伝子ミックスが異なる人類と交ざったりと紆余曲折を経て進化してきたのです。
1投稿日: 2024.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代ゲノム解析にもとづく人類の進化史とホモサピエンスの拡散と集団の成立史。 ホモサピエンスという視点から民族を考察した場合、そもそも民族集団の成立が数千年前と人類史から見たらごく最近であり、また、その集団内の遺伝的な性格はそれぞれに違い、遺伝的な性格を変化させていることから何々民族が優秀だとか劣っているとかはナンセンスであり、将来は他集団との混合で民族が生物学的な実態を失っていくとの指摘はなるほどと思いました。 ホモサピエンスのゲノムは99.%が共通で0.1%に姿形や能力の違いの原因となっている変異があることからだが、その大部分は交配集団の中に生まれるランダムな変化であるとの指摘にもそうかと納得でした。 ゲノム分析により人類、文明や民族の認識が広く変わっていくのだろうと思いました。
1投稿日: 2024.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログアフリカでホモ・サピエンスが誕生し、生物の進化みたいに、直線的に世界に広がっていったというイメージでしたが、そうではなく、各地に発生したホモ属との交雑を経て、滅んだ種族もある中で今日のホモ・サピエンスが世界に広がったとのこと。そう言われれば、その方が自然。交雑の中で一番残っている遺伝子がホモ・サピエンスということなのでしょう。研究が進むにつれどんどん真実がアップデートされていく分野なんですね。世の通説はあまりに単純化されている気がします。本書は学術度が高く素人には多少しんどかったです。
1投稿日: 2024.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代の人間の起源をゲノム解析から明らかにしようとしている研究の成果がよく解り、驚かされます。ただ、この研究の最も価値ある成果とは、民族や人種に優劣はなく、もとを辿れば皆1つだ、ということ。それは世界平和に科学でアプローチしようとしている、と私は感じました。是非、この研究がさらに進歩するとこを祈ります。
1投稿日: 2024.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類の起源や移動について、化石の骨格や年代から推定する20世紀の手法に変わり、近年のDNA解析によりわかってきた事実を詳細に書き記している。 のだが、ゲノムからわかる人類の交配・進化・移動が複雑すぎて頭がこんがらがった。しかもサンプルがまだ足りないときているので、研究はまだまだ続く。 ものすごい研究であるのはわかるが、ちょっとした興味本位で読んだためカウンターパンチを食らってしまった。 現代人のゲノム解析をして、ルーツを見ていたのは面白かった。
12投稿日: 2024.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人類の起源をDNA解析による研究をわかりやすくまとめている内容 PCR法などが進み DNA解析が進んできており 恥ずかしながら 私が学生時代に学習した内容は古くなっている サヘラントロプス・チャデンシスはなんとなく知っている程度である デニソワ人とネアンデルタール人の関係は面白そう また、その中で交雑が行われているということは驚きだった
1投稿日: 2024.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ遺伝子から人類の起源を追うだけではなく今の私達というのはあらゆる場所、時代の人間の遺伝子が複雑に絡み合っている。 それを通じて今の人種という区分け、生じる差別には少なくとも長期スパンで見ると全く意味の無いものだということを伝えてくれる大事な本だと感じた。 残念ながら私はこういう方面の知識が詳しく無いので理解せずに読んでた部分もあるけど、それを通しても今の差別問題に対して新たな方法を提示してくれるのかもって希望が見えた気がした。 できるなら読める人は読んだ方がいいかもしれない…それくらい新しい視点を与えてくれる本。
1投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログゲノム解析など新しい技術のおかげでこの10年でだいぶ様相が変わってきている。5年後はもっと新しいことがわかるのだろう。長生きするのが楽しみになる。
4投稿日: 2024.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近のDNA分析によって人類の起源や日本人の起源、成立の過程について、これまでの定説が覆されるケースも出てきていることがわかった。 この著者の方は、断定せずにこうこうこういう理由でそうじゃない可能性もあるよと正直に書かれているところに好感。結局まだ何にも分かってないのねと残念ではあるが、サンプルの少ないにも関わらず、とても偏った見方で自説を言い切っている本もあるから、ちゃんと事実だけから判断してそう解釈できるのか見極められているのか怖くなる。言い切ってくれたほうがわかりやすいのだろうけど。 それから、この本にも新たな文化とかが自然的に産まれたと解釈するより渡来した人がもたらしたと考えるほうが正確という記述があったが、何故なんでも渡来した人がもたらしたと考えるのか不思議でならない。最初に生まれた地域はあるのだし、交流関係なく同時に生まれることもあるだろうし。昔からそこが疑問。
1投稿日: 2024.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いけど,興味と基礎知識がないとちょっと読みにくいかも。 絶滅した人類の話、現代人の各集団の近さなど、テーマ自体は興味のある人が多いだろうけど、今解明されていることから判りやすく現生人類の形成史を説明、、、という一般向けな読み物によくあるパターンとはちょっと違う。 むしろ、どういう研究の結果から今の定説に至ったかを丁寧に解説している感じで、学問史に近いかもしれない。この分野の最先端の研究手法など知りたい人にはすごく良いと思う。
1投稿日: 2024.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ小中でかつて習った人類の歴史が、今や覆されてる、とは聞いていたが、こういうことだったかとわかった。 サルからヒトへ、一直線というか枝分かれしながら進化してきたイメージだが、ネアンデルタール人と、分岐後も交雑してきたとのこと。ゲノム解析がいかに強力か。 内容自体は、科学用語も多く、流し読みは難しい。新書なので、一般向けに解説されている。
1投稿日: 2024.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログDNA解析によって人類の古代史研究は進歩を遂げている。ミトコンドリアDNAを中心した研究があったのは昔から知っていたが、核のDNAの解析が2010年代から行われるようになり、人類史の常識は大きく変わっていった。その成果の一つが現生人類はネアンデルタール人等の別種の人類と交雑していて、その遺伝子の一部を引き継いでいること。 日本人の起源として語られる縄文人と弥生人の二層構造モデルについても、縄文人や弥生人の遺伝的多様性を単純化し過ぎているということが分かった。 ただ、本書を読んでも、人類の進化の全体像を理解するのは難しかった。
3投稿日: 2024.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ何が衝撃かって、おそらく歴史学とか言語学とか(はたまた文化学かも)は根本から覆ることになるだろうってことです、DNA解析みたいなことは。それくらいの物的証拠を見出せるんですから。例えば昔よく聞いた縄文・弥生の人たちの違いに関する考察って最早素朴な素人的意見としか思えませんもの。 しかし、いやぁ、ヒトって太古からはるか遠くに動いているんですねぇ。
1投稿日: 2024.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ2022年のノーベル医学・生理学賞を受賞者したのは古遺伝子学の創始者、スバンテ・ペーボさんだったことは記憶に新しい。ペーボさんの研究はシベリアのデニソワ洞窟で見つかった古人骨のDNA分析から、未知の古人類「デニソワ人」を「発見」した。 そんな、今最もホットな科学分野である人類史の最新情報を、本書はできるだけわかりやすく(少なくともこういった分野に関心がある人たちに対して)、嚙み砕いた言葉で丁寧に伝えてくれる。刊行から1年が経ち、時の流れとともに更新される情報も少なくないであろうことを差し引いても、今すぐに、手っ取り早く読める、「人類の誕生から拡散の過程、そして、DNA遺伝子学が描く未来」までを解説した入門書としては、現時点では最良の本ではないか。こんな内容の濃い本を1000円ちょっとで買えるなんて、本当にありがたい。著者の言葉の選び方一つにしても、そのお人柄と卓越した知性をうかがい知ることができる。まだまだこれからの科学分野、過去の定説がいくつも覆り、これから先も、新発見や研究結果が発表されて人類史がどんどん書き換えられていくことだろう。なんと、わくわくする未来だろうか。 宇宙の秘密を解き明かす量子力学と、我々人類の足元を照らす古代ゲノム研究、我々はどこから来て、どこへ行くのか。2つの科学分野の最新情報をこれからも刮目して見守っていきたい。
1投稿日: 2024.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ化石からゲノムの分析が可能になり、人の起源は10年前とは全く違ったことになっている。 ミトコンドリアDNA、Y染色体の分析などにより、文化や文明の伝播まで推測することが可能になっている。もちろん全てが明らかになったわけではなく、未解明なところもたくさんあるのだが。 いやもう、圧倒。子供の頃勉強した教科書の知識なんか、それにしがみ付いていては寧ろ誤解しか生まないのかあ。 具体的に、どこからどう進化してとか、詳細は殆ど頭に残っていないが。 亡くなった後に化石で見つかるのもあれなんだが、数千年、数百万年後に、どこどこで交雑したとか、何喰ってたとか、近親婚だったとか、噂されると思うと恥ずかしゅうて堪らん。
1投稿日: 2024.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ原人、旧人、そして、現生人類、すなわち、ホモ・サピエンスがどのような系統や経緯を経て産まれてきたのか、あるいは、ホモ・サピエンスがどのように世界中に散らばっていったのか、といったようなことについては、少し前までは発掘される遺跡や人骨の形態的特徴をもとに行われていたが、人骨を含む発掘物のDNA鑑定・ゲノム解析をすることによって、より正確に、より詳細に、物事が分かるようになってきた。すなわち、DNA・ゲノムを調べるという技術が確立されてから、学問の方法論が大きく変わったのである。 本書は、古代DNA研究により明らかになりつつある、人類の足跡を、明らかになっている範囲で説明したものである。テーマとしては壮大で興味深い。ただ、説明が詳細に渡り、また、学問的な正確さをも確保しようとした記述なので、なかなか、簡単に筋が頭に入りにくい(要するに読みにくいということ)。もう少し、「かいつまんだ解説」「素人に分かりやすい説明」があると、もっと面白いのにと思った。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ここからは、全く別の話 ブグログには、いくつかの統計的機能が備わっているが、それによると、私の書いた感想数は、いつのまにか2000を超えたことになっていた。我ながら、よく書いたものだと思う。 ダッシュボードによれば、私の「ブグログ歴」は、今日(2024年1月20日)で、4564日となっている。12年と180日程度なので、「ブグログ歴」が始まったのは、2011年の半ばという計算になる。ただ、私は、既にないブログ「たなぞう」から「ブグログ」への移転者なので、実際に感想をブログに書き始めたのは、もう少し前のことになる。最初に書いた(あるいは、少なくとも初期に書いた)感想は、関川夏央の「汽車旅放浪記」だったような気がする。それの出版は2006年6月、私が感想を書いたのは2007年1月6日のことだという記録が「ブグログ」に残っていた。すなわち、今から17年前のことになる。 17年かけて2000冊の感想を書いたということは、1年間に約120冊弱の感想を書いたことになる。これも、我ながら、よく続いたものだと思う。 以前はメモ書き程度の感想しか書いていなかったが、最近は、少し時間をとって丁寧な感想が書ければ良いな、と思っている。感想を書くために、メモをとったり、少し読み返したりすることで、そうしない時よりも、本をよく読めたような気になったりもする。 1冊の本を読む時間は、本の長さによって全く異なるが、仮に感想を書いている時間を含めて1冊読むのに4時間かかっているとすると、2000冊で8000時間。8000時間を24時間で割ると、約333日。1日眠らずに24時間本を読んでいたと仮定して(そんな仮定は実際には成り立たないが)この17年間のうちの1年間程度は、朝から晩まで本を読んでいたことになる。それは、自分にとっては、とても大切で楽しい時間だったわけであり、あらためて、本を読むことが好きで良かったなと感じる。
23投稿日: 2024.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログDNAをたよりに、まだ人類アフリカから世界へ拡散した時代の事が分かるなんて、本当に科学の進歩のおかげです。しかも、超昔なのに骨が無くてもかつて住んでいた土壌からゲノムが採取できるって心底驚きでした。 それにしても、ネアンデルタール人ってどんな人たちだったのでしょうか。脳容量が人類より大きかったらしいですが、発達していたのは視覚に関わる後頭葉部分で、思考や創造性を担う前頭葉が発達した人類とは異なっていたそうです。興味が尽きないですね。
1投稿日: 2024.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代人のDNAなどから分かること,推測できることから,昔に習った人類の起源などは大きく書き換えられていることが分かった。 びっくりすることも沢山書いてある。
2投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔の人類学は骨の形からしか調べることができなかった。 今の人類学はDNAから調べることができるそうです。 一万年も昔のDNAが今も残っているというのは、生物の不思議さ、偉大さを感じます。 主成分分析を使ったグラフで異なるグループ、縄文人や弥生人、朝鮮半島の人、台湾人などのゲノムの近さを表現していて面白かったです。
1投稿日: 2023.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代DNA研究の最新成果に基づいて、人類の進化史、そして現生人類であるホモ・サピエンスの拡散と集団の成立について解説。 読んでいてワクワクする、知的好奇心を満たしてくれる内容だった。最古の人類がサヘラントロプス・チャデンシスだったり、現代人にもネアンデルタール人の遺伝子が受け継がれているということだったり、デニソワ人の存在だったり、自分が習った20年くらい前の高校世界史なんかの人類史の知識とは全然違ってきていて、とても興味深かった。この分野の研究は日進月歩のようなので、今後も最新の動向をフォローしていきたいと思う。
1投稿日: 2023.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ遺伝子、ゲノムでほぼなんでもわかる感じなんだね。今は。でも結果しかない、先祖やつながりなど複雑なことをズバッと言い切ってるけど、どうしてそういう決断を下したのか、判定したのかがないので、イマイチ面白くない。博物館の館長が言うから間違いないんだろけど、逆に説明されても難しすぎるのか?最初はいいとして、5000年くらい前くらいになると、遺伝子的には結果出てるけど、単純じゃないみたいなこと言ってて(そりゃそうだろう)普通の歴史結果と同じになってる。アメリカ大陸の話で偶然によって遺伝子の頻度が変化する遺伝子浮動や、。。とあると辻褄の合わない話はそれが原因とかなると。ハテ。前提が崩れやしませんか。
1投稿日: 2023.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ近年人類化石から核DNAが採取できるようになり、それを基にした各種人類の発展の経路が改めて分かりつつある。ホモサピエンスが、アフリカ大陸から各地に散らばっていったという説は最有力だし、そこから南米大陸まで時間をかけて進めていったということはほぼ確か(南米からポリネシアには行っていない様子)だが、各地でネアンデルタール、デニソワ人と混血し、その混ざり具合が異なる現生人類が各地にいるという観点から、昔の各地で人類が個別に発展したという説はまだ完全には捨てきれないとしている。
1投稿日: 2023.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり多くの情報が集約されている。私が子供の頃はホモサピエンスが生き残りネアンデルタール人は滅びたとの定説があったのに、我々ホモサピエンスとネアンデルタール人が交雑して私達の遺伝子に組み込まれていることが解った。そのように人類史はこれからもどんどん新しい発見が情報を更新していくのだろう。我々のルーツを知ることは自分自身のなかに生きている歴史の遺伝子を探求するということ。
2投稿日: 2023.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ私には読みにくかった。新書が、どのような読者をターゲットにしているのかは知らないが、 これは専門家の書く新書なので、学者として省略できない部分があるのだろう。 この手のものでは川端裕人さんのものが、とても読みやすくまとめられていた。 あと、新書はこの本だけでなく、図とその図を見ながら読みたい部分が、あまり良い配置になっていないので、これは担当編集者が、もっと著者とともに工夫してほしいなあ。
2投稿日: 2023.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ数万年前の古代人骨のゲノム解析で、人類の起源を探る 出アフリカから地球に行き渡るまでの過程にとどまらず、ネアンデルタール人やデニソワ人などの他のホモ属(私たちホモ・サピエンス以外は全て滅びてしまった)との交雑。 骨は発掘され、そしてロマンを語る
2投稿日: 2023.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学の発展の中で、人類の起源を「合理的に」語ることができるようになった過程を説明した上で、DNAがこれまで歩んできた壮大な地球上の旅を、素人にもわかりやすく伝えてくれる良書。異なる種族同士の交雑や、戦闘、日本人のルーツが三段階の移住と衝突を経て作り上げられたこと、遺伝子の多様性と神秘を感じることができた。
1投稿日: 2023.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでる最中。 p.38 ネアンデルタール人は小集団に分かれてユーラシア大陸に広まった。デニソワ人は60人程度の集団。小集団では近親相姦が行われやすく、遺伝子の多様性が失われがちで、徐々に数が減っていく。
1投稿日: 2023.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔は分からなかったことが、科学の進歩によって分かってきている、だけどまだまだ分からないことがイッパイあるよ、と教えてくれる本。 今後の発見に期待
1投稿日: 2023.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログDNA解析の見地からは日本人の特異性・優位性は、いくら探しても見つからなかった。30万年前、日本列島はまだ無かった。 ネアンデルタール人たちとは交雑していた。
1投稿日: 2023.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代ゲノム分析という最新の学問分野において、人類そして日本人の起源を論ずる旬な内容。ただ、生命科学に疎い素人としては、分析結果の論旨展開がなかなか頭に入ってこないのが辛いところ。ミトコンドリアDNAとかPCR法とかSNP(一塩基多型)とか専門用語がいっぱい。 ただ、ロマンを感じさせる内容であるのは確かです!
1投稿日: 2023.06.14牽強付会からほど遠い、知的興奮が詰まった1冊です
昨年ノーベル賞を得たペーボ氏らが拓いた進化遺伝学による人類の系譜について、現時点での知見がまとめられている。座組がしっかりした研究集会を覗いている感じで、言葉は平易なのだがモザイク状に広がった考察を自分の頭で整理するのは一苦労する。昭和に学んだ人類学がかなり覆っているのが恐ろしくも凄かったです。
0投稿日: 2023.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
全く専門外の本なので、とても難解に感じたが、分かるところは興味深かった。 DNAの解析に次世代シークエンサという方法が使われるようになったことで、古代人のDNAの解析が非常に進んだとのこと。 ネアンデルタール人やデニソワ人などの旧人のDNA解析、現代人とのDNAの乖離、また地域ごとのDNAの乖離、本当に「我々がどこから来たのか」という問いに真摯に向き合っている。 イギリスで発見されたチェダーマン、肌は褐色。ネアンデルタール人も褐色の肌を持っていたのでは、とこの書籍に書かれている。現在のヨーロッパの肌の白さは人類史の中では比較的新しいものらしい。 私は金田一少年の事件簿、という漫画が好きだった。あるストーリーの推理の根拠にされていた、金髪碧眼、肌の白さ、に関係性がある、という事象は現在は否定されているようだ。 原語と文化、そして遺伝子の特質、関わりがあるところもあれば、ないところもある。人間営みを科学的に証明する一助にはなるけれど、全部を解明することは無理なのかなあ、無理だからこそ追い求めたくなるのかなあ、と本書を読んで感じた。
5投稿日: 2023.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ2023/5/23読了。古代史の領域は学説先行で突つき難かったが、本書を読み進める中で20世紀後半から21世紀に入って、と言うより極めて最近になってゲノム解析の進歩が1万年前(一応旧石器時代とは知っていたが)以降の完新世に属する古代人の集団の成立をデータに基づいて語ることが出来るようになって来たとのこと。これは驚きであり、非常に興味深い。東アジアで見ると農耕民の拡散が、周辺の狩猟採集民を巻き込む形で起こったこともわかったとのこと。ヨーロッパなどでは農耕民が狩猟採集民を駆逐する形で拡大したとかどんどんと明らかにされて来ている。移動、混合を繰り返して人類は進化して来た。今後、この分野ではゲノム解析が進むことによって、言語グループの成立に関するさらに詳細なシナリオが描かれることになるだろうと著者は予測する。楽しみである。
1投稿日: 2023.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書大賞第2位、ということで読んでみようと思った。昔から日本人はどこから来たのか?ルーツは?という疑問が議論されてきている。 本書でも最新の研究に基づいて述べられているが、やはり混血の繰り返しによって現代日本人は形作られている。また、同じ日本の中でも地方によって混ざり具合が異なるようだ。 これらの研究は自分の肌感覚でも理解できるところがある。 昔、40年ほど前にタイへ行った時、「タイという国は、南アジア系、中国系、韓国系、日本系、、様々な人種が住んでいるところで混血の途上なのだろうな。」と深く感心したことがある。 タイから日本に帰国して身の回りを見回してみると、改めて気がついた。「日本もタイと全く同じような状況ではないか!様々な人種がいる!」 さて、自分自身は一体どのようなルーツを持っているのか?なかなか自己分析ではわからない。 しかし、難しい本であった。新書大賞というのは玄人向けの賞なのかもしれない。確か新書大賞第1位の本も難しすぎた。私が馬鹿なだけかもしれないが。
8投稿日: 2023.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史的な文系の本かと思いきや、DNA、ゲノム解析等のかなり専門的な話がでてきて、理系科目はつくづく苦手だなと思ったが、食わず嫌いを克服したいと頑張って読み進めた。 理解できていない部分も多かったかと思うが、近年のゲノム解析技術の進歩によって教科書の歴史の修正にリアルタイムで立ち会えたような感覚を得られて嬉しかった。弥生時代には急に集落が生まれたのではなく、朝鮮から文化や人種が渡来していた。等。 またゲノム解析を通じた著者の見解も素敵だ。人種という括りは生物学的に明確な境界がなく、恣意的な括りにすぎない。世界中の人類のDNAは99.9一致しており、肌の色や身体能力、知能の差などは0.1%の差でしかない。わずかな差に注目して研究を進めるのは科学としてはオーソドックスだが、現代生活において0.1%の違いに重きを置くべきか、99.9%共通しているという部分に価値を見出すべきか。答えは明白だろう。
4投稿日: 2023.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代DNA研究は、2006年に次世代シークエンサという技術が実用化され、人類の成り立ちに関する研究が活況を呈し、従来の定説がいくつも覆される状況が生じている。また、最新の学説も、今後の解析の行方によっては大きく更新されることも十分にあるという、これからの展開が非常に楽しみな分野であることが分かる。 本書は、次世代シークエンサによって明らかにされた最新の研究の成果をまとめている。ホモ・サピエンスが出アフリカを遂げ、交雑・置き換えをしながら全世界に展開する様子が分かりやすく描かれる。今後の研究の行方も気になる。
2投稿日: 2023.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ最新の遺伝子やDNA 解析技術をもとに、ホモサピエンスがいつ頃どこで誕生し、世界にどう広がっていったかを示す。 特にヨーロッパ、アジア、日本、そして南北アメリカ大陸へのホモサピエンスのジャーニーの定説が、実は新たに発見された人骨や土壌分析等で覆されるような研究結果が出てきたり。 もちろん研究が進むにあたって更なる仮説が出されるだろうが、我々の祖先がどう進化してきたか、また例えば日本人の起源は何かと言うことにもつながり、興味が沸いてくる。 それにしても、古代の人骨の点的な解析を集め、線で結びつけ、歴史を紐解くなんて、解析技術は目覚ましいものだ。 著書が言いたかったことは、最終章にある以下のことばだろう。 集団の持つ遺伝子の構成は時間とともに大きく変化していくので、長いスパンで考えると、特定の遺伝子の有無を集団の優劣に結びつけることには意味がない。 ヒトの遺伝子は持つ価値は99.9%が共通で、そちらを重視すれば「人類は平等である」という考え方にたどり着く。現実の社会を見ると、違いのほうに価値を持たせすぎているのではないか。 現在の研究が明らかにしようとしているのは人類集団の起源と拡散の歴史だが、現時点で重きが置かれているのは、ホモ・サピエンスの誕生の経緯をめぐる研究、そして出アフリカ後の初期の拡散の状況の再現。ネアンデルタール人やデニソワ人のゲノムの解析からは、今までまったく知られていなかったホモ・サピエンスの成立に関する経緯が明らかになりつつある。 将来的に、彼らのゲノムを数百体レベルで解析することができれば、ホモ・サピエンスに特有なゲノムがより明確になり、私たちは何者なのか、という問いに対する答えがもたらされることが期待される。 現在の教科書的記述に欠けているのは、「世界中に展開したホモ・サピエンスは、遺伝的にはほとんど同一といってもいいほど均一な集団である」という視点や、「すべての文化は同じ起源から生まれたのであり、文明の姿の違いは、環境の違いや歴史的な経緯、そして人々の選択の結果である」と言う認識だろう。
2投稿日: 2023.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2023/1/8 ジュンク堂神戸住吉店にて購入。 2024/5/16〜5/21 2022年のノーベル医学・生理学賞を受賞したペーボ博士の研究で有名になった古代人のDNA解析。そこからわかる我々人類の進化の過程のお話。いやあ、非常に面白い。今ではこんなこともできるようになってるんだ。
2投稿日: 2023.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
化石や、人のいた痕跡(住居跡の土の中のDNA片など)からDNA解析を行う技法を開発した、ペーポ博士が2022年のノーベル医学生理学賞を受賞、と聞いたとき、正直、「そんな画期的な業績か…?」と思った。 しかし本書を読めば、その技術で遺伝的な近さ、遠さを明示できるようになったことで人類史が大きく前進した、と言うことがわかる。いままで形状的な特徴から、「この種とこの種は似ている」というところどまりだったものが、交雑の有無やその年代まで特定できるのだ。また現生人類のDNAと比較することで肌の色や髪の色、体格までわかる、と。大事なことだが、性別も間違いなく判定できる。 世界各地の人類化石の分析から浮かび上がってきたものとは… 人類の遺伝子の99。9%は共通で残り0.1%の違いで違いができる、ということ。これは非常に示唆的で、 「イギリスに住んでいた人々は5000年前には褐色の肌をしていた」 「種族/部族の移動があると、交雑して混ざるか、どちらかがどちらかを圧倒して遺伝子を置き換える/イギリスの例でいえば、ストーンヘンジを作った人々はそのあとイギリスに現れた部族に圧倒され、短期間に90%以上のDNAが置き換わった」 「交雑などで発生したはずだが消えた(絶滅?他の部族に吸収された?)部族も多い」 これを本書を読んで知り、人類のしてきた行いがなんと愚かで根拠のないものだったかがわかる。本書の内容と、私のつたない知識を重ねてみる。 アーリア人が優れた民族、としたヒトラー。ほんの数千年前まで白人種の肌が褐色だったという。青い目も金髪も白い肌も単に遺伝子の発現によるものでこれら3つはまったく別個の遺伝子情報によるものであり、たまたまこの3つが現代アングロサクソン人に揃っただけ、と知ったら? 人類の起源はアフリカでそこから各地に人類が広がった、と言うことを知っていたら、アフリカの人々を劣った人として奴隷にできただろうか。 奴隷制の理論的な支柱の一つが、「彼らは奴隷になることでキリスト教に触れ、神の存在を知るのだから奴隷にされても(しても)よい」という理論だったと記憶するが、このことがキリスト教の成立時期にもし明らかになっていたとしたら、教義は大きく影響を受けたのではないか。 日本人のルーツについて、①南から渡来した人々が縄文人として日本列島全体に定着、②朝鮮半島経由、大陸内部の民族のDNAを持った人々が渡来して混血、③アイヌ民族は縄文人がシベリアに渡り、そこで獲得した遺伝子を持って鎌倉時代に北海道に入る、ということのよう。 1万年前頃から手前だと言語学や使用された道具とDNA解析を組みあわせ、より具体的な民族の交流が明らかになる、としている。 非常に勉強になった。新年に読むにふさわしい本だった。
4投稿日: 2023.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログネアンデルタール人とデニソワ人とホモサピエンスを追う本。 ホモサピエンスは子孫を残しやすい遺伝子だったという事実も面白い。 放射性炭素年代測定法、ミトコンドリアDNAの調査、乳糖耐性遺伝子の調査などの技術が進み、より得られる情報が増えることで、類推もより正確になっていく。
2投稿日: 2022.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログホモ・サピエンスの変遷を交雑に焦点を当てて解説している一冊。 遺伝的要因と地域差を参考に、様々な集団がどのように形作られてきたかをじっくり考察しています。 日本を含むアジア集団の解説は内容が濃く、残された謎や旅路にロマンを感じました。
19投稿日: 2022.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログゲノム解析という分子人類学の技術が人類の歴史を明らかにしている。この20年程の人類史に関する知見が飛躍的に進んできていることに驚きを隠せない。全く結びつかなかったような学問・生物学が歴史、言語学とも結びついていることに感動する。ネアンデルタール人、デニソワ人というホモ・サピエンスと別の人類が如何にホモ・サピエンスと交流し、そのDNAが現在に残されているのか。子どもの頃に学んだ世界史の常識が全く一変しているのだ。これにより日本人の起源、ミクロネシア・ポリネシア人の来歴と南米との繋がり、北南米へのユーラシア大陸からの移動もゲノム解析でその時代が分かる! 何よりも出アフリカの時期さえも明らかになってきたとのこと。今後、遺跡から人骨が出てくるたびに謎が解き明かされていくということにワクワク感を感じた。 新型コロナウイルス感染症を重症化させる遺伝子はネアンデルタール人に由来する可能性のことまで触れられるとは圧倒される!
2投稿日: 2022.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の移動と系譜は単純な線形ではないということが延々と懇切丁寧に説明されていく。平易な文章だけれども、内容はとても難しい。つまり人類の起源は全く単純じゃない。 縄文人と一口に言っても西日本と東日本でミトコンドリアの系列が大きく違う。 人類はアフリカで生まれたとされているけれども、どの猿人からいまのホモサピまで繋がっているのか、特定が大変困難で、よくわかっていない。 教科書的にはネアンデルタール人とホモサピとは別人類とされているけれど、ゲノムを見ると互いに交配しながらユーラシア大陸を複雑に巡っている。 アメリカ先住民はシベリアから何度も何度も新大陸へ流入したことを示唆する痕跡が出ている。 アラスカの遺跡の古人骨は、実はそれよりも大昔に北アメリカの南部に到着した人類が、温暖化に伴い反転北上して住み着いた痕跡のようである。 とても面白い。
2投稿日: 2022.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代人ゲノムの分析は、スヴァンテ・ペーボが2022年にノーベル賞を取ったことで世の中の注目を集めた。ネアンデルタール人と現代人との混血の証拠や、デニソワ人の進化上の位置づけを明らかにするなど傑出した成果を残し、人類史の精度を格段に進歩させたまさに同賞に値する研究だ。 この本は、ペーボらをはじめとした研究で、古代人のゲノム分析手法が確立されたことによって明らかになった人類の足跡について、現在分かっている最新の情報をまとめたものである。 著者の篠田さんは2007年に『日本人になった祖先たち DNAから解明するその多元的構造』という本を出されたが、そのころから比べると数多くのデータが取得されたことからより精緻な結論が出ている。同書も2019年に改訂版が出されたようなので、日本人の起源を知るにはそちらの方がより多くの情報が詰まっているのだろう。 本書は、ネアンデルタール人、デニソワ人といった旧人と現生人類であるホモ・サピエンスとの関係、ホモ・サピエンス誕生の地アフリカでの人類の発展と出アフリカ、そしてより多くのデータがそろっていると思われるヨーロッパ・ユーラシアへの人類の進出(農耕と牧畜の拡大、ヤムナム族の進出)、アジア・オセアニア、日本列島集団の構成 (縄文と弥生の二重構造モデル)、アメリカ先住民の出自、と一通りの人類の旅路について記載されている。これらから、これまでの遺跡や人骨に頼った研究とは一段階も二段階も精度と確度が上がった人類史が確立しつつあるということがよくわかる。 こういった類の本として、デヴィッド・ライクの『交雑する人類』がある。実は、こちらの本の方が読み物として面白い。一方で本書は、新書という制限もあるのかもしれないが、研究からわかった事実を淡々と記載しているという印象がある。事実を網羅的に知るにはこちらの方が効率的だという言えるかもしれない。その意味では良書だと思う。 著者は、あとがきで、「民族」間の遺伝子の違いよりも、個々人の違いの方が大きく、遺伝子的な違いに価値をおくべきではないと強調する。遺伝子研究において集団の優劣にその研究が使われてしまうことに強い懸念を持っている。例えば、ネアンデルタール人出自の遺伝子の割合は、地域によって大きく異なる。特にアフリカ人には出アフリカ後に交雑があったという経緯から当然ほとんど含まれない。ネアンデルタール人由来の遺伝子には人間の能力に何か違いをもたらすものが含まれている可能性もある。このことをもって集団の優劣につなげて議論されることを懸念しているのだ。おそらくそれから目を逸らすのではなく、より”正しい”理解を持つように啓蒙することが重要だと思う。 また、この本で取り上げられた古代人の遺伝子解析ができる研究所は数少なく、人も資金も多くかかり、十指に満たないビッグ・ラボでしか実施できないということが書かれている。このことで研究がある地域に偏ってしまわないようにとは思う。 なお、日本列島集団の分析プロジェクトが2022年で終了し、その成果を発表出るだろうということだ。自分が属する集団がどのように形成されたのか、その遺伝特性とはどのようなものなのかというのは興味のあるところである。 ---- (参考) 『交雑する人類―古代DNAが解き明かす新サピエンス史』(デイヴィッド・ライク)のレビュー https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4140817518 『ネアンデルタール人は私たちと交配した』(スヴァンテ・ペーボ)のレビュー https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/416390204X 『日本人になった祖先たち DNAから解明するその多元的構造』のレビュー https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/414091078X
9投稿日: 2022.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類をDNA分析、いわゆるゲノム分析から分けたものである。類似度は%でしか表せないし、ごく少数のサンプルから分析するということはあるものの、わかってきたことは多い。ただ、日本人に関するものがわずか50ページにも満たないということで、なかなか身近には感じられない。
2投稿日: 2022.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 過去を知り今の見方を知る。偏見や差別を打破する第一歩は事実に虚心坦懐に向き合うこと。科学は未来への道標ともなるか。
2投稿日: 2022.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ遺跡から発掘した人骨に残されたDNAを解析することに寄って、人類の起源が明らかになり始めている。ホモ・サピエンスのDNAを、一番近い種であるデニソワ人やネアンデルタール人と比較したときにサピエンス固有のDNAは、全体の1.5~1.7%程度にすぎない。また、地域によって、サピエンスは、デニソワ人やネアンデルタール人のDNAを2%程度持っているが、これは交雑によるものと考えられている。 人類がアフリカから出ていったのは複数回に及ぶと思われる。 日本列島への人類の進出は、縄文人が先に入って、後で農業文明を持た弥生人が入って縄文人を追いやった、という単純な構図ではなく、縄文人自体も複数回の進出の混合したものだし、弥生人の進出も一回ではない。 同じく、アメリカ大陸への人類の進出も、数万年にわたって複数回行われていた。
2投稿日: 2022.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人類の起源 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」 著者:篠田謙一(国立科学博物館館長) 発行:2022年2月25日(再版3月15日) 中公新書 著者の専門は分子人類学で、京大理学部卒、医学博士で理系の人類学者。古代DNA研究は80年代から始まったが、その技術の進歩はめざましく、2006年から「次世代シークエンサ」の技術が使えるようになると、核のDNAが解読できるようになった。2010年から古代ゲノム解析が可能となり、初めてネアンデルタール人の持つ全てのDNA解読に成功したという。こうした古代ゲノム解析による人類の起源に関する研究について紹介した本だけど、著者独自の説を展開するという類いのものではなく、最新の事情を紹介している感じ。著者もあとがきで言っているが、執筆した2021年時点で分かっていることなので出版時にはまた進んでいるかもしれない、とのこと。初版から1年で再版になっているため、その間になにか新たな発見があって書きかえられたのかもしれない。 言うまでもなく、我々が中学や高校で学んだものとはかなり違ってきている。猿人→原人→旧人→新人の区分けは同じだが、最近では初期猿人という区分けも加わっている。その初期猿人(三属)の次の猿人が、教科書で最古の人類として教えられたアウストラロピテクス属で、上記の4区分となっていくものの、それぞれに重なる時期もかなりあり、交雑もあるからこうした区分への批判もある。ただ、便利なため今も使われているそうだ。この本で扱うのは主に、旧人と新人(ホモ・サピエンス)。 旧人の代表選手はネアンデルタール人だが、その後に新人(ホモ・サピエンス)が誕生し、その代表選手としてクロマニヨン人の名を覚えさせられた。しかし、ネアンデルタール人と新人との間に、もう一つ重要な旧人を入れる必要が今はあるようだ。デニソワ人という。ロシアの、中国、モンゴルに近いデニソワ洞窟から発見されたネアンデルタール人で、DNA解析によってデニソワ人と呼ぶにふさわしいことが分かってきたようだ。 ネアンデルタール人とデニソワ人がホモ・サピエンスにDNAを残し、交雑し、ネアンデルタール人とデニソワ人も逆にホモ・サピエンスからDNAを受け、さらにそれが交雑して・・という具合に複雑に遺伝子を残していったらしい。 21世紀の初頭には、ホモ・サピエンスの中にネアンデルタール人のミトコンドリアDNAが見つからないことから、交雑はなかったと断定された。ところが次世代シークエンサにより交雑が証明され、その説が覆った。 ホモ・サピエンスは、今ではアフリカで誕生したというのがほぼ定説。しかし、ネアンデルタール人とデニソワ人が共通祖先から分岐したのが60万年前で、最も古いホモ・サピエンスの化石が30万年前の地層から発見されていて、30万年間分がなにも見つかっていないため、アフリカを出た原人のうちユーラシア大陸にいた原人の中からホモ・サピエンスとネアンデルタール人、デニソワ人が誕生したのではという解釈も一定の説得力を持つそうだ。そして、30万年前以降にアフリカ大陸に移動したホモ・サピエンスのグループがのちに世界に広がることになるアフリカのホモ・サピエンスとなり、ユーラシアに残ったがグループはネアンデルタール人と交雑した後に絶滅した、と。 そんなわけで、新たな発掘やDNA解析技術の進化により、人類の起源について昔とは大きく塗り変わっているが、こんな調子で説明されてもややこしくて頭に図式が残りにくい。後半に日本人のルーツについて章をさいていて興味が持てるが、それもいろいろと混ざっているということで全体像を専門外の我々がつかむことは困難でもある。 では、この本から我々はなにを学ぶべきか。終章に著者の力強い解説と見解が書かれていて、納得できた。 「人種」という言葉は、もはや自然科学の分野では使わないそうだ。遺伝子解析により、黒人、白人、黄色人種という区分けができないことが明らかになっている。人類の起源の過程で混ざり合い、変化していったため、単純に3つで分けられるわけがない。その中間というような〝人種〟は無限にあるかもしれないとこの本を読めば分かってくる。 著者は「民族」という言葉の括りについても警告している。日本人の感覚だと同じ民族といえば遺伝的にも斉一性の高い集団だと考えがちだが、近年の古代ゲノム研究によって、人類集団は離合・集散を繰り返しながら遺伝的な性格を変化させてきたため、他集団との混合を経ずに存続する集団という面でいえばせいぜい数千年のレベルでしか存在しないことが明らかになっているからである。昨今の風潮がいかにおろかなことかがよくわかる。 *** ①初期猿人 700万年前 現代人とチンパンジーの分岐 サヘラントロプス・チャデンシス(チャド) 600万年前 オロリン・ドゥゲネンシスの化石(ケニア) 580~520万年前 アルディピテクス・カダッパ(エチオピア) 440万年前 アルディピテクス・ラミダス(エチオピア) *サヘラントロプス属、オロリン属、アルディピテクス属の三属を初期猿人とする ②猿人 420~200万年前 アウストラロピテクス属(肉食傾向) 260~130万年前 パラントロプス属(植物を食べていた) 200万年前 ホモ・ハビリス、ホモ・ルドルフエンシス(初期のホモ属でのちのホモ属につながる) ③原人 190~150万年前 ホモ・エレクトス(北京原人、ジャワ原人ほか。最初の出アフリカを成し遂げる、ジャワ原人は20万年前の化石からも、インドネシアのホモ・フロレシエンシスじゃ6万年前まで存在) 30万年前 ホモ・ナレディ ④旧人 80万4000年前 デニソワ人とネアンデルタール人の先祖が分岐 64万年前 デニソワ人とネアンデルタール人が分岐 60万年前 ハイデルベルゲンシス 30万年前 ネアンデルタール人(アフリカで誕生したハイデルベルゲンシスのうち欧州に渡ったグループから誕生し絶滅、アフリカに残ったグループの中からホモ・サピエンスが誕生、と考えられてきた) ⑤新人 30万年前 最も古いホモ・サピエンスの化石(アフリカ) ******** 日本列島に最初にホモ・サピエンスが到達したのは4万年前(旧石器時代)。 1万6千年前には土器が作られ、縄文時代に。 3000年前からは弥生時代。 ヨーロッパ人と東アジア人では、後者の方がわずかに多くネアンデルタール人のDNAを受け継いでいる。 コロナで重症化させる遺伝子がネアンデルタール人に由来する可能性が示されたが、その遺伝子は南アジア系の人が高い頻度で保有し(バングラディッシュ人は60%)、ヨーロッパ系も20%。一方、アフリカ系と東アジア系で保有する人はほとんどいない。 共同体の規模が大脳の新皮質に比例すると考えると、猿人は50人、原人が100人、ホモ・サピエンスは150程度。ダンバー数と呼ばれている。 牧畜生活は遺伝子の突然変異が可能にした。哺乳動物は母乳で育つが、乳糖を分解するラクターゼは授乳期を過ぎると活性が低下して分解できなくなる。成人期でもラクターゼを合成する突然変異があったので牧畜が生まれた。牛乳を飲むと下痢をする人がいるが、ラクターゼが合成できない人。 6万年前から気候は温暖化、5万年前から寒冷化に。2万1000年前に最も氷床が拡大した最寒冷期。それ以降、徐々に温暖化に向かったが、1万3000年前に「寒の戻り」が一時的にあった。この環境と地形のドラスティックな変化が、ユーラシア大陸にいたホモ・サピエンスの離合と集散を促した。 ホモ・サピエンスがアフリカを出たのは6万年前。1万年ほど中東で停滞し、5万年前からヨーロッパからシベリアにかけての全世界へと広がった。 オーストロネシア語を話す人々は、台湾から東南アジアの島々、ニュージーランド、ハワイ、イースター島などの太平洋の島々、アフリカ大陸東岸のマダガスカルまでの地球半分を占める広大な地域で話されているが、台湾が源郷。 トンガの人々は台湾にルーツを持つことがゲノム解析から証明された。 縄文人の遺伝的な要素がどれぐらいあるかを計算すると、北海道のアイヌ集団で70%、琉球列島の現代人で30%、本土日本人で10%。 宮古島から出土した縄文時代の人骨をゲノム解析したところ、予想に反して本土の縄文人と類似するものだった。縄文時代以降の琉球列島での主なヒトの移動は本土、とくに九州からの流入だったと考えられる。
2投稿日: 2022.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類史の激動の時代になったことを実感しました。 SDGsがキーワードとなって、人類、世界中の人々が、共通にサステナビリティを考える時代となったこともあり、その共通性を科学的に意識出来るように、なったことはとても重要だと思う。 世界中の国の教科書に、人類の、ホモサピエンスの変遷をしっかりと記載できるようになリ、皆が理解することで、世界の人々のサステナビリティに関わる今後の取り組みが飛躍出来るように思う。
2投稿日: 2022.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ私自身の大好きな分野であり非常に興味深く読ませていただきました。今後のさらなる研究成果に期待します。
2投稿日: 2022.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類の起源の真実に近づく過程の中間報告ーー著者は本書をそう位置づける。今や骨片からでも、堆積物からさえもゲノムを検出できるようになったと言う。日進月歩の分野であり、多くの説が塗り替えられた。科学は間違うものと言う著者の姿勢は誠実だ。人類の歩みが以前考えられていたよりもずいぶん複雑だということ、未解明のこと、今後解明されるだろうことが随分と多いという印象を受けた。「世界中に展開したホモ・サピエンスは、遺伝的にはほとんど同一といってもいいほど均一な集団である。」この圧倒的な科学的事実は世界をかえるだろうか?
2投稿日: 2022.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ古人骨に残されたDNAを解析して、ヒトがどのように移動してきたかを読み解く。古代DNA研究って凄いですね。ネアンデルタール人は教科書に出てきたから知っていたけど、デニソワ人という人類も登場して、面白かった。
2投稿日: 2022.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人類の進化史、ホモサピエンスの拡散と集団の成立を”古代ゲノム解析”によって分かってきたこと」を解説した内容。 ゲノムの解析が人類の歴史を大きく書き換えつつあることが分かる。 人類史、出アフリカの詳細、ネアンデルタール人やデニソワ人との混合、そして日本人の構成と歴史についても詳しい。日本人についてわれわれ(私など)が抱いてきたある意味定着した概念が大きく書き換えられるデータがゲノムの解析により生じている。 非常に興味深い内容でした。
2投稿日: 2022.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ今はミトコンドリアDNAから先に進んで核DNAを解析する時代に入っているということを初めて知った。科学技術の発達を仕入れとかないと、この手の話題についていけなくなるな、と自分のアンテナ感度をチューニング中。
2投稿日: 2022.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ図が多用されていて、とてもわかりやすかったです。「世界中に展開したホモ・サピエンスは、遺伝的にはほとんど同一といっていいほど均一な集団である。」「すべての文化は同じ起源から生まれたのであり、文明の姿の違いは、環境の違いや歴史的な経緯、そして人びとの選択の結果である」...というp267の著者の言葉が、心に残りました。
2投稿日: 2022.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ私たち人類はいかに誕生し、どのように世界に広がったのか。最先端の古代DNA研究から「グレート・ジャーニー」の全貌に迫る。
2投稿日: 2022.02.08
