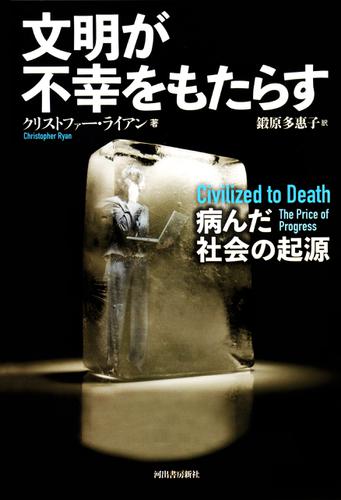
総合評価
(4件)| 2 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログそもそもこの本の主張となる懐古主義的「原始生活が幸せ」論には、感覚的に賛同できない。確かに、ハーバードMBAとメキシコ人漁師の話のように、本当の幸せは、欲張らずにのんびり暮らす事だという感覚は大賛成だ。しかし、餓死や疫病、暴力から、文明は少しずつ良くなっていると信じたいし、というか、文明化しなければ支配されるという構造的な必要性から、そもそも選択肢がなかったような気もする。 しかし、そうした競争がないなら、本質的にこの本の主張は正しい(気がする)。特に以下の話は気になる部分。コロンブスの話は、まさに、文明の先行者が支配するという凄惨な具体例だ。その後の資源についてもそう。脱文明化は、支配される。 ー コロンブスの日記の最初の二週間で、「黄金」という言葉が七五回出てくる。黄金に執着した著名な探検家は、地獄のような決まり事を強行した。黄金採掘のノルマを達成しなかった先住民は、両手足を切断されたのである。島々にあまり黄金が埋蔵されていないことはヨーロッパ人にとって問題ではなかった。 この点を除けばコロンブスを賞賛する伝記作者サミュエル・エリオット・モリソンも認めるように、狂気じみたヨーロッパ人から逃れるすべはなかった。「山中に逃げ込んだ者は猟犬によって探しだされ、これを逃れたものにも空腹と病気が待っていた。絶望の末、何千人もがキャッサバの毒でみずから命を絶った」。モリソンは一四九四年から一四九六年のわずか二年のあいだに、三〇万人いたタイノ人のうち三分の一が死んだと推測している。一五〇八年には、生きていたのはたったの六万人だった。全体としてわずか数十年で、「世界一善良な人びと」のうち残っているのはほんの数百人になった。 ー 地球の反対側では、一九九九年、レーガン政権やブッシュ政権とトップレベルでつながりのあったベクテル社(アメリカの機密扱いの国防工事請負人)の子会社が、ボリビアのコチャバンバ市の水道事業を政府から買い上げた。同社の社員が、すぐさま井戸 ー多くは村のコミュニティが掘って管理していた ーに水道メーターを取りつけた。市民の水道代は平均で五〇%上がったが、井戸の多くが彼ら自身で掘ったものだった。市民は新しい水道メーターの設置費用の支払いを請求され、今後は雨水をためる行為が違法になると警告された。所有権を示す書類を提示できないことから、何世紀も暮らしてきた土地を追われた採食者、羊の世話をして生きる十八世紀スコットランドのハイランド地方の人びと、初の就職先に勤務する前に何万ドルもの債務を背負う現代の大学卒業生。こうした市場経済にかかわらない選択肢は一貫して排除されてきた。 本書の白眉(私にとって)は、以下のマルサスとホッブズの理論解釈。新たな視点だった。植民地を正当化する理論ならば、歓迎される。現代の我々の感覚からは、道理で違和感ある論説だと思い、納得感のある解釈である。 ー 人口はつねに資源よりはるかに速く増えるので、欠乏と飢えは不可避だというのがマルサスの主張だった。すべての人に行き渡るほどの富はないし、これまでもありはしなかったのだ。反証不能に思える計算は、マルサス流の厳然としたドグマとなった。慢性的な人口過多、したがって破壊的な貧困は未来も絶えることはなく、人類が避けて通ることのできない運命なのだ。マルサスは述べる。「社会の底辺にはびこる貧因と惨めさは決して防ぎようがない」 ひどい話に聞こえるかもしれないが、彼の説は上流階級の多くに歓迎された。マルサスの主張によれば、当時広まっていた深刻な貧困は上流階級の責任ではないし、その問題の解決のために彼らが何もしないことを強力に正当化してくれたからだった。「決して防ぎようのない」問題なのだから、お茶とホットケーキでも食べて貧民の苦しみを忘れるがいい。貧しい者はいつの時代でもいるのだ。それに、彼らの悲惨な状態が自然の一部で永遠にあるものだと人びとに納得させられれば、反乱の芽をつむこともできる。人間の自然な状態を変えようとするのは、闇の中を行進するくらい無意味なことなのだ。 ー ホッブズの見解も間違いであることが今ではわかっているが、事実ではなくても有用であった。つまり、植民地化に対して正当化する論理として必要だったと言う事。
45投稿日: 2024.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かに文明がある種の不幸を人類にもたらした事は間違いないのだろう。 人は、他人との比較において幸不幸を感る事が多い。他人の情報を湯水のように受け取るからこそ、これでいいのか悩み、傷つく。 しかし、知りたいと言う欲求こそが人類であるとするならば、知らない事を是とすることも難しい。足るを知る、これが出来ればいいのだが。
0投稿日: 2023.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまた冒頭の文章が意味不明だ。5~6回も見直して入力する羽目となった。これほどおかしな文章が多いところを見ると、訳者というよりも河出書房新社の校正の問題と考えざるを得ない。まあ酷いものだ。よくも出版社を名乗れるものだな。名著だけに許し難いものがある。 https://sessendo.blogspot.com/2021/02/blog-post.html
0投稿日: 2021.02.02文明は史上最大の詐欺
ハラリは『サピエンス全史』で農耕革命を「史上最大の詐欺」と呼んだが、われわれの祖先は、快適な暮らしを求めて苦しい採食生活を捨てたわけではない。 むしろ農耕は選ばれたのではなく、「悲劇的な気候変動に対する無計画な適応から生じた偶然の産物」として発明され、文明が発達したのだ。 しかしその文明も、解消したと言われる危険の大半は、そもそも自らが生み出したか拡大させたもので、その代償は計り知れない。 崩壊していく環境に対する反応から足を滑らせて落ち込んだ穴は、悲劇的なほど底が無いことを、今年ほど痛感させれた一年はなかった。 文明が健全であるためには貧困が不可欠で、貧困がなければ労働も利益もない。 市場経済にかかわらない選択肢など存在せず、われわれは「銃を突きつけられてカジノをやらされているようなもの」だ。 「世代を超えて身ぐるみを剥がされ、あげくの果てにギャンブル中毒と告げられるのだ」。 本書では繰り返し、文明社会の人が先住民の暮らしに戻った事例は何千も記録されているが、その逆の、先住民が自ら望んで文明社会を選んだ事例はほとんど記録にないことが明かされる。 優れた社会なら必要ないはずだが、歴史は人を強制的に集めた事例に満ちている。 「私たちがここにいるというだけでは、この世界がこれまで踏みにじられて捨てられたどの世界よりいいということを、かならずしも意味しない。歴史がたまたま現在の道を選択したからといって、それが最善とは限らないのだ。そうでないと思うためには、何らかの宿命を信じ、ここにいたる途中で支払った通行料 - 奴隷制、戦争、大量虐殺 - は、どれもそれだけの価値があったと言う必要がある。私たちが長く存続してきたのは間違いない。だが、それは長い上り坂、長い下り坂、ただの長い道のどれだったのだろう」 「考古学的記録は、人類が採食から大規模な農耕と定住に移行したあとで『戦争が起きるようになり、独裁が増え、暴力が急増し、奴隷制が拡大し、女性の地位が下がった』ことを『明確に』示している。文明のおかげで人間の暴力の猛威が減じられたわけではないのだ。むしろ、文明こそ人間による大半の組織立った暴力行為の源だったのである」 感染症は、「文明によって引き起こされたものであって、文明によって軽減されたものではない」。 「文明は史上最大の詐欺だ。それは私たちに無料のものを壊すように仕向け、代わりに高価で劣化したコピーを売りつけようとする」。 「他者の苦しみを感じられない性質は、極端な富の格差によって生じる不快感を打ち消すための心理的な順応であると考えていい」。 「結局、私たちは寿命を延ばしたわけではなかった。自分たちの苦しみをスローモーションに変えただけだったのである」
0投稿日: 2020.09.14
