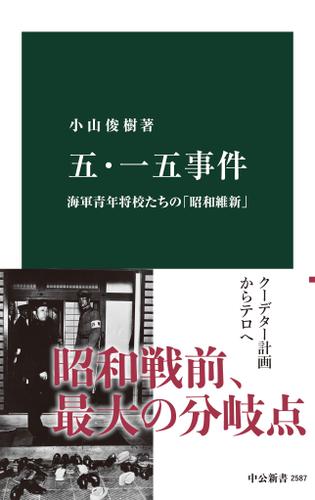
総合評価
(23件)| 10 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ革命・維新の影にはいつも純粋無垢な若者達の存在がある。社会への強い憤り、抑圧され行き詰まったやり場の無い熱い想い。それ以外の手段が無いと決め打ち、更には死をも共にする事を約束・覚悟した仲間同士の団結。その様な先にあるのは社会の潮流を大きく変える事件と、それに伴う誰かの死だ。 昭和初期に発生した五・一五事件は、良く知られる陸軍軍人が起こした二・二六事件と良く比べられ、かつ同事件への道筋を作ったと言われる、海軍軍人主体の事件だ。そこには前述した様な熱を帯びた若者達の気持ちがある。社会は犬養毅首相の強権的な政治手腕によって次々と施策が遂行され、国家全体が変わりゆく中で、農村は置き去りにされていく。おりしも世界恐慌の煽りと経済政策の失敗はそうした農村部を完全に置き去りにすると共に、食うにも困り娘を売り払う事態まで引き起こす。更には世界的な軍縮の波の中で軍艦保持対英米7割の維持すらも難しく、そのまま行けば軍人はやがて用済みになる。この様な背景で軍人達が政党政治の失態を許すはずもなく、熱気を帯びた若者達が立つ理由はいくらでもあった。五・一五事件を表面から見ると、概ね教科書からはその様なレベルでしか学んでこなかったが、そこに登場する人物、出来事を一つ一つ丁寧に紐解き、事件発生までの道のりを明らかにする様に、また束ねていく。そして事件後、また再びそれに関わった人物のその後の人生、事件によって変化する社会について、今度は結んだ紐がまるで解けていく様にそれぞれの紐の先を解説していく。本書はその様な表現が相応しい。 事件を引き起こした海軍将校達はその後も後進の育成に政治に力を注いでいく。彼らが倒したかった政党政治は天皇親権の実現とまでは至らないものの、その後は軍部を中心とした政治体制へと変わっていく。更にはそれがその後の日本を太平洋戦争へと導き、敗戦、奇跡的な経済復興を経て、結果的には現代の日本へと続いていく。彼らが犬養首相に放った銃弾が全てを変えたとは言えない。彼らも首相への個人的な恨みがあったわけでは無い、と言うのは真実かどうか分からないにしろ、間違いなくその後の歴史の流れに少なからず影響は及ぼしたはずだ。そしてこうして書籍の中にまた蘇る。 彼らが正しいか間違っていたかではなく、確かに熱い想いに突き動かされ、行動を起こした若者がいた事を現代の私たちは忘れかけてはいないだろうか。政治は偉そうな老人達(悪意は全く無い)に任せて、私利私欲だけで生きていたりはしないだろうか。戦後80年足らず、事件からもたかだか100年しか経っていない。流石に関係者は大半が鬼籍に入ってしまったであろうが、そのDNA・精神まで失ってはならないと強く感じた一冊である。 日本の戦前戦後の政治や世の中の流れを俯瞰するにも、こうした歴史上の事件一つにフォーカスして背景・原因を追っていく事で、たくさんの学びにつながると感じた。
5投稿日: 2024.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ五一五事件が、以後の日本に重大な影響を与えたにも関わらず、わかりにくい、二二六に比べて被告達の刑が軽い等、謎な事件だが、当時の政党政治の行き詰まり感が強く、それが事件の深刻さを恰も軽減してしまっているように感じた。
2投稿日: 2024.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容の濃い1冊で1度で理解するのは難しかったです。日本が戦争に突入していく過程としてこの事件は習うものの、本書を読むと大正から続く流れであることがよく分かります。
1投稿日: 2023.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ五・一五事件。青年軍人たちが首相官邸へ突入。「話せばわかる」と冷静に説得を試みる犬養毅首相を銃殺。この事件を発端に日本は政党政治が終わり、軍部主導政権のこと、戦争へ突っ走る。 青年軍人たちによる現役首相の殺害という大事件の割には歴史的注目度が低い気がしていたのだが、本書を読んで、その理由がなんとなくわかった。それは本事件があまりにずさんで計画性がなく、首謀者のバックボーンに深みがないからだろう。 過激青年たちの若気の至りにすぎない事件だが、問題はこの事件を軍部がうまく利用してしまったことだ。事件をきっかけに軍部は政党政治がいかに醜悪で金権的であるかを積極的にアピール。犬飼首相をテロに倒れた不幸な英雄ではなく、殺られるべく殺られてしまったという世論にしてしまった。犯行者たちは同情され、一人も死刑にならなかった。それどころか、出獄後に政治活動をする者もいた。 こうした軍部の暗躍の結果、軍人が首相の地位を独占することになる。
2投稿日: 2022.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ2021.12.30~2022.02.09 何をしたかったのか。学校の日本史ではわからない裏側が見えた気がした。 当時の状況から考えて、行動を起こさなければならない、とういう考えを、若者が抱いたのは理解しよう。だが、暴力で解決することには、共感できない。ましてや、それを擁護するなんてあり得ない。署名運動や自決なんて・・・ もしかすると、もっと深くその時代のことを学べば、違う考えを持つのかもしれないが、今の私には、こんな感想しか持てなかった。
1投稿日: 2022.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分自身、教科書で読んで、五・一五事件は犬養毅が暗殺されて政党政治が終わりました、程度の知識。 だが当然の話で、それだけの出来事ではない。 ・なぜ海軍青年将校たちは事件を起こしたのか ・なぜ五・一五事件は政党政治を終わらせたのか ・なぜ国民の多くが青年将校に同情し、減刑を嘆願したのか といった点に注目して解説している本。 あくまで、五・一五事件は、政党政治を終わらせるきっかけの一つとなったが、直接的な原因ではない。 ※テロが有効であったと感じさせないためには「憲政の常道」にしたがって政党政治を続けるのが合理的。 党利党略に振り回される政党政治の状況や、元老・天皇の思惑が絡んでいた。 また、政党政治が終わったことをきっかけとして、国の機関どうしの対立がより大きなものになってしまったことも興味深い。 当時の天皇の在り方についても、懐かしいが、過去、受験で勉強した通りだと再確認できた。 天皇はあくまで、国会・軍部etcの各機関の決定を承認する。天皇の「聖断」は避けるように動いていた。 こんな調整ゴト、胃に穴が開きそうだな・・・。
0投稿日: 2021.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ西田は当時30歳。その胆力は鬼神の域に達している。辛うじて一命は取り留めた。4年後の昭和11年(1936年)に二・二六事件が起こり、西田は北と共に首魁として翌年、死刑を執行された。二人をもってしても青年将校の動きを止めることはできなかった。 https://sessendo.blogspot.com/2021/12/blog-post_0.html
0投稿日: 2021.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直な話、この事件を起こすことによって、何をどうしたかったのかという点が、よく分からなかった。(本書の説明の仕方ゆえということでなく)事件を起こした人物達の発想が。
0投稿日: 2021.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ2.26事件にならんで著名な5.15事件。が、2.26関連本が山ほどあるのに対し、こちらはそうでもない。本書はその欠落を埋めるもの。筆者は日本史の研究者だが、ノンフィクション的な筆致も随所に採用されていて、読み応えがある。第1章で事件当日の動きを詳細に描いたのち、事件前→事件後に進む構成も面白い。関連して発生した血盟団事件についても触れられている。 興味深いのは、関係者が出獄後もかなり「活躍」していたことだった。この点は、首謀者の大半が処刑された2.26との大きな違いだろうか。戦時期に東條倒閣工作に関与したり、戦後も密輸をしたり、選挙に出たりといった具合であるが、吉田、中曽根、細川など歴代内閣の指南役にまでなった人物もいたことには、日本政治の闇が垣間見えて、寒気を覚えた。
11投稿日: 2021.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ二・二六事件と比べ作品の少ない五・一五事件。現役首相が現役軍人に殺害された事件の全容を明かす良作。 1932年(昭和7年)、日本史の教科書で必ず出てくる海軍青年将校が首相官邸を襲撃し犬養毅首相を殺害した事件。政党政治の終わり、と試験対策で覚えたが事件の詳細は知らなかった。 本書は事件の当日を詳述した第1章にはじまり事件の背景、事件後の政党政治の終焉、法廷闘争そして当事者たちの戦後という構成。倒叙形式のミステリーのように読み始めからグイグイと書に引き込まれる。 本書の目指したテーマは、以下の3つ。 1.海軍青年将校どうして事件を起こしたのか。 2.なぜ政党政治は終わったのか。 3.なぜ国民の多くが青年将校たちに同情し、減刑を嘆願したのか。 被告たちの動機の純粋さを利用して国民感情を守り立てる陸海軍。動機がテロ行為を正当化し、実行犯を英雄視するところは、昨今の半島を彷彿させる。どこか同じ東アジアの民族の遺伝子があるのだろうか。 筆者は昭和51年生まれ。いつの間に、こんな世代が昭和史の研究分野の第一人者となっている時代。 圧倒的な事実の前に息をつかせぬ展開。入手しやすい新書として屈指の出来であるように思う。 相変わらず中公新書特に歴史部門は熱い!
0投稿日: 2021.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ海軍青年士官たちにより首相暗殺。政党内閣の終焉をもたらしたテロ事件ではあるものの、その全容は一般には知られていない「五・一五事件」の計画から実行に到るまでの動きと、事件後の政党軍部宮中といった諸勢力の激しい鍔迫り合いの末に政党政治が終焉を迎えるに至った経緯を明らかにする。 読後、戦中戦後を通して純粋であることを貫き通した三上と老練狷介さを以て五・一五事件後の政局で暗躍した森恪の対照的な人物像が印象に残る。 本事件を単体で取り上げた一般書が皆無な中、本書の刊行は一読者としては本当に嬉しい限り。
0投稿日: 2021.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログコンパクトにまとめられていて、読みやすかった。 事件後の裁判、その後のこともよくわかった。 三上卓って釈放され、懲りもせず東条首相も暗殺しようとしたとは。
0投稿日: 2021.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人の殆どがこの事件の名前だけは知っていて、ではどういう事件で何があったのかは説明できないのでは、と思ったので。なんとなく漠然と、時の首相が軍人に殺された重大なテロ事件なのにその後に起こった二・二六事件と比べて処分も妙に軽かったような気がしていつかはちゃんと内容を追ってみようと思っていたので手にとってみた。冒頭、事件の概要が説明されているのだが...まぁ後知恵ではなんとでも言えるのだがかなり粗く正直なところかなりお粗末でこれでよく時の首相を殺せたものだと思ったほど。計画はグダグダだし移動手段は主にタクシーで旧式の手榴弾は不発だらけ...ちょっと恥ずかしくなったほどだ。しかしこの事件の本質はそこではなく、いわば社会の捨て石となって世の中に警鐘を鳴らしたいというところが目的で...そのようなテロは古今東西まれなのではないかと。つまり革命を起こし権力を奪取するという目的が皆無な、極めて日本的というか世界史的にも変わったテロ事件でそれ故にその処理もかなり特殊。結果として政党政治が終わってしまい軍が政治をも支配する道を開いてしまったという...。分かりやすく非常に興味深い内容でした。これはおすすめ。
0投稿日: 2021.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ昭和戦前期の大きな分岐点である五・一五事件について、その背景からその後に至るまでを克明に描く。 優れた実証的な歴史書であるが、人間ドラマが浮かび上がるルポ的な書きぶりで引き込まれた。格差拡大等の事件を招いた時代状況や、状況によって転変する世論など、現代への示唆にも富んでいた。
0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログどうしても、加害者側に国民の支持が集まったのか分からない。当時の社会情勢を説明されても、「志があれば理由があればテロを容認するのか」という疑問は解決されない。加害者側(特に軍属)は全員恩赦にあずかり、その後の政局に関与するところまでいっている。やっぱり軍の力を抑えられなくなった契機の事件だし、それだけ国民が政治にきたいしていなかったことが分かる。 2020年の今も、政治に期待できないのは同じだけど、国民は食に事欠くところまでは追い込まれていないし、当時の軍に代わる勢力がない。これっていい事なのかどうかは分からないけど。
0投稿日: 2020.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ海軍青年将校らは、なぜ天皇親政の「昭和維新」を唱え、首相暗殺など兇行に走ったか。昭和戦前の最大の分岐点の全貌とその後を描く。
0投稿日: 2020.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ血盟団事件の時も感じたが、行動力のある馬鹿ほど恐ろしいものはない。警視庁での乱闘計画(不発)等はよくできたコント、今舞台で実演すれば間違いなく爆笑ものである。 民間の狂信者であった血盟団はともかく、軍人としてのエリート教育を受けたはずの五一五の連中が、何故これほど杜撰極まりない計画で国を左右できると考えたのか、本書を読んでもまだ理解できない。
1投稿日: 2020.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ心に響いた箇所 A氏らは〇〇首相が君臨する「一国一党」は「幕府」であり、ファシズム・共産主義になると考えて。一君万民の結束を妨げる存在を創ってはならない、と訴えたのではないか。
0投稿日: 2020.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ五一五事件の実行犯たちの行動、動機、戦中戦後の余生と、 裁判や後任内閣の決定など、事件への周囲の対応や反応を、 かなり具体的に記述している。 「政党政治を終わらせた画期的な事件」として教科書的には整理される五一五事件だが、 先行する暗殺事件たちと比べて、そのような評価を得るほど特別な事件ではなく、 事件とは別の理由からたまたま後任内閣が政党人には委ねられなかったために、画期となったという印象を本書の具体的な記述から受けた。 農村の窮状、国際関係の緊迫化という国難のさなか、 ポストや利権をめぐる争いを優先する腐敗した政党財閥などに対抗して、 軍(官僚)や農民など(今日ならオール市民とでも表現するのだろうか)が一致団結して反対を表明するデモが五一五事件の根底であり、 陸海軍と農民が参加したという事実が実行犯にとって最重要で、 首相や要人暗殺は象徴として必要だが、未遂でも成功でも二の次であったという実行犯のナイーブな供述は興味深かった。 少なくとも、「政党から軍部へ」という安直な理解にはおさまらない、戦前史の地下水脈を感じさせる面白い本でした。
0投稿日: 2020.07.29犬養毅暗殺は主目的ではなかった
二・二六事件に比べて、映画やドラマ、小説や漫画で取り扱われることが少ないのはなぜなのか疑問に感じていたが、本書を読むとその謎の一端がよくわかる。 なるほど、わかりにくい事件である。 それもそのはず、計画は二転三転し、決起した者たちでさえ、要人を暗殺したら自害するはずが、ますます混迷し、しまいに「計画が複雑すぎる」と吐露するほど。 一番驚いたのが、首謀者にとって、君側の奸を打ち取ることが主目的だったのではなく、桜田門の警視庁に乗り込んでの決戦がハイライトと考えていたこと。 彼らにとって警官は「支配階級の私兵」なのだから、襲撃相手に相応しかったらしい。 その後は、憲兵隊に乗り込んで堂々と自首するという筋書き。 武器も当然、将校たちだからいくらでも持ち出せたのだと思っていたら、ヤクザの抗争と変わらず、風呂敷に隠してコソコソと調達してもらっている。 投じた手榴弾の不発が多いのも、普段から使い慣れたものでなかったためか。 そもそも二・二六事件のように、なぜ軍隊を使わなかったのかも昔から疑問を呈する人がいて、天皇の軍隊を私兵化することは駄目だと肝に命じていたから。 この他にも彼らには、海軍主導ではあるのだが、海軍・陸軍・民間の三者が一致して決起することに強く拘った。 右翼と一括りに言っても、革新右翼と観念右翼は違うらしく、前者が大政翼賛的な全体主義を志向するのに対し、後者は天皇の前では皆平等で各自の覚醒をひたすら希求する。 二・二六事件が成功していたら、五・一五事件の関係者は殺されることになっていたというのも、本書ではじめて知った。 もっと驚いたのが、犬飼首相が凶弾に倒れても政党政治は十分に存続が可能だったのに、昭和天皇の意向が働いて、政党の凋落や議会の価値の低下が始まったという指摘だ。 それにしても「私心なき精神」か「昭和維新」か知らないが、青年将校や士官候補生がこのような事件を起こした後の、陸軍や海軍の指導部の反応が本当に解せない。 あまり罪を重くせず内密に処理したいというのは面子の問題だから理解できるのだが、組織的には軍規の乱れを重視して内部の締め付けに動くのかと思ったら、「若い連中が弔い合戦だと騒いでいる」と慌て宥めすかしたり、出所後は手元不如意だろうと300万円ほど握らせ海外に赴任させるなど、部下にとことん甘い上司たち。 無官が好き放題に文句を言えて、責任ある立場の人間はひたすら彼らを慰撫し取り繕う風潮は、今と全然変わっていない。
0投稿日: 2020.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
五一五事件前後の政治過程、青年将校たちのメンタリティや思想がきめ細やかに描かれた名著。天皇の下の平等を目指した思想は、陸軍統制派による軍部独裁政権とも反目した。それにしても、五一五事件があれ程場当たり的だとは知らなかった。クーデターというよりは、明治維新の先駆けとなった桜田門外の変を模したイメージか。
0投稿日: 2020.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ目次 はじめに 第1章 日曜日の襲撃—1932年5月の同時多発テロ 第2章 海軍将校たちの昭和維新—国家改造と軍縮条約 第3章 破壊と捨て石—クーデターからテロリズムへ 第4章 議会勢力の落日—何が政党政治を亡ぼしたか 第5章 法廷闘争—なぜ被告は減刑されたか 第6章 さらに闘う者たち—元受刑者たちの戦争と戦後 あとがき 本書は「五・一五事件」の詳細とその思想的、社会的背景を跡づけたものである。 第一に、なぜ海軍青年将校たちは事件を起こしたのか。昭和維新を断行するという思想醸成の背景には昭和恐慌という経済的危機があったことは間違いないが、北一輝・大川周明らの革新思想、権藤成卿・橘孝三郎らの農本思想、井上日召らの直接行動論などがあった。それらに影響された「忘れられた青年将校」藤井斉の存在も大きかった。またしばしば一括りにされるこれらの右翼思想は決して一枚岩ではなかったことは、二・二六事件との性格の違いや後々の近衛新体制運動の結果としても表れている。 第二に、なぜ政党政治は終わったのか。首相が暗殺されたケースは原敬、浜口雄幸があったが、いずれも「憲政の常道」にしたがい、高橋是清、若槻礼次郎が後継内閣を率いた。犬養暗殺後は政友会の鈴木喜三郎に引き継がれずに齋藤眞が挙国一致内閣を率いることになった。これはなぜか。元老西園寺公望も当初は鈴木内閣を想定していたが、直前に変心があった。著者はここで昭和天皇の存在をクローズアップする。また政友会の森恪の動向にも強く目を向けている(著者は森恪の本格評伝も著している)。 第三に、なぜ国民は海軍青年将校たちに同情し、減刑を嘆願したのか。またそれは判決に影響を与えたのか。結論から言えば、減刑嘆願運動高揚の背景として「特権階級」への憤り(ヒーロー待望の大衆社会的状況の現出)、海軍内の政治的策動(条約派と反条約派の対立)などがあったと著者は論じている。 著者は「あとがき」で「「五・一五事件」は歴史となった。」と書いている。二・二六事件と違って関係者の多くが遺族も含めて戦後長く生きたことで逆に「歴史」になるのが遅かったという意味である。「五・一五事件」をきちんと理解することが難しいのはそういった事情もあったわけだ。
0投稿日: 2020.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ二・ニ六事件に比べ、適当な概説書がなかったところなので、大変勉強になりました。特に、政党内閣が終わってしまったのは何故なのか、という点にフォーカスを当てて、具体の政治過程を記述していたところは参考になりました。
0投稿日: 2020.04.20
