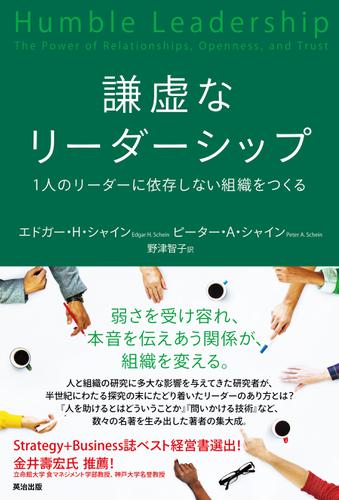
総合評価
(15件)| 0 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者はOCLI.org共同創業者COO. 従来の組織牽引役としてのリーダーシップを、リーダーとメンバーの人間関係のレベルで定義しなおし、以下のLvel1⇒2を事例によって示す。 Level-1:人間味のない、支配と強制 Level1:Transactionalな役割や規則に基づいて管理・監督、サービス提供。ほどほどの距離感を保った支援関係 Level2:友人同士/有能チーム。個人的で互いに助け合い、信頼し合う関係 Level3:感情的に親密で互いに相手に尽くす関係 最終章(第9章)では、ステップ毎の実現ステップ有。 ・よりよいことをしたいと思い、ほかの人たちに一緒にしてもらうこと ・メンバー自ら課題を発見し、改善に向けて行動する自律型組織(≒ティール組織)として、変化に対してより柔軟に対応できるように ・素直に話し、過ちを認める ・対人関係やグループダイナミクス有意義。グループ・センスメーキングやファシリテーションスキル
0投稿日: 2025.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手がいるなかで、対話によって協力を最大化し、複雑だったり変動的なタスクをクリアしていくことが、現代におけるリーダーシップである。 ということが書かれてる。 謙虚なというワーディングが微妙な気がする。むしろ、みんなで共に前へ進む、ということを叶える、集団主義的なリーダーシップというか、We型リーダーシップというか、そんなかんじ
0投稿日: 2025.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ別の本で推薦図書に挙げられており、面白そうだったので読了。 どちらかというと「ついてこい系」よりもこっち派で動くことが多いので、今後も参考になりそうな点が色々とありました。良書です。
1投稿日: 2025.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログリーダーシップとは、関係性にほかならない。真に成功しているリーダーシップは、きわめて率直に話をし、心から信頼しあうグループのなかで成果をあげている。 部下を下に見ないようにしよう。部下の成功を積極的に支援するつもりであることを際立たせるために。
0投稿日: 2024.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ序盤と最後の方が良かったです。職場は、サーバントリーダーシップを目指してるらしいから、これはちと違うけど、風通しのよさという点では、参考になった。後半集中力がきれちゃって、まずまずな理解でした。
0投稿日: 2023.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ変化が激しいVUCAの時代、カリスマ性のあるリーダーより、民主的なリーダーが結果も残すし、組織の継続性にも効果的であるということを実例を含めて解説、最後に謙虚なリーダーシップ発揮のためのエクササイズもついている。
0投稿日: 2023.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
複雑化するビジネス環境においては、カリスマ性で引っ張っていくリーダーシップは過去のものになりつつある。 必要とされるのは、関係者とうまく協力しつつ素早く変化していく謙虚なリーダーシップである。 謙虚なリーダーシップでは、対人関係のプロセスやグループプロセスを改善することに注力する。 謙虚なリーダーシップとはグループや関係者との業務関係を、レベル1からレベル2にパーソナイズすることで、グループプロセスを改善することである。 レベル1: 業務上の役割や規則に基づいて、監督・管理したり、サービスを提供しあう関係 レベル2: 個人的で、互いに助け合い、信頼し合う関係
0投稿日: 2021.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ翻訳のせいか少し難しく感じるところもありました。アメリカとの文化の違いも大きいかもしれません。 これからのリーダーは、予測不能な未来に向けて謙虚なリーダーである必要があるということです。機械的な立場上のつながりではなく、チームのメンバーと親密な関係を築き、率直な意見のやりとりができるようでなくては、これからの時代はうまくやっていけません。 たとえ、仕事上の人間関係でも、相手のことをよく知り、人として尊重する姿勢が、これからのリーダーには必要なのだということでした。
0投稿日: 2021.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ『謙虚なコンサルティング』に続く著作。心理的安全性のキーワードをシャイン流にまとめ直した感じですね。単なる業務上の関係性ではなく、個人的で信頼し合う関係をいかに構築するかが謙虚なリーダーに大切である。サーヴァントリーダーシップを発揮するため不可欠なプロセスであるという点は面白い位置付けだと感じた。今作から息子のピーターとの共著になっていて、おそらく前半がピーター担当なのかな。前半の文章にワクワク感や勢いがまったくなくて面白くない。後半は多少面白みを感じたからたぶんエドガーが書いてる。次作以降も共著になるんだろうなぁ…
1投稿日: 2021.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ馴れ合う組織は良くないが、お互い距離がある組織も良くない。成果を出すならお互いを知って信頼を築く必要がある。読めば当たり前だけど、現実は難しい。課題でくす。
1投稿日: 2020.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在は、英雄的なリーダシップの時代ではない。 メンバー一人一人を完成された個人だと考えて接する。 トップダウンではなく、一緒に考える、学ぶ事が大切。
1投稿日: 2020.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人との関係には、次の4つのレベルがある。 レベルマイナス1 全く関係のない、支配と強制の関係 レベル1 単なる業務上の役割や規則に基づいて監督・管理したり、サービスを提供したりする関係。大半の「ほどほどの距離感を保った」支援関係 レベル2 友人同士や有能なチームに見られるような、個人的で、互いに助け合い、信頼し合う関係 レベル3 感情的に親密で、互いに相手に尽くす関係 謙虚なリーダーシップとは、 この組織のレベルをレベル1からレベル2の段階に引き上げるために、個人的な関係を重視するリーターシップのことだ。 教育で考えると、ついつい子供たちを集団として捉えたり、意図せずとも番号的に認識したりしてしまうことがある。 そうではなく、まずはひとりの人間として考えようとすること。 よく言われることだが、もう一度自分が意識できているか振り返ってみたいと思った。
0投稿日: 2020.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ組織が環境変化に適応し、成果を上げ続けるために必要なリーダーシップのスタイルとして、支配や強制、監督管理ではなく、互いに助け合い、信頼し合う関係を作る「謙虚さ」の重要性を解説した一冊。 著者はリーダーシップを、新たな、よりよいことをしたいと思い、それをほかの人たちに一緒にしてもらうことと定義し、VUCAの時代にマッチョなリーダーが情報を独占し、パワーで組織を支配し続けることは困難であり、それよりも組織のメンバーを、各自が担う役割ではなくひとりの人間として考え、より個人的で信頼し合う関係を作る必要があると主張する。これにより、「リーダー対フォロワー」の関係は、常に上司の指示を待ってそれをこなすことから、メンバー自ら課題を発見し、改善に向けて行動する「リーダー対リーダー」の関係となり、自律型組織として、変化に対してより柔軟に対応できるようになるという。 そのためにリーダーは、常に素直に話し、過ちを認めるとともに、対人関係やグループダイナミクスに集中し、グループ・センスメーキングやファシリテーションといったスキルを磨く必要があることを、著者は多くの実例をもとに解説する。「謙虚」であることの意味合いは欧米と日本で若干異なるのかもしれないが、古いタイプのリーダーシップに取り憑かれたままの上司と、そのようなリーダーシップが全く通じない新世代の部下に挟まれた中間管理職にとっては、目から鱗が落ちる読書体験になるかもしれない。
0投稿日: 2020.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログリーダーシップの責任を分かち合うとかチームに溶け合うとかそんな方向性に見えた。そのために関係性に目を向け、1人に依存しない組織をつくる。指揮官とか英雄のいない世界。しなやかに適応し続けるという言葉はしっくりきた。苦難の道だろうけど。
0投稿日: 2020.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『本書を書いたのは、職場での関係構築のプロセスののとを、仕事の内容と同じくらい、あるいはそれ以上に、読者によく考えてもらいたいからである (p.203より)』ここを、もっと冒頭にはっきり書いてくれたら、もっとこの本は読みやすかったのかもしれない。 『キャリア・アンカー』の著者らしく、人の価値観やその人そのものに個人的な関心を寄せることがリーダーシップにおいて大事であることを、様々な事例をもとに主張している。 内容としては共感できるけれど、これは訳者の問題なのか非常に読みにくい。直訳すぎて、そこが気になって途中からいらいらしてしまった。読み終わるまでに辛抱した。もっとわかりやすい訳にしたら、きっともっといい本なのではないかと思う。 ✴︎最も役立ったポイント アメリカ軍における謙虚なリーダーシップ例 原子力潜水艦マルケ艦長の事例。 ヒエラルキーが強く、言われたことをやるだけの階層型組織が、やる気に溢れ抜群の成果をあげるようになった。 マルケがした上等兵曹にした問い Q今の仕事のやり方に満足しているか?それとももっといいやり方に変わって欲しいか? Q現行の手順の中で自分が変えたいと思うものはあるか? また、部下の提案の言葉遣いを変えた。 これまで:〜したいのですが、わたしはどうすればいいですか?どうすべきでしょうか? という許可を求める言葉遣い 改革後:〜したいと思います、〜するつもりです、私は〜します、 →権限を与えられている。明確な意志があると乗組員自らが感じられるようにする アメリカ軍なんてヒエラルキーの極みだと思っていたので、ちょっと意外な事例だった。
0投稿日: 2020.05.06
