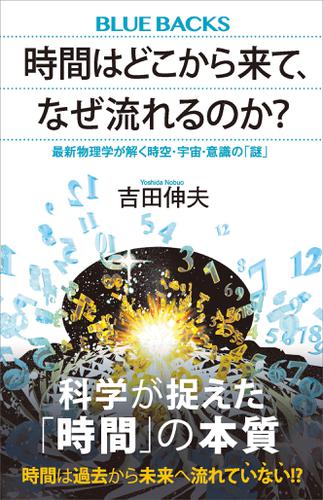
総合評価
(43件)| 10 | ||
| 8 | ||
| 17 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ良い本だと思うが、自分には難し過ぎた。 難しいと感じた理由は、以下のとおり。 1.本書の読者はある程度の知識、表現に対するイメージ化が可能な人を前提としていると感じるが、私はそれら持ち合わせていなかったことにある。 2.電子書籍で読んだため、図表への戻りが困難で、先に進んだページで過去のポンチ絵を示されてもなかなか容易にアクセス出来ず、理解の妨げになったことにある。 3.ビジネスシーンでよくある表現ではなかったこと。図表など、時間の軸を表す時、横軸として表現したりするが、本書では縦軸で表現されており、ポンチ絵の細かな差異がノイズとなったことにある。 内容は、理系の方から見ると良いもので、上記3点も界隈の方なら普通なのかもしれない。 私の知識、読書背景などからこのような評価となった。
0投稿日: 2025.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間の本というより、物理の本だった。 相対性理論だったり、ワームホールとか、二重スリットとか耳馴染みのある話が多かった。 図とかグラフがあまり理解できないので時間空けてまた読んでみたい。
0投稿日: 2025.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログSummary of the Texts Introduction: The Nature of Time and Space Conceptual Challenges of Time and Space The text begins by interrogating the nature of time and space, particularly in the context of atomic theory. It poses fundamental questions about existence in a vacuum devoid of atoms: What remains when atoms are removed? Does a true vacuum contradict the notion of existence? If no changes occur in a completely empty space, can we speak of the passage of time? The discourse highlights the difficulties in articulating the concepts of space and time from a strictly atomic perspective, revealing the limitations inherent in traditional atomic theory. Newtonian Approach to Time and Space Isaac Newton's approach is examined as a formalistic attempt to delineate the concepts of space and time. Newton did not define the properties of space and time that remain after matter is removed, treating them instead as necessary constructs for describing motion. Newton's framework considered space and time as absolute entities, distinct from the physical phenomena they support. Emergence of Field Theory Evolution of Atomic Theory By the early 20th century, the concept of atoms was well-established; however, the Newtonian worldview, which treated vacuum as devoid of properties, was increasingly challenged. This led to a revival of Aristotelian views, where physical phenomena were believed to be caused by underlying entities present everywhere. Discovery of Electric and Magnetic Phenomena Phenomena such as the attraction of dust by amber and magnetic properties of lodestone (magnetite) were recognized much earlier. However, it wasn't until the 17th century that these were understood as electrical and magnetic phenomena. Systematic studies began after the invention of the battery in the late 18th century. Field Theory's Role Experimenters like André-Marie Ampère and Michael Faraday demonstrated that the carriers of electric and magnetic forces were distinct from the atoms that make up material bodies. These forces filled the vacuum, giving rise to the concept of a field, which became essential in understanding physical interactions. Consequently, fields and space were recognized as interdependent, dismissing the need for an abstract, formalistic conception of space. Time and Space in Physics The Interplay of Time and Space The text delves into how gravity influences the measurement of time. Albert Einstein's theory of general relativity illustrates that the presence of mass alters the fabric of space-time, thereby affecting the passage of time itself. The phenomena of gravitational redshift and light bending near massive bodies exemplify this relationship. Implications for Observations and Measurements When observing celestial objects, time appears to slow down in stronger gravitational fields. This leads to discrepancies in the observed frequencies of light from stars compared to laboratory measurements on Earth, a phenomenon known as gravitational redshift. Theoretical Frameworks and Experiments Minkowski Geometry The summary emphasizes Hermann Minkowski's contributions, which unify space and time into a four-dimensional continuum known as spacetime. This framework allows for the examination of the behavior of objects under various conditions of speed and gravitational influence. The Double-Slit Experiment A pivotal discussion focuses on the famous double-slit experiment in quantum mechanics, which showcases the wave-particle duality of matter. It reveals that particles, such as electrons, can exhibit characteristics of both waves and particles, depending on whether they are observed or not. Quantum Interference and Decoherence The text details the concept of interference in quantum mechanics, where particles can simultaneously take multiple paths. The phenomenon of decoherence explains how particles lose their quantum coherence and transition into classical behavior, resulting in distinct outcomes. The Nature of Time Time's Directionality and Entropy The relationship between time and entropy is analyzed, particularly in the context of the second law of thermodynamics, which states that entropy tends to increase in isolated systems. The text posits that the flow of time is inherently linked to the direction of entropy, marking a distinction between past and future. Time Perception in Consciousness The last section delves into how consciousness perceives time, emphasizing that the experience of time is not merely a passive reception of events but involves active processing by the brain. Experiments illustrate that our perception of time can be manipulated and does not always align with objective time. Conclusion Synthesis of Time, Space, and Quantum Mechanics The texts present a comprehensive view of time and space that intertwines classical and modern physics, illustrating the complexities of these concepts. The shift from Newtonian mechanics to Einstein's relativity and quantum mechanics signifies a profound transformation in our understanding of the universe, revealing that time and space are not absolute but are influenced by various physical phenomena. Future Directions in Understanding Time and Space The ongoing exploration of fields, quantum behaviors, and the nature of consciousness continues to challenge and refine our understanding of time and space, suggesting that future discoveries may further revolutionize our conceptual frameworks. This detailed summary encapsulates the intricate discussions presented in the original texts, providing a holistic view of the philosophical and scientific inquiries regarding time and space. はじめに―時の流れとは 1. 時間の本質 1.1 時間とは何か? 時間は物理的な現象と深く結びついているが、その定義や理解は時代と共に変遷してきた。特に、アインシュタインの相対性理論は、時間についての従来の考え方を根本から覆した。相対性理論によると、時間は絶対的なものではなく、観測者の運動状態や重力の影響を受ける。 1.2 時間の流れの感覚 人間は「現在」という瞬間を特別視する傾向があるが、実際には時間は絶えず流れているわけではなく、意識の処理によって流れるように感じられる。この感覚は、脳内の神経活動に由来し、時間の流れを意識する過程には多くの心理的要因が関与している。 2. 時間の測定 2.1 機械式時計と原子時計 時間の計測は、古代の日時計から始まり、機械式時計、さらに現代の原子時計へと進化してきた。原子時計は、原子の振動数を基にしており、非常に高い精度を誇る。原子時計の精度は、重力の影響を受けるため、標高の異なる場所で異なる時間を示すことが確認されている。 2.2 時間の相対性 アインシュタインの特殊相対性理論によると、異なる場所での時間の流れは異なり、これは重力や速度によって変化する。高い場所では時間が遅く進むという現象は、科学実験によって実証されている。 3. 時間の哲学的考察 3.1 時間の方向性 時間には過去から未来へと向かう方向性があるが、これは物理的な法則やエントロピーの増大と関連している。ビッグバン以降、宇宙は膨張し続け、時間の流れもこのプロセスと深く結びついている。 3.2 意識と時間の関係 意識は時間の流れをどのように感じるのかという問いは、哲学的な議論を引き起こす。意識が時間をどのように認識し、どのように過去の経験と未来の予測を結びつけるのかを探ることは、心理学や神経科学における重要なテーマである。 4. 結論 時間の流れについての理解は、単なる物理学の枠を超え、哲学や心理学にも関わる複雑な問題である。相対性理論によって示されるように、時間は一様ではなく、観測者の立場や状況によって異なる。人間の意識が時間の流れをどのように感じ、認識するかは、今後の研究によってさらに深く探求されていく必要がある。 第1部 現在のない世界 1. 時間はどこにあるのか 時間の概念は、物理学と哲学の両方で深く探求されてきた。時間は、私たちの経験において重要な役割を果たすが、その本質は未だに謎に包まれている。ニュートン的な見解では、時間は絶対的で一様に流れるものであり、全ての物体に等しく作用する。しかし、アインシュタインの相対性理論は、時間が観測者の運動状態や重力場の影響を受けることを示しており、時間の絶対性を否定する。 1.1 時間の相対性 アインシュタインの特殊相対性理論において、時間は、運動する観測者によって異なって測定される。具体的には、速く動く物体の時計は遅れることが示されている。これが「時間の遅れ」と呼ばれる現象であり、光速が不変であることと関連している。この原理は、時間の流れが単なる経過ではなく、観測者の位置や速度によって変化することを意味している。 2. 過去・現在・未来の区分は確実か 時間は過去、現在、未来の三つの区分に分けられるが、これらの区分が実際に確実であるかは疑問視されている。相対性理論によれば、過去と未来は物理的に存在する時空の一部であり、観測者の運動状態によって異なる時間経過が生じる。このため、過去、現在、未来の明確な区分は相対的であり、絶対的ではない。 2.1 時間の非線形性 時間の流れは、必ずしも直線的ではなく、複雑な相互作用によって形成される。たとえば、量子論における重ね合わせの原理は、粒子が同時に複数の状態を持つことを示しており、これが時間の概念に新たな視点をもたらす。また、ウラシマ効果のように、動く観測者が異なる時間経過を経験することも、時間の非線形性を示す一例である。 3. ウラシマ効果とは何か ウラシマ効果は、相対性理論における時間の相対性を具体的に示す現象である。この効果は、ある物体が高速で移動する際、その物体の内部で時間が遅れることを指す。具体的には、宇宙旅行において、地球に残された人々と宇宙船に乗った人々の間で年齢差が生じるという点が興味深い。 3.1 ウラシマ効果の実験的検証 アインシュタインが提唱したウラシマ効果は、実際に様々な実験によって検証されている。例えば、粒子加速器を用いた実験では、高速で移動する粒子の寿命が延びることが確認されている。このような実験的証拠は、相対性理論の妥当性を裏付けるものであり、時間の流れが観測者の運動に依存することを示している。 3.2 時間の哲学的考察 ウラシマ効果を通じて、時間とは何かという哲学的な問いが再び浮上する。時間は単に物理的な現象の一部であるのか、それとも人間の意識や経験に根ざす概念なのか。この問いは、時間の本質を理解する上で重要であり、哲学的な探求が続けられている。 結論 時間の概念は、物理学と哲学の交差点に位置する複雑なテーマであり、相対性理論やウラシマ効果を通じて新たな理解が深化している。時間が絶対的ではなく、観測者の状態によって変化することは、私たちの時間認識を根本的に変えるものである。今後も時間の本質についての探求が続くことが期待される。 第2部 時間の謎を解明する 1. 時間はなぜ向きを持つか 1.1 時間の不可逆性 時間には明確な向きがあり、私たちは未来に向かって進むと感じます。この向きの理由として、エントロピーの増大が挙げられます。自然界の法則において、エントロピーは常に増加する傾向にあり、これが時間の流れを一方向に感じさせる要因となります。たとえば、熱は常に高温から低温へと移動し、物理現象は不可逆的です。この不可逆性が、時間に対する我々の直感的理解を形成しています。 1.2 ビッグバンと時間の起源 ビッグバンは、時間の起源として重要な出来事です。ビッグバン以前は、宇宙における時間の尺度が存在しなかったとされ、ビッグバンからの距離が時間の進行を定義します。この観点から、時間は単なる流れではなく、ビッグバンからの進行を示す指標と考えられます。 2. 「未来」は決定されているのか 2.1 決定論と不確定性 未来が決定されているかどうかの議論は、物理学における基本的な問いです。古典的な物理学では、初期条件に基づいて未来の状態を予測できる決定論が支配的でした。しかし、量子力学の登場により、微細なスケールでの不確定性が強調され、未来の状態は確率的にしか予測できないという見解が広がりました。この不確定性は、物理現象が波動性を持つことから生じ、位置や運動量などの同時確定が不可能であることを示しています。 2.2 時間の流れと物理法則 物理法則は、時間に対して対称性を持っていますが、エントロピーの増大により、実際の時間の流れは一方向であると感じられます。これにより、未来の出来事があらかじめ決まっているという考え方は、エントロピーの観点からも支持されません。 3. タイムパラドクスは起きるか 3.1 タイムトラベルの理論 タイムトラベルの概念は、物理学的な理論において興味深い議題です。ワームホールや負の質量を持つ物質など、タイムトラベルを実現するための理論的枠組みは存在しますが、実際には物理法則に反する可能性があります。特に、「親殺しのパラドクス」など、過去に戻った場合の論理的矛盾が問題視されています。 3.2 パラドクスの解決 タイムパラドクスを解決するためには、時間の流れが単なる直線的なものではなく、時間そのものの特性を再考する必要があります。エネルギーの分配や因果関係の捉え方を変えることで、新たな視点からタイムパラドクスを理解することができるかもしれません。 4. 時間はなぜ流れるように感じられるのか 4.1 意識と時間の知覚 時間が流れるように感じられるのは、脳内での情報処理に起因しています。意識は、リアルタイムで変化する情報を処理し、時間の流れを感じる結果を生み出します。「ルビンの盃」のような視覚的な錯覚を通じて、意識の構成要素が交代する様子が観察でき、これは時間の知覚に重要な役割を果たしています。 4.2 神経活動と時間感覚 意識の構成要素は、大脳皮質の神経活動によって維持され、特定の神経回路が興奮することで時間の経過を感じることができます。これにより、時間は直線的に流れるものではなく、より複雑な神経の協同現象として理解されるべきです。 結論 このように、時間の謎は多岐にわたる要素から成り立っており、時間の向き、未来の決定性、タイムパラドクス、時間の流れの感覚についての理解は、物理学や神経科学の観点から新たな知見をもたらします。時間は単なる流れではなく、物理現象や意識の構成要素と深く関わっていることが示されています。 本書で強調されている内容のまとめ 1. 量子論と干渉 - 干渉と脱干渉: 量子論における波動性と粒子性の二重性に関する実験結果を強調。特に二重スリット実験における干渉パターンの形成が重要視されている。 - ピッグパンのパラドクス: 時間の流れや因果関係についての新たな視点を提供。 2. 時間と空間の理論 - 時間の向き: 時間は過去から未来への一方向に流れるのではなく、エントロピーの法則と関連している。 - ミンコフスキーの幾何学: 時間と空間が相互に関連し、時空としての枠組みを持つことを説明。 3. 原子時計とその実験 - 運搬時の影響: 原子時計の精度に影響を与える要因として、温度変化や標高の違いが挙げられる。特に、標高が高いほど時間の進み方が速くなることが確認された。 - 重力の影響: 重力が時間の尺度に与える影響についての実験結果を示し、重力による時間の遅れを具体的な数値で示す。 4. エントロピーの法則 - エントロピーの増大: 自然界の物理過程におけるエントロピーの役割、特に不可逆的な変化としてのエントロピーの増加が強調される。 - 熱とエネルギーの移動: ヒートポンプなどのメカニズムを通じてエネルギーの移動やエントロピーの減少が可能である点を説明。 5. 相対性理論と時間の理解 - アインシュタインの理論: 相対性原理に基づく時間と空間の理解が進められ、静止と運動の区別が原理的に存在しないことが示される。 - 時空のゆがみ: 大きな質量を持つ物体が周囲の時空をゆがめる様子を説明。 6. 時間のパラドクス - タイムループの可能性: 時間旅行が可能である場合、過去の変更がもたらすパラドクスについて議論され、特に「親殺しのパラドクス」が取り上げられる。 - 時間の流れと因果関係: 時間の流れが因果関係に与える影響についての見解が示され、未来の出来事が過去に影響を与える可能性が探究される。 7. 意識と時間の感覚 - 意識の構成要素: 意識は瞬時の情報処理によって形成されるものであり、時間の感覚もこのプロセスによって生まれることが説明される。 - 「ルビンの盃」の例: 意識の変化についての具体的な例を通じて、視覚情報がどのように処理されるかを考察。 結論 本書は、量子論、時間、相対性理論、エントロピー、意識の形成など、現代物理学の豊かな内容を包括的に扱っており、自然界の基本原理に対する理解を深めることを目的としている。特に、時間の流れや因果関係に関する新たな視点が強調され、読者にとって興味深い洞察を提供している。
0投稿日: 2025.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
イメージするのが難しい部分もあったが、物理学だけの切り口だけでなく、脳の働きから人間の時間の感じ方を論じていることが面白い。 脳の働きについては、「進化しすぎた脳」でも近い話が載っていたと思う。
0投稿日: 2023.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
少し難しい話でしたが、物理学について学習できました。相対性理論なども少しずつ学習して理解できるようになりたいと思います。
0投稿日: 2023.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ噛み砕いて書かれているとは思うのですが難しい。 ただ、“定説”とか“常識”などに対して疑問に思って調べてみたりすると面白い発見があるなと感じました。
0投稿日: 2022.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ3回読んだけど理解できないことばかり。 ブルーバックスだよね。まぁだからといってこれ以下のレベルまで落とせないのかもしれない。 頭悪いのに評価してごめんなさい。
0投稿日: 2022.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログとても難しい著書だった やはり自分は量子論などをすぐには理解できない 実際に感じるものと違う世界が実際にはある 量子論が今現在の最先端の物理学 時間は無数に存在している
0投稿日: 2022.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログニュートン力学、特殊相対性理論、一般相対性理論、量子論の関係と、時空の意味。 素粒子から成る原子、分子、ビッグバンから成る宇宙の物理。 そして地球上で我々人類が見知っていた物質、更には生命の成り立ち。 最後に脳の反応から時間は我々が感じているものであったとは。 知らなかった事を総括的に説明して頂き、大変勉強になり、考えさせられる事が増えました。
0投稿日: 2022.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログオーディオブックにて。 内容が難しくてあまり頭に入らなかった。タイムマシンとかタイムリープとかの話は想像しやすかった。
0投稿日: 2022.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間の話はSFっぽい観念も含めて 気になってしまう。 標高差が時間の進み方に与える影響を調べた実験から始まって 「タイムパラドクス」「時間はなぜ流れる(ように感じる)のか」など ワクワクする小見出しが並ぶ。 とはいえ、中身はそれなりに手ごわい感じではあるんですが、正直 なかなかきっちりついていくのは難しかったです。 時間が位置と比べて特権的なものではない、というところだけわかっておけば 一般人としては十分でしょうか。 逆に、詳しく知りたい人向けの短めのコラムも充実していて だいぶ欲張りな新書になってると思います。 未来は決定されているのか、など SFの設定にこだわりを持ちたい人はこのあたりのことは 目を通していてもいいかもしれないですね。 議論になっているところもそのまま提出されていることが多くて 探求心の強い方に応えてくれる内容ではないでしょうか。 時々ロマンティックな言い回しも出てきて、 そういうところもよいですね。 ”相対性原理を認めるならば、「現在」だけがリアルなのではなく、「過去」も「未来」も同じようにリアルだと考えざるを得ない。「現在」という物理的に特別な瞬間など、もともと存在しないのである。(p.76)” この後、「持続的に存在する」という用法が批判されているときに、ベルクソンを思い出すけれども、彼は意識について持続を用いたのであって、物質が持続しているわけではないので、彼の主張は維持できそう。 そして、実際、本書の時間の流れも意識にかかわってくる。 ”人間にとって日常的な大きさとは、空間が1メートル程度なのに対して、時間は1秒程度である。人間の時間のスケールは、物理的に自然な単位の数億倍である。 日常的に使われる時間の単位が空間に比べて桁外れに長いのは、それだけ脳の働きがゆっくりしていることを意味する。(p.208)” 光が自然現象の基本だとしたら、という話ではあるけれど、 光が速いというよりも脳が遅い、というのも面白い。
0投稿日: 2022.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間がどこから来て、なぜ流れるのかなんて普通の人には当たり前過ぎて考えたことも無かった。理系の方々はそのような事を、量子論やら微分方程式やらエントロピーやらを用いて解き明かそうとして、なんかもう本当にご苦労様です。
1投稿日: 2021.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログひさびさに読んだブルーバックス。時間の概念を相対性理論、量子論、宇宙論、脳科学など分野横断しながら説明することを試みる本。時間に方向性があるのはビッグバンがエントロピーの低い秩序立った状態から始まったからという点と、人間の時間感覚や記憶認識は光や素粒子反応など多くの物理過程に対して人間の神経反応の処理速度が遅すぎることにあるという点は特に印象的。その他、タイムリープやタイムパラドックス、世界線、量子ワープなどSFネタの背景にも多く触れられてて楽しかった。
0投稿日: 2021.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ“時間”について、物理的な概念や人が認知するものを解説している。本書を読むと、時間は宇宙で一様に流れていないことや、時間も空間のように拡がりを持つことなど、時間に対する認識が変わる。「時間が流れる」という認識があるのは、意識が影響しているようで、著者は脳の仕組みから時間の流れについて解説している。カバーする範囲は想像以上に広く、本当に理解するには、この1冊だけでは無理だが、考え直すきっかけくらいにはなると思う。一般に向けて解説しているので数式は一切出てこない。その分、図で感覚的に理解させようと努力されているのだが、まだ難しい。もっと図を入れてほしかった。著者の他の本を読んで、もっと理解を深めたいと思う。
2投稿日: 2021.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログものすごく楽しく、面白かった 普段、ノンフィクションを読まないし理系は苦手な自分でも楽しめた 読んでからも、謎は残って、あれこれ時間について考えたのも楽しい時間。
1投稿日: 2021.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで、分かったつもりであった点が、この本でより深く理解できた。 例えば、時間軸を含む4次元世界では、時間も空間の如く広がりを持つと言う点は見聞きしてはいた。しかし、本書の「物体は時間方向に伸びた存在」という指摘や、ミンコフスキー幾何学の説明等々で、「時空」のイメージの解像度が増した。 (光速度不変より、ローレンツ普遍性の方が重要視されるのも、分かった気がするぞ!) エントロピー減少の話も分かりやすかったし、量子論の「観測の有無に関係しない客観的量子論」と言う観点は、新鮮であり、腑に落ちるものでもあった。認知のフローから切り込む最終章も、得るものが大きかった。 落ち着いていながらも熱い文体も良かった。 著者の量子論の本も今後読んでみたい。
0投稿日: 2021.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は哲学からのアプローチとはまた違った、「時間とは何か」という問題への取り組みを、専門的な知識のない人にも明らかにしてくれるものになっている。わたしはどちらかというと、この手の問題については物理学からではなく哲学からのアプローチのほうに馴染みのある人だったが、全体を通して読んでみると、こちらの方が言っていることがはっきりしていて、より多くのことが明らかになっているような印象を受けた。ただ、物理学についての知識が高校の物理基礎程度しかなかったのと、図書館の返却期限に追われて読んでいたのとで、なかなか理解が追いつかないところがあったので、また時間のあるときに読んでみたい。
1投稿日: 2021.06.13時間は実在しない。
非常に面白かった。 時間については、これまでもわずかながら書籍を読んでいて、非常に興味を持っていた。少し前に、カルロ・ロヴェッリ氏の著書を読んで、何と無く自分なりの答えがつかめて来ていたが、本書を読んで、さらに自分なりの理解が深まったように感じる。 本書は2部に分かれていて、前半で時間とはどういうものかの本質に迫り、後半でその性質からくる様々な疑問に答える構成になっている。自分にとっては、とてもわかりやすく、興味深い説明が聞けたと思う。 時間とは、誰にも尋ねられなければ自明のものだが、誰かに説明しようとすると非常に難しいものだという。もう少し読み込んで、自分の言葉で説明できるようになりたい。
0投稿日: 2021.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ物理学のみならず脳科学にも触れ、時間が流れるとはどう いうことかを解き明かそうという意欲的な著作。数式を 使わず例えによって直感的に理解できるように書かれている ので理解するのはさほど難しくはなかったのだが、その内容 について納得するかどうかは別問題だと思う。特に脳科学に 話が及ぶ段になると、その短さで済ませていいのだろうか という気になってしまった。 ビッグバンの瞬間が最もエントロピーが低い秩序立った状態 だったという点と、人間の情報処理能力は圧倒的にスロー だという点が印象に残る。
0投稿日: 2021.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく難しいことをなるべく簡単に説明しようとしてくれているけど、やはり難しい。 若干持論ぽいところがあるのだが、定説としてとらえてよいのだろうか。
0投稿日: 2021.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
耳学ではついて行けなかった。とても難解。ただ、量子論や相対論など、私の時代の高校物理では触れられもしなかったテーマに興味を持てたので、また後日、今度は紙の本で読んでみたい。 以下は、読書メモ。 ニュートンは「宇宙全域に一様に時が流れる」と考えていたが、 アインシュタインは「場所が変われば、時間の進み方も変わる」と考えた。 私たちは、「未来は想像、過去は記憶、現在のみがリアル」と考えがちだが、物理学的にはその根拠はない。時間も空間と同じものであり、「ここ」が「あそこ」や「そこ」と同様に存在するのと同じく、「今」と等価に「今」以外が存在する。 時間は場所によって異なるので、物体が運動しているか、静止しているか、は、実は実験ではわからない。 ウラシマ効果(観測者によって時間の流れが異なる)の説明。 時間に向きがあるのは、実は『ビッグバンが極めて整然とした状態であり、そこからエントロピー増大の法則に従って、完璧な状態が崩れていくという不可逆的な反応が起きている』から。ビッグバン以降に星が生まれる(乱雑からまとまりへ)のも、ヒートポンプにおける熱の原理と同じやり方で説明できる。 未来は、初期条件で決定されているのではなく、ある確率で生起する不確定性原理によるもの。タイムパラドクスは、生じ得ない。 時間が流れるように感じるのは、人間の錯覚。脳は必ずしも時間軸にそって物事を認識背背宇、理解しやすいように処理している。物理的現象の生起するタイムスケール(ミリ秒以下)を認識できない(神経伝達は、イオン反応などの「ゆっくりした」物理現象によるものだから)から。
0投稿日: 2021.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログニュートン力学では時間も空間も研究対象ではなく(と言い切ると語弊があるか)、天与の目盛りとして背景にある。 ローレンツ対称性がマクスウェル方程式に見出されて相対論から時空の相対性が確立されると、時間も空間も観測系の運動状態に応じて相対的なものとなり、本書のテーマで言えば時間など物理的には存在しないこととなった。 時間が流れるように感じられるのは人間の知覚と脳内情報整理の結果でしかない。 というようなことを飄々と解説しているわけだが、類書よりも面白かった。学者としての防御姿勢を過剰には取らずに言い切る書き方のためだと思うが、これが本書の真骨頂。 また、ニュートン力学では過去も未来も計算できるが、量子論で粒子が揺らぐ結果として決定論的には計算できないとの指摘もあり、言われてみればなるほどその通りだが改めて蒙を啓いて頂いた。 類書にない踏み込みのある名著だと思う。
0投稿日: 2021.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ物理学的には時間の流れは存在しない。 前著の「宇宙に終わりはあるのか」がとても面白かったので読んでみたが、こちらも刺激的で好奇心をくすぐる一冊でした。 第Ⅰ部の相対論、ウラシマ効果などはある程度理解できたが、第Ⅱ部初めの「時間はなぜ向きを持つのか」については難しかった。秩序あるビッグバンとエントロピー増大の法則を元に説明されているがなんとなく腑に落ちず。 最終章も脳は無意識の行動を後から整理しているに過ぎないという話は聞いたことがあったが、構造的な処理速度の問題から時間が流れているように感じられているというのは興味深い。感じられない過去未来も現に存在していることを意識して生きてみるのも面白いかも。
0投稿日: 2021.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間とはなにか?を論じるためには宇宙の始まりについて考えなくてはいけないの、わくわくしません? 時間がないないと普段言っているけど結局なんなんだろう、と思って手にしたこの本。高校物理と医学を少しかじったくらいで、なんとかついて……いけ……はないですが振り落とされはせず、楽しく読めました。 わからないところも勿論ありますが、出来る限りやさしく書こうとしていただけてるのが伝わります。 物理から地学、数学、化学、はては脳神経学まで、学際的な本を読むとやっぱりわくわくがとまりません。 読み終わったら「今まで考えていた時間なんて存在しなかった…?」というような不思議な感覚に陥ります。 結局時間は私が今まで考えていたような絶対的なものではなく、物理変数のひとつであるということ、そしてフィルム映画のようにコマ切れに瞬間が積み重なっているのではなく、広がりのあるものであること(空間のように)。新しい概念をいっぱい手に取ることができました。ありがとうございます。
2投稿日: 2020.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000328588 , http://www005.upp.so-net.ne.jp/yoshida_n/
0投稿日: 2020.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ素粒子の専門家による時間の話。過去は過ぎ去ったもの、未来はまだ見ぬもの、現在だけが存在しその瞬間はすべての場所で同一時刻というのは、ニュートン力学の世界の話であって、現代物理学では、時間はすべての場所毎で異なるものと理解されている。Blue Backsらしく論理的にかつ明快に、時間について説明している。もちろんすべてが理解できたわけではないが、勉強になった。 「(5台の原子時計による実験)5台の時計のどれもが、標高が低いほどゆっくりと、高くなるにつれて早く進んだ。セシウム原子から放出される電磁波の振動回数で言うと、小金井本部に対する変化の割合は、おおたかどや山送信所で100兆分の8、はがね山送信所で100兆分の13だった」p22 「かつては太陽の動きを利用した日時計や、振り子の等時性を使った振り子時計を使っていた。だが、近代以降に利用される正確な時計の大半は、金属製バネの振動を利用した機械式時計も含めると、原子スケールで起きる周期的な振動現象を利用している」p38 「媒質中を伝わる光の速度は、真空中に比べてn分の1に低下する(電磁気学の法則によって、屈折率は必ず1より大きくなる)。例えば、水の屈折率は1.333であり、水中では、光は真空中の4分の3の速度で進む」p41 「「未来」はまだ実現されず「過去」はすでに過ぎ去ったのだから、どちらもリアルではなく、ただ「現在」だけがリアルだ。こうした常識的な見方を支持する物理学的な根拠はない。相対性原理が成り立つならば、「同じ時刻」を一つに決められず、したがって「現在」という「それだけがリアルな瞬間」が実在することはない。過去・現在・未来という区分は、物理的に無意味である。「ここ」以外にさまざまな場所が存在するのと同じように、「いま」以外にもさまざまな時刻がリアルに存在する」p50 「素粒子論によると、光以外にも、時間と空間の界面に沿って進み、速度が1(ないし1に極めて近い値)になる素粒子がいくつかある。ただし、その大部分は、原子スケールよりも遥かに短い距離しか進めないので、実際に観測するのは難しい。例外的に長距離を進むことができるのは、光以外には、ニュートリノだけである」p102 「大マゼラン雲は、地球から16万光年の距離にある。16万年前にここで生じた超新星爆発で、さまざまの放射や物質が放出されたが、そのうち地球に到達できたのは、光とニュートリノだけである。観測結果によれば、爆発によって放出された光とニュートリノは、宇宙空間を16万年にわたって飛び続けた後、どちらも1987年2月23日に地球に到達した。最初に観測に掛かった光とニュートリノの到達時間差は、わずか3時間しかない。ニュートリノは、16万年もの間、ほとんど光と並んできたことを意味する」p103 「互いに運動するアリスとボブが、手元に時計を持っていることを考えよう。このとき、アリスとボブの時間軸は互いに傾いているので、斜めになった2つの物差しと同じように、相手の時計の進み方が自分の時計と異なるように観測される。これが「動く時計は遅れる」という現象である。この遅れは、互いに斜めになった物差しのケースと同様に、あくまで見かけのものであり、現実に時間の尺度が変化したわけではない。アリスからするとボブの時計が遅れるのだが、ボブの目にはアリスの時計が遅れるように見える。実際には、どちらの時計も同じように時を刻んでおり、天体近くで重力作用を受ける時計のように、現実に遅れるわけではない」p106 「空間内部での回り道は、直線ルートに比べて必ず道のりが長くなるのに対して、時間と空間を併せた世界では、回り道をした方が経過時間が短くなる。これは、ミンコフスキーの幾何学では、長さを定義するのに時間部分と空間部分の差を取るせいである。空間で遠回りをすると、道のりはかえって短くなる」p109 「宇宙背景放射は、1964年に衛星通信用に地上に設置されたアンテナで初めて観測された。宇宙からの背景放射は、温度がほぼ零下270℃(零下273.15℃を零度とする絶対温度で表すと、2.725度)の物体の放射と等しい。この温度が場所によってわずかに異なっており、その揺らぎが10万分の1程度であることを明らかにした(2006年ノーベル物理学賞受賞)」p124 「揺らぎがわずか10万分の1しかなかった点こそが重大である。10万分の1の揺らぎとは、どんなものなのか。容器に、小麦粉を10㎝の厚さに敷き詰める場合を考えよう。小麦粉粒子の大きさは数十分の1㎜なので、場所による厚さの違いが10万分の1とは、小麦粉1粒の何十分の1かのデコボコしかないことを意味し、見た目には完璧なまでに平坦な状態である。同じ厚さの金属ならば、表面に髪の毛一筋(0.05~0.08㎜)ほどの傷もなく、鏡のように光を反射するだろう」p125 「(時間の方向性)「なぜ過去から未来へという方向性があるのか」という謎に対しては、「宇宙の始まりが整然としたビッグバンだったため、この完璧な状態が崩れていくという形で、時間の方向性が生まれた」と答えることができる」p126 「ビッグバンが整然としておらず、エネルギーの揺らぎが大きいと、宇宙空間のあちこちに巨大なブラックホールが形成されてしまう」p129 「気体では分子同士の接触が稀となり、固体では動けないため、いずれも化学反応が進まない。熱の流入に応じて化学反応が進行するためには、分子が液体の中を動き回れなければならない」p138 「地球は、太陽光線を浴びる地表でエントロピーの減少を実現し、生命にあふれた惑星になれたのである」p140 「惑星上で活動する生物の姿だけを見ると、宇宙とは無縁の時を刻んでいるように感じられよう。しかし、実際には、生化学反応は太陽からの光の流れに駆動されて進行する。あらゆる出来事が、ビッグバンの整然とした状態が崩れていく過程の一部であり、「ビッグバンから遠ざかる向き」に進行する不可逆変化なのである」p141 「ヒットを打った後のインタビューでは、球種を見極めてからバットを振る決断をしたと答えることがあるが、これは、生理学的にありえない。目で見てから体を動かすまでの反応時間を考慮すると、球種がわかるほどボールが進んでからでは、バットをボールに当てることは不可能である。バットを振る意思決定が行われるのは、投手の手からボールが離れた直後(あるいは直前)のはずである」p203 「人間の頭の回転は、多くの基礎物理過程に比べて、極めて遅いと考えた方がよい」p208
1投稿日: 2020.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
前半は相対性理論の説明。光りは時間と空間の界面を走るのでそれ以上の速度はありえないという説明はなるほどとおもうのだけど、グラフの図が無いとわからんかったかもしれない。 時間は空間のように広がっていて、過去も、未来も現在もない。それは脳の錯覚であるということ。 で後半は、量子論と脳科学にまで話がすすんでいく面白かった。 いろいろと創作のネタになると思う。
1投稿日: 2020.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学的な時間論を交えず、諸科学を横断して「時間とはなにか?」の問いかけに答えを求めていく。後半、ヒューム的な「現在」に近づきつつ「ヒュームとはやや異なる現在」が解説されているあたりはおもしろい。 「時間」という主観的な存在を「科学」というなによりも客観性が求められる分野で語ることの楽しさあふれる一冊でした。
4投稿日: 2020.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間は過去から未來へ流れない。 時間と空間の関係。 脳が人間の記憶を捏造している。 親殺しのタイムパラドックス 時間という目に見えない世界。ひとの⏱️の感覚が秒に対して時間は無限に広がる。正直、本の内容を最後まで理解しきれなかったですが、宇宙から見たら、ひとの悩みや些事なんてないようなものだと実感。アインシュタインの相対性理論は何も分かりませんが、物理の原則を越えた時間の流れの尻尾を人類はいつかつかめるのかな。
0投稿日: 2020.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログウラシマ効果、世界線。タイムトラベルものでよく出てくる単語がここにも登場し、門外漢でもそれなりにわかるよう解説されている。 ミンコフスキー、エントロピー、量子論。時間というものを理解するために必要な前提知識、素養は莫大な量であることが伺いしれる。 本書は極力わかるように、と腐心したあとがみてとれるが、それでも難解だった。
0投稿日: 2020.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ我々が時間が流れるように感じるのは「錯覚」.時間は空間同様に複数あるし,空間と不可分.どこかで聞いたような話であるが,より明確に説明されている.
0投稿日: 2020.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでるときは理解できるけど、読み終わってからなんだかよくわからんってなった。その原因を考えたけど①ほんとは理解できてなかった、②直感に反することを抽象的な議論で進めてる、③そもそも難しく相対論や量子論を未習だとこうなる、の三つが寄与してるんだろうなあという感じだと思う。出直します。
1投稿日: 2020.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ相対論の基礎の復習になった。ただ、ビッグバンがあるので一方向に流れているように見える、の件がよく理解できなかった。読み直さないといけないと思う。 終章は人間の認識の仕方に言及しており、残念ながらこれも理解はできてはいないが、そこから攻めるか、という印象を持って、面白かった。
0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ当方の無能力はひとまず差し置くとして、少々惜しい内容かと。 インフレーション理論からの時間の考え方など、おっ、なるほどーと思わせるものが多々あるのにそれを上手く「読ませる」内容に消化・昇華できていない感あり。まざ、専門家からすれば、この程度は当然なんでしょうが、書きよう・読ませようは一杯あるよなぁ、と思わざるを得ず。返す返す惜しい。
0投稿日: 2020.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログウラシマ効果やタイムパラドックスの原理等について、数式は使わず読み物として説明していますが…まぁ難しいですねw わたしの期待が SF 寄りだったせいもあるのか、ワクワク感なども少し中途半端な感じでした。
0投稿日: 2020.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログビックバンが極めて均一な高温状態だったから、そこからエントロピーが増大する方向に時間の方向性が生まれたといっている。が、そこに説明がほとんどない。エントロピーの増大の法則が時間の矢だといっているのと同じで、何も説明いない。時間が流れるように感じるのは、人間の意識によるものだというのも賛同できない。人類が誕生する以前から、地球の歴史(地球時間の流れ)が地表に刻まれているし、地球から見た宇宙の歴史は遠い天体から観測できる。 「時間は存在しない」という本があったが、その本ではエントロピー増大と時間の矢とは無関係と書いてあった。が、個人的には、完全な平衡状態の熱力学的死に至ったとしても、光は振動するし、固有時間は存在すると思う。時間の矢の方向性は、ビデオの逆回ししても区別できなくなるので、はっきりしなくなるのは確かだが、やはり、固有時間は過去から未来に流れると思う。
0投稿日: 2020.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
素粒子論を専門とする理論物理学者による、「時間」に関する一般向けの論考。前半は主に(特殊)相対論の解説となります。ブルーバックスなので数式はなるべく使わずに、相対論を分かり易く説明してあります。その辺は読みやすくてともて良かった。でも相対論はあくまでも導入で、本書で著者の言いたいことは、どうも「時間は一方向に流れたりしない」と言うことのようです。時間を計る目盛は何らかの物理的な振動現象に過ぎない。空間軸上を自由に行き来できるのと同様に、時間軸上も本来自由に行き来できるということのようです。相対論的には時間の流れ方が観測者によって異なるのも理解できるし、ミンコフスキー空間のような理論的な扱い上で時間軸を空間座標軸と同等に扱うのは良いとしても、「時間が流れない」とはどういうことなのか。著者としては、「ビッグバン以降、宇宙のエントロピーが増大する方向に物事が進んでいる」だけであって、「時間なんて流れていない」ということのようです、多分。でも、その辺の著者の主張が良く分からなかった。エントロピーが増大する方向に物事が変化することを「時間が流れる」と言っても良いと思うので、トートロジー的な印象を受けたのだが、私が理解できてないだけなのかもしれない。 終盤ではさらに、著者の専門外の心理学、脳科学的な最新の研究結果からインスピレーションを受けた考察が論じられています。 「時間が(過去から未来へ一方向に)流れる」と感じるのも人間の錯覚にすぎない。人間の意識(脳)は必ずしも(時間軸に沿って)順番に起こった通りに現象を認識するのではなく、適当に順番を入れ替えたりという処理をしてから意識として感じている。その順番自体が、人間が時間の流れと思っているだけである、と。 人間の”意識”とか”心”は大脳皮質の脳神経がなす高次の抽象的な存在(システム?)なので、物質的、量子論的に論じることは不適切のように思われるが、著者はそうではないと論じている。たとえば水素分子は水素原子の集まりではなく、水素分子として量子論的な共鳴状態が存在するのであり、水素分子自身が独立して存在すると見なせる。ベンゼン分子は炭素原子6個の集まりでは無いのと同様。それを拡張していけば、人間の意識も一つの共鳴状態として独立した存在と見なすこともできるだろう、とのこと。南無~~。
0投稿日: 2020.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しかった。現代物理学の基本である場の量子論はニュートンなどの古典的な原子論とは違うロジックで物理現象を記述しようとする。時間は空間と一体となって時空となり、場所によって時間の進み方は違う。時間とは何なのかを場の量子論を元に簡易に説明してくれるのだが、中々頭には残らない。頑張って想像しようとするが難しい。ただ、物理学者達のそうした日々の努力の結果、色々な基本的な物理原則が解明されてきているというか、様々な方法で問題に解を与えようと試みている事は良く分かった。分からないけどたまにはこうした本を読み、分かろうと努力してみるか。ビックバンの前?直後は整然とした空間でだからこそ時間に方向性が生まれるとか分からないけど面白い。
1投稿日: 2020.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「時間はどこから来て、なぜ流れるのか?」 吉田伸夫(著) 2020 1/20 第1刷 (株)講談社 2020 3/8 読了 難しい事を難しく書いてある本。 知れば知るほど 分からない事も増えて行く。 分からない事が無いと存在出来ないのが 研究者という職業なんだろうなぁ。 簡単に分かっちゃったら 仕事が無くなるもんね。 思ってた以上に認識って 個人差があるんだろうなぁ… 空間や時間は もはや真実は自分のオモイの中にしか 存在しないのかも。 眠れない夜には最適な本ですが 良い夢は見られないかもねー。
6投稿日: 2020.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し前にカルロ・ロヴェッリの「時間は存在しない」を読んだのですが、日本語版のタイトルにまんまと騙されました! なんと原書のタイトルは"L'ordine del tempo”だし英語版は”The Order of time”だった。 上記の本においても、ちゃんと時間は存在していることを事実として話を進めています。 「時間」について考えるお助け資料としては、まさにBLUE BACKS 的解説の本書のほうがとっつき易いです。 ポイントを簡単にまとめてみました。 第一部 現在のない世界 第1章「時間はどこにあるのか」 ニュートンが思っていたように宇宙全域に単一の時間が流れるのではない。あらゆる場所に個別の時間がある。 観測で確認された事実(相対性理論:重力の作用による時間の伸び縮み)のおさらい。 第2章「過去・現在・未来の区分は確実か」 場所によって時間も異なる。 「ここ」以外にさまざまな場所が存在するように、「いま」以外にもさまざまな時間が存在する。 「現在」という物理的に特別な瞬間などもともと存在しない。 第3章 ウラシマ効果とは何か 飛行機に原子時計を積んで長距離飛行すると、地上に残した時計よりフライトをした時計の方が理論的な予測どおりに遅れる。 第二部 時間の謎を解明する 第4章 時間はなぜ向きを持つか ビックバンから遠ざかる向きに進行するエントロピー増大の法則。これが「過去から未来へ」という時間の方向性。 生命の秩序正しさは究極のエントロピー縮小のように思えるが、太陽からの光の流れに駆動されて進行しているエントロピー増大の法則の中で生じる一現象にすぎない。 第5章 未来は決定されているのか 不確定性原理により決まらない。 初期条件が確定しないので「始まりの瞬間にすべて決まっていた」ということはあり得ない。 これは複雑すぎて天気や地震を正しく予測できないことと本質的に異なり、物理学の本質的な結論。 第6章 タイムパラドクスは起きるか 過去に戻って自分を生む前の親を殺すと自分はどうなるか?という因果関係のパラドクス。 タイムワープの可能性としてはいろんな仮定を元に「負の質量が存在すれば過去に戻るルートが考えられる」というがそんな物質は見つかっていない。 タイムパラドクスは起きようがない。 第7章 時間はなぜ流れるように感じられるのか 物理的には現在という特別な瞬間は存在しないのに、心理的には現在しか存在しないように思える。 熱いものに触って、手を引っ込めた。引っ込めるのは脊髄反射で、引っ込めた時点では脳に熱いという信号は届いていない。 脳は「熱いと知覚したから手を引っ込めた」という時間に沿ったストーリーに作り替えて記憶する。 脳の記憶のありかたによる。 最後の章は物理学的な回答ではありません(私の個人的な意見です)。 物理では自然界で起こる出来事の背後にある基本法則や原理といった根本的な部分を "理由は考えずに" 究明する学問です。 なぜ宇宙が存在するのか?のような質問の答えを考えるのは哲学です。 ましてや時間の感じ方といった意識の話になると、物理学者に感じ方の答えを導く方程式は作り出せませんから。
20投稿日: 2020.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログいったん積読 「#時間はどこから来てなぜ流れるのか?」(ブルーバックス、吉田伸夫著) https://amzn.to/39CpZq4
0投稿日: 2020.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトル通り「時間」について物理学の視点から紐解いていきます。 世界中の時計は実は場所によって進み方が違うなんて話はとても興味深くワクワクしますね。 過去・現在・未来と時間は流れていくのか、それとも時間に流れなど無いのか。 面白かったです。
1投稿日: 2020.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間はどこから来て、なぜ流れるのか。 時間の神秘にとても興味をそそられます! ぜひ読んでみたいです(*^^*)
1投稿日: 2020.01.29
