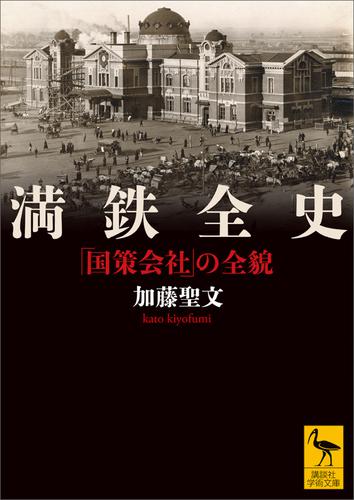
総合評価
(7件)| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ植民地経営の主力となる民間の会社、という意味では、オランダ、イギリスにおける東インド会社に当たるような位置付けの満鉄のお話。 有名どころでは、満鉄OBとして、後藤新平、松岡洋右、十河信二(初代国鉄総裁にして新幹線の生みの親)、岸信介、宮崎正義(石原莞爾の”先生”)、などが登場。 外務省、陸軍省、陸軍参謀本部、関東軍、拓務省に翻弄されながらも、大陸最高のシンクタンクとして奮闘した満鉄調査部の活躍は良い。
4投稿日: 2022.09.28「国策である」ことは免罪符にならないし、してはならない
後藤新平が東インド会社をモデルとして構想した組織が、満鉄・外務省・関東軍・政党等々にこねくり回されていった様子が克明に記されています。 国家戦略や国策という言葉が日本において見かけは華々しく、実は曖昧で無責任で暴力的であることは、現在進行形でよく見る景色です。その貴重な事例を、少し引いて確認できるのはありがたいことだと思いました。
0投稿日: 2020.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログプロローグ―「国策会社」満鉄とは何だったのか 第1章 国策会社満鉄の誕生 第2章 「国策」をめぐる相克 第3章 使命の終わりと新たな「国策」 終章 国策会社満鉄と戦後日本 エピローグ―現代日本にとっての満鉄 著者:加藤聖文(1966-、愛知県、日本史)
0投稿日: 2019.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「満鉄」 この言葉から受けるイメージは、中国東北部を支配した機関というものがあるが、この本を読んでみると、そう言う通りいっぺんの事柄では語れないほど複雑な組織であったことがよくわかる。 そして、満鉄と言えば“アジア号”であるが、その高速列車と中国東北部を支配したと言うイメージが、どうも一致しなかったが、ま「いろいろあったんだな」と言う事がよくわかった。 驚いたのが、戦後、東海道新幹線を実限させた十河信二が、満鉄の理事経験者であったと言う事。不勉強でした。十河に限らず、あの当時の政財界の重鎮達は、多かれ少なかれ、どこかで交わっているんですね。
0投稿日: 2019.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は2006年に登場し、2019年に文庫本になっている。その辺は“あとがき”にも少し詳しく触れられている。本書は、より手にし易い文庫本となって、より広く読まれる価値は高いと思う。 「満鉄」というので、昭和の初め頃の<あじあ号>のような話しが詳述されているのかとも思ったが、本書はそういうようなことに力点が置かれているのでもない。日露戦争後に鉄道の権益を得たことから会社が興され、それ以降の会社が辿った経過、大陸での様々な展開との関係、満鉄の内部や周辺で活動した色々な人達の事績や言行、それらが「戦後処理」というような段階に至るまで、読み易い範囲を逸脱しない程度に、かなり詳細に語られている。正しく「全史」なのだ。 本文をゆっくりと読んで読了したが、本書にはかの後藤新平や松岡洋右というような少し有名な名前を含む歴代経営陣の名簿、かなり細かい“満鉄社史”的な年表や、本格的研究をする人にも有益であろう参考文献等、充実した資料も収められている。 或いは本書は、「満鉄の記憶」というモノが喪われてしまう直前の時期に貴重な証言や史料を掘り起こす事も伴いながらの、価値在る研究を纏めた一冊かもしれない。色々な意味で広く薦めたい。
0投稿日: 2019.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ満鉄ってアジア号か満鉄調査部、しかも名前くらいしか知らなかったんやけど、松岡洋右とか十河信二とか出て来てびっくり。いや、松岡洋右は時代的に納得やけど、十河信二って新幹線の人としか知らんかったから。
0投稿日: 2019.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ満州と聞くとワクワクしてつい本を手に取ってしまう。 もし20世紀前半に生まれていたら、絶対満州に行っていたと思う。そして新しい国家計画や大連のエキゾチックな街並みに浮かれていたと思う。 そんな満州帝国の基幹企業であった、満鉄の誕生から終結までを辿った本。 日本人のご都合主義な帝国主義の妄想が花開いた、というか徒花と散った、壮大な40年。 もちろん現地に対する多大な侵犯行為で迷惑を掛けたに違いないが、それでも日本人が満鉄で何万キロもの線路を敷設し、石炭や製鉄、化学、物流、図書館や新聞社まで、100近い企業を興して産業を発展させ、現地民も何万人も雇用した。 戦後の中国東北部に大きな財産を残したことは間違いない。 当初から、満鉄は国内政治、外務省、軍の思惑に挟まれて押し引きされ矛盾を孕んだ存在だった。それだけではなく、ロシア、中国国民党、ドイツ、アメリカなど国際情勢の変化にも翻弄され続ける。 壮大な矛盾と妄想と。そのいかがわしさに惹かれずにいられない。 戦後満州に残された日本人は150万人に上ったという。 「流れる星は生きている」は私の中で衝撃的な読書体験だった。 今度は朝鮮、台湾統治についても読んでみたい。
1投稿日: 2019.08.01
