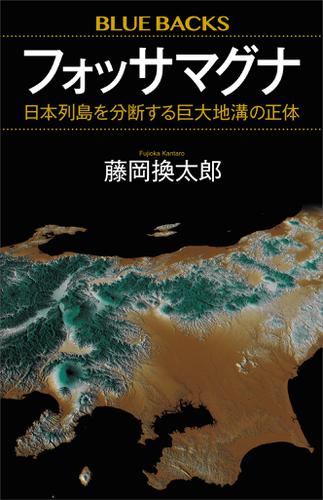
総合評価
(37件)| 10 | ||
| 16 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログとある事情により、「フォッサマグナについての知識を得たい」と思っていたところ、定期的に通っている図書館で見つけたので、借りて読んでみました。 恥ずかしながら、この本を読むまで、フォッサマグナについては、その成り立ちも含め、わからないことがたくさん、という事実を知りませんでした。 本書は、フォッサマグナ、あるいは、それに関係しそうな現象として、何がわかっているか、どこからはわかっていないかを明らかにしつつ、フォッサマグナ、そしてその成り立ちを類推していこう、という内容です。 そのため、本書については、すべてが事実、というわけではないのですが、「ここまではわかっている」「ここからは推測」であることを丁寧に補足しているため、たとえ正確さに欠けている部分があったとしても(大胆な推測であったとしても)、非常に誠実さを感じつつ、読み進めることができました。 フォッサマグナについて、北部と南部で成り立ちが違うことは、今回初めて知りました。 また、西の境界ははっきりしているのに対し、東の境界はよくわからない点は、何となく聞いたことがありましたが、どうやらフォッサマグナの成り立ちに関係するようで、この点については、今後の研究の進展により、きっと明らかになっていくことでしょう。 著者は、研究者としては第一線を退いているせいか、本書は、いい意味で肩の力が抜けた、読みやすい本になっていると思います。 それでいて、内容も充実しているので、いろんな方(とくに、地学を勉強している中高生)にお勧めしたい本だと思いました。 そういえば、ブルーバックスは久しぶりに読みましたが、最近は、こういう読みやすい本が多いのでしょうか? ブルーバックスの他の本も読んでみよう、という気にさせてくれた一冊でもありました。
0投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ途中知識のなさから難解に思うところもあったが、日本列島の形成の歴史がわかりやすくまとめられている。フォッサマグナは奥深い。地学や地理をもっと学生時代に勉強しておけばよかった。
0投稿日: 2024.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ1100 藤岡換太郎 1946年京都市生まれ。東京大学理学系大学院修士課程修了。理学博士。専門は地球科学。東京大学海洋研究所助手、海洋科学技術センター深海研究部研究主幹、グローバル・オーシャン・ディベロップメント観測研究部部長、海洋研究開発機構特任上席研究員を歴任。現在は神奈川大学などで非常勤講師。潜水調査船「しんかい6500」に51回乗船し、太平洋、大西洋、インド洋の三大洋人類初潜航を達成。海底地形名小委員会における長年の功績から2012年に海上保安庁長官表彰 この地形に関心を抱いたナウマンはその後も、この地域を二度、調査旅行で訪ねている。 あらためていうと「フォッサマグナ」とは、本州の中央部の、火山が南北に並んで本州を横断している細長い地帯のことを言います。ナウマンはフォッサマグナの範囲として、日本海側の新潟県糸魚川市~高田平野付近から、太平洋側の静岡県旧清水市(現・静岡市清水区)~神奈川県足柄平野付近に至るまでの広い地域を示しています。北から見ていくと、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県、静岡県、東京都です。さらに関連する府県を入れると、富山県、岐阜県、群馬県を含む関東から中部日本となります。 このようにプレートの境界はほとんどが海の中の海溝です。そこでは海側のプレートが陸側のプレートの下に沈み込んでいて、プレートどうしのせめぎ合いが起こっています。これが「プレートテクトニクス」です。4枚のプレートがひしめく日本列島はたびたび巨大地震に見舞われるなど、数奇な変遷を繰り返してきました。そしてフォッサマグナについても、プレートテクトニクスを通して考えなければ理解できないのです。 私たち地質学者が研究を行う手法は、いわば探偵が殺人事件の全貌を明らかにするのとよく似ています。私は推理小説やミステリー映画が好きで、アルセーヌ・ルパン、シャーロック・ホームズ、金田一耕助などの登場する本を読みあさったり、刑事コロンボ、アガサ・クリスティなどの映画を好んで鑑賞したりしてきました。名探偵はいつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように、のいわゆる「5W1H」について、証拠捜しや聞き込みなどによってありとあらゆる材料を手に入れます。そして、それらの材料を用いて事件の動機や殺害の方法などを時系列にしたがって矛盾なく説明します。こうして事件の全貌がわかれば、一件落着です。 伊豆・小笠原弧の衝突にともなう、南部フォッサマグナでのさまざまな現象を見るのに最適なのが伊豆半島ジオパークです。伊豆半島全体と、その北の箱根との境界までが含まれるという広大さで、行政の中心は伊東市(静岡県)、本拠は修善寺にあります。 フォッサマグナについて知れば知るほど、日本列島のど真ん中にこのようなものを抱えていたら、いつ地震が起きるか、いつ火山が火を噴くかと、気が気でなくなってもおかしくありません。なにしろ、フォッサマグナ地域にはいまも活火山である富士山がすっぽり入っていて、糸静線などの活断層が何本も走っているのです。
0投稿日: 2023.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「フォッサマグナ」名前だけは覚えてるけど、何なんだっけなあ…と思ってたところに先日のブラタモリでの糸静線の回を受けて、再度興味を持ち、本書を購入したが、あたり。 まあ、仮説というか試案とはいえ、なーんとなく、フォッサマグナの成り立ちについてイメージを持つことができた。それにしても、不思議な地形なんだなあと改めて。
0投稿日: 2022.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「日本沈没」を読んだ勢いでこちらを。用語が専門的でところどころ難しかったですが、概要は理解することができました。それにしても日本列島の地学的に複雑なこと。もしかしたら何かのはずみで本当に日本沈没もあるんじゃないかと考えてしまいました。
0投稿日: 2021.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校の『地学基礎』適度の知識と、日本の地理についての知識がある程度あると、読み進めやすいと思う。 後半に進むにつれ、地理感や地質区分が整理できていないと、難しく感じてしまうかもしれない。 内容全体としては、非常に面白かった。 一読ではしっかり理解出来なかった。また改めて読み直したい一冊。
0投稿日: 2021.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログいまだ未知なもの。それの来歴を推測して行く楽しさ。 中央構造体についても触れられており、日本列島がどのような性格をもつのかを学ぶ楽しさがあった。
0投稿日: 2021.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログフォッサマグナ? ええ、知っていましたよ。 もちろん、名前だけを。 フォッサマグマとか、ホッサマグナと思っていた人と、何ら変わりないレヴェルですよ。 ということで、私も何も知らない状態だったのだ。 が、これが研究者にとってもわからないことが多いということに、まず驚く。 天竜川辺りから北を望むと、大きな凹地から、突然急峻な山々が壁のように立ち上がる。 これがナウマンに発見され、のちのフォッサマグナと名付けられた特異な地形。 西端は割とはっきりしている一方、東端がどこだか決められない状態なのだそうだ。 断層線のようなものだと勝手にイメージしていたので、糸魚川静岡線から、東は伊豆半島の東あたりまでの広大な領域、富士山もその中にすっぽり収まるという。 そして、関東山地の南北で、地質がかなり違うとも。 謎だらけのフォッサマグナ。 筆者は、「蛮勇を振るって」、どうやって形成されたかの仮説を出している。 キーワードはホットプルームとオラーコジン。 まだユーラシア大陸についていた原本州。 のちに日本海になるところに、プルームがY字に浮き上がり、それがふたつに分かれていた原本州の間を埋めた、ということらしい。 スケールが大きすぎて、ため息が出た。
0投稿日: 2020.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ斬新な仮説だが読み応えがあって面白い。フォッサマグナの形成に関するレビューにもなっている。頭の中が整理されて良い。北部と南部で形成プロセスが異なるのは合点がいく。伊豆小笠原弧の衝突と日本海の形成が同時に起こったのはホットプルームによるオーラコジンの生成に起因し、海溝三重点がそれを飲み込む形であるというのは、ホンマか嘘かはさておき、スッキリする説明でsる。
0投稿日: 2020.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログフォッサマグナミュージアムにまた行きたくなった。ジオパークにも行って断層みたくなります。微妙なバランスに住んでいる我々も奇跡かも。
0投稿日: 2020.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ◯面白い。ただ、この本の性質上、前半部分でややもたつくというか、うまく頭に入らないことがある。また、今更だが地名が頭に入ってないと、どこの話をしているのかよく分からなくなる。 ◯しかし、こういったことは抜きにしても、フォッサマグナの成立過程は実に興味深く、この本自体が一つの推理小説のようにできている。 ◯解答編の試論はまさに解決編で、いままでモヤモヤしていたものが一気に歩に落ちるところは爽快。 ◯この本のまとめがとても壮大な話で、地学の魅力に溢れている気がする。大変満足の一冊だった。
7投稿日: 2020.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログフォッサマグナ地域の東西では、約1~3億年前の古い岩石が分布しているのに対し、内部は約2000万年前以降の新しい岩石でできている。ボーリングによる掘削調査では、基盤岩に達したことはなく、深さは6000mと推定されている。 糸魚川-静岡構造線は逆断層になっており、新第三紀層の後期以降で見られる。 北部フォッサマグナに分布する地層は、砂岩や泥岩などの堆積岩が多く、約1600万年前から海底に堆積した地層。石油や天然ガスを産出することで有名な秋田-新潟油田褶曲帯にも、同様の地層が分布している。 南部フォッサマグナは、上下2つの地層群から成り立っている。下位の地層群のほとんどは、中新世中期の海底噴出の火山岩類と遠洋性の泥岩から成り、これらが堆積した当時は本州から遠く離れた海底であったと考えられる。上位には、中新世後期から鮮新世の地層があり、山地周縁の低地に分布する。陸地からの砂や礫が大量に含まれており、本州に近くなったと思われる。鮮新世の末までに海は退き、陸地になった。 中央構造線は、1億4500万~1億4000万年前に、イザナギプレートがユーラシアプレートに対してほぼ平行に北上したために、横ずれ断層が起こったことによりできた。 5200万年前に、太平洋プレートの運動の向きが北北西から西北西に変わり、伊豆・小笠原海溝への沈み込みを開始した。その後、3400万年前までに海底火山列が誕生し、伊豆・小笠原弧ができた。2500万~1500万年前に、四国海盆の拡大、フィリピン海の形成、フィリピン海プレートの北上、伊豆・小笠原弧の本州への衝突が起きた。伊豆・小笠原弧の衝突により、まず巨摩山地が形成され、1200万~1000万年前に御坂山地、500万年前に丹沢山地、100万年前に伊豆半島が形成された。 海溝から沈み込んだプレートがプルームの材料となる。プレートは、深さ670kmで停滞した後、重くなるとさらに沈み込んでいく。深さ2900kmに達して外核と接すると、高温となり、上昇流となる(プルームテクトニクス)。プルームはマントルの対流を引き起こし、マントルの上にあるプレートが移動する原動力になる。 著者は、日本海やフィリピン海を拡大させたマグマは、プルームの上昇によってもたらされたと考える。そして、北部フォッサマグナにあたる場所が日本海の拡大によって深海に陥没した時、ほぼ同時に伊豆・小笠原弧が衝突して陥没を埋め、大地を隆起させて南部フォッサマグナをつくったと考える。
0投稿日: 2020.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログブルーバックスを買ったのは20年振りくらいか?言葉としては聞いた事があったが全く知らないものだと分かりました。日本の地下にある鵺のような存在。世界で唯一かもしれない存在。まだまだ知らない事がたくさんあると分かる一冊。
0投稿日: 2020.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ・フォッサマグナ(FM)とは:大地溝帯.左は(西は)糸魚川ー静岡構造線(=著明な断層)ではっきりしてるが,右側はどうもはっきりしない.FMでは古い地層が深さ6千メートルに存在し,そこに北部では土砂が堆積した.FMは南北に分けられ,北部FMはもともとその場所にあって,その上に上記の通り岩土砂が堆積した.南部FMは,伊豆半島andアルファが太平洋プレート(?)の上を動いてきて列島にぶつかった
0投稿日: 2019.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログhttp://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000313392
0投稿日: 2019.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ地質学における比較的新しいパラダイムである「ホットリージョンマイグレーション説」や「オラコージン説」を用いて、唯一無比の構造であるフォッサマグナの成立過程を安楽椅子探偵さながらに洞察して行く。新書らしい手軽さがありがたい。ジオパークのガイドもついており有用。
0投稿日: 2019.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ地球科学は、まだまだ発展途上の分野らしくプレートテクトニクスも戦後に初めて唱えられた学説で今も新しい学説がどんどん出ている状況らしい。著者も「定説ではないですよ」という前提のもとに彼なりのフォッサマグナ形成に関する説を説明しています。地球科学関連の書籍としては昨年(2017年)9月に出版された本なので、過去の研究成果も踏まえながらの説だと思います。その点では従来よりもより説得力のある内容になっているのではないかと思います。
0投稿日: 2019.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりにネットではなく,本屋さんで出会った本。そして久しぶりに手に取ったBLUE BACKSです。 「そういえば,フォッサマグナについてはしっかり調べたことがなかったなあ」「この本は読みやすそうだな」と思い購入。予想どおり,とても興味深く,ミステリアスで,謎解きのような本でした。 フォッサマグナがどのように出来たのかについて,まだ定説がないことにビックリ。それでも,藤岡さんは,他のさまざまな事実を総合しながら,自分の仮説を提出してくれています。 糸魚川静岡構造線の境目には私も行ったことがあります。地層の様子が明らかに違っていてなかなか興奮する場所でした。近くの駐車場には枕状溶岩の露頭も見れます。もう一度,行ってみたくなったな。 本書は,フォッサマグナといいながらも,結局は,日本列島はどのようにして出来たのかがちゃんと書かれていて,そういう意味でも,日本列島の誕生を知る入門書となっています。 いやー,地学っておもしろいわ。
3投稿日: 2019.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ小さい頃から耳にしているフォッサマグナだが、なんだか巨大な断層くらいにしか理解していなかった。 本書は、フォッサマグナの特殊性、日本の成り立ちの足跡としての意味、未だに解明されていないその成立の謎について、専門的知識のない読者にも分かるように説明されている。 日本の一地域の特殊な地質的特徴が、全地球的なメカニズムの発露につながるのかと思うと、非常にスケールが大きく、知的好奇心をかき立てる内容である。 本書を読んで、興味を持つ読者が多く現れるといいなと思う。 学問の地域性というか、その場所に特殊な事象があることで、該当領域の学問が促進される側面があるかと思うが、そういう意味では日本は地球物理学のフロンティアになる可能性があるのだということを改めて感じた。
0投稿日: 2019.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログフォッサマグナ。名前の語感の良さで小学生の理科の授業で初めて聞いてから忘れたことのない単語。 当時は、一本の線のような、断層や中央構造体のようなものだと思っていたが全然違っていて、もっと面白くて、もっと謎で得体の知れないものだったんだなと。 内容としては、著者によって、今ある仮説に次ぐ仮説をうまく組み合わせ、フォッサマグナの謎に迫ろうとする一冊。素人にもわかりやすい文章と内容で、専門外だけど少し興味ある人はわりとすんなり理解できると思う。
0投稿日: 2019.02.16日本海は拡がり、千葉沖は沈み込む、そして
世界に唯一の地形フォッサマグナ、そしてこれまた世界にひとつしかない海溝三重点。日本海の生成からフォッサマグナが生まれるまで何があったのか、謎は全ては解けてはいない。 フォッサマグナといえば日本海から太平洋にかけて本州を横断する大地溝帯のことだが有名なのは糸魚川ー静岡構造線だろう。長野の大町から諏訪を経て甲府まで左に日本アルプス、右には八ヶ岳などの山塊に挟まれた地形は確かに地溝としてはわかりやすい。実際に糸魚川ジオパークでは糸静線が目に見える。しかし糸静線はあくまでフォッサマグナの西端であり東端は明確にはなっていない。秩父などを含む関東山地は日本アルプスや東北地方と同じ古い地層だが関東平野がフォッサマグナに含まれるかどうかがはっきりしない。フォッサマグナの底は少なくとも地下6000mで日本アルプスとの落差は1万mほどになる。大昔は日本海と太平洋は繋がっていたかもしれないというまさに大地溝帯なのだ。 1900万年前日本は大陸にへばりついていた。その後日本海が拡大し1500万年前には日本列島は今の位置に落ち着いたと考えられている。ここからは仮設だ。プレートが沈み込むと冷えて重くなりマントルの底に沈み込む。一方高温のマントルからは地殻破って上昇するスーパーホットプルームが生まれマグマの供給源となる。このスーパーホットプルームが到達したことにより地殻は押し出されるように引き裂かれ拡大する。オラーコジンという説ではこの中心点から三方に裂け目が広がりTの字の上部は直線上に伸びる広い裂け目となり日本海を作った。下の細い裂け目がフォッサマグナとなったのだ。拡大する日本海に対しフィリピン海プレートが北上し、太平洋プレートが西進する。西日本は時計回りに、東日本は反時計回りに回転し今の日本列島の原型ができた。 同時期、フィリピン海プレート北端の伊豆半島が本州にぶつかり一体化した。沈みきれず剥離した地殻は乗り上げ丹沢山地となる。フォッサマグナの南側の堆積は海からもたらされたわけだ。中央構造線は九州から豊橋までほぼ一直線に伸びその後諏訪に向けて北上する。そしてフォッサマグナでは一旦姿を消すが関東山地の北側から霞ヶ浦に向かってまた現れる。伊豆半島に押し上げられた形だ。 北海道からフォッサマグナまでがのる北米プレートは東から太平洋プレートに南からはフィリピン海プレートに押され、西では西日本がのるユーラシアプレートで日本海が拡大した。房総沖海溝三重点から相模トラフ、糸静線からスーパーホットプルームの上昇点あたりまでが北米プレートの南端となる。プレートの境界に裂け目が広がり三重点を軸に北日本がねじれ、フォッサマグナが拡がったというのが本書から得たイメージだ。 プルームから生み出された三方の亀裂と海溝三重点の対比で締めくくられるのだがひとつ疑問が残った。3つのプレートのもうひとつの三重点は本書ではあまり触れられていない。甲府盆地辺りでユーラシアプレートと北米プレートとの境界線(糸静線)とフィリピン海プレートの北端が1点で交わる。つまりフィリピン海プレートの北端にあるのが富士山だ。これは偶々なのか?地下では何が起きて起きているのだろう。
0投稿日: 2019.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログフォッサマグナを発見したのは、ナウマン象で有名な、あのナウマンさん。明治初期に政府がドイツから東京帝国大学に招いた地質学者で、現在の産総研地質調査総合センターを設立した人。まだ若くて気質が激しく難しい人だったらしい。この人がいなければ、日本の地質学はもっとずっと遅れていたのだろう。まだちょんまげ結ってる人もいた異文化の日本に、よくぞ来てくれたもんだ。フォッサマグナとはラテン語で、大きな地溝、の意味。フォッサマグナの西縁は糸魚川から静岡にかけてのラインだが、東縁は諸説あり、まだはっきりしていない。 地球はマントルの深い部分にある熱くて溶ける寸前のプルームがゆっくりと移動し、地表にマグマとなって噴き出したり、冷えて沈み込んだりしながらプレートを動かす。それにより大陸同士がぶつかって超大陸をつくり、また分裂することを繰り返しながら、1億年くらい前に現在の五大陸が形成された。そのころ日本列島はユーラシア大陸の一部だったが、さらなる地殻の変動によって切り離され、千五百万年くらい前に、今の日本列島の原型ができたらしい。その過程で、東北日本とと西南日本を分けていた海が埋まり、フォッサマグナとなった。だから、フォッサマグナはその両サイドとは地質が違い、海底の形跡が見られる。 日本列島は、形は安定はしているものの、今なお少しずつ動いている。ユーラシア、北米、太平洋、フィリピン海という四つのプレートがせめぎ合っているのが、Google earthで見てもよくわかる。私たちはひょっこりひょうたん島の住民みたいなもんだな。思いは千々に飛んでいく。 著者は「しんかい」に51回乗船し、太平洋、大西洋、インド洋の三大洋人類初潜航調査を達成。難しいことを易しく説明した本で、地球科学の面白さ、奥深さを知らしめてくれる本だ。
1投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログフォッサマグナの何たるかは何となく分かったが、図表と地質学的な説明が専門分野外の人間には分かりづらかった。専門書としては簡易すぎるし、一般書としては専門的すぎる。
0投稿日: 2019.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ15 Ma (Mega annum = 100万年前 :地質年代の表記法)に生まれた深さ6000m以上の世界唯一の地形 巨大地溝『フォッサマグナ』 フォッサマグナとは何なのか?どのようにできたのか?いまできる精一杯の考察、答えを記した一冊 私は全くのど素人ですが、そんな私にも読み易く、とても面白かったです^^* すごくわくわく浪漫を感じた(笑) 地球のほとんどの大陸が合体してできた「超大陸パンゲア」 とてつもなく巨大なスーパープルームによって引き裂かれ プレートテクトニクスによって動き回る大陸 次に超大陸になるのは2億年後だそうです(笑) o(^-^)o ワクワクッする ←行ってみたいっ!!← 糸魚川ジオパーク 男鹿半島・大潟ジオパーク
0投稿日: 2018.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
フォッサマグナという言葉は有名だけれども、実際にその範囲、定義、成り立ちを理解している人はすくないんじゃないかしら。 実は、フォッサマグナの西側は糸魚川静岡構造線だけれども、東側についてはまだ論争中らしい。 じゃあ、なんで論争かというと、「出来方」について定説が固まってないらしい。 では、どんな出来方説があるのか、ということで、 地球内部構造、プレートの動きから、日本海とフォッサマグナの成り立ちの各学説を、きちんと解説した一冊。
0投稿日: 2018.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ明治初期にナウマンが発見した、日本列島を真っ二つに分断する「巨大な割れ目」フォッサマグナ。その成因、構造などはいまだに謎に包まれていて、一般向けに書かれた解説書はなかなかつくられない。しかし、フォッサマグナを抜きにして、日本列島の地形は語れないのだ! ブルーバックスで人気を集める地学のエキスパートが挑む!
1投稿日: 2018.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ秀作。 フォッサマグナ、謎に包まれている。 日本列島は、不安定な場所だということがわかった。災害が多いわけだ。 地質学面白い。
0投稿日: 2018.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログフォッサマグナとは、日本列島の真ん中にある構造のこと。6000m以上の深さの地溝がありその上は堆積物が積み重なっている。世界でも珍しい構造で、それがなぜできたかを、前提から少しずつ説明して、最後に持論を展開する。 内容は非常に興味深くおもしろいが、肝のところはかなり難しい。 この本で示された試論は、北でオラーコジンができて日本海が拡大、南でフィリピン海プレートができて伊豆小笠原弧が衝突、それが同時期におきたから。 両者が同時期におきたのはスーパープルームによる。 オラーコジンは、餅を焼いてふくらませたときに3つに裂けるようなこと。そのうち2つは発達する。
0投稿日: 2018.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ2018/11/27:読了 フォッサマグナの定義とか、成り立ちとか、こんな複雑だとは思わなかった。 日本海の広がりによって、日本の東と西が、大陸からそれぞれ逆回りしながら移動してきたものが出会ったところに、伊豆-小笠原弧が本州にぶつかったと、かなり壮大な話だった。
0投稿日: 2018.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ナウマンはフォッサマグナを発見した当時、この地形は世界でここにしかない稀有な構造と言っています。私の知るかぎりでも、このような名前(「大きな溝」の意)を冠した地質構造はほかにありません。フォッサマグナは世界でも特異な地形なのです。 フォッサマグナがなぜ特異な地形なのか、もう少し考えてみると、ナウマンが最初に感じたんはもちろんフォッサマグナの「深さ」ではなかったはずです。地下6000m以上もの地溝が埋まっているとは、いかなる天才地質学者でも気づきようがありません。では、ナウマンは何をもって世界に稀有な構造と直観したのかといえば、それは序章でも述べたように、平坦な大地の向こうに、いきなり2000m以上の山々が壁のように屹立しているその「落差」の大きさだったのでしょう。落差こそがフォッサマグナを世界に無二の地形にしているのです。 では、そのような落差はなぜもたらされたのでしょうか。それは、北部フォッサマグナに当たる場所が日本海の拡大によって深海に陥没したとき、地質学的な時間でいえばほぼ同時に、伊豆・小笠原弧がたまたまそこに衝突し、陥没を埋めたばかりか、さらに激しく大地を隆起させて南部フォッサマグナをつくったからではないかと思われるのです。つまり、陥没と隆起が絶妙なタイミングで起こることが、フォッサマグナ形成の必要条件だったのではないかと。もしそうだとすれば、そのような巡りあわせを生んだものはいったい何だったのでしょうか。(pp.140-141) 日本海の拡大は200万年ほどでマグマがなくなって終わりましたが、今度は日本海そのものが太平洋プレートとともに日本列島の下へと沈み込みを開始しました。しかし、日本列島の反対側には海溝三重点という強大なアンカー(錨)が存在しているため、日本列島そのものが形を変えていくようなことはありませんでした。そのかわり、とくに東北日本には強い東西方向の圧縮が起こり、その結果、フォッサマグナでは赤石山脈が隆起し、さらに北アルプスや中央アルプスのような高い山脈ができていったのです。海溝三重点の一が変わらないかぎり、こうした東西圧縮はこれからも続くでしょう。(p.195)
0投稿日: 2018.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ糸魚川の「フォッサマグナミュージアム」に行ったので読みました。 日本列島の背骨をまっぷたつのフォッサマグナ。 地質学的にもすごいけど、言葉や味付けの境目になってるのも面白い。
0投稿日: 2018.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ北部フォッサマグナ:新第三紀、南部フォッサマグナ:丹沢地塊(伊豆・小笠原弧の衝突で形成)多摩川、相模川は昔のプレート境界で八の字。伊豆半島・富士山:駿河トラフと相模トラフ境界が通る。スーパープルームでオラーコジン形成(3つにひび割れ):フォッサマグナ形成
0投稿日: 2018.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログフォッサマグナというと糸魚川静岡構造線のことというイメージでしたが、面的な広がりがあって、しかも出来上がるまでの経緯が複雑怪奇。1500万年の歳月がもたらした大きな動きに圧倒されました。
0投稿日: 2018.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本とは、地球上相当特異な地点にあるのだ。ということがはっきりした。いつものことながら、電車の中で半分居眠りしながら読んでいるので、頭に残っていないことが多い。けれど、映像としてなんとなくイメージできる。日本列島ができあがっていく様子が。観音開き。フォッサマグナを境に、西日本と東日本が反対まわりで開いていく。そして日本海が広がっていく。おもしろいなあ。地球の歴史というのは本当におもしろい。興味が尽きない。同時に「文化地質学」というのも、またおもしろそうだ。並行して「マン・チン分布考」も読んでいるが、地質と方言とか食べ物とかいろいろな文化との関係が見えてくると、またそれもおもしろそうだ。ちょっと注目しておこう。城崎近くの玄武洞は、はじめてパートナーと旅行したときに立ち寄った思い出の場所だ。何とも思わずに見学したけれど、興味を持って眺めれば、違うものが見えたことだろう。また行ってみたい。フォッサマグナが鵺かどうかはわからないし、退治ができたかというとそうでもなさそうだけれど、もし退治していたら、今度はタタリがこわそう。
0投稿日: 2018.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本人として普通に地理で習った「フォッサマグナ」。それがこれほど珍しい地形だとは。 日本列島は二つに分断していたものが観音開きの戸が閉まるように合わさるようにできたのではないか、背後に日本海ができたのもその余波、と。 「日本海その深層で起きていること」を読んで日本海に興味を持っていたがここでつながるとは。
0投稿日: 2018.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログフォッサマグナとか、ブラキストン線とか、興味あるんです。日本列島の成り立ちからフォッサマグナ生成過程の推理まで、楽しく読める一冊でした。
0投稿日: 2018.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
子どもの頃から知ってるつもりのフォッサマグナだが、意外にも、これまで学問的にはあまり研究されてこなかったとか。それが、近年になって、学会でも注目が高まっていて、本書も、最近の研究成果も踏まえつつ、著者の大胆な予想を織り込みながら書かれている。 プレートテクトニクスのイロハを知らずに読むと、やや難しいかもしれないが、フォッサマグナだけでなく、日本列島の成り立ちやフィリピン海の構造まで解説されていて面白い。できれば、トランスフォーム断層の成り立ちや構造といったものをもう少し詳しく解説してほしかったが。
0投稿日: 2018.08.30
