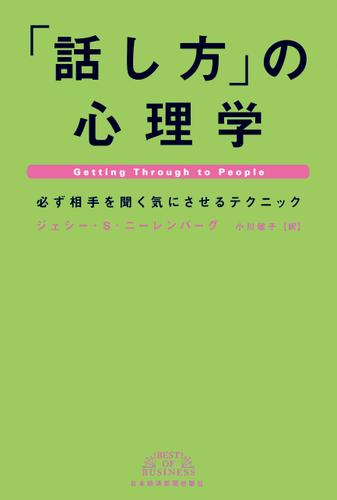
総合評価
(28件)| 7 | ||
| 12 | ||
| 8 | ||
| 0 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ人は自分でもわかっていない理由で物事をしりぞけることがある。そこで適切な質問が最も重要となってくる。
0投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔からサザエさんの状況を他人と共有できる回想シーンに、あれが使えればなぁと思っていた。 いくら筋道を立てて論理的に話しても、聞き手と同じレベルの情報を共有することはほぼ無理。なぜなら価値観、経験、状況が異なるから。という身も蓋もない前提から始まる。たしかに同じ本を読んだって(読書なのだから自発的に)、読後の感想は180度違うこともある、全く同じなんてことはない。 そこを出発点として、どうしたら能動的に聞いてもらえるか?心を開いて話してもらえるか?会話できるか?を説いていく。題名は「話し方」だしテクニックという言葉もでてくるが、人間は機械ではないのでマニュアルはないと認識しているように、ハウツー本感は少なく、「心理学」を軸に人間の普遍的な心理にアプローチしているためか、50年前の本でも、文化の異なるアメリカ人著者の本でも違和感はない。 目から鱗の記述があるわけじゃない、ただ実践できているかどうかは別。 こういう本は本当に悩んでいる時に読む方が効果が数倍あると思う。 結局、会話の上達に近道はなく、日々の訓練とこちらの誠意+「ちょっとしたコツ」なんだと思う。 2020.7.15
3投稿日: 2020.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ答えを急がないこと。相手の話を最後まで聞くこと。感情は吐き出させること。訓練しないと難しい。しかし全てがインスタントで済ませられるからこそ、忍耐強く話を聞いてくれる人が求められているのかなとも思う。
0投稿日: 2019.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ和訳している本はちょっと理解が難しい。 当たり前のようなことだけど、実際習得するまでは難しいかも。 わかっているつもり。 具体例が多くてわかりやすいけど、内容がてんこ盛りでどう手をつけていいのかわからない。 この本に書いてあることを実践で活かすためにはかなり読み込まなきゃダメだな
2投稿日: 2019.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログはなしかたについての本 結論としては深く相手の話を聞くことによって相手の懐に入り、自分の考え意見を伝えやすくするというもの
0投稿日: 2018.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこれ、アメリカのビジネスマンに向けた心理学。 たとえ話が、日本的でないところが多々ありすぎて...失笑。日本なら中高生向け。
0投稿日: 2016.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
第1章 人と分かり合うことの難しさ 意思疎通を妨げる5つの性質 ①変わることへの抵抗…人は自身にとって見返りがあることにしか習慣が定着しない。考え方等もそうだ。 ②相手の話に耳を傾けない。聴講としては、見当違いの発言をする、不必要な質問をする、解決済みのことを蒸し返す ③先入観を持った聞き手…聞き手が持つ願望がものごとを歪んだ目で解釈するようにしてしまう。聞き手は勝手に言葉を捕捉し、派内を自分い都合よく解釈してしまう。 ④根拠のない推測…相手が話を聞いていることを家庭に話すのはいけない。 ⑤根強い秘密主義…自分のことを話したがらない。聞かれたことだけを答えた人がいる。 第2章 会話に乗ってもらうために 会話に乗ってもらうための3つの方法 ①会話の目的を告げてから会話に入る ②相手の気持ちを尊重する ③的外れの質問を受け止め、なぜそのような質問が出るのかを考える 相手が的外れなことを言ううときは相手の中では必死に考えて居たことだと受け取る。なざなら、相手は話しながらももう一つの施行で別のことをずっと考えて居たりするからだ。 第3章 人の考えを引き出す ①簡単に答えられる質問…YESNOで答えられるような質問、簡単に答えられるものは相手にとっても気持ちがいい。はじめはこういった質問から。 ②抽象的な質問…相手をもと会話に参加さることができる。 第4章 人の感情にどう向き合うのか 第5章 言葉に託されたメッセージを読む 第6章 思考を伝え、相手からフィードバックをもらう 第7章 話を聞いてもらうために 第8章 頭をはたらかせる 第9章 相手の抵抗にどう対処するか 第10章 発言の意図をつかむ 第11章 会話におけるギブ・アンド・テイク 第12章 複数の聞き手に意思を伝える 第13章 説得の手法 まとめるのがめんどくさくなりました。笑 もくじを見て内容を思い出せるのでこれでよし!笑
0投稿日: 2014.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ必ず相手を聞く気にさせるテクニック/Getting Through to People ― http://www.nikkeibook.com/book_detail/31244/
0投稿日: 2013.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分がどんな感情の中で会話をしているのか、同じく相手がどのような感情で会話しているのかの心理がよくわかった。 日常の具体的な会話と照らし合わせて納得できることが多く、今後の多様な会話の場面で実践できる、会話の基本や説得の方法を知ることができた。
0投稿日: 2012.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ人と接する機会が多い今の仕事。 話し方で相手の印象が変わることは同じスタッフをみていてもすごく感じる。私は人に好かれたいし、認められたいと思っているので、相手に対して失礼でやる気を起こす話し方ができればと思って購入しました。 内容は想像していたものとちょっと違いましたが、どの本でも書いてあることは相手の話をしっかりと聞くこと。すぐに反論してしまうのは、よくないですね。
0投稿日: 2012.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
どうやって話せば、相手はしっかり聞いてくれるか を説いたハウツー本。 この本自体の元の本が、アメリカで1963年に書かれていることに驚きました。1963年に書かれたものなのに、現代でも通じる内容です。 随所に会話例もあり、終始説明となっておらず良いと感じたが その例が、いかにもアメリカっぽいものもあり面白かった。
0投稿日: 2012.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「心理学」に関するものではなく、会話テクニックを心理学的に解釈した本。学術的な論理の展開は少なく、あくまでハウツーと捉えたほうがよさそうです。会話の例が多数掲載されていてわかりやすい。上司と部下、親子、夫婦、医者と患者などの会話例があり、すべてではないものの、どれか参考になるものがあると思います。私の場合は、第12章「複数の聞き手に意思を伝える」がたいへん参考になりました。
0投稿日: 2011.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログページ数は約300ページと多いけど、スッと頭に入り、読みやすい一冊。 内容は、「話し方」を心理学面で語り、論理的に説明している。 相手の「話し方」から、考えていることを読み解く方法も記載。 また、話し方に加えて聞き方も記載しており、「聞き上手は話上手」という理由が分かる一冊。 実際に使えることばかりで、非常に読み応えのある内容でした! また一度読み直してみたい!!
0投稿日: 2011.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ上手くMeetingをファシリテートできていないと感じて手を伸ばした本ではあるが、すぐにでも活用できそうなこと数多く書かれており、この先も手の届く場所に置いておきたい本。 ここにも書いてあるのですが、聞き手は聞いているようで、違うことを考えていたりするんですよね。そんな時に、聞き手に考えさせる会話をするという部分は非常に参考になります。
0投稿日: 2011.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログテクニカルというよりは、人と話す上でのマインドセットを促してくれる良書。ハウツー本チックではなく、タイトルの通り本当に話し方について学術的に考察した感じ。コミュニケーションを行う上での、人間の感情により引き起こされる「障壁」がことこまかに記されている。 テクニカル寄りの本と合わせて読めばシナジーが出せそうな気がする。
0投稿日: 2011.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ原著が1963年と、50年近くも前の本でありながら 自分にとって目からウロコの内容が盛りだくさんだった。 と同時に、いかに自分が独りよがりな話し方を行っていたのかを 思い知らされる結果にもなった。 この本を読んで改善すべき点はたくさんあるけれども、 まずは ・会話の相手の反応を意識する(相手をよく観察する) ・質問をうまく利用してコミュニケーションロスを埋める ・相手の話を遮らずに最後まで聞く この、ごくごく基本的な3点を意識して改善してから再度 読み直したいと思う。
1投稿日: 2010.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ会話を始めるにあたってのコミュニケーションの難しさをはじめに書いたうえで、 ◆聞き方 相手の情報を引き出すためには 感情との向き合いかた 潜在的なメッセージの読み方 ◆話し方 話しにひきつけるための方法 相手の抵抗への対応 といった内容が書かれています。 コンサルタントとしてクライアントと話しているときに、必要以上に反発してくる方もいらっしゃいます。 そんなときには相手の抵抗への対応という部分に書かれていた内容が参考になるなと思いました。 人が本音を悟られまいとして全然関係ないところで反発しているのを、突然ロジックで隠れた衝動をむき出しにしてしまうというのは危険なので、 ・まず相手に理解を示す ・反発していることを自覚してもらう ・反論を相手とともに検証する といったステップをちゃんとふもうとするのは大事ですね。 ロジックと感情両方の観点から話さないといけないなと再認識する本です。 あとは、これもまた仕事をしているうえで気にしていることとして 誰かが発言したときの潜在的なメッセージを読むというのがあります。 【引用】 ・なにかを質問するときに、なぜその情報が必要なのかという理由を省くと、相手に不信感をもたれやすい ・じっさいの会話では、本題とは無関係のコメント、つじつまの合わない意見に耳をかたむけ、流れをきるような唐突な話題転換にもついていくことをすすめたい。きっと理由があるはずだ。 ・自分の鼻や髪に善悪の判断を下さないのと同様に、感情もまるごと受け入れる。 ・(潜在的なメッセージを人がつかう理由としては何か怒りや恐怖をかんじたときに社会的なルールからそれを押し込めてしまう。ただし)押さえ込まれたエネルギーは消えるわけではない。 どこから外に出ようとする。がすっかりルールに飼いならされた身には、こうしたむき出しの衝動は攻撃的で威圧的なものに感じられる。そこでやむなく潜在的なメッセージを送るという形をとるようになった。 ・こうした自画自賛(潜在的なメッセージ)は認められたいという思いの裏返しである。 自分は特別な素質を授かっている存在であると思いたい、人から認められたい、そう思っているのだ。 相手からそういう潜在的なメッセージを受け取ったたら、言葉でしっかり肯定してやればよい。 ・なぜ本題とは無関係の話題が出てくるのか。それは自分の感情を表現したい、単なる情報交換ではなく相手と人間関係を築きたいという願望があるからだ。 ・相手がすでに知っていることを念押しすると、会話の勢いがそがれてしまう ・相手の注意力をひきつけておくには、繰り返しのたびになにかを加えてゆく。 ・意見が違うから反発するとは限らないのである。 たまたまそのときに、抵抗したい、反発したいという願望を抑えきれなくなっただけなのかもしれない。 それが一見、会話の相手への反発に見えるだけなのだ。 ・なぜ反発するのかを深く話し合ううちに、理屈に合わない動機、つまり本題とは無関係の動機はしだいに弱まっていく。 ・自分の考えを誰かに採用してもらおうとするときには、自分は相手にどんな反応を期待しているのか、それはなぜかと自問自答してみる。 ・話したいという欲求があると、聞く力はがくんと落ちる。このような事態を避けるには、話したいという欲求を発散させる方向にもってゆくことだ。 自分から話そうとしないなら、合い間合い間でうまく誘導して言いたいことを引き出す。出口を封じられた欲求は会話を妨害する。たとえ本題に関係のないことでも、話してもらう方がよい。
0投稿日: 2010.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ話すとうことは、感情を抜きには捉えられないということがよくわかった。例えが多かったり、周りくどい文体がいまいちで星-1。
0投稿日: 2010.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「話し手」が優位に話をするための単純な技術解説ではなく、 「聞き手」が何を考えているかという部分を心理学的な視点から丁寧に解説。 人と話が擦れ違うことや噛みあわないことは寧ろ自然なことであり、 基本的に人は分かり合えるものではない、という出発点が、 読み終える頃には相手への肯定感として抱けるようになるのだから不思議なもの。 何より腑に落ちたのは、話術のテクニック本でたまに見かけるような、 ただ人の気持ちを操作するための内容とはまるで異なっていること。 まずは自分側の思い込みや心構えを解きほぐすための構成になっている。 読んでいて納得する話も多く、目から落ちた鱗が二枚や三枚ではすまなかった。
1投稿日: 2010.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ■話し方 ①聞き手は勝手に言葉を補足し、話を自分に都合よく解釈する。 ②何かを質問するときに、なぜその情報が必要なのかという理由を省くと、相手に不信感を持たれやすい。 ③会話をするとき、頭の中で相手と入れ替わって自分の言葉を聞く立場に立ってみよう。 ④こたえやすい質問からはじめる。迷わずに答えられるというのは、誰にとっても快適なことである。 ⑤感情を表現させる。感情は緊張を呼ぶ。緊張が高まった状態では人の言葉を受けとめてじっくり考えることはできない。だいいち、耳に入らない。だからここはぐっと言葉を飲み込んで、相手に話をさせる。 ⑥言葉がつたえるのはものごとの一断面にすぎないのに、それで全体像を伝えた気になる。 ⑧会話で質問する習慣をつけよう。
0投稿日: 2010.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ会話をしている時のお互いの心理が上司と部下の場合、夫と妻の場合などシチュエーションを含めて説明されているので非常にわかりやすい。古典的ということでいつの時代、どの世代の人にもあてはまる内容なのでこれを頭の片隅においているだけで次第にコミュニケーションが上手にとれるようになっていくかもしれない。
1投稿日: 2010.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ他のこの手の日本のビジネス書と比較すると、この本の方が納得できる。 そもそも人は他人の話など聞こうとしないものだ、というのが前提として書かれている。
1投稿日: 2009.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ相手からうまく話しを引き出すための質問の仕方がわかりやすい。 聞く時には最後までコメントを排除せず、その後、YesやNoでは答えられない具体的な質問をする。 特に、感情が高ぶっている時に論理は無力でしかないので、高ぶりを受容し、欲求を吐き出させる。 受け入れの下地ができたサインが出るまで待つ。 興味深かったのが、人は相手の話を聞きながら思考することは非常に難しいということである。 自分が話してになっている場合、相手に的確な返事を期待しがちだが、それはやめた方がいいということだろう。 自分に置き換えてみても人の話しを聞いている最中はうまい考えは浮かばないものである。
0投稿日: 2009.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ章ごとに明確なテーマがあり、それのための方法論が具体例と共に分かりやすく書かれている。 重要な部分は太字になっているため、「章題(または節題)=問い、太字=解」をサクサク目で追える。 時間がない場合は具体例を読み飛ばすこともできるので、読者のニーズに応じて読むことが可能である。 タイトルに心理学という単語が入っているが、専門用語は皆無である。 記述が詳しく説得力があり、しかもこの原著が日本人以外である点が大きい。 日本人であろうがそうでなかろうが、コミュニケーションの基本は変わらないのだろう。 決して話をする側だけの目線ではなく、コミュニケーションをトータルでとらえている。 その理由としては、逆説的だが、相手の話をよく聞くことがこちらの話をよく聞いてもらえるというスタンスをとっているからだ。 コミュニケーションでの心がけとその方法論を知りたい人にはお勧めである。
0投稿日: 2009.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ超おススメ。 人と話すことどうなっているのか。 人とすれ違うのはなぜか。 ちょっとショッキングだけど、 とても参考になる本。
1投稿日: 2009.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書はアメリカで長年売れ続けて、やっと日本に翻訳されて発売された らしい。著者は、心理学博士であり、それなりのキャリアを持っている。 本書の内容は、まず相手はこちらの話しなど聞く気もないし、聞いてない という大前提を理解する事から始まる。そして、会話を進めていくに場合に そって、助言を述べている感じか。内容は、結構ボリュームがありそうで 少ないので、以下に重要だと思われる点だけ述べる。 会話にのってもらうには、 1.会話の目的を告げてから会話に入る 2.相手の気持ちを尊重する 3.質問の内容を考える まぁ、至極当たり前な内容になっていると思う。 しかし、当たり前な事が出来ていない事が多いのだろう。ここで、言わなければ ならない事は、本書の内容はビジネスシーンに限定される話であるという事である。 例えば、普通の会話で目的を話してから、会話を始める人はいないが、 会話の目的を確認する事は大切だ。愚痴りたいだけなのか、笑いたいのか、 悩み事を聞いて欲しいだけなのか、自分を責めたいのか等である。 愚痴りたいだけなのに、その愚痴に対して文句を言ってしまってはなかなか コミュニケーションが上手くいかない。又は、ブラッシュアップさせたいのに それを悪意と見なしては、磨きがかかるものもかからない。 会話とは難しものである。
0投稿日: 2009.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の目的 人に話を聞いてもらうには? ----------------------------------------------------------------------------- ●人は会話で感情を表現し、潜在的メッセージがこめている。 ●コミュニケーションが難しいのは人と人だから。人の内面なんて「何でもあり」 ●説得するには、まず下地づくりから。 ----------------------------------------------------------------------------- 3年くらい前に読んで、すごく影響を受けた本でした。 再読すると、意外とサラっとした感じでした。(日常で実践してある程度身になってることが多かったのかも) 「話し方の心理学」というタイトルですが、中身は、相手に話を聞く土台をいかにつくらせるかという内容。 説得やアドバイス、力づけてやることでさえも、相手が求めていないものはおせっかい。 すべてに共通するのは、「話す前に聞く」、「相手の感情を発散させる」。 「話す」と「聞く」は切っても切れない両輪。
1投稿日: 2008.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ【目的】:話をきちんと伝えるコツが知りたい。 ・話の目的、方向性を最初に知らせる。 ・無言でうなづいていても、理解しているとは限らない。 ・相手の気持ち・感情を尊重する。受け入れる。 ・自分の感情も言葉で語り、相手の感情も引き出す。 ・言葉はイメージの断片。主観的な言葉から受け取るイメージは人によって異なるので、具体的数値や例を説明したり、相手の理解を質問してみる。 ・話を聞いてもらうためには、本題からそれないこと、一度の発言で伝えたいことは一つにすること、分かりきっていることは話さず、繰り返しに同じ表現は使わないこと、具体的な言葉を使うこと。 ・質問により相手に考えさせる。 ・確認、繰り返し、要約で理解を深めさせる。 #相手と意見が違うと、つい論理的に議論したくなるが、相手の状況により、特に感情的な不満・怒りの表現などには、論理的な展開は望めないこと、まず相手とその感情を否定せず、受け入れることが大切だと理解できた。 #言葉のあいまいさと確認、質問の大切さを感じた。
1投稿日: 2007.09.15
