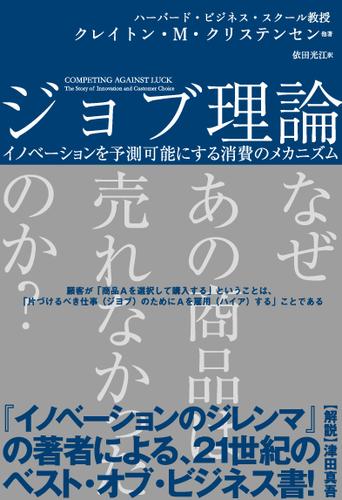
総合評価
(135件)| 55 | ||
| 48 | ||
| 22 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
作者曰く、「顧客が進歩を求めて苦労している点を理解し、顧客の抱えるジョブ(求める進歩)を片付ける解決策とそれに付随する体験を構築する」ための本とのこと。 個人的には「"ユーザーに対する深い洞察をどこから学ぶべきか"をエピソードベースで伝えてくれる」本だと感じている。 本書の中で語られている「ミルクシェイクの逸話」がこれを最も表現していると思う。 ----- とあるファーストフードチェーンでは、ミルクシェイクを売るためにユーザーのデモグラフィック情報や意見を徹底的に収集し、改善を図っていた。 しかし売上は一向に変わらず。 「どんな状況で、何のためにその商品が雇われているのか」というジョブ理論の視点に切り替えて観察した結果、「平日の朝には"退屈な通勤時間をやり過ごす"というジョブを片付ける存在」としてミルクシェイクが選ばれていたことが見えてくる。 ----- ビジネス本ではあるものの、上流のデザインにおける考え方に通ずる点が面白い。 「課題を解決するために、どこにフォーカスすべきか」という観点を授けてくれる点では、良書だと思う。 ただあくまで「理論」の本で、ノウハウ本ではない点には注意。
0投稿日: 2026.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログプロダクトアウトからマーケットインの考えにするには、顧客が何に悩んでいて、その悩み=ジョブをどう解決するか考えるべきかを考えるべきであることを学んだ。 平均はニーズではないことは気づきになった。
0投稿日: 2026.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブ理論は相関関係ではなく、因果関係のメカニズムを踏まえてイノベーションを成功させる世界へと案内してくれる。 野心的なものなら、何でも破壊的イノベーションではない 働き方や生産性を上げたいと言うジョブにオフィスを雇わせたい ジョブを明らかにして把握できた後は、そこで得た知見を、優れたプロダクトサービスの開発に落とし込む青写真に翻訳しなければならない。この過程に含まれるのが、ジョブを解決する上での、プロダクトサービスに付随した体験の新しい構築法だ。さらにジョブを一貫して捕捉できるように、最終的には社内の能力とプロセスを統合する必要がある。 何が原因で何が起こるのかと言うこの上なく、実用的な質問に焦点を絞る 顧客は進歩を望んでいる。この進歩のことを顧客が片付けるジョブと言う。 ジョブをある特定の状況で人が溶けようとする。進歩と提示する。重要なのは、顧客がなぜその選択をしたのかを理解することにある。ジョブとは進歩を引き起こすプロセスであり、独立したイベントではない。 ジョブの定期には、状況が含まれる。ジョブはそれが生じた特定のコンテクストに関連してのみ定義することができる。 そのコンテクスト文脈を整理するにあたって、重要な質問はたくさんある。今どこにいるのか、それはいつか、誰と一緒か、何をしている時か、30分前に何をしていたか、次は何をするつもりか、どのような社会的、文化的、政治的プレッシャーが影響及ぼすかなどだ。 感情的なニーズが、機能的な欲求よりも、はるかに大きいことがある ジョブ理論は、消費者がさほど困っていなかったり、存在する解決策で充分間に合ったりするときには役に立たない 無と競争する 当社が届けるのはプロダクトではなく、実際にはプロセスなのだ。しかもそれは投資対効果を測定できるプロセスである。 競争相手のいないジョブの周りに、自分たちを位置づける 重要なのは、顧客が進歩を遂げるのに役立つ体験なのである ジョブ理論が効果的なのは、顧客のジョブの複雑な面をイノベーションの成功にとって欠かせない要素に分解するからだ 何も雇用していない人からも同じ位多くのことを学べる。ジョブを満たす解決策を見つけられず、何も雇用しない道を選ぶことを、ここでは無消費と呼ぶ。 我々がビックハイアと呼ぶ人がプロダクトを初めて買う瞬間のみを追跡する。しかし同じ位重要なもう一つの瞬間は、実際にそのプロダクトを消費する時だ。これをリトルハイアと呼ぶ。 当社の商品が雇用されるために必要なのは、何を解雇させることか 損失回避に働く力は、利得の魅力よりも心理学的に2倍強いとされる 解雇には躊躇するものだ。これはB2Bの領域でも同様である。 十分に良いものかの問いに答えようとすると、意見が出すぎて、議論はいつまでも終わらない。この種の状況でこの種の進歩を遂げようとする。顧客にとって十分に役立つかと言う問いなら、答えは簡単に得られる。 顧客のストーリーボードを作る イノベーターは、ビッグハイアとリトルハイアの両方の緊張苦労。ストレス不安に敏感にならなければならない。 ジョブの特定、求められる体験の構築、ジョブ中心の組織の統合と言う3つの層に分かれる 競争優位を得るのは、ジョブの解決を中心に据えたプロセスを通じてである 片付けるジョブをプロセスの中心に据えることで、組織を何に向けて最適化するかと言う視点がそっくり変わってゆく。 測れる事は実行できる ジョブ理論は、成功の尺度も変える アマゾンは注文品がいつ出荷されたではなく、いつ顧客に届いたかを重視する 顧客を登録まで誘導するのは至難の業だとわかった 調査のための機能を挟み込んでおかなければならない 最終目標は顧客のジョブを片付けることであり、すべてはここから逆算して設計されている 競争相手が模倣できないものは、プロダクトではなく、顧客の片付けるジョブに完璧に成功した経験とプロセスだったのだ 顧客のジョブに沿っていない状態で、プロセスを最適化する事は、間違った方向にどんどん進んでいくことと同じである 社内力学の前では、もろい既存のプロセスを維持しようとする重力は極めて強いのだ 市場のプロダクトとなった途端、受動的データは、既に追いやられ、能動的データが声高に迫ってくる どの組織も、自分の視点にとって支えとなる情報のみを注目する。ある種の確証バイアスのもとで動いている。だから、自分たちが売りたいプロダクトを顧客は買いたがるはずだと言う思い込みにつながってしまうのだ。 データにはさらに根本的な問題がある。数字で表した定量的なデータの方が、定性的なデータより客観的で信頼できると多くの人に思われていることだ。 現象のどの面のデータを収集し、どの面を無視するべきかを決めるのだ 従来のインタビューを最大限に活用するから、インタビューを排除するへの大転換 ビジネスリーダーは、自分が継続的に指示を下さなくても、どのポジションにいる社員でも、日々の選択を正しく行えるようにしなければならない そのジョブがシンプルだからである 決定を下すことと、それを実行することとは話が別である データは諸刃の剣になる。データはジョブとは無関係なモデルも作り出す。大企業の場合は特に会社の内側にいるマネージャーが顧客を直接知る事は滅多になく、彼らはデータを通してのみ顧客を知る。 ジェフベゾスは遅延を事故、あるいはシステムの何らかのパフォーマンスがたまたま劣っていたせいだとはみなさず根絶するべき欠陥とみなす。 PIC Aとは観点、洞察、文脈、分析のことだ。 理論を帰納的に構築する上での鍵は1つかそれ以上の枠組みを作ることだ。相関は事象間の静的な結びつきを明らかにするが、枠組みは因果関係の動的な作用を理解する足がかりとなる。なぜ理論における枠組みの役割について、ここで触れたかと言うと、ジョブが枠組みそのものだからだ。 片付けるジョブは動詞と名詞て表現できる。 このクラスでは、何が原因で、何が起こるのかを説明する理論を学びます。物事の仕組みを知ることには大きな価値がある。
0投稿日: 2025.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客提供価値を高めるために、多くの人が考えるのは機能的な価値をどう付加するか考える、蓄積したデータだけを信じて改善を考えるなど、顧客を分かったつもりになってしまっている。イノベーションを生み出すようなサービスを考えるのは、人がなぜある特定の商品やサービスを購入するのか、という因果関係を明らかにしなければいけない。人はどんなジョブを片付けたくて、そのプロダクトを雇用するのか?私たちが商品を買うということは基本的に何らかのジョブを片付けるために何かを雇用するということである、ということ、この問いを考えることが、考え方のアプローチとして学びとなった。 ジョブを起点に考えられる組織とそうでない組織にどのような違いが出てくるのか、多くの事例からジョブ起点に考えることの重要性、その考え方を学ばせてもらえる本。 データについて、そもそも人の手が介在して出ているもので、必ずしも鵜呑みにしてはいけないということ、データがどういう形で出されたものかを押さえることや、感情や社会的側面など定性による要素も含めてジョブを捉える必要があることが学びとなった。
0投稿日: 2025.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
モノを売る、ということに携わる人には必読いただきたい名書です。 ⚫︎冒頭にある問い とあるアメリカのハンバーガー屋さんでシェイクをもっと売り込みたい。ある方法で成功したのだが、どう成功したのでしょう? ↓ 以下ネタバレ ↓ ⚫︎不正解 ・値段を変える ・味を甘くする ・量を増やす 。。。etc ⚫︎正解 ・シェイクを溶けにくくした ⚫︎正解の背景 シェイクを買う顧客の多くは、アメリカ国内を移動する長距離ドライバーたち。彼らは移動中ヒマになるため、シェイクを飲んで気晴らしをしていた。シェイクが溶けにくくなることで、シェイクが長持ちし、気晴らしに使える時間が長くなった。 このように、顧客というのは『モノを買う』のではなく『困りごと(ジョブ)を解決する』というのがジョブ理論。 たしかに昔、任天堂の山内組長が『みんなゲームをやりたくて、仕方なくゲーム機を買うんだよ。』と言うておられた気がします。 モノを買ってもらうことに携わる人は知っておくべき考え方が満載、ぜひ読んでもらいたい名書籍です!
0投稿日: 2025.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、私のデザイン観、特にUXデザイン領域の考え方に最も強い影響を与えた一冊となりました。 世界的に成功しているプロダクトが、この「ジョブ」というシンプルかつ普遍的なメカニズムに当てはまっている事実に驚いたし、面白かった。 この本を読んでから、「ジョブの眼鏡」をかけて世界を見るようになりました。SNSで人気なコスメとか便利グッズとか、話題の映画とかカフェとか。売れていそうなモノを見た時、「これは何のジョブを片付けているんだろう?」と考えてしまうのですが、それがまた面白いのです。 最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事をきっかけに、興味のきっかけや新しい発見に繋がれば幸いです。
0投稿日: 2025.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
印象に残ったことは「何も雇用していない人からも学ぶことがある」。 「ジョブ」という視点で考えれば、競合する相手は競合他社の製品ではなく、一見全く異なるもの・ことかもしれない。あるいは無消費かもしれない。 これは手段と目的と近い考え方かもしれない。 「子どもが両親を雇用して片づけるジョブは何か?」にハッとした。 子どもが私を雇用して片付けようとしているジョブは、抱っこしてくれる。自分を見てくれる。甘えさせてくれる。であって、スマホでクリスマスプレゼントを探すことではないと気づいた。
0投稿日: 2025.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ解決するジョブは何か。 ここを見ていくと競合は無数にあるし、ここが定まってないと売れる商品にはなりにくい。 とても面白い。
0投稿日: 2025.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ•彼らの生活に発生した具体的なジョブをマックシェイクを雇用して片付けている ◦朝通勤の時に買うマックシェイク ▪時間潰しとして他より優れている ◦夕方息子に買う時のマックシェイク ▪他のおもちゃの代替 ◦一つの意味ではなくいろんな意味があって良い •マーガリンの雇用理由 ◦飲み込みやすいようにパンの耳や皮を湿らせる何かが欲しい •セグウェイ ◦いつ?なぜ?どのような状況で?何が問題?などが解決されないまま発売されたプロダクトアウトな商品だったので誰のジョブも解決しなかった
0投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログイノベーションにおいて「顧客課題から始めるべき」という誤った論説が流布しているせいで、その誤った宗教に染まっている人も多い。そんな人たちにせひ読んでほしいのが「ジョブ理論」だ。 この本の中核をなすのが「人は製品やサービスを“ジョブ(やるべきこと)”のために雇う」という視点だ。「ジョブ」とは願望や欲求そのものではない。それは、“不完全な現実”において、“仕方なく”選んだ手段であり、「本当はこうしたい」が実現できない文脈にこそ宿る。 たとえば、あの有名なミルクシェイクのエピソード――朝の通勤時、子どもを静かにさせたい父親が、粘度の高いミルクシェイクを“雇う”という話。ここには、「子どもがジュースを好きだから」という表層ではなく、「静かにしてほしい」という背景の“仕事”がある。この視点の転換がまさに「顕在化された課題」とその先で行き着く「矮小なアイデア」から脱却する鍵になる。 ジョブ理論を応用した「ジョブ・ストーリー」の構文はぜひ参考にしたいフレームワークだ。 ・When(状況) ・I want to(やりたいこと) ・So I can(目的) ・But(阻害要因) ・Therefore I have to(雇われた手段) これを活用して顧客理解を進めることで、「非言語のインサイト」に光を当ててくれる 。単なる課題解決ではなく、「この人がなぜこの選択肢を選ばざるを得なかったのか」という現実の葛藤に向き合うことで、より強いプロダクトコンセプトを生みだすことができる。 多くのマーケティングやペルソナ分析が見落とすのは、「顧客は論理的に意思決定をしているわけではない」という点だ。ジョブ理論は、合理的なニーズではなく、“文脈における衝動”を扱うフレームである。 「顧客課題から始める」とこうした“無意識の圧力”を見落としたまま、仮説検証を進めてしまうことで、イノベーティブさから程遠い「矮小なアイデア」に行き着いてしまう。 顧客のインサイトとは、とどのつまり「課題は“感じていない”が、困っている」という矛盾だ。そして向き合うべき"Pain"は、「それでも現状維持する理由」である。ジョブ理論は、まさにこの違和感に名前を与え、構造として抽出してくれるツールだ。 ただし、あえて一石を投じるなら、ジョブ理論の危うさは“個別性”への過信にある。最初の一歩としてN=1に向き合うことで、それを浮き彫りにすることは当然すべきである。一方で、「ジョブは状況ごとに異なる」と言い切ると、スケーラビリティの視点が抜けがちになってしまう。 事業において重要なのは、「どこまでが個別性で、どこからが共通性か」を見極める設計力である。N=1のインサイトを、どうN=1000に拡張可能な言語に変換するか。この「編集力」こそ、ジョブ理論の“次の地平”として持つべき観点であり、これを「グランドデザイン思考」と名付けた。 『ジョブ理論』は、マーケティングでも、事業開発でも、「顧客理解とは何か」を再定義する思想書である。単なる手法ではなく、「どの視座で顧客を観察するか」という根底の“問い”に迫る。この本を読んだ後、誰か一人の顧客に深くインタビューしてみてほしい。きっと、あなたの見ていた「顧客像」が、音を立てて崩れていくはずだから。
1投稿日: 2025.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ概要: 「ジョブ理論」(原題:Competing Against Luck)は、クレイトン・クリステンセンが提唱したマーケティング理論。顧客が「商品を購入する理由」を「ジョブ(用事)」という観点から捉えることで、顧客ニーズを深く理解し、イノベーションや新しいビジネスモデルを生み出すアプローチ。 主要なポイント: 1.ジョブとは何か? •顧客が特定の状況で達成したい目的や解決したい問題のこと。 •例:「お腹が空いたからコンビニでおにぎりを買う」 → ジョブは「空腹を満たすこと」。 2.ジョブ理論の4つの構成要素: •状況: 顧客が置かれた具体的なシチュエーション。 •進展: そのシチュエーションで顧客が達成したい進展。 •障害: 進展を妨げる障害や不安。 •代替手段: 現在使っている解決策(競合)。 3.ジョブを見つける手順: •顧客インタビューを行い、「どのような状況で、なぜその商品を選んだのか?」を深掘りする。 •表面的な機能ではなく、「なぜその商品を雇用したのか?」という視点で考える。 4.顧客の進展を助けることが価値創造: •商品の機能だけでなく、「顧客が望む進展」を理解し、それをサポートするサービスや製品を提供することが重要。 5.イノベーションの源泉: •ジョブ理論を活用することで、顧客の隠れたニーズを発見し、既存市場の再定義や新市場の開拓が可能となる。 具体例: •ミルクシェイクの例: •あるファストフード店で、朝の通勤時にミルクシェイクを買う人が多いことが発見された。 •調査の結果、「退屈な通勤時間を楽しく過ごしたい」「空腹を満たしたい」がジョブだった。 •その結果、「持ち運びしやすく、満腹感を与えるミルクシェイク」が最適解として商品改善が行われた。 ビジネスへの応用: •新商品開発: 顧客の「ジョブ」に基づいて商品を設計する。 •マーケティング戦略: 広告メッセージを「ジョブ」に合わせて訴求。 •顧客分析: 購入動機を「ジョブ」として捉え、ターゲティングを再定義する。 ⸻ ジョブ理論の強みは、「顧客の行動の背後にある目的(ジョブ)」を掘り下げることで、新しい価値提供の道筋を発見できる点です。これは従来の属性分析とは異なるアプローチであり、顧客の生活シーンや行動を深掘りすることで、新たな製品・サービスの着想を得る手法です
0投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「顧客はなぜ自社の商品を買うのか」→「顧客はどんなジョブを片付けたくて、自社の商品を雇用するのか」ととらえるジョブ理論。 本書ではデータばかりにとらわれ、相関関係をもとに策を出すのは間違いだと批判している。相関関係は因果関係ではない。顧客がどんな『片付けるべきジョブ』を抱えているのかを知り、向き合って寄り添うことの大切さを説いている。 「顧客がほしいのはドリルではなく穴」の例が本書内でも紹介されているなど、決して目新しかったり難解だったりする理論ではないが、大切なことを述べている。最近のポピュラーなビジネス書ほどの読みやすさはないけれど、事例紹介も多いので経営学の土台がなくても全然読み切れる。一度は触れておいて損はない本。
0投稿日: 2025.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ消費行動の理由がわかり、行動の本質を学べる一冊。 本質を知る上で「なぜ」そのサービスを利用するのかを考え続けることで目的を把握できる。 対企業において、ジョブの本質に応え続けた企業は続いている。その生存理由と背景「ある特定の環境・状況」についても理解しやすい。 「ジョブ」は人がある特定下で成し遂げたい進歩。 【明日からのtodo】 自身の消費行動はジョブ理論の何に該当するのかを言語化する。 【本の難易度】 最初の話で理解できなくても、具体例(企業等)をもとに説明があり、理解しやすい。
0投稿日: 2025.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログクリステンセン教授の著作を読むのは「イノベーションのジレンマ」、「イノベーションの最終解」に続き、十年振り三作目。 もっとも有名な前者が、なぜ優秀な会社が元々低位の破壊的イノベーターに負けてしまうのか、を論理的に実証したのに対して、本作は、どうすれば、イノベーションを起こせるか、を問うた本。 ジョブ=お客様が解決したい用事・やっかいごと=(the job to be done) という設定で議論が進む。最初に登場するミルクシェイクの事例は、読んでて「なるほど」と思うものの、そのあとは、同じような驚きはなく、そりゃそうだ、という感じだ。この本の考え方が既に世の中に浸透して長いからかもしれない。 ドリルの刃を買う人は、ドリルの刃が欲しいわけではなく、穴が欲しいのだ、という有名な訓話に近い話が続く。 いわゆる「ソリューション営業」と「インサイト営業」の中間ないしは融合、のようなものかと思う。
22投稿日: 2025.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ商品を顧客が買う理由、商品そのものではなく商品を使って何を成し遂げたいのか?ジョブ(片付けるべき用事)という視点に着目する点が勉強になった。
0投稿日: 2025.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
前から一度読んでおこうと思いつつ時間が経っていたがようやく読んだ。 すでに他の書籍で読んでいた事例も多数あったが、後半のジョブを中心に据えた組織の構築という部分は特に参考になった。
0投稿日: 2024.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本のここが好き 「画期的なインサイトは、あとから振り返ればあたりまえに見えるかもしれないが、あたりまえであったことはほとんどない。そうしたインサイトはむしろ、逆張り屋のこじつけに見えることすらある。その人に見えることがほかの人には見えないからだ」
0投稿日: 2024.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客ではなく、ジョブにフォーカスすることの重要性が語られている一冊。顧客が成し遂げたい目的(ジョブ)は何か?ジョブを具体化するために必要なのは購買理由を知ること。何を買うか(手段)ではなくなぜ買うか(目的)。事例に基づきジョブを知る必要性が紐解かれていく。
0投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客はプロダクトを買っているのではなくジョブを雇っている(解雇もする) 企業は物を売っていると思っていても実際にはジョブを解決するために雇っていることが多い ミルクシェイクを買う人はミルクシェイクを飲みたいのではなく通勤中の暇な時間の暇を潰すために飲んでいる。 ・ジョブは動詞で表せる ・ジョブは適切な抽象度で表せる ・ジョブはあらゆる業界での解決策を有している
0投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブのレンズを通してみる。新しい視点が間違いなく得られる本。新しいアイデアを求めるビジネスパーソンにとって必携の一冊。
0投稿日: 2024.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログあらゆる商品を購入する顧客は、そのプロダクトを購入したいのではなく、何かジョブを片付けるために購入するのである。 ジョブとは特定の状況で人あるいは人の集まりが追求する進歩である。ジョブは日々の生活の中で発生するもので、その文脈を説明する状況が定義の中心に来るイノベーションを生むのに不可欠な構成要素は、顧客の特性でも、プロダクトの属性でも、新しいテクノロジーでもトレンドでもなく状況である。 例えば、家を建てて売るビジネスだと思っていたビジネスが、実際には顧客の人生を移動させるビジネスなのだとわかった時、それは新しいジョブを提示することになる。
0投稿日: 2024.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ目に見える属性に注目した通常の市場調査からは見えない、生活様式や行動様式に注目して顧客自身も気付いていないもしくは当たり前で半ば諦めていた潜在的かつ共通性のある欲求(ジョブ)を明らかにすることの重要性がきれいに説明されていて面白かった。 実際にマーケティングに落とし込む際には「ジョブはこれでしょ?それならこのサービスが最適。」と当てがうのは禁物で、顧客が自分で選択したと感じさせることが重要かつ難しいポイントだろう。著者がジョブを考える時には適切な抽象度が重要だと言っているのは、この辺りと相性の良いと感じた。
0投稿日: 2024.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ星4.5 最高の良書、ホームラン本(樺沢紫苑氏の言葉)だった。この著者の本は有名な本たくさんあるがまだ見れていないので早速購入したいと思った。
0投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白い視点を得られた。 ユーザーが購入するというのはジョブをなし得ると捉えるのはとても新しい視点だと思う。 もともと仕事というのはそういうものだったのかもしれない。
0投稿日: 2024.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ新規機能開発において、要求・要件定義の指針がほしかったので、読みました。「ジョブ」とは、「ある特定の状況下で顧客が成し遂げようとする進歩」と理解しました。ジョブの設定において特定のプロダクトやサービスは特定されず、また名詞と動詞で表現されます。私が朝出社する途中にあるドトールコーヒーに入るのは、「コーヒーを飲む」というジョブではなく、「出勤時間までの間に落ち着いて本を読む」というジョブです。ジョブを定義し、組織をそのジョブに向かわせ続けることが、イノベーションへの道であるという論旨です。主張が明快かついまの自分にとって考えを巡らせる材料になりそうで、とてもよい本でした。
0投稿日: 2024.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログクレイトン・クリステンセンが「なぜそれを買うのか」でイノベーションの鍵を解説。ジョブ理論に基づき、商品の売れなさや成功の要因を明らかに。ビッグデータだけでなく、「顧客の片づけたいジョブ」に焦点を当て、無消費者も取り込む戦略を提案。事例としてイケア、GM、P&Gなどを取り上げ、ジョブ中心の組織づくりやデータ活用の重要性も論じる。最新のビジネス書として注目される。
0投稿日: 2024.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ『#ジョブ理論』 ほぼ日書評 Day734 ジョブ理論、原語ではjobs to be done(JTBD)だ。 ネットを検索すれば、星の数ほど解説文が見つかり、(おそらくは)ほぼ全てでニーズとジョブの違いについて解説がなされていると思うが、本書でも取り上げられる有名なドリルと穴の例をしっかり位置付けているケースは意外に少ないように思われる。 ジョブ理論以前は、ドリル=wants、穴=needsと解説されることが多かったのだが、本書ではその中間にjobという概念を持ち込んだ。 評者の解釈では、ニーズの実現(構成)要素を "done? y or n" が判定できるレベルまで具体化・細分化したものがジョブである。 よって「穴」はジョブであり、本来のニーズはその穴をもってして実現したい何かということになる。 内容的には例によってサンプルがアメリカ的過ぎて共感しづらいものが多い(冒頭の運転しながらミルクシェイクを飲むとか)が、もっともピンと来るのは、コストコで700ドル(10万円超)のベッドマットレスを「衝動買い」した一般男性の例か。 売り場の一角にあった、わずか2種類のマットレスから、実際に横たわってみて寝心地を確かめることもせずに、そんな高額な買い物を即決できた理由を探る。 決断自体は一瞬だったが、古いマットレスには眠りの質を妨げるということで、1年以上不満を抱いていた。この場合、質の悪い眠りを排除することがジョブとなる。 そして、そのジョブをdoneにするために、何らかのプロダクトやソリューションを雇用することが必要となり、それがここでは新しいマットレスということになる。 ただ、注目すべきは、新しいマットレスを雇用(hire)したい気持ちより、古いマットレスを解雇(fire)したい気持ちの方がはるかに強かったということ。 そして、コストコという一般には寝具購入とは縁遠そうな店でそれをしたのは、マットレス専門店で販売員の営業攻勢にさらされたくない。妻と一緒の買い物シーンだから、後々面倒なことにならない。コストコは不具合があれば返品を受け付けてくれる。こうした一連の要素だという。 ところどころ牽強付会に感じられる箇所もあるが、B2CだけでなくB2Bの世界でも、実際のエンドユーザーの立場になってのジョブを今一度考え直してみることは有用と考えさせられた。 https://amzn.to/40HOjlA
1投稿日: 2023.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客の求めているものをわかったつもりでは、イノベーションが成功するかは、一か八かだ。 何が顧客にその行動をとらせたのかを真に理解していないかぎり、賭けに勝つ確率は低い。 ものの見方を変えること。大事なのは、プログレス(進歩)であって、プロダクト(商品)ではない。 私たちが、商品を買うということは、基本的に、なんらかのジョブを片付けるために何かを「雇用」することである ■ジョブ理論の概要 ・ジョブを明らかにして把握できたあとは、そこで得た知見を優れた、プロダクト・サービスの開発に落とし込む青写真に書き換えなければならない。 ・ジョブには複雑さが内在する。機能面だけでなく、社会的及び感情的な側面もある ・ジョブはつくりだすのではなく、見つけ出すものだ。 ・ジョブそのものは変化しなくても、解決の方法は、時が経つにつれて、大幅に変化することがある ・顧客がなぜその選択をしたのかを理解できていなければ、根本的に欠陥をかかえたプロセスの進め方がうまくなるだけだ ・イノベーションをみると、その中心にあるのは、顧客ではなく、顧客が片づけるべきジョブである ・ジョブを最初に発見するのは、偶然やあてずっぽうではない。ジョブ理論を深く理解することで組織はイノベーションの取り組み方と成長する方法を根本から変える能力を手に入れられる ■ジョブ理論の奥行と可能性 ・問題は道具にあるのではなく、何を探し、観察した結果をどうつなぎ合わせるのかにある ・ヒントは、①身近な生活の中、②無消費に眠る機会、③間に合わせの対策、④できれば避けたいこと、⑤以外な使われ方、のなかにある ・片づけるべきジョブは、市場調査に頼るのではなく、人々の生活を注意深く観察して彼らの望みを直感し、それに従って進むことによって、探すことができる ・市場に成長の余地はもうないと感じられたら、ジョブを適切に定義できていない可能性がある ・できれば避けたいジョブは、進んでやりたいジョブと同じくらい沢山ある ・人は視野を広くもたなければならない。システムの世界で、ユーザ体験というと、美しい画面にボタンを使いやすく整列させることがすべてとおもいがちだ。 ・顧客が自分の要求を正確にもれなく表明できることはめったにない。顧客の行動の動機は、本人がいうよりも複雑であり、何かを購入するまでの道筋ははるかに入り組んでいる。 ・顧客が達成しようとする進歩は、文脈の中で理解しなければならない ・顧客がなしとげようともがいていることは何か、それがうまく機能していないのはなぜか、何か新しい解決策がほしいと彼らに思わせているのは何か ・ジョブを思いつくときには直観がものをいう。感覚としてはあっている ・片づけるべきジョブを明らかにするのは、最初の一歩にすぎない。あなたが売るのは、進歩(プログレス)であって、商品(プロダクト)ではない ・新しいプロダクトが成功するのは、その特徴や性能がすぐれているからではない、それに付随する、「体験」がすぐれているからだ ・もっとも知りたいのは、同じジョブのためにそのプロダクトを雇用したレビューアたちが何と言っているかである ■かたづけるべきジョブの組織 ・プロセスは目で見て理解するのが難しい、プロセスは、公式に文書化された手順と、非公式な習慣的な行動とでできている。 ・プロセスは手で触ることができない。企業と一体化している。 ・痛みを伴うリストラクチャリングは、だいたい臨んだ成果に結びついていない ・ジョブのレンズを通すと、誰が誰の指揮下にあるかよりも、顧客のかたづけるべきジョブを完璧に解決するプロダクト・サービスを組織が体系的に提供できることのほうがはるかに重要である ・顧客の片づけるべきジョブを中心に組織全体をまとめるには、予測可能で、反復可能なプロセスがなければならない ・うちでは、組織よりも、プロセスのほうをはるかに重視している。当社が迅速に動ける理由のひとつは、会社全体を通じて、同じ技術、同じプラットフォームを使い、同じ指針に沿っていることだ。 ・プロダクト指向ではなく、プロセス指向だ ・顧客がほしいのは、プロダクトではく、問題の解決策だ。 ・イノベーションのデータの誤謬 ①組織の情報フィルターが多層化するにつれて、ジョブではなく、企業は数字を管理するようになる ②大きな利益、すなわち、見かけ上の成長へフォーカスしてしまうと、ジョブへのフォーカスを失ってしまう ③確認したいデータのみに目がいってそれ以外のデータに注目しなくなってしまう ・組織に選択を正しく行うことができるようにするためには、かたづけるべきジョブのコンセプトを単純にしなければならない ・ジョブ理論が力を発揮すると、業務は引きしまる。無駄や、間接費が体系的に減り、使う時間や、エネルギーイや資源が最小化される。 ・私たちは、あらゆるものを測定できる。しかし、何を測定するかが重要だ。 目次 序章この本を「雇用」する理由 第1部 ジョブ理論の概要 第1章 ミルクシェイクのジレンマ 第2章 プロダクトではなく、プログレス 第3章 埋もれているジョブ 第2部 ジョブ理論の奥行きと可能性 第4章 ジョブ・ハンティング 第5章 顧客が言わないことを聞き取る 第6章 レジュメを書く 第3部 「片づけるべきジョブ」の組織 第7章 ジョブ中心の統合 第8章 ジョブから目を離さない 第9章 ジョブを中心とした組織 第10章 ジョブ理論のこれから 謝辞 日本語版解説 索引 ISBN:9784596551221 出版社:ハーパーコリンズ・ジャパン 判型:4-6 ページ数:392ページ 定価:2000円(本体) 発売日:2017年08月01日第1刷 発売日:2018年05月20日第6刷
11投稿日: 2023.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ一見、面白い新手の考察かなと感じて読むが、よくよく考えると、著者の論理の強引さによる抜け穴がそのまま、反証として成立する危うさを感じる。つまり「人が何かを買い求める際には必ずしも確度の高い理由がある」、こうした前提は成り立たないという事だ。その理由の深さや広さを尺度として、割とピンポイントのものを〝ニーズ“、付帯する潜在的関連性まで見抜く事を〝ジョブ“と呼んでいる。しかし、換言しているだけで、違いは無い。勿論、この物差しだけで、ある人には気付きを与えるのかも知れない。デザイン思考の手法のように観察すれば見えてくる潜在的な因果律を拾う。しかし、大多数は強い理由などなく、流されるような、経路依存を生きている。そしてこのルーチンから抜け出た微弱な新たな選択も、価格という決定打で簡単に妥協を生む。この抜け穴こそ、我々が与えられた一見新たな論説、言ってしまえば詭弁に感動する本著の建て付けに似ているという事だ。 なぜ売れるのか。なぜ売れないのか。 企業が今ほど顧客のことを知っている時代はなかった。ビッグデータ革命のおかげでデータ収集は多様性でも量でも速度でも、飛躍的な進歩を遂げた。集めたデータを分析するツールも高度化し、データの山から大きな宝を掘り当てようと日々様々な分析が行われている。しかし、データを拠り所にしても、ヒット商品に辿り着かない。本著では、ミルクシェイクを一例に挙げる。ミルクシェイクを朝買う人たちに人口統計学的な共通要素は無い。彼らに共通したのは片付けたい共通のジョブ。長い通勤時間ゆっくり飲めるシェイク、空腹を紛らわすことだと。 また、別の事例も紹介する。パンパースは中国で売れないオムツを売れるように改善するために、オムツを履かせる文化を作ろうとしたが失敗。おむつを履いた赤ちゃんがよく眠れるようになり両親に自由な時間が生まれた、あるいは乳幼児の睡眠時間が知能にもたらす影響をデータ提供したことにより最も売れる紙おむつのブランドとなった。 ここで挙げた二つの例は、いずれも「時間」に関わるものだ。プロダクトの本源は「自己の有する相対時間を向上されるモノ」。つまり、寿命を延ばす、限られた時間を有意義に過ごす、効率的に過ごす、楽しく過ごす、時短、性的接触のショートカットなど。で、偶々それを強く意識付けた、関連付けたプロダクトが先手必勝となるという理屈だろう。だとすれば、時間を要する失敗はしたくないから、日々、同じものを買うのだ。プロダクトの持つジョブとプロダクトを持たぬ状態のジョブの対立。これが、著者の論理の抜け穴ではないだろうか。
9投稿日: 2023.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ『イノベーションのジレンマ』で破壊的イノベーションがどのようにおきるのかを明らかにした著者が、なざイノベーションはおきるのか? どうすればイノベーションを起こせるのか? を書いたのが本書になる。 顧客はいったいどんなジョブを片付けるために商品を雇用したのか? 製品やサービスを、その性能でとらえるのではなく、それを使う人がそれを必要とする理由に注目することを教えてくれる。 「人は4インチのドリルではなく、4インチの穴がほしいのである。」 人は、特定の場面で、ほしい変化があるから、その商品やサービスを求める。 例えば、朝、ミルクシェイクがほしいのは、長い通勤時間に、気を紛らわせてくれて、小腹も満たしてくれ、しかも、運転中に片手で飲めるものがほしいからだ。 特定の場面で、ほしい変化を本書ではジョブと呼び、そのジョブに注目して、製品を考えていくことがイノベーションを起こすことにつながると述べている。 仕事をする上で、自分たちの提供しているものは、はたして、どんなジョブの為に求められているのか、もっとジョブに注目したものにすべきでないか、考え続けることが重要だと感じた。
4投稿日: 2023.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ジレンマ」に比べるとBtoC向け。結局良いイシューを見つけて、一番に解決するってことのよう。ブルーオーシャン戦略に似ている。最近だとチョコザップが例に挙がりそう。
0投稿日: 2023.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客が求めるニーズの本質を考えていかなければならないことを学べた1冊でした。最初は内容が難しく読み辛さを感じてしまいましたが、読み進めていくうちに「顧客が片づけたいジョブ」に対して理解を深め、とても面白く読み終えることができました。この本で学んだニーズの問いかけについて、仕事に活かしたいと思います。
0投稿日: 2023.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブという言葉を「顧客が解決したい問題」だと脳内で上書きするまで時間がかかるが、ニーズ (顧客が欲する商品・サービス) との違いがわかればどんどん読み進められる。商品・サービスの機能自体ではなく、そこから得られる体験を重視するトレンドは「CX」書籍からも認識できるが、具体例の豊富さ・わかりやすさで理解がより深まる。 読者は自分の立場に照らして「当社の商品・サービスは顧客の人生を向上させるために役立っているか」という根本的な問いを立てるところから始める必要があるのではないだろうか。
0投稿日: 2023.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ・顧客の購買目的は製品やサービスの購入ではなく「進歩(プログレス)」である ・「進歩」は、「ジョブ」を片付けるもの=製品やサービスの雇用で実現できる ・顧客の抱える片付けるべきジョブをもとにブランディングを考えるべきである
0投稿日: 2023.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログマーケティングでよく言われる「顧客ニーズ」というものの解像度を高めたのが「ジョブ」であると感じた。 本書を読み、「ジョブ」に関して以下のように捉えた。 ・顧客が特定のプロダクトを生活の中に引き入れる理由を説明するのが「片付けるべきジョブ」理論 ・ジョブの定義は、「ある特定の状況で顧客が成し遂げたい進歩」 ・自社商品を雇用する顧客のジョブを捉えることで、自社商品が万能の薬と思い込まないようにする ・ジョブは適切な抽象度を持たなくてはならない
0投稿日: 2023.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに読み返しました。仕事の進め方だけでなく、人生の生き方についても何が本質なのか考えて行動すべきと改めて思いました。
0投稿日: 2023.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログクリステンセン教授のジョブ理論。ジョブという概念に注目して商品・サービスの企画設計から組織設計までを考えるというもの。 ジョブとは、顧客にとって解決しなければならない課題であって、必ずしも顧客がクリアに認識しているものではない。本書の例で言えば同じミルクシェイクでも、朝のドライバーにとっては運転中の空腹を満たすことであり、夕方の子連れの親にとっては子供の要求を否定せずに受け入れてあげることといったことになる。2つともに表面的にはミルクシェイクに紐づかない。だから普通の販促や商品の多様化をしても売上は伸びないのだ。 これを追求していくと、自社は顧客のどのようなジョブを解決するためにサービスや商品を提供しているのか、あるいはどのようなジョブを解決したくて商品を開発しているのか、といった視点が生まれる。それは言わばニーズに近いものだけれど、本書ではニーズは明確に認識された要求ぐらいに定義されているのでジョブほどの奥行きを持っていないとしている。だけど、それはアカデミックな区別のためのものであって、実務家としてはそこまで気にする必要はないと思う。 本書の白眉は、一度ジョブを的確に捉えて成功したキャンベルスープが従来通りの製品の種類を増やして複数のジョブに対応しようとして、逆に本来のジョブを見失ってしまったこと。顧客のジョブをみせてくれる受動的データを無視して、製品別売上などの従来通りのデータ=能動的データをみて、顧客のジョブを見失ってしまうことを事例をあげながら説明しているところだろうか。またコストコでマットレスを購入した顧客へのインタビューの仕方は、なぜコストコのキャッシャーの直前に置いてあったマットレスを「衝動買い」してしまったのか、具体的に顧客のジョブを浮き彫りにしようとする方法として興味深い。ここまで聞いてくれるのかとインタビューされていた顧客が驚くほどで、結局はこういうところが重要なのだなと思わせる。 当たり前といえば当たり前なのだけれど、これを実践できたら強いと思わせる理論がジョブ理論なのだと思う。
0投稿日: 2023.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ【印象に残った点】 ・今はこれまでになく顧客のことを知っている(データ集積された)時代 ・一方、相関関係が見えても、因果関係が理解されていないケースが多い ・示唆にすべきは、なぜ顧客がそのプロダクトを採用したのか? ・プロダクトの採用=片づけたいジョブ(用事、仕事)のためにプロダクトを"雇用"すること ・ジョブ=顧客が成し遂げたい進歩
0投稿日: 2022.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ大枠はUXデザインやデザイン思考などで到達したいことが事例豊かに語られている。 しかし、そういったフレームだけでは抜けてしまいがちな視点が豊富に語られており、気付きを与えてくれる良書。
0投稿日: 2022.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログやり遂げたいジョブを解決するために商品を「雇用」する。少し昔の言い方だと手段と目的なのかなと思うが、これが事業やアイデアを創発するための基本かと思う。 以下、備忘として印象的なフレーズ。 ・“ひとつですべてを満たす”万能の解決策は結果的に何ひとつ満たさないのだ。 ・私たちはあらゆるものを測定できる。しかし、何を測定するかが重要なのだ。
0投稿日: 2022.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ前々から積読状態だった「ジョブ理論」にようやく手を付けました。 この本も有名になり過ぎて、本を読まなくても何となく内容が理解できるので、 「まーいっか」となっていたいのですが、 読まざるを得ない環境に追い込まれたので、読んでみました。 重厚な見た目とは裏腹に、案外読みやすいです(アリガタヤ)。 そして副読本として、「「ジョブ理論」完全理解読本」と一緒に読みました。 こんな本があるなんて!って感じでしたが、知人が教えてくれました。 ※「ジョブ理論」完全理解読本 https://booklog.jp/users/noguri/archives/1/4798157104#comment 後半に進むに従って、少し尻すぼみ感はありますが、 それでも「顧客のジョブを解決するために顧客は 商品やサービスを購入している」という考え方は画期的だと思います。 この考えは忘れないように生きていきたい! クリステンセンの本は初めて読みましたが、 他の本も読んでみたい(ちょっと勇気がいるけど)と 思わされるような良書でした。
24投稿日: 2022.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ解決すべきジョブは何か? 顧客を階層などの固まりで捉える事では辿り着けない視点の持ち方。 シンプルであるが故に強い軸になり得る視点ですね。
0投稿日: 2022.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ事業アイデアの基礎。 「ドリルが欲しいのではなく、穴が欲しいんだ」を絶対に忘れてはいけない。 課題に対してソリューションは一つではないと気づきを得られる。
0投稿日: 2022.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ有効なジョブは形容詞や副詞で説明しない。「片付けるべきジョブ」は名詞と動詞で表現できる。 マーケットではデータから読み取れないこともある。消費者が何を思い、考え、その人の生活までも視野に入れた俯瞰的で具体的なキーワードを寄せ集め、ジョブを適切な抽象度を保ちながら明確にしていく必要がある。
0投稿日: 2022.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログwhatでなくてwhy 改善よりも改革 役に立つかでなくて意味があるか 真に解決すべき問いは何か? と言った話に近しい。 内容についての納得感は十二分である一方、 よく言われる話。 ということはつまり、(自身含め)理解しつつも行動を変えられていない。或いは、分かったつもりになっているだけ。 ということなのか。 企業が売りたいと思ったものは売れない の話に関連した、受動データ/能動データの話や真に主観的でないデータは存在しない。という考察は興味深かった。
1投稿日: 2022.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分を例に取ると味噌汁の個包装が思い当たる。 現在、一人暮らしでよく自炊をしている。 自宅には和食に使う調味料が多く(他には中華もある)、献立はもっぱら和食になることが多い。 和食となると、ご飯、主食、菜食、汁物と並ぶが、一人暮らしのIHコンロが一口の生活には全てを揃えるにはハードルが高い。主食と菜食を作り置きしておくことがあるが、毎回ではない。例えば、主食を作っている間はコンロが埋まってしまい、菜食も汁物も作れない。しかし、個包装の味噌汁があれば、湯沸ポットで沸かした湯を注ぐだけでできてしまう。 しかも、コンビニで売っているようなカップ状の味噌汁に比べてコストがかなり抑えられる。確かカップは具材にもよるが、1食分で100円ほどする。一方、個包装のものは一袋24食分ほど入っていて300円ほど(1食分で12.5円)と圧倒的なコストパフォーマンスを発揮する。 また、応用も効きやすい。例えば、麻婆豆腐を作ろうとした際に、味噌がいる。一人暮らしで作る量的に、あの個包装の味噌が丁度いい。 あと、会社での昼ごはん。出社した際に弁当を買うことがあるが、その際に個包装で買った味噌汁を一組持って行くだけで簡単に味噌汁ができるのも良い。だいたいの会社の休憩室には給茶器があり、紙コップかプラコップがあるので、それを容器にできるから、わざわざ感もなくて良い。 あとは、登山に行く時にも使える。山頂でコーヒーを楽しみたいと思っているから、だいたいバーナーと耐熱容器は持ち合わせているもの。昼ごはんにおにぎりなどをチョイスしたら、最高のお供になる。 これがジョブ理論の考え方だろうか。
1投稿日: 2022.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ人が何かを「買う」時、その製品そのものが欲しいのではなく、その製品を使って自分の生活を向上させたいのである。これが本著の核心である。この理論を使えば、自社のプロダクトやサービスの潜在顧客をより広く捉え直すことができる。 本著ではこの理論を適用した様々な事例が紹介されており、帰納法に結論を描いていくという構成になっている。故に冗長ではあるが、コンセプトが理解しやすい。
0投稿日: 2022.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの「そもそもユーザーは何の解決が目的なのか」という視点、そこからのジョブ理論についての書。 翻訳本なので少しボリュームはありますが、読み返していきたい一冊です。 #最後読み切っていなかったのですが、ようやく読了。
0投稿日: 2022.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり面白かった。 商品を求める人の特徴を知るのではなく、なぜその商品を求めたのか、どんなジョブを片付けるためにその商品を雇用したのか、という目線でビジネスを考える本。 言われてみればその通り、、!と納得することばかりで、小難しい言い回しなどもなく、具体例も的確ですごく読みやすかった。 ただ、少し長い。
1投稿日: 2021.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログあまりにも面白く、文字通り衝撃を受けました…。この本を読み、自分の仕事の捉え方が変わり、顧客とのコミュニケーションにも大きな変化が起きています。 「顧客は特定の状況下で成し遂げたい進歩(ジョブ)があり、その為に何か苦労をしている、それを片付けるための解決策や付随する体験を求めている。」 ごく当然のことなのですが、ある企業で同じ仕事をしている同じ年代の人でも、状況(ライフステージ、家族構成、財政状況)は個別に異なっていて、エージェントに解決して欲しいことや、解決したいと考えていることの時間軸も違います。 1対1で顧客に向き合うビジネスだからこそ、分かった気にならず、顧客の抱える複雑を踏み込んで捉えにいきたいですし、顧客が言葉にできないことを言葉できるようになる、そのプロセス・体験を創る力を磨いていきたいです。 全然違う分野ですが、本書に登場するミルクシェイク、おむつ、マットレスの購買プロセスの分析もめちゃくちゃ面白くて、目から鱗です。
0投稿日: 2021.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブ理論の問と答えは至ってシンプルではあるが、だからこそ奥が深い。新規事業系の人に限らず読んでほしい一冊。
0投稿日: 2021.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・データを平均化することで顧客の需要を把握できなくなること ・顧客がどういったストーリーを持って、そのプロダクトを雇用しているかを分析すること 後半はたしかに前半と同じことを繰り返している感じがしたが、全体的に具体例が多く散りばめられていて読んでいて飽きない、そんな作品に感じた。
0投稿日: 2021.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのての分厚いビジネス本にありがちな、 「後半いる?」感はありました。 でも、理論としては「鋭いな」と思った。 これをどう活かすか?ですが。
0投稿日: 2021.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログとても良かった。 プロダクト作りを進めていく上に置いて1つの観点を与えてくれる書籍。 何を作るかや既存のプロダクトを考えていく時に、顧客の抱えているジョブを理解し、そのジョブの達成のために採用される手段としてプロダクトが用意されている、という観点は忘れてはいけないなと思った。 この各領域におけるジョブが何なのかについては詳細な調査と洞察を使わないと見つけられない部分なので、数字だけでなく顧客が抱えている文脈を正しく理解する必要がある。 筆者自身は顧客の属性ごとの分類(セグメンテーション)はあまり意味ないと語っている。 そのような形でとても面白い本だった。
1投稿日: 2021.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://twitter.com/itaya_gaiax/status/1403664865361743877?s=21
0投稿日: 2021.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まではどうしてもプロダクトアウトの考え方、商品をどうより良くするのか、という改良の面を考えることが多かった。 そうではなく、そのジョブをどう雇用してもらい進歩させるか、その考え方が重要だと気付かされた。 日常でも満たされないなぜ、という場面は多くある。 そこにビジネスチャンスがあると思うので、日常のなぜを注意深く観察していく。
0投稿日: 2021.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ人が商品・サービスを購入・利用するのはジョブを片付けるためであるという考え方。ジョブは機能だけでなく社会的、感情的ニーズも重要であり、人々の生活の中の「状況」を捉えることがジョブ理論の根幹になる。 デザイン思考とかにも近い考え方に思えた。ジョブを正しく捉えるとミルクシェークの競合がバナナやベーグルになるなど市場の見方が変わるのは面白い視点。 「顧客はドリルが欲しいのではなく、穴が欲しい」
0投稿日: 2021.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて知った概念。私はその商品を買ってどのようなジョブを解決したいのか。起業する上でも持っていたい視点だ。
0投稿日: 2021.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログどんな『ジョブ(用事)』を片づけたくて、あなた(顧客)はその商品・サービスを『雇用』するのか? それに気づけるか否かは日常の注意力とか観察力とかみたいなものが勝負かなと思った。 風呂に入ってる時も子供と遊んでいる時もスーパーで買い物してる時も何かしら気づきを拾う好奇心とか注意力が大事。それでいて仕事や業務とか成果とかみたいなものに心を支配されない気持ちの遊びみたいなものも大事。 難っ! と思った。やってみる。
0投稿日: 2021.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ”イノベーション”って言葉を聞いた事が無い人は少ないかと思うのですが、実際にどんな事でどんな意味なのか知っている人は少ないですよね。当書籍では”ジョブ”の定義から始まり、その具体例を全10章に纏め、ビジネスリーダーに対する問題提起もされております。イノベーションの成否は顧客データや市場分析上の数字ではなく、”顧客の片づけたいジョブ(用事・仕事)"であるという事です。気になる方は手に取って下さい。
0投稿日: 2021.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはさすが。 ビジネス考えてるとどうしてもいかにしてマネタイズするか、ユーザーを集めるか という方法論に注力しがちだけど、「そもそもこれってどんなジョブを解決するためのサービスなんだっけ?」と問いかけるきっかけをくれる本。
0投稿日: 2021.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム クレイトン・M・クリステンセン タディ・ホール カレン・ディロン デイビッド・S・ダンカン 著 2017年の本 改めまして、「ジョブ理論」を今更ながら読んでみた。非常に面白かったし勉強になった。(お恥ずかしながらイノベーションのジレンマ、は、実はちゃんと読めていないのでどこかのタイミングで改めて読みなおしてみたい) いくつかのビジネス書の有名どころを読んでいったとすると、クリステンセン教授の偉大な思想の件には何度となく引用されてきたし、ベーシックとして知っておかねばな、と思って「ジョブ理論」を改めて読んでみたいと思った。 先日読んだ「世界標準の経営理論」の中で、何が理論であって何が理論でないのか、という観点での入山先生の見解を見た後にあえて「ジョブ理論」を読んでみるとすると『経営・ビジネスのhow,when,whyに応えること』という観点において「ジョブ理論」はすばらしく踏み込んでの記述がされているなぁと、一読者としては感銘を受けていたところである。(ハーバードが学術業績よりビジネスよりという見解もあるだろうが) ちなみに本書P57 には以下のように記されているのであえてここで抜粋しておきたい。 === アカデミックな場に身を置く私は、特別な知識もない業界や組織のビジネスが抱える課題について意見を求められることが年に何百回とある。それでも見解を述べることができるのは、何を考えるのかというより、どのように考えるかを教えてくれる、理論の詰まった道具箱を持っているからだ。優れた理論は、最も役立つ答えが得られる質問を投げかけ、それをつうじて本当の問題が何かを組み立てる。理論を採用するということは、学術的な細ごましたことにとらわれるのではなく、むしろその逆で何が原因で何が起こるのかという、このうえなく実用的な質問に焦点を絞るためである。 === 参考:ジョブ理論の中ではよく『片付けるべきジョブ』という記述がされていて、英語では「Job to Be Done」という言葉で表現されている、とのこと。 抜粋フレーズ、自分が気になった・引っかかったフレーズ、重要と思ったポイントというところで。 ========== P15 『どんな“ジョブ(用事・仕事)”を片付けたくて、あなたはそのプロダクトを“雇用”するのか?』 P58 ジョブ理論の中核には、単純だが強力な知見が込められている。顧客はある特定の商品を購入するのではなく、進歩するために、それらを生活に『引き入れる』というものだ。この「進歩」のことを顧客が片付けるべき「ジョブ」と呼び、ジョブを解決するために顧客は商品を「雇用」するという比喩的な言い方をしている。この概念を理解すれば、顧客のジョブを発見するという考え方が直観的にわかるようになる。 P91 片づけるべきジョブ理論のレンズを通してみて、ルブランたちは気づいた。18歳ではない、非典型的な学生がSNHUを雇用して片付けようとするジョブは、高校を卒業してそのまま大学に入学する学生のジョブとはほぼ共通点がなく、取り巻く状況が大きく異なっていた。通信課程の学生の平均年齢は30歳、仕事と家庭を両立させようとやりくりしていて、さらに勉学の時間をねじこもうとしている。(中略)将来のキャリアアップを目指し、ひいては家族の生活水準を向上させるには、いまより立派な学歴が必要だと悟ったのだ。青春時代の経験ならすでにある。彼らが高等教育に求めるものは、利便性、サポート体制、資格取得、短期修了の4つあった。ルブランのチームは、そこに途方もないチャンスが眠っていることに気づいた。 P119 見込み客が転居を決断できないのは、建設会社が魅力的な提案をできていなかったからではなく、人生にとって深い意味をもつ何かを手放すことに不安を感じるからだった。 P202 イケアは、人口統計学的な特定の層へ向けた販売を重視していない。新しい環境で自分自身および家族の生活をととのえようとするときに、おおぜいの顧客がもつジョブ -「明日までに新居の家具をそろえる必要がある。 明後日からは仕事だから- を中心に組織を築いた。 P203 彼はイケアを雇用することを選んだが、それは他の解決策うより値段が高かったとしても変わらない。なぜなら、イケアが他のどこよりもジョブをうまく片付けるからだ。ジョブを解決する商品にふつうより高い値段を払ってもいいと思うのは、ほかの商品はジョブを遂行できず、結果的に時間を無駄にし、ストレスを溜め、金も無駄にしてしまうからだ。解決策を見つけるまでにすでに時間とエネルギーを消費しているため、プレミアム価格を提示されたとしても、すでに費やした金銭および個人的資源と比較すると小さな差にしかみえない。 P242 ジョブのレンズを通すと、誰が誰の指揮下にあるかよりも、顧客の片付けるべきジョブを完璧に解決するプロダクト/サービスを組織が体系的に提供できることのほうがはるかに重要である。幹部たちが顧客のジョブに集中していれば、それはイノベーションを推し進める方向を示す明確な磁石となり、さらには、内部構造を組織する際のぶれない理念となる。 ==========
0投稿日: 2021.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ物事がなぜ起きるのか、その仕組みを「ジョブ」という切り口で説明する理論に関する本。 ジョブ理論はイノベーションを運任せのものから必然のものに変えるために必要な概念で、日本企業が忘れてしまった顧客目線を再認識させてくれる。
0投稿日: 2021.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客が人生の特定の状況において望む進歩を「ジョブ」とし、これを解決するための手段として企業のプロダクトを「雇用」するという枠組みを軸に、企業は自社のプロダクトが顧客のどのような「ジョブ」に対する解決策なのか、自社プロダクトが「雇用」されるために何に注力すれば良いのか、当該ジョブに対して自社プロダクトと競争関係にあるのはどの業種のどのようなプロダクトか、これまで解決策を顧客が「解雇」して自社に乗り換えてもらう抵抗感をなくすために必要な策は何か に留意することでイノベーションを成功させることができ、その後も、自社がターゲットとするジョブを社内に浸透させて組織文化とし、ジョブを片付けることを軸に組織とプロセスを構築し続けることで持続的競争優位を確保できると説く。
0投稿日: 2021.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ400ページ近い分厚さに圧倒されたが、 読み始めるとわかりやすく身近な具体例も多く示されていたので、大変興味深くスラスラと読み進めることができた。 ジョブ理論とは「なにが原因でなにが起こるのか」を学ぶ理論である、と。とても面白い。 マーケターとして、自社のプロダクトを顧客が雇用するとき、どういうジョブを解決したいのか、施策検討の際には立ち返りたい
0投稿日: 2021.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブ、進歩や課題が満たされてる時代に発見することが難しい時代ゆえに、アートな思考を、というのが最近の流れか。無理に見つけることだけじゃなくて、もっと基本的な価値を磨くことも忘れずに。
0投稿日: 2021.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで、私は、提供者目線で、サービスの優位点、他社と比較した差別化を考えて商品企画をしていた。しかし、それでは、真に選ばれる商品は生み出せないことに気づかされた。顧客の片付けたいジョブは何か?その一点に集中する事の重要性を学んだ。
0投稿日: 2020.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ商品開発は消費者のジョブを解決することからスタート、P&Gで言うWHOを決めるために必要。でも片付けたいジョブが正しいのかを消費者リサーチで確かめることやそしてジョブを解決するWHATやHOWの革新性が成功を決めるという気もする。
0投稿日: 2020.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ統計的なデータを分析しても消費者と商品の関係は読み解けず、結局は人を見にいかないといけない。 人はなぜその商品を買うのか?普段行動している私たちですら、言語化できず、無意識で購入していることが多いと思います。 本書ではそんな”購買”という議題について、ジョブ理論をもとにその購買行動を解明しようとしています。 "私たちは自分の課題(=ジョブ)を片付けるために、商品を雇用し、解決する" 消費者・商品・課題の関係について、具体例を交えながら説明されているのでわかりやすかったです。マーケティングの勉強をしたい人におすすめです。
0投稿日: 2020.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ”顧客はある特定の商品を買うのではなく、進歩するためにそれを生活に引き入れている” この言葉と、本書にあった5つのポイントを頭に叩き込んでいれば、私にもマーケティング思考が身に付くはず。 その他のポイントとしては、「ジョブ」とは「ニーズ」とも「トレンド」とも違う、遥かに複雑な事情を考慮している。 プロダクトを機能面だけでなく社会的および感情的な側面も考えてみること。 顧客のジョブを解決するうえで、プロダクト/サービスは何と競合するか。ネットフリックスがビデオゲームやワインを飲むことと競合しているように、同じ業界意外に競争相手はいないか考えること。 現状では満足な解決策が存在しない「無消費」とも競合すること。 顧客が新しいプロダクトを雇用するまえに、それと引き換えに何を解雇する必要があるかを理解すること ::::::::::::::::::::::::: ちょっ私には難しくて読み辛かったので、一度読み終わったあとにブクログの感想を読んで、もう一度本書をざっと読んでみた。 やっぱり後半部分は頭に入ってこなかったので、今の自分にはまだ必要ではないのかもしれない。
0投稿日: 2020.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログジョブとは片付けるべき用事であり改善である。 つまり彼ら彼女らの抱える課題の解決策である、それは決して、プロダクトの過剰な改善を追い求めることではない。 ジョブとプロダクトの一致が支持されるパーパスブランドと呼ばれる市場を代表する一大商品に成長する。 求めているものはスプレッドシートにあるのではなく、顧客が片付けたいジョブをベースに考えることで、イノベーションの成功に一歩近づける。 あと、謝辞が長い
0投稿日: 2020.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログプロダクト設計を担当する人は必読 プロダクトを作る上で、考えるべきことは「ジョブ」である。 “ジョブはそれが生じた特定の文脈に関連してのみ定義することができ、同じように、有効な解決策も特定の文脈に関連してのみもたらすことができる。” 性年代別のクラスタリングによる設計ではなく、ジョブを軸にしたプロダクト設計を行うことが重要であると感じた。 ジョブを片付ける上で考慮すべきなのは無消費の存在である。 競合は、類似のプロダクトや同じジョブを片付けるプロダクトだけではなくそれを消費しないことも競合になりうる。 プロダクトを作っている人は、一読するとプロダクト設計を考える上での有益な視点をもたらしてくれる本だと感じた。 メモ ========== ジョブの定義には「状況」が含まれる。ジョブはそれが生じた特定の文脈に関連してのみ定義することができ、同じように、有効な解決策も特定の文脈に関連してのみもたらすことができる。ジョブの状況を定義するにあたり、重要な質問はたくさんある。「いまどこにいるか」「それはいつか」「誰といっしょか」「何をしているときか」「 30分前に何をしていたか」「次は何をするつもりか」「どのような社会的、文化的、政治的プレッシャーが影響を及ぼすか」などだ。ここでいう「状況」とは、その他の文脈上の要素、たとえば、ライフステージ(学校を卒業したばかりか、中年期の危機に陥っているか、もうすぐ定年か)や、家族構成(既婚、未婚、離婚? 乳幼児が家にいるか、親の介護が必要か)、財政状態(債務過多? 超富裕層?)などに拡大することができる。ジョブを定義するのに(その解決策を見つけるためにも)状況が不可欠なのは、なし遂げたい進歩の性質が状況に強く影響されるからだ。 ・ジョブとは、特定の状況で人あるいは人の集まりが追求する進歩である。・成功するイノベーションは、顧客のなし遂げたい進歩を可能にし、困難を解消し、満たされていない念願を成就する。また、それまでは物足りない解決策しかなかったジョブ、あるいは解決策が存在しなかったジョブを片づける。・ジョブは機能面だけでとらえることはできない。社会的および感情的側面も重要であり、こちらのほうが機能面より強く作用する場合もある。・ジョブは日々の生活のなかで発生するので、その文脈を説明する「状況」が定義の中心に来る。イノベーションを生むのに不可欠な構成要素は、顧客の特性でもプロダクトの属性でも新しいテクノロジーでもトレンドでもなく、「状況」である。・片づけるべきジョブは、継続し反復するものである。独立したイベントであることはめったにない。 ジョブ理論が重点を置くのは、?誰が?でも?何を?でもなく、?なぜ?である。 その人がなし遂げようとしている進歩は何か。 苦心している状況は何か。 進歩をなし遂げるのを阻む障害物は何か。 不完全な解決策で我慢し、埋め合わせの行動をとっていないか。 その人にとって、よりよい解決策をもたらす品質の定義は何か、また、その解決策のために引き換えにしてもいいと思うものは何か。 たとえば、ティーンエイジャーには昔から、口うるさい両親に邪魔されずに連絡をとり合いたいというジョブがある。 何年かまえまでは、学校の廊下でメモを渡すか、自室のいちばん端に長々と電話コードを引っぱっていったものだった。だが最近のティーンエイジャーは、メッセージが届くとほぼ同時に消えるスマートフォンのアプリ〈スナップチャット〉など、数十年前には想像すらできなかったものを雇用しはじめている。スナップチャットの考案者はティーンエイジャーのジョブをよく理解し、優れた解決策を生み出した。しかしもちろん無敵ではなく、特定の状況における社会的、感情的、機能的側面の入り混じったティーンエイジャーの複雑なニーズをさらによく理解した競合相手が現れれば、とって代わられるだろう。 人がフェイスブックを雇用する理由も多くが喫煙と共通している。仕事の合間に休憩しようとフェイスブックにログインし、仕事とは別のことを考えながら数分ほどリラックスして、遠く離れた友人たちと仮想井戸端会議を開く。ある意味フェイスブックは、じつはタバコと同じジョブをめぐって競い合っているといえる。喫煙者がどちらを選択するかは、その特定の時点でその人が置かれている状況によって異なる。 社会的、感情的、機能的側面については何を考慮すべきか。
0投稿日: 2020.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。これぞ商売の本質だと思った。そして自分の取り組み方がそれほど間違ってないこともわかった。あと何冊かジョブ理論について読んでみたい。
0投稿日: 2020.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログイノベーションのおこしかたを「片づけるべきジョブ」から導こうとする理論。ジョブと聞くと日本人にはあまりなじみがないが、冒頭の「ミルクシェイクのジレンマ」のケースは秀逸でよく理解できた
0投稿日: 2020.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しい。何度も迷子になる。 ニーズやインサイトとの違いが、わかったようでわからなくなる。 でもメーカーのお仕着せ・仕様からの勝手な分類ではなくて、生活者の立場で役割を捉え直さなければならないんだな、というのはとても伝わった。 だからこそ真の「ニーズ」的なものを捉えたかったら、大袈裟に言えば体験をデザインするような行為視点が必要なのかも。
1投稿日: 2020.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客のジョブ(用事、仕事)を片付けるためにプロダクトを雇用する、という考え方がジョブ理論。顧客のジョブを発見する方法、自社のライバルは同業他社以外にも実はいることを教えてくれ、視野の狭さ、ものの見方が偏っていることに気づいた。
0投稿日: 2020.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログあるものを購入するのではなく、進歩するために生活に引き入れる 進歩 が ジョブ 顧客が片付けるべきジョブ マーケティングする際機能面だけで捉えてもうまく行かない 成功するイノベーション 顧客がの成し遂げたい進歩を可能にし、困難を解消 満たされない念願成就 物足りない解決策しかなかったジョブ 解決策がなかったジョブを片付ける 機能面だけじゃなく社会的及び感情的側面も重要 機能面より強く作用することある JOBとニーズは大きく異なる 状況が定義の中心 ニーズはトレンドと似ている ニーズだけでは購入のアクションにつながらない 心に残った内
0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ジョブ理論 著:クレイトン・クリステンセン <所感> * 良著。いわゆる「痛み」発信のアプローチについてこれまで学んできたことを多分に含んでおり、今読んだことで理解もすっきりと進んだ。 * クリステンセンの「イノベーションのジレンマ」が破壊的イノベーションに関する理論書の性格出会ったのに対し、本書「ジョブ理論」はもう少し実践的で、アクションにつなげやすい。 * DAにおけるサービス考案の際にも参考にしたい記述がいくつもあった。定期的に立ち戻りたい。 <メモ> * ジョブの解決という行為を体験と結びつけることは、競争優位を獲得するうえで極めて重要である。なぜなら、競合相手にとってプロダクトの模倣だけなら簡単にできてしまうが、自社のプロセスに強く結びついた体験を模倣することは難しいからだ。 * ジョブは、「ある特定の状況で人が遂げようとする進歩」と定義される。重要なのは、顧客がなぜその選択をしたのかを理解することにある。すなわち、ジョブの定義には「状況」が含まれる。ジョブはそれが生じた特定のコンテクストに関連してのみ定義することができ、有効な解決策もまた特定のコンテクストに関連してのみもたらすことができる。→カスタマーストーリーに沿った体験の構築の重要性 * 成功するイノベーションは、顧客の成し遂げたい進歩を可能にし、困難を解消し、満たされていない念願を成就する。また、それまでは物足りない解決策しかなかったジョブ、あるいは解決策が存在しなかったジョブを片付ける。 * ジョブ理論は、消費者がさほど困っていなかったり、存在する解決策で十分間に合ったりするときには役に立たない。 * 顧客のジョブを見極めるということは、顧客が実際に支払おうとするもの以上に機能を増やしすぎてはいけないということだ。 * ジョブの見つけ方 * 生活に身近なジョブを探す。自分の生活の中にある片付けるべきジョブは、イノベーションの種が眠る肥沃な土地だ。 * 無消費と競争する。片付けるべきジョブについて学べるのは、何らかの商品やサービスを雇用している人からだけではない。何も雇用していない人からも、同じくらい多くのことを学べる。 * 間に合わせの対処策。ジョブをすっきりと解決できずに間に合わせの策で苦労している消費者に着目する。 * できれば避けたいこと(「ネガティブジョブ」)はイノベーションの優れた機会であることが多い。 * 意外な使われ方。顧客がプロダクトをどう使っているのかを観察することでも多くを学べる。 * 特定したニーズは、顧客が今何に苦労しているのかという社会的および感情的な側面は考慮せずに、機能面ばかりを重視したものとなりがち。感情的および社会的な側面は多くの場合、機能的なニーズと同じ平面上にあるのではないか。→DAサービス考案でも意識したいポイント。 * 現状に満足はしていないものの、今のやり方になれている消費者の「変化に反対する力」は大きい(損失回避バイアス)。それを打破するだけの価値・体験を提供できるか? * 新しいプロダクトを成功に導く地検は奥深く込み入っていて、統計データよりもむしろストーリーに近い形で現れる。個々のインタビュー結果をカテゴリーに分類するのではない。→起業の科学でも言われていた点。 * ジョブを中心にしたイノベーションの考え方の3ステップ * ジョブの特定:どのジョブにも、機能的、感情的、社会的側面があり、それぞれの重要性はコンテクストに依存する。 * 求められる体験の構築:3つの側面を踏まえ、ジョブ遂行に伴う体験を構築する。 * ジョブ中心の統合:ジョブの周りに社内プロセスを統合し、求められる体験を提供する。 * 自社製品を購入するときだけでなく、使用するときに、顧客はどのような体験を求めているのか?→UI設計において意識すべき点 * Airbnbでは、地元の雰囲気やゲストに提供できる体験について事前に説明文や写真を駆使して伝えている。これは、ゲストに自分の選択にがっかりさせないために、そして厳しいレビューを書かせないために大切なのである。→レビューがモノをいう時代だからこそ、ユーザーの期待値コントロールは重要となる。 * GMの車載情報通信サービス「オンスター」の開発過程がとても参考になる(DA)。 * 「スタックの誤謬」とは、技術者が自分の持つテクノロジーの価値を高く評価しすぎ、顧客の問題を解決するための、下流のアプリケーションを低く評価しすぎる傾向のことを指す。これは、テクノロジーの領域外でも当てはまる。→プロダクトアウトvsマーケットイン * マネージャーには、職務柄、情報に反応する習性がある。否定的な情報であればなおさら、素早く対応せざるを得ない。このため、売上データ等の能動的データに引きずられやすくなる。 * われわれは自分に適したデータを選び出す習性がある。「アイデアを引き出すための道具としてではなく、自分の意見を補強するために調査を利用するときによくみられる。→材料探しにコンサルを起用するようなイメージ * ジョブを形容詞や副詞で説明しているとしたら、それは有効なジョブではない。明確に定まった片付けるべきジョブは、動詞と名詞で表現できる。 * 提供者のジョブと消費者のジョブが整合することが望ましい。医療業界において、病気の患者が増えることは提供者にとって収益機会だが、消費者にとってはunhappyである。これを整合させるために、病気予防に関するイノベーションが促進されるのは健全な流れ。→保険の場合、ロスを減らすことが双方にとってwin-winである。ロスプリや安全社会構築はその面で筋好。
1投稿日: 2020.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前であればこの手のノウハウ本が大好きだったが、最近はどれを読んでも似たような内容に思えてきてしまい、途中からは各章のまとめだけをチラ見して終わった。
1投稿日: 2020.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ【髙島】 イノベーションのジレンマのアンサーソングみたいな本(著者が同じ)。消費者のニーズを、「消費者が特定の目的のためにサービスや製品を雇用する」という観点で解明する。ジレンマより腹落ちしました。
0投稿日: 2020.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ営業マンにも是非読んでいただきたい一冊。 人が商品を買うメカニズムが解明されています。 購入は手段であり、なぜ買ったのかを理解する必要があります。ものを売る時、「〇〇%が購入」という事実ではなく、その人が購入した目的を伝えることが大切です。
0投稿日: 2020.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログどんなジョブを片付けたくて、何を雇用するのか。そして何を解雇するのか。この考え方で自身が取り組むべき課題を言い当てることができると良いのだが、、 自身を例に考えると、ある製品を提供しようとするとき、その技術仕様・スペックでお勧めするのではなく。相手のジョブをどう片付けるかという視点をもって対面すべき、ということなのだろう。ただ、そのときの姿勢を具体的に想像するまでには至らなかった。
2投稿日: 2020.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログイノベーションのために顧客理解に新しい視点をくれる。 第1章の3分で読み終わるミルクシェイクのエピソードにグッとこなければ、そのあと350ページを読んでも何も響かないので読む必要なし。でもたぶんグッとくるはず
0投稿日: 2020.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログざっくり言えば「解決すべき課題を社会的・感情的側面からとらえ、一番大事な要素を見ぬき、それを解決する体験を作れ」ってことになるのかな。機能性・利便性に偏ってることを自覚させてくれる良書だった。
5投稿日: 2019.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログものの見方としては面白い。 しかし経営学の本にありがちな、後付感が否めない。本人はイノベーション専門のコンサルタントとして活動しているらしいが、それはジョブ理論の正しさを証明しない。新規性は何か、ジョブとニーズは何が違うのか、イノベーションをすべて説明するのか、一部なのか。一部な2割か8割か。お世辞にも科学的な作法に則った理論とは言えない。 批判的な考察が全くかけている。 ポッと成功してしまったビジネスマンの書いた本よりは断然いいのは間違いない。
0投稿日: 2019.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ我々は顧客が片付けるべきジョブを解決し提案していく必要がある。そういう意味でビジネスの本質を突いていると思う。大事なのはプログレス、彼らの抱えるジョブを片付ける解決策を、ジョブ=顧客の欲しがるもの、機能的・社会的・感情的側面の理解、適切な体験を構築できれば大きな価値生まれる。顧客が言わないことを聞き取る、これらすべてはマーケティングに通じる。意識していきたい。
0投稿日: 2019.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ売りたいものから考えるのではなく、お客さんの片づけたいジョブをどうやって助けて解決するか?という視点で、仕事を考えよう。
0投稿日: 2019.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ商品開発におけるジョブ理論とは、と言う観点で読んでみた。 プロダクトとは、ジョブ(プロセス)を解決するために雇う対象であり、プロダクトそのものに価値があるわけではない。多くの企業でプロダクトそのものの価値にフォーカスすることで、事業を見誤っている。成功している企業として、メイヨークリニックやインスティチュートのクイッケンなど挙げられていたのが興味深かった。 220520 再読 改めてジョブ理論に基づく、商品価値の考え方にハッとさせられた。
0投稿日: 2019.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ記述は冗長だったが顧客の背景含めたジョブに注力することが重要なことはスッと頭に入ってきた。うまくいっていたスタートアップが組織が大きくなるとデータに囚われてうまくいかなくなることもうまく説明されていて納得感が得られた。
0投稿日: 2019.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログイノベーションのジレンマと同様、なかなか骨の折れる本だったけどこの本の“ジョブ”は一貫して「顧客のジョブ(片付けたい用事)を理解し、集中することが、運に頼らずにイノベーションを起こす方法である」というメッセージを読者に伝えること。 まずはジョブを明らかにすること、そしてジョブを中心に組織を編成しプロセスを統一していくこと、どちらもいったん出来上がった組織の中でやっていくのは難しい。けどそれが出来ている組織は強い。 ジョブを見つける、という所は特にマーケティングの本質でもあるなと思った。「ジョブ視点」を日頃から鍛えていきたいな。
0投稿日: 2019.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ製品やサービスを売るのではなく、顧客が片付けたいジョブを解決する、という視点。メーカーで働く自分にとって、確かに競合との性能差を意識したり、新機能をどんどん開発したり、無駄な仕事を無くして効率化を図ったりする毎日だけど、それは何のためにやっているの?というスタート地点に立ち返る為に必要な視点だと思った。まずは顧客のジョブを知ろうとするところに重点を置かなければいけないけど、組織全体でそれを習慣づけるって難しい。むしろそんな事考えた事無い人ばかり。社会情勢、顧客の状況、顧客の立場を把握して、ジョブに気付けるように。そしてその姿勢、マインドを組織で習慣化するためにはどんな仕組みを作れば良いか。良いヒントになった本でした。
0投稿日: 2019.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ客はそれを雇うからジョブとは目の付け所がすごすぎるけど こういう本の常として後付の説明の感が拭えない 本の中にも記述がありますが、これを理論と呼べるのか 考え方ではないのかn
0投稿日: 2019.07.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「イノベーションのジレンマ」以来かな。今回はジョブ理論。前に読んだ「アフターデジタル」にミルクシェイクの話が出ていたので、改めて読んでみたくなりました。一言でいうと、こういうストーリーを含めて我々は「ニーズ」と呼んでいたような気がするし、必ずしもでもグラフィックな要因で層別するなんてことは私が学生だった30年以上の昔から言われていたことなのだけど、商品を買う側には色々な理由があってその商品を買うのであって、必ずしも品質とかじゃないよね、ということを改めて色々な事例で説明してくれている感じ。iPodだって、いい音を聴きたかったら今でもSONYのNW-WMの方が良いと思っているけど、売れるのはiPod。今はそれでも無いと思うけど、ジョブをストーリーとして説明するのは賛成。そして、建前なんかじゃなくて、本当の意味での購買動機を掘り下げて考えましょうというのは絶対に必要だと思う。でも、人は必ず本当のことを言う訳ではないから、アフターデジタルにつながっていくんだろうなとそんなことも感じました。
1投稿日: 2019.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ購買行動のメカニズム、ユーザーは機能でなく解決したいジョブ(課題)の為に商品を雇用するという考え方。有名なミルクシェーキ以外も、実例が多く読みやすい。付加価値をつけて売るかという目線では、エスキモーに氷とか100円のコーラを1000円に近いかと思う。
0投稿日: 2019.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
レビューを拝見すると賛否両論あるみたいですが、ビジネス初心者には学びのある本だと思いました。 成功体験を語る本や成功事例を分析するだけの研修などより、この本を読む方が体系立てて学べると思います。特にビジネス初心者向けかもしれません。 イケアやミルクシェイクの例はもはや有名すぎて新鮮味はなかったですが、そのほかの知らない事例を知れたのは面白かったです。 昨今話題になっているデザイン思考にとても似ています。(本文にも関連性の記載はありました) 顧客が進歩したいジョブを見つけるBtoCの例が多いですが、例えばCO2削減をなくすといった社会貢献的なジョブにどう対応するかが個人的にはわからなかったです。 どうやってジョブを見つけるかの方法論はないので、日頃から事実を観察したり推測したりすることが大事なのかなと思いました。ジョブを見つけるには訓練が必要そうです。 章末にあるリーダーへの質問はとても参考になるので、時折見返したいと思います。
0投稿日: 2019.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ2年ほど前に売れた本だが、カスタマーサクセスという概念が一般化した今こそ示唆的。 解決すべきはニーズではなく、ジョブ。 細かい要望(ニーズ)を聞きすぎるのではなく、顧客はなぜこのプロダクトを雇うのか?(ジョブ)を考え抜き、明確にすることこそが、カスタマーサクセスへの第一歩であり、指針となる。 「片づけるべきジョブは明確か?」 これが明確であるなら、組織は自律的に判断し、適切な行動を意欲的に取れる。強いCSチームとはそういう組織だと思う。
0投稿日: 2019.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ勧められて手に取りました。原題は「ツキを超える」と訳せばよいのでしょうか、市場での成功を「運」に任せるのではなく、うまくいく確度をどうやってあげるかを解くことが本書です。邦題はキャッチに「ジョブ理論」と打ち上げていますが、ユーザインサイトの重要性やレビットのドリルの穴の警句と同様な知見を、わかりやすく、多くの例証で示したものです。教科書的な本であり、必見であることは間違いなさそうです。
0投稿日: 2019.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客の「片付けるべきジョブ(課題や作業)」に注目する 製品に求められるものは機能の豊富さではなく、顧客のジョブをどれだけ解決できるかどうか 工具メーカーは「ドリル」を売っているつもりだが、顧客が欲しいのは「穴」 顧客は求める結果を得られるより良い手段を求めている 企業は他社と競争するよりも未解決のジョブを解決することに取り組むべき 解決できれば多くの顧客が満足し、未開拓の市場が手に入る
0投稿日: 2019.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ新しいなるほどがあんまりなかった。 でも、丁寧にまとめてくれてるのは嬉しいので、章のまとめにある、リーダーへの質問、は定期的に読んで、自分の考えが偏らないようにしよう。 顧客をセグメンテーションするのではなく、なぜ顧客はプロダクト/サービスを雇用するのかを考えよう。 片付けるべきジョブ。 組織作りの話も書かれているのがグッド!
0投稿日: 2019.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
イノベーションのジレンマ、解、最終解でも著名なクリステンセン氏の本書は イノベーションをどうやって起こすか、消費者の行動に注目してジョブを解決するべきだと説いた本 ジョブという名ではあるが、顧客が行動するモチベーションのようなものと理解した マーケティングに近いが、実際のイノベーションを考えると、確かにジョブ理論は納得できるし 顧客行動を追い、なぜこの顧客がこの商品を選んだかを注意深く観察したり 背景環境を考えることがイノベーションにつながるかもしれない 絶対再読する予定の一冊
0投稿日: 2019.05.06
