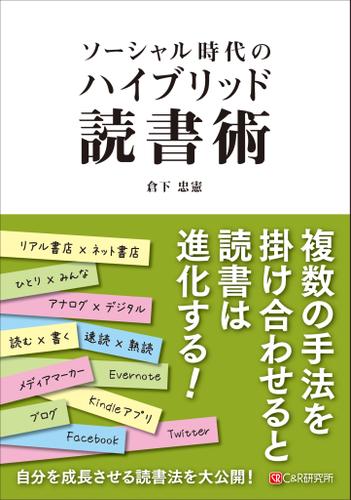
総合評価
(19件)| 2 | ||
| 2 | ||
| 12 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かに、多くの読者が指摘するように、メディアマーカーがサービスを終了している点など、2013年4月初版発行だけあって、ある種古い面もある。しかし、この著書には普遍的で時代横断的な、読書に関する真理も含まれている。 例えば、P.37〜39に記載されたT型人間、逆T型人間、そしてI型人間という表現は、大変興味深い示唆であるし、p.97の速読・熟読の功罪に関する論考も、ひとつの定理といっても過言では無いだろう。 これまで、さまざまなタイプの読書術に関する本を読んできたが、ここまでニュートラルでフェアな著書は初めてかもしれない。 時代を超えて、残って欲しい良書であると、心底感じた次第である。
0投稿日: 2022.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
Evernoteの使い方を学びたく読んでみたが、出版から時間が経っていためあまり参考にならなかったのが残念。 しかし、自軸をつくるや、ハイブリッドな読書の方法は参考になった。
0投稿日: 2020.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログいわゆるオススメ本の紹介はひとつもなく、読書術に特化した内容。 基本的に書かれている内容で真新しいものは少ないがタイトルとおりハイブリッドという、物理的な環境である本や書店と、ITを駆使したクラウド、ソーシャルメディアを利用した本への接し方について、わかりやすく書かれている。 すべて従うと読書することに疲れてしまうが、思考整理のための読書をするには書かれている内容を試すのことは有効だと思う
0投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログメディアマーカーの献本でいただいた本。 久しぶりに読書術の本を読んだが、著者も文中で語っているように、目新しい読書術の本ではなく、これまでの読書法をまとめたものと言った方がよい。だからこそのハイブリッド(組み合わせ)。 読書術の本だが、著者の問題意識は、読書ではなく、「自分の頭を使うこと」にある。 FBの「いいね」で済ませてしまい、頭に浮かんだモヤモヤを言葉にしない、という記述や、本を見ながら話していたという新人占い師の話からもそう思える。 気になる読書ノートについては、読了直後ではなく頭が冷めてから、という指摘は、そういう考えもあるのか、と思った。これまでは、忘れないうちに・・・と思っていたので。 また、「情報の関係性を脳内に取り込む必要のない」本や、「レバレッジメモを作成するだけの本」という表現は目から鱗。言われてみれば確かにそうなのだが、自分のなかでは、レバレッジメモ=読書メモだったので、メモを作る本というのは上等な本、というイメージだった。 読書感想を引き出す7つの質問というのは使える。私もブログで書評的なものを書くときや、読書メモを書くときには、同様の考え方で、フォーマット化をしていた。最近は使ってないが。 読書×EVERNOTEに興味がある方にオススメです。 [more] (目次) 1 自軸を作る読書術 (これからの読書スタイル「ハイブリッド読書術」 読書の技術、その前に ほか) 2 リアルとウェブで本と出会う (シンプルな接書戦略 接書戦略の2つの要素 ほか) 3 速・精・熟を組み合わせるハイブリッド読書術 (本の読み方を考える 読書の準備を整える ほか) 4 Evernoteにクラウド読書ノートを作る (読了後に何をするのか 読書ノートに関する注意点 ほか) 5 新しい読書の可能性 (新しい読書とは? ソーシャルリーディングとは ほか)
0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ購入の経緯:Amazonのおすすめで、タイトルみてピンと 対象読者:ソーシャルや読書の初心者向け 筆者の考え:読書の意義を再確認し、実行可能なものを、いろいろ組み合わせて。 その考えへの自分の感想・印象:スタンスは同感。紹介されているツールやスタンスはだいたい既存の読書術に載っているもの(のうち特に基本的なもの)が多いが、ソーシャルメディアやデジタル読書と無理なく組み合わせて新しいスタイルを提案しているところは面白い。最後の「Chapter5 新しい読書の可能性」が最も面白かった(逆に言うと他はそんなに目新しくなかった)。 印象に残ったフレーズ・センテンス:特になし 類書との違い:デジタルやソーシャルを礼賛し過ぎということがなく、ツールに振り回されず、自然に組み合わせているところ。また、著者の売りであるEvernoteを無理なく紹介している読書システムの中に据えているところは他の本では読めないと思う。 関連する情報:書中で紹介されているウェブサービスなどの一部は、この本をみて新たに登録した。「電子書籍サーチ」「ブクペ」「新刊.net」など、Mediamakerは前から使っていたが、Evernoteとの連携方法は新しく、早速導入した。
0投稿日: 2018.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログウェブで本の情報を探すサービスとか知らなんだ: Meet Up 大阪 @ blog http://meetuposaka.seesaa.net/article/442419314.html
0投稿日: 2016.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと、途中までしか読めていなかったので、えいや!と読み終えようと一気に読んでみた。 いわゆる読書術に関する本であるが、それは誰でもできるようにかつ普遍的な考え方も説明した上で手法が示されていて、昨今はやりの読書術とは一線を画すものかと感じた。 本との向き合いかた、そして読書ノートの作り方やそれを実際にEvernoteを使ってのやり方が丁寧にかかれている。 そして、これからのソーシャルリーディングについても考え方、やり方がが示されている。 読書術についてはこの本をハブとして、参考文献を読み、熟考して自分のスタイルをつくっていけばよいのでは、の思いました。
0投稿日: 2015.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログevernoteを使う読書ノートの作製保存方法が出ていたので読んでみた evernoteの読書ノートをハブとしてリンクをもちいる方法が紹介されている 一番重要な点は書いてある中身だが、記録を書くときの注意点も紹介されており役立ちそう 手書きとクラウドのハイブリッド ひとり読みとsnsのハイブリッド
0投稿日: 2015.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ食事→消化、排泄→食事 思考には情報が必要 情報→理解、要らないものは捨てる→新しい情報の取り込み 本書で扱う読書術の対象①本の情報を入手すること②実際に本を読む行為③読了後の行動 経済学 コモディティ化 物識りの価値は急速に低下 テクノロジーは常に人を楽な方向に導こうとする。→どんどん頭を働かせなくなる。 フェイスブックへコメント→考えがもやもや→「いいね!」押すだけ わざわざ読書をする意義 柔らかいものしか食べない→あごの筋肉の退化 マッキンゼー T型人間 縦に深い知識 横に広い教養 接書戦略 バイキング(歩き回る食べ放題)形式 ネット時代の書店→本と出合える場所を提供 ネットの蔵書管理サイト ブクログ メディアマーカー 読書メーター Amazonでほしい物リストを管理→実際の書店で提示してもよい。 話題の本の要約 bukupe.com☆休止中 フライヤー(有料・要約でニュアンスを掴むのは限界アリ) 古典作品を無料で入手 青空文庫 本選び→失敗の経験が選択力を上げる。 読書の準備 目的は?趣味、学習、研究、読んだだけで終わりになるか? 本へ書き込み→主体的に本を読んでいる感覚→読書に参加する。 短い時間を重ねる→5分読み。 ネットを減らす。 サプリメント本→「2時間でわかる○○」→わかった気になる→数冊読んで自分でサプリメント本がつくれれば理想 休息を意識 英単語→睡眠を挟む 論理性→一気に行う。 著者と対話する書き込み型読書→重要な部分は自分の言葉で言い換えてみる。英語に訳してみる。 考えるという作業が得意でない人→考え方の方法論が不足している。 読書ノート 最低でも1日程度時間をおいてから取りかかる。 本田直行 レバレッジメモ→☆書類がたまり見返せなかった→ブクログへ記録 人生のパートナー本と出会うために→100冊読んで1冊ほどの確率 エバノ ノートリンク 読書ハブノート ブログを書く。→文章化、他人にわかるように書くこと→自分の理解が深まる。→自分の意見にも注目する。 書評記事、読書感想文の書き方 ①購入の経緯②本の対象者③著者の考えは④その考えに対する印象は⑤印象に残ったフレーズ⑥類書との違いは⑦関連する情報はあるか?メディア、映画… 電子書籍 新しい本の形→新しい物事=不確実な要素が付きまとう☆今から将来を予想しておくこと。(ネット、携帯、音楽配信 予想できたか?)
1投稿日: 2015.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書時間 2時間20分(読書日数 7日) プロブロガーでもある筆者が、この情報社会の中で生きて行く上で「読書の重要性」と「今の時代にあった読書方法」を説いている本 〈所感〉 複数の手法(アナログとデジタル)を掛け合わせる方法というのは、とても良いものであると実感はできた。「レバレッジ・リーディング」(本田直之 著)の中でもこういったことが紹介されていたのを知っていたので、実践(完全にとは言えないまでも)もしていた。 ただ、私にとっては荷が重すぎるというか、どうしても「苦手意識」が払拭できないので疲れてしまったというのがある。 ここをどうやって脱却するかが私の最大の課題でもあるが「自軸は「I(大文字のアイ)を広げる」というのは凄く印象に残ったので、ここを意識した本選びをしていきたいと思った。 また「読書は熟考するためである」という考え方も、大事だと思った。速読だけだったらネットサーフィンするのと変わらない。考える力を身につけるためにも、深く読み込む重要性を知った。
0投稿日: 2013.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書術については知っていることも多く、ハイブリッドのよさを感じなかった。しかし、読書記録の必要性については考えさせられた。
0投稿日: 2013.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の言う「ハイブリッド読書術」とはリアル書店とネット書店、アナログとデジタルなど違うものを組み合わせて行う読書術です。 最近、読書術の本をよく読むのですが、読書後のアウトプットが大切というのが共通しています。この本ではより具体的なアウトプット方法、中でもEvernoteの利用法について詳しく書かれています。 ただ読むだけじゃダメなんだな〜と思わされる1冊です。
0投稿日: 2013.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書に関する本は定期的に読みたくなります。 本の探し方、買い方、読み方、記録の仕方などクラウドなどによってかなり便利になってきています。その一方、アナログに頼るべき点も多々あるのも事実です。 そういう意味では、両者のいい面を組み合わせて目的を達成しようという本書のスタンスは、個人的に思っていることと方向は似ています。 個人的には、読書後の管理・活用について工夫したいと思っていたので、ヒントは得られました。でも、ここまでやれるかと言ったら自信はありません。自分なりのスタイルを見つけていきたいところです。 「ハイブリット」=性質の異なる2つ(あるいはそれ以上)のものを組み合わせて、1つの目的を成すもの ・コモディティ化を避けるために、皆と別ルートを辿ることが必要 ・情報を扱う力を身につけるために、読書は大きな役割→「自軸」を育てる 良い書店の特徴 ・書店員のおすすめがある ・特集コーナーがある ・面陳列(棚で表紙を見せて陳列すること)が多用されている ・関連書籍が並べられている ・他にはない品揃えがある 読書中の姿勢:「信頼せよ、だが検証せよ」のスタンス もともと1つの本に没頭するのは不自然な行為 深く考える力を持っている人は、大抵読書家。知識が豊富なだけでなく、自己と対話する集中力を身につけている 書評記事を書くための7つの質問 1.購入の経緯は? 2.本の対称読者は? 3.著者の考えはどういうものか? 4.その考えにどのような印象を持ったか? 5.印象に残ったフレーズやセンテンスは何か? 6.類書との違いはどこか? 7.関連する情報は何かあるか? フランシス・ベーコン 「読書は、論争のためではなく、そのまま信じ込むためでもなく、講演の話題探しもない。それは、熟考のためのものだ。」 <この本から得られた気づきとアクション> ・読書後の記録をどう残していくかが課題ではあった。ブクログの結果を簡単にエバーノートと連動できるといいのだが。 ・どのようなことにもアナログとデジタルの良さはある。それぞれの長所を活かし、融合させていくという姿勢は常に持つべき。 ・1冊の本の記録を残すのい、著者ほどの精緻に行うことまでは考えていないが、今のままでもやや不満でもある。効果的な読書のスタイルを追及したい。 ・T字型人材、逆T字型人材、π方人材など、いろいろ聞いたが、この「自軸」という考えは面白い。今後意識したい。 <目次> 1 自軸を作る読書術 2 リアルとウェブで本と出会う 3 速・精・熟を組み合わせるハイブリッド読書術 4 Evernoteにクラウド読書ノートを作る 5 新しい読書の可能性
0投稿日: 2013.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログAmazonとかエバーノートとかを駆使して効率よく読書をしようという提案。最近よくある読書本、という感じ。自分なりの読書法を持っている人には、あまり響かない内容かも?
0投稿日: 2013.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書における、デジタルとアナログの融合について述べたもの、という感じがほとんどしなかった。というのは、自分が倉下氏の著作を複数読んでいたり、EVERNOTEの扱いが日常化してきているからなのかもしれない。 EVERNOTEを使った読書方法の一例を提示していただいたという意味では、「復習」あるいは「応用」のための一冊といった位置付けになろうか。
0投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ20130502 読書術の本を何冊も読んでいるせいか、目新しいことはなかった。 SNSの部分は参考になった。 一つの本に一つ以上の発見があれば十分である。(受け売り)
0投稿日: 2013.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「読書」に対して大きな価値を見出している方、あるいは逆に大した価値があるとは思わない方。 「読書」に対する価値観は人それぞれです。 本書では、インターネット時代における「読書」の意味合いを論じるとともに、この体験をただ読むだけ以上の存在へと変える様々な手法の紹介、そしてそれらの根底にある考え方を紹介しています。 著者曰く、現在では知識を持っているだけでなく、それを独自に加工し、新たな情報を作り出す力が大切であり、「読書」を通してその力が身につくとの事。 本書はこの情報創出力を身につける読書の仕方を紹介しており、本の選び方や速読と熟読の比較、読書へのモチベーションの抱き方と言った初心者向けの内容等、読書習慣の無い方でも参考になるものとなっています。 しかし、完全に初心者向けの本なのかと言えばそうではなく、本への書き込みのすすめ、読後に行う本の内容まとめ方などが解説されており、特に本への書き込みの重要性を訴えています。 " #読んでいて途中、本との出会いに図書館の利用が紹介されていないのはなぜだろうと疑問を抱いたのですが、本へ書き込みをするというのであれば、確かに図書館の蔵書は利用できません。" 紹介されているテクニックとしては、重要箇所に線を引く、読後にA4用紙1枚へ内容まとめ(その際、情報のふるい落としを行う)、evernoteを活用した「内容まとめ」の整理等があり、それぞれに参考になる箇所があるかと思います。 これをそのままの形で活用するのもいいでしょうが、本書の肝はテクニックの根幹をなす「読書に対する考え方」ですので、それを把握できれば後は自分で応用が効くかと思います。 "#読書習慣の無い方はまずは本書を参考に自分にあった本を選ぶことから始め、ある程度読書を嗜む方は参考になる点をピックアップして取り入れるのも良いでしょう。" 尚、文体は(砕けている訳ではありませんが)決して小難しいものではなく、また、文字のサイズが若干大きめかつ行間も多めにとっていますので、普段読書をしない方でも最後まで読みきれるのではないかと思います。 読書の習慣を身につけたい方や、読書からこれまで以上に多くを得たいという方は一度目を通してみては如何でしょうか。
0投稿日: 2013.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の目的、リアル書店とウェブ書店の付き合い方、目的別の本の読み方、evernoteやtwitterなどを利用した読書記録の方法、ソーシャルリーディングの可能性など、興味深い論点であった。ベストセラーは耳学問で済ませた方が良いとか、本を読んだ後のアウトプットの大切さなどの主張はとても賛同する。
0投稿日: 2013.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書、読書法についての一般的な考え方、アプリやWEBサービスの使い方が網羅的に取り上げられています。
0投稿日: 2013.04.05
