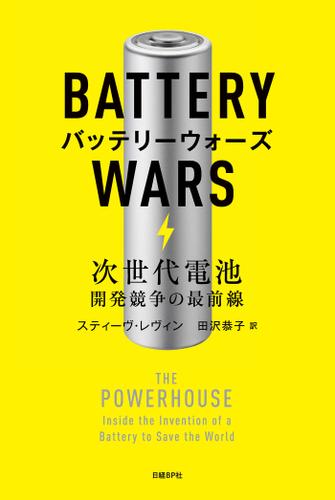
総合評価
(9件)| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログシカゴ近郊のアルゴンヌ国立研究所のバッテリー・ガイたち。電池のスタートアップ企業園ビアの歩み。モバイル機器、電気自動車とともに重要度が増す電池開発競争。 進んでいる日本の遅れている米国とか、外国人研究者家族が日本で暮らす困難とか、さりげに出てくる日本の描写が、新鮮でした。
0投稿日: 2018.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログようやく読了。物語の店舗は速く、登場人物もたくさん出てくるので、関係性の把握が難しい。しかし、確かなことはリチウムイオンバッテリーをスマホやPC、ドローンなど身近な電子機器に浸透している。しかし、ひしひしと感じたのは、安全に、安定した高出力の電池はまだまだ開発途上であるということ。一般的には日の目を見ないバッテリーだが、科学者たちの飽くなき研究の積み重ねでここまでの電池ができている、ただただ「すげーなー」の一言だ。iPhoneのバッテリー消耗はやーよなんて言っている自分を恥ずかしく思う。
0投稿日: 2018.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ超絶読みにくい。電池産業と電気自動車に興味があればお読みください。 しかし米国の電池産業では、日本は技術泥棒で韓国はパートナー扱いなのね。
0投稿日: 2017.02.23電池のイノベーションには期待しているが
アメリカの電池研究のハブとなったアルゴンヌ研究所とベンチャー起業エンビアそしてそこで働くバッテリーガイたちが目指すのは日本や韓国企業に差をつけられている電池のイノベーションを起こし電気自動車をきっかけに巨大な電池産業を生み出すことだ。この本では技術的な内容も語られるがむしろテーマはもっとドロドロした人間関係やバッテリーガイたちのエゴむき出しの姿だ。 1991年ソニーがリチウム電池を発表し現在に続くモバイル機器の誕生のきっかけが生まれた。この電池の開発にはMITのジョン・グッドイナフが大きな役割を果たしていた。グッドイナフはそのころアイデアが生まれたばかりのリチウム電池の性能をもっと上げられると考えた。ここで採用した酸化物の正極と炭素の負極という組み合わせはその後のリチウム電池の基礎を築いた。グッドイナフは最初のリチウムイオン電池で中心的な役割を果たしたにも関わらず、特許料を一切受け取っていない。所属したオックスフォードが正極材の特許取得を拒否したためだ。1980年代電池は儲からずその権利を買い取り改良を重ねた日本企業がリードしていく。 リチウムイオン電池の概念はそれほど難しいものではない。放電する際にリチウムが正極材から負極材に移動する。移動速度がパワーで移動する総量が電池の容量だ。問題は金属酸化物の正極にどれだけリチウムを詰め込めるのかとそれをどれだけ引き抜けるのか。正極材のほとんどがリチウムだと引き抜いた際に正極材がすかすかになり崩壊してしまう。つまり正極材は繰り返しの充放電で物理的な構造を保ち続けなければいくら初期性能が良くても使い物にならない。過放電でバッテリーが死ぬのは正極材の構造が変わりもはやリチウムを取り込めなくなるからだろう。 南アフリカ出身のサッカリーは独自のアイデアで酸化鉄の電極を開発した。グッドイナフの計算では構造中にリチウムが入る隙間はなかったが電圧をかけてリチウムを押し込むと構造が変わり有望な材料に生まれ変わった。サッカリーはさらに有望な材料系としてニッケル、マンガン、コバルト系のNMCを正極材として開発した。基本的にはこれが現在のリチウムイオン電池の基礎になっている。 グッドイナフの研究所に来た日本からの研究者が同僚の発見を持ち帰りNTTが特許を出願したとこの本では描かれている。日本は知財権ではやられっぱなしのイメージだが、この本では抜け目なく材料技術の改良に労力を惜しまない強力なライバル扱いだ。権利化はその後も泥沼の様相で、MIT教授の蒋がグッドイナフの材料に手を加え特許を取得しA123というベンチャーを設立した。ここから流れた技術が中国のBYDに流れたとの噂を著者は示唆している。 サッカリーと並ぶスターとなったのがモロッコ出身のハリール・アミーンだ。京都大のポスドクをへてアルゴンヌに加わったアミーンは研究に情熱を燃やすサッカリーとは異なり市場に製品を送り出すことに関心を持ち自分の権利を徹底的に主張する攻撃的な人物だった。アミーンは見過ごされていた電解液に目をつけ新たな分子を導入することで発火の危険が減ることを突き止めた。アミーンは後に日本式のやり方を取り入れた。どこかで手に入れたアイデアに手を加え部下の研究員をチームとしてまとめ片っ端から研究させる。アミーンチームは論文数、特許数で実績を積み10年間で120件の発明を生み出した。。このやり方は一部の研究者から批判を読んだが日本などではフェアであると認められ、結果を出せば賞賛される。「日本、中国、韓国は、他者のアイデアを平気で足場としながら経済的優位を保ち、いずれ収益性の高い産業が生まれると確信して何年間も金を注ぎ込み続けた。アミーンはただ日本式のやり方をまねしているだけだった。」やけに批判的だが産業スパイとは次元が違う普通の企業活動だと思う。 2012年ボルトの販売台数は7671台、中国でも1万台に届かず、日産リーフも同様だった。一方でトヨタのハイブリッド車は累計400万台、勝負はついている。アメリカには長期的な計画に予算を組む企業はなく電池関連の会議は静まりかえっていた。30年後EVがまだメジャーになれないもう一つの理由は車体価格の差だ。電気が安くても初期費用の差が埋まらない。 しかしテスラの登場から雰囲気ががらっと変わる。テスラは最先端の技術は選ばず枯れた技術を工学的に磨き上げる方法を選んだ。そしてわずか4ページの最終章は楽観的な見通しに終始する。「テスラは平均的な乗用車よりやや割高だがもはやニッチな存在ではない。EVを100万台走らせるといったオバマの目標はまもなく達成されるだろう。」「アメリカはきっと勝てる。」どろどろのバッテリーガイの描写はよく書けているが、電池の未来はまだまだ先にありそうだ。
3投稿日: 2016.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ160402 中央図書館 どうも、何が面白いのかよくわからない。優秀な電池というのは素晴らしいものだが、電気自動車を爆発的に普及させるだけのブレークスルーは、まだ得られていないのは確かだ。
0投稿日: 2016.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカにおけるバッテリー開発の競争がかなり激しいということは、何となく分かったが、本に出てくる人達は、結局のところ開発が上手くいかなかったようだ。何とも後味の冴えない話しだ!
0投稿日: 2016.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本経済新聞社 小サイズに変更 中サイズに変更 大サイズに変更 印刷 この一冊バッテリーウォーズ スティーヴ・レヴィン著 米蓄電池ビジネスの過剰な熱気 2016/1/17付日本経済新聞 朝刊 2008年のリーマン・ショックで世界経済がメルトダウンしたとき、人類は次世代電池に夢をみた。電池の進歩で、20年に電気自動車とハイブリッド車の市場規模は780億ドル(約10兆円)になると予言された。太陽光発電をそこに貯蔵できれば、売り上げはさらに数百億ドル増える。石油が不要になり、都市の大気汚染が消え、世界が地政学的に揺らぐとも伝えられた。その後、どうなったかに答えるのが本書である。 蓄電池の原理は至って単純。放電のときに正電荷を持つリチウム原子が、負極から正極へと移動する。だから、リチウム原子を反対に正極から負極へ移動させれば蓄電ができる。基本的に電池の性能は、電極に使う素材、リチウム原子が通る電解質の種類の組み合わせで決まる。開発競争では、容量を増やし、安全性・安定性を高め、量産コストを下げることを目指した。 米アルゴンヌ国立研究所は、ニッケル・マンガン・コバルトを組み合わせた複合素材を突破口に、次世代電池に挑む。その技術に着目した新興企業エンビアは、同研究所とライセンス契約を結び、商業化に動き出した。エンビアは、電池の経済性を1年半で半分以下のコストにする野心的な目標を掲げる。多数のベンチャーがエンビアを買収して将来、高値でさやを抜こうと活動した。オバマ政権が15年までに米国内で100万台の電気自動車を走らせると宣言したことも、熱気を後押しした。 ところが、技術進歩は早々に壁に突き当たる。充電を繰り返すと、電圧が下がる放電電圧の劣化が起こったのだ。課題は時間が経過しても十分に解決されなかった。この種の停滞は例外ではない。電気自動車には原油下落で燃費の節約分だけでは高価な車体価格を回収できないというハードルも立ちはだかった。多くのベンチャー投資が、研究開発の次の段階に移行できずに資金不足に陥って頓挫する。 物語はアルゴンヌ研究所が曲折を経て、米エネルギー省のコンペで勝利し、共同開発のパートナーになって一歩を踏み出すところで終わる。まだ次世代電池は発展途上だとしても、開発への期待は過剰だった。リーマン・ショック直後の電池開発の熱狂には、従業員、サプライヤー、株主、政府、市民に対し、前向きなモチベーションを持たせる建前があったという。翻って、わが国でも経済停滞を抜け出す便法のようにイノベーションが多用されているからこそ、私たちは反面教師としてこの事例に学ぶ意義がある。 原題=THE POWERHOUSE (田沢恭子訳、日経BP社・2000円) ▼著者は米国のビジネスニュースサイト「QUARTZ」のワシントン特派員。新アメリカ財団フェロー。ジョージタウン大准教授。 《評》第一生命経済研究所首席エコノミスト 熊野 英生 このページを閉じる NIKKEI Copyright © 2016 Nikkei Inc. All rights reserved. 本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。
0投稿日: 2016.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカのLiB開発の話。細かいところは分からないところも多く、カタカナを覚えられないこともあり、スムーズには読めなかったが、自国・他国へのステレオタイプの差など面白かった。日本を愛する普通の日本人としては、日本は知財を守る側侵害される側という認識だが、まったくそんなこともなく。一方のアメリカのアメリカ観も日本からのものとまったく異なる。 本題についてはこれからにもよるけど、特に日本で報じられてないように感じたのはどうなんだ…
0投稿日: 2015.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ次世代エネルギーを巡る熱い戦い。 化石燃料からの脱却を視野にいれ、電気自動車のシェア争いなども絡む。 アメリカの視点で見ると日本は研究の商業化が上手いらしい。 国立研究所は基礎研究ばかり重んじている。 新しい発見ばかりありがたがって、過去の改良は軽蔑して見る。 研究者は概して起業精神がなく、失敗を恐れる。 日本の報道などのイメージとは異なる。 自国に対しては誰もが厳しいのだろうか。 結局本書では電池の未来は未知数として終わるが、かなりエキサイティングだった。 ベンチャーはなかなかハートの強さが求められるようだ。 かなり楽しめた。 電池のニュースに注目したい。
0投稿日: 2015.12.03
