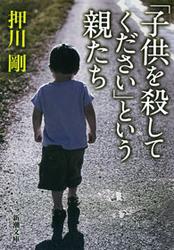
総合評価
(84件)| 11 | ||
| 21 | ||
| 30 | ||
| 7 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ思春期の子を持つ母として、注意欠陥多動の子を持つ母として、身につまされるものがありました。 今は外で心に傷がついたり壁にぶち当たったり都合が悪くなればすべて母のワタシに責任転嫁してくることも多くあります。 思い返せば自分の育児に後悔ばかりですが、今からでも、後悔や反省しつつ、子どもからの批判は真摯に受け止め不完全だけど子どもにとって安心できる親になりたいと思うのであります。しかしだれしも タイトルの様な親たち予備軍にならないとも限らないし、他人事ではないなと思いました。 ここまで自分語りが過ぎましたが、、、。 ドキュメントでは、救いがなくてそれからどうなったんだろうと言うケースばかりでした。診療報酬からの3カ月ルールは、なるほだと思いました。鎮静させて一旦穏やかになってもらうって感じなのかな。退院したとて病識のない人に服薬の習慣つけさせる難しさは、家族で実感していますし。 司法と医療のグレーゾーンの難しさ。 病院から自宅退院までのワンクッションをすごせる中間施設があればよいのに。服薬習慣や生活習慣のリズムをつけるリハビリができるような、、、。精神科にも回復期リハビリがあってもいいかな、なんて。
6投稿日: 2025.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神を病んだり、引きこもりになったりしている当人がかわいそうになるくらい、その周りの家族がひどい そりゃそうなるわなーと 赤ちゃんや子どもの頃はその人の尊厳を平気でふみにじる事をしてきたんだろうなと思う 精神病院に面会に行った時に病院でできた友達を紹介されたというくだりがあって 精神的に病んでしまった人を治して現実世界に戻すことではなく 彼らにとってはそこでそう生きることも幸せ って事もあるのかもしれないなーと思った 現実に戻っても、親兄弟や親戚から疎ましく思われ、精神病院にずっと入れておきたいと思われながら一緒に過ごすくらいなら 民間業者と言うことは いわゆる引き出し屋というやつなのかな?と ブラック支援を読んでから思った こちらの方はまだまともな引き出し屋さんなのかな いずれにしても 現状を知る事ができてよかったです
0投稿日: 2025.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後の章はあまり面白そうではなかったので割愛 子育てに失敗したからなのか本人の特性によるところが大きいのかは分からないが、子を持つ親としてはこうならないよう最大限にの努力はしないといけないなと思いつつ、どうしたら本著に記録されているような最悪のケースを避けられるのか…
0投稿日: 2025.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ兄弟が非行やひきこもり、両親の不仲・別居等、さまざまな経験をして幼少期を過ごしました。家庭を持ち暮らしていますが、この先両親が死んだ後、兄弟とどう接していけばいいのかわかりません。わたし自身、子ども達をうまく愛せていない、傷つけるような言葉を吐いてしまう、感情がうまくコントロールできないこともあります。同じ過ちを繰り返さないように、自分自身と子どもと向き合っていきたいです。 ケーキの切れない非行少年たちから、押川さんの存在を知りました。とても読みやすく、話もわかりやすかったです。
1投稿日: 2024.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ本人に病識が無く、通院や服薬を拒む患者を家族や保護者に代わり医療の現場に繋げる「精神障害者移送サービス」という特殊事業を営む筆者による著作。 お恥ずかしながら、このような事業があることを今回初めて知った。私事だが、ここ数年のコロナ禍による生活環境の変化をきっかけに我が家も不安定な状況が続いている。先日は家庭内トラブルが原因で、急遽警察の方に来ていただいたりもした。派遣された生活安全課の刑事の方はとても優しく、動揺する自分に利用できそうな支援制度を丁寧に教えて下さった。とても感謝している。 本の前半部分はこれまでに著者である押川氏が遭遇した「精神障害者の移送依頼」にまつわるエピソードが語られており、後半部分は精神障害者を取り巻く医療・福祉の現場のリアルな状況と、それに対する問題提起が行われている。 現在の日本の精神医学は薬物療法に偏りがちなところがあり、自ら通院せず服薬も拒む扱いにくい患者は現場において煙たがられているという話は正直耳が痛いものがあった。(なぜならわたしの家族の場合も本人に病識がなく、心療内科から処方された薬に抵抗を示すからだ。身に覚えがありすぎる……) 押川氏によると、現状こうした扱いにくい患者の相談窓口や受け皿になっているのは警察だという。警察関係者は職務上ハイレベルな対人能力と危機管理スキルを有しているので、精神錯乱状態で暴力を振るい、自傷他害リスクのある患者に対しても適切な対応が出来るのだそうだ。これに関しては、実際に対応していただいた側の立場として納得するものがあった。しかしそれと同時に、わたし自身も著者同様に警察の現機能だけではこうしたトラブルへの受け皿としては不足していると感じる。今表沙汰となっているケースはほんの一握りで、水面下ではもっと「精神障害をもつ家族と向き合うこと」に悩み苦しんでいる人々がいると思うからだ。押川氏の活動に改めて感謝と敬意を示しつつ、今後は国や行政が主体となり、十分な支援体制が整えられることを願っている。 この本では年老いた親が精神障害を持つ子どもにどう向き合うかということが主題になっており、子どもとの暮らしに行き詰まった絶望の果てに、表題の「子どもを殺してください」という台詞を紡ぐ家族が何パターンも出てくる。それがまた、個人的に胸が痛かった。親と子どもという関係性。置かれた立場は逆だが、以前にわたしも家族から敵意と攻撃的な言葉を浴びせられた際、同じようなことを考えたことがあるからだ。不謹慎なことだが、自分に関係のないところで、ひっそりといなくなってくれたら……なんて願ったこともある。 しかし、これはただの逃避に他ならない。押川氏は終章でこうした言葉を綴っている。 「子供は対応困難な問題を繰り返すことで、親に自分の心を突きつけている。こうなるまで気づかなかった、子供の心の痛みを受け止めてほしい。問題から目を逸らしたり、子供の心を縛るのでは無く、真摯に現実を受け止め、一人の人間として尊重する気持ちを持たれるように……」 わたしも家族ときちんと向き合わねばならないし、今も、その覚悟が足りていないのかもしれない。そうした自省の念を抱いたりもする。
5投稿日: 2023.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ閉じ込めることしか対策を思いつかない。攻撃性のある知恵のある人間。家族任せにできない放置できない問題であることは明確。
0投稿日: 2023.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想を書くことがとても難しい。 本書に登場する子供、彼らを保護する人、子供の親、警察、福祉関係者はそれぞれの立場、利害をもち行動する。私は心中でそれぞれの行動に対して直感的に肯定的または否定的な意見を持つ。しかし私自身が本書で取り上げられるような問題の当事者でないということからその意見はとても無意味なものに思えてしまう。当事者でないことは私がある問題に対して何らかの感想を持つことに対する自信を奪うときがある。 一方で本書で取り上げられた問題はもっと社会で大きな議論をして、対策を講じなければいけない問題だ。私が当事者でなくても、まさにいま私が問題の渦中にいるのだという意識を持つべきだ。筆者も当事者でない我々に問題提起をするという意味で本書を書いた側面もあると思う。 私が本書を読んでどの立場を取るにせよ、この問題に対して一定の立場と見解を持つことを恐れないようにしたい。 最後に筆者に問いたい。 「当事者ではない私たちには何ができますか?」
0投稿日: 2023.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ先日の相模原殺傷事件が起こり、とても興味深く読みました。精神保健福祉法が改正され、2014年4月に施行されてから、複雑かつ対応困難なケースほど、なかなか医療につながらず、入院できても半ば強制的に早期退院を促されるようになっているらしい。二度とこのような事件が起こらないよう取り組んでほしい。また子どもを持つ親は、子どもの顔色をうかがうような事なく、子どもを大切し、本気で子どもと対峙していかなければならないと思いました。
0投稿日: 2023.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神科病院で働く前には「なんだこの本!!」と憤りに近い感想を抱いたものでしたが、勤務後は「わからなくもない」に変わりました。 ただ病院はいつも満床満杯。午前中1人退院しても午後には新たな患者が入院してきます。受け入れたくても受け入れられない現実もまた事実。保護室が空かないってのもざらだし。
1投稿日: 2022.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【崩壊した家族を救え .ᐟ.ᐟ】 ※実際にあった事件なので、事件の内容ではなく、全体の構成の読みやすさ、著者のこの事件を通して読者に訴えたい事が伝わったかどうかで評価 かなりインパクトのある題名が気になり先に漫画版を読んでいたのだが、Kindleにあったので読むことに。 なかなかハードな内容なので漫画から読むのがおすすめだが、社会問題として詳しく現状を知りたい方は本作を読むといいだろう。 内容は、精神障害者を医療に繋げる移送サービスと、自立・更生支援施設を運営している著者によるリアルな現状が記されている。 本作の前半では著者が請け負ったケースが紹介され、後半では医療や行政の現状や問題提起、子供の向き合い方に分かれている。 強制拘束を否定し、対話と説得によって患者を医療につなげるスタイルには苦労や落胆することも絶えないだろうが、時には家族より対象者に向き合い接している姿に尊敬した。 せっかく医療につなげたとしてもだいたい3ヶ月程で退院させられてしまったり、通院履歴がないと行政で対応してもらえなかったりする現状。 対象者自身が病気の自覚がなく同居する親も同時に病んでしまっているので、家庭ごと救わないといけないこと。 幼少期に問題行動はなかったか、その時子供にどう向き合っていたか思い返してみること。 『点ではなく、線で考える』こと。 精神障害はけして他人ごとではなく、誰でもなり得る。 社会全体で考え、知る必要がある問題だと一石を投じている一冊だ。 こんなひとにおすすめ .ᐟ.ᐟ ・社会派が好きなひと ・子育て中のひと ・大人 ・医療や行政関係者
1投稿日: 2022.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ#読了 精神障害者移送サービスを営む押川さん著書。2015年の精神保健福祉法改正前後に書かれた本なので、改正後の運用についてかなり懸念されていた。現時点で精神保健分野がどうなっているのか、興味深くはある。 押川さんが関わった実例を元に家庭内でも病院でも行政でも持て余されている精神障害者の現実がいくつも書かれている。あまりにも救いのない話が多くて辛くなる。 最近、罪を犯した者を医療に繋げなくてはならないという本を複数読んだ。犯罪のかげに見逃されている精神障害や知的障害が潜んでいる可能性は、周知されるべきだと思うし、されてきたのではないかとも思う。
0投稿日: 2022.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神疾患に加えてアルコール依存、薬物、家庭内暴力など別の問題があること 本人だけではなく家庭環境の影響も少なからずある可能性があるということ 精神疾患と一言でいうには難しいように感じました。
0投稿日: 2022.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ個人の尊重や平等を謳う時代で世間から取り残されている人たちの話。ノンフィクションだからこそ、本に書かれている人達の完全なる社会復帰も今の現象では難しいのもよく分かる。手を差し出し命を救っている押川さんだからこそ帰る一冊だと感じた。
0投稿日: 2022.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ幼少期から本音でぶつかり合ったこともなく、ガラス細工のような脆さで集ってきた、見せかけだけの家族が多いことを痛感させられます。(P.275)
16投稿日: 2022.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ題名に衝撃を受けて、ずっと気になっていた本。現実にあるんだろうけど、実感が湧かないくらいの家族間の問題。 でも、他人事ではなく 親の育て方、子供への関わり方によって誰にでも起こりうる事なんだと知り、本当に怖くなった。 家族のサポートで回復した人の話は、薬や病院だけでは治らない心の支えは信頼できる人なんだと改めて実感。 愛情を伝える育児を心がけていこうと、違う角度から子育てを見直させてくれる本でした。
4投稿日: 2022.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなに大変な思いをしてる家族を助けることも出来ず、家族が子に殺されてしまう、というのを見るとどうやって助けることが出来るのか、を考えないとなと思った。
0投稿日: 2021.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログAmazonを眺めていてたまたま出会った本。精神疾患をもつ人の扱いは本当に難しい。自分の周りにも精神疾患をもつ人がいるが、外面はいいんだよな。身内にはきつくあたり、周りの人も疲弊していく。読んでいて疲れたが、ページをめくる手がとまらなくなる。
1投稿日: 2021.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ親子との関係は望む望まないに関わらず、人の人格形成に大きな影響を与えるものだと思う。 この本に出てくる親子は経済的には恵まれているのだが、どこか関係性が一方的で歪な感じが否めない。 必要以上に自分の思い通りの子育てを強いる親、長年抑圧された鬱積が爆発して暴君と化してしまう子供。 どのモデルケースの親子関係の結末も、改善の兆しも希望的観測も見えることなく終わるため、どんよりとした思いだけが残り、修復不可能な現実を思い知ることになる。 崩壊した家庭を放置し続けた結果、殺人などの大きな事件につながるケースもあると著者は述べており、わずかでも解決の糸口があればと思うが、方法を誤ると更に状況は悪くなる可能性もあり、むしろそうなる可能性の方が高い。
0投稿日: 2021.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ毒親の話と思いきや、精神疾患などを抱えた親の苦悩を紹介した一冊。 知り合いの紹介で出会った。本当に現実なのか信じがたいエピソードの数々は、救われない展開で読むのが苦しい。専門家とは言い難い著者による、結局親が悪いという論調も読むのが辛かった。
0投稿日: 2021.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもの本人の病気や気質だったり、または親の虐待の結果であったり、要因は様々だと思いますが、助けられない子どもがどこに行き着くのか勘付いてしまうと、虚しくなります。 命はどうして授かるのでしょうね。
1投稿日: 2021.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
精神障害を抱えたまま長年引きこもりを続けると、症状が悪化し、やがて固定化してせん妄、薬物・アルコール依存などから抜けられなくなる。男の場合は特に暴力・威嚇によって家族をコントロール下においてしまう。家族はそれを恥として隠そうとしたり、社会も本人の意思を尊重するというのが大原則なので、問題はますます悪化する。パーソナリティ障害のような、認知も治療法も進んでいない病を医療につなげるために尽力してきた著者が、現状を豊富な実例と共に伝える。 後半には2013年の精神保健福祉法の法改正について触れている。精神病者を家族ではなく社会で広く受け入れる体制へ変更されたが、現場の態勢が脆弱なまま、家族という堤防の決壊を招いている。この現状では、いつ犯罪行動へと患者が向かうか分からない、という危機感も書かれている。対応困難な患者の背景には、必ずといっていいほど親子関係の問題も隠れているという話も示唆的だ。 自分も青年期までは依存症の患者を家族に抱えていたし、最近ではたまたま仕事で精神障害を抱えていると思われる人の対応に追われることとなった。家族の困難は理解できるし、そうした困難に真正面から立ち向かう著者の仕事は、かけがえのないものだと感じる。 障碍者のインクルージョンはひと昔前に比べればずいぶん進んでいるが、同時にそこから零れ落ちる闇もますます深くなっているのだろう。他者に対する寛容さを失った社会で、制度や法が人権保護という名の下にそうした人たちの居場所をかろうじて作っている。しかしそれも万能では、もちろんない。他者への不寛容なまなざしは、巡り巡って自分にもかえって来るはずだ。問題についてオープンに話していく土壌を作っていくことが必要だと思う。
4投稿日: 2020.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ衝撃的な事実の数々。 もはや言葉の通じない「何モノか」としか思えないような 人たち・・・・が、現実に多数いるのだという。 心の病と一言で言うのは簡単だが、彼ら・彼女らの現状を正しく言い表すには不足する。 そして、著者が言うには・・・・(もちろん皆とは言わないが)彼ら・彼女らをそういう状況に追い込んだ要因の一因は両親の育て方にもある、という。 うん、一理あると思う。 さらに・・・ここで紹介される「身勝手な親」の存在にも頭が痛む。心も痛む。 そして、もちろん、、、、上記のような「ある意味自業自得な親」ではなくても子供が“そう”なって苦しんでいる親もいるであろうという現実。 去年だったか一昨年だったか、、、、某省庁だかの元エリート官僚が我が子を刺殺した事件が記憶に新しいが、そのため、よりリアリティをもって読むことになり、うすら寒い思いがした。 ★3つ、7ポイント半。 2020.02.11.新。
4投稿日: 2020.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ少子高齢化が進む中でどうして親が子供を殺してくださいというのか。人間として色んな人に考えてほしくてこの本を選びました。 請求記号:493.7/O76
0投稿日: 2019.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の精神障害や暴力に苦しめられる親・家族の7ドキュメント事例。親たちの状況、頼りにならない専門機関や専門家、精神保健福祉法改正の影響、今後の取り組みに向けて。対話と説得で患者を医療につなげるサービス従事者として。 社会にとって重要な、事件防止には、親に対しても子に対しても、適切に介入することが必要だし、知見と、その能力をもった人を育てることも重要だと思います。
0投稿日: 2019.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ特別支援教育職員の端くれとしてハッとしたり、親として不安になったりしながら読了。 自分がこんな親になったらどうするか…いや、うちはならないか…と考えながら、本書に出てくるどの親も、自分がこんな親になるとは思わずになったんだろうと思うと苦しい。 親子とて他人。
1投稿日: 2019.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ・小説ではなく、ノンフィクション。精神疾患の子供を持つ親、兄弟の苦悩。 ・統合失調症、パーソナル障害、うつ等であっても、本人が病気であるという意識、病識がないと入院も大変であること。 ・また、入院できたとしても、3ヶ月で退院させられ、また元に戻ってしまうこと。 ・家族、第三者に危険が及ぶことが予想されながら対応が難しいこと。 ・警察は事件が起こってからでないと動けないこと。 ・グレーゾーンが広く、診断が難しいこと。 ・親も変な人が多い。自分のことしか考えていない。
0投稿日: 2019.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ押川剛『「子供を殺してください」という親たち』新潮文庫。 つまらないノンフィクションであった。読んでいて、著者が行っている事業である精神障害者移送サービスの宣伝と思われるような強かな内容が殆んどであることに辟易するのだ。他人の不幸をビジネスにしているとまでは言わないが、ある種のあざとさを感じる。続編の『子供の死を祈る親たち』と併せて購入したのは失敗か…… 近年、確かに精神障害者による事件や事故を見聞きする。こうしたことの背景にはテレビやゲーム、インターネット、アルコールといった外的な刺激が一段と過剰になっている一方で、近隣社会のみならず家庭内でもコミュニケーションの機会が激減したことがあるのではないだろうか。決して、著者が主張するような育児や教育の失敗ではないと思う。
4投稿日: 2018.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルのインパクトが凄いノンフィクション。 書店でみかけたときはてっきり育児ノイローゼ関連かと思っていたのですが、精神疾患の子をもつ親の悲痛な叫びでした。 精神疾患の子、と言っても中年以降のもう手遅れ状態の大人。家族の依頼でそういう人たちを然るべき医療機関へ受診させたり入院させたり、世話をみるのが著者の仕事であるようだった。 ドキュメントを読む限り、そりゃあ殺してくださいと思うよなぁといった感想しかでてこない。著者は「親はこうなる前にもっと本音で子供と向き合うべきだったのだ」と述べている。 子育て失敗の成れの果て。無関心や虐待のツケをこうして払わされるのだ、と思うと恐ろしかった。
3投稿日: 2018.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ発達障害やコミュニケーション症を(気付けずにも含めて)放置してしまうと、後々大変になってしまうケースがあるという事。 ここまで来てしまうと、結局、医療機関も施設も(国の法改悪もあって)何もできなくなってしまい、解決や改善に向けた道が閉ざされてしまう現実を突きつけられます。 なので、家族の不調や苦しみには早い段階でしっかり向き合う事が大事だという事がわかりました。
0投稿日: 2018.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
どうやら漫画化もされているらしいですね。 先に登録した『子供の死を祈る親たち』は、この本の続編にあたります。 この本を読んだ印象としては、著者は発達障害の概念について懐疑的であるか、または発達障害の過剰診断を疑われているのかな、と感じました。現実問題としては、引きこもりなどの問題を抱え、家族とも社会とも折り合いが付けられない人の多くは、発達障害の診断基準を満たしているのではないかと思うのですが。 精神科病院が積極的に受け入れないタイプの患者については事件化させるしかない、というのは、絶望的な話。まずは家族が、極端な話、殺される覚悟で子供に受診を促すなどしなければならないということですからね……
0投稿日: 2018.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常にきつい内容でした。身体の病気と違って心の病気、依存症、発達障害などに対する理解、知識がまず一般にない。多分家族にすらない。これは綺麗事ではすまされないし、これからもっと大きな問題になると思う。どの角度から見ても八方塞がりに思えて考えるのがしんどいです。 子供と言っても大人になってしまえば、親は歳をとるばかりで体力的にも経済的にも支えられない現実。 サポート窓口がはっきりしていなくて責任のなすり合いみたいになってしまうのが現状のようで苦しい。
1投稿日: 2018.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【読了2018/04/30】前職を思い出す。診察・面接に本人を連れてきて…とは言われるものの、それこそが家族にとっては極めて高いハードルになって、茫然となる。 精神障害者等を移送する民間企業を営む著者が語る事例では、家族からタイトル通りの言葉がもれるのも無理もないと思わせられる実状が示される。同時に、支援側の制度や態度、家族の問題への向き合いを訴えずにはいられない思いがにじみ出ているように思われる。 「みんな勝手だなぁと思ってね…」(『聲の形』)
0投稿日: 2018.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ世の中、こんな崩壊した家族もたくさんいるのかと。当事者だったら迷いなく死んでくれって思うだろうな。若い人は治療?もできそうだけど、年取ってもうまわりの迷惑や驚異にしかならず家族も近隣も怯えながら暮らすとかそうなると、もう閉じ込めるかするしかない。著者はそういった人もそうなった原因があり被害者でもあると言ってて正論なんだが、でもそこを人権人権って言うとまわりに不幸になる人量産されるしなーって。問題起こすだろうってわかってて、普通のバイトに就職させて世間に馴染ませるって話があるけど、結局同僚ともめたり喧嘩したり急に休んだり、お店に迷惑かけるんだけど、もう1度チャンスをあげよう!って続けさせたり。で、警察沙汰。雇う側からしたら迷惑しかないしな。。。あまり共感はできなかった が、こういった人は本当に必要で救われている人も事実多いわけで尊敬する。
0投稿日: 2018.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログケース例を見れば そういう人たちが入院しつづけられず シャバに出た時にどうなるのかって やっぱり不安になってしまう。 ただこの人のいうようにやっぱり仕組みが 大事だから、でも難しいよな〜。 といろいろ考えさせられた。
0投稿日: 2018.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログあまり衝撃的すぎないように、という気づかいからなのか、全体的にぼんやりした印象。 とりあえず『相当ヤバイ人が野放しになってるから気を付けて』という警告として受け止めるしかない。
0投稿日: 2018.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神を病んでいるのに自覚のない子供を抱えた親たち。 しかし、なぜそうなったのか。 そして、これからどうしたら良いのか。 現日本の抱える法整備や施設の受け入れ状態等々の問題点が書かれている。 知らないことも多々あった。 とても難しい問題。 2018.3.4
0投稿日: 2018.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは表紙がずるい。ミスリードさせようとしている。こんな幼い子供の丸まった小さな背中を見たら、「子どもを殺したいとはなんて非情だ!鬼!悪魔!」という怒りが瞬時に湧いてくるに決まっている。想像するのはネグレクトとか児童虐待とか、暴力に抑圧されている非力な存在の子どもの姿だ。 でも読み始めると内容が全く違う。成長した子どもの暴力と殺意に怯える親や兄弟の姿がそこにはあった。 不謹慎にも、殺してあげられるなら殺して差し上げたい、という気持ちすら芽生えてくる。もちろんそんな犯罪行為は許されるわけはないのだが、我が子や肉親に命を狙われるという救いがたい状況下におかれたことがない者には、彼らの切迫感は想像もできないことだろう。 命を狙われているから助けて欲しいと訴えているのに、肉親なんだから家族内で解決してよ、という論理。子どもがそんな状況になったのは親の育て方が悪かったんじゃないの、という突き放した態度。あぁ、なんとも冷たい。非行少年少女の家庭内暴力と勘違いしているんじゃないのか? 読めばわかるが全く違う。親子の絆、兄弟の絆なんてもうない。あるのは近親憎悪からくる殺意だけだ。殺意をもったストーカーが肉親だったと考えればイメージとしては近い。 精神を病んだ理由は様々だろう。確かに親の育て方に問題がある面も多少はうかがえる。失恋やいじめ、進学、就職の失敗など。しかし、そんな状況になっても、ほとんどの人は親兄弟に殺意を抱くようにはならない。たぶんほんの一部なのだ。 自分には壮絶な甘えのように見えるが、専門的にはどうなんだろう? 著者は精神科医ではないので、その辺には突っこんでいない。 逮捕や入院とという事態になっても、粗暴なのは家族の前だけで、警官や医者の前だと大人しくなる患者もいるため、その先の切迫した事態が理解できない警察や病院もある。 それにも関わらず、病院は長くて3か月の入院で追い出す。それ以上入院させていても医療点数が稼げないので儲からないからだ。設備の整った、新しくきれいな病院ほどそうすると言う。患者や家族のことなんて考えない。優先されるのは利益のみ。そんな制度になってしまっているのは行政にも責任がある。 そして家族を殺したいと思っている患者が、家族のもとに帰される。 具体的な事件名は伏せられているが、実際に何件かこのような状況になって殺人事件となった事例も紹介されている。 どうしたらいいのだろう。なんのアイデアも浮かばない。途方に暮れるばかりだ。 続編も刊行されているので読もうと思う。
1投稿日: 2017.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ殺到、急増、一点張り。語彙多くなく推測の話し少なくない。しかしこれらの問題対応が簡単でないことも良くわかる。海外の対策や国内で良策を出している地域や機関の例があるともっと良い。
0投稿日: 2017.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ借りたもの。 病識のない精神疾患患者を、医療機関に繋げる支援をしている著者が見た、当事者家族の姿と現在の精神医療の問題点を垣間見る本。 子が精神疾患を患う患者の原因は親にあると明言する。何故なら親子関係――それは人間関係の根本である――が原因だからだ。 しかし、親にその自覚などあるわけが(そして認めるわけも)無いし、親が原因であっても、それを自覚した上で改善しようとする本人の努力が大事でもある。 とはいえ、この本に挙げられる家庭は往々にしてそれを妨げる傾向がある気がする。 大抵は世間体を気にしたり、肉体的・精神的暴力などで辟易して関わりたくない(←この気持ちはわかるけど…)という理由から。 また、現在の精神疾患への医療機関が、本来治療を必要とする重度の患者を受け入れる体制が整っていないこと、「儲からない」「手がかかる」という理由、更には法律・制度から早期の退院を促していること等、問題を指摘している。 p.267から記載されている行政機関、医療機関などの専門機関へ相談に行く際にまとめておくべき要項はきちんと解説されていて、とても大切なことだと思う。 児童の後ろ姿の表紙から児童虐待問題の本かと思っていたら、違った…… しかし、これは一種の虐待が潜んでいる。それを暗示しているのかもしれない。
1投稿日: 2017.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ思っていた内容と違った。 もうちょっとそれぞれのケースに踏み込んだものを期待してしまった。 後半は、ただ作者の演説を聞かされてるだけ、みたいな気分になった。
3投稿日: 2017.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は、著者がこんなにも「精神病院に入れなければ!」「もっと長く入れなければ!」となっているのは、精神病院を素朴に万能視しているからなのかと思ってた。 でも、精神病院でこういう人たちを治療することに限界があることや諸外国と比べても日本の精神病院に問題があることもちゃんと知っていて、それでも精神病院に望んでいるというのが意外だった。 著者は、家族側に立てば、この社会の中でこんな風になっている人たちを収容するのは精神病院でしょう(少なくとも現状では。)という結論なのかな。 あと、著者は、精神障害者についての偏見や差別の助長の問題についても少し書いてるけど、著者こそ、ツイッターでの精神障害者の事件のピックアップの仕方とか自身が関わっている漫画の内容とか、この問題のその部分をそういう風に見せるの世間に向けて良い効果になると思うんですか?とか思ったりもするけど。
1投稿日: 2017.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容(「BOOK」データベースより) 自らは病気の自覚のない、精神を病んだ人を説得して医療につなげてきた著者の許には、万策尽きて疲れ果てた親がやってくる。過度の教育圧力に潰れたエリートの息子、酒に溺れて親に刃物を向ける男、母親を奴隷扱いし、ゴミに埋もれて生活する娘…。究極の育児・教育の失敗ともいえる事例から見えてくることを分析し、その対策を検討する。現代人必読、衝撃のノンフィクション。 題名と表紙から、駄目な親が幼い子供を放棄する事に対する本かと思いきや、そうでは無く精神を病んだ人々の家族の痛切な思いを受け止めて来たノンフィクションでした。こればかりは誰がそういう風な状況になるのかは最後まで分からないと思うのですが、人の人命に関わるような激しい精神疾患についても事件になるまでは割と放置になる事が分かって、とてもとてもびっくりしました。症状が悪くなればなるほど受け皿が無く途方に暮れる現状が分かりやすく書かれています。筆者は疾患のある人々を医療機関へ繋ぐのが仕事なのですが、完全にそこから逸脱して頑張っておられます。是非色々な人に読んでいただきたい本であります。
2投稿日: 2017.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ強烈なタイトルのこの著書。 自傷行為や家庭内暴力、他人への誹謗中傷やストーカーを繰り返してしまうなどの精神疾患のある子供と対峙していくにつれ疲れ果てた親が、実際に口にする言葉なのだそうです。 こういった後天的な精神疾患のある患者を医療機関に移送する民間サービスを営む著者押川氏は、 自治体や警察に相談したにもかかわらず適切な治療行為を受けられなかった精神疾患を持つ患者が、その直後に無差別殺人などの重大な犯罪をおかしてしまう光景を目の当たりするにつれ、 対象患者に対する日本の法制度や医療制度、そして何より子供に対する親の意識の低さに警鐘を鳴らしています。 まず著書が作中で、こういった後天的な精神疾患の回復や治癒がうまくいかない原因が親にあると痛烈に断言している点が印象的でした。 親が見栄や外聞を気にしてわが子の現状から目を背けようとしたり、治療や保護を病院や警察や保健所や著者のような民間サービスなどに「人任せ」にする現状を、 子供を持つ全ての親が正しく認識しないとこの問題は解決しないと述べられている点は、子供を持つ一人の親として非常に心に刺さる指摘でした。
1投稿日: 2017.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
精神障害者移送をしている著者の活動記録のようなもの。 移送だけじゃなくて面会やら環境調整やら宿泊施設経営やら、とにかく手広くやっている。 物々しい言葉使いやパターナリスティックな態度などで敵意を持たれやすいと思うが、内容に批判を加えるのは簡単ではなさそうというくらい実情をよく見ている印象。 本人の問題、家族の問題、病院から制度まで、どれか一つに帰責しないで多角的に分析している。 別に医療化や入院が最適なソリューションじゃないことを著者自身はわかりつつ現実に対応して支援しているようだ。 そのうえで敢えて書くけど、ちょっとナイーブ過ぎて被害的。文章のトーンが。そのあたり「頑張っている」と自認する関係者は腹立つかも。 各種メディアで見る姿と本で読んだ印象はだいぶ違うので、興味のある人は読んでみるといいと思う。
3投稿日: 2017.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ家庭内暴力に疲れ果て、年老いた親が中年になった子供を殺害 する。先日もそんなやりきれないニュースがあった。 しばらく前に本書の著者・押川氏をテレビで見た。精神障害者移送 サービスなる業務を行っている押川氏の仕事に密着したドキュメント だった。 自覚症状もないままにアルコール依存症に陥り、家族に暴力を振るう 男性や、暴君のように母親に自分の欲求を満たす為の要求を繰り返す 少年。彼らを説得し、いかに医療に結び付けるかの過程が紹介され ていた。 本書では押川氏が実際に手掛けた事例の紹介と、精神科医療周辺の 問題点と対策を検討する書である。 なんともショッキングなタイトルだが、実際の事例はそれ以上に衝撃的 だ。我慢に我慢を重ねた家族が、藁にも縋る思いで押川氏に助けを 求めるのだろう。 殺すか、殺されるか。そんなギリギリの状態にまで追い込まれた家族。 そして病識もなく、荒れて行き、精神に異常を来して行く子供。双方が やりきれない。 だが、そうなった結果は「親が悪い。教育が悪い」と結論してしまうの はいかがなものか。確かに本書で扱われている事例はある程度の 資産があり、教育程度も高い家庭がほとんどで、幼いころから多大な 期待を背負わされたり、欲しい物はなんでも手に入る環境に置かれた 子供が多い。 しかし、同じような環境で育った子供のすべてが初めての挫折から 引きこもりになり、家族を振り回す存在になる訳でもないだろう。 それの証拠に、本書でも老いた親に変わって保護者の立場を 引き受けた弟や妹の、「その後」の苦悩も紹介されている。 心の問題は難しいよね。人間、程度の違いはあるもののストレスに 晒されて生きている。「こうでありたい」と描いた理想とは違った生活 を送っていることだって少なくない。 それでもどこかで折り合いをつけて生きているんだと思う。折り合いを つける。そのことが出来なかった人たちが心を病んでしまい、鬱屈し た気持ちが一番身近にいる家族に向かってしまうのではないかな。 著者が言うように、取りあえずは医療に繋げることは重要だと思う。 それでも、退院後の受け皿がなければ元の木阿弥なんだよね。 自傷他害の恐れがある人の受け皿のないことが、悲惨な事件を 招いているのは日々のニュースを見ていても分かるもの。 日本では殺人事件の発生件数は減少傾向にあるという。だが、事件 件数のうち、家族間の殺人発生率は増加しているそうだ。 遠くない昔のように鉄格子のはまった医療施設に閉じ込めておけば いいとは思わない。それでも「3か月で退院」という現行の制度では 救えない家族がいるんだよね。難しいわ。 だって、私だっていつ・何が原因で精神を病んでしまうかも分からない のだもの。
1投稿日: 2017.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ救いのなさに驚くばかりでした。 人を傷つけたり殺す可能性があるような危険人物ほど 入院を拒まれるという現実。入院して問題を起こすとブラックリストに載るらしく、入院拒否って。本当に危険な人物ほど野放しにされるという現実。 でもだから医師や看護師さん、他の患者さんの命の危険云々があるだろうし 過酷な現場で耐えられる人が少なく経験者が育たないのもわかる…というか逆に精神を病んでしまうのでしょうね…。 入院出来ても治療の効果がみられなくとも3ヶ月で出されてしまったり、問題を起こせば3ヶ月をまたずに退院させられてしまったり。 長期入院させられそうだったとしてもその金額が…500万とか。 家族内に本当に危険な人物が出てしまった場合、治療が困難だったらもう逃げ場がないじゃないですか。 何かあったら警察に、で終わるのがお決まりのパターンのようで。 殺して下さいどころか親が殺すか、縁を切って本気で逃げ続けるか、耐えるか。…親が殺されるか。 「家族のために犠牲になれる人」という言葉が重かったです。 やはりというか何と言うか親の育て方が人格を破壊するという要因が多いようですが 結局は本人の資質というかそういうものも大きいと思いますが。 虐待されて育っても幸せになる人もいるし、人生を滅茶苦茶にされたと思っていても壊れきれず、暴力も振るえず、普通に生きられない苦しみを抱え、自殺も出来ずに生きている人もいる。 精神疾患の話ではないのですが「親がお金を持っているのを知っている」人間のタチの悪さは実例をいくつか聞いた事があるので→働かないで親のお金(もらって)で生活しようとする らしいですが お金持ちの子供が壊れた場合→親からお金を巻き上げるようになる で、しかも親が普通に渡してしまうらしいのが凄い。結局あるとそうなるのか。ないものは出せないけどあるから出しちゃうのか。 親が裕福で立派な職業でその子供が挫折した時の壊れっぷりは哀れだったけど何もかも違いすぎて共感できない;両親が弁護士で自分が弁護士になれなかっただけで壊れるの?そういう家庭とか一族とかって小説の中くらいでしか知らないので次元が違いすぎるー。「一族の恥」とかいう台詞が実際出たりするんだろーか…。
1投稿日: 2017.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「精神障害者移送サービス」という仕事があるのか。それは役所の仕事じゃないかと思うけど、いろいろ難しいんだろうな。しかし家族は大変やでこれ。。そりゃたまにはアレな家族もいるだろうけど。。
1投稿日: 2017.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログただ題名で買いました。しかも内容を勘違いして(犯罪系の話かと) しかし、読むほどに興味を惹かれ人としても親としても考えさせられました。 著者は強制拘束をイメージとする精神障害者の移送を対話中心に行ってきた経験を元にこれを執筆しています。 そんな仕事も存在すら知らなかった。そしてこんな世界があることも知らなかった。 本書は著者の出会った現場のリアル、現在までの変遷、そして問題点、更には当事者家族の対応方法が書かれている。全てが当事者や関係者でしか感じられない現実である。 そして何よりも「子供を殺してください」とにわかに信じられない非現実的な題名が付いている。決してこれは過大広告ではない。この現実の前では自分も親の立場として口走る可能性はゼロでは無いだろう。 実際にも第三者よりも親や親族に殺される子供の方が多いと読んだことがある。 やはり、本書の内容は他人事では無いのだろう。精神疾患が身近になった昨今。 親子に、近所に、隣に突然現れるかもしれない現実である。 その時、本書は読んでいるかいないかでは人間として対応を分けてくる内容の一冊かと私は思います。
1投稿日: 2017.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ衝撃的な内容に惹かれて購入 追い詰められているにも関わらず、問題を先送りにする当事者たち 見たくないことを見ず、ちょっと治ったら楽観視する。ある意味人間らしいが、命を脅かす事に繋がる場合を想定すべき… 現実は厳しい
0投稿日: 2017.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初の章の具体例が一番心に残った。身近な人間でこの予備軍だったなと思う人がいるだねに、身につまされる。 問題の難しさがよくわかった。
0投稿日: 2017.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ30~40代になって"異常"行動があるのは、やはり子どもの頃からの生育環境が原因なんでしょうね。ただ、行政や医療に繋げるのは重要ですが、こころの病をどうやってカンカイさせていくか、家族の関係をどうしていくかですね。精神医療のサポートと警察等の行政の連携が重要になってくるのでしょうね。
0投稿日: 2017.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初に実例を列挙して、分かりやすく精神科領域に関わる犯罪を解説。その後、現状の問題点と今後の展望に関する筆者の見解を提示。頭に入ってきやすい構成だと思うし、実際、読みながら特に違和感を感じることもなかった。同時並行で隣に並んだ「家族狩り」を読んでいたこともあり、シンクロした内容に少し驚いたりもして。精神科診療と警察介入の微妙な関係性とか、そういう点でも見どころはあったけど、親子関係を見つめ直すきっかけにもなる内容。不幸な病気という側面もさることながら、向き合い方ひとつで変わってくるという、身体疾患とは一線を画す面にも留意が必要。身につまされました。
0投稿日: 2017.05.11衝撃的なタイトルそのままの…。
2時間ほどで読み終えました。 実は、私の知人に同じような経験をいま、まさにされている方がおり、その話を聞いては暗澹たる気持ちになっていたから、この本を読んでみようと思いました。 知人(男性)の子供は、多分高校中退か卒業した男の子です。 彼は、多くを語りません。「精神科に入院させた」、「腫れ物に触るように接している」、「しばらく距離を置くため一人暮しをさせた」などぽつぽつとこちらが水を向けた時に話すのみです。「あなたは?奥さんは暴力振るわれてない?」といった問いかけには無言でした。無言の肯定だと思います。 男の子が小学生から青年になる過程を私は知りません。まさか、そんな深刻な事態になっているなんて、思いもよりませんでした。でもこの本を読んで、私が考えている以上に、彼(私の知人)を取り巻く状況は厳しいのだと痛感しました。 でも知人にはこの本を読んで、なんて気軽に薦めることはできません。この本から幾つか得たヒントを忘れないようにして、知人夫婦の声にならない声を聞き逃さないようにしたいです。
8投稿日: 2017.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の精神医療の実態、なぜ精神障害者による犯罪が多発しているのか、等がよく分かり勉強になった。 家族に精神障害者がいる人にとってはとても耳の痛くなるようなことが書いてあって、実際自分がその立場になったらと思うと想像するだけで辛い。家族でもどうしようもない凶暴な患者を相手にするのは病院の人だって敬遠したくなるのは当然だと思うし、実際改善もせず、閉じ込めておくこともできないならどうしようもないと思ってしまう。 だからといって、事件が起きたら警察、司法のお世話になってくださいね、それまではどうすることもできません、という現在の病院や保健所の対応はおかしいと思う。ストーカー相手に警察がこんな対応をしていたら世間から袋叩きに遭うだろう。 とても難しい問題だというのが分かって読んでよかった。
0投稿日: 2017.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログんー…まぁまぁですね! 子供に関する症例…つまりはドキュメントの部分は楽しめましたけれども、精神医療だとかともかく著者がつらつらと精神医療の現状だったり、対応策だったりを述べたりしている部分は別に読まなくてもいいかな…と。 それに1000以上の問題のあるお子さんたちを医療施設へと繋げてきた著者だからこそ、もっと実際の例を紹介してもらいたかったんですけれどもねぇ…まあ、ともかく、ドキュメントの部分は読み応えありましたね! ヽ(・ω・)/ズコー 今後ますます家族の関係が変化…それもどうやら悪い方向に…変化していくくさいのでこの本に紹介されていた症例のような子等も増えるかもしれません…混沌とした時代の到来です(!)…。 さようなら…。 ヽ(・ω・)/ズコー
0投稿日: 2016.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神障害者移送や更生支援施設運営などで様々な精神を病んだ人々と接してきた筆者。本書では実際に対応した患者と家族の事例やその経験から見えてくる方策、精神医療と法整備のあり方について書かれている。第1章ではアルコール依存症となり父親を切りつける息子や子供を殺してくれと懇願する親など、ショッキングな事例を紹介。第2章以降は法改正を中心に精神医療の現状等が書かれているが、要は「他人任せにせず、家族が当事者意識を持ってしっかりしてください」ということか。“現代人必読”という触れ込みは少し大袈裟かな。
0投稿日: 2016.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「司法と医療の境目」という言葉にハッとした。人間ってこんなにも脆いものなのかなと。親の見栄や不仲、そんなどこにでもありそうな家庭環境が、こんなモンスターの病原菌を植え付けてしまうものなのだろうか。生まれもった何かがあるのか、生育過程が関係あるのか、わからないけれど、こんなにもロジックを飛び越えたやりとりが存在しているのかと思うと、やりようがなくてつらい。家族は切っても切れないから。 社会で支えるなんて非現実的だと思う。異質者は何事もないように社会から切り離されてしまうから。悪意なく。 ただ、遠い世界の出来事ではなく、自分の世界にも起こりうるものだと捉えよう、と思った。
0投稿日: 2016.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神障害者移送。聞いたことのない言葉だった。 精神障害の背景にある歪んだ親子関係。 子は親の鏡。 長年にわたるプレッシャーが形を変えて噴き出す。 体を強く押すと痣ができるように、心に強い圧迫が長期に加わると心が病むのだ。
0投稿日: 2016.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神の福祉って難しい。 修羅場の地獄のような家庭があり、前向きな未来を感じられない。それでも最善を尽くす方法を模索しないといけない。 私には想像もできない世界。
0投稿日: 2016.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
精神医学に分類されていましたが私はこちらもやはり社会問題の分類に入るように思います。 タイトルと表紙の写真から何となく虐待であるとか、未成年の子供を扱いかねる親の話なのかという印象がありますが、全く違いました。 人格障害と思われる子供を持った家族の苦悩がこれでもかこれでもかと出てくる一冊です。そして根本的解決は見当たらない。救いが無いと皆さんおっしゃっていますがその通りです。でもこういう現実の家族がいるということを知る必要もあるということでしょう。 こういう人に対処する場合、医療機関も公的機関も結局たらいまわし的扱いになるでしょう。今の制度のままではそうならざるを得ません。根本的対策がないのですから。 新しい制度が必要なのだと思いますが、それを誰がどのように決めて施行してくれるのか。一歩間違えば個人情報侵害や人権侵害と言われかねない状況もでてくるでしょうから大変対策は難しいと思われます。 でも、こういうどうにもならない人間て現実にいます。「殺してください」とまで言わしめる苦悩は当事者でなければおそらく本当にはわかり得ないのではないかと思います。 どう対処しても無理な人間がいるのは事実なので、親の責任ばかりを問うことは出来ない場合もあると私は思います。 逆に親が率先して子どもを精神疾患ということにして犯罪の隠れ蓑にしようとしているというケースもあると本文中に指摘があります。それもまた本当のことだと思います。 そのまた別のケースで、子供が犯罪を犯した後、精神鑑定で精神疾患と認定されて犯罪者として裁かれたほうがまだ良かった、と言った親も私は知っています。 こういう人間を家族に持ってしまったら、家族は暮らしも認識も、常識とかけ離れた状況になっていってしまうのかもしれませんね。 アメリカでは人口の15%がパーソナリティ障害だというデータがあると本文中にでてきますが、ショッキングな数字と言ってもいいと思います。(もちろんパーソナリティ障害だからといって犯罪を必ず犯すわけではないのですけれど人には言いにくいことではあります) 「何かあったら110番を」って何かあってからでは遅いけれども、現実にはそれしかないのでしょうか。 著者の方が本書中で述べられている警察OB組織による「グレーゾーン」対策、出来たらすごいなと思いますが現実的には無理な気がします。
5投稿日: 2016.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ平成28年6月16日読了。手段は180度異なるが、押川氏が目指しているベクトルの先は、戸塚ヨットスクールの戸塚宏校長とほぼ同じではないかと思った。親にもどうすることもできなくなったモンスターを『処分』するためには、戸塚先生は必要悪であり、誰も触れたがらない問題を使命感を持って請け負う様は、押川氏と同じスタンスを感じざるを得ない。 親子問題や家族間の紛争を外野から批判するのは容易いが、いざ当事者の立場になったら絶望してしまうだろうと感じながら読み進めた。後味の悪い読後感である。
0投稿日: 2016.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
精神的に追い詰められた家族を救う筆者。 当人、その家族の実際にあった彼らの話。 第1章、リアルなケースを綴ってある 結構細かく書かれています。全7ケース。 第2章、親からの願い 手に負えない状況に陥ってしまった患者の親からの願い。 第3章、最悪なケースほどシャットアウト グレーゾーンだったり、110番しろだったり。 第4章、精神保健福祉法が改正されて何が変わったか ある意味、何も変わらないように感じるのは私だけ? 第5章、日本の精神保健のこれから 犯罪精神医学が行ってきた事を鑑み、日本へのスペシャリストの必要性。 第6章、家族のできること、すべきこと 果たして家族はどうやって向き合っていけばいいのか。 読んだ感想としては どうしろというのか? と。 今までの事例を挙げて。 でも。 自分の感想としては、どうしたらいいのか? しか出てこない。 自分の周りも、自身も当人なので。
0投稿日: 2016.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログここまでの親子関係になってしまう前に、なんとかならなかったのか。幼児教育に関わる身として、乳幼児の親子関係の重要性を痛感する
0投稿日: 2016.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神を病んだ人たちを説得して病院に搬送する、民間会社。患者とその家族が抱える問題と病院側の事情なと、ノンフィクションで綴られる。
0投稿日: 2016.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはもう、なんちゅうか、重すぎて・・・いったいどうしたものやら?という感じ。 家庭環境で病が発症したり、重症化したり、ということもあって悲惨極まる。 また、家族の努力によって、普通の暮らしに戻れる人もいる。かと思うと、親が放棄して、兄弟姉妹に負担がのしかかる場合もある。 病院も人道的な対応をしてくれなかったり、関わっていないと知ることなく過ごしてしまうだろうことが、これでもかというように書かれていて、いっそう暗い気分になる。 著者のやっていることは、ホントにすごいことなのだなぁと思いを馳せる。
0投稿日: 2016.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログいかにも重さうな内容を示唆する表題であります。手に取るのを躊躇するところですが、何となく目を背けてはいけない事が書かれてゐるのではと思ひ、一読した次第なのです。 心の病気と一口に言つても、その内容は実に多岐に亘ります。例へば認知症。誰でも発症する恐れがあり、実際多くの人が罹患してをります。わたくしも血圧を下げる薬を飲んでゐる為、将来に影響がないか不安に思ふところです。発病して夜間徘徊し、踏切に立ち入り電車を止めることが無いと、誰が言へるでせうか。 そんな様々な精神疾患ですが、以前は「精神病」などと差別的に言はれて、「隔離」の対象でした。昔の映画なんかで、精神病と認定された人が、無理矢理精神病院に連れられて行き、本人は「俺はキ○ガイぢやない、正常だ!」などと叫んでも強引に鉄格子(!)の中に幽閉されてしまふ場面がありました。映画『マタンゴ』(本多猪四郎監督)でも、久保明が無人島での体験を話すが、余りに荒唐無稽すぎると思はれたのか、精神病院の檻の中に入れられてゐました。 著者は、精神を病んだ人たちを、患者本人を説得した上で(強引な拘束などは排除し)医療の現場へとつなぐ仕事をしてゐる人。精神疾患の中でも、内に籠る場合と、外に爆発するケースがあります。本書では主に、後者に属する実例を紹介してゐます。 もう成人してゐるのに、社会への適応能力が著しく低く、仕事も長続きせず、悪いのは皆他人の所為だと被害妄想に陥り、親や兄弟姉妹に当り散らし、暴力を振るい家中を破壊しまくり、近隣住民ともイザコザが絶えず、「このままでは殺される」と生命の危機さへ覚え、警察に相談しても「事件がなければ動けない、何かあつたら連絡して」といふことで、万策尽きた親が著者に相談に来るさうです。その究極の依頼が、本書のタイトルになつてゐます。 著者は既に1000人以上を医療機関へ移送した実績を持つさうですが、その中で感じた問題や課題は、国レヴェルで解決しなければならぬ事が多いと。まづは、さういふ他人を殺傷する可能性がある患者は、どこの医療機関でも受け入れたくありません。運良く受け入れてくれても、やはりスタッフや他の患者とトラブルになつたり傷つけたり、病院の備品を損傷したりして、追ひ出されてしまふ。そしてかういふ、じつくりと長期で治療しなくてはいけない患者も、一律で最大三か月間しか受け入れてくれないのださうです。わづか三か月では、家に戻しても結局元通りで、何の解決にもならぬのであります。 何でも三か月以上入院させても、病院としてはカネにならぬのださうで。その辺の事情は本書を覗いてみて下さい。ここでも「最後は金目でしよ」といふ訳か。 著者は、かういふ患者たちの為に、専門の公益財団法人(スペシャリスト集団)の設立を提言してゐます。事実上、医療の現場から見離されてゐる患者たちは行き場がありません。放置は、即ち家庭の崩壊・殺傷事件の誘発を招きます。そのスペシャリスト集団は、経験豊かな警察官OBを中心に組織すれば良いと述べてゐます。せつかくの能力・経験を活かさないのはもつたいないと。 同時に著者は、患者の家族(多くの場合はその親)に対しても注文を付けてゐます。専門家に押しつけて、後はお任せします、ぢやあよろしくと、まるで他人事の親が多すぎるさうです。著者としては、むろん依頼を受ければ全力で解決に当るのですが、何よりも家族の理解と協力が必要であると。 子供の問題行動は、その親に原因がある場合が多いのではないかと、注意を促してゐるのです。憎まれるのを覚悟で(実際、この指摘には批判が多いさうです)問題解決のために敢へて苦言を呈す、といふところでせうか。 出口の見えない問題だけに、読後は重苦しさが残ります。しかし、知らないままだつたら、自分は偏見を持つたまま過ごすのだらうな、と思ひますので、やはり多くの人が目を通すべき一冊ではないかと存じます。 では今夜はこんなところで。御機嫌よう。 http://genjigawa.blog.fc2.com/blog-entry-619.html
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神疾患者を医療につなげようと活動してきた押川さん。精神疾患者とその家族を救う受け皿はとても少ない。特に、他人を傷つける恐れのある精神疾患者は他の入院患者の安全のために病院も受け入れを拒否する。このような現状を打破するためには警察OBによるスペシャリスト集団を作ればいい、というのが筆者の意見。
0投稿日: 2016.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログそれぞれ個々の事例が書かれている第1章は面白かったが,後の章は重複していることも多く,もう少し具体的な体験談とうまくいったケースの症例があれば良かったと思う.
0投稿日: 2016.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
重かった。 それぞれの家庭に癖がある。 誰の責任て一概に言えない。 精神病院、行政、民間、連携が取れてないんだなあ。
0投稿日: 2016.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ショッキングなタイトル。内容も衝撃でした。 精神に疾患があるとされる人が起こした事件に、どうしてそんなことになってしまうのだろう、そこまでいかない内に止める手立てはなかったのだろうかと思っていましたが、水際でくいとめようと頑張っている人もいるのだなぁと少し救われる気持ちになりました。 ですが、著者が頑張っていても、受け入れる施設、体制、国の施策、社会の受容等まだまだ不十分な現状では、追い詰められている家族が沢山いるのです。 本著には具体的な事例が何件か紹介されています。それだけで一括りに原因はこうだと断定することは出来ませんが、やはり、本人が育った環境が影響していると思います。親の育て方、否、関わり方という方が適切かしら。きちんと子どもに向き合っていれば異変に気付くのも早いし、その時点でしかるべきところに相談して治療すれば大事に至らなかったかもしれません。勿論、親の側からすれば精一杯育ててきたのでしょう。 どうしたらよいのか分からないけれど、考えてしまいます…。
0投稿日: 2016.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ大人になったところで、親になったところで、 責任を果たせない人は多い。 子どもが犠牲になり、親に疎まれ、隠され、 どうにかされればいいと願う。 助けを必要とする親子なのだろうが、 関わりたくないと思う気持ちを 持つことを責めるわけにはいかない。
0投稿日: 2016.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本に好感を持てるのは、著者が自分が実際に見、経験したこと以上のことを書いていない点である。帯には育児・教育の究極の失敗、という文字や現代の家族の闇を暴く、という文句が記されているが、そういう内容を期待して読むとかなり裏切られることになるだろう。著者は自身の経験を丁寧に、謙虚に綴り、それ以上の臆測を書かない。家庭内で子供が異常ともいえる行動とる背景には多くの場合に親との関係と言う問題が横たわっていると考えられる。しかし、敢えてその部分には深く触れずに、自分の専門である移送という場面でどのような事態を見、処したのかを淡々と綴っていく。
0投稿日: 2015.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「子どもを殺してください」と、親は言いたかったんだろう。そんな事件が度々起きる。以前から精神障害を持っていて、社会性のない行動をとり、周囲に迷惑をかけ続けたあげく、殺人などの大事件を起こしてしまった犯罪者のことだ。 著者はこうした精神障害者であり、犯罪予備者である家族を抱えた者からの相談を受け、民間の立場からアドバイスをしたり、公営サービスへの紹介・仲介をする事業者。 本書では、著者の壮絶な現場体験事例が記され、障害者家族や医師、行政機関、法律家へ指摘の言葉が並ぶ。特に障害者家族への忠告が厳しい。やはり、精神障害者を社会復帰させる最重要パーツは家族の決意と忍耐なのだ。 とはいえ、家族にも自分の生活、人生がある。「子どもを殺してください」と願う者へ強いることのできる負担にも限界がある。そこで、福祉行政や医療の出番なのだが、彼らは苦労している家族ほど、その家族任せにしてしまう。苦労している家族ほど孤立して報われないという状況を変えていく必要があると思う。
0投稿日: 2015.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
番組で押川さんを知り、読んでみた本 いくつかのケースを読んで精神疾患患者との関わりの難しさが伝わってきました。 さらに法改正について、またスペシャリスト集団設立を通して今後の精神疾患患者の救済までの取組み 行政が行っているとばかり思っていたことは ほとんど成されておらずグレーゾーンと呼ばれる 本当の意味での救済が必要な患者や家族たちの苦悩が 昨今よく報道されている事件に直結していると実感できる1冊でした。 押川さんの行動が行政を動かし 本当に救済が必要な人たちを救うことで みんなが安心して暮らせる社会になることを願います
0投稿日: 2015.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人らしい奥ゆかしさがなくなってきたと感じる昨今である。些細なことで激昂し、訴えてやると声高に脅して拳を振り上げる… 家庭環境によるところも多いのではと感じることがある。本書で扱われるのは単なるクレーマーではなく精神疾患から問題を引き起こす人々だが、根底に繋がりがあるように思う。家族は随分犠牲になっているが、その家族の有り様が、益々彼らを追い詰めていることも多いようだ。「医療機関と司法の間」このどっちつかずの状態が更に問題を悪化させている。ストレス社会の今後の精神医療体系を、今こそ見直すべきなのだろう。
0投稿日: 2015.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
新聞の書評がきっかけで購入した。 この本に登場する精神疾患の子供を抱える家には傾向がある。資産家で裕福か、父親がエリートかのいずれかである。 亡くなった父親が資産家で、母親は働く必要がなかったという家庭で育った子は引きこもりになった。また、父親がエリートで自分の価値観を押し付けるような家庭では、自己肯定感を持てない子が育った。 恵まれた環境は人をダメにするのか。 TSUTAYA社長の増田氏は恵まれない環境に育った。食うに困るというわけではなかったが、一族の中では、肩身の狭い思いをした。また、事故が原因でいじめられた。この経験から培われたハングリー精神が増田氏の根底にあることは間違いない。 しかし、子供は機械ではない。こう育てればこう育つという絶対法則がある訳ではない。 子供が持って生まれた個性と、育った環境の2つが重なって、子供の人格形成が成される。 したがって、親の価値観や教育が子供に与える影響は半分であるが、子供の問題の後ろには、必ずと言っていいほど、親の問題がある。 2014年4月から、改正精神保健福祉法が施行された。この改正は、「保護者から地域へ」という思想が元になっている。 さらに、医療保護入院制度の見直しにより、長くても3ヶ月の入院になった。 その結果、治療が必要な患者が退院し、地域で面倒を見ることが求められる。 重度の精神疾患を抱えた隣人が事件を起こす可能性がある。 現に2015年3月に、精神疾患を抱えた人間が5人を殺す事件が起きてしまった。ペルー人が起こした事件もあった。
2投稿日: 2015.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ民間の精神障害者移送サービス業を営む著者による本 扱った事例の描写は詳細で生々しい。薬物中毒や人格障害を嫌がる精神医療の現場や長期入院を前提とした入院加療が受けられなくなっている現状などについても概ね正確。 内容的には養育を含めた親の態度に対する批判が多く、やや公平を欠くように思う この手のサービスと言えば患者を病院に搬送するだけで数十万円と単位の高額を要求されるとイメージがあったが著者の会社は500万円なんだそうだ。他に方法はないかを考えたり、人権を守りながら後後のフォローまでするとなるとそれぐらいの金額を要するのだろうか
0投稿日: 2015.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログもともと警備会社を経営していたという著者。 従業員の精神疾患から、精神障害者を医療に繋げるという移送サービスを始めたのだそうだ。 前半が著者が実際に対応した実例が紹介され、後半を5章ほどに分けてケーススタディを交えながら、精神障害者とその家庭における実態、苦難、また社会が抱える問題点などを考察していく。 著者も言うように、ご家族がこの問題に真摯に向き合う覚悟ができていているならば、なんとか事態を前にすすめることはできる。ただ、本人の抱える問題を、家族の在り方がより悪いほうへと増幅させているケースも少なからずあるようで、このあたりが精神障害というものの置かれている状況の困難さであるとも言えるだろう。社会の制度しかり。世の中の意識しかり。 単なる無責任な一読者の立場から言わせてもらえば、著者がかかわったケースのその後がどのように変化したか、現在はどうしているのか、などが知りたかったとは思うが、大人の事情もあって難しいのでしょうね。
3投稿日: 2015.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ精神障害者移送サービスの会社を運営している著者のノンフィクション。 著者が作中「精神障害を抱える子供の親は、意外と高学歴、高所得者が多い」といった事を書いているが、このサービスを利用しようという人は高所得でないと利用できないからではないのか。(もちろんそれなりの費用がかかるのは百も承知だが) こういう仕事があるよー、こんなひどい状況の人が世の中にはたくさんいますよー、と。それ以上でもそれ以下でもない。無駄に不安を煽るだけのような内容でした。まさに救いを求めている人が読むべきではない。高所得者は例外なのかな。……わからん。
0投稿日: 2015.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトルを見ると、あれ?児童虐待の本かな?と思いますが、逆です。各種パーソナリティー障害や育つ環境によって、自己愛が肥大しすぎて、家族に暴力暴言を吐き、支配下に置いてしまうような「大人になった」幼児たちのドキュメンタリーとその解決策について言及しています。 自分の社会性のなさ、実力のなさ、人間関係での躓きを親のせいにして、親に金銭的な意味で際限なくたかり、殺すか・殺されるかという状態になっている家族があるそうです。そういった家族から、精神科への移送を請け負っているのが、この著者。当然ながら、毎回修羅場。詳細書きませんが、凄まじいです。精神科に入院させても、長くて3か月程度で退院してくるので、その間に人格がまともになり、経済的にも社会的にも自立が可能になる…わけもなく、再度家族には重い負担、というか命の危険が差し迫ります。 このような大人の家庭内暴力はいまだスポットライトが当たってない現実。児童虐待やDVは社会的認知も進んできており、シェルターなども出来ているようなので、今後はこのような家庭内暴力についても、医療・司法・そして社会的なセーフガードが必要になると思います。
0投稿日: 2015.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルの通り。 ほぼ救いが無く、これでもか、と現在の制度と周りの目線を淡々と説明してくる。読んでいると若干気落ちしてくる位。 「救いは無いのかよ!」と言いたくなるが、救いが無いような状況だから「子供を殺してください」と親が言う訳で……。 自分が事実に直面した時に「もしかしたら明日はもっといい日かも」と解決を先延ばしにするより、直視したほうがいいと考えさせられる一冊。 心にゆとりがあるときにぜひ。
0投稿日: 2015.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルも衝撃的だが、救われない内容で辛い。両親が子供への関心が薄いとか、注いでいる愛情が少ないとか、いずれにしても親に原因があるケースが大半のよう。パーフェクトな親にはなれないけど、矛盾とかないようにはしたい。
2投稿日: 2015.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ事件を起こし続ける子どものケアに疲弊した親への取材ドキュメンタリかと思っていたのだけどちょっと違ってた。 精神障害者移送サービス、という会社と、本気塾という自立更生支援施設を立ち上げた著者による、ノンフィクション。 病識のない患者を説得して病院に連れて行き、その後のケアも行っているという。 追い詰められた親の必死のSOSを、今の日本の医療では救いきれない現実。 なにが、どこに、一番の問題があるのだろうか。
2投稿日: 2015.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ世の中にはこんなにも不労所得で暮らす家があるのか。 エリート一家に生まれた、絶対働きたくない長男は面白かった。病気のほうが生きやすいこともあるのだ。箒木さんの閉鎖病棟という小説を思い出した。外で生きるのが善、という思想と全く相容れない者。
2投稿日: 2015.08.13
