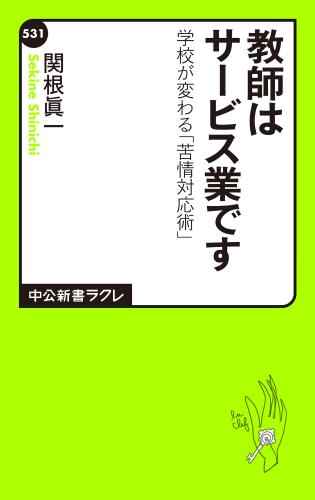
総合評価
(12件)| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと久しぶりに、関根コミュニケーション論。春から職場を替わることもあり、もう一度、クレーム対応について勉強しなおしといた方が良いかな、と。基本的な内容は他の作品と変わらず、即ち大原則の普遍性が高いということ。あとは反復練習あるのみ、ってことですわな。邪魔なプライドから自由になるっていうの、言うは易し行うは難しですわ、マジで。
0投稿日: 2019.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ百貨店で長年クレーム対応を担当してきた現クレーム対応アドバイザーである著者が、異業種の事例を織り交ぜつつ教師、学校向けにクレーム対応の心構えとノウハウを説く。長く学校と付き合っていく親の立場でもお役立ち。 新聞連載時の編集局記者の名前に懐かしくも驚いた。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ思ったほどは参考にならず。 教育業界のクレームの例をあげつつ具体的な対応も書いてはありますが、全く出来ない人の意識が変わり、具体的なスキルを身につけ、本を読みながら現場で実践できるようになる本ではないです。経験が重要という記載が繰り返しでてきていて、「それ言われたら本読む意味無いじゃん」と思ってしまいました。 それでも、クレーム対応するときの心の持ち方などは参考になりました。
0投稿日: 2018.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログモンスターペアレントなど悪質な苦情を言ってくる親たちがいたり、最近の教師はとても大変そうである。 しかし、この本モンスターペアレントにもきちんと言い分があることをまず理解してから、対応することを、丁寧に説いている。 元百貨店の苦情対応窓口を長年経験した著者からの言葉には、なるほどと思わせるものだらけ。 教師だけではなく、いろいろな面で役に立ちそうな、「苦情対応」。しかし簡単に身につけられるものでは無いね。
0投稿日: 2017.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ大して考えずに手にとったけど、思ったよりよかった クレーム対応をするような状況を作らないのが一番だけど、まるで事故や天災のように、こちらの行動とは関係なくそういう状況になっていることがある 参考になりそうな考え方も随所に見られた
0投稿日: 2017.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ良薬口に苦し。タイトルへの反感で読まないのはもったいない。デパートの苦情処理担当の視点は保護者対応でも参考になること多く、何より内部にはない視点多々。他山の石として役立てたい。
0投稿日: 2016.10.19言い方一つで状況が変わる。
教師向け書籍。教師向けと言っても専門書ではなく、表題通りの苦情対応の雑学的ハウツー要素満載です。基本的な内容は、クレーム対応なので、各職業に置き換えても良いですし、学校の先生方が悩んでいる視点が理解できるので、逆に保護者が読んでも面白いと思いました。
0投稿日: 2016.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業のお客様対応のプロである著者が、企業で行われている対応方法を教育現場にも生かせるはず、という内容で実践マニュアルを紹介している。 いくつかは以前から学校現場でも既に言われてきたことではあるが、学校以外の社会経験の少ない教員にとっては有為な内容だと思う。 例えば保護者対応には、 ・相手の体面を立てるように話す ・真摯に相手の話を聴く(傾聴) ・相手が感情的な時は、間を空ける ・必ず学年団や学校内の組織と情報の共有化を図る などの方法をとることで、保護者からの「クレーム」は有為な情報共有の機会となるのである。 教員の対応次第で「モンスターペアレント」なるものはいなくなるのである、筆者は述べている。 教員や児童・生徒の保護者には必読の一書。
1投稿日: 2016.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログクレーム対応のベテランの筆者が、学校、教師に対するクレームに対してどう対応するのがいいのか記した本。教師はサービス業と考えれば、そしてその道のプロだという自覚で対応すれば自ずと今までの対応と変わらざるを得ないだろう。
0投稿日: 2015.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ百貨店お客様対応部門出身者による教員のためのクレーム対応本。 教員に不足している能力を、外部の人間が鮮やかに描き出している。 マニュアル本としては物足りないが、ロールプレイを含む研修の 回数を増やそうという提言に対しては、 積極的に取り組むべきものであると思う。 学校現場に新たな研修を受け入れる余裕がどこまであるかは 疑問符が付くけれども。
0投稿日: 2015.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ百貨店の「お客様相談室」などで様々な苦情・クレームに対応してきた著者による、教育現場における保護者からの苦情対応術について。保護者が苦情をわざわざ訴えてくる背景、他業界も含めた苦情の対応事例などが紹介されている。 納得できる部分が多かった。いつか先輩の先生が「初期対応を間違わなければモンスターペアレンツなんて出来ない」と言ってたが、まさに同じことが「クレーマーとは、そもそもの実態があるわけではなく、苦情を受ける側の対応力の不足から後天的に作り出される存在なのではないでしょうか」(p.39)と、第一章に書いてあった。第二章では保護者の心理について書いてあるが、もし保護者が間違っていた時でも、「学校の説明が悪かったとか、言葉足らずでしたなどと軽い謝罪をし、相手の体面を保ってあげることが肝心」(p.44)とあるが、これは本当、難しそうだ。こういうのは著者も紹介しているような「ロールプレイ」の手法で訓練することができるのだろうか。ところで、第二章だけ、途中から突然、保護者目線で、苦情を言う時のマナーやコツといった保護者へのアドバイスが紹介されだすので、ちょっと戸惑った。第三章以降、ちょっとしたノウハウが紹介されているが、目線を落として間を置くとか、「なるほど」という相槌はふさわしくない、とか、参考になった。 本当に理不尽というか無理難題のイチャモンを本格的につけてくる保護者というのにまだ出会ったことがないので、いくらポイントを押さえておけば大丈夫とは言っても、この本を読むとちょっと恐ろしい、と思ってしまった。(15/09/10)
0投稿日: 2015.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ<目次> はじめに 第1章 追いつめられる教師たち 第2章 保護者は苦情を”やむなく”言っている 第3章 保護者対応マニュアル「基本編」 第4章 保護者対応マニュアル「実践編」 第5章 苦情対応力の強化に「ロールプレイ」 第6章 状況別マニュアル 第7章 苦情対応の最新情報 最終章 サービス業として開きなおれ! <内容> デパートの苦情対応係を長年やり、現在はサービス業関係の苦情対応を指導する仕事をしている著者が、日本教育新聞に連載していた「教師」の苦情対応の仕方を述べた本。タイトルの通り、今や教師は”聖職”でなく、サービス業の一環であり、今後保護者は本当の“モンスターペアレント”化する恐れがある。それに対して、まずは各教師個人が最低限の対応力を身につけ(何よりも初期対応が大事)、管理職や教育委員会もその上の対応力をマニュアル化しておく必要がある、との説。もっともで、50代の教員の方が、若き日にまだ”聖職”だったころの対応をしてしまって、保護者の苦情に火に油を注ぎ、モンスター化してしまっている、との指摘は耳に痛い。この本を読んでもすぐに対応力は身につかないが、覚悟と準備(ロープレなど)を意識できる。
0投稿日: 2015.07.30
