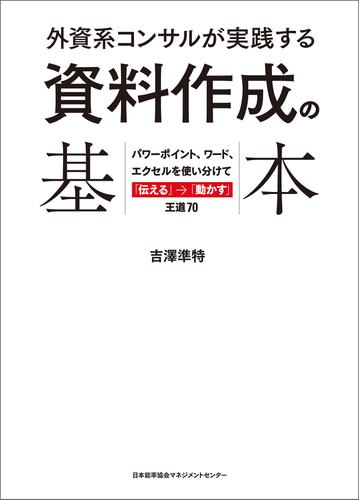
総合評価
(18件)| 4 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料作成に際してもう一冊。序盤はコンサルでしか使えないテクか?と思ったけどそんなことはなかった。かなり実践的な細かいこと(テキストボックスの余白はどの数値で設定すると見栄えがいいとか)を多岐にわたって教えてくれる。今回は図書館で借りたけど、必要な時々に見返したいと思うので買います
0投稿日: 2024.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ分かりやすいし実用的。先輩が後輩に教えるようなことを漏れなく纏めたような感じなのかな。コンサル入社前の課題図書には最適。 ただ、レイアウトなどの細かいところが間違ってると資料全体の信頼性が損なわれる!と説く本書自体に、ちょこちょこと誤植や図のズレ(それも、矢印の指している先が違うとか)があるのが気になった。 あと著者の経歴が不透明で、どこのファーム基準なのかが良く分からないのも微妙。
2投稿日: 2021.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログパワポでの資料作成を極めしもの、もしくは極めようとするものが読むべき一冊。 流行りの「外資系◯◯」なので危ない気がしたが、内容が重厚すぎて最後まで読み切ることができなかった。資料作成がメインの業務である方には、多くの益がありそう。 普通の資料作成人は「科学的に正しいずるい資料作成術」で十分。
1投稿日: 2021.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事で企画書を書くようになったので。 先輩からオススメされ、とりあえず勉強で読んでみた。 色々書いてあって、それなりに参考になったけど、読後に印象に残ってるのは ・スケルトン(全体構成のモック的なもの)作るの大事 ・企画書とか報告書の構成には定石がある 他は、必要になった時に見返せばいいのかな〜という感じ。 グラフの形の選択とかは、わりと今まで直感だったので、改めて「こういう場合はこのグラフを使いましょう」という説明は新鮮でした。 あとは、グレースケールでも分かる色使いとか。 パワポのマスターの作り方とか。 テクニック的なところも結構紹介されての、王道70でした。
0投稿日: 2019.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログスケルトンの位置づけを明確に示している。 パワーポイントやエクセルのテクニカルな解説だけではなく、資料のドラフトから完成までのプロセスにも言及がある点は、参考になる。
3投稿日: 2019.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログスケルトン、ドラフト、フィックスの三分法や、次の6つの発想パターンが面白かった。 つみあげ確認型、論より証拠型、ひらめき発見型、トライ&エラー型、1+1=3型、ひかえめ誘導型
0投稿日: 2018.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログパワポに限らず、誰に(who)、何を(what)、理由を(why)提示するための方法として、パワポ、ワード、エクセルのどれを選ぶべきかから解説している本。 <王道70とあるが70ポイントであり> 1章 スケルトン作成(相手、内容、理由を選んで目次作成まで) ※王道1〜9 2章 ドラフト作成(文章編) ・文章は、テンプレ、書式や配置等 ・わかりやすい文章やワークシートはエクセルで作る ※王道10〜24 3章 ドラフト作成(図編) ・図解は、わかりやすく適した図表を選ぶこと ・図形と線の使い方のルールを選ぶこと ・読みやすい色を選ぶこと 王道25〜59 4章 フィックス作成(魅せる資料に仕上げる) ・コンテンツの説得力を強化する ・印刷物の見栄えをよくする ※王道60〜70 であった。とりあえず全体像がわかって、それなりのものを感覚的にではなく、ロジカルシンキングで作成する人にとってはよい助けになるような気がする。
0投稿日: 2018.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ外資系コンサルが実践する資料作成の基本 パワーポイント、ワード、エクセルを使い分けて「伝える」→「動かす」王道70 吉澤準特 2014年8月25日第1刷発行 2017年6月25日読了 良くある外資系コンサルが教える資料作成本。1冊くらいは読んで手元に置いておいても良いかと思う。 この本の著者はシステム系なのかも知れないが、資料作成の例示が営業システム改善のプレゼン資料作成を引き合いに出している。 担当者が、資料作成をしてみたら上司からダメ出しが入り、「こうすれば良かった」という形式で色々な資料作成のコツが書いてある。 第1章、第3章が本書のキーポイントであると思うが、1章では「スケルトン作成」と題して、資料を作成していく際にいきなりエクセル、ワードで作り始めるのではなく、目的と相手と理由をハッキリさせてから作ろうということが書いてある。特にスケルトンが資料の設計図になるので大事であり、必ず手書きで作ること。 第2章では、ドラフトの作成(文・表)としてレイアウトの統一や見易さ、書式など「王道」ルールを使うとより見やすい=伝わりやすい資料になる技が書いてある。 第3章では、ドラフト作成(図)として、8タイプのチャートと9の図を使った具体例が提示してあって、ここまでの技を自在に使えたらかなり資料作成のレベルは高いと言える。 が、ここが問題でどの図をどう扱えば良いか?がやはり簡単ではなく、その辺はひたすら自分でトライ&エラーで磨くしかないのかなー。とも。 ただし、その時に闇雲にトライするよりこうした本を元手にやる方が効率もクオリティーも上がると思う。 あくまで色々な資料作成の一手順かも知れないけれど、自分の資料作成の一基準として使っても良いかなと思いました。 特に、考え方としては第1章の手順。具体的な技としては第2章、3章。
0投稿日: 2017.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最近読んだ外資系資料作成本3冊の中では一番良かった◎パワポ資料作成だけじゃなく、エクセル、ワードなど求められているものに合わせた資料作成が提案されていて好印象。パワポ部分だけに限れば内容としては十分ではないかもだけど、資料作成の考え方や基本などが具体的な事例に沿って紹介されていて分かりやすい。また、印刷時やデータ提出時の注意点やテクニックなども参考になった。これ一冊手元に持っておけば、仕事力が少しレベルアップしそう◎ 以下、ハイライト ・スケルトン⇒ドラフト⇒フィックス
0投稿日: 2016.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこの手の本にしては、珍しく内容のある本。 大げさなプレゼンではなく、日々の資料作りに即役立つ情報がてんこ盛り。
0投稿日: 2016.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ[図書館] 読了:2015/8/15 p. 141 星取表は「Y」と「-」にすべし。なぜなら欧米とアジアでは「⚪︎」と「×」の意味が逆になるから。
0投稿日: 2015.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ資料の見映えを良くするためだけのハウツー本が多い中、誰に何をどのように伝えるべきか?からまとめられているので、今までの自身の資料作成を再考する良い機会にもなった。
0投稿日: 2015.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ・太字はヘッダー部のタイトルと本文部の見出し、本文部コンテンツの重要部分向け。下線は本文部の見出し(コンテンツには使用しない)。斜体陰影は使わない。 ・スライドは、左→右、上→下、左→右→下、上→下→右 ・文章はスリム化する。修飾表現を除いた最小限の文を作り、修飾表現を一つずつ戻し、文意を再現出来たら止める。 ・定量表現を用いるのは、相手の意思決定に影響すると思われる個所にしぼる。準備大変だから。 ・色を使うときは5種類。 強調色(明るさ128)、基本色(明るさ64)、極薄色(明るさ32)、無彩色薄、無彩色濃 ・ファイルが重い場合は不要なスライドマスタが存在する可能性あり。 ・ISERROR関数で「#DIV/0!」を変換できる。
0投稿日: 2015.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ大枠の作り方から、実際の資料の魅せ方まで幅広く一通りの説明がなされており、資料作成のバイブルになる。
0投稿日: 2015.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログめちゃめちゃ良書。資料作成のノウハウがさすが綺麗に纏まってます。 わかりやすい資料を作るのって本当に難しくて、私も相当苦労した時期があったんですが、当時コレがあったらどれだけ救われたか。 企画書・提案書・報告書など、どう作ればいいかわからず悩んでる人いれば、コレ読んだらスムーズに進めれます。我流の人もコレ読んだらクオリティ上がります。 私もバイブルとして、手元に置いておきます。
0投稿日: 2014.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ今までは自分のルールで作ってしまっていたが、この本をベースにしながら、自分のアレンジを入れていくことを意識してみようと思う。
0投稿日: 2014.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ先輩に薦められて購入。 ワード、エクセル、パワーポイントにおける資料作成について、フォント設定から構成まで詳細に記述されている。 対象、目的はどこで何を伝えたいのか、そのために齟齬なく、効率的に伝えるための資料作成方法。 優れた資料作成には経験がものを言うが、当著のノウハウを把握し、数をこなせば、ただの経験だけではなく、短い時間で修得できるだろう。 要実践andまとめ。
0投稿日: 2014.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログメルマガ購読中の吉澤準特氏の新刊。 世にある資料作成本の不足部分をしっかり補っている、良書かと。 これまで在籍したコンサル会社で教わったことは、一通り載ってた。ある意味体得していることが多かったが、こういう整理をした本は無かったので、他人に伝えるのに重宝しそう。 最後にまとめられているExcelの使い方については、必要なのかな?と思う、蛇足感あり。
0投稿日: 2014.08.22
