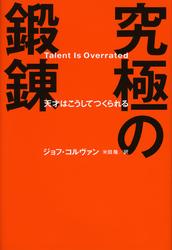
総合評価
(42件)| 8 | ||
| 15 | ||
| 9 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ生まれつき持っている才能がなくとも人間と言うものは偉大な業績を残すことができると言う事を著者は様々な調査から述べています。これほど素晴らしい本はないと思いました。人間と言うものは持って生まれた才能があるからこそ偉大なる能力を発揮できると言うふうに今までは一般定義されがちですが、この著者は最先端の心理学の調査結果を決め細かく読み込んで鋭い問題提起をしながら偉大な業績や素晴らしい成果を世の中に出していける人は類稀な究極の鍛錬を行なってきているのだ!と言うことをあらゆる観点から説明されています。真の努力を行えば必ず結果が出てくる、そのために必要な時間やノウハウが書かれており非常に人々に生きる希望と歓喜をもたらす本と言えます。必ず読んでおくべき本です。
0投稿日: 2022.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
世界的な業績をあげている人々はどこが違うのか? この問題を解くために気鋭のジャーナリストである著者は徹底的な調査を行います。そして、モーツァルト、タイガー・ウッズ、ビル・ゲイツ、ジャック・ウェルチ、ウォーレン・バフェットなど、天才と呼ばれる人たちは共通する原則に基づいて鍛錬を行っていたことがわかります。さて、著者が「究極の鍛錬」と呼ぶその方法とは?
0投稿日: 2021.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ才能があるからといって大きな成功をおさめられるわけじゃ無いし、才能が無いからといって大きな成功をおさめられないわけじゃない。 究極の鍛錬の共通項を抑え、その通りに実行できれば誰でも成功はできる。ということを、実験結果などの事実をもとに論じている本。 コンフォートゾーン(自己成長無いが居心地が良い環境)にいては成功はできない。 パニックゾーン(自分の能力を遥かに超える課題にぶつかり思考停止の状態)では自信喪失して前に進めなくなってしまう。 いかに、ラーニングゾーン(自分の能力より少し難しい事に挑戦する状態)に自分を置き続けられるかが成長を重ねるための大きな要素の一つとなる。
0投稿日: 2020.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログエリクソンの著書と内容の見分けがつかないほどだが文章は断然こちらの方がいい。因みにエリクソン本は1/3ほどで挫折した。「限界的練習」の中身をもったいぶって手の中に隠すような構成にウンザリしたためだ。尚、「究極の鍛錬」と「限界的練習」が単なる翻訳の違いなのかどうかは確認しておらず。たぶん一緒だと思う。マルコム・グラッドウェルの著作はまだ読んでいない。 https://sessendo.blogspot.com/2019/11/blog-post_96.html
0投稿日: 2019.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ・一流と二流の差を生み出す要因は、単なる「努力」、あるいは「才能」ではない。人が偉業を成し遂げるカギは、「究極の鍛錬」 ―― 専門分野で一生上達するために行う、考え抜いた努力であることが、研究によって明らかになっている。 ・究極の鍛錬には、次の5つの要素がある。 ①実績向上のために特別に考案されている 実績を上げるのに改善が必要な課題を特定し、それを継続的に鍛え上げていく必要がある。 ②何度も繰り返すことができる 特定の活動を何度も何度も繰り返すことが求められる。 ③結果へのフィードバックが継続的にある 鍛錬の成果をフィードバックする必要がある。成果がわからないと上達せず、注意深く練習をしなくなってしまう。 ④精神的にはとてもつらい 自分の技術や能力の至らない点を、継続的に洗い出し、改善しようとするため、精神的な負担が大きい。 ⑤あまり面白くない 究極の鍛錬では、不得手なことにしつこく取り組むことが求められる。そのため、楽しいものではない。 ・究極の鍛錬が実を結ぶまでには、長い時間がかかる。こうした大変な努力を行える人は、次の2つのものを持っている。 ①この先何年も自分の人生をつぎ込めるほど、つかみ取りたい目標がある。 ②鍛錬を毎日数時間、何年もの間実行し続ければ、いずれ頂点に至ると信じる心がある。
2投稿日: 2019.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々な分野の第一人者といった突出した成果は才能なのか、訓練なのか?才能だけではないのは十分示されているが、才能がいらないのかは?とりあえず、才能があり、かつ必要な技術を分解し、戦略的に獲得していく訓練を積めば達人になれるようだ。
0投稿日: 2019.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB03668450
0投稿日: 2019.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の自分に足りないことなので刺さりました!究極の鍛錬 鍛錬のタイプ 一緒に働く仲間に求めるもの などが言葉で説明できるようになったと思う。
0投稿日: 2019.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ能力の限界に挑戦する練習を設計し、何度も何度も繰り返し、コーチからフィードバックを受け、精神的負担に耐えること。基盤となる情熱は本当に欲しいものを知り、鍛錬の成果を心の底から信じること。(いや、それが常人にはなかなかできない。)
0投稿日: 2018.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログvia Twitter​ http://ift.tt/​1ympAlN ​ チェスや楽​器のプロを調べ、​達人は毎​日4時間以上、10年という​総量が必​要としたエリックソンの研​究が有名ですが、『​究極の鍛錬』とい​う訳書がエリック​...
0投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在五月だが、間違いなく今年今までに読んだ本の中でベストの一冊。今私がいろいろ感じていたものや、今後の方向性について大きな示唆を与えてくれた。 感触としては「天才!」の実践編というものだろうか。 コメント欄で簡単に書ける物ではないので、書評をまた書くとする。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ一言で言うと、英語のタイトルの通り、"Talent Is Overrated" である。 すなわち、世界的な業績を上げるにあたっては、一般的に信じられている「才能」ではなく、「鍛錬」が必要である。 ここでの「鍛錬」とは、著書のタイトルともなっている「究極の鍛錬」であり、?実績向上のためのプログラミング、?繰り返す、?フィードバック、?単調で辛い、?面白くはないようなトレーニングであり、投入した累積練習量(時間という意味の量と集中力などの質の両面から)がパフォーマンスを左右する。この鍛錬の結果により、達人は多くを認識し、知識を持ち、記憶することができる。 ポイントは、要素に分解した上で自分の課題を知り、1つ1つを克服していくこと、及び、コンフォートゾーンから一歩踏み出す(本書では「ラーニングゾーン」としている)勇気である。 これはビジネスについても応用できる。イノベーションと言われる革新的なアイデアも決してひらめきではなく、思考錯誤や長い時間積み重ねてきた知識が実を結ぶ。この際には、自主性が大切な要素である。 そして、過去と比べて、マスターすべき知識や技量が増大している現代においては、業績を上げるために必要な練習量も従来よりも多くなっている。したがって、何よりも早く始めることである。しかも、競争の少ない分野であればなおよし。 最後に究極の鍛錬を繰り返す上で必要な動機についての言及もあった。 やはり、単調な練習をどこまでも積み重ねることが遠くへいくための唯一の方法なのかも知れない。
0投稿日: 2018.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の専門分野はこれです!と言える人は少ない。 専門分野を持ち、それにたゆまぬ努力と工夫をしている人を見ると、 言わずもがな、尊敬してしまう。 超一流の人は、なぜ超一流に成れたのか、 それは、明確な動機と具体的な目的を持って「自分ができないこと」に 多大なる時間と心血を注いだからという。 と、当たり前のことを、この本では述べている。 そして、究極の鍛錬の要素を展開している。 何かを一生懸命学んでいる人なら、非常に参考になると思います。 多くの人は、「自分が、できること」ばかり行い、 「上達すること」に対して、達人ほどエネルギーを注がないが、 並外れた結果を残している人は、自分自身の知らない、 できない、わからないを認めて、自分自身へ挑戦している。 意識を変えるだけでも、結果は全然違うものとなるんだろう。 見た目には、同じことをやっていても、 問題意識の違いで、全然違う結果を生む。 専門分野を持ちたい人、専門分野を持っている人も、 これから、もっと成長を感じて、よりよく生きていきたいなら、 この本は、たくさんの視野を与えてくれる。
1投稿日: 2018.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ究極の鍛錬を積めば偉業につながる。大抵は心理的な要因で集中できず、継続できない。 各記録能力が伸びているのは、人間の能力の使い方が向上しているから。高いIQは必要ない。 企業が伸びるのは人的資本が優秀だから。microsoftやグーグルの採用試験が厳しい理由。人間の能力開発に限界はない。 生まれつきの才能が存在するとしても重要ではない。 モーツァルトでさえも、18年間訓練された後に素晴らしい作曲をした。タイガー・ウッズも両親から教育された。 練習を積めば、記憶技術には際限がない。 フットボールのライスのトレーニングは、他の人はついていけないレベル。実戦ではなく練習を積むことでうまくなった。しかし練習は面白くない。ひとりで練習することが重要。 考え抜いた努力を行うこと。 究極の鍛錬の方法=正しい方法、時には教師の手を借りる。何度も繰り返す。継続的にフィードバックを受ける。精神的に辛く面白くない、しかし効果がある。 1時間半のトレーニングでもよいが、心を込める。心を込めたトレーニングは1時間半しかできない。 ラーニングゾーン=もう少しで到達できる成長域を強化する。コンフォートゾーンで練習してもだめ。 年齢に伴う変化は不可避、しかし究極の鍛錬に費やした時間は減らない。 自分の専門分野については驚異的な記憶力を持っている。 コンディショニングと固有スキルの訓練。 危機のときは10倍の学習ができる。 傑作が生まれるまで10年の沈黙が必要。 インスピレーションが生まれるには知識と熟す時間が必要。突然降りては来ない。 組織では、新しいことに友好的ではない。 ノーベル賞の受賞年齢は伸びている。単に全体の寿命が伸びているからではなく、最先端までの知識を身につけるのにより時間がかかるようになった。 達人は、加齢によって普通の分野で衰えても、専門分野では衰えない。 フリオ・フランコは徹底した練習と注意深い食事による体調管理で、加齢を克服している。 「体が言うことを聞かなくなるのではなく、選手自身がこれ以上限界に挑戦することをやめるだけだ」 もう練習できなくなるまで、鍛錬は続けられる。 内的動機と外的動機。自分の中から生まれる満足のために辛くて面白くない練習をする=練習が好きになる。 内的動機を高めるような外的動機づけは効果が高い。 乗数効果=上手になるほど練習が多くなる。注目や賞賛は乗数効果の燃料になる。 競争者の少ないところで始める。クリエイターは大都市出身でないことが多い。
0投稿日: 2017.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
その人が一流になるか、ならないかは、生まれつきの才能があるか、ないかではなく、その人が意味のある鍛錬(練習)をいかに多く積み重ねたか、ということに尽きる。もちろん、生まれつきの才能、才能と言うか、例えば、身体的な有利さ、背が高いとか、手が大きいとか、そういうものを全て否定するわけではないけど、持って生まれた才能が、一流になるために寄与するものは少なく、多くは、どのように訓練してきたかということだ。 如何に多くの時間を費やすことができるかは、言い換えれば、如何に早く訓練を始めるか、ということになる。ただ、訓練を続けようとすると、訓練とは辛い事も多いため、幼少の頃の親の役割は大きなものとなる。そして、その訓練を長く、少しはやりがいを感じながらも続けるには、少しずつ上を目指しながら難易度を上げていくことが重要となる。例えば、都会と田舎を比べると、田舎からはじめ、地方の競技大会やコンクールなどでよい成績をとり、次のステップへ少しずつレベルを上げていくことが長く鍛錬を続ける秘訣という。 一般的に言われていることに、一流になるには、1万時間の訓練を費やすことが必要だという。しかし、意味の無い訓練を続けても仕方がない。ちゃんとフィードバックがあるような訓練でなければ上達しない。フィードバックは、競技大会で何位になるというのもそうだし、先生について、そうじゃない、こうだ、というのもフィードバックだ。 天賦の才について、イギリスの研究者が調査の一環として、音楽の才能についてインタビューをしている。研究の被験者は、みな卓越した才能の持ち主だ。インタビューした結果、被験者が徹底的な訓練の前から、早熟の萌芽があったという証拠は見出すことはできなかった。その他の分野において、後にすばらしい業績をあげるような人たちも、ほとんどは早い時期から才能を示していたわけではない。音楽家、テニスプレーヤー、アーティスト、水泳選手、数学者を対象とした研究でこれらが明らかになっている。もちろんこれらの研究は、才能が存在しないということを証明しているわけではないが、生まれつきの才能が仮に存在したとしても、それは重要ではないかもしれないということを示しているということだ。現時点では、ピアノを上手に弾ける遺伝子や、投資をうまく行う遺伝子、会計業務を得意とする遺伝子は見つかっていない。モーツアルトは、5歳で作曲し、8歳の時に公式の場でピアニストとバイオリニストとして演奏会を行い、その後、次々と作品を生み出していった。モーツアルトの父親は音楽家としての能力は平凡であったが、教師としては一流だった。モーツアルトが生まれたときに父親が書いたバイオリンの教則はその後何十年も音楽業界で強い影響力を持った。まだほんの幼い頃から息子のモーツアルトは同居するベテラン教師の下で厳しい訓練を受けていたのだ。もちろん子供時代のモーツアルトの作品は素晴らしいものに見えるが、作品の真偽については議論がある。手書きの楽譜は少年モーツアルトの手によるものではないからだ。父親が他人が見る前に修正を加えていたのだ。モーツアルトを教え始めてから、父親はぴたりと作曲をやめている。モーツアルトは、今でも現存する手書きの楽譜を見れば分かるとおり、執拗に書き直し、消してはまた全体を書き直し、一部を書いては数ヶ月、ときには数年にわたって置いておく事もあった。モーツアルトが奇跡的な作曲能力を持ち、ほとんど完璧な形で頭の中に曲が浮かび上がってくるといった、モーツアルトを神格化したようなものではなく、普通の人が悩み、書くように、モーツアルトも作曲していたのだ。 究極の鍛錬には、いくつかの特徴的な要素がある。その要素とは、①しばしば教師の手を借り、実績向上のため特別に考案されている。②何度も繰り返すことができる。③結果に関し、継続的にフィードバックを受けることができる。④チェスやビジネスのように純粋に知的な活動であるか、スポーツのように主に肉体的な活動であるかにかかわらず、精神的にはとてもつらい、しかも、⑤あまりおもしろくない。 究極の鍛錬では、業績を上げるのに改善が必要な要素を、鋭く限定し、認識することが求められ、意識しながらそうした要素を鍛え上げていく。こうした究極の鍛錬の例はあちこちにある。偉大なソプラノ歌手ジョアン・サザーランドはトリルに数え切れない練習時間をつぎ込んだことで有名だ。基本的なトリル音だけではなく多くの異なるタイプの音も練習した。タイガーウッズは、バンカーに何個もボールを落とし、その上を足で踏みつけ、ボールを打つにはほとんど不可能なバンカーからの球出しの練習を繰り返した。偉業を成し遂げた人たちは、自分の取り組んでいる特定の課題をハッキリとわかるように選び出し、うまくなるまでその課題に集中して練習し続ける。そして次の課題にうつる。こうした特定の課題を自分自身で見つけれること自体が重要な能力だ。このポイントを大学教授は説明している。一番内側の円をコンフォートゾーン、中間をラーニングゾーン、一番外側をパニックゾーンと名づけた。人はラーニングゾーンを強化することで成長するとしている。身に付けようとしている技術や能力がもう少しで手が届くところにあることを示している。一方、パニックゾーンでの活動は、あまりにも難しく、どうやって取り組んだらよいか分からず、コンフォートゾーンでは進歩は望めない。自分の手でラーニングゾーンを明確にすることはたやすいことではない。加えて、常に継続的にラーニングゾーンにいるように自らを強いることはさらに困難だ。このため、①の教師の手を借りて、実績向上のために特別に考案されている要素が、一番重要な究極の鍛錬の特性となる。 普通の人も達人の領域に行く道は実際にある。ただし、その道は長くつらい。だから最後までその道を歩み続けるものは少数しかいない。どんなに遠い旅路になろうとも、その旅路は常に有益で、究極の鍛錬を構成する諸要素を適用すれば、いつでもはじめることができる。 結果に関し、役立つフィードバックの無い訓練は価値がない。達人は普通の人が自分自身をみるようには自分のことを甘く見ない。自己査定が具体的だ。普通の人は自己満足で終わってしまうが、達人は自己評価にあたり、達成しようとしていた事柄に適切な判断基準を持って判断に挑む。時にはこれまでの自分の最高の出来と比較したりする。また時には直面するかもしれない競争相手の能力と比較する。さらにあるときはその分野で最も優れた人間と比較する。究極の鍛錬かどうか、鍵になるのは、現状の自分の能力を少し超えた基準に自分を引き上げ、能力の限界を高める強さの課題を選ぶことだ。基準が高すぎると人は意気消沈してしまい、低すぎると進歩は無い。自己査定の重要な点は、何で失敗したかを見つけることだ。普通の人は、失敗は自分がコントロールできないことによって引き起こされたと信じる。競争相手が幸運だったとか、課題が難しすぎたとか。それに対し、達人は、失敗したのは自分に責任があると考える。達人は容赦なく、自分自身の実績を見ることに集中している。 達人になるためには、自分が選んだ分野で達人になろうと大きな投資を行うこと、より熟達した指導者を求めること、学びのなくなってしまうコンフォートゾーンを抜け出すために自分を常に追い込むこと、常に自己の限界に挑戦することである。 ほんとうにゼロから突然浮かんでくるヒラメキと言うものはなく、そういう瞬間は、何時間もの思考と研究、究極の鍛錬の結果、ああ、こうするんだ、と生まれてくるものである。 NBA史上第2位の得点王のカールマローンは、選手の高齢化についてロサンゼルスタイムスにこう述べている。「体がいうことをきかなくなるのではなく、選手自身がこれ以上、限界に挑戦することをやめるだけだ」
0投稿日: 2017.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ[関連リンク] 才能という幻想、卓越へと至る道 Honkure: http://honkure.net/rbook/archives/1035
0投稿日: 2016.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功するためには、才能よりも正しい努力を積み重ねること。 究極の鍛錬の要素とは ①実績向上のために特別に考案されている ②何度も繰り返し返すことができる ③結果のフィードバックが、継続的にある。 ④精神的にはとても辛い ⑤あまりおもしろくない 自分が選んだ分野で達人になろうと大きな投資を行うこと、より熟達した指導者を求めること、学びのなくなってしまうコンフォートゾーンを抜け出すために自分を常に追い込むこと、常に自己の限界に挑戦すること。 根性論ではなく、本当に努力する意義が 書いてある。
0投稿日: 2016.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ究極の鍛錬は苦しくてつらい、しかし効果がある。究極の鍛錬を積めばパフォーマンスが高まり、死ぬほど繰り返せば偉業につながる。 卓越した能力をもたらすのは経験ではない。長年取り組んでいることでたいした業績を上げず経験だけは豊富な人が周囲に多くいるし、実際に多くの分野で何年にもわたり携わっていることでむしろ能力が下がっている人がいるという証拠もあるからだ。
0投稿日: 2016.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ●読むキッカケ ・意志力系の本を読み漁ろうとした流れで読んだ記憶。 ●サマリー ・努力が重要であるのは自明だが、その努力の仕方にも工夫をしましょうねというお話。 ・スポーツなんかでは、意識しやすいけど、 ビジネスの現場においてそれをいかにやるのかが、きっと難しいし、 その課題と対処方法がわかると嬉しいんだけどなあ。 ・少なからず、得たいものを人や本によって設定し、 その出来ている状態をイメージする。 そんで、振り返りをして、それができているかを確認し、 出来ていなければ修正してまたやってみる。 まあ、無理くりPDCAを回していくということ、 そして、そのPDCAを回すということにおいても、 PDCAを回すと良いのだろうなあとは思う。 ●ネクストアクション ・自分の毎日の振り返りを、もっと洗練させれないかを考えてみる。 −恐らく、目標があんまりイケてない、というかマインドに寄りすぎているので、 スキル面に寄せることを考える。 ・コーチを見つけるなり、上長を見つけるなりして、成長環境を構築するようにすること。 ●メモ ・成果を出す上では、才能よりも、鍛錬(努力)が重要であると述べていた気がする。 ・究極の鍛錬には以下の5つの要素が必要である ①実績向上のために特別に考案されていること ・無為な努力を積むのではなく、目標の達成に結びつくものであるべきこと ・コンフォートゾーンではなく、ラーニングゾーンであるような努力を行うこと ②何度も繰り返すことが出来るものであること ・量×質のうち、量も一定量必要だということ ③結果へのフィードバックが継続的にあるもの ・カーテンが垂れ下がった状態でボーリングをしても、一向に上手くならないのと同じこと ④精神的にはとてもつらいものであること ・集中が求められるから ・出来ない現状を正しく認識し、そこから改善の努力を行う必要があるから ⑤あまりおもしろくない ・上記と同じ理由であると思って良さそうだ ・結果ではなく、結果に至るプロセスに注目し、それを改善するように心がける ●WEB記事から引用 ・ 私の考えでは「ビジネスパーソンの訓練」は日本社会での合意事項ではないと思う。おそらく特定の企業ではそういった訓練を意識しているところもあるだろう。そういう環境に身を置くことができれば、徐々に力を付けることができる。そういった企業に身を置かない場合は、自分で自分を鍛えるか、トレーナーをつけるしかない。 大抵の企業は、仕事に関する簡単な知識を伝え、あとは現場で覚えていくしかない。「習うより慣れろ」だ。それはゴルフを始めたばかりの初心者に、クラブセットとボールを与え、「じゃあ、ホール回ってきて。アンダーパーで」と言っているのに等しい。確かにホールを回る中でしか得られない経験はたくさんある。そういったOJT的トレーニングは否定しない。ただ問題はその中に「どうやって訓練すればいいのか」という示唆がまったく含まれていないことだ。 結局、見よう見まねでホールを回ることができるようになっても、その次の一手がまったく見つからない。結局できることと言えば、そのホールを周り続けることだけだ。そして「そのホールだけが異様に得意な人」ができあがる。それはつまり、「転職したくてもできない人」ということだ。会社と個人とが会社人生を前提とした付き合い方をしているならば、それでよいのかもしれない。しかし、現代はどうみてもそんな環境にはない。 結局、訓練のやり方を教えない企業に入った人は、自分自身で自分を鍛えるしかない。あるいはまったく別の所にアドバイスを求めるしかない。もし、あなたの身の回りに「有益なアドバイスをくれる先輩」というものがいるならば、それは大変ありがたい存在と考えた方がよい。そういうのは探してもなかなか見つからない。 今ビジネス書に注目が集まっているのも、先ほど指摘したような環境があるからだろう。しかし、ビジネス書の中で語られている部分の多くが「どうやって仕事をするか」である。それは、7番ホール第二打目の打ち方、のようなものだ。あるいは、3番ウッドの効率よい使い方だ。ぎりぎりでアイアンの上達法といったところ(本当に上達するかは不明だが)。 こういう状況では、スポーツ界のようなレベルの向上は望めない。日本のホワイトカラーを見回してみても、それは悲しいくらいに現実だ。それは「誰が悪い」という話ではない。基本的に「ビジネスパーソンには訓練が必要」という感覚が欠落しているのだろう。 しかし、ノマド社会、ギルド社会的な中での「職人としてのビジネスパーソン」には絶対的に訓練は欠かせないものだ。少なくとも、どのような業界でも「プロ」と呼ばれている人たちは生き残りをかけて必至に自らの技量を鍛え上げている。
0投稿日: 2016.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログすっごい面白かった。これは個人的には超おすすめです。どんな分野でも達人を目指す人なら読んでおいて損はないでしょう。これは今年読んだうちのベスト3に入ります。
0投稿日: 2015.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ上手くいかないことを意識する 他責ではなく、自責と捉えて改善に取り組む ・効率 特別に考案された方法を実施すること 何度も繰り返し実施できること 鍛錬したらフィードバックをえる、もらうこと ・時間 能力を得るための代償を払うこと
0投稿日: 2014.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
優秀かそうではないか、成果を出すか出さないかを分けるのは、才能ではない。生後の環境や努力によるものである。その努力には、単にやり続けるだけではなく、究極の鍛錬が必要である。では、つらく面白みのない究極の鍛錬を続けられる人は、なぜ続けられるのか?とう問いまでつきつめて検討されている。 究極の鍛錬とは・・・ ①実績向上のために特別に考案されている ②何度も繰り返すことができる ③結果に関し継続的にFBを受けることができる ④精神的にはとてもつらい ⑤あまりおもしろくない 〈IQテストが測定するものがどんなものであろうとも、認知上複雑な形式を持つ他変量推量を行いうる能力をIQは測ることができない。この他変量推量という言葉は日常生活ではあまり使われる言葉ではないが、実際には職場での活動や一流だと言われる人の手際よい仕事ぶりを実に見事に表現しているものだ。物事を卓越して行うには、世間で言われているような意味で特に賢くある必要などないのだ〉 真に「できる人」というのをうまく言語化してくれている。そういう人間を育てることが必要なのに、どうしても旧来のやり方にしがみついているケースが非常に多いと感じる。 究極の鍛錬を行うと、性格のいつ部を変えることもでき、先天的な性格に制約を受けることはない。
0投稿日: 2014.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ1、しばしば教師の手を借り、実績向上のため特別に考案されている。 2、何度も繰り返すことができる。 3、結果に関し継続的にフィードバックを受けることができる。 4、精神的にはとてもつらい 5、あまりおもしろくない 達人になるために 1、自分が選んだ分野で達人になろうと大きな投資を行うこと。 2、より熟達した指導者を求めること 3、学びのなくなってしまうコンフォートゾーンを抜け出すために自分を常に追い込むこと、自己の限界に挑戦すること チクセントミハイ教授の提唱する有名な「フロー」という概念は、人が仕事に完全に熱中すると時間がゆっくり流れるように感じ、喜びが高まりほとんど苦痛がなくなる心理状況を指す。この心理的に「ハイ」になる状況は、取り組んでいる課題がその人の技能にマッチしているときに発生する。
0投稿日: 2014.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ価値観が変わる本。 厳しさや辛さが必要なことだと知ることができた。 続けることが才能とよく聞くけど、本当だった。 なおさら自分に言い訳ができなくなった。(笑)
0投稿日: 2014.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ天才、と言われるアスリートや音楽家、ビジネスマンなどは、持って生まれた資質を最大限伸ばすために、とにかく長時間かけて鍛錬した結果、そうなったわけで、いきなり天才になったわけではないということ。 人生限られた時間の中で、才能を開花させるかは、それにかけた時間や努力によるものだということが、わかった。 遺伝に関する本も読んだが、タイガーウッズやモーツァルトは親による、遺伝的な強み資質の猛烈な教育の成果であり、彼らが天才として生まれたからではない、ということなのでしょう。 親の得意なことは、少なからず子供にも遺伝するわけで、自分の強みを知っている親からの教育は、かけられる時間が多い幼い頃からのスタートし、大人になる頃には、それが天才的と思われる形で現れる、ということなのでしょう。 自分自身の強みを理解し、今からでも猛烈にそれに時間をかけることで、天才的な形でいつか現れるのでしょうか?まず、猛烈に時間をかけるほどの時間、また体力があるのかわからないけど、何れにせよ、何かを成し遂げるために、努力と時間は必ず必要だということなのでしょう。 さぁ、天才にはならないかもしれないけど、身につけたいことは、今自分ができる究極の鍛錬をして行こう! 楽しかった、この本。
0投稿日: 2014.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ天才はこうしてつくられる/ Talent is overrated ― http://www.sunmark.co.jp/book_profile/detail.php?cmn_search_id=978-4-7631-3036-5
0投稿日: 2013.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ最も効果を生むトレーニング法についてのある種の究極の解答がここにある。 特定の技能に集中した特殊なトレーニングを、反復し、フィードバックを受けること。特殊なトレーニングの発見には優れた教師が必要で、トレーニングの精神的なつらさと面白くなさを堪えうる忍耐力が必要であると。 遺伝的要因に関する部分は今後の知見によって少し書き換えられるような気もするが、ここまで直球で切り込んだ本は珍しい。 個人的に、今後の観察研究を期待したい。
0投稿日: 2013.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
才能というものは幻想であって圧倒的な時間を積み重ねた適切な努力が大切だよっということを説いた本です。
0投稿日: 2013.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ才能よりも自分を信じてまさに鍛錬。それはつらい局面も多いが、自分を信じて鍛錬し続けていくべきなんだろう。それならやはり自分の好きなことをやるべきだ。私はいろいろと手を出しがちだが、取り組んでいることに飽きた時、それが更に上に行くことを望む活動であるならば、動機づけにまた読みたい。
0投稿日: 2013.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ才能は過大評価されがちで、偉人と呼ばれる人々はつまらないけど自分にとって必要な鍛錬を積み重ねたから素晴らしい業績を残している。つまり、適切な努力をコツコツしていれば、誰でも素晴らしい「才能」の持ち主になれるということがわかりました。
0投稿日: 2013.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界的偉業を成し遂げるのは、才能でも、生まれ持ったものでもなく、「努力」 並大抵でない努力がおもしろくない… そのおもしろくない努力の可否で 普通の人と世界的偉業を成し遂げる人に分かれる おもしろくない&途轍もない努力を継続するためには「好きなこと」をしてなくちゃいけないな〜!
1投稿日: 2013.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ指導者が設計した体系だった鍛錬メニュー、自分の弱点を繰り返し練習すること、その直後に受けるフィードバック、能力向上のため徐々に高くなる課題設定、けっして面白くない訓練内容。
0投稿日: 2012.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
生まれつきの才能だとかセンスを過大評価しすぎる、と著者 は指摘します。 ・天才と呼ばれる人は、皆、究極の鍛錬をひたすら愚直に 重ねている ・究極の鍛錬に必要な要素: ①教師の手により、特別に考案されたメニュー ②何度も繰り返し可能 ③継続的なフィードバック ④精神的にとても辛い ⑤あまり面白くない ・豊富な経験や知識を集積することは、力の源泉となる ・究極の鍛錬に耐えるためには、自分が何をやりたいのか を知ることが重要 ・すばらしい業績を上げる者は、自分は出来るという強い 強烈な信念を持ち、同時に努力は報われるという強い 信念を持つ ・創造するという営みは、通常思われているよりもずっと、 意図的な努力の結果である この本の本文の最後の一文、なかなかグッときます。以下に ご紹介。。。 確信を簡単に与えてくれるものなどない。トップレベルの 能力を入れる代償はとてつもなく大きく、そのためこうした 代償を支払う用意のある人が多くないのも当然だ。しかし、 同時に、少数ではあるものの、偉業を成し遂げた人たちの やり方を見習うことで、誰にとっても能力向上のチャンスが あることも事実だ。「偉大な業績」は、必ずしも神によって 事前に定められた人だけのものではない。「偉大な業績」 は誰でも手に入れることが出来るのだ。
0投稿日: 2012.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログジョフ・コルヴァン著、米田隆訳「究極の鍛錬」サンマーク出版(2010) いかに生きるか、いかに死ぬか。私たちは人生に2つの選択しかありません。本当に手に入れたいと思い、憧れているのに才能がないと簡単にあきらめてしまう人生で本当によいのでしょうか?著者は達人と素人の違いは特定の専門分野で一生上達するために考え抜いた努力をどれだけ行ったかの違いであると説いています。つまり自分の意識が自分の人生を決定していくのです。今からでも遅くありません。主因は内にあり!! *究極の鍛錬が有効に機能するには10年ルールといわれるような一定以上の累積訓練量が必要であると著者は記しています。人より早く始めることは有利となる一方で、卓越した水準を生涯にわたって維持するには継続が欠かせない。 *より少ない情報から多くを知る。どの分野でも少ない情報から多くを知るという能力は成功するには不可欠である。正しい意思決定を迅速かつ安価で行うことが出来ればどの分野でも競争で優位にたてる。達人は長期間にわたる究極の鍛錬を通じ、自分が専門とする分野でもっとも重要な意思決定を行うためにこの能力に磨きをかけている。 *もっとも業績のよい企業の多くが、一般的な経営脳虜おくよりはむしろ業界固有の知識を深くもつことが大切だと認めている。 *「知識が偉業に中心的な役割を果たしている」ということは「偉業は生まれつきの才能に基づく物である」という主張に対して理論上の深刻な問題を投げかけている。なぜならどんな分野でもはじめから膨大な知識をもってうまれてくる人間はいないからである。 *もっともすばらしい業績をあげるものは結果ではなく、結果に至るプロセスに目標をおく。重要なのは「態度」と「信念」である。つまり、1つの分野で達人になろうとすることは長くつらい仕事を成し遂げようとすることです。 *自分の問題を他人や他の偶然のせいにすることは達人はない。達人は容赦なく自分自身の実績を見ることに集中している。
0投稿日: 2011.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ今日のブックナビでこの本を紹介。過去にライブラリートークに出てた著者の渾身の書。事例がたくさん出てて面白い。これで貴殿も第二の横峯パパ?!
0投稿日: 2011.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「達人」になるための究極の鍛錬について書いてある。 達人を目指したい人には、必読でしょう。 原題は、Talent is overrated.才能は過剰評価されている。 つまり、達人になるのに、才能は関係ないと。 才能よりは、訓練しだい。 ただし、辛い訓練を長期間行ったものだけが達人になれる。 これは、「正しい訓練方法」を示した本。 マルコム・グラッドウェルの「天才! 成功する人々の法則」と比較できると思うが、実際に「天才」なり「達人」を目指したいならば、こちらの本の方が実践的。 内容は、理解したが、実践に近づけるためには、どこかでもう一度読もう。 2度読む価値がある本と認定します。 (2011/8/27 2回目、2012/3/5 3回目) ところで、三枝さんの本と一部シンクロするところがありました。 確か三枝さんの本では、(成長するために)「仮想的に失敗する」という表現でしたか。 目標を非常に具体的に、設定する。そして、そこからずれたら(他から見えたら失敗と思えなくても)自分では、失敗と思い、自ら結果のフィードバックを受けて、修正する。 この本によるとビジネスの達人は、みんなやっているらしい。 三枝さんの本では、失敗から学べるが、本当の失敗は、ビジネスでは、なかなかできないので、「失敗の疑似体験」ということを推奨していました。 ★めも ◆究極の鍛錬の要素 ①しばしば教師の手を借り、実績向上のために特別に考案されている。 ②何度も繰り返すことができる。 ③結果に関して継続的にフィードバックを受けることができる。 ④チェスやビジネスのように純粋に知的な活動であるか、スポーツのように肉体的な活動であるかにかかわらず、精神的にはとてもつらい ⑤しかも、あまりおもしろくもない。 ◆何が究極の鍛錬で何がそうでないか ・「結果に与えるもう一つの重要な要素は、どれだけ鍛錬に努力をつぎ込むかということだ。」 「単に練習時間を比較するのではなく、どれだけ熱心に練習に打ち込んだかも見ない限り本当のことはわからない。」 ・「自動化の回避が究極の鍛錬を継続することの一つの効果。自分がうまくできない点を絶えず意識しながら練習するという鍛錬の本質から、自動化に基づく行動をとることが不可能となる。」 ◆究極の鍛錬はどのように作用するのか ・「具体的には、普通の人に比べより良く認識し、より良く知り、より多く記憶できるようになることだ」 ・「他人が気づかない細かな差異がわかるということは、もう一つの物事をより多く認識することができる力だ。」 ・「知識にこそ、力の源泉がある」 「もっとも業績のよい企業の多くが、一般的な経営能力よりはむしろ業界固有の知識を深く持つことが大切だと認めている」 ・「達人は自分の専門分野を深く理解し、身につけていく莫大な量の情報を次々と長期記憶として思えられる情報引き出し構造を手に入れているのだ」 ◆究極の鍛錬を日常に応用する ・「仕事自体を訓練の場にしてしまう」 ・「もっと素晴らしい業績を上げるものは、結果ではなく、結果に至るプロセスを目標に置く」 ・「最も素晴らしい業績を上げている者たちは、研究者が自己有能感(自分は出来るのだという感覚)と呼ぶ強い強烈な信念を持って仕事に臨んでおり、同時に努力は報われるという強い信念を持っている。」 ・「自分の精神で自分の身に今何が起こっているかを客観的に観察し、どのようになっていくのか自分自身に尋ねている。つまり自分自身に関して知り、自分に関することを考える」 ◆革命的なアイデアを生み出す ・「自分が選んだ分野で達人になろうと大きな投資を行うこと、より熟達した指導者を求めること、学びのなくなってしまうコンフォートゾーンを抜け出すために自分を常に追い込むこと、常に自分の限界に挑戦することである。」 ◆どんな家庭環境が良いのか ・「他者よりも秀でる、全力を尽くす、懸命に努力する、時間を建設的に使う、ということが何度も何度も強調されていた」 ・「家庭環境は刺激を促すもので、両親は小さい頃から子供の好奇心を促し、子供の質問に大変丁寧に答えていた。」 ◆情熱はどこからやってくるのか ・乗数効果= 「ある分野で偶然起こったちょっとした優位性が、一連の出来事を生み出し、それがのちにはるかに大きな優位性につながっていく」 ■メモ追記:マーケティング鍛錬 繰り返すこと、フィードバックがあること、ラーニングゾーンであること。体系的知識 ・マーケティング基本本を再読含めて読む ・フェースブック、ブログでまとめる ・事前に計画する、判断をめも、結果フィードバックをみる
0投稿日: 2011.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ究極の鍛錬には次の5要素がある。 1、実績向上のために特別に考案されている 2、何度も繰り返すことができる 3、結果へのフィードバックが継続的にある 4、精神的にはとても辛い 5、あまり面白くない ま、最後二つは置いといて。 1~3までは、その通りなんだろうな。P&Gの人材開発と同じこと言ってる。 自分で全部できるのが理想的だけど、「有能なコーチがいる環境」も大切な気がする。キャリア、悩みますね。
0投稿日: 2011.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ量は全てを凌駕する - 究極の鍛錬法 - 読んだものまとめブログ http://t.co/Y48zD0
0投稿日: 2011.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ偉大な業績を上げるのは生まれつきの才能ではなく、究極の鍛錬と著者が呼ぶ鍛錬法にある。天才と呼ばれている偉人達も広く信じられているような超人的な能力を生まれつき持っていた訳ではなく、早い年齢からの累計練習時間によるものだという説は、神がかった天賦で片付けられてしまうより希望が持てる。しかし実際に究極の鍛錬を行える人はごく少数なのだろうというのにも読んでいて納得した。
0投稿日: 2010.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ何かを極めるには早く始めること。 そして、環境、先生、適切なフィードバック、つまらなくて辛いけどそれをいかに継続して内部動機・外部動機を保って続けることが大事と解いている。 ビジネスに応用したい。。
1投稿日: 2010.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書のポイントは、究極の鍛錬に対する定義であろう。その中でも特に重要なのは、「究極の鍛錬はつまらないし、つらい。」ということだと思う。 楽しむことが一番大事という言葉が過大に評価されている現状で、一番有効なことはつまらないということをはっきり主張している本書は評価されるべきと感じた。
0投稿日: 2010.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ研究の参考にもなるかも!? 『天才!』とかにもでてきたけど、基本的に鍛錬の絶対時間がかなり大事だよ、という話。 ただしその内容に関しても注釈がある。(全部は忘れてしまったが) 1)優秀な教師などによって作られた体系られたもの 2)反復できるもの 3)フィードバックを素早く得られるもの 4)精神的にツライもの 5)基本的に楽しくはない だいたいこんな感じ。考えさせられる。。。
0投稿日: 2010.05.02
