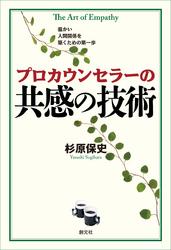
総合評価
(31件)| 15 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ「共感」 世間一般で言われているものと違った。 真剣に相手に向き合って携わるから 言葉にされないものを聞き取って通訳することができる。 言葉の整理、表現力を言葉にアウトプットをしていくので、ある意味才能でもあるなと思った
0投稿日: 2025.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログまさか共感に関する本でメメントモリが出て来るとは。 大好きな言葉です。 自分にとって共感というものを学ぶ以上の様々な大切なことに気付かせてくれる本です。 きっと今後、何度も読み返すと思います。
0投稿日: 2025.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
①Information (客観的な情報) 多くの人が「共感されたい」と思いつつ「絶対共感されたくない」という側面を持っている その人にしか分からない、分かり合えない領域がある前提で一体となろうとする営みが「共感」である 考えるな!感じろ! → 一生懸命聴いていても、聴き手の頭の中で何かを「考えて」いて、自分が「感じて」いることに注意を払っていなければ共感と言えない →とにかく「自我」を捨てて、相手の表情や姿勢、声色、視線の投げ方をひたすらに感じる →話の内容ばかりに気を取られるな、機微の変化も察してFBしてあげると気づきにつながる アイコンタクト、話す前の「間」、呼吸で集中力を整えることを意識する 時には相手を「信じて」、自分の胸中を思い切って伝えてみる 愚痴を聞く際は、相手の気持ちにフォーカスしてあげる →その時どんな風に感じたんですか?どんな気持ちだったんですか? 共感を「拒絶」された時の返し方 →あなたの辛さは誰にも分からないね、共感できないのかもしれないね 負の感情そのものに害はない、むしろ負の感情による被害を妄想して、逃げ続ける方が破滅を招く →感情の体験を避けることが、結局はその感情を増幅させる悪循環になってしまう 鸚鵡返しの上位互換 →もう頑張れない〜限界まで頑張ってきたんだね →いい加減なまま辞めて良いのか〜辞めてしまいたい気持ちなんですね ②Insight(〜かもしれない、〜なはずだ) 共感と、「相手に寄り添った気になって満足する」は紙一重なのかもしれない 互いに独立した生き物だからこそ、無理に交わろうとするのではなく「存在承認」から始めるのが、相手の心を開く一歩になるはずだ ③Intelligence (学びや改善点、ネクストアクション) 上記学びをコーチングや家族恋人との会話で実践する
0投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ平易な優しい言葉で書かれていて、文章の感じがとても好きでした。 共感しすぎてしまう時についての章が、今の自分にとって、とても参考になりました。 高齢だったり、困難な状況で支援につながる方の書類を毎日見たり、聞いたりしていると、私も人ごとではないので、その人になった気がして、その一番苦しい箇所で共感して、ぐっと固着してしまう、そういう毎日があったのですが、文を読んでいて、少し視点が広がり、呼吸が深く安心する感じがしました。 また、認知行動療法を自分でやる時の、見方の広がりの参考にもなりました。 折にふれて、読み返したいです。
4投稿日: 2023.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログプロのカウンセラーの共感の技術】 教師や子どもと関わったり人と関わったりするすべての人に必須の本です。 私が、誰かと話をしていて「残念だな」というか「悔しい」と思うのが、 しゃべっている時に話を遮られたり、 「それ違う」と否定されることです。 あるいは、 自分の課題に入ってこられて、「つまりそれってこういうことだよね。こうするべきなんじゃない」と頼んでもいないのに解決されようとすること。 全て「善意」なのかもしれませんが、 それをされるとカチンとくる。 絶望的な気分になる。 それは、自分の話を聞かれていないというか、受け止められていないんだな、というふうに感じて哀しいわけです。 抜けない釘が心に刺さったみたいないやーな感じが続き、 イライラが治らず、 心の中で相手を裁いてしまっている心の狭い自分に対しても自己嫌悪が続き、、、となる。 「どうせわかってくれない」。 ここまで書いて、 「うわーーー!これやっちゃってる!自分やわ!」 と思い当たっている方もいるかと思いますが、 そこはどうか自分をお責めにならないでください。 これって、練習と技術でかなりうまくいくものなのです。 結局、問題のヘッドピンはどこか、人が一番求めているのは何かというと、 「共感してもらえること」なのです。 「受容してもらうこと」なのです。 「ジャッジせず、価値判断を交えずに受け止めてもらいたい。」 答えを出してもらえるとか、問題を解決してもらうことは、その後なんですね。 というよりも、「心から受け止められた」と感じることから自動的に変化、変容は始まっていきます。 そのための技術の一つとして、 「ミラーリング」というものを紹介させていただきたいと思います。 例えば、ある人が「もう限界」と言ってきた時に、どう返すか。 「頑張れよ」と励ましたり、 「どうして?」と聞いたり、 「いやいやそんなことないよ。大丈夫」と言ったり、 「そんなこと言っちゃダメだよ」と責める人もあるかもしれません。 それらの反応とは異なり、 「もう限界なんだね」とそのまま反射で返す、ということです。 もちろん単なるおうむ返しではなく、 聴き手は、余分な方向づけをせず、話し手が表現したことを足場にしてさらにそこから表現を発展させるように促しているのです。 ◆ ひょっとすると現代人の多くの孤独や悩み苦しみの淵源にはこの 「共感」の欠如が横たわっているのではないでしょうか。 「どうせ誰も自分のことなんかわかってくれない」が満ち溢れている。 伝えてばっかりで、コントロールしようとしがちで、 存在をそのまま受容できない。じっくり受け止められない。 そこから人と人とのほつれが始まり、断絶に至る。 もし、私たちが少しでも、この「共感」と「受容」という態度を身につけるだけで、あらゆることが変化していくのではないでしょうか。
2投稿日: 2023.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
関わって感じ表現する 相手に巻き込まれて感じ表現する 関わりと観察のバランス 共感とは自分と相手との協会があいまいになる いつか死ぬことわかってるひと共感たかい 苦しみはわけ会えば半分、喜びはわけ会えば倍になる 共に喜ぶこと共に楽しむこと、ともにわらうこと 青年にとって、恐さを共感してくれた上で、その恐さをどう乗り越えていくかを一緒に考えてくれる人が必要なのです。共感は、その作業のための必須の礎石となるものではありますが、その作業に代わるものではありません。
1投稿日: 2022.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログどんな悩みであっても、それが語られるとき、そこで求められているのは相手からの共感です。そういう意味では、すべての悩みはどれも同じであると言えます。悩み相談において最も重要なのは共感であると言われるゆえんです。 現代人は孤独だと言われます。コミニュティが崩壊し、社会はバラバラな個人の寄せ集めになってしまいました。もはや隣人がどんな人物で、何をしているかも知らないし、関心もない、というのが当たり前の社会です。ですから、現代人はみな孤独であり、孤独を癒したいという願望を抱いているはずです。誰かとつながりを感じたいと願っているはずです。
0投稿日: 2022.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ共感というテーマに絞られており、細かな技法が沢山提供されるのがよかった。 たとえば反射のやり方にもさまざまなパターンがあるというのはとても示唆的で、そのような細かな掘り下げはカウンセリング的な対話術全般を扱う類書には見られないものだった。 また、自分の精神と向き合う際のやり方についての言及も散見された。こちらは、思い悩んでいる依頼者へのアドバイスとして直裁的に役にたつだろう。 読了してよかった。
4投稿日: 2021.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ他人に共感する技術について書かれたものですが、自分への共感も大事なんだなと気付かされます。他人に対しても自分に対しても、共感は、同じ空間にいることを全身で感じるものということも、大事だということ。とするとコロナ禍という同じ空間にはいない中で、今後はどんなふうな共感ができるのかな、とも思いました。
1投稿日: 2021.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
共感とは、ということについてとても詳しく書かれている。対人サービス職、マネジメント層の人は1度読んでおくと良いかも。 memo 共感は、「人と人とが関わり合い、互いに影響し合うプロセス」のこと。互いの心の響き合いを感じながら関わっていくプロセスであり、それを促進していくための注意の向け方や表現のあり方などを指すものである。 共感は「感じたままに受け取る」で終わるのではなく、感じられたものは〝表現される、伝えられる〟必要がある。 誰かに共感するためには〝観察力〟〝想像力〟〝注意のコントロール力〟〝表現力〟が必要。 本人にしか解決できないことだから、一人で取り組ませておけ、というのはあまりに冷酷な姿勢。一人ではできないことを、一緒に考えてくれる人が必要なのです。(=カウンセラーの役割)
0投稿日: 2021.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
p46 あなたは共感しようと努力する必要は少しもありません。ただ、いつの間にか共感している自分に気がつくだけです。 p56 誰かに共感するためには… 観察力、想像力、注意のコントロール力、表現力 p62 価値判断を留保した態度で、そのままに、ありのままに受けとめる態度が受容であり、そこで感じられることに注意を向けて感じ取ることが共感なのです。 p108 葛藤の両面をつなぐときに、そして、それと同時に、その一方でといった接続詞を使ってその二つを穏やかな関係でつなぐ。コメント全体を穏やかな声で言う。 p155 自分の気持ちに注意を向けることをしない習慣を長年にわたって発展させてきた人の場合、単にそのときあなたはどんな風に感じましたか?という質問をシンプルに尋ねるだけでは、いったいなにを尋ねられているのか、質問の意図がピンときてないことが多い。 p178 悪意のある話の背後に、必ず傷つきの体験があると保証できるわけではありませんが、私の経験からはしばしばそうだと言えます。悪意そのものよりも、その悪意の背後にそうした傷つきが感じられるかどうかがら、その人と共感を深めていけるかどうかの重要な分かれ目だと思います。 p185 率直に謝ることは強さであり、それ自体が大切な教育です。 p186 共感があからさまに失敗したこうした最悪の瞬間を修復する作業が、共感を深めます。共感は、「共感の傷つき」を共感自体で癒し、それによって太く育つのです。
0投稿日: 2020.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ価値観が多様化し、1つ1つの価値観の重要性が相対的に薄れていく現代でこそ、『自分の価値観を明確にした上で、価値判断を含まない関わり方』をする重要性が際立つのではないでしょうか。もし人々が、自分の価値観が大切だという世論を持っていなければ、自分たちを導いてくれる答えを求めるように感じます。 「ある一定の価値観によって、啓蒙されない状況」つまり、「1つ1つの価値観が尊重される状況」に対して、自分がどのように感じるかに敏感になるところから、始めようと思います。
1投稿日: 2020.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ共感とは何かを、心理学の学問としての説明から、実際どうやってするかを例を挙げて説明しています。 実際共感に問題を感じている方の対処法の本です。
0投稿日: 2019.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【気になった場所】 共感には感受性が必要 ・相手の気持ちを感じる感受性 ・自分の心を感じる感受性 共感とは →人と人とが関わり合い、互いに影響し合うプロセス →相手とまったく同じ気持ちになる必要はない 例) 男性の自殺率が女性の2倍である理由 →人に気持ちを打ち明けない傾向が強いため →心理相談やメンタルヘルスの相談に自発的に現れることが少ない 共感の手順 ・感じていることに注意を向ける ・相手の立場に立ち、価値判断抜きの態度で感じる ・共感する気持ちを表現する 共感は訓練や経験によって開発できる 共感に必要な能力 =観察力+想像力+表現力(+忍耐力) 反射≠オウム返し →相手の気持ちをそのまま繰り返すこと 共感に対する誤解 ・相手の気持ちをピタリと当てる必要はない →相手の気持ちを感じたままに伝えること ・相手の話を遮っても良いことがある →相手との間に十分な間を設けること ・相手の気持ちに賛同できなくても良い →相手に共感できないと感じることが重要 深い共感とは →相手が言葉にできないことを聴き取ること →相手の振る舞いから違和感を感じ取る 例) 特徴的な言葉の選び方、不自然に力みのある考え方、声、姿勢、視線、態度や素振り等 相槌の打ち方 ・相手の声の調子に合わせる →相手の声のトーンに注意を向ける 建設的な愚痴の聞き方 ・まずは話を聴いてあげる ・その時に相手がどう感じたかを尋ねる →回答が曖昧なら、さらに相手の気持ちを深掘ってみる →自分の気持ちに注意を向けていない人は多い 家族への共感は難しい理由 →家族に無自覚のままに共有している不自然で無理のある暗黙の了解が、家族に苦しみやストレスをもたらし、互いへの共感を妨げる
0投稿日: 2019.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
近しい関係の方がとても悩み苦しんでいます。その方が私に苦しみを話してくれた時に、少しでもその方の力になれたらと思って、この本を手に取りました。 悩み苦しんでいる人の話を聞いた時に、自分の経験したことのない程の苦しい物事だった場合、私は、その人の本当の気持ちを心から理解して寄り添うことがとても難しいと感じます。自分の発する言葉がとても安易に感じてしまい、自分の非力を感じ悩んでしまう事もありました。 以下、とても参考になりました。 -誰かと共感的なコミュニケーションを取ると決めたならその時間はただ相手の気持ちを受け止めることだけをするように心がけます -人は基本的に物事を自分中心に考えてしまいます。共感的なコミュニケーションをすると決めたなら、相手中心に考えるのです。相手の気持ちを感じとるのです。 -自分の意見は脇に置きます。共感できない自分の思いは放っておく心構えが必要です。自分自身の評価や気持ちから離れるのです。 -その人のありのままを「受容」し「共感」し「変化促進」を促します。 -正解のない道のりです。結局自分で答えを出すしかありません。それを踏まえた上で一緒に悩んでくれ、孤独な道のりを共に歩んでくれる人が、悩んでいる人には必要なのです。 -「反射」の受け応え。悲しいんです、に対して、悲しいんだね、と返すことで、悩んでいる人はさらに発展させて話すことができます。 -悩んでいる人の、まだ話していないこと、話せないでいることを聴く方がもっと大事です。声、視線、姿勢などにおぼろげに現れた影に、気づき、言葉を与えること、それが深い共感です。 -相づちは調子を合わせる行為です。ダンスのステップを踏むように。 -人は常に矛盾や葛藤を抱えて生きています。また、人の気持ちは時間とともに変化します。性急に白黒つけようとしてはいけません。悩んでいる人が持つ、葛藤や相反する気持ちがある辛さを共感し受容するのです。 学ぶことの多い本でした。 最後に。一番大事なことは、相手を信じきること。悩んでいる人のありのままを信じきること。だと思いました。 実践できる人間でありたいと思いました。
0投稿日: 2019.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ冒頭から心に刺さることがずばり書かれていた。 「多くの人は、共感とは相手の感じているのと同じ感情を具体的にそっくりそのまま感じることだと考えています。…多くの人は、共感をこのように定義づけた上で、「共感なんて本当にできるのか?」という問いをくり返しくり返し、問いかけ続けます。」 私がこの本を手に取ったきっかけは、友人に何気なく「カウンセラーに向いてそう」と言われたからだ。それと同時に、日頃から「共感」を上の「多くの人」と同じように定義づけていたため、自分が人に共感するなんてできっこないと思っていた。あらためて共感とは、心理カウンセラーとはどんなものなのか知るために本書を読んでみた。 著者は現職のカウンセラーで、説明のための実例も書かれており読みやすい。 医者は体の不調は治せるが、心のわだかまりについてはそこでは置き去りにされる。法律の問題でもそうだ。弁護士は法律の専門家ではあるが、法的な争いにおける心理的なケアまでは行わないだろう。身体的な問題であれ法律的な問題であれ、人間には心の問題というのが同時につきまとう。むしろ、心理的な問題を解決することで前向きな行動をすることができ、心理的ではない問題を乗り越えることもできる。そうした心理的ケアのひとつとして、「共感的な関わり」は欠かせないものである。 心理学については河合隼雄の著作を読んだことはある。大学で精神分析入門の講義を履修したこともある。しかしそれらはいわゆる「学問」の領域で、実際に目の前の人間と対峙するようなものではなかった。学問としての心理学も非常に興味深いのだが、こうした実践的な内容も実に面白かった。 カウンセリングの実例の中で、ふとクライアントの苦痛の核が見える瞬間が、大袈裟かもしれないが感動的だ。傷ついた人間が再び前を向く瞬間は美しく、小説や映画の中では物語のクライマックスにもなるだろう。それを体験できるカウンセラーに憧れを感じた。もちろんその過程には色々な試練があるのだろうが。 私はカウンセラーではないけれども、日常の気軽な会話の中でも共感的に人と関わってみたい。知識として理解するだけではなく、体験して実感したい、そう思った。
0投稿日: 2019.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ文字通り、プロカウンセラーの共感の技術について書いた一冊。 共感について深く知ることができた。
1投稿日: 2019.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ受容と共感、そして変化促進 話し手に寄り添い、受け容れ感じる。自分の思いは棚上げにして相手の思うことを感じ取る。 一言難しい。
1投稿日: 2019.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ共感することは大切だけど、「わかってる」とは言うべきではない。相手が欲しい言葉を観察することで発見し、さらに相手が気づいていない言葉を引き出す方法が書かれていてとても興味深い。しかし当然ながら難しく、おそらくそれを生業としている人じゃないとコツは掴めないかなぁと思った。
0投稿日: 2019.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログどこがいい、と表すのが難しいのだけれど、読んでよかったなあと思える本。一般向けで平易に書くことを心掛けられているとよくわかる。もちろん専門職にも役立つ。 内容をかいつまむと ・「寂しいんですか?」と「淋しいんですね」はまったく違う ・共感しすぎるというのは、共感の焦点が固定していること ・共感は自然のままでは進歩せず、ありのままの反応を放出するよりは共感的なふりをする(模倣する)こと。そこからはじめられるものがある ・共感できないときはそれを認める。自分も相手も責めない、そのうえでどうかかわるかを考える ・病気や孤独の受容は共感能力を高める というあたりが印象的
0投稿日: 2018.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログただ聞くのではなく、話し手の発言の裏にある意図とか気持ちの部分に注目するのは、大事だけどなかなかすぐにはできないと思う。 反射の技術もあらゆる表現を持っているとすごく有効な気がした。
0投稿日: 2017.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ★★★★傾聴するときにどんな言葉を発して何は言わない方がよいのか。ただ聴くだけでなく受容して行動変容を起こさせるには。考えずに感じることなど、共感の方法について細かく深く、具体的に書かれている。実践していきたい。
1投稿日: 2017.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログうつ病からの寛解を勝ち取った今、願っていることがある。 この経験を人のため、社会のために活かしたいということだ。それには、病気に対するきちんとした知識を身につけたい、と思っている。 リワークプログラムに通っている時にある心理士のスタッフから言われた。 「皆さん方は、下手な医者や心理士より、メンタルヘルスについての専門家です。病気の辛さと回復する感覚を、実感として持っているから」 題名にある「技術」という表現は、誤解を招くかもしれない。しかし、きちんとした「技術」なく対話の現場に出れば、大火傷をしてしまう。 共感とは、優しい癒しのイメージで捉えらがち。しかし、それは勇気の挑戦であり、一種の賭けでもあると著者は語る。 疲れるし、エネルギーも使う。 だからこそ、報われた時の喜びも大きいのだと。 「苦しみは分け合えば半分になり、喜びは分け合えば倍になる」 心は工なる画師の如し。 対話によって、共感によって、自身を見つめ、心を通わせる。 多くの現場を踏んできた著者のわかりやすい具体例の数々。 知恵は現場にあり、だ。
6投稿日: 2017.01.30人は人との関わりで傷つき、人との関わりで癒される・・・
リストラされた社員はリストラの現実よりも「その時の言われ方」にショックを受ける事が多い。無理矢理に共感を押し殺し厳しい内容を伝えている上司もリストラされなかった社員も皆が傷ついている。自分の淋しさや弱さ、人間としての限界をしっかり受け容れている人は共感する能力が高い。カウンセリングの現場での話しばかりでなく実際の身近な話題も多くわかり易い内容。共感を伴わないコミュニケーションは怖いと思った。まさに、人は人との関わりで傷つき、人との関わりで癒されるのです。 ===再読===前回、42の項目を一気に読んだことで矛盾を感じる点もあったので読み直した。しかし【人間の矛盾】についてもきちんと本書は解説していた。そもそも人間の欲求や願望には二面性がある。そして時間の経過と共に変化する。白黒つけようとしないで受容すれば良いのだ。多くの人は共感されたいのと同時に絶対共感されたくないと思っている。簡単に分かるわなどと言ってもらいたくないのだ。分からないという気持ちをありのままに感じて逃げ腰にならずに関り互いに影響しあうプロセスが共感なのだ。白黒つけようとして読んで矛盾したのであった。
0投稿日: 2017.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ現役のカウンセラーによるもの。 全体的にホワホワとしていて感覚的に書かれたように私には思えて、ハウツー本的なものなのに不思議な本だった。 考えずに感じること、価値判断しないでただ受けとめること、等々もやもやすることが書いてありました。たとえばカウセリングをしている人はこれを読んで「そうそう!」って思えるのだろうか?と疑問に思った。私は今まで、それだけ共感が何であるか知らずに人とコミュニケーションして来たのか…と考えた。(あ、ここでも感じないで考えてる?) 上記のもやもやポイントは、私にとって理解しにくいことであるのと同時に「なるほど」ポイントでもあって、他にも「カウンセラーは人の話を聞いておうむ返しの相槌をするだけ、というのは実際には違う。話を聞きながら『反射』はするが、単純なおうむ返しとは異なる。」という部分が特におもしろかった。 これだけ読むと「?」と意味がよくわからないが、著者の例によれば、「もう頑張れない」という人に対して「もう頑張れないんですね」と単におうむ返しで応じるのではなくて、「限界まで頑張ったんですね」と返すのがカウンセラーの反射らしい。 この人の言った「もう頑張れない」という言葉は、「限界まで頑張った。(=だからもう頑張れない)」というのと同じ意味、だということだそう。この括弧内の言語化されていない部分を感じとって、言語化して返すのがカウンセラーの共感と反射というわけで。共感の意味がなんとなく理解できてきたような感じがしましたまる
0投稿日: 2016.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016/3/15 ・当たり障りのない相槌だけでは、「そのカウンセラー」に話を聞いてもらう意味はなくなる。 ・「聴く」だけではなく、その間に「よく観察する」ことが大切 ・Aさんの行動に対するBさんの愚痴を聞くときは、Aさんの行動ではなくBさんの気持ちを描写してもらう 言葉は心の遣いだなぁ。
0投稿日: 2016.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の気持ちを素直に感じること。自分の意見は脇に置いておいて、相手の気持ちを受け取るように聞く。 おかしいなどと価値判断をしない。葛藤の両面に触れる。共感の気持ちを表現するなどということが書かれていた。
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2015年の56冊目です。 相手に共感することを、自分の信条としていました。 特に、女性の話を聞く時は、共感を心がけようとしていました。その共感とは、相手の感情に同意するというレベルだったと思います。相手「凄く、苦しかったです」。私、「そうか、それは、苦しかったですね」。相手と同じ感情を抱くといえば、少し高度な感じがしますが、それが私の理解している共感でした。 しかし、著者は、共感は個人の境界を超えることだと定義しています。境界を超え、響き合うことだと述べています。 本のタイトルからしたら共感のKnowhowが並べてあると思いましたが、そのような表面的なことはほとんどなく、そこからさらに踏み込んだ経験的考察による考え方が説明されています。カウンセラーが良く行う「オウム返し」(悲しいよ。悲しいんですねみたいな感じ)=反射にも、多様なバリエーションがあり、相手の状況を観察して、自分から何かを付けたすことが無い範囲で、具体的な反応をすることも反射の一つとしています。まさにプロカウンセラーの言葉だと納得できました。
1投稿日: 2015.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログプロのカウンセラーが日々の仕事の中で得た知見を分かりやすく開陳してくれた貴重な本である。 カウンセリングで大事なのは、傾聴と変化である。結果と言い換えてもいい変化を意識しすぎると、傾聴による信頼関係が弱くなり結局変化しないという結果になりがちである。そういう豊富な事例からTIPSとしてまとめたのが本書である。 また、相手に共感しすぎていると見えることも、ある狭い範囲に固定して共感しているに過ぎない場合が多い、という知見はハッとさせられた。共依存もそうだが、視野狭窄になってしまうと変化しにくくなる。しっかりと共感をした上で、立ち位置を変えてより広い範囲を見ることで別の解決方法も見えてくる。これがカウンセリングの本質なのだろう。 人間関係苦手だとする人、なぜか人間関係が上手くいかないと思っている人は読んでみるのも良いかもしれない。
2投稿日: 2015.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
カウンセリングの基礎となる「共感」がどのようなことなのか教えてくれる。 共感は、相手と同じ感情になることではなく、自分の自然な感覚であり、相手との関係性の境界を響き合わせるような関わり方だという指摘や、受容だけでなく、それをフィードバックすることの重要性の指摘は、とても新鮮かつ重みをもって響いた。 「淋しいんですか?」など、疑問形での応答を避けるなどの具体的な技術も大いに参考になった。 15-43
0投稿日: 2015.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ私はカウンセラーではないのにカウンセリングの役割を強いられ続け、私自身がおかしくなってしまいそうでした。この本を読んだのはそんな自分の感情に折り合いをつけるためですが、著者は他者の感情の動きを非常によく観察されているのだなと感じました。そして、そう考えると納得の行く事柄がとても多かったのです。反射、共感、感情の気付きに導くこと。感情に溺れている人にいくら真実を突きつけても、それを受け入れる余裕はないと思います。けっきょく、自分で気づかせるしかないのです。
0投稿日: 2015.01.31
