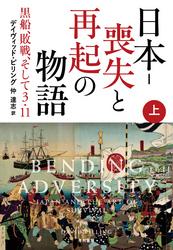
総合評価
(18件)| 4 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ「日本―喪失と再起の物語」 https://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51918247.html
0投稿日: 2025.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国人の目で、分かりやすく日本の近代、戦前、戦後を総ざらい。 第4章、「なぜ日本は戦争に向かったか」は、日本が戦争に至った(至らされた?)状況がよくわかる。 欧米に肩を並べたいが、認めてもらえず、劣等感が不満に変わる。日本ばかりが牽制されると思い込み、暴発し、ついには太平洋戦争に至る。 アジア侵攻も当初は解放戦争かもと思われていたが、実際は露骨な人種差別政策をとり、近隣諸国から失望された。
0投稿日: 2020.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本史のおさらいとしてとてもよくまとまっていたのがありがたかった。英語でなく日本語で読めるのは楽でよい。
0投稿日: 2019.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログFinancial Timesのアジア編集長にして元日本特派員のDavid Pilling氏、日本を巡る渾身の論考、世界的にもかなり売れているらしい。 第1章、津波の章だけでも読む価値があるが、本書のもっとも魅力的な点は、日本という類まれなる秩序と繁栄を手にした国に対する最大限の敬意を表明しつつも、根拠のない「日本特殊論」には一切くみせず、他の多くの国と同じように、多くの悩みを抱えた不完全な存在として描いていることだ。 「・・・日本人は自国がほかに例のない調和の取れた社会であると考えたがる傾向があるが、他国と同様、この国にも階級、地域、性差、年齢などによる対立があるし、主流派の文化に対抗する非主流派(サブカルチャー)が存在し、社会構造の変化によって流動化することもある。だから『日本人はこう考える』というフレーズで始まる発言はまず疑ってかかった方がいい」(上巻、P.47)。 もちろん、日本人から見ればあまり深さのない事実のサマリーと感じる部分もあるし、例えば避けてとおれない戦争や憲法の問題についてこちらの言い分を主張したくなるあれやこれやはある。が、本書はほとんどのトピックで様々な意見を両論併記的にカバーしている。結論としてはどうも「左寄り」の肩を持っている気がする、と思う人は確かにいるかもしれないが、英国のジャーナリズムにとって権力との緊張関係は大前提、といった点も考慮する必要があろう。 ともあれ、杉田玄白の解体新書から小泉政権の郵政改革まで、これほど網羅的にカバーした本は滅多にないし、それを世界のEducated personが関心を持って迎え入れたということに深く思いを致さずにはいられない。そして日本の抱える課題についてこれでもかとあげつらったこの本は、しかし読めば「それでも再起する」日本への最大級の賛辞でもあることがわかるはずだ。 ここに描かれた日本像は、Financial Timesの信用力もあいまって海外から当面の「スタンダード」として受け止められる可能性が高い。そのことを、私としては(100%都合のいい本なんてあるわけない前提で)十分納得できる、と感じた。
0投稿日: 2019.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は、フィナンシャル・タイムズの元東京支局長。東日本大震災の体験をきっかけとして、この本を執筆した。 主なテーマとしては津波と東日本大震災、著者が考える日本の歴史、現在の日本について考察している。震災以降、日本に対する海外の見方は悲観的だが、日本は決して衰退していないと説く。日本はこれまで、何度も厳しい危機的状況に陥っているが、その度に復興する力を示してきた。だから様々な議論はあるが、今後も上手くやっていけると考察している。但し、現代の日本人に対しては手厳しい意見もあり、特に日本の政治家の右傾化には不信感を持っているようだ。 ジャーナリストらしい視点で多くの日本人にインタビューし、現代の日本人とは何かを考察しており、とても面白かった。最近はメディアの日本賛美論が蔓延していて、日本の凄さを世界に誇り喜ぶ風潮がある。良い話を聞くのは確かに気持ち良いが、それを鵜呑みにするのではなく、日本に対する辛口の意見も読んで、自分の考え方が偏っていないかバランスを取ることも必要だろう。この本は、そういう目的で読むといろいろ考えさせられることも多かった。
0投稿日: 2016.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログわかりやすくまとまっています。 取材先の人物について著者の好き嫌いが如実に文章に現れていて、個人的には面白かったです。人によっては不快に感じるでしょう。
0投稿日: 2016.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白いけど、思い込みインタビューが多い。 藤原や飯島との対応は必要以上の揶揄が多く、不快な気分になる。 対して自分寄りの意見は外見など褒めながらサラッと流して あまり公平感がなく、結論ありきの強引感がある。 縦横無尽な勉強っぷりと、論理の組み立ては面白いのだけど… まあ、イギリス人だしな‼︎←偏見
0投稿日: 2015.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ英・フィナンシャルタイムズ記者による、反「日本論」的、日本論。つまりステレオタイプな日本論に属することを良しとしない、現代日本論。よい意味で、見たこと・聞いたことがあくまで中心。ちゃんと外から見た日本って感じ。下巻と合わせて、時代を振り返る一冊として。
0投稿日: 2015.06.10知日派経済記者の目に映る現在の日本の姿
著者は、3・11の震災直後に「日本の奇跡は終わっていない」と題する記事を全世界に配信した経済記者で、自然の破壊力とそれに応じた日本人のイメージを手がかりに、これまでに奇跡を生み出し続けてきた日本人が今回も「災い転じて福」となせるかに期待を寄せてきた。 本書では「将来の日本がどうあるべきかではなく、現在の日本が私の目にどう映っているか」が主題となっている。 あらゆる否定的な意味が込められた「日本化」など、海外で繰り返される悲観的な日本像には組せず、行き過ぎた誇張を否定し、見過ごされてきたものを提起している。 タイトルから受ける印象とは異なり、日本人を賞賛したり励ましたりする内容ではない。 第4章の論述には首肯しがたく、海外の日本像と、日本人の持つ自己像との乖離が感じられた。 ここでは、なぜ日本は戦争に向かったか、それは近代化の不徹底と、個人尊重や主権在民が顧みられず前近代的な天皇崇拝に回帰したためとし、明治維新を必敗自滅の始まりとしているが、著者の言う「奇跡」もここに端を発するのではなかったか?
2投稿日: 2015.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ黒船、敗戦、バブル崩壊、3.11と多くの国難に見舞われながら、その度に立ち上がってきた日本という国と日本人の物語である。上下巻に分かれている。原題は『Bending Adversity: Japan and the Art of Survival』そのまま訳すと「災い転じて福となす:日本とその生き残りの芸術」といったところか。英語の他にも独、伊、仏、中国語などに翻訳されるようである。上巻では、3.11の地震と津波に襲われた被災地から物語ははじまる。そして、震災の時に日本人が見せた規範意識の高さから、話は「日本論」へと移っていく。本書の第一の特徴は著者が直接インタビューするなどして得てきた情報が多いことである。『国家の品格』の藤原正彦、言わずと知れた作家『村上春樹』、そのほかにも政治の中枢にいる人間や海外の政治学者や作家などその取材先は多岐にわたる。違和感のある記述もあるが、それも含め日本を良く知る外国人がどのように日本を見ているのかがよくわかる。
0投稿日: 2015.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ黒船以降現代に至る日本の軌跡を考察するのですが、その分析と編集の手腕が非凡です。ジャーナリストらしく、多くの取材により、両サイドの見方を紹介している点も評価できます。視野が広い点もいいですね。アングロサクソンは侮れません。今は、細かな点をあげつらうより、早く下巻に進みたいものです。書き出しが3・11なので、最後はそこに回帰するのでしょうか?希望ある展望で終わって欲しいものです。
0投稿日: 2015.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ好評判に期待して読んだのだが。 リアルタイムの経済状況についての評価はまだしも、幕末以降敗戦までの近代史は表面的な知識を賢しらにひけらかすもので、読めたものではない。
0投稿日: 2015.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前から新聞書評で見かけて気になっていた本でしたが、読み始めると期待以上のおもしろさ。フィナンシャル・タイムズの記者による日本論ですが、日本を是々非々で見ていて、非常にバランスの取られた意見で説得力があると思いました。 引き続き下巻も楽しみです。
0投稿日: 2015.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ファイナンシャルタイムズの日本支局長を務めたイギリス人である著書が、現在の日本が彼の目にどう見えているかを描いている。 上巻では東日本震災、明治維新、敗戦からの復興、バブルとその崩壊、小泉劇場を扱う。多くのデータやインタビュー、著作を引用して、楽観・悲観どちらにも大きく偏らないよう気をつけている感じが伝わってくる。押し付けがましくなく、また突き放しもしない、ほど良い距離感で書かれていて参考になる。翻訳も読みやすくてよい。 はかなく消えゆくものに美しさを感じる感性は日本人の「文化的連想」で説明ができる、つまり生来的に日本人に固有のものであるという説明を持ち出す必要はないのではないか、という指摘に大きく納得した。
0投稿日: 2015.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「日本論の新・決定版」 書評は偽りでなかった。文句なしにおもしろいの五つ星評価。「災い転じて福となす」のことわざを引用した東日本大震災のレポートから始まり、「島国」「明治維新」「失われた20年」「小泉純一郎」等のキーワードでなぜ今の日本がこうなったかがわかる。しかも無味乾燥でない文で。藤原正彦氏、村上春樹氏、飯島功氏へのインタビュー内容も興味深かった。すぐ下巻を読むつもり。
0投稿日: 2014.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ新聞の書評欄で、2紙に同日に掲載されており、興味を持って購読。 知日派の英国人ジャーナリストの日本文明論。 東日本大震災のルポルタージュから始まり、刺激的な内容にたちまち読み進んだ。
1投稿日: 2014.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ私たちは未知を失い、どちらの方向に進めばいいのかわからなくなっています。でもそれはとても自然なことだし、とても健全なことなのです。 日本人が日本たたきを気にするのは日本が世界経済における重要性を失っていないことの証。 日本が海外との関係で経験した悲惨な歴史は、日本に強烈な劣等感をもたらし、国際的地位への執拗なまでの執着心を生んだ。 日本が中国から離反したのは、欧州の学問的な魅力だけでなく、中国自体がかつての輝きを失ってしまった。 福沢は東アジアの将来は日中間の対立を中心に展開すると考えていた。東アジアが儒教権ブロックになるか、近代国家ブロックになるか結着をつける必要があった。 1995年は日本にとって奇跡的な成長神話が終わった年だったと村上は述べていた。 小泉さんは、些細な問題は全てシャットアウトして、要点だけに考えを集中していた。
0投稿日: 2014.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014年111冊目。 黒船襲来、第二次世界大戦における敗戦、そして3.11、日本が直面してきた困難と、そこからの再起をフィナンシャルタイムズの東京支局長であった著者が描き出している。 「日本は言われるほどの停滞をしていない」という意見には励まされ、逆に「期待されていたほどの成果が出せていない」という意見には危機感が生まれ、歴史認識を揺さぶられる。
0投稿日: 2014.11.14
