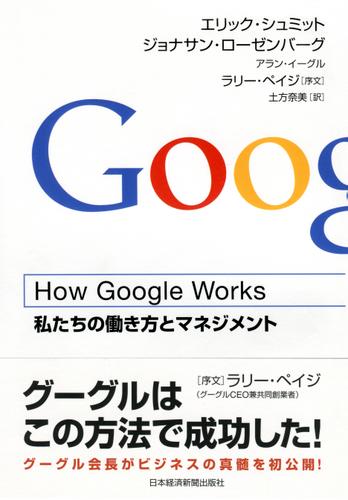
総合評価
(149件)| 41 | ||
| 53 | ||
| 37 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleはなぜ、私たちをワクワクさせてくれるのか?の問いに答えを与えてくれる1冊。それは自分が思うにスマート・クリエイティブ達自身がワクワクしながら仕事に取り組むからなのだろうと。
0投稿日: 2015.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログsmart creative とはどんな人たちなのか、平易な語り口で、ユーモアを交えながら語られている。ところどころでとても厳しい言葉が挟まれ、smart creative たちがsmart creative たる所以がわかる。
0投稿日: 2015.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ150322 中央図書館 グーグルの元CEO他が、同社におけるマネジメントのTIPSをオープンに紹介していく本。日本の普通の大企業が参考にするには、社員の質の差、会社の目的の差、シリコンバレーという特殊な競争環境にある世界的企業との差異など、あまり鵜呑みにできないところは多いだろう。しかし、マイクロマネジメントや、社内コミュニケーションのあり方は、今後、世界のあらゆる企業が真似していくところだと思う。
0投稿日: 2015.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ翻訳本独特の読みにくさはあるが、リーダー層には読んでもらいたい一冊。 Googleがいかにエンジニアを活かすマネジメントをしてきたかがよくわかる。
0投稿日: 2015.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの組織文化がいかに構築され、そして洗練されてきたかを説いた書。ベースとなる価値観を持ちつつ、組織文化も論理と情熱により仮説検証を繰り返して磨き上げてきた様は正にGoogle way。
0投稿日: 2015.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
グーグルの開業から現在の発展を、創業者ではない二人が語ることで、ある種、客観的に読むことができて面白い。 MBA的な発想を嫌い、現場のエンジニアをあらゆる面で大切にするところが非常に好感を持てる。 〈技術的アイディアを見つける方法〉 ・オタクを見つけ彼らの手がけるおもしろいものを見つける ・小さな問題の解決策に注目し、適用範囲を広げる 〈スマートクリエイティブに従来型の経営モデルは通用しない。特定のものの考え方を押し付けても無駄。彼らがモノを考える〝環境〟をマネジメントする。それも毎日喜んで出社したくなるような環境をつくる〉 〈ビジネスパーソンが磨くべきもっとも重要なスキルは、「面接スキル」〉 採用すべきは、情熱、知力、ラーニングアニマル、おもしろさ、を持っている人 〈正しいコミュニケーション過剰の基本的ルール〉 ①そのコミュニケーションは、あなたが全員に伝えたい重要なテーマを強調するものか? ②コミュニケーションは効果的か? ③コミュニケーションはおもしろく、楽しく、刺激的か? ④コミュニケーションに心がこもっているか? ⑤コミュニケーションは正しい相手に届いているか? ⑥メディアの選択は適切か? ⑦正直かつ謙虚に。不運な事態に備えて好意を蓄えておこう
0投稿日: 2015.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログイノベーションは、真に顧客志向を持つ人材(スマートクリエイティブ)に、自由を与えてこそ生まれるということをグーグル経営陣は信じている。自社を省みると、意見を言えば、やってみれば?の前に潰される文化が蔓延っている。刺激を受ける一冊である。
0投稿日: 2015.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの成功を実現した、働き方とマネジメントについてその要諦を標した本。ただし、現存する企業なので神髄を教えてくれる訳ではなく、そこは想像するしかない。 業務プロセスはかなり適当だったが、一方でその信念やエンジニアを大切にするという根本は揺るがない。例えば、TGIH(Thank God, it’s Friday!)という議題自由の全社会議があることもそうだ。 ワークライフバランスについてのコメントもある。ワークはライフの一部である。よって、ワークを活き活きとするようにマネジメントするのが仕事だ。よって、時間外を監視することは仕事じゃないと。イエスという文化を醸成することも大事で、前に転がっていく文化があるかどうかだ。もう一つ、楽しい仕事であるかどうか。本当の楽しさは、イベントだったり社員同士のジョークの言い合いだったりする。必ずしも、オフィシャルな飲み会ではない。これは、採用チームにいた頃を思い出す。みんなで夜中までやって、そのまま温泉に繰り出したり、焼肉やるぞみたいなテンションで笑いが耐えなかった。最高のパフォーマンスを上げていたのも、きっとモチベーションが高かったのも、ワーク自体とその環境が楽しかったからだ。 自分の下で働きたいと思うような上司であれ。自己評価は難しいが、自分自身を批判することで360度評価なんかよりもよっぽど有益な情報が得られる。 メールの心得。すぐ返信すること。内容は簡潔に。一度書いたら、読み返して不要な言葉を全て消す。受信トレイをきれいにしておくこと。Only Hold Once. 本書は、グーグル社員向けに書かれたレジェンドの記憶といった趣だが、経営の要諦もきちんと書かれている。それは、社員やチームが思う存分働ける環境を作ることが大事だという原点だ。その為には、20%を自分の好きな研究に当てても良いというルールや、それをプレゼンする機会を準備している。こうした革新的な経営スタイルは、果たしてどう解釈されてゆくのだろう。自分自身のチームは最強であって欲しい。
0投稿日: 2015.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ビジョンなど、繰り返し伝え、報奨によって強化しなければ、それが書かれた紙ほどの価値もない。(p.54) 燃え尽き症候群の原因は働きすぎではなく、自分にとって本当に大切なことを諦めなければならなくなったときに起こる。スマート・クリエイティブに決定権を与えよう。そうすれば、自分にとって好ましい働き方はどんなものか、最適な判断を下すだろう。(p.80) 技術的アイデアを見つけるもう一つの方法は、小さな問題の解決策に注目し、その適用範囲を広げる方法を考えることだ。(p.110) ライバルの近くにいると、安心感が得られる。ヨットレースでもおなじみの戦略で、先頭を走るヨットは後から来るヨットに合わせて船の向きを変える。後続船が別の方向に進み、自分より強い風を見つけるのを防ぐためだ。ライバル企業はダンゴ状態になり、どこか一社が抜け駆けをして別の場所で新たな風を見つけることを許さない。だがラリー・ペイジが言うように、「同じようなことをしている他社を負かすだけでは、仕事としてちっともおもしろくないじゃないか」。(p.132) 情熱家はそれ(情熱)を表に出さない。心に秘めている。それが生き方に表れてくる。粘り強さ、気概、真剣さ、すべてを投げ打って没頭する姿勢といった情熱家の資質は、履歴書でははかれない。(中略)何か本物の情熱を抱いている人は、最初はうまくいかなくても努力を続ける。情熱家に失敗はつきものだ。情熱のある人間は、自分の興味があることについて際限なく語りつづける傾向がある。(p.145) 「自分の情熱と仕事を結びつけることができるのは、究極の贅沢です。そして間違いなく幸せにつながる道でもあります」(p.197) 正しい意思決定のあり方を考えるうえでまず理解すべきは、正しい選択をすることだけに集中していてはいけない、ということだ。判断に到達するプロセス、タイミング、そして判断を実行に移す方法も、判断の内容そのものと同じくらい重要なのだ。そのどれか一つでも欠ければ、おそらくまずい結果になるだろう。(p.205) 「人間の本質は、質問に答えることではなく、自ら質問することだ」(p.243) 会話はいまでも最も重要かつ効果的なコミュニケーション手段である。(p.249) 「人類はことさら制約が厳しいとき、ことさらすばらしいものをつくる」(p.308) 「何が起きるか」ではなく、「何が起こり得るか」と自問しなければならない。「何が起きるか」を考えるのは予測であり、こんにちのような急速に変化する世界では意味がない。「何が起こり得るか」という問いは、想像力をかきたてる。常識の枠内では想像もできなくても、想像しようと思えば本当はできることは何か?(p.344)
0投稿日: 2015.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
簡単に言えば、Googleには優れた理念があり、優れた人間が集まっているので、それらの優れた部分を殺さぬようにいかにマネジメントしていくか?ということが書かれています。 当然、これがそのまま流用できるのは世界屈指の魅力的なサービスを提供していて魅力的な人材が自然と集まる魅力的な企業、だけであると(まず採用時に徹底的に妥協無く厳選すると書いていますし)思うので、これを読んで、さあ!私も明日から!となると肩透かしを食らうと思います。 それでも、でも、自分の企業をほんの少しだけでも良くできるかもしれない、そう思わずにはいられない魅力的な本でした。
0投稿日: 2015.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
チェック項目19箇所。三つの強力な技術トレンドが相まって、ほとんどの業界で競争条件が根本的に変化した、第一に、インターネットによって情報が無料に、豊富に、そしてどこでも入手できるようになった、たいていのことはネット上にある、第二に、携帯端末やネットワークが世界中に広がり、常時接続が普及した、第三に、クラウドコンピューティングによって、無限のコンピューティング能力やストレージ、たくさんの高度なツールやアプリケーションを誰でも、安価に、しかも利用時払いで使える仕組みができた。スマート・クリエイティブは、自分の”商売道具”を使いこなすための高度な専門知識を持っており、経験値も高い。リスクをいとわない、失敗を恐れない、失敗からは常に大切なことを学べると信じているからだ。自発的だ、指示を与えられるのを待つのではなく、また納得できない指示を与えられたら無視することもある。たいていの会社は成功を収めたあとに、文化を文字にしておこうと思い立つ、その役目を押し付けられるのは、創業時を知らない人事あるいは広報部門のスタッフが多く、それなのに会社の本質を表すようなミッションステートメントに仕上げることを期待される、成功する会社とそうでなはない会社の違いは、従業員がこうした文言を信じているかどうかにある。組織はフラットに保つべきだ、スマート・クリエイティブがフラットな組織を望むのは、トップの近くにいたいためではなく、仕事をやり遂げたいためで、それには意思決定者と直接折衝する必要があるためだ。小さなチームは大きなチームより多くの仕事を成し遂げることができ、内輪の駆け引きに明け暮れたり、手柄が誰のものになるのか思い悩むことも少ない、小さなチームは家族に似ている、ケンカをしたり、機能不全に陥ることもあるが、ここぞという場面では一つになる。組織に関する最後のルールは、一番影響力のある人たちを見きわめ、彼らを中心に組織をつくることだ。私たちは社員にしっかり休暇を取るよう勧めている、誰かが自分は会社の成功に欠かせない存在なので、一~二週間も休暇を取ったらとんでもないことになる、と思っているなら、かなり深刻な問題があるサインだ。優れたベンチャー企業、優れたプロジェクト、ついでに言えば優れた仕事は、楽しくなければいけない、あなたが死ぬほど働いているのに、ちっとも楽しくないという場合、おそらく何か間違っている、楽しい理由の一つは、将来の成功の予感かもしれない、だが、一番大きいのは、同僚と一緒に笑ったり、ジョークを言いあったり、ともに仕事をすることの楽しさであるはずだ。成長の可能性がある専門分野を見つけることが、プラットフォームを生み出す近道になることもある、グーグルは1990年代末、検索プラットフォームを拡大するため、たった一つのことに集中した、最高の検索サービスの実現である。「ぼくの重要な仕事は、社員にライバルのことを考えさせないようにすることだ。一般的に、人はすでにあるモノのことを考えがちだ。ぼくらの仕事は、まだ考えてみたこともないけれど、本当に必要なモノを思いつくことだ」。すばらしい人材の集まる会社は、すばらしい仕事を成し遂げるだけではない、さらに多くのすばらしい人材を引き寄せる、最高の従業員は群れのようなものだ、お互いについていこうとする、最高の人材を何人か獲得できれば、その後まとまった数を確保できるのは間違いない。スマート・クリエイティブの明確な特徴は、情熱があることだ、ただ、本当に情熱的な人間は「情熱」という言葉を軽々に口にしない。大切なのは優秀な人が「何を知っているか」ではなく、「これから何を学ぶか」だ。スマート・クリエイティブは四つのカテゴリーすべてで高い評価を受ける、【リーダーシップ】【職務に関連する知識】【全般的な認知力】【グーグラーらしさ】。イノベーションとは「新たな大ブーム」をつくりだすことだ、少なくとも「新たな流行語」であることは間違いない。イノベーションとは、新しく、意外性があり、劇的に有用なものでなければならない。イノベーションが生まれるには、イノベーションにふさわしい環境が必要だ、イノベーションにふさわしい環境とは、たいてい急速に成長しており、たくさんの競合企業がひしめく市場だ。
0投稿日: 2015.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログとりあえず「会議」に関しては私の職場の構成員に3回くらい熟読していただきたいと思う(苦笑。 迂遠な愚痴は置いておいて、「スマート・クリエイティヴ」「目標は10倍の規模で」「邪悪になるな」辺りが心に残った。 全く違うジャンルで働いていたとしても、たいへん役に立つと思う1冊。
0投稿日: 2015.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログジョン・ウッデン 本当に大切なのはすべてわかったと思った後に学ぶことだ ヘンリー・フォード 人は学習を辞めた時に老いる。20歳の老人もいれば、80歳の若者もいる。学び続けるものは若さを失わない。人生で何よりもすばらしいのは、自分の心の若さを保つことだ パットン将軍 全員同意見というのは、誰かがものを考えていないということだ スコット・アダムス 失敗は壁でなく、道と考えるほうがいい
0投稿日: 2015.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ所在:展示架 請求記号:007.3/Sc5 資料ID:11401591 googleは、この方法で成功した!「他とは違ったやり方をする」ことで有名なgoogleの、ビジネスの真髄を初公開。 選書担当:伴野
0投稿日: 2015.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ経営者目線での話という感じだったので、全体的な雰囲気としては良い感じだったが、立場の違いからか、自分が求めているところとはあまりマッチしなかった。 OKRという目標管理の方法については、チーム内でうまく消化して取り入れられたらと思う。
0投稿日: 2015.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログエンジニアが組織の中心となるような企業が目指す文化の一例なんだと思う。個人的にはこういった文化を持った企業で働きたい。
0投稿日: 2015.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ管理職級以上向け。しかも大天才をたくさん抱える企業の。いろいろと面白いことが書いてあるけれど、超優秀な人材が確保できなければ何の役にも立たなそう。
0投稿日: 2015.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleがスマート・クリエイティブの採用にこだわり、世界最高のイノベーションを続ける原動力がわかる。自らデータ重視というだけあり、出典の記載も精緻。一般的な日本人からみると夢のような環境だが、プロフェッショナルな姿勢に刺激され、発送の飛躍を体感する本。
0投稿日: 2015.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界トップクラスの企業集団の社風いわゆるスマートクリエイトについて創業者のシュミットが語った本です。非常に内容が濃く読むのに苦労しました。無から有をつくりだす、クリエイト集団の難しさがひしひしと伝わります。
0投稿日: 2015.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく面白い。常識にとらわれない経営だけど、ブレない軸をキープし続けられるのは、その信念が正しいからだろう。
0投稿日: 2015.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ一般的には良書の部類だと思うけど 私にとっては面白くなかったです これって過去のことであってこれから出るであろう ポストgoogleって違うと思うんですよね 根拠はないですけど
0投稿日: 2015.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社に置いてあったので年末年始の一冊として持ち帰り。読んでみてまず思う感想はとても良いと思う反面「とは言えグーグルだからなぁ」という気持ち。本書にもそれっぽい記述があり、スティーブ・ジョブズのプレゼンや思考法を研究すればその様になれるかと言うとそれは無理な話であって、パンピーから見ればグーグルという会社もそれは同じだろうと強く思う。 とは言えグーグルをグーグルたらしめるトピックやエッセンスが有用なのは間違いなく「よし、これを読んで明日からはウチもグーグルの様にやるぞ!」というのではなく、自分自身、チーム、部署に本書から得たトピックとエッセンスを少しずつ加えて行くのが正しい読み方なんだろうと思う。 本書においてはエリックシュミット、そしてジョナサンローゼンバーグという目立たない番頭とでも言えばいいのか、何かとめちゃくちゃな創業者(と頭が良すぎて変なヤツばかりの従業員)を上手くまとめて組織化していく手法が裏方的な立場から語られているのがとても興味深い。特にジョナサンローゼンバーグを筆頭にしたプロダクトマネジャーチームの考え方についてはそれに焦点をしぼって是非一冊出して欲しいくらいである。 製品(特にIT分野における)開発マネジメント、採用、企業文化について考えている経営者やそれに近いレイヤーの人にとっては読んで損の無い一冊であると言えるだろう。
0投稿日: 2015.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際にベトナムの現場で立ち上げたばかりの有期の会社で働いて、この本の言う企業文化の重要性をヒシヒシと感じている。立ち上げってめっちゃ大事。
0投稿日: 2015.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogle社に務めるグーグラー(すなわちスマートクリエイティブ)が備えておくべき能力に関して記載されている書籍。企業文化は人が創る。人(特に採用)に対する考え方は弊社と特に酷似しており、今後も同様の採用を暫くは継続すべきであると感じた。
0投稿日: 2014.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログとても面白かった。Googleの経営についての本だから、あらゆるところに刺激的なヒントがある。 スマートクリエイティブについての話であり、組織の作り方の話であり、新規事業の立ち上げ方、人材採用、競合分析、あらゆることのGoogle流が書かれている。働き方にしても、このような組織を目指していかなければならないんだなと思った。
0投稿日: 2014.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの神髄を、文化、戦略、人材、意思決定、コミュニケーション、イノベーションをテーマに詳細に開示。ただただ脱帽の域である。大きく出遅れる日本のビジネスマン必読の書。
0投稿日: 2014.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログエリック・シュミットがグーグルの経営について書いた本。 話の中心は「スマートクリエイティブ」と名付けたエンジニアが凄いし活かそう、という内容でした。 物凄く採用に力を入れてるのは伝わった。本気で人材の力を信じるならそらそうなるでしょう。 グーグル内情を知るには良い本だと思います。しかし、マネジメントを知るにはあまり適してないかもしれない。 基本方針が「すごい人材を集めてできるだけ自由にさせる」ということなので、一般的な知見に昇華させにくいのかもしれないですね。
0投稿日: 2014.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの創立時から現在までの運営のやり方、人材採用など会社文化を書いてる内容。経営会議、面接人事などデーターが重要で面接で採用決定をした職員達もその決定が間違ってなかったか?数値化されているとの事。結局は優秀な人材が会社を発展させる考えは、大昔からあったな。あとはジョブズの先見の明、Google中国撤退の話、Amazonの良さなどインターネットを通しての可能性を説いている。個人的にはGoogleアースが登場した時は感動した。
0投稿日: 2014.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートクリエイティブを中心とした企業の経営がよく分かります。しかし、マネできるかというと別物でしょう。 とびきり優秀な人材を金に糸目をつけず集め、彼らが自由に働ける環境を用意すれば結果は自動的についてくる、その前に資金がショートして潰れるのが大半じゃないでしょうか。
0投稿日: 2014.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログエンジニアならこういう会社で働きたいと思う。 ワークライフバランスは、ただ早く帰ればいいのではなくワークとのバランスなので、人それぞれ比重が違う。 創業の初期から根付いている企業文化が羨ましい。
0投稿日: 2014.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年ナンバーワンの本。充実した経営学の本であるとともに、現実の経営にも多大なる示唆を与えることができると感じた。この発想を活かし、更に超えていくことが、未来を作り出すことだと感じている。希望的な意見としてできる限り早くこの本が陳腐化して欲しいと強く感じた。
0投稿日: 2014.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
CEOより遥か高給を得るスマート・クリエイティブの世界かぁ。責任の重さより、実力というか戦力の大きさで金銭的価値が決まるって社会は、凡庸な者としちゃ避けたい。確かにプロスポーツの世界では当然なんだけど…。常時イノベーションを念頭に息つく間もない彼らは、間違えなく別世界で生きていて欲しい。『イスラエルの戦車司令官は戦闘を開始するとき、「突撃!」とは言わない。「アハライ!(ついてこい!)」と叫ぶのだ。スマート・クリエイティブのリーダーを目指すなら、この姿勢を学ばなければいけない。』それだけ同感。
1投稿日: 2014.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleが成功した最大の理由の一つは上場時に作成した事業計画にある。そこには財務予想や収入源に関する議論は一切なく、市場調査もない。事業ドメインも営業戦略、チャネル戦略、プロダクト戦略、組織図、製品開発のロードマップ、予算、営業目標、マーケティング目標もなにもなかった。なぜならなにも判らなかったから。判っていたのはたった一つ、我々が20世紀に学んだ事の殆どは間違っており、それを根本から見直す時期が来ているという事だけだった。 3つの強力な技術トレンドが相まって殆どの業界で競争条件が根本的に変化した。 インターネットにより、情報が無料に、豊富に、どこでも入手できるようになった。 携帯端末やネットワークが世界中に広がり、常時接続が普及した。 クラウドによって無限のコンピューティング能力やストレージ、高度なツールやアプリを誰でも安価に利用時払いで使える仕組みができた。 「古い世界ではもてる時間の30%を優れたプロダクトの開発に、70%をそれがどれほど素晴らしいプロダクトか吹聴してまわるのに充てていた。今はそれが逆転した。ージェフベゾス」 Yelpの利用度が高い地域ではチェーン店から顧客が流出している。 こんにち多くの企業が採用している経営管理プロセスは、100年以上前の遺物であり、失敗のコストが高く、全体の情報を持っているのが経営トップだけという時代のもので、リスクを抑え、情報量の多い一握りの経営者だけに意思決定を委ねる事を主眼としていた。このヒエラルキー構造は意思決定のスピードをあえて遅くするように設計されているので、スピードが要求される現在にはそぐわない。 あなたに1ペニーあげたらあなたは豊かになって私は貧しくなる。でもあなたにアイデアをあげたら二人とも豊かになれる。 会社の浮沈を左右するのはスマートクリエイティブの存在に尽きるが、彼らに特定のモノの考え方を押し付けてもムダ。それよりも彼らがモノを考える環境をマネジメントする事。 本当に大切なのは、すべてわかったと思った後に学ぶことだ。 まずは最高のスマートクリエイティブを惹きつける方法から始める。その出発点は企業文化。自分達のモットーを信じられなければ大成功はとうてい望めない。次に取り上げるのは戦略。スマートクリエイティブは強固な戦略の土台に根ざしたアイデアに何より魅力を感じる。事業計画を支える戦略の柱こそが事業計画そのものよりもはるかに重要。次が採用。これはリーダーの最も大切な仕事であり、最高の人材を十分集める事ができれば知性と知性が混じりあり、クリエイティビティと成功が生まれるのは確実。 持続的成長を実現する唯一の方法はプロダクトの優位性を維持する事であり、それはイノベーションの原始スープから生まれる。この原始スープに満たされた環境を作る事が唯一の道。 スマートクリエイティブが職を探すときに重視するのは「文化」。どんな環境で働くかがもっとも重要だと解っているから。 チームメイトに以下の質問をしよう。 ぼくらにとって大切なことは何か? 信念は何か? どんな存在になりたいのか? 会社の行動や意思決定の方法はどうあるべきか? の答えをまとめよう。おそらくその内容は創業者の価値観を網羅するだけでなく、メンバーの様々な視点や経験によって膨らみをもたせたものになる。これこそがその会社のミッションステートメントになる。成功する会社とそうでない会社の違いは従業員がこうした文言を信じているかどうかにある。 グーグル創業者達は短期利益の最大化や自社株に対する市場の評価などは一切気にしなかった。会社のユニークな価値観を未来の従業員やパートナーに示すことの方が長期的成功にははるかに重要である事を知っていたからだ。 インターネット世紀のプロダクトマネジャーの役割は、最高のプロダクトの設計、エンジニアリング、開発を担う人々と共に働く事。何より求められるのはプロダクトをさらによくする為の技術的ヒントを見つけること。 意思決定の質と報酬の水準は本質的に無関係。経験イコール説得力のある主張とされる企業が多い。 「誰のアイデアか」よりも「まともなアイデアか」が重視される職場。 1番偉い人は威圧的な態度で主張を通そうとする。責任ある立場についたものの、その職務に圧倒されているような状況では、「つべこべ言わずに俺の言うことを聞け!」と言ったほうが簡単だからだ。だが、必要なのは部下を信頼する事。そして彼らにもっと良いやり方を考えさせる度量と自信を持つこと。 最低7人の直属の部下を持つこと。部下が多いとマイクロマネジメントしている時間はなくなるから、スタッフはより大きな自由を手にいれられる。 できる限り組織は機能別にするべきと考えている。そして各部門が直接 CEOにレポートするのだ。なぜならばプロダクトライン別にすると自分の事業部の事だけを考えるようになり、情報や人の自由な流れが阻害されるから。独立採算制は各事業部の実績を測るのに都合が良さそうだが、人々の行動を歪めるという好ましくない副作用が生じる。つまり、事業部の責任者は、自らの事業部の損益を会社の損益より重視するようになる。サンでは事業部制にした結果生産性が大幅に低下した。なぜならば各事業部のリーダーと会計士が実際に収益をもたらす最高のプロダクトを生み出すよりも決算の結果を良くする事ばかりに気をとられるようになったから。 ピザ2枚のルール。一つのチームはピザ2枚で足りるくらいの規模にとどめるべき。小さなチームは大きなチームよりも多くの仕事を成し遂げる。 最高の経営システムは、アンサンブルを土台にしている。スーパースターの共演より、ダンスチームのパフォーマンス。能力の高い人間が大勢集まり、チャンスがあれば誰でもリードダンサーを務められるシステムの方が組織は長期的に安定する。 財務、営業、法務等、オペレーション関係の人間は議論の主導権を握るべきではない。プロダクト開発者に最も大きな影響力を持たせるべき。 大抵のプロダクトリーダーが立てるプロダクト計画は最も重要な要素が欠けている事が極めて多い。それは大幅なコストダウンにつながったり、機能や使い勝手を何倍も高めたりするような新たな技術の活用法やデザインの事。 大切なのは、顧客が思いつかないような、あるいは解決不可能だと思っていた問題へのソリューションを提供する事。 あなたの会社のオタクをみつけ、彼らが手がける「面白いもの」をみつけよう。成功をつかむのに必要な技術的アイデアはそこにある。 新しい技術は個別具体的な問題を解決する手段として、かなり原始的な状態で誕生する事が多い。蒸気機関は機関車の推進力となる遥か以前から炭鉱から水を汲み出す便利な手段として使われていた。当初のラジオも船と陸との通信手段でしかなかった。ベル研所は1960年代に生み出したレーザーをあまりに低く評価していた為、特許すら取得しなかった。 技術的アイデアをもとにプロダクト戦略を立てれば、顧客の要求を満たすだけの凡庸なプロダクトを生み出さずにすむ。ヘンリーフォードも顧客の要望を聞いていたら速い馬を探しに行っていただろうと語っている。「あなたのプロダクトの技術的アイデアは何か?」という質問に答えるのはとても難しいが、答えが見つからない時はそのプロダクトは考え直した方がよい。 成長を最優先させる事。「今四半期の売り上げが8%伸びた」というのは長くは続かない。何かを猛烈なスピードでグローバルに成長させる事。スケール化は戦略的土台の中核。競争優位は長続きしないので、速く大きくなる為の戦略が必要。インターネット世紀に大きな成功をつかむリーダーとはプラットフォームを生み出し、一気に成長させる方法を知っている人物。 アマゾンは金融アナリストにいくら収益性の低さを批判されてもひたすら成長に注力した。結果、小売、メディア、コンピューティング業界で最も破壊力を持つ企業となった。 プラットフォームの重要なメリットはそれが成長し、価値が高まると投資が集まってくること。結果、プラットフォームが支えるプロダクトやサービスの質を高める事ができる。 20世紀は閉鎖的ネットワークを持つ巨大企業が支配したが、21世紀を引っ張るのはグローバルでオープンな企業。プラットフォームを創る機会は私たちの身の回りにいくらでもある。それを発見するのが優れたリーダー。 成長の可能性がある専門分野を見つけることが、プラットフォームを生み出す近道になる。特化すべき対象を見つけること。 グーグルには、ユーザーができるだけ簡単にグーグルのプロダクトから退出できるようにする事を任務とするチームがある。公平な競争環境で戦い、プロダクトの優位性によってユーザーの支持を勝ち取りたいから。顧客が自由に退出できるようにすると、彼らをつなぎとめる為に懸命に努力しなければならなくなる。 組織の中で、一定以上の地位に達すると、自分の会社の状況と同じくらいライバル企業の状況を気にしなければならないルールでもあるかのよう。強迫観念にとらわれている事が企業の上層部のデフォルトの心理状態になっているケースがあまりに多い。これは凡庸さへの悪循環につながる。他社を観察し、真似ばかりし、ようやく目をそらしたかと思えばリスクを取ることに慎重になり、インパクトの小さな漸次的変化しか起こさない。ライバルばかり見ていてはイノベーティブなモノは絶対に生み出せない。 正しい戦略にはある種の美しさがある。多くの人やアイデアが成功の為に一つになっている感覚とでも言おうか。それは、まず「5年後はどうなっているか?」と尋ねる事から始めよう。そこから現実に戻って慎重に検討しよう。5年の間には多くの市場に破壊的要因と機会が現れる。市場調査や競争分析に頼るのはやめよう。スライドは活発な議論を封じ込める。代わりに会議室に集まった全員にインプットを求めよう。 成功している大企業は例外なく次の点から出発している。 問題をまったく新しい方法で解決する その解決法を生かして急速に成長、拡大する 成功の最大の要因はプロダクトである 一緒に戦略を検討する仲間は、在職期間が長いとか、職位が高い人ではなく、最高のスマートクリエイティブ、そしてこれから起こり得る変化を見通す能力が高い人を選ぼう。 大企業の幹部に「あなたの仕事のうち、一番大切なものは?」と聞けば、ほとんどの人が反射的に「会議にでる事」と答えるだろう。そこでさらにしつこく、「いやいや、一番退屈なものじゃなくて、一番重要なもの」と聞けば、ビジネススクールで学んだ経営の基本を並べ立てるだろう。「優れた戦略を立て、事業機会を捉えてシナジーを生み出し、競争が一段と激化する市場でも着実に業績を向上させる事」といった具合に。でも、同じ質問を一流のスポーツチームのコーチやGMにしたら、彼らは「最高のプレーヤーをドラフトで獲得するか、スカウトするか、トレードで持ってくる事」と答えるだろう。優秀なコーチは、どれだけ優れた戦略を立てても優れた人材の代わりにはならない事をよく知っている。優秀な人材のスカウトはひげを剃るのに似ていて、毎日やらないと結果にでる。経営者の場合、「あなたの仕事のうち一番重要なものは?」という問いへの正解は「採用」である。 ヒエラルキー型の採用がダメな理由は、自分より優秀な人材が採用されない事。これは人間の本能である。 最高の従業員は群れのようなもの。最高の人材を何人か獲得できれば、その後まとまった数を確保できる。スマートクリエイティブが集まってくる理由は福利厚生ではなく、最高のスマートクリエイティブと一緒に働きたいから。 ヘンリーフォードは、「人は学習を辞めた時に老いる。20歳の老人もいれば、80歳の若者もいる。学び続けるものは若さを失わない。人生で何より素晴らしいのは自分の心の若さを保つ事。」メリーゴーランドよりもジェットコースターを選ぼう。 知力より専門能力を重視するのは間違い。優秀なゼネラリストには偏りがなく、多様なソリューションを見比べて最も有効なものを選択できる。 知力、情熱、ラーニングアニマルのマインドセットが採用候補者には欠かせないが、人格も重要。単に親切で信頼感があるだけでなく、多才で世界と深く関わっている人間つまり、「面白い人間」である事。 面接手法として、例えば「1996年に君が見逃したインターネットの重要なトレンドは何?君の推測が当たった部分、はずれた部分はどこ?」と聞く。これで、応募者は自分が予測した事を明確にし、現実に起きたことを分析し、両者の比較からわかった事を述べなければならない。月並みな発言や適当に答える事ができないのだ。 大切なのは応募者の予知能力ではなく、どのように思考を組み立て、失敗から何を学んだかを見定める事。「私に特別な才能はない。ただ情熱的なまでに好奇心が旺盛なだけだ」はアインシュタインの自己分析。 LAXテスト。空港で6時間足止めを食らったとしてもその相手と楽しく会話をしながら過ごせるか? 人種、性的志向、身体的障害など様々な面で多様な人材を採用する事は、道徳的観点以上の価値がある。視点の違いは全く新しい発想を生む。多様な人材が同じ職場で働く事で生まれる幅広い視点には計り知れない価値がある。 素晴らしい才能の持ち主の外見や行動はあなたとは違う事も多い。だから自分の先入観を自覚し、目の前の相手が素晴らしい成功をつかむ為の情熱と知性と人格を持っているかだけに意識を集中する事。 経験の乏しい人材は、「通常は不可能と思われている事すら知らない」人材である。 社員数が500名を超えるころになると、マネジャーは誰を採るかよりも、頭数を確保する事ばかり考えるようになる。とびきり優秀な社員の数を二倍にするには、社員全員に一人ずつ優秀な人間を連れてきてもらえばよい。採用を人事任せにすると、社員の質は低下する。 採用を全社員の担当業務に含める方法は、紹介者の数や面接数等、結果を測ること。 「何に驚きを感じましたか?」「学費をどう工面しましたか?」「あなたのウェブ検索履歴を眺めたら、履歴書に書かれてないどんな一面が発見できますか?」等、相手の理解を深められたり、思考能力が判る質問をする。マネジメント候補の場合、「あなたが危機的状況に陥ったらどうしますか?」等のシナリオ問題も役に立つ。 面接のフィードバックは48時間以内にすること。最高の面接官は、面接直後にフィードバックフォームに記入している。 面接時間は30分で。回数の上限は5回とすること。 スマートクリエイティブが高い評価を受ける4つのカテゴリ リーダーシップ 職務に関連する知識 全般的な認知能力 グーグラーらしさ (曖昧さへの許容度、行動重視の姿勢、協力的な性向) インターネット世紀でもっとも重要なのは、プロダクトの優位性。なので、もっとも手厚い報酬を受け取るべきは、最高のプロダクトやイノベーションの近くにいる人々。 採用プロセスを厳格にする事。偽陰性(採用すべきだったのにしなかったケース)が出る方が偽陽性(採用すべきじゃなかったのにしたケース)が出るより好ましい。これが運用されているのかのテストをしてみよう。下位10%の社員を解雇し、代わりに新規採用者を入れたら組織全体のパフォーマンスが改善するか?する場合は採用プロセスを見直したほうがいい。もう一つ、退社したいと言われても、懸命に引き留めようと思わない社員がいるかどうか。 他人をクビにするのが好きな人間には注意する事。解雇は恐怖の文化を醸成し、それは間違いなく組織を蝕む。「できない奴はクビにすればいい」と言うのは採用プロセスの適正化に十分な時間をかけない言い訳に過ぎない。 グーグルの採用の掟 ・自分より優秀な人物を採用せよ。学ぶもののない、あるいは手強いと感じない人物は採用してはならない。 ・プロダクトと企業文化に付加価値をもたらしそうな人物を採用せよ。両方に貢献が見込めない人物は採用してはならない。 ・仕事を成し遂げる人物を採用せよ。問題について考えるだけの人物は採用してはならない。 ・熱意があり、自発的で、情熱的な人物を採用せよ。仕事が欲しいだけの人物は採用してはならない。 ・周囲に刺激を与え、協力できる人物を採用せよ。ひとりで仕事をしたがる人物は採用してはならない。 ・チームや会社とともに成長しそうな人物を採用せよ。スキルセットや興味の幅が狭い人物は採用してはならない。 ・多才でユニークな興味や才能を持っている神斑を採用せよ。仕事しか能がない人物は採用してはならない。 ・倫理観があり、率直に意思を伝える人物を採用せよ。駆け引きをしたり、他人を操ろうとする人物を採用してはならない。 ・最高の候補者を見つけた場合のみ採用せよ。一切の妥協は許されない。 特にハイテク業界では、優れた仕事をするだけでは成功できない。巨大な波を少なくとも一つはとらえ岸まで乗っていかなければならない。一番大切なのは正しい業界を選ぶこと。なぜなら別の業界に移るのはとても難しいから。業界は波乗りをするポイント、企業は波だ。 財務に関する意思決定をする場合には、通常現金と売上高だけに集中すればよい。EBITDAやADR、BPMなどは不要。 コンセンサスの語源はラテン語で「一緒に考える、感じる」であり、「満場一致」の意味ではない。全員にイエスと言わせる事ではなく、会社にとって最適解を共に考え、その下に結集する事。これの達成には意見の対立が不可欠。オープンな雰囲気の下、出席者が自分の意見や反対意見を述べる事。全ての選択肢を率直に議論しなければ全員が納得し、結論を支持する事は不可能だから。 「全員同意見という事は、誰かがモノを考えていないという事~パットン将軍」 正しいコンセンサスプロセス 包含(全ての利害関係者に参加させる) 協力(ときには少数意見や個人の主張を犠牲にしても全体にとって最適な決定を目指す) 平等(全ての参加者が同じように大切で、反対意見を述べる事が認められる) ソリューションの質(最高の判断であり、最低限の妥協ではない) 「自分の意見を通す事より、最高の意見を見つける事を考えよ。」 会議のルール ・単一の意思決定者、すなわち、オーナーを置く。 ・意思決定者自らが招集する。 24時間前までに議題を配布する事。終了後は、意思決定者自身(他人にやらせてはダメ)が決定内容や行動計画をまとめ、48時間以内に参加者全員にメールする。 ・会議の目的が意思決定ではない場合も必ずオーナーを決める オーナーは参加メンバーの顔ぶれ、議題が明確である事、必要な作業がきちんと行われていること、会議後に行動計画が迅速に配布される事に責任を持つ。 ・会議は政府機関ではない。簡単に廃止できるように。 ・会議は8名以下が妥当。 ・会議に出る事が重要な人間の証ではない。 十中八九、会議の参加者は少ないほどいい。 ・時間管理は重要 時間通りに始め、時間通りに終わらせる。締めに、結論と行動計画をおさらいする時間を残すこと。海外のスタッフへの配慮はあなたへの敬意につながる。 ・会議に出るなら真面目に マルチタスクはNG。副職をしない。全員、その内容に集中すること。出席する会議は最小化する事。 カウボーイルール インターネット世紀には、リスク回避最優先姿勢は通用しない。企業の進化のスピードが法律の変化をはるかに上回るから。 企業で権力者となる人間の多くはチームワークに優れている為ではなく、経営上層部での権力闘争に勝ち抜いた為にその座を掴んだのであり、それは情報を隠そうとする意識を助長する。だが、現在の従業員の仕事は「働く事」から「考える事」に変わった今、会社全体の情報の流れを24時間、365日最適化する事が重要。今日の企業にとって真の生命線は情報である。スマートクリエイティブに十分な情報を与えない限り、素晴らしい仕事をさせる事は不可能。 TGIFでは多くの情報が赤裸々に語られるが、この情報が外部に漏れたことは一度もない。重要な情報を社員を信頼して共有すれば、彼らはその信頼に応えようとする。 「人間の本質は、質問に答える事ではなく、自ら質問する事だ。」 新プロダクトや主要機能を発表した後、担当チームに反省会をさせる。 全員で集まり、うまくいったこと、いかなかったことを話し合い、結果を公表する。この最大の成果はプロセスそのものである。率直で透明性の高い、誠実なコミュニケーションをうながす機会を逃さない事。 単調な会議を面白くする簡単な方法は、参加者に出張の報告をさせる事。出張した人がいない場合は、週末に何をしたかでも。担当業務に関わらず、会社全体、業界、パートナー企業、異なる文化について自分の意見を持つ事を奨励しよう。 年1回、自分自身の仕事ぶりを振り返って書き出し、読み返し、自分なら自分の下で働くか考えてみよう。これを自分のスタッフ達に共有しよう。まずは自分自身を批判する事で、周囲の人間が率直に意見を言いやすくなる。これは360度評価よりもよほど有益な情報が得られる。 メールの使い方 ・誰に対してもすぐに返信する フラットで能力主義的な企業文化を構築できる ・無駄な長文はいらない ・受信トレイは常に綺麗に ・LIFO(last in first out)で対応する 新しいメールから先に対応する事 ・自分がルーターであるのを忘れずに 共有すべき人に共有しよう ・BCCは原則NG 隠し事は非生産的で企業の透明性が下がる ・メールで相手を叱らない 叱るとき必ず会う事。 ・仕事の依頼をフォローアップしやすくする 誰かに行動を求める場合、件名に「フォローアップ」と書いて自分宛にも送っておく。 ・あとで検索しやすいように工夫する 1対1の面談リスト MTG前に以下の中から話し合うべきトップ5項目を双方で書き出して照らし合わせる。 1. 職務に対するパフォーマンス A.売上数値など B.プロダクトの発売、マイルストーンなど C.顧客からのフィードバック、品質など D.予算数値など 2. 他の部署との関係 A.プロダクトとエンジアリング B.マーケティングとプロダクト C.セールスとエンジニアリング 3. マネジメント・リーダーシップ A.部下の指導、コーチングをしているか? B.質の低い社員を選り分けているか? C.採用に真剣に取り組んでいるか? D.部下たちを英雄的行動に駆り立てているか? 4. イノベーション(ベストプラクティス) A.常に前進しているか。どうすれば常に向上できるか考えているか? B.新しい技術、プロダクト、仕事の方法を常に評価しているか? C.自分と業界・世界のトップ企業を比較しているか? 取締役がやるべきは「首は突っ込み、手は出さない」事。 事業は常に業務プロセスを上回るスピードで進化しなければならない。だからカオスこそが理想の状態。 「全てがコントロールできていると感じるのは、十分な速度が出ていないサインだ。~マリオアンドレッティ。F1レーサー」 カオスの中で必要な業務を成し遂げる唯一の手段は人間関係。社員の配偶者、子供の名前、重要な家族の問題を覚えておこう。 イノベーションは単に「新しい」だけでなく、意外性も不可欠。つまり、「新しく意外性があり、劇的に有用」なもの。 また、イノベーションを部分的にではなく、包括的に定義すれば、既存事業に携わる者でも誰でもチャンスはあるという考え方につながる。 それが対象としているのは、数十億人に影響を及ぼすようなものか? すでに市場に存在するものとは根本的に異なる解決策のアイデアはあるか?その為の画期的な技術はあるか? イノベーションに取り組む舞台には、今後大きくなりそうな市場を選ぶのがよい。からっぽな市場には企業の成長を維持するだけの規模がない。 その分野の技術はどのように進化してくか?現在との違いは何か?他にはどんな違いが生まれるだろうか?その進化する環境の中で、持続的に他社との明確な違いを出していくための人材はそろっているか? CIO(最高イノベーション責任者)は無意味。イノベーションは管理して生まれるものではないからだ。イノベーティブな人材にイノベーションを起こせという必要はない。そうする自由さえ与えていればよい。イノベーションは原始スープから生まれる突然変異のように、自然発生的なものである。その過程で強力なアイデアほど信奉者を集め、勢いをつける一方、弱いアイデアは道端に打ち捨てられていく。この進化を人為的なプロセスで生み出すことはできない。決まった生成プロセスが存在しないことこそがイノベーションの顕著な特徴。 イノベーティブであろうとする企業は、まず創造に必要な多様な要素が自由自在にこれまでにない面白い形で衝突し合うような環境、つまり原始スープを生み出す時間と自由を与えよう。 イノベーションの原始スープは、イノベーティブであろうとする人々(丘の斜面で一人で踊っている愚か者)にやりたいようにやらせる環境だが、それと同じくらい重要な事として、イノベーティブな取り組みに加わりたいという人々(踊りに加わる二人目から200人目)の背中を押すためのもの。業務や地域の壁を超えて、会社全体に浸透させなければならないのはこのため。イノベーティブな活動を特定のグループに隔離すると、そこにはイノベーターは集まるが、最初のフォロワーが十分確保できない。 新しいアイデアを思いつくだけの頭の良さと、それがうまくいくはずだと考えるだけの頭のおかしさを持ち合わせた人材を採用しよう。そんな楽観的な人材を見つけ、獲得したら、彼らが変化を起こし、冒険できる場所を与えよう。 グーグルでは、主力プロダクトに重大な変更を加える数週間前になっても誰も詳細な収益分析をしていなかった。なぜならそれがユーザーファーストになる事だけは明らかだったから、それを実施する事が正しい経営判断であると誰もが考えたのだ。 ユーザーか顧客かの対立が起きた時、業界を問わずどんな企業でもユーザー側に立つべき。なぜならユーザーの力はかつてない程強大だからだ。 優れたOKR(Objective and Key Result)の特徴は、大局的視点に立った目標を、測定可能性の高い意味のある結果と組み合わせる事。 70:20:10ルール リソース配分の7割をコアビジネスに、2割を成長プロダクトに、1割を新規プロジェクトに割り当てる。 最高の人材を採用し、つなぎとめたいならば、彼らに多くの意思決定を任せ、ヒエラルキーではくアイデアに基づいて経営しなければならない。最高のアイデアが勝利しなければ、優れた人材は会社にとどまらない。 優秀な人材を採用し、放っておく事。 20%ルール(就業時間の2割を自由な活動にあてる)の最も重要な成果は、そこから生まれる新プロダクトや機能ではなく、新たな試みに挑戦する経験を通じて社員が学ぶこと。日常業務では使わないスキルを学び、普段は一緒ではない同僚と協力する事で以前よりも優秀になる。このルールほど効果的な社員教育プログラムはないだろう。 プロダクトを作り、世に出してから手直しする。勝つのはこのプロセスを最も速く繰り返す事のできる企業。 世界的イノベーションの多くは全く用途の異なるものから生まれている。アイデアは潰すのではなく、形を変えよう。 自分たちにとって一番嫌な質問をしよう。未来に向けて何をすべきか、会社についてあなたは気づいているのに他の人々が気づいていない事、あるいはわざと無視している事は何か?簡単に答えの出ない一番嫌な質問は。大企業のリスク回避的な変化に抵抗する傾向を抑えるのに絶大な効果を発揮する事がある。 5年後に何が真実となっているか、考えるところから始めよう。企業が潰れるのはたいてい自分たちがやってきたことにあぐらをかき、漸進的変化しか生み出さないためだ。常識を捨て、想像力をたくましくし、これからの5年であなたの業界で起こり得ることは何かを自問しよう。一番速く変わるものは何か?全く変わらないものは何か?未来がどうなりそうか考えがまとまったら、さらに難しい質問を考えよう。カニバリや売上減少を理由にイノベーションの芽を摘んでいないか?利用が拡大するのに伴い、リターンや価値が高まるようなプラットフォームを構築するチャンスはないか? 経営陣は採用を経営の最優先課題にしているか?幹部は実際の採用活動に時間を割いているか?優秀な社員のうち、3年後も残っていそうなのはどれくらいか?ライバル会社から10%の昇給を提示されただけで会社を去りそうな人材はどれくらいいるか? 従業員はどれだけの自由を手にしているか? 新プロダクトに関する決定は、利益ではなく、プロダクトの優位性に基づいて行われているだろうか? 情報を囲い込もうとする人と、ルーターのような働きをする人では社内でどちらが成功しているか?縦割り主義によって情報や人の交流が妨げられてないか? 金融のハブ ニューヨーク、ロンドン、香港、フランクフルト、シンガポール ファッションのハブ ニューヨーク、パリ、ミラノ エンタメのハブ ロス、ムンバイ ダイヤモンドのハブ アントワープ、スーラト バイテクのハブ ボストン、バーゼル エネルギーのハブ ヒューストン、ダーラン 輸送業のハブ シンガポール、上海 自動車のハブ 南ドイツ スマートクリエイティブを獲得するために、私たちが出かけていくべきか、それとも彼らを私たちの方に呼び寄せる方法を考えるべきか? 教育は確実に進化するはずであり、テクノロジープラットフォームによって、自らの強みや弱みをこれまで以上に正確に把握できるようになり、自分のやりたいことに合わせてカスタマイズされた教育内容を選択できるようになる。生涯教育は積極的に推進されるだろう。
0投稿日: 2014.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートクリエーティブ 自分にとって一番嫌な質問をする 5年先を考える 10倍のスケールで考える 狭い方がいい 会議で発言しないのは、会議に出る必要がなかったということ 学び続けるものは若さを失わない ラーニングアニマル Laxテスト 最高の役員会議の資料とは、全ての主要事実が紙1枚に要約され、その裏付けとなる資料が一式揃っている 収益の8割を稼ぐ事業に8割の時間をかけよ 上昇、告白、順守→パイロットの掟
0投稿日: 2014.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「どんな分野でも、他の人々に一歩先んじる最高かつ最も簡単な方法は、それについて知識を深めることだ。最適な方法は、文献を読むことである。」
0投稿日: 2014.12.06 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの働き方マネジメントといえば、 通勤(専用バス)や食事(有名シェフによる無料の食事)など社員への厚遇ばかりが取り上げられがちですが、本書は、そこから先、グーグラーと呼ばれる人々の本当の 執務エリアと、そこで行われている業務の基礎となるプロトコルにしっかり触れられる一冊。 スタイリッシュで自発的で寛容などという言葉だけで済むものではありません。やはりそこには絞り出すような技術研鑚と濃密な人間関係の泥臭さが在ります。 だって、あれだけの会社が綺麗ごとだけで廻るわけがない。 職場というより実験室に近いような同社ですが、企業理念やダイバーシティなどへの同社の真摯な取組みにも本書では触れられ ています(以下、一部引用)。 --- これがどの会社の企業理念であるか分かる だろうか。 「当社の使命は、従業員の知識と創造性と 献身を通じてお客様と比類なきパートナーシップを築き、価値を生み出し、それによって株主に最高の結果をお届けすること です」 これはリーマン・ブラザーズのミッション ステートメント、あるいは少なくともかつてミッションステートメントだったものという事ができるだろう。
1投稿日: 2014.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleがどういう会社で、何を目指し、どう運営されているかをリアルに感じられる。スマートクリエイティブを如何に大切にしているか、ユーザー重視の考え方など徹底した社風と、それを支えるシリコンバレーのエコシステムや、エリックシュミットとその周りを囲む様々な人々など。 テクノロジーによって様々な業界が向こう数十年で大きく変革する中で、どの企業にも重要な組織論、経営論、人生論など盛り沢山。
0投稿日: 2014.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleと言えばエリートが集う最も先進的な企業のイメージだが、その秘密が凝縮された1冊だと思う。 大半の企業では企業理念は形骸化しているように感じるが、 本書のGoogleでは「邪悪になるな」というミッションによって個々が自らアクションを起こせる風土・文化が形成されているのだと感じた。 グローバル企業にも関わらず絶えず挑戦・イノベーションを起こせるのは凄いの一言に尽きるが、日本にもそのような企業文化が根ざしていく事を期待したい。
1投稿日: 2014.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの人材戦略であるスマートクリエイティブ(ドラッカー的には知識労働者だろうか)について語られています。従来の希少価値をベースにした価値観が変わりつつある。新しい価値を生み出すために有益な方法論はグーグルーは作り出せた。その仕組みを知ることができる内容になります。
0投稿日: 2014.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログエリック・シュミットが文化、戦略、人材、意思決定、コミュニケーション、イノベーションなどGoogleの経営について語ります。身も蓋もない言い方をすれば、情熱、知力に勝り、学習熱心そして面白いエンジニアを採用し自由闊達な雰囲気で会社で楽しく過ごせるような設備を整えれば、コミュニケーションはよりオープンになるだろうし、イノベーションも起こるだろうな思う。チャレンジを是とする彼らですが、採用が思いのほか慎重、企業は人なり、やはりここを最も重要視しているようですね。
0投稿日: 2014.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートクリエイティブがキーワード。 ユーザ中心のプロダクト製作、会社の透明性、技術力が今のgoogleの成功を作った要因であると言った事が書かれている。
0投稿日: 2014.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ方針が一貫し、建て前じゃないのがよくわかる。 いいことが散りばめられて書かれている。 自由に見えるけど厳しく徹底されていることもあるんだな。 Googleでなきゃ星3をつけてそうな気もする(^_^;)
0投稿日: 2014.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleのようなスマート・クリエイティブな人材を惹きつけ、強い組織を作るには? いやー面白かった。 こういう会社で働くのは楽しいだろうな。 スタートアップはもちろん、あらゆるマネジメント層が読んで損はない1冊。何か気付きが得られると思います。
0投稿日: 2014.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログSmart Creativeを集めるために、googleがどれだけ熱心に取り組んでいるかということが非常によく分かる一冊です。Startupはもちろん、あらゆる組織においてマネジメントに関して気付きがある一冊です。
0投稿日: 2014.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログどこからでも繋がれるモバイルデバイスや便利なウェブサービスなどテクノロジーが、さも当然のように享受されている世の中。よく考えれば、こんなのが普通の消費者の手に入ること時代が驚異的はなず。スマートクリエイティブと呼ばれる一部の人間達が生み出してきたテクノロジーをただただ消費するだけではいかんだろうと改めて思った。 また、成功への優位性を確保するために、スピードが求められているのがテクノロジーで、それが昨今のめまぐるしすぎるアップデートなど製品やサービスのサイクルが短くなりすぎている原因でもある。変わらなければ生き残ってはいけないのだろうが、それでもスピードがはやすぎるなあとぼやく自分。
1投稿日: 2014.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleのようなタレント揃いの強い組織を作るには? そもそもタレントをどのように組織に呼び込むのか? 継続して独創的なアイデアを出し続けるにはどうすれば? を紹介してくれています。 ・成果が出た人に対しては報酬で応える ・失敗=駄目といった文化を作らない ・自由に発言させる環境を作り上げる と色々なことを紹介してくれていますが、 中でも興味深かったのは「採用」 採用が出来る人は、それだけで評価が高いといった 印象を受けるくらい大事にしていると感じた。 確かに採用では相手を理解するために 色んな質問を投げかけたり心理を探ったりするので、 交渉力向上に繋がるといった効果もあるのだろう。 しかもほとんどが初見なので、難易度の高い仕事でもある。 短い時間の中で候補者を見極め評価するだけでなく、 評価した結果のフィードバックを、 論理的に相手に分かるように返さなければならない。 結局は仕事の大半はヒューマンスキルで決まってしまうので、 一番成長に繋がる職務かもしれない。 また、Googleがスペシャリストではなく、 ゼネラリストを求めているというのも意外だった。 ゼネラリスト=吸収力が高いという考え方だそうな。 未来を創るという観点では、今がどうではなく、 将来の変化についてこれるか否かが大事なのだそう。 だから、ゼネラリストのほうが好ましいとのこと。 とはいえ、中途半端では駄目なのも事実。 だから採用は狭き門となっているんだろう。 他にも色々見習いたいことがあるので、 今後の仕事の中で活かしていこうと思う。 【勉強になったこと】 ・スマートクリエイティブであれ スマートクリエイティブとは、 分析力にすぐれている ビジネス感覚もすぐれている 競争心旺盛 ユーザをよく理解している 好奇心旺盛 失敗を恐れない 自発的である あらゆる可能性にオープンである 細かい点に注意が行き届く コミュニケーションが得意 である人のことを指す。全てを兼ね備えるのがベストだが、 最低限、ビジネスセンスがあって、クリエイティブで、 自分で手を動かせる姿勢を持っていること。 ・ビジョンなど、繰り返し伝え、報償によって強化しなければ、 それが書かれた紙ほどの価値もない。 ・成功している大企業の特徴 ①問題をまったく新しい方法で解決する ②その解決法を活かして急速に成長・拡大する ③成功の最大の要因はプロダクトである ・情熱のある人間は情熱を口にしない 逆に心に秘めており、それが生き方に表れてくる。 粘り強く、真剣で、全てをなげうって没頭している。 ・面接のスキルを高めるには練習するしかない。 時間的制約の中で相手を見極めるのは非常に難しい。 準備を怠らず、相手とのやり取りを通して、 相手を理解することが重要だが、初見であるがゆえに、 高度なスキルが要求される。 ・Googleの採用のおきて 自分より優秀で博識な人物を採用せよ プロダクトと企業文官に付加価値をもたらす人物を採用せよ 仕事を成し遂げる人物を採用せよ 熱意があり、自発的で、情熱的な人物を採用せよ 周囲に刺激を与え、協力出来る人物を採用せよ チームや会社とともに成長しそうな人物を採用せよ 多才でユニークな興味や才能を持っている人物を採用せよ 倫理観があり、率直に意思を伝える人物を採用せよ 最高の候補者を見つけた場合のみ採用せよ ・相手の行動を変えたいなら、説得力のある主張をするだけ でなく、相手のハートに触れなければならない。 ・自分の下で働きたいと思うような上司であれ ・最初のフォロワーが孤独な愚か者をリーダーに変える ・70対20対10のルール リソースの70%をコアビジネスに、20%を成長プロダクトに、 10%を新規プロジェクトに充てること。 新しいアイデアに投資をしすぎるのは、投資が足りない のと同じくらい問題である。 過剰な投資をすると、プロジェクトの良い部分だけを 見ようとする意識的な確証バイアスが生じ、 健全な意思決定の妨げとなる。 ・経営者の仕事は、 リスクをとり、避けられない失敗に耐えられるだけの 強靭な組織をつくることである。
0投稿日: 2014.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ5年後のキャリア計画を考えようって、今の僕にはピッタリだと思った。自分は一体どうなりたいんだ?たどり着きたい場所をきちんと定めたい。 大きな組織にいて、考え方が八方ふさがりになってないか?いろんな制約を忘れて、自由な発想ができなくなってないか? 会社員だから、とか関係ない。気持ちはいつも自由で。
1投稿日: 2014.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログあらゆる物事について、Googleがこれまでにどのような行動をしてきたか、というエピソードをたくさん寄せ集めた事例集のようなものになっていて、その一つひとつが面白かった。 いまや数十億ドルを稼ぎだすようになったグーグルの広告配信サービス「アドセンス」は、ある日たまたま本社で一緒にビリヤードをしていた、さまざまなチームに所属するエンジニアたちが発明した。あなたの配偶者やルームメイトがどれほどすばらしい人でも、自宅で二人で休憩していて数十億ドルの事業を思いつく可能性はきわめて低いだろう(たとえビリヤード台があったとしても)。オフィスに社員を詰め込み、たくさんの娯楽施設を用意し、積極的に使ってもらおう。(p.64) 候補者の経歴が空きポストと合致するか否かにかかわらず、とにかく優秀な人材を採用することに集中する。エリックは、シェリル・サンドバーグにふさわしい仕事がないにもかかわらず、採用のオファーを出した。ほどなくしてシェリルは法人営業チームの立ち上げという職務を担当することになったが、それは入社した彼女自身がつくったポストだ。(p.142) 私たちが新たな20%プロジェクトを立ち上げようとする社員に常にアドバイスするのは、まずはプロトタイプを作ってみろ、ということだ。それが周囲の人々を夢中にさせる最適な方法だからだ。アイデアを思いつくのは割りと簡単で、それより何人かの同僚にプロジェクトに賛同してもらい、自分だけでなく彼らの勤務時間の20%を投じてもらうほうがずっと難しい。(p.313)
0投稿日: 2014.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ間違いなく現代のリーディングカンパニーであるGoogle。旧来の概念に縛られないマネジメントを”実践”しているところが素晴らしい。 ・「戦略の基本」はもはや通用しなくなった。計画は流動的だが、基礎はゆるがない ・21世紀を引っ張るのは、グローバルでオープンな企業だ ・自分の意見を通すことより、最高の意見を見つけることを考えよ ・リーダーは常に”コミュニケーション過剰”であるべきだ ・ユーザーはかつてないほどの力を手にしている ・物事を10倍スケールで考える ・「何が起こるか」ではなく、「何が起こり得るか」を自問しなければならない
0投稿日: 2014.10.25
