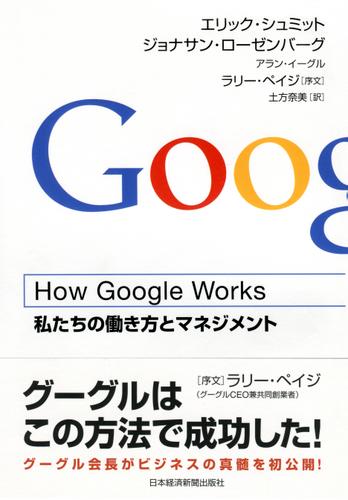
総合評価
(149件)| 41 | ||
| 53 | ||
| 37 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ職種は違えど楽しく働くためにはが詰め込まれた一冊だと思った。仕事を楽しく熱中できるように自分もまだまだ勉強したいと感じた。
0投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ前々から気になっており,図書館で借りて読了 いろいろと発想のきっかけがある本だった. ベンチャーでないと参考にならないのでは?と思いそうだが,世界的大企業になった今でもイノベーションを続けていることを考えるとそんなことはない.新しいことってこういう時に生まれるというのを思い出させてくれた. 本書全体に通じているのは「いかにスマートクリエイティブがクリエイティブな仕事ができるようにするか」ということで,そのために目次にもあるように 企業文化・戦略・人材・意思決定・コミュニケーション の軸でGoogleの考え方(つまりは創業者であるラリーとセルゲイの考え方)が書かれている. 人によって参考となる部分,微妙と思う部分はそれぞれだろうが,私の場合, ・プロダクトの優位性を築くのは技術的アイデア(マーケットインは当たりやすいかもしれないが優位性が難しい) [P103] ・マネジャーの最も大事な仕事は採用ということ(意外と見落としがち!)[P140] ・イノベーションと統一的な指揮命令系統は自己矛盾的であること(早くない・尖らない・試せない..)[P285] など. 一度で全て覚えるのはできないので,たまに見返すのがいいかもしれない.
5投稿日: 2025.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログAppleの元取締役でGoogleの元CEOのエリック・シュミットと、Googleの元上級副社長で現在はアルファベット社取締役会顧問のジョナサン・ローゼンバーグが著者。 タイトル通り、経営者向け。 Google流の働き方と考え方は他の会社とはかなり違う。 著者は入社後すぐにビジネスとマネジメントを学び直さなければならないと悟ったそうだ。 スマート・クリエイティブと呼ばれる優秀なエンジニアだけが集まる企業が、どんな方法で社員達がアイデアを生み出しているか、イノベーションとはどんなことかなどが書かれている。 『オープン』にこだわる。 狭いオフィス(コミュニケーションやアイデアの交流) 組織はフラット。 20%ルール(仕事時間のうち、20%を自分の好きなことに使える時間。GoogleMapやgmailもここから誕生したらしい) 他、まだまだ沢山ある。 いやいや働いている人などいなそう。 やなやつも淘汰されそう。
11投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログスマート・クリエイティブ 計画を立てたところで、そのプロジェクトはうまく進まないことが決定 面接官はトレーニングが大事 面接時間は30分 こんな会社で働きたい Mountain View, CA 会議は8人がmax全員が意見を言えるように
1投稿日: 2024.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書はグーグルの前CEOだったエリック・シュミット氏と同僚のジョナサン・ローゼンバーグ氏によって、グーグルのマネジメントについて幅広く紹介している本です。題名通りHow Google Worksということが多面的かつきわめて骨太に記述されていて、とても勉強になりました。 本書を読んでグーグルについて知らないことがたくさんある自分に気付きました。その意味で「グーグル」を知らない人はほとんどいないと思いますが、「グーグルという会社」がどういう会社か、について私は本書から多くを学び、そして親近感がわきました。 具体的には、本書を読む中で、グーグルと高度経済成長時代に世界を席巻していた日本企業との間にいくつか共通点があることにも気付きました。例えばグーグルは顧客第一主義で、顧客に最高の製品・サービスを提供すれば、あとは(業績など)全部ついてくる、という信念。これなど典型的な日本の製造業の考えですよね。上場したのも、株主指向の経営をしようという意味では全くなく、従業員にグーグルの信念や価値観を明文化して広めるよいチャンスだと捉えたため、というような点です。 日本企業(特に成熟した大企業)の経営幹部は、グーグルと聞くと、変化の激しいIT業界にいて、大学みたいな会社でうちとは全然違うのだから何も学ぶものはない、と思う人もいるかと思いますが、日本企業が忘れかけている大事な信念を持ち続けている会社と思って見る必要があると思います。 またグーグルは人材確保に極めて重きを置き、世界のスマート・クリエイティブを惹きつけることにかけては大成功しているのですが、その根本には顧客に最高の製品・サービスを提供するには、なるべく多くのスマート・クリエイティブを集める必要がある、ということで、これはIT業界に限らずどの業界でも共通なわけです。本書はIT業界に限らず成熟した業界の人も是非一読して、自社に足りないもの、自社が忘れかけているものに気付くきっかけになるのではと思います。
0投稿日: 2023.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読書というのは常々、コスパの高い投資と思うが、本書はまさにそれ。 Googleのプロダクトや人の採用(スマート・クリエイティブ)を重視している姿勢をよく学べたと思う。 新しいことのチャレンジも、連戦連勝ではないこともよく理解できた。 webの世界は、物理的なモノがない、というか見えにくいので、プロダクトという概念があまり自分にはなかったが、実際にはかず多くのプロダクトがあることも学べました。 読んで損はないどころか、得るものばかりでした。 ユーザを中心に考える。 企業の成功に最も重要な要素はプロダクトの優位性。 失敗するコストが大幅に低下、成功やプロダクトの優位性を支えるのはスピード。 スマートクリエイティブを惹きつける出発点は企業文化。 →リーマンのミッション事例。従業員が信じられるかどうかにある。 世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること。 ビジョンは繰り返し伝え、報奨によって強化しなければ、それが書かれた紙ほどの価値もない(ジャック・ウェルチ) 楽しい…一番大きいのは、同僚と一緒に笑ったり、ジョークを言い合ったり、共に仕事をすることの楽しくさであるはずだ。お楽しみイベントには、本当の楽しさがない。 邪悪になるな。 市場調査ではなく技術的アイデアに賭ける。 大切なのは、顧客の要望に応えるより、顧客が思い付かないような、あるいは解決できないと思っていた問題解決へのソリューションを提供すること。 失敗したケースは例外なく技術的アイデアが欠けていた。 速い馬はいらない。 ライバル動向へのこだわりは、凡庸さへの悪循環につながる。 どれだけ優れた戦略を立てても、優れた人材の代わりにはならない。 組織内での地位が上がるほど幹部は採用プロセスから遠ざかる傾向があるが、本来はその逆であるべきだ。 情熱家はそれを表に出さない、心に秘めている、生き方に表れてくる、粘り強さ、気概、真剣さ、没頭する姿勢。履歴書には表れず、既に成功してるとは限らない。 ムダ話をさせるのではなく、むしろムダ話を奨励。 自分より優秀な人間を採用せよ。 ビジネスパーソンが磨くべき最も重要なスキルは、面接スキル。 採用の質を落としてまで埋めるべきポストはない。 会議が時間の無駄だと文句を言う人は多いが、運営がうまい会議ほど、素晴らしいものはない。 経営者にはコーチが必要。 自分の下で働きたいと思うような上司であれ。 メールはすぐ返信。了解、でも良い。コミュニケーションの好循環のため。 ユーザに焦点を絞れば、あとは全部ついてくる。 世に出して手直しする、アプローチはあとで改善することを前提に、質の低いプロダクトを送り出しても良いという考え方ではない。 何が起きるか?ではなく、何が起こりえるか?
0投稿日: 2023.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ僕は2015年入社の現役のグーグル社員なので、中の人ゆえにかなりスムーズに内容が入ってきた感じがありましたが、(外の人から見てどうかはわかりませんが、あなたがエンジニアなら非エンジニアの僕より内容がスラスラと入ってくるかもしれませんね)。書評としては、必ずデスクの上に置いておいて、逐一参照したい一冊だと思います。この本を今まで読まなかったことを後悔しています(まぁ読んでたら読んでたでちょっと破天荒にやりすぎていたかもしれないが)。この本が書かれた2014年と今日(2023年)ではかなりグーグル内も変わったと感じます。2014年の社員数と今の社員数では一体何倍に増えたんだろうというレベルでグーグルは成長しました。自分(非エンジニア)が本書に書かれているようなスマートクリエイティブかどうかは定かではありませんが、少なくとも僕が入社した2015年時点では、僕は本書に書かれているようなスマートクリエイティブの Googleyness を何度も見てきましたし、今でもそれを実践している人もよく知っています。僕もなんだかんだ古株になりつつあるので、グーグルの創業メンバーやエリック、ジョナサンの志に賛同するので、ユーザーの為に働き、他の社員を助け、プロダクトの優位性を大切に考えながら仕事をしていきたいと、再認識しました。
1投稿日: 2023.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ情熱のある人は情熱を口にしないという言葉がとても刺さった。 また、リーダーシップ、職務に関する知識、問題解決力、グーグルらしさの4カテゴリーが特に大切だということも学んだ
0投稿日: 2023.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦略、人材、意思決定、コミュニケーション、イノベーションについて、各章でまとめられている。 技術的アイデアは何か、ゴールに焦点を絞る。
0投稿日: 2022.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログアハライ→ついてこい! イスラエルの戦車司令官は、突撃!とは言わず、アハライ!(ついてこい!)と叫ぶらしい。 これが求めるべきリーダー像ということ。
0投稿日: 2022.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ良書 実質6つの章にGoogleでの仕事のやり方が集約されています。各章の内容の一部を以下へ 序文 ・漸進的なアプローチでは時代に取り残される ・テクノロジの世界では革命的変化が起こりやすい ・アイデアを生かしてありえないことに挑戦しよう はじめに ・三つの技術トレンド インタネット、携帯端末、クラウド 文化 ・共に働く仕事場をよくする ・フラットな組織 ・組織は機能別に 独立採算はとらない ・社員に責任と自由を与える ・イエスの文化 戦略 ・事業計画にではなく、人に投資する ・市場調査にではなく、技術的アイデアにかける ・小さな問題の解決に着目し、適用範囲を広げる ・特化すべき対象を見つける ・ライバルに追随するな 人 ・自分より優秀な人材を採用する ・情熱のある人は情熱を口にしない ・ラーニングアニマルを採用する ・人材の発見・獲得の輪、発掘・面接・採用・報酬 意思決定 ・データに基づいて決定する。でもハートも ・最適解に達するには意見の対立が不可欠 ・すべての会議にはオーナーが必要 コミュニケーション ・情報を隠すのではなく共有する ・人の本質は、質問に答えることでなく、自ら質問すること ・会話は最も重要かつ効果的なコミュニケーション手段 ・人に伝えたかったら20回繰り返せ ・自分の下で働きたいと思うような上司であれ イノベーション ・楽観主義 ・実現不可能な目標を設定する ・皆がもっているアイデアをつかう ・世に出してから手直しする ・良い失敗をする おわりに ・プラットフォームの台頭 ・世界の産業活動のハブの成長 ・コンピュータとの協業を行う
9投稿日: 2021.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの印象が変わった。 和訳された本なので、随所に記載されているジョークについては理解できない部分があった。
0投稿日: 2021.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「マイクロソフトに対抗するにはプロダクトの優位性を維持するしかないこと、その最も有効な方法は既定の事業計画に従うのではなく、優秀なエンジニアをできるだけたくさんかき集め、彼らの邪魔にならないようにすること」 「大切なのは顧客の要望に応えることより、顧客が思いつかないような、あるいは解決できないと思っていた問題へのソリューションを提供することだ。」 技術者のモチベに全てを捧げて、リスクを取ってイノベーションに賭けよう!!って感じでまんまスポ根で青春。 そこで問題が起きない為に、通底する「文化」が大事ってのもわかる。 否定は全くしないけど実現するのは中々むずいよね。 目から鱗の人材育成や組織論はとてもとても興味深く為になる。反面、どうしても自分は猛スピードのイノベーション(と、そのために身を粉にすること)を絶対的な善、と妄信する事ができない。 この本と「欲望の資本主義」を連続で読むと頭が混乱しちゃうだろうな。
2投稿日: 2020.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016年に読んだ時の評価は二つ星だったが、今回は格上げ。 組織のマネジメントを考える立場でみると、Googleみたいになるのは無理だ、ではなく、強い気持ちでやるねん!ということかと。 以下、留めおきたい内容→ 一度でも悪党らしき行いをした人間は、ずっと悪党だ。一瞬だけ誠実さを忘れる、といったことはあり得ない。 キャリア計画を作るステップ 5年後の理想の仕事とは?どこで何をしていくら稼ぐどんな内容の仕事か?転職サイトに載せる説明風に。 その仕事についた自分の履歴書はどんな内容か?そこまでに何をしたのか? 強みと弱みは?どんなスキルを磨く必要があるのか? どうすればその仕事に就けるのか?どんなトレーニングや実務経験がいる? デザイン的思考の中核的マインドセット:行動志向は、実践的で試行錯誤を厭わない考え方。ある行動をとることが正しいか確信が持てないなら、一番いいのは実際にやってみて、結果に応じて軌道修正すること。 事業は常に業務プロセスを上回るスピードで進化しなければならない、だからカオスこそが理想の状態だ。 従来型企業が迫られる選択: ❶これまで通りの生き方をする道 テクノロジーが変革のツールではなく、単にオペレーションを最適化し、利益を最大化するためのもの。市場に参入してきた新たなライバルが引き起こそうとしている破壊的影響は、ロビイストや弁護士を使って封じ込める。こうした現実逃避型アプローチは必ず悲劇的な結末を迎える。顧客の選択を妨げ、業界のイノベーションの足を引っ張るのが目的。理由は、企業レベルでは革新的なプロダクトはちっぽけで価値がないと見えること、個人レベルでは大企業の社員はリスクをとっても評価されず、失敗すると制裁を受けるので、個人にとっての見返りが非対称なため、合理的な人間なら安全な道を選ぶから。 ❷Googleのようになること 企業には必ず聞かれて嫌な質問があるが、聞かれないままのケースも多い。良い答えがなく、誰もが不安になるからだ。しかし、だからこそこうした質問に意味があるのだ。みんなを安穏とさせないためである。ライバルが本気で潰しにかかってくる前に、仲間内からの問い掛けで不安になった方がよい。
0投稿日: 2020.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ自身の勤める会社とは異業種で、且つトップを走るGoogleの経営陣が著した本書。6年前の本とはいえ古さを感じさせない。また単なる経験談に限定されずアカデミックな研究とも相まった内容であり、興味深い。どのような業界の企業であれ、学ぶべきところは多分にある。Googleの精神を知ることによって彼らの商材に対する関心も高まった。「スマート・クリエイティブ」という人称について当初はイメージがつかなかったが、深く理解できた。起業家や経営者だけでなく、社会経験があり、深く内省する習慣のある社員や、具体的なGoogleの事例を自社に置き換えて革新を進める意志のある方には是非ご一読頂きたい。単に読み物としても面白い。
0投稿日: 2020.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの人事観はリクルートに非常によく似ています。 優秀な人材を採用することを経営の重要事項に置き、 各部署で営業をかけるかのように採用するさまはあるべき姿であり、 それが成長の原動力にもなっていると感じました。 ビジネススクールでは採用の重要性を教えるが、 優秀な人材かを見抜くスキルや口説くスキルは誰も教えてくれないという点はまさにその通りだと思います。 小手先のノウハウを真似るのではなく、 まずは人事観から真似ることが大事です。
0投稿日: 2020.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleがなぜイノベーションを起こし続けているかが納得できる。 目習うべきたくさんのTipがあり、日本の大企業は少しでも変革すべき。 オールドスクールなやり方の自社営業部を少しでも変えていきたい。
1投稿日: 2019.07.28時代の変化に対応するには優秀な人材を集める、に尽きる
本書内で登場する技術力もビジネススキルも兼ね揃える優秀な人材スマートクリエイティブ、彼らを惹きつけ、いかにノビノビと働かせるかが、成功の鍵となると説く。 情報収集、高速通信への接続、コンピューティング能力利用のハードルが著しく下がったこの時代の変化から、プロダクトそのものの優位性を保つことのみが企業の優位性を保つ唯一の手段となりつつある現状にフィットしたようだ。 優秀な人材、そして彼らを惹きつける企業文化・環境をこれまで以上に重視しなければいけないが、具体的な企業運営方法は、なかなか見えにくい。 それでも、幾つかの事例が紹介されている本書から、Googleが先行して蓄積したノウハウの片鱗は掴めるかもしれない。
0投稿日: 2019.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートクリエーターのモチベーションをいかに維持するか? 70:20:10の法則 企業の成功に最も重要な要素=“プロダクトの優位性”とその根底にある“技術的アイデア” 小さくてもよいものを生み出せる企業は生き残る。 大きな成功をつかみたいなら、単に「成長する」だけでは足りない。 「スケールする」必要がある 取締役会の議事録は全社員に公開する。 ※図書館で借りたのを紛失したので新刊を買って返却
0投稿日: 2019.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ刺激受けまくりでした。 もっともっと変化を起こせるように頑張ります。 でも、果たして今いる会社にずっと居続けることは正解なのか?ということもこの本を読んで考えました。
0投稿日: 2019.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログHow Google Works (ハウ・グーグル・ワークス) ―私たちの働き方とマネジメント こんな会社で働きたい! でも、それなりの スーパー能力がなければ !!(>д<)ノ 今から近未来のビジネスのあり方が、豊富な経験談や引用によって語られる。 IT業界でそうそうたる人物が登場するエピソードなど、 単なる読み物として、Googleのことを知るだけでも、すごく面白い。 凡人には想像もつかない理念や将来展望で成長してきたGoogle、 最初にシンプルな検索ページを見て使った時からその虜になっています。 使っていたのに消えてしまったサービスにもそれなりの理由がありことも分かったし、 今後 実現しそうな画期的なサービスにも期待しています。 ・ URLはこちら https://www.google.com/opengallery/ 『Google Open Gallery』 : 美術館や個人のギャラリーをウェブ上で公開できる ・ URLはこちら https://www.google.com/culturalinstitute/home?hl=ja 『Google Cultural Institute』 : Google Cultural Instituteは,「アートプロジェクト」「World Wonders Project」,「歴史アーカイブ(アーカイブ展示)」の3つのプロジェクトを主に進めている。 2014/12/04 予約 2015/7/10 借りる。7/11 読み始める。 7/27 読み終わる。 内容と著者は 内容 : 戦略、企業文化、人材、意思決定、イノベーション、コミュニケーション、破壊的な変化への対応といったマネジメントの重要トピックを網羅し、 Google社内の秘話を、驚異的なスピードで発展した社史とともに明かす。 【ビジネス書大賞2015、準大賞受賞作!】 グーグルは、この方法で成功した! グーグル会長がビジネスの真髄を初公開! 序文はグーグルCEO兼共同創業者のラリー・ペイジが執筆。 ■グーグル現会長で前CEOのエリック・シュミットと、前プロダクト担当シニア・バイスプレジデントのジョナサン・ローゼンバーグは、グーグルに入社する以前から経験豊富なIT業界のトップ・マネジャーだった。だが、2人が入社したグーグルは、「他とは違ったやり方をする」ことで有名だ。これは、ビジョナリーであり、人とは反対の行動をとりがちな共同創業者2人、ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンの方針に沿ったものだった。 ■入社してすぐにエリックとジョナサンは悟った。グーグルで成功するには、ビジネスとマネジメントの方法をすべて学び直さなければならない、と。本書では、著者2人がグーグルの成長に貢献しながら学んだ「教訓」を豊富な事例とともに語る。 ■テクノロジーの進歩は消費者と企業のパワーバランスを激変させた。この環境下では、多面的な能力を持つ新種の従業員――スマート・クリエイティブ――を惹きつけ、魅力的で優れたプロダクトを送り出す企業だけが生き残れる。戦略、企業文化、人材、意思決定、イノベーション、コミュニケーション、破壊的な変化への対応といったマネジメントの重要トピックを網羅。 ■グーグルで語られる新しい経営の「格言」(「コンセンサスには意見対立が必要」「悪党を退治し、ディーバを守れ」「10倍のスケールで考えよ」……など)やグーグル社内の秘話を、驚異的なスピードで発展した社史とともに初めて明かす。 ■すべてが加速化している時代にあって、ビジネスで成功する最良の方法は、スマート・クリエイティブを惹きつけ、彼らが大きな目標を達成できるような環境を与えることだ。本書は、ただその方法をお教えするものである。 内容(「BOOK」データベースより) グーグルはこの方法で成功した! グーグル会長がビジネスの真髄を初公開! 目次 : 文化 ― 自分たちのスローガンを信じる 戦略 ― あなたの計画は間違っている 人材 ― 採用は一番大切な仕事 意思決定 ― 「コンセンサス」の本当の意味 コミュニケーション ― とびきり高性能のルータになれ イノベーション ― 原始スープを生み出せ 著者 : エリック・シュミット Schmidt,Eric グーグル取締役会長。アメリカの大統領科学技術諮問委員会、イギリスの首相諮問委員会の委員を務める。 ジョナサン・ローゼンバーグ Rosenberg,Jonathan グーグル勤務。ラリー・ペイジCEOのアドバイザー。 アラン・イーグル Eagle,Alan
0投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ譁ー縺励>邨?ケ碑ォ悶?ら、コ蜚?↓蟇後s縺ァ縺?k縲 荳?譁ケ縺ァ縲√せ繝槭?繝医け繝ェ繧ィ繝シ繝?ぅ繝悶〒縺ェ縺??莠コ縺ッ縲??疲婿縺ォ證ョ繧後※縺励∪縺??ゅ?
0投稿日: 2018.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ・失敗するコストが大幅に低下した ・ビジョンなど、繰り返し伝え、報奨によって強化しなければ、それは書かれた紙ほどの価値もない ・マネージャーは肩書きが作る。リーダーは周りの人間が作る ・計画は流動的だが基礎は揺るがない
0投稿日: 2018.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
googleが成功したのは会社のためでなく、ユーザー至上主義であったために成功できたんだなぁと。 より優秀なスマートクリエイティブ同士が集まれば、収益はもちろん大事だけども、結果はあとからついてくるという信念のもと、プロダクトやサービスを作り続けているのは流石の一言。 コンセンサスは同意ではなく、その場のみんなで考えることだというのも自分にはなかった考えでした。 仕事の20%を自分の学びに使用できるのも素晴らしい文化だと思います。 僕も常にラーニングアニマルの姿勢で物事に取り組みたいと思います。
0投稿日: 2018.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ・「誰のアイデアか」より「まともなアイデアか」 ・グーグルで大切なのは、「何ができるか」であって、「どんなヤツか」ではない ・マネージャーは肩書きがつくる。リーダーはまわりの人間がつくる ・やるべき仕事があれば、忙しい人に任せろ ・学ぶこと自体が目標になると、くだらない質問をしたり、答えを間違えたりしたら自分が馬鹿に見えるのではないかなどと悩んだりせず、リスクをとるようになる ・意思決定者の任務とは、適切な期限を設定し、これ以上の議論や分析は意味がないと思ったら打ち切り、全員が最終決定を支持するようにチームを導く。ただ、切迫感に圧倒されてはならない。ギリギリの瞬間まで、どんな方向にも動けるような柔軟性を失わずにいよう ・会議は8人以下が妥当。10人が限界 ・メーリングリストを使わず適切な相手だけ選ぶようにすれば、受け取った相手が読むか確率が高くなる ・メールは「読者が読み飛ばしそうな部分は削る」 ・人間関係を深める―配偶者や子供の名前、重要な家族の問題などの細かな情報を覚えておく(スマホの連絡先アプリのメモ欄に入れておく) ・イノベーションとは、新しく、意外性があり、劇的に有用なものでなければならない
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016年4冊目 朝活アウトプット読書会で章単位に読んでいて、ようやく読み終わりました。 googleの現会長エリックシュミットとシニアバイスプレジデントが語るGoogleの働き方。 ・文化 ・戦略 ・人材 ・意思決定 ・コミュニケーション ・イノベーション の切り口で紹介。 まあ、独特の会社です。 文化の章では、社員にはしっかり休暇をとるように進めている。自分が会社の成功の為に欠かせない存在なので、1〜2週間も休暇をとったらとんでもない事になると思っていたら深刻な問題があるサインだとと言ったり、 戦略では、のっけから事業計画があれば、それは間違っているという事は100%断言できると述べている。 人材では経営者の一番大事な仕事は採用と語り、 意思決定では、会議では常に意思決定者をはっきりさせておく、意思決定者は自ら会議を招集するなど自ら動くなどいいつつも、会議に出る事が重要な人間の証ではないとも言っている。 コミュニケーションでは、情報は社員にはすべてオープン。 イノベーションでは業務の20%は自分の好きな事に使える。そこから新たなGoogleのサービスが生まれてくる事を紹介している。 どんどん新しいサービスを展開するGoogle。中に入ると自由闊達に見えてもかなりスピードが早い だと感じました。
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ【由来】 ・amazonからのメール 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・まぁ、期待した通りの内容。参考になる部分もあれば、あまり参考にならない部分もあり。 ・情熱、知力、ラーニングアニマル(P150) ・面接の目的は相手の限界を確かめること。最高の面接は友人同士の知的な会話のようなものだ(今、どんな本を読んでいる?など) ・エレベーター・ピッチを用意する。30秒でエレベーターで社長に自分のやってことを伝える。これはI'm readyということで、大前研一も言ってた。 【目次】
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログどのようにGoogleでは動いているか。Smart Creativeを集め、情熱を燃やし、課題に果敢に挑戦し続ける方法。文化、戦略、人材、意思決定、コミュニケーション、イノベーションの各章に渡ってGoogleでの働き方を述べている。
0投稿日: 2018.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログアップルが企業文化の貫徹がスティーブジョブズというカリスマに頼っていたのとは対照的に、本書を読むと、ジョブズのような人物はそうはいないのだから、企業文化を組織として築き上げていかなければならないという意識が存分に感じられた。また、コミュニケーションの重要性を幾度も説いており、藤本氏の言う日本企業が得意な「擦り合わせ」に通じるところがあり、興味深かった。 「経営者をしていて意外だったのは、プロジェクトチームにとんでもない野心を抱かせるのは、とても難しいということだ。どうやらたいていの人は型破りな発想をするような教育を受けていないらしい。現実世界の現像から出発し、何ができるか見定めようともしないで、最初から無理だと決めてかかる。グーグルが自律的思考の持ち主を採用し、壮大な目標を設定するためにあらゆる手を尽くすのはこのためだ。」 「マイクロソフトに対抗するにはプロダクトの優位性を維持するしかないこと、その最も有効な方法は既定の事業計画に従うのではなく、優秀なエンジニアをできるだけたくさんかき集め、彼らの邪魔にならないようにすることだと思うようになっていた。」 「インターネットの世紀のプロダクト・マネジャーの役割は、最高のプロダクトの設計、エンジニアリング、開発を担う人々とともに働くことだ。」 「私たちはできるかぎり、組織は機能別にすべきだと考えている。そしてエンジニアリング、プロダクト、財務、セールスなど各部門が直接CEOにレポートするのだ。なぜなら組織を事業部、あるいはプロダクトライン別にすると、それぞれの事業部が自分のことだけを考えるようになり、情報や人の自由な流れが阻害されるからだ。」 「実際のところ、計画はあってもかまわない。だが、事業を進めるのにともない判明したプロダクトや市場についての新事実に対処するために、計画を変えることを頭に入れておこう。」 「スマート・クリエイティブの明確な特徴は、情熱があることだ。何かに対して、強い思い入れがある。ただ、本当に情熱的な人間は『情熱』という言葉を軽々に口にしない。」 「情熱家はそれを表に出さない。心に秘めている。それが生き方に表れてくる。粘り強さ、気概、真剣さ、すべてをなげうって没頭する姿勢といった情熱家の資質は、履歴書でははかれない。…何かに本物に情熱を抱いている人は、最初はうまくいかなくても努力を続ける。」 「ここまで情熱、知力、ラーニング・アニマルのマインドセットが、採用候補者に欠かせない資質であることを述べてきた。もう一つの重要な要素が人格だ。単に親切で信頼感があるというだけでなく、多才で、世界と深くかかわっている人間、つまり『おもしろい』人間だ。」 「技術者や科学者が犯しがちな過ちがある。データと優れた分析にもとづいて、賢明かつ思慮に富んだ主張をすれば、相手を説得できるはずだ、と考えるのだ。これは誤りだ。相手の行動を変えたいなら、説得力のある主張をするだけでなく、相手のハートに触れなければならない。私たちはこれを『オプラ・ウィンフリーの法則』と呼んでいる。」 「オプラの法則を実践する、いたって簡単な方法がある。議論を打ち切り、出席者から100%支持されているわけではない結論を出すときに、こう言うのだ。『どちらも正しい』。誰でも自分の意見に反する決定を心から受け入れるには、まず自分の意見がきちんと聞いてもらえただけでなく、その意義を認めてもらえたと感じる必要がある。」 「いまや”部下に任せる”というスタイルは通用しなくなった。リーダーは細部を把握していなければならない。」 「仕事に限った話ではないが、何かを人に伝えたいと思ったら、たいてい20回は繰り返す必要がある。…だからリーダーは常に”コミュニケーション過剰”であるべきだ。エリックのお気に入りの格言は『お祈りをいくら繰り返しても御利益は減らない』。」 「…アップルとグーグルのイノベーションに対するアプローチはまったく違っており、特に重要なのが『コントロール』に対する考え方の違いだ。グーグルはアンドロイドを通じて、オープン・プラットフォームのもたらす優れた経済効果を実現しようとしており、また自分たちはオープンであることの必然的な結果でもある。… 一方、アップルのアプローチは正反対だ。iOSのコードは非公開で、アップルストアでアプリを販売するには、アップルの正式な承認が必要だ。… アップルの統制型モデルが機能するのは、スティーブ・ジョブズの傑出した才能だけでなく、ジョブズがつくったアップルという会社のあり方のためでもある。」 「きみがスティーブ・ジョブズ並みの直観と洞察力を持っているなら、ジョブズのやり方を見習えばいい。でもそんな人間は世界に何人もいないんだ。私たちと同じ”その他大勢”の方に入る人には、私たちのアドバイスが役に立つかもしれないよ。」 「新しいアイデアが初めから完璧であることはあり得ないし、完璧になるまで待っている時間はない。プロダクトをつくり、出荷し、市場の反応を見てから、改善策を考え実践し、再び出荷しよう。『世に出してから手直しをする』。勝つのはこのプロセスを最も速く繰り返すことのできる企業だ。」
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログやはり自分は採用や組織作りに興味があるんだなと感じる。こういう組織だからイノベーティブなんだ、と腹落ち。 情熱のある人間は情熱を口にしない。 ラーニング・アニマルは、「到達目標」ではなく「学習目標」を設定する。 特定の行動を選択するのは、できるだけ遅らせたほうがいい。 最初のフォロワーが孤独な愚か者をリーダーに変える。
0投稿日: 2018.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ▼以下メモ 企業文化 ・社員同士の距離を近づける。 ・「悪党」すなわち、傲慢な人間、妬む人間からは仕事を取り上げる。 ・人に「ダメ」といわない。 戦略 ・計画は流動的に。 ・利益より「大きくなること」を重視する。 人材 ・採用は絶対に妥協しない。学ぶ意欲の高い人物を採用する。大事なのは「何を知っているか」ではなく、「これから何を学ぶか」である。 ・好き嫌いではなく、人格と知性で選ぶ。 ・採用を全社員の担当業務に含め、「スゴイ知り合い」を紹介させる。貢献度は評価に入れる。 ・報酬は、低いところから始め、成果を出す人にはずば抜けた報酬を支払う。 スマートクリエイティブとは ・リーダーシップ、職務に関連する知識、全般的な認知能力 ・高度な専門知識と高い経験値 ・実行力にすぐれ、単にコンセプトをかんがえるだけでなくプロトタイプを作る人間 ・分析力がすぐれ、データを扱う事が得意で意思決定に生かす事ができる。一方で、データ分析の限界も理解している。 ・ビジネス感覚に優れている。専門知識をプロダクトの優位性や事業の成功と結びつけて考える事ができる ・競争心も旺盛、猛烈な努力ができる ・ユーザー理解が深く、ユーザー目線 ・好奇心旺盛、現状に満足せず常に問題を見つけて解決しようとする ・リスクをいとわない、失敗を恐れない、失敗からは常に大切なことが学べると信じている。 ・自発的、指示を待たない。主体性 ・あらゆる可能性にオープン、他者との協力が得意でコミュニケーションを大事にする コミュニケーション ・役員会の議事録であったとしても、法律、あるいは規制で禁じられているごくわずかな事柄を除き、全て共有する。 ・会話を促進する。話しやすい雰囲気を作る。時にはコミュニケーション過剰と言われるくらい。
1投稿日: 2018.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートクリエイティブを部下に持つようなマネージャーには為になるのではないかと思います。 普通のビジネスマンにとっても参考にできるようなこともありましたので、読んで損はないと思います。 少し、カッコが多くて読みにくかったので、星3で。
0投稿日: 2018.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
Googleがすごい会社だということがよく理解できた。失敗を恐れず、イノベーションを追求していく姿勢に感銘。10倍の価値を目指す。
0投稿日: 2018.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログすべてが加速化している時代にあって、ビジネスで成功する最良の方法は、スマート・クリエイティブを惹きつけ、彼らが大きな目標を達成できるような環境を与えることだと説く。
0投稿日: 2017.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートクリエイティブについて スマートクリエイティブを要する組織におけるリーダーシップとは、彼らをマネジメントするのではなく、彼らがディモチベートされるような要因を排除し、より自発的に、主体的に働ける環境を作り出すことが大切。 採用について 採用をなんとなくやって、その後の人材教育に力を入れるのではなく、採用に最も力をいれて、自己成長欲の高い人材を確保すべき。そのような人材は、機会を与えれば勝手に育つ。 20%ルール、ユーザーが全てetc. 全体としてGoogleの成功の秘訣が見てわかる。 経営者として参考にしたい本。
0投稿日: 2017.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleの凄さが伝わってきた。やはり人、スマートクリエイティブが重要。世界でもトップレベルの人が集まる文化を持っているのが強み。 以下メモ スマートクリエイティブとは・・・ 高度な専門知識と経験 コンセプトだけでなくプロトタイプを作る データ分析力が優れているがデータに振り回されない 専門知識をビジネスの優位性と成功に結びつける ユーザ目線を持ち、自らパワーユーザー アイデアが豊富で視点の転換が出来る リスクをいとわず、失敗からも学ぶ 他者と協力し、細かい注意も怠らない 会社の文化が一番大事 短く本当の言葉で会社の理念をうたう 色んな物や人との関わりでイノベーション起こる 意義を唱える義務を作る イエスの文化、イエスと言うと物事が一歩進む あなたのプロダクトの技術的アイデアは何か? 成長を最優先、プラットフォームを形成する 強みに特化する、ハリネズミ ラーニングアニマルが成長には必要 学ぶことをやめた日から老いが始まる 過去のトレンドに対し、自分の推論が当たった部分と外れた部分はどこか? リーダーシップ、職務知識、認知能力、グーグラーらしさで評価 仕事を面白くする方法をひねり出す グーグラーとは 企業文化とプロダクトに付加価値を与える人 仕事を成し遂げる人 自発的で情熱的な人 周囲に刺激を与え協力的な人 チームや会社とともに成長する人 仕事遺骸にも多才でユニークな人 倫理館があり、率直な人 キャリアの計画が必要、5年後にはどうなっていたいか?その為に欠けているものは何か? 人生は下水管、何を入れたかで何が出てくるかが決まる エレベーターピッチ、あなたは今どんな仕事をしているのか?、アイデア、想定される結果、会社への貢献、を考える 自分の下で働きたい上司になっているか?自己反省をしているか? メールは即返答、短文で、受信ボックスは少なく 新しい部署では仕事より人間関係や部下の課題把握をまず行う 全てがコントロール出来ている時はスピードが足りない時 新しいプロジェクトは、波及する人数が多いか?根本的に異なるアイデアか?実現可能な技術が存在するのか? イノベーションは成長の余地のある巨大市場 自社に持続的に他社との違いを出していく人材はいるか? ユーザに焦点を絞れば、後は全部ついてくる ユーザと顧客は違う、ユーザに焦点を 今考えている事の10倍のスケールで考える 具体的かつ大局的視点にたった目標を立て、達成度をはかる。他の目的には使われない 70コアビジネス 20成長プロダクト 10新規プロジェクト エンジニアは20%を好きなプロジェクトに使用できる、アウトプットと社員の成長が期待できる まずはプロトタイプを作ってみろ 失敗したアイデアから学ぶ、分解して生かせるものは無いか、形を変えられないか 自分、グループ、会社の今の課題は何か? 聞かれて嫌な質問は何か? 業界で起こり得ることは何か?常識的には考えられなくても、想像しようと思えば出来ることは? 大きな問題でもデータが取れればほとんど解決できる
0投稿日: 2017.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの会社の在り方について述べている。 経営の知識がないことは強みだと思っていた。 インターネットのおかげで、すぐれたプロダクトであれば簡単に広がるようになった。それ以前はすぐれたものを作るよりも広告に多くの費用を使っていた。 管理職の部下は7人以上にする。 組織は事業部でなく、機能別にする。 ベンチャーの立ち上げの時は自分のアイデアを信じ、同じような犠牲を払おうとする従業員を見つけなければならない。 採用で見るのは4点。、リーダーシップ。職務に対する知識。全般的な認知能力。グーグラーらしさ。 コアビジネスに7割、成長プロジェクトに2割、新規プロジェクトに1割。
0投稿日: 2017.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ似たような業界に身を置く人間としては、理想的な働きかたが述べられていると思うと同時にできていない事の多さに愕然とする。日本企業だと自動運転とか思いついてもまず自動車メーカと話をしないとという事になり、位置づけ論に終始して技術の話まで持っていけないだろう。
0投稿日: 2017.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ17/08/10読了 採用ステージから違うので安易に見習えないことはわかりつつ、知っておきたいことで満載
0投稿日: 2017.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートクリエイティブはどんな業界でも当てはまる。「ユーザーを中心に考える」、「70%20%10%ルール」などなるほどとおもえる話が多く学ばせて頂きました。林業経営者にもお勧めの1冊。
0投稿日: 2017.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの働き方とマネジメントがよくわかる。 スマートクリエイティブの概念は参考になる人は多いと思う
0投稿日: 2017.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
インターネットの世紀においては、20世紀に学んだことのほとんどは間違いで、それを根本から見直すべき時期にある。 それは3つの大きな技術トレンドによる: 情報が無料に、豊富に、どこでも手に入る。携帯端末やネットワークの全世界的普及による常時接続。クラウドコンピューティング。 プロダクト開発の経営においては、「希少性」よりも「柔軟性」「スピード」を重視した経営が求められている。劇的に優れたプロダクトを生み出すのに必要なのは巨大な組織ではなく、数え切れないほどの試行錯誤を繰り返すことなのだ。
0投稿日: 2017.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルのスゴさがよくわかった。 スマート・クリエイティブがいるって素晴らしいけど、全社員がスマート・クリエイティブだったら会社回らない気もする。
0投稿日: 2017.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「すげえ、負けた」と言った感想、googleさんやっぱすごい。シンプルで一貫した戦略と高い遂行能力、うらやましい!既存の経営の枠組みを無視して自分たちのやり方を貫き、世界イチの企業を作り上げた様は圧巻の一言です。 でもなー、勉強になりましたと書きたいところですが、日本社会で本書で学んだことを活かすってとっても難しい。商習慣や法律との葛藤を乗り越えながら日本を変えていくのか、それとも違うルールの場所を選ぶのか、本書を手に取ったスマートクリエイティブの皆様は問われるのではないでしょうか? ・人材が大切 ・IT社会では既存の経営学の枠組みで企業の成長を測れない ・すべてはユーザのため、いいもの≒技術的な競争優位 ・スマートクリエイティブ(天才)を邪魔しない
0投稿日: 2017.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログgoogleの働き方が参考になるかと思って読んでみた。 ただ、 スマートクリエリティブ(できる人) はすごいできる だから、彼らの働きやすい環境を整えよう。 みたいなことが延々と書かれていた。 個人的にはそこまで参考にならなかった。 (OKRをちゃんと決める + 20%ルールぐらい。) あと、注釈が最後にまとまってるのも大変読みづらかった。
0投稿日: 2017.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ伝統的会社組織のダメな点を指摘しつつ、組織本来の楽しさを教えてくれる本でした。 「ユーザーを中心に考える」「ラーニングアニマル」というフレーズは特に印象に残りました。 普通に会社勤めをしていると過度に組織内の要望に気を取られたり、評価を得る事に腐心してしまいがちですが、Googleでは「魅力的プロダクト」を「卓越した技術」で実現し「ビジネス」を行うというシンプルな市場原則を社員が当たり前に保持しながら日常業務が行なわれているという点に衝撃を受けました。
0投稿日: 2017.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルが驚異的なスピードで成長した秘密を、同社の幹部が明らかにしている。キーワードはスマート・クリエイティブ。プロトタイプを作り出すことができる優れた人材のことで、彼らを採用し、活躍できる環境を整えることに力点を置き、スマート・クリエイティブを惹きつけるのは、シンプルな原則に基づく経営を徹底する文化だと断じている。それをベースに組織の作り方、技術やプロダクトの重要性を論じているが、特に人材の採用に関してのくだりは示唆が多い。多くの会社や人はグーグルのようにイノベーションを起こすことはできないが、状況をよく考え把握していないと自分が新しい技術によって片隅に追いやられる激しい時代を生きていることを自覚させられる。
0投稿日: 2017.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログやや古い話ではあるが、ベンチャー企業の立ち上げという観点では大変参考になる一冊であろう。 グーグルで働く人間の多くは大学でも優秀で、それこそ勉強が楽しくて仕方がなかったという人材が多いように思われる。 それこそがグーグルが求める「スマート・クリエイティブ」としての素質であり、彼らは仕事自体が報酬と考え、プロダクトを誰よりもユーザ目線で見、好奇心旺盛で自発的である。そして、彼らは混乱した状態に戸惑うどころか力が湧いてくるタイプであり、「やっているうちにわかるだろう」という前向きな考え方で事に当たる。 創業時からそのような厳格な基準によって人材を採用することが 「自律的思考」をあらゆる活動の基礎 とするグーグルの企業文化を維持するために重要であり、偽陰性(本当は採用すべきだった)よりも偽陽性(本当は採用すべきでなかった)の面に目を光らせて採用活動を行っている。 ユーザに焦点を絞らないと最高のサービスを生み出すことはできず、最高のサービスを提供できさえすれば、お金はあとからついてくるという考え方は、「小倉昌男 経営学」のヤマト運輸と共通するものがあると感じた。 「邪悪になるな」という企業理念がそのまま社員の行動指針にリンクすることにより、エンパワーメントがしやすくなっている。また、中国内の検閲規制に対して思い切った行動(自発的撤退)ができたのも、このスローガンが果たすところが大きかったのだろう。 ブクログでの評価が非常に高かったので読んでみたが、異常に時間がかかってしまった…自分自身の読み方(ベンチャー企業の自慢話のように捉えてしまった)にも問題があったようにも思う。
0投稿日: 2016.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ2014年に初版が出た本というだけあって2年後の今読むと少し古いと感じる部分がある。また、世の中で成功しているベンチャーは、この部分をリスペクトしたなかもな、というケースがかなり多いのも興味深い。 個人的にはスマート・クリエイティブという、高度な専門知識を持ち、コンセプトだけでなく、実行力に秀でた人材になりたい!と強く思った。 また、法務として問はれているのは、全ての可能性を詳細に検討するのではなく、不確かな未来を探り、意思決定者に、賢明、簡潔なアドバイスを提供すること!っていのは凄く腹落ちした。
0投稿日: 2016.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ元CEOエリック・シュミットと、プロダクト責任者ジョナサン・ローゼンバーグがGoogleに入社して衝撃を受けたその働き方の文化について語った一冊。 テクノロジーに対する思いと、プロダクトを作ることを優先する人々。スマート・イノベーティブな社員にいかにしてクリエイティブな仕事ができる環境を提供するかにこだわった数々の制度、設備。 超優秀な社員が集まる世界トップの企業だからこそできる働き方ではあるが、とかく過去の例や、慣習に拘りすぎ、柔軟さを失いがちの日本企業は、素直な態度で学べることがないか、もう一度彼我の違いを見直すべきではなかろうか。
0投稿日: 2016.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルは技術的アイデアを信じている。それが素晴らしければ必ず成功するはずだ、と。マーケティングに携わる者からすればちょっと寂しいが、ともかく、コスト削減や、営業の力、マーケティング戦略よりも、製品の技術的アイデアが第一という考え方については興味深く読んだ。 その他のメモとしては、1.プラットフォームとオープンソース化。 2.採用:情熱を測るには興味ある話題についてのムダ話。
0投稿日: 2016.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで読んだビジネス書のなかで、トップかもしれない。これくらいの分量の本は、いつもなら4~5時間で読めるけど、これは10時間以上かかったと思う。一つ一つの注釈まで内容がぎっしり詰まっていて、一度読むだけでは足りないと思った。もう一度読みたい。
0投稿日: 2016.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleという会社に根付いている考え方や文化を知り、自分の今のポジションに当てはめて考えてみることは、おそらくすべての人に対して有用である。 特に、「意思決定」「コミュニケーション」の章は、今すぐ役に立つであろうhowtoも多い。 翻訳本特有のとっつきにくさはあるものの、今年出会った書物の中でも極めて有用で、何度でも読み返したくなる一冊。
0投稿日: 2016.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり具体的にGoogleの働き方が描かれてる。 ただ、あまり目新しいものはなかった。 スマートクリエイティブをたくさん集めて、 ユーザーを第一に仕事する。 これだけでうまく回っている会社は素晴らしいと思う。
0投稿日: 2016.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogle検索愛用者でしかない私だったけど、こんなにすごい会社だったんだ…。と、のんきな感想になってしまう。まさに昔ながらの考え方の会社に勤めている事を実感しつつも、刺激的な考え方を読めて勉強になりました。こういうエキサイティングに楽しく仕事ができるっていいなーとも思ったり。 2016/3/20完読
1投稿日: 2016.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ刺激的で示唆に富んだ一冊。 ICTの先端を走るGoogleの、従来の企業とは全く異なる、経営哲学と企業文化。 世界のトップはここまで行っているかと茫然。 文化、組織、人材から、メール扱い、会議の仕方までノウハウを公開している。 自社の考えだけでなく、ライバル社の経営者の言葉とうも引用されている。それらが、丁寧に見開き左側のページに索引として参照文献が示されている編集もよい。好感が持てる。
1投稿日: 2016.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログgoogleがなぜ凄いのかを、中はこうやって運営してるから、を具体的な内容で教えてくれる本。 本当に凄いと思う。逆に、組織が固まった既存の組織では実践だけでなく、考え方を取り入れるのすら難しいと分かる本。 会社からの制約は少なく、自由に、自律的に社員が活躍できる組織なので羨ましいが、それは素晴らしい人材という言葉では足りない位にスーパー級の人材でなければならない事、かなりの数の機会に自分の成果を示し続けなければならない事、が求められるので、凄いと思う反面、自分ができる自信はなく、憧れは砕かれる本でもあった気がする。
2投稿日: 2016.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ●読むキッカケ ・研修をやるにあたって、他者の事例を知りたくなり。 ●サマリー ・文字通り、Howが沢山記載されている本で、概念的なものにまとまってはおらず、 エリック・シュミットのGoogle愛にあふれた本だったなあという印象。 また、具体のケースはいいなあとは思いつつ、何らか自分の中に変化を起こすものではなかった。 確かに、今必要な組織観ではないあなと思った。 ●ネクストアクション ・また、何らか必要なタイミングが在れば読み返せれば良さそう。 ●メモ ・Googleにおいて採用基準として、しなやかなマインドセットの持ち主を採用する。 その人は、ラーニングアニマルで、失敗に拘らず、 結果として成長していくからとのこと。
1投稿日: 2016.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか読むのに苦戦しました。内容は興味深いけど翻訳物はやはり苦手なのかな?イノベーティブになりたい!読了日2016.01.02
1投稿日: 2016.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleにおけるグーグラーの働きっぷりについて、元CEOのエリック・シュミットらが書いた本。簡単に言ってしまうと、とにかく優秀なスマート・クリエイティブを惹きつけて、オープンに、自律的に、そして思う存分ストレッチして最高のプロダクトを世の中に出すためにワークしてもらうことがGoogleのポリシーだということかと。今でこそインターネット広告市場という鉱脈を引き当てて、そこを足掛かりにAndroid、Gメール、Google Mapと革新的サービスを広げてきた。また、その価値は技術的要因に支えられたプロダクト中心になっている。 スケールすることの重要性も説かれるし、『ワーク・ルールズ』にも詳しい人事の仕組みについても書かれている。会議の原則やメールの原則にも触れられている。会議には単一のオーナーを決めるというのは参考にすべき点かもしれない。 共著者にJonathan Rosenbergという方がいるが、あの人とは別人だった。
1投稿日: 2016.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
感想は以下 http://masterka.seesaa.net/article/431892178.html
1投稿日: 2015.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体的に勉強になったが、特に採用の章は学ぶことが多かった。 ・採用は重要。優秀な人材を集めるには、採用基準を高めること。本当は採用すべきだったのに採用しなかったケースの方が、本当は採用すべきではなかったのに採用したケースが出るより好ましい。 ・仕事を成し遂げる人物を採用せよ。問題について考えるだけの人物は採用してはならない。 ・自分の意見を通すことより、最高の意見を見つけることを考えよ ・自分の下で働きたいと思うような上司であれ 社内の人への質問方法 「君の仕事はどうだい?どんな問題があるの?目標の達成度を説明してくれないか?」
1投稿日: 2015.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルのトップが書いたグーグルのこと 【記しておきたいポイント】 『情熱のある人間は情熱を口にしない』
1投稿日: 2015.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ・ダラダラと読んでしまい読み終わるのにすごく時間がかかってしまった ・Googleという素晴らしい企業がどんな風に採用や会社の制度などを考えているか分かって面白かったしとても参考になった ・しかしあまり新しい発見や気付きはなかった気がする ・★3.5という感じ
1投稿日: 2015.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログエリック・シュミットとジョナサン・ローゼンバーグの綴るグーグラーの働き方。ワークスタイルを紹介するだけで、ビジネスの真髄に触れることになる、Googleの組織としての偉大さと、一般的な大企業の組織構造及び集団理念が如何に理想とかけ離れているかが、よくわかる。
0投稿日: 2015.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルの経営について、文化、戦略、制度、価値観などいろんな側面から紹介されている。 テクノロジーが発展し、何もかもが物凄い速さと威力で変化する現在、大切なのは 1.プロダクトの優位性を保つこと 2.スマート・クリエイティブ(と著者達が呼ぶなんかすごい人たち)をいかに集め、留め、能力を発揮させるか だと説く。そのために重要な要素として以下のようなものを挙げている。 ・文化 大きな自由と責任、ユーザー主義etc ・採用 いかに優秀な人材を採用するかという点について、具体的な採用制度や面接する側のスキルetc ・制度 20%ルール、OKRという目標管理などスマート・クリエイティブの能力を最大限発揮させ、会社にとどまってもらえるような制度 その他、イノベーションについて、グーグルの取る戦略(オープンをデフォルトにetc)、会議やメールについて具体的な方法論 引用が豊富で、また反対意見を提示した上で主張を検討する場面もあり、かつそれぞれリファレンスが記載されているのでしっかりとした説得力を感じた。実例も多く紹介されている。ところどころユーモアも織り交ぜられ読みやすかった。
1投稿日: 2015.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ★SIST読書マラソン2015推薦図書★ 【所在・貸出状況を見る】 http://sistlb.sist.ac.jp/mylimedio/search/search.do?target=local&mode=comp&category-book=all&category-mgz=all&materialid=11401591
1投稿日: 2015.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ極めて普通な内容だった。ネットビジネス戦略科目のGoogleの学びのが深かったかも。 たまたま金曜の午後にオフィスでラリーの「この広告はムカツク!」の慶事を目にして、「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」を指名に掲げる会社が、ムカツク広告を表示するのは非常に問題であるということに気づいた。だから、自分の仕事の責任外で、週末であっても、何とかしようと思ったのである。 悪党の割合にはティッピング・ポイントがある。意外と低いそのポイントに達すると、悪党のように行動しなければ成功しない、とみんなが思うようになり、問題は更に深刻化する。 悪党は誠実さの欠如から生まれる。悪党はチームより個人を優先する。 誰かが自分は会社の成功に欠かせない存在なので、1~2週間の休暇をとったらとんでもないことになる、と思っているなら、かなり深刻な問題があるサインだ。必要不可欠な人間などいるべきではないし、またそんなことはあり得ない。 休暇は無理にでも取らせ、本人をリフレッシュさせ、その間に代役を務めた人は自信がつくように促すべきである。 「お楽しみ」イベントには1つ問題がある。本当の「楽しさ」がないのだ。 廊下を歩きながら目に付いたゴミを拾い上げる、毎朝自分で新聞をとってくる、机を拭いて回るなど。自分たちはチームであり、必要だがつまらない仕事を免除されるようなえらい人間は1人もいないのだ、というメッセージである。しかし、そもそもそういう行動が出来る人は、会社をとても大切に思っているからだ。リーダーシップには情熱が欠かせない。あなたにそれがないなら、さっさと降りた方がよい。 同じようなことをしている他社を任すだけでは、仕事としてちっとも面白くないじゃないか。 優秀なコーチは、どれだけ優れた戦略を立てても、優れた人材の代わりにならないをよく分かっている。それはスポーツだけではなく、ビジネスでもだ。優秀な人材のスカウトは、ひげをそるのに似ている。毎日やらないと、結果に出る。 「群れ効果」は+にも-にも働く。Aクラスの人材は同じAクラスを採用する傾向があるが、BはBだけでなく、CやDまで採用する。だから妥協したり、誤ってBの人材を採用すると、すぐに社内にBのみならずCやDまで入ってくることになる。 人は学習を辞めたときに老いる。20歳の老人もいれば、80歳の若者もいる。 5年後の自分にとって理想の仕事を考えてみよう。どこで何をしたいか、いくら稼いでいたいか、仕事内容を書き出そう。そこにたどり着くために自分の強みと弱みを評価してみよう。自分はどんなスキルを磨く必要があるのか、他者からも評価を受けてみよう。 もし、理想の仕事がいまの仕事だという結論に達したら、それはあなたの野心が小さすぎるということだ。 「目的地がどこかわからないときは、注意したほうがいい。おそらくそこにはたどり着けないから。」 全員同意見というのは、誰かがモノを考えていないということだ。 仕事に限った話ではないが、何かを人に伝えたいと思ったら、たいてい20回は繰り返す必要がある。数回言うだけでは、みんな忙し過ぎて、おそらく気づかないだろう。さらに何回か繰り返すと「あれ、なんか聞こえたかな?」くらいに思ってもらえる。 もし20回いっても伝わらないのであれば、それはテーマに問題があるのかもしれない。
1投稿日: 2015.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ適切な人材と壮大な夢がそろえば、たいていの夢は現実になる。たとえ失敗しても、きっと重要な学びがあるはずだ。適切な人材とは何かにのめり込むことができる人。その人に成果に繋がる可能性のあるテーマを与える。 夢とは、あったらいいな♪と思う事。ドラえもんの道具じゃないけれども、あったら良くないことも起こるんだけれども、あったらいいなと思うことを実現しようと思わなければ、絶対に誕生しない。 これほど情報があふれ、魅力的な選択肢がたくさんある状況では、いくら歴史やマーケティング予算があっても、質の低い店に勝ち目はない。反対に、オープンしたてでも質の高い店は、クチコミで評判が広がる。同じことが自動車、ホテル、おもちゃ、洋服のほか、ネットで検索できるありとあらゆるプロダクトやサービスに言える。顧客には豊富な選択肢があり、またネット上には売り場面積の制約はない。しかも顧客には発言力もある。粗悪なプロダクトや不快なサービスは、企業にとっても命取りになりかねない。 企業が衰退する原因は、経営者や管理職、従業員が、会社の利益ではなく、個人の利益(既得権益、現在の地位や収入)を守るために、リスクを恐れて攻めを怠り、守りに回ることだ。Googleのように移り変わりの激しい業界ならもちろん、そうでない業界でも、成長し続けるためにはテクノロジーの進歩に敏感になり、伸長するもの、衰退するものを見極めなければならない。平凡な人間の採用を控え、仲間に迎い入れる人間を卓越した人間(スマート・スマートクリエイティブ)に絞らなければならない。そして、彼らに自由を与えるのだ
2投稿日: 2015.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ常にイノベーションを起こすグーグルの秘密の一端がわかる。スマートクリエイティブを惹きつけ、彼らがとんでもない偉業を成し遂げられるような環境を作り出すこと。グーグル文化のありかた。 ソニーが普通の大企業になってしまったようにグーグルもいつかそうなるのではないか。それともそうならないのか。 ・市場調査ではなく、技術的アイデアに賭ける。 ・グーグルの採用のおきて 自分より優秀な人物を採用せよ。最高の候補者を見つけた場合のみ採用せよ等 ・
2投稿日: 2015.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ◯劇的に優れたプロダクトを生み出すのに必要なのは巨大な組織ではなく、数え切れないほどの試行錯誤を繰り返すことだ。つまり成功やプロダクトの優位性を支えるのは、スピードなのだ。(32p)
1投稿日: 2015.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログスマートクリエイティブ集団のGoogleとは、が書かれていた。 技術屋でクリエイティブな人たちを活かすための文化であったり、採用への厳しさが印象的だった。 中国問題での判断力が興味深かった。
0投稿日: 2015.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ★★★☆☆ 社畜ではなくワーカホリックだ! 【内容】 超企業Google.その秘密を大公開する。 【感想】 恐ろしい企業だ。TVとかではご飯が無料だったり、ビリヤード台があるイメージしかないんだけど、本を読むと印象が変わる。 それは大変厳しい企業だってこと。とにかく"自分でやる"って点が重要であり、働きがいってやつはすごいありそう。 本書のような理念があるかぎり、Google帝国の反映は続きそうだ。 【引用】 オフィスの広さや高級さを重視するような文化は社内に有害な影響が広がる前に排除した方がいい。オフィスデザインは従業員を孤立させたり、地位を誇示させることではなく、エネルギーや交流を最大化することを目的にすべきだ。 プロダクトマネージャーに求められるのおは、プロダクトをさらに良くするための技術的ヒントを見つけることだ。 マネージャーは肩書きがつくる。リーダーはまわりの人間が作る。 リーダーシップには情熱が欠かせない。 ライバルの動向へのこだわりは、凡庸さへの悪循環につながる。 ライバルを誇りに思おう。ただ、追随はしないこと。 イノベーションとは「斬新で有用なアイデアを生み出し、実行に移すこと」だ。 イノベーティブな人材に、イノベーションを起こせと言う必要はない。そうする自由を与えればいい。 「世に出してから手直しをする」アプローチはあとで改善することを前提に、室の低いプロダクトを送り出してもいいという考え方ではない。プロダクトは提供する機能に置いて最高のパフォーマンスを実現しなければならないが、当初の機能は限定的でも構わない。
1投稿日: 2015.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ5年後を見据え、リスクを取り、素早くやって失敗し、軌道修正する。 これが今の時代を生きる私たちの働き方なのかもしれない。 (以下抜粋。○:完全抜粋、●:簡略抜粋) ○劇的に優れたプロダクトを生み出すのに必要なのは巨大な組織ではなく、 数えれきれないほどの試行錯誤を繰り返すことだ。(P.32) ○スマートクリエイティブはリストの一番上に文化を持ってくる。 実力を発揮するには、どんな環境で働くかが重要だとわかっているからだ。(P.50) ○「当社の使命は、従業員の知識と創造性と献身を通じてお客様と比類なきパートナーシップを築き、 価値を生み出し、それによって株主に最高の結果をお届けすることです」というのはどうか。(P.52) ○あなたが許可しようがしまいが、 自分が正しいと信じることをしようとする人材に投資すべきだ。(P.74) ○イスラエルの戦車司令官は戦闘を開始するとき、「突撃!」とは言わない。 「アハライ(ついてこい!)」と叫ぶのだ。(P.95) ○事業計画が間違っている以上、人は正しく選ぶ必要がある。 優れた人材が集まったチームは、計画の欠陥に気づき、軌道修正することができる。(P.99) ○成功している大企業は例外なく、次の点から出発している。 ①問題をまったく新しい方法で解決する ②その解決法を生かして休息に成長・拡大する ③成功の最大の要因はプロダクトである(P.135) ●応募者に過去の失敗を振り返ってもらうことだ。 「1996年に、君が見逃したインターネットの重要なトレンドは何かな? 君の推測が当たった部分、はずれた部分はどこだろう?」(P.149) ○あなたがリスクをとり、彼らに新しい職務への挑戦を促せば、 優れた人材を獲得できるだろう。(P.156) ●グーグルでは候補者の評価を四つのカテゴリーに分解。 リーダーシップ、職務に関する知識、全般的な認知能力、グーグラーらしさ。(P.170-171) ○キャリアの出発点で間違った業界を選んでしまうと、 社内で成長する機会は限られている。 上司も居座る可能性が高く、 他の企業への転職を考えても売りになるスキルは身につかない。(P.190) ●キャリア計画を立てよう(P.192) ①五年後の理想の仕事を考える。 たとえばその仕事は転職サイトでどんな説明になっているだろうか? ②理想の仕事に就いた、その時点の経歴書はどのようになっているだろうか? その理想の職に就くために、何をしたのか? ③理想の仕事を念頭に置きながら、強みと弱みを評価しよう。 どんなスキルを磨く必要があるのか? ○私たちはビッグデータの時代に生きている。 ビッグデータを理解するには、統計のプロが必要だ。(P.194) ○ある行動をとることが正しいか確信が持てないなら、 一番いいのは実際にやってみて、結果に応じて軌道修正することだ。(P.217) ●会議の時間管理は重要。皆人間で、家族もいる。 会議に出るなら、まじめに出よう。会議中に他の事をしているなら、その会議はいらない。(P.227) ○一流のスポーツ選手にはコーチが必要なのに、あなたは要らない?(P.234) ○会社で部下があなたのところに悪い知らせ、あるいは問題を報告しに来たら、 「上昇、告白、順守」を実践しているのだと考えよう。 どうすればよいか、思い悩んだ末に来たはずだ。 だからその率直さに報いるために、話に耳を傾け、支援の手を差し伸べ、 次に着陸を試みたときには必ず成功すると信じよう。(P.248) ○グーグルの検索エンジンは毎年、500件の改良の力が組み合わさった結果、 劇的な進化を遂げている。(P.281) ○最初のフォロワーが孤独な愚か者をリーダーに変える。(P.288) ○イノベーションは私たちが「パスツールの象限」で活動しているとき、 すなわち「現実世界の問題を解決するために 基礎科学を進歩させようとしている状況」でおきやすいという言う。(P.296) ○リソースの70%をコアビジネスに、 20%を成長プロダクトに、 10%を新規プロジェクトに充てるのである。(P.305) ○10%という配分が適切なのは、もう一つ理由がある。 クリエイティビティは制約を好むのだ。 絵画には額縁があり、ソネットは14行と決まっているのはこのためだ。(P.306) ○世に出してから手直しする(P.320)
0投稿日: 2015.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログgoogleと言う世界最高峰の企業理念やメンバーの考え方、働き方を惜しげなく披露してくれている。 能力のある職員つまりスマートクリエイティブには、できるだけの自主性を与えて彼らのやりたいようにやらせることが、結果的にイノベーションを起こす、企業利益につながつて行くということを示してくれている。 ありきたりの組織でなく、イノベーティブな企業は明確な理念に基づき、各自が自主的に考え、発展していくものなのである。企業はその邪魔をしてはならず、よくありがちな管理的運営は避けられるべきである。
0投稿日: 2015.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んで分かった。自分はGoogleでは働けない。いや、読まなくても分かってはいたけど……。 『フランスの洞窟壁画』と検索すると、洞窟壁画が明らか取り扱っていないサイトの広告で『フランスの洞窟壁画を買うなら××で』という広告が表示されるという問題は見たことあるような気がする。いや、というよりも、何を検索しても、『○○を買うならamazonで!』という広告が表示される時期があった気がする。 それにしても、採用に関する話に驚き。グーグルの創業初期にはある候補者を30回以上面接したのに、採否が決まらなかったということがあったんだとか。その数に唖然としたのだけど、その後に書いてあったのが、『30回以上面接することを禁止するルールをつくった』。できたら、1……、いや、2回までにしてほしいです(今は5回が上限らしい)。普通に書いてあったのだけど、もしかしてアメリカではよくあることなんだろうか。日本ではそんな回数面接をしなきゃいけない会社ってそうそうないと思うのだけど。 グーグル・ウェーブは使ったことないけど、開発中止発表直後に日本でグーグル・ウェーブの入門書が発売されたのは覚えている(http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1008/05/news081.html)。悲しい事件だったね。 後、何気に最後のほうに書かれている、『この本を書いているのは、グーグル社内で最後までブラックベリーやアウトルック・メールをつかいつづけた人間たちだ』という告白に驚き。そうなのか……。
0投稿日: 2015.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログエリックのセミナーを聞いてからその場で購入。 ストーリーを交えて、難しい話は一切なく、マインドや周りの環境について記されている。どうやって働いたり、どうやっていいプロダクトを作るかの気付きになる。
0投稿日: 2015.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleのイノベーションは、どのように支えられているのかが書かれた本。優秀な人材を集め、彼らのモチベーションを高く保ち、そのモチベーションを高く保つ仕組みがさらに優秀な人材を呼ぶ。それが、Googleだ。
0投稿日: 2015.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこんな会社で働きたいと思ってワクワクしながら読みました。 いろいろなGoogle語が出てきます。 ゲイグラーはトランスジェンダーの従業員からなるGoogleのダイバーシティグループで、Googleで大切なのは「何ができるか」であって「どんな奴か」ではないというところが共感できました。 そして最先端なIT企業のイメージのGoogleですが、Googleブックスのプロトタイプはマリッサ メイヤーが本のページをめくり、ラリー ペイジが撮影をして作ったというくだりを読んでどれだけアナログなの?と驚きましたが、血が通っている感じがしてステキです。 仕事時間の20%は好きなプロジェクトに使えるという「20%ルール」もいいですね。 スマートクリエイティブにとことん居心地の良い環境を提供するGoogleの姿勢が素晴らしいです。
0投稿日: 2015.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ採用の仕方や組織風土の作り方など、とても興味深い内容だった。しかし、我が社はグーグルではないのであった。
0投稿日: 2015.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと古いがグーグル社のことが書いてある本。 文化、戦略、人材、意思決定、コミュニケーション、イノベーション。
0投稿日: 2015.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題になっていたので購入したが、読まずに放置していた。 ふと思い出して読んでみたが、若干旬を過ぎてしまった様な。 まあ、面白いと思えるところもたくさんあるにはあるけど。
0投稿日: 2015.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ20150519読了 タイトル通りグーグルについて書かれた本。 要は「優秀な人材を集めて、そいつらが自由に出来る環境を作る」と初めは解釈。違ってるかも。 グーグルだから出来るんでしょ、的な所もあるけど、一般的な企業でも真似したい考え方などは大いにある。 特に、「技術的なアイデアを中心にして経営する」的な考えはメーカーとして当然持っておきたいと感じた。実際それだけだと難しいんだけど。 優秀じゃない人も大勢いて、なおかつガチガチに管理しなきゃいけない日本の製造業が勝てるわけないな、と思った。
0投稿日: 2015.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログp60 チャートの扱いが得意で、資本コストを上回るリターンを生むような計画を手際よくパワーポイントにまとめたり、経営陣のお墨付きを得たり、自分がその遂行に欠かせない存在であるかのように演出する能力に長けた従来型のプロダクトマネージャー p64 カバの言うことは聞くな 誰のアイデアかよりまともなアイデアかが重視される職場
0投稿日: 2015.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社の文化が大切と説いており、データ志向と傑出した人材の採用と活用には非常なこだわりを持っている。 スマート・クリエイティブ、ラーニング・アニマルというのが彼らの使う表現だが、そういう人材を集めることで、通常業務の質の向上と効率化が図られるだけでなく、新たなプロダクトやサービスが生み出される。経営者としてやるべきことも示されているが、個別具体的な指示というよりは、ミッションとビジョンの明確化と社内浸透、人材採用、決定事項の伝達あらりなのだろう。従業員が傑出している企業では、従業員に任せた方が上手くいくことが多いということだろう。 感覚ではなく、データを大切にし、パワーポイントで訴える前に、データをきちんと見ようというのは納得。データにこそ真実が潜んでいるんだと思うし、成功確率を上げるにはデータを活用すべきだろう。世の中や物事はそんなに大きくは変わらないし、過去から分かる未来というのは知っているのと知らないのは違いが大きいよな。 3週間ルールは非合理なようで、実は合理的であり、私自身もそれを実践することで、新たなチームがうまく動くように留意したいと思う。 全体的に多くの気づきを得られた書籍であり、ビジネスって本質的にこういうことを突き詰めないといけないのかもな、と思わされた。
0投稿日: 2015.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ会社によってこうも雰囲気が違うのかと。将来の働き方、という意味では『WORK SHIFT』と似たようなターゲットだが、現場の意見と学者の理論では具体性に基づく説得力が違う。グーグルはスマート・クリエイティブ(ビジネスセンス、専門知識、クリエイティブなエネルギー、自分で手を動かして業務を遂行しようとする姿勢)を集めて、彼らに任せて、ダントツのプロダクトを作るのだ、ということ。多産多死で適切に止めること(失敗は減点されず挑戦の結果を生かす考課)。問題に気づいたら担当に関わらず行動を起こすこと(それが非難されずに称賛される風土)。一番嫌な質問を自分自身にする。 そのプロダクトは、ユーザー中心、市場がある、技術的に優れていて実現可能があること。テクノロジーの破壊力はとても強力で従来企業の参入障壁を打ち破ることができる(参入障壁の蓄積量が質的障壁になっていると困難だが)。
0投稿日: 2015.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ具体的な方法論がかなりの量まとまっていて、実践的かつ勉強になる。惜しみなく書いちゃうあたり、根っからオープンな会社だなあ。 世界中のエンジニアがこの本を読んで、この働き方をカリフォルニアのスタンダードとしてフォローしようとしている。Googleの真のすごさは、技術ではなく彼らのスタイルの方だったらしい。楽しんじゃってる人には誰も勝てないという真理。まだまだ強い、シリコンバレー。
0投稿日: 2015.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログプロダクトデザインから、その会社の組織図が浮かび上がるようではいけない。iPhoneのように、顧客であるあなた自身が重要な人であるべき。p75 クーグルの求める、スマートクリエイティブの条件。p170 1. リーダーシップ 2. 職務に関連する知識 個別のスキルセットだけでなく、幅広い強みや情熱を持った人材 3. 全般的な認知能力 どのように問題を解決するか 4. グーグラーらしさ 曖昧さへの許容度、行動重視の姿勢、協力的な性向
1投稿日: 2015.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015/05/14 GoogleがどのようにしてGoogleたり得るか、ということを述べた本。内容としては、Googleはこのようにしているという事は分かったが、それが果たして会社として、または、働く個人としてのスタンスとして正しいものはかどうかは、定かでは無いように思える。それぞれの項目について、そうしていることの根拠が少し乏しいように思える。ゆえに、実際に働いていてそういった状況が具体的にイメージってきて、かつ、そうしたほうが合理的だと思えれば、適用できるかもしれないが、今の自分には少し難しい内容だったのかもしれない。 ただ、その中でも使える部分はあり、主体性を持って答えを探すのではなく作り出すというスタンス、
0投稿日: 2015.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこの会社が何よりも凄いのは、組織のトップからボトムまでこの変化著しい時代を生き抜くための文化が徹底して浸透していること。それができる人間にしか門戸を開かない厳格な人材選抜にある。と私は思っている。 意思決定、コミュニケーション、イノベーション、どの章に書かれてあることも、皆誰しもが気付いていながら組織としての実現が非常に難しいものばかり。当たり前だが中々実践できないことをGoogleはやってのけている。 実現しているのは、彼らがスマートクリエイティブと呼ぶ次代のナレッジワーカー、エンジニアを厳選して抱え、それに追随するメンバーも極めて優秀な人材に絞っているからこそ。 そしてそんな彼らを惹きつけるビジネスモデルと思想を築き、ブレずにここまで拡大してきた経営層がいたからこそ。 本著を読んでのファインディングは、Googleが戦略らしい戦略を持たない、旧来の経営戦略にはほとんど意味を成さないとして大胆に切り捨てている点だった。もちろん、その意味でそれこそがGoogleの戦略と言えなくもない。 いずれにしても、極めて図抜けた頭脳集団である彼らとその牙城を切り崩すプレイヤーは今後数年現れそうにないが、破壊するとしたらどんな集団なのか、非常に楽しみでもある。 ◼︎読書メモ ・主要な生産費用曲線が下降すると地殻変動が起きる。現代においてそれは情報、インターネット接続、コンピューティング能力の3つである ・正しい意思決定とは、内容の正しさだけでは成立せず、そのプロセス・コンセンサスの獲得までを含む ・データで語り、言葉でのデリバリー、演出は極力少なく ・少なくとも年に一度は、自分で自分の評価を定めることを実施しよう ・二つの企業が一部の分野で競合しつつ 、別の分野では協力関係にある 、という興味深い状況が出てくる ( 「コ ーペティション (協力 +競争 ) 」 「フレネミ ー (友人 +敵 ) 」といった造語もある ) 。こうしたケ ースにうまく対処するには 、人類最古のコミュニケ ーション技術の一つ 、すなわち 「外交術 」を身に着ける必要がある ・インタ ーネットの世紀で成功するベンチャ ー企業の定常状態はカオスである 。何もかもがスム ーズに動いており 、組織図のコマと人間が一対一の対応関係に収まっているという状況は 、業務プロセスやインフラが事業に追いついてしまったことを意味する 。これは悪いサインだ ・事業は常に業務プロセスを上回るスピ ードで進化しなければならない 。だからカオスこそが理想の状態だ 。そしてカオスのなかで必要な業務を成し遂げる唯一の手段は 、人間関係だ ・グ ーグル xチ ームは新しいプロジェクトに取り組むかどうかを決めるとき 、ベン図を使う 。まず 、それが対象としているのは 、数百万人 、数十億人に影響をおよぼすような大きな問題あるいはチャンスだろうか 。第二に 、すでに市場に存在するものとは根本的に異なる解決策のアイデアはあるのか 。グ ーグルは既存のやり方を改善するのではなく 、まったく新しい解決策を生み出したいと考えている 。そして第三に 、根本的に異なる解決策を世に送り出すための画期的な技術は (完全な姿ではなく 、部分的なかたちでも )すでに存在しているのか 、あるいは実現可能なのか
0投稿日: 2015.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルがグーグルたる所以。 そんな内容。 そりゃすげー企業なるわいな! と単純に思う。 極端な理想論を 論ではなく、実施している 内情を知らんから、どこまで 論に実が近いのかは知らないけど。 普通の会社が真似しても 真似にならないことばかり 参考になるけど、参考にしていいのやら。 おもろいけど、もどかしくなる一冊。
0投稿日: 2015.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
グーグルの組織文化、働き方、考え方をつづった名著。 非常に参考になり、おもしろい。 <メモ> ・古い世界では、持てる時間の30%を優れたプロダクトの開発に、70%をそれがどれほどすばらしいプロダクトか吹聴してまわるのに充てていた。それが新たな世界では逆転した。ジェフベゾス ・ビジョンなど繰り返し伝え、報奨によって強化しなければ、それが書かれた紙ほどの価値もない。ジャックウェルチ ・オフィスデザインは地位を誇示させることではなく、エネルギーや交流を最大化することを目的にすべき。お互いが手を伸ばせば相手の肩に触れられるような環境では、コミュニケーションやアイデアの交流を妨げるものは何もない。デフォルト状態として活発な交流が起きているような状態に。 ・利益ではなく、規模を最大化する。 ・技術的アイデアをもとにプロダクト戦略をたてれば、顧客の要求を満たすだけの凡庸なプロダクトを生み出さずに済む。 ・コースの定理について、「インターネットによって取引コストが劇的に低下したため、コースの法則は逆から読んだ方がよくなった。いまとなっては、企業は社内で取引をするコストが社外と取引するコストを超えないようになるまで規模を縮小すべき」 ・成功している企業は例外なく次の点から出発している ①問題をまったく新しい方法で解決する ②その解決法を生かして急速に成長・拡大する ③成功の最大の要因はプロダクトである ・ヘンリーフォード「人は学習を辞めたとき老いる。20歳の老人もいれば、80歳の若者もいる。学び続けるものは若狭を失わない。人生で何より素晴らしいのは自分の心の若さを保つことだ」 ・面接、あなたが危機的状況に陥ったらどうしますか?自分でやる方がいいと思うタイプか、周囲の力を借りようとするタイプかをみることができる。前者はすべてをコントロールしようとする、後者はすばらしい人材を採用し、信頼して仕事を任せる可能性が高い。 ・スマートクリエイティブが高い評価をうける4つ ①リーダーシップ チームの成功への貢献。チームを動かすためにどのようなことをしてきたか ②職務に関連する知識 与えられた役割で成功するための経験、経歴 ③全般的な認知能力 どのようなものの考え方をするのか。どのように問題を解決するか ④グーグラーらしさ 曖昧さへの許容度、行動重視の姿勢、協力的な性向。 ・グーグル採用のおきて 自分より優秀で博識な人物を採用せよ。プロダクトと企業文化に付加価値をもたらしそうな人物を採用せよ。仕事を成し遂げる人物を採用せよ。熱意があり、自発的で、情熱的な人物を採用せよ。周囲に刺激を与え、協力できる人物を採用せよ。チームや会社とともに成長しそうな人物を採用せよ。多才でユニークな興味や才能を持っている人物を採用せよ。倫理観があり、率直に意思を伝える人物を採用せよ。 ・理想のしごとを思い描き、強み弱みを評価してみよう、どんなスキルが必要か。 ・エレベータピッチができていないということは真にそのことを考えられていないということ。 ・正しい意思決定の在り方を考える上でまず理解すべきは、正しい選択をすることだけに集中していてはいけない。判断に到達するプロセス、タイミング、判断を実行に移す方法も判断内容と同じくらい重要。 ・議論の初期段階ですべての反対意見を吸い上げるようにする。「全員同意見ということは、誰かがモノを考えていないということ」 ・会議は運転しやすい規模に。8人以下が妥当。 ・コアビジネスに集中し、愛情を注ごう ・デフォルトをオープンに。基本的に全てを共有しよう。 ・OKR(objectives達成すべき戦略的目標、key results 目標達成度を示す客観的指標)全ての社員が四半期ごとに自らのOKRを更新して、イントラに公開している。 単に肩書きではなく、取り組んでいる仕事、大切に思っている仕事を自分の言葉でまとめたものになっている。 ・リーダーはコミュニケーション過剰であるべき。メッセージはなかなか伝わらない。エリック「お祈りをいくら繰り返してもご利益は減らない。」 ・イノベーションにふさわしい環境は、急速に成長しており、たくさんの競合企業がひしめく市場。検討すべき要素は技術。 ・優れたOKRの特徴は大局的視点に立った目標を測定可能性の高い意味のある結果と組み合わせること。そして、発想を大きくすること。 ・まずプロトタイプを作ってみること。 ・イノベーションを生み出すには良い失敗の仕方を身につけなければならない。失敗から学ぶこと。アイデアはつぶすのではなく、形を変えよう。 ・何が起きるかではなく、何が起こりうるかを自問しよう。何が起きるかは予測であり、何が起こりうるかは想像力をかきたてる。
0投稿日: 2015.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ真剣なマネジメント。 ・ミッションの共有→職責を超えた参加 ・独立採算制をやめる ・狭いオフィスの利点→コミュニケーションの増加 ・悪党の排除、ディーバの保護 ・≠ワークライフバランス →働きすぎるような楽しい仕事をつくる →1~2週間の休みをとる方が仕事にプラス →1~2週間の休みをとっても問題ないマネジメント ・弱い立場はオープンで戦う ・ライバルを誇りに思う。ただし追随しない。 ・採用について ・本当に情熱のある人は、最初はうまくいかなくても努力を続ける ・面接の質問 1.興味のあるテーマ 2.これまでの人生の失敗、そのときとった行動 3.実際に起こったことに対する考え、起こる前の推測、違った点を認めること 4.最近驚いたこと 5.最近読んでいる本、学んだこと ・意思決定におけるプロセスの重要性、賛否意見を記録する機会 ・政府:イノベーション阻害ではなく促進のためにルールを変える(なくす)
1投稿日: 2015.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグル社の採用については、いろいろな話をあちこちで目にするところ。だが、思っていた以上に本気で冷徹に考えているのだなと感じた。 戦略、事業計画については、絶えず新しいものを生み出す会社であれば、記述の通りなのだと思う。多くの会社はそうではないだろう。環境の変化に対応していたらいつまでもリリースできない。対応できる力がほしい。 本筋ではないが、注釈も面白い。さまざまな研究や事項があり、読み物として面白く、世界が少しずつ広がる。
1投稿日: 2015.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogle社で行われているプロジェクトの進め方を元に、どのようにマネジメントしているかを記している一冊。 帯に書かれている「グーグルはこの方法で成功した!」はちょっと違うんじゃないかなと思う。カバー表紙をめくると、「グーグルで成功するにはビジネスとマネジメントの方法をすべて学び直さなければならない」とあり、Google社での働き方を示している。本文中に書かれているのは、後者のほうが近い。 では、この本を読むことにより学べることは何か。それはこれからの社会はスピード勝負だということと、ITでできることはまだまだたくさんあるということだ。本書も終盤に差し掛かってきたところ(P350 大きな問題は情報の問題である)にその記載があり、Google社が考えている未来の一端が見える。 Google社の事例が多く記されており、それ自身のお話は面白いのだが、そこから何を読みとり、自分のポジションでは何ができるのかを考えながら読むと面白い。
0投稿日: 2015.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログシリコンバレー生態系がシリコンバレー以外で生まれない理由は、この「ピンキリ」の「ピン」を最大限生かす姿勢かもしれない。規模が大きくなってくるほど「キリ」が増える。グーグルは採用段階で徹底的に「ピン」を採用し「キリ」を排除する、担当させる業務がないとしても。組織が巨大化すればするほど「ピンキリ」の「キリ」に合わせて組織を作り始め、それを「ダイバーシティ」と呼び正当化する。 著者が一流スポーツの例える「スマートクリエイティブ」たちに合わせた組織設計は見事だし、いままでのところ恐ろしく素晴らしく機能している。普通の企業が真似をしても確実に失敗するし、今後さらにグーグルが強さを増していくことを感じさせられる一冊である。
1投稿日: 2015.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
働き方に関する考え方を集めた本。 Aクラスの人材はAクラスの人材を集めるが、Bクラスの自在は、Bクラス、Cクラスの人材を集めるとか、詳細過ぎる事業計画は要らないといったような、既に広まっているような考え方が多かったから個人的に学びは少なかったけど、整理して理解するのは良かった。
0投稿日: 2015.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了。未来は明るい。久しぶりに徹夜で読んでしまった。それぐらい面白い!「企業には必ず聞かれて嫌な質問がある」もう一回と言わず何回も読むことになる一冊。
0投稿日: 2015.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
How Google Works Google の文化・戦略・人材・意思決定・コミュニケーション・イノベーションについて 様々な考え方をまとめてある。 どれも、「確かに」「そりゃそうだよね」と思うような内容が多いのだが、 実際に日本のシステム開発の現場でどれほど実践できているか? 逆に言うと、知的労働者が富の源泉となるような組織に置いて 当たり前のことを当たり前にできることがどれだけ強みになるのか考えさせられる。 以下、気になったフレーズ ・組織は機能別にする。ライン別にすると情報や人の流れが阻害される ・組織の構成単位は小さなチームで。ピザ2枚で足りるくらいの規模。大きなチームより多くのことを成し遂げる。 ・顧客に必要ではないもの、あるいは顧客のメリットにならないものを売るのも悪党 ・ディーバはエゴがあり、自分を優先するが圧倒的な成果を生む。悪党と混同されがちな振る舞いが大井野で、誤って排除してしまわないようにする。きっと投資に報いてくれ ・小さなチームは燃え尽き症候群に気付きやすい ・楽しさが重要。お楽しみ企画は楽しくない。チームビルディングのための企画ではなく本気で楽しむことを目的にすべき ・スマートクリエイティブは「こんにちの変わりやすい環境に柔軟に対応しようとするしなやかさ」がある。すべての答えがそろってると称する計画は信頼しない ・新たに入手できるようになった技術やデータと既存の方法の組み合わせで技術的アイデアを生み出す ・新しい技術のアーリーアダプター、アダルト産業。色んな機能がアダルト産業のフィルタリングへの試行錯誤の過程で生まれた。アダルト産業にちょっぴり感謝してもいい ・あなたと一緒に戦略を検討する仲間について。賢く選ぼう。在職期間が長いか、社内の職位が高いといった人ばかりを集めるのではなく、最高のスマートクリエイティブ、変化を見通す能力が高い人材を選ぶべきだ。 ・採用で重要なのは空きポストを埋めることではなく、とにかく優秀な人材を採用すること ・群れ効果。すばらしい人材はすばらしい人材を引き寄せる ・何を知っているか、ではなく、これから何を学ぶか。ラーニング・アニマルを採用する。知力。変化対応能力が重要 ・ラーニング・アニマルを採用できたら、彼らに学習を続けさせよう。常に新しいことを学ぶ機会を与えよう。社業の役に立たなくても構わない ・とびきり優秀な人を2倍にするには。誰もがスゴイ人を一人は知っている。全社員が一人ずつ優秀な人を連れてくればいい。 ・すべてをオープンにすることで組織の規模が大きくなっても同じ方向を向くようにする ・安心して真実を語れる環境づくり。炭鉱のカナリア。 ・新しいアイデアを思いつくだけの頭の良さと、それがうまくいくはずだと考える頭のおかしさを持ち合わせた人物 ・Google でユーザーといえば、プロダクトを使う人。他の会社ではエンドユーザーとお客様が異なる場合、お客様をユーザーと言うこともあるようだ。Google は常にプロダクトのユーザーの側に立つ
0投稿日: 2015.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ文字が小さめで結構濃厚な本だけど、たくさんのエピソードを交えつつ、グーグルの考え方や仕事のノウハウがふんだんに入ってて役に立ちつつ面白い。
0投稿日: 2015.03.27
