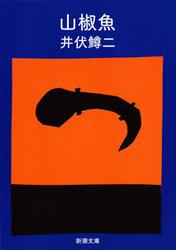
総合評価
(119件)| 19 | ||
| 30 | ||
| 39 | ||
| 11 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ山椒魚とは一切関係ないけど、アサイリョウの作品に、「登場人物のセリフに自分が言いたいことをそのままのっけてるみたいで没入できない」といったことを意見してるひとがいて、わたしがアサイリョウを読むときに抱いていたきもちわるさが言語化された
0投稿日: 2025.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ有名な「山椒魚」。 読んでみると、実際にこういう人いるよなあと思わされる。 自分の過失なのに腹を立てたり、誰かを道連れにしようと意地悪したり、卑屈になってしまうような人。 そんな山椒魚に対して、蛙はなぜ閉じ込められたことを恨んでいないんだろう。 むしろ山椒魚のことを憐れんでいるのかもしれない。 短い話なのに、考えさせられることが多かった。 他の作品も時代を感じさせるものが多く、有名なのは「屋根の上のサワン」。 雁を助けてペットにして、サワンという名をつけた物語。 自由を奪いながらも愛を注ぎ共生しようとする飼い主と、仲間と外の世界を望むサワン。 動物を飼育することとは何か、動物にとっての幸せは何か。 誰かを愛することとは。 愛することが利己的になっていないか?
23投稿日: 2025.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ふつうの軽音部から、海と山椒魚、そしてこちらへ。 サブカルから近代日本の名作小説に繋がるのだから、色んな作品に触れるのは大事だなと。 山椒魚の話は人間の照らされたくない本性を描く、非常に本質的な部分に焦点を当てた作品。 妬み、恨み。同じ環境を共有したからこそ来る同情、好意。 一言では表せない複層的な感情が入り混じった作品でとても好きでした。
1投稿日: 2025.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題作を含むいくつか作品を除けば、その場の空気感を描いたスケッチ的作品が多い。いずれも短すぎて散漫な印象は拭えず。
8投稿日: 2025.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ孤独と孤高と孤立。この作品を読むたびに、これらの違いをうまく伝えられない自分に気づく。 たった数年籠っていただけで家から出られなくなってしまった山椒魚は、外の景色を馬鹿にしてみたり、闇雲に憎んだり恨んだりする。それにしてはその目に映る景色は色鮮やかに美しく、光が満ち満ちている。そこに憧れや輝きを求めている彼はやがて嘆く。自分を省みるのではなく、ほとんど神に嘆くのだ。これは現代においても覚えがありそうだ。 最後のやりとりを読み、時々ふと考えてしまう。彼らの幸せはどこかにあった気がしてならない。
12投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ井伏さんは人も動物も、ユーモアと切なさの入り混じった視線で見つめているのだろうなと、そんな風に感じさせる短編集だった。 収録作の内だいたいの作品で主人公は旅に出ている。井伏さんは旅が好きだったのだろうか。旅情が良いアクセントになっている。 ベストは「屋根の上のサワン」だ。空という名の自由を渇望する鳥のサワンと、サワンの気持ちが痛いほど分かりつつ迫る別れを淋しく感じる想いに葛藤する「わたし」の姿が心を揺さぶる。文体が敬体なのも好みだ。
36投稿日: 2025.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ■参加者の感想をピックアップ■ ・表現力が素晴らしい。川の中の綺麗な様子、岩に閉じ込められる閉塞感などが、飾らない言葉や過不足のない表現で、読者が簡単に想像できるようになっている。 ・ラスト、蛙が「今でも別に、怒ってはいない」の一言で終わるのが唐突で、置いていかれた感がある。 ・作者の意図したメッセージが全く読み取れなかった。「正解」が何か気になり、読書会が楽しみ。 ・山椒魚が嫌な奴だと思った。自分ではどうしようもない不運な境遇に陥ることはあるが、だからといって他人を不幸に陥れることは良くない。 ■読書会後の私的感想■ メンバーの皆さん共通して、「表現力が素晴らしく、岩に閉じ込められた山椒魚がありありと思い浮かんだが、ラストが唐突でメッセージが読み取れなかった」という感想でした。 私も「山椒魚嫌なやつだなぁ」という小学生の読書感想文のような感想しか持てなかったので、集まりの前にネットで「予習」してから臨んだ珍しい会でした。 やはり読む人によって感想は変わるようですが、山椒魚と蛙を老人と若者に例えて、過去の栄光を顧みるばかりで今の状況の改善に全く興味のない老人世代。フットワーク軽く意欲に富み現状の改善へ尽力したい若者世代。そして理解できないもの全てを「今の若い世代は」の一言で切り捨てた上、あまつさえ変化の妨害とまでなる老人世代と、それに対して怒りよりも諦めを覚えてゆく若者世代…という現れという意見がありました。 もう一つの主流が、蛙のため息は諦めのため息でなく、岩屋の隙間から見える風景の美しさに対して思わず漏れた感嘆のため息だった説。岩屋から出れないと現状を嘆き希望を捨て、あまつさえ自ら目を閉じた山椒魚に対して、閉じ込められた当初こそ悲観にくれたものの。岩屋の中でも美しいものを見つけ愛でるという前向きな感性を見せる蛙。だからこその、『今でもべつにおまえのことを怒ってはいないんだ』との発言だったのではないでしょうか。 会の途中ではかなり穿った見方として、満州事変後世界戦争へと加速していく日本国と、預かり知らぬ間に戦争から逃れられない状況になってしまった一般市民、という時代背景が「岩屋へ閉じ込められる山椒魚」の比喩になっているのでは、との意見も出ました。 読書会の間には著者の井伏鱒二の人柄について話すこともありました。 明治の終わりに生まれ平成の始めに亡くなるという、日本近代史を全て体験した著者でしたが、他の文豪たちとは違い驚くほど作品内容に戦争や社会情勢が現れていません。太宰治が生前最も頼りにしていた人物であった井伏は、太宰が精神的に不安定な頃にも交友関係をやめず、精神病院へ入院させたりと世話をしていたそうです。強靭な精神力か、良い意味での鈍感力があったみたいですね。 ■今月の課題本■ ・井伏鱒二著「山椒魚」 ■開催日時■ 2021年9月 ■参加人数■ ・4人
0投稿日: 2025.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
名作バイアスかもしれないけど、山椒魚は良かった気がする。うっかりして2年のうちに岩屋の外に出られなくなる。 カエルは山椒魚のことを憎まないのか。自分がカエルの立場に立たされたと考えると憎くて仕方ないけどなあ。今でもべつにお前のことをおこってはいないんだ。どうして あとは屋根の上のサワン、へんろう宿、夜ふけと梅の花もいい感じ。 あとはそうでもないかなあ、読み心地はいい。 井上靖の短編集もこんな感じだった。
1投稿日: 2025.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでると、なかなか映像として浮かびにくい文章だった。作家との相性が悪いのかな?と一瞬思ったけど、屋根の上のサワンとか夜ふけと梅の花とかはめっちゃ入り込めるしちょっと泣いちゃいそうになったりもしたりして、なんだろこの魅力。それにしたって古典の中でも文体がすごく独特な気はする。井伏節ってやつなのかな。どちらにせよおばちゃん、おばあちゃんになったときまで大事に手元において何回も読み返したいなと思える作品だった。
1投稿日: 2025.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「山椒魚」だけで星5つけられる。 短編集の中で面白い話はいくつかあったが、「山椒魚」だけは別格なように感じた。読後感がスゴイ。2025年7月までに読んだ本で今年1番面白かった。 「山椒魚」は以前から気になっており、井伏鱒二の本は今回初めて読んだが、なんとなく独特な雰囲気が伝わった。特に作中のさまざまな地方の方言や、余韻のある読後感がすごかった。終わり方が独特なので、「え、ここで終わるの?」という終わり方のやつも多かった。長編の一章しか読めてない感覚。 好きな作品をメモっておく 「山椒魚」 「屋根の上のスワン」 「夜ふけと梅の花」 「寒山拾得」
1投稿日: 2025.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ井伏鱒二の短編集 山椒魚は示唆していることがわかりやすかったですが、そのほかの作品はストーリーだったり情景などを楽しむ感じかな 余韻のある終わり方が特徴よね 朽助のいる谷間 掛持ち 大空の鷲 上記の作品が面白かったです。
9投稿日: 2025.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ確か山口周さんの「人生の経営戦略」でこの物語が引用されていて、図書館で借りて読んでみた。まあ何か分かりやすい寓話。岩のなかでのんびりくらいしていたら、ずうたいが大きくなって出られなくなったという話。ゆでガエルと同じことだろう。うーん、これを文学的に味わったり、深い意味を洞察する力は私には無かった。
8投稿日: 2025.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ井伏鱒二氏による短編集 はっきり言うとそこまで読みやすくはないし、わかりやすい文章ではない。しかし、文章の表現、言い回しの面白さと丁寧さは抜群であり、ある程度教養のある読み手であれば場面を想像することもできる。 また、登場するものも人間でないながらも、人間よりも生々しく人間らしいものやどこか偏屈でネジが足りていない人々など個性豊かな(もはや狂気と言ってもいいかもしれないものもいるが)ものが多い。 ちなみにわたしは通学中の電車内で読んでいたので、話がよく飛び読み直すことが多々あった。なので、読む際は短編集ごとに一気に読むことを薦める。 なお、軽いネタバレになるが、短編同士に直接の繋がりはないのでどれから読んでもいいと思う。ただ、やはり彼の作風を知るためにはまずは山椒魚を読むべきだろう
1投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすくはないし、単調な雰囲気もあるが、絵が浮かぶ文章で、ところどころ引っかかるところもある。正直そこまで好きな作風ではないが、どこか心に残り、ふと思い出すことになりそうな気もする。解説にもあったがたしかに老人の登場が多い。
23投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題作の『山椒魚』は、伊坂幸太郎の『楽園の楽園』を辿って。『掛持ち』は社会関係資本を示す本で少し読んだことがあり、『思いがけず利他』かと思ったら、『ソーシャル・キャピタル入門』だった。
0投稿日: 2025.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ小さなプライドを持ち、虚勢を張りながらいきていく。でもやっぱり最後はそこを捨てていかなければならない。そんなことを、気づかせてくれる作品
2投稿日: 2025.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ改めて読んでみた。表題作は幾通りもの解釈ができそう。『掛け持ち』が最高。屋根の上のサワンも好きです。自然描写が細かいとおもったら、作者は絵をよくする人だったそうなので納得。太宰治が有名だが、多くの現代作家も憧れる人らしい。新潮文庫は表紙が安西水丸。すてきです。
3投稿日: 2024.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容云々よりもただただ作者の文章が好きすぎる。 いい意味で庶民感覚のある素朴な風景の描写が好きです。 物語系に疲れた人にぜひ読んでほしいです。 内容でいえば「へんろう宿」「女人来訪」「寒山拾得」が特に好きです。 1/28追記 「屋根の上のサワン」「岬の風景」も大好きです。作者の文章にはかわいらしい、くすっと微笑んでしまう所があり、素朴な描写に加えてそうした点が好きなのかなと思います。
2投稿日: 2024.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分自身の読みの力不足を反省しながらも、 自分なりにどんなことを感じたり考えたか を大切にしながら読んだ。 夜ふけと梅の花と女人来訪はホラー要素というか 気味の悪さが面白くて読む手がどんどん進んだ。 屋根の上のサワンは一番好きなお話だった。 一冊を通して仄暗い雰囲気を纏った短編集だが この作品は切なくもあたたかく、心の中に一筋の光がさすような読後感がある。 黒い光も読みたい。
1投稿日: 2024.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ言葉を発することはつねに、意味を裏切ることと同じだな、と思った。 心にある本当を表すことはできないから、すれ違いや、諍いが生じるのかもしれない。
1投稿日: 2024.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ短編集で、タイトルになっている『山椒魚』は、短い(10ページと少し)ですし、読後に山椒魚とカエルのやりとりや関係性に考えを巡らせることができてとてもよかったです。 自然の描写がきれいだなと思いました。
2投稿日: 2024.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ山椒魚。山椒魚は悲しんだ。から始まるわけだけれども最後のかえるの台詞を受けての山椒魚の気持ちがわからなくて、これ国語のテストに出たら0点だっただろうな。現在46歳。
1投稿日: 2024.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ目が滑って読めたもんじゃない。 初井伏鱒二だったのだけれど、特色も魅力も掴むことができず。小説の中に突然2コマ漫画が乱入してくるような。意味のあることを言ってるんだけど意味がまるでないような。もう少し私の経験値が必要なのは明らかなので、それまで積読。
7投稿日: 2024.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜいま井伏鱒二を読もうと思ったのか、それが全然思い出せない。 2、3ヶ月まえに青木南八との交流をテーマにした「鯉」を読んだけれど、この『山椒魚』はそれより随分前から積読されていたから、「鯉」を読む前から何かが気になっていたのだろうと思う。それが一体何だったのか。 ただ何となく思うのは、何か「手触り」のある小説を読みたかったのではないかということだ。 歳をとって小説が読めなくなってきた。 原因はよく分からないけれど「世界を立ち上げる力」が弱くなってきたんじゃないかという気がする。 物語を読んでも昔のように世界が現れてこない。だから最初から確かな世界が描かれている、そんな小説を読みたかったのではないだろうか。 井伏鱒二の小説はその点で非常に優れているように思う。山椒魚にせよ、鯉にせよ、サワンにせよ、あるいは朽助にせよ、彼が住んでいる谷間にせよ、そこに描かれているものが、何か固形の重みを持って感じることができる気がする だから書かれていることが分からなくても読むことができるのではないか。 そんな気がした。
1投稿日: 2024.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ滑稽な ほのぼの 朗らか ユーモア 庶民的な 生き生き 可笑しみ 飄々 ↑読んでいて思い付いた言葉 文章に愛嬌があって 本人の性格が出てる気がする 古本トワサンにて購入
9投稿日: 2024.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ近代文学って慣れてないと読みにくいイメージだけど井伏の文章はスラスラ読めた。掛持ち、寒山拾得、夜ふけと梅の花、女人来訪、辺りが面白かった。主人公の語尾が「〜だぜ」なのもシャレてて好きだな。全体的にフワフワしてる感じとかも他の作家とは違った魅力の一つなのかも。
2投稿日: 2024.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代物の文学作品を読むのは厳しいな 表題作を含めて12の短編集だが、山椒魚を読んだあとは1番少ないページ数の「へんろう宿」を読んで終わりにした
1投稿日: 2024.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ井伏鱒二の初期作品12編。 一編がかなり短くて物語の余白がたっぷりと残されているため、どう感じ解釈するかは読み手に委ねられている印象である。 豊かに表現される自然描写はとても詩的で、孤独や悲しみがユーモラスに描かれていた。 特に心に残った作品は、「山椒魚」「朽助のいる谷間」「屋根の上のサワン」。 うまく言えないのだけど、さみしさやかなしみの根底にある愛情っていうのかな。人間の奥深さを感じた。著者の懐の深さもね。 以下は覚え書き。 「山椒魚」 成長しすぎて岩屋から出られなくなってしまった山椒魚と蛙のやりとりがユーモアに描かれる。悲しみ、嫉妬、怒りといった感情から始まった二人の関係が、一緒に時を過ごしていくうちにいつの間にか変化していく。 「朽助のいる谷間」 私と、かつて私を育てた朽助という男と、朽助の孫娘のタエト。朽助の家がダムの底に沈むことになったが、決して立ち退こうとしない朽助を説得するようタエトから私へ手紙が届き、私は朽助の元へ向かう。最後の場面の描写が美しい。 「岬の風景」 細い二つの岬に抱かれた港町へと移り住んできた私は、仕事の傍らで女学校出の少女に英語を教えることに。二人は自然と恋愛感情を抱くが、少女の付き人の由蔵と彼の下宿先の賄娘の視線が恋路を躊躇わせる。しかし少女と賄娘が話す姿の眩しさに、躊躇わせていたのは自分の心だと知る。 「へんろう宿」 へんろう宿を営むのは、50くらいの女と80ぐらいのお婆さんと60くらいのお婆さんの三人の女だけ。隣室の客とお婆さんの話し声が耳に入ってきたことから、男手がまったく見当たらない理由が明らかになる。それはかなり衝撃の事実だった。 「掛持ち」 温泉宿の番頭を掛持ちする喜十という男。甲府の温泉宿では三人いる番頭の中で一番うだつが上がらない三助だが、夏場と真冬の閑散期だけ番頭を務める伊豆の温泉宿では誰もが一目置く紳士としてふるまっている。甲府の温泉宿での三助の喜十をよく知る客が伊豆の温泉宿に現れてさあ大変。 「シグレ島叙景」 ある島で廃船をアパート代わりに住む男女とそこへ移り住んだ私。男女は50歳前後、夫婦ではないが、いつも息の合った言い争いばかりしている。そんな二人の様子を眺めながら、時には仲裁役もしてなどをして暮らす私。奇妙な設定と軽妙な人物描写がなんとも可笑しい。 「言葉について」 ある島の住民はみな喧嘩腰な言葉づかいをする。旅行客には住民のおしゃべりや愛情が伝わらないほどの。しかし、一見すると不躾な言葉に聞こえても、言葉の真意を汲み取ることができれば問題ないのだ。言葉の持つ力の大きさと、表面的な言葉の意味に囚われない大切さを思った。 「寒山拾得(かんざんじっとく)」 寒山さんと拾得さんは唐の時代の天台宗の修行僧。寒山さんはお経を手に持ち、拾得さんは箒を持っていて、ふたりともげらげらと笑っている。寒山拾得という水墨画の作品を見ると、この物語のような二人の声が聞こえてきそう。 「夜ふけと梅の花」 梅の花が咲く頃、夜更けの道を歩いていたら、電信柱の影から出てきた男に話しかけられ、男はお礼に金を渡して去ってしまう。その金を返さなければと気にしながらなかなか返すことができず、一年後に男の勤め先に出向くと、男は売り上げを持ち逃げしていなかった。 「女人来訪」 まだ新婚なのに家庭争議の素が舞い込んだ。第3者としての一女性という妙な差出人からの手紙。”岡アイコ”の知り合いらしい女性からだった。8年前、岡アイコは私の結婚申し込みを断っておきながら、私のことが気になって仕方がなかったという。そんな彼女が自分を訪ねてくることに。 「屋根の上のサワン」 散歩中、沼池のほとりで猟銃で撃たれて苦しんでいる雁を見つけ、家に連れて帰り治療し、羽を切り”サワン”と名付けた。雁との心通わせる日々が続いたが、ある月夜、サワンは屋根の上で飛び去っていく雁たちへ鳴き声をたてており、そして… 「大空の鷲」 御坂峠にはクロとして知られる鷲がいる。東京の小説家は、鷲が猿を襲撃し猿を捕まえて飛び去るのを見て驚く。映画の撮影隊がそこへやって来たが、一人の女優が東京の小説家の知り合いだった。その女優が子供の頃に、その家に下宿していたことがあったという。東京の小説家は、少女が女優になるまでの出来事を空想していき...
33投稿日: 2024.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ12の短編集であり、一気に読めた。 方言や見慣れない表現に難しさもあるものの、それぞれ描かれる風景や心情に惹き込まれた。 共通して動植物が印象を深め、各編に一貫性を感じさせる。
0投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ18年ぶりくらいに読んだ。 最後の蛙の台詞の「てにをは」が気になって仕方がない。 「今でもべつにおまえのことを怒ってはいないんだ。」 「今で『は』」じゃなくて? 現在の蛙の心境として『は』よりも『も』の方が適当なのだろうか、としばらく考えていた。 完全なるフィクションなのに、心に期する感情は誰もが共感できるほどの圧倒的なリアリティー。 この作品が名作として伝わっていくなら、僕はこの国が好きだ。 2016.5.11
2投稿日: 2023.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の読んだ文庫はこのカバーじゃないけどまあいいか。 町蔵さんの『私の文学史』で取り上げられていた「掛け持ち」が収録されている文庫がうちにあったので1冊読んでみる。平成9年の奥付で、当時は挫折したが、今回は読了。 表題作と「屋根の上のサワン」(サワン、って傷めた左の翼=左腕ということかな?でも普通は大丈夫なほうを名前にすると思うのでやはり思い過ごしか……)は、たしか学校の教科書で読んだ記憶がある。 で。 「山椒魚」はカフカではないかい。個人的には「シグレ島叙景」「寒山拾得」「夜ふけの梅の花」が好み。 「なんかに似ているな……」と思いつつ、読んでいて気づいた。つげ義春の漫画に似ている作品がけっこうあるのだ(個人の感想です)。
1投稿日: 2023.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ井伏鱒二の懐の大きな文章が堪能できる短編集。ストーリーとか小説の意味とか関係ないというのは乱暴すぎるかもしれないけどとある視点で絵画的に世界を優しく切り取るというようなふうに感じる。その結果「これは何を言いたいんだろう」という感想を持ってしまうものもあるけど、それが世界というものかもしれない。 代表作とされる山椒魚はそんな観察が浮き出る印象。朽助のいる谷間はストーリー感が強めに出る印象。屋根の上のサワンは全体的なバランスのよさを感じた。そのほか、へんろう宿、掛け持ち、女人来訪が印象に残った。女人来訪の文章は面白すぎる。大空の鷲はすごく実験的な作りの小説のようにも思えるけど語り口は井伏鱒二的で不思議な感触。 女人来訪の一番印象に残った部分。 「あなたも岡アイコさんも、どちらも愚劣です。不自然なロマンスはむしろ猥褻です。あなたは榛名山の譬え話で、ふんわりしてしまったんでしょう?」彼女はそれから笛の音に似た声でピイという声をあげて泣き出した。
0投稿日: 2023.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ作品の出来不出来が激しいように思えた。旅する主人公と、その旅先の人々との交流を描いた話が多かったが、同じ型の作品を並べるとこうなってしまうのかもしれない。 似た作家として、漫画家のつげ義春を思い出した。特に「言葉について」などは彼の「紅い花」とよく似ている気がする。比較して読んでみるのも面白いかもしれない。(じぶんはやらないが)
1投稿日: 2023.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ山椒魚と岩屋との関係が、ひとと自我に思える。自我という折。そして、びくりともしない岩屋は、脱出不可能な牢獄にも見えてくる。 そこが怖い。 山椒魚の世界で描かれる岩屋は〝壊れない〟し〝出ることができない〟のだ。 そして日々は続いていく。山椒魚は倦み、病んでいく。山椒魚が、岩屋から眺めた、群れでしか泳げないメダカからすれば、ひとり安全で、生きて行くことに、事欠かない安息の地のような場所でだ。 山椒魚には天敵がない。身の危険が無い。なのに、こんなにも孤独なのはなぜか。 ひとにとっての岩屋とは?もう出ることのできない牢獄のようなものとはなんだろう?しかも、犯罪を犯したわけでも、法に触れたわけでもない、ひとの閉じ込められる〝岩屋〟とは何なのだろう? 注意深くなかったため?ぼけっと時を過ごしていたため? 岩屋がからだで、山椒魚がこころだとしたら? 岩屋が家庭のようにも思えてくる。蛙と山椒魚が、老夫婦にも思えてくる。山椒魚を怒らずにいた蛙は、自由でいたけど、その実、孤独だったんじゃないか。山椒魚との生活で、自由とは程遠いが、孤独ではない日々を過ごせたのではないか。愛ではなかったが、憎しみを持って、他者と繋がることが蛙の孤独を癒やしたのではないか。 メダカにとっては、群れという折に包まれた、不自由な個体にも見えるし、物思いに耽る小海老も、その小さな体が影響を及ぼせる範囲以上の、考えても仕方のない壮大な思考に身を委ねている姿から、その思考自体が、せっかく自由に泳ぎ回れるのにそうせずにいる小海老の岩屋に見えたのかもしれない。 山椒魚の目が見た世界は、結局のところ、どの生きものにとっても、それぞれの岩屋なしには生きては行けず、そこから出る術のない世界に見えたのかもしれない。或いは、酸っぱい葡萄のように、もう岩屋から出ることのできない山椒魚の、負け惜しみに近い皮肉かもしれない。そんな世界に置いて、本当の自由なんてあるわけが無くて、「まぶたを閉じた」暗闇のなかでの幻想としての自由があるのみだと悟ったのかもしれない。 蛙は他者だ。山椒魚は自分の孤独な岩屋に蛙を閉じ込める。ひとりがふたりになる。自分と同じ制約のもとを生きる存在が、他者でなくなるのだとも見える。べつに増えたり、減ったりはしない、拘束を、等しく肩に持つ存在。それが、この世界における友達や、伴侶、なのかもしれない。 ここまで書いて、やっぱり、岩屋とは〝自分〟じゃないかと思う。肥大化した自我は、現実面での行動を拘束してしまう。観念に殺されるひとに共通することじゃないだろうか。精神の牢獄。 この環境をすべて、山椒魚だと見ても面白い。見えてる世界がすべて、山椒魚そのものだとしたら。 まだまだ答えは出てこない。折に触れて思い返そう。。
8投稿日: 2022.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めての伊伏鱒二でした。表題作の「山椒魚」が一番好きかな。これ彼のデビュー作なんですね。天才だ...。 全体通しては、大きな山が何もないのに文章が上手いから話が先に進んでいく...という印象。いや、勿論山はあるんですけど、いつの間にか文章が終わっている。結構突然ラストが来るので余計そう感じるのかも。後書きでも評されてましたが「ストイック」「大袈裟を嫌う」というのがこの人の文章を言い表しているかな、と思いました。 割と初期の作品が多そう?なので、中期、後期の作品も読んでみたいです。
3投稿日: 2022.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
夜ふけと梅の花に出てくるセリフで、 「僕は、酔えば酔うほどしっかりする。」 というセリフがあるんだけど、このセリフが個人的には1番好き。酔っ払った時に言ってみようと思う。 あとは山椒魚グッズが欲しくなった。
1投稿日: 2021.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読む態度について反省している。 僕は集中力がつづくほうではないので、ちょこちょこ読んでは一度SNSを開いたりと、そうやって本を読んでいくことがおおい。しかし井伏鱒二のこの小説はそうやって読もうとしても、続きが頭に入ってこない。前半の何作か、そうやって意味を取りこぼしたまま、物語を終わらせてしまった。 五作目の『掛け持ち』から、一作品読み終わるまでは本を離さないと決めて取り掛かった。 今回、読書をちゃんとし終えられたのは後半の四作だけだったと思う。 しかしちゃんと読めた自信のある作品はどれもこれも、読み終えて作品世界から抜け出したときの自分のいる場所がなんだかおもしろいような気がした。
2投稿日: 2021.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
高校時代放送部に足首浸していた頃、本書収録「屋根の上のサワン」を朗読コンクールで用いました。本文ののびやかな調子も、緊張しいの我が声帯にかかっては跡形もなし。当然の帰結ではあれど去りゆくサワンに寂しさを覚えたものです。
1投稿日: 2021.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ詩を読んでいるかのような文章。 ユーモアのセンスの良さ。 心地よい文体。 また、読み返そうと思う作品。
2投稿日: 2020.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ奇妙な短編集。 表題の山椒魚をひさかたぶりに読みたく、手に取る。 山椒魚とはまさにひきこもりである。 やがて無為自閉へ至るが。 主人公は誰もが、「常識人」風である。(『山椒魚』は除く) 自然描写の精緻さは言わずもがな、だけれども、自然描写の影に、心性の描写は限定的だ。 従って、「察する」という作業を読書に強いる文体なのかもしれない。 これが、精緻なバランスというものだろうか。
7投稿日: 2020.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この短編集の中ではへんろう宿が一番好きです。淡々とした冷めたような文体で不幸な生い立ちながら明るく日々を生きている人々を描写しているのですが、私は作家にとても共感します。作家の感情表現が極力省かれているのにそれでも共感できるんです。読んでいると落ち着きます。
4投稿日: 2020.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ井伏鱒二の代表作だが、自然描写が何とも美しい。 川端康成も自然描写が非常に美しい作家だが、井伏鱒二もまた美しいと感じた。
2投稿日: 2020.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ人物や風景の細かい描写に長けてる。その場面場面における感情を上手く表現しきっているのが良いです。 個人的には朽助のいる谷間がおすすめ。老人の悲哀や少女の生半熟を上手く書いている。なんとなく美術絵の描写を文章化したような印象です。
2投稿日: 2020.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
別の小説のセリフの中に出てきた本だったので読んでみた。うーん、分かるような分からないような、、、 その別の小説内の解釈が好きで読んでみたんだが、私の理解力が足りないのか、、、そしてその別の小説ってのが思い出せない、、、!
0投稿日: 2019.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し昔の作品を一年に1冊以上は読もうと思う。 何か他の作品で山椒魚が気になり、古本屋の100円コーナーで偶々発見! 表題作、山椒魚の外11作品 いろんな町 旅情的な風景が浮かんで来る街を舞台とした作品が多く見受けられる。 個人的には 『へんろう宿』 『掛持ち』 『言葉について』が良かった。 歳をもう少しとったら読み返そうと想う。
3投稿日: 2018.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログおこがましいから書評なんかできないし。 ところで表紙のせいでずっとオオサンショウウオをイメージしてたけど、よく考えたらモデルは普通のサンショウウオだよね?
1投稿日: 2018.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ処女作と思えない老成した感じの「山椒魚」 設定が面白い「掛持ち」 ひねくれたユーモアの「言葉について」 幻想的ですらある「朽助のいる谷間」「へんろう宿」「シグレ島叙景」 女性との関係を滑稽に描く「岬の風景」「女人来訪」 いっぽうこちらは男同士「寒山拾得」「夜ふけと梅の花」 鳥シリーズ「屋根の上のサワン」「大空の鷲」 肩の力がぬけた独特の読み味。
0投稿日: 2018.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初の3篇くらいを読むのにめちゃくちゃ時間がかかったのでそこでやめて、ずーっと読まずに置いていたのを最近続き読んだらすんなり読めたので、以前手に取った時は読む時期じゃなかったんだなあとか思った。 表題作がやっぱりいちばん面白かった。 ちょびっとせつない読後感になる短編が多い。 へんろう宿と掛持ちが印象に残っている。
1投稿日: 2018.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
初期の短編集である。たぶん、図書館のリサイクル市でもらってきたもの。本棚にねむっていたものの中からふと取り出して読んだ。きっかけはある。クイズ番組で「山椒魚」の最初の場面が出てきて、何か答えられなかった。学校の教科書にもあるというが、読んだ記憶がなかった。おもしろかったか。まあふつう。どれもこれも印象に残るものはない。ただ読んでいて、動物が好きなんだろうかとか、風景が目に浮かぶようだなあ、とか思っていた。解説によると画家にもなりたかったとのこと。そういう感じが垣間見える、ような気がする。そして、どれもこれも、本当にあった話ではないかと思えてくる。個人的には「女人来訪」が楽しい。新婚早々、別の女が訪ねてくる。そんなこともあるのだろうか。それから、「夜ふけと梅の花」そんなに心配しなくても、もらっておけばよいお金のような気がするが。「俺は酔っぱらえば酔っぱらうほど、しっかりするんだぞ。」著者の叫びのような気がした。
1投稿日: 2018.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の初期の頃の短編集。 人間って愚かさという意味で面白いなぁ、と思わずには得られないユーモアあふれる話。人間って、と述べたが表題作の主人公は山椒魚。それでも、人間のおかしさが存分に表現されているのだから。 細かく言えば、話の随所随所ではっとする。「へんろう宿」で主人公が二人の子供の名札を確認するのを、自分も同じ行動をしていると錯覚する(同じタイミングでそういえばこの子たちの名前は、と振り返りたくなった)。「シグレ島叙景」ではオタツが戻ってきて伊作へお土産を渡したときの、伊作の反応がわかってしまう。話自体は勿論フィクションだろうが、随所随所で既視感を感じる。よくある日常系に陥らない、この作風は新鮮で読みやすく面白い。
1投稿日: 2018.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ今更ですが…。若い時読んだことなかったので。初期作品12作の短編集。個人的に「夜ふけと梅の花」が一番好きです。このユーモアとヒヤリ感が…。
0投稿日: 2018.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ『シグレ島叙景』『へんろう宿』辺りを読んでる最中、なんだか『不思議の国のアリス』を読んでる時と似た感覚に陥ったんですが、これは作品に漂うユーモアと、主人公とその周囲にある疎通できない壁みたいなのを感じるところから来てるのかな。 主に初期の作品を集めたモノですが、どれも読みやすく飄々としたユーモアで面白かった。
1投稿日: 2017.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ別の小説のセリフの中に出てきた本だったので読んでみた。うーん、分かるような分からないような、、、 その別の小説内の解釈が好きで読んでみたんだが、私の理解力が足りないのか、、、そしてその別の小説ってのが思い出せない、、、!
0投稿日: 2017.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直よくわからなかった。手に取るのはまだ早かったかな……しかし素直な心で素直に味わうことが出来れば必ず面白い、と評されているようなので、あるいは遅かったのかもしれない。目を見張るほど鮮やかかつ艶やかな描写に目を覚まされることが時折あれど、全体としてはつかみ損ねたかな、という感じ。ただ、動物の描写、あるいは動物が出てくる物語は、比較的読みやすかったし、生き生きとした脈動が感ぜられるように思った。あと数年したらまた読んでみよう……。
0投稿日: 2017.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ辻原登の本の中で、井伏とコルタサル二つの「山椒魚」の読み比べを進めていたので再読。まだ、コルタサルな読んでないが。 今では、井伏氏の描く日常がピンとこないので作品を理解するのに苦労するものもあったが、この短編集はバラエティもあり、サスペンス風のもの、掛け合い漫才風のもの、動物もの色々あり楽しめました。あまり名作だからと構えて読まないほうがいい。
3投稿日: 2017.07.02肩の力がぬけた独特の読み味
処女作と思えない老成した感じの「山椒魚」 設定が面白い「掛持ち」 ひねくれたユーモアの「言葉について」 幻想的ですらある「朽助のいる谷間」「へんろう宿」「シグレ島叙景」 女性との関係を滑稽に描く「岬の風景」「女人来訪」 いっぽうこちらは男同士「寒山拾得」「夜ふけと梅の花」 鳥シリーズ「屋根の上のサワン」「大空の鷲」
3投稿日: 2017.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れた名作。 特に山椒魚と屋根の上のサワンは国語の教科書でもお馴染みで懐かしく読んだ。 不思議な感じのする小説で、 小説というより詩のような印象を受けた。 とにかく感情を揺さぶられない。 例えば、電車から窓の外を見ているような。 気にしなければ何も思わないが、注目すれば確かに感じるものがある。 現代小説には、この趣きのある著者は少ない。
0投稿日: 2016.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログどこまでもイメージや象徴の世界に生きていたひとなんだと思う。なるたけ言わずに眼前に示したい、そんなことを目指していたように感じられる。 だから、書くということにかけて、非常にタイトで、文章に無駄がない。ヘミングウェイのそれと同じ匂いがする。そういう点で、太宰が絶賛したのは十分にわかるし、大家であると思う。 けれど、どうしても精神に欠けているように思えてしまう。ことばからイメージを抽出しようしようと、うーんとうなっている姿は見えるが、生きてことばで考えてみようとは考えていない。ことばの存在を前提にしているため、彼は、それを不思議に思ったり、存在に思いを馳せる性質のひとではないのだと知った。 別にそれが悪い訳ではないし、物語を書くということで必ずしも必要だとも限らない。 けれど、非常に不自由だと感じてしまう。何を表現するかで頭を悩ますより、何が表現されているのか考える方がよっぽど生産的だと思う。 ただ、彼ほどの大御所にもなってくると、何を述べるかで、多大な影響を及ぼしてしまうというのもあったのだろう。
1投稿日: 2016.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ20190611 名作に関しては、中学生の頃読み漁っていたが結局、何にも残っていない。読み直しの時期もあるのかも知れないが印象に残るように感じる。次は誰にしようか。
0投稿日: 2016.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「何たる失策であることか!」が滑稽で可愛らしい、山椒魚が主人公の表題を含む短編集。超生き生きとした老人、若しくは動物が異常に登場する。 がっつり心に残る話がある訳ではないけれど、読んでいる内に共感を覚える場面がとても多い。
0投稿日: 2016.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ理由はうまく説明できないが今まで読んだ短編の中では一番好きかもしれない。山椒魚と蛙の関係、何を意味してるのか今一不明ですが....
0投稿日: 2016.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語に余白があって、 その余白のことを想像してみることが楽しくなったのは 本当に最近のことです。 それまでは、はっきりくっきりしないのが もどかしくてむずがゆかった。 私の大好きな山椒魚という小説にも 読む人で色々な捉え方ができる小説です。 あの時こうしていれば、こっちの道を選んでいれば。 穴倉になんか入らなければ。 人は出来なかったことを嘆いて生きていくけど、 それだけでは息さえできない。 カエルがどんな気持ちで 「今でも別におまえのことはおこってはいないんだ」 と言ったのか、もっともっと この人生で考えて考えて 答えをだしていきたいと思います。 「掛持ち」もこの短編集の中で好きな一つです。 人には同時に一面だけでなく 二面三面と色々な顔をもつ生き物。 高校の友達と大学の時に知り合った友達とを 引きあわせて一緒に遊んだ時に感じた 居心地の悪い感じを思いだしました。 「大学ではそんな感じのキャラなんだ?」的な視線を感じて あぁ恥ずかしいと思っていたあの時の気持ち。 私は今までその人の性格がその人の人生や役割をつくっていくと思っていたけど、 それは逆で人は与えられた役割の中に順応して性格や 人生が形成されるのかもしれない。 囚人と刑務官が実験で役割交代をしたら その人たちの性格が反転してしまったように。 性格を人は重視して一番大事な判断材料のように扱うけれど、 もしかして、本当はそんなに自分たちが思っているほどには 大した物ではないのかもしれない。 そう思えると、私には最後に主人公がふっと肩の力がぬけた理由が見えてきた気がします。
3投稿日: 2016.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログダメだ、、、僕には文学は無理!! (^_^;) 『文学作品の楽しみ方』はわかったけど、 その楽しみ方が『僕には楽しくない』のがわかった。 これは決して、 「この作品が面白くない」と言っているのではなくて、 単純に『合う、合わない』の話です。 なので、評価はしてないです。 もっと言うと、評価出来ないのです。 だって、僕は文学の本質の分かってないから。 僕がひとつだけ言えることは、 昔の作品のわりには文語体なので読み易かったし、 短編集ってのも取っ付き易かった。 文学作品の入門編としては良いかも? まぁ、そう思った作品だからこそ、 僕は不得手なのがよく分かったけど。 (^_^;)
1投稿日: 2015.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れた、超有名な作品。 教科書にも採用されたらしいが、多分習っていないので読む機会がなかった。 表題作『山椒魚』は、改変前のもの。 蛙の気持ちになってみると、いよいよ自分の命が尽きようとしているとき、怒りの感情が沸いてこないのも頷ける気がする。 ずっと二人で岩屋の中にいて、悪態ついて過ごしてはいたけど、自分がいなくなった後、1人取り残される山椒魚の哀れさを思うと、自分の境遇よりもなお悪いのではないかと思ってしまう。 閉じ込められて初めて、その孤独や不安を痛感し、いたずらに飛び回って見せて煽るのではなかったと後悔もしたかも知れない。 いずれにしても、面白かった。
0投稿日: 2015.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ解説で「井伏鱒二は無用人」としての自覚があるって書いてあって、なるほどなと思いました。 作品自体は50年くらい前のものとは思えないほど、読みやすい…のだけど、これも解説の言葉だけど「飄々踉々」としてて、掴み所がなかなかみえない作品で、読んでみないと伝えられない感じです。
1投稿日: 2015.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログまず特徴的なのは、淡々とした文章。そして、細やかに綴られる風景描写。 実体験を綴ったエッセイだと思ったのだが、後書きから推測するに、実体験に多くを基づいた限りなくノンフィクションであるかと思われる。 とにかく、実体験と思うくらい、描写が繊細なのだ。まことしやかに思われるが、奥さんの名前が実名の秋元節代さんと違って雪子さんだったりするので一応、フィクションかと。。。 wikiで見ると、山椒魚は改定されてしまったらしい。私が読んだのは、たまたま図書館で借りた古い本で、改定前のものだったが、改定前の方が優れていると思う。 山椒魚はたった10ページなのに、よくまとめられていて、内容は深い。 改定前の部分を含むことによって、同じ境遇の弱者が自己憐憫に似た情を感じる切なさやら何やらが伝わってくると思う。それに、不幸な境遇から、蛙を出してもいいと思える山椒魚の心理の推移なども興味深い。 池波正太郎のエッセイでもそうだが、一昔前の小説家らしく、少し不良。年端のいかない娼婦とのやりとりなども、オブラートに包まれているが、関係が示唆されたりと。この人の文学には、ヒッピー的要素がかなりある。引用の無職の下りは、経験者なら、よく分かる心理が鮮やかに描かれている。 岬の風景で、家庭教師をした娘さんと恋仲になってしまう。それを太陽に見張られている気がする主人公。こういう気持ちって分かるけど、そんな事考えてるの?と、盲執的だと言われそうでなかなか人には言えない事な気がする。無意識に。それをこうして文学にしてくれると、自分だけじゃない安心感を与えてくれる。 掛け持ちは、面白い。 二つの宿で季節ごとに働く番頭さんが、それぞれの場所で全く違う扱いを受けている。上等な扱いをしてくれる宿では、粋な着物を着こなしたり、人間の虚栄をユーモラスに綴る。そこへ、もう1つの宿からの客が偶然やってきて、とまどう番頭さん。 夜ふけと梅の花もなかなか。 酔っ払いに絡まれて、妙な約束をしてしまうが、それが気になってしょうがない主人公。相手が暴力的な人間であったため、数年の間、怯えつつ暮らす。これまた、人間の心の弱さを飄々と描く。 井伏鱒二の他の作品も読んでみたくなった。
0投稿日: 2015.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
小説の世界は広大無辺だ。俗に<ダム小説>というジャンルがある。当該作品のほとんどが、現在は絶版状態になっていて、簡単に入手できないものになっている。石川達三、小山いと子、久保敦子などがそうだ。 <ダム小説>を書いたひとりに、井伏鱒二がいる。「朽助のいる谷間」という作品だ。他の小説と同じように、簡単に入手できないのではないか、と半ばあきらめながら調べてみた。びっくりした! 新潮文庫『山椒魚』の中にしっかり収録されているではないか。 読めるのか……ああ…。感動と安堵の入りまじった息をもらしながら、噛みしめるように「朽助のいる谷間」を繰り返し読んだ。なんだよ、おい。ダム湖に沈む家を舞台にした、うぶな恋愛小説ではないか……。
1投稿日: 2014.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「誰も言ってはならぬ。」 岩屋の棲家に暮して2年。気がつけば身体は岩屋の入口より大きくなり、外へ出ることはかなわなくなっていた山椒魚の悲哀を描く「山椒魚」。「朽助のいる谷間」「岬の風景」「へんろう宿」「掛持ち」「シグレ島叙景」「言葉について」「寒山拾得」「夜ふけと梅の花」「女人来訪」「屋根の上のサワン」「大空の鷲」12編の短編を収録。 本には興味が無いという同僚ですら「からだが大きくなっちゃって出られなくなる話でしょ?」という井伏鱒二の「山椒魚」。 この話、よほどインパクトがあるのか、あるいは教科書にのってでもいたのだったか。とりもなおさず日本一有名な山椒魚くんである。 岩屋から出られなくなっていることに2年も気づかないないうっかり者である上、出られないとわかっていながら、岩屋の入口に何度もヅツキを食らわせて、その度に全身コルク栓と化して、小蝦の失笑を買ったりしている。 死ぬまでそこからでられないという、これが例えば人間の話ならば、笑ってなどはいられないだろうが、悲劇の主人公を山椒魚にすることでこの話はある種のユーモアを伴ったペーソスを以って読者に迫ってくる。 何しろ発表された当初のこの作品のタイトルは「幽閉」だったというのだから。タイトルを「山椒魚」とし、言い方を変えれば、これが山椒魚の身の上におきたことになっていることで救われるというか。山椒魚くん、ごめんよ。 岩屋の中に閉じ込められて一生を終わるつらさは山椒魚にしかわからない。だからこの話にはなんびとも共感したなどと言ってはならない。 言うことを許されるものがあるとするならば、それは理不尽にも山椒魚によって同じ岩屋に閉じ込められ、格闘の末に同じように一生ここから出られぬと観念し、山椒魚に対して「今でもべつにお前のことをおこってはいないんだ」という境地に至った蛙のみである。
1投稿日: 2014.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題作ほか読みやすい佳作12編。 「朽助のいる谷間」のエロティシズム、「へんろう宿」の咀嚼不能感、「掛持ち」の焦燥、「女人来訪」の機微と同情、「大空の鷲」の太宰治。備忘まで。
1投稿日: 2014.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ教科書で読み、山椒魚という話が大好きになりました。ですので他の井伏作品も見たいと思いこの短編集を購入しました。どの作品も風景描写が事細かにしてあり、美しい風景が目に浮かびました。 また全編を通して老人に対する観察、親愛の目があるように思えて素朴な優しさや温かさを感じました。作品自体も素敵でしたが、河盛好蔵さん、亀井勝一郎さんのあとがきもとても面白く読みました。作中で感じた自分の印象が、井伏さんの来歴や人物像から形作られたものだとわかりやすく説明されていて、なるほどと頭がすっきりしました。あとがきを読み、もう一度読み返したいと思いました。 ついでに山椒魚以外で好きな作品は、朽助のいる谷間と屋根の上のサワンです。
0投稿日: 2014.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ初期の作品ということもあるのか、出来にムラがあるような気が。 それでも『山椒魚』『夜ふけと梅の花』だけでもこの文庫を手に取る価値は十二分にある。 『山椒魚』ってもしかして教科書で部分的に読んで以来の事実上の初読?いやそんなことは無いかな、、、 山椒魚は言わずもがな、蛙が絶妙、締め方含めて秀逸。教科書ってことで端から馬鹿にしてはいかんですよ。
1投稿日: 2014.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ改訂される前の版を読みました。 なぜ、和解の場面を削除したのだろうか。 自分はあったほうが良いように思えた。
0投稿日: 2014.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ辻原登の「東京大学で世界文学を学ぶ」第四講義に登場するのは井伏鱒二とフリオ・コルタサルの同名短編小説「山椒魚」である。この講義の中で辻原氏はこの二つを読み比べてほしいと言っているので、読んでみることにした。(この本は井伏鱒二の短編集であり、「山椒魚」のほか11編の短編を収録している。) まず井伏の「山椒魚」は岩屋の中で成長した山椒魚が出入り口の穴より大きくなり過ぎて外に出られなくなる。その腹いせに岩屋に迷い込んだ蛙を閉じ込め、自分と同じように外に出られなくする。そうすることによって溜飲を下げているようだ。しかしいつまでも現状は変わらないのだった。 コルタサルの「山椒魚」では水族館にいる山椒魚を観察する話である。主人公である「ぼく」は水槽の中の山椒魚を細かく観察しているが、いつの間にか山椒魚が「ぼく」を観察しているという不思議な文章である。 どちらも現実の世界に似たようなシチュエーションがありそうだ。現実の社会を皮肉っているようにも思える。
0投稿日: 2014.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ思い出深い作品集 田舎に移ってきた男が、部屋の窓から遠くに見える女の子を見ているという描写があったようななかったような 笠と笠がすれ違う描写があったようななかったような 作品の内容は、ふわっとしか覚えていない もう処分してしまった本、また読みたいけど、読む日は訪れるだろうか
0投稿日: 2013.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み切ったのは短編『山椒魚』のみ。素晴らしい作品だ。 山椒魚の悩みや葛藤は、人間に繰り返し悩むそれと同じで、リアリティを感じさせる。例えば最近の若者の、『引きこもり』の悩みなどは、この小説と同じだ。 私個人としては、昔の小説の言葉の使い回しが、読みづらくて仕方ないのだが、内容だけを見たら、この小説は素晴らしい。
0投稿日: 2013.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ傲慢になるか如何に虚しいことか教えてくれる 特に、金に対して不満をこぼすことがあっても傲慢になることがあってはならない
0投稿日: 2013.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
目の前には大きな世界が広がっていたが、 いつでも出れるさと余裕綽々だった。 しかしいざ出ようと思っても もはやその場から動くことができなくなってきた。 しかし蛙は、その場所を死に場所に選んだのである。 山椒魚と同じようなあり方をしているものはいくらでもいる。 山椒魚は水の底から明るい光をみつめながら呟く。 「あぁ寒いほどひとりぼっちだ!」
0投稿日: 2013.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学校の教科書に有ったかな?あんな終わり方って忘れていた、と言うよりまったく記憶にないが八方塞がりで苦しい。
0投稿日: 2013.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログユーモアと悲哀、他人と心を通わせる喜びとその煩わしさ、旅の一場面や日常の生活風景に立ち現れる人々の触れ合いを描きながら、その実、物語が触れているのは人々の「孤独」であるように思う。 家族であったり、近所の者であったり、登場人物たちはいろいろな形で互いに「境界」を接し合う。その「境界」つまり「自分とは違うものである他人」「心の底まではわかりかねる他人」というのが、どうにも「孤独」で互いの距離がひどく遠く、でもそれだからこそ、その距離を縮めようと足掻いている。その辺が良い味になっているのかしらん、と各短編をしみじみ味わいました。 変わった人たちがちょくちょく出てくるのだけど、主人公(語り手)にとっては誰も彼もが「腹の底では何を考えているのだかどうにもわからん」という人物ばかり。物語にぐいっと引き込まれていくのはその「わからなさ」のせいのように思います。 描かれているのは、何ということのない場面であることもしばしば。 だのにそれが諧謔に満ちて面白いのは、単なる人間観察の賜物ではなく、他人を「わからないもの」として興味を抱いて見つめることから生まれているのではないかと。
0投稿日: 2012.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構「名作」に挙げる人が多いので、期待して読んだ。結果的には自分には「もうひとつ」というところだった。格式高い文章や余韻を持たせた終わり方など、雰囲気はかなりいいが、なんとなく薄味な感じが・・・。自分が最近のどぎついストーリーに染められているのか?そういう意味で自分自身を考えさせられてしまった。
0投稿日: 2012.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ週刊モーニングに掲載されていた漫画「草子ブックガイド」に山椒魚の話が取り上げられていた。山椒魚には3つのバージョン違いがあるのだそうである。山椒魚。昔、教科書に載ってたな。しかし、井伏鱒二については山椒魚しか知らない。 そういえば、昔、東京都下は中央線近くに住み始めたとき、父が荻窪には井伏鱒二が居たんだよと云っていた。まあ、その程度の知識しかない。 久しぶりの山椒魚。少年の頃は和解の物語と読んだが、今読むと蛙が死を前にしていることを昔より意識せざるを得ない。 その他の短編。遅れてきた高等遊民のよう。女性から不良だと云われるし、好色さを見抜かれている。 変な処の旅先の話が多い。つまり放浪の人なのか。幼さを残している少女が土地柄か、ぶっきらぼうな口をきく。彼女にいやがらせをする少年と主人公の会話が最後のシーン。つげ義春の「もっきりやの少女」とか「紅い花」を想い出す。つげ義春も中央線の人だったかな。 「屋根の上のサワン」愛情と束縛。山椒魚に通じるような物語。 「女人来訪」など、嘘だとは言わないが、どこか本当らしくない話。 人生なんて無用なものかと思えてくる。そんな短編集。
2投稿日: 2012.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ#dks 読書会用に井伏鱒二「山椒魚」読んだ、今!なんと、初の井伏鱒二だ。ドリトル先生でしか井伏鱒二を読んだこと(?)がなく、今回が初オリジナル読み。でも山椒魚に出てくるいくつかの決め台詞は、ラーメンズの読書対決で知っていた。「ああ寒いほどひとりぼっちだ!」とか。。 #dks この「山椒魚」がデビュー作で、オリジナルタイトルは「幽閉」だったのですね。ラストを削除した改変版を味わうために途中で強制終了してみましたが、そのバージョンのほうが「幽閉」というタイトルにふさわしい終わりかたに思えます。 #dks 狭い岩穴で身動きとれずにひとりぼっちでこの先何年生きていかなくてはならないのか、を想像するのはかなり恐ろしいです。乗組員が自分だけのスペースシャトルが軌道から外れて延々漆黒の宇宙を漂うのを想像するのと同等です。ああ、想像だけで発狂しそう。 #dks 嫉妬と子供じみた愛情表現(いや、ただの甘えか?)をぶつけ、挙句に死なせてしまう。取り返しがつかないところまで事態を悪化させつつ、責めを逃れるために許しを乞うところも姑息な感じ?これは人間世界に置き換えたらかなりショッキングな悲劇。いや、原発事故の話ではないです…
0投稿日: 2012.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『山椒魚』は、短編ながらかなり想像を掻き立てられる小説であった。 他の短編も、例えば『大空の鷲』など、絵画や映画をそのまま文章にしたような、目の前にその風景が広がっているような、正確で色彩豊かな描写が印象的であった。 井伏鱒二はもともと画家になりたかったと知り、納得のいく思いをしたことがあるが、文章の中にもそういった絵画的描写の正確さがにじみ出ていると感じた。
0投稿日: 2012.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ12本の短編集。 表題作は教科書か何かで読んだ記憶はあるけど、今読み返しても中々面白いとおもった。 ただ、その他の作品って………
0投稿日: 2012.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題作は著者の処女作で、太宰や小林秀雄からは絶賛されたようだ。 そんな文学的な妙味までは分からないが、結末部分で山椒魚が蛙に言う次の台詞、 「お前は今どういうことを考えているようなのだろうか?」 これは初読から強く印象に残った。 なぜ、「考えているのか?」ではなく「考えているようなのだろうか?」なんて言い回しなのだろう? その前の台詞である「それでは、もう駄目なようか?」につられた表現になってるだけか?とも思えるが、なんだか、2年の虚しい月日を過ごした後の山椒魚と蛙の心境と関係が滲み出ているような気もする... 『寒山拾得』では、ラストで二人が画の中の拾得先生の笑い声を再現しようと 「げらげら、げらげらげら」と笑いあって競うのだが、 これ、ほんとに文字通りに「げらげら」と発声してるんじゃないよね...? 実際どんなふうに発声したんだろう?と思案しつつ、歴史上で最初に「げらげら」を笑い声の擬音として思い付いたやつは天才だと思った。 『女人来訪』で妙におかしかった一文、 彼女はそれから笛の音に似た声でピイという声をあげて泣きだした。
0投稿日: 2012.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ蛙の嘆息は「自己肯定」ではないか。岩屋から出る出ないは問題じゃない。みんな孤独だけど、それを和らげてくれる相手の存在を肯定的に受け入れられれば、それでいいじゃないかと。
0投稿日: 2012.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題作「山椒魚」について(井伏の処女作) 教科書にいかにも載せられそうな作品だと思った。今だとイジメ問題とかと絡めたりされるのだろう。(ちなみにこの場合、ラストを削る前のものを掲載するのだろうか。) 短く、かつ内容に展開もほとんどない。教科書的な主題を読み解く対象としては、わかりやすく扱いやすいはずだ。しかし、その読みを当てはめた瞬間、一気に色褪せる魅力。あまりにも薄っぺらくなってしまう。 実際この作品が描くことは、そうした主題とかなり類似しているのであろうし、そしてそれゆえに井伏が後に最後を大幅に削ったのであろうが、たとえどれほど主題的なものが道徳的なアレゴリーを含むとしても、この作品において重要なのはその寓意性ではなく、いかに描かれているかである。 そしてまた、「山椒魚」を評価しうるとすれば、それは、あつかましいほどのアレゴリーの、描かれ方によってでしかないであろう。 技術的な側面からはほとんど何も言えないが、この時期によくあるような翻訳調が見られるということと、それと絡んで語り手がユーモラスな感じを醸しているのがまあまあ良い。 ラストについては感慨深いのだが、今ここで語ることがこの作品を低めることになるであろうから、何も言うまい。
0投稿日: 2011.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログある日ふと気づくと、頭が大きくなりすぎて岩屋から出られなくなってしまった山椒魚の姿を描く。滑稽さの中にある悲哀が光る井伏鱒二の処女作。短い小説ですが、詩的な表現が魅力的な作品だと思います。
0投稿日: 2011.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに、また読んだ山椒魚。 岩屋の中に住んでるうちに体が大きくなり、外へ出られなくなった山椒魚。 いつのまにか、自分にも藻が生えて、岩同然。 あたしも、山椒魚みたいに、ここで大きくなるのだろうか。 居心地に甘えてはいけない。 明日は、何かひとつでも、新しいことをしよう。 まずは、通勤路をちょいと変えてみるとする。
0投稿日: 2011.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ岩屋から出られなくなってしまった山椒魚の話。中学のとき教科書でさらっと読んだけど、大人になってからじっくり再読しました。山椒魚の置かれている状況と心の動きを丁寧に描いており、孤独でいることのやるせなさを思い起こさせます。山椒魚とカエルだけの狭い世界なのに、ちゃんと物語が成り立っているのがすごいところ。
0投稿日: 2011.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ『山椒魚』のほか、『屋根の上のサワン』『へんろう宿』など12編を収録。 表題作は思っていたよりずっと簡潔だった。観察眼と、それを膨らませる想像力に圧巻。 全体的に、起承転結に乏しいノッペリした語り口。それを味がある文章と捉えるか、オチのない退屈な文章と捉えるかは好みの問題だと思う。ちなみに私自身はどっちかというと後者。
0投稿日: 2011.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学校時に通っていた塾でこの「山椒魚」に出会った。すごく面白くて続きがやたらに気になった記憶がある。なんともいえないおかしさのようなものを感じていたのだと思う。 後日読んだらなんだここで終わりなのか、と思った記憶も。
2投稿日: 2011.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ老成と若さの不思議な混交、これを貫くのは豊かな詩精神。飄々として明るく暗い。本書は初期の短編より代表作を収める短編集。岩屋の中に潜んでいるうちに体が、大きくなり、外へ出られなくなった山椒魚の狼狽、なかしみのさまをユーモラスに描く処女作「山椒魚」、大空への旅の誘いを叙情的に描いた「屋根の上のサワン」ほか、「朽助のいる谷間」など12編。 井伏鱒二1898~1993 新興芸術派 ジョン万次郎漂流記、黒い雨
0投稿日: 2011.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかくオチがない。だからどうした?という話ばかり。 観察眼はすごいのだろうが、劇的な展開も腑に落ちるオチもないのでやや退屈。
0投稿日: 2011.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ山椒魚に限って言えば、観察力がすごい。友情とか葛藤とか描きたいなら人間にやらせたほうがやりやすいはずなのに、わざわざ生き物(しかもちょっとレア)をして話を進めるってのは細かい観察の賜物なのではと思う。
0投稿日: 2011.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めて井伏さんの本を読んだ。「朽助のいる谷間」がめちゃくちゃ好み。 すごく短い話ばかりで、頭を切り替えながら読むことができた。しかし基本的に電車での立ち読みだったので、今一消化できないまま次の話にいってしまうのが残念。これは自分の責任か(笑)次はゆっくり読み返そうと思う。 田舎の風景とかがすごく綺麗に頭に浮かび、余韻を残してくれた。
0投稿日: 2011.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題作「山椒魚」が好きだとこの年になってから思う。学生時分にはユーモラスであるなぁと思うくらいの感情しか抱けずにいたが、それは授業で習うものだという偏見に満ちた捉え方だったので、三十路を迎えて改めて触れて面白さ(特別なものというよりも、ふとした一節にハっとさせられるような)に気付く事が出来た。「山椒魚は今にも目が眩みそうだと呟いた」この一節で、山椒魚が本当に淋しくて仕方が無くて、苦しんでいるのだというのが伝わってなんとも言えない気持ちになった。 「ああ寒いほど独りぼっちだ!」と山椒魚は嘆く。気付いて欲しいことほど、気付いてもらえないのは世の常であるのかもしれない。(2010.11.22 読了)
0投稿日: 2010.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ山椒魚が読みたくて購入。 読んだ感想、あれこんなんだっけ? 子供のころ国語の教科書で読んだのと違う・・・気がするし、こんな長かったっけ? やっぱり教科書は添削されているのかな・・・
0投稿日: 2010.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすいし面白い短編集。面白いけれど、ダイナミックでもドラマチックでもなければドラスティックでもない。痛快なオチがあるわけではないけれど、映画のなんでもないワンシーンが印象に残るような読み心地。あと登場人物の方言が気持ちよい。
0投稿日: 2010.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログすごくエンターテイメントですよね。『山椒魚』に関してはそう感じます。 二人(二匹)の掛け合い、結末、セリフの滑稽な感じ、短さ、色々な点で純粋に面白いし、楽しい。深く読み込めるし、あーあ、と思っておしまいでもいい。舞台は狭いのに自由を感じる。 なのに井伏鱒二の他作品は決して読みやすいとは言えない。不思議です。
0投稿日: 2010.09.15
