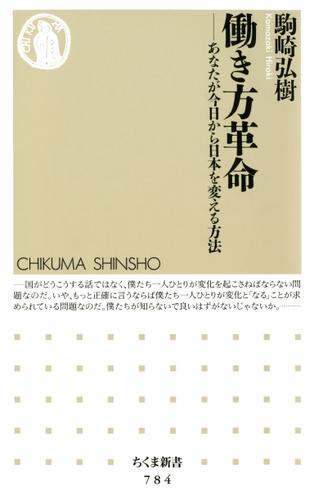
総合評価
(138件)| 45 | ||
| 52 | ||
| 24 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で、題名に釣られて借りた本だがなかなか刺激になった いまほど 働くってなんだろう? と問われる時代は無かったのではないか しかも、その解答はどんどん難解になってきている 明確な答えなんてないだろう それよりも 著者自身の苦労の積み重ねを伝え聞くほうがはるかに答えとして与えるものが大きいだろう この本はノウハウよりも、経験談の方を大きく割いている 読み応えもあり、おすすめです
0投稿日: 2011.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ他のレビューにあるよう、方法論自体はライフハック本で見たことあるような事。だけどそれはどうでもよくて、大事なのは著者がそれを自らの言葉にし、行動し、物語として、その中に生きていることだ。自戒としてでなく、行為したい。 11.01.17-18
0投稿日: 2011.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログここ数年の自身を振り返ると社会に対してはなかなか働き掛けが出来ていませんが、家庭でも働くことを心掛けてきました。著者の姿勢や理念には大賛成です。ただ本としては半分以下の厚さで書けるのではないかな、という冗長さが気になりました。内容、文体とも若い人には受け入れられやすいだろうけど、逆に年寄には受け入れられなさそうで、それが実社会でも若者の障壁になっているんだろうなあ。
0投稿日: 2010.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログワークライフバランスに関する本。 勝間さんや小室さんといった人たちと同じ系統なのかな? とにかく面白くてすぐ読み終わりました。 ワーカホリックだった著者の変わっていく姿(考え方・実行していくこと)にすごく引き込まれました。 働き方、生き方そして「そういう人生を送りたいのか?」を考える面白い本でした。
0投稿日: 2010.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ一人称での書き出しに少しおどろいたが、提案としてうなずける部分がおおく、若い人に期待をいだいた。仕事達成へのプロセス姿勢や、物事の処理が逆に印象にのこった。
0投稿日: 2010.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ素直に受け入れられない会社の、上司の価値観に縛られ苦しんでいる中で出会った一冊。 やらせれば良い、といって投げつけられる雑用が楽しくないのはフラグメントだから。 引退しても、地域には生きてる限り仕事がある。 プライベートを含めて、他者に価値を与えること全てを働くことと定義する。 自己啓発本に書かれているような事もたくさん書かれていますが、それ以外にもはっとさせられる言葉が多く登場します。 79年生まれと若い方くしてこんなにもいろんな事ができるのかと刺激を受けました。
0投稿日: 2010.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ同じ年とあってか、著者の考え方に非常に共感が持てた。働くってことは、仕事だけではなく、家事や社会貢献も働くってこと。自分たちが働き方を変えて、日本を変えて行こうという心意気が素晴らしい。自分も社会貢献につなげる何かをしてみたいと思った。
0投稿日: 2010.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ(しゅんぺい) 将来パパ志望の男性はマスト読書。 「はたらく」とは 傍(はた)の人を楽にすること。 会社だけでなく家庭、地域社会への貢献も仕事である。 という駒崎さんの考えは凄く響いた。 いいパパになってママを支えよう。
0投稿日: 2010.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 残業・休日出勤して、人生を会社に捧げる時代は過ぎ去った。 長時間働いても、生産性が高くなければ意味がない。 誰よりも「働きマン」だった著者がどのように変わったか、そして仕事と共に家庭や社会にも貢献する新しいタイプの日本人像を示す。 衰えゆく日本を変えるには、何よりも私たちの「働き方」を変えることが、最も早道だ。 なぜか? その答えは本書の中にある。 [ 目次 ] 序章 なぜこのような本を書かざるを得なくなったのか 第1章 自分は働くことで、誰かを壊している? 第2章 自分のライフビジョンて、何だろう? 第3章 「働き方革命」の起点-仕事のスマート化 第4章 「働き方革命」でたくさんの「働く」を持つ 第5章 「働き方革命」が見せてくれた世界 終章 「働き方」を革命し、日本を変えよう [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2010.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書というよりは自己啓発に近いかな。 小規模社長だからこそできることが多くて 一介のサラリーマンには難しい事例も多いけど 夢があって詩的で読むと元気が出る。 働くことに希望が持てる良書。
0投稿日: 2010.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ20100630読了 働き方革命 仕事の定義を、食い扶持を稼ぐための仕事から生活全般まで範囲を広げて捉え直すこと。
0投稿日: 2010.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事中毒だった著者が自身を見つめ直し、変化していく様子を著者自身の体験から語った本。 方法論ではなく、何に悩み何を考えどういう目標を持ってそれを行ったか、そういった事に非常に感銘を受けた。自分の生き方に疑問を感じた時にちょっと読みたい良書。1時間程度で読み終わったが、ハウツー本より印象に残る。 著者の「そう、誰かが言っていた。日本語の「働く」という言葉は、傍(はた)を楽(らく)にさせることから来ている、と」という言葉がキーフレーズ。
0投稿日: 2010.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間は自己イメージの周辺を心地よいものと感じて、そこから出ることを極端に嫌がります。今、あなたはあなた自身に、常に忙しい人という自己イメージを与えています。だからそのイメージに反するような行動を、無意識のうちに嫌がっているのです。忙しい状態というのが、あなたの安定領域なのです。働き方を変えたいと思いながら、古い自己イメージをもっているから、その安定領域に縛られている、新しい自己イメージを持ちなさい。そのために自己対話をしなさい。望ましい自己イメージを描く。自己対話を 目標は必ず言語化し、繰り返してみて、自分自身にすりこんでいきなさい たとえ解決できないようなものでも、悩みの重量は口に出す前よりも出したあとのほうがよっぽど軽くなるのだ 仕事で使うレポートトークと家庭で使うラポールトークは違う。レポートトークは結論から、ラポールトークはプロセスを共有する パートナーと言うものがいて、それに出会うのではない。人はパートナーになっていくのだ、しかもそれを相手に期待するのではなく、自分がかわることで新しい関係性を創り出すことができるのだ。
0投稿日: 2010.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ□ 著者はNPO法人「フローレンス」を運営する社会起業家、駒崎弘樹氏。 □ 働く=傍を楽にする/他者に価値を与える □ 彼の団体の仕事は、働く女性が急に子供の具合が悪くなった時だけ預かる病児保育というもの。 □ 最初は代表として死ぬほど働いていたが、あるセミナーで人生について考えた。 □ 会社で必死に働いても誰も幸せになれない。女性は時間を制限されるか仕事を辞める。 □ 男性は遅くまで残業して鬱か過労死、運良く定年を迎えてもやることがない。 □ 代表の自分は社員や家族を殺しているのではないか。そう思ったとき、変革を決意したそうだ。 □ 働くは周りを楽にすることなのだから、家で家事をする、地域ボランティアをする、子供と遊ぶ、趣味に打ち込む、誰かの介護をする等、これらすべてを「働く」と定義する。会社以外にもたくさんの働き口を作るのだ。そのために会社での働き方を変える。
0投稿日: 2010.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ質は二の次で長時間働くことが評価される時代では、もはやないと思います。今でもそういう考え方が大勢を占めていますが、いずれ立ち行かなくなるでしょう。駒崎氏のような考え方ができ、行動に移せる経営者が、どんどん増えることを願っています。行動すべき内容は難しいものではないですが、周囲を気にしていたら、初めの一歩を踏み出すことは難しいかもしれません。「働き方を変えたら優秀な女性社員がやって来た」という部分に、今の日本社会が抱えている問題の解決方法が表れていると思います。
0投稿日: 2010.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ共感した本でした。著者の駒崎さんは、大学在学中にIT事業を起こしたが、社員の病気や退職をきっかけに、がむしゃらに働くやり方への疑問を抱き、IT事業を譲渡し、現在は働き方を支援するNPOの代表を務めているという。 「働く」ことや「自己実現」には、いろいろな考え方があると思うが、駒崎さんは: * 子育てをする人(男性でも女性でも・・・)が定時に会社を出れて、 * 男性でも家事を担うことで家庭への『働き』を楽しみ * 社会へも貢献(いろいろな型があってよい)することでその『働き』を楽しむ 社会を志向している。 単にもっと女性の労働力を活用しようとか、男性も育児や家事に参加をとか、地域社会への貢献もしようと言っているのではない。駒崎さんは「働きマンな自分が好き」と言えた過去を持ち、しかし次第にそのことがいろいろな問題を放置、あるいは起こしていることに気付く。例えば、夫婦の1人(典型的には男性)が深夜まで働くとなると、がむしゃらな働き(長時間労働)による生産性の低下、後継者が育ちにくいという会社内の問題、家庭で会話が失われるなどの問題、病気や育児によって可能性のある人が働けなくなる問題、などがある。 僕も長時間働くことで自分を立ててきた人間だ。同時に効率性や創造性も追い求め、より大きな仕事をしようと心がけてきた。仕事大好き人間、そしてやりたい仕事ができて毎日が楽しかった。しかし、ゆっくりと成功体験が自分を蝕んでいく。高い山を見ると登りたくなる。しかしその山は自分が登るべき山か、登った体験をどう活かすのか、登った後にどこへ行くのか、を考えることはなかった。何故登るのか?それはその山がより高いところにあるからだ、と。 自分の感情や家庭も犠牲にしてきた。「昔だったら、プライベートだから何かをしよう、例えばテレビを見たり、外食をしたり、という形で何か行動を伴っていることがプライベートへの切り替えだったと思う。今は、何もしなくても幸せを感じる、ということがプライベートだと思う。」という変化を語ったことがある。文脈をここで補足すると、そこでは”何もしない”ことが良いと言うのではなく、言葉を通じて心が通じた家族といることによって何もしなくても満たされる、ということを書いている。そして、このことは、当然に作用・反作用の力学でしか継続しない。つまり、僕が”満たされる”のと同時に相手のことを”満たす” のだ。 働き方の問題は、僕らの気持ちだけでは成就せず、一義的には経営者と価値観が合っているかという問題であるだろう。従業員は会社という器を選ぶことが転職によってもできるけれど、今のような不況では簡単ではない。もし、今働いている会社が長時間労働に依存するようなやり方をしていたら、個人としてそれを打開するのは容易ではない。 しかし、もし長時間労働に疑問を持ち、そして競争社会の中で昇進だけを糧に頑張る方法に違和感を感じたら、どういう働き方が良いのか、自分を活かす場所はあるか、について考えておくことは意味があると思う。チャンスはいつか訪れる。そのときにチャンスと気付くかどうか、そのチャンスに賭けると思えるかどうか、は普段の準備にあると思う。 ボクのブログより:http://d.hatena.ne.jp/ninja_hattorikun/20090830
0投稿日: 2010.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログそうなんだよ、そうしたいんだよ、と思いながら、サラサラと 読んでしまいました。 自分の意識を変えるきっかけになりました。 スリムタイマーはとっても面倒な感じがするけど、集計する には使った方が便利なので使ってみよう。
0投稿日: 2010.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ涙が止まりませんでした。 がむしゃらに働くことは決して悪いことじゃない。目指す方向によっては必要な通過点。それぞれみんな必要だと思ってやっているのて、絶対他人が否定出来るものではない。 だから深夜帰ってきてmacbookの上にこれが置いてあった時は、良い気分ではなかった。でも読んでみてよかった。嫁に感謝。 あとでちゃんと感想書きたい。
0投稿日: 2010.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ下記blogにて書評を公開しています。 http://wisdomofcrowdsjp.wordpress.com/2010/05/14/r024/
0投稿日: 2010.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログフローレンスの駒崎さんの著書2冊目です。 今回もフローレンス関連、社会起業のススメかと思っていた ら・・・ 主題は全然違ってびっくりしました。 私がポイントだと思った第3章からタイトルを抜き出すと・・ ◇◇◇ ○定時退社経営者 ・6時にオフィスを出てみる ・スリムタイマーで仕事時間を計測 ○仕事のスマート化 ・マネージャーのスマートワーク化(6時で帰宅命令) ・仕事の仕組み化(マニュアル化と活用の仕組み) ・企画スタッフの在宅勤務・ひきこもりの制度化 ◇◇ ワークライフバランスというのは、男女の区別はないもの。 送りたい人生を送って、 仕事でも家庭でも なりたい自分になる為の時間を再配分だと 教えてもらいました。 駒崎さんがあるきっかけで取り組み始め、 彼の身に起こった様々な変化体験を語ってくださった すばらしい本だと思います。 もちろん、これまで駒崎さんが一生懸命、能力を磨き 高い仕事の能力を持っていた事が前提にあります。 けれど、ベンチャー(NPOですが)の経営者が6時に帰る。 これを実行することはハードル高そうです。そして、全員に浸透するまで実行し続けるのは不可能めいた事に思えます。 興味を持たれた方は、 ぜひ、自分はどんな人生を目指したいのか 今一度振返ってみてはどうでしょう?
0投稿日: 2010.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事中毒で、起きている時間の全てを仕事についやして、ギリギリのところで生きている現状を、自身で見直し、変革させてゆく物語。読み物としても面白い。一緒に住むパートナーとの関係がよくなってゆく様子や、両親・2人の姉とのやりとりがからんでくるあたりも おもしろい。 日本全体で考えると 「ワークライフバランス」を変革してゆくのはいかに難しいかを思い知る。トップの意識が変革しないと、その下で働く者もなかなか変えられない。その点「フローレンス」はすばらしい。 ひとりひとりが自分の人生を大切に生きれるように変わったときに、この国にも新しい「働き方」のかたちができているのだろうか。
0投稿日: 2010.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ今現在、この考えに対する批判が思いつかない。 革命には時間がかかることを再認識した。 やりがい=裁量権のある仕事
0投稿日: 2010.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログまずこの本は「新書」という枠からはみだしています。(良い意味で) 若干30歳の社会企業家の駒崎弘樹さんという方が著者であり、新書にありがちな小難しい単語は使わず、かっこつけず、口語で書かれているため直球に言葉が入ってきます。 まさに社会だけでなく、新書の世界にも革命を起こしてくれている気がします。 その駒崎さんが、自分の働き方をマネジメントしていく中での気づき、発見、思いをシンプルに語ってくれるため、それを自分に照らし合わせて今後の働き方も考えて直してみる気になれました。(まだ働いてませんが。。) 自分の夢を自分の携帯宛に自動送信するという妙案は早速試してみようと思う。
0投稿日: 2010.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ病児保育事業に取り組むNPO法人フローレンスの駒崎さんの著書。 少子高齢社会がものすごいスピードで進展していく21世紀の日本にあって、労働問題は重要な課題である。 労働人口の減少に対してはいくつかの対策が考えられる。 海外労働力の活用。 定年制の廃止による高齢人材の活用。 女性労働力の活用。 などなど。 特に女性労働力の活用を進めるためには、日本の労働慣習(長時間・激務)を改めなくてはいけない。 それを改めることによって、共働きがしやすくなったり、育児しながら働きやすくなったりということにつながる。 で、その労働慣習の改革をどうやるのか、という問いに対する駒崎さんの答えが「一人ひとりが変えていけばいいんだ!」というもの。 実際駒崎さんが実践したことは、たった一人の人間の変化なんだけど、とても大きな変化であり、胸がすく思いがした。 ただ、表面的に「考え方の問題」と表面的に読んだだけでは、進◇ゼミのマンガになってしまう。 流れるような変化の中で、駒崎さんはものすごくロジカルに考えてる。 自分のライフビジョンは? そのために今日すべきことは何か? 「働く」という概念を、飯を食うために会社で労働すること、だけではなく、自分のライフビジョン全体に敷衍して捉えること、そして周囲に良い影響を与えること(傍を楽にする)、と広い新たな概念で捉え直すという発想は面白い。 ただ、本書の中でも友人になかなか伝わらない、というエピソードが出てきたけど、何か別の言葉で表現したほうが良かったんじゃないかなと思った。 何か対案あるわけじゃないけど。 まぁとにかく、自分もジェンセンおやじみたいな人生が送りたいと思った。 この本、若い人には比較的受け入れられてるようですね。上の世代の人にはまったくらしいですが。 これを受け入れられる世代が多数派になっていくには時間がかかるかもしれない。 けど、その時間を少しでも短くするためには、マクロ政策よりも、一人ひとりにアプローチする方が効果的、という駒崎さんの考え方には賛成です。
0投稿日: 2010.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2010/1/15読了)一言でまとめると「ライフワークバランスのすすめ」ということになりますが、単なる理念だったりノウハウだったりせず、ご本人の具体的な体験談がベースになってて、物語仕立てで読めるのが面白い!16時間労働の仕事中毒だった著者が、8時間労働に激変する様がすごい・・・。
0投稿日: 2010.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半がおもしろい。 優秀な女性が家に入ってしまうことを「監禁男」呼ばわりしていた著者が、もしかして自分も??と気づき、周りの人たちとコミュニケーションしていく様子がリアルに描かれている。こんなふうに気づいて変化していける、そしてそれを表明しても否定されなくなった社会になって嬉しい。さて、この男性の意識変化に本当の意味で女性がついていけるかですね。 後半は、最近のキーワードである「仕組み化」「効率化」を軸に展開。このあたりは多くのビジネス本と共通するところ。100111
0投稿日: 2010.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、ある同僚と私の間で、ライフハックツールがはやっている。 主にタスク管理に関するライフハック的なアプリだとか、Webサービスだとかを使っては、これいいよ、とか教え合う。 その同僚が、スリムタイマー(slimtmer.com)を紹介してくれて、「この本に載ってたんだよね。もう読まないから、この本、あげるよ」と、いとも簡単にこの本をくれた。 そんないきさつで偶然手にした本だったが、読み物として面白く、そしてとても共感できる内容で、あっという間に読んでしまった。 会社を軌道にのせた著者は、いつの間にか、無駄な時間を許せなくなりどこでもメールを見て、仕事をしながらランチを食べるようになり、他の人の生産性の低さが目について叱ることが多くなり、土日は寝るだけ・・・ 仕事のスピードだけはあがって、どんどん多忙になるスパイラルに入っていった。 そんな著者が、あるきっかけから、自分のライフビジョンを描き、それを実践していった結果、「闇夜の泥道を這うような働き方」から「晴れたハイウェイに愛車を走らせるような働き方」に変わっていく。本著には、その過程が描かれている。 面白おかしく書かれていて、少し脚色が入っているのかも、と思う。 でも、具体的にどうやってワークライフバランスをとっていったのかが書かれていてとても参考になる。 著者の本を読んだ、とてもとても優秀な女性の何人かが、著者の会社に入社したというエピソードも書かれていたけど、すごく、よくわかる気がした。働く女性キラーですね、この本は。 あと、個人的には、著者の姉との会話にめちゃウケ。 外資系勤めの著者のお姉さんが、「身振りと手ぶり」を駆使しながら、「私がアグリ-なのはね・・」とかカタカナまじりで言っているシーン。 ・・・私のまわりにいっぱいいる。っていうか、私もそのうちの一人だ~。 普段は出ないようにしてるけど、同類と話すと、100%出る。 よく観察してますね、駒崎さん。なはは。 【とくに印象深かった箇所:本書からの引用です】 ・ ジェンセンおやじは、仕事を楽しみ、一所懸命やりながらも、将来の自分のために勉強をして、家族を愛し、家族のために時間や気持ちを使い、地域にも貢献していた。ジェンセンおやじという1人の個人の中に、いくつもの世界があった。いくつもの世界がジェンセンおやじの中で綾をなしてキラキラと輝いていた。 ・ 「会議のルール」から: - ひとつの会議は1時間半を越さない。 - 議題は前日までに出し、議題にないものはと議論しない。 ・以前は、読書しても、100読んでも5しか参考にならないことを「95無駄にしてしまった」ととらえ、時間を無駄にしたくなかったから読む本を厳選し、結局なかなか読めずにいてしまった。 しかし、5が継続的に得られるということは偉大なことだ。1か月に1回5が得られるのと、3か月1回15が得られるのでは、前者のほうが得だ。なぜなら、最初の1か月5を得られれば、少なくとも残りの2か月は何も得られていない状態より、5だけすぐれた行動ができる。 この「時間差」が変化の速い時代には聞いてくる。経営者にとって、数か月が命取りになることもある。継続的に読書などのインプットの時間がある、というのは経営者やマネージャーにとって、命綱になりうるのだ。 ・ 昔から「パートナーとなるような人と出会いたい」と思っていろんな女性と付き合ってきた。しかし致命的な間違いを犯していたことに「働き方革命」を始めた後に気がついた。パートナーというものがいて、それに出会うのではない。人はパートナーになっていくのだ。しかもそれを相手に期待するのではなく、自分が変わることで新しい関係性を創りだすことができるのだ。 ・ マネージャーのマネジメントを管理する方法として、プロセスを管理するやり方がある。彼がどういう人材を仕事につけたのか、部下のキャパシティにどの程度タスクを詰めているのか、というチーム内経営資源の配分を見ていくことで、うまくマネジメントしているかどうかわかる。しっかり効率的にマネジメントできていれば、残業時間数はゼロになるはず。 ・ 自分のために、自己中心的に仕事の手を抜いて、自分のことに時間を使おう、ということではない。人生そのものを「働く」としてとらえる。食いぶちを稼ぐことも、家族と生きることも、自分のために学ぶことも、全部ひっくるめて「働く」と考えたらどうか。「働く」を「他社と自分のために価値を生み出すこと」とする。
0投稿日: 2009.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者のまっすぐな性格が伝わってくる書き口でとても読みやすい。納得することは多く、自分も忙しさにかまけていないで時間を作らないといけないなぁ、と反省。
0投稿日: 2009.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「しごと」に対する考え方とかやり方とかの本。 感想としては「できる人はできる。できない人はできない。」かな。 やり方としてはGTDに通じるところもあってわかりやすいけど、時間を時給で比較するところところとか違和感が。
0投稿日: 2009.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会起業家として著名な彼が、これまでに経営者として生きてきた時間を振り返りながら、時にコミュニケーションや仕事の割り振りを考えるビジネススキルを磨き、時に自分の働き方の違和感から時間の使い方からひいては長い人生設計そのものにまでつなげるなど、おおむねマネジメント全般を体験的に叙述した本です。 なので、言ってしまえば問題点として著者自身が発見するものは身近なものであり、管理職たりえる人となるには基本的に必要となるであろう項目が書かれているだけなのです。その点では新鮮味というものはあまり感じられません。しかし、駒崎さんと私の年齢が近いこと、そして彼が取り組んでいる分野が私の仕事領域と完全に重なること、さらには彼自身のかなり口語的でぶっちゃけ気味な文体な醸し出す親近感に引き寄せられる感覚が、この本を2時間弱でサラッと読み終えてしまえた理由なのかも知れません。 なので文章を読みながら考えるという私が選ぶ書籍でよくありがちなパターンにははまらず、読み終えてみて振り返りながら自分の明日にどう役立てるかというプロセスがこれまでにないスピード感で爽快感さえ感じることができました。本来ならば新書はこの程度のスピードで読まれるべきものなのかもしれませんがいかんせん遅読の私にはなかなか体験できないものでした。 既に読み終えている他の書籍との関連性でいえば、人口減少社会のこの国にあって一億総中流社会や男性中心社会など、高度経済成長期を通じて暗黙のうちに作り上げられてしまったテーゼを何によって突き崩していけば良いのかを考えるために必要な考えにワーク・ライフ・バランスがある理由を、考えるきっかけになると思います。折からの不況でやることがたくさんあるのに何が定時退社、何がノー残業デーだと言われることもあるかもしれません。 でも、一方で個人的にはなかなか達成できていない中で、自ら帰宅が遅いときには次のように割り切ることもあります。限られた時間の中で仕事を処理しきれないのは、自分のキャパシティに合わないほど膨大な仕事が集中しているか、もしくは与えられた仕事を時間内に処理しきれない自分の能力の無さを責めるのか。大概にしてわたしが後者であることが多い分、著者の訴えを実現できるように自己研鑽を続けて1分1秒でも早く自宅の扉を開けられるようにしなくては、改めて思える書籍でした。
0投稿日: 2009.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ一気に読んだ。働きマン、寝る時間も惜しんで働き、残業しない日はない、日々笑顔を忘れ、仕事のメールに追いまくられ、効率ばかり求めていた著者の「働き方革命」。一言で言うとワークライフバランスがうまくいった人の話になっちゃうけど。自分がどう生きたいか、考えていることを書き出してそれを実行していく。なぁんだ そんなこと と思うけど、思うだけなのと実際実行するのでは、10年経ったとき天と地ほどの差があるんだろうね。まず目標とするライフビジョンを描くことから始まる。・私は家族と仲良しである・両親が丈夫で楽しく暮らしている・仕事にやりがいを感じて充実している などなど。そうだね〜私も書いてみよう!これもマインドマップと同じで、こうしたいっていう思いを描くとそれに向かって行動も自然とそうなっていくんだろうと思う。それもただ描きっぱなしではなく、毎日毎日見ることが大事。お金持ちになるのではなく、時間持ちになったというところも「うらやましい」って思う。
0投稿日: 2009.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ一人一人が、自分の未来についてマジになる。 革命ほどではないけど、変化は一人一人がもたらす時代になっているんだ。
0投稿日: 2009.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「働く」ということは、「仕事をする」と言うこととはイコールではない。 働くとは、家族との時間を共有したり、地域の活動に貢献したり、自分磨きの時間にあてたり といろいろなことをするためにあるものであると。 働くということについて、もっと多くの人が考え始めたら本当に変わるのではないだろうかと思う。 自分も含め、多くの人が「働く」ことに対して改革を起こす時期が来ているみたいです。
0投稿日: 2009.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ【オススメ人】中村奈津 【読んでほしい人】就職活動生・働く父親、母親 【オススメポイント】 「働く」というのは会社に行って仕事をすることだけじゃない。 「傍(はた)を楽(らく)にすること」それが働くの語源。 ワークライフバランスというのは、なにか新しい価値観ではなく 当たり前に存在していた価値観だったと気付かされた本でした。 就職活動をする際、自分はどう働きたいのかという考えを 広げて考えようとするので精いっぱいで、 しかしそれ自体が視野が狭くなっていることと同じでした。 就活を終えてみて、多くの学生・社会人は 「あの頃は必死だった、懐かしい。」と振り返る。 しかし就職活動は一時の試験なのではなく、 将来を考える一番大切な時期だと思う。 この本を読むことで、本当に自分の人生を考えていくことができる気がする。
0投稿日: 2009.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ自己イメージが、私たちの行動を規定する(52頁) アフォーメーション(54頁) 目標は必ず言語化し、繰り返し見て、自分自身に刷り込んでいきなさい。(69頁) メール自動転送 「自分のやるべきことを把握し、それに沿って仕事を組み立てる」ということから逃げていないか。(87頁)
0投稿日: 2009.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ働き方革命と題し、働く=他者に価値を与えることと広い意味で再定義。目標を掲げライフビジョンを描くことが大事。仕事のスマート化の為、スリムタイマーを活用とかいており、導入したいと考えた。育児、介護、様々な課題が山積する課題先進国日本が解決策を輸出出来る様、まずは帰る時間と寝る時間、休日の調整を図り、コミットメントを増やしていきたい。
0投稿日: 2009.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の多くの会社が似たような現象を起こしてる。就業時間が長過ぎる。友人と話しても、必ずどこかで忙しさ自慢になる。「今週全然寝てないよ」「土日も会社行かなきゃだよ」って。 え、でもこんなに働かなきゃ、日本ってまわらないのかな?こんなに頑張らなきゃ、食っていけない国なのかな? この疑問はずっと、僕の中にあって。もしそうなんだとしたら、変えなきゃいけないと思う。「働き方」を。筆者が言うように「働く」の概念を拡張するんだ。傍を楽にさせること、それを全部「働く」ととらえて。 僕のライフビジョンは著者のものともう少し違うと思うけど、みながその実現に向けていけたらいい。
0投稿日: 2009.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ2月1日、はっきりとした口調で駒崎さんが言ったこと。 「勉強しなさい。ついてこれないやつはついてこなくてよろしい。」 正直、学生を切り捨てるような怖さを感じた。 でもそうじゃないことがよくわかった。 挑発― 伝わらない人には伝わらない。 でも伝わった瞬それはとても大きな力になる。 駒崎さんのような、人間になりたいと心底思った。
0投稿日: 2009.05.21
