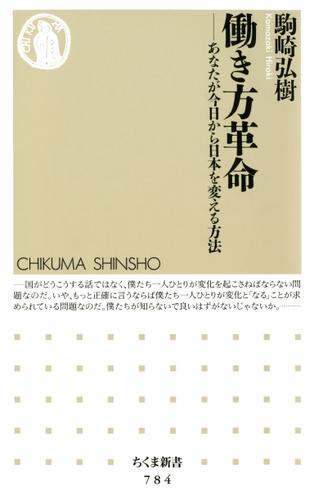
総合評価
(138件)| 45 | ||
| 52 | ||
| 24 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みやすい文章だった 認知的不協和 安定領域 忙しい状態が安定領域となっていないか 自分が忙しいのは忙しがっている自分自身の責任 どういう人生を送りたいか、それに向かって行動する 側を楽にする 他者と自分のために価値を生み出すことを働くと定義する スリムタイマー使ってみたい
0投稿日: 2023.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログとある思考の回数が多い部分のニューロンが発火し、道ができ、よりその思考がされやすいよう脳が作られる。 潜在意識ともいう。 だから潜在意識で自分には無理だと思っていると行動に出られない。 働くということを、食いぶちのためだけでなく、人生を豊かにする地域貢献、家庭の仕事、育児、家族との関係、すべて
0投稿日: 2021.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ【実現のためにはまずビジョンを設定せよ】 ビジョンドリブンな働き方や組織運営を早々に説いた本。 2010年に読み終わっていたが、2020年に再読しても切れ味抜群だ。 ・「働く」に対しても目標設定をし、目標は必ず言語化し、繰り返し見て、自分自身に刷り込んでいくこと。 ・「仕事とプライベートを完全分離し、生活のために稼ぐことを『働く』と定義すること」から「プライベートを含めて、他者に価値を与える(傍を楽にする)こと全てを『働く』と定義すること」へ ・「キャリアアップ」ではなく「ビジョンの追及」 ・「自分探し」ではなく「コミットメント(参画・貢献・自己投入)の連続による自己形成」 ・「金持ち父さん」ではなく「父親であることを楽しむ父さん」 仕事における立場が上がってたきたり、プライベートで結婚して、子どもができて、育てていたり、そういった要因もあるおかげで、再読しても染み入ったのだろう。 うまく時間を見つけ、自身のレベルアップとビジョンの可視化を行いつつ、他者に価値を与えながら、一石二鳥、三鳥を狙って広く楽になる仕組みを提供できるようになりたいと思った。
0投稿日: 2020.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ完全に私の言葉での要約だが、Work life balance ではなく、life as workを唱える本だ。life as labor ではない。そしてlife as action かもしれない。 食いぶちを稼ぐ働くだけでなく、家庭や地域などで働くことで、労働だけに忙殺されない国に変えていこうという話。労働に時間を取られなければ、自己実現や研鑽、子育ても人生の「働く」として取り組める。 駒崎氏はworkの言葉は使っておらず、「働く」を「傍(はた)を楽にする」ととらえ、働くことでは他者に貢献した他者を楽にすることを目指す。本には駒崎氏がNPOを立ち上げて死ぬほど働いていた状態から職場でもプライベートでも改革を進めていった実例が書かれている。これを参考に実践につなげられる。 ただ労働に絡め取られている人は、他者への貢献と考えるほど余裕がないと思う。だからworkと言ってみたが、workも労働に取り込まれているように感じる。そんなとき思い出したのがハンナ・アーレントの『人間の条件』。 アーレントは人間の条件をlabor, work, actionとした。actionでは多数の異なる他者と活動することで、個人が独自性を獲得する。駒崎氏の話はworkよりもactionの話だ。この本は失われたactionを取り戻す運動かもしれない。life as action. こちらのほうが、いま現実味のある表現だ。しっくりくる。
0投稿日: 2019.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ働き方改革が連日のようにニュースになる現在。 この25年間、日々ワーキングマザーとして疲労困憊し、悩んでいた。 この本で筆者が実現しようとしている社会。 こんな社会で働けたらどんなに良かったか。 次世代のためにできることをしようと強く励まされました。
0投稿日: 2019.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生そのものを働くとして捉えるということは、なるほどと思った。 Work as life ではなく、life as work。 響きだけ聞くと、働き尽くしの人生!? と考えられるかもしれないが、そうではない。 つまり、自分に関わる全ての他者に貢献することができる「働き方」ということだ。 それは職場の人だけではなく、友人、パートナー、家族。 多岐にわたって考えられる。 そのためには、自分のライフビジョン、あり方をどのように設定するかが重要だ。 自分自身を見つめ直す一冊になった。
0投稿日: 2019.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに一気読みした本。 働き方改革ではなく、革命。今の働き方改革が叫ばれるより前に書かれた本。 実体験をもとに書かれており、自分もやってみようと思えた。
0投稿日: 2019.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ”“何ていうか、人生そのものを『働く』として捉えるんだ”にシビレた。 他のワークライフバランス系書籍とは一線を画す内容。How ではなく Why に深くふかく切り込みながら、駒崎さん自身の思い・感情・行動が赤裸々に語られていて、読んでいる僕に強く響いてくる。 「やりたいけど、できないんですよねぇ」は、本心では「やりたくない」のだ。 自分のなかにある本気の「やりたい!」に気づき(再会し?)、誠実に向き合うことではじめて時間管理やライフハックの追求につながるにちがいない。 アドラー心理学を学び、原因論から目的論へと頭が切り替わってきたのも、この本との出逢いにつながった気がする。著者駒崎さんをはじめ、僕の日常にあるすべての人・こと・ものに感謝! <キーフレーズ> ・国がどうこうする話ではなく、僕たち一人ひとりが変化を起こさなければならない問題なのだ。いや、もっと正確に言うならば、僕たち一人ひとりが変化と「なる」ことが求められている問題なのだ。(p.16) #変化となる! ・「イメージしてみなさい。さっき君が言ったような働き方を。イメージして、それが実現した時の気持ちになってみるのです。(略)新しい自己イメージを持ちなさい。そのために自己対話をしなさい。望ましい自己イメージを描く、自己対話を。」(p.57-58) #研修後のルー・タイスさんの言葉 ★ジェンセンおやじは、仕事を楽しみ、一生懸命やりながらも、将来の自分のために勉強して、家族を愛し、家族のために時間や気持ちを使い、地域にも貢献していた (略) 僕はジェンセンおやじみたいな人生が送れたら良いなと感じていた。(p.64) #ルー・タイスさんのリーダーシップ研修で学んで帰国する直前、駒崎さんに「目的」が降りてきた瞬間! ・「イタい」けど自分のビジョンを設定する(p.73-) #駒崎さんの設定したライフビジョン。両親、姉弟、恋人・妻、友人、運動、学び、社員・仕事、時間・自己投資・プロセス の9項目。 #毎日眺めることが肝心! ・上流が未来だとしたら、時間は未来からこちらに向かって近づいてくるのだ。そして自分を通り過ぎて、それは過去になっていく。(p.88) ・仕事のスマート化(第三章全般) #会議のルール、社内メールルール(冒頭に「してほしいこと」と「期限」)、9時6時で働く(自分→マネージャー→現場) ・そういえばこの前会った人に、仕事の場で使う「レポート・トーク」と家庭で使う「ラポール(安心感)・トーク」は違う、って教わったぞ。() #発言の主は安藤哲也さん(p.198) ・好きなことをしている時の彼女の表情は、本当に綺麗だった。(p.130) #あー、これはオレも感じる。 ・「荻原さんの会社がそういうフェーズに来た時って、どんな課題が出てきましたか?」(p.147) #メンターに、こんな風に経験を聴くのはいいなぁ。(年齢、家族との関係、仕事の役割 etc) ・定期的な運動という投資は、「体」という生涯を通じて僕が乗るビークル(乗り物)の性能を上げた。(p.160) #素敵な表現! ★何ていうか、人生そのものを『働く』として捉えるんだ。『働くこと』と『そうじゃないこと』があるんじゃなくって、食いぶちを稼ぐことも、家族と生きることも、自分のために学ぶことも、全部ひっくるめて『働く』っていう風に考えたらどうか、っていうことなんだよ。(略) 会社という場所で働きつつ、自分を含めた社会のために働くんだ。そのために職場での『働く』もあれば、家庭での『働く』もあり、地域での『働く』もあるんだ。それぞれ楽しいんだ。それぞれで自己実現できるんだ。そういう風に『働く』スタイルを変えていく。そう、『働き方革命』だよ。(略) 違うんだ。みんなで戦わないとダメなんだ!(p.181) #内閣府会議の休憩中、高校時代の友人に電話で思いを語る駒崎さんのセリフ!これが働き方革命の原動力。 ・「働き方革命」に関するキーワード(p.192) #個人的に気になったワードを抜粋すると… #自己実現→「社会実現(あるべき社会像の実現)を通しての自己実現」 #市場価値→「私が社会に与えられる価値は?」 #年収1000万→「目指せありたい自分」 #ブランド企業に底上げしてもらっている自分→「自分の生き方にOKを出せる自分」 #家族サービス→「家族も、自分も楽しいイベントづくり」 #家事を手伝う→「自分の仕事としての家事」 <きっかけ> 代官山蔦屋書店、ビジネス書の棚にて発見。 最近のものかと思ったら 2009年発行。けれど、いまの自分が出逢うべくして出逢った一冊、という感じがする。”
0投稿日: 2019.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ若い人だが読み手を惹きつける文章を書く人だ。どこまで本当かはわからないが、主張していることは理論的だ。
0投稿日: 2019.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「一日の活動時間を決める → 打合せや人と会う時間を差し引く → 残った時間で”絶対に”しないといけない事柄を書き出す → 当日行うことを全力で行う」という方法が書かれている。 これが真実だよなぁ。欧米人はこれを実践しているんだよな。
0投稿日: 2019.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ駒崎さんは社会的意義のあることをやっていると思う。立派だと思う。しかし、これが「普通の人」に適用できるかといえばそうではない気がする。仕方ないけど。それなりの家庭のご出身でSFC出て起業して…。願うだけでかなったら世話ないよなーと。多くの人は思ったところで変えられないことの方が多い。ただこうした問題提起は素晴らしいし、変えられることはないか?と考えるきっかけにはいいと思う。
0投稿日: 2019.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ漫画を読んでるようにわかりやすくて面白い。物事を変えていくには、素直さと、恥ずかしさにもぶつかっていく度胸、が必要なのかなと思った。
0投稿日: 2019.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログどのような働き方が幸福なのか、就業現場での課題と実践が具体的に示されており、とても読みやすく共感できた。
0投稿日: 2018.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2009年刊。著者はNPO「フローレンス・プロジェクト」代表理事。 業務のスリム化、効率化を実現し、トップたる自身のみならず、従業員に関しても時短を実現させた著者の自叙伝的回顧録である。 勿論、非常に良いように書かれていて、試行錯誤や失敗が余り見受けられない。その意味で信憑性如何に疑義がないではない。また賃金の問題(殊に時短に伴う賃金下落)には触れられない。 もとより残業代込みで生活が支えられているのならば、それ自体は問題である上、本書で指摘する健康面(著者はジム通い)や、知的ブラッシュアップ(著者は執筆活動)。あるいは、妻ないしパートナーとの関係や子育てという観点で見るに、時短の齎すプライスレスの価値を否定することはできないだろう。本書はその意義を具体的に教えてくれるものだ。 重要な視点は、①使っている時間と業務内容の見える化、②権限委譲と配分、③直接の部下、就中、中間管理職の時短取組みの支援と実施(ここでも業務内容と時間の見える化が鍵か)如何である。 さらに、業務に集中するのための方法(特に電話による職務中断、いやこれは妨害に等しいので、いかに回避するか)の創出=電話を受けない集中タイムの採用/一定の在宅勤務の許容/集中するためのパーソナル引き篭もりの採用-ここでは近隣のカフェで。 といったあたりが、なるほど感を感じさせた件である。 まぁリーダーが時短を実現しようと本気になったことが大きいのだろうが…。そういう意味では、サービス残業が衒いもなく横行する会社ではとても導入は無理だし、高プロのような時短に逆行するような施策を嬉々として賛成・採用する会社じゃ無理であろうが…。
0投稿日: 2018.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事をする上でヒントとなることがあったと思う。 仕事以外のプライベートの部分も社会に貢献するための仕事、家庭に貢献するための仕事として捉えるというところが新鮮。
0投稿日: 2018.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2009年にすでに発行されていた本書が、もっと浸透していれば、2015年の電通過労死事件のような話は起こらなかったのではないだろうか。 特に興味を持ったのはライフビジョンとプレイングマネージャーの働き方改革。 どんな人生を生きたいか、自分にとって豊かな生き方は何か。 ちゃんと言葉にできるくらい具体化する。できないなら色々新しいことにチャレンジして、経験を積む。 プレイングマネージャーの一番の仕事は、部下の仕事ぶりを見て、躓きを解決し、より生産的にするのが役目。 目から鱗じゃないけど、一番の優先はそこなんだ…!そこでいいんだよね?!と感動した。 祖父祖母世代はお見合いかつ亭主関白が主。 親世代はバブルを経験して、いつかクラウンをキーワードにしたサラリーマン+専業主婦スタイルが多い。 20代30代には目指す家庭のモデルが限りなく少ないのではないかな。 しかも、不景気で男性も低賃金かつ長時間残業の中で、自分たちで探りながら新しいスタイルを産み出すのは大変だと思う。 けど今の働き方改革の流れは好ましい。 (ただ、役員達が部下にいい感じに改善してって丸投げするケースも少なくないのは残念。 そういう方たちこそ直近で親の介護問題にぶつかるだろうし、奥さまに熟年離婚されないように働き方を変える必要があると思う)
0投稿日: 2017.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書が世に出たのは2009年。まだ、電通事件も起きておらず、時短などは言われていたけれどもまだまだ夜中まで働く文化はある種よきものとして残っていたように思う。時を経て、2017年現在、自分が働く会社においても「働き方改革」ということで残業抑制の指示が出ている。それが「働き方革命」という本を手に取った理由である。 今までの日本人の働き方が、パートナーの働き方を制約するものであり、日本全体としても生産性を落としている理由ではないかとするのは理解できる。特に今後労働者人口比率がどんどん下がってくるにあたっては女性もこれまで以上に社会に出て働く機会が多くなるだろう。もっときちんと言うと男性と女性とで同じように働き、同じように家庭の中で役割をこなすことが当たり前になっていかないといけないのだろうと思う。 著者の駒崎さんは、障害児保育をサポートするNPO団体フローレンスの代表を務めるなど、その筋では有名な方らしい。本書の中にも描かれているように政府の様々な委員会にも呼ばれている。もともとは著者も学生時代にITベンチャーを起業し、無茶な働き方をしていたのだが、あるアメリカでのセミナーをきっかけにそれまでのやり方ではいけないと気付いたという。 実際に自分もそうなのだが、「忙しい自分」というのがセルフイメージの安定領域になってしまっていたことに気が付いたという。そのままではいけないという認識から、新しいセルフイメージを持つこと、ありたい自分を肯定的に想像すること、が大切だと気が付いたというのだ。 そもそも経営とはリソース配分をいかに行うのかということである。「自分の時間」という絶対的に有限のリソースの配分を考えることこそ第一にやる必要があることである。その時間を使って、よい会社にしようということから、よい社会にしようと言う考え方に変わっていこうというのがメッセージといえる。そこから「働き方革命」が始まる。 他にもいくつかのメッセージが含まれている。オープン化が進むこの時代においては、内よりも外を見ることが必要。短期よりも長期を見て行動する。何よりも他の組織、他の会社に行っても通用する「ポータブルスキル」を獲得することが大切。そのためにアウトプットだけでなくインプットを継続することが重要な行動規範になってくるだろう。 色々と考えるきっかけにはなった。変わるきっかけにはなるだろうか。
2投稿日: 2017.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本の内容や出版年度をよく把握せずに買ってしまったのが悪いが、残念ながら得るところは少なかった。ビジョンを持つことが大事だということはよくわかった。
0投稿日: 2017.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「自伝的小説」風。読み終わっても再読だったと気づかなかったのは、環境や心境が7年前に読んだ当時とは違うからだと思う。日本は今ようやく変わろうとしている。
0投稿日: 2017.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆きっかけ 『ルポ 父親たちの葛藤 仕事と家庭の両立は夢なのか』では「国の制度は先に変わらないので、自分たちから変わるべき」とありましたので、自分の変え方を書いた本を読みました。 ◆概要 ずっとバリバリ仕事をしていた方が、ライフワーク・バランスを見直し定時上がりをすることになった自伝書かつ指南書です。 読んで損はないと思いますが、自分にはあまり大きな影響はありませんでした。なにせ、もともと時短勤務で定時上がりですし、作業記録や業務効率化は実施済み。どちらかといえば時間外業務が多い夫向けですね。 それから文章が情緒的で冗長で自分にはなじみませんでした。たとえば「……と決心をしながら、窓の外の夕焼けを眺めた。いつもよりひときわ美しく感じた。」というような文章がとても多いです。 じゃあ勧めるなって?lol ◆引用と感想 >人口減少とは、今まで11人でやっていたサッカーチームを9人にして他の国と戦ってくれということ この例えはうまいと思いました。 >政府が「カエル・ジャパン・プロジェクト」なんてやっているが認知度が低い 私も初耳です。 >裁量権がない仕事はつまらないので、自分(夫である著者)の家事に裁量権をもらった それで著者が食器洗い乾燥機を買ってしまうのはいかがなものかと思いましたけれどね(笑)。 私は家事分担よりも家事シェア派です。気づいた人や時間のある人がゴミ出し、洗い物、お風呂掃除といったことをやるのが理想です。現実はゴミ出しだけ旦ry そういえば独身バリバリの7年前はこんな本を高評価していました。 ・『プロの残業術。 一流のビジネスマンは、時間外にいったい何をしているのか?』 今でも内容には賛同しますが、有用度はほぼゼロです。私が2人いたら、兼業主婦ではなくて、独身キャリアウーマンと専業主婦の両方の人生を歩みたい。 ー↓修正前↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ライフワークバランスのこと。半々にこなすのではなくて、どちらも頑張るから相乗効果が見込め、人生が豊かになるという話。そのための小手先論など。 ちょっと文章が情緒的で冗長。「…と決心をしながら、窓の外の夕焼けを眺めた。いつもよりひときわ美しく感じた」(引用ではなくイメージです)といった文章が多く、その部分は個人的に馴染まなかった。 読んで損はないと思うけど、自分にはあまり大きな影響はなかった。もともと時短勤務で定時上がり、作業記録や効率化はやってるし、どちらかといえば夫向けかも。 --- メモ ・本より ★私見 --- ・人口減少とは、今まで11人でやっていたサッカーチームを9人にして他の国と戦ってくれ、と同じ ・日本の時間当たりの生産性は先進国7ヶ国中ビリ ★政府のカエル・ジャパン・プロジェクトなんて知らないw ・裁量権がない仕事はつまらない→夫の家事に裁量権を持たす ★それで著者(夫)が食器洗い乾燥機を買ったのはどうかと思うけどね。たしかに合理的だけど、モヤモヤする ★家事分担より家事シェアのが理想かな。実家はそうだった。気づいた人、時間のある人が洗い物とかやる --- ・日本がどうするかではなく、個々人がどうするかの本 ・今までバリバリやってた人がライフワーク・バランスを見直すことになった自伝書
0投稿日: 2016.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ働き方を効率化することで、プライベートの時間を確保し、地域や家族に貢献しようというのが趣旨。 その働き方の効率化については参考になるところが多く、弊社内でも取り入れている。以下参考になった点を。 ・スリムタイマーで仕事時間を計測 ・会議のルールを作る(1時間半以内、など) ・属人化を排し、マニュアル化へ ・メールの効率化 ・電話会議の活用 ・「頑張るタイム」という集中して作業に取り組む時間の設定 ・自宅作業の導入
0投稿日: 2016.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前の著者の働き方は日本企業の多くの方の固定観念にある働くというスタイルなので、もちろん以前の私もそうだった。本当に働いているのか、目先のタスクを片付けることで忙しくして満足した気になっていて、本当にしなくてはいけない仕事から逃げていないか、耳がいたい人も多いのでは。
0投稿日: 2016.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「働く」という言葉の再定義によって、オンオフの二元論ではないワークライフバランス論を展開していて新鮮だった。新書でありながら非常に読みやすい口語体で書かれており、考えがよく伝わった。それに笑えた。
0投稿日: 2016.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ7年前に書かれたということは、自分が遅れているのか。。今まさに自分が直面している問題とこうありたいというぼんやり思っていることを言語化してある。 独身の時に読みたいと思っていた本だったが、子育てと仕事の両立がうまくいっていないと感じている今読めたことには理由があると思えてならない。 私も、働き方革命を起こす。 まずはライブビジョンを描く!
0投稿日: 2016.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「働く」という概念を覆す本。ライフ・ビジョンを描いて、仕事、家庭、地域、趣味など自分の24時間をどう使うか考えるヒントをくれる。 タイムログをつける、家事のマネジメントはすぐにやってみた。
0投稿日: 2016.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読もう読もうと思いながら、こんなに遅ればせながらになってしまった。 さくっと読めるんだから、もっと速く読めばよかった! だけど、自分の中で、「働き方」が大きなテーマになっている今、出会えて良かった1冊。 「だらだら生産性の無い残業はイケてない」という感覚が、少しでも早く浸透することを切実に願う。 願ってるだけじゃ変わらないから、早速出来ることから、「働き方革命」を実行!
0投稿日: 2015.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ育休復帰後の仕事と生活の両立が不安で読みました。 予想される状況の打開策が少し見えた気がします。ヒントを得たことを、さっそく、いまの生活で試してみようと思います。アファメーションとか、スリムタイマーとか!わくわく。
0投稿日: 2015.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ所属チームと共有したい内容がわんさか。 メールのタイトルについて 日報について 働くの概念について 実践あるのみ!
0投稿日: 2015.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログCSPスタッフやマネージャーにこそ読ませたい。1日もあれば読了可能。全200頁も、実質5時間足らずで読み終えた。共感度100%だ。シニア世代にも、若い世代にもお薦めの1冊
0投稿日: 2015.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
どんな仕事がしたいかとか、どんな事業を生み出して、自分の組織をどういう風にしていこう、という仕事のビジョンは描き続けてきたけれども、自分がどういう人生を送りたいか、つまりライフビジョンを描いたことは全然なかった。 飯を食うための「働く」があって、人生の何らかの価値を実現するための「働く」もある。もちろんそれらが重なってもよくて、飯を食う仕事を通して素晴らしい価値も実現できるだろう。いずれにせよ僕たちは同時にいくつもの価値を実現できるのだ。これらのお金が対価ではない仕事は「ジョブ」ではないし「レイバー」でもないのだけれども、でも何か大いなる価値を次元するため御真剣な行為は、「働く」と言っていい気がする。そう、誰かが言っていた。日本語の「働く」という言葉は傍(はた)を楽(らく)にさせることからきている、と。 プリントアウトは止めておこう。出来れば自分だけが見るような方法がいい。タイスさんも「他人は簡単にダメだしする。彼らは悪気なくドリームキラー(夢を殺す人)になってしまうから、他人に言わなくてもいい。自分にだけいつも言え」って言ってたし。 僕も「働く」を拡張し、本業の食いぶち稼ぎ(ペイワーク)も含めてライフビジョンの追求そのものを「働く」とした。そしてそれは間違いなく(本業の)仕事にも良いリターンを返してくれた。 仕事だけに専門特化「しない」ことが、職場において働くことだけを「働く」としないことが、逆に仕事を充実させる。 僕は知ったのだった。知らない人や知らないこと、知らない物語、発見と感動と冒険は、遠くに行く個おtで得られるのではなく、向こうから訪ねてくるのだ。僕たちが心のチューニングを合わせることで、向こうから訪れる。チューニングにかかるほんの少しの時間を確保すれば。働くことを狭く限定せず、自分たちのあるべき人生の姿を形作る作業全体を「働く」と定義すれば。 違う、そういうニュアンスじゃないんだ。自分のために、自己中心的に仕事の手を抜いて、自分のことに時間使おう、っていう話じゃないんだ。なんていうか、人生そのものを『働く』として捉えるんだ。『働くこと』と『そうじゃないこと』があるんじゃなくって、食いぶちを稼ぐことも、家族と生きることも、自分のために学ぶことも、全部ひっくるめて『働く』ッテいう風に考えたらどうか、っていうことなんだよ。『働く』を『他社と自分のために価値を生み出すこと』とするんだ。
0投稿日: 2015.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ・日本だとボランティア団体に毛の生えたような認識しかされていないNPOだが、欧米だと企業に負けず劣らずの存在として社会のインフラを担っている。 ・日本のNPOに対する認識を変えてやろう ・自己イメージが、私たちの行動を規定する ・仕事をしながらも、地域・家族・自分の未来に貢献する ・目標を必ず言語化し、繰り返し見て、自分自身に刷り込む ・人生そのものを働くとして捉える。 働く=他者と自分のために価値を生み出すこと(幸せにする、負担を減らす、喜ばせる、感動させる、やさしい気持ちになってもらう) →地域で働く、職場で働く、家庭でも働く。 ・長時間がむしゃら労働から決められた時間で成果を出すスマートワークへ ・自分のための仕事から自分を含めた社会のための仕事へ
0投稿日: 2015.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログライフワークバランスという言葉はよく聞くようになりましたが、この概念を具体的な事例を交えながら上手く説明した一冊だと思います。お勧め! 働くというと「会社に行って一生懸命働いて、給料をもらう」この一連の流れを差すと思いがちだが、もっと解釈を大きく広げてみる。周りの人がより良く、楽しく人生を生きられるように貢献することを、働くと捉えなおしてみる。そもそも働くとは傍を楽にするが語源とか。食い扶持を稼ぐ働くは当然必要だが、地域社会への貢献、家族への貢献、自分自身への投資、等々、傍を楽にする取り組みはいくらでもある。自分自身のライフビジョンをしっかりと打ち立て、そのビジョンの達成の為に、有限の時間を主体的にどう割り付けるかを考えるべき。 サイボーグのように食い扶持の仕事にのめり込むという事が、却って自分の成長を留めてしまうことがあるという指摘は同感。 マネージャーがしっかりマネージメント出来ているかの1つの指標は残業時間に表れる。良いマネージャーとは、各メンバーの能力を鑑みながら、限られた時間が最大限生かせるようにタスクを割振る能力。
0投稿日: 2015.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者の体験談を交えて働き方を変えていく方法を書いている。ポジティブな自己対話を繰り返すことで自己イメージを決定。仕事の仕方の具体的な方法も書いてある。
0投稿日: 2015.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ2015.01.17読了 アファーメーション こぼれていく時間の砂を慈しむように。 タイスのおっさん 実現のためにはまず、ビジョンを設定せよ 「目標は必ず言語化し、繰り返し見て、自分自身に刷り込んでいきなさい。」 「その時に湧き上がる感情をリアルに書け」 「具体的にイメージできるような書き方に」 毎日眺めるために、自分自身にメールが来るように設定 「働き方革命」によって仕事もプライベートも統合(インテグレート)して、それを一つのプロジェクトとして捉えることで、日常の日々そのものが歯ごたえのある、やりがいのある毎日に変わっていくのではないだろうか? 計画を立てて、それを実行することの重要性。 自分自身の仕事時間の計測により 仕事のスマート化 何に時間が掛かっているか?認識して変える 会社の規則、マニュアル。作り方等の参考。 会議、メール、電話会議の活用等 最後のまとめを抜粋 働き方革命のコンセプト 働き方革命のキーワード 成功ではなく成長 亭主関白ではなくパートナーシップ 家族を養うではなく共同運営 家族サービスではなく家族も自分も楽しいイベントづくり 家事を手伝うではなく自分の仕事としての家事 働き方革命の第一歩 ライフビジョンを描きだし、スマートワーク化へのモチベーションを惹起(維持)する。 スリープタイマー 手帳術 働き方革命による、広い意味の働く事例 地域の祭りに参加 夫婦や家庭のビジョンをつくり、その達成を目指す 自らの周りに快適な世界を実現する行為、すなわち家事を行う
0投稿日: 2015.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ産後の仕事復帰をして8ヶ月。働き方を改めて見直す時期に来ており、手に取りました。 ワーカホリックだった著者がそれに気づき少しずつ改善してゆく様子は、リアル且つすぐに真似できそうなことも沢山ありました。それを実践できるかは、やはり自分のスキルにかかっているなぁと感じました。やりたいけど、できない…頑張ってるのに、早く帰れない…改めてこれは自分のスキル不足だなぁと突きつけられました。 今年は少しでも働き方革命、出来たらと思いました。
0投稿日: 2015.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、ワークライフバランスやこれからのあるべき働き方に興味があって読んだ。 バリバリに働いていた人が、どう長時間労働をやめたか、それを意識だけではなく効率的な働き方といったノウハウも含めてまとめている。それだけではなく、会社の仕事だけが働くことではない、地域のために働くこと、家庭のために働くこと、家族のために働くこと、自分のために働くこと、それら全てを行って生活に潤いをあたえるべきであるという。その様子が主観的に細かく書かれているため、リアリテイがあった。 そして、自分だけが働き方を変えるのではない。周りの人をどう変えるか。マネジメント論でもある。
0投稿日: 2015.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「はたらく」の新定義を、また、残業しない仕事の仕方で得られる効果効能を実体験に基づきながら、親近感の沸く語り草でされているので、べき論で固められた自己啓発とは違って新鮮でした。 ただ、残業削減の風が社内で吹き荒れているなか、どうしたらいいんだろうと悩んでいる時に手にしたので、具体的な方法が得られるのかと期待していたのですが、著者が代表としての立場からの働き方や視点の変化を主に述べられていたので、参考にできる点は少ないのが事実でした。 しかし、勇気やパワーを貰えるドキュメンタリーとしては読んで損はないと思います。
0投稿日: 2015.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログやめてみることの大切さを学んだ。大量の資料作り、長い何も決まらない会議、残業など、回りにはやめてみても困らないことが多い。それに気づいた。 こういう考えが日本に広まることを期待しているし、行動していきたい。
0投稿日: 2014.08.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ働き方革命。 制度を作り、それが知識として浸透し、更に実践者が出始め…もちろん環境を整えることは先決だけど、それと同じくらい大切なのは、トップや制度を作る人間がまずは実践して、しっかりアナウンスするということ。 実利用者からのボトムアップでは、下手をすると権利の主張と職場の不公平感を冗長させることになりがち。 その点、経営者である駒崎さん自身が、社員に先んじて革命を行ったことが素晴らしい。 社会に貢献すること、人に喜んでもらうことも自分の仕事のひとつ。 つい何事もゼロサムで捉えがちだけど、その考え方をまずは変えていこう。
0投稿日: 2014.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ大好きな駒崎さんの本。 働き方を見直すに至った背景が描かれており、 とても共感できる内容となっている。
0投稿日: 2014.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局、働き方もどんな人生を送るかも、自分の選択の結果だということにつきるってことなんでしょう。それをどれだけ、具体的に、イメージできるかが、分かれ目ってことかも。 あっという間に、読んでしまいました。
0投稿日: 2014.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりに一気読みの勢いで楽しく読み切った本です。 働くことの概念を変えること、そのための効率化の実例、著者の周りで起きた変化、3つ揃ってお題目でないストーリーとして成り立っています。時間がない、忙しいが口癖の方はぜひ一読をお勧めします。
0投稿日: 2014.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ嫁のオススメということで読み始め、1日で一気に読んだ。 筆者の主張には非常に共感。二児の父で共働きの自分としても真似したい。 その一方、現在の勤め先でこれを浸透させるのは骨が折れると感じるが、草の根で徐々に革命を起こすしかないのだろうか。筆者のように組織のトップが動くというのが最も効率的だが、そうでない一労働者としては、社畜前提の企業を選ばないという行動で革命に参加するのが現実的な闘い方なのかとも思う。 それにしても筆者の駒崎さんは頭のイイ人なんだなと随所で感じる一冊でした。
0投稿日: 2014.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログどんな優れた経営者でも 今の成功は、数多くの苦労と苦悩の末に成り立っているんだ と考えさせられました。 朝から夜まで働く、これが果たして 正しいのか。 駒沢さんの本はいつも面白く、これも3冊目くらい。 何が喜ばれるのか、何に対して働くのか、をいつも 考えるきっかけを与えてくれます。 6時に帰社、できるものならやってみたい。 でも強制的に6時以降仕事ができなくすると、 なんだかんだ本当に必要な仕事しかしなくなるので、 効率はあがるんだとか。それに1人で抱え込まずに 人に振る事をおぼえる、と。 会社の為に頑張って、彼女の為に頑張って、 妻の為に頑張って、子供の為に・家族のために・地域の為に頑張る。 会社人間でもなく、家庭人間でもなく、 全ての場面において頑張れる存在、望んでいきたいです。
0投稿日: 2014.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ序章 なぜこのような本を書かざるを得なくなったのか 第1章 自分が働くことで、誰かを壊している? (1)働きマンな自分が好き (2)会社のオーナーは自分だが、会社が自分のオーナーに (3)愛する人の可能性を殺す働き方 第2章 自分のライフビジョンて、何だろう? (1)アメリカ人グル(導師)との出会い (2)目標とするライフビジョンを描く 第3章 「働き方革命」の起点 (1)自分の手持ち時間を見直す (2)仕事時間をダイエットし、生産性を上げる 第4章 「働き方革命」でたくさんの「働く」を持つ (1)パートナーに対する「働く」に時間投資 (2)家族や学びに対する「働く」時間投資 第5章 「働き方革命」が見せてくれた世界 (1)「働く」とは、あるべき人生を形作ること (2)「働き方革命」で職場が変わる 終章 「働き方」を革命し、日本を変えよう
0投稿日: 2014.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ病児保育のフローレンス駒崎さんの著書。革命済の私としては余り参考にならないのだが、周囲の人には是非読んでもらい残業ゼロを達成してもらいたい。仕事って定時の7-8割でコントロールしないとピーク時に対応出来ないよね。うん。
0投稿日: 2014.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480064868/ , http://www.komazaki.net , http://komazaki.seesaa.net , http://www.florence.or.jp
0投稿日: 2014.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログフォロー先なので読んでみた。NPOを経営する社会起業家が自己啓発系セミナーによりワークライフバランスに目覚める経緯という満貫くらいなアレだが、その怪しさも十分認識した上でであり実現可能性もわりと考慮されてるし使えうるかなあ、と。あと、進研ゼミ的物語としても十分面白かった。
0投稿日: 2014.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間は自己認識の方へと導かれて行く。 (物覚えの例:「私はもの覚えが悪い」なんて思っていると物事を意識的・無意識的に覚えようとしなくなる。=>習慣化しだんだん物覚えが悪くなっていってしまう。) ナルホドその通りだと感動した。 大切なのは、ゴールイメージを持つことと、その言語化。 そして働き方を「会社と自分」だけでなくワークライフバランスとして捉える。 こういう風に書くとなんか宗教的に感じじるかもしれないか、文体は分かりやすくエネルギッシュだった。児玉教仁「パンツを脱ぐ勇気」と同じ香りを感じた。 働き始めたこのタイミングで読めてよかった。 紹介してくれたK君に感謝。 追記:マスターキートンのように生きるという一言も琴線に触れた。そう有りたい。
0投稿日: 2014.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
長時間労働もしてきて、30代になって就職活動も 困難になってしまう経験をして、私も「働くこと」に 思うことがある。 「働き方」の価値観というのが変わりつつあるのは 都会へ行くほど感じる。 派遣労働問題、介護問題、女性の社会進出、 子育てと仕事との両立、男性の家庭への参加、 付加価値の商品開発、企業が多様性を受け入れること…。 現代社会の中で変わらざるを得ない気がする。 経済成長の時代の成功体験が邪魔をして、新しい価値観へ 移行できない現役世代も多い。 著者は、若手経営者で、残業に追われる毎日。 しかし、ある経験から自分の働き方が、危険なことに気づく。 トップダウンで長時間労働を止めさせ、 効率化へと企業組織を変えていき、 持ち前の素直な心で、自分の生活の価値感も かえっていった経緯が綴られている。 結果、見事に成果を上げていく。 この人は、本当に素直な人で、良いということが理解できると 抜群の実行力を持っている。 この前向きな行動力がとてもうらやましい。 最後に、心に残ったキーワードは… ■働くことの定義をプライベートも含めて、他者に価値を 与えることすべてとして考える。 ■自己イメージが私たちの行動を規定する。 ■「家族を養う」ではなく「共同経営」
0投稿日: 2014.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の働き方に革命を起こすまでのきっかけやプロセスがありのまま丁寧に書かれていて、働き方を変えようというメッセージにも心を動かされた。
0投稿日: 2013.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ若いにもかかわらず、流石は経営者。立派なビジョンと行動力があります。また仕事の効率化を実践する場面で立て続けに難題をこなして行く様が、まるで有川浩の小説のようで見事でした。いろいろなアイデアが紹介されていましたが、スリムタイマーが気になりました。ちょっと試してみようかな。
0投稿日: 2013.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ【HIKO】 理想ですが、ひとりひとりが意識を持って行動することで社会が良い方向に変わっていければいいなと思います。 (TAKE) 優秀でワーカホリックな青年実業家が、ちょっと成長して「地域」「家族」等とのつながりを通じて価値観が変わったことを記した本。彼個人という縦断的な見方では「働き方革命」だったのでしょうが、社会一般(いや、私らの業種特有かもしれないが)という横断的な比較でみれば「当たり前なこと」という感じもしました。それでも、現実の社会には、「働き方革命」というタイトルが成立してしまうほどの「キビシイ現実」があるんでしょうね。
0投稿日: 2013.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっとずつ実践するぜ。いろんな人に読んで欲しいけど、まずは会社同期におススメします(業績不振なので)
0投稿日: 2013.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ普通に面白かった。interestingというよりfunnyの意味で。 3時間くらいでパッと読めてしまう上に、業務効率化の具体的な方法が分かりやすく書いてあるので普通に役立つ。
0投稿日: 2013.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ夏の読書10冊目。 いろいろなところでバラバラしていたぼくの生き方に必要なパーツをつなげてくれました。ステイトメントをなぜ作成するのか、働くことの意味を広げるとはどういうことなのか‥ やってきたことをつなげてくれた一冊。出会えたことに感謝しています。
0投稿日: 2013.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ社会を変える、なんて大きすぎて自分には何もできないのではと感じていた。それでも、自分が理想の生活を実現し、親しい人に、家族に、地域の人にその姿を見せ、身近なとこらから変えていく、それが大切なんだなぁって思った。周囲とは違うことしてみる、変革を起こすってかなりのエネルギーがいることだけれど、何だかワクワクすることだなって。
0投稿日: 2013.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログプライベートを含めて他者に価値を与えること全てを『働く』と定義する 家族を養う→共同運営 家事も、社会貢献も「働く」と考える 「ワークライフバランス」や「働く」のイメージを変える一冊。 私自身もこういった働き方を目指しているものの 「働く」という言葉を使わない、向かない、意味が違うものと感じていた。 それは「生き方」なんて言葉だったりしたが、それが「働く」おかしくないと感じた。
0投稿日: 2013.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者特有の語り口(書き方)で、平易ながらも熱い想いが伝わって来て、一気に読めてしまう。 世の中にかなり閉塞感がある事を国としても認識している事、しかしその打開策は、今までの経済発展の成功しか知らない国からは出てこない現実が、まずは語られる。 なので、我々、これからの社会を担う世代に対し、一人一人が変わり、動いて行く必要があるという事、そのために参考なりそうな方法が語られている。 そう、少しずつでもいいから、変わっていこうと思わせてくれる筆者の語り口が心地いいです。
0投稿日: 2013.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想:NPO法人フローレンス代表駒崎さんの著書。前々から読みたかったのだが、ブックオフでやっと見つけられた。 物凄い本。読んだ後の頭をガツンとやられた感が物凄い。 学ぶべき点、吸収すべき点が溢れているが、特に重要だった学びを2点。 ①自己イメージ=自分の行動を規定 前半部分で出てきたアメリカでの研修の中で。 人はそれぞれ自己イメージがあって、それによって行動を規定される。なぜか。その自己イメージの安定領域から出るのは居心地が悪いから。 高級レストランに合う自己イメージを持っていなければ高級レストランで食事するのは苦になる。 ただし逆説的に、ポジティブに考えると、高級レストランに合う自己イメージを描ければ全く苦にならない。 ということは、自己実現や夢で置き換えて考えるなら、なりたい姿や成し遂げたいことを自己イメージで描ければ、それらは叶えることができるということ。 なぜなら自己イメージによって行動は規定されるのだから。理想の自己イメージが描ければ、自然とその理想に合う行動をするようになり、一歩ずつ理想に近づいていく。 では自己イメージをどのように根付かせるか。それはイメージして、言葉にしてとにかく反復して繰り返す。 その具体的な方法として、本の中で挙げられているのが、毎日メールを自分に送ること。著者は自分の理想の自己イメージが書かれたメールが自動的に自分に送られてくるようにした。これは早速自分でもやってみようと思う。 一言でまとめるなら、理想の自己イメージを描き、反復して自分に植え付けられれば、「イメージ=現実」になるということ。できない理由とか恥ずかしいとかは抜きにして、素直に自分がなりたい姿を描くこと。 ②未知との出会い=向こうから訪れるもの。訪れてきたときに受け入れる心の余裕を持つこと(働く=他者に貢献すること) 本の後半部分。著者が「働き方革命」を実践し、仕事だけの毎日から解放された後に感じたこと。 世界は広い。自分が知らないことはいくらでもある。著書いわく、「無数の世界がミルフィーユのようにいくつも折り重なり、関わり合っている」がこの世界。 知らない世界は旅行などで遠くに行くことで出会えるもの。それは確かにそうなんだけれども、わざわざ遠くに行かなくても実は普段の日々の中で気づいていないだけで、自分が知らないことはいくらでもある。 ではなぜ気づけなかったか。それは毎日日々の仕事に追われていたから。存在しているけど、自分では「見えていない世界」があった。そのものたちは気づかれるようにシグナルを出していたのに。 そもそも毎日の仕事に追われるのはなぜか。それは「働く」の定義が誤っているから。「働く=お金をもらえる仕事のみ」という感覚があるが、著者はその既成概念をぶち壊す。 すなわち、「働く=他者への貢献」。お金をもらえる会社での仕事だけでなく、家族や友人、地域を楽にすることも「働く」ことの一部である。そうしたパラダイム転換があって、初めて会社での働き方を見直すようになり、それができれば未知を迎え入れる心の余裕が生まれ、人生が豊かなものになっていくのでは。 このような重要な学びが書かれているが、それらを支えているのが何といっても「読みやすさ」。書き手からしてみれば、本というものは自分の考えを伝えるツールであり、伝えたい何かがあって、本を書いている。でも自分の伝えたいことを文章化して、会ったこともない人に伝えるのは難しい。数値化するなら、伝えたいことが70%伝わればいい方ではないだろうか。でも駒崎さんの本は、読んだ後に自分の脳が受ける刺激の量を考えたら、100%かそれ以上のものが伝わってくる。例えもわかりやすくて秀逸だし、言葉選びのセンスも絶妙。たまにホッとするようなおふざけのくだりがあるから、真面目に書いてる部分が際立つ。 個人的に2013年に読んだ本の中でナンバーワン。 時期:2013/6/17〜22 評価:☆☆☆☆☆
0投稿日: 2013.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ家事やプライベートの活動も「働く」と捉え、人生を充実させる生き方を提案する。著者の経験談が豊富に語られているのでイメージしやすいため、大いに参考になる。 確かにこの「働き方」が浸透すれば、日本は変わるだろうと思わせる。それが自分たち一人ひとりの行動にかかっているというのは、とてもわくわくすることだ。 自分も目標とするライフビジョンを描き、その実現に向けて努力していきたい。
0投稿日: 2013.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったです。 駒崎さんは、文章も上手く、構成も面白い。 引き込まれてどんどん読みたくなる新書でした。 仕事の困難を克服するように、生活すべてが働くことで、より良くする工夫にやりがいを感じることって素敵だと思いました。
0投稿日: 2013.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログワークライフバランス、というとぼんやりしたイメージになってしまうが、具体的にどのような目標設定をして、どう実践していくか。著者の経験を交えて考えがよく伝わってきた。優等生的な感はあるが、今のこの世代の人達にはぜひ実践してもらいたい。問題は40代以上の世代。今更、働き方を変えるなんて!とても試練になるに違いないだろう。しかし、変えなければ、不幸な老後に突入することはあきらかである。気づいて変えたもの勝ちだな。
0投稿日: 2013.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ1読む目的 2この本に対する問い 3サマリ 4感想 1目的 自分のグループの働き方を変革するヒントを得ること 2問い 働き方革命を推進する強い動機付けとは?具体的な施策とは? 3サマリ ①日本では今後、労働人口が減る(2030年には現在の84%になる) ②減るので、政府は対策として全員参画社会(主婦シニアが働く社会)を作りたいと考えている。 ③その障壁になるのが、子育てをしながら働くことができないこと。夫の帰りが遅いこと、そもそも長時間労働が標準となっていること。 ④だから働き方を変える必要がある。労働時間を減らし、成果を上げる必要がある。 ⑤働き方革命の流れ:ビジョンを立てる→業務効率化を行い早く帰る→ビジョンを実現する施策を行う ⑥具体的な施策:可視化(slimtimer)、属人的な仕事をマニュアル化、集中力担保のため在宅ワーク、メールのフォーマット化 ⑦日本は課題先進国である。つまり課題解決を海外に輸出できる。 4感想 「働き方を変える」ことは日本にとって極めて重要なアジェンダである。駒崎さんが働き方を変えられたのは、自分でビジョンを描き自分がやることを決めて継続したからで、国策でもなんでもない。働き方を変えるのは自分で、人に影響を与えられるのも実際にそれを行っている人だけだ。 ======= 2013年に記入↓ 仕事の属人化を回避することで、自分の時間を確保できる。多様なインプットによって仕事のアウトプットを創造的にする。 労働人口の現象、大量生産の時代から知的生産性が求められる時代に変わったこと、これらから必要とされる考え方、らしい。
0投稿日: 2013.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログフローレンス代表駒崎くんがどんな働き方をしていて、いかにそこに至ったか。 また、「働き方」の意識が、あり方が社会にどれだけ影響を与えるか。 社会を変える、とか、働き方の意識を変えるとか、ともすれば「意識高い系」いうか、こっぱずかしいところもあったりするのだけれど(駒崎さんも実際恥ずかしがったりしている。でもそれによって身近に感じられるというか、自分も、と思える)。 非常にマジメで、でも近くに感じられる、という本だった。
0投稿日: 2013.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ2013年5冊目。 ずっと読んでみたかった、NPO法人フローレンスの駒崎弘樹さんの著書。 捉え方によって、ワークライフバランスの話にもあるし、日本社会の労働問題の話にもなるし、組織の経営者としての話にもなりうる。 アメリカでの研修プログラムに参加した後の、駒崎さんの様々な気づき、考え、行動の流れは、すごく心に響くものだった。また、とてつもなく賢い方なのだろうなと改めて思った。 僕自身、春から良い働き方をできるように頑張りたいところ。
0投稿日: 2013.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ職場で働く、家庭で働く、地域で働く今生きている中でそれぞれの場で貢献し、またそれを楽しんでいる。自分もそうなっていたいと思わせてくれました。
0投稿日: 2013.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「働く」ということを『プライベートを含めて、他者に価値を与える事(傍を楽にする)すべて』と定義して、駒崎さんの人生から考え直す一冊。 自分のための仕事から、自分を含めた社会のための仕事としたうえで、「やりたいことがない」から「やりたいことを創造する」ことを基調としている。 働く経験がないとされる学生ももしかしたら、働くことの一部を実践しているかもしれないと感じた。 1年生から就職活動を終えた4年生までおススメできる。すぐ読める一冊。
0投稿日: 2012.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログはたらくとは、傍を楽にしていくこと。 自分や愛する人を苦しめる働き方ではなく、幸せにする働き方とは何か 実際の経験に基づいた試行錯誤が書かれており 筆者の「働き方」に関する当事者研究本ともいえるかも。 これを鵜呑みにするのではなく、自分だったらどう実現できるか考えるのがいいのかもね
0投稿日: 2012.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で借りて読んだ。社会全般のことというよりは、作者の働き方が、どういう風に変わっていったか、というお話。 読み物としては面白かったけど、自己啓発本として読んだ方が良かったかも。
0投稿日: 2012.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログポジティブな自己対話をすることによって、ポジティブな自分イメージを潜在意識に形成できる。人は自己イメージと現実が異なる場合に認知的不協和になってしまう。 望ましい自己イメージを反復によって書き込みを行う。
1投稿日: 2012.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ現実的でまっとうなライフハック本だと思う。どう働くかってことを常に考えないとマズイなー。スリムタイマーはすぐにでも真似してみたい。
0投稿日: 2012.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ印象にのこったところ ・自己イメージが、私たちの行動を規定する。 ・社会実現を通して自己実現する。 ・私が社会に与えられる価値を考える。 ・日本は課題解決手法の輸出国。
0投稿日: 2012.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「働く」=傍を楽にさせると共に、自らも成長していく。 素晴らしい言葉だっと思った。 この本を読んで、自分に足りないのは、夢や目標を具体的にしていくということ。 著者は徹底的にやり抜いている。 そのプロセスを面倒くさがらずにやることが今の私の課題だと思った。
0投稿日: 2012.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログマネージメント論と、モチベーションコントロールのノウハウに関するストーリーを、一冊にまとめた感じですね。 バリバリのNPO代表の方の手記です。 シェア読書会にて借りた本です。 共感するエッセンス多数、過去に別書で読んだ思い当たるテクニックも多数。 悩ましい日本の「生産効率」の悪さ(質の方が特に)に焦点を当てたストーリーに読めましたが、ほとんどが既存のルールに足を引っ張られて、浅い改善しかできなかったりして。 その辺も悩ましい。 いよいよ会社組織の一般的な悩みは、日本の国家としての悩みそのものな感じがしますね。 結局本書では、組織のTOP・責任者クラスであれば多少改善できるネタはありましたが、なかなかおいそれとできるものじゃなさそうですな。 紆余曲折を味わって、組織ごとになんとかするしかない、苦しい現状を感じずにはいられませんでした…。
1投稿日: 2012.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事や家庭、プライベートなど、それぞれをどう両立させ、バランスを取るのか。 時間や気力などをどう使って、生活を充実させていくのか。 それらについて考えるきっかけとなりました。 仕事とは何か、読者にそう問いかけてくるようでした。
1投稿日: 2012.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の「僕が姪にプレゼントしてあげたい社会」に共感! はたらく(傍を楽にする)場面は、仕事だけで無く、家族・家事・地域・PTAなど、人生の中で自分が接するもの全てなんですね。自分がどんな事で傍を楽に(他者に価値を与える事が)出来るかと言う観点で考えて行こうと思います。
0投稿日: 2012.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者のように我武者羅に、病になるほどまでに働いた経験がないため、逆に本著で筆者が気づいたことを当たり前のように感じていた。 しかし、今後働くことになったら、この本を読みなおすことで新しい発見が必ずあるだろうと思う。 なので、就職してから再読するように!!!
0投稿日: 2012.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログネット上でも、駒崎氏の名前はよくみかけるし、在学中からITベンチャーを立ち上げていたりと、経営者としてとてもすごい方なのかと思い読んで見たら、少し期待はずれ。著者自身のセルフイメージ等には、特にカリスマ性は感じなかった。 しかし、自分のビジョンを、毎日自動でメールで送られてくる、というくだりは少しおもしろかった。 働き方革命とはかなり誇張ですが、働き方を変えるヒントにはなると思います。
0投稿日: 2012.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
はじめの「これまでの状況」等はじぶんも同じ状況で、さてどう革命していくか?と読み進めたのですが、どうもウチの職種では革命難しそう・・理想は賛同するけど現実は?ま、否定してばっかりではダメなので、何とかしないと。 いきなりとか完全に模倣するのは当然無理な話だけど、少しでも参考にしないといけないよね。考えさせられる1冊です。 そもそもじぶんの考え方がすごく古い、という自覚はある。WLBは満足するに越したことはないが、目の前の仕事は誰がどうやって片づける?「じゃ、仕事が多いなら断ればいいじゃん。キャパオーバーしてまで仕事する意味は何?」と聞かれると返答に窮します。 ウチの職種は結局、知的労働に徹しきれないからじゃないかな。外的要因の影響受けすぎだし。課題・問題点は愚痴のようにナンボでも出てくる。なら、それの解決策を考えればいいだけ。いいだけ?ちょっと落ち着いたら課題問題を棚卸しよう。 社内のロールモデルも確かに見直さないと。働き方を変える時機に来ているのは間違いないからね。
0投稿日: 2012.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ働くイコール傍を楽にする。互いの幸福のために働き、貢献する。ビジョンを描き、それを肯定し、実行していく。自分の働き方を変え、他人に良い波及を与え、社会が良くなっていく!
0投稿日: 2012.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「働くことは傍(はた)を楽にさせること」。そこから「いろんな働き方があっていいはず!」と指摘するコンセプトの本。 社蓄や過労が叫ばれる今日。働くことに対して、いいイメージを持てない。しかし、本書は働くことで働く人もそれに関わる人もみなが幸せになれる方法を提案する。 ところどころ実体験や冗談もまじっており読みやすい。 経営やビジネス書読みすぎて意識高すぎ系な人になっちゃった人におすすめ。
0投稿日: 2012.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ自身の経験を元にして書かれているので理解しやすく、働き方に関しての考え方を変えてくれる本。 特に本の最後に纏められている「働き方革命」実現に向けてが秀逸。 図書館で借りたけど、自分用に買おうと思った。
1投稿日: 2012.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログNPOフローレンスの代表の方の本。 めためた忙しい人が、いかにして仕事みスリム化して行ったかのか、リアルに伝わってくる。オススメ。ライフビジョン。たくさんの働く場。子供たちのどのような社会にしたいか。
0投稿日: 2012.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本を通じて自分の将来(働き方・生き方)に目を向けてみてください!! 日本では、働きすぎ・子育ての余裕なし・少子高齢化などの問題が叫ばれて久しいです。それらの解消を政治に任せっきりにするのではなく、一人ひとりが「自分の働き方を工夫する・そういった意識を持つ」ことが必要です。 筆者は若くして「社会起業家」として名前が知られています。本書ではその筆者自身の経験も踏まえ、今後どのような働き方が望ましいのかについて書かれています。 その中に『会社の仕事をするだけが「働く」じゃない』という言葉があります。 よく言われますが、「就社」すれば良しという時代は終わりました。これからは各自が「社会の中でどんな目的(何の・誰のために)を持って働くか」が更に問われるように思います。 学生のうちにおぼろげながらもそういった考えを持っておくことが必要ではないでしょうか。その際に参考になる一冊です。 (2011ラーニング・アドバイザー/教育 TAKEDA) ▼筑波大学附属図書館の所蔵情報はこちら http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1400090&lang=ja&charset=utf8
0投稿日: 2012.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ2012/2/17読了。 少しずつ実践していこう。 (でもビジョンを描くのはだいぶ気恥ずかしい…) ・人は自己イメージと現実が異なる場合に、『認知的不協和』を起こしてしまう。これに対して人はバランスを取ろうとする→できると思えばできる。ポジティブな自己イメージの形成が大切 ・仕事だけでなく、プライベートも統合して、それをひとつのプロジェクトとして捉える ・家事をマネジメントする。手伝う、ではなく、自分の仕事として認識する ・仕事は仕事でも、金にはならないけど、社会のためになる仕事がある ・常にベストパフォーマンスを出せるように、体のメンテナンスをしっかりとする ・残業代が減る→コストが減る(うちの会社の数字を出してみるのが、実感できていいかもしれない) ・資金繰りが怪しくなった時期のエピソードになんだか泣きそうになった。余力があることの大切さを感じた(今のうちの会社はどうだろうか、という問いとともに)
0投稿日: 2012.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログん~ライフワークバランス関係の本を読んでいると、意外とふつーのことがあ書かれていたな・・・。でも、これを読んで、やっぱりちゃんと努力して効率化や定時退社に取り組めば、どんなに忙しい業界でも実践できるのでは?と思います。なにもシステム化してないのに「うちの業界は特殊だから」とはなっからあきらめていてはいつまで経っても残業三昧の日々になってします。 小室淑江さんの本も含め、うちの会社の上層部の方々にぜひ一読いただきたいです!
0投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ残業、休日出勤が当たり前だった著者が、いかに働き方を変えていったかを語った本。まさに少し前の自分を見ているよううだった。我々は「働く」ということをもっと広く捉え直す必要があると思う。オススメの一冊。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 【読書メモ】 ●自己イメージが、私たちの行動を規定する。・・・ポジティブな自己対話をすることによって、ポジティブな自己イメージを潜在意識に形成できる。 ●「目標は必ず言語化し、繰り返し見て、自分自身に刷り込んでいきなさい」「その時に湧き上がる感情をリアルに書け」「具体的にイメージできるような書き方に」「毎日自分宛てにビジョンが届くように設定する」 ●会議のルール 1.一つの会議は1時間半を越さない 2.議事録はプロジェクタで映し出しながら、その場で取る 3.議題は前日までに出し、議題にないものは議論しない 4.タスクは会議の場で期限を決め、次の会議が始まるまでに進捗をグループウェアに貼る5.定例会議ごとにファシリテーター(司会)とロガー(議事録作成者)を決め、彼らが会議の内容と時間に責任を持つ ●フルメンバー・サブメンバー制度・・・その会議に絶対必要な人はフルメンバー。ある議題にだけ必要な人はサブメンバー。 ●自分だけで完結する業務は、わざわざマニュアルなんて作らなくとも、なりがちだ。そこで(ジョブローテーションを定期的に、頻繁にやるようにし)無理やり人に説明せざるを得ない状態にする。異動の引き継ぎは、嫌でもやらないといけない。 ●ひとつの業務をなるべく1人で抱え込まないよう、「ダブルワーク」制度を作った。すべての業務を一人ではなく、主担当と副担当の2人でやることにした。 ●マニュアルに基づいて仕事を行うという「仕組み」を作り、「仕組み」が陳腐化しないような、「仕組み」を運用することによって、人に張り付いて非効率かつミスの多い仕事を、スマート化していった。 ●メールの先頭に「してほしいこと」と「期限」を必ず入れる・・・ex.駒崎代表【意思決定】【0317迄】・・・この他、【依頼】【要FB】【共有】などのコードを定めた。 ●仕事の場で使う「レポート・トーク」と家庭で使う「ラポール(安心感)・トーク」は違う・・・「レポート・トーク」は結論から。「ラポール・トーク」はプロセスを共有する。 ●仕事が「フラグメント(切れ端)」だからだ。誰かから「これ、適当にやっといて」って仕事ほど、うぇ、面倒くさいな、っていうものはない。フラグメントの対極にあるもの。それは「裁量権を持った仕事」である。 ●仕事とは、職場に行って滞在して帰るまでの行為ではない。その定義は人それぞれであって良いのだし、拡張された仕事観を持つことにより、本業の仕事に対しより広い視野で眺められるようになるのだ。 ●仕事だけに専門特化「しない」ことが、職場において働くことだけを「働く」としないことが、逆に仕事を充実させるという逆説。 ●昔から「パートナーとなるような人と出会いたい」と思って色んな女性と付き合ってきた。しかし致命的な間違いを犯していたことに、「働き方革命」を始めた後で気づいた。パートナーというものがいて、それに出会うのではない。人はパートナーになっていくのだ。しかもそれを相手に期待するのではなく、自分が変わることで新しい関係性を創りだすことができるのだ。 ●僕は一つの世界を生きつつ、僕の見ているものは物事のほんの一つの側面、一つの世界だけで、世の中には無数の世界がミルフィーユのように折り重なり、関わり合っていることを知る。それら見えない「もう一つの世界」を僕は知ることで、単調な繰り返しどころか、多層な世界のハーモニーを奏でる交響曲の指揮者として、働くことができる。 ●知らない人や知らないこと、知らない物語、発見と感動と冒険は、遠くに行くことで得られるのではなく、向こうから訪ねてくるのだ。僕たちの心のチューニングを合わせることで、向こうから訪れる。チューニングにかかるほんの少しの時間を確保すれば、働くことを狭く限定せず、僕たちのあるべき人生の姿を形作る作業全体を「働く」と定義すれば。 ●マネージャーのマネジメントを管理する方法として、プロセスを管理するやり方がある。彼がどういう人材をどういう仕事につけたのか、部下のキャパシティにどの程度のタスクを詰めているのか、というチーム内経営資源の配分(アロケーション)を見ていくことで、うまくマネジメントしているのか、そうでないのか、分かる。 ●アロケーションの巧拙は、残業時間数で見られるようになった。しっかりと効率的にアロケーションを行えば、残業時間数はゼロになるはずだ。しかしそれができないということは、仕事(タスク)に対して、人材の適切な受け入れ容量(キャパシティ)を確保していないということを意味する。もちろん季節の繁閑差等はあろう。しかしそれは事前に読めるものが8割だ。忙しくなる時期は人員の増員を依頼するなり、基幹業務に集中して補助業務を停止させるなりして、アロケーションを行えば良い。 ●「先進国は先進国でも『課題先進国』さ。どこの国よりも早く少子高齢化社会に突入する。それによる労働人口減少。年金をはじめとする社会保障の破綻危機。日本が先頭を切って、そうした今日的な社会問題にぶつかる。・・・我々は何の因果か、1人で早めにテストを受けなくちゃいけなくて、過去問もなく、カンニングもできない状況なんだよ。」・・・「そうしたら、日本が答えを出せば、他の国にその答えを教えてあげられる、っていうことですよね?問題の解決策を『輸出』できる。そしたら日本は人類に貢献できる、っていうことじゃないですか。」 ●「僕たち失われた世代が、働き方革命を起こし、我が国を変えるでしょう」 ●「働き方革命」のコンセプト ・「長時間がむしゃら労働」から「決められた時間で成果を出す」スマートワークへ ・「自分の(自分のキャリアの、自分の家族の)ための仕事」から「自分を含めた社会のための仕事」へ ・「仕事とプライベートを完全分離し、生活のために稼ぐことを『働く』と定義すること」から「プライベートを含めて、他社に価値を与える(傍を楽にする)こと全てを『働く』と定義すること」へ ・「他社に価値を与える(傍を楽にする)」ことは、大げさなことでなくてもよく、「他社を幸せにすること」「他社の負担を減らすこと」「喜ばすこと」「感動させること」「優しい気持ちになってもらうこと」など、私たちが日常的な感覚で行うことができるものでよい ●「働き方革命」に関連するキーワード ・「成功」ではなく「成長」 ・「就社」ではなく「就職」 ・「やりたいことがない」ではなく「やりたいことは創る」 ・「良い会社に行けば良い仕事ができる」ではなく「良い社会にするために良い仕事をしよう」 ・「自己実現」ではなく「社会実現(あるべき社会像の実現)を通しての自己実現」 ・「私の市場価値は?」ではなく「私が社会に与えられる価値は?」 ・「目指せ年収1000万円」ではなく「目指せありたい自分」 ・「キャリアアップ」ではなく「ビジョンの追求」 ・「自分探し」ではなく「コミットメント(参画・貢献・自己投入)の連続による自己形成」 ・「ロスト・ジェネレーション(失われた世代)」ではなく「ブースト・レボリューション(改革を加速する世代)」 ・マンガ『課長島耕作』(大企業で出世し、女にもてよう)というロールモデルではなくマンガ『マスターキートン』(世界にとって価値のある夢を追うため、無様な試行錯誤をいとわない)というロールモデル ・「金持ち父さん」ではなく「父親であることを楽しむ父さん」 ・「ブランド企業(学校)に底上げしてもらっている自分」ではなく「自分の生き方にOKを出せる自分」 ・「亭主関白」ではなく「パートナーシップ」 ・「家族を養う」ではなく「共同運営」 ・「家族サービス」ではなく「家族も、自分も楽しいイベントづくり」 ・「家事を手伝う」ではなく「自分の仕事としての家事」 ・「社会=国・政治」ではなく「社会=家族・友人・すぐそばの他社の連なり」 ・「ボランティア活動」ではなく「社会へのコミットメント(参画・貢献・自己投入)」 ・「終わりなき日常」ではなく「ビジョン実現に至る、日常という冒険の旅」 ・「課題先進国 日本」ではなく「課題解決手法の輸出国 日本」 ●「働き方革命」第一歩である、スマートワーク化の最初のアクション例 ・ライフビジョンを描き出し、スマートワーク化へのモチベーションを惹起する ・「帰る時間」と「寝る時間」を朝、設定する ・タスクリストなどでやることを見える化する ・自分の作業をスリムタイマー等によって計測し、気づいていない非効率性をあぶりだす ・手帳を活用し(手帳活用術は本屋さんにたくさん並んでいるので、好きなものを選択)、効率的なスケジューリングを徹底する ・目標残業時間を個人的に、あるいは職場全体として設定し、その達成のために業務改善に取り組む ・時間の無駄になりがちな会議を変革する(会議術は本屋さんにたくさん並んでいるので、気に入ったものを選択) ・自分のメール処理方法を見直す(メールの効率化は「ライフハックもの」として本屋さんにたくさん並んでいるので、自分に合ったメッソドを選択) ・仕事の定型化、仕組み化について実践する。「仕組み仕事術」等の仕組み化本を参考に、自らの業務の定型化を推し進め、生産性を改善する ●「働き方革命」による、広い意味の「働く」事例 ・ブログで意見を表明し、トラックバックを活用して議論する。多様な言論が地域経済を下支えする ・地域の祭りに行ってみる。時には御輿を担ぐなど参加し、心ゆくまで楽しむ ・便利なプログラムを開発して、無償配布する ・バンドやフットサルチームを結成し、小さなコミュニティを創る ・夫婦や家族のビジョンをつくり、その達成を目指す ・自分の周りに快適な世界を実現する行為、すなわち家事を行う ・子どもの保育園の父母会やPTAにコミットし、より良い環境をつくる ・NPO・NGOにプロフェッショナル・ボランティアとして関わる ・自分が気になる社会問題にチャレンジしている団体に対し、継続的に寄付をする ・区役所や市役所のホームページ上の「市長へのメール」を活用し、地域の問題を指摘し、解決策を提示する ・気に入った議員の講演会会員になって(年会費3000円~1万円が大半)、ちゃんと彼らが機能しているかウォッチする ・投票し、家族や近しい人達に投票を呼びかける
0投稿日: 2012.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事を通じて、おじさん化してきた著者。 仕事は絶対!という感覚から、本当に必要なものと無駄なもの区別が付かなくなり、家庭を顧みないおじさんとなった。 でも、彼は「働き方革命」と題して大きな自己変革を遂げました。 それは、スマートで小ぎれいでかっこいいパパへの変身。 元々駒崎さんは、病児育児という分野で先進的な取り組みを多く実施し、 パパ、同い年のビジネスパーソンとしてもうらやましい社会起業家です。 それに今回の「働き方革命」での自己変革が加わり、 早朝型パパが目指す理想的な「働く」を本を通じて教えていただきました。 一歩も二歩も先を行っている同じ年の駒崎さん。 はるかかなたの遠くの存在のように感じますが、 〜マスターキートンを目指す。〜に共感。 早朝型パパがあこがれていた漫画キャラクターは、そう「マスターキートン」です。 小学5年生の時に近くの美容室で読んだマスターキートン。 強くてスマートででもおっちょこちょい。 どちらがマスターキートンになれるか競争です!
0投稿日: 2011.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本は著者の飾らない目線で書かれた「働き方革命」が記されている。著者が目標とした、「食いぶちのための仕事も、自分の能力向上のための努力も、父親としての仕事も、地域社会のための仕事も楽しむ『ジェンセン親父』」の姿なんかは「いいなぁ」と思えてしまう。 若くして経営者となった著者だが、感覚は同年代の人と変わらないと思う。ルー・タイスに言われた目標の言語化を「うわー、イタい」と赤面しながらやっていたり、ジムに行けば自分の体力低下具合に愕然としたり…。彼女との会話では経営者の専門用語をバリバリ使って、でも「会話ってこういうもんだよな」と思いなおすこともある。彼女の生活サイクルを見直すために電話をしたら「私、浮気なんてしてないからね!」と返されたのには笑った。 目標を自動メールで見られるようにしたり、皿洗いの効率化のために彼女に「プレゼン」までやるところはやっぱ経営者?だなぁと思うけど。 著者の家族との会話も面白い。歳の離れた上の姉二人にタジタジになったり、母からはピーナッツをぶつけられて「この小坊主」と言い放たれたり。 それも、著者が自分の生活を見直して生まれたやりとりなのだろう。 寝る暇もなく働き続けた著者がどのように働き方を変え、そしてその結果どういうことが起こったか。 読むと元気が出てくる本だ。
0投稿日: 2011.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ働き方革命とは? 働き方を変える為に、働くことを捉え直す… 仕事だけに専門特化[しない]ことが、職場において働くことだけを[働く]としないことが、逆に仕事を充実させるという逆説… 働き方革命のコンセプト… 長時間がむしゃら労働者から⇨決めらられた時間で成果を出すスマートワークへ 自分のための仕事(自分のキャリア、自分の家族の)から⇨自分を含めた社会のための仕事へ 仕事とプライベートを完全分離し、生活の為に稼ぐことをを[働く]と定義することから⇨プライベートを含めて、他者に価値を与えること全てを[働く]と定義することへ 他者に価値を与えることは、大げさなことではなくてもよく、他者を幸せにすること、他者の負担を減らすこと、喜ばすこと、感動させること、優しい気持ちになってもらうこと、など、私たちが日常できれば、な感覚で行うことができるものでよい。 働き方革命の第一歩は、ライフビジョンを設定して、かき出し、モチベーションをあげること。 帰る時間と寝る時間を朝、設定する。 タスクリストなどで、やることを見える化すること等 まずは、自分自身のパターン認識を変えないといけない。 自己イメージを知らず知らずのうちに刷り込まれている…
0投稿日: 2011.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ病児保育などのNPO活動に尽力され、社会起業家としても知られる駒崎さんの著書です。 社会起業には自分も興味があり、昨年末に前の会社を辞めたときには、社会事業への転職もちょっとだけ考えました。今にして思えば、興味本位での検討だったので、実際にそちらに移っていたとしたら、現実とのギャップが大きくうまくいっていなかった可能性が多いのですが。 この本で見る駒崎さんのやり方は、『「最高のチーム」をつくるシンプルな仕掛け』 http://www.amazon.co.jp/dp/4769610041 の黒岩禅さんに似た部分があるように思いました。つまり、ある方法で外面的には成功しているものの、自分の中では全く納得できていない。やり方を根本的に見直すことで、自分の中でも納得のいく成果を出し、外面的にもこれまで以上の成功を遂げている、ということです。成果や数字にのみとらわれた働き方から、自分も周囲の人々も幸せにする働き方への変革、という部分でも共通していると言えるでしょう。 仕事をする以上、成果を出さなければなりません。その方法として、ただ闇雲に動き回るのか、ゴールを見据えて必要なことを必要な手順で進めていくのか、いろいろなやり方がありますが、長い時間一生懸命にやっても自己満足に終わるのでは、成果が出ているのとはちょっと違うのではないかな、と感じます。 仕事の効率を劇的に改善して、家にいる時間が長くなった駒崎さんが、パートナーの家事のやり方まで手を出してしまう場面。その後の展開を読むまでは、「過ぎたるは及ばざるがごとし」になってしまったのではないかな、と思ったのですが、通読して何が言いたいのか理解できました。 「働く」というと、勤め先で仕事をすることだけを想像しがちですが、日常生活のすべて、ほかの誰かのために行動することすべてが、「働く」なのだと。だからこの本のタイトルでもある「働き方革命」は、仕事の場だけではなく、あらゆる生活の場を変えていくきっかけになるのだと、気づきました。 『ザッポスの奇跡』『『ワーク=ライフ』の時代』とこの本、仕事に関わる本を3冊続けて読みました。自分の問題意識とも重なるのですが、3冊とも主張は共通しています。感じ方は人それぞれだと思いますが、もし、どれかとどれかが真逆のことをいっているように読み取れたとしたら、あまりに表面的な読み方になってしまっているのではないかと自分には感じられます。 共通した主張というのは、やっている仕事の「中身」、言い換えれば仕事の「本質」が重要だ、ということです。いくら長い時間一生懸命に仕事をしても中身が伴っていなければ何にもならないし、ワーク・ライフ・バランスを曲解して仕事の本質をないがしろにしてしまっては、元も子もありません。 今の仕事の本質は何だろうか。本質をとらえて仕事をできているだろうか。もっと広く、自分が1日1日を暮らすにあたって、人生の本質を見失ってはいないだろうか。 もう一度、じっくりと考えたいと思います。
0投稿日: 2011.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログNPOフローレンス代表 駒崎弘樹さんの著書。 本書は物語のように書かれていたので、とても読みやすかった。 結論を言えば、個人レベルで「働く」ことを見直し実行することによって、集団、地域、国といったように、国レベルで社会を変えることができるということを筆者は伝えたように思う。 自分にとって参考になった部分は、 • 自己イメージは、私たちの行動を規定する。 ☞知らないうちに、人は潜在意識の中にある自己イメージによって行動する。 • 思考の反復がパターンを創る。 • 目標は言語化し、繰り返しみて、自分自身に刷り込む。 • 優秀なビジネスパーソンはアスリートである。日々、コミュニケーションの一瞬一瞬でベストな自分を出せるよう常にメンテが必要。 • 仕事だけに専門特化しないことが、職場において働くことだけを「働く」としないことが、逆に仕事を充実させるという逆説。 • 知らない人や知らないこと、知らない物語、発見と感動と冒険は、遠くにいくことで得られるのではなく、向こうから訪ねてくる。 • 日頃からのコミュニケーション • 働くとは、他者と自分のために価値を生み出すこと。 • 目指せありたい自分 この方の尊敬できる部分とは、 実行する能力と他人からの批判を真摯に受け止めることができる素直さ。
0投稿日: 2011.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容的には大賛成なんやけど、ごめんなさい、全編自慢話の感が否めない。評価されてる人なんやから、そんな自慢しなくていいよ。 16時間労働から6時退社に切り替えたその日から、部下誰も困ってないし、緊急の電話もなかったなんて、ありえない。それまでよっぽど無駄なことしてたってことじゃないの? 「ワークライフバランス」の正しい意味は、勉強になった。
0投稿日: 2011.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ久しぶりにいい新書に巡り合えた! 筆者は、「働く」≠「会社で仕事をする」であり、人生はトータルにおいて働き続けなければならないと考えている。 つまり、家事をすることも「働く」ことだし、自分の将来のために勉強をしたりすることも「働く」こと、誰かのために何かをすること全てが「働く」ことである。 現代の日本社会では、まだまだ「働く」ということは、会社で社会に対して何らかの働きかけをすることであるという認識が強い。そのため、未だに多くの会社員が夜遅くまで残業をし、土日でも仕事のことを考えたりしている。それが悪いと言い切れるわけではないけど、それで本当にあなたの周りの人たち、そしてあなた自身は幸せですか?と社会に対する問いを投げかけてます。 この本では、そういった現状を打破するために、筆者がどういうことに取り組み、その結果がどうなったか、ということが書かれている。 基本的に経験談ベースで、斬新な取り組みの内容が書かれていたり、目新しい発想があるわけではないんやけど、それでも社会的風潮からの脱却を図ろうとする筆者の姿勢は素晴らしいと、オレは個人的に思う。 「ワークライフバランス」という言葉に対して、みなさんはどういうイメージを抱いていますか? オレ自身は正直、「早く家に帰ってのんびりしたい人の口実」みたいな印象をずっと抱いてました。でも、それも日本社会の風潮が作り出したイメージに過ぎず、本来は仕事と自分の人生とのバランスを保ち、充実した毎日を送るために考えられた発想だということを、もう一度主張していかなければならないと思う。 少子高齢化によって労働人口の現象が叫ばれている現代やからこそ、女性の社会進出をもっと進めるべきやし、そのためにはこういった考えは欠かせないはず。 ちょいちょい出てくる筆者の自慢話が癪に障るけど(笑)、「働く」という言葉を捉え直す本としては、読みやすさという点から見ても最高の一冊やと思います。 働くとはなんなのかを、見つめ直したい、考え直したい人にオススメ。
0投稿日: 2011.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか面白い。簡単に読める。漠然とかんがえていたことが、文章になっていたので、素直に共感できました。 あとは実行するだけだ。
0投稿日: 2011.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が若かったため、あまり期待せずに読んだ。 年が近く同じ業界の経営者であるため、親近感が持て、共感できたり参考になることがあったりと収穫が多かった。
0投稿日: 2011.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログワークライフバランスの話し。時間の使い方を徹底すれば仕事の本質を最短時間でこなし、結果に結び付く。さらに時間に余裕がうまれ、実りある自活に没頭できる。仕事も家事も趣味も「働く」の価値にたどり着くところが今までの日本人の発想になかったこと。もう家で本を読むことは仕事をサボることではないと自信をもっていいと思う。知識、経験はめぐりめぐって皆を幸せにするはずだ。働く事の意識を変えさせてくれる面白い本。もう働くのがつらいなんてことはどうにでも回避できる。
0投稿日: 2011.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「あ、僕大学出たらすぐ起業します」または「個人単位から日本を良くするために頑張ります」。図書館で適当に借りたのだが大当たり。大企業に行く気は完全に消え去った(そもそも行けるか知らんが)。 ①スマートワーク化から生み出される時間→人生の充実→更なるスマートワーク化 ②「働く」を「あるべき人生を作ること」に定義→日本中がそうなれば個人レベルから、家族、地域、国レベルに発展→皆わっしょい ・ライフビジョン ・彼女→パートナー
0投稿日: 2011.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ駒崎さんの本ってことで興味があって、手に取ってみたけれど等身大の内容がとてもしっくりきました。 ワークライフバランスの話だけれど、1つ1つのステップがとても身近で「あぁ、そうそう」って感じで納得できました。 いつか実際にお会いしてみたいなぁ。。。(^^)
0投稿日: 2011.01.31
