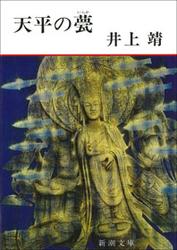
総合評価
(116件)| 31 | ||
| 42 | ||
| 30 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログはるか1300年前に、海を越えて唐へ渡った名もなき留学僧たちの物語。仲麻呂、真備といった日本史で馴染みの人物も登場するが、彼らを主役とせず、歴史に埋もれた遣唐使たちに焦点を当てた所が面白い。鑑真和上を来朝させるという一つの目的のため、命の危険を冒した僧たち。留学生としての自らの使命を果たさんとする一途な姿が胸を打つ。中でも業行という、年老いた僧がひたすら写経に打ち込む様子は強く印象に残る。彼は正しい経文を日本に持ち帰ることが自らの使命と考え、在唐の長い年月をただ経文を写すことに費やした。彼の人生そのものとも言える経文を、命に代えてでも日本に持ち運ぶことを普照に約束させる姿には、鬼気迫るものがある。しかし業行の経文も、おそらくは彼自身も、水底に沈んだ。あまりにも残忍な運命の悪戯である。 ところで人には「生まれてきた以上、何事かを成し遂げて死にたい」という思いがあるのではないだろうか。我々は生まれたから生きるのであって、本来、生には何の意味もないのかもしれないが、そうであっても意味のない生を、いくらかでも意味あるものにしたいと切なく願うのが人間だと思う。よく天命とか天職とか言うが、そんなものが本当にあるのか、甚だ怪しい。しかし「これが己の使命である」と思う(思い込む)ことによって、人は生の不安と孤独、空虚さを埋めようとしているのではないか。私には、私自身も含めて「自分探し」に悩む大勢の人々が、詰まるところ「使命探し」に躍起になっているのではないかと思える。そして、それはとても人間的な悩みであると感じる。 業行の「使命」は、経文を日本に持ち帰ることができなかったという意味では果たされぬものだった。だが業行の人生が無意味だったとか、空虚だったとか言うことはできないのではないだろうか。少なくとも彼は自分の「使命」を見つけ、それに生涯を捧げることができた。その幸不幸は量るべくもないが、私には理想的な生き方であると思える。
0投稿日: 2009.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ天平時代(8世紀)に6度に渡って渡日を試み、ついには失明しながらも、日本へとやってきた唐の僧、鑑真和上(688〜763)と、彼を招来した日本人僧・普照(ふしょう)の話です。鑑真といえば、唐招提寺で有名ですね。 そもそも遣唐使というのは、時の政府が莫大な費用をかけ、多くの人命の危険も顧みず、遣唐使を派遣するということの目的は、主として宗教的、文化的なものであって、政治的意図というものは、もしあったとしても問題にするに足らない微小なものであった。 大陸や朝鮮半島の諸国の変遷興亡は、その時々において、色々な形でこの小さい島国をもゆすぶって来ていたが、それよりこの時期の日本が自らに課していた最も大きい問題は、「近代国家成立への急ぎ」であった。 中大兄皇子によって律令国家としての第一歩を踏み出してからまだ90年、仏教が伝来してから180年、政治も文化も強く大陸の影響を受けてはいたが、何もかもまだ混沌として固まっていはいず、やっと外枠が出来ただけの状態で、先進国唐から吸収しなければならないものは多かった。人間の成長でいえば少年から成年への移行期であり、季節でいえばどこかに微かに春の近い気配は漂っているが、まだまだ大気の冷たい三月の初めといったところであろうか。(P.6) この時代に唐に行くということは、それだけ危険があったが、それと同時に、まだ生まれたばかりの日本にとっては人の命では変えられないくらい重要なことであった。その遣唐使に選ばれた普照、栄叡、戒融、玄朗が、それぞれ自分は何のために唐へ来ているのか、何を学んで帰らなければいけないのかという使命について悩み、それぞれの道に進んでいく。 この時代、日本にふたたび帰って来れるかどうかもわからないのに、勉強するために海を超えて大陸へ行くなんて相当の恐怖やったやろうな。
0投稿日: 2009.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ学校で配布された 課題図書。 むずかしかったです。 いつかすらすらと 読めるようになりたいなー(^^)
0投稿日: 2009.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログある僧が第九次遣唐使船に乗り唐へ渡り、20年後日本の土を踏むまでの話。 行くのは気楽だが、帰るのは大変。 次の遣唐使船は15年、20年たっても来るかわからない。 政権が変われば遣唐使すら無くなるかもしれない。 船が出ても難破し、岸にたどり着いても原住民に捕らえられるかもしれない。 文化伝来が大量の犠牲、献身、覚悟の上に成立していたことがわかる。 ☆☆☆。 あまり語られない、遣唐使の唐での生活、阿倍仲麻呂や鑑真の唐での様子を追いかける。 何のために留学をするのか。自分の役目は何なのか。何を学ぶのか。 流されるままだった主人公が、同期留学僧との死別、別離、鑑真渡航を経て、帰国を果す。 20年が経過していた。 学校で学んだ鑑真や吉備真備、ゲンボウ、行基といった坊主が勢ぞろい。 当時の中国の先進性、日本が中国から学んだことの多さ、 言葉は違えど、仏教を通じ日本、中国、ベトナム、果てはインドまでが 分かち難く結ばれていた当時の世界状況を体感することができる。 鑑真の10年以上に渡る渡航失敗、失明、難破、中国大陸放浪を見るだけでも面白い。
0投稿日: 2009.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ鑒眞和上の静かな決意も、普照や栄叡の意気込みもすごくて 抒情的に書いてない箇所でもぐっとくるものがあった。 スケールはダウンするが 例え霞んでしまうほどものでも 自分が死ぬ時に何かのバトンを繋げていたら幸せだと思った。 あと3、40年たったら、今の自分のこの気持ちはどうなってるんだろう? 残酷かもしれないがちょっと楽しみでもある。
0投稿日: 2009.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2月15日読了。5回渡日に失敗し、失明しながらも6度目に渡日を果たした鑑真和尚と、彼に付き従った普照をはじめとする、5人の日本人留学僧たちそれぞれの運命。漢文交じりの悠々たる文体だが、そこで語られるのは「漢(おとこ)」が命をかけるべき仕事・なすべき定めとは何か?という熱いメッセージ。自分が生涯をかけて挑んだ「写経」が海の藻屑と消え後には何にも残らない・・・ゾッとするほどはかない、その仕事のはかなさを承知しつつもそれに身を投げ出さずにはいられない男たち。うらやましいような、真似したくないような・・・そんな気にもなる。
0投稿日: 2009.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ時代小説というと、戦国時代や江戸時代のものが多いので、その時代のものには馴染みがあるけれど、この小説の場合、天平時代の出来事を描いているところが新鮮でいい。 阿部仲麻呂や吉備真備のような、教科書以外では見たことのない人々が、物語の中の登場人物としてしゃべっているところも、なんだか奇妙で面白い。 この話しは鑑真が主人公なのかと思っていたら、鑑真についてはあまり詳しく書かれていずに、どういう人だったのかということもよくわからないぐらい、あっさりとした扱われ方だった。 本当の主人公は、それよりも、無名ではありながら人生の大部分をかけて、何十年もひたすらに写経した経典をなんとかして日本に持ち帰るということに異様な執念を燃やした、業行のほうだろう。 物語の配分から言っても、鑑真や普照が日本に戻ってきた後のことについてはほとんど触れられていずに、遣唐使というものがどれほどに命懸けで、日本と唐との間で文化や教義を伝えようとしていたかという部分にほとんどの紙数を費やしている。 五度の失敗の後、失明をした後に60歳を過ぎてようやく鑑真を日本にたどり着かせたものは、運以外の何者でもなく、幸運にも日本に着いたものより何倍も多くの書物や人が海の藻屑と消えていった。 海を超えて異国の地に渡るということが、常に死を賭した決死行だった時代には、たった一巻の書物や一人の人間を運ぶということだけでも、ものすごい覚悟が必要だったのだということがよくわかる。その、先人たちの執念のすさまじさが伝わってくる物語だった。 こうしたことを、いままで多勢の日本人が経験して来たということを考えている。そして何百、何千人の人間が海の底に沈んで行ったのだ。無事に生きて国の土を踏んだ者の方が少ないかも知れぬ。一国の宗教でも学問でも、いつの時代でもこうして育ってきたのだ。たくさんの犠牲に依って育まれて来たのだ。(栄叡)(p.25) 俺はこの国はいまが一番絶頂だなと思った。これが一番強いこの国の印象だ。花が今を盛りと咲き盛っている感じだ。学問も、政治も、文化も、何もかもこれから降り坂になって行くのではないか。いまのうちに、俺たちは貰えるだけのものを貰ってしまうんだな。たくさんの蜂が花の蜜にたかっているように、各国からの夥しい留学生たちが、いまこの国の二つの都にたかって蜜を吸っている。(戒融)(p.34) われわれの場合だって、無事に帰国できるとは決まっていないんだ。帰国できるかも知れないし、できないかも知れない。われわれはいま海の底へ沈めてしまうだけのために、いたずらに知識を掻き集めているのかも知れない。(玄朗)(p.52) 併し、普照にも、鑑真の渡来と、業行が一字一句もゆるがせにせずに写したあの厖大な経典の山と、果たして故国にとってどちらが価値のあるものであるかは、正確には判断がつかなかった。一つは一人の人間の生涯から全く人間らしい生活を取り上げることに依って生み出されたものであり、一つは二人の人間の死と何人かの人間の多年に亘る流離の生活の果てに始めて齎されたものであった。それだけが判っていた。(p.179)
0投稿日: 2009.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログあれ?横(←)に本の表紙が表示されない。 せっかくの平山郁夫画伯の海の中の仏様が印象的な絵なのに。 海の青色がとても綺麗。 いつか見た、同画伯の描いた薬師寺玄奘三蔵院伽藍の大唐西域壁画(ふだんは非公開)を思い出す。 あれも砂漠の月夜の空の青が印象的だった。 この本を初めて読んだのは高校二年の夏。 夏休みの宿題、読書感想文のための課題図書だった。 最初は小難しい話でイヤイヤ読んでいたのが、留学僧の生き様に引き込まれ、不思議な感動があったのを覚えている。 それを、中国に住むようになった私が再読。 中国に何の興味もなかった高校生のときとは読み方が全然違う。 この本を読んだ誰もが感じると同様に当時は、唐での時間をただひたすら写経にのみ費やしたが、結局膨大な教典とともに海の藻屑となってしまった業行へ哀れみの気持ちが多かった。 今では、教典等の机上の学よりも中国の国土そのものから(ブッダの教えを)学ぶことを見いだした戒融や、人一倍望郷の念強く心寂しさを抱え唐の女と結婚し留学僧の身分を捨てた玄朗の生き方に親しみを覚える。 普照の生き様にも親近感が。 必死に学問をしようと意気揚々唐土を踏んだものの、虚無感に襲われたり、望郷の念強かったにもかかわらずいざ日本へ帰ってみると、日本がちっぽけに見えたり、唐僧のそばにいるほうが心が落ち着いたり。 外国に住むものとしてよく分かる。 この小説には日本と中国両国に関わった人びとがたくさん出てくる。深く読み込んでみたいと思う。 私自身の中国とのかかわりを除いても、天平の昔に日本から唐へ渡り鑑真を渡日させた留学僧を描いたこの小説は逸品。 こういう小説こそ本当の小説。 井上靖こそ本当の小説家、ともいえるのでは。
0投稿日: 2008.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ徴税を逃れるために出家する百姓が続出するという社会問題が起きていた当時,日本の仏教の戒律を正すため,唐から高僧を招聘するという使命を帯びた普照,栄叡が唐に留学をした.二十年以上の時を費やし,鑑真を筆頭とする高僧たちを招聘し,日本の仏教を盛んにした. というあらすじであったが,どうも話の起伏が足らないように感じ,物足りなさを感じた.普照と鑑真は日本に渡るまでに10年以上を費やしたことや,その間5回渡航を試みて4回は嵐に遭い失敗したなど多くの苦難が,淡々と書かれており,盛り上がりに欠けるかなと感じた.
0投稿日: 2008.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは名作だと思う。 あまりにも難しくて、読むのがしんどかったけど、読んでるうちに惹かれてしまった。影の薄い作品ではあるけど、個人的には井上靖のなかでは最も良いと思う。
0投稿日: 2007.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ遣唐使が来日する時代、鑑真が唐に渡る話。 船舶技術の未発達の時代、海を渡るということは死と隣り合わせであることを意味する。仏教を布教するため死を覚悟で学びに行くことは正しいことなのか。二回にわたる唐への渡航で失明という代償が伴う。使命感に満ち溢れた人の行動力は、無謀というべきか、偉大というべきか。
0投稿日: 2007.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ奈良時代の僧侶が、日本の仏教は今のままではいかん、ということで中国に行っていい感じのお坊さんを連れて帰ってくる使命を帯びて中国に渡るのだけれど、なんか色々あって大変な話。 仏教とかわからなくても、僕はこういうの好き。 で、鑑真がやってるくるわけですな。
0投稿日: 2007.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ良かったです。淡淡とした歴史物を書く作家がこれからも出て来て、評価されたら嬉しいと思います。人物の着目が一般と違っていい。個人的な感覚では、業行の叫び声が聞こえるっていうような感じを信じてやまないので、それが苦しいです。光を当ててあげる必要はないから、願いをかなえてあげたい。
0投稿日: 2007.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「遣唐使」「鑑真」 歴史の授業で習いはしたけれど, その中身なんてほとんど何も知らなかった. そんな時代の4人の遣唐使を中心にした物語. 鑑真を日本に連れてゆくという夢 半ばにして病に倒れた人. 唐を放浪し,日本人である,ということには意義を見出さない人. 日本に帰りたいとはじめから願いながら,唐で妻を持ち,結局は唐に生きる人. そして,流れに乗るように生きながらも日本に帰り,日本で生きる人. 何十年も日本に持ち帰るための写本を続け, 最後は海に消えた人. 命がけで日本に知識や技術を持ち帰ろうとした人たちの物語.
0投稿日: 2006.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史的な偉業である鑑真来訪は歴史の中では大きく名前を残さなかった遣唐使留学生によってなされたのだった.阿倍仲麻呂,吉備真備といった有名人にまぎれて無名の遣唐使が鑑真来訪に奔走する姿がかつての日本を想像させる.語りは淡々としていて主要な人物も淡々と死んだり,メンバが離脱したりする.すると読者は歴史そのものはどう展開したのだろう?と小説としてよりも歴史としてこの本を読んでいくことになりそうだ.
0投稿日: 2005.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ私蔵書は新潮文庫版平山郁夫氏の装丁。天平の甍=井上靖=平山郁夫 とイメージが連鎖する程強い印象。先日至上唯一の鑑真直筆!?の書が発見されて、和尚は全盲ではなかったのでは?とか。
0投稿日: 2004.11.13
